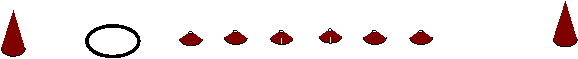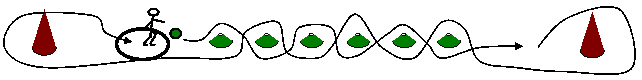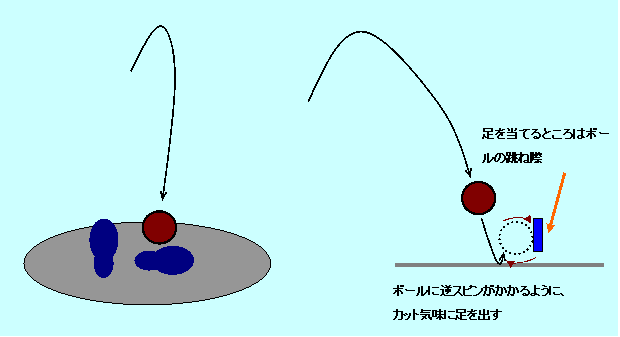|
�P�N���̗��K���e�@ �Q�O�O�P�N�V�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쐬�F�����P�R�N�V���R�O��(Rev.�`)�@ |
||||||||||
|
�ځ@�@�@�� |
||||||||||
|
�X�[�p�[�X�^�[�ƌ���ꂽ�I��B�͖w�ǂ��h���u���[���B�Â��̓W���[�W�E�x�X�g�A�y���A�P�r���E�L�[�K���i������ƌÉ߂��邩�ȁH�j�A�W�[�R�A�}���h�[�i�A���i�E�h�A�I���e�K�A���o�E�h�A�W�_���A�E�E�E�B����˔j�o�������ɂȂ����W�����G�̒��ł��A�}���ȃX�s�[�h�ω��A�u�ԓI�ȕ����]������D��������ؗ�ȃt�F�C���g�ŏu���ɔ�������A����ɃV���[�g�`�����X���������A����V���[�g�������肷��B�����������N�ł��h���u���[�ɂ�������Ă��܂����낤�B�ߑ�T�b�J�[�ł͒P�ƃh���u�������ł͊ȒP�ɓ˔j����Ȃ��悤�Ɏ�������g�D�I�E�V�X�e���I�ɂȂ��Ă���B�U��������ɑR���邽�߁A�g�D�v���[��D�悷��悤�ɂȂ����B���̕��h���u���[�̊����ʂ������Ėʔ��݂����Ȃ��Ȃ��Ă͂���B����ł���������`�[���ɓV�˓I�ȃh���u���[������P�P�̏�ʂ͂������ȏ�ł���������Ă����̂ł͂ƏI�n���҂ɋ���c��܂��Ă�����B �U���������I�D�ʁi������l�����������ƂōU���Ȃǂ�D�ʂɐi�߂���j�ɂȂ��Ă�����A�}�[�N�̂��Ă��Ȃ������I��Ƀp�X���o���Ό���I�ȁi�Ⴆ�L�[�p�[��1�P�Ƃ����悤�ȁj�`������B���I�D�ʂ����ɂ̓p�X�����ł͍���B��͂�h���u���Ől�����Ƃ��K�v�ɂȂ�B���������_������h���u�������ɂȂ邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�v�Ȃ��Ƃ��B �@���z�I�ȃh���u���́A �@�h���u�����Ȃ����Ɏ��͂̏��f���o���邱�ƁB �A�{�[�����������痣��Ȃ����ƁB �B���ł����̗͂v���i�p�X�A�V���[�g�A�t�F�C���g���j�ɉ������邱�ƁB �ł���B ��ɍőP�̏��f�����邽�߂ɂ́A�{�[�����قƂ�nj����Ƀh���u�����o���邱�Ƃ��K�v�ŁA����ɂ͏�Ɋ���グ�ĉ��������n����p����S�|���邱�Ƃ��厖�ł���B�܂��A�{�[�����������痣��Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A��Ƀ{�[�����R���Ă͂����Ȃ��B���̃C���t�����g��A�E�g�t�����g���g���Ă��炩�ȃ^�b�`�Ń{�[�����g������h���邢�́g�r�߂�h�����ōs���Ƃ悢�B |
||||||||||
|
�@�h���u�������ɂ�����ɂ͂ł��邾�������Ȃ���{�[����G�鎞�Ԃ𑽂����邱�ƂƁA�S�͂ł�点�邱�Ƃł���B�P�N���ɂ́A�܂��͒P���ȃh���u����������n�߂��B�P�T�`�Q�O�������ă��C���s�Ɉ����A���̊Ԃ�S���Ńh���u������������Ƃ����P���Ȃ��̂ł���B�������A�{�[�����������痣��Ȃ��Ȃ����邽�߁A�u�h���u�������Č��������̃��C���܂ōs�����瑫�̗��Ń{�[�������C����Ɏ~�߂Ă��������v�Ƃ������[���ɂ����B�S�����X�^�[�g�E���C���ɕ��̂��m�F������u���[�C�E�h���v�ƍ��}������ƁA�����ɑS�����S�̓h���u���Ō��������̃��C���܂ő����Ă������B�������A�����]���đ唼�����C�����z���Ă��܂����B�u�́[���B�P���́������A�Q���́������A�v�Ǝ��X�ɒ����������ƍs���߂����q���K���ɂȂ��Ċ撣��o���B�߂鎞�ɍQ�Ăă{�[���𐨂��悭�R���Ă��܂��ŏ��������Ɖ����Ƀ{�[����]�����Ă��܂��q�����Ȃ肢�����A���Ƃ��P��ڂ��I���B������R��J��Ԃ����B�R��ڂɂ͂������ɑ啝�ɉz���Ă��܂��q�͂��Ȃ��Ȃ�A�唼�̓��C����O�ŃX�s�[�h�_�E�����Ă���Ȃ胉�C����Ƀ{�[�����~�߂悤�Ƃ����ӎ����������B���̗��K�́A�܂����K���J�n�������C�Ȃ����ɂ�点��Ɨǂ��Ǝv���B |
||||||||||
|
���Q�[���`���̃W�O�U�O�h���u������ �m�R�[�`���J�������H�Q�[���`���̃h���u�������́A�q���̋����S�����܂�����悤�ɏo���Ă��āA�N�����ꐶ�������̂ŁA��N��6�N���̗��K�ł��悭�g���Ă����B����𑁁X��1�N���ɂ������Ă݂��B�h���u�������Ƃ����Ă��A�ŏ��Ɍl��ŗ\����s���A���̌��ʂŌ��܂����`�[���őR����s���A�Ƃ����Q�i�K���ɂȂ��Ă���̂ŁA���������܂Ŏq���B�̏W���͓͂r�₦�Ȃ��B �@�܂��A�n�߂�O�Ɉȉ��̂悤�ɃR�[�����Q����ׂ�B�l���������ꍇ�͂R��ɂ���B
�A�R�[���̌��Ɏq���B���l���ɂȂ�悤�ɕ�����B�p�ӂ��o����������Ɍl����s�킹��B�h���u���̃��[�g�́A���̐}�̒ʂ�ł���B�O���ƌ���̑傫�ȃR�[�����t�^�[�����āA�Ō�ɉ~�̒��Ń{�[�����~�߂���S�[���ł���B����ł܂����ʂ����߂āA���ʒʂ�ɃR�[���̌��ɕ����Ă����B
�B�l�킪�I�������A���ʂ��l�����ė͂�������x�����ɂȂ�悤�Ƀ`�[���������s���B �Ⴆ�A�P�ʃ`�[���̂Q�ԖځA�R�Ԗڂ��Q�ʃ`�[���̂Q�ԖځA�R�ԖڂƓ���ւ��铙�B �C�e�`�[�����ŏ��Ԃ����߂Ă��炤�B���̍ہA�A���J�[�ɂ̓r�u�X�i�[�b�P���j�����Ă��炤�B �D���x�̓`�[���R�h���u���E�����[���s���B�X�^�[�g�͉~����Ƃ���B�O�̐l���X�^�[�g������A���̐l�͉~�̒��ő҂B�Ō�̃R�[����������Ƃ���Ŏ��̐l�Ƀp�X���Ȃ��ł����B�Ō�̃A���J�[�����́A�~�̒��Ƀ{�[�����~�߂邱�ƂŃS�[���ƂȂ�B �@�������A���̃����[�͂Q���E���h�ŏ�������̂ŁA�P��ڂ̃A���J�[�̓g�b�v�Ƀ{�[����n�����ƂɂȂ�B ���āA���߂Ă̂P�N���͂ǂ����������H�܂��h���u�������܂��o���Ȃ��q���������Ă���̂łǂ����Ǝv��������F�����Ƃ������ƂŕK���ɂ���Ă����B�ŏ��̌l��ł�����x�Z�p���x���̃����N�t�����o���A������l�����ă`�[�������������̂�����t���āA�`�[���R��͐ڐ�ƂȂ����B���Ȏq����l���邾���ł͏��ĂȂ��`�[���Q�[���ł���̂ƁA���Ȏq�ł��������Ď��s����Ǝ��Ԃ������Ȃ��قǒx��Ă��܂��v�f���������Q�[���Ȃ̂ŁA�Ō�܂ŊF��������߂��Ɋ撣��悤���B �����o�[��������D���������ȃ`�[�������ʂ̓��X�g�ƂȂ�A�������`�[���͂��ꂵ�������̂܂o���Ă͂��Ⴂ�ł����B |
||||||||||
|
�E���̗��Ɨ����C���T�C�h�Łu�R���[���A�`�����A�`�����v �U�����ŏЉ���u�B���̗��ʼn��Ƀ{�[�������v�́A���r���[�ȓ��e���������A����͖{���̂����܂Ői�߂��B���Ȃ킿�A �@�@�O��F�E���̗��Ń{�[�������ɂ��낪���A�����̃C���T�C�h�Ŏ~�߂�B�i���̌�t���s���j �@�@����F�E���̗��Ń{�[�������ɂ��낪���A�����ˉE���̏��ɃC���T�C�h�Ń^�b�`����B���̍� �@�@�@�@�@�@�u�R���[���A�`�����A�`�����v�Ƃ����|�����i�m�R�[�`�J���j��������ƕ�����₷���B �@�@�@�@�@�@������E��������ƌ��݂ɍs���B �E�������̌���ʂ� �@�S�C�T�C�U���Ƒ�3�����o�߂����̂ŁA�V�����{�[���^�b�`��lj������B����́A �@�@�@�g�E���̗��ň������{�[�����A�E���̃C���T�C�h�ŗ������i�����j�̌���ʂ��B �ʂ�����A�̂��{�[���̂��낪���������i�����j�Ɍ�����h �Ƃ������̂ł���B����́A���̗��ň����̂ƃC���T�C�h�ŕ�����ς���Ƃ����Q�̓�����A�A�����čs��˂Ȃ�Ȃ��B���₭���{���������Ƃ���A�N��������������Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA����������Č������B����ƊF�^�������o�����B���ɂ��܂��ł������m�F���Ă��炨���Ǝv���āu�����H�v�u�����H�v�Ǝ��X�ɃR�[�`�ɕ����Ă���B�������A�w�ǂ̎q�͘A���Z���o���Ȃ��悤�������B���炭�ʎw�������Ă�����A���l��������肾���o����悤�ɂȂ��Ă����B�{�[���^�b�`�͏����̃t�F�C���g�̏K�����ɂ��ōs���Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ���l�ł�������̂������B�������A���̊w�N�Ŋo���Ă��܂��A��ł������y�ɂȂ�͂��B�܂��A���O����o���Ȃ����̂Ƃ�����߂Ă��܂��q�͂��Ȃ����A���ł������������Đ^����������̂ŁA�����������D�̃`�����X���Ǝv���B���������̗͂�Ȃ��Z�́A�ł��邾�����������Ɋo��������\�肾�B |
||||||||||
|
�@�g���b�v�Ƃ́A�ȒP�Ɍ����Ύ����̏��ɓ]�����Ă������A����ł����{�[�����A�y�Ɏ��̃v���[���ł���悤�ɃR���g���[�����邱�Ƃł���B�q���̃T�b�J�[�̋Z�p���x�����ǂ�Ȃ��̂��c������ɂ́A�h���u����V���[�g�Ȃǂ�������́A�������̃g���b�v�̎d�����������������B����قNjZ�p�I�ɓ���v�f���܂�ł���B �@��w�N�̎q�ɂƂ��ē��ɓ���̂́A����ł����{�[����A�傫���͂���ł����{�[���̏����ł���B���̗��R�́A���Ԏ��͂��܂����܂��@�\���Ă��Ȃ��̂ŁA�X�s�[�h�̂���{�[��������ł���{�[���ɂ́A�ڂŊ��S�ɒǐ��ł��Ȃ����炾�Ǝv����B�����ŁA�P�N���ɂ͎��̗l�ȋɂ߂Ċ�b�I�ȃg���b�v���狳���邱�Ƃɂ����B �@���̃g���b�v �A�C���X�e�b�v�̃g���b�v�i�N�b�V�����E�R���g���[���j �B�C���T�C�h�̃g���b�v�i�E�F�b�W�E�R���g���[���j �g���b�v�̗��K�́A���̓{�[�����t�e�B���O��C���T�C�h�L�b�N�̗��K�ŁA���ӎ��ɂ�点�Ă͂���̂����A�����������K�ł͏o���Ȃ����e�ɍi�����B���̗��K�������悢���Ƃ����ƁA�܂���ꂪ�o�Ă��Ȃ����K�J�n����̎��ԑсA���Ȃ킿�u�{�[�����t�e�B���O�̗��K�v�i�U�����ŏЉ�j�̌�ɂ��Ƃ���Ȃ�s���悤���B �@���̃g���b�v �@�u��œ����グ���{�[�����A���ɓ��ĂĂ����Œ͂�ł��������B�v�ƌ����Č��{��������B���̎��A�{�[����������u�ԂɁA�����������ɂ��炵�čs�����Ƃ��K�v���B�������炵�Ď��s����q�́A�قƂ�ǂ������������Ă��Ȃ������B���ƈꏏ�ɂ����܂Ō��ɂ��炵�Ă��܂��B���������q�ɂ͂�͂�A���������������������������������悢�B�����Ă��o���Ȃ��q�ɂ́u�����̃w�\�����Ă��Ȃ����B�v�ƌ����ƕ�����₷�������m��Ȃ��B���ꂪ�o�����q�ɂ́A�u���Ńg���b�v������A�g�����h�܂��͑��ɓ��ĂĂ����Œ͂�ł��������v�ƌ����Ă�点��Ƃ悢�B �A�C���X�e�b�v�̃g���b�v�i�N�b�V�����E�R���g���[���j �@�u��œ����グ���{�[�����A�C���X�e�b�v�ɓ��ĂāA�{�[�����͂��܂Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B�v�ƌ����Č��{��������B�{�[�����t�e�B���O�̗��K�ł́A�{�[�����y���R���Ă����B���������̏ꍇ�̓{�[���̗����ɍ��킹�đ����y�������Ƃ����A�S���t�̂��Ƃ����Ȃ�������Ȃ��B�R�[�`�����̂����Ă���q�������͊F�A�{�[�����قƂ�ǂ͂��܂Ȃ��̂����ĕs�v�c���邪�A��̍b�œ������Ƃ����Ɣ[������悤���B���p��ł͑��̍b���N�b�V�����̂悤�ɂ���̂ŃN�b�V�����E�R���g���[���Ƃ����B�����͂��܂��o���Ȃ��������A���������������Ă�点���̂ŁA���̂��������ł���͂�ł���Ǝv���B �B�C���T�C�h�̃g���b�v�i�E�F�b�W�E�R���g���[���j ���̃g���b�v�́A�傫���͂��{�[����A�ӂ�����ŗ��Ėڂ̑O�Ńo�E���h�������ȃ{�[�����g���b�v����̂ɕ֗����B�����́A�{�[�����n�ʂɗ����Ēe�ޏu�ԂɃ{�[���̒[�ɑ��̃C���T�C�h�������čs�������ł���B�e�ރ{�[�����A�ォ�牟�������ă{�[���̐������E���̂͂��Ȃ�������{�[���̃T�C�h���肬��ɓ��Ă�ƁA�{�[�����͂������̕��t�X�s�����������āA���ꂾ���Ń{�[���͒e�ސ������Ȃ����Ă��܂�����s�v�c���B���̃g���b�v���K�́A�{���͒N���ɓ����Ă�������{�[���̕������₷���B�������A�P�N�����m�ł�点��Ƃ܂����܂��������Ȃ��̂ŗ��K�ɂȂ�Ȃ��B�ŏ��́A�����Ă�������{�[���Ō��{��������B���Ɏ����ŏ�ɓ����グ���{�[�����g���b�v����Ƃ����������B�u�����A����Ă݂悤�v�ƌ����ĉ�������{��������ƊF�^�����������B�������w�ǂ̎q�͂͂��{�[���ɐG����Ȃ����A�ォ�牟�������邩�̂ǂ��炩�ł������B���������q�̂��ɂ����ĉ����{���݂��Ă�����A���X�o����q���łĂ����B��������������Ă����A��Ŋy�Ƀ{�[���������i�g���b�v�j�ł���悤�ɂȂ�Ǝv���B
�o�E���h����{�[���̃T�C�h���肬��ɑ��̃C���T�C�h�������Ă����̂��R�c�B�n�ʂɗ�����O�ɐG���Ă͂����Ȃ��B �n�ʂ���{�[�������ˏオ�鏊�ɁA���̃C���T�C�h�ŏォ�牺�ɃJ�b�g�C���ɓ��Ă�ƁA�{�[���ɋt�X�s����������A���R�ƃ{�[���̐������Ȃ��Ȃ�B |