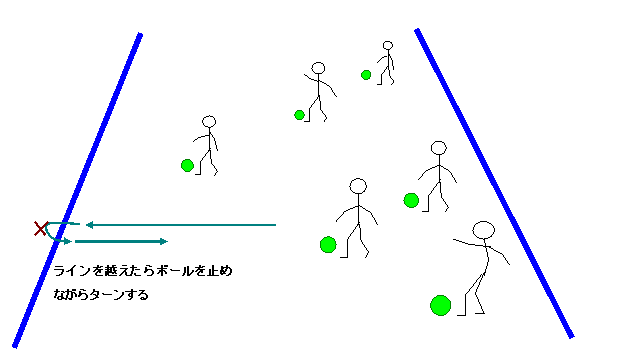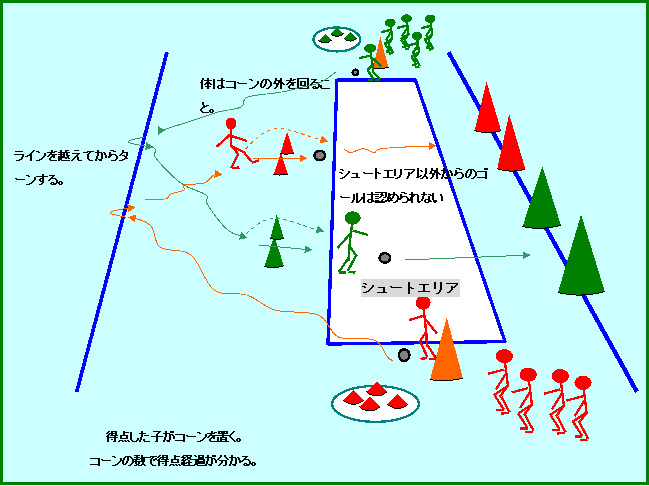|
�P�N���̗��K���e�@ �Q�O�O�P�N�X�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쐬�F�����P�R�N�X���P�U��(Rev.�`)�@ |
|
�ځ@�@�@�� ���^�[�� |
|
�{�[�����t�e�B���O�ɂ��Ă�6�����ŏЉ�����A�厖�Ȋ�b���K�Ȃ̂ŗ��K�J�n���ɂ͕K�����悤�ɂ��Ă���B����܂ł́A�g�����h�A�C���X�e�b�v�A���̃��t�e�B���O�����ꂼ��ʃ��j���[�Ƃ��āA�Ɨ������Ă���Ă����B�����n�߂Ă���5�����o�߂��Ă���A���낻��}���l�������Ă����̂ŁA8�����{����͉��p�҂ɓ������B�}���l�����Ŕj�̎�i�Ƃ��ẮA�g�A�������h�Ɓg�Ⴄ���ʂŘA�����čs���h��2���ڂ��������B �E�g�����h�ƃC���X�e�b�v�̑g�ݍ��킹 �@�g�����h�̃��t�e�B���O���Œ�1�A���v��20���点��B���̌�ɁA�g�����h�ŘA��3��ȏ�ɒ��킳����B�u�o���邾���A�E�A���A�E�ƌ��݂ɂ���Ă݂悤�B�o���Ȃ���Η����������ł��n�j�v�Ƃ����B���̎��A�u�A��3��ȏ�ł����炻�̉������Ă��������B�v�ƌ����Ƃ���ɐ���オ��B �A�u�g�����h�ł�����A�C���X�e�b�v�ɓ��Ă��邩�ȁH�v�ƌ��{���������B���炭����ƁA�R���̂Q�ȏ�̎q���o�����悤�Ȃ̂ŁA�u���́A�C���X�e�b�v����g�����h�͏o���邩�ȁH�v�ƌ����ċt�p�^�[������点�Ă݂��B�����悤�����A��̕�����������悤�ŁA�܂��R���̂P�����܂Ƃ��ɏo���Ȃ��B �E���ƃC���X�e�b�v�̑g�ݍ��킹 �@���̃��t�e�B���O�́A���O�ɕK������Ŏ������{�|���ɂP�O�Ă����Ă���B���̎��Ɂu�{�[���̖D���ڂ����Ă�邱�Ɓv�ƕK�������B�ڂ��ł��邾���Ԃ�Ȃ��悤�ɁA������K���Â��Ă����Ȃ��ƌ�ł̏C��������Ȃ邩�炾�B���̌�ɁA�����œ����グ���{�[�����P�����t�e�B���O������B���̎����A�u�{�[����������Ƃ��ɖD���ڂ������邩�ȁH�v�Ƃ����������āA�{�[������ڂ����炳���Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B��l�ł��Ȃ��Ȃ�������u�Ԃ܂Ŗڂ��J���Ă��邱�Ƃ͓�����A�������ł���点������Ώo����悤�ɂȂ���̂ł���B �A���̌オ���p���K�ɂȂ�B�u�����A���x�͓��ɓ��Ă��{�[���𑫂��g�����h�ŐG��邩�ȁH�v�ƌ����Č��{���������B����́A�����ȏオ�o�����B����ɁA�u�o�����q�́A�����������ƘA���ł���Ă݂悤�v�Ƃ�����Ɖۑ���������Ƃ���قƂ�ǂ��o���Ȃ��������A�ۑ���N���A�����q��V���Ȃ��悤�ɁA������Ƃ����e��ς��ďW�����ێ�������悤�ɂ��Ă���B �E���̕��ʁi�A�E�g�T�C�h�A���j�ւ̒��� �@�@�@�u���́A�A�E�g�T�C�h�ɓ��ĂĂ݂悤�v�ƌ����ĉE�������ɏグ�ăA�E�g�T�C�h�Ƀ{�[����u���ē��Ă�Ƃ���������Ă��猩�{���������B�����ɑS�����^�������������B�F���Ă�ӏ��͂킩�����悤�������B�u����ł́A�o�����q�̓A�E�g�T�C�h�ɓ��Ă���A�C���X�e�b�v�ɓ��ĂĂ��������v�ƘA��2��ɒ��킳�����B����͂�����Ɠ���悤�ŁA�R���̂P�ʂ����ł��Ȃ������B �@�@�A�u���́A��ŏ�ɓ������{�[�������ɓ��ĂĂ݂悤�B���Ă���́A���̂ǂ����ɂ�����Ă��������B�v�ƌ����Č��{��������ƁA�F�^�������������B������o�����q�̓A�E�g�T�C�h�Ɠ����ʂ̐l���������B �@�@�@�Ƃɂ����A�̗͂͗v��Ȃ����A�Z�p�I�ɓ�����Ȃ��̂́A���������ɂ�点���̂ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B��点�Ă݂ďo��������������́B�傫���Ȃ��Ă���ł́A�o����̂ɂ����Ǝ��Ԃ������邩������Ȃ��B����������`�����X���ǂ����́A��点�Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B |
|
�{�[���^�b�`�����l�A���p�҂�������悤�ɂ����B���K�̖ړI��������x�������߂��B�P�N���ɂ͂܂����Ȃ����A�u����ȗ��K����ĉ��̖��ɗ��́H�v�ƌ����q������B�����������Ɏv���n�߂��q�́A����ȏ�͂��܂��Ȃ�Ȃ��B���������q�́A�R�[�`�Ɍ���ꂽ�Ƃ���ɑ����������ŁA�u�������̗��K���I���Ȃ����ȁ[�v�Ƃ������C�͂������ƂȂ��`����Ă�����̂��B����ȕ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���K�ɂ͉�������Ӗ������邱�Ƃ�����ƂȂ������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��B �E�������݂̃C���T�C�h�^�b�` �@�ʏ�͗����C���T�C�h�Ō��݂Ƀ`�����`�����Ƃ����Ƃ��������̒P���ȗ��K�����A�����������Ə����^���I�ɂ�点����A���p�҂Ɉڂ�B �@�@���p�҂́A������g���đO�ɂ���G�����K��������Ƃ������́B���̎q�̂܂�O�܂ōs���āA�C���T�C�h�^�b�`�ł��̎q�̉��ɏo���A�t���C���T�C�h�ʼn��ɗ������{�[������������悤�ɂ��Ĕ���������́B�T�b�J�[�̐��p��ł́g�_�u���^�b�`�h�Ƃ����Z�p�ł���B �@�@�u�����A����ł͗����Ō��݂Ƀ`�����`�����ƃ^�b�`���Ȃ���V�l���������܂��B�R�[�`���Ă����܂��܂���B�V�l������������Ă��������B�N���P�ԂɏI��邩�ȁH�N�����X�g�ɂȂ邩�ȁH��[���A�X�^�[�g�I�v�ƌ����đS���ɋ�����������B �E�Б������ŃC���T�C�h�^�A�E�g�T�C�h�^�b�` �@�@���́A�����������ŘA���I�Ƀ^�b�`������K����点��B����Ă�����A�R�[�`����u�C���A�A�E�g�A�C���A�A�E�g�v�ƌ����Ȃ�����ۂɉE�������ŘA���I�Ƀ{�[�����^�b�`���Ȃ���q���B�����{�������B �@�@�u�����A���x�͕Б��̃C���T�C�h�A�A�E�g�T�C�h�Ō��݂Ƀ`�����`�����ƃ^�b�`���Ȃ���V�l���������܂��B�R�[�`���Ă����܂��܂���B�V�l������������Ă��������B�N���P�ԂɏI��邩�ȁH�N�����X�g�ɂȂ邩�ȁH��[���X�^�[�g�I�v�ƌ����đS���ɋ�����������B �E�G�̑O�Ń{�[���������Đi�s������ς���i�E���ł���A�E90�x�j �@�@���́A�G�̑O�ɍs���đ��̗��Ń{�[�����������K�Ɉڂ�B��������A�{�[�����X�O�x�J���������i�E���ň�������E�ɂX�O�x�j�ɃC���T�C�h�Ŏ����čs���̂��|�C���g�B���������������̂ɂȂ����܂����̈ʒu�ɖ߂��Ă��܂��q�����邪�A����ł͓G�Ƀ{�[��������Ă��܂��̂ň������Ӗ����Ȃ��Ȃ�B���������q�ɂ͌��{�������Ă����ɏC�������邱�Ƃ��K�v���B �@�@�u���́A���̎q�̑O�܂Ńh���u���ōs������A�{�[���������ĕ�����ς��鋣�������܂��B�V�l�������������Ă��������B�N���P�ԂɏI��邩�ȁH�N�����X�g�ɂȂ邩�ȁH��[���X�^�[�g�I�v�ƌ����đS���ɋ�����������B �@�@���͂�����Ƃ����ω��������Ă݂��B�u���x�͏������[����ς��܂��B���ʂɌ������������玩���̃{�[���������Ď���Ȃ��悤�ɂ���܂ł͑O�Ɠ����ł����A���̎��Ɍ��������đ���̃{�[�����^�b�`���Ă��������B���̎q�̃{�[�����V�l���^�b�`����������Ă��������B�K�����ʂ��珟�����邱�ƁB��납��s���ďR��̂̓_���ł��B�N���P�ԂɏI��邩�ȁH�N�����X�g�ɂȂ邩�ȁH��[���A�X�^�[�g�I�v�ƌ����āA�S���ɋ�����������B |
|
���^�[�� �@�Ȃ�ł��ꐶ������点��ɂ́A����������̂���Ԃł���B�����������Ĉꐶ�����ɂȂ����Ƃ���ŁA�o���Ȃ��q�����W���I�ɓ��P������ƁA��葁���Z�p���g�ɂ��悤���B �@�^�[���̗��K��ڂ͎��̂R�Ƃ����B �@�C���T�C�h�E�^�[�� �@�@�@�O�ɓ]�����Ă���{�[������肱��ŃC���T�C�h�Ń{�[�����X�g�b�v���Ȃ���^�[������B�E���ł��ꍇ�́A���v�Ɣ��Ύ���ʼn�荞�ށB �A�A�E�g�T�C�h�E�^�[�� �@�@�@�O�ɓ]�����Ă���{�[������肱��ŃA�E�g�T�C�h�Ń{�[�����X�g�b�v���Ȃ���^�[������B �@�@�E���ł��ꍇ�́A���v����ʼn�荞�ނ��A���̂ܐ悪�ł��邾���߂�����������悤�ɂ���̂��|�C���g�B�ܐ悪�ߑO�������Ă���ƃ{�[���͂��܂��X�g�b�v�o���Ȃ��B �B���̗��̃^�[�� �@�@����͂V�����A�ŏЉ�����A�܂��������t�ɂȂ��Ă��܂��q�����l�����̂Ō��{�����������A�Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B�����ŁA�E�����̎q�ɂ́u�E���Ń{�[�����������獶�����Ă��������B�v�ƌ����Ă�点���Ƃ���A���x�͍���肪����Ȃ�ł���悤�ɂȂ����B �u�����A�ד��m�Ԃ���Ȃ��悤�Ƀ��C���Ɉ��ɕ���ł��������B���}��������A��ĂɃX�^�[�g���܂��B�h���u�������Č��������̃��C�����z������^�[�������Ă��������B�ŏ��͂��ׂăC���T�C�h�Ń^�[�������Ă��������B�Q����������A�Ō�͏o���������C���Ƀ{�[�����~�߂Ă��������B�P���A�Q���A�R���ƃ��X�g���N�ɂȂ邩�����ł��B�v�ƃ��[�������������A �u�����̑O�ɂ�����Ƃ����C���T�C�h�E�^�[���̗��K������Ă݂܂��傤�B�S���ł��邩�ȁH�v�ƌ����ď������K�����ďo���Ȃ��q�ɂ����������Ă��B�������o������A�u��[���A�X�^�[�g�v�ƌ����Ďn�߂�B �@�I������瓯�l�̎菇�ŁA�A�̃A�E�g�T�C�h�E�^�[���A�B�̑��̗��̃^�[���̏��ɍs���B
|
|
�@�V�����ŏЉ���g�P�P�̃V���[�g�Q�[���h�́A�h���u���œG�����킵�Ă���V���[�g�ł���̂ŁA�q���B�ɂƂ��Ă͊y�������K�ɂȂ��Ă���悤���B��������ɂ͖�肪���邱�Ƃ��킩�����B�V���[�g������܂łɂ����玞�Ԃ������Ă��悢���炾�B�T�b�J�[�ł͂P�b�ł��������f���Ă��₭�v���[�����邱�Ƃ��ɂ߂đ厖���B�������Ȃ��ƁA����I�ȃ`�����X�𐏏��Ŏ����Ă��܂�����ł���B �����ŏЉ����K�́A�h���u������V���[�g�Ɏ���܂ł��A�ł��邾�������v���[����悤�ɏK���Â��邱�ƁA��ړI�Ƃ����B�������A�P���Ńn�[�h�ȓ��e�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�ȉ��̂Q�_����K�̏����ɓ���邱�Ƃ͂���܂łƓ������B 1. �����������͂����肵�Ă��邱�ƁB 2. ���_���������Ƃ��A�����̃`�[���̏����ɍv�����邱�ƁB ���̂��߂ɁA���_�͎����B�ł��A���`�[���̓��_�o�߂��S���ɕ�����悤�ɂ���B �E�`�[������ �܂��S�����W�������Ĉ��ɕ�����B�u�O���珇�Ԃɔԍ��������Ă��������B�ԍ����������q�͂����ɍ����Ă��������v�B��������ƁA�����܂����Ԃ����܂��Ă��܂��B�����ł��Ƃ���1�Q�l������A�u�Q�C�S�C�U�C�W�C�P�O�A�P�Q�Ԃ̎q�̓[�b�P�������Ă��������B�v�Ƃ����ă[�b�P������������B �E���� �~�j�S�[�����Q���B�^�[�����郉�C���A�V���[�g����͈͂��������C���������B�h���u���R�[�X�̓r���ɃR�[�����Q���u���B�݂��̃S�[���̘e�Ɉ��ɕ�����B�X�^�[�g�n�_�ɑ傫�ȃR�[����u���B
�E���[������ ���Ƀ��[�����������B �u�e�`�[�������l���o�ď������܂��B�R�[�`�̍��}�œ����ɃX�^�[�g���A�������̃��C�����z���Ă���߂��ė��ăV���[�g�����܂��B�����ƈ���āA��ɃS�[���ɓ��ꂽ���̏����Ƃ��܂��B�r���ɃR�[��������܂����A�K�����̊ԂɃ{�[����ʂ��A�̂̓R�[���̊O��������Ă��Ă��������B���̌�V���[�g�����܂����A�V���[�g���łĂ�̂͂��̃��C���Ƃ��̃��C���̊Ԃ����ł��B�����͂ǂ��炩���S�[���ɓ����܂łȂ̂ŁA���s���ăS�[�����C�����z���Ă���蒼�����ł��܂��B���_������A�����ȃR�[���������i�����ŏ��������_�G���A�j�ɓ���Ă��������B�[�b�P���`�[���͐Ԃ��R�[���A�[�b�P�������`�[���͗ΐF�̃R�[���ł��B���10�_������`�[���������ł��B�X�^�[�g���鎞�́A�K���R�[����Ў�ŐG���Ă��邱�ƁB�v�ƌ����Ă���n�߂�B �E���̗��K�Ɋ܂܂�Ă��邱�� �@���̗��K�ɂ́A�T�b�J�[�ő厖�Ǝv����v�f�����R�Ɛg�ɂ��悤�Ɏd�g�܂�Ă���B 1. �����V���[�g��łƂ��Ƃ��āA���R�ƍŒZ�����̃h���u��������悤�ɂȂ�B 2. �����V���[�g��łƂ��Ƃ��āA���₭�^�[��������B 3. �R�[���̊ԂɃ{�[����ʂ��̂́g�܂������h�̗��K�����A����ł̓{�[����ʂ�����ɐl�����킷���Ƃ��K�v�ł���A�ӎ��I�ɃR�[���̊O������点�āA����Ŗ𗧂悤�ɂ��Ă���B 4. �����V���[�g��łƂ��Ƃ��āA�܂������̌�_�b�V��������B 5. �V���[�g�G���A��݂������ƂŁA�{�[���������̑̂��痣��Ȃ��h���u��������悤�ɂȂ�B�ނ�݂ɉ�������R��Ȃ��Ȃ�B�܂��A�S�[���ɋ߂Â��߂��Ă���̃V���[�g�͖����ɂ��Ăł��邾�����߂ɃV���[�g��S�|�������Ă���B 6. �V���[�g�����s���Ă��A���肪�܂��S�[���ɓ���Ă��Ȃ�������S�͂Ŏ����Ń{�[�������ɂ����Ă�蒼���@���^���Ă���B���ʂ̃V���[�g���K�ł́A�~�X�������_�Ŏ~�߂Ă��܂��Ƃ��������K�������B |
|
�x�e�O�̉ۑ�ɂ��ẮA�U�����ŏЉ���B �ȉ��ɍŋߎ��{���Ă�����̂��������Љ��B 1. ��œ����グ���{�[�����w�f�B���O�őO�ɗ��Ƃ��A������V���[�g����B 2. ��œ����グ���{�[�������őO�ɗ��Ƃ��A������V���[�g����B 3. �g�����h�Ń��t�e�B���O���A�{�[���𗎂Ƃ����ɃV���[�g����B 4. �W�����v�����i�������ɂ���j��ԂŃV���[�g������B�E������������A�E���œ��ݐ�A������O�ɏグ�Ĕ��������ĉE���̃C���X�e�b�v�ɓ��Ă�B����͂W���������ɃR�[�`�̂�������Ƃ����悤���܂˂łł����悤���B���{��������̂���Ԃł���B 5. ��œ����グ���{�[�����o�b�N�w�b�h�ŃS�[���ɂ����B�����͂P���ʁB 6. ���̋�������p���g�L�b�N�ŃS�[�����C�����z����B |