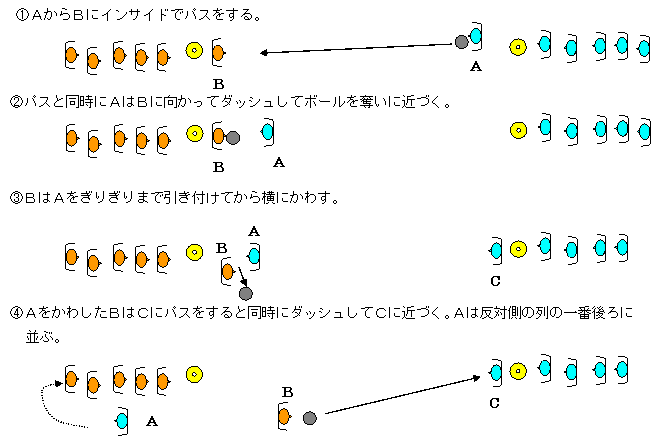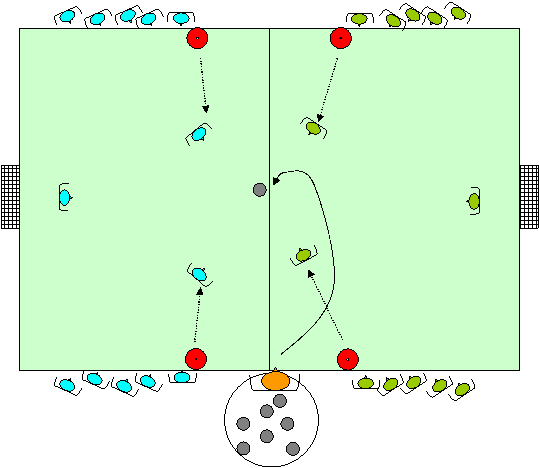|
�R�N���̗��K���e�@ �Q�O�O�R�N�T�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쐬�F�����P�T�N�T���Q�S���@ |
|||
|
�ځ@�@�@�� |
|||
|
�����ʂ��痈��G�����ɂ��킷 �������ł͏ꏊ���\���m�ۂ��ł��Ȃ����Ƃ������B�����������ɂ́A�V�`�P�O���ʂ̋��������Ƃ���Ƀ}�[�J�[��u���Ă��ꂼ��̃}�[�J�[�̌���1��ɕ����Ă��낢��Ȋ�{���K�������Ă���B ����́A���ʂ��痈��G�����ɂ��킷���K������Ă݂��B
���K�̃|�C���g �P�D�p�X�A���h�S�[�̓O�� ���̎q�̓p�X������{�[���̍s�������Ă��܂��B�`�ɂ̓p�X������_�b�V�����Ăa�ɋ߂Â�����B�p�X�A���h�S�[���������B����ɂa�ɋ߂Â����ɔ��Α��̗�̌��ɒ��ڍs���Ă��܂��q���łĂ���̂ŗv���ӂ��B �Q�D�g���b�v����u�Ԃ�_�킹�� �`�ɂ͐^�������S�͂ła�Ɍ������ă{�[�������ɍs������B���ɂ��킷�Ƃ�����{���K�Ȃ̂Ŏn�߂��烏���T�C�h�J�b�g�̂悤�ȉ�荞�ރ{�[���ւ̊��͂����Ȃ��ق����ǂ��B�������������͑��肪�P�O�O�����ɂ��킹��悤�ɂȂ������_�ł���B�܂��͂a�܂ł̍ŒZ������S�͂ŋ߂Â����Ăa���g���b�v����u�Ԃ�_�킹�������悢�B �R�D��������肬��܂ň����t���Ă��牡�ɂ��킷 �@�`���܂��߂Â��Ȃ������ɎߑO�Ƀ{�[�����o���Ă��܂��q���o�Ă���B����ł͂`�����킹���Ƀ{�[����G���Ă��܂��m���������Ȃ�B���肬��܂ł`�������t���Ă���ł���A������Ɖ��Ƀ{�[�����o�������ł`�����킹��͂����B �S�D�`�̏�����1�� ��x���킳�ꂽ�`���������a�̃{�[����D���ɂ����ƌ��ő҂��Ă���q�̗��K���ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�`�̃{�[����D���ɂ�����͂P��܂łƂ���B �T�D���킵����͂����Ƀp�X �@�`�����킵����A�a�ɂ͂����Ƀp�X��������悤�Ɍ����B�h���u���������Ă��܂��Ƃb�܂ł̃p�X�̋������Z���Ȃ�A�b�ɂƂ��Ă͂��܂��Ă���a�����킷�̂�����Ȃ邩�炾�B�܂��A�����ł͓G�����킵����̓h���u���ł͂Ȃ��p�X���ɍl�������������悢�̂ł��̗��K�ɂ��Ȃ��Ă���B ���� �܂����̗��K�̂����������ł��Ȃ��q���܂����Ă���u���b�N�ł́A�܂Ƃ��ȗ��K�ɂȂ�Ȃ������B�܂��A�p�X���C���T�C�h�łł��Ȃ��B�p�X�������B�p�X�����̂ɁA����Ȃ��B�����Ă��{�[�������ɍs���Ȃ��B�{�[���������Ƀp�X���ꂽ��O�֏R���Ă��܂��B���킵���̂Ƀp�X�����Ƀh���u���ő���̂Ƃ���܂ł����Ă��܂��B�P�l�ł����������q�������炱�̗��K�͑������Ȃ��̂ŁA���X���K���~�߂Ăł��Ȃ��q�Ɍʎw���������B ��b���������肵�Ă���q���W�܂����u���b�N�ł́A�����ӂ����Ă��邤���ɔ����ȏオ�ł���悤�ɂȂ����B���킷�^�C�~���O���A����d�˂閈�ɗv�̂Ă����B�����~�j�Q�[���Ő��ʂ���˂�����ł��鑊������ɂ��킹��q�������Ă����̂́A���̗��K�̐��ʂł͂Ȃ����Ǝv���B |
|||
|
���p���g�L�b�N����Q�Q�̋��荇�� �@�ȉ��͍ŋ߂̌�����������K�����ł̔��ȓ_�ł���B �@�������̏��������܂��ł��Ȃ��B�ڑ�������ē�����z���Ă��܂����A�g���b�v���Ă��{�[�����̂���傫������Ă��܂��B �A�傫�ȃG���A�ɂȂ�����f�͂��݂�A�����オ�����{�[���֊��X�s�[�h���x���Ȃ�B�ŏ����猩�Ă��邾���ŋߊ�낤�Ƃ��Ȃ��q������B �B���������̃h���u���˔j���ł��Ȃ��B�r���ŗ͐s���Ď���邩�A�����R�肷���đ���̃S�[���L�b�N�ɂȂ��Ă��܂��B �C�傫�ȃG���A�ŃI�[�v���X�y�[�X�ɂ��閡�����������Ȃ��B�䂦�Ƀt���[�Ȗ����Ƀp�X�i���ɉ������j���o�����Ƃ��o���Ȃ��B ����́A�����̖����ɉ��P���悤�Ɖ��̐}�Ɏ��������K������Ă݂��B ���̗��K�͂����Ȃ���̂ł͂Ȃ��A�������K�Ƃ��Ắu1�P�̋��荇�����V���[�g�v�����炭����āA�P��1�̏����������܂��Ă���ɂ����B ���K���� �S�����ɕ����A�Е��̃`�[���Ƀr�u�X��t��������B�n�[�t�R�[�g�Ƀ~�j�S�[�����Q�u���A�S�[���L�[�p�[���݂��̃`�[������P�l���o���B�e�`�[��������ɂQ�ɕ����ă^�b�`���C���Ɍ��������킹�ɂȂ�悤�ɕ�����B����̃^�b�`���C���ɉ~������ă{�[�����W�߂�����B ���� �@�u������p���g�L�b�N�ŏグ���{�[�����A�Q�Q�ŋ��荇���ăV���[�g�����Ă��������B���ꂼ��̏ꏊ����P�����A�e�`�[���Q�l���̂Q�Q�̋��荇���ł��B�L�[�p�[�����荇���ɎQ�����Ă����܂��܂��A�L�[�p�[�̓V���[�g���ł��܂���B�܂��A�n�[�t���C������o���܂���B�{�[�������C���̊O�ɏo������������Ƃ��܂��B�S�[�������܂����`�[���͓��_�ɋL�����Ă��������B�������I�������{�[���͕K���~�̒��ɖ߂��Ă��������B����ł́A�e��̐擪�̎q�͎���グ�Ă��������B�v ���� �@�����オ�����{�[���ɑ��ĂƂ肠���������n�_�ɑ��肱�ފ��o���g�ɂ��Ă���B�ǂ��ł͂��ނ��ڑ������Ȃ��q�ł�������Ă��邤���Ɍ덷�����Ȃ��Ȃ��Ă���B �A�L�[�p�[�ɂȂ����q�́A�҂��Ă��鎞�ԑт��Ȃ��A���ł��̃Q�[���ɎQ���ł���̂ŁA�D��ł��B�������n�[�t���C���܂Ŏ����̈ӎv�œ�����̂ŁA�L���͈͂ł̃L�[�p�[�̍U���������o���o����������B �B�S�[�������߂�܂ł̑I��������������A���ۂ̎����ɋ߂����o��g�ɂ�����B���������̃h���u���˔j����V���[�g�A�t���[�Ȗ����ւ̃p�X�A�t���[�Ȉʒu�Ń{�[�������炤�����A�L�[�p�[�̓��������ăV���[�g����A�ȂǂȂǁB
|