| 迷!?ルポライターとJR近畿オーナーがめぐる、 JR近畿京都線の探訪記 |
| 迷!?ルポライターとJR近畿オーナーがめぐる、 JR近畿京都線の探訪記 |
|
||
| 階段を上がったふたりが入口の自動ドアから中へと入ると、フロントにいた女性がその姿を見つけ、微笑みながらカウンターを回って出てきました。 「いらっしゃいませ、オーナー。せっかくのお越しのときに迎えの車がトラックで、申し訳ございませんでした。ほんとにシンたら、肝心なときに役立たずで」 「おお、久しぶりやな、マユコはん。まあまあ、そう言わんでももええがな。車が故障したのはシンちゃんのせいやないやろし…」 女性が雨竜の奥さんと気がついた裏紙は、なんであの雨竜氏にこんなきれいな人が…と、やっかみ気分で見惚れて突っ立っています。 「今日のゲストの裏紙はんや。ダンナの同業者やからサービスしとかんと悪口書かれるで」 オーナーは軽口を叩きながら裏紙を紹介しました。 「あらまあ、怖いこと。裏紙さん、ようこそいらっしゃいませ。お部屋の用意はできておりますので、どうぞ」 「そやな、ひと風呂浴びてから乾杯といきまひょか。マユコはん、ワシはいつもの部屋に勝手に行くよって、裏紙はんを案内したってや」 オーナーは勝手知ったるわが家のように、スタスタと奥へ歩いていきます。 裏紙はマユコについて二階への階段を上がりながら、尋ねました。 「ここにはオーナー専用の部屋があるんですか?」 「ええ、そうですのよ。屋根裏なんですけどね」 「ええっ? 屋根裏って、倉庫みたいじゃないですか。どうしてまたそんなところに?」 「営業している以上、お客さん第一ですのでね。気を使っていらっしゃるんでしょう。でも、その屋根裏がすごい部屋ですの。あとで裏紙さんも招待していただけるでしょうし、ご覧になったら絶対ハマりますわよ」 謎をかけられたような裏紙は怪訝な表情のまま、用意された部屋に着きました。 「お部屋はここですわ。オーナーは1時間後にフロントの横にあるレストランに来られますので、それまでごゆっくりなさってください」 「いや、これはどうも。では、その時間に私も行きますので…」 そして1時間後、風呂で汗を流した裏紙はリラックスした服装に着替え、レストランに現れました。最も奥のボックス席には、十人ほどの女性のグループが、おしゃべりに興じながら食事をしているのが見えます。 「あっ、裏紙さん、こちらへ用意しますので、どうぞおかけください」 ちょうどワゴンで料理を運んできたシンが、裏紙に声をかけました。すぐに白のスェットに着替えたオーナーもやってきて、ガラス張りの壁に沿ったテーブルに、ふたりはつきました。 「あれ? オーナーは荷物を持ってなかったのに、どうしてそんな着替えができたんですか?」 不思議そうに裏紙が聞きました。 「ワシ専用の部屋には、服やらなんやら、生活道具の一部が置いてありますんや。家を追い出されても、いつでも泊まれるちゅうわけですな。アッハッハ」 その会話をニコニコして聞きながら料理を並べ終わったシンが、オーナーに言いました。 「奇多野さんから電話をもらって、いつもの料理を用意しましたが、それでよかったんですよね?」 「おう、それでええんやけど、また奇多やんか。ホンマに早手回しやな。とにかく、ノドが乾いとるんで、早いとこビールを頼むわ」 そこへタイミングよく、生ビールのジョッキをふたつ持ってマユコが来ました。 「さすがはマユコはんや。言わんでも絶妙のタイミングで出てくるがな。さ、とりあえず乾杯といきましょ。取材一日め、ご苦労はんでした。明日もよろしゅうに。ではカンパーイ!」 オーナーと裏紙がジョッキを合わせて一口飲んだところに、乾杯の声を聞きつけたかのように、奥の女性グループの中からすらりとした美人が立ち上がり、こちらへと近づいてきました。 |
| 「こんばんは、オーナー。今日はこちらにお泊りでしたの?」 その声に振り向いたオーナーは、相好を崩して答えました。 「おお、これはこれは、リヤカー先生やないですか。センセもこちらに泊まらはるんでっか?」 (今日は美人によくお目にかかる日だな。でも「リヤカー先生」って、何者だろ?) 裏紙はそう思ってふたりの様子を眺めています。 「その最後の『カ』を伸ばして呼ぶのは、いつまでたっても治りませんわね。今日はね、仕事仲間のテニスサークルの集まりですのよ」 女性は微笑みながら言いました。 「裏紙はん。紹介しときますわ。ウチの顧問弁護士をやってもろてるアサブキ先生です」 オーナーが裏紙にそう言うと、女性はバッグから名刺入れを抜き出し、白魚のような指先で名刺を差し出しました。 「あっ、これはどうも。私はこういう者でして…」 美人に見惚れてしかも名前の謎?を考えていた裏紙は、あわてて名刺を交換し、受け取った女性の名刺をよく見てみると、「弁護士・浅噴 理弥佳」とあります。 「リヤカさんやから親しみを込めて、リヤカー先生ですがな。こないな別嬪さんが弁護士てな堅い仕事してはるんやから、アサブキ先生なんて呼んだら、余計遠い存在になってしまいますからな」 オーナーは生ハムを口に放りこんで賞味した後、裏紙にそう紹介しました。 「アサブキ弁護士といえば、難事件を多数手がけられた有名な女性弁護士がいらっしゃいましたが、まさかその方では?」 裏紙の質問に、リヤカー先生は笑いながら答えます。 「残念ですけど別人ですわ。あちらとは名前が一文字違うだけですので、よく間違えられますのよ」 オーナーも、美人の登場で楽しそうに会話をサカナにビールを飲んでいます。 「そうそう、オーナー。今回はテニスはなさりませんの? 以前の勝負は引き分けのままで、決着がついていませんわよ」 「ありゃ、そうでしたかいな。今日は申し訳ないけどお客さんをつれてますので、また次回ということで…」 「そうですわね。では改めてご都合のよい時に、またご連絡させていただきますわ。それではどうぞごゆっくり」 リヤカー先生はそう言って、元の席に戻っていきました。 「いやあ、今初めて聞きましたが、オーナーはテニスをされるんですか?」 「ハハハ。体型的にはそんなことしそうに見えまへんでっしゃろ。ほんでもこう見えてもね、若いときにもろた日本プロテニス協会の会長はんのハンコ押した認定証みたいなもんは持ってまっせ」 「ええっ?! まさかプロってわけじゃないですよね?」 オーナーの言葉に驚いた裏紙は、思わずテープルに身を乗り出して尋ねました。 「いやいや、そないにたいそうなもんやのうて、『ターゲットテニス15級』ちゅう認定証ですわ」 裏紙は、身を乗り出してテーブルについていた両肘が滑って、ズッコケてしまいました。 「何ですか、そのターゲットテニスって。しかも15級?」 「どっかの新喜劇みたいにそないにコケんでも…。こいつはテニスの腕前を測る基準のひとつで、1級から30級までありますんやで。15級はちょうどど真ん中で、まあ、バリバリの中級ですがな」 オーナーには驚かされてばかりだなと思った裏紙は、ますますこの人物の魅力にとりつかて来ました。 「さあ、食事しながらインタビューでもなんでも受けますよって、聞きたいことがあれば遠慮せんと聞いてや」 ピールの酔いが少しずつ回ってきたオーナーにそう言われ、仕事のことを思い出した裏紙は、オーナーが追加注文したビールで喉を潤し、質問を始めました。 |
| 「今回の取材の趣旨は、お昼時にお話しましたよね」 裏紙は取材ノートを開きながら言いました。 「今日一日ご一緒させて頂いて思ったんですが、古い車輌をたくさん持っていらして、しかも現役で運行されている。それもイベントじゃなくて、足回りなどを最新の機器に交換されたりして通常に使用されていますね。費用も相当かかるでしょうけど、なぜそういう方針なのか、お聞かせ下さい」 「のっけからえらい真面目な話ですな。あれはでんな、ワシの理想というか理念というか…」 オーナーは大きなエビフライを一口かじってから、話し始めました。 「鉄道ちゅうのは公共の交通機関でっさかい、無事故で安全に、しかも時間に正確でなければいかんというの当然ですわな。それでもって大量の人や物の移動という需要を満たすのが社会的な使命ですやろ」 裏紙は要点をメモしながら耳を傾けています。 「しかしそれだけやおまへんな。さすがに自動車に主役はとって代わられたとはいえ、百年以上もこの国の繁栄の基礎を支えてきた物流の基幹産業でっしゃろ? そんな中で先人の方々が、苦労して築き上げて来たもんがたくさんありますわな」 残りのビールを飲みほし追加を注文してから、オーナーは続けます。 「車輌にしたらSLに始まって新幹線まで、技術が培われてきて今や世界での最高水準を維持してますな。そして鉄道では脇役ですけど、トンネルを掘ったり橋を架けたりする土木技術に、最近では列車を制御するエレクトロニクスまで、技術立国の象徴のような存在と言えますやろ、鉄道は」 また新しいジョッキを受け取ったオーナーは、ひと口飲むと話の続きに戻りました。 「ワシに言わしたら、たとえ古くさくなっても産業遺産として後世に伝えていかなアカンと…。せやから古いちゅうだけで車輌をスクラップにしたり、歴史のある建造物を壊すことは、あんまりやりとうないんですわ」 「しかし費用がかかれば採算が取れないでしょう?」 「それはそれ、でんな。ワシも少なからず関西で財を成したんやさかい、これからは関西に恩返しということにしといてもらいまひょか」 右手にペンを持ち左手でビールのジョッキを持ちながら、さらに裏紙は尋ねます。 「はあ、なるほど。でもそれでは、会社全体が博物館になってしまうんじゃないですか?」 「あはは、なかなかオモロい表現でんなあ。けど、それもエエんとちゃいまっか? 確かに大都市圏では難しいことやけど、地方のローカル線に車輌を持っていって、しかも木造の駅舎なんかも集めるかそのまま残すかして、その線まるごと博物館、てなことも考えてまっせ」 オーナーは我が意を得たりという顔で、旨そうにビールを飲んでいます。つられて裏紙もビールが進んでいきます。 「それが実現したら、鉄道ファンやマニアが泣いて喜びそうですね。全国から集まってくるんじゃないですか」 裏紙はそう言ってジョッキを飲みほしました。すると、奥の席で談笑していたリヤカー先生らの女性グループが、食事が済んだらしく、出口の方へと流れてきました。その中からリヤカー先生がこれまたひとりの美女を伴って、こちらの席に近づいてきます。目ざとくその美人を見つけた裏紙は、その女性に見覚えがあるらしく、一瞬驚いたような表情を浮かべてそちらを見ていました。 「お食事中に申し訳ないんですけど、オーナーに紹介しておきたい人が来てますのよ」 リヤカー先生はテーブルの近くまできて、オーナーに声をかけました。 「今度東京のほうから、私の事務所に移っていただいたタカバヤシ弁護士ですわ」 紹介された女性は、「鷹囃子 香魚子」と刷られた名刺をすばやく取り出し、オーナーに渡して挨拶しました。 「すんまへん。今日はこないにくつろいだ格好ですんで、改めてご挨拶に行かせてもらいます。しかし、こりゃまたセンセのところに行く楽しみが増えましたな」 そんなやりとりを裏紙は、ニヤニヤしながら聞いています。 |
| 裏紙の存在に早くから気づいていた鷹囃子弁護士が、笑顔で声をかけました。 「こんなところでお会いするとは思いませんでしたわ。『ニセのウラガミ』さん」 「ハハハ、とんだところで、とんだご挨拶ですね」 ふたりが面識があるということに、オーナーとリヤカー先生は驚いています。興味津々の顔つきでオーナーが尋ねました。 「へぇー、こりゃまた、なんちゅう偶然ですかいな。で、どういうお知り合いでっか?」 「鷹囃子先生は、ホンモノのウラガミ氏の追いかけている鉄道絡みの事件を手がけることが多いんですよ」 「ほう、それはまた、ウチにとっては心強い…」 オーナーは、ビールのジョッキを片手に持ったまま、ふたりを見比べて言いました。 「ホンモノのウラガミ氏はドキュメンタリータッチの週刊誌で事件を追いかけ、鷹囃子先生はドラマ仕立てのテレビ番組で事件の謎解きをする、という関係なんです」 フムフムとうなづきながら聞いているオーナーに、裏紙が続けます。 「実は私、先生のお仕事ぶりを取材させていただいたことがあるんですが、その時にホンモノ氏と同姓同名であることが知られまして…。それからは『ニセのウラガミ』と呼ばれているという訳なんです」 「そうでしたんか。ワシも、最初ウラガミちゅう記者さんからの取材やと聞いて、ホンモノのほうと勘違いしましたからな」 「まあ、そうでしたの。でも『ニセモノ』とはあまり人聞きがよくありませんこと?」 リヤカー先生も横から、会話に加わってきました。 「いえいえ、ホンモノ氏は私なんかよりはるかに有名ですから…。そのニセモノを売りにして取材のきっかけを掴むとこもありますのでね」 「あらまあ、なかなか商売がお上手ですわね」 そう言って笑ったリヤカー先生は、思い出したようにオーナーに尋ねました。 「そうそう、私達はカラオケルームをお借りしているんですけど、後でいらっしゃいません? ぜひともオーナーの美声を皆さんにお披露目して頂きたいのですけど…」 「おや? オーナーはカラオケがうまいんですか? とてもそうは見えませんよ」 また知られざるオーナーの特技に驚かされた裏紙は、思わず口走ってしまいました。 「こう見えてもね、谷村新司の『三都物語』を歌わせたら、プロに勝るとも劣らない絶品ですのよ」 「センセ、『こう見えても』は余計ですけどなあ。アッハッハッ!」 ビールのジョッキが空いたオーナーは、キープしてある焼酎のボトルと水割りセットを出すように頼んでいます。 「いやあ、それって、前にJR西日本がCMで使ってた曲じゃないですか。オーナーがそんな歌を歌うとは、全くもって想像つきませんですよ」 「自分で言うのもなんやけど、レパートリーは結構広いでっせ。ほんでも今日は遠慮させてもらいますわ。お客さんと一緒やさかいね」 「それは残念ですわ。でも初めてのお客様がおみえのときは、いつもあの部屋でお楽しみですものね。それでは次の機会にということで、失礼させて頂きます」 そう言ってリヤカー先生は、鷹囃子先生を促してカラオケルームのほうに消えていきました。リヤカー先生の言葉に、変な胸騒ぎを覚えた裏紙は、オーナーに尋ねました。 「さっきから、部屋の話ばかり聞きますが、いったいどんな部屋なんですか?」 「まあまあ、それは後のお楽しみということで…。あっ、裏紙はん、焼酎はいけまっか? 芋でっけど」 自分の水割りを作ってから、裏紙にも勧めて言いました。 「あっ、頂きます。それより取材がまだ終わってないんで…」 水割りの濃さを確かめるように一口舐めたオーナーは、答えました。 「そうでんな。そしたら食事と一緒に仕事をかたづけてしまいまひょか」 (こりゃ、酔う前に仕事を済ましておかないとついていけないぞ) そう思った裏紙はペンを握り直しました。 |
| 「オーナーの鉄道に対する思い入れは、先ほどお聞きしました。で、その思いの根源というか、源はどこにあるのでしょう?」 オーナーは遠くをみつめるような眼差しで、話し始めます。 「今でこそ一人前のツラしてまっけど、小さい子供の時分は貧乏な工場のハナタレ息子やったんですわ。両親は日曜でも工場で働いとったんで、家族でどこかに出かけるてなことは、夢のまた夢でしたな」 裏紙は意外な話の展開に、聞き耳を立てています。 「旅行なんてしたことはほとんどないし、遠くにお出かけいうたら、盆暮れに父親の実家に行くか、たまに婆さんが自分が好きやった菊人形を見に遊園地に行くときに、いっしよに連れてってもらうぐらいでね」 「菊人形ですか。そういえば昔は、秋になるとどこかの遊園地で必ずやってましたね」 「もちろん家に車なんかないし、そういうときだけ電車に乗れましたんよ。ほんでもって、遊園地に行ったら必ずせがんで乗せてもろたのが、ジェットコースターやメリーゴーランドやのうて、園内一周のミニ鉄道でしたな」 おサルの電車を想像した裏紙に、オーナーは続けます。 「たぶん今頭に浮かべはった、猿が運転してるようなちゃちなもんとちゃいまっせ。軽便鉄道ぐらいの大きさのやつですわ。それで園内を一回りして電車で旅行した気分やったんでしょうな」 「ということは、その頃から鉄道マニアの素質を備えていたわけですか?」 「そうかも知れまへんな。確かにたまにしか乗れん電車に憧れはありましたからなあ。裏紙はんはそんなことはありまへんやろ」 焼酎の水割りをちびりちびりと舐めながら、オーナーは聞きました。 「いや男の子なら誰でも一度は似たような時期があると思いますよ。私も幼い頃は電車の座席の上に昇って窓から景色を見たりしてましたし、近所の友達と電車ごっこなんかもよくしましたしね」 「乗り物に興味を持つことは、ようありまっしゃろけどね。ほんでも大概は、大きなってく途中で別のもんに興味が移って行きますわな」 「そう、そうなんですよねえ。でもまたそこへ帰ってきた男の子が鉄道ファンになるわけでして…」 いつのまにかメインディッシュのステーキを運んできたシンが、横から会話に加わってきます。 「シンちゃんもその口やなあ。で、鉄道ファンになったら、今で言う「撮り鉄」や「乗り鉄」などに分かれていくわけやが、鉄道を愛する気持はみないっしょということやな」 「私もこういう仕事のなかで、鉄道がテーマになれば俄然力が入りますし、鉄道ファンの一員に入れていただけるかと…」 「そういうことですね。裏紙さんも立派な鉄道ファンですよ。ねえ、オーナー」 シンは空いたオーナーのグラスに焼酎と氷を足しながら、言いました。 「子供の頃から鉄道に興味を持ち続けて大人になったんが、今度はその鉄道を動かす側の人になる…。こんなエエこと、ないでっせ。初めにも言いましたけど、まだまだこの世の中、鉄道は必要とされてますからな」 シンから受け取ったグラスを持ったままで、オーナーの言葉には熱がこもってきました。 「そやからこの業界にも、鉄道に情熱を持った新しい世代がどんどんと入ってきて育っていかなあきまへん。鉄道に魅力がのうなって子供が見向きもせんようになったら、それも叶わん夢になってしもて、衰退していきよる。これではいかんと思たんですわ」 |
| 女性団体客の席の後片付けが済んだようで、シンは近くのテーブルからイスを持ってきて二人の脇に座り、話に加わりました。 「鉄道ファンじゃない一般の人たちにとっても、鉄道の旅というのはロマンを感じさせますよね」 「そやな。飛行機は早ようて便利やけど空に上がってしもたら景色は見えへん。船も景色といえば海と島ぐらいですやろ。バスは景色は楽しめまっけど、狭い空間に閉じ込められて車内での自由がないわな。自動車は少人数になるし誰かが運転せんならん。その点、鉄道は景色を眺めるのはもちろん、車内も自由に動けますな」 オーナーはシンという心強い味方を得て、饒舌になって話を続けます。 「それに急ぎの場合なら新幹線や特急があって、のんびりした旅なら鈍行という選択肢もありますやろ」 あとを受けてシンが言いました。 「最近は減ってしまいましたけど、食堂車という楽しみも大きかったですね」 「そうそう、トワイライトやカシオペアが人気なんも、そのへんが理由になっとるかも知れまへん。ちなみにウチでは食堂車やロビーカーは大事に残して走らせとりまっせ」 裏紙はそこまで聞いて、はたと思い当たりました。 「つまりはこういうことですか。旅行の楽しみは現地での見聞や体験がメインでしょうけど、そこに行くまでの移動の途中も楽しみのひとつにしてしまう…」 「なかなかわかってきはったな、裏紙はん。旅における交通機関の役目は『移動』やけれども、その移動の間をも楽しみにしたいちゅうことがワシの考えですわ」 しっかりとここまでの話の内容をノートに書きとめ、さらに裏紙はオーナーに尋ねました。 「もうひとつお聞きしたいのは、今日列車に同乗させてもらって思ったことなんですが、旅客ではない鉄道ファンにも気を配っていらっしゃるようですね。たとえばいわゆる『撮り鉄』のためにお立ち台を整備するとか…」 その問いにオーナーが答える前に、シンが口をはさみます。 「なかには常識外の行動をする者がいるので、鉄道会社からするとあまり歓迎したくないファンもいますね、撮り鉄には。でもオーナーは逆にそんな連中に教育的指導をしているんですよ」 「アハハ、そんなたいそうなもんやないけどなあ。まあ、一部の心ない連中に対しては当然厳しく対処しとりますよ」 芋焼酎をとうとうロックで飲み始めたオーナーは、さらに語ります。 「この問題はマナーや礼儀ということにもつながりますやろ。ウチの取り組みとして、にわかに増えてきとる子供のファンにそれを教えようと、駅や撮影ポイントにはOBやボランティアの協力で指導係が常駐して、ついでに撮り方のコツてなことまで説明したりしとります」 「ホントは親か学校ががやらなければいけないことなんでしょうけどねえ。教える立場にある大のおとなでも、マナーすら守れないのがおりますからね」 「シンちゃんの言うとおりやけど、ワシも子供の頃は大阪駅の中をバカチョンカメラを持って走り回ったこともあるし、若い頃は相当無茶したこともありまっせ。けど、人様に迷惑をかけたり鉄道運行の邪魔をしたことはありまへんでしたな」 「ハハハ、またそんな昔の話を持ち出してきて…。今とは較べものになりませんよ。ねえ、裏紙さん」 シンはそう言って、オーナーと裏紙のグラスに焼酎を注ぎ足しました。 |
| 「たしかに昔と今とでは、カメラをとってみても、今の子供の中にはデジタルの一眼レフを持っている子もいるし、もっとすごければハイビジョンムービーですからね」 「そうですな。私らが子供の頃からすれば、機材については月とスッポンの差がありますなあ。でも、所詮撮影しとるのは人間やよって、人に迷惑をかけたり、ましてや運行の邪魔になるような撮影をしたらあかんということは、昔も今も変わることやない」 両手で持ったグラスを見つめてオーナーは言いました。 「鉄道のファン、鉄道に関する趣味を持っている者が、それを誇りにできるようになれば…というのがワシの理想ですわ」 「そのためにオーナーはいろんなことを考えておられるんですよ」 シンもどこからかグラスを持ってきて、水割りを作ってご相伴に預かりながら、話に加わります。 「たとえば親子で加入するファンクラブを作って、見学会や撮影会でも必ず親子で参加させるとか、小学校などの社会見学を受け入れる場合は、車内でのマナー教室なんかもやっているんです」 「昔は他人の子供でも平気で注意をし、聞かなければ軽い体罰を与えても誰も文句は言わんかった。そやけど今は注意する大人もおらんし、自分の子供でもほったらかしや。これではいかん。親は常に子供をしつけるものやし、他人に注意されるようなことをしたらあかんと教えるのが当たり前でっせ」 「ということは、オーナーは鉄道の趣味の世界を教育の場にしていきたいとお考えなのですか?」 「アハハ、そやからそないにたいそうやのうて、親子のコミュニケーションとか、公共の場でのマナーを考えてもらえたらエエのですわ」 焼酎のロックを飲み干したオーナーは、シンにおかわりを頼みました。それを見透かしたかのようにマユコがやってきました。 「あらあら、あまり度を過ごしたら後のお楽しみの時間がなくなりますわよ」 「おお、やっぱりマユコはんはしっかりしとるな。シンちゃんはまだまだ飲み足らんやろうけど、ここはお開きにしますかな」 マユコの登場でまたニコニコ顔に戻ったオーナーが、裏紙に言いました。 「裏紙はん、こんなもんでよろしいでっか?」 「ええ、ひと通りオーナーの考えはお聞きしましたので、これで記事に厚みを持たせることができますよ」 「さよか。ほな、ぼちぼち私の部屋へご招待させてもらっいまひょ。おい、シンちゃん、ちゃんと手入れしてくれとるやろな」 「とかなんとかおっしゃって、オーナーは先ほど試しに動かされたんじゃないですか?」 シンが空いた食器やグラスを片付けながら答えました。 「いやいや、バレたか。まあ、シンちゃんだけにはさわってもええと言うとるんで心配はしてへんけどな。アッハッハ」 オーナーは上機嫌になり、裏紙を促します。 「さあ、今日の取材は店じまいでまた明日ということにして、お楽しみの時間といきましょ」 何が始まるのか怪訝そうな裏紙を連れて、オーナーは廊下の突き当たりにある非常口のような扉の前に立ちました。 「屋根裏にあるんでこの中の急な階段を上がりますのや。さあどうぞ。ワシについて来てや」 オーナーは狭くて急な階段を、意外に身軽な足取りで登っていきました。後からついて登った裏紙が、真っ暗な屋根裏部屋に顔を出したところで、オーナーが声をかけます。 「あぶないさかい、ちょっとそこで待っててや。今すぐ灯りをつけますよって…」 |
| オーナーが照明のスイッチを入れると、一瞬眩しさに目をしかめたものの、すぐに慣れて階段を登りきった裏紙は、周囲を見回して絶句してしまいました。 「なっ、なんですかっ、これは!」 8畳ほどの部屋の壁面に沿って広がっていたのは、なんとNゲージの鉄道模型レイアウトで、まさにその中心部に立っているのでした。 「期待通り驚いてくれはりましたな。ここに来たお客さんは、誰でもびっくりして、しばらくはあいた口がふさがらへんのですわ」 そう言ったオーナーが、コントロールパネルの電源をオンにしてレバーを操作すると、駅から489系の7輌編成が走り始めました。きょろきょろと四方を見渡していた裏紙は、また別のことで驚いています。 「あれっ? ちょっと待ってくださいよ。このレイアウトはJR近畿の京都線にそっくりじゃないですか? 今日通ってきた駅や風景に見覚えがありますよ」 「さすが、だてに記者をやってはりまへんな。ほら、この真ん中に出っ張った部分が、暇崎の操車場ですがな」 ポイントの切り替えスイッチをいくつか操作して別のレバーを回し、その操車場からDD51の牽くコンテナ貨物列車が出発させました。そしてそれは本線へと進入していきます。 「いやいや、これは参りました。なんとまあ、今私たちがいるペンションもここに立っていますね」 「アハハ、分かりましたか。ほぼ実景をスケールダウンしてありますけど、スペースの都合でデフォルメや省略してるとこもおますな」 オーナーがさらに別のレバーを回すと、ローカルムードが漂う駅から2連のキハ52が発車し、トンネルに消えていきました。 「この駅が明日行く予定の旧線の西大爺駅ですわ。今日ここへ来る途中から見えてましたやろ」 そう言いながら次々にポイントなどを操作して、複々線の新線に4本、単線の旧線に1本の、計5本もの列車が走らせています。 「いやあ、これはすごい! 壮観な眺めですねえ。しかし、これだけのものを作ったとなると、相当な費用がかかったんじゃないですか?」 「確かに材料費はかかりましたけど、工賃はただでっせ。なんせ私がひとりで作りましたからな」 裏紙は再び目を白黒させて言いました。 「こんな大きなレイアウトをオーナーひとりで作られたんですか。本当にオーナーは多芸多才ですねえ」 レイアウトを快走する列車たちを目を細めながら眺めているオーナーは、つぶやくように話します。 「ワシが子供の頃は、Nゲージはまだ初期の時代でHOが鉄道模型の中心やったな。ところが金属でできた車輌は高うて、子供には手が出なんだ…」 コントロールパネルの前の椅子に腰掛けたオーナーは、裏紙にも来客用のソファーを勧めて続けます。 「入門セットのおもちゃのような車輌を、飽きもせずぐるぐる走らせとったら、金持ちのボンボンの友達がSLを親に買うてもらいよってね。自慢げに走らせとるのを見せられて、オレはいつかはでっかいレイアウトを作ったるぞと、心に決めましたな」 「しかし、それが今では実際に鉄道会社のオーナーとなって、実物の車輌を走らせているとは…」 「そうなんですわ。それは夢にも思わんかったことですけどな」 オーナーはふと思いついたように、レイアウトの下にある棚からパーボンウイスキーのボトルと水割り用のセットを取り出し、さらに隣の冷蔵庫から氷とミネラルウォーターを出して、折りたたみのテーブルを広げた上で、水割りを作りだしました。 「ここへ来ると、模型を走らせながら一杯やるのが楽しみですんよ。裏紙はんもどないでっか? 今はやりのハイボールもできまっせ」 |
| 「いやいや、あまり呑みすぎるとと明日の取材に響きますので、薄めの水割りにしておきます」 裏紙は、旧線の駅をしげしげと眺めながら答えました。 「さよか。あと、おつまみはチーズかアーモンドあたりでよろしいな?」 手早く自分と裏紙の水割りを作ったオーナーは、冷蔵庫の中を物色してテーブルに並べていきます。 「しかし、150分の1とはいえ、見事に細かいところで作りこんでいますねえ。この貨物ホームの荷物なんかもよくできてますよ」 「お褒めに預かり、おおきに。今ではいろいろな素材やパーツが市販されとりますからな。昔にくらべて苦労は減りましたわ」 「でも、それらがただ並べてあるだけでじゃなくて、なんかこう、生活を感じるんですよ」 振り返った裏紙は、ソファーに座りなおし、オーナーに言いました。 「あんた、模型の世界もなかなか詳しそうやね」 オーナーは水割りのグラスを持ったままで、にこりとして裏紙を見ながら言います。 「その荷物もそうでっけど、ただ積んであるだけでは芸がおまへんな。これを運んできた人間がこのスペースにこれだけの物をどう置くか考えてやってみると、実感的というか自然な感じがでますよってね」 「なるほど、自分がレイアウトの世界に入り込んでいるような感覚なんですね」 「うまいこと言いまんな。まさにそのとおりですわ。たとえばこんな街中の建物でも…」 オーナーはレイアウト上の市街地の部分を指して続けます。 「既製品のビルや建物を、ただ道路に沿って並べるだけではのうてね。実際にある町並みを想像してみますんよ。ここらへんは、中層のビルが並ぶところで、この程度のビルなら横に駐車場を持っててもおかしないし、角地の商店でもここならこの業種がありそうやなという具合ですわ」 「たしかにそうですねえ。ビル街には八百屋・魚屋はまずないでしょうし、ましてや木造の住宅なんてありえないですよね」 すでに1杯めの水割りを空けたオーナーは、グラスに氷を加えながら言いました。 「要は実際の風景や街をしっかり観察することでっしゃろな。”事実は小説より奇なり”というて変わった情景もようあるやろけど、それは置いといて、さもありなんというのがええんやないですかな?」 裏紙も2杯目の水割りを自分でつくり、レイアウトを覗き込むように見ています。 「それともうひとつ気づいたんですが、人形や看板といった小さいパーツも見ていて面白いですよ」 「裏紙はんもいっぱしの模型人みたいでんな。なかなか目のつけどころが鋭いでっせ」 チーズを一切れ口に運んだオーナーは、運転席の椅子に座り直しました。 「人形も数を並べるだけではあきまへん。人はそれぞれ目的を持って行動するわけやから、当然それに合わせた動きのポーズが必要ですんや」 オーナーが指差す先には、駅前で待ち合わせの相手を見つけて手をあげている女性の人形がありました。 「それとやたらと看板があるんですが、全くうるさくないというか、町並みや景色に溶け込んでいるように見えますよ」 「看板なんかも適当につけたり置いたりするのではダメですな。普通は鉄道や道路からよく見えるとこに向きを考えてつけますわな。道路標識もいっしょでっせ」 ふむふむと頷きながら、ちびちびと水割りをなめている裏紙は、レイアウト上のある一点が気になりだしました。 |
| レイアウトの上を走り回っている車輌を目で追いながらも、ちらちらとそちらを見ている裏紙にオーナーが言いました。 「なんか、おかしなところでも、おましたかな?」 裏紙が気にしているのは、旧線の西大爺駅の駅舎でしたが、はたと気がついてオーナーにたずねました。 「この駅舎の向きはちょっと違和感を感じるんですけど…。現実にはあまりなさそうというか」 「またまた鋭いでんな。駅舎の向きが変やと言いたいんでっしゃろ? 明日実際に見てもろたら分かりはるやろけど、ちょっと手を加えてますんよ。もともとこういうタイプのローカル線の駅舎は、線路に並行するように建っとりますわな」 ちょうどその駅に戻ってきたキハ52を止めて、対向線に止まっていた「北びわこ号」のヘッドマークをつけたC56牽引の12系客車列車を出発させながら、オーナーは言います。 「元々は平行して建っとったんやけどね、引込み線や貨物ホームや駐泊所を作ったときに、スペースの都合で横向きにしましたんよ」 「そうでしたか。え? ちょっと待ってくださいよ。今、貨物ホームや駐泊設備は後から作ったとおっしゃいましたね。ということは…」 「そう、最初はなんにもあらへんかった駅やったんですわ。SLを復活させて走らせるようになったら、運行と整備上の必要性と、似合う設備の雰囲気作りを兼ねてここを拡げましたんでっせ」 オーナーはそう言いながら、再びポイントを操作してキハ52を引込み線に収容してします。 「この給水塔や給炭台に駐泊庫、ほんでもって貨物ホームの上屋まで、あちこちの路線でいらんようになったものから、いい感じのものを集めてきましてね」 「はあ〜、それは気がつきませんでした。前からずっとここにあるようなムードだったので…」 しきりに感心する裏紙を横目に、オーナーは続けます。 「最近では映画やテレビドラマのロケに結構使われてますよって、どっかで見る機会もありますやろね」 三杯目の水割りの作ったオーナーは、しゃがんでレイアウトのベースあたりまで視線を下げて覗いています。裏紙もそれを真似て横に並び、同じように覗き込みます。 「ほんとですね。こうしてみたら本当に実感的で、どこかのドラマのシーンにあったような気がしますよ」 「あっ、そうそう。走らせてほしい車輌があったらリクエストしてくれてよろしいでえ。そっちの下のキャビネットを開けたらありますよってね」 オーナーに促された裏紙は、キャビネットの扉を開いて腰を抜かしそうになりました。なんとそこには、ズラリと車輌収納のケースが並んでおり、さらに別のキャビネットにはプラの単品ケースがぎっしりと詰まっていたのでした。 「こりゃまた、夥しい数の車輌ですね。ざっと見ても千は超えてるんじゃないですか?」 「いやいや、このあいだシンちゃんに数えてもろたら、二千を超えてましたわ」 「新型があるかと思えば古い形式もあるし、近畿・西日本地区だけじゃなくて、北海道や四国の車輌まであるじゃないですか」 「模型やったら、今ではない車輌をいつでも走らせられるし、時には北海道の車輌ばかりを走らせたり、絶対にありえへん北行きと南行きのブルトレをすれ違いさせてみたり、好き勝手にやりたい放題できまっせ。アッハッハッ」 笑い声が大きくなり、オーナーはアルコールが回ってきた様子です。 「車輌のコレクターも多いでっしゃろけど、やっぱり鉄道模型は走らせてこそ…ですな。こうした風景の中を走らせたら尚更ですわ」 キャビネットの中を、端から端までひととおり見た裏紙が、時計を見ながらオーナーに言いました。 「この中から選んで走らせてたら、いくら時間があっても足りませんよ。もう結構いい時間になってきましたし…」 「そうでんな。明日も取材の続きがありますよって、ちょっと早めにお開きにしまひょか」 走っていた車輌たちを駅に止めながら、オーナーは確認するように聞きました。 「明日は9時出発でよろしかったかな? ではフロント前にその時間に集合ということにしまひょか?」 「はい、それで結構です。いやあ、本日はいろいろとありがとうございました。明日一日、よろしくお願いしますよ」 裏紙はそう挨拶してから、自分の部屋に戻るため急な階段を降りようとしています。 「裏紙はん。酔うてはるから気〜つけてや。足滑らしてケガでもしたら、明日の予定はパーでっせ。アッハッハッ!」 水割りのせいで少し足元が心もとないなか、一歩一歩確かめるように降りていく裏紙の頭上から、また一段と大きな笑い声が降ってきました。 |
第四章を読む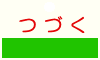 |