| 迷!?ルポライターとJR近畿オーナーがめぐる、 JR近畿京都線の探訪記 |
| 迷!?ルポライターとJR近畿オーナーがめぐる、 JR近畿京都線の探訪記 |
|
||
| 小鳥たちのさえずりが騒がしいほど聞こえてくる中で目覚めた裏紙が時計を確認すると、朝の7時にもう少しという時間です。まだ少し早いかなと思いつつ身支度を整えると、ぶらぶらとフロントまでやってきました。 「あら、ウラガミさん。おはようございます。夕べは遅くまでオーナーのお部屋にいらっしゃったようですけれど、よく眠れまして?」 レストランから出てきたマユコが、裏紙をみつけてにっこり微笑みます。 「おはようございます。いやはや遅くはなりましたが、お酒のせいか朝まで一度も目が覚めませんでした。まさにぐっすりですよ」 裏紙はそう言ってから、レストランを覗き込みました。 「朝食を召し上がられます? ご用意できておりますわよ」 「ああ、ありがとうございます。で、オーナーはもう起きてこられたんでしょうか?」 「ええ、とっくに…。ほら、ちょうど戻っていらっしゃいましたわ」 マユコの視線の先には、テニスコートに繋がる通路をリヤカー先生と笑いながら歩いてくるオーナーの姿がありました。ふたりともそろえたかのような白のテニスウエアで、ラケットやボールを抱えています。自動ドアから入ってきたところで裏紙に気づいて、オーナーが声をかけました。 「おお、ウラガミはん、お目覚めでっか? 朝メシはこれからで?」 「おはようございます。ええ、そうです。しかし、昨日は結構呑んでいらっしゃったのに朝からテニスとは、元気ですね」 「リヤカー先生が決着つけようって、うるさいよってね。ちょっとひと汗かいてきましたわ」 裏紙と朝の挨拶を交わしてから、リヤカー先生がオーナーに言いました。 「今日のところは負けを認めますけれど、次はしっかりとリベンジさせていただきますわよ」 「いやいや、返り討ちにしてあげまっせ。アッハッハッ。その前に約束のアレ、お願いしまっさ」 「分かりましたわ。サークルのほうは朝食を済ませたら解散ですので、その後でここでお待ちしていますわ。それでは失礼します」 リヤカー先生の姿が部屋の方向に消えた後、オーナーは裏紙に言いました。 「ワシが勝ったら駅まで車で送ってもらうことにしましたんよ。見事に勝ちましたよって、トラックやのうて乗用車に乗れますわ」 それを聞きつけたシンが後ろから声をかけてきました。 「おはようございます、ウラガミさん。でもトラックも悪くはなかったでしょう?」 「こらこら、お客さんをトラックで送迎はあきまへんな。ほな、ウラガミはん、ワシはシャワーを浴びたら用意して出てきますよって」 スタスタと自室に向かうオーナーを見届けてから、マユコは裏紙を朝食の用意されたテーブルへ案内しました。 「出発は9時と伺ってますので、まだ時間はありますわね。どうぞごゆっくりとお食事なさってくださいね」 朝食を済ませ、再び自室に戻って今日の取材のスケジュールを確認した裏紙は、9時前にフロントに向いました。オーナーもすぐに現れ、マユコとシンに見送られながら駐車場への階段を降りていくと、真っ赤な外車の運転席で待っているリヤカー先生がいました。 「さあ、どうぞお乗りください。それで、どちらまでお送りすればよろしいですの?」 「今日は旧線やさかい、西大爺駅へ行ってもらえまっか?。なあ、ウラガミはん、それでよろしいな」 オーナーはそう言ってさっさと助手席に乗り込みました。 |
| 裏紙が後ろの座席におさまると、リヤカー先生はマユコとシンへ挨拶代わりに軽くクラクションを鳴らして、車をスタートさせました。 「うん、さすがにええ車は違いまんな。昨日のトラックとは大違いや」 オーナーは滑るように山を降りていく高級車に満足そうに言いました。 「でも雨竜さんらしくて、おもしろい経験になったのではありませんこと? ねえ、ウラガミさん」 「はあ、まさかオーナーがトラックに乗っていくなんて思いもしませんでしたから。本当に昨日からオーナーに驚かされてばかりなんですよ」 「きっと今日も旧線で驚かされること、請合いますわ」 車は昨日着いた駅には向かわず、さらに坂を下っていき、トンネルに入っていきます。そしてトンネルを抜けてすぐの信号を右折すると、昨夜模型で見た景色が現実として目の前に広がりました。 「さあ、西大爺駅に着きましたわよ。ここでよろしかったですわね?」 「はいはい、おおきに。ところでセンセ、リターンマッチは空いてる日やったらいつでもお受けしますよって、また連絡頼んますわ」 オーナーは車から降りがけにリヤカー先生に言いました。 「そうですわね。それまでにまた腕を磨いておきますわ。それでは、おふたりともお気をつけて。ウラガミさん、変な記事を書いたら訴えますのでよろしくね」 「その点は大丈夫ですよ。先生とまたお会いするところが法廷というのは御免蒙ります」 「なかなかうまいことおっしゃるわね。それではこれで失礼させていただきます」 リヤカー先生はオーナーと裏紙に別れを告げると、颯爽と車を走らせて行きました。 「ほな、ウラガミはん、仕事にかかりまひょか?」 オーナーは駅の入口に向かって歩き始め、裏紙は駅舎とその周りの風景をカメラに収めて、後を追いました。 「古めかしいタイプですけど、なぜか懐かしさを感じさせる駅舎ですね」 「そうでっしゃろ。これを壊して新しいのを建てる計画を上げてきよったんで、即却下しましたわ。なんでもかんでも新しいのがええとは限らんて言うてね」 木造の駅舎をもの珍しそうに見回しながら、裏紙が言いました。 「日本の駅の原風景というのは、まさにこんなのを言うのでしょうね」 「おっ、センセの言うとおり、なかなかうまいこと言いまんな。今日は冴えてまっせ。アッハッハ」 「まあこれでも、文章を書いてメシを食ってるルポライターの端くれですので…」 裏紙は頭をかきながらそう答えました。 ちょうどその時、遠くの踏切の音が鳴りだして、やがてキハ35系の2連の列車が駅に滑りこんできました。 |
| 到着した列車から降りてきた乗客たちを避けるように改札口の外に出たふたりは、駅舎沿いに奥の貨物ホームに向かって歩き出しました。 「なるほど、もともとはこの軒が対面式のホームにかかっていたんですね」 裏紙が軒先を見上げながら言いました。 「そうですわ。きのうも言うたとおり、今の駅舎は90度方向が変わっとります。で、この先の貨物ホームは昔はなくて駅前広場やった…」 オーナーも懐かしい過去を振り返っているような眼差しで答えます。 「あの貨物ホームの上屋も、よそで取り壊し寸前まで行っとったやつを持ってきましたしな」 「しかしまた、小口の貨物の取扱いをして採算は採れているんですか?」 ふたりが貨物ホームへつながる道をまがると、トラックから荷卸しの最中の作業服の男の姿が見え、そのうちのひとりがオーナーに気づいて会釈をしました。 「いや、はっきり言うて採算は度外視してますな。ああして使ってくれはる人がおる限りは続けるつもりですわ」 ホームに上がるオーナーに続いて裏紙も上がっていきます。 「コンテナが主流のこの時代に、2軸の黒貨車が似合う貨物駅の風景があるとは思いませんでしたね」 上屋やそこに並べられた荷物を、裏紙はカメラに収めていきます。 「案外とね、駅に持ち込んで駅留めで送る小口の荷物需要はありますんよ。宅配便でも営業所留めとか、郵便局でも局留めとか、ありまっしゃろ? それとおんなじ感覚でんな」 ホームの端まで行くと、これまた古ぼけた懐かしいリヤカーが眼にとまりました。 「ウラガミはん、先に言うときますけど、今どきこのリヤカーで荷物は運びまへんで。これは映画のロケにここを提供したときの大道具でね。撮影が済んだら壊すちゅうんで、置いといてもらいましたんや」 「アハハ、いくらなんでもそこまでは思いませんよ。でもまるで映画のセットみたいなところですね」 「まあ、映画やテレビドラマのロケでSLや古い駅舎なんかが必要なときは、大井川鉄道はんがよう使われてますわな。ほんでもこの駅自体が比較的大都市の近郊にあるんで、最近は頻繁になってきよりましたわ」 裏紙はふと気づいたようにオーナーを見て言いました。 「ということは、ロケで貸すという収入をあてこんで旧線のこんな古い設備を残しているんじゃないんですか?」 「いやいや、もっともっと大きくて深い事情があってのことですわ。おおっ、あそこにいてはったか」 オーナーが見つめる先には、SL用の給水・給炭設備の手前で、図面をひろげながら話し込んでいる背広姿の二人連れがいました。 |
| 貨物用ホームのスロープを降りて、オーナーはスタスタと二人連れをめがけて線路脇の通路を歩いて行きます。後を追って裏紙も、何が始まるのかと期待をしながらついていきました。 「これはこれは、大御所おふたりで作戦会議でっか」 オーナーが満面の笑みで声をかけると、初老の域に入っているものの、やや大柄でがっしりした体格と純朴そうで小柄な背広の二人連れがそろってこちらに気づき、敬礼をしながらも笑顔で答えました。 「おやおや、こちらこそ。オーナーの直々のチェックとは恐れ入ります」 「ほんま、ご苦労はんでんな。おっと、今日は記者さんも来てまっせ。せっかくやから紹介しときますわ」 裏紙を振り返ってオーナーが言いました。 「うちの子会社の警備会社で、現場を取り仕切ってもろてる責任者でね。大きいほうがトツガワはん、小さいほうがカメイはん」 オーナーの口から飛び出た聞き覚えのある名前のコンビに、びっくりした裏紙は、あわてて尋ねました。 「まっ、まさか!警視庁捜査一課で鉄道に絡んだ事件を次々と解決してきた、あの超有名なお二方では?」 「さすが記者さん、やはり気づかれましたか。もっとも警視庁はとっくの昔に定年退職してましてね。その何年かのちにこちらのオーナーからお誘いを頂きまして、こうしてカメさん共々お世話になっているんです」 「私たちは鉄道を舞台にした事件をたくさん手がけたものですから、鉄道から離れて寂しくなったなと、定年後も親交のあった警部と話してたんです。オーナーのお誘いはまさに渡りに舟で、東京から移ってきたという訳なんですよ」 二人の話をにこにこしながら聞いていたオーナーが言いました。 「ウチでは殺人事件が起こらんので物足らんやろうと思てましたけどな。アッハッハッ! まあ、鉄道を知り尽くしたお二人からはいろいろと警備上の助言を頂いとります」 裏紙は二人と名刺を交換し、「突側」「蚊鳴」と名前の入った名刺をしげしげと見ています。 「まさかこんなところで、日本中に名の知れ渡った名刑事とお会いできるとは…。で、お二人は今日は何の捜査をされているんでしょうか?」 「いやいや、今は老いぼれた警備会社の社員ですから、捜査なんてめっそうもありません」 そう突側が言うと蚊鳴が続けます。 「実はね。再来週にここで行われるイベントの警備計画の検討中なんですよ」 蚊鳴がそう言ったところにオーナーが割り込んできます。 「後で驚かせようと裏紙はんには伏せてたんやけど、うちが復活させたSLを何輌かここへ持ってきてね。撮影会をするんですわ。ほんでもって旧型客車を引っ張らせて旧線を走らせますんよ」 その時、タイミングを見計らったかのようにトンネルから列車の走行音が聞こえてきました。 「おおっと、1輌めが来る時間やったか」 そうつぶやいたオーナーは、トンネルの出口に目を向けました。 |
| 真っ暗な闇に沈んでいたトンネルに灯りが灯ったかのように壁面が照らされ、続いてディーゼルエンジンの音とともにゆっくりと姿を見せたのは、北の大地からの移り住んだ「赤熊」ことDF200でした。そしてさらにその赤熊の後ろには、まるでエスコートされるように繋がれた動輪3つのテンダーつきSLが見えました。 「オーナー、これが今回の”目玉商品”ですな」 蚊鳴がそうオーナーに言い、懐かしむような目を向けています。 「カメさんは東北の生まれで、若い頃にSLの牽く列車に乗った記憶があるから、懐かしいんだろうね」 突側もそう言いながらホームに停止したDLとSLを眺めています。DF200はSLを切り離し、前進してから対向線に入ってSLの後ろに回り込みました。その様子をカメラに収めながら、裏紙は蚊鳴の言った”目玉商品”の意味を考えていましたが、見当がつかずにオーナーに問いかけました。 「私はあまりSLの形式には詳しくないんですが、あれは珍しいものなんですか?」 「そうでっせ。なんせ日本で17輌しか作られへんかったヤツですからな」 再びSLを連結したDF200は出てきたトンネルに半身を突っ込んで停止した後、ポイントの切り替えを待って留置線にSLを押し込んでいきます。作業の終わりを待ちきれないオーナーは、給炭台の横を通って詰所のあるほうへ線路を渡って行きました。裏紙や突側らも後からついてきます。 「C54ちゅう形式でな。トラブルの多さから短命に終わったんで、残念ながら保存もされとらんのですわ」 DF200は係員との連携で所定の位置にC54を切り離してから、少し前進して停車しました。 「ではオーナー、これをどうやって再現したんですか?」 突側の疑問に、したり顔でオーナーは答えます。 「古い図面や資料を探し回って、ウチの技術陣が新たにこしらえましたんよ。それに他形式からの流用部分もあって、各地の保存機を訪ね歩いて譲ってもろたところもありますな」 「またとんでもなくすごいことを、いとも簡単にやりますねえ。これは確かに目玉商品ですよ」 C54の周りを歩き回っている裏紙はそう言って、シャッターを切り続けています。 「しかし残念ながら今回は無動力での展示だけなんですなあ。もっともそれだけでもファンは押しかけきますが」 蚊鳴も携帯電話を取り出してC54を撮りながら、誰にともなく言いました。 「次のイベントの機会までには本線を走らせられるようにしまっさかいね。その時はまた、突側はんと蚊鳴はんにも警備で世話をかけますけど、よろしゅうに」 「了解致しました。オーナーの鉄道ファンに対する考え方には大いに共感しておりますので、万全の態勢で当たりますからご心配なく」 そう言った突側の後方に停車していたDF200が、ホイッスルを軽く吹鳴してから、次の仕事へ向かってトンネルに消えていきました。 |
||
| ひととおりC54の写真を撮った裏紙は、オーナーのほうを振り向いて尋ねました。 「先ほど何輌か持ってきてとおっしゃいましたが、あとは何が来るのですか?」 「あとは前からある人気の形式ですけどな。まあ、SL以外でおもろいものも来まっせ」 意味ありげなオーナーの回答に、裏紙は興味津津の表情を満面に表わしています。 「久しぶりにアレのお披露目ですな、オーナー」 蚊鳴も楽しみにしているようで、ニコニコしながら言いました。 「まあ、ウラガミはんだけにはこっそり教えまひょ。次の便がそろそろ着くやろし…」 オーナーの言葉のあとに続くように、DF500が消えていったトンネルとは逆の方向から、甲高いホイッスルが聞こえて来ました。 「来ましたな。ではちょっと私たちは駅のほうで部外者のチェックをしますので」 突側と蚊鳴がそろって駅舎のほうに小走りで向かいました。駅の先の踏切が列車の接近を告げて鳴り出し、そらにその先のトンネルの内側が明るくなってきました。そしてトンネルポータルからゆっくりと姿を現したのは、DD51の重連です。その後方にはシートでくるまれた車輌がつながれています。裏紙は近づいてくるDD51をカメラにおさめて、覆面された車輛を不思議そうに見つめています。 「やけに厳重ですけれど、何か貴重な車両なんでしょうか?」 オーナーは目を細めて眺めながら言いました。 「ウラガミはんは初めて見るやろね。私でも現役で走ってるとこは見たことないんですわ」 駅に進入してきたDD51の重連は一旦停止の後、覆面車両の後方に係員が貼りついてから、トンネルに入って行きます。牽引する覆面車輌が引き込み線への分岐を過ぎたところで一旦停止し、係員の転てつ器切り替えを待って、バックで駅構内の引き込み線へと入ってきました。そして先着のC54のとなりの線の斜め前で覆面車両を切り離します。 「おーい、ちょっとシートをどけてくれんやろか」 近寄ってきた係員たちにオーナーが指示を出し、彼らは分担してロープをはずしシートを取り除き始めました。 「なんか真っ黒な車体が見えてきましたが、いったい何ですか?」 「ウラガミはん、『キマロキ』てご存じでっか?」 「ええっ?、キマロキというのは確か豪雪地帯で除雪にあたった伝説の編成のことですよね」 「あれはそのキマロキのなかのロ。ロータリー車ですんよ」 シートの下から現れたのは、裏紙が写真や古いフィルム画像でしか見たことのないロータリー除雪車の巨体でした。 |
| 「こっ、これがロータリーの除雪車ですか。しかし…でかいもんですね」 裏紙は黒い巨体の迫力に呑みこまれてしまいそうになりながらも、シャッターを切りまくっています。 「写真はなんぼ撮ってもろてもかまわへんけど、当日までのシークレットやさかい、公表せんように頼んますで」 オーナーはそう言って、除雪車に近づいていきます。そして後をついてくる裏紙を振り返りました。 「ほんまはマックレー車も復元してコンビを組ませたいんやけど、そっちはまだ先ですわ」 「しかし、この辺は雪なんて積もらないでしょう? なのにどうして除雪車なんか復元したんですか?」 赤く塗られたロータリーの羽根を覗き込みながら、裏紙が尋ねました。 「ゆうべもちょこっと言いましたけど、ワシの道楽というか、やりたいことがおましてな」 「ああ、鉄道遺産の保存ですね。でも昨日の話からするともっとすごいことを考えていらっしゃる気がするんですけど…」 ルポライターの嗅覚を刺激された裏紙は、ここが突っ込みどころと意気込んでいます。 「この旧線を本当にまるごと博物館にする気なんじゃないですか? ぜひお聞かせくださいよ」 「まあまあ、そう焦らんでも…。ほんなら駅の本屋でお茶でも飲みながら話しまひょか」 裏紙と本屋のほうに向かって歩き始めたオーナーは、途中で作業員たちに声をかけてました。 「おう、すまんかったな。またシートかぶせてあんじょうしといてや。大事な”目玉商品”やさかいな」 ホームを歩いて本屋の中に入ると、ちょうど突側と蚊鳴の両名も戻ってきたところでした。オーナーが駅長席の横にある小さな応接セットにどかりと腰を降ろし、それを見た蚊鳴が声をかけてきました。 「私たちはコーヒーで一息いれますが、よろしければごいっしょにいかがですか?」 「おおきに。すまんけどワシは日本茶がええな。ウラガミはんはコーヒーのほうがよろしいやろ?」 オーナーの向かいに座った裏紙が答えます。 「ありがとうございます。コーヒーで結構です。それよりオーナー、先ほどの話の続きを…」 「せっかちなお人やな。ほな披露させてもらいますけど、全部を記事にせんといてもらえまっか?」 「もちろんです。許可を頂いた分しか載せないことをお約束します」 裏紙は取材ノートを開いて、次のひとことを待ち受けています。 「ローカル線をまるごと博物館にしたらおもろい、てな話でしたな」 蚊鳴が入れてきたお茶を手に、オーナーは語り始めます。 「ご存知のようにウチの管内にも多数のローカル線があって、赤字で走っとります。さてこれらは地域の足としては残していかなあかんのやけど、採算が採れんようでは企業としては困りますな」 「どこの鉄道会社でも抱えている問題ですね。オーナーはそれでもなんとか残したいのですよね?」 蚊鳴からコーヒーカップを会釈して受け取った裏紙は、一口すすってからまたメモを取り始めます。 「よその会社では特別な列車を作ったりして、風光明媚なローカル線を走らせるという観光列車が増えとりますやろ」 「JR九州がその先駆けですね。移動の時間も楽しめるとか、列車に乗ること自体が楽しみとか」 お茶をテーブルの上に置き、オーナーは裏紙を見つめて言いました。 「ワシはね、その両方をいっしょにミックスしたいのですわ」 「というと、車窓の風景とか乗って楽しめる部分と、その列車に乗るとイベントのようなサプライズがあるとか、そんな感じでしょうか?」 「ハハハ、なかなか鋭いでんな」 突側と蚊鳴の名コンビはコーヒー片手に、笑顔でふたりの会話を聞いていました。 |
| 「ウラガミはんは、SLが旧型客車を牽いて架線柱の下を走るのを見て、どう思いはりまっか?」 オーナーの急な質問に.面くらいながらも裏紙は答えました。 「確かに違和感はありますよね。時代的に不一致ですし…」 「そうでっしゃろ? やっぱ古い車輛はそいつが活躍しとった時代の風景の中を走るのがお似合いでんな」 静かにうなづいている突側と蚊鳴を横目に、オーナーは続けます。 「SLの混合列車が着く駅は木造の駅舎やないとあかんし、古い気動車が高層ビルの前を行くなんて、単なるリバイバルトレインのイベントになってしまいまっしゃろ?」 裏紙はふと頭に浮かんだことがありましたが、まさかという否定の気持ちが先に立ち、恐る恐る尋ねました。 「ひょっとしてオーナーは、古い時代のローカル線を再現しようとしているんじゃないですよね?」 「ピンポーン! 正解ですわ! なあ、そこの名コンビさん」 突側と蚊鳴はどちらが答えるか、一瞬顔を見合わせてから、促されるままに蚊鳴が話します。 「オーナーはね。路線をまるごとクラッシックなローカル線の世界に仕立てるという計画をお持ちなんですよ」 「この路線に乗りにくれば、あの時代に帰れる、郷愁にも浸れる。そして若い世代は体験できる、とね」 付け足すように突側が言いました。 「いわば路線まるごとのノスタルジックな鉄道のテーマパークみたいなもんですわ。列車から見える建物や自動車なんかも当時のものを再現する。沿線の住民の方々にも協力を仰いで、当時のままに住宅に住んだり、店舗なんかで働いてもらう。もちろん服装もその時代のものを着てもろてね」 「そっ、そんなことができるんですか?」 驚きのあまり泡を食った表情で質問する裏紙は、メモをとることも忘れています。 「そら、急には無理ですけど、水面下ではこっそりと動いとりまっせ。もちろん生活がありますよって、毎日昔の暮らしを再現するわけにはいきまへんけど、日を限定したイベントという手もありますわな」 オーナーはお茶のお代わりを頼んで、さらに続けます。 「協力してもらえる住民の皆さんにはエキストラとして出演料をお支払いしますし、住居・店舗などの維持費もウチが出します。また沿線の観光施設や祭りなどの行事とタイアップしたら、集客にもなってその地区の活性化や収入にもつながりまんな。ほんでもって雇用の機会が増えれば若者の定着もあるやろし、最終的にはそのローカル線の赤字解消にもなっていきますわな。さらにさらに古い鉄道遺産の維持・保存や技術の伝承もできますやろ」 ここまで一気にしゃべったオーナーは、駅員が持ってきたお茶でのどを潤しています。その向かいで、壮大な計画に圧倒された裏紙は、感動すら覚えて聞き入っていました。 |
| その様子を微笑みながら見ていた突側が言いました。 「オーナーの夢が叶うまで私たちも現役でいたいものです。ねえ、カメさん」 「そうですな。我々もチョビひげでも生やして、当時の制服を着ておまわりさんにでもなりますかな」 その会話を聞きながら、裏紙はオーナーに聞きました。 「この計画はどれぐらい先に実施する予定なんですか?」 「そうでんな、とりあえずは路線の確定や基本方針を決めなあきまへんので、だいぶ先になるやろね」 遠くから聞こえてくる通過のディーゼル特急のエンジンの音に、窓を見やりながらオーナーは答えました。 「ただ、そんな遠い将来のことではおまへん。プロジェクトとして準備段階に入っているところもありますんでね」 「だいたいでも結構ですから、教えてもらえないですか?」 オーナーは大きく顔の前で手を振りました。 「あかんあかん。簡単には教えられまへんな。これは絶対に書いてもろたら困る重大な機密事項でっせ」 「そうですか、残念です。でもオーブンにできる時が来たら真っ先に教えてください。お願いします」 裏紙は頭を床に触れんばかりに下げて頼み込みました。 「わかりました、ウラガミはん。約束しましょ。マスコミに発表する前に特別に早くお知らせします」 「ありがとうございます。こちらもお約束します。その時には特集を組んででもPRさせて頂きます」 オーナーと裏紙は、がっちりと握手をして約束を交わしました。 「あんたを見込んでちょこっとヒントをあげますわ。予定してる路線についてですけどな」 オーナーがウラガミの耳元でささやきます。 「国鉄時代から長大な本線でありながら偉大なるローカル線と呼ばれてる線はご存じでっか?」 「ええっ? まさかあの山陰本線ですか? でも隣のJR中国にまたがってしまいますよ」 「もちろんウチの管内だけですけどな。京都から丹波・但馬まで、山あり海あり川ありの絶景がありますやろ。それにところどころに元の機関区やった設備が残っとりますからね」 取材のメモも忘れて裏紙は聞き入っています。オーナーはまた耳元に顔を寄せて言いました。 「ホンマに内緒にしといてくださいや。SLももっと復活させたいし、気動車やDLが牽く客車列車も保存を兼ねて走らせてみたいんですわ。今やっとるイベントや保存活動は前哨戦みたいなもんですな」 ますますオーナーの話のスケールの大きさと熱意に引き込まれていく裏紙は、熱のこもった目でオーナーを見つめています。 「貴重な情報をありがとうこざいます。ぜひぜひ実現してください。微力ながら私も協力を惜しみません。できることなら実現までのドキュメンタリーを書かせて頂きたいぐらいです」 本屋の脇を通過していく特急のジョイント音が響くなか、オーナーと裏紙はどちらも無意識のうちに自然に握手を交わしていました。 |
第五章を読む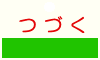 |