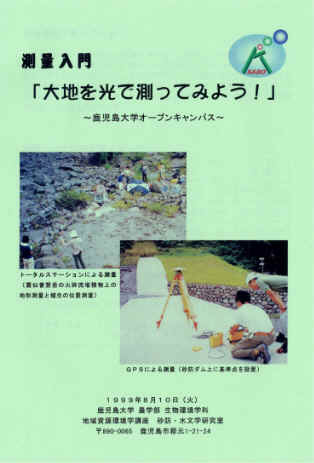
<テキスト内容>
- 「測量」ってなに?
- 「測量」には,どんな種類がある?
- 「測量」と私たちの暮らし
- 「GPS」ってなに?
- 「単位」は,なにを基準にしている?
- 「メートル」はどうやって決めた?
- 「キログラム」はどうやって決めた?
- 「SI単位系」ってなに?
- 「距離」には,どんな種類がある?
- 「距離」を測るには,どんな方法がある?
<実習課題>
1.2点間の距離を測る。
①目測によって
②歩測によって
③巻尺を使って
④光波測距儀(トータルステーション)を使って
⑤ノンプリズム測量
2.桜島の高さを測る(時間不足で省略)
三角水準測量
3.自分の位置を知る
GPS測量

-
参加した高校生2名(前列右から2名)と研究室の大学院生・4年生(残り4名)です。
-
高校生の出身は2名とも宮崎県でした。

目測:2点間の距離を何も使わずに自分の経験と感性で測る。
歩測:物差しや巻尺の代わりに人間の歩幅を使う。ペースをしっかりつかむと結構正確な測定ができる。
物差し,巻尺を使う。
光波測距儀:点Aから発する光を一定周波数の強弱の波に変調し,これを他端Bで受けてAに送り返す。2点間に含まれる波の数と,1波長に満たない最後の波の端数を測定して距離を求める装置。光は電波と違って天候障害の影響を受けやすいが,比較的近距離で用いると非常に高い精度が得られる。

自分の位置をGPSで測定中。
GPS(Global Positioning System=全地球測位システム)
高度2万kmに打ち上げられた人工衛星を使って,地球上の任意の位置を正確に知ろうという最新の測量方式。計測誤差は実距離100kmあたりで数mmときわめて高い。
GPSを応用したものとしてカーナビゲーション(カーナビ)がある。これはGPSと地図を組み合わせたもので,クルマの現在位置と目的地との関係を即座に確認でき,指示どおりに走行すればだれでも目的地に早く確実にたどり着くことができる。昨今のカーナビの普及はめざましいものがあり,私たちの生活における最も身近なGPSの利用といえる。
GPSは,地震や津波対策などの防災管理,陸上・海上・航空交通管理の分野にも利用されている。
(内山一男(1997):測量なぜなぜおもしろ読本,教文堂より)