�ً}�n�k���e���r�ŗ����̂������1964�N10��1���ɊJ�Ƃ������C���V�����J�Ƃ̍����v���o�����B�l�͓���6�N�ځA���̔N��6��16���ɂ��̐V���n�k���N����A���S�͐V���w�\��������̗������]�����ăf�B�[�[���J�[���Ԃ����肵���ق��A���Q�������ނ�A�u�n�Ղ̉t���ہv�𑽂��̐l�͏��߂Ēm�����̂������i���Ȃ݂ɖl�̊w�ʘ_���i1971�j�͒n�k�ɂ��y�̉t�Ɋ֘A���Ă���j�B
���C���V�����̘H���́A���̓����܂ŒN������ɂ��Ȃ������̂ŋĂ����A����������n�Ւn�т����I��Œʂ��Ă���B���܂��ɂقƂ�Ǎ����y�Ō��݂���Ă�������A���̒n�k�ŐS�z�ɂȂ������S�{�Ђ���Z�p�������ɉ�������l����Ƃ����}�Ȗ��߁B�����A���S�̒n���������́A����N���ΎR�ϑ��������߂ēS���Z���ɖl���ォ������Ă����e��y�i�̐l�j�Ɩl�̓�l�������Ȃ������B�y�؉���n�����Ƃ��ǂ��W�܂��Ĕ��c�������ʁA���O������l�łȂɂ��l����Ƃ����B�n�k�Ő��H���j�Ă��A��Ԃ������̂܂ܓ˂����ނ��Ƃ����͔��������B����Ȏ��̂��N�������ꍇ�̕⏞�z���������Ă����������������B
���̂悤�Ȏ��̂�h���ɂ́A�n�k�����m������A�����u���[�L�������ė�Ԃ��߂邵���Ȃ��B�����œ����E�V����500�L����20�L�������ɂ���25�ӏ��̕ϓd���ɒn�k�����x�v��u���A���ꂪ���郌�x��������d�����Ւf�������l�����B�V������1�b�ȏ��d����Ɣ��u���[�L��������悤�ɂȂ��Ă������炾�B�ł��A����3���������Ȃ��B�n�k�v�̐��삪�Ԃɍ������낤���H�l�����͖^�n�k�v���[�J�[�Ɍ����݂ōޗ�������悤���������B
�Ƃ��낪�A���S���ǂ́A����ȏd�厖�����S���������Ō��߂Ă������낤���Ƃɂ킩�ɕs���ɂȂ����̂ł���B�����Ŋ������悭����@�Ƃ��āA���̓����ۑ�𓌑吶�Y�Z���̂n�����i�̐l�A�ϐk�H�w�j�Ɉϑ������Ƃ��Ĉ˗������̂ł���B�����N���l���Ă������悤�ȓ������o��Ɍ��܂��Ă���B�������́A�����̗̍p�����n�k�v���[�J�[���A�l�����̗����[�J�[�ƈ���Ă������Ƃ��B�������Ėl�����Ƒł����킹�Ă������̃��[�J�[�̉c�ƒS���҂́A�����ݔ����Ŏ����Q�̐ӔC����炳��Ă��̉�Ђ����߂邱�ƂƂȂ����B
���̑��u�́u�ϐk�h�쑕�u�v���Ă�A���̌シ�ׂĂ̐V�����Ɏ���ɉ��ǂ���Ȃ�����t����ꂽ�B���k�V�����ł́A���ƂȂ�n�k�̑����͎O������k���Ƃ��邱�Ƃ���A���k�����H���痣�ꂽ�C�ݕt�߂ɒu���A�C�݂�����H�܂ł̒n�k�g�`�d���ԂŃu���[�L���Ԃ��҂���ł͂Ȃ����Ƃ����A�C�f�A���A����F��y�������������B���̍��܂ł́A�n�k�̎�v�����v���Ă���A���̋���Ńu���[�L�������邩�ǂ������߂Ă����̂ł���B����200�L���̗�Ԃ���܂�܂łɁA�����ɂ��2~3�L�����[�g�������Ă��܂�����A���H�̔j��ӏ��ɓ˂�����ł��܂���������Ȃ����A����ł���܂�܂łɌ����͂��Ă���킯�����牽�����Ȃ����͂͂邩�ɂ܂����낤�Ƃ����l���������B�i���̍��A�l���u�V�����͊�Ȃ�����Ȃ�ׂ����ȁv�Ɠ����̂s�N�ɂ������炵���A�ނɌ�X�܂ł���ꂽ���̂��B�j
���̋Z�p�͌�ɂ���ɔ��W���āA�����������v�����Đk������т��̑傫���肵�A����ɂ���Čx����o�����Ƃ����Ƃ���܂ōs�����B����͓S�������̂e���̌�C�A�m�A�`����ɂ����ǂ���A���Ɍ��݁A�C�ے��ً̋}�n�k����ɗ��p�����Ƃ���܂ł����Ă���B�]�v�Ȃ��Ƃ����A�l�����i�e����Ǝ��j������Ȃ��Ƃ���炳�ꂽ���Ƃ́A�S�������̂`������m��Ȃ������B����͓����̍��S�͉B���̎��ŁA����Ȃ��Ƃ͕��O��ň�ʂɂ͂܂��������\����Ȃ���������ł���B�m���͂��̋Z�p�ʼn�Ђ������A�`���͓S�������̌����Œ��������E�E�E�B
�����̑ϐk���ɂ��Ă͋ꂢ�v��������������B�l�͋���F�挴�q�F�{�݂Ȃǂ̈ꕔ�́u�������v�O���[�v�Ƃ͂Ȃ����Ă͂��Ȃ����A����͑�����Ȃ��Z�p���Ǝv���Ă�������A�����̐܂Ɍ������ݗ\��n�̐l�����Ɉ�������o����ď��������肷�邱�Ƃ����������B�֓d���ዷ�p�����ɑ��������̌���������Ă��邩��A�֓d�̌ږ�I�ȍH�w���◝�w���̐�y���������Ǝ�����Η����闧��ɂȂ��Ă��܂��Ă����B
�����d�͕l�������̑�R���F���������A���߂�100���L�����b�g���̌��q�F���v�悳�ꂽ�Ƃ����̓���z��Y���i�����y�n���@�̑��n�w�ҁj����{�Ȋw�҉�c�É��x���̏����ƈꏏ�ɂ��̌v��̔ᔻ�ɉ�������B�l���É����������A�l�����������A�Z���ɏ�����Ė��_���������u���ɂ������Ƃ��A��X�I�ɐ�`�J�[���u����̒m�点�𗬂��Ă��ċV�������Ƃ�����B���̃P�[�X�Ŗl����ԋC�ɂ��Ă������Ƃ́A�l�������͌�O��ɂ���A������N����ׂ����C�n�k�ɐk����̐^��Ɍ��݂����̂�����A�n�k���N����Ζ��m�̊��f�w�����ꂽ�肵�āA�C����n���ǂŎ����Ă����p���n���j�f����鋰�ꂪ����B��p���j�]������ǂ�����̂��Ƃ������Ƃ������i�n�k�f�w�ƌ����̖��́A�̂��ɓ��C�n�k�̌����������ł���D�G�Ȓn�k�w�ҁA�����F���i�_�ˑ�w���_�����j�炪����ɒNj����Ă���j�B�����l�����̔ᔻ�ȂLj�ڂ����ꂸ�H���͋��s����Ă��܂����B���������ł́A�����ƂЂǂ�����ǂ��܂��ɂ����������Ƃ��N�����Ă���ł͂Ȃ����I�ŋ߂̃j���[�X�ɂ��ƁA�����d�͍͂���̕��������̎��Ԃ����āA�Q�|�R�N���ɍ���10�����[�g���̖h��������Ƃ����������炵�����A�ʂ����Ď��ԓI�A�����I�ɂ���ŊԂɍ������ǂ����H
�ዷ�p�̌����̗�p�n����肪����B����͂قƂ�ǃu���b�N�W���[�N�ɋ߂����A�Ă��߂��鍠�A�����ɂ͂��炰����ʔ�������2����p�n�̋��������ӂ����ł��܂�����ł���B���̑�͂��܂肢�����̂��Ȃ��A�d���Ȃ��Ԃƕ��ہi�Ђ��Ⴍ�j�ňꐶ�����������ĂƂ��Ă���Ƃ����̂����Ԃ��B���{�̌����͂��ׂĊC�ӂɂ���A�Q����p���ɊC�����g���Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�ǂ̌������Ôg�̋��Ђɑ����ꏭ�Ȃ��ꂳ�炳��Ă���Ƃ������Ƃ��B�h�C�c�̌����̓��C���쉈���ɂ���A�͐쐅�̕��˔\�������W��������ᔻ����Ă���B������h�C�c�́u�E�������j�v��1���R�ɂȂ��Ă��邩������Ȃ��B
�O��̋{�錧���n�k��1978�i���a53�j�N�ɔ������܂����B���N�i����23�N�j��6���ŁA�O��̋{�錧���n�k����33�N���o�߂��܂��B�{�錧���n�k�̌J��Ԃ������Ԋu�͉��̃O���t�Ɏ����悤�ɕ��ϓI�ɂ�37�N���x�ł���A���ɂ��N�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ������ɓ����Ă��܂����B
�@���̂悤�ȏ��A����̋���ȓ��k�n�������m���n�k���������܂����B
�@2011�N4��26���̒n�k�\�m�A����ɂ��ƁA���k�n�������m���n�k�������ɋ{�錧���n�k���N���Ă����Ƃ��錩�������\����܂����B�{�錧���n�k�̐k����̒f�w�����k�n�������m���n�k�̒f�w�ƈꏏ�ɂȂ��ē������Ƃ������߂ł��B
�@�{�錧���n�k�ɂ��Ă�������
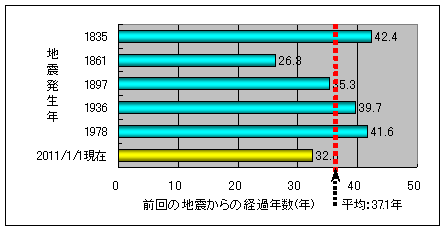
��Ў҂ɂ͐g�߂Ȑl�̎��A���Y�̑r���A���ƂȂǂ̍Ђ����d�Ȃ�܂��B�ЊQ����̍��g�������_��Ԃ̎������߂���ƁA�����̓W�]���J���Ȃ����Ƃɂ��NJ��ƌǗ����ɂ��A��Ў҂͐��_�I�ɒǂ��l�߂��Ă����܂��B
��Ў҂̐����Č����l�̖��Ƒ�����ƁA���͎����̊m�ۂł��B��Вn�Ɏd�����Ȃ��A��������`��������Ɏg���悤�ȏ������A�d�������߂Ĕ�Вn�𗣂�邱�ƂɂȂ�܂��B��ЊQ�̏ꍇ�͒��ړI�Ȑl�������Ɛ������ł��Ȃ����߂̐l�����o���d�Ȃ�A��Вn�͍r�p���Ă����܂��B
�@1771�N�̔��d�R�n�k�Ôg�ł͒Ôg�ɂ���Q�����Ȃ������n��ł����l���̌������N����A�l�����Ôg�ȑO�ɖ߂����̂�148�N��̑吳8�N�ł������Ƃ����Ⴊ����܂��B
���݂̂悤�Ɍo�ς̂Ȃ��肪��������ɂ͔�Вn�ł���n��Љ����̕���̉e�����S���ɓ`�d���A���{���̂����ނɌ��������Ƃ������O����Ă܂��B
��Ў҂������ւ̊�]�����o�����Ƃ��ł������Ƃ��Č��̐����Ƃ���Ȃ�A������Ƃ���1927�i���a2�j�N�̖k�O��n�k�������邱�Ƃ��ł��܂��B
�k�O��n�k�i1927�N�j�͋��s�{�k���̋��O��s��^�Ӗ쒬���P�����}�O�j�`���[�h7.3�̒����^�n�k�ł���A�O�タ��߂�̎Y�n���������܂����B���ɕ�R���i�����O��s�j�ł͏Z���97%���S�Ă܂��͑S�A������24%�����S���܂����B�O��̕����͒O�タ��߂�Ƃ����n��Y�Ƃ̕������s���ł���Ƃ��A�@�ƎҌ����ɂ͕��������̑��ɋ@�ƕ��������⋤���H�ꏕ�����Ȃǂ̓��ʂ̎������݂��o����܂����B
�����Č��ƕ�������̂ƂȂ��ċ}���ɐi�����ɂ́A�n��Y�Ƃ𗧂Ē����������������ꂽ���ƁA��Вn�Ōٗp�����܂ꂽ���ƁA���a���Q�̂��Ȃ��ɂ���Ȃ���D��Δ����Ƃ����D���Ƃ����Љ���Ɍb�܂ꂽ���ƂȂǂ�����܂��B���i������邱�Ƃ������ӗ~��ٗp�̊g��݁A�D�@�䐔�͐k�Ќ�1�N�ɂ��Ă��Ƃɖ߂�܂����B����ɂ͐V���ȑg�D�̐ݗ���V���x�̓����ɂ���Đk�БO�ɂ͂Ȃ������n��Y�Ƃ̎���Ɨ�����ɂ��܂����B
�@�Ȃ��A�n��Y�Ƃ͒n�悪���ӂƂ���Y�Ƃł���A�{�����������͂������Ă��܂��B�X�ɁA�V�����{�ݐݔ��̓����ɂ���ċ����͈͂�i�ƍ��܂�\������݂��Ă��܂��B
�ȏ���܂Ƃ߂ĉӏ������Ɏ����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�[���Ȏ����̋���
�@�@�A�@�n��Y�Ƃւ̎x��
�@�@�B�@�@�A�A�ɂ�鐶�Y�{�݂̌��݂Ƌ@�B�̓���
�@�@�C�@�B�ɂ��ٗp�̊m��
�@�@�D�@�D�i�C�ɂ��㉟��
�@�@�E�@�w���҂̕����ւ̋����ӎu
�@�@�F�@���x���v�̒f�s
�@�@�G�@�@�`�F�ɂ��A�����Č��ƕ�������̉����Ď���
�ߋ��̍ЊQ���݂�ƁA�n��Љ�̂܂Ƃ܂肪�ア�ꍇ�͍ЊQ���l�̖��Ƃ��Ĉ�����X��������A�n��Љ�ɐM�����ꂽ�w���҂����邩���Ȃ����ɂ���Ĕ�Ў҂̏������傫���ς邱�Ƃ�����܂��B�����Č��ƕ����ɑ��Ēn��Љ�̈ӎu���܂Ƃ߂��Ȃ��Ɣ�Ў҂͏����ւ̓W�]���J���Ȃ��Ɗ����A���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɔ�Вn�𗣂�Ēn��Љ�͂��ɂȂ��Ă����܂��B����ɁA�����Ƃ������̂��Ƃɍ��⌧�Ȃǂ̏�ʑg�D�̎w����w���ɂ���āA�Љ��Ղł��铹�H��{�݂���Ў҂̈ӎu�Ƃ͊W�Ȃ����݂���Ă����܂��B�l���̗��o�E�����������͐��N��ɂ͂����S�Ŋ��̐��������ɐ��܂�ς��Ƃ��Ă��A��U���̒n���Ŏd���ɕt�����l�X���߂��Ă��邱�Ƃ��ł���ł��傤���B�d���͂���̂ł��傤���B���邢�́A�l�����o��\�z������ʑg�D�͏d�_�I�E�W��I���邢�͑����I�����Ƃ��āA�ꕔ�̒n������̂Ă͂��Ȃ��ł��傤���B
�k�O��n�k�̏ꍇ�͐����Č��ƕ����͂قړ��`��ł������A����̍ЊQ�ł͕����ɏd�_���u����A�����Č�����ɂȂ�Ȃ����ƌ��O����܂��B�n��Љ�͎���̋����ӎu�������Đ����Č��ƕ����ɗՂ܂Ȃ���Ύ������g��Ƒ������Ȃ��������邩���m��܂���B�������ŒN������Ў҂̂��߂̕����ł͂Ȃ�������̂��߂̕����ł���ƍl���Ă��Ȃ��ł��傤���B
�n��Љ�̑��ӂł����Ў҂̐��͋��͂ŒN���������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ʂ������Ă��܂��B1�������������Č��ƒn��Љ�̕����������܂��悤�ɁB
�n��Љ����@�Z���𒆐S�Ƃ����ʏ�̐������ŁA�w�Z��a�@�E���X�Ȃǂ��܂ޒ����E�n����x���C���[�W���Ă��܂��B�E�ꂪ�n��Љ�̊O�ɂ��邱�Ƃ�n��Љ�Ƃ̌W��肪���Ȃ��ꍇ�ł����Ă��A�n��Љ�=���e����ł����������ł���Ƃ����Ӗ��ł͏d�v�ł��B
�E�̃O���t�Ɏ��Ґ��E�s���s���Ґ��Ȃǂ������܂��B���̃O���t��莟�̂悤�ȏ��ǂݎ��܂��B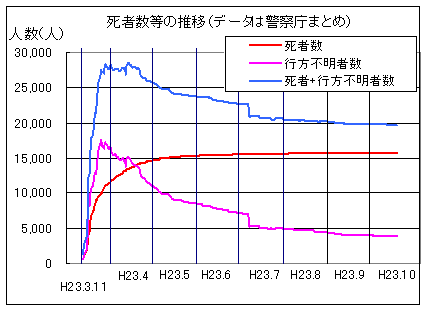
1.�@�s���s���҂��ő�ƂȂ�̂�3��24���̒n�k��������13����ł���B
���i���߁F�n�k��������13����Ɏ��ҍs���s���Ґ��̊T���c�����\�ƂȂ�B�j
2.�@���ҍs���s���Ґ����p���I�P���Ɍ������n�߂�̂�4��22���i�n�k��������42����j�ł���A���̌�������X���͌p������B�Ȃ��A7��8������A�s���s���҂̐���1����1800�l���x��������B
���i���߁F�n�k��������42���㍠��萶���ҁE���ҁE�s���s���҂̏ƍ�����i������B����A�傫�Ȗ��m�F�s���s���҂��܂܂�Ă���A�������̂������Ŋm�F�ł��Ȃ������̂��A�P�Ȃ�W�v��̌��ł��������͕s���ł���B�n�k��������6������ɂ����Ă������҂��m�F�����P�[�X���p�����Ă���B�����̐����҂͎����̈ӎv�Œn���𗣂ꂽ���E�]���҂Ȃǂł��낤���B�j
3.�@1������̎��ґ�������3��21���i�n�k��������10����j����范�����邪�A100�l�����ƂȂ�̂͒n�k��������40�����4��20���ȍ~�ł���B���Ґ��͒n�k����3�������1����5�`10���A6�������1����1�`2���̑���������B
���i���߁F��̂̔�������q���Ă���B���I�̓P���̒x��ƕ�����ꌴ�q�͔��d���ɂ����˔\�ɂ��e�����傫���B�j
4.�@1��ڂ̏W���{���i4/1�A4/2�A4/3�j�ł͎��q����P���W��l�A�ČR��V��l�̂ق��A�C�ہA�x�@�A���h���Q�����A���q���ƕČR�̍q��@�v��120�@�A�͒���65�ǂȂǂ��������ꂽ�B�܂��A2��ڂ̏W���{���i4/10�j�ł͎��q����A�����J�R�Ȃ�2��2000�l�ƍq��@90�@�A�͒�50�ǁA3��ڂ̏W���{���ł́i4/25�A4/26�j���q���𒆐S�Ƃ��Ė�2��4800�l�Ƌ�@90�@�A�͒�50�ǁj�̑̐��Ŏ��{���ꂽ�B�W���{���͂���Ȃ�̌��ʂ��������ł��낤���A�O���t�ł͎��Ґ��̑�����s���s���҂̌����Ƃ��Ė��Ăɂ͕\��Ă��Ȃ��B
���i���߁F��̑{���̍���������Ă���B���I�̉��[���ɖ����ꂽ��̂͊��I�̓P�����i�܂Ȃ��Ɣ����ł��Ȃ����A�C�ɗ����ꂽ��̂̔����͔��ɍ���ł���B�j
5.�@�n�k��������7�������o�߂������݂̎��҂�15,800�l���x�A�s���s���Ґ���3,900�l���x�ł���A�i����+�s���s���ҁj�ɑ���s���s���҂̊����͖�20%��ł���A
���i���߁F�]����5�l��1�l���x�͍s���s���҂ł���B�����͒Ôg�̈����g�ɂ���ĉ��ɗ����ꂽ�l�X�Ǝv����B�j
----- ���҂ƍs���s���҂̔䗦�ɂ��� -----
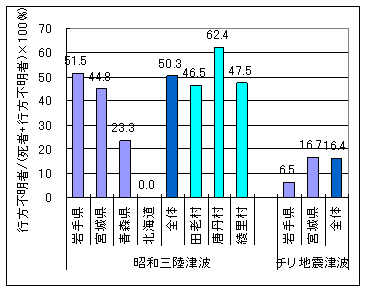 |
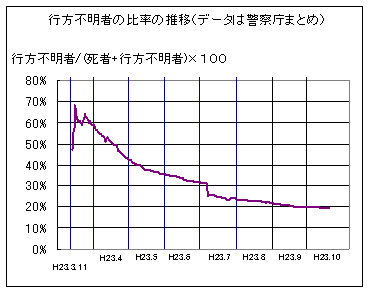 |
��̃O���t����1993�i���a8�j�N�̎O�����n�k��1960�i���a35�j�N�̃`���n�k�Ôg�ɂ�鎀��+�s���s���҂ɑ���s���s���҂̊��������i�s���s����/���ҁ{�s���s���ҁj�~100�j�ŕ\�������O���t�ł���A�f�[�^�͎���2�ɋL�ڂ���Ă��鐔�l��p���Ă��܂��B���a�O���n�k�͏��a8�N��3��3���̐[��2��30���ɔ��������n�k�Ŕ�����30������1���ԂŒÔg���k�C����O�����݂ɒB���܂����B��Q�̑傫�������c�V�����͂��߂Ƃ��đS�̂ł��]���҂�50%���x���s���s���҂ł����B�s���s���҂̑������Ôg�̈����g�ɂ���ĊC�ɉ^�ы���ꂽ���Ƃ���u�����g�̋��|�v�Ƃ��\������Ă��܂��i����2�j�B�`���n�k�ɂ��Ôg�͒n�k�����̗����̏��a35�N5��24��2��20�����납����{�̊e�n�ɉ����܂����B�`���n�k�Ôg�̏ꍇ�͔g�����キ�������������������߂ɏ��a�O���n�k�̒Ôg�Ɣ�r���čs���s���҂̊��������Ȃ������i����2�j�ƍl�����Ă��܂��B
�@����A����̒Ôg�i�ȉ��A�����Ôg�ƌĂԁj�ł̍s���s���҂̊����̐��ڂׂĂ݂�Ə�̃O���t�E���̂悤�ɂȂ�܂����A���a�O���n�k�̒Ôg�i�ȉ��A���a�Ôg�ƌĂԁj�̏ꍇ�Ɣ�ׂĂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�������ł��傤���B
�悸�A2�̒Ôg�ɂ��đ��Ⴗ����܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
1.�Ôg�̋K�͂Ɣ͈͂́i���a�Ôg�j<�i�����Ôg�j
2.���ҍs���s���҂́i���a�Ôg�j<�i�����Ôg�j
3.��Ќo���̂Ȃ��V�����Z�l�Ɛl�����x�́i���a�Ôg�j<�i�����Ôg�j
4.���������́i���a�Ôg�j����ԂŁi�����Ôg�j�����ԁi��������3���œ����j
5.�s���s���҂̑{���̋K�͂Ɗ��Ԃ́i���a�Ôg�j���قƂ�Ǎs���Ȃ������̂ɑ��āi�����Ôg�j�͑�K�͂Œ����Ԃɘj���Ď��{
6.���ҍs���s���҂̒����́i���a�Ôg�j�ɔ�ׂāi�����Ôg�j���p���I
7.�g���s���̈�̂́i���a�Ôg�j�͍s���s���҂ɓ��邪�i�����Ôg�j��DNA�Ӓ�ȂǂŎ��҂ɓ���\��������
8.�Ôg��i�h����A�h���сA���H�A�����ړ]�j�͂��ꂼ�����Ă������A��ʂɂ́i���a�Ôg�j�����K�͋Ǐ��I�ŕ����Ôg����K�́i�h����͒Ôg�̐N�������ƈ����g�̗�����ቺ��������ʂ�����j
��L�̂悤�ȏ܂���Ɣ�������̈قȂ�Ôg�ɂ��āA�s���s���҂̔䗦��P���ɔ�r���邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ����Ƃ�������܂����A����̒Ôg�ł͍s���s���҂̌����ɂȂ���v���i�Ⴆ�Ώ�L4.�`8.�j�������ɂ��W��炸���ҍs���s���҂�5�l��1�l���x���s���s���ł��鎖���́A���a�O�����n�k�̒Ôg�̏ꍇ�Ɠ��l�Ɂu�����g�̋��|�v��\���Ă�����̂Ǝv���܂��B�Ȃ��A1896�i����29�j�N�̖����O�����n�k�Ôg�ł͎��ҍs���s����2��2�疼�Ƃ�����Q���������܂����B�����͎��҂ƍs���s���҂��ċL�^����K�v�����F������Ȃ��������߂ɍs���s���҂̔䗦�͕s���ł����A����2�ɂ��Ύj���̋L�ړ��e����́u���a�̒Ôg�ȏ�ɍs���s���҂̔䗦�����������Ɛ��������v�Ƃ��Ă��܂��B
�i�Q�l�F1995�N�̕��Ɍ��암�n�k�̏ꍇ�A����6,434�l�ɑ��čs���s���҂�3�l�j