�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����20�N12��13��(2008.12.13)���͔x���ɜ늳�����B���M38.1���`39.9���ɒB���鍂�M�������A�P
���A�\ႁA�l���̐߁X���ɂ��B�܂ÃC���t���G���U�ƍl����l�ŃN�C�b�N�r���[����(�C���t���G��
�U�̌���)������A(-) �^�~�t�����l�������A������ɂ��ăt�����b�N�X3T/day�𑱂����B���M�͂�
�̌�������R���܂��P�e�b�N300mg�~2T�Ɋ����A�X��12��19����胆�i�V��S�Ò��p3g�~2���[�{�s��
�����A��M�����B�����w���B�e�ʼnE���x��ɔx���蒆���삩���A�W���Z��������A�ꌩ�ٌ^�x����
���Ɏ��Ă���Ǝv�������A����ÏW�����@16�{�@�}�C�R�v���Y�}�@40�{�����Ŕے�I�ł������B�v��
��ɔx���ɜ늳�A����̐V�����R��������p���Ă��Ȃ��Ȃ����ʂ��łȂ��āA10���Ԃ̒����̎��Â�
��������炸��M���Ȃ������B�R�������̌����Ȃ��x���ł������B
���̎��_�Ōd��Ȃ��t�ł���A�R���܂̔��B��������A����Ȕx���łȂ�������A�x���͕���
2�`3���ŁA�����Ă�5���ȓ��ʼn�M����͂��ł���B����ȂɍR�������̌����Ȃ��x���͂���������
�C�t���ׂ��ł������B
������F��-Streptococcus(GPC) (+)�@TB��(-)�@����ȍۂ͌��o����Ȃ��BMRSA���A���ܑϐ���
�A�V�l�o�N�^�[�̊����ł��Ȃ������B
����ႂɂ���זE�f���A��
2008�N12��22�� S�����a�@���@

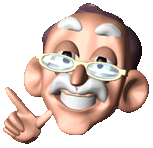
 �@�@�@
�@�@�@