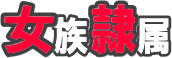
2−1 痴女電車
ポーン軽い音を立てて、エレベーターがとまる。
「えーと、忘れ物は…無いよな」
正樹はもう一度、カバンの中を覗きこむ。
うん、すでに用意されていた教科書もノートも持った。
お昼を買う用の財布も持ったし、電車の定期券も持った。
冴子さんの準備は万端だったようだ。
冴子さん……
その途端に、首筋につけられたキスマークと股間がうずきだす。
「だめだめだめ…」
正樹はぷるぷると首を振って欲望を払いのける。
そう……あの後、結局、玄関で2回、入り直したお風呂で1回、激しく美貌の叔母さんに誘われるままに交じり合い、さらには急いで玄関に向かったはずなのに、気がつけばまた正樹のペニスはお口で咥えられザーメンを搾り取られていたのだ。
しかも朝は忙しいキャリアウーマンは時間がないとかで、少年のスペルマを全部飲み干すと、口元から白濁液を滴らせながら会社に行ってしまったのだ。
そんなエッチすぎる保護者の出勤を見送った正樹はシャワーでもう一度体を洗い、学生服に着替えるとマンションの扉からようやく出られたのだった。
あぁ……僕なんてことを…
っと悩んで見ているが、その実、その顔は十二分にやけていた。
昨晩まで女性のことなど何も知らなかった自分が、今では誰もが羨むほどの最高の美女を手に入れ、あまつさえその抜群の体と高貴な心を好き放題してしまっているのだ。
冴子さん……
正樹はついさっきまで愛し合った綺麗過ぎる叔母さんの淫らな姿を思い出して、心ここにあらずといった感じになってしまう。
その時
「あの、乗られないのですか?」
どうやら、ぼーっと考え事をしていたせいで目の前でエレベーターの扉が開いたのに気がつかなかったらしい。
「へ?あ…はい、乗ります!」
反射的に正樹はそう答えると急いでエレベーターに乗り込む。
そこには先ほど自分に声を掛けてくれた一人の女性が乗っていた。
二十代の後半ぐらいだろうか、高級そうな着物を着こなした、しっとりした美人さんだ。
うわっ凄いな、なんか高級クラブのママとかそんな感じだ。
正樹はテレビで仕入れた知識と目の前の美貌の女性を見比べる。
確かに正樹の考えは年齢以外は間違ってなかった。
高く結い上げた髪に、和服の品にあった小物、薄めだが計算され尽くされた上品な化粧の仕方、優雅な物腰、どれもが一日で手に入るレベルの物でない。
ポーン
思わず、正樹は動きをとめて、見惚れてしまっていた。
「何階ですか?」
「いっ一階ですぅ、一階をお願いしますぅ」
緊張のあまり声が裏返ってしまう。
「クス…一階ね」
桜色の爪がタッチパネルをさわり、微かな作動音とともにエレベーターが下降しだす。
「新しく入居されたかたね」
「え…あ、はい、冴子さん、いえ、川奈さんのところでお世話になることになりました、高梨 正樹です…その管理人さんですか」
「クス…新浜 由乃よ、このマンションのオーナーなの、屋上のペントハウスに住んでいるのよ」
口元を着物の裾で抑えながら微かに笑う。
「あっ、よろしくお願いします」
「はい、こちらこそ」
お互い狭い密室で深々と礼をする。
「クス」
「あは」
しゃちほこばった正樹の様子が面白かったのだろう、由乃は優しげな笑みを浮かべてクスリと笑う。
それにつられて正樹も笑みを浮かべると、お互い顔を見合わせ思わず笑い合っていた。
この一件で新浜 由乃と正樹はお互い打ち解けることができ、正樹は年上の女性と密室でいることも忘れリラックスしていた。
そのままわずかな時間であったが一階につくまでに色々と話がはずんでいた。
「--そうなの、今日から新しい中学校なのね、がんばってね」
「はい」
スッと扉が開くと、豪華なマンションのエントランスフロアが見える。
「いってらっしゃい」
「はい、いってきます」
正樹は素敵な出会いに感謝しながら、朝日に輝くフロアに駆け出していた。
タタタタッと駆け出していくその後ろ姿を、着物の袖をふって由乃は見送っている。
「素直ないい子ね、気にいったわ」
クスッと笑うその口元が、謎めいた笑みを浮かべていた。
「すっ凄い人だ」
駅のプラットフォームは正樹の想像を越えた人で一杯だった。
テレビや人づてに聞いていたが通勤ラッシュがこんなにスゴイものだったとは……
その様子に圧倒されていた正樹は人の流れに飲み込まれ、プラットフォームの中ほどまで押されてしまう。
うわぁっ、なんでこんなに人がいるんだよ。
さすがに、今日はお祭りですか?とは言わなかったが、田舎のバスで通学していた正樹にはちょっとしたカルチャーショックだった。
「なんでこんなに人がいるのよ!」
その時、自分の横で同じような声があがる。
なにげなく、振り向くとそこには二人の女性が立っていた。
「もう、何なのよこれは!」
「……申し訳ありません」
「別にあなたに言っているわけじゃないわ、気にしないでレン」
「……はい、ボス」
二人の女性は日本人ではなかった。
文句を言っている方が上司なのだろうか、彫りの深い鼻筋に、大きめの唇、それに青い瞳。
アングロサクソン系の豪快な美貌が流暢な日本語で話している。
ソバージュのかかった豪奢な金色の長髪が波打ち、ベージュ色の高級そうなスーツがモデルのような外人特有の抜群のスタイルを覆っている。
受け答えをしている方も、日本人ではないのだろう。
短くそろえられた赤い髪に、茶色の瞳、静謐とした落ちついた雰囲気の女性だった。
存在感としては隣にたつ豪華な金髪美女には負けるが、凛とした清涼感を漂わせている。
そして淡いブルーのビジネススーツに包まれた体は、上司に負けないスタイルと美しさをはなっていた。
「しかし、まいったわね、電車なんて乗るの久しぶりよ」
「……わたしもです、ボス」
滑らかな日本語が艶やかな赤い唇から流れ出る。
外人のため、正樹には正確な年齢がわからなかったが、おそらく二十代の半ば過ぎあたりだろうか?
金色の綺麗な人のほうが、赤い髪の美しい女性にくらべ幾らか年上の様な雰囲気だった。
そして二人とも、抜群なスタイルを誇る長身で、おそらく正樹より頭一つ分背が高いだろう。
正樹はなんとなくコンプレックスを感じながら、ちらちらと二人の美女を覗き見る。
よくみれば、周りの人たちもみんな彼女たちを意識して見ていた。
その様子はまるで二人が混雑するホームの真ん中で、舞台のスポットライトを浴びたように悠然と立っているようだった。
「…そうか、みんな外人が珍しいんだ」
周りの様子に合点がいった正樹も、テレビ以外で初めてみる白人女性をマジマジと見つめる。
だが、いまのご時世、外国人が珍しくて眺めるなんて事は、そうそう無い。
実際は映画の中から抜け出てきたようなこの二人の白人女性の、あまりの美しさに誰もが見とれていたのだ。
周りのサラリーマンや学生らしき青年達は前かがみになりながら彼女たちを見つめ、女性たちは、売店のおばちゃんも含めて羨望の眼差しを送っていた。
だが、当の二人はそんな視線など無視して会話を続けていた。
「申し訳ありません、わたしのミスです、このような……」
「いいのよ、レン、社の公用車が故障したのも、ハイヤーが捕まらなかったのも、あなたのせいではないわ……でもこの混雑は」
「……ご辛抱ください、ボス」
きりっとした眉毛をピクピク振るわせる上司に、冷静な口調で赤毛の女性が声をかける。
「ほんとにもう」
金髪の美女は相当イラついているのか、長い爪の先を真っ赤な唇でカリッと噛む。
その仕草があまりにも色っぽくて、周りの男性たちは思わず生唾を飲み込み、鼻の下を伸ばす。。
そして正樹も、海外の有名グラビア雑誌から飛びでて来たような二人の美女の虜になっていた。
すごいなぁ、この人達に、冴子さんといい、由乃さんといい、さすが都会、美人が多いや…
本当の所、そうそう、むしゃぶりつきたくなるような美人がいるわけではないが、正樹はこれまでの恵まれすぎた出会いから、都会は美人が多いのは常識だと思い込みだしていた。
ただ、単に彼の周りにはすこぶるつきの美人が集まってくるだけなのだが……
『まもなくホームに電車が参ります、白線の内側に…』
スピーカーからアナウンスが流れ出すと間もなく、黄色い電車が正樹たちの目の前に流れ込んでくる。
カシュッ、ガー―――
作動音と共に扉が開くと、今までじっと立っていた人たちが、開け放たれた電車のドアにむかって一気に殺到しだしていた。
「え!…あ、あ?」
当然、正樹はその流れについていけるわけも無く、次々と車両に吸い込まれていく人たちを唖然とした顔で眺めるだけだ。
『ドアが閉まります、ご注意ください』
しかも、ものの数秒とたたないのに、まだ人がぎゅうぎゅうと乗り込もうとしているのを無視して、無常にも締め切りのアナウンスが響く。
「嘘だろ!まだ乗ってないよ」
通勤ラッシュは戦争なのだ。
悠長な事は言ってられない。
これに乗らないと、初日から遅刻決定だ。
「でぇいい」
正樹は一足遅れて人の壁が立ちはだかるドアに向かって走り出す。
そんなどんくさいのは正樹一人……だけではなかった。
「なんなのよこれ!」
「……どうやら先着順のようですね」
例の二人の美女も髪を乱して走っていた。
「うぐっ」「きゃ」「…」
三者三様の声を上げながら、三人は一つのドアに殺到する。
体格の良い二人の美女がぐっとその体を突き入れた隙間に正樹が入り込む形でなんとか車内に滑り込む。
それとほぼ同時に……
ブッシュ―――
電車のドアが作動音と共に閉まる。
そして、まるで痺れを切らしたかの様にすぐさま電車はホームを離れ走り出す。
この日の乗車率は200%を軽く超えていた。
「むううう」
「きゃ、なによこれ」
「……痛いです」
最後の最後に無理やりなだれ込んだ正樹と外人女性の二人は、ドアに押し付けられる様にして満員電車の洗礼を受けていた。
正樹の姿勢はドアを背にするように立ち、その右前と左前にそれぞれ例の二人の美女が覆い被さる様に少年を挟んでいるといった具合だった。
「たく、ひどいわねこれは、レン大丈夫?」
「…問題は…ありません、ボス」
ボスと呼ばれる上司らしい金髪の女性と、レンと言う名の赤毛の二人は車内に背を向け、正樹の頭越しにドアのフレームに手を付いてなんとか姿勢を安定させていた。
「……」
そして、正樹は真っ赤になって下を向いていた。
理由は簡単、目の前に二つの大きな胸の膨らみがあるのだ。
右にはベージュのスーツをバンと押し上げる張り詰めた巨大なバスト、左には淡いブルーの膨らみをこちらもドンと突き出すボリュームたっぷりに大きな存在感のバスト。
……すっ凄い胸…
しかも、二人の外人美女は小柄な正樹より頭一つ高いため、二人のスーツを押し上げるバストの頂が、丁度正樹の顔の前に突き出された形となっていた。
ガタン ガタン ガタン
電車が揺れる度に二つの巨乳が正樹の顔の左右で上下に弾むように揺れている。
服の上からでも、その肉の柔らかさと形の良さがわかる程の揺れ方だった。
「本社のある駅までどれくらいかかるの?」
「……三十分ほどだと」
さらに、頭の上から二人が話す度に甘い吐息が漏れてくる。
その色気を感じただけで、正樹の股間に血がどっと集中する。
しかも、右からドアと正樹を挟むように立つ豪奢な金髪美女のほうの長い脚が、正樹の足の間に入っているのだ。
腰の位置が異様に高いため、微かに曲げた美脚の膝が正樹の股間ぎりぎりを掠るように動いている。
…あぅ、だめだ
極めつけは、二人の美女が電車の振動ごとに体を揺らすため、その度に正樹の体に触れるか触れないかの刺激を与えてくるのだ。
「……う」
目をつぶってやり過ごそうとするが、逆に彼女達の小さな動きや甘い吐息が意識される。
うううう、だめだぁ
昨日、いや今朝まであんなに冴子さんと愛し合ったのに、股間のモノは少年の意志に反してすでに大きくなりつつある。
あぁ、いつのまに僕はこんなスケベになってしまったんだ?
冴子さんと一晩中ヤりまくったはずなのに、性欲は衰えるどころかますます増してくみたいだった。
冴子さん……
思わず脳裏に、豊かなバストを腕で寄せ投げキッスをしている冴子さんが浮かぶ。
「あう…しまった、よけい股間が…」
おもわず、股間に手をやる正樹。
その時、
「この痴漢!最低ね!」
目の前の美女が大きな声を張り上げる。
「ひっごめんな……あれ?」
肩をすくめた正樹を無視して金髪の美女がぐるっと後ろを向く。
「この手はなに!」
ぐいっと上に突き出されたその手には、彼女の後ろに立つ真面目そうなビジネスマンの腕が握られていた。
「…いや…私は…これは…その」
しどろもどろになるビジネスマンに金髪を揺らす美しい野獣が大きな口をゆがめて笑いかける。
「はん!あんたが私のお尻を触っていたのは判っているのよ、見ていたでしょレン」
「……はい、ボス」
「……そっそれは…」
「このまま警察につきだしてやるわ、痴漢は立派な犯罪よ」
その綺麗できつめの顔立ちと同じように、この金髪美女の性格は炎のように熱しやすいのだろう。
怒りで睨みつけるその姿はまるで狩りをする豹の様に気品と野生に満ちていた。
「……すいません…つい…でき心で」
その眼光で睨みつけられたビジネスマンは顔を青くしながら痴漢をすぐに白状してしまう。
周りの乗客は黙ってことの成り行きを眺めているようだった。
もっともその心中は、関わり合いにならないように思いながらも、男性客のほとんどがビジネスマン風の男に同情していた。
あんな魅惑的な尻を振られたら誰でも触るよ……と
だが、恐ろしいほどの色気と怒気を放つ金髪美女にはそんなことは通じはしない。
「ほら、ごらんなさい、レン警察に連絡なさい、罪には罰を与えないとね」
「……はい、ボス、わかりまし…あっ!」
「きゃ」
男が罰と聞いた途端、その手を振り払ったのだ。
「ごめんなさぃいい」
雌豹に背を向け謝罪の言葉を叫びながら、辺りの人を掻き分け遁走しだす。
「ちょっと待ちなさ…」
ガタン、キィィイイイ
「きゃあぁ」「うわぁぁぁ」「わっぁぁあああぁぁ」
ちょうどその時、電車が大きくカーブを曲がりだし、予期しない遠心力が襲い掛かる。
乗客たちが数名悲鳴をあげ、どっと車内全体が、正樹のもたれるドア側にむかって押しやられる。
「あ、こら!待ちなさい」
正樹の体にもたれかかる様にして難を逃れた金髪の人が声をあげる。
これをチャンスと痴漢の男性は、人ごみを無理やり押しのけ邪魔な人を押し倒し逃げ出すと、強引に隣の車両に移っていったのだ。
追いかけようにも、混乱した満員の電車の中をこれ以上進むことはできないだろう。
「ちっ、逃がしたか」
「……大丈夫ですか?」
「あら、私があれくらいでへこたれると?」
「……いいえ、ボスではありません、そこの少年です」
「え?」
彼女が驚いて振り向くと、そこには彼女のお尻とドアの隙間で挟まれる正樹の姿があった。
「あら、君そんな所で何しているの?」
「あうぅ…なにって…」
先程、カーブの惨劇の時、金髪の女性がドアにぶつからずに済んだのは正樹がクッションになっていたからだった。
そのことに遅まきながら気がついた彼女は、乱れたスーツの襟を直しながら正樹に声をかける。
「あら、ごめんなさ…」
だが、謝罪の言葉が正樹の顔を見てピタリと止まる。
「?」
「……」
じーーと見つめてくる青い瞳。
なにか気に入らなかったのだろうか?
被害者なのに正樹は不安になって話し掛ける。
「あの…どうしました?」
「…………ふふ、痴漢しといて、よく言えるわね」
突然、グラマラスな金髪美女は正樹の方を睨みつける。
「どうせ、あなたもあの男と同じ穴の狢じゃないのかしら、いやらしい男ですものね」
流暢な日本語で話しながら、異国の美貌がそっと正樹の耳に口をよせて囁きかける。
「い・や・ら・し・い」
「ちっ違いますよ」
「あらどうかしら?」
そう言うと、今度は豊満な胸の下で腕を組み、スッと正樹を睨みつける。
正樹を睨みつけるその顔は、美人なだけに迫力が凄かった。
正樹も自分がやってもいないのにまるで犯人のような気分にさせられる。
きっと会社でも相当なやり手なのだろう。
今なら、先程吊るし上げられたビジネスマン風の男の人の気持ちが良くわかる。
だが狼狽した正樹は、金髪美女の勝気な瞳が、悪戯好きな猫の様に輝いていることも、組んだ腕が胸を押し上げ正樹の体にわざと押し付けられていることにも気がついていなかった。
「ぼっ僕違いますよ、本当です」
「嘘おっしゃい」
「……ボス、彼は違います」
正樹の横でレンが正樹の無実を訴える。
だが、彼女の上司はとまらなかった。
「ふっ、この子は、痴漢よ、間違いないわ」
「……ボス?」
レンは小首をかしげた。
彼女の上司はたしかに激しやすい性格だった。
型破れの常識と行動力で世界有数の企業の幹部までのし上がった、超切れモノだ。
だが、こんな理不尽なことはする人ではなかったはず……
どう見ても、この場合彼女の上司が後ろの少年にぶつかったのだ。
長年この上司に仕えてきたが、こんなことはレンにとっても初めてだった。
「……どうしたのですか、ボス?」
「レン、この子がわたしの体に触っていたのよ、ひどいでしょ」
「僕…そんなことしてません……本当です」
正樹にも何がなんだか分からなかった。
目の前の女性が痴漢を捕まえた時は、びっくりしていただけだし、電車が傾いた時も慌てふためいている間に、もたれかかってくる目の前の女性に押されただけだ。
正樹はとりあえず助けを求めて周りを見回すが、先程の混乱から乗客は誰もが電車の傾きに耐えるため吊り輪や取っ手にしがみ付き、こちらに気がついている人はいない。
「ふん、そう言って君も逃げる気でしょ…逃がさないわよ」
ぐいっと金髪の女性の体が正樹をドアに押し付ける。
「あぷっ」
ふにゃん、と大きな胸がスーツごしに正樹の顔を覆い尽くす。
「ふふ、これで逃げられないわね」
「……ボス!」
上司の驚くべき行動に慌てるレン。
「大丈夫よ、証拠もあるの、ほら」
そういって金髪女性は片手で持っていた何かを彼女の部下に渡す。
「……これは?」
「あたしの腰にひっかかっていたのよ、それ、この子のでしょ」
レンの手のひらの上には皮製の腕輪が乗せられていた。
「あ…それは僕の!」
「……あなたの?」
レンの茶色い瞳が正樹のそれにぶつかる。
その瞬間、ぴくっとレンの体が小さな雷に打たれたように震えていた。
「そうです、僕のです」
しかし、幸か不幸か、正樹はそれには気がつかなかった。
「あら白状したわね」
金髪美女はニヤリと笑みを浮かべると、自分の胸の谷間で押さえつけている少年を見下ろす。
「そんな…僕、痴漢なんて……っあ」
その時、正樹は自分を見つめる青い瞳がトロンと濁っていることに気がつく。
これは……!!
そうだ!昨晩の風呂場で最初冴子さんがおかしくなった時の目にそっくりだ。
「ふ、観念したわね」
ぎゅっと押し付けられた胸がわざと上下に揺らされ、白い指先が正樹の顎をなぞる。
「ふふ、痴漢をした悪い子には、お仕置きが必要ね」
その途端、正樹のズボンの股間にさわっと白い手がふれる。
「あっっ」
「あら、もうこんなに、やっぱりね、いやらしい子」
それはそうだ、こんな美人に体を密着されれば誰だってこうなっちゃうに決まっている。
こんな美女に、抱きつかれて、うれしい、うれしいけど…
だからといって、こんなところで…
「やっやめてください」
「あら、先にわたしに触ったのは、君よ、ほら」
その途端、白い指がなぞるように正樹のズボン越しにペニスを撫で上げる。
「あぅ、うう」
「ふふふ、いけない子ね」
だれかに助けを!
しかし、背の高い彼女が壁になり車内の他の人はまったく見えない。
その時、横から微かな声がした。
「……ボス」
「どうしたの、レン」
たすかった!そうだこの部下の女の人が助けてくれる。
冷静な感じのこの女の人ならきっとなんとかしてくれるはず……。
だが、正樹の願いは残念ながらかなう事はなかった。
おもむろにレンが横からぎゅっと正樹を抱き締めてきたのだ。
「……私もお仕置お手伝い致します」
「え!」
ついさっきまでクールな光を宿していた茶色の瞳が、欲情で狂っていた。
白い頬はピンク色に燃え上がり、豊かな胸が上司のそれに負けないように正樹の顔に擦りつけられる。
気がつけば正樹は電車のドアと、二人の美女の柔らかい体に挟まれていた。
「ちょっ、ちょっと待ってくださいぃ」
「あら、ダメよ、あなたは犯罪者なんだから、わたし達の好きにできるのよ」
「……ええ、そうですよ、おとなしくしてください」
股間を弄ぶ手が一本増えていた。
「そんなむちゃくちゃな…あ、あ、あ、あぁ」
背の高い二人にすっぽり囲まれ正樹の体は車内の他の人からまったく見えない。
ガタンガタン
列車は満員のお客を乗せて走り続ける。
その車両の一つで、正樹と二人の美女が絡みあっていた。
金髪の美女は、ねっとりとピンク色の舌でエロティックに唇を舐める。
「罪には罰を与えないとね」
赤毛の美女は、半開きの唇からチロチロとピンクの舌を覗かせる。
「……覚悟してください」
二つの甘い肉体が電車の隅に少年を追い詰めると襲い掛かっていた。
誤字脱字指摘
11/24 mutsuk0i様 12/10 2/1 TKX様 12/12 あき様 9/20 H2様 7/26 花房様
ありがとうございました。
11/24 mutsuk0i様 12/10 2/1 TKX様 12/12 あき様 9/20 H2様 7/26 花房様
ありがとうございました。