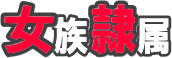
3−5 雌虎降臨
『ぴりりりり〜〜〜』笛の音が鳴るとの同時に正樹は屈伸の姿勢のままグラウンドに突っ伏してしまっていた。
「ひぃい、しんどい」
隣ではお調子者の賀川が汗を流してグラウンドから立ち上がっている。
確かに、つらい。
準備体操だけでもうへとへとだった。
「大丈夫か?高梨顔青いぜ」
細目の山岸が正樹に手をかし立たせてくれる。
「ありがとう山岸君」
「山でいいって」
「うん……やっ……山さん、ありがとう」
そういってなんとか立ち上がる正樹。
その格好は学校指定の冴えないジャージ姿だった。
胸には「山岸」のネームが貼られている。
その時……
「おい、そこ私語は厳禁だぞ」
鋭い声とともに正樹の上を大きな影が覆う。
「すいません春風先生」
山岸は柄にもなく、ぴしっとした声をだし背筋を伸ばす。
そこには、ジャージ姿の女教師がたっていた。
なにより際立っているのは、その大柄で抜群のプロポーションだろう。
身長は優に180は超えている長身に、大学の頃から鍛え上げた自慢の体をジャージが覆っている。
そして茶色のベリーショートの髪型に、にっと大きな特徴的な唇、意思の強そうな大きな瞳。
そのワイルドな魅力を余すことなく引き出す美貌に長身がみせるモデルのような抜群のプロポーション、それが普通科2年の体育担当教師、春風 弥生だった。
彼女のファンの賀川情報では、年は今年で26才、担任の薫子先生の一つ下になるらしく大学からの先輩後輩の間柄だそうだ。
そのせいかどうか知らないが、その長身の胸元、真赤なジャージをぐいっと押し上げるように大きなバストが張り出している。
なんでも指導する時、あの胸があたるらしくてそれ目当てにこの授業を受ける生徒も少なくないらしい。
確かにきりっとした美貌に、あのスタイル、男ならだれだって迷わずこの授業を受けたくなるだろう。
だが、その性格は……
「私語厳禁、お前ら連帯責任で全員グランド10週だ!」
バリバリの体育会系だった。
しかも中学生相手だろうが容赦なく厳しい。
だいたいマラソンの準備運動で筋肉痛になるほどのスクワットに腕立て伏せをさせる先生もそうそういないだろう。
本人にとっては軽い運動なんだろうけど……
「んん?そこの転校生なんで「山岸」のジャージを着てるんだ?」
「あっこれはまだ自分のなくて借りてたんです」
正樹は突然示されて慌てて背筋をのばす。
春風先生はじっと正樹の目を見ると一つ頷き、生徒の名簿が入ったファイルを開く。
「え〜と、名前は高梨正樹でよかったか?」
「はい、高梨です」
まるで軍隊コントのようにしゃちほこばる正樹。
それほど目の前の女体育教師は威圧感をもっていた。
「う〜ん、体の線が細いな、もっとちゃんと食べないとだめだぞ」
グイッとその美貌が正樹の方に突き出される。
「はっはい」
自分ではまったく意識していないのだろう、その魅惑的な胸が正樹の目の前に押し出され、整った顔が間近まで接近していた。
これは健全な男子中学には体育の時間よりさらに辛い拷問みたいだ。
思春期の彼らにとって普通の女の人にこんな事されれば興奮するような物なのに、相手はそうそういない美貌に引き締まったプロポーションの持ち主。
興奮しないほうがおかしいぐらいだ。
しかも、下はジャージ姿だから勃起なんてしようものなら大変だ。
正樹は心の中で必死に数学の公式を思い出したりして気を紛らわせる。
やがて、正樹の体をまじまじと眺めた魅惑の女体育教師はひとり頷いて大声をだす。
「よし、正樹以外の者はグラウンド10週!正樹はこっちについてきな」
『え〜〜』と不満をのべるクラスメイト達は春風先生の一睨みで立ち上がると急いで走り出していく。
「あの……僕は?」
「あぁ、初めての生徒は全員基礎体力の測定をして貰う事にしている、基礎体力もわからずに指導はできないだろ」
春風先生はついて来いと顎で示すと、正樹の前を歩き出す。
ジャージに包まれたヒップはくいっと持ち上がり、細い腰を軸に軽快に揺れている。
堂々としたその歩き方はまるでモデルのようなウォーキングスタイルだ。
「はっはい」
正樹はその後ろ姿を心持ち前かがみになりながら急いで後を追っていた。
「これは?」
「ん?鉄棒だよ、見てわからんか?」
大きな胸を突き出すようにして春風先生は腰に腕をやり快活にしゃべる。
「まずは懸垂をしてもらおうと思ってな、ほらやってみろ」
「あっはい」
正樹はくいっと顎で鉄棒をさされ鉄棒を握ろうとする。
「ん?ちょっとまて、正樹、体育の時は腕時計をはずさないとダメだぞ」
「え?あっちょっと先生これは……」
正樹の腕がぐいっと引っ張られると腕につけられた例の「母の形見の腕輪」が無造作にはずされる。
「ああぁ!」
「んん?どした?あれこれ時計じゃないのか?飾りか?」
「そっそれは母の形見なんです、返してください」
なっなんてことだ!大変だ!
正樹は春風先生の目を見ないようにして腕を伸ばす。
「えっ、そうなのか……悪いことをしたな、すまん、高梨」
さっぱりした性格そのままに春風弥生は素直に謝ると、正樹の手にそっと腕輪を返す。
「そんな事情があるとは知らなかった許してくれるか?」
その声は本当に反省しているのだろう、しょんぼりとした悲しげに聞こえ正樹は思わず先生を見あげて返事をしてしまう。
「いえ、いいですよ気にしてませんから」
にっこり笑って微笑む。
「そうか、よかった」
ほっとした様子で胸を撫で下ろす春風先生。
そんな二人の視線はしっかりと結ばれていた。
そして正樹の腕輪はまだはめられることなく手のひらの中。
「あっ!」
正樹は慌てて俯くと、腕輪をはめる。
しまったぁ、腕輪を返してもらったから油断しちゃった。
もしかしてもう……
正樹はおそるおそる、しかし心の底で少しだけ期待しながら目線をあげる。
だがそこは生徒のファイルを開き顔をそむけた先生の姿しか目に入らなかった。
「先生あの……」
「じゃぁ懸垂してみろ、正樹」
事務的にそう言いながらファイルにペンを走らす春風先生。
今のところ何の異常も見られない。
思い過ごしだろうか?
まさか「僕のこと好きになっていますか?」などと聞けるはずも無く、正樹は黙って補助を伝って鉄棒を掴むと懸垂を始める。
補助台をけって宙に浮かぶと腕の力だけで上体を引き上げる。
「ううっ…いちぃ」
ろくに鍛えたわけでもない正樹にとって本格的な懸垂は非常につらかった。
正樹は必死に鉄棒にしがみつき懸垂を繰り返す。
だが四回もしないうちに腕の筋肉がピクピク振るえ、いまにも滑り落ちそうになる。
「ごっ、ごぉぉ」
なんとか顎を上げるようにして鉄棒を越すが、もう力がでない。
「ほら、どうした?まだできるだろ」
春風先生の叱咤がすぐ側で飛び、正樹は目を閉じ歯を食いしばりながらそれでもなんとか体を持ち上げる。
正樹にも美人の女体育教師に良いとこを見せたいって意地があった。
足をバタバタと振りながら最後の足掻きでなんとか鉄棒の上まで顔を持ち上げる。
「……ろっ、ろーくぅう」
だがここがもう限界だ。
「先生……もう落ちそうで……」
正樹の細い腕がプルプルとふるえ今にも鉄棒から離れそうだった。
「なんだ、まだ六回しかできてないじゃないか……しかたないな手伝ってやる」
「え?」
春風先生はそう言うと、鉄棒にぶら下がる正樹の正面から抱きつくよう支え上げる。
「ちょっちょっ先生」
体力測定なのに手伝うのは反則じゃないのだろうか?
などという正樹の疑問など届かないように春風先生が腕に力を込める。
ちょうど鉄棒からぶら下がる正樹の胸に女教師の顔が埋まり、ジャージ上着の張り出したバストに下半身が押し付けられる。
……あっ先生の胸が……柔らかくていい気持ちいい……
正樹の股間に急激に血がめぐると、ぐんぐん大きくなり先生の胸を圧迫する。
お互いのジャージ越しにまるでパイズリするような格好だ。
遮るのは薄い2枚の布だけ、春風先生だって正樹の股間がテントを張っているのは丸わかりだろう。
だがそれにまったく気づかない素振りで春風先生は正樹の体を支えて持ち上げる。
「ほら、正樹腹筋に力いれな、あげるよ、七っ」
ぐいっと下から持ち上げられて正樹の体は懸垂を再開する。
「いいぞ、ほら、ゆっくりおりて」
屈託のない春風先生の声とは裏腹に、その体は正樹の下半身にべったりとひっつき、腰に回された腕もしっかり組まれている。
「せっ先生恥ずかしいですぅ」
「いいから、次いくよ、八ぃ」
それでもお構いなしに、ぐいぐいと押し付けられる柔らかな乳房。
ジャージ越しに擦れるその感触が正樹を追い詰める。
「あぁ先生……だめ……僕」
「我慢しな、ほら九ぅっ」
ぐいっとあがった体につられ、下半身のテントが春風先生のジャージの膨らみを押しのけ口元にせまる。
凛々しい美貌の体育教師はぐいっと顔を正樹の膨らみに押し付ける格好になっていた。
「あうぅ」
「ほら、手をしっかり持ちな、ふざけてると怪我するよ」
先生がしゃべるとその息がジャージ越しに正樹のペニスにねっとりと襲い掛かる。
しかも、開いた唇のほんの数ミリ先にテントの先端があるのだ。
「ほら、腕のばして」
「あぁ……こっこんな……」
……春風先生はもしやあの時僕の不思議な魅了の力に捕らわれたんじゃ……
正樹はガクガクと振るえる体をゆっくりと降ろしながら唇をかんで耐える。
「次、十っ」
ぐいっと擦り付けられる巨乳の感触。
……間違いない、もうぜったいワザとだ。
僕のあの力がまた働いちゃったんだ。
どうしよう?どうしたら?
だが慌てる正樹を春風先生が放すわけはなかった。
テントの先が胸の谷間をぐいぐいっと押し上げ、感触のいい塊が下半身を刺激する。
そしてハァァッとジャージ越しにかけられる甘い息。
「ううぅっ」
正樹は眉をゆがめて鉄棒の上に顔を無理やり上げさせられていた。
「ふふふ、よくできたぞ……んっ」
「あうっ」
その時、かぷっと春風先生の唇がジャージ越しに正樹のテントの先端を甘噛する。
「あっあっ先生何を……ううっ」
「十回できたらからご褒美だ、んっ」
下を見ると鉄棒からぶら下がった下半身を抱き締めた春風先生が、ニヤリと淫蕩に微笑みこちらを見上げている。
その半開きの大きな口の先が正樹のジャージの膨らみに吸い付き、はむはむと歯を立てる。
「だっ駄目、やっやめてください、かっ噛んじゃ」
「ふ〜ん、噛むのはいやか、じゃぁ別のご褒美だな……ちゅく」
「うひぃ」
春風先生は唇の先をすぼめるとちゅうちゅうとジャージを啜りだす。
べっとりと唾液を含ませられ、びしょびしょになっていく正樹の股間。
ちゅじゅくじゅくちゅじゅじゅ
ジャージの膨らみに美貌が吸い付き、湿った水分で蒸らすように愛撫している。
「あっううぅ…こんなぁ…ああぁ」
「はぁ…すごい匂いが漂ってきてるぞ、正樹、授業中にこんなとこを大きくするなんていけない奴だな」
その生徒の股間に顔をうずめて幸せそうにする先生のほうがもっといけないのだが、そんなことはどうでもよかった。
ねっとりと舌が這いまわり、濡れたジャージ越しにはっきり正樹の肉棒の形が浮かんでくる。
「ふふふ、あたしで感じてくれてるんだな、可愛いぞ」
ぱくんと大きく口を開くと、じゅるじゅると先走りと唾液を啜り美味しそうに目を細める。
そのあまりに淫乱な口撃は、あっという間に正樹を絶頂に導いていた。
「あっあっもう……ダメェェ」
だが正樹がパンツの中に精を放つ前に、その腕が鉄棒から離れてしまう。
「うわぁぁ落ちる……あれ?」
「ほいっと、がんばったな正樹」
正樹は春風先生に抱きかかえられていた。
ひょいっと軽々正樹の体を肩に担ぎ上げると、まるで何事もなかったかのように足元に優しくおろす。
「さてとちょっと片付け物あるんだ手伝ってくれるか?」
春風先生は何事も無かったかのように地面に座りこむ正樹を見下ろしている。
「え?……はっはい」
鳩が豆鉄砲をくらったようにきょとんとしながら正樹は反射的に頷いていた。
「そうか、じゃぁそこのラインマーカー持ってきてくれ、わたしはこれを持って行く……奥の体育用具室だ」
颯爽とそう言うやいなや、春風先生はそばに放置されていたハードルをいくつか肩に担ぎあげるとスタスタ歩き出していた。
『お〜〜い、お前ら今日はあとグラウンド20周な、それが終わった者からあがっていいぞ』
春風先生が向こうのグラウンドでひぃひぃ走る生徒達に声をかける。
それを聞いて倒れる者も出る始末だ。
正樹は唖然としながらその光景をぼんやり見ていた。
「おい、正樹なにしてる?はやく持って来い」
その声に正樹は濡れている下半身を気にしながら急いでラインマーカーを引きずると、先行して歩き出している先生の魅力的なヒップを追いかける。
その歩みはまるで何かに急かされるように急いでいた。
「いったいどうなっちゃったんだろ?」
正樹はただ呆然としながらも、自分の力がどこまで働いているのかという焦りと期待を持ちながらその後に着いて行くしかなかった。
「先生、一時の気の迷いだといいんだけど……」
もちろんそんな訳はなく、正樹に見えない向こう側で春風弥生はにんまり淫らに微笑んでいた。
これから起こるであろう気持ちのいいことに女の園を濡らしながら。
ガラリ
引き戸を開けるとそこには様々な用具がしまわれていた。
大きな籠に山と積まれたサッカーボール、ずらりと並べられた金属バット、棚には縄跳びやバトン等の小物が積まれている。
「えっとこれはここでいいか」
春風先生は両肩にかついだ重いハードルをものともせず、ずんずんと倉庫の奥に歩き出す。
「ほら、ついてきな」
正樹も先生にいわれるままにマーカーを持ち上げると体育倉庫の奥へ運び入れる。
「それは、もっと奥だ、正樹」
「はい」
フラフラしながら何とか正樹は薄暗い倉庫の奥に入っていく。
大きな高跳び用のマット横、石灰の袋が積み重ねてある横に正樹は何とかマーカーを運び入れていた。
「ふう」
歩いているうちに少しは乾いたがそれでもやはり股間の濡れたのが気になってしかたがない。
なんだか授業よりも疲れたかも……
それに先生大丈夫なのだろうか?
さっきの鉄棒でもあんな風になっていたのに……
このまま何事も無くすんでくれればいいけど……
「もう疲れたのか?だらしないぞ高梨」
その時、春風先生が薄暗い体育倉庫の隅でいきなり正樹の肩をつかむ。
「うわっ」
「やっぱり、さっきの鉄棒でも思ったが全然筋肉ついてないじゃないか、中学男子ならもっと鍛えないといけないな」
青いジャージの腕がぐいぐい正樹の二の腕を掴み上げると、撫でまわしてくる。
「ぼっ僕あまり運動とかは得意なほうじゃないので」
「そうか?正樹の体つきは鍛えたらそこそこいけると思うけどな」
豪快に笑いながら短髪の美女はさらに正樹の体に手を伸ばそうとする。
「やめてください……僕筋肉ないですよ」
「ふ〜ん、だめだなぁ高梨は、あたしを見ろこれ日々の精進だ」
自慢気に笑うとおもむろに先生はジャージの腕を捲くり上げてぐいっと力瘤をみせる。
確かに、そこには無駄な贅肉ひとつない綺麗に伸びた筋肉が躍動していた。
ぐいっと突き出された二の腕が鼻先に突き出される。
運動の後だろうか、美女のほのかな香りが正樹の鼻をくすぐる。
「うはははは、高梨も鍛えたほうがいいかもな?」
腕に力をいれていた先生はぐいっと正樹につめよってくる。
「別に僕はそこまで体を鍛えようとは思ってませんから」
正樹はなんだかとんでもない方向に進もうとしている会話を必死に修正しようとする。
「いいからいいから、ほらあたしが体をもっとよく見てやるよ、そこに手をつきな」
そういいながら大柄なその体がぐいっと正樹に押し付けられると、むりやり壁にむかわせて両手をつかせる。
「あっ……そんな」
「大丈夫だ、これでも大学でスポーツ科学の学位をとったんだぞ、高梨の体の状態をチェックしてやるよ」
壁に両手をついてたつ正樹の背後からしっかりと女教師は抱きつくと身動きを封じる。
「そっ、そうじゃなくて、こんな所でそんな……」
正樹は身をよじって逃げようとするが、大柄な春風先生は後ろから抱きついて正樹の薄い胸板を撫でまわしだす。
「ふ〜〜ん、ほんとにぜんぜん筋肉ないな贅肉もないけど、もっと運動しないとだめだぞ」
「ちょっちょっと先生」
背後から抱きつく女体育教師の大きな胸がジャージ越しに正樹の背中にあたっている。
「腹筋もぜんぜんないじゃないか」
「やっやめてください」
正樹は震える声をだすが春風先生は一向におかまいなしだ。
「先生冗談はやめましょうよ」
「……あのね、冗談でこんなことすると思う?」
耳にふっと息をかけながら春風先生はいままでにない甘い声をだす
あぁやっぱり……
正樹はうれし泣きのような声をだしていた。
これはもう確実だろう。
とほほっと泣きながら正樹は確信していた、春風先生も自分の力の影響を確実に受けている事を……
しかも相手はまた自分の先生。
そりゃ薫子先生はこれは僕の特技の一つだって言っていたけど……
でも……あぁ胸の感触気持ちいいし……いいのかな?……このまま溺れちゃって……
その時、正樹の頭の中に、裸エプロンでにっこり微笑む冴子さんの光景が浮かぶ。
『ご主人様』
そだ!冴子さんだってこんなことしてばかりじゃ怒っちゃうかもしれない!
しかし、正樹の思いと裏腹に、魅惑の叔母さんの肢体を思い出した下半身は、正樹の理性を無視してさらにヒートアップしてしまう。
うわぁん、逆効果。
そっそうだ、ここはまずはっきり先生に言わないと……
「先生!聞いてください!先生がおかしくなっちゃっているのは、僕のせいなんです」
正樹は柔らかい胸の感触を確かに感じながら大声をだす。
「僕……僕……だいぶ変で……その、信じられないかもしれませんけど、腕輪をはずすとなんだかみんな僕の事が……その、好きになっちゃうというか……変になっちゃって、それで先生も僕のことを」
柔らかい感触と甘い匂いにくらくらしながら正樹は必死に説明しようとする。
そして春風先生は――
「んふ、正樹の髪の匂い良いな、くんくん」
などと言いながらさらに強く抱き締め正樹の髪に顔をうずめたり、耳に唇を這わしたりと悪戯をしかけていた。
……駄目だ、先生まったく聞いてないよ
とほほほっと嘆く正樹の顔がぐいっと後ろを向けられると、そこにはトロンとした瞳の女教師がまっていた。
まるでまたたびを嗅いだ猫のようにうっとりと正樹の顔を眺めている。
「さっきのご褒美が途中だったからな……んんっ」
ぐいっとねじられた正樹の顔に春風先生の美貌が迫り、唇が重なる。
「んんっ」
「あうぅ……んんっ……んん」
それはまるでむしゃぶりつくような濃厚なキスだった。
春風先生の大きめの唇が正樹のそれを覆い尽くし、長い舌が唇を開け強引に押し込まれるとまるで奪い去るかのように絡みつき、唾液を啜っていく。
んんっちゅるんん、ちゅちゅじゅるるる
「んは、すごっ、美味しっ、正樹の唾液凄い美味しいぞ……んぐっぐちゅ」
ぐいぐいと押し付けられる美貌とともに甘い匂いが辺りを包み込む。
それは冴子さんのような優しくスケベなキスとは異なり、まるで獣のような激しいものだった。
んんぐ、んちゅんちゅちゅちゅちゅ
「あん、んぐ、ああぁぁ、正樹いいよ、んっ、舌もっと絡めて…あぐっ…そう…いいぃ」
「ううっ…むむ…むぐっ…ぷはぁ」
音をたてて唇が離れると、唾液の橋がつつっと落ちる。
「こんなキスはじめて…なぁもっと」
「だっだめですよ」
いままでの経験でなんとか理性を保っている正樹が必死に声をだす。
「とっとりあえず…先生話を聞いてください」
「いいよ、もっとキスしてくれたら聞いたげる」
んんっと伸びた舌が正樹の唇をなめ、くちゅくちゅと中に潜り込もうとしてくる。
「んんっ…ぷはぁ…だめです!今聞いてください…先生が僕のこと求めてるのは勘違いなんですよ」
「は?何をいっている?そんなこと関係ないだろ?」
「え?…だから、先生が僕のことこんなになるのは…」
正樹は後ろから抱き締められ大柄な肉体に包まれながら声をだす。
「ふ〜〜ん、正樹はあたしのことバカにしてんだな」
麻薬のようなキスをやめられ春風先生はいらだって声をだす。
……本当に正樹はわかってない!
まるであたしが生徒をつまみ食いする淫乱教師みたいないいかたして…あたしが食べるのは正樹だけってしっかりわからせてやらないと。
などともう完璧に落ちてしまった思考で腕の中のか弱い生徒に声をかける。
「ちっ違いますよ、僕はただ」
「あたしはね、お前のことが好き、すごく好き!それで抱きたいから抱く、わかる?ただそれだけだ」
あまりにもストレートな愛情表現に正樹は声も出ない。
ジャージの上から正樹の股間がまたすりすりと撫ぜられる。
「あうぅっ…僕の意見は…」
……ふふふふ、正樹は本当にわかってないな、正樹の意見なんて関係ない。
もし、正樹をいま抱けなかったら…どうなちゃうか…それを考えただけで弥生はおかしくなりそうだった。
ここは強引でもいい正樹にいろんなことしてあたしを認めさせてやらないと!
「それに正樹もこここんなにしてあたしを求めてくれてる、お互い欲しがっててSEXしちゃだめなわけないだろ?な?」
どう考えても学校の先生、しかも年頃の女の先生の言葉とは思えない。
だが、春風にとってはこれで十分だった。
「しかも、あたしはお前が好きだし…これで文句ないよな」
「でっでも、僕は…」
冴子さんもいるし……それに薫子先生も……あぁ電車の中の外人のお姉さんだって……
まだ中学生、それに童貞をすてたばかりなのにもう5人の美女の告白をうけて正樹は目を白黒させていた。
そりゃ春風先生みたいに素敵な先生に慕われて嬉しくないわけないけど……
「だっだめですよ…薫子先生にも悪いし…あぅ」
正樹は、思わず数時間前に自分のペット宣言をした美貌の爆乳女教師のことをもらしてしまう。
その股間がぎゅうっと掴み上げられる。
「あひっ」
「いまなんて言った正樹……まさか先輩とも?」
ぎゅうぎゅうと締め付けられる正樹の股間。
「あうぅ…やっやめてください…」
「だめだ、あのお堅い薫子先輩をあたしみたいにしちゃったんだろ?」
春風弥生にとって、薫子先輩って言えば、大学のころからの付き合いで良く知っている・・・・自分みたいなお気楽教師じゃなくて、見た目はふざけちゃいるが超がつくほどの真面目な教師だ。
それをこの子が……
あぁ…あたしにもして欲しい…同じことを、いやそれ以上を!<SPAN>
もうピンク色に蕩けた思考で春風先生は正樹を抱き締め詰問する。
「どうなの?どんな風に薫子先輩としたの?」
さらにぎゅっと少年の股間の張りをにぎって促してやる。
「あっ…それは…その…先生が…僕のペットになるって…それで色々」
「あの先輩が…ふぅ〜〜ん、薫子先輩は良くてあたしは駄目なんだ?正樹」
ぐいっとペニスの先が形が浮き出るほどに掴まれ、ジャージの上からまたしゅっしゅっと擦られだす。
「あっ……そっそれは…ううぅ」
「そうだよね、先輩胸大きいし、女っぽいし、あたしみたいな乱暴なのとは大違いだよねぇ」
そう言いながらも、耳を噛んだり股間をこするのをやめはしない。
「あぁ、あたしも正樹に薫子先輩みたいに飼ってもらいたいなぁ…だぁめぇ?ねぇ、正樹?」
チロチロと舌が正樹の耳の縁をなぞり、ゆっくりと中に潜り込んでいく。
「ね?ね?ね?う〜〜んとサービスするから、わたしもペットにしてくれよ」
それは肉の甘い餌をつかった脅迫のような物だった。
肉感的な肢体をもつ女体育教師に抱きつかれ股間を弄ばれて落ちないわけがない。
正樹は無意識のうちに頷いていた。
「あん、ありがとう正樹、これで今日からあたしも正樹のものか…あぁ中学生のペットになるなんてね、ふふふふ」
満足げに笑いながら春風先生は正樹の体をそっと放す。
「あっ…先生」
正樹は体を包んでいた暖かさと、股間をまさぐる巧みな手を失い寂しそうな声を出す。
「ふははは、心配しなくても逃げないよ、まずは正樹にあたしをじっくり堪能してもらおうと思ってさ」
そういうと春風先生は薄暗い部屋の中でバサリとジャージの上を脱ぐ。
そこには汗で乳首が浮き出た白いシャツが大きく突き出していた。
それとともに広がる汗と女の蒸れたような甘い香り。
「どうした?じ〜〜と胸ばっか見て、そんなに好きか?」
「えっ……それは……」
即答できず口篭もる正樹の両手がむんずと掴まれる。
「じゃぁ十分触って感じるといい、あたしのおっぱいをさ」
ぐいっとシャツの隙間から押し込まれる。
固く割れた腹筋の上に、ぶるんっと突き出す挑発的な肉の塊。
「あっ…先生」
「どうだい?気持ちいいだろ?これが今日からお前のもんだよ」
自慢気に笑いながら春風先生は正樹の腕をシャツの下で自由にさせ、うれしげに目を細める。
その驚くほど張りのある突き出した美乳を正樹の両手はタプタプと揉みしだき、こねくり回す。
「あっ…正樹いいよ…すごく…ふふふ…いいだろあたしのおっぱい」
「はっはい」
嘘ではなかった、薫子先生のように爆乳ではないが、それでも常人以上のその巨乳は鍛えられた腹筋と大胸筋で支えられスケベなミサイルのように突き出している。
やがて女教師の頬も欲情にそまり、乳首が痛いほど勃起してシャツの生地を突き破らんばかりになっていく。
正樹はたぎる欲望にまかせておっぱいを触りながら春風先生に声をかける。
「先生…ブラジャー」
「あぁ、つけてないよ」
あっけらかんとした口調でいう春風先生。
「だってさ、あれきつくてやなんだよね、それにあたし胸の形くずれない自信あるからさ」
ぐいっと自分の巨乳に手をあてる少年の小さな手をシャツの上から押さえつける。
そこにはおっぱい特有の柔らかさと同時に、発達した大胸筋でぐいっと持ち上げられた張りがあった。
「ジャージ着てれば乳首あんまり気にならないしな、それに教師の安月給じゃあたしのサイズにあうブラ買うのも大変なんだぞって、そんなこと気にせずもっともめもめ、ほら」
豪快に正樹の手を掴んでぐにぐにと押し付ける。
「あ…そんなに…先生」
「ふふふ、どう気持ちいいだろ?コリコリしててさ、あたしの自慢のおっぱい触らせてやってるんだぞ」
確かに自慢するだけあって、ぷりぷりとした手触りは正樹の股間をダイレクトに刺激する。
「どうだ?」
「その…気持ちいい…です」
正樹は真赤になりながら、春風先生に導かれるまま手を動かす。
ぐんっと突き出された白いシャツの中を正樹の手が動き回り、指が張りのある肌にめり込み痣をつけるほど絞りあげ揉み倒す。
「あっ…んん、うまいじゃないか、正樹」
ほんのりと頬を染めながら春風先生は大きな口を半開きにして喘ぎ声をあげると、ぐいっと正樹を抱き締める。
「うぶっ」
正樹の顔がシャツ越しに抱き締められ、爆乳にうまる。
「せっ先生」
「ふふふ、なんだか抱き締めたくなっちゃったからさ」
正樹と春風先生の身長は頭一つ分以上ちがい、その大柄な女体に抱き締められるとまるですっぽり包み込まれるような具合だった。
「うむむむ、うはぁ」
窒息するほど抱き締められた正樹が顔をあげると、そこにはにっこり微笑む体育教師の笑顔があった。
「ほんとお前って可愛いよな、生徒にこんなことするなんて思わなかったけどさ」
「そっ…そう思うならやめてくださいよ」
正樹はその大きな胸と腕の中ですねたような声をだす。
「え?本当にやめていいのか?」
くすくす笑いながら春風先生の腕が正樹の股間をさらにジャージの上から擦りだす。
「あぁ」
すでに魅惑の肉体美でビンビンになっている正樹の股間はジャージの上からでも丸解りだった。
「こんなにしてるくせに」
「そっそれは先生が…いろいろと」
「むむむ、口答えしない!そんな子にはお仕置きだぞ」
「え?」
ばっと抱擁から開放された思った瞬間、正樹の体が宙を舞っていた。
えええ?なんだ?
「うわぁ」
次の瞬間ドサッとそばの体育マットの上に投げ飛ばされる。
「なっ何するんですか?」
「だっかっら、お仕置き」
がばっと仰向けにねる正樹にのしかかってくる大柄な美体。
「ちょっちょっと先生、駄目ですよ、あぁ、ズボンを脱がさないで」
「だ〜〜め〜」
いくら抵抗しようとしても、鍛えられた大人の力には適わない。
それに体に押し付けられる大きな胸の感触に、甘いねっとりとした大人の香り、ハァハァとした欲情の息遣いが正樹の抵抗の力と理性を半減させていた。
「先生っ」
「ふふふふ、ほらもうズボンがぬげちゃったぞ、次は……」
それとは逆に春風弥生は正樹と体を触れ合わすたびに言い知れぬ心地よさを感じていた。
抱き締めれば抱き締めるほどランナーズハイにも似た爽快感とそれ以上の麻薬のような心地よさが襲ってくる。
冗談めかしてしゃべっているが、切羽詰っているのは実は春風のほうだった。
「ふふふ、そらぁ」
「だっ駄目ですってば」
疲れて抵抗をやめた正樹のズボンとパンツが引きずりおろされ、元気なペニスがビイインっと薄汚れた体育準備室の天井に向かって聳え立つ。
「すっ凄、ここは立派なんだな正樹は」
うっとりとした顔で春風先生はその美貌を正樹の股間に擦り付けんばかりに寄せる。
「そっそんな見ないでください」
「だ〜め〜〜、んんっこの匂い、正樹の匂いなんだな」
ビクンビクンと脈動する先端に形のいい唇がより、ふっと息を吹きかける。
「うはぁ」
「ふふふ、またビクッてしたぞ…どうだ?どうして欲しい?正樹は?」
「どうして欲しいって」
正樹はマットに押さえつけられながら、首をふる。
「言わないとできないよ、だってあたしお前のペットだもん、ふふふふ、ご主人様命令してくださいませってね」
意地悪に笑いながら春風先生はあ〜〜んと口を開けてわざとチロチロと舌をだす。
その先が正樹のペニスにつくかつかないかで、ぴったりとめる。
「あぁ…そんなぁひどいよ先生」
「んんっひどいのは正樹だよ、ちゃんと命令してくれたらあたしは何でもしてやるって言っているのにさ」
タラリとこぼれた唾液の雫が鈴口を伝わり流れ落ちる。
もう…もうだめ…我慢できないよ
「おっお願いします…先生の口でしてください」
「ふふふ、素直が一番!あ〜〜ん……んぐっ」
ぱくりと春風先生の大きく開けた口のなかに飲み込まれる。
「うっ…うわ…あぁぬるぬるして…ううっ」
「うぐっ…ずずずっ…んんっ」
ズッズズズズッ
喉の奥までいっきに飲み込まれ、ねっとりとした舌が絡みつく。
「どうら?きもひいい?ん?…んぐ…ずずずっ」
春風先生はあふれでる唾液と同時に生徒の肉棒を啜りこむと、頬をすぼめてきゅっと圧力をかける。
その大きな瞳は喘ぐ正樹の顔をのぞきこみ、満足そうに笑っている。
「そっ…そんな…激しく…しちゃ」
「むふ…こうは?どうだ?」
ズッズッズッズッズッ
根元をしっかりにぎったショートカットの髪が上下に揺れると、正樹のペニスがすぼめられた唇から出たり入ったりを繰り返す。
「だっ駄目です…うっうっうっ」
「んっんっんっんっ」
正樹はばたつきながら、春風先生の頭を押さえようと手をやるが、それでもその勢いはとどまるどころかますますエスカレートしていく。
ズチュズチュズチュ
「うわあぁぁぁ、すっ吸われてる…それに…だっ駄目やめてください。あぁぁぁ」
がくがくとマットの上で背筋を伸ばして射精をこらえる正樹。
「んっんっんっ」
その股間に顔をうめた体育教師は生徒の声などまったく無視でまるで叩きつけるようにフェラをすると喉の奥で吸い上げ絞り続ける。
いやらしい音と粘液を吐きだし肉棒を責める喉と頬肉。
ぼこっぼこっと音をたて頬が窄まるたびに、正樹の背筋が反り返り絶え間ない快楽に脳の奥が破裂するようだった。
ズッズッズッズツゥ
「あぁもう…もう…もううぅ」
正樹が女の子のような悲鳴をあげ限界が近いことを告げる。
にんまりと笑う春風先生の細い指先が玉袋をコリコリと揉みしだき、射精をうながす。
もちろん頬をすぼめ吸いながら激しく頭を上下させることは忘れていない。
「あぁ…うっ」
ドピュドピュドクドクドクドク
ぶしゅううっと吹き出る濃厚な白濁液。
「うっうぐぅ…んっ…ごくごくごく」
美貌の女体育教師の頬がぷくぅと膨らむが、鍛えられた喉がゴクゴクと上下してすぐに嚥下する。
だが、朝からの性行為を繰り返しSEXすればするほど強靭になっていく不可思議な正樹の体はそれ以上の量のザーメンを注ぎ込む。
「うぐっ…んっんっんっ…ぶふっ」
唇とペニスの隙間からこぼれでる泡だった精液。
しかし、そこはさすが豪快な春風先生、最初は目を見開いて驚くが、グゥと頬に力をこめると喉を鳴らしてさらに飲みだす。
しかも射精しつづけるペニスをしっかり掴むと、さらに激しく頭をふり正樹のザーメンを搾り出す。
「うっ…あぁぁぁああ…吸われてる…僕…僕…うううっ」
ドピュドピュドピュ ゴクゴクゴクゴク
「んぐ…うぐ…んぐ、んぐ」
まるで清涼飲料水を飲むようにゴクゴクと喉を鳴らして飲みつづけつる女体育教師。
「ぁあぁあぁああ…うっ」
「んぐ、んぐ、んぐ…ぷはぁ」
やがてその全てが美女の胃の中に注ぎ込まれていた。
「はぁはぁはぁはぁ…あぁぁ」
「んぐっゴクゴク…ずずずっ…ぷはぁ」
ぐぽっと音をたてて大きな唇が長々と精をはなっていたペニスを吐き出す。
「んんっ…すごい量だな、胃の中がお前のザーメンでちゃぷちゃぷいってるみたい、ふふふ」
にんまり笑いながら更に春風先生は横からペニスをぱくりと咥え、したたり落ちるザーメンをおいしそうにちゅうちゅう啜り上げる。
その大きく健康そうな唇は正樹の精でねっとりと輝いていた。
「あっ…ううっ…先生全部…その、飲んで…」
「うん、飲んじゃったぞ、だって正樹が一生懸命だした子種だもんな、飲むに決まってるだろ?」
さも、当然といわんばかりにニッと笑うとペニスを握りペロペロまた舌で愛撫する。
「それとも顔にかけたかった?それならそれでもいいけど…でもあたしはお前の子種を無駄にしたくないからなぁ…んっあっここにも垂れてる」
玉袋を伝いアヌスのほうに落ちたザーメンがベロンと舐め取られる。
「うわっ」
「へへへへっ、さてと、こっちは元気なままだし、そろそろいただきますか」
たぷんと大きなバストをシャツ越しに揺らして春風先生が起きあがる。
「え?」
「だからぁ、いただいちゃおうかなぁって、正樹をさ」
「いただくって…」
「もちろん犯すの」
嬉しそうにそう言うとマットに仰向けに寝転がる正樹をまたいで立ちあがり、ゆっくりとジャージのズボンと下着を脱ぎ始める。
「せっ先生」
ごくりっと正樹の喉がなる。
今目の前自分の真上で、美人でスタイルが良くはきはきとした女体育教師がそのズボンを降ろしているのだ。
「ふふふ、よく見てるんだよ」
ぷりんっとまるで剥き卵のようなお尻が現れる。
真下から見ている正樹の目には、鍛えられた筋肉の浮かんだ太股の付け根、むっちりとした肉の狭間に、茶色の濃い茂みに隠れた美女の肉の入り口がはっきり見えていた。
「あん、もうびしょびしょ」
くいっと形のいいお尻が揺れるたび、正樹のお腹の上にぴちょんぴちょんと愛液の雫が垂れ落ちている。
「それじゃ正樹いい?」
「はっはい」
それを合図に、まるで和式の便座に座るようにゆっくりと大きなお尻が下りてくる。
「あっ…あうぅ」
「ふふふ、よく見てな、お前のおち○ちんがあたしの中に入っていくぞ、ずぶずぶってな」
にんまり笑いながら正樹の直立したペニスが上からせまる肉の壺の入り口に挿入され、
その花びらからタラリとこぼれる愛液が正樹自身に絡みつく。
ズズズッ
「あうぅ」
「んんっ」
びくんと振るえる引き締まった桃尻。
その肉の割れ目にペニスがゆっくりゆっくり埋もれていく。
「あっ、あっ、見て、見て、正樹のが、あぅうぅ入ってくる、わたしを貫いているよ」
喉をそらして喘ぐ女教師の唇からこぼれる欲情の唾液。
ズッズッズッズッ
「ううっ」
正樹の亀頭が花びらを割ると濡れた肉の壁に抱き締められる、まるで誘われるように奥へ奥へと差し込まれる。
自分の意志とは関係なく肉欲に狂った体育教師に正樹はまさしく犯されていた。
「あはぁ…すごいよ…正樹のすごい…入っただけで、体中ぶるぶるして…あん」
そして、それは春風先生もまったく同じ心境だった。
春風だって男性経験がないわけでない、いやむしろ薫子に比べたら格段に多いほうだろう。
それなりに色んな体験をしてきた。
でもそれももう終わり。
今日、自分の全てを与える相手にめぐり合ったのだ。
それが中学生で自分の生徒で、自分の友人をペットにしているようだが、そんなの関係ない。
ただ、彼に……正樹に尽くすことだけが今の春風の望みだった。
ついつい意地悪したくなるようなこの可愛い飼い主様に。
「あうぅん…気持ちいい…あぁう」
ぐにゅっと亀頭が体の中に入った瞬間、あまりの気持ち良さに彼女の足から力が抜ける。
ふわりと宙を浮く大柄な美体、そしてその下で待ち受ける愛しい飼い主様の肉の槍。
ズチュウウウゥウウ
「あぐっうう」
「ううっう」
二人の腰と腰がぶつかり根元までペニスが貫き通す。
春風先生は火花が散るほどの快楽に喉をのけぞらせ、快楽の絶頂に簡単に駆け上がると、その鍛え上げられた肌から汗が迸り、ぎゅうっと筋肉が美しく盛り上がる。
「ううっ締まる」
正樹のペニスを根元まで飲み込んだ膣内が、鍛えられた腹筋で締め上げられ絶妙の快楽を与えてくる。
「あぅ…うぅうう…凄いよ…あぁぁ先生」
「はぁはぁはぁ……あっあたし入れただけでいっちゃった、ふふふじゃあ動くぞ、しっかりあたしのおま○こで正樹のおち○ぽしごいてやるからな、期待してろよ」
ポタポタと顎先から汗を流しながら、美貌の女教師はそっと生徒の薄い胸板に手をつき騎乗位を楽しみだす。
ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ
突き立った肉棒が膣内をかきまぜる音が響き渡る。
「あんっんんっ…ううっいいよ、ち○ぽいいぃ」
春風先生はまるでダンスを楽しむかのように目をつぶり、ゆったりと体を揺らしながら正樹の腰に自分の腰をからめて円を描く。
気持ちよさそうなその唇から涎の筋が流れ落ちている。
「先生…あぁ…僕も」
正樹はそのうねるような気持ちの良さにどっぷりと浸っていた。
春風先生の中は、膣内のザラザラとした感触に加え鍛えあげられた腹筋の締め付けが素晴らしかった。
ぐちゅぶぎゅぐちゅぐちゅぐちゅ
「ふふふ、正樹いいだろ?ほらここも触っていいんだぞ」
くいっくいっと腰を動かしていた春風先生が汗でべっとりひっついたシャツをたくし上げる。
そこにはぎゅっと引き締まったお腹に、ぶるんぶるんと挑発的にゆれる剥き出しの巨乳が汗で光っていた。
「ふふふ、正樹の好きなおっぱいだぞ、ほれ」
捲り上げたシャツの裾があまりにも大きなバストの上で引っかかり止まると、春風先生は正樹の腕を魅惑の肉塊に誘導する。
「あぁ先生…ううっ…あぁう」
ギシギシと腰を揺らしながら正樹は、女教師の形のいい美乳をまた揉みしだく。
うっすらと埃も立ちこめる体育準備室の中、古びたマットの上で女教師が生徒の上に騎乗位でまたがって腰を揺らし、大きな胸を与えSEXを貪っている。
お互いの陰毛が絡まり合い、その間から卑猥な液が混ざり合い流れ出て、さらに卑猥な音を奏でる。
「ふふふ、ほんとに可愛いな、おっぱい好きな子にはご褒美だ」
春風先生は腰を揺らして淫らに笑いながら、春風先生は正樹の顔の上にタラリと唾液をこぼす。
「あぁ…んぐっ…ごく」
ねらい違わず滴り落ちた唾液は正樹の口の中に消え、さらに唾液の甘い攻撃が続く。
「んっ…おいしいか?あたしのお口?んんっ…ほらもっと」
だらだらと流れる甘い液体が空中を伝わり正樹の口を顔を胸を浸す。
その間も二人の腰は休むことなく波長のあった動きを繰り返していた。
「んっ…んぐ…うはぁ」
「あっあっ…いいよ正樹、あぁそこえぐってるぅ、あぁそうそう、んんっ、ほんとすごい、気持ちよすぎだよ、あぁぁ」
その時、体育倉庫の薄いベニヤ板の向こうから休憩時間になったのだろう他の生徒のガヤガヤと騒がしい声が聞こえだしてきていた。
「あぁほんと今日は疲れた」
「だよなぁ春風先生すぐいなくなっちゃうし、損した感じ」
正樹はその聞き覚えのある声にビクンとする。
「あふぅ…いいぞ…もっと…正樹」
「せっ先生みんなが外にいます…ううっ」
正樹は必死に声をかみ殺そうとするがうまくいかない。
春風先生が正樹の上で淫らに腰を動かし続けているのだ。
「先生…駄目ですって…ううっ動いちゃ声がでちゃう」
「ハァハァハァ、あぁだめだよ、正樹気持ちよくて腰がとまんない…あたしじゃなくて腰が勝手に動くの」
いまだに外の喧騒は聞こえている。
「なぁ高梨どこにいったんだ?あいつ次の授業の予定わかるのかな?」
「どうだろ?初めてだとこの学校難しいしな、迷子になっているかもしれないから探しに行こうぜ」
「OK〜俺急いで着替えてくるよ」
バタバタとせわしない足音が響き、やがて遠くなっていく。
今の山岸君たちだ。
正樹は申し訳ない気持ちになりながら、それでも春風先生の巨乳を揉む手を放すことはできなかった。
「ふふ、行ったみたいだな…あぁん、正樹もスケベなんだな、腰を動かすなって言って自分はあたしの乳首をひねってくるだもん、おかしくなりそうだったぞ」
「そっそれは…先生があんまり動くから…それで」
正樹は言い訳がましくそういいながら、そっぽを向いてしまう。
しかし正樹はその背徳感のような行為になんとも言えない魅力を受けているのも事実だった。
「僕…どんどんスケベになってるのかも…あぁうう」
ぐいっと腰を押し付けられ、正樹は思わず胸から手を放し美女の細い腰を押さえつける。
「ほら、正樹今はあたしだけを見てくれよ…それともあたしとするのいやか?正樹は…あぅ」
クイクイッとリズミカルに腰を動かしながら、組み敷いた少年を見下ろす。
「そっ…そんなことは無いです…けど…あぁ」
「約束したよな、薫子みたいにあたしも飼ってくれるってさ」
「かっ飼うって…」
肉の誘惑に負けて思わず頷いちゃったけど。
そりゃ先生みたいな最高の女の人を自分の物にできたらって誰もが思うことだけど……
先生なんだよ…
でも、こんな美人を……それに薫子先生だって…
実はもう心の奥の欲求では結論の出ている悩みに、正樹が悩んでいると。
先生の張り詰めた太股がぴったりと少年の腰をはさみ、腰の動きを一時的にとめる。
「あぅ…せっ先生ぃそんなぁ」
「どうする?ちゃんとあたしを飼ってくれる?んんっっ」
「そっそんな…さっきは腰が止まらないって…」
にんまり微笑ながら春風先生は正樹を見下ろしている。
その健康的な肌は汗にまみれ、妖しく色づいていた。
「あたしを飼ってくるなら腰を動かしてあげてもいいんだけどな」
そういいながらも、お互いの腰は微妙にちゅくちゅく動いている。
止められないって言うのは嘘じゃなかったのだろう。
どちらも我慢できず止めたつもりが無意識のうちに動き出してしまっている。
「さぁ言って宣言して、正樹があたしの…春風弥生のご主人様だって、飼い主だって、そしたら動いてあげる」
正樹の薄い胸についた手が、乳首をもてあそびコリコリとひっかきだす。
「あっ…あぁ駄目だよ、そこはやめてぇ…あぁう言うから、言うよ」
「ふふふ、良い子…さぁ弥生は何?」
期待に頬を染めならがら春風先生はねっとりと自分の唇を淫蕩になめる。
そのさまは獲物をねらう猫科の肉食獣のソレだった。
「春風先生は…あぁう」
「だめよ、弥生、ペットは呼び捨てだろ、な?」
「ううっ…弥生は僕の…ペットです」
「ふふふ、それで」
ゆさゆさ大きなおっぱいを揺らしながら弥生は愛しい飼い主を見つめる。
さあ、はやく言っちまいな、お前の口から!
あたしが卑しいペットだって!
正樹専用の精液処理ドーブツだって言ってくれ。
言わないなら可愛い乳首をつねって体中を舐めまわしてやる。
「僕は…あぅ…春風弥生の主人です、飼い主です、いつでも弥生に僕を…あぅ…入れて…ぶち込んで性欲を処理しますぅ」
「あは、よく言えました、それじゃご褒美だ、たっぷり正樹のペットのま○こ味わってくれよ」
猛然と美女の腰が少年の上で動き出していた。
ぐっちゅぐゅちゅぎぐちゅぐちゅ
二人とも長いタメがあったせいか急激に高みに上っていくと、まるで獣のようにお互い求め合い愛し合う。
「あっあっあっあっ…ううぅ」
「はぁはぁはぁはぁ、いい、ぎもちいいぃ、だめ、おかしくなる、あぁぁぁ」
ズンズンズン ぐちゅぐちゅじゅくじゅく
その激しさに、体育用具室のトタン板がガタガタゆれ、棚からリレー用のバトンが転がり落ちる。
だがそんな音は獣のように肉の交わりにふける二人には関係なかった。
「あぁ、いいよ、いいよ、弥生すごく…ううっ」
「はぁはぁはぁ正樹もご主人様も、ゴリゴリして、あぅうこんなのはじめてぇ」
汗が迸り、二人の間から淫液が弾け飛ぶ。
薄暗い部屋は熱気に満たされやがてそれは臨界点を迎えていた。
「ううぅう、でるでる〜でちゃうよ」
「いいよ、そのままあたしの中に沢山だして、あぁあぁ正樹の精子あたしの卵子にぶっかけてぇぇええええ」
二人が汗をとばし獣のように絶叫する
ドピュウウゥウ ドピュウ ドピュ
正樹の肉棒の先から飛び出した白いマグマは、子宮口を通り弥生の中に注ぎ込まれていく。
「あぅ…んっ…うううっ…いいよ、出てる正樹の子種があたしの中で泳いでる、あぁまたドクドクって…うはぁぁ」
正樹の腰の上に座った美女は体を艶やかに動かしながら、それでも射精しつづけるザーメンを一滴残さず貪欲に絞り取り、引き締まった腹に収めていく。
ドクドクドクドク ドクドク ドク
やがて常人では考えられない量と濃度の精液が残らず女体育教師の鍛えあげられた肉体を満たす。
「いっぱいでたな、ふふ」
ばったりと汗まみれになりながら、下になる正樹の胸に倒れこむ弥生。
「はぅ、気持ちよかった」
桃色の吐息を吐きながら甘えるように頬を寄せてくる。
ほんとうにこんなこと弥生には初めてだった、ここまで愛することも、それにことがすんだ後こんなに気持ち良くて、またすぐに元気になってしまうことも。
その全てが嬉しくて、そしてなにより正樹と一つになれたことが幸せだった。
「んふふふふ」
自然と零れ落ちる笑みを浮かべながら正樹の頬を指でなぞる。
「ほんとたくさん出したな、あたしの中、正樹で一杯だぞ」
「すっすいません」
思わず謝る正樹。
そうだよな昨日からみんな生で中だしだもん…
僕大変なことをしちゃってるんじゃ…
「コラ、なに謝ってんだ?あたしはありがとうって言ってるんだよ、大丈夫、正樹に迷惑かけないからさ」
正樹は唖然としながら、ゴロゴロと胸に抱きついてきている春風先生の美貌を見つめる。
正樹の精をお腹一杯満喫したその顔はまるで獲物をとらえた野生の獣のように満ち足りていた。
「あぁでもこれであたしは正樹の飼い猫になっちゃたんだ、薫子みたいにさ」
「そっそんな」
どちらかというと飼われてるのは正樹のほうだ。
それに猫というよりトラっていったほうが似合ってるような気がする…
などとは口がさけても言えない正樹。
「それで、毎日犯されちゃうんだよなぁ、きっと」
「そっそんなこと……」
正樹があわてて否定しようとすると、胸の上で満足げに目を細めていたメス虎がギラリと睨む。
「何?」
「あうっ…します、犯します」
ぎゅうっと肉壺に咥えこまれたままのペニスが締め付けられる。
その気持ちいい反抗に情けない主人はあわてて声をあげていた。
「むふ、よろしい、それでさ毎日体育の授業の前にはいやだって言うのにあたしをガンガン犯しちゃうんだよねえぇ…授業中ももちろんみんなが真面目にマラソンしてる時に、あたしを捕まえて水飲み場でさかってくるの…」
「そっそれは先生のほう…あぅ…わかりました…みっ水飲み場で犯します」
きゅうっと正樹の胸の先が摘み上げられ、ペロペロと頬が舐められる。
「もちろん授業の後はここでたっぷり可愛がってくれるんだよね」
「…あっはっい、はい、可愛がります…ううっ」
少年の胸の上で美体がしなやかに動き、甘いに匂いと淫靡な柔肌を擦り付けてくる。
「どうだ?嬉しいか?こ〜〜んな美人の女教師を好き放題だぞ」
「うっ嬉しいです」
正樹は快楽でゆるくなった涙腺から涙を流しながら、微笑む美貌を見上げる。
にんまりと獲物を捕らえた笑みで正樹の顎先を舐めるピンクの舌。
鍛え上げられた体は汗と淫液でむせかえるほど大人の女の匂いを放ち、大柄な体がマットに沈む少年をけっして逃がさないように抱き締めている。
「そっか…あたしも嬉しいよ」
声のトーンががらりと変わり、まるでつぶやくような弱々しい響きが耳にとびこんでくる。
「え?」
今までとの落差に思わず声を失う正樹。
その肩口に女教師の顔が押し付けられる。
「せっ先生?」
だが、正樹の声に返事はない。
いままで威風堂々としていた人物同一とはまったく思えなかった。
その時、正樹は獣のように荒々しいその抱き締め方がふっと緩むのを感じた。
「ほんとに?嬉しい?」
そう、たずねる弥生の瞳の奥は震えていた。
野生の獣ように正樹を抱き締め愛欲のかぎりをつくしたとは思えないほど、弱々しい恐れのような物が見え隠れしている。
そこにあるのは拒絶されたらどうしよう……その怯えだけ…
それが痛いほどわかる視線だった。
正樹はじっとその瞳をみつめると、やがてほっとため息をはくように声を出す。
「本当に嬉しいですよ春風先生、いえ弥生さん、これから僕が毎日貴方を犯します…これでいいですか?」
優しく微笑んでそっと抱き返す。
「うん、ありがと正樹」
それに応える安心し満ち足りた最高の笑顔。
豪快でだれにも縛られない美しい虎が正樹の魅力に落ちた瞬間だった。
「それじゃ、さっそく犯してもらわないとね」
ばっと顔をあげたそこには先程までのしおらしさなどまったくなく、また淫蕩な笑いに満ちたワイルドなメス虎にもどっている。
「はっ春風先生、いまさっき…ううっ」
抱き合ったままつながっていた正樹の肉棒が鍛え上げられた腹筋でまた締め上げられる。
「だって、ここず〜〜と立ちっぱなしであたしの子宮をコツコツつついてるんだもん」
「そっそれは先生が…あぅぅ」
ゆっくりと起き上がる女教師の上半身。
たくし上げられたシャツからはみでたおっぱいがぶるんと振るえ、腰がいやらしく動き出す。
ずちゅずずっぬちゅ
「ふふふ、たっぷりご奉仕してやるからな、ご主人様」
「あぁぁ」
正樹にまたがったメス虎が容赦なく腰をふりだしていた。
『キ〜〜ンコ〜〜ンカ〜〜〜ンコ〜〜〜ン』
お昼の開始を伝えるチャイムが響き渡っている。
「あっおい高梨どこいってんだよ?探したんだぜ?」
「山岸く…あっ山さん、え〜とその、またお腹こわしてさ」
正樹は教室に戻ると、みんな思い思いに机を寄せ合い昼食の準備をはじめていた。
「大丈夫か?」
寺田が覗き込むように正樹をみる。
「うっうん」
まさか春風先生と体育準備室で4時間目をさぼってSEXしまくっていたとは口がさけても言えない。
あの後、お互い狂ったように抱き合い貪り合うように交尾を続けていた。
最低でも4回、いや5回はしちゃったもんなぁ
正樹は乱れて意識を飛ばしながらキスをせがむ春風先生の美体を思い出しまた股間を熱くしてしまう。
「どっした?マジでお前顔赤いぞ?保健室またいくか?」
「いっいや、トイレにいったら収まったしいいよ」
正樹は賀川に手をパタパタふって言い訳するとさりげなく山岸に声をかける。
「その山さん、借りてたジャージだけど明日洗濯して返すよ」
「え?いいよそんなん、べつに俺は気にしないからさ、それより…」
山岸はほんとに気にしていないのだろう、正樹の腕の中のジャージの入った袋を取ろうとする。
「いや!それじゃ悪いよ!洗濯させて」
「…あぁ、別に高梨がしたいならそれでもいいけど…」
おとなしい感じの正樹の大声に山岸は釈然としない様子だったがそれでも手をひっこめる。
「ありがとう」
まさか、春風先生とのSEXで汚れちゃったなんて言えないし…
あのシミって普通の洗剤で落ちるのかな?
とほほほっと人知れず涙を流す正樹だった。
「ところで高梨、メシはどうするんだ?」
「何も、パンでもあれば買おうと思ってたけど…」
正樹はそそくさとジャージの袋をしまうと財布を確認する。
朝方、冴子さんが用意してくれた奴だ。
開けると中には一万円札が数枚と、テレホンカードなどが詰まっている。
それに携帯の番号の書かれた紙に「がんばってね」の文字。
「うひょぉ正樹、むちゃ金持ちじゃん」
金髪の賀川がのぞきこんで口笛をふく。
「いや…その初日だし…なにかと必要かと思ってたくさん持ってきたんだよ…ほら、教科書代とか」
「なるなる、でもそんなに金使うことないぜ、まぁ俺としては帰りにマックの照り焼きセットでOKだがな」
「じゃ俺シェイク…ってそういや賀川おまえ俺にこの前おごるって約束しただろ」
「あり?そうだっけ?」
賀川と寺田がふざけながらじゃれあいだす。
「メシだけど学食も沢山あるし売店もあるからな、俺たちは家から弁当持ってきているけど…なんだったら付き合おうか?」
そんな二人を尻目に山岸が正樹に声をかける。
「うん、ありがとう山さん」
正樹はにっこりと山岸に微笑みかける
「おっおうよ」
なぜか糸のような細い目の下を真赤にして頬を掻く山岸。
「じゃあよ、俺たちも学食でメシ食おうぜ」
「OK〜俺のお勧めは第三学食「どさん亭」のAコースだ、あそこは量が多くてさ……」
うんちく好きの寺田が正樹に学食のお勧めを話し出した。
その時
『普通科2年14組の高梨正樹、至急第三保健室まで学生証持参で来ること』
味も素っ気もない学内放送がたった一度響き渡る。
「あれ?今の僕?」
きょとんと自分を指さす正樹。
「あぁ第三っていえば保健管理のところだよな、たぶん転校の手続きかなんかかな?」
山岸が顎に指をやり考えている。
「だな…だったら途中でパンでも買うしかないか」
寺田がそういいながら教室のドアを開く。
「高梨行こうぜ、購買経由で第三保健室までご案内〜」
「あ、うん、ありがとう」
正樹はパタパタと後をついて歩き出した。
途中、まるでコンビニのような品揃えの購買でジュースとサンドイッチを購入すると、迷路のような階段といくつも連なる校舎を越えて、4人はくだらない冗談を言いながら十分ほど歩いていた。
「ごめんね、ご飯さそってもらったのに…」
「いや、いいよ、メシなんていつでも一緒に食えるさ、おっ、ここだ」
目の前には『中等部第三保健室』とかかれたプレート。
「そんじゃな、また今度メシ食おうぜ」
「うん」
正樹は手をふって歩いていく三人を見送っていた。
「あら、君は?」
第3保健室のドアを開けると、そこには小太りの保健医らしいおばさんが立っていた。
「あっあのさっき呼び出しで呼ばれた2−14の高梨正樹です」
正樹はなぜか緊張しながら裏返った声を出す。
「あぁ、ちょっとまってね」
保険医は正樹に背を向け大きな書類棚をあさりだす。
その保健のおばさんの後ろには無数のベッドが置かれており、まるで普通の保健室を数十倍にそのまま広げたような光景が広がっている。
なんか野戦病院みたい……
よくみればナースの格好をした人もいるし、なんとも凄い所だ。
「えっと、あぁ、あったわ、あなた身体測定のデータがでてないのよ、えと、あなたの担当は……」
なぜかピクンと固まる保健のおばさん。
「あの?どうしました?」
「いえ、何でもないわ、あなた第5保健室でこの書類みせて測定してもらってきて」
パサリとクリアファイルに挟まれた書類が渡される。
「第5保健室ですか?僕まだ不慣れで道が」
「あぁ、これ持っていきなさい…そう…そこに書いてある通り行けばいいわ」
そういって渡されたのは「中等科保健室ガイド」とかかれたパンフレットだった。
「どうもありがとうございます」
正樹はきちんとお辞儀をすると第3保健室を後する。
「第5保健室か…迷わないでいけるかな…」
そんな心配をしながらパンフ片手に廊下をあるきだす正樹は、午前中のあまりに強烈な出来事に友人達から聞いた「あの噂」のことを綺麗さっぱり忘れていた。
そう、第5保健室には魔女が住むという噂を……
「しかし、めずらしいこともあるものねぇ、第5保健室に呼び出されるなんて、あたし初めて見たわ」
第3保健室の保健のおばさんはそう首をひねるが、すぐにそんな些細なことは忘れてしまっていた。
ここに勤めて35年のベテランの彼女にとって、そんなことより遥かにたくさんの生徒を相手にする仕事がまっているのだから。
誤字脱字指摘
10/7 りく様 11/28 mutsuk0i様 2/1 TKX様 2/1 あき様
ありがとうございました。
10/7 りく様 11/28 mutsuk0i様 2/1 TKX様 2/1 あき様
ありがとうございました。