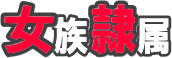
※ 超注意事項:属性は当然寝取り、孕ませ専門デス
初日(1) 若妻催惑
高梨 正樹が、駅前ロータリー広場についた時、待ち合わせ相手はまだ到着していなかった。正樹が通学で利用している最寄り駅から数駅分離れた駅前は、複数の路線が乗り入れる乗換駅でもあり様々な人々で溢れかえっていた。
携帯片手に立つ若い女性、大声で楽しそうに笑う大学のサークルらしき学生の一団、仲良く腕を組むカップル、はしゃいで走り回る子供とその両親。
大半の人々が皆、大小様々な旅行ケースやバックを持ち、いかにもこれから行楽に行って来ますと言う出で立ちをしている。
それもそのはず、何せ今日は三連休の初日。
気象庁は快晴続きを約束し、まさに絶好のレジャー日和だった。
そしてこの連休を行楽地で過ごすため駅に集う人々の中に、高梨 正樹もいた。
無論、正樹の目的も周囲と同様、連休を使った小旅行であり、自分の体に似合わない大きなボストンバックを抱えている。
「少し早く着き過ぎちゃったかな……」
正樹は、叔母さんにプレゼントされた携帯電話に目を落とし、約束の時間までまだある事を確認すると、カバンのサイドポケットから一冊のパンフレットを取り出す。
「小沢山温泉 山泉荘」と楷書で印字された質素ながら高級感溢れる冊子だった。
これこそが、正樹の待ち人でもあり、この三連休を温泉で過ごす計画を立ててくれた相手、妙齢の美女、一条 静江から渡されたものだった。
一条静江は華月流のお茶の女師範であり、ボランティアで正樹の所属する茶道同好会の顧問も勤めている涼やかで落ち着いた美貌の佳人であり、三十過ぎとは思えない若々しさと気品の漂う優美な立ち振る舞い、そしてなにより凛とした筋の通った姿勢が綺麗な貞淑な良妻でもあった。
もし彼女に操を立てる夫がいなければ、周りの男たちは一瞬たりと放ってはおかないだろう。
そんな色気たっぷりの妙齢の和風美女という言葉がぴったりの女性だった。
実のところ、一条静江が他人の妻だからと諦めきれる男性は少なくなく、様々な男性がこの艶やかな佳人を手に入れようとアプローチを繰り返していたが、その全てが貞淑で清楚な静江のつれない態度にあえなく轟沈していた。
そして、かくいう正樹も、静江の着物に包まれた豊満で柔らかい乳房とむっちりと大きなお尻、そして襟首からのぞく白いうなじの誘惑に見事に負け、夕日が差し込む狭い茶室で、意図していなかったとはいえ襲い掛かってしまっていた。
その結果、中学生の少年は貞淑な良妻であった筈の美人妻と情事に及ぶ事に成功し、あまつさえ、なんとその貞淑な人妻の心も身体も陥落させてしまっていたのだ。
もっとも正確には、正樹が持っている未だに詳細不明な「年上の異性を魅了し隷属させてしまう」という何とも不可思議で本人にも制御不可能な力が発動し、幸か不幸か麗しい茶人を服従させ性欲処理の奴隷へと堕としたわけなのだが……
過程はどうであれ妙齢の和服人妻、一条静江は今では自ら進んで中学生の少年高梨を「旦那様」と呼び、その艶やかな肢体を使って少年に尽くす自称お妾さんとなっていたのだ。
そしてその日以来、貞淑な人妻の貞操観念は逆転していた。
夫にしか許さない筈のその麗しい肉体を、逆に夫には指一本触れさせる事なく、中学生の愛するご主人様にだけ与える徹底ぶり。
日々、放課後の茶室で中学生の少年を立派な旦那様に育てるべく、人妻の妙技を尽くしてご奉仕し、熟れた肢体を絡ませ、正つきっきりで褥の指導をしているのだった。
肉感的な茶人のきめ細かい白肌は、少年の舌に嘗め尽くされ、豊満な乳房と丸く大きな尻は若い性欲を吐きだす場所となっていた。
慎ましやかな朱唇や貞操を守るはずの膣内に、夫以外の男性のスペルマを注がれ、お茶の女師範の熟れた肢体で少年の精を浴びていない場所はもうありはしない程だったのだ。
だからと言って正樹が、淫らで大人の色気たっぷりの和服美女に飽きる筈もなく、むしろ更にその肢体の虜となり、部活のある放課後は決まって避妊もせずにセックスに夢中になっていた。
そして当の静江も、そんな少年を喜んで迎え入れ、お妾さんとして少年に寄り添い幸せに過ごしていると言った具合だったのだ。
そんなある日の放課後。
正樹の通う学園の広大な敷地の一角、茶道同好会所有の庵「湖月庵」で、いつものように正樹は人妻の着物の裾を捲り上げ、白いお尻を抱えて後背位で責めぬいていた。
愛する旦那様に抱かれ幸せそうに頬を染めたお茶の女師範は、着崩れた着物の襟元に差し込まれた少年の手で、豊満な乳房をたぷたぷと揉まれながら、官能に震える声で囁きかけていた。
「ねぇ旦那さま、温泉…いきませんか?……二人っきりで」
柔らかな響きをもつアクセントで静江はそう言うと、きょとんとする正樹に、ほつれた黒髪も色っぽく微笑みかけ、事の次第を説明しだす。
何でも静江の旧友が経営する温泉旅館が地元の名士を集めたお茶会を主催する事となり、華月流の免許皆伝を持ち茶道に明るい彼女が助っ人として、今度の連休に来てほしいと誘われているとの事だった。
「落ち着いた雰囲気の離れを用意してくれはったみたいで、ねぇ旦那様、温泉でしっぽりと」
静江は頬を染めながら、年下の旦那様の耳に朱色の唇を寄せ、ねっとりと舌を絡ませる。
勿論、正樹がそんな美女の誘いを断るわけがない。
正樹は耳まで赤くなりながら「うん」と元気に頷いていたのだった。
そんなこんなで、正樹は熟れた美人妻と二人きりの温泉旅行に向かうべく、この駅前で待ち合わせをしていたのだ。
三連休をフルに使った、二泊三日の泊まりがけの温泉旅。
行き先である小沢山温泉の宿「山泉荘」までは、電車で一時間半、そこから更にタクシーで二十分程だと、静江に渡された宿のパンフレットに書かれていた。
正樹は大きなバッグをよたよたと抱え直して、パンフを見直していた。
ちなみにこの大きな荷物は、正樹の保護者でもある叔母の冴子さんが中身を詰めてくれたのだが、手際のいい冴子さんにしてはやけに大荷物になっていた。
―― 替えの服をこんなに沢山入れなくても良いのに……
と思いながらも、その理由がわかる正樹だった。
なぜなら、今朝方出かける間際……
「本当なら一緒したいけど日ごろ私が独占しちゃっているからね、今回は我慢するわ、ふふふふ、いってらっしゃい、お茶の先生にヨロシク言っておいてね、正樹くん」
冴子さんが妙に含みのある笑みを浮かべながら、玄関先で正樹に擦り寄りお見送りしてくれていた。
勿論正樹にもうメロメロな美人の叔母さんが、それだけで済むはずがなく。
「あら、もう、ここをこんなに大きくして、そんなに楽しみ?人妻先生との不倫旅行? もう正樹くんはスケベね、これは少し抜いておいたほうが良いんじゃない?叔母さんのお口とかで?」
などと言われ、目先の欲望に流される正樹は、容姿端麗の冴子さんの口腔内にたっぷりと濃いのを二発も注ぎ込んできてしまったのだ。
結局その際、朝履き替えたばかりの下着を早速また着替える事になり、持って行く荷物に替えの服が沢山あった方がいい事が見事に実証されたのだった。
そんな事を思い出し、正樹は、とほほほっと自分の欲望への抵抗心のなさをいつもの通り反省しながら、「小沢山温泉 山泉荘」と書かれたパンフレットに再度目を落とす。
目的の温泉宿は、どうやら相当に高級なようだった。
温泉なんて田舎にいる時に町内会の集まりで行った事のある安っぽい温泉旅籠しか知らない正樹でも、パンフを見ただけでランクが違う宿である事が容易にわかる。
温泉も、よくある大浴場なんてものではなく、部屋ごと個別の露天風呂やら贅を凝らした趣向がされているらしく、いかにも由緒正しき高級保養地といったといった趣だ。
――詳しく判らないけど、凄いんだ、そうに違いない絶対。
何故にまだ一度も行った事のないその温泉旅館をそう思うかと言えば、少なからず理由がある。
その理由は、パンフの最後、バストショットで微笑む赤い艶やかな肉厚の唇が特徴的な和服女性の写真にあった。
旅館の女将「水無瀬 京香」と紹介されている、静江の旧友の写真。
女としての存在感たっぷりのこの妙齢の美熟女を知らない人の方が少ないだろう。
無論、老舗の隠れた名旅館 山泉荘の女将としてではない。
超がつくほど有名な女優の水無瀬 京香としてだ。
そう、この温泉旅館の女将は、ほんの数年前まで美貌と演技力を兼ね備えた実力派女優としてドラマや映画で活躍し名を馳せていた女優の水無瀬京香、まさにその当人なのだ。
あまりテレビは熱心に見るタイプではない正樹さえその名前と色気に溢れた円熟した容姿を知っている程の有名人。
迫真の演技力と抜群の容貌、特に妖艶な肉厚の唇が印象的で、視聴者を自然と惹きつける数少ないまさに本物の女優だったのだ。
だが水無瀬京香は、数年前に結婚後すぐに夫と死別してしまい、若くして未亡人となった後、その突然の不幸からか芸能活動から一線をひいていた。
今では実家である老舗旅館の女将として第二の人生を歩みだしていると報道されていた。
それでも、その際立った妖艶さと抜群の存在感で内外から彼女を惜しむ声は数多く、特に請われて映画などに出た際などは、例え端役であってもそれだけで世間の話題を浚う、人気の衰えない美貌と才能を兼ね備えた女優だった。
そんなテレビや映画で活躍する凄い人がやっている宿なのだからきっと凄いのだろう、そう漠然と正樹は思っていたのだ。
余談だが、正樹は有名人に会えるかもと、サイン色紙まで購入して持ってきていたし、学園の親しい友人たちに芸能人に会うんだと、ちょっとした自慢までしていた。
勿論、静江との二人きりの旅行である事は伏せていたが……
なにせ田舎にいた時は、テレビの中に出てくる芸能人は一生テレビ越しでしか見る事はないと思っていたのだ。
それが全国区で誰もが知っている、あまりにも有名な女優さんと会えるとなればハイテンションになっても仕方ないだろう。
そんな美貌を売りにする芸能人レベルの容姿を持ち合わせた美女達なら正樹の身の回りに何人でもおり、例えばマイカやレン等はもう世界レベルでの超有名人なのだが……幸か不幸か正樹はマイカ達の美しさは十分堪能しているが、それと同等、いやむしろそれ以上のインパクトを持つ社会的な地位の凄さは、まったく理解していなかった。
何にせよ、正樹はこの二泊三日の旅行が楽しみでしかたないのは間違いなかった。
もっとも一番の楽しみは、人妻美女の一条静江と温泉宿での夜を過ごす事だったが……
中学生の分際で、美貌の人妻と温泉旅行を楽しみにする羨ましすぎる境遇の少年。
その時、そんな不埒で羨ましい環境を持つ正樹の前に、黒塗りのハイヤーが滑る様に走りこんできていた。
どうやら、何時の間にか待ち合わせの時間になっていたようだった。
正樹の目の前に停まったハイヤーのドアが開くと、涼しげな藍色の着物を着こなす思わずため息が出る程魅力的な女性が、足を揃え上品に降りてくる。
「静江――いっ、一条師範、おはようございます」
一条師範の旦那様教育の成果で、つい目の前の和服美女を下の名前で呼び捨てそうになり、人前である事に気がつき慌てて言い直す。
「ふふふ、おはようさん」
そんな正樹に、涼やかで洗練された麗人はにこやかな微笑みを返す一条師範。
切れ長の黒い瞳、すっと通った鼻筋、紅をさした艶やかな口唇。
優雅な黒髪は後ろに結わえ上げられ、色っぽいうなじを覗かせている。
そして、凛と背筋を伸ばした彼女の着物の下からでもわかる、肉感的なスタイル。
帯に締められていてもその母性に溢れた豊かな乳房は隠しようが無く、見事にくびれた腰から円熟しむっちりと張りのある尻までのラインは、まさに世の男性の目線を奪ってはなさない静謐な佇まいをみせる大和撫子の色っぽさだった。
正樹は何度も見ているはずのその美貌とスタイルに今更ながら見惚れてしまう。
そんな、熱にうかされた様にぼーっと立っている少年に、静江は柳眉を顰めながら本当にすまなさそうに声をかけていた。
「堪忍してね正樹さん、実は……今回の旅行二人きりじゃのうなってしまったんよ」
「はひ?」
素っ頓狂な声をだして正直に驚く正樹。
そんな少年が目にしたのは、静江に続いてハイヤーから降りてくる二人の女性の姿だった。
二人ともどちらも正樹の見知らぬ年上の女性で、そしてどちらも極めつけの美女だ。
間違いなく平均的な容姿からは一桁以上飛びぬけていると誰もが認めるレベルの鮮烈な魅力を放っている。
そんな二人の美女達は、ほけーっと立ち尽くす正樹の前にやってくると、それぞれ自己紹介を始めていた。
「一条先生、こちらが例のお子さん? おはよう、キミが正樹クンね、アタシは坂月 彩よ、キミと同じ先生のお茶のお弟子さんってわけ、今日から三日間ヨロシクね」
二人組の片方、背の高い方の女性が、幅広のサングラスを頭の上にのせかえ眩しそうに目を顰めながら、軽やかな声で挨拶をする。
襟首あたりで少し外に跳ねているセミロングの紅茶色の髪に、印象的なペルシャ猫のような気品と色気のあるアーモンド形の目、そして西洋的な端正な顔立ち。
見た目は静江よりは年下、おそらく二十代の前半だろう。
まさに色気をムンムンと漂わせた、いかにもアダルトな感じのセクシーな美女だった。
モデルのようにスラリとした肢体を包むのは、活動的な細身のロングパンツに、襟足の高いアイボリーのブラウスといったカジュアルな装いで、彼女の積極的な性格を反映しているようだった。
そんなアダルトな美女、坂月彩は、ラメ入りのルージュの引かれた唇に笑みを浮かべ、面白そうに正樹を見下ろしていた。
「どっ、どうも、よろしくお願いします」
慌てて返事をする正樹は、目線のやり場に困っていた。
何故なら、サングラスを頭の上にあげ、腰に手をやって堂々と立つその長身の美女は、とてつもなくスタイルがいいのだ。
服の上からでも、ギリシア彫刻のようなメリハリのきいたダイナミックな肢体のラインが容易に見て取れる。
特に正樹が目のやり場に困ったのは、身長の関係からも目の前にくる坂月彩の胸元、それも外人モデルの様に大きく突き出したバストのせいだった。
形のいい豊満なバストは、まるで砲弾のように重力に逆らいそのエロティックな形を見せつけている。
おまけにアイボリーのブラウスの襟首がけっこう大胆に開いているので、そこから肉感的な深い胸の谷間が覗き、ネックレスの緑宝石が埋もれている様がより卑猥な感じを引き立てていた。
「あはは、けっこうシャイなのねキミ、急にお邪魔したのはこっちの方なのだから気にしないで」
そう気楽に言って、ひらりと手を振る彩の左手の薬指には、既婚者を示すシルバーリングが輝いている。
「いいですか? わたしもご挨拶させてくださいね、こんにちは正樹くん、わたし今野美沙って言います、わたしも一条先生のところでお茶を教えてもらっているんですよ、よろしくお願いしますね」
格好のいいモデル立ちの坂月彩の横から、ひょっこり顔を覗かせ正樹に微笑みかけるもう一人の連れの女性。
彩よりも更に年が若い感じの今野美沙と名乗ったその女性は、諭すように優しく丁寧な口調だった。
にこやかに目を細め、のんびりとした微笑を湛えたフェミニンな雰囲気を振りまいている。
背中まである軽やかな栗色のウェービーヘアは、サイド部分に流した髪を二つにまとめて編み、いかにも清楚なお嬢様育ちといった様相だった。
服装の方も、柔らかなニット地のノースリーブの上にストールを上品に羽織り、色合いを合わせた腰周りからヒップへのラインがタイトなスカートをそつなく着込なし、その朗らかな美貌にマッチした柔和な印象を醸し出している。
そして、そんな美沙の指にも彩同様に既婚者を示す細身のリングが嵌っていた。
「こちらこそ、よろしくお願いします」
先程から、しきりにぺこぺこし通しの正樹は、これまた目のやり場に困っていた。
なにせ、彩に負けず劣らずのハイレベルな容貌をもつ美沙は、スタイルにおいてもまったく遜色がない見事なモノだったのだ。
美沙のニット地のハイネックは、その肩から二の腕までが露出しており、羽織ったストールがめくれると、白く女らしい柔らかな肩の曲線が垣間見え、思わず正樹はドキっとしてしまう。
そして今野美沙の胸元は、坂月彩と同じ、いやそれ以上のたっぷりと大きな特盛りの柔らかそうな丸みを帯びているのだ。
ニット地を肉感的に盛り上げる重量感に溢れる豊かな膨らみは、中学生の少年には目の保養――もとい目の毒としか言いようがない。
――うわぁぁ、どうしよ、目のやり場に困る……じゃなくて、こんな綺麗な人たちと一緒なんだ。やっぱり都会は美人が多いんだ。
静江との旅行への思わぬ参加者達の登場に、正樹は視線のやり場以上に困惑しつつ、こんな凄い美人に会えた事に驚いてた。
まるでファッション雑誌から抜け出てきたようなスタイルとオーラ。
こちらに引っ越してきてから、驚くほど綺麗でそして知的な女性達ばかりと巡りあえた正樹は、単純に都会ってすごいやと納得していた。
たとえ人口が多い都会でも、これほどのレベルの女性はそうそうお目にかかれないのだが……
「あら、どうしたんですか? 正樹くんは恥ずかしがり屋さんですか?」
美沙は優しく丁寧な口調でそう言うと、スカートの前を両手で押さる姿勢――つまりは二の腕でその豊かなお胸をむにゅっと押しつぶす格好――で前かがみになると赤面する正樹の顔を覗き込んでくる。
美沙の豊満すぎる重そうなバストは、二の腕に押し出され見事な紡錘形を見せつけている。
その柔らかく丸みのある母性の象徴の膨らみが少年を惑わしている事に、美沙本人はまったく気がついてない様子で、慈愛に満ちた美貌で微笑んでいた。
――あううっ、見ちゃいけない、見ちゃいけない
ヤリたい盛りの中学生であり、例の不思議な力のせいで常に準備万端、性欲旺盛となっている正樹は、自分の中に溢れる劣情を抑えようと視線を泳がしあらぬ方向に向けようと努力する。
そう、少しは理性が成長していたのだ。
ちなみに、ここ最近、正樹は正樹なりに自分の魅了の力の特性を考え、常日頃から魅力的な女性に意識を向けない様に、心がけるように……なるべくしていた。
保険医の麻耶が、力のメカニズムを調べてはいるが、まだ全然不明とのことだった。
女性を虜にするというとんでもない力以外にも効果はあるようなのだが、わかっている事といえば、麻耶の雪の肌の磨きがさらに増したとか、薫子先生のおっぱいが心持ちまた大きくなったとか、春風先生のマラソンの距離が伸びたとかぐらいだ。
何でもデータが全然足りないので、正樹の力が発揮される理由を調べるにも実際に試して絞り込んでいくしかないらしい。
今のところ確実にわかっているのは、正樹が腕輪をはずすと力が発揮される事、そして美人保険医が身を挺して証明した目線を合わせないでも虜になると言う事だけだった。
何にしろ、根は純朴な正樹にとって、この力は美女を意のままにできる夢の能力であったが、同時にわけがわからない不気味さもあった。
もっとも、正樹の周りに集った女性達があまりも世間一般の水準を超えた稀に見る美女ばかりだったため、目が肥えた正樹が意識する程の異性は日頃めったに――と言うか殆どいないのが現状だったのだが。
だが、その例外がいきなり目の前に現れてしまったのだ。
しかも二人も同時に。
「あぅっ」
そんなわけで正樹は、なるべく意識しないように二人の美貌から目線をはずしたのだが……。
しかし、今度は例の二つのスケベに張り出した砲弾バストと、重そうに揺れる紡錘形の巨乳が目に飛び込み、さらに慌てて目線を落とす。
だがその視線の先には、幅広のベルトを斜めに巻いた彩の細くくびれた腰つきや、スカートの上からでも判る美沙の肉感的なヒップが視線に入ってしまう。
「わっ、あううぅっ」
慌ててさらに目線を落とし、最後には地面に敷いてある無機質なタイルの隙間を見つめる始末だった。
「正樹くん、ごめんなさいね、こんなおばさん達が突然来たから困ってしまったんですよね?お邪魔しませんからおばさん達も連れて行って貰ってもいいですか?」
妙な唸り声をあげ顔を落とす正樹を、がっかりと肩を落としていると誤解した美沙がすまなさそうに謝ってくる。
「え?……あっ、すっすいません、そんな事ないです全然、是非一緒に」
正樹は、はっとして顔を挙げると、自分の欲望のせいで目の前の人たちに要らない気づかいをさせてはいけないと、精一杯の笑みを浮かべてみせる。
それが、数多の美女達を虜にしてきた無邪気な笑顔であることも知らず。
そして、案の定、彩と美沙の若妻美女二人組は、少年の笑顔に一瞬動きを止められていた。
「ごっゴホン……あっありがとう正樹くん、おばさん達と一緒に温泉旅行楽しみましょうね」
「ちょっと、美沙さん、おばさんはないんじゃないかしら、せめてお姉さんとかさ、ねぇ、キミ、アタシはおばさんなんかじゃないわよね?」
メリハリの効いた魅力的なスタイルの彩が砕けた口調でそう言いながら、ゾクッとするような流し目を正樹に送り、くびれた腰をひねってロングパンツに包まれたきゅっと吊り上ったヒップを冗談めかして少し揺らせてみせる。
「は、はひっ、ちっ違います、全然、はい」
青少年には鼻血モノのパフォーマンスに、正樹は思わず声を裏返し、しゃきっと直立してしまう。
「あははは、可愛いわねキミ、いい事、今後はアタシの事は彩お姉さんと呼ぶように……んっ、さてと、荷物を取ってこないと」
「ふふふふ、もう彩さんったら、こんな小さな子をからかっちゃ駄目ですよ、中学生から見たら二十過ぎの私達なんておばさんなんですから、それじゃ正樹くん、また後でね」
唐突に現れた坂月彩と今野美沙の二人の若妻は、シャチホコばった正樹をひとしきり笑うと、トランクから荷物を降ろす運転手の方に向かって去っていく。
アダルトな女の艶やかさを漂わせる色っぽいお姉さんの坂月彩。
エレガントな気品を振りまく優しく清楚なお姉さんの今野美沙。
二人のタイプの違う美女に魅入られた正樹は、ぽかんと突っ立ったままになっていた。
そんな少年の耳元に、若い彼女達とは一味異なる爛熟した女の色気を漂わせる和服美女が、朱色の唇をそっと寄せ囁きかける。
「堪忍してね、旦那様、あの二人言い出したらきかなくて、二人ともうちのお茶の生徒なんやけどその関係でどないしても来たい言われて断れんで……この埋め合わせはきっとしますから、今回は、ね」
「いいよ、静江、気にしないで、それに僕、温泉普通に楽しみだったからね」
「もう、旦那様ったら……本当なら……」
彩と美沙に聞こえない小声で、主人と妾の口調で言葉を交える正樹と静江。
一条静江は、隣に立つ大事な旦那様である中学生の少年の横顔をそっと見つめると、こうなってしまった事情を思い出し、心底後悔していた。
そう、静江にとっても本当なら今日はまさに特別な日だったのだ。
大事な旦那様との初めての二人きりの旅行。それも二泊も。
その事を考えただけで、彼女の旦那様に子種を頂いた下腹部はうっとりと熱を孕み、最近特に張りの増した乳房の先が固くなる程だった。
そのせいか、少しばかり気分が緩んでいたのだろう。
本家での定例茶会の席で、心が弾みいつもと様子が違う事を、お茶を師事している生徒の二人、坂月彩と今野美沙に気取られてしまったのだ。
しかも「先生、今日はご機嫌ですね」と言われ、ポロリと温泉旅行の話をしてしまったのが運のつき。
慌てて正樹の事を勘ぐられてはいけないと、親友が経営する温泉旅館の良さを多少大げさに語ってしまったのだ。
その弁解があまりにも熱が入り過ぎてしまったためか、「あの落ち着いた一条先生がそれほど熱心に薦める温泉なら是非ご一緒に」という具合にトントン拍子に話が進んでしまい、結果、彩と美沙の二人が同行する事態になってしまっていたのだ。
静江はその事を思い出して、はぁっと儚げにため息をつくが、すべて後の祭り。
旦那様との二人きりの温泉、色々して差し上げたいことがありましたのに……
だが、事を知られた二人が坂月彩と今野美沙であったのが災いした。
他の生徒ならやんわりと旅行への同行を断れたし、それでも無理なら何かと用立ててお茶会から足を遠のけさせることも容易だった。
だが、彼女達は静江の動揺をお茶の腕前から見抜けるほど腕がたつ生徒に育ってくれていたし、少しばかり下世話な言い方になるが、静江が身を寄せているお茶の流派、華月流本家を支援する大口のパトロンでもある。
正樹に最初に挨拶をした長身の美女、坂月彩は、夫も某上場企業の幹部役員だったが、それ以上に彼女個人も二十代前半という異例の若さで既に事業で成功を収め、一角の経営者として名を馳せていた。
大学時代に有名ファッション誌の読者モデルとして頭角を現し、卒業後はその経験を活かしモデル事務所を開設、トップモデル兼マネージャーとして美貌だけなく類稀な商才を存分に発揮。
結婚後もアパレル関係の事業を次々と立ち上げ軌道に乗せるその敏腕ぶりは、その業界では美しさと卓越した経営者としてのセンスで有名な存在だった。
何でも最近は新たにブティック経営も始めたらしく、既に六店舗目を先日開店し、独自のブランド展開で話題となっているらしい。
まさに競争社会の若き成功者、あまり静江の好きな言葉ではないが俗に言う勝ち組と言うのに相応しいハイエグゼクティブなビジネスウーマンだった。
そして、もう一人の今野美沙は、克己心に溢れた彩とは対照的な地元では有名な資産家の箱入り娘、まさに生粋のお嬢様育ちの優雅な麗人だった。
地元の親が理事を務める短大を卒業と同時に親に勧められるまま婿養子を迎えたが、結婚の前も後もその穏やかなライフスタイルはまったく変わっておらず、悠々自適なまさに若き有閑マダムといった感じの若きセレブリティだった。
そんな若妻二人は、金銭的にもまた社会的にも華月流を援助している大口のパトロンであり、お茶の師範である静江でも無下に扱う事はできない大人の事情があったのだ。
そんな理由があったのだが、旦那様の横顔をみつめる静江の胸中には、妾として期待されていた奉仕ができなくなった事への不甲斐なさと、それ以上に甘美な時間が失われた事に対する未練が沸々と湧き上がってくる。
だが災い転じて福となす、静江はこの機会に前々から考えていたある企てを心に思い浮かべていた。
――そうやわ、旦那様は沢山の妾を囲える度量をそろそろ身に着けて頂く必要もありますし、ちょうど二人ならうってつけ、ここは一つ……
少し迷ってから一条師範は一人満足げに頷くと、薔薇のように赤い唇を正樹に寄せ、再度耳打ちする。
「ねえ、旦那様、何とか時間をつくりますよって、その時はよろしいですやろ?」
静江の白い繊細な指先が正樹の指先に触れ、まるで何かをシゴくのを連想させるように、ゆるゆると愛撫を繰り返す。
「だっ、ダメ、ダメだよ、ほっほら、こっ、今回は他の人もいるし」
「ふふふ、大丈夫ですわ旦那様、ぜんぶ貴方様の妾である静江にお任せくださいな」
「でっ、でも……うぅぅ、うん、わかったよ」
少し躊躇しただけで、熟女との爛れた肉の味を覚えてしまった正樹はあっさり頷いていた。
そんな旦那様の愛欲と信頼を得ている静江は、誇らしく微笑みながら、這わせた指先をさらに絡めていく。
華奢な中学生と凛とした和服の美人人妻。
二人は、荷物を受け取り此方に向かってくる美沙と彩を見つめながら、そっと人目を忍んでお互いの指を淫らに絡ませ続けるのだった。
列車の窓の外を、凄いスピードで景色が通り過ぎていく。
正樹達は、目的地の温泉宿がある山奥の温泉郷「小沢山温泉」に向かい超特急で走る列車に揺られていた。
静江が用意したのはファミリー向けの個室で、ゆったりとした座席が二席分向かい合う所謂ボックスシートだった。
その席上には、正樹と静江が隣り合い、その向かいに彩と美沙が座っている。
列車が駅を出発し十分足らずしか経っていなかったが、個室の中の一団はすっかり打ち解け会話が弾んでいた。
「ねえ、キミ、喉かわいたんじゃない?何か飲み物でも頼もっか?」
彩が優雅に腰掛けた姿勢のまま、列車の売店に直結しているフォンに手を伸ばす。
「えーと、まだいいです、坂月さ、あっ、彩お姉さん」
坂月さんと言いかけた正樹は、背筋がゾクゾクする彩の流し目に睨まれ、慌てて「彩お姉さん」と言い直す。
先程の美沙の「おばさん」発言を受けて、彩お姉さんと呼ぶように強制されていたのだ。
もっとも、正樹の目から見ても、どう逆立ちして見ても「おばさん」なんて年ではない二人なので、その呼び方にまったく違和感はなかったが、「お姉さん」と他人を呼ぶ事はなんとも気恥ずかしかった。
「あら、正樹くん呼び方を間違えてますよ、彩さんは「彩おばさん」でいいんです、でも私の事は「美沙お姉さん」って呼んでくれると嬉しいわ」
美沙が相変わらずの柔らかな丁寧口調で冗談めかしてそう言いながら、棚に置いた荷物から小さな手提げカバンを取り出し椅子に腰掛ける。
「もう、美沙さんったら、正樹クン、こんな「美沙おばさん」の言うこときかなくていいわよ、キミはちゃんと彩お姉さんって呼ぶように、あっ、お姉様でもいいけど、あははは……あら?美沙さん、それ何?」
「旅行の記録係は美紗お姉さんにおまかせです」
そう言って美沙が手提げカバンから取り出したのは、小型の記録メディアが内蔵された長時間録画できるハンディカムだった。
「あら、ちょっと撮ってみてよ、あっアップはやめて、もう、こら、キミも笑ってないの」
他愛も無い会話は途切れる事無く、目的の温泉郷へ向けて楽しげな雰囲気を乗せたまま列車は快調に走り続けていた。
彩も美沙も相手に合わせて会話を楽しめる心に余裕のある女性であり、また当初緊張していた正樹も「彩お姉さん」と「美沙お姉さん」と愛称で呼ぶ事で親近感を持て、互いの距離がぐっと縮まり会話がよけいに弾んでいた。
彩と美沙の二人としても、旅行に同伴させて貰った身であり、静江が学校でお茶を教えているという少年に不快な思いはさせたくなかったのだ。
何より、最初の挨拶で見せた正樹少年のはにかんだ可愛いらしい笑顔が、二人の若妻達の心に多大な好印象を与え、その思いを一層強くさせていた。
特に少しばかり年下好み、俗にショタといわれる傾向が無意識にある坂月彩は、すっかり正樹が気に入った様子で、もうしきりに正樹に「ねぇ、正樹クン」「キミはどう思う?」などと話を振っている。
そして正樹も、西洋的な印象のあるアダルトな彩も、おっとり癒し系の美沙も、どちらも闊達で人当たりのよい性格であったため何の不満もなかった。
懸念したあの不思議な力の発動も、腕輪をしっかり嵌めてさえいれば問題ない様子で、ひとまず安心を促す材料となっていた。
もちろん、正樹の心の中には、力が勝手に働いてこの二人の美女とももしかしたらと言う期待がなかったと言えば嘘になり、一抹の落胆があったのは事実だったが……
まあ、これ程の美女達を前にすれば、世の男性ならば誰でもこんな素敵な美人とお付き合いしたいという願望が脳裏に浮かぶのは確実で、正樹の落胆もある意味、健全と言ってもいい範囲だろう。
それでも正樹は用心を怠らず、彩のセクシーな仕草や、ダイナミックに突き出される胸元とその深い谷間、ロングパンツに包まれた長い美脚にドキマギするたび、なるべく視線を窓の外に反らしていた。
さらに、美沙の包み込むような笑顔や、ちらりと覗く白い肩や脇、それに丸みを帯び重そうにゆれる豊満な胸の曲線に思わず見惚れてしまうたび、しっかりと腕輪を押さえる事は忘れなかった。
自分の中の欲望に負け、力が発動してしまわないように、そして正樹自身は意識してはいなかったが、もし力が発動しても後で自分に言い訳ができるようにと……
それぐらい二人の若妻美女達は魅力的だったのだ。
そんな一見和気藹々とした楽しげな車内で、涼やかな藍色を基調とした着物を着こなした白皙の美女、一条静江だけが心中穏やかではなかった。
大人の女の色香をはなつ人妻熟女は、端から見れば一見満更でもないという風情で会話に頷き優雅に微笑み、場に軽やかな雰囲気を提供している。
だがしかし、その熟れた肉体の奥では、トロトロと溢れ出す情熱の収まりがつかなくなり、他の三人に見つからない様に着物の下でむっちりした太股の付け根を何度ももじもじとさせていたのだった。
――あっ、あきませんわ、うち、うち、他の人の目もあるのに……もう、こないな事に……
静江はぎゅっと気を引き締め、長年の修練で鍛えられている筈の精神に活を入れる。
だがしかし、旦那様である正樹にすっかり調教され雌奴隷として服従する喜びを覚えこまされた熟れた肉体が、容易くそれを塗り潰していく。
この個室が良くなかった。
もともと静江は、旦那様に色々と電車の中でもご奉仕する心算でこの個室を予約したのだ。
――マイカさんとレンさんの外国お妾さん達は、毎朝電車の中でご奉仕なさっているって言うてはったし、うちだっていっぺんぐらい……
マイカの訪問を受け同じ主人に従う牝奴隷として友誼を深めた際に聞かされた話に触発された静江は、二人きりの旅行で四席分のしかも鍵のかかる個室を探し予約したのだ。
逆にそれが裏目に出て、三連休という混み合う時期にも関わらず二人分の座席が空いていた事が、彩と美沙の飛び入り参加をさらに後押ししてしまっていた。
旦那様といちゃいちゃしながらの列車の旅を楽しみにしていた一条師範は、恥ずかしながらそれを想い、夜な夜な一人で車内でのいけない事を想像して、自らの指で慰める事もしばしばだったのだ。
「…………はぅ」
色っぽい吐息とともに、抑えきれない疼きが朱色の唇からこぼれ出る。
――本当なら、この個室で、すぐ側に座る旦那様に抱かれて……そして、静江と名を呼ばれながら口を吸われて……あの硬いモノを……
寝床で想い描いていた正樹との秘め事が、静江の脳裏に鮮明に蘇ってきてしまう。
――あきません、あきません、あきません、しっかりしないと、まだ今は……
静江はそう自分に言い聞かせながらも、切れ長の黒い瞳で横に座る正樹の顔をつい追ってしまう。
一方、その正樹はと言えば……
「撮れてますよ、綺麗に、ほら」
「あら、ほんとね、意外に使うの簡単ね、これ」
などと、静江のお茶の生徒達と楽しそうに語らっている。
「ねぇ、一条先生、先生も使ってみますか?このデジカメ」
そう言って笑いかけてくる無邪気な笑み。
「ふふふ、やめておくわ、またの機会にね」
静江は内心の熱い想いを一切見せる事無く、涼やかに微笑みかえす。
「そうですか……あっ彩お姉さん、そこの温泉の冊子取って貰えますか?」
正樹は別に他意は無いのだろう、あっさり坂月彩の方を向き直ってしまう。
――もう、旦那様ったら、うちにもっと構ってくれてもええのに、彩お姉さんやら美沙お姉さんなんて呼んで、うちだけ先生と呼ばんでも。
そんな正樹のつれない態度に、ちょっとした嫉妬心と悪戯心が湧き上がってくる。
静江は、少しだけならと自分に言い訳すると、淡い藍の着物に包まれたお尻を動かして隣の正樹の方ににじり寄る。
そして、その白魚のような手を陰からのばすと、向かいに座る二人に見えないように、そっと正樹の手に指を絡めていた。
先程、駅のロータリでしたように、淫らに、まるで愛撫するように……
「ん?冊子って、これかしら? はい、どうぞ」
「すいませ、あっ」
彩から温泉旅館の冊子を受け取りながら、びくっと動きを止める正樹。
「ん? どうしたの?」
正樹は唐突に動きを止め心もち赤面した様子だったが、やがて「な、何でもないです」といかにも平静を装っていますと言わんばかりの顔つきで冊子を開き、彩と美沙に温泉の話をふる。
「えっと……お二人とも……こっ、ここの温泉は行った事あり…ますか?」
「いいえ、ないわよ、美沙さんは?」
「わたしもないです、ところで正樹くんどうかしましたか? 気分が悪いの? 電車に酔っちゃったのかしら?」
バレバレの硬直振りを見せる正樹に、不信そうな二人。
「あら、高梨くんは少しはしゃぎ過ぎたみたいね、ほら、うちに寄りかかってええんよ」
ぎこちない正樹とは異なり、静江は本当に自然に見える笑みを作ると、隣に座る少年を自分の肩に寄り掛からせる。
その間も、静江の指先は、正樹の指と指の間を這いまわり、情熱的に絡みついていた。
「……はっ…はい、すいません、静……一条先生」
正樹は勧められるまま大人しく一条師範の肩に身を寄せ、頬を染め熱い息を吐く。
「大丈夫かしら、何か冷たい飲み物でも頼む?」
「窓が開けばいいんですけど、ここは無理ですよね」
彩と美沙が、突然の正樹の容態の変調に心配そうに声をかける。
「だっ、大丈夫です、少しすれば落ち着きますから……」
正樹はそう掠れた声で言うと、隣に座る一条静江にさらに密着し身を任せていた。
傍目からでも少年の目は少しばかりトロンとしており、その頬は赤く、まるで熱を患っている様子にも見えなくはない。
「一条先生、正樹くん何か持病でもあるんですか?」
「いいえあらしません、多分気が張っていたみたいやからそのせいかと……そうやわ、高梨くん、お熱はかりましょか?」
静江はそう言うと、その白皙の美貌を少年の顔に寄せ、こつんとおでこを当てる。
艶っぽいお茶の女師範は、着物に包まれた肢体を少年に押しつけ、裾がめくれて白い脹脛を見せている事さえ気にする様子はない。
それどころか、少年の額に重ねた自分のおでこをそのままに、鼻先をくすぐるように摺り合わせる。
「うーん、お熱はないみたいね、でも、もう少し測っておきしょうね」
額を寄せ合ったまま、潤んだ切れ長の瞳でそう囁く静江は、さらに頬まで寄せんばかりの様子だった。
それは子供の熱を測るにしては余りにも色気のある所作で、どう見ても女が意中の男を誘うようにしか到底思えない姿だった。
「あ、あの一条先生? 熱を測るのはもう十分じゃないですか?」
おっとりとした美沙は、事態がまったく飲み込めていない様子だったが、二人の只ならぬ雰囲気におされ、やや遠慮がちに声をかける。
一方、彩は、何故か熱い輝きをその猫目に宿し、成熟した大人の女が可愛らしいまだ少年の男の子に体を押しつける様を、唖然としつつも何処か陶酔した面持ちで見つめていた。
その時……
「あんっ」
少年の額に顔を寄せていた静江が色っぽい声をあげ、びくんっと震える。
「どうしましたか、一条先生?」
「なっ何でもあらしませんわ……あんっ……あっ、おいどを…触っちゃ……あんっ…もっ、もう悪戯しませんから、かっ堪忍してくださいませ…あひっ、指うごかしちゃ…あんっ」
静江までもが正樹と同じように頬を染め、隣に寄り添う少年にまるで睦言を囁くかのように、何事かを呟きだす。
彩と美沙の二人から見えない死角で、正樹の手が静江の臀部とシートの間に忍び込み、着物も上からその尻を鷲掴みこねあげだしていた。
「? 先生、どうなさったんです?」
「いっ、一条先生……まっ、まさか…そんな……子供と…」
状況がわからず不信がる美沙と、何かを確信し目を見張る彩。
だがもう静江はそんな二人の方など構っている余裕もないのか、少年に寄り添い「んっ、んんっ」と甘く媚びるような女の声をはっきりとあげている。
その様は、まさに見つめ合い抱擁し合う恋人同士そのものだった。
もっとも片方はまだほんの幼い少年で、もう片方は分別のある年長の艶やかな熟女と、到底ありえない組み合わせだったが。
だが、大人の女である一条静江の顔は、どう見ても情欲に染まっており、男を誘う雌の色気を濃厚に発している。
そして色気に誘われた正樹は、何時も通り簡単に我慢の限界を超えてしまっていた。
「っ…もう……僕っ…ごめんっ…し、静江っっ」
少年は女師範を呼び捨てにすると、鼻先を寄せ合う肉感的な熟女の朱唇に、人前であるにも関わらず、しゃにむにむしゃぶりつく。
「あっあきません…みっ見られて…んんっ…んっ…ちゅっ……んふぅ」
静江はわずかに躊躇うが、少年の口が自らの濡れた唇に触れた瞬間、調教された女の性がそうさせるのか、少年を受け入れるように朱唇を開き、うっとりとした表情を傾け、深い接吻に溺れていく。
くちゅっくちゅっ、と唾液が絡み合うねばっこい音をたて、三十代の美女熟女とまだ中学生の少年が濃厚な接吻をはじめていた。
貪りあう唇の間からは、激しく絡まる淫らな舌の睦みあいが見え隠れし、ねっとりと啜りあう様子をまざまざと見せつける。
それはもう親愛の情の表現などで済まされない、口で肉欲を交える激しいセックスのようなディープキスだった。
「「…………」」
向かいの席に座る若妻二人は、幼い子供に口を吸われ恍惚としているお茶の女師範の痴態をただ呆然と見ているしかなかった。
二人が見つめる中、正樹に欲望たっぷりに吸いつかれ舌を突き入れられて口腔内をクチュクチュと好き放題されていた静江だが、やがて覚悟を決めたように目を細めると大人の女の手管で少年のキスに応えだす。
「んんっ…んんっ…れろっ…ちゅっ……んふっ…んんっ、んっ」
甘美に浸る艶っぽい女の声をだして少年の舌を逆に吸いあげ、たまった唾液を嚥下する。
そして、息つぎの間に唇を甘噛みし、すぐさま長く濃厚な接吻に導いていく。
そんな口を吸いあい、舌を絡めあう熟女と少年の様子を息を止めてみていた彩が、震える唇からようやく声を絞り出していた。
「あっ、あなた方、二人、そっ、そういう関係なの……そっそんな、こんな男の子と……この子、まだ中学生でしょ、大人の女性がすることじゃないわ、こんな」
そう言いながらも、何故か彩はその西洋的なメリハリのある美貌を紅潮させ、ぎゅっと堪えるようにロングパンツの太股を両手を握り締める。
「そういう関係って、え?え?……これ冗談ですよね、だって一条先生って結婚されていますし、旦那様もいらして……??」
夫がある身の円熟した人妻が、まだ幼い男の子と情熱的にキスをする現場を目撃しながらも、おっとりとした美沙は自分の道徳観念からはずれたこの行為が、何かのドッキリであるといまだに思っているようだった。
「んっ…ちゅるるっ……んふぅ…ふぅ……はぁ……」
やがて、じゅるるっっと音をたて正樹の唇を愛しげに丹念に吸い上げると、一条静江はゆっくりと顔を離す。
「ふぅ、少し予定より早くなりましたけどこうなったら、もう、お話しするしかあらしませんわね」
そして向かいに座り目を驚愕に見開いている彼女の生徒達に声をかける。
それは彩と美沙二人が知る凛と佇むお茶の師範の顔ではなく、妖しいまでの淫靡な色気に満たされた女としての存在感に溢れた顔だった。
それでもなお、その美貌は優美さという一条静江の本質を一切失っていない。
こんな状況だと言うのに、彩もそして美沙も、静江のその白皙の美貌に見惚れてしまう程だった。
「ふふふふ、うちは正樹さん、いえ、旦那様の妾としてお仕えさせてもろうていますのよ」
まるでその事が、当然のように静江は落ち着いた口調でそう切り出す。
「め、妾って、こっこんな……お、男の子の」
彩が猫のような目を見開き、身を乗り出してハスキーな声をあげる。
美沙は言葉もなく、ただただ驚いたように口元を手でおさえ、彼女のお茶の師匠と少年を何度も見比べていた。
「ええ、そうですわ、この男の子のお妾さんなんですのよ、うち」
一条静江は、自慢げな笑みを浮かべ、女弟子達の驚愕の視線を平然と受け止める。
一方、正樹の方は真っ赤になって誰とも目を合わさず、美人熟女の着物の襟首に顔を埋め、ふるふる震えていた。
そして、時折「あっ、あぁっ」と何故だか小さく声をあげている。
「妾って……こっ恋人の事ですか?」
此方を見ない正樹を恥ずかしがっていると思った美沙は、静江の古風な告白が理解できていないようだった。
そんな美沙を放っておいて、彩はごくりと唾を飲み込むと、彼女が一番聞きたかった事を口にする。
「それって……この子と先生は……その…いたしちゃってるわけですか?」
「ええ、いたしていますわ」
それが何か問題でも?と言わんばかり躊躇なく即答し、にっこりと艶やかに微笑む一条師範。
「うちは旦那様に囲われている妾なんですから当然です、妾の仕事は旦那様に抱かれることですから、あら? はっきりいいましょうか? 旦那様と交おうて、何時も胎の中にお種を頂いて子作りさせてもろうてます」
まるで世間話でもするように静江は、涼やかな顔でとんでもない事をあっさり口にしていた。
「え?ええ?そっそんな、こっ子作りって、旦那様って……一条先生は結婚されてて、ご亭主もいるのに、こんな子供と不倫しているのって、え?」
いつも微笑んでいる細い目を見開き、美沙はようやく状況を把握しだしていた。
「不倫ではあらしません、本気です」
そこを間違えないでくださいねと付け足して、少年にすっかり魅了されている一条師範は、それが当然という雰囲気を漂わせていた。
「うちはもう旦那様に生涯尽くす覚悟でおります、この事、御二方がどう捉えてもうちは構しません、ただ、旦那様の迷惑になるような事は堪忍して欲しいの、大人の御二方なら判って頂けると思てますわ」
「…………」
彩と美沙は、その落ちつき払った静江の口調の中に、今までに感じた事もない強い気迫と意志を感じ、驚きも忘れただ圧倒されて押し黙っていた。
この事は内密にして欲しい、そう静江は言っているのだ。
実際のところ、あまりの急展開に二人とも困惑し尽くし、正常な判断をつきかねていた。
何せ、ほんの少し前までは、目の前の二人は普通のお茶の先生と生徒として旅行をしていたのだ。
そんな三十過ぎの爛熟した人妻に、中学男子との肉体関係を突然告げられたのだ。
あんな濃厚なキスをしていたのだ、嘘や冗談ではないだろう。
しかも、一条先生は遊びなんかでなく、真剣ときている。
自分を妾と言い張り、しかも中学生の男の子と子作りしていると言い切るとは……
常識的に考えると到底ありえない関係だし、とんでもない事態だった。
だが、現実にあの貞淑で良妻な一条静江が、他の男、それも中学生の男の子に熱をあげ、身体まで許している。
静江の茶道の師範としての冴えきった雰囲気と、今の淫らな状況との剥落ぶりが彩と美沙の思考をますます混乱させていた。
とりあず、この事を公にできないのは間違いない。
何より、彼女達にお茶を教えてくれる一条静江は、今回の事を別にすれば、淑やかで優美な尊敬に値する人物であり、その静江を困らせたいとは彩も美沙もさらさら思いもしない事だ。
そしてこんな類のゴシップをわざわざ誰かに話すような、愚かしく浅ましい気もまったくない。
二人にとって色々な意味でショッキングな事実だったが、おそらく胸の内にしまっておいた方がいいのだろうと、同時に確信していた。
幾らこの美女と少年の組み合わせに、密やかな興味を持ってしまったとしても……
一方で静江は、こんな事態にもかかわらず非常に落ち着いていた。
正樹の口づけを受けた時に、もうこの機転のきく聡いお妾さんは旦那様のために自分が何をすべきか悟っていたのだ。
おそらく目の前の二人には、どんな弁解も通じないであろう。
悪戯心を起こして旦那様にいらぬちょっかいをかけてしまった自分が悪いのだ。
熱を測ると偽り向かい合った時、覗き込んだ正樹の目を見て静江は、その事を確信していた。
正樹が時折みせる、自分を愛してくれる時のあの情熱的な瞳。
あの熱い瞳が、静江を見つめていたのだ。
初めて茶室で抱かれ、拒否する彼女を組み伏せ、交わってきたあの時。
膣内射精をたてに、夫よりもいい事を告白させたあの時。
そして、人妻である静江の膣中に、たっぷりと子種を注ぎ込み孕ませ、妾としての隷属の幸せを教えてくれたあの時。
まさにあの時と同じ瞳で、周りも気にせず彼女を求めてくれていたのだ。
そして正樹に心底隷属している静江にとって、そんな旦那さまの肉欲を受け止めないなんて選択肢は事は有り得なかった。
幸か不幸か、向かいの席に座る二人は、彼女の知る中でも信用に足る人物であり、声高に騒ぎたてるようなヤボな真似をするような性格ではない。
下手に言い訳をして信頼感を失うよりも、きちんと今の状況を説明した方がいいのは間違いないだろう。
そしてゆくゆくは彼女達にも……
静江は、お茶のお手前を反復するように、あらかじめ思い描いていた企てを心中でなぞると、その場の流れを読み、正樹を立派な旦那様に育てる計画に、そっと修正の筆を加えていく。
同時に、重要な事をおろそかにしていた事に気がつき、心底慌てるのだった。
そう今、彼女の口を吸ってくれている旦那様のお相手を!
彩や美沙の事など些細な小事なのだ。
今はただ彼女を求めてくれる旦那様に応えてさしあげる、これが彼女にとって一番重要な事だった。
――そう、まずはたっぷり口を与えてあげませんと、それからうちも大好きな舌吸いをもう一度してさしあげないとあきませんわね……それから……猛った肉棒を……
妖しい色香と淫靡な吐息を漏らし、愛しい旦那様がくださった唾液を嚥下しながら、静江はこの温泉旅行が彼女の期待していたモノ以上になる事を確信していた。
やがて、静江に暗に口止めをお願いされた彩と美沙は、しばらく考えた後、少年に抱きつかれたまま、此方を見つめ微笑を湛えるお茶の女師範に答えを返していた。
「アタシとしては特に誰かに言う気はありません、けど……」
「私もです、ですけど……一条先生、これは世間的には褒められることではないです、考え直されたほうがいいかと……」
二人は多少言葉を濁しながら、社会人として年端もいかない男の子と関係をもつ既婚の女性の行動を諌めようとする。
「彩さん、美沙さん、ほんまにありがとう、それは重々承知していますわ、その上でのお願いですから……あんっ、あきません旦那様、今、大事なお話を……顔を舐めるのは後に……んっ…なさって……あんっ」
その時、今まで和服美女のうなじに顔を埋めていた少年が耐え切れなくなったのか、涼やかな静江の白皙の美貌に口を寄せていた。
陶器のように白くきめ細かい一条師範の美貌に、さしだされた正樹の舌が這いよっている。
「あん、もう、後でたっぷり顔舐めさせてあげますから、ねっ、今はココをこするのだけで堪忍ね……あんっ…んんっ…もう旦那様っ、ほんまうちのお顔、嘗め回すのが好きなんやから……んんっ」
静江は迫る舌から、その端正な美貌をそむけるが、どう見ても嫌がっておらず、むしろその朱色の唇は歓喜に震え戦慄いている。
「「あっ!」」
その時、彩と美沙も同時に気がついていた。
片目をつむり美貌を背けるお茶の女師匠のしなやかな手先が、少年のズボンの中に潜り込み、妖しく動き続けている事に。
少年が先程から何も言わず真っ赤になって震えていたのは羞恥ではなく、それが理由だったのだ。
そして一条師範が、至極冷静な落ち着いた顔で彼女達と話をしながらも、その陰では少年の肉棒を指でさすり慰め続けていた事にも。
「でっでも……静江っ、はぁはぁ…静江…もう僕……ねぇ駄目?」
先程からずっと肉棒を弄られていた少年は、かすれた声でお茶の師範を呼び捨てにし、舌を尖らせ熟女の澄ました美貌を嘗めようと必死になる。
もう、彩や美沙の事など正樹の眼中にない。
彩と美沙には、正樹のその我慢のできない様子は至極理解しやすいものだった。
同性から見ても肉感的で大人の色気と魅力たっぷりの脂ののりきった一条師範が、あそこまで奉仕してくれているのだ、状況やら場をわきまえて冷静でいられる男なんていないだろう。
ましてや、正樹はまだ中学生、性を覚えたての少年には、静江の誘惑を我慢などできるはずも無いのだろう。
「しっ…静江っ……ねっ、おっお願い」
必死に首を伸ばして舌を突き出し、麗しい美女に迫るその姿は、端から見ればあまりも滑稽でそして子供らしく無邪気な我侭に溢れていた。
その姿に、彩と美沙もその場の重かった雰囲気を忘れ、思わずクスリと笑みを浮かべてしまう。
「ふぅ……これは、何ていうかお熱いですね、まあ今はお二人の関係の事はとやかく言いませんわ、旅行にお邪魔しているのはアタシ達の方ですし」
「……まぁ、確かにそうですけど………でも、ほどほどにしてくださいね」
彩も美沙も、少年の場をわきまえていない発情ぶりに肩の力が抜けた様子だった。
「かっ、堪忍ね、二人とも、もうっ旦那様、お話済むまでって…あんっ…わっわかりましたわ、じゃあ、お胸、お胸で我慢なさって…あひっ…おっ帯びは解いては…あっ…そないに急がれなくても…静江は旦那様だけのモノですわ、あんっ……もういつも言ってますやろ、旦那様は泰然と構えて、あひっ」
どうやら正樹を立派な旦那様にする教育はまだまだ行き届いてないようで、許可を貰った少年はすぐさま静江の背後から腕をまわすと、着物に包まれた胸をぐいっと揉み上げる。
そして人妻の端正な美貌を陵辱するのを諦めたのか、今度はその白い首筋に舌を這わせだしていた。
「キミ、ほんとに一条先生が好きなのね、そんな必死になって」
長身の彩は、美貌をほんのりと桜色に染めると、シャツを押し上げる豊満な胸の下で腕を組み、椅子に寄りかかって一息つく。
そのハスキーな声は、いまだにうわずっており、明らかに目の前の情事に圧倒されている様子だった。
しかし先程自分で言ったように、これ以上咎めようとはせず、むしろ興奮した面持ちで興味深そうに正樹の様子を眺めだす余裕も取り戻していた。
「あっ、あの一条先生、何も今その…しなくても……でっ電車の中ですし……正樹くんに我慢してもらって続きはお宿についてからにしては……」
一方まだ全然動揺の収まらない美沙は、興奮ではなく激しい羞恥を感じながら、子供にむちゃくちゃに胸を揉もまれ首筋を舐められてビクビクと気持ち良さそうに震えるお茶の女師匠に、至極もっともな提案する。
「んあっ、あんっ……そっ、それは、堪忍してあげて、まだまだ子供やから旦那様いっぺんこうなると収まりがつかなくて……うちが先に少々悪戯してもうたから……それに……うちももう…んひっ…はぁはぁ……堪忍ね、美沙さん」
静江は、美沙には到底想像できない返事をし、うっとりとした女の表情で自らの胸をもむ隣席の少年を見つめている。
いつものお茶の席での楚々とした良識ある様子で佇む女性と同じ人とは到底思えない言動だった。
「でっ……でも……え? 今ここでですか?」
「いいじゃない美沙さん、二人とも合意の上なんでしょ、ところで一条先生、どうやってこんな小さな男の子、おほん、えっーと、正樹クンと?」
真っ赤になる美沙をさっと手で制して、彩が興味津々といった感じで質問する。
「あっ彩さん、そんな事、今聞かなくても……そっ、それより、わたし達ちょっと席を外した方がいいですよ」
「いいから、いいから、ねぇ、この事、黙っている代わりに、少し教えてくださいません、一条先生」
興味津々の彩の様子に美沙はため息をつき諦めると、なるべく二人の様子を見ないようにと列車の窓に視線をやる。
それでもやはり気になるのだろう、たまにチラチラと様子を伺うように目線を動かし、その度に更に頬を赤らめさせる始末だった。
一方、坂月彩の視線は、正樹の赤く火照った顔と、静江の指がチャックの間から差し込まれもぞもぞしている股間とを何度も往復していた。
「ええですわ……あんっ……ええですわ、お話しましょ」
胸を揉まれる静江は、妖艶な微笑を浮かべながら、まるでその会話の流れを待っていたように、官能に満ちた声をだす。
「正樹くん、いえ、うちの旦那様は、元は唯のお茶の生徒さんやったの、学園で教えているね、もっともあったその日に、こないな関係になってしもうて……んんっ…お茶室で二人きりで出会ってほんの数十分よ、もう、うちはこの人の虜になってしもうて……最初はいややって言うたんやけど、旦那様がはなしてくれなくて……何度も抱かれて旦那様の精を注がれているうちに、うちももう虜になってしもうて……ふふふ、ほんま旦那様は凄いんよ」
静江は、少年の髪を片手で優しく梳き、もう片方の手を少年のズボンに差し入れ撫でながら、自慢げに惚気だす。
「で、出会って直ぐですか? 」
興味が無いフリをしていた美沙だが、素っ頓狂な声をだしてついつい会話に参加していた。
あの清廉でまさに良妻の鑑といった一条静江先生が、不倫を、しかも一回り以上年下の中学生とこんな関係になっているのだ。
美沙としては、相当な理由があると思っていたのだが……
――それが出会って直ぐだなんて……一目ぼれという事かしら?
自分自身はお見合い結婚で特に恋愛も知らず、そういった方面にめっぽう疎い美沙は、単純にそう結論づけていた。
そしてその隣で彩も意外そうに目を見開き、ひどく興奮した面持ちでその美貌を火照らせていた。
もっとも、彩の着眼点は初心な美沙とは違うところにあったのだが……
「こんな子供が、大人の女に……そこまで言わせるなんて……っ」
思わず喉を鳴らす彩は、その間にも細身のロングパンツに包まれた長い脚を無意識のうちに何度も組み替え、まるで、その付け根をこするように忙しない様子となっていく。
「ふふふ、ちゃんと理由があるんよ、何でも旦那様には不思議な力があるそうですわ、大人の女性を魅了する力が……旦那様はうちの他にもぎょうさん妾さんを囲ってはりますのよ、ふふふふ、お二人も旦那様の魅力にやられんよう気をつけてね」
少年の股間をしごき、豊満な乳房を与えながら、静江が優美な笑みを浮かべそう続ける。
「べっ別に、私達はそんな気はないです、ねぇ、彩さん」
「………こんな可愛い子が沢山の大人の女を……って、えっええ、もっ、勿論よ」
静江が、少年を自分達に取られないよう牽制する為そんな出鱈目を言ったのではと思った美沙は急いで否定の返事をし、それに少しばかり反応が遅れて彩も見た目にはしっかり頷き返す。
「ふふふ、信じないの無理あらしません、うちも最初はそんな事と思いましたし……そうそう、旦那様が腕につけてはる腕輪、あれがあるとその力はあまり働かんそうですから、くれぐれも腕輪を取ってはいけませんよ」
「……はぁ」
「…………」
当然ながら美沙と彩には、到底信じられない滑稽な話だった。
それでも、眼前で正樹少年と絡み合いながら含みをもった微笑を浮かべる静江の、その色気と気迫に圧倒され、わけもわからず頷くしかなかった。
「ふふふふ、わかって貰えればそれでええんですわ、まぁ、うちはそないな力なくてもいずれは旦那様のモノになってましたから宜しいですけど、お二人は……あんっ、あっ旦那様っ」
静江がさらに話しを続けようとするが、着物の上から触るだけでは満足できなかったのだろう、正樹が背後から回した手で、人妻の和服の襟をぐいっと広げ邪魔をする。
「「あっ…」」
美沙が口を両手でおさえ、目を熱っぽく見開いた彩が、無意識に赤い唇を舐め湿らす。
その目の前では、欲望に狂う少年の手が、緩まった静江の和服の襟に入り込み、たわわに実った母性の象徴のような白い乳房を片方、ぶるんっっと引きずり出していた。
「あひっ…だっ旦那様っ……むっ胸は触るだけって…あっ…きっ着物が乱れて…あきませんっ…あきま…あひいっ」
だが、正樹は無言で、剥き出した豊満な乳房に顔を寄せると、お餅をくびるように片手でむにゅっと押しあげ、その先端で震える桜色の乳首にむしゃぶりつく。
「あひっ…あっ…もう、そないにに、おっぱい吸って…ああっ…んんっ…あんっ」
麗しい人妻に甘い声をあげさせながら、少年はなれた様子で、大きく口を広げて白い乳房にかぶりつき、じゅるるうっと音をたてて吸いたてる。
「あひっ……あっ、あっ……かっ、堪忍ね、彩さん、美沙さんっ…んひっ……だっ旦那様、おっお胸が好きで…よう、うちの胸も…こないにして……あひいいっ…ちっ乳首噛んだらっ…あっあきませんって…いつも言って…んあっ…んっんっ……はぁはぁはぁ……そっそれで、なっ、何処まで話しましたやろか?うち」
ほつれた黒髪も色っぽく、着物の襟から片乳をまろびだし、少年に根元から揉みしだかれ淡く色づいた先端を吸われている妖艶な姿の一条師範。
その藍色の着物がはだけたせいで、鎖骨からまろやかな乳房まで雪のように白い美肌が艶やかにあらわになっている。
そして、その白い肌の至る所に、幾つもの桜色の跡、つまりはキスマークがついていた。
それが一つたりとも彼女の夫がつけたものではなく、少年がつけた他人の妻を独占している印である事は明白だった。
「はぁ………すっすごいわ……こっこんな事まで……こんなコドモにされてるなんて」
彩が、カラカラに乾いた喉でやっとの事で声をだす。
一方、美沙はもう、今にものぼせて倒れてしまいそうに真っ赤になり、両手で口だけなく顔中覆ってしまう。
今まではキスと、それにズボンに隠れてよく見えない卑猥な何かだけだったのが、ここにきて本格的な肌の交わりとなったのが、美沙には刺激が強過ぎたのだろう。
もっとも興味はあるのか、その視線は指の間から何度もチラチラと覗き、陵辱の跡の浮かんだ白く綺麗な同性もうらやむ艶やかな肌に送られていた。
「えっ、ええ、胸だけではあらしませんのよ、旦那様ったらうちの肌に口の跡をつけるの…んんっ……えらい気に入って、ああっ……胸だけや無くて、背中にも、ふとももも、お尻にも、もうほんまそこかしこ、消える暇なんてないぐらい」
静江は、たっぷりとした豊かな乳房を少年に与えながら、自慢げに自分の細い鎖骨の上に残る唇の跡を撫でる。
その間にも、絞り上げられ卑猥に形をかえる豊満な白い乳房は、音をたててちゅうちゅうっと吸いつかれ、新たな所有の印をつけらていた。
「あんっ…ふふふ、これだけじゃあらへんのよ……他にも、当然、旦那さまの性欲処理を…あひっ、しっ、仕込まれていますの……あひっ…はんっ…くっ口でおしゃぶりする作法も……子種を注がれる格好だっていろいろと……座って腰を石臼のようにこねるのや、ああぁっ…おっ、お犬さんみたいに後ろからして頂くのまで……んんっ…どっどれも旦那様に教えて頂いてますの…あぁんっ」
「………はふぅ」
もう美沙は、その言葉の内容についていけてない様子で、ウェービーな栗色の髪を揺らし、クラクラしている。
「……そっそんな事まで……こんな男の子と……」
一方の彩は、白い喉を何度もゴクリと動かす。
その姿勢は椅子にもたれていたはずが、いつの間にか前のめりになり、メリハリのきいた肉感的なバストを組んだ両腕で押し上げるようにして、モジモジとさせていた。
そんな淫猥な雰囲気が支配する電車の個室の中。
ねちゃねちゃと唾液の音をたて熟女の豊満な乳房を嘗め回し、時折、腰をひくつかせていた少年が、またしても絶え絶えといった感じの声をだす。
「しっ…静江……もっと……ちゃんと…僕っ…」
理性を飛ばした正樹には、当然もう静江しか見えていない。
揉み上げるようにして鷲掴む美女のバストに、すりすりと頬をすり寄せながら、うっとりと惚けた顔で、お願いをする。
「ふふふ、判りましたわ、すぐにたっぷり抜いてさしあげますわね、旦那様の子種汁」
静江も、そんな少年の目に見つめられただけで、彩と美沙の存在など忘れたように、いやむしろまるで見せつけるように、正樹のズボンのチャックに差し込んだ白い指先を淫らに動かしだす。
「あぁぁぁっ、静江っ……あうっ」
少年の気持ちよさそうな声とともに、熟女の巧みな五指にしごかれながら、若い肉棒がズボンの間からひきずりだされていた。
「っ……これが……正樹くんの……男の子の……」
その様を凝視した瞬間、彩はびくっと身体を硬直させるが、すぐに何かを期待するように無意識のうちにぺろり赤い唇を舐めのめり込んで行く。
ロングパンツに包まれた形のいいお尻は、列車のシートから微かに浮き上がり、指で慰められそそり立っている少年の肉棒に今にも覆いかぶりそうになっていた。
「あっ、あぁっ、指いいっ、そこ触るの…あうぅ…」
「ふふふふ、旦那様、ええんですか? ほなら、これはどうです?ここ、こちょこちょってするのええでしょ?ああっもうヌルヌルさんが垂れてきて…あひっ…まっまた乳首噛んでっ…もう、旦那様っ…そんな旦那様にはこうですわ」
列車の座席で、ぴったりと身を寄せ合い仲睦まじく淫らに弄りあう、少年と熟女。
正樹は、はぁはぁと息をつきながら、美人熟女の着物からこぼれた乳房に顔をうずめ舐めまわしコリコリと乳首を噛み、静江はそんな少年の股間でそびえる肉棒を、ひんやりとした指先を輪のようにし根元から激しくコスリ上げている。
もう誰の耳にも列車のレールを走る音は聞こえていない。
ただ、肉棒をコスる音と、粘つく唾液の音、そして饗宴を堪能する喘ぎ声だけが全てだった。
そんな光景は、少しばかり特殊な趣味であるショタ傾向を隠し持っていた坂月 彩には刺激が強すぎた。
「すごい……あんなに硬そうに…あっ一条先生の指……裏側までこすって……あぁ、正樹クンったたらビクビクって……ああ、そうなのね、ソコが気持ちがいいのね……こんな幼いくせに、こんなにスケベに……あぁ、また胸に顔を、そう大きな胸が好きなんだ、キミ」
彩は、気持ちよさそうに白い乳房に顔を埋める少年を食い入るように見つめながら、いつの間にか心の中の声を口に出して呟いているのにも気がついていない。
「ねぇ、彩さんもう出ましょうよ……すっ、少し時間を他で潰してきて……できるならわたし達はこの旅行はお暇させてもらったほうがいいんじゃ」
こちらもすっかり二人に当てられている美沙は、なるべく絡み合う姿を見ないように視線をそらせながら、ちょいちょいと彩のブラウスを引っ張り、席から立とうとする。
「だっ、駄目よ!……そっその…みっ、見といた方がいいわよ、美沙さん、こんな、こんな、可愛い男の子の…もう…見る機会なんて…」
「ちょっ、ちょっと彩さん、何でそんな積極的なんですか、おかしいですよぉ」
「うっ……べっ別に…あっ、アタシは、こんな小さい子に興味があるわけじゃ……ただ、そのほら……ねっ」
なにが、ねっ、なのか良く判らないが、美沙は彩にそう言われて、しぶしぶと言った感じで席に着く。
もっとも美沙としても、恥ずかしながら興味が多少…いや大分あったのだ。
彩の手前もあり、良識をかざす必要があったが、制止を振り切ってまでこの個室から出ようとは思わなかった。
今野 美沙の夫は、子沢山の家庭を夢見る彼女とは正反対でまったく子供に興味がなく、そのせいか非常に淡白で、普通の男なら喜び勇むような艶やかな肉体と癒し系の美貌をもつ清楚な妻を抱く機会はそうなかった。
資産家である美沙の家柄だけに引かれ婿養子にきた夫には、それで十分だったのだろう。
それゆえ、美沙の体の底には、知らず知らずのうちに欲求不満が溜まっていた。
そのせいもあり、あまりにも濃厚な絡み合いから目がはなせず、それはある意味で美沙には非常に魅力的に映っていたのだ。
だからと言って美沙は、夫を裏切る不埒な行為をする気などさらさらなかった。
もし目の前の静江の相手が性欲に溢れた壮年の男性だったり、複数の男性であれば、彼女も間違って襲われるかもしれないと身の危険を感じすぐさま部屋を出ていただろう。
だが相手はただの小さな少年、しかも見れば年上の女性の静江にいいように弄ばれている様子の無力な男の子なのだ。
その事が美沙の安心感を誘っていた。
夫の夜の営みからくる無意識の欲求不満、それに間違っても自分にまで手がかかる事はないだろうという安堵感が、美沙をその場に留まらせてしまったのだ。
勿論、それが大きな間違いである事を、後になってその身体で知る事になるのだが……
今はそんな事を露とも知らない美沙は、ぼーっと上気した瞳で、視線を窓の外に向けるフリをしながらも、お茶の女師範がその白い指先で少年の性欲を処理する様をチラチラと垣間見ていた。
もっとも羞恥心と隣席する友人の手前、少年の股間を直視できず、静江と正樹の顔を見るのが精一杯だったのだが。
そんな正樹の喘ぐ顔は美沙から見てもとても可愛らしく、今にも上りつめそうなのを必死に堪えている様は、いじらしくも思えた。
「ああぅ、あっ、もっ…もっと…つっ強くっ、両手で…」
だがしかし、少年は、美沙の予想と異なり、人妻熟女が片手で与える指先の快感だけでは満足できないのか、さらなる欲求を求めだす。
「んっ、堪忍ね…旦那様…この姿勢では、片手しか…もっと強うこすりますから」
「そっ…そんな…あぁっ…こっこれじゃ…っ……もっと…して欲しいですっ」
静江は、喘ぐ正樹の顔を、手コキに使っていない方の手で優しく胸にかき抱き、髪をすくと、その端正な顔を美沙と彩に向ける。
そして熟したイイ女が見せるちょっと悪戯な眼差しで、向かいの席に座る二人の生徒を見比べると
「ねぇ、彩さん、旦那様の向こう側に座って、少しお手伝いお願いできるかしら?うちの手もうあまっとりませんので、ええかしら?」
「あっアタシですか……え?……まっ正樹クンのを……アタシが……」
彩は身を乗り出した姿勢のまま、ごくっと喉を鳴らし、静江と正樹そして起立する肉棒を何度も見る。
「ええ、お願い、ほんに少しだけでええのよ、ね、旦那様苦しそうでしょ、助けると思うて…ほんに少しだけ、ね」
静江が、潤んだ瞳で哀願するように彩をみつめる。
そのセリフはすっかりこの淫靡な個室の雰囲気に飲まれた彩の心に容易く忍び込んでいく。
お茶の師範に懇願する目で見つめられらた彩は、何度か長い睫をしばたかせると、やがて無言でこくりと頷いていた。
「え?…ちょっと彩さん、一条先生も、なっ何を言ってるんですかっ」
この場で一番慌てていたのは、今は関係ない美沙だった。
だが、そんな美沙を放っておいて、メリハリのきいた肉感的な肢体をもつ彩は、うっとりた熱に浮かされた様子で席を立つと、正樹の隣、静江の向こう側に、誘われるままに席を移る。
「大丈夫よ、美沙さん……すっ、少しだけ、少しだけ手伝うだけなんだから」
彩は熱っぽい声でそう呟くと、ロングパンツに包まれたぱっつんぱっつんの美尻を正樹の隣にぐいっと埋める。
二席分のシートに無理やり三人が座った事で、その身体はいやがおうにも密着するしかない。
彩は、席が狭いからしかたないのよっと自分に言い聞かせ、頬を火照らせながら、スポーツジムで絞り込まれた自慢の肢体をぐいっと少年に寄せていく。
「ね、正樹クン…あのっ……彩お姉さんも…少しだけだけど…協力してあげるわ…少し、少しだけよ」
彩は、自分でも驚くほど甘く、そしてハスキーな声で少年に囁きかけていた。
だがしかし、とうの正樹は静江に夢中で、彩が座った事にも気がつかず、顔を反対側にそむけ静江の白い乳房を吸いキスマークをつける事に夢中になっている。
「ちょっと、正樹クン……キミ……少し失礼よ、お姉さんの方も向きなさい」
恥ずかしさからか、少女のように唇を尖らせ、声をあらげる彩。
「ふふふ、触ってあげたら気づくかもしれませんよ」
子供に母乳を与えるように正樹に乳房を吸われる静江が優美に微笑むと、切れ長の瞳からねっとりと絡む視線で手淫を促す。
「………こっこれを…触るの……男の子の…正樹クンの…」
彩は、羞恥の色を残しながらも、うっとりした瞳を下に向ける。
そこには、しゅっしゅっと音がするほど静江の白い指先で擦られている、少年の肉棒がそそりたっていた。
その先端からは、すでに透明な液がとろりと流れ、鞘のほうまで滴り落ち、逞しくビクビクと震えている。
「うわ…すごいわ…ガチガチね……」
彩は、こくっと白い喉を鳴らし、いつの間にか溜まっていた唾を嚥下する。
「彩さん、いいのよ、触って撫でてシゴいてくれて、旦那様の……男の子のおち○ちん」
彩の心の奥を見透かすかのように、ゾクッと背筋を撫でる静江の淫靡なセリフ。
「おっ……男の子の…おっ…おち…おち○ちん」
その声に誘われるように、彩のネイルアートで彩られた爪先が、ゆっくりと震えながら少年の肉棒に伸びていく。
その指の根元に光るのは、既婚者を示すリングの輝き。
「……あっ!……あっ熱いわ…それに……すごい…みゃっ、脈打ってる…これが……男の子」
彩の指先の先端がほんの少し触れただけで、肉棒は驚くほど跳ね、過剰に反応してくれる。
少年のその反応が嬉しくて、彩は美貌に艶やかな欲情の笑みを浮かべると、さらにひんやりとした自分の細い指先を、硬く熱い男の子に絡めていこうとする。
その時……
「彩さん、なっ何をしてるんですかっ、こっこんな……だいたい、彩さんだって結婚してるんですよ……不潔です、だっ駄目ですよ」
美貌を淫らに歪め陶酔とする彩の耳に響く、美沙の制止の声。
ビクンッと止まる白い指先。
だが、それはほんの僅かの間だけだった。
彩は、少年の可愛く喘ぐ顔とヒクヒクしている肉棒に、チラチラと目をやると、自分に言い聞かせるように、火照りうわずった声をだす。
「ちっちがうわよ、これは…その、お手伝いよ、正樹クン苦しそうでしょ、はやく楽にしてあげないと……それに触るだけなら不倫じゃないわ」
「え?そうなんですか?……って、違いますぅ、もう、とにかく、その、破廉恥です、よくないです」
「美沙さんは黙ってそこで見てなさい、あっ、アタシはこの子を…ごくっ…こんな可愛い男の子を…あぁ、もう我慢できないのよっ」
そう言うやいなや、彩の結婚指輪をつけた白い手が、少年の肉棒に絡みつく。
「すごい、すごいわよ、正樹クン、こんな熱くて…あぁぁぁっ…こんなので一条先生を…大人の女を…泣かせてるのね……子供のくせに…はぁ……なんて男の子かしら」
熱い吐息をはく美女の指先は、くねくねと動きながら、やがて大胆に指の腹も使い、肉棒の先端にあふれる粘液を広げ、這い回る。
「ふふふ、旦那様、おち○ぽコスられるの、気持ちええですか?ほら、うちだけだなく、彩さんも旦那様のおち○ぽ撫でてくれはりますのよ、彩さんよ、ほら、彩お姉さんよ、ちゃんと見てあげて、旦那さまの目で」
「はひっ、いいっ…へ?…あっ」
静江の声と、何より今までと違う肉棒への感触に、正樹がぼんやりと白い乳房から顔をあげ首をひねる。
その視線の先で、あの出会ったばかりの美人のお姉さん、坂月彩が頬を上気させ微笑んでいた。
「あっ、ああっ……あっ彩お姉さん」
「あら、ほんとに気がついたね、ふふふふ、スケベねキミ」
「はひっ?なんで?あれ?」
いまだに欲望の中に埋もれ理性を飛ばしている正樹は、ぼんやりと気持ちイイ感触にひたりながら、必死に頭を回そうとする。
「大丈夫よ、旦那様、彩さんには、お手伝いを少し頼んでますの、さあ、彩さんもしごいてあげて」
静江は、戸惑う正樹の髪を優しく撫で、頬にふんわりと接吻すると、肉棒の根元で彩に手本を示すように、指の輪を激しく前後させだす。
「えっ、ええ、こっこうかしら?」
すっかり少年の肉棒に触る事に抵抗が無くなったセレブ美女は、お茶の師匠に促されるままに指を絡め、ズリズリと動かしだす。
「ああぁっ…あっ、あっ、あっ」
肉棒に絡みつきシゴキあげる美女達の十本の指の感触に、正樹は背筋をビクビクそらせながら絶え絶えに快楽の声をだしていた。
「ふふふ、彩さんもっとぎゅっと握ってええんですよ…そう…それに空いている指で裏側をこすって…ええ、そうですわ」
「……はぁはぁ…こうね……あぁ、すごいわよ、キミ、こんなにして…はぁ…おっお姉さんの手の中で暴れてる……あらっ、今びくってしたわね? ふふふ、お姉さんの手が良かったんだ……ここがいいの、いいのね、ほらもっと擦ってあげる、あぁ、アタシ、男の子をいじってあげてるのね」
静江に導かれ、陶酔した表情を浮かべる彩は、興奮した様子で心の中の声を全て吐露しながら、淫らな手淫に没頭しだしていた。
その猫のような瞳からは、やり手経営者として名を馳せたキャリアウーマンのプライドは霞んで消え、朱色の唇にうっとりと笑みを浮かべ、今まで心の奥に隠していた願望が満たされ至福の時を過ごしている事を示している。
少年の妾である妖艶な和服人妻と、新たに年下の男の子に夢中となったキャリアセレブ人妻。
二人の指先は、そそりたつ若い肉棒に、まるで吸盤の生えたかの様に吸いつき、どんどんとその激しさを増していく。
そんな二人の美人人妻に挟まれた正樹は、まさに夢見心地で肉棒をいじられ、心底気持ちよさそうに声をあげ続けていた。
「あぁぁつ、あぁ、あっ、すごいよ、きっ気持ちいいですっ」
そんな少年の顔を、彩も蕩けて色気に満ちた女の視線で愛しげに見つめる。
彩の心に疼く欲求が、正樹の可愛い声をもっと聞きたいとせかし、拍車をかけてくる。
もっと、もっと、この子をいかせちゃいたい、そうアタシの手で。
彩は湧き上がるその欲求にゾクゾクと震えながら、喘ぐ少年に淫靡に輝く美貌を寄せ、囁きかけていた。
「はぁはぁ……ほら、キミ、だれにおち○ちん弄られてるか言ってみて? だれ? キミのおち○ちんこんなにエッチに弄ってシゴいてるのは、だれかしら?」
「あひっ…あっ…ああぁっ…彩さんっ…彩お姉さんですぅぅっ」
あはっ、この子ったら、アタシの名前を言ってるわ……
こんな可愛い男の子に…エッチな事して、名前を呼ばれてるうっ♪
正樹の素直な返事に、彩の心の中で枷に入れられしっかりと封じられていた禁断の欲望がどんどんと漏れ出していく。
ジンジンと下腹部を熱くしながら彩は、紅茶色の前髪が少年の頬にかかるほど更に顔を寄せ、とろっと蕩けそうな甘い息を吹きかけながら、囁きかける。
「ふふふふ、そうよ、彩お姉さんよ、キミの、男の子のスケベおち○ちんいじってあげてるのよ……ああぁ…またビクビクして……ふふふ、今のも良かったのね? ここの先っちょ弄られるのいいのかなぁキミは? あぁぁ、その顔、はぁ、正樹クン可愛いわ、ほんとに」
彩は目を細めて、喘ぐ少年の幼い顔をみつめると、その頬にルージュの光る唇を寄せ何の抵抗もなく、ねっとりと淫らに舌を這わせだしていた。
唾液を滴らせて淫靡に這わされる美女の舌は、長くまるで肉食の猫科の動物を思わせる。
その長い舌は卑猥にくねりながら、とろっと少年の頬を舐めあげる。
正樹のあげる快感の声、その耳に心地いい響きを聞くために。
その為ななら、何でもしてあげたくてなってくる……
そう例え誰かに背く事になっても……
長身モデル体型のセレブ人妻、坂月 彩の長く淫らな舌は、頬から鼻筋へと正樹をゆっくりと舐めあげ、まるで自分の所有物と言う様に光る跡を残していく。
「あぁっ…彩お姉さんっ…あぁっ……いいっ」
正樹に名前を呼ばれる度に、ゾクゾクと背筋を震わせる彩。
「れろっ…んふふふ、そうよ、正樹クン、キミの彩お姉さんよ、ほらもっと名前を呼んで…んっ…お礼にたっぷり舐めて、しごいてあげるから……ふふふ、お姉さんの舌長いでしょ?ちょっとした自慢なんだから、これでたっぷり舐めたげる、れろっ」
彩は、名前を呼んだご褒美とばかりに、濡れる色っぽい唇を動かし、伸ばした舌先を淫靡にくねらせ少年の顔を舐めまわし、握り締めた肉棒をシゴきまくる。
その反対側からは、正樹に魅せられる彩と同様に、涼やかにそして淫らに微笑む静江が顔を寄せ、同じように舌を這わせて、喘ぐ少年の頬を舐めだしていた。
「旦那様、気持ちええですか? れろっ…んっ…ふふふ、ドクドクいうて、ええんですね?」
「れろっ…んふふふ、当然気持ちいいわよね? 嬉しいでしょ? こんな美女に二人がかりでこんな気持ちの良い事して貰えるなんて、キミは幸せ者よ…れろっれろろんっ……ふふふ、まだ子供なのに、こんないい思いして……ふふふ、あぁぁん、もうほんと可愛くて…あぁ…おち○ちんまでビンビンにして…んっ…え? あんっ!」
その時、少年に覆いかぶさるようにして顔舐めと手コキ苛めに没頭していた彩が、びくんっと動きを止める。
その原因は、正樹が背後からシートと彩の背中の間に手を伸ばしぐいっと抱き寄せ、外人モデルのように大きく突き出すバストに、ブラウス越しに指を食い込ませてたせいだった。
「あふぅ…なっ、なんて子なの、こっ、この子は……んあっ…はふぅ……そっ、そんな指をむにゅむにゅ動かして……そうなのね? そんなにお姉さんのムネ揉みたかったのね? でもね、これはねキミみたいな子供のものじゃないのよ」
なじる様にそう言いながらも彩は逃げたりせず胸を揉ませるにまかせ、また舌を動かし、愛情たっぷりに少年の頬を舐めまわし、手首を派手に動かし肉棒をシゴいてやる。
正樹は、抱き寄せた彩のスケベに張り出したバストをブラウスの上から、もう好きほうだいに揉みまくっていた。
「ふふふ、言いましたやろ、旦那様は、お胸が好きって…んああっ」
そう言う静江もまた、うっとりと目を細めヒクヒクと震える。
その和服の人妻の白い乳房も、背後から回りこんだ正樹の腕に弄りまわされていた。
「うふふふ、幸せそうね、こんな美人のお姉さん達のムネが揉めるんだもの、キミみたいな男の子なら当然よね……あぁぁ、いいわよ、もっと強くなさい…かわりに、お姉さんも、うんと強くシゴいてあげるわ、キミのおち○ちん」
抱き寄せられ搾乳されるように挑発的なバストを揉みしだかれている彩は、少年の肉棒を覆う白い手は、手首のスナップを激しく使ってシェイカーを振るようにリズミカルに前後に振れだしていた。
「あひっ…ひあぁっ…あぁっ、いい…ぅ…こっこするの…いぃ」
正樹は、掌にあまる美女達の大きな胸を両手に抱き、背筋をそらせ列車のシートに背中を押し付けながら、気持ちが良すぎるためか、舌をつきだし喘でいた。
「はぁはぁはぁ…何?何なのキミ? 舌なんかだして……そう、お姉さんに舌を舐めて欲しいんだ……ふ〜ん、胸の次は、舌?舌を舐めろって? ねぇ、アタシが人妻って知ってやってるの? なんて子なの、まだ子供のくせに、他人の奥様に舌を舐めさせようだなんて、えらそうに、そんな子はこうよっ……んんんっ…れろっ、あふぅ」
色気をむんむんと発する彩お姉さんは、少年を叱りながら我慢できなくなった様子で、その長い舌をくねらせ、自分からむしゃぶりついていた。
にちゅっ、じゅるるるっ、ちゅっ、れろろろっ
卑猥な音が響き渡り、スケベな彩奥さまは少年の舌を舐めしゃぶり、絡ませ、とろとろと唾液を滴らせる。
「あぁっ、彩お姉さん…れろっ…舌柔らかい…んんっ…もっとっ…」
「れろっ…んっ、なんて子…んぐっ…舌からませるの…うまいじゃない…れろっ…いいわぁ…いいわよっ…おっお姉さんの舌…全部吸いなさいっ…んぅ…そんなにツバを出して…だっ、唾液まで飲ませるつもりね、キミは人の奥さんを何だと思ってるの、この口はキミのものじゃないよ、ちゃんと覚えておきなさい、じゅるっ、じゅるるっ」
彩は叱り付ける口調とはうらはらに、ますます少年に覆いかぶさり、わざと音を立て舌を絡ませ、頬をすぼめて唾液をすする。
「んぐっ…んふうぅ…じるるるっ…あふぅ…こっこんな気持ちのいいキスはじめてよ…あふぅ、アタシこんな子供とキスしてるのね……ダンナがいるのに……こんな子にキスしちゃってる」
アダルトな美貌を蕩けさせながら、淫蕩な色気をたっぷり含んだ瞳で、舌を絡ませる愛しい少年に囁きかける。
「ダンナにだってこんな事した事ないんだから、喜びなさい……んふぅ…じゅるるるっ…れろっ……あぁっキミのヨダレ美味しいわよ、んぐっじゅるっ……ほら、口の中も舐めるわよ、開けなさいっ…お姉さんがキミの舌も歯も全部舐めたげるから、あ〜んするの……よし、いい子ね、んんっ」
素直に口を開く正樹の口腔内に、セレブ妻の涎まみれの長い舌が踊りこむ。
じゅるるぅ、じゅるっ、ちゅるっ、ちゅちゅっ、じゅるるっ
今まで以上に濃密でねちっこい唾液と舌が絡み合う音が響き渡る。
「んふぅ、んんっ、いいわよっ…んんっ……んんっ……だぁめっ、ヨダレは全部、彩お姉さんの口に吐くのよ、ぺってなさい、特別に飲んであげるから、ほら、さあ、お姉さんのお口に出して」
少年の口を啄ばみ貪る妖艶でセクシーな美女は、自慢の舌を引き出すと、ねっとりと唾液の糸をひくルージュの引かれた唇を開ける。
「あぁぁ、彩、彩お姉さん……んっ」
情熱的な美女とのキスの虜になっている少年は、喉の奥から湧き出した唾液をためると、促されるままにその目の前の差し出された彩の舌の上に、どろっと垂らしていく。
「んふぅっ……ふふ……いいわよ、ほら、唾液を頂戴、お姉さんの舌の上に垂らすのよ、あふ…んふふふ……じゅるっ…んっ、ちゅっ、じゅるっ」
坂月 彩は、突き出した長い舌の上に垂らされた少年の唾液を美味しそうに啜り上げると、陶然とした笑みを浮かべていた。
「んふぅ……最高ね」
「…………」
一方、今までなら人妻にあるまじきその行為を止めていたはずの良識ある友人、今野 美沙は、既に言葉を失っていた。
それは決して、愛欲たっぷりに情熱的に少年の口を吸い、ヨダレを啜る彩に呆れかえったわけではない。
彼女もまた、この狭い個室の中に充満する淫靡な雰囲気の虜となっていたのだ。
そして美沙を虜にし、言葉もなく魅せ続けているのは、静江と彩の二人の手でシゴかれ、今にも爆発しそうにビクビク脈打つ男の子のシンボル。
「………すっすご……い………」
いつの間にか席から立ち上がり、座席の間に座り込むようにしている美沙の目の前では、正樹の肉棒がほんの目と鼻の先で、十本の女性の細い指に絡みつかれ揺れている。
美沙は、男性の性器を直に見るのは、実はこれが初めてだった。
もちろん夫のいる身、性体験はあるがそれは全て暗い室内、布団の中で行われ、彼女が大抵何かを感じる前に全て終わっていた。
その目の前に、この光景なのだ。
本当なら常識ある彼女は目を逸らせる筈なのだが、彩と静江がもう正樹に夢中になり、だれも彼女に関心を示さなかった事が、美沙をこんな大胆な行為に走らせていた。
勿論、触る気はない……けど、ほら見るのなら不倫にはならないから…多分……っと自分に言い訳する。
「………こんな風に……一条先生…これでいつも……されちゃってるんですね」
美沙は、スカートの中の太股をぎゅっと寄せると、自分の下腹部から湧き出す言い知れぬ疼きに突き動かされながら、今にも欲望を吐き出しそうなその肉棒をマジマジと見つめ続けていた。
そして、そんな美沙の上では、いままさに、不倫とか貞淑とかそんな言葉を忘れ、ただ淫蕩な時間の虜となった 若妻、坂月彩が、少年の口をたっぷりと吸い唾液を嚥下しながら、白い掌から伝わる脈動が限界に達しているの感じ、胸を高鳴らせていた。
「んちゅっ……ふぅ……どう、お姉さんに唾液を飲ませた感想は? ふふふ、トロンっとしちゃって人様の奥さんのお口を好きにできるの相当気に入ったみたいね……あらあら、それにキミのいけない子がドクドク言ってるわよ、そろそろ、我慢できないんでしょ」
抑えきれない興奮に頬を火照らせながら、徐々に手馴れていた様子で手首を上下させ肉棒をシェイクする彩。
その濡れた朱唇からは、少年の舌にまで唾液の橋ができており、たっぷり絡み合った舌の激しさを物語っていた。
「ほら、いくなら、いくって、言いなさいよ、彩お姉さんが、キミのイク顔ちゃんと見ててあげるから、白いのビュビュって出しちゃう顔をね」
とろっと垂れる唾液の橋を、美女は唇をすぼめて啜りとると、まるでそうするのが当然のように白い喉をゴクリとさせて飲み干し、淫らに囁きかける。
「あひっ…あぁっ…あぁっ」
美女とのたっぷりねっとりのディープキスに惚けた正樹は、下半身を刺激する快感の摩擦に酔い、さらに顔を緩め、きちんと返事もできない。
それでも、片手で彩のブラウスに皺がつくのもお構いなしに、柔らかく突き出た砲弾バストを揉みまわし、もう片手で静江の母性に溢れる乳房を鷲掴みにしているのは流石だった。
「旦那様っ、いきそうですの? ほら、彩さんを見てあげて、いくならいくと、言ってあげてくださいまし、さあ」
そんな正樹に、彩と反対側から抱きつく静江が、ちろっと赤い舌を伸ばし耳に這わせ、甘い艶声で主人を正気づかせる。
「へあっ……ああっ…うっうん…ああっ……はぁはぁ……ぼっ僕、こっこすられ…てっ……いっいきそうです…だしちゃうっ…ぼっ僕、だしちゃうよ」
二人のお姉さんにめちゃくちゃに甘やかされ、手でコスコスしごかれまくる正樹は、舌ったらずな口調で何とか声をだす。
「んふふふふ、よく言えました、いい子ね、正樹クンは……ちゅっ……そう、もうだしちゃうのね、お姉さんの手でシゴかれて、このおち○ちんから、白い液だしちゃうのね、あぁ悪い子ね、こんな電車の中で射精しちゃうんだ、んふふふ、ほら、ほらっ、だしなさいっ、全部お姉さんの手に吐き出すの」
正樹の告白をうっとりとした表情で聞いた彩は、彼女の夫や経営する店の従業員には決して見せない心底嬉しそうで淫らな美貌を輝かせ、その手を激しくぬちゅぬちゅと動かし、少年の耳にたたみかけるように囁き続ける。
「ほらっ、いきなさい、ほらっ、ほらっ、お姉さんが搾り出してあげるわ、根元から一滴残らず、絞ってあげる」
「ふふふ、彩さんにお願いして良かったわ、旦那様、おだしくださいませ、静江達の手で熱い子種を思う存分」
じゅっちゅ、にゅちゅっ、ぬちゅっぬちゅっっ
粘着質な音を散々たて続ける正樹の股間。
そこでは、静江と彩の指先が絡み合い筒状にされ、その中に少年の熱く硬い肉棒をくるみこみシゴキあげ、激しく蠢いている。
「さあ、呼んで、お姉さんの名前、キミのお子様おち○ちんシゴいてる、お姉さんの名前呼んで、いっちゃいなさい、ほらほら、いくの、いきなさいっ」
彩の手が強弱をつける様にぐっぱっと握られ上下にシェイクし、静江の指先が連動するようにコスコスと激しく淫らに動き回る。
そして、ついに……
「あああっ、彩お姉さんっ、お姉さんっ、いいいっ、いくうううっ」
手コキする二人の美女の豊満なバストを、ぎゅうっと抱きしめ、ガクガクと身を震わせる正樹。
美女達の手が、ぬちゃぬちゃと絡む肉棒の先端から、激しい脈打ちとともに、精道をかけあがった熱く濃い白濁の粘液が吹き上がる。
「うううっ」
どびゅっ
最初の濃い一絞りが吹き出た、次の瞬間。
どびゅびゅびゅびゅっ
立て続けに脈打ち激しく噴出するたっぷりと濃いドロドロとした精液。
「あは♪ いったわ、この子ったら、彩お姉さんって言ったわね、アタシの名前呼んで、いったのね、あは、いい子ね、キミのいってる顔、可愛いわよっ、あぁほんとに素敵な男の子ね、んんっもう、食べちゃいたいくらいよ」
彩は、呻きながらドクドクと射精を続ける正樹の顔をうっとりと見つめ、全ての抑圧から開放されたような途方もないエクスタシーを感じ歓喜に心を震わせながら、頬にキスの雨をふらす。
こんな可愛い男の子が、自分の手で、しかも自分の名前を呼びながら精を放ったのだ。
彩はもう、ロングパンツの下のショーツを濡らしながら、手の中で熱い迸りを吐き出す肉棒を愛しげにいつまでも撫でさすっていた。
「旦那様、素敵でしたわ、ほんまに、うちの旦那様は最高ですわ…んっ」
静江も自らの掌で射精する主人の肉棒の脈打ちに、艶然として潤んだ瞳を見せ、彩と反対側から感謝をこめて頬にキスをする。
「あひっ…気持ひ良かっ…た…ですぅ…あぁぁっ」
そして正樹も、彩と静江から頬に沢山の感激と感謝のキスを受けながら、まさに雲上にいるようにぽわんっとした極上の気分を味わっていた。
そのまま、ただシゴかれるにまかせて尿道に溜まった残りの一滴までザーメンを吐き出し、心地良さそうに目を閉じるのだった。
一方、美沙は、そんな抱き合う三人をぼんやりと見つめていた。
ボックスシートの座席の間の床で、ちょこんと膝をついた姿勢で座るお嬢様育ちのおっとりとした上品な若妻。
その清楚な美貌には、どろっと濃いザーメンがまんべんなく降りかかっていた。
「?…これって?」
まるでヨーグルトのような白濁のその粘液の塊は、今まで美沙が熱心にみていた例の男の子のシンボルから、白い指先によって搾り出され、ほけっと顔を上げていた彼女の顔にびちゃびちゃと落ちてきたのだ。
やがて、いまだにぼんやりと顔をあげている美沙の、すっと通った鼻筋をたれ、白濁液の塊が一つ、半開きの口の中にトロリと流れ込む。
「はれ?……あっ苦いです」
その味はまったく美味しくなかったが……
何故だか、美沙の下腹部をじんじんと熱くさせる効果は十二分だった。
「ふぁ……」
肌にからみつきそうな濃厚な淫気が満ちた列車の個室の中。
穏やかな清楚さを身に纏う若妻、今野 美沙は、正樹のドロドロのスペルマをその美貌でうけ、放心したように座席の間で膝をついていた。
「あらまぁ、美沙さん、すごい顔ね」
色気たっぷりアダルトさ満点の美女、坂月 彩は、そんな親友の様子に気がつくと、激しいキスでルージュが乱れた唇を舐めながら、淫靡な微笑を浮かべる。
その美貌は、正樹の肉棒を手コキした興奮で紅潮し、男を吸い寄せる魔性の色香を存分に醸し出していた。
そんな彩は、友人の痴態を眺めると、射精の開放感でだらしなく椅子にもたれたままの正樹に擦り寄り、囁きかける。
「ふふふ、ねぇ、ほら見なさい、キミのだした男の子の汁で、美沙お姉さんが顔中ドロドロよ、すごいわ、あんなに濃くって、まるでヨーグルトみたい、たくさん溜まってたのね、どう、気持ちよかった?」
「………はぁはぁ……はっはい…きっ…気持ちよかった…です」
「ふふふ、そう、いい子ね」
彩は、ハァハァッと荒い息をつき満足そうにシートに身を埋める少年に、軽くキスをして褒めてやる。
そうしながらも彼女の視線は、精液まみれで呆然としている美沙の顎先から、ドロっと滴る白濁液に釘付けだった。
彩の薄茶色の瞳は、淫らな欲情と羨望で染まり、辣腕女経営者としての理性をすっかり覆い隠していた。
「んふふふふ、それにしても、ほんと凄い量と濃さね、どっろどろに粘ついて、とっても臭そう、あら、今、美沙さんのお口に垂れ落ちたわよ、あんなモノを口に含むだなんて……ごくっ……ふふふ、考えただけで……ゾクゾクするわね」
魅惑のセレブ人妻は、熱を孕んだ口調でそう言うと、スペルマを搾り出した後もシゴいていた正樹の肉棒から、名残惜しげに手をはなす。
次いで、少年に寄りかかっていたメリハリのきいた肢体を優美に起こすと、その長身を屈めて、跪く美沙の上に覆いかぶさり、その淫靡に満ちた美貌を寄せていく。
「あっ…彩さん?」
「ふふふ、美沙さんったら男の子のザーメンをべっとり顔中にはりつけて、綺麗な顔がだいなしね……ん〜〜凄いわこの匂い、これが正樹クンのなのね、ふふふ、いいわぁ、美沙さんすぐに綺麗にしてあげる」
にんまりと笑みを浮かべる彩は、可憐な花をあしらったネイルアートの施された指先を、美沙のスペルマ塗れの両頬に優しく添える。
「え?彩さん?」
「それじゃあ、ご相伴にあずかろうかしら、正樹クンのザーメン」
彩は、恍惚とした表情で紅い唇を窄め、固定した美沙の頬にゆっくりと寄せていく。
「あっ彩さん、なっ何を?」
「いいから、美沙さんはじっとしていて、大事なザーメンが垂れ落ちちゃうでしょ、んふふふ、正樹クンのザーメン汁っ、今、アタシが綺麗にしてあげるわよ、んっ……じゅるるるぅぅっ」
彩は、窄めた唇を親友の頬に寄せると、へばりつく白い粘液の塊を下品な音を立てて、一気に啜り取り出していた。
それはもう、舐めると言うより直接口をつけてバキュームするような、浅ましく淫らな美女の精飲する姿だった。
「じゅるっ……れろっ……じゅずずずっ……んはっ、はぁはぁっ、なんて臭くて不味いのっ、こんな臭い汁を、美沙さんにかけるなんて、いけない子ね、もう、こんなスケベなザーメンっ…じゅるるっ…んぐっ、全部、アタシが飲んであげるわ」
ずずずっっと音をたて、彩の窄めた唇が、粘つく精液を啜り上げる。
「彩さんっ……んっ……だめですよ、やめてくださいっ」
淫蕩な雰囲気に飲み込まれ状況に流されるままになっていた美沙は、自分の頬や鼻筋に同性の唇が吸いつく感触に、徐々に事態を把握し正気を取り戻していく。
だが、いやいやと首を振ろうとしても、彩の長い指先が美沙の顔をしっかりと捕まえて、振り解けない。
「じっとしていて美沙さん、全部、全部綺麗にしてあげるから、じゅるるっ…んふっ、アタシったら正樹クンのザーメンを飲んじゃってるのね……じゅるっ……はぁ、口の中に絡みついてっ…んぐっ……ああぁ、濃くって喉にべったりはりつく感じ……これを全部アタシの指で搾り出してあげたのね……んっ、じゅるるっ……んぐっ」
「あっ、彩さん、だめですって、あんっ、んっ」
美沙の制止の声など聞こえない様子で、彩は猫のように目を細め、突き出した唇でスペルマを啜り取り続ける。
さらには、その口腔中で、泡立てる様に自分の唾液とくちゅくちゅと混ぜると、最後には白い喉をならして躊躇無く嚥下していた。
「んふぅ、美味しいわ、正樹クンのザーメン」
坂月彩にとっては、精子をたっぷり含んだ正樹の粘つくスペルマは、もう何の忌避も感じさせない、むしろ、飲んであげるのが当然のモノに感じられていた。
彼女の中で、本人でさえ気がついていなかった年下好みの性癖が、正樹の笑顔を見た瞬間から芽をだし、この一連の騒動ですっかり熟成され開花していたのだ。
その隠れた性癖の芽は、これがもし普通の状況であれば今まで通り直ぐに彼女の心の奥底に枷をつけて封じられ、本人が意識する機会も無く、一生開花する事などなかっただろう。
だが、尊敬するお茶の師範、一条静江とその生徒である中学生の高梨正樹少年との関係の告白、それに続く淫らな行為があっさりとその枷を取り払っていた。
そして、その倒錯的な願望は、この淫らな列車の密室の中ですっかり花開き、彩の心に根を下ろしていたのだ。
――そうよ、これは全部アタシが搾りだしてあげたんだもの、アタシが飲んであげるのが当たり前よね。
自分が出させてあげたのから、これは当然の行為。
いや、むしろ彩にとって正樹の精液を啜る事は、権利であり義務なのだ。
彼女は、その人生で初めてスペルマに口をつけたにもかかわらず、むせかえるような濃い体液を、じゅるじゅるっと啜り、たっぷりと匂いと味を堪能して、喉の奥に流し込む。
無論、人妻であり良識を持ち合わせている彩には、これが常識に外れた淫らな事という認識はしっかりと残っている。
坂月 彩と彼女の夫は、夫婦というよりも寧ろお互い社会的パートナーとして対等に渡り合っている関係だった。
夫婦の間に子供はなく、むしろ邪魔という感じでお互い家庭は顧みず仕事に没頭してきた。
その結果、結婚して僅かの間で、彼女と同じくキャリア重視の夫との間は疎遠になりがちとなり、ブティック経営が軌道にのりだしてからは、ますますその傾向が強くなってきていた。
それでも、責任ある大人の女として、また社会的な成功者としての矜持が、坂月彩の高いモラルを守り続けていたのだ。
そこに、お茶の師範であり尊敬に値する女性であった一条静江の、少年の妾として生きているという告白が大きなヒビを入れていた。
しかもその相手が、彩の心に琴線に触れる少年、高梨正樹だった事がヒビを大きな穴に変えると、その穴から、意識の奥に閉じ込めていた年下の男の子を可愛がりたいと言う願望が、溢れ出し、またたくまに理性を染め上げていたのだった。
―― 一条先生だけ、こんな可愛い子と……アタシだって本当は……少しだけ、後、ちょっとぐらい……
女師範への羨望と嫉妬の感情は、彩のモラルに空いた穴を大きく広げていく。
――そうよ、正樹クンのザーメンを出させてあげたのは、アタシだもの……それを飲んであげるだけなんだから……
トロンと目を蕩けさせ、喉に絡みつく精液を啜りながら、まだ心に僅かばかり残る崩壊したモラルの欠片と折り合うと、類まれな色香の美女は、少年のザーメンを啜りとる行為に再度没頭していくのだった。
「じゅるっ……じゅるるっんんっ…ごくっ……ずずずずずっ……くちゅくちゅっ」
彩は、熱っぽい潤んだ瞳で、正樹の出した欲望の名残を啜り、口の中で味わって嚥下を続ける。
だが、その隠された欲望が満たされる至福の時間はあっけなく終わってしまう。
そう、彩の両手で固定された美沙の顔には、もう僅かばかりもスペルマの名残は残されていなかったのだ。
同性に顔を舐められ唇を這わされ続けた美沙の顔には、スペルマの変わりに親友である彩の自慢の長い舌が這い回った涎の跡が、べっとりと残っているだけだった。
「あら、もうないの?あんなにたくさん搾り出してあげたのに」
どれだけ長い間、自分が親友の顔を、丹念にねっとりと舐め続けていたかも気がついていない彩は、形のいい眉を顰めて落胆する。
「あっ、彩さん…もっもうやめてください……」
正樹のザーメンにかわり彩のヨダレで顔中を汚した美沙が、嘆願するように口を開く。
その美沙の戦慄く唇をみつめていた彩は、ふいにニンマリと笑みを浮かべると、次いで、蟲惑的に笑いだしていた。
「んふふふふふ、なぁんだ、まだあるじゃない、美沙さん、それはアタシのモノよ、返してもらうわ」
「へ? なっ、何をですか?」
ぽかんっと口を開けたままの美沙は、再度覆いかぶさってくる彩を呆然と見つめる。
そんな美沙の唇の端に、わずかに付着する白濁した残りカス。
次の瞬間、うら若く美しい人妻達の唇が重なり、深いキスを交えていた。
「んぐぐっ、あっ彩さっ……やっ……んんっ」
「んふぅっ……じゅるぅっ、駄目よ美沙さん、口を開けて、この中にも隠してるんでしょ……全部舐めとってあげるわ……んんっ」
彩は、美沙の顔を強引に傾けると、その唇に吸いつき、スペルマの残りも美沙の唾液も全てまとめて、ちゅるちゅると啜り上げる。
彩の自慢のよく動く長い舌は、貪欲なまでに美沙の口腔中を貪り泳ぎまわると、歯の裏側まで丹念に舐め取り出していた。
「んぐっ……んんっ…あふぅ……あっ彩さん…やめて…っ」
美沙の制止の声も、彩の口の中に唾液とともに飲み込まれる。
やがてザーメンの残りを全て啜ったにもかかわらず、彩のキスは止まる事無く、むしろより積極的に美沙の口を味わいだしていた。
「あっ…彩さんっ……んんっ…っ」
くちゅ、ちゅるっ、くちゅっ
長く深く美女同士の混じりあう唾液の音が響く中、彩の情熱的に動く悩ましい長い舌が、縮こまる美沙のソレを吸い上げ、絡ませ、ねっとりと蠕動する。
「美沙さん……顔もっと傾けて……そうよ、んっ」
まるで先程の少年とのキスを再現するかのように、彩は親友の若妻の唇を甘く噛み、舌を何度も伸ばし、唾液塗れの舌を丹念に、にちゃにちゃとすり合わせる。
彩にとって、それは僅かにでも残る少年の匂いを求めての行為であり、同性の口だからといって何の躊躇もない。
「んんっ……彩さん……あぁっ……あふぅ…こっこんな事……だめですぅ」
一方の、美沙は、同性とのキスという生理的に受け付けない行為を何度も拒絶していた。
しかし、小さく丸まっていた舌を吸われ、舌の腹を摺りあわされているうちに、おっとりとした細目をさらに細くし、いつしかついには抵抗をやめてしまっていた。
実は、美沙にとってこれが生涯初めてのディープキスだったのだ。
淡白な美沙の夫は、とことんそう言った行為に興味がないらしく、たまにある夜の営みの際でも、お義理とばかりに口を少しだけ重ねあう程度だったのだ。
そんな美沙に、同性同士とはいえ、この舌を絡ませる濃密な刺激はあまりにも強すぎた。
資産家の箱入り娘だった美沙は、もう何も考えられず、ただ彩の与えてくれる粘液の絡み合う強烈な刺激に陶然とし、腰からヘタリこんでしまう。
その穏やかな瞳は、うっとりと細められ、強張っていた手足から力が抜け、すっかり彩のなすがままだった。
「あぁ……彩さん……やめ……やめないで……ください、んんっ」
初心な美沙はすっかり彩とのキスに心酔していた。
舌と唾液が絡みあう音が、何度も何度も際限なく響きわたる。
その出所は、女同士が重ねあう艶やかな唇の間。
それも極上の容姿とスタイルを併せ持つ美女同士の倒錯的なディープキス。
微かに揺れる列車の個室の床で、紅茶色の髪の色気たっぷりのアダルトな長身の色妻が、ウェービーな栗色の長髪を揺らすうら若い容貌の清楚な若妻に、覆いかぶさり深く丹念なキスをする。
二人の濡れ光る唇は、何度も重なり合い、その間では妖しく舌がほつれあっていた。
「んんっ……はぁ……もう残ってないみたいね」
そんな長時間重なり合っていた深すぎるキスも、覆いかぶさっていた彩がそっと口をはなし、ようやく終わりを告げていた。
トロっと唾液の糸を引いて、二人の濡れそぼった赤い唇が引き離される。
「あぁ、彩さん……やめちゃだめぇ、もっとぉ」
だが、すっかりディープキスに魅了され蕩けている美沙は、親友の唇を追うように口をつきだし、甘く吸いついてくる。
「美沙さんったら、もうお終いよ、んっ、どうしたの?」
「え?あっ?……あっあの、その……わっわたしったら……あうぅ……あっ彩さんが悪いんです、こんなの……はっはじめてだったんですよ……だから…その……あの……あぁっ、もう」
はっと我にかえった美沙は、顔を羞恥で染めると、あうあうと声をだし小さく首をふる。
それでも上品な洋服に包まれた肢体を、彩の方に甘えるように押しつけ離れようとしないのは、すっかり出来上がってしまっているためだろうか。
「ちょっと、美沙さん、今のは美沙さんについた正樹クンの汚れを取ってあげようとしただけで……その、深い意味はないのよ?」
「はっはい!わっ、わっ、わかってます、わかってますぅ……ただほんのちょっと気持ちよくて……わたしったら……」
美沙はきまりが悪そうに顔を背けながらも、その白い指先でしっかりと彩のロングパンツの裾を掴んでいた。
「そっ、そう、ならいいんだけど……あっ!!」
「っ!!」
その時、微妙な雰囲気になりかけていた二人の美女は、そんな空気も吹き飛ばす衝撃的な光景を目にし、同時に言葉を失っていた。
彩と美沙の視線の先では……
色気たっぷりの和服人妻が、少年に背後から犯されていた。
「あんっ、んあっ、旦那様っ、旦那様っ、ええんですっ、あひっ、ああっ、当たってますぅ、奥っ、奥にっ」
「静江、静江っ、ああうぅ、気持ちいいっ、たまんないよっ」
一条静江が椅子の上に乗り上げ、背もたれに両手をつきお尻を突き出す姿勢で、顎をそらせて見栄えのよい美貌を恍惚とさせながら、甘い声をあげていた。
その淡い藍色の着物の裾は、背後から大きく捲り上げられ、丸く白いお尻が剥き出しになっている。
そして、その肉感的な美女のお尻は、背後に立つ少年の両手で抱きかかえられ、肉を打つ卑猥な音を何度も立て腰が叩きつけられていた。
腰が揺れるたびに、その結合部では、人妻の蜜にあふれた膣を、少年の肉棒がズプッズプッと激しく抜き差しを繰り返している。
「あああっ、旦那さまっ、ええですぅ、ああっ、旦那さまのがっ、あんっ、硬くてっ、あひっ、うちの中っ、あっ、あっ、あんっ」
「静江の中っ、ああっ、絡みついて、ヌメヌメでっ、あぁぁぁぁ、きっ気持ちいいよっ、ううっ、うううっ」
ずちゅっ、ずちゅっ、ずちゅっ、ずちゅっ
激しく絶えまなく響く愛液を攪拌する卑猥なリズム。
その度に、欲望で理性を失った正樹が、食いしばった歯の間から心地よさ気なうめき声をあげ、貫かれ小刻みに揺れる静江が色っぽく唇を開き嬌声をこぼす。
「すっ、すごいわね」
「はっ、はい、凄いです」
彩と美沙が、濃厚すぎるキスにお互いのめり込み周りを見失っていた間にも、少年と熟女はそれ以上の淫らな営みを繰り広げていたのだ。
生々しくそして淫蕩な光景に、彩と美沙の二人は食い入るように見入っていた。
だが、その視線に気がつく様子もなく、中学生の少年は立ちバックでむっちりとしたお尻を抱きかかえ美貌の人妻を咽び啼かせ続けている。
「あうっ、うっ、うっ、ほら、もっと、もっと、静江を気持ちよくしてあげるね、ううっ」
年上の女師匠を名前で呼び捨てにし、ズバンズバンっと腰を美女の尻肉に叩きつける。
「あひっ、ひあっあっ、旦那様のおち○ぽええですっ、よっ、よすぎておかしゅうなるぅ、なりますぅっ、あん、はあん、あんっ、あんんっ」
そんな少年を旦那様と呼び、背もたれを掴み座席に膝をついた姿勢で、着物の裾をめくって白いお尻を与える麗しい美女。
膣奥を突かれ、小刻みに揺らされる肉感的な曲線は、どんな男性でも獣欲の限りを尽くし貪りつきたくさせる艶やかなで色っぽい極上の淫靡さを立ち昇らせていた。
「あんあんっ、ええんですぅ、旦那様っ、旦那さまの、んんっ、すっ、すごいのっ、うちをえぐって、子宮までずんずんって突いてますっ、ふあぁっ、あんっ」
静江の乱れた淡い藍色の着物の襟首から覗く華奢な鎖骨。
荒く甘い吐息をもらす紅ののった真っ赤な唇。
その美貌には、ほつれた黒髪が張り付き、白い顎先から汗が垂れ落ちている。
そして、少年が背後から突き入れる度、剥き出しにされたバストが卑猥に弾み、女の脂ののった白い尻が揺れ動く。
慎ましく品のあるお茶の師範の肢体は、まさに女の色気をたっぷりと含んだ汁気に富んだ最高級の熟れた果実だった。
「あっあっ、あっあっんあっ、だっ、旦那様、静江は、静江はもうっ、あふぅ、かっ感じすぎて、んあああっっ」
世の男性を魅了するには十分すぎる美体をさらす一条静江は、舌を出し涎を垂らしながら喘ぎ声を響かせ、汗でぬれ光るその大きな白い尻肉をくねくねと妖艶にうねらせる。
そんな美女の鮮やかな模様の入った帯に締められた胎の中では、中学生の少年の勃起したペニスが、ぬめぬめと絡みつく肉襞にくるまれてズリズリと前後に動いているのだ。
「はぁはぁ……あふぅ、気持ちええですか? 旦那様、うっ、うちは正樹様の、ダンナ様の女です、んああっ、旦那様だけのこの体、どうぞたっぷり味わってくださいませ、あん」
「うん、いいよ、気持ちいいっッ、たっ、たまんないよっ、ああっ絡みついて、静江の中、最高に気持ちいいよっ、あっあっ」
まだ年端もいかない少年に大きな白い尻を与え、声をあげよがる人妻和服美女。
そしてそれを当然のように貪り、ぬめる女陰に肉棒を挿入し、激しく腰をふる中学生男子。
二人はもうお互いしか見えていないのか、この場にいる旅行の同行者、坂月彩と今野美沙を無視し、激しいセックスに溺れていた。
そんな光景を瞬きも忘れ魅入っていた彩と美沙は、やがてこの車内の個室を支配する肉欲と淫蕩な空気に操られるように、ゆっくりと動き出していた。
「ねっ、ねえ、キミ……」
彩は、生唾を飲み込むと、一条先生のお尻を抱きかかえ腰をふる正樹の隣に移動し、その結合部を覗き込みながら、掠れた声で囁く。
「ほっ……ほんとにしちゃってる……こっこれ生よね……すっ、すごいわ」
本日何度目になるのか忘れた「すごい」のセリフを口にする彩の視線の先では、一条静江のむっちりとしたお尻の間を、硬く勃起した肉棒がぬぷぬぷと気持ち良さそうに出入りを繰り返している。
そのペニスは、当然のように避妊具に包まれておらず、まさに絡みつく熟女の蜜肉を直接味わい濡れそぼった肉ヒダを掻き分けているのだ。
ここまで激しく出入りされれば気持ちいいだろうが、こんな若く元気な少年の精子を中だしされてしまったら妊娠はさけられないだろう。
「……わ、わたし、他人がするところ初めて見ました、すごいですね、こんな風になっているなんて」
目の前の様子に驚愕する彩を尻目に、美沙は意外にもあまり驚いた様子はなく、じっと観察するように、腰を動かす正樹に寄り添うように立っていた。
つい先程まで、良識と道徳観念に囚われていた筈の美沙は、彩との初めてのディープキスで何かふっきれてしまったのか、ひどく落ちついた様子だった。
もっとも、その様子とは裏腹に、その上品なつくりの細い目の奥では、欲望の灯火が満ちている。
彩は、そんな体の芯を熱にうかされている美沙をチラリと見て、きっと自分も同じような目つきになっているのだろうと思い至り、微かに笑みを浮かべると、正樹にまた視線を戻す。
「ねぇキミ、正樹クン、お姉さん聞きたい事があるんだけどいいかしら?」
だがいつも通り理性なんかあっという間にロストしている正樹は、彩の声などまったく聞こえない様子で、気持ちよさそうに美女の蜜肉に腰を打ちつけ、ぬちゅぬちゅっと膣穴を蹂躙し、極上の快楽を与えてくれる女体を貪るのに夢中の様子だった。
「ちょっと、聞いてるの?正樹クン」
「あうぅっ…はぁはぁ……いいっ…うううっ」
正樹は理性のないケダモノ状態で、ただひたすらに美女の膣肉を肉棒で突きまくり、その柔らかい肉ヒダを捏ね回す。
「あん、もうしかたない子ね、ほら、キミの大好きなお姉さんのお口をあげるからちょっとはこっちを向きなさい……んんっ」
やれやれと肩をすくめた彩は、指先で少年の顎を強引にくいっと横に向けると、何の躊躇もなく唇を重ねて自慢の長い舌を絡ませてやる。
さらにスポーツジムでシェプアップされ磨き上げられた自慢のボディを正樹に寄せ、学生の頃に有名雑誌の読者モデルとして垂涎の的となった形のいい魅惑のバストを押し当ててやる。
「あふぅっ…っ……あっ! 彩、彩お姉さんっ」
ぼんやりとした瞳にわずかながら理性、と言うよりも新しい獲物を見つけた欲望をともらせ意識を取り戻した正樹は、唇を重ねてくれる艶やかな美貌にようやく気づき、惚けた声で答えていた。
その間も正樹の腰は一条師範のむっちりとしたお尻を捏ね回すように嬲り、蜜が滴る肉厚の膣奥をズリズリと亀頭でコスリあげ、快感を貪っている。
「んっ…ちゅっ……あは、ようやくこっちを見てくれたわね、まったく……れろっ……ねぇ、いつもこんな事、一条先生にしてるの、キミは?」
彩は、ねっとりとネバつく唾液の糸を引きながら口をはすと、正樹の大きくうねる腰に手をまわし、囁きかける。
「うっうん、して…ます、いつも……こっ、この前もお茶室で我慢できなくて…あぁっ……いいよ、静江っ……あうっ……彩お姉さんも、もっと舌を」
「はいはい、しょうがない子ね、ほらベロだして……れろっ、じゅるるっ…んんっ……あん、これ以上は駄目よ、ねぇ、お茶室でどんな事してるの? お姉さんに教えて? そしたらキミのだ〜い好きなお姉さんの長いベロで、ぺろぺろ舐め合うのもっとしてあげてもいいわよ?」
彩は、正樹の蕩けた瞳でもしっかり見えるように、自慢の長い舌の先端を淫らにれろっと動かすと、欲情を誘うようにそのメリハリのきいた肢体をこすりつける。
「あひっ……うっうん、言います、言うから……おっ、お茶、お茶をたててる一条師範の後ろ姿を見て、が、我慢ができなくなって、お手前中は駄目だって言われて、だっ、だからお茶をたてて貰いながら……後ろからつながって部活の間中……ううっ……ずっと繋がってましたっ……ねぇ彩お姉さん、言ったから、ねぇ、舌ぁ」
「んふふふ、いい子ね、ほら、ご褒美、アタシの舌、好きなだけねぶりたおしていいわよ……んふうっ、んんっ、あん、そんな吸いついてっ…んっ、んんっ、ぴちゃ、くちゅっ」
彩は、唇からさしだした長い舌を少年に絡ませてやりながら、その脳裏では、少年が語った茶室での情事の様子を思い描いていた。
狭い茶室の中、優美な着物姿でお茶をたてる楚々とした一条師範。
その背後から、欲望に燃える小柄な男の子が抱きつくと、女師範の着物の衿の合わせから手をいれ、肉感的な女師範の胸を揉みしだき、うなじに舌を這わせだす。
さらには抵抗する女師範を正座の姿勢のまま尻だけあげさせると、まるで性欲を処理するためだけのように、着物の裾を捲り上げ、容赦なく肉棒を突きいれる。
狭い茶室の中、胡坐をかくように畳の上に座る少年、その膝の上で、胸を揉まれ背面座位で貫かれ咽び乱れる着物姿の美人師範。
それでも、きっと一条先生は快楽に震える唇を噛み締め、肉棒で身体を揺すられる度にお茶をこぼしながらも、お作法を続けていたに違いない。
――なんて、羨ましいの、一条先生ったら夫がいる身で、こんな可愛い正樹クンとそんな事、あぁ、アタシだって、アタシだって……本当は……正樹クンに……
正樹に抱かれる一条師範への羨望を抑えきれない事を誤魔化すかのように、少年へのご褒美のキスに没頭する彩。
そして、そんな嫉妬と羨望に焦がれる彩の反対側から、そっと身を乗り出してくるすっかり雰囲気に呑まれている美沙の姿があった。
「ねぇ、彩さん、二人だけでキスして………ずるいです」
おっとりとした清楚な美貌は、羞恥と愛欲が交じり合い桜色に染まっていた。
美沙は柔和な笑顔のまま、瞳をとろんと蕩けさせ、正樹の頬に端正な美貌をすり寄せると、絡み合う舌を羨ましそうに凝視している。
「羨ましいです、そんなに舌を動かして……はぅ……もう、正樹くん、あんまりわたし達を誘惑しないでくださいね、わたし達は人妻なんですから……でも、キスぐらいなら、アノ人も許してくれますよね……正樹くんがそんなにエッチなのがいけないんです、そうです、そうに決まっています」
美沙は、一人で勝手な言い訳を誰にともなく言うと、驚いた事にあれだけ貞操観念の高かった筈が、気恥ずかしそうにしながらも、そっとそのピンク色の口を寄せていく。
「そうです、これくらいなら彩さんもしてますから……その…大丈夫ですよね……一条先生はやりすぎですけど」
ちらっと視線を送った先には、肉棒をズンズンッとハメられ、シートの背もたれに顔を埋めて喘ぎ声をあげる静江の後ろ姿。
「少しだけ、少しだけですから……もう一度、あのキスがしてみたいだけなの」
美沙はそう自分に呟きかけながら、口を寄せ合いくちゅくちゅと舌を絡ませ合う彩と正樹の間に、一大決心の元、舌をそっと差し入れていた。
「んふぅ……あふぅ、すごいです……あんっ、この舌が絡まるの……すごいわぁ……あふぅ、ごめんなさいアナタ……でもキスだけだですから……んんっ」
差し出された美沙の舌は、すぐさま正樹と彩の絡み合う舌の睦みあいに迎え入れられ、交じり合っていく。
それぞれの口から突き出され、見せつける様に顔の前でねっとりと絡み合う、少年と美女二人の蠢く舌。
「んっ、ちゅっ、んんっ……あら、美沙さんったら……そんなにベロでくちゅくちゅするの気に入ったの? いけない奥さんね……ふふふ」
正樹の舌を舐める彩は、片目をつぶって色っぽく微笑みながら、美沙をからかう。
「あんっ…っ…あふぅ……あっ彩さんのせいですよ、こんなキスがあるなんて教えるから……せっ責任とってくださいね……れろっ」
優しそうな瞳をスケベに細めて、恍惚とした表情でそう答える美沙。
「あぁ、みっ、美沙お姉さんまでっ…あっ…ちゅっ…レロレロっ…あぁ、いいですぅ」
うっとりとする正樹の目の前で、二人の端正な美貌の女性が顔を寄せ合い、はぁはぁっと甘い吐息を弾ませながら、舌を突き出し絡ませてくる。
もうおかしくならない方がどうかしていると言うものだろう。
お茶の先生、一条静江の極上の蜜肉に肉棒を包まれその心地よさにビクビクと震える少年は、二人の若妻、彩と美沙によって捕らえられ、甘露のような若妻達の蜜まみれとなっていた。
彩の長い舌が正樹の舌の上表面をザラザラと大胆に擦りまわり、下側からは美沙のたっぷりと涎をひいた舌が控えめに舐めあげてくる。
「れろっ…んふっ、よかったわね、キミ……ちゅっ、じゅるっ、こんな美人と同時にキスできるなんて……んんっ、くちゅっ……感謝して味わうのよ、んっ」
興奮した彩は舌をくねらしながら、小刻みに震える正樹の首にしっかりと腕を絡めると、さらに愛情を込めて深く濃厚に絡めだす。
「んっ…じゅるっ……あぁ、彩さんの舌も、正樹くんのも……もうヨダレでぐちゃぐちゃですよ…んっ…あふぅ、この絡み合う感じが…ああっ、素敵です…んんっ」
頬をほんのり染めた美沙は、もつれ合う舌の感触をたっぷり堪能するように、清楚な美貌をつきだし、覚えたばかりのディープキスに溺れている。
夫にもした事のない舌同士を吸いあうキスに、美沙はもう夢中だった。
正樹の舌を舐めあげ、彩と一緒に垂れる唾液を啜るたび、美沙の細くしなやかな背筋は震え、彼女を官能の高みに何度も押し上げ、それがさらにキスに深く没頭させていく。
「あふぅ…じゅるっ……ところで質問が途中だったわよね正樹クン、ねえ、キミってば何時も、こんな風に一条先生にいれちゃってるの?……そのゴムもなしで、直接?」
彩は、器用に舌先を尖らせて正樹の舌腹をくすぐってやりながら、色気を帯びた目を細め、質問を再開する。
「あうっ…うっうん、いつも、いつもしてますぅ……れろっ、んぐっ……ああっ静江の中、ぎゅうぎゅうして暖かくてっ、お姉さん達の舌も…ああっ美味しいです…んっ」
正樹はもう自分が何を言っているのかわかっていないのだろう。
ただひたすらに己の肉棒で静江の気持ちの良すぎる膣穴をずちゅずちゅ突きながら、舌を蠢かせ美女達の蜜味を貪り続けている。
「れろっ…まぁ、いつもですか? んっんっ、れろっ……んちゅっ、あふぅ……そう言えば、先程も一条先生はもっとたくさんの女の人とも、んっ、こんな事しているって言ってましたよね? ホントですか? 正樹くん?」
彩にかわって今度は美沙が、欲情に堕ちた細い目で正樹を見つめながら、桜色の唇でちゅっと少年の舌を吸いながら聞いてくる。
「はっはひぃ、たくさんしてますぅ……冴子さんや、マイカさんや、レンさんとも…れろっ、んんっ…あぁ学校の先生達ともっ…ああっ、みんなこうやってさせてくれて……いっ、いつもしてますぅっっ」
後背位で妙齢の和服美女にペニスを突き入れる幸福感に浸りながら、両脇に寄り添う二人の若妻達と同時にキスを交える、汗とヨダレまみれの少年。
その口から、何人もの女性を隷属させ、セックスをしていると言う事実がこぼれだす。
「ほっ本当ですか?そんに沢山の人と…そんな事…ある筈ないですよね……もう、正樹くん嘘はめっですよ、ちゅっ」
美沙は、貞淑だった一条先生の変わり様を思い出しながらも、少年の熱に浮かれたセリフだと首をふって否定すると、すっかりハマってしまったディープキスに再度没頭する。
だが一方、彩の思いは親友の美沙とは多少異なっていた。
――そうよ、ありえないわ……でも、こんな子供がそんな沢山の女性と……よしんば、それが本当なら、アタシにだって、アタシにだってこれ以上の過ちが起きたっておかしくないわよね。
心の底に隠されていた嗜好を認識してしまった彩にとっては、それはある意味、今でも残るモラルの最後の欠片すら無くす事ができる、まさに不義を許す免罪符。
そう、先進気鋭の経営者にして若く美しい人妻の坂月彩は、もう正樹とのディープキスだけでは満足できないでいたのだ。
それでも激しいアパレル業界を生き抜いてきた大人の女の最後の矜持がそうさせるのか、彩は慌てた口調で美沙に同調する。
「そっ、そうよ、そんなバカな事あるわけないわ……そっ、それにしても、キミってば、なんて子なの……ちゅっ、れろっ……大人の女を何だと思っているのかしら? ……とんでもない中学生ね、キミは……ねぇ、お姉さんもそんな風にしちゃう気じゃないでしょうね、許さないわよ」
シートに上半身をしがみつかせ甘く喘ぐ一条師範の声を聞きながら、彩は心に生じた誘惑を冗談交じりの言葉で必死にかき消そうとする。
「あっ彩お姉さんにも……しっしたいですぅ、あ、うぅっ」
だが、そんな彩の冗談のつもりのセリフに、女師範を背後から犯す正樹は、欲望そのままの何にも考えていない素直な返事をしてきていた。
「なっ!!」
彩は、正樹のあまりの言葉に猫のような目を見開き、思わず絶句してしまう。
「ばっ……ばっ、馬鹿を言いなさい……こっ子供のくせに! それにアタシは結婚してダンナもいるの……それをこんな子供にハメまわされるなんて……っっ」
彩は、瞬間的に耳まで真っ赤になると、うろたえまくり視線をあらぬ方向に迷わせだす。
その艶っぽい美貌は、すっかり羞恥に染まり、その奥では……
まんざらでもない、隠しきれない笑みが浮かんでいた。
「そっ、そうですよ、もう、正樹くんったら、お姉さん達を惑わしちゃ駄目って言いましたよね? 彩さんはもう結婚してるんです、他人の奥さんなですよ、そんな事を言われたら……はぅ……ほっ、ほら、今だけ特別にキスまでしてあげますから、んんっ」
美沙は、動揺する割に明確な否定のセリフを言わない彩の様子に戸惑いながら、正樹の興味を別に向けようと、体をすりよせ舌を絡ませる。
だが、すっかり肉欲に目がくらんだ少年は、今度はそんな美沙をみつめ、恍惚とした表情で、またしても素直な欲求を口にしていた。
「僕、美沙お姉さんともしたいですっ、美沙お姉さんのお腹の中に出したいですぅ」
「わっ、わたしとも!!……なっ中にって……ちょっ……だっ、駄目、駄目です、そっ、そそ、そんな事……でっ、できないです、絶対……絶対ダメですぅ」
彩と同様に、羞恥に染まりうろたえる美沙。
そんな美沙の様子をみた彩が、正樹の首をぐいっと抱きしめる。
「コラっ、アタシだけならまだしも、美沙さんにまでなんて……キミはなんて節操のない子なの……正樹クンみたいな子供がアタシを欲しがるなんて十年早いわよ……ほらっ分かったらキスで我慢するの、いいわね、ベロもっと動かしなさい、んんっ」
彩は早口でそう言うと、何かをごまかすように今まで以上に積極的に正樹にメリハリの効いた肢体を寄せ、正樹の言葉を封じ込めるように、にちゅにちゅっと唾液の音をさせて激しく舌をもつれ合わさせる。
「あっ…彩さん……ずるいです、独り占めは」
正樹の素直すぎる返事に動揺していた美沙も、あわてて清楚な美貌をよせ、正樹と彩の舌に自分のソレを重ねると、三人での淫らなキスが再開される。
正樹と舌をからませ丹念に嘗め回し、啜り上げる二人の美人若妻。
その内心では、今まで以上に少年への欲求が沸々と湧き上がり、ディープキスをさらに淫らなモノにしていた。
――まったくもう、なんて事いうのよ、この子は……アタシとしたいだなんて……ああっもう……可愛すぎよ、この子ったら……んんっ、もう舌が蕩けるまで舐めまわしてあげるんだから!
彩の舌は過激に、そしより扇情的に少年を愛撫し、弄りつくす。
すっかり自らの性癖を自覚してしまった年上の美女は、もう止まりそうになかった。
――正樹くんったら、わたしともしたいだなんて……それも中に、お腹の中に出したいって……あぁん、どうしたらいいのかしら……お姉さんだからリードしてあげないといけなけど、でもわたし経験ほとんどありませんし、困りました……って違います!違いますよ、わたし! 夫がいる身でなんて事を……そうです、キスだけ、キスだけです、これ以上は絶対だめです!
一方の美沙の方は何とか最後の理性を取り戻し、状況に流されるのに抑えを効かせようとしていた。
だが、困惑しながらもそれでも初めて知ったディープキスという禁断の蜜を味わうことだけはやめられない。
そんな二人の間で抱きしめられた正樹が、あううっと快感の声をあげ、さらに腰の動きをはやめると、後背位で貫く和服美女への責めを強めていく。
「それにしても、こんな子供のくせに、あの身持ちの固い一条先生をここまで虜にするだなんて……それにアタシまで……普通ならこんな事信じられるわけないわ……信じられない、どうやってこんな…」
ディープキスだけで満足してしまっている美沙と異なり、さらに少年を求める衝動に駆られる彩は、滴る唾液を当然のように正樹の唇から舐めとりながら心の葛藤をそのままに口に出す。
無論、誰かの返事など求めてはいない、夫のいる身ながら少年と関係を持つ一条静江への羨望が彩に独り言を言わせていたのだ。
「そうよ、非常識よ、こんな子供と不倫だなんてそんな事、普通なら……普通なら到底無理よ、なにか普通じゃない事が起きないと……そうね、普通じゃない事が起きてくれれば……アタシだって正樹クンと……」
そう呟いた時、彩は心の奥ではある一つの事柄に思い至っていた。
彩の脳裏に浮かぶ、静江の言っていたあの話――
『旦那様が言うには、不思議な力があるそうですわ、なんでも大人の女性を魅了する力が……』
そう大勢の女性が虜となったのは、正樹の大人の女を狂わせる不思議な力が原因となっているというアノ到底信じられない話を。
シートの背もたれに顔を埋め、もう言葉もなく咽び泣きよがり狂っている一条師範が話したあの荒唐無稽な正樹の力。
そう嘘か本当かわからないが、力はあるのだ。
正樹クンがそう言ってるのだから。
不思議な力を持っている本人が……
「あは、そうか、そう言うことね、んふふふ」
年上の女性を虜にする力、その意味するところを、抜群の経営センスをもつ坂月彩の明晰な頭脳は、解き明かしていく。
そうなのだ、力が本当にあるのか、ないのかは今の彩には関係ない。
そしてそれは一条先生も、話の中ででてきた本当だとすれば、少年の叔母や、女教師達も関係ない事だったのだろう。
そう、ただ目の前の少年は自分にそんな不可思議で都合のいい力があると信じているのだ。
それが一番重要なトコロ。
力の有無や、真実は重要でない。
少年がそう信じている……それが重要なのだ!
そう例えそんな力がなくてもそのせいにすれば……
きっと一条師範も同じように考えたにちがいない。
なら自分もその前例にならってそうしてあげればいいだけ。
そして正樹クンが、目の前の可愛い少年がそう言い張る力を使ってしまったと思い込む方法、そう彩に最後の一押しを与えてくれる禁断のスイッチは……
抜群の記憶力を誇る坂月彩は、なんなくそれを思い出していた。
静江が、着物中でその豊満な胸を少年の手でまさぐられながら、さりげなく囁いた言葉を。
『そうそう、旦那さまが腕につけてはる腕輪、あれがあるとその力はあまり働かんそうですから、くれぐれも腕輪を取ってはいけませんよ』
「なるほど、腕輪……ね」
全てを確信した彩は、猫のような目をニンマリと細めると、何か悪巧みを思いついた子悪魔のように微笑む。
そして正樹の背後に回していた手を、そっと動かしていくのだった。
誰にも気づかれないように……
もっとも、明晰な頭脳は残念ながら、常に理性ある判断を下すとは限らない。
特に色恋に染まった場合には……
ちょうど、その時。
「もうもうっ、あああっぁっ、僕、いっいきますぅ、いくぅっ」
美沙と接吻を交えていた正樹が、唾液の橋をひきながら口をはなすと、背筋をそらせ辛抱の限界を伝える声をはりあげる。
官能で震える手が静江の白いお尻を掴みあげ、こねくるような動きだった腰が、激しいリズムで階段をかけあがるように速まっていく。
「ああっ、んんーーっ、んんっぁぁん、旦那様ぁ」
そして、後ろから子宮を突き上げられていた麗しい和服美女も、その激しいリズムに合わせいっそう嬌声を大きくし、背筋をそらせビクビクと官能の波に乗り上げだしていた。
「まぁ、出すのね、キミ、ホントに、出しちゃうのね……一条先生の中に、あの濃いザーメン出しちゃう気なのね」
別の事に意識を向けていた彩が、すっと目を細め紅潮した美貌で期待に満ちた声をだす。
ルージュの乱れた唇をはぁはぁっと弾ませゾクゾクとした興奮に包まれながら、彩は人妻に膣内射精をしようとする少年の顔を覗き込み、背後に回した手をモゾモゾと動かしながら、何度も確かめる。
「ほら、お姉さんに教えて、出すんでしょ? 出しちゃうのよね?」
「うんっ、うんっ、もう出るぅ、静江の中に、静江の膣内に僕のセーエキっ」
ずちゅ、ずちゅ、ずちゅ、ずちゅ、ずちゅっっ
淫らな音を立てて小刻みに動く腰は止まらない。
淫液を滴らせながら、正樹のペニスがさらに激しく静江の膣奥を突き上げ、暴発寸前の亀頭をぐりぐりと子宮口にこすりあてる。
「あひっ、んーーーあぁっっ、旦那様っ、奥ぅゴリゴリって、あひっ、いいっ、静江もいくっ、いきますぅっ、中に中にくださいませ、旦那さまの子種注いでくださいませっ」
少年の欲望を受け止めるべく、美貌の和服人妻は黒髪を乱し、艶やかな白い尻をふるわせ、肉棒を咥えこんだ膣肉を献身的に引き絞る。
ネットリ絡む膣内を、ずちゅずちゅっと激しく最後のスパートをかけて肉棒が攪拌する。
「ああぁぁっ、でっでるぅぅぅぅ、もうもう、ああううううっ」
正樹は、ぎゅっと眉を寄せて叫びながら、静江の大きなお尻を抱え込むようにして腰を密着させると、ビクビクっと激しく痙攣し膣内射精を開始していた。
「あっ、あっ、あっ、あっ、ああっ、あああぁぁぁ」
心底気持ち良さそうに顔を蕩けさせながら、遠慮なく美人熟女の膣内に子種たっぷりの迸りを注ぎ込む中学生。
「ひあっ……あっ、あぁっ、だっ旦那さまがっ、ひあっ、あっ、でっでてますぅ、静江のおくにぃ、おくにぃ、せーえきっ届いてるぅ」
腰をぴったり押しつけたままビクビクと小刻みに震える度、和服美女の子宮口に押しあてられた亀頭の先端から、ぶびゅっ、どびゅっ、と溢れかえるほど大量の白濁液が吹き上がり、子袋の奥へトプトプと流し込まれていく。
「んんんっ、きょ今日も、たったくさん、あひっ…すごい量が…んっ……おっお腹の奥に注ぎ込まれて……あふぅ、ああっ、旦那様のモノになってます、うちの体全部、ダンナ様の、正樹様のモノです…あぁっ」
朱色の艶かしい唇を戦慄かせながらシートに突っ伏し少年のスペルマを子宮で受け止め続ける麗しく淫らなお茶の女師範。
例えようもない官能で開ききったその艶やかな肢体は、人妻でありながら、完全に少年の所有物に成り果てていた。
「すごいわね、溢れかえるぐらい出して……ほんとに直で膣内射精しちゃってるわ、この子……大人の女の中に避妊もしないで生でだしてちゃってるのね」
彩はゴクリと生唾を飲み込みながら、汗と淫液で淫らに濡れ光る一条先生の丸いお尻をそっと撫でる。
しっとりと手に馴染むその臀部の奥では、肉壺の中に少年のペニスがくるまれているのだ。
そして、その硬く脈動する先端からは、あの濃厚な精液が止め処なく噴き出て、なんの障害もなく他人の妻の子宮中に子種を注ぎ、たっぷりと溜まっているのは間違いない。
その様子を想像する彩の瞳には、正樹と交わることへの羨望の光が、はっきりと宿っていた。
「ううっ、うっ、うっ、静江っ、いいよっ、ああっ、まだ出るっ、出ますぅ」
若さだろうか、それとも大人のオンナそれもすこぶるつきの美女を征服したい執着心と独占欲からか、正樹はまだまだ精液を打ち止める気はないらしい。
シートに突っ伏す静江の尻を抱え上げると、逆流してくる精子を押し込むように肉棒を膣奥におしつけ、白濁液をどぴゅっどぴゅっどぴゅっっと心底気持ち良さそうに送り込んでいる。
「ホント気持ちよさそうですね、正樹くんも先生も……一条先生ったら白目を剥いて……正樹くんもドーブツみたいに腰を押し込んで、ほんとに全部一滴残らず一条先生のお腹の中に注いじゃう気なんですね、あの濃くてトロトロの白いのを………」
美沙は、何処かうっとりと見惚れているようにもとれる恍惚とした表情で、少年に篭絡され全てを捧げたお茶の女師範の様子を、知らずに口にだして実況している。
「ううぅぅっ……ふぅぅっ」
彩と美沙が見つめる中、正樹は腰をぴったりと押しつけたまま、尿道に残った最後のほとばしりまで極上の蜜壺の中に排出し終えると、ゆっくりと静江の背中の上にもたれかかっていく。
「はふぅぅっ、とっても気持ちよかったよ、静江」
「……んんぅ……旦那様……うちもです……ほんに……ありがとう…ございますぅ」
快感で半ば虚ろとなっている一条師範は、正樹の声に応えながら艶っぽい美貌をほころばせ、首をゆっくりとひねり背後を向くと、大事な旦那様の口に自分のソレを重ね、舌を絡める。
舌をゆるやかに絡ませ合う、端正な美貌の和服人妻とまだ幼い少年。
その色っぽい美女の子宮の中には、一回り以上年下の少年の元気な精子がうようよと泳ぐ白濁液がたっぷり注がれ、ドロっと溜まっていた。
そしてそんな愛情一杯な後戯に耽る人妻と少年の睦み合いに当てられた美沙が、ふと視線をそらし足元に向ける。
そこには、正樹の腕輪がポツンと転がっていた。
「あっ、これってもしかして例の腕輪じゃ……」
美沙は訝しげに愁眉をよせる。
美沙の様子に気がついた彩が、紅いルージュの乱れた唇に蠱惑的な笑みを浮かべると大根役者のような棒読み口調で話し出す。
「あらあら、正樹クンったら大切な物を不注意で落とすなんて、激しく動いたみたいだからはずれたのかしら?でもこれがはずれちゃったら、どうなるか知ってる筈なのに、ねぇ、自己責任って言葉は大切だと思わない? 美沙さん」
やや大げさなゼスチャーも交えてそう言いうと、彩は腕輪を拾い上げる。
「そんな大げさですよ、だいたいあんな話デタラメです…………って、彩さん、まさか!」
おっとりしているからと言って決して頭の回転が遅いわけでない美沙は、彩との長い付き合いから彼女の行動とその微笑みから、彩の言いたいことの真の意味を悟る。
「ふふん♪ ちゃんと嵌めておかない方が悪いのよ、あら、正樹クンは静江さんの胸にもたれてお休みみたいね、んー、そうね、それじゃこの腕輪は正樹クンのカバンの中にしまっておくとしましょう」
美沙の非難を込めた視線を彩はまったく余裕の微笑みで受け流し、正樹の大きなバッグの中に腕輪をしまってしまう。
それもなかなか取り出せそうにないカバンの一番奥の方に。
「彩さんったら本気ですか? わたしも……その、勢いでキスをしてしまった手前強くは言えませんけど……正樹くんはまだ子供ですよ……それに……」
自分も負い目がある美沙は、非難しているのか羨んでいるか判りづらい表情で彩を見つめる。
「だから、それは全部不思議な力のせいなわけよ、仕方ないわ、魅了の力だっけ?アレのせいよ……あ、そうすると美沙さんもやられちゃう事になるわけよね、正樹クンのその力に」
「そっ、そっ、そんなわけないです、絶対……いえ、多分」
歯切れの悪い美沙のセリフに、彩はクスクスと笑い続けていた。
実のところ、そんな二人の背後で、一部始終を見届けていたモノがある事を、車内にいる誰もが気づいていなかった。
それは、ツインシートの上、録画中を示す赤いLEDを瞬かせる放置されたハンディカムだった。
列車の中でずっと録画状態となっていたその機材は、長時間録画用のメディア中に事の一部始終を収めていたのだ。
交わりあう静江と正樹の後ろ姿、その正樹に左右から寄り添う彩と美沙。
そして、背後に回されていた坂月彩の怪しく動く手先。
正樹の腰が震え、まさに今、膣内射精をしようとする無防備な瞬間、彩の手がすばやく動くと、正樹の腕から腕輪をはずし、床にまるで偶然はずれたかのように転がす所まで――克明に記録されていた。
そんな事を知る由もない正樹は、静江の柔らかな白い女体に抱かれたまま、すやすやと心地良さそうに寝息を立て始めていたのだった。
誤字脱字指摘
2007/9/8 ふりゅ様 9/11あき様
ありがとうございました。
2007/9/8 ふりゅ様 9/11あき様
ありがとうございました。