
残念ながら、平日に行われたため見学できませんでした。後で聞いたところによると、雨天の中、かなり大がかりな作業となったようです。
基礎工事前に土地の神様をお迎えし、工事の安全を祈ります。本来は神主さんを招いてとり行うのですが、わが家では簡略化して棟梁にお願いしました。最初に、祭場の前で2礼、2拍、1礼。次に、土地の4角に鬼門(北東)から時計回りに、米、塩、酒をかけて回ります。残ったものは中央の盛りつけした部分にかけて清めました。そして、安全を祈願して酒で乾杯。約20分の簡単な儀式でした。
|
|
土地の中央に、葉のついた青竹と注連縄(しめなわ)で斎場をつくります。白いのは幣足(へいそく)というそうです。用意したものは、酒、米、塩、水、海の幸、山の幸。 |
|
|
|
|
|
|
|
そして、次の日にはもうほとんど完成していました。 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 大型のクレーンを使って荷下ろしです
大型のクレーンを使って荷下ろしです

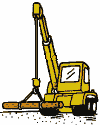
|
|
|
|
|
|
|
|
よく見ると、木口(こぐち)に番号が書いてあります。これは、工場で一度仮組みしたときに書かれたもので組み上げる位置を表します(上)。床材も無事に到着しました(左)。 |
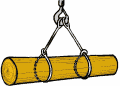 クレーンのフック(先端)
クレーンのフック(先端)
|
|
|