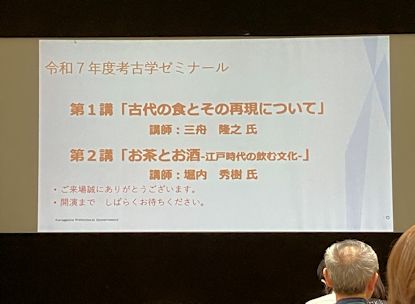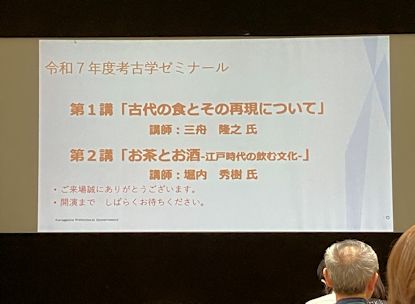神奈川県埋蔵文化財センター主催の「考古学で探る いにしえの食卓」の 第1講と第2講を聴講しました。
第1講「古代の食とその再現」の主な内容は、
①古代食研究は、考古学からは、食べ物たものそのものは残らないので、土器の形状や残渣のおこげなどから調べる。
②文献史学からは、食材や調理器具や食器はわかっても、実際にどう調理したかはほとんどわからない。
③そこで古代の食を再現する試みを行う。
・米をどう炊飯するか?
弥生時代の炊飯法は湯取り法では?
古墳時代は米蒸し法ではないか?
その後炊き干し法ではないか?
④古代の発酵食品の再現
・醤
・古代の水産加工品「荒堅魚」「煮堅魚」「堅魚煎汁」
⑤古代食の階層性(貴族、官人、庶民」の再現例は本当か?
などが説明されました。
第二講「お茶とお酒ー江戸時代の飲む文化ー」では、
①お茶の飲み方(団茶、甜茶(抹茶)、煎茶、など)の推移
②その時々に用いられた茶道具類の例(尾張藩邸への御成など)、
③絵画資料にもとづく道具の変化
・例えば土瓶は18世紀中葉から
・急須は19世紀中葉から
④文人趣味と称される中国趣味の流行にともなう器種・装飾の変化など
⑤お酒については
・宴会の例
大名の宴会
家臣の宴会
私的の宴会
などについて、実際の発掘例や絵画例などを用いて説明がありました。