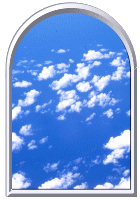
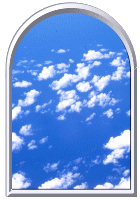
「うっ…ん……」 軽い吐息を吐き出して、新一は気怠い躯の態勢を入れ替えようと身動いだ。けれど態勢は入れ替わる事はなく、半瞬後、自分が長い腕に抱き締められていると、朧な意識で理解する。 ツッと、指先に当たる慣れた感触に、瀟洒な指が感触を確かめるように滑って行く。暖かい感触に、新一の意識は知らず覚醒を促されて行く。 「ん〜〜?」 ケットに深く潜り込み、尚且つ恋人の腕に包まれている新一は、半覚醒の意識の中、無自覚に恋人の腕の中で瞬きを繰り返す。繰り返せば、眼前には見慣れた褐色の胸元が在るのが判る。 褐色の肌に触れる指先を視界に映せば、一回りは大きい袖口が映る。濃紺のパジャマは、服部のものだ。 今日が日曜とあって、昨夜は早々にベッドに潜り込み、情交に及んでいた。一体何時寝たのかの意識も朧だけれど、身綺麗なシーツにパジャマを羽織っていると言う事は、相変わらず自分を抱き締め眠る事に躊躇いを見せない褐色の肌の恋人が、綺麗にしてくれたのだろう。そう思えば、羞恥が湧かずにはいられない。 昨夜、激情のままに抱き合った狂態を思い出せば、白皙の面が紅潮して行くのが判る。激情に任せた情交に失神した自分を、服部が綺麗にしてくれたのだろう。そんな事に、一体何時から慣れてしまったのか?慣らされたのか?今はもう思い出せない。 元々神経質で、他人との接触が苦手な自分が、こうして誰かと温もりを分けあえるとは思わなかった。まして相手は同性だ。分けあえるとしたら、それは大切な幼馴染みの蘭だと思っていた。それなのに、現実はこうして同性の腕に抱かれ、触れる温もりに安堵を覚えてしまっている自分が在る。時折その事が不思議でならない。 「お前さ、俺でいいわけ?」 本当に? 不意にそんな言葉が口を付く。服部に聴かれれば、盛大に小言を言われる事は判りきっているし、傷つける言葉だとも判っている。だからこうして寝顔を見詰め、問い掛ける事しか出来ない。訊けば小言の後に、言われる台詞も判りきっていた。 ソロリと躯を半分起こし、未だ眠りの淵に在る恋人を真上から覗き込み、囁き掛ける。穏やかな寝顔に、知らず無自覚に笑みが漏れる。 こんな穏やかな気配が愛しいと、服部と出会う事がなければ、きっと知らずに過ごしてきたのだろう。そうして少しだけ胸が痛んだ。 自分を愛する事で、一体どれだけの疵を背負わせてしまっているのか?人の事は疵も自覚できない子供だと言う服部は、けれど自分の疵を自覚できていないと新一は思う。 自分を愛する事で、服部が胸を痛め、より大人であろうと課している事を、気付かない新一ではなかったから、自分を愛して服部が苦悩を深めてしまった事実に、胸が痛んだ。 「諦めないけど…判んねぇぞ…」 母親譲りの細面の貌に、苦笑とも自嘲とも付かぬ笑みを刻み付ける。 諦めるつもりなど毛頭ない。けれどそれは、最初から分の悪い賭のように思えるのに、絶望を通りこした場所には、諦めの文字は欠片も見当たらない。それが新一の真骨頂であり、本質的な靭さなのだろう。 自分の躯は、生体機能が狂っている。隠していたその事実が露呈して、服部はより深く抱えてしまった筈だ。以来、より優しくなった服部だったから、同年代の恋人が、どれ程のものを背負ってしまったのか、判らない新一ではない。だから胸を痛めても、それでもこの穏やかな感触を、もう手放せない自覚はあった。自分は案外独占欲が旺盛だったのだと、思い知るのはこんな時だ。 「物好きな奴」 クスリと、ひどく優しい笑みを覗かせ、服部の面差しを凝視する。褐色の肌に、荒削りではあるけれど、スッキリとした鼻梁や柳眉、近頃益々鋭角になった輪郭が、その端整さを物語っている。時折グレーの陰影を描く様すら、完成された大人の男を連想させる時があって、新一は無自覚にドキリとなるのだ。 何も自分ではなくても、相手に不自由してはこなかっただろう服部の女性関係を、新一は知っている。街に出れば、年上の女性から声が掛かる服部なのだ。自分に出会う事などなければ、そうやって女性を愛し、普通の恋愛をしていただろう。何を好き好んでと思えば、より切なさが湧く。いつからこんな風に想いを深めてしまったのか?考えても、もう判らなかった。 暫く穏やかに眠る服部の寝顔を見詰め、新一は思い付いたように、ベッドサイドに置かれた時計に視線を移す。時間は5時半近くを指している。 昨夜散々に睦んだ時間は判らない。激しく求め、番い、極めては目蕩み、そんな時間を繰り返していた。その事を考えれば、自分では驚く程、睡眠時間は少なかった。まして休日前夜に求めあった翌朝は、大抵起床は昼近くだったから、新一はらしくない自力覚醒に、少しだけ驚いていた。 睡眠自覚は短い筈なのに、妙な程頭の芯が冴えている気がした。暖かい恋人の腕の中に戻る事は、ひどく優しい眠りをくれるだろう。けれど眠る気分ではなかったから、少しだけ考えて、新一はソロリと身を起こす。 フローリングの床の感触が、少しだけ冷たい。そう思えた。夏はその感触が心地好かったのだから、確実に季節が移っている事を物語っているのだろう。 雨戸のない洋館作りの出窓には、母親の少女趣味を発揮したレースのカーテンの上に、遮光カーテンが引かれている。 息子の部屋を、少女趣味に飾り立てるのは勘弁してくれと、何度となくレースのカーテンをはずしてはみたものの、帰国の都度、諦め悪く再びカーテンを付けてしまう母親に、結局新一が勝てる筈はない。 未だ世界の恋人と言われてしまっている母の有希子は、その少女めいた容貌に似合わず、父の優作や自分を驚かせる破天荒な才能にも恵まれていたから、新一の部屋の窓は、レースのカーテンが引かれたままになっている。所詮子供は母親には勝てない。そう実感した新一なのだ。 新一は、ソッとカーテンの端を捲ると、外は白々夜が開け始めていた。 秋の夜長と言う程、秋は夜の時間が長くなる。実際刻まれる時間は何一つ変わりない普遍性だと言うのに公転の関係で、これからの季節は夜が長い。外は漸く夜が開け始め、秋の高く蒼い空が、垣間見えた。つい最近までは、4時を少し回った時刻で、白々としていた筈なのにと、新一は移り行く季節を思った。 こんな空を、風景を、以前視た。思い出せば、懐かしい記憶に、新一はクローゼットから着替えを取り出し、足音を忍ばせ室内を出て行った。 その場所は、家から歩いて20分程度の距離に在る、米花一ツ橋公園だった。休日の昼間ともなれば、家族連れで賑わう公園は、東屋や、ボートも漕げる池が在り、春から夏に掛けては緑が豊富な都内でも有数の公園だった。けれど今は休日の早朝とあって、人はまばらで、早朝ジョギングや散歩を楽しむ人間が、数人在るだけだった。 散歩コースになっている補正されたアスファルトのサイドには、ピクニックに訪れる人間が寛げるように、芝生が整備されている。その芝生の上に、新一はゴロリと寝転んでいる。 早朝の空気を肺一杯に吸い込んむと、清涼な空気が心地好く流れ込んでくる。身の裡から、清浄される感触がある。それがひどく心地好い。こんな朝の清涼な気配に満たされた気配を、今まで忘れていたと思い出す。元々朝は苦手で、学校も事件もなければ、前日はほぼ徹夜状態で、翌朝は昼過ぎ起床というのが常だった。 寝転んだ視界一杯に広がる高く澄んだ秋の蒼穹。両手を思い切り天に伸ばす。 真夏のような熱に射られるような鋭さも、身を灼く暑さもない日差しは、確かに季節が映っている事を新一に伝えていた。薄い木漏れ日が、伸ばした掌中の隙間から零れてくる。 「コラ、工藤、何してんねん」 突然、頭上から振ってきた声に、新一はさして驚いた様子も見せず、視線だけを動かした。 其処には、つい先刻まで、穏やかに眠りを貪っていた服部が佇み、腰に両手を当て、屈み込んで自分を覗き込んでいる。 「良く此処だって判ったな」 「散歩行くって、リビングのテーブルに置き手紙あったやん」 新一の台詞に、判って当然だと、服部は新一の隣に腰を下ろした。 「心配するやろ。どないしてん?」 新一は、朝に弱い。大抵情事で無理をさせてしまえば、起こすまで起きない。その新一が、気付けば腕から在なくなっていたのだから、心配するなと言う方が服部には無理な事だった。 服部が新一の不在に気付いたのは、新一が家を出てから、さして経ってはいない。失せた温もりに覚醒を促され、何処に在るのかと気配を探っても慣れた気配は感じられずリビングに降りて、新一の置き手紙を見つけた。 ただ一言、『散歩に行く』と、見慣れた文字が書かれていた。 淡如に書かれた置き手紙に、新一が行くだろう散歩コースに予測を付け、訪れた服部だった。 「別に、眼が醒めちまって、なんか頭の芯冴えちまってたから」 「そんで散歩かい、今度からは、ちゃんと起こしてや」 「近所散歩するくらいでいちいち起こすか。お前さぁ、過保護すぎだよ。俺はもうコナンじゃねぇんだからな」 それはもう何度となく言い募り、結局馬耳東風のように、服部には何一つの効力のない台詞となっている。 「そんでも心配なんやから、仕方ないやろ」 幅広い肩を竦め、苦笑する。その苦笑が、完成された大人さながらで、新一の胸を騒がせる事を、けれど服部は知らない。 仕方のない事。それは服部には切実だった。 工藤新一と言う人間は、他人の疵や痛みには敏感なくせに、自分の痛みには気付かない、子供のような面がある。そうして必要だと判断した時は躊躇いもなく、自らを切り捨ててしまう。だから彼の性格を十分知っている周囲の人間は心配するのだと言う事に、けれど新一の自覚は薄い。だから尚服部は心配するし、不安にもなるのだ。それさえ新一に言い募っても、結局効力は薄く、それさえ仕方のない事だと、服部は内心深々溜め息を吐いた。それでも近頃は、別口の人間が小言を言う事も手伝って、多少なりとも自覚が促されてはいるのかもしれないけれど……。 「そんで、こんな所で寝っ転がって、何しとるんや?」 芝生に寝っ転がっている綺麗な恋人に、服部は上から覗き込むように口を開くと、新一は服部のジャケットの裾を引っ張った。 「お前もさ、寝っ転がってみろよ」 服部のジャケットを引っ張りながら、新一は意味深な笑みを鮮やかに垣間見せる。 「なんや?」 新一の笑みに魅了されつつ、服部は不思議そうな貌をする。 「いいから」 掴んだ裾を引っ張ると、服部はゴロリと新一の隣に寝っ転がった。 「違うもんやな」 寝っころがると、視点が変わる。視界一杯に広がる蒼空が、眩しかく映る。 「だろ?」 服部の声に、新一は穏やかな笑みを見せている。 「こうして外で寝っ転がるなんて、ガキの時以来やな」 頭上に広がる天など眺めるのは、記憶を想起すれば、随分以前な事に気付いた。深呼吸すれば、朝の空気が心地好く肺を満たす。 西都の高校生探偵として事件捜査に関与し、新一と知り合ってからは、彼を案じ、心配する事だけが優先されてしまい、呆れられながら、毎週大阪と東京を往復した。それでさえ、心配など失せる事はなく、案じても不安は消し去る事はできない。それは今も変わりない。こんなに近くに在て、肌に触れ、情を交わし、それでさえ、身の裡の喪失の予感は拭えない。時折、ゾッとする恐ろしさに、足下から底冷えがして立ち尽くしてしまう。 「なんや、随分健康的な朝やな」 長い腕を隣に伸ばすと、サラリと前髪を梳き上げる。 休日の朝、事件以外でこんなに早く起きる事など殆どない。昼近くまで目蕩んで、互いの肌の感触を手放す事など出来ないのだ常だ。 「だからお前、人前でするなって」 言っても何一つの効力はない台詞だと学習した筈なのに、それでも早朝の公園でされると、つい羞恥が湧いてしまう。それでも触れてくる手を振り払う気配は微塵もない。 「俺さぁ」 触れてくる指先の感触に、心地好く新一は眼を閉ざす。口ではどう言っても、触れられる心地好さを、既に知っている。それが時折、無性に不幸だと思う時がある。知らずにすんでいられたら、そう思う時がある。そんな想いは何処か子供じみていると思う反面、知って手放す事など皆無なくせにと、内心の苦笑と自嘲が交錯する。 「どないしてん?」 言い淀むとは違う一旦言葉を区切った台詞に、服部は仰向けになっていた姿勢を入れ替え、片肘を付き、新一に向かって横になる。 朝の光りに照らし出された白皙の貌。長い睫毛が縁取る繊細な眼差しが伏せられている様は、綺麗な彫像のような気分をもたらされる。 「中学の時さ、家出したんだ」 「家出?工藤がか?」 新一の台詞に、服部は素頓狂な声を上げる。 工藤新一と家出と言う図式は、結び付かない気がしたからだ。 品行方正、天の才を与えられた推理力。確かに中学生の時は探偵としてマスコミに登場する事はなかったけれど、当時の新一を知れば、もたらされる台詞は不釣り合いに思えた。 「なんだよ、不思議かよ」 「結び付かん」 「家出っても、まぁそんな大袈裟なもんじゃねぇけどな」 閉じた眼差しが開けば、視線がチロリと流れて服部を視る。その眼差しが、どれ程煽情的な色を放っているか、新一に自覚は皆無だ。だからタチが悪いと、服部は内心溜め息を吐いた。 「なんでや?」 「中学の時、丁度受験終わった冬だった。なんか急に独りになりたくなってさ」 「そんで家出かい」 「お前は、ねぇ?」 チラリと、透けた眼差しが服部を間視する。 「家出っていうか、独り旅やな、俺の場合は。自転車乗って」 「ヘェ〜〜いいなソレ」 「リュックと寝袋担いで、自転車乗って、行ったんや。大した距離は行けへんかったけど、ガキの頃は、そんでも随分冒険した気ぃすんねん」 「判る、俺もそうだった。本当、今考えれば、大した距離じゃねぇんだよな。でも、冒険なんだよな」 「俺も、服部と同じ。自転車で独り旅したよ」 「黒羽?」 突然頭上から気配もなく振ってきた声に、新一と服部は流石に驚いた顔を見せた。 其処には、先刻の服部同様、何処か悪戯気に笑う、黒羽快斗が佇んでいる。白いタキシードに、闇夜に眩しく映え、風に翻る白いマント。キッドの印象が眼にも痛い鮮やかな白なら、新一と服部を覗き込み、笑っている快斗の印象は不思議と黒だ。それは今身に付けている服が、黒だからというだけでは、ないのかもしれない。 「お前ぇ、何してんだよ」 気配なく現れた快斗に、新一は憮然と口を開く。 「副業の帰り」 悪戯気に笑ったまま、シレッと言う快斗は、新一の隣に腰を下ろした。 「パクるぞ、お前」 冗談だと判る台詞に、新一は呆れて薄い肩を竦めた。 いつだって快斗はこうしてフラリと現れる。現れては軽口を叩いて行く。 一体いつからそんな関係を築いていただろうか?確か初夏に関わった事件の折り、近付けば命の保証はないと、忠告しておいた筈なのにと、新一は首を傾げている。 それは快斗だけではなく、服部にも言える事で、だからこそ最初は、差し出された服部の腕を取る事を、拒んだ新一だった。 自分に関われば、周囲の人間に危険が及ぶ。巻き込んでしまう可能性を、新一は何より恐れていた。だから心配する幼馴染みの蘭にさえ、幼い姿になってしまった経緯も何もかもを話さず、頑なに口を閉ざし続けていた。。けれど服部は違った。 拒んでも、勝手に関わるだけやと宣言し、新一に関わり続けていた。そうして新一は服部の腕を選んだ。 状況に流される事はなく、自らの意思で服部の腕を選んだ。だからこそ、快斗に言わせれば、新一が危険に巻き込むと承知で選んだ相手は服部だけだと言う事になる。巻き込むと承知で選んだ相手。その意味の重さを、快斗が読み違える筈はなく、そうして服部が間違える筈もなかった。 「だから、現行犯が基本でしょ」 穏やかな声で、快斗は鷹揚な笑みを覗かせる。 「何してるんや」 快斗の台詞に呆れて口を開けば、快斗はなお悪戯気な笑みを見せるばかりだ。それが快斗の真骨頂なのだろうと、服部は内心思っている。快斗がその事を知っているのか、いないのか?それは服部にも判らなかった。 「だから」 「アホ、副業は夜やろ。それとも趣旨変えしたんか?月下の奇術師は」 平成のルパンから始まって、怪盗紳士、月下の奇術師、etc.怪盗KIDに付けられた愛称は数多い。そうして国際指名手配犯としては、怪盗1412号として、国際手配されている。 闇夜に眩しい白いマントにタキシード。レトロとさえ言われる変装が、けれど快斗には似合う気もするから不思議だった。 そうして自分達は対極に位置しながら、互いの存在が不快ではない事が不思議だった。馴れ合っているつもりはない。けれど、快斗は快斗のやり方で、新一を心配している事が服部には判っていた。そうして新一も判っているのだろう。憮然としながらも、決して快斗を遠ざける事はない。たとえ忠告をしたとしてもだ。そう思えば、東西の名探偵と言われる自分達と快斗の関係は、不思議なものだ。けれど悪い気分が微塵もないから、尚更不思議なのかもしれない。 「口悪いよ、西の名探偵は」 鷹揚に笑うと、新一の隣に佇みながら、ゴロリと芝生の上に横になる。 「さっきの話しの続きだけどさ、俺もさ、服部と同じく自転車で独り旅に出たよ。リュックと寝袋持って、中学一年の夏の時」 新一の隣に横になり、態勢を服部と同じく入れ替える。片肘を付き、鷹揚に笑い、隣の希代の名探偵を愛しげに眺めいる。 「なんや俺もそうやで、中1の夏休みや」 「案外どっかで擦れ違ってたりしてな」 「かもしれへんな」 懐かしい記憶。子供だった過去。今でも子供だと自覚している事が、服部をただの子供にはしなかった。 それはきっと、快斗も同じなのかもしれないと思う服部だった。 今思い出せば、本当に子供だった。大した距離も進んではいない。けれど確かにアノ時の自分には、冒険だったのだ。そしてそれが成長過程に必要な儀式だったのだろうと言う事も、今なら判る。 「迷ってる時、なんだよな」 二人の軽口を聴きながら、新一が当時を振り返り、独語に呟くように口を開いた。 「せやな」 「途に迷って不安な時」 確かに、当時を思い出せば、そうだったように思う。子供だと思うからこそ、大人になりたいと背伸びして、そうして未来への不安に迷い独り旅に出た。途を探す為に。 「俺さ、今朝早く目ぇ醒めて、思い出したんだ」 瀟洒な両腕が再び天に向かって伸ばされる。大きく息を吸い込めば、清涼な空気に浄化される気がした。 「あん時見た、冬の澄んだ早朝の空」 夜が白々明けた頃、こっそり家を出た。その時に見た、夜明けの空。身を切る空気の凛冽さが心地好かった。未だ都会は寝静まり、深閑とした厳かな朝の空気や気配が心地好く肌身に纏わり付いた。アノ時の、高く澄んだ蒼い冬の空。思い出すと、無性に懐かしくなった。 「独りになりたくて、結局独りにはなれんと知ったのはあん時やな」 「そうそう、いろんな人に会ってさ。結局色んな人の想いに触れて、思えばきっとそれが冒険だったんだ」 旅先で見た雄大な夕日。沈み行く太陽が一日の終わりを告げていて、知らず涙を流していた。 「怒られたか?」 二人に、新一は尋ねていた。 「いんや、『見つかったか?』そう言われたわ」 自分の迷いや何もかも、父親は知っていたのだろう。だからただ『見つかったか』そう言われた。その時程、父親の偉大さを思い知った事はないのかもしれない。 「さっすが大阪府警本部長」 『恐ろしい人だねぇ』と、快斗は軽口を叩く。けれどそれには本音が混じっている事を、聞き逃す新一と服部ではなかった。 「そういう黒羽はどうなんだよ」 「俺?まぁ母親心配させたけど、男の子なのねって、言われた。名探偵は?」 「俺は、母さんに泣かれたけど、父さんは何も言わなかった。お帰りってそれだけだった」 心配性の母親は盛大に泣き、帰ってきた自分に抱き付いた。けれど父親は穏やかに笑って『お帰り』と、頭を撫でただけだった。 アノ時の手の温もりや大きさ、そうして穏やかに笑った気配や何もかも、今も鮮明に覚えている。父親というものはこういうもので、いずれは自分もそうなるのだろうと、疑ってはいなかった過去。 「まぁなんやな、父親の偉大さって、こんな時に感じるもんなんやな」 「そういうもんなんだろうな」 快斗にとって、父親の記憶は薄い。朧気な過去の額縁に入っている。けれど、血が、呼ぶ気配は確かに有る。受け継いでいると言う事は、そういう事なのだろうと、快斗は理解していた。 父親は、自分が幼い時に亡くなった。正確には、殺されたのだと思う。『何故』と、自問自答を繰り返し、現在が在る。 「すまねぇ…」 快斗の父親が、在ない事を、二人は知っている。 「名探偵が、謝る事じゃないよ」 他人の疵を、自分のもののように感じてしまう名探偵のその性格は、困ったものだと快斗は笑う。 「忘れられない風景って、アノ時見た夕日かな」 「俺もやな」 たった独りで見た風景。地平線に沈む雄大な夕陽。その雄大さに、自分の存在の小ささを思い知った。 「父さんが言ってた。それは宝物だって。初めて独りで見つけた風景や言葉や想いは、宝物なんだって、言ってたな」 帰った自分に手向けられた父親の言葉は、アノ時はまだ子供の自分には良く判らなかった。けれど、今なら判る。 「宝物か。そうかも」 「せやな、そんな気ぃするわ」 迷って自分を見詰めたくて旅に出た。先々で見つけた人の想いや言葉や風景は、今も覚えている。懐かしいのは、それが迷いの中で、独りで見つけたモノだからなのかもしれない。 「良い事言うね、流石世界のベストセラー作家。独りぼっちで見つけたものは、確かに宝物なんだろうね」 「でも今は、違う宝物見つけたで。忘れられない風景や」 「アアそれ俺も。服部とは、本当に気ぃあうよな。絶対同じもんだもんな」 「なんだよ、ソレ」 二人で気を会わせている服部と快斗に、新一は途端憮然となる。 「別に俺は黒羽と気ぃあわせとうないで」 きっと今以上に、懐かしく愛しく、切ない風景は見つからない。それは予感ではなく、二人にとっては疑う必要も余地もない、確信でしかない。 「宝物の風景はね、ココにあるから」 ココと、瀟洒な指先が、新一の長い前髪を弄ぶ。 「ココって何処だよ」 快斗の台詞に首を陰るより早く、新一の手は、鬱陶しげに快斗の手を振り払う。払いながらも、マジシャンの手は、繊細なんだなと、不意に思う。その繊細な手で、難解な鍵を開け、鮮やかな手口で宝石を盗んで行く。その意味を、多分自分は知っているのだろうと新一は思う。 血に塗れ、凄惨な状況で、それでも前を向いていた眼差しを思い出す。標的に照準を会わせた獣の眼が、確かにアノ時、暗闇の中で凛冽に放たれていた事を、自分は知っている。意味も理由も、憶測の域を出はしない。けれど、多分自分は知っている。いるのだと、新一は快斗を凝視すれば、自分の隣で希代の怪盗は、内心を読ませない笑顔を放っているばかりだ。だからより新一が憮然となってしまう事まで、流石の快斗も判らなかった。 「名探偵、相変わらず、国語苦手なんだね」 払われた手に執着する事もなく、長い腕は胴に戻っている。そうしては、新一の台詞に可笑しそうに笑う。そうすれば、新一は益々憮然となる。そんな風景が、快斗や服部には限りなく愛しいものなのだと、きっと新一は気付かない。 「ココって言ったら、ココやで」 ひどく優しい眼差しが、白皙の貌を映す。 不思議そうな、憮然とした面差し。凛冽で怜悧。完璧な頭脳と推理力。新一に纏わるマスコミの無責任な称賛の言葉。けれど、違うのだ。新一は、完璧など望んでいなかったし、今も望んではいない。極限られた人の中で、新一は子供のように表情を変える。だから、それは何にも換えがたい、宝物の風景だった。 「お前ぇら、俺に判る言葉で話せよ」 「話してるやろ?」 「これ以上ない程、判りやすい言葉だよ」 服部と快斗。二人揃っての台詞に、新一は益々憮然となる。そんな時間がひどく愛しいと、誰だって判っているのだ。肌身で感じる感触や気配は、言葉以上に雄弁に誰の内心をも語るのだから。 憮然となりつつ、新一はスラリと長く細い腕を天に広げた。 「何か、視えるの?」 先刻から繰り返されるその仕草に、快斗は問い掛ける。 「何視える?」 してみろよ、言外に滲ませ、新一は蒼旻に焦点を絞っている。 「手ぇ」 片肘を外して寝っ転がり、新一同様両手を高く伸ばし、服部は端的に答えた。 「空」 服部同様、快斗も寝っ転がると、答えた。ご丁寧にも、ポケットからモノクルを取り出して、小さい視界を覗いてだ。その様に、新一も服部も呆れを隠せない。 「物証有りで、パクッてやる」 「これくらいで、物証にならないでしょ?コレ、仕事用じゃないし」 「なんや?」 「即席で作ったイミテーション、まぁ一時期、使ってたけど。何せホラ、名探偵が、頑丈に加工してくれたの持ってるから」 「なんやソレ〜〜?工藤〜〜」 「ダ〜〜〜うるせぇ、いちいち叫ぶな。エッグの事件の時、こいつの壊されたからな、拾ったの俺だし、こいつには借りあったし」 「お揃、だったんだよね、一時期さ。コナンちゃんのメガネと」 「……工藤〜〜探偵が泥棒の手助けしてどないするん」 アノ幼い子供のメガネと同じと言う事は、強化されたレンズ使用という事で、博士に頼んだと言う事になると気付かない服部ではない。 「そう言って、こいつ拾って懐かれたの、お前ぇだろうが」 「でもホラ、俺その前に、名探偵に拾われてるから」 結局自分は、負傷した姿のまま、二人に拾われている。 「お前ぇ、猛禽だかんなぁ。俺犬なら飼いたかったけど鳥類はいらねぇ」 「犬なら、在るでしょ?忠実なの。まぁ犬ってより、狼かな」 ホラっと、長い指が新一の向こうを指差している。 「せやったら、お前は黒豹やないか?」 「そう?まぁ猛禽は、名探偵かもね」 「なんで俺が猛禽なんだよ」 「空から標的見据えて急降下」 「そりゃキッドん時のお前だろ」 白い翼。ボロボロになっても、飛び立つ事もやめられない翼を持っている怪盗紳士。 標的を狙い、淡如で凛冽な眼差しで冷ややかに見据えるその眼差し。決して理性を失う事のない冷静さで標的を見据え、意志と自由と、幾許の枷を持って、天を舞う白い翼の所有者。それでも、猛禽が飛翔を望むのは当然の事だ。それ故の翼。ボロボロになって疲れて血を吐いても。目的の為に飛び続け、鋭利な眼差しで地平を目指す。快斗の白い翼は、きっとそんな翼だ。 「それでもね、ホラ、名探偵、例えばその細い足首に鎖掛けられても、飛び立つ為なら、自分の足食いちぎって飛び立つ性格でしょ?」 「だったら、お前等二人、そうじゃねぇか」 走り出す為なら、二人共やはり従属は食いちぎって走り出すだろう。たとえその身を喰ってでも。誰にも従属しない意志の靭さ。自らの意志で選択を決定するその強さ。 「それでもだよ」 快斗は苦笑する。それは新一には自嘲に視えた。 「でも工藤、仕草的にはネコやで、気紛れな所も」 「どっちかって言うと、ネコ科でしょ、名探偵の場合。じゃなきゃ、やっぱ猛禽」 「せやったら」 そこで服部と快斗は新一を間に挟んで器用に視線を合わせ、酷薄な口端に、意味深な笑みを刻み付け、同時に笑った。 「獅子」 「なんだよソレ」 「獅子は、ネコ科でしょ?」 「肉食獣って事かよ」 寸分の違いもなく答えられた新一は、両隣を交互に眺め、憮然となる。 「判っとらへんな。まぁええよ」 「判ってる人は、判ってるから」 世俗的な称賛な言葉でもなく、その潔さを知る人間ならば、判る筈。彼の躊躇いのない行動の裏。常に哀しみや痛みが隠されている。そんな内心を決して人前で見せない意思の強さ。俯く事なく、正面を見詰め続けている静かな双瞳。そんな時、いつも思い知る。その強さや勇気。それはまさしく獣の中の獣。肉食でもなく、猛禽でもなく、ただ草原に静かに佇む靭やかな獣。誇示もなく、傲然さもなく。 「俺はちっとも判んねぇよ」 言葉で投げ捨てると、天に伸ばした両手の先を、色素の薄い眼差しが凝視する。 「切り取った空」 モノクルから覗いた空は、人口レンズを通して屈折度が変わる気がした。切り取った視界の中、それでも覗く事のできる世界が、自分の世界だと思っていた。 「工藤は、何視えたん?」 新一の、細く長い腕の先。瀟洒に伸ばされた指先の白さに、フト眼を奪われる。 「何だと思う?」 当ててみろよ。新一の眼差しは、そう語っていた。 「俺が家出して見上げた空に、答えなんて在る気がした。こうして伸ばした手の先に」 朝日を浴び、細い指先が零れてくる陽の光。眩しく閃く繊細なライン。泣き出したい程愛しいと、快斗と服部は新一の姿に眼を細めた。 「答えなんて、案外極身近にあるんだって思ったぜ」 「なんや?」 「服部、探偵でしょ?推理しなよ」 「黒羽、人に言うんやない、自分で考ぇ」 「だったらお前らは?どうだったんだよ。独り旅して、夕陽視て。何感じたよ」 それはきっと、そんなに大差のない気がした。それは感傷かもしれない。けれど、似た季節、似た時期、似た年齢で、迷って独り家を出たなら、今でも忘れられない光景を持つなら、それは全く同じものではなくても、似たものだと新一は思う。 「あの時……」 快斗と服部は、記憶を想起する。 雄大な夕陽。赤々と燃え立つ茜の空。沈み逝く太陽の悠然さに、自分の存在など小さいものだと思い知った時。急激に途が開けた気分だった。あの感触や感覚や、忘れられない大切なナニか。 「……途…」 「未来……」 「ビンゴ」 珍しく逡巡の後に告げられた二人の声に、新一は穏やかに笑う。 「俺は夕陽じゃなくて、冬の早朝の青空視て、こうして手を伸ばして、思った」 続く途。坂道も下り坂も平坦に補正された公道も。明日へと続いて行く一本の途。狭かったり、細かったり、広かったり、時には獣道だったり。 何処までも続いていく空。伸ばした手の先にも広がる時間に、急速に迷いが晴れた気がした。否、それも言葉にすれば語弊がある。 迷っていた。足掻いていた。けれどそれは何を迷い足掻いていたかの明確さはなく、ただ漠然と、将来に対しての不安や何かだった。 迷う事さえ迷っていた。足掻く意味さえ知らなかった。子供だったのだと、今なら思える。けれどあの時の迷いがあるからこそ、今自分はきっとココに在るのだろうと、新一は思う。大切な人達と共に。たとえ大切な人を苦しめてしまっても。 「工藤らしいな、ほんま」 「好きだよ、名探偵」 「……コラ黒羽、どさくさに紛れて言うてるんやない」 「別にいいでしょ?服部みたいな色含んだ告白じゃないんだし」 恋愛ではなく、けれど、同年代に向ける友情ではない。きっともっと別の切実な部分で、新一を好きなのだと快斗は思う。好きと言う言葉も少し違う気がした。言葉が不便だと思うのはこんな時だ。言葉にすると、それだけ少しずつ本当に伝えたい想いやナニかは、違ったものになってしまう気がする。 「俺も、お前の事は、まぁ気にいってるかもな」 「工藤〜〜」 サラリと言う新一に、服部は泣き真似をして見せる。 「だから、無茶ばっかしてんなよ」 「無茶は、別にしてないんだけどね」 「してるだろ。エッグの事件の時は撃たれるし、去年の夏だってそうだし、小さい傷あげれば、きりないだろ」 「それはそのまま名探偵に返すよ。無茶はダメだよ。名探偵」 言い募っても、効力のない言葉だとは知っている。自分が言われても、真実の為に走る事を止められないのと同じくらい、新一には効力のない台詞。それでも、告げずにはいられない言葉がある。 「俺にとって、お前は大切な人間だからさ」 「大切?」 「なんだよ、可笑しいかよ」 キョトンとした快斗の顔は、滅多に見られものではないのかもしれない。 新一は、自分の隣でそんな面をしている快斗の顔を眺めた。 「別にね、サラリと言葉にしてくれちゃうから」 大切で大事で、だから無茶して傷付いてほしくはない。それは肉体的な傷を指し示すより、精神的なものの比重がより大きく多い面積を指し示している言葉。 傷付けられて、受けた疵の痛みも自覚出来ない希代の名探偵だからこそ、無茶をして、自らを傷つけてほしくはなかった。 『大切』 そんな言葉を、サラリと新一は告げてしまう。 好きって言うより大事で大切。きっと新一に向けられる自分の想いを適格に表現するなら、そんな言葉なのかもしれない。 まぁ、言葉は苦手で、言う事ちっとも聞いてくれない人だけど、こうして極簡単に、単純に、当たり前のように、言葉を救いあげる事は、造作なくやっちゃうんだよね、この人は。と、快斗は内心肩を竦めた。 「そら可笑しいやろ。探偵が泥棒大切なんて、間違っても、他言できへんな」 「だったら黙ってろ。どうせお前と灰原以外、知りゃしないんだ」 「刑法60条……」 「共同正犯」 少しだけ拗ねたような服部の台詞に、快斗は笑う。 「今更今更、服部十分じゃん。刑法100条、103条、169条三つも違反しちゃってるし」 「……誰のせいやまったく…」 第一泥棒のくせに、なんでそないに刑法に詳しいんや、服部の言外が語られる。 「感謝してます」 それは本当だと、笑う快斗の眼差しが真摯に瞬いている。 新一にも、服部にも助けられて、こうして自分は彼等と共に在る。大切に守りたいと思う存在に出会えた事に、感謝さえする。 「諦めないから」 極静かに、何でもない事のように、淡如に告げられた言葉に、服部と快斗は息を飲む。 もしかしたら、新一はそれを確認する為に、こうして一人で早朝の空を見上げに来たのだろうか? 「アホ」 「判ってるよ。名探偵は、諦めない人だって。でもね、疲れたら、休んでいいんだよ。じゃないと、飛び続ける事も、走り続ける事もできないから」 「休んでるじゃねぇか」 こうしてと、新一はひどく静邃に笑っている。その笑みが、泣き出したい程切なく視える。どんなに静かに佇んでいるのか、きっと自覚はないのだろう。 『哀しい程の静謐さ』形容詞として使用される言葉の本質的な意味合いを、形として初めて実感した気がした服部と快斗だった。 「お前等在るし」 「ウン、在るよ。どっか行けって言われてもね」 「置いてかれても、追いかけたる。言うたろ?約束したやろ?呼んでくれって」 「服部」 「そうそう、そうやって、呼んでや」 新一の声に、服部の腕が伸び、芝生に乱れた髪を梳く。 「腹減った」 「工藤〜〜〜」 ガクリと服部が脱力してしまっても、罪はないだろう。 「俺も、折角だから、服部お手製のフレンチトーストと、フレンチオムレツ付きで、ご馳走になろうかな」 「ふざけんやない」 「ケチだねぇ〜〜いじゃん、一人分も二人も、手間は同じでしょ」 「んじゃ黒羽、オムレツはお前の担当にしたる」 「マジシャンのこの繊細な指、傷つけたら仕事にさしさわる」 「黒羽、随分いい根性しとるやないか、何が繊細な指や」 「嘘は言ってないよ。俺外科医に向いてるって言われた事あるもん」 「誰にや」 「知り合いのドクター」 「嬢ちゃん、言うんやないやろな」 「まさか、違うDr」 「黒羽、お前本業に世話なってるんじゃねぇんだろうな」 ついつい心配してしまう新一は、たいそう快斗を気に入っているのだろう。きっと、自覚はないのだろうけれど。 「口堅い人だから」 「そう言う問題じゃねぇ」 「ええやん、自分の事には責任持てるやろ」 「よく判ってるじゃん」 それが信頼を預けた言葉だと、判らない快斗ではない。何とも奇妙な付き合いだと、きっとこの場で三人が三人とも思っているだろう。けれど、決して悪い気分は欠片もない。ない事が、不思議だった。 「ほんまええ性格しとるわ」 「だったら、朝飯ご馳走して」 「どういう理屈や、まぁしゃないな」 自分も大概甘いと、服部は内心深々溜め息を吐くと、威勢付け起き上がる。 「リクエスト、あるか?」 起き上がり、未だ寝っ転がっている新一を真上から覗き込む。 「フルーツのヨーグルト和え追加」 「OK」 手を差し出してきた新一の細い腕を救いあげると、新一は反動をつけ起き上がる。 「黒羽何寝とるんや、置いてくで」 新一が起き上がり、隣で未だ寝ている快斗に声を掛けると、快斗は眼を細め、ゆっくりと身を起こす。 「何してるん?」 「眼福だなって」 「なんだよソレ?」 「ん〜〜朝日を浴びて、佇む名探偵」 「俺はモデルじゃねぇ」 街に出れば、何度となく掛けられる声を思い出したのか、新一は途端憮然となる。 「そりゃ名探偵には、そこいらのモデルは足下にも及ばない」 その独特の気配や雰囲気やナニかは、誰もが付け焼き場で真似の出来るものではない。新一の周囲は、空気の色が違うのだ。 陰惨な殺人事件の現場にあってさえ、新一の周囲だけは、不可侵な透明な静謐さに満たされている事を、快斗も服部も知っている。 「蹴るぞ」 どうせ俺の顔は母親譲りの女顔だと、新一は快斗を蹴る真似をしては、笑顔を向けた。 「アホ言うとらんで、帰るで」 二人の会話に呆れて、服部は促した。 「それじゃぁ。服部の朝御飯、ご馳走になろうかな」 威勢良く、それでいて空気の動く気配すら感じさせず、快斗は綺麗な所作で起き上がる。 三人で、並んで歩いて行く。笑いながら、戯れながら、軽口を叩いて。そんな時間かひどく倖せだと実感しながら。 「そういえば、さっきの話しにピッタリな言葉あったね」 不意に快斗が思い出した様に、口を開く。 「?なんだよ」 「迷って旅に出て」 「アア」 快斗の台詞に、思い付いた様に服部が相槌を打つ。 「アレやな」 「少年よ、大志を抱け」 「惜しい」 新一の台詞に、快斗も服部も穏やかに笑い、次には二人が口を揃えた。 「少年は、荒野を目指す」 荒れ野を一歩一歩確実に踏み締めて、荒涼とした荒野を駆ける。目指す途を見据え、自らを指針に、正面を向き、頭を垂れず。自らの途を信じていく強さと勇気。たとえ血反吐を吐いたとしても。 「この途だって、どっかに繋がってる」 続く途。未来へと。あるかどうか判らないけれど、自分には。 それでも、確かに在るのだろう時間の先。 薄昏い闇だとしても、汚濁に満ちた世界だとしても。決して光量に満たされた光りの中ではなくても。深淵だとしても。 「久し振りに、いい朝を堪能した気分」 新一の内心をそうと察したのだろう。快斗が軽口に背伸びする。 「そらいい朝やろ、これから人ん家で、朝飯まで食ってく言うんやからな」 服部は、快斗以上に感じているだろう。新一の内心を。 「お前ぇら、本当バカだな」 二人の気遣いが判らない新一ではないから、薄く細い肩を竦め、走り出す。 「コラ工藤、走るんやない」 「腰に響くのにねぇ」 とは、服部なだけ聞えるように、ボソリと快斗が呟いた声だ。 「余計な事言うんやない。朝飯食わしたらんで」 「遅ぇよ、お前ぇら」 走り出し、クルリとターンする優雅さで、振り返る。笑顔が眩しい、そう思う。 新一の背後に視える蒼空。何処までもつづくソレに、せめてもと祈りを込める。 歩く途が同じではない事くらい、百も承知している。人は決して誰かと同じ途は歩けない。人は同じ途を歩いているように視えて、自分の未来を歩いている。だからこそ、重なり合う時間は奇跡的なのだから、大切にしたい。それぞれの途を歩きながら、誰かの存在を大切にしながら。 見上げた空。その蒼さ。何処までも続く透明なソレが、愛する人の上に、倖せが降るように。 少年は荒野を目指す |