 |
 |
|
|
消費税増税法案が8月10日に国会を通過し、可決成立した。最近の政治状況を見ていると、国民の政治への信頼が崩れ、日本の将来に対する失望感のみが残った気がする。
野田首相は法案成立後の記者会見で、2009年の衆議院議員選挙時の民主党マニフェストに記載がなかった消費税増税について「深くお詫びしたい」としたが、この発言に納得した国民は少ないだろう。
2009年マニフェストには消費税増税が記載されていなかっただけでなく、逆にはっきりと「消費税は増税しない」と明記されている。ここが重要だ。増税しないと公約して政権を取った政党が、3年も経たないうちに党を割ってまで正反対の政策実現に全力を集中している姿は、国民への背信の政治を示す歴史的事件であり、後世に語り継がれる汚点となるだろう。
また、解散総選挙について「近いうち」ということで、民主・自民・公明の三党で合意したとされているが、他の野党が密室談合だと批判しているように、理解に苦しむものがある。
私の個人的な感想では、自民党が野田首相の言動に丸め込まれているように見える。
欧米では、政権与党と野党第一党で連立が組まれたことは一度もない。与野党の一体化という事態は、即ち民主政治の否定に繋がるということなのだろう。
近づく選挙のため、各党は早くもマニフェスト作りに精を出しているが、今後は政党や政治家がどんなに力を入れてもっともらしいマニフェストを作っても、もはや政権公約など信じる国民は少ないだろう。我が国の政治歴史上に残された傷は、決して小さなものではない。
一部には必ずしもマニフェストにこだわる必要はないという意見もある。確かに選挙公約は絶対に守らなければならないものではなく、重大な出来事…例えば原発事故の発生など新たな危機に際しては、マニフェストに縛られない対応が必要な場合もある。
しかし、今回問題の消費税は大衆課税である。増税を迫られる国民は納得いく説明を求めるだろうし、政権は国民の問いに答える責任がある。
野田首相はこれまで、消費税増税の実施前に民意を問うと繰り返していたが、増税法成立後の現在もその動きは見えない。「民意を問う」の意味が解散であれ議員任期満了であれ、国民が意思表示できるのは増税への賛否ではなく、増税確定後の政権政党に対する可否でしかなく、結局「後の祭りの一票」ということになる。
公約違反の法律を成立させておいて、そのあとで国民に信をというというのは、到底民主政治とは言えないのではないだろうか。
マニフェストに対する議論は多々あるが、3年前に民主党が政権交代に成功した勝因が、増税反対や子ども手当支給、高速道路無料化にガソリン税廃止…などを盛り込んだ良い事づくしのマニフェストだったことは間違いないだろう。今回の問題は「マニフェストのありかた」という議論とは明らかに異なる。地盤・看板・鞄と言われる利益誘導型の政治から国民がいかに脱却して、自ら政策を選択し、成熟した政治を進めることができるかが係っている。
マニフェストには法的拘束力は無くとも、投票に先立って示される約束事として、国民が候補者や政党を選択する判断基準となることが民主政治の基本理念であり、政治倫理でもある。これは2003年の衆院選以降定着しつつあったのだが…
次の選挙で示される各党のマニフェストを、果たして国民は信用するだろうか。 |
あと数日で東日本大震災が発生した3月11日から1年が経つが、余震は未だ終息する気配を見せない。広大な地殻変動によって発生した地震の影響は、この先数年に及びそうだ。
今年の1月28日には、日本列島で1日の間に23回の有感地震が発生し、この内の11回は富士山周辺だったため、富士山噴火との関連性が懸念された。
また、政府の地震調査研究推進本部などの研究機関でも、将来の地震発生確率の上昇などが発表され、地震予測手法の見直しも進められている。
この中で、三陸沖から房総沖で発生する恐れのある地震を見直した結果、将来予測される地震の規模として、初のマグニチュード(M)9を想定。今後30年以内に30%の確率で同クラスの地震が発生する予測を公表した。
南海トラフの巨大地震の想定について論議している検討会でも、「東海、東南海、南海の3巨大地震の震源想定域を約2倍に拡大する」とした報告を発表。
東京大地震研究所は、東日本大震災の影響で地震活動が活発化していることを受け「首都圏でM7クラスの直下型地震がある」との計算結果を1月末に公表している。
茨城・千葉でも比較的規模が大きい地震が連発するなど不気味さが漂う中、文部科学省のプロジェクトチームが3月7日に会見。首都直下型地震のひとつで、M7.3と想定される「東京湾北部地震」について、想定震度を6強から7に引き上げたことを発表した。東京都東部の沿岸地域が、震源の浅い震度7の地震の脅威に晒される可能性があるとしている。
これまでの想定を覆す多くの予測が正式に発表されたことで、対象地域の自治体では防災計画の見直しに向けた動きが加速するだろう。
また、防災の基本は個人の心掛けにあることも肝に銘じ、自分のいるところは大丈夫だろうという安易な考えを捨てて、防災意識を高めていく必要がある。
|
現在、日本の財政状態は先進国の中で最悪であることは間違いない。これからどうなるかは、いろいろの状況の中で総合的な判断が必要であるが、当面問題視されている項目を考えてみよう。
① 日本は、国債の国内保有率が高く、現在では国内で94%を消化している。
最近問題視されているイタリアは、10年位前までは80%を国内消費していたが、現在は約50%まで急激に落ち込んできている。国内で保有していれば、利息分が海外に流出しないので国債収支上でもプラスになる。
しかし外国人の保有率が6%と少ないから大丈夫だと言えるだろうか。少なくとも相場を撹乱するきっかけは十分にあり、その上外人保有国債は中・短期のものが多く動かしやすいということが言える。
国内保有国債にしても、関与する金融機関が将来ともに絶対に安泰であるとは言い切れず、不良債権を出さないためには売りに出ることもある。
② 日本人の個人貯蓄率が高いので大丈夫だともよく言われる。1400兆円ともいわれる個人貯蓄は、外国に比べて高いのは事実で、これが金融機関を通じて国債を引き受ける原資となっている。
そこで、この預貯金が将来ともに続くかを考えてみると、これは疑問視せざるを得ない。
国民の可処分所得貯蓄に回せる比率は、約20年前は10%くらいあったが、現在では2~3%にまで落ち込んできている。それだけ貯蓄する余裕が無くなっており、しかも預貯金の大半を高齢者が所持していて、高齢化が進めば当然取り崩しが始まることは必至だ。
③ 先日、日本の貿易収支が41年ぶりに赤字になったと報じられた。経常収支は貿易収支・サービス収支、所得収支及び経常移転収支の合計である。
海外旅行などのサービス収支の赤字や海外援助などの経常移転収支の赤字は、これまでは貿易収支と海外から受け取る利息・配当などの所得収支の黒字で補填していた。
2011年は東日本大震災や急激な円高などの特殊事情があり貿易収支が赤字になったが、所得収支の黒字で辛うじて経常収支の赤字転落はまぬがれた。
しかし、震災や円高は一過性のものだろうか。いよいよ日本産業の国際競争力は後退してきていると言われている。輸出産業では生産の場を海外に移す例が増えてきており、日本からの輸出減となっている。
一方輸入は、発電用燃料などを含めて、今後増加が予想される。近い将来、日本は貿易赤字国となるのではないだろうか。
輸出が減っても利息・配当などの所得収支で補填し、経常収支が確保できればよいが、投資効率の低い日本では、後数年で経常収支が赤字に落ち込むことが考えられる。
④ 日本の消費税率は、先進国中では低く、財政状態の改善の余地もあるという意見も多い。消費税率を上げるためには、政府の国民に対する説得力が必要であり、その上で国民の意識が問われる時代になったのではないだろうか。これからの推移を注意深く見守っていく必要がある。
結論的には、現在の円と国債はバブル状態にあり、日本の国債の行方は非常に不透明なものが多い。いずれ国債バブルがはじければ国際価格は崩壊し、財政破綻により円バブルもはじけ、次に来るものはインフレ円安だと極論する評論家もいる。
折しも、銀行最大手の三菱東京UFJ銀行が日本国債の価格急落に備えた「危機管理計画」を作ったことが報じられていた。
|
| 今年の日本経済はどうなるのか? |
平成24年1月6日 |
平成24年の年明け、4日には各界の仕事始めで歯車が回り始めた。昨年を振り返れば、リーマンショックから立ち直り始めた矢先の震災や、夏以降はEU財政不安を背景とした円高による日本経済の失速と、散々な年だった。
今年こそはという声がよく聞かれ、政府は実質経済成長率を4.2%と見込んでいるが、これは期待感を含めた数値で、あまりにも不安定要素が多い。
不安定要素として予想を覆す要因には、次のようなことが挙げられる。
①ユーロ危機の影響 ③原発と電力事情 ⑤主要各国指導者の選挙
②原油価格の高騰 ④消費税増税と政局 ⑥財政再建など重要課題の先送り
①ユーロ危機の影響
昨年末にユーロが急落、一時100円を切り、年明け早々には98円台で推移している。
ドルに対してもヨーロッパの財政危機を背景としてユーロ安となっており、今年も大きく揺れてその影響が各方面に拡大することが危惧される。
日本経済は輸出に頼る度合いも大きく、企業の業績が悪化すれば日本経済も悪化する。
昨年11月のEU首脳会議では、財政協定や欧州安定化メカニズムを作ることで合意したが、各国では議会の承認を取る必要があり、時間をかけている間にも危機は進行する。前進ではあるが決定打ではない。
債務危機国であるギリシャ・イタリア・スペインなどの国債償還は今年が山場であり、2~4月には利払いも必要となってくる。
また、金融機関の格付けのランクが下がり、これらの影響は他の国にも及んでいる。EUとの貿易上での繋がりが深い中国・ブラジルなどの新興国も影響を受けることは避けられない。
ユーロ危機が深刻化すれば、世界同時不況となると予言している人もいる。
②原油価格の高騰
年明け早々、原油価格が高騰している。この背景にはイランの核開発疑惑に対しアメリカが金融制裁を行う動きを見せたため、対抗策としてイランがホルムズ海峡を封鎖すると言い出し、世界の原油市場では一気に緊張感が高まった。
このような状態が発生すれば、石油タンカーの8割がホルムズ海峡を通過している日本の経済は、大混乱に陥ることになる。
③原発と電力事情
原油などエネルギー資源の心配は、国内の電力需給関係の問題でもある。
電力の供給余力として担保されていた原子力発電は、国内に54基の原子力発電設備があるが、現在稼動しているのは6基だけ、しかもこれからも4~5月にかけて定期点検に入ることになる。
一方で定期点検が終了する予定の原発が10基あるが、これの運転を再開するためには地方自治体の同意が必要である。これまでの福島原発事故や電力会社のヤラセ問題の表面化などで同意が取れず、原発は全てが停止状態で推移することも考えられる。
長期的には再生可能エネルギー発電技術の開発で、ある程度の電力が供給可能となるが、即効性には乏しい。
昨夏は節電協力などにより何とか乗り切ることが出来たが、今後の世界の原油供給の不安や国内の電力供給問題は、日本経済の足を引っ張ることが懸念される。
④消費税増税と政局
野田内閣は、消費税増税の方針を固めた。やむを得ないとの面もあるが、過去橋本内閣が消費税率を3%から5%に増税した際に、国内の景気が悪くなったという実例もあり、増税に反対する人も多く、与党内でも意見は対立している。
月内には通常国会が召集されるが、政権交代のスローガンを掲げて勝った民主党は、今や政党の態をなしていない。国会運営も難しい茨の道が待っているだけだろう。
政局が安定しなければ経済に与える影響は大きい。なるべく早く安定した政局に戻すためには、政界再編成、総選挙だという人も多い。
⑤主要各国指導者の選挙
今年は激動の年。世界情勢の先行きを左右する国家のリーダーが一斉に交代する。
1月には台湾の総統選挙、3月にはロシア大統領選挙、5月にはEU主要国のフランス大統領選挙、11月にはアメリカ大統領選挙、12月にはお隣の韓国で大統領選挙がある。そして選挙のない中国も10月には国家主席の交代が予定されている。
なかでもフランス大統領選挙は、ユーロ危機の最中のため、その行方は世界中の注目を集めている。
いずれにしろ世界経済に与える影響は大きく、注意深く見守る必要がある。これに加えて日本も、政局の状況によっては総理大臣が変わる可能性が大きい。
⑥財政再建など重要課題の先送り
先送りされてきた課題は多いが、もう先送りできない筈だ。その代表例が財政再建だろう。
昨年末に民主党政権は、ようやく消費税を2014年4月に8%、15年10月に10%と、段階的に引き上げるという案をまとめた。
国の借金は1千兆円にも上るという世界最悪の状況が、未だに先送りされている。
増税スケジュールがそのまま行くか。多くのハードルが待ち受けている。もし実現したとしても、単年度の国債依存度はあまり減らないので、更なる手段を講じることが必要だ。
本当に日本の債権をどうするのか。真剣に次の手を考えなければならない。同じ事が社会保障にも言える。年金・医療保険など、小手先の手直しは行われているが、世界一のスピードで進む少子高齢化、企業の海外への進出で起きる雇用減、デフレ脱出に時間がかかり過ぎているなどの中で、先送りは許されない。
また、行政改革、内需主導の経済への模索などは、現在では全く手が付けられていない大きなテーマとして残されている。
国民の生活は数字の上では弱干良くなっているかも知れないが、若い人の雇用・所得などは大きく改善されそうにもない。加えて増税や社会補償の負担増などで、将来の不安感を払拭することが出来ない。復興需要や消費税増税の駆け込み効果で景気が良くなるとしても、あくまでも一時的なものである。
日本の経済の行き先には、すっきりした晴れ間が見えないが、年末には晴れ間が見えてくるよう願わざるを得ない。
|
| 原発事故の終息宣言に違和感 |
平成23年12月17日 |
12月16日、野田首相は福島第一原発事故の「収束」を宣言した。事故を起こした原子炉に絞った収束だとしても、まだ多くの難題を内外に残したままでの終息宣言は早すぎるのではないだろうか。
事故炉の中心部は直接見ることも出来ず、計測器の数値を信用して推測している状態で、なぜ収束なのだろう。
首相が自分の立場だけで、国際会議で公約した「年内完了」に固執して宣言したのではないのだろうか。また、廃炉処理には40年がかかるという現段階で、炉には溶けた核燃料があり、この処理方法さえ見通せない現状では、いかにも「収束」という言葉を使うのは不自然で、我々には違和感だけが残る。
これは少なくとも政治の上での話で、科学的には絶対使えない言葉だ。うがった考えをすれば、総選挙を意識した方便とも受け取れる。
原発事故の被災地の住民は、この宣言をどういう気持ちで受け止めているのだろう。多くの人が憤りの中に、虚しささえ感じているのではないだろうか。
今の政治は、「収束」を宣言することでなく、事故処理や放射能問題が現在はどういう状況にあるか正確な情報の公開を行い、その中で「事故収束に向けた工程表ステップ2(冷温停止状態の達成)が確認できた」と発表することに止めるべきではなかっただろうか。
|
| TPPは本当に国益になるか |
平成23年10月21日 |
(先日慶応義塾大学の金子教授の講話を聞いて、大変共感を覚えたので、概要を紹介します。)
これまでの経過を振り返ると、TPP参加の議論は、東日本大震災で一旦は中止されたが、9月21日の野田首相とオバマ大統領の会談でTPPへの交渉参加を促されたという経緯がある。
TPPはもともとシンガポールなど4ヶ国から始まったのが、アメリカ・オーストラリア・その他が加わって10ヶ国になってきているもので、日本が参加した場合のGDPを見ると、9割を日米で占めることになり、結果的にはTPPは、アメリカが日本をターゲットにした戦略だというふうに位置づけられるのではないか。
実際にオバマ大統領は、昨年の一般教書で、ここ5年間に輸出を倍増して、200万人の雇用を創出するという計画を打ち出しているし、これがTPPの一環であることは疑いがない。
よく考えれば、日本がアメリカに対して輸出を伸ばすためだということにはけしてならない。特にオバマ大統領は、失業率が高止まりする中で、再選が危ぶまれている。しかも財政赤字の削減を迫られる中で、輸出以外の手段がなくなっている。 したがってTPPへの参加は、アメリカを助けてくれませんかという話になる。アメリカ当局は、ドル安戦術で円高を放置しており、このところ120円より4割近くの円高になっていて、これが輸出産業に打撃を与えているのである。TPP問題というより、このドル安戦術に対する問題を忘れてはならない。
今後の日本にとって重要な輸出事業は、中国をはじめアジア市場である。アジア市場に入るためにTPPに加入する必要があるといっている人もいるが、中国・インド・韓国などが参加していない現状では、日本の参加は疑問視される。
そもそもTPPに参加して輸出を伸ばそうという話はロジックとして成立しない。まずアジアでの結びつきを強め、環太平洋の自由貿易では、中国などが参加した段階で交渉に参加したほうが、日本にとっては有利になる。
中国・韓国の農業は水田が中心で、その平均耕作面積は1~2ヘクタールと、日本と同じ規模であり、小麦・玉蜀黍などの穀物や畜産物などは競合しておらず、条件が似ているので交渉がしやすく、まとめて交渉することも出来る。
農業分野に対する課題も大きく取り上げられているが、農産物市場へのアクセス問題はTPPの一つの問題に過ぎない。また農産物だけが被害を受けて、工業製品が伸びるかのような言い方をする人もいるが、TPPは24の分野における様々な政策領域が交渉の対象となる。
自動車や農薬の安全基準から、高額医療保険のあり方、移民規制、弁護士、介護士などの免許の問題、公共事業の入札条件等も対象となる。
これまでアメリカから対日貿易要望書という形で突きつけられてきた、幅広いサービス関連部門なども交渉の対象となる可能性がある。
TPPに参加して、とりあえずルール作りの交渉に参加しよう言い方もされているが、実際にどのような問題が発生するのか、政府が明確にしていないので、問題を喚起して国内論議を高めることが出来ない。
FTAと違って、条件なしで例外なき関税撤廃といった交渉条件となるので、普天間問題で見せた今の外務省・経産省に交渉能力があるとは、とても思えない。アメリカの言うがままになるのではと懸念される。
農業への影響も無視できない。よく、規模を拡大して日本の農業の国際競争力を付ければよいとの主張があるが、実情を完全に無視した議論だ。
そもそもアメリカは、1戸あたりの耕作面積は200ヘクタール位あり、オーストラリアにあっては3000ヘクタールだから、日本の平均1.9ヘクタールとは比べものにならない。農地法を改正して大規模化を図るといっても、虫食い状態に農地が拡大しても何の意味もない。
また、戸別所得補償を見ると、欧州は耕地面積の平均が50~70ヘクタールあっても農業生産額に匹敵するほどの戸別補償をやっている。カルフォルニア米は、玄米で1俵3000円程度、日本は1万4000円を基準として戸別補償を考えているので、これを埋めるだけで1~2兆円が必要となる。
政府はこれを負担する覚悟が出来ているのかということが全然見えてこないため、規制緩和で農業の競争力が高まる等と議論している人は、本当に農村に行ったことがあるのかとさえ思われる。
もう一つは、このままではデフレが加速し、農産物価格が下がり、あらゆる農業経営が影響を受けることは疑いない。民主党政権は、当初、安全・安心政策で非価格競争で輸出を伸ばそうと言っていたが、福島原発事故の放射能問題で、ほとんどの国が輸出制限を行っており、国内でも残念ながら消費者離れが起きている。この問題が解決しない限り日本の農作物の国際競争力の議論にはならない。したがって、汚染土壌の本格的除染とか食品の全量検査をきちんと実施するなどを優先することが必要だ。
このようなことを放置したままTPPを行うと、日本農業は壊滅的打撃を受けるのではないかと心配される。
まずは、原発事故の終息に全力で取り組むことが課題である。国の安全保障もエネルギーも海外に依存している状態で、さらに食料を海外に依存することになれば、日本は完全に米国の言うなりになってしまうのではないかと危惧される。
食糧問題は日本の安全補償でもあるから、ヨーロッパの国々はなぜ食料自給率が100パーセント以上なのかということを、平和ボケすることなくきちんと受け止めて考える必要がある。 |
大正12(1923)年9月1日11時58分44秒、伊豆大島付近、相模湾北西部の相模トラフを震源 とする海溝型大地震『関東大地震』が発生しました。
この地震はマグニチュード7.9、震度6の規模で、南関東一円を中心に、死者・不明者14万2,807名、家屋全半壊25万4千件余、焼失した家屋は44万千余、山岳部では山崩れが多数発生し、海岸部では津波が発生しました
東京消防庁による東京(当時は東京府)の被害状況は、焼失した家屋は22万1,718棟、焼損面積38.30平方キロメートル(東京ドームの約1,400倍の広さ)、死者6万420人、行方不明3万6,634人、傷者3万1,051人でした。
この9月1日を「防災の日」として関東大震災の教訓を忘ず、この時期に多い台風への心構えの意味も含めて昭和35年に制定されたものです。
また、暦の上では立春から数えて210日目を特に「二百十日」と呼び、台風が吹き荒れることに注意を促したしきたりもありました。
防災の日は、避難訓練などの災害時を想定した訓練をおこなう日として知られていて、「防災の日」が制定されるまでは、9月1日に行われる行事は、関東大震災犠牲者の慰霊祭が中心でした。しかし、「防災の日」が制定されてからは、全国各地で防災訓練が実施されています。
今回、35都道府県が行う訓練には、住民など51万人超が参加しています。都道府県など自治体には実践的な訓練が目立っています。
死者、行方不明者が2万人以上にのぼる東日本大震災は、発生から間もなく半年ですが、復旧・復興の道は険しいく、原子力発電所の事故が起きた福島県では、災害は、まだ現在進行形という状況が続いています。「災害列島」の日本は、地震や津波、水害など、どこでも自然災害と無縁ではいられません。今回の震災から教訓を学び、防災訓練などを通じて備えを強化する必要があります。
東日本大震災では緊急用通信網が途絶し、物資輸送も大幅に遅れました。今年の政府の総合防災訓練は首都直下型地震が発生したとの想定で、閣僚の安否確認や、関係自治体への物資輸送手段の確保・点検を重点項目に据えています。
家庭では、いざという時に備え避難場所の確認や非常持ち出し袋を用意しておくことが大切です。中身は一人で持ち出せる最低限のものを。また、一年に一度は必ず点検、電池やミネラルウォーター、缶詰などは古くなっていれば新しいものと交換します。
その他にも、災害直後には持ち出せなくても後々使用できるように水やインスタント食品を別にストックしておくと安心です。
最近は、非常に優れた防災グッズも販売されています。災害の恐ろしさを再認識し、日ごろの準備と心構えが大切です。 |
| 一貫性のない菅総理と新エネ法への突然の執着 |
平成23年07月03日 |
菅内閣発足以来の僅かな1年間の間に、菅総理は消費増税、TPP、税と社会保障の一体改革、大連立構想、新エネルギー法などと看板をめまぐるしく架け替えてきた。トップリーダーとしての一貫性のなさは際立っている。
また民主党内も、小沢さんという特異な実力者をめぐる党内抗争を繰り返し、今回の両院議員総会の雰囲気はギスギスし、同一政党としての連帯感はまったく感じられなかった。
これでは政権政党として東日本大震災や福島原発事故を抱えた国難を乗り切っていくことができるとは到底考えられない。
菅さんは自分の辞任条件の一つに「自然エネルギー普及法案」の成立を突然とも言えるタイミングで持ち出してきた。昨今の言動を見ていると、衆院解散総選挙を見据えているのではないかとさえ噂されている。
何といっても喫緊の課題である震災復興対策や原発放射能対策が、置き去りにされている感がする。
菅総理が突然の執着を見せた「自然エネルギー普及法案」について、朝日新聞のS編集委員が「身を引いて信の回復を」と題しての記事があり、共感が持てたので下記に紹介する。
『もはや限界を超えた。自分の顔を見たくないなら早く通せ。再生エネルギー促進という脱原発の明日に直結する法案について、最高権力者がこんな脅しめいたことを言い放つ国に住む不幸を私達は甘受せよというのか。
やっと東日本大震災の復興基本法は20日成立したが、政治の次の動きは鈍い。それもこれも、辞任の見返りにこの法案も成立させろ、あの予算もだ、と菅直人首相が条件闘争に走るためだ。
それは、熟議を旨とする議会制民主主義の根幹を踏みにじるものであり、出処進退をここまで軽く扱う首相もかってない。強調を損ねる乱暴な政治作法と事故の責任に無頓着な言葉の軽さ。それが菅政治の本質だ。
思い出そう。この一年、いかに首相が次々と乗る馬を換えたかを。消費増税、TPP(環太平洋経済連携協定)、税と社会保障の一体改革、大連立構想…。だが考えてほしい、どの課題も2大政党間で決定的な対立案件ではなかったではないか。
つまり、この国の首相がもっと謙虚で、冷静に丁寧に正確に手順を踏んで与野党の合意形成を育てていれば、幾多の課題処理が進んだ別の幸せな日本になっていたはずだ。
それを全面協力か、さもなければ「歴史に対する反逆行為」かといった対立図式でしか政治を動かそうとせず、結果、合意の芽を摘んだのが菅首相である。今また会期延長で同じ手口を使い、その先に「脱原発解散」まで想定しようというのだろうか。
脱原発を同じ運命に陥らせてはならない。今最も肝心なのは、電力不足はじめ多くの負担や不便を強いられる国民からいかに信を取り付け続けるか、その地道で真面目な政治の作法である。それは菅政治とは逆の道だ。
震災復興へ、貴重な今この時が刻一刻と無為に消費されていく。一日も早く、首相退陣を契機に、信なくば立たずの政治へ局面をはっきりと転換することが、与野党に課せられた共通の責務である。』
菅さんがこの1年にめまぐるしく架け替えてきた看板で、国会で慎重審議されてきた議案はあったのだろうか。3月11日に発生した東日本大震災より4ヶ月が経過しようとしている。震災対応の遅さは政権の態を失ってしまっているのではないだろうか。
|
平成23年3月11日に発生したマグネチュード9.0の東北太平洋沖大地震は、未曾有の津波が発生し、東北と関東の一部に甚大な災害を引き起こし、現在もなお広範囲にわたる個所で発生する余震や誘発地震が毎日のように報じられている。
また、この地震や津波により、福島の原子力発電設備が被害を受け、電源の手当てができないまま冷却水循環設備作動せず、放射能の拡散問題は地震・津波と共に大震災の主要事項となり、まさに「東北関東大震災」となった。
この震災の影響で、東北電力及び・東京電力管内の発生電力が落ち込み、他の電力会社からの融通電力も一割に満たず、災害により消費電力がー落ち込んでいるにも関わらず、計画停電の実施を余儀なくされている。
特に西日本からの融通電力は、富士川を境にした周波数の違いにより、境界点に設備された2か所の周波変換設備も最大5万キロワットのみにとどまっているため、強力な助っ人とはなりえない。
日本における原子力発電は、総発電力の40%を占め、将来としては50%を目標としていただけに、今回の原発事故が、今後の原発行政にもただならぬ影を落としていることを考えると、総合的な電力計画の再構築が必要である。
電力を発生する発電設備としては、水力発電・火力発電・原子力発電、それに最近台頭してきた新エネルギー発電に大別される。
日本においては、大規模水力発電の開発ポイントは少なくなり、火力発電は環境問題から敬遠される立場にある。今後原子力発電が敬遠されるようになれば、残すのは新エネルギー発電ということになる。
新エネルギー発電としては、風力・小水力・太陽光発電等が考えられるが、いすれも小規模施設で、しかも開発途上で、時間の問題があって大電力を賄うには程遠い。
今後の電力行政で、原子力発電の占める比重が期待されていただけに、将来の展望は大きく変更せざるを得なくなった。現政権は「コンクリートより人へ」の掛け声のもと、ダム建設が大きく見直されようとしている。この災害を契機に、方針の再検討をする必要性を痛感するのは私だけだろうか。
熊本県としても、建設計画途上でストップされている川辺川ダム、ダムの撤去が決まっている荒瀬ダム等のクリーンエネルギー水力の利用も、将来のエネルギー構想の中では、再検討する必要があるのかも知れない。もっとも国民の電力消費に対する意識改革も必要だろう。
|
平成23年度予算案が1日未明に衆議院議員を通過した。これで、少なくとも3月末には自然成立が確定した。しかし関連法案の行方は不透明で、関連法案の中でも赤字国債を発行するための公債特例法案が最も核心となる。
赤字国債を発行する場合は、一年毎に法案を国会に提出し、成立させる必要がある。野党は民主党のマニフェストを守るためのバラマキ法案には一貫して賛成できないとしているので、この法案が国会を通過しない場合はどうなるのだろう。
本予算案自体が参院差し戻しで成立しても、関連予算が通過しなければ、全体予算の約45%を赤字国債で賄っているので、予算執行が難しくなる。
その結果、これまでに経験したことのない未知の世界が待ち受けており、国民生活にはどのような影響が出てくるのだろうか。
景気はどうなるか。産業・経済への影響、地方自治体も国の予算に依存しているところが大きいし、福祉・医療、それにマーケットの反応次第で株価や為替への影響もある。また公務員の給料の支払いにも関係してくるだろう。
論客の中には、国民生活が滅茶苦茶になるという人がいるが、大した影響はないという人もいる。
しかし、国は急場凌ぎのために政府短期証券(国債)を年間20兆円までは発行できるので、6月から8月頃までは何とかやっていけるだろう。
ある人の言葉を借りれば、このような事態により、国民が我慢して不便や痛みに耐え、どこまでやれるのか。未知の世界の社会実験とさえいえる。万が一にもこれが成功すれば、国の赤字体質を改める一つのきっかけになるかもしれない。しかし、失敗すれば国民の怒りを買い、その矛先は政権与党、野党、あるいは政治家に向けられることになる。
2年前の政権交代の時期から、日本の政治は大変動の時代になってきているから、何でもありきの時代だとの覚悟が必要なのかも知れない。
|
菅内閣で2回目の党首討論が23日に開かれた。「国民生活への影響」を避けるため、「ねじれ国会での野党の責任」を強調し、法案成立への協力を求めたが、自民・公明との溝は更に深まった感じだ。
菅首相は引き続き協議を呼びかける姿勢を崩していないが、政権内からも退陣論が噴き出す中で、党首討論を繰り返すことへの批判も出てきている。
民主党マニフェストの破たんと党内意見の分裂、政権維持能力の崩壊、民主党内の会派離脱問題は、党内体制の立て直しは至難であるから、早期の解散総選挙を実施し、その結果で与野党を超えての衆智を集め、国内外の難局に対峙することが必要でないか。
民主党の内紛等を見ていると首相延命のための責任逃れに思われてならない。
22日の小沢民主党元代表に対する党員資格停止処分の決定に反発してか、松木農水政務官が辞表を提出し、衆院議員16名の会派離脱届の提出に続きいて、党内対立の深刻化が浮き彫りになってきた。
また、小沢氏に近い民主党の原口元総務大臣なとの「日本維新の会」の立ち上げが発表されており、勉強会には約50名の人が終結するなど、党内の亀裂は拡大の様相だ。
日本の財政再建が掛け声だけで一向に進まぬ上、数多くの難題を抱えている。現在の政権では、誰しもがこれらの問題の解決には疑問を持っているだろう。
このまま、だらだらと政権が運営されるより、思い切った政権の交代をするほうが、国民の利益につながるのではないか。
|
米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズが日本国際の格付けを引き下げた。日本の財政に対する国際的な信用を示すものだ。
日本は世界最大の債権国でありながら、日本の国と地方の債務残高は、国内総生産(GDP)の200パーセントを超えて、主要先進国の中では突出している。ここで、日本国債の95パーセントが国内で消化されているのが強みだが、長期的に見ると急速な高齢化で、社会補償費が急増する一方、デフレでの資産の目減りや、貯蓄者層の若年化による貯蓄率の低下傾向などを考えれば、国内投資家が日本国債を見限ることも考えられる。
さらに格下げ理由の中に、日本の政治状況が取り上げられている。ねじれ国会のもとでの政治状況は厳しく、新年度予算案の関連法案が成立しない可能性すらある。この懸念が国債の格付けに響いている。
格下げについて聞かれた菅首相は「そういうことには疎い」と発言、ほぼ関心のなさを露呈し、枝野官房長官も「民間調査機関の発表だからコメントしない」と政治家としての危機感すら感じられない。
日本の財政再建が掛け声だけで一向に進まぬことへの警鐘で、日本政府の財政運営に対する不信感が、この格下げの原因ということを肝に銘じてもらいたい。
『内閣府が31日発表した09年の国民経済計算によると、国や地方自治体を合わせた「一般政府」が持つ土地や建物、株式などの資産から、国債などの負債を差し引いた「正味資産」は、09年末には前年末より54.9兆円減り、48.8兆円のマイナスになった。』
国債の大量発行が主因で、「埋蔵金」などを取り崩したことも原因だ。 日本国債や地方債を合計した約1,018兆円の債務。この政府部門の1,000兆円を超える債務は国民が銀行等に預けている預金である。
今のところ財政状態が深刻なのは政府部門だけで、家計部門は資産超過となっており、当面の影響は少ないが、長期的に見ると問題が大きい。
銀行や生損保などは全部ではないが、こうしたお金の大半が日本国債で運用されていると考えると、日本国債がデフォルトすると国民の預金や保険も無価値となる。、日本政府は使える金額までほとんど使ってしまっていて、後が無い状況ということが今回の国民経済計算から推察される。
消費税などの税率を少々上げても駄目だという人もいる。下手に増税しても駄目なら預金封鎖して、最後はインフレで国の借金を帳消しにする事だって考えられる。こうなれば我々の貯金はゼロになるといった恐慌時代が来る。
今年は国民受難の年だという人がいる。自然現象だけを見ても日本海地域の記録的降雪、霧島の新燃岳の爆発的噴火と空振、鶏インフルエンザの猛威等があるが、政局の混乱も国民に直接の影響がある。
菅首相の国会所信表明演説は、年頭所感を少し肉付けしたものの域を出ず、新聞各紙は「実現にはかなり困難がある」と報道している。野党との摺り合わせをどうするか、与党内でも足並みが揃っていない。予算案についても最初から増税ありきの提案であり、小沢と金の問題を抱えている。さらに野党は解散総選挙へ持ち込む方針を変えていない。
|
24日召集の通常国会へ向け「最強の態勢」を目指した菅直人首相。その核となるはずだった「仙谷由人官房長官続投」を断念し、第二次改造内閣が発足した。
新内閣の顔ぶれを見て驚いたのは、ついこの前まで自民党の重要ポストを占めていた与謝野氏が入閣したことだ。ずいぶんと民主党の政策を非難し、この党をつぶすために新党まで立ち上げた人だ。このような人にまで頭を下げて入閣を頼んだのでは、今後ますます自民党の政策に回帰してくるのではないか。
また、新閣僚にベテランの藤井官房副長官や江田法相が入閣、菅内閣が高齢者に頼らねばならぬ人材不足の現状を露呈し、ある野党党首からは「国会対応内閣」だとか「廃材内閣」などと揶揄されている。
朝日新聞の社説の中に『登山をしていて「輪形彷徨」に陥ることがある。道を失って同じところを歩き回ることで、体力を消耗して死につながる。民主党の政治も似ていよう。歩いても歩いても「小沢山」「マニフェスト谷」「ねじれ峠」…と同じ地形が悪夢のように現れてくる。(中略)早く稜線へ出て、新しい地平を見せてくれるのが、何をおいても政治の使命だろう』とあるが、同感である。
政権の最優先課題は何なのか。国民に方向性を明確に示し、理解を得るための丁寧な努力が必要である。
なお、残されている小沢氏の「政治と金の問題」、この問題を早急に処理しない限り火種はいつまで残り、政治の不安定な状態は続きそうだ。
|
景気に大きな影響を持つ海外経済を見ると、先進国の低成長に対し新興国や開発途上国の高成長といったパターンは今年も変わりそうにない。アメリカの回復力は鈍く、ドル安傾向も続くだろう。
EUも財政破綻が囁かれている国が燻っており、各国とも財政再建に懸命で、景気への配慮が弱い。一方新興国などは景気がよいが、インフレへの懸念から政策金利を上げる方向へ進んでおり、政策の中心をインフレ対策にシフトしてきている。
個人消費が景気を持ち上げるためには雇用が回復し、支払い賃金の総額が増える必要がある。企業の3月期決算は、円高の中でもまずまずの成績が残せそうだが、内部留保と設備への対応が中心で、賃金の方までは廻りそうにもない。
日本経済の構造的課題として、人口減少・高齢化は世界に類を見ないほどのスピードデ進行しており、各先進国からも注目されている。人口減少による産業構造の衰退に対しては、生産性の向上、技術革新、外国人労働力の受け入れなどが論議されているが、どういう風にこれを選択し、具体的に実行し、効果を上げていくことが肝心で、日本はまだ議論の段階で、結論が出たいない。早急に手を打つ必要がある。
日本の財政赤字は、先進工業国の中では最悪の水準にある中で、急速に進む人口高齢化に耐える年金等の社会保障制度の改革が必要だが、財政が火の車では何もできず、社会は安定しない。
TPPへの加入問題や財政再建問題も同じことで、議論し、結論を出し、実行に移すことが求められている。
リーマンショック以前のアメリカ経済は、浪費により経済成長を求めるものであった。これはもはや通用しなくなった。これからの日本を含めて世界が必要とするのは、節約と成長が両立する経済構造が必要だ。具体的なものとしてはデンマークの例などが挙げられる。
財政赤字に関連して、消費税の増税議論が出ているが、今の赤字の補填のための方策としての議論が先行しており、日本の社会の在り方に対する基本の議論がなされていない。
一昨年の政権交代以来、政治は未だに何も生み出していない。この状況こそが問われてしかるべきではないだろうか。
現政権等の民主党が掲げたマニフェストは、国民の間から多くの問題が指摘されている。これを一応白紙に戻し、現実を踏まえ将来を見据えた指針を新たに確立すべきではないかと思う。また、勢いよく官からの脱却を叫んだが、やはり官僚制度の優れた点を活用するだけの度量が必要だ。
おりしも西岡参議院議長の文芸春秋への投稿文に関する、記事が、朝日新聞(7日付)に掲載されたので下記に紹介しておこう。
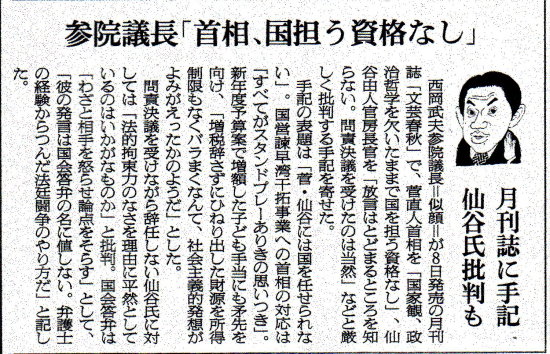
|
世界的な金融危機を招いたリーマンショックが発生した2008年の9月から2年以上が経過した。最も影響を受けた日本も、経済的に一応の立ち直りを見せたかに思えるが、最近の政治不安定は我が国の経済危機を推し進めている。
政権の急激な支持率の低下は何を意味しているか。政権基盤が揺るぐ中、政治状況の変化は、従来型の政治手法への回帰が始まっている。
現政権は内需拡大政策への転換を民主党の政治姿勢と位置づけていたが、かろうじて景気を引っ張ったのは輸出が25%と伸びたためで、国内需要は逆に7%と減少している。即ち内需はマイナス成長であった。今なお賃金の下落傾向は続き、その政策の中実を含めてストップする気配も見当たらない。
菅総理は、環太平洋パートナーシップ協定「TPP」参加をにらみ、農業再生のための農地の集約化が大事だといっているが、民主党政権が導入した農業所得補償制度が、農地の「貸しはがし」をはじめ集約化を阻み、TPP導入に完全に逆行する現象が各地で起きている。
政府は2010年12月16日、臨時閣議を開き、2011年度税制改正大綱を決定した。民主党政権になって2回目の大綱は、法人税実効税率を5%引き下げる一方、所得税の控除見直しなどで個人税を増税するのが最大の特徴となっている。
デフレ脱却を目指し、企業優遇による経済成長を優先させるとともに、富裕層への課税強化という形での「格差是正」という政権の姿勢を前面に出した形だが、子供手当の財源確保などを含め、目先の数字合わせに四苦八苦し、「高額所得者など取りやすいところから取るろうとしただけ」との批判もある。
今回の法人税、個人の控除縮減、環境税創設などは「税制の常識では、それぞれ数年がかりの議論が必要な『大玉』のテーマであり、これに大胆に踏み込んだ形だが、実際には法人税率を5%下げるとしていても、財源の捻出のための各種優遇措置の圧縮のため、減税規模は限られたものとなり、経済効果は乏しいという失望感すらある。
「帳尻合わせは限界だ」「財源手当はどうした」といった声は大きい。専門家からも「控除見直しは子ども手当の財源を生み出すためという動機が不純」(朝日)、「理念がないままとりやすいところから取ることに終始」(読売)などの酷評が目立つ。
こういう現状や高齢者社会の進展、拡大を続ける社会福祉費の安定財源としても、消費税が最大の論点となってもしかるべきであ。老後に心配のない安心感のある、不平等感の少ない社会を作れば、消費は伸びるという他国の実例もある。
社会補償制度と消費税の一体改革が必要なのは当たり前で、政府は11年度から社会保障制度と消費税を含めた税制抜本改革の議論を本格化させ、11年半ばに抜本改革案をまとめる方針を立てていいるが、ねじれ国会で11年度改正の関連法案の成立の保証さえなく、民主党内の政争の激化で菅政権の基盤が一段と不安定化する中で、「不人気の消費税増税に踏み込むのは無理ではないか」との悲観論が早くもささやかれる。
政府は昨24日に臨時閣議を開き、11年度政府予算案を決定した。予算全体の規模を表す一般歳出総額は92.4兆円で、10年度当初予算(92.3兆円)を上回り、過去最大規模を更新する。民主党政権として初めて概算要求基準の段階から策定した予算案で、菅内閣は6月に策定した「新成長戦略」を本格実施するための予算と位置づけている。
しかし、税収の落ち込みが長期化する懸念がある中で、充分な財源の裏づけがないままに政策を一杯に詰め込んでいて、財政の硬直化を招く構図は来年度も変らないようだ。しかも2年連続して国債の発行額が税収を上回る異常事態が続き、このままでは国の借金があっという間に膨らんでいくことが危惧される。
財政赤字の膨張に歯止めがかからねば国民生活の基盤が根底から崩れ、民主党が掲げる生活者の視点に立った政策は実現不可能である。 |
菅総理がTPP加入問題を「平成の開国」と表現し、自由貿易は絶対的に正しいということを前提としているようだが、果たしてそうなのだろうか。
比較生産費という考えから自由貿易は正しいと教えられることが多いが、これまでは自国の保護貿易の立場から、国の競争力がついてから自由貿易に移るということが一般的であった。
自由貿易は極端に言えば弱肉強食の世界であるから、国際競争力のある国が断然有利で、これから産業を育成しようとしている国は、丸裸にされ不利になる。自由貿易による得失は、発展段階の異なる国の力関係を表しているというという認識が必要だ。日本も同じプロセスをたどってきている。
これまで、日本の輸出入の相手先として米国との関係が引き合いに出されることが多かったが、いつも対米交渉のたびに農業が保護主義の槍玉に挙げられていて、日本の農業は裸同然にされているというのが実態で、日本農業は衰退の道をたどっていると言えるのではないか。
TPPは農業以外にも重要な問題が含まれている。余り議論されていない分野で、労働市場の開放、移民労働者の受け入れなどがある。現況でもアメリカが参加できない日本の市場そのものが不公正だとして、制度そのものをアメリカに揃えろとか、アメリカに市場を割り当てろといった強引な要求が目立っている。
いまや、世界は輸出入貿易の構図が変化してきている。米国経済の衰退、中国経済の台頭、EU経済圏の混乱、東南アジアの隆盛など、国際情勢は大きく変ってきている。
WTOという国際自由貿易が実現できないでいる中で、ブロック経済の現代版とも考えられるTPPは、自由貿易という名を借りて市場の囲い込み競争をしているだけで、新しい自由貿易体制とはなりえないのではないか。
最も強い国が、率先して貿易を開き、強い産業での一定の例外規定を認めるような国際的な貿易体制ができてこないと、経済的発展はありえない。例外なき撤廃を求めているTPPは、おそらく新しい自由貿易体制をを築く基礎とはなりえないのではないか。
本当に自由貿易は日本の利益になるのか、アメリカの国情から対日要求が高まり、日本は犠牲だけになるのではとの懸念もある。特に世界は激動期に入っている。北朝鮮を取り巻く情勢を含めて広く熟慮が必要だ。
|
| 「尖閣ビデオ問題」と「外交」 |
平成22年11月14日 |
9月7日に海上保安庁の巡視船に中国の漁船が衝突した時のビデオを一般公開するかどうかは、世論の対立した問題点だろう。
菅内閣は、公開しない方針を採ったが、野党の要求に抗しきれず、11月1日に衆参両院の予算委員会の理事に限定して6分50秒に編集したビデオを公開した。
ところが11月4日の夜、インターネットで衝突ビデオが44分間流れ大騒ぎとなった。しかも11月10日になり、このインターネット上にビデオを投稿したのは神戸海上保安部の海上保安官が、自分であることを認めたので、菅内閣は一層の窮地に陥いることになった。
マスコミ各社は、尖閣ビデオの公開に積極派と慎重派に分かれていた。各社の論調を見ると「菅内閣は、情報を隠蔽した非を認め,直ちに政府の手ではビデオを全面公開すべきだ」から「政府は時期を見て公開すべきだ」と入った意見になっている。
菅内閣がビデオを実質的には一般公開されてしまったにもかかわらず何故一般公開しないのか。その理由として、この事件で悪化した日中関係に配慮してのことだろうが、毎日新聞は11日の署名入記事で「菅国民外交の虚構」とし、「衝突事件でまずくなった日中外交で、仙谷官房長官が外務省を通さずに北京に送り込んだ民主党議員団に、中国側は関係改善の条件として、衝突映像の非公開と沖縄県知事による尖閣視察の中止を求め、日本側はこれを受け入れ、10月4日偶然を装ったブリッセルでの日中首脳の接触につながった」としている。
したがって「北京での結果は、菅内閣を現在でも拘束していると考えるのが自然だ」としている。
これでビデオが一般公開されない理由に納得がいく。
さらに「日中の互恵関係が、死活的な互恵関係である以上、相手の国民感情を悪化させないよう映像公開を見送るという外交手段は成立つ」とも言っている。
問題は、政府が国民の前で公開の利益、不利益を比較比較して国民の理解を得る努力をしたかどうかにあり、間内閣は「その努力を怠っている」と談じている。
菅内閣が国民外交を看板として掲げても、名ばかりで実質が伴っていないことを、海上保安庁をはじめ外務省や検察庁の職員は見抜いている」と続けている。
民主党は政治主導、官僚政治の打破と威勢がよいものの、実際は官僚を凌駕するだけの力量を備えていないので、官僚に見透かされているだけでなく、国民からも見放されているようだ。
その結果、8日の世論調査では菅内閣の支持率は35パーセント、不支持率は55パーセントとで支持率を大きく逆転した結果が発表されている。
横浜で行われたAPECにあわせて行われた米・中・ロとの首脳外交、菅総理はその成果を誇示しているが、日米・日中・日露ともに難しい問題が残されており、今後の外交は容易ではない。 |
| 「農家戸別所得保障制度」と「TPP」 |
平成22年11月04日 |
民主党政権の目玉政策として始まった農家への戸別所得保障制度は、夏の猛暑による品質低下やコメ余りに伴う価格低下に加え、制度の分は安くして欲しいという卸売業者からの要求圧力もあり、「ここまで米価が落ちたのは戸別所得保障も原因だ」と苦い思いをする農家も多い。
これまで農業政策として進められていた耕作地の大規模化による農業経営の合理化は、戸別所得保障により農業の大規模化からの逆行が始まっており、将来の農家の弱体化に向かって進み始めている。
一方、最近急速に議論が高まっているTPP(環太平洋パートナーシップ協定)は、環太平洋における戦略的・経済的連携協定のことで、自由貿易協定を結ぶことにある。
TPPは、菅首相が「消費税」発言に続く、10月1日の所信表明演説で、「TPP交渉参加を検討」と言明して世間を騒がしているが、民主党内部でも議論が別れている。
TPPは、多国間のすべての品目について関税を撤廃するのが原則で、これまで2国間協定などで交わされた例外規定は認められない。したがって日本のように農産物に高い関税をかけて国内産業を保護していた場合、安い農作物が輸入されると農家は深刻な影響を受ける。ある機関では、価格の低下に加え安い輸入品の増加で国内自給率は、現在の41パーセントから14パーセントまで落ちるとの試算もある。
その他、TPP協定に加盟した場合には有利になる分野も多く、農業のほか24の分野がある。また、金融や労働市場の開放、公共事業などの開放が必要になる。
いずれにせよこれからの農業に求められるのは、国内はもとより国際的にも競争力をつけることが
必要で、戸別所得保障ではこの問題は乗り切れない。
今後十分な検討が必要だが、2日の熊本県議会では臨時会を開き、TPPについて「日本の農業と地域社会を崩壊させる」として、全会一致で参加表明に反対する意見書の案を可決、「農業振興や食料安全保障を十分考慮」し、慎重に対応するよう政府に対して求めた。 |
| 「柔道内柴選手」現役選手生活から引退 |
平成22年10月23日 |
オリンピック男子66キロ級柔道で2連覇を達成した金メダリストの内柴正人選手が、10月22日に正式に引退を発表、今後は後進の指導に専念することになりました。
高木けんじは、内柴選手のアテネオリンピック出場が決まった2004年当初より後援会長を引き受け、オリンピック現地にも応援に出かけ、内柴選手も高木けんじの選挙応援に駆けつけてくれていました。
朝日新聞の10月23日付紙面に関連記事が出ていましたので、紹介しておきます。
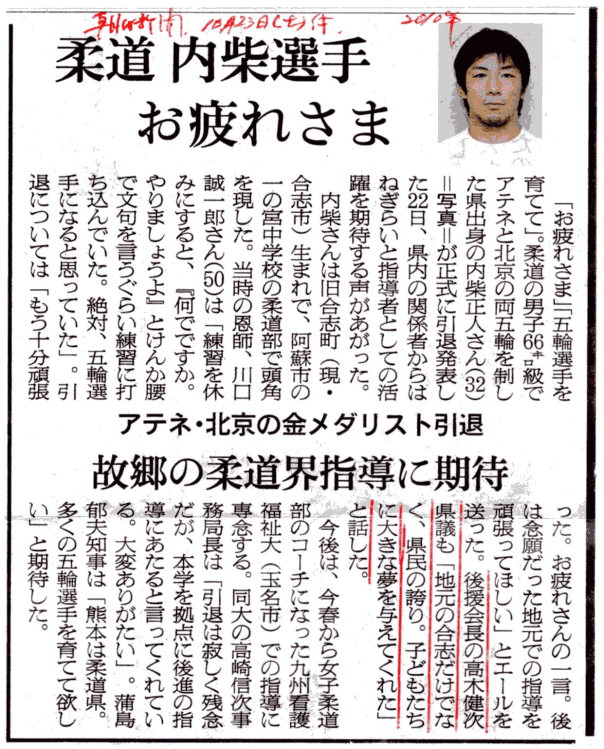
|
| 「小沢氏のけじめ」新聞記事より |
平成22年10月12日 |
検察審査会で強制起訴が決まった小沢氏、その後の一連の氏の発言について報道各紙は一斉に、批判のコメントを出していたが、10月8日付けの朝日新聞の社説では
「民主党はこれでいいのか]という記事が掲載された。
小沢氏の政治的けじめは強く求めなければならないとし、最低限、離党勧告か除名をすることが必要だとしている。
社説に共感を覚えたので、この社説の前文(一部)について関連記事に内容を記載して見たい。
関連記述(朝日新聞10月8日社説より)
菅直人首相と民主党は小沢一郎元代表に対し、政治的なけじめを強く求めなければならない。証人喚問に応じるなど国会での説明を促し、離党勧告か除名をする。最低限、それが必要だ。
小沢氏はきのう「政治活動は淡々と続ける」と述べ、離党も議員辞職もしないことを明言した。真相解明は[司法の場に移っている」とし、国会での説明にも前向きと言えなかった。
検察審査会の議決で強制起訴は決まったが、公判の行方は予断を許さない。しかしながら小沢氏には、自らの政治資金をめぐる問題で元秘書ら3人が逮捕・起訴された時点で、すでに極めて重い政治的な責任が生じている。
鳩山由紀夫前首相とともにダブル辞任に追い込まれたのに、わずか3ヵ月後に党代表選に立ち、多くの国民を驚かせもした。一連の政治行動に、選良としての節度を見ることはできない。
有権者の期待を裏切らず、歴史的な政権交代の意義をこれ以上傷つけないためにも、強制起訴決定の機会に議員辞職を決断すべきだった。
今後、法廷で闘うということだが、そのかたわら国会議員の重責を果たせるとは到底考えられない。
……中略……
小沢氏が自らけじめをつけないというなら、これから厳しく問われるのは菅首相と民主党の対応である。
……後略……
|
まず貿易について考えてみよう。昨年の日中貿易の収支は、日本は中国に対して1兆2千億円の輸入超
過の状態で、日本の企業も輸出によって中国の産業を支えているとなっているが、中国のほうが日本に対しては輸出超過となっているのだ。すなわちギクシャクすれば中国も、非常に傷つくことになる。
次に人の動きを見てみよう。昨年日本人が中国を訪れた人は332万人、中国人で日本にやってきた人は101万人で、今年の上半期の入国者は対前年比で40パーセント増えているが、これが50パーセント以上増えたとしても150~160万人だろうと言われている。報道などで中国人の来日が非常に増えていると思われているが、これでもはるかに多くの日本人が中国を訪問している。
互恵関係とは、冷静にお互いが考えないといけないだろう。
もう一点、尖閣問題について考えてみよう。尖閣問題は日米安保の対象にはならないのかとの議論が
出た。日米で連携して中国に対峙するという構図で、結局日本を守ってくれるのはアメリカだとして、ひとつの方向性がとられようとしているが、注目しておかねばならぬ事は、米国と中国の関係である。
考えている以上に米中関係の密度は濃くなっている。例えば昨年の日米貿易は1469億ドルだが、米中貿易は3659億ドルという数字が出ており、日米間の2.5倍もの数字になっている。また、昨年アメリカから日本を訪れた人は70万人だが、米国人として中国を訪れた人の数は171万人となっている。日本より100万人も多い人が中国を訪れたことになる。 |
| 民主代表選終わり、政権の行方は? |
平成22年09月18日 |
民主党の代表選挙が始まった。新聞各誌は小沢氏の候補資格について論じ、今回の選挙ほど候補者の資格・適格性が問題となった事は無かったと報じている。
3ヶ月前に政治資金問題で責任を取って辞めた人が何故だ。党自体がこういう人を担ぎ出すとは、開いた口が塞がらないとした新聞も複数あったようだ。
関連記述
今月1日より民主党の総裁選挙が開幕、14日には結果が出されるが、今回ほど候補者の資格、適格性が問題となった例はなかっただろう。
新聞各誌は、小沢前幹事長について、再び小沢氏を担ぎ出す民主党には開いた口がふさがらない(産経・朝日)。わずか3ヶ月前に政治資金問題で責任を取って辞めた人物が、何故だ!!毎日や日経も同様の疑問を掲載している。
しかも、候補者の適格性にまで踏み込んで、「不適格、あるいは適格性が問われる」として各誌は揃って論じている。
小沢氏は、検察審査会の結果によっては強制起訴が行われることもあり得るとして、疑問が投じられ、はたして小沢氏でよいのかという、小沢氏の適格性を最大の焦点とする論調が多かった。 |
| 本世紀は、災害多発世紀か? |
平成22年09月01日 |
9月1日は[防災の日]、関東大震災の発生日を防災の日したものだが、以前は台風襲来の特異日で「二百十日」という言葉の印象が強かった。
今年は梅雨明け以来記録的な猛暑で、8月末になっても各地で猛暑日が続き、熱中症での死亡者も大勢出ている。
世界全体を見回しても異常気象と大規模災害が多発している。
まさに異常気象が世界を覆っている状態だ。
関連記述
今年今年の月日の梅雨明け以来、全国的な猛暑に見舞われ、気象庁観測開始以来の最高気温が各地で発生している。南に位置する九州が暑いという常識は崩れ、東海地方、関東地方、それに東北・北海道までが記録更新している。
高齢者を中心に熱中症で死亡する人が増え、就寝中に倒れる人も多い。
一方、世界を見回すと、ヨーロッパの東部からロシアの西部にかけて記録的な猛暑、永久凍土地域の泥炭にも火が着き、森林・泥炭火災の広がりを受け、ロシアのモスクワ州など被害の大きい中部の七つの共和国・州では非常事態が宣言された。
パキスタンでは大規模洪水災害が発生、死者は1400人以上で、一ヶ月を過ぎようとしている現在でもまだ収束していない状況である。
中国の吉林省と新疆ウイグル自治区では洪水被害が発生している一方で、内モンゴル自治区では大規模な干ばつ被害に見舞われ、さらに南方の複数の地区では気温37℃以上の猛暑が続いた。
また、甘粛賞では土石流の土砂が川を堰き止め、川の水が街にあふれて大災害になり、死者・行方不明者は1500人以上が出ている。その後雲南省・四川省あたりでも大雨による洪水が起きている。
一方、現在真冬に当たる南半球では、記録的な寒波に襲われ、南米のペルー・チリ・アルゼンチンなどでは氷点下の日が続いており、死者も出ている。ペルーの南部あたりでは、気温が零下24度位まで下がってしまい、アルゼンチンでも低体温症で死者が出るという状況が続いている。
最近の気候変動を見ていると、今年だけでなく、大きな流れの中のターニングポイントになっているのではないかという危惧さえ感じられる。
|
| 株安・円高・GDP減速が日本を覆う |
平成22年08月21日 |
景気持ち直しの動きに、冷や水を浴びせたような動きが相次いでいる。政府は追加経済対策を検討しているが、果たして有効な手段が打ち出せるのだろうか。
6月期のGDPはかろうじてプラスというが、これも実質変動率であって、名目変動率で見た場合は既にマイナス成長となっている。
関連記述
現状は、円高が円高を呼び、長期金利も1パーセントを割った。これは国債に金が集まっているための現象で、政府も目先だけの八方美人的な施策に偏っている気がしてならない。
景気浮揚対策には、必ず財政出動が必要で赤字が膨らみ、国の借金は金利の支払いだけでも莫大な金が必要となる。将来の国民の負担を減らすための方策としては、支出の削減に努め、大増税を行う必要があるが、景気に悪影響を与えるなど非常に難しい。
誰しもが目先の景気にとらわれがちちだが、将来の国民のためを考えれば、景気が悪くなることも覚悟の上で財政再建をやらざるを得ないのではないだろうか。
おりしも民主党の代表選挙が近まり、政権党は内輪の権力争いに終始し、日本の危機的状況への対応が二の次にされている。
これからの秋から冬に向けての日本経済の行く方には、国民は注意深く見守る必要がある。 |
中国の10%にも及ぶ経済成長が、世界経済を牽引していると、よく報じられているが、10%は都市部に限った数値で、地方はゼロ成長であって全体では3パーセント程度だという人がいる。
中国が発表する数値に世界が踊らされているとしたら、今後の世界はどうなるのだろう。
関連記述
現状は、円高が円高を呼び、長期金利も1パーセントを割った。これは国債に金が集まっているための現象で、政府も目先だけの八方美人的な施策に偏っている気がしてならない。
景気浮揚対策には、必ず財政出動が必要で赤字が膨らみ、国の借金は金利の支払いだけでも莫大な金が必要となる。将来の国民の負担を減らすための方策としては、支出の削減に努め、大増税を行う必要があるが、景気に悪影響を与えるなど非常に難しい。
誰しもが目先の景気にとらわれがちちだが、将来の国民のためを考えれば、景気が悪くなることも覚悟の上で財政再建をやらざるを得ないのではないだろうか。
おりしも民主党の代表選挙が近まり、政権党は内輪の権力争いに終始し、日本の危機的状況への対応が二の次にされている。
これからの秋から冬に向けての日本経済の行く方には、国民は注意深く見守る必要がある。 |
11日の参議院議員選挙の結果は、自民党が大敗した先の参院選とは対照的に政権党の民主大敗で幕を下しました。
衆・参の捻じれ現象の再発、近年は二大政党論が囁かれていましたが、民意の多様化と小政党の乱立に加えて民主党の内紛で、政界再編成の動きを予測する人も多く、政局の混迷が深まりそうです。 |
7月11日の参議院議員選挙が迫り、最重点選挙区として熊本にも各党の党首クラスが応援に駆けつけています。
自民党も谷垣総裁が来県、光の森でも大勢の支援者の前で応援演説が行われました。 |
|
|
|
| 米国経済危機対策と日米関係 |
平成20年10月05日 |
米国のリーマン・ブラザーズの破綻から急速に広まった深刻な金融不安を背景に、全世界にも証券や銀行にも飛び火し、記録的な株安が広がっています。
米下院は現地時間の3日午後、上院が1日可決した緊急経済安定化法案(金融安定化法案)の修正法案を賛成、反対の賛成多数で可決しました。
下院は9月29日の採決では否決しましたが、上院が預金者保護の充実など修正を加えたため、今回は可決に転じたものです。ブッシュ大統領が同日署名し、法律は成立しました。最大7000億ドル(約74兆円)の公的資金で金融機関から不良資産を買い取り、金融安定化を図る政策がようやく動き出す事になります。
この法案をめぐっては、米国民から「税金による金融機関の救済」との批判が高まり、下院は9月29日に行なわれた採決で、賛成205、反対228の反対多数で否決したことにより、同日のニューヨーク株式市場が過去最大の下げ幅を記録するなど、世界の金融市場に衝撃が走りました。
これを受けて、上院が預金者保護を充実させた修正法案を可決。下院でも、再度の法案否決は世界的な経済危機を引き起こしかねないとの考えが広がった上、ブッシュ大統領が前回採決で否決した議員に対し賛成するよう説得したため、58人が反対から賛成に回って、やっと可決したものです。
しかし、米国の多額の負債をベースに荒稼ぎする投資銀行の錬金術は、完全に破綻したのではないでしょうか。信用膨張で国民は収入以上の消費を享受してきたが、今後は許されなくなるのでは?
これらの一連の経過を見るとき、なぜ最初の議会で否決されたのかとの疑問がわきます。国民からの批判は、もちろん多額な税金が使われることにありますが、その他に金融証券業界が、役員・従業員に男女を問わず破格の年俸を払い、1億円を超す巨額の報酬を多くの人が得てきたウォール街に対する国民感情が根底にあります。
一方、これらの経過に対する日本のマスコミの論評では、世界的な恐慌を誘発する米国の身勝手な対応に、揃って批判的でしたが、これまでの世界の動きに対する米国の態度を見ているとき、「自国優先主義」が目立っています。身勝手だとさえ思えます。
米国との同盟関係を堅持している日本にとって、何事も米国追従している現状で、一旦緩急の事態が生じたときに、自国の利益のみに終始し、果たして日本を救ってくれるのか疑問にさえ思えます。
いずれにしろ、即効性の妙薬は見当たらず、金融不安の収束は、当分の間は見通しが立ちそうにもありません。
|
農薬やカビで汚染された輸入米が、工業用の使途を逸脱して食用として全国で流通し、大問題となっています。一方国内では減反政策まで取られており、米余りの状態なのに、なぜ輸入するのかとの疑問をもたれると思います。
減反政策とは、「米余り」に対処するため、米の生産を抑制し、その分の水田でコメ以外の作物を作るという生産調整を政策的に実施することにより、過剰供給を防いで米価の安定を図り、消費者の安定した生活を守ることを目的とした、農業・経済政策です
1970年頃から本格化し、現在に至っていますが、最近、減反政策の見直しに触れる政治家も出ています。
農民は、自分達が生産した米が捨てられる事。また、貯蔵して「古古米」としてマズくなった米が売られる事に対してはショックを感じています。
一方で、輸出しようにも、米を主食とする国は発展途上国が多く、値段が高くて売れない。それで、値段を下げて輸出したところ、国民から「なぜ安くするんだ。日本の米も安くしろ」という非難が起きました。
現在も減反は進んでいますが、米不足にならないどころか、まだ余っています。日本人の食事もラーメンやパスタ、パンなどが好まれるようになっていて、3食米飯という日本人は少なくなっているのも原因の一つでしょう。
一方で国の減反政策は、若者の農業を離れを助長し、労働や頭脳人口の流出が続いています。結果として都市への富の集中化が進んでいます。
このように、国内的には米余りの状況が続いているのに、「何故米の輸入」が必要なのかと思いますが、1993年のウルグアイ・ラウンド合意で、日本は輸入米に778%の高関税をかける代わりに、一定量の米の輸入が義務付けられました。
Uruguay Round/ウルグアイ・ラウンド交渉は、1986年9月に南米ウルグアイのプンタ・デル・エステで開催されたガット閣僚会議での合意に基づき開始され、貿易等の新たな分野を含む包括的な交渉として進められ、7年3か月後の93年12月に合意に至ったものです。
本交渉における農業交渉の特徴は、国内支持(農業補助金等)や輸出競争(輸出補助金等)にまで交渉の対象が拡大されたことにより、各国の国内農業政策にまで影響を与えるような結果となったことがあげられます。
汚染米などの事故米は、輸入時に厚生労働省が調査して除外するのが原則ですが、輸入したした商社は、汚染米が出た場合でも、返品や廃棄せずに糊等の原料となる安い工業用として活用することにし増した。
この汚染米を購入した流通業者が、工業ようとしての利用に反し、架空伝票などでごまかし、価格の高い食用米として販売しているのが判明し、大きな事件となりました。
国民感情から言えば、食の安全性が叫ばれる中、汚染米は全て廃棄し、地産地消や日本の自給率の向上などから、米の消費拡大も総合的な国策として確立していく必要があるのではないでしょうか。 |
財政調整基金とは、経済不況等による大幅な税収入の減や、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされるような場合に備えて、財源に余裕がある場合に積立(貯金)することをいいます。
熊本県では財政調整に活用できる基金として財政調整基金、県債管理基金、職員等退職手当基金、県有施設整備基金の4基金があります。基金総額は平成4~5年頃が最大で1300億円ほどありましたが、90年代の公共工事ラッシュで急速に取り崩され、バブル崩壊の時期とも一致して、平成12年当初には期首予算では56億円まで落ち込みましたが、その後の財政健全化の取り組みで平成17年には162億円まで回復していました。
近年では、財源不足の補充に使用され、平成20年度6月補正予算では平成13年の財政健全化取り組み前のレベルを下回り、53億円(前年同期に比べ63億円/45.7%減)にまで落ち込んでいます。
ちなみに熊本県の平成19年度末の借入金残高は約1兆2581億円で、この額は県民一人当たり約68万円となります。
|
|
| 道州制問題について意見交換(県議会特別委と合併市町村首長ら) |
平成19年09月07日 |
県議会道州制問題等調査特別委員会の委員と県内の合併市町村の首長らによる合併や道州制についての意見交換会が非公開で行なわれた。
「道州制」という言葉はよく耳にするが、具体的に行政においてどのような動きがあるかを知っている人は少ないと思う。
九州においては、1960年代から「九州はひとつ」の理念の下、経済界主導で議論が始まっていたが、2000年代に入って市町村合併の動きが加速してきた中で、次の方向として考えられるのが「道州制」である。
道州制を導入すれば、州都の設定をはじめとする地方の再編が行なわれることは確実で、合併による行財政改革の成果が疑問視されるとき、問題点を提起し住民の意見を積極的に取り上げていく必要がある。
九州地区は他地区に比べて州界などの問題が少なく、東アジア貿易拠点構想などはまとまりやすい反面、人口マップが偏っていることの問題がある。熊本市の政令都市化構想問題も重要な課題となってきそうだ。
後顧の憂いがないよう、我々も大いに関心を持ち、意見を行政に上げていく必要がある。
|
| 選挙告示(公示)・選挙の運動期間 |
平成19年07月17日 |
7月12日に参議院の通常選挙の公示があり、今日17日には衆議院の補欠選挙が告示された。同じ国政選挙であるにもかかわらず、「公示」と「告示」が使い分けられていることに、何故と思われた人も多いのではないだろうか。
結論からいうと、衆議院総選挙と参議院の通常選挙だけが「公示」とされ、その他の地方選挙と国政選挙の補欠選挙は「告示」だという。国の国事行為として出されるのが「公示」で、選挙管理委員会から出されるのが「告示」と思っておけば間違いなさそうだ。正確には憲法第7条第4号との絡みもあり、憲法でいう国会議員の「総選挙」と公職選挙法で言う「総選挙」が異なっているという矛盾がある。この条文についても憲法の見直しは必要だ。
公職選挙法で規定する選挙活動が行なえる期間は、選挙の種類によって異なっている。次に選挙種別ごとの選挙告示(公示)日からの運動期間日数を示す。
○国会については、参議院が17日間、衆議院は12日間
○都道府県知事は、17日間
○政令指定都市の市長は、14日間
○都道府県・政令指定都市の議会議員は、9日間
○政令指定都市以外の市・東京23特別区の首長および議会議員は、7日間
○町村の首長および議会議員は 5日間
ただし、繰上げ投票が行なわれる場合の特例を除く。
|
国政選挙が近づくと、マスメディアによる世論調査がいやに多くなると感じるのは私だけだろうか。内閣支持率が時には政界を揺るがすなど、「世論」の影響力は無視できない。これまでに自分の周囲で世論調査の対象になった人を聞いた事がないが、対象者になった場合の回答は直感的に返事をしている人が意外と多いのではないかと思う。
また、マスメディアによる世論形成への影響は非常に大きいものがあり、世論が誘導されている危険性はないのだろうか。調査を行なうマスコミにより、微妙に質問事項や集計、解説に差が見られる。
世論調査の結果に影響を受ける国民も多いはずだ。マスメディアは十分に責任を持って客観的な対応を心がけることを要望したい。
|
女性一人が一生涯に生む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率は、過去最低を記録し続けてきたが、6日発表された厚生労働省の人口動態統計で昨年の出生率が1.32と上昇に転じたことが明らかになった。
結婚数が増え、生まれる子どもが増えたのが原因だが、今年の出生率は伸び悩みの状態で、「回復は一時的」地の見方もある。
政府も内閣府に少子化対策推進室を設け、少子化対策を打ち出しているが、ここの対策の効果は明確でない。地方の行政や議員の施策にも必ず「少子化問題」対策が取り上げられているが、これからが本当の正念場になる。
上昇に転じたとはいえ、出生率1.32では人口減少は続く。人口維持や増加に繋がるためには2.0を大幅に上回る出生率が確保されなければならない。まだまだ問題の出口は遠い。
|
| 合志市の工業団地誘致状況は? |
平成19年06月05日 |
このところ地方自治体の工業団地の売れ行きが好転している。新団地造成の動きに出ている自治体もむ多い。地価の値下げや企業誘致の取り組みに加え、景気見通しが改善し、生産活動が活発化していることが背景にあるが、わが合志市はどうなっているのだろう。熊本県でも熊本空港に近い工業団地は既に完売の状況と言う。
工業団地の誘致には、工業用水と輸送ルートの確保は必須条件となる。豊富な地下水は問題ないとしても、合志市内の道路状況は決して整備されているとはいえないようだ。高速道路や熊本空港に通じる幹線道路の構築も企業誘致には必要になる。
|
|
|