JOURNAL 2002.Septembre de l'espoir.
〜東京幻想旅行記〜
☆2002年9月1日(日)快晴☆
国分寺を散歩。
カフェスローへの道すがら、写真を撮る。
いつもは撮らない花の写真なども撮る。
最近の殺伐とした生活のなかで、
“キレイなもの”を心が求めたようだ。
カフェスローの豆のカレーと、
南インドテイーは本当に美味しい。
辻信一氏の「スロー・イズ・ビューテイフル」という本を購入。
僕らは・・・いや、“僕”はいま、新しい生き方を模索している。
ゆっくりは美しい。
世界中の人たち、特に“北”の人たちみんながそう思うようになれば・・・
*
夜、職場の若い仲間から電話が入った。
お父さんが、バイク事故で大怪我をしたと。
ご快復を、心の底から願う。
彼のために、そして彼女のために、祈る。

☆2002年9月7日(土)雨☆
土方朋子さんの作品、「黒い椅子」を受け取った。
土方さんらしい静けさと温かみのある素晴らしい絵。
対象への眼差しの温度。
本物の絵というのは、こういうものなのだと思う。
いくら見ていても、見飽きることがない。
見ていると、心が落ち着いてくる。
大切にお預かりしようと思う。

(国分寺散歩中に見かけた木戸)
☆2002年9月8日(日)曇/晴☆
川崎能楽堂にて某劇団公演を観る。
勤務先でアルバイトをしている女性が出演している。
アルバイトをしながらの演劇活動、たいへんだなあと思う。
しかし彼女はそれを苦にするふうもなく
アルバイトも、“アーテイストの身過ぎ世過ぎ”で
仕方ないからやっているというふうでもなく、
真面目に熱心に取り組んでいる。
アルバイトも演劇も、この人にとっては
生きるという事の一部ということなのだろう。
この人は生きることそのものに対して真摯なのだ。
彼女から学ぶことは多い。
僕などは、この人には到底及ばない・・・。(sigh)
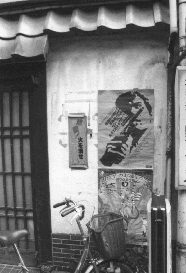
☆2002年9月10日(火)曇☆
五反田の沖縄居酒屋にて職場の飲み会。
麩チャンプルーとソーキソバが美味。
☆2002年9月14日(土)曇☆
吉祥寺にて、友人とバーボンを飲む。
その後で、夜の玉川上水沿いの道を上流に向かって歩く。
ひんやりとした空気が心地よかった。
静寂の中で、玉川上水のせせらぎが聞こえた。
武蔵境の駅へ出て、中央線の東京行き電車に乗って帰途につく。
ほとんど乗客のいない空いた電車の中で、
森田童子の“蒼き夜は”などを聴きながら
藤原新也氏の『メメント・モリ』という写真集を見る。
“メメント・モリ(死を想え)”というタイトルの
この写真集には、インドで撮影された、
人間の死肉を喰らう犬の、あの有名な写真をはじめとして、
様々な死の場面の写真が収められている。
何故だか悲惨な感じを受けなかった。
かえって不思議な安堵感を覚えた。
人間はいつか死ぬ。すべての生き物と同様に。
それは自然で当たり前のことだ。
藤原新也氏の写真と森田童子の歌と深夜の中央線の電車が
ひとつの調和した時空を形成していた。
友人がテレビのドキュメンタリーで見たという
日本人の精神科医の話が印象に残った。
医師はボランテイアとして、アフガニスタンの悲惨な戦争で
心に傷を負った子どもたちをケアしている。
その子供達の傷つきかたと、日本のビジネスマンたちの
激しいストレス社会の中での傷つきかたが全く同じだという・・・・。
この世界は、何かが狂っている。
吉祥寺の古本屋さんで、「メメント・モリ」の他に
ポール・ニザンの「妻への手紙」、
美術手帳 94年10月号「美大生白書」を購入。

(西国分寺の空。米軍機。)
☆2002年9月15日(日)曇☆
2,3日前から、どうしても蕎麦が食べたくて仕方なかった。
今日、ついに西荻の蕎麦屋“鞍馬”で田舎蕎麦という
コシのある太目の蕎麦を食べて満足した。
夕暮れ時の西荻の街を散歩。
西荻は夏祭りで、どこからともなくお囃子が聞こえてくる。
ほびっと村の中の本屋さんで
小林エリカさんの「空爆の日に会いましょう」という本を購入。
☆2002年9月20日(金)晴れ☆
昨日から職場に泊り込みの仕事。
まるで戦場のようだった。
激しい疲労感。
これもまた、生きることの一局面・・・?
生きることの・・・・・?
☆2002年9月21日(土)晴れ☆
新橋のマキイマサルファインアーツにて大塚ゆかこ展、
ギャラリーイセヨシにて今泉敦子展を見る。
夕方、白山を散歩。白山神社のお祭り。
☆2002年9月22日(日)雨☆
吉祥寺にて友人と飲む。
帰りに、駅前で若いジャグバンドが
演奏しているのを見かけた。
*
中央線の中で、森田童子を聴きながら、
つげ義春の「貧困旅行記」再読。
その中の「ボロ宿考」と題された小文に改めて魅了される。
「・・・そういう貧しげな宿屋を見ると私はむやみに
泊まりたくなる。そして侘しい部屋でセンベイ蒲団に
細々とくるまっていると、自分がいかにも零落して、
世の中から見捨てられたような心持ちになり、
なんともいえぬ安らぎを覚える。」
(「貧困旅行記」つげ義春)
“安らぎを覚える”というこの文の結ばれ方に魅了される。
この文に、森田童子の“蒼き夜は”の詩句、
“それとも このまま
君と堕ちてしまおうか”
が重なって、不思議な感動を覚えた。
つげ義春や森田童子にとって、
零落は恍惚とするほどの幸せな夢だ。
*
森田童子の“G線上にひとり”という歌の感覚が
このごろ何故だかよくわかる。
“やさしい風は
ぼくをなでて
ひとりは とても
いい気持
夏草の上に
ねそべって
いま ぼくは
死にたいと思う”
これほどの幸福感が他にあるだろうか・・。
幸福に満ちたりて、幸福に包まれて
その中で死にたいと思う、と童子は歌う。
その気持ちは、今の僕にはよくわかる。
☆2002年9月23日(月)曇り☆
森田童子の夢を見た。
東京郊外の小さな町の古い映画館で
奇跡的な1回限りの復活コンサートをしている。
僕は偶然、別の用事でこの薄暗い映画館に来ていた。
横のドアからこっそり中に入って、
一番前の、童子のすぐ近くの位置から、
彼女が歌う姿を眺める。
僕が知らない歌を歌っている。
コンサートの最後に、伴奏者やスタッフ達とともに
観客に挨拶をしている。
また歌い続けて欲しいという人々の声に微笑んで、
静かに首を横にふっていた。
僕はなんとなく納得して、その場所から立ち去った。
☆2002年9月24日(火)晴れ☆
夕暮れ時に、昔町を歩いていたら
金木犀の香りがした。
*
夢想に耽るのが好きだ。
子供のころからそうだった。
夢見る時こそ、僕の本当の人生の時間だ。
夢を見る時間が奪われてしまえば、
生きることに意味はない。
☆2002年9月28日(土)曇り☆
ビデオで映画“スケアクロウ”を観た。
これで何度目だろうか。
最初に観たのは、高校生の時、テレビの深夜放送で。
その後、目黒にあった名画座で観たり・・。
映画の冒頭、風の吹きすさぶ荒涼たる草原で出会ったとき、
アル・パチーノ扮するフランシスは
何故、彼に声をかけたのだろう・・・。
スケアクロウという思想。
なんて孤独な思想・・・。
「新宿ゴールデン街」(渡辺英綱著/晶文社)を読む。
ゴールデン街の詳細な歴史。非常に面白い。
そこで生きてきた著者が出会った数多くの人々のリストが載っている。
残念ながら森田童子の名前は見当たらないけれど・・・
☆2002年9月29日(日)曇り☆
東向島の現代美術製作所にて、三田村光土里展を観る。
三田村光土里さんの作品は、
ひとつの家族が生きた“時間”そのものを表現している。
他人の家庭を訪れたときに感じるその家独特の匂い。
その匂いとはその家族の歴史が醸し出すものだ。
「それぞれの人生のどんな過去も現実も、親しみをこめて
クスっと笑ってしまおう」という三田村さんの言葉に、
ますます彼女が好きになった。
現代美術製作所は町工場だった建物を
そのままギャラリーにしていて、独特の味わいがある。
帰り、東武伊勢崎線・鐘ヶ淵駅までひと駅歩いた。
町工場やアパートの立ち並ぶその街から見上げた空に
鱗雲が美しく、のどかに浮かんでいた。
その後、駒込へ出て、中里の古本屋に寄る。
トム・ウルフの「現代美術コテンパン」(晶文社)、
吉本隆明「西行伝」(講談社文芸文庫)購入。
そしてずっと探していた大泉実成氏の
「消えたマンガ家」(新潮OH!文庫)をついに購入できた。
この中の「嘆きの天使は永遠に〜孤独のマンガ家・山田花子」という
文章が読みたかった。それほど長い文章ではないけれど、
作家への愛惜と共感を根底にもつ、感動的な文章だ。
現実との壮絶な格闘の末に、若くして自ら命を絶った
山田花子というアーテイストの生き様に
尊敬の念と共に深く共感する。
命を絶ったということに対してではなく、
彼女が彼女なりに精一杯生きたという事実に対して。
古本屋の2階のマッサージ屋さんでマッサージを受ける。
とても感じの良い中年女性の指圧師。
マッサージを終えて、駒込駅に向かって歩いていると
パンフレットを渡すの忘れたと言って追いかけてきて、
二,三の親切なアドバイスと共にそれを渡してくれた。
誠実ないい人だ。
夕暮れ時の駒込の商店街の賑わいの中で
ちょっと暖かな気分になった。
![]()
![]()
![]()