1.社会保障・税一体改革関連法案の内容
消費税率の引き上げ等を柱とする改革関連の法案が8月10日参議院本会議で民主
自民・公明の3党合意で可決成立し、8月22日に公布されました。
それ以前、6月22日の衆議院本会議での採決時に消費税率引き上げ法案に対し、
民主党内から40人以上の離反者が出ました。
消費税率は平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き
上げられることとなります。
社会保障の安定・強化のため、必要な財源を税法と一緒に検討・実行するのが目的
です。マスコミでは消費税率が10%になることだけが取り上げられていますが、消
費税率引き上げの時期に併せて2つの大きな年金改革を行うことになっています。
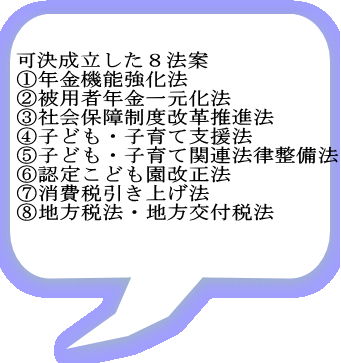
2.年金法はいつから施行されるの?
(1)平成26年4月1日より
・基礎年金の国庫負担2分の1の恒久化
・遭族基礎年金の父子家庭への拡大
(2)平成27年10月1日より
・受給資格期間の短縮
・被用者年金の一元化
(3)平成28年10月1日より
・短時間労働者への社会保険の適用拡大
(4)平成26年8月までの政令で定める日
・産休期間中の保険料免除
3.遺族基礎年金を父子家庭にも
遺族基礎年金について、「被保険者又は被保険者であった者の子のある配偶者又は
子に支給する」と改正されました。
消費税率が5%から8%の引き上げに伴い、今までは「子のある妻」という母子家
庭に支給されていた遺族基礎年金が「子のある配偶者」に改正されたことにより、平
成26年4月以降に受給権が発生した父子家庭にも支給されるようになります。
4.老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮
消費税率の8%から10%の引き上げに伴い、平成27年10月から施行されます
年金改革に必要な財源を、消費税収から賄うとしているためです。
老齢基礎年金は、今まで25年で受給権が発生していたのですが、改正により保険
料納付済期間、免除期間、カラ期間を足して10年を満たせば年金受給権が発生する
ことになります。現在、納付済期間等が10年以上25年未満で無年金者になっていた
人も、請求を行えば平成27年10月以降に受給権が発生し、年金を受け取れるよ
うになるのです。その対象者は約17万人と言われています。
受給資格期間短縮や平成24年10月からスタートする後納制度を利用して年金
を受ける権利が得られるようにするのが目的でしよう。
老齢基礎年金は、40年(480月)保険料を納付した場合の年金は786,5
00円(月額6.5万円)です。10年納付した場合の年金は、196,600円
(月額1.6万円)となり低年金者が増えるのでは・・・と思っています。
小さな年金額に本当に魅力はあるのでしょうか。
5.被用者年金の一元化
自民党政権時代から引き続き検討課題となっていた被用者年金(共済年金と厚生年
金)の一元化が平成27年10月から施行されます。この改革は消費税収の財源絡み
ではありません。
①共済と厚生年金制度差異の解消
②保険料率の統一
・共済年金の保険料率を毎年0.354%ずつ引き上げ公務員共済は平成30年
私学共済は平成39年に厚生年金保険料と同じ18.3%にしていく
③共通財源とする積立金の仕分け
④事務組織の活用、新しい厚生年金制度全体の財政状況の開示
⑤共済年金の職域部分の廃止
6.短時間労働者への社会保険の適用拡大
短時間労働者については、現在は会社で通常働く人と比べて労働時間や日数が4分
の3未満の人について適用除外とされていました。
今回の改正で平成28年10月より次の要件を満たしていれば厚生年金保険、健康
保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる
③月収が8.8万円以上(年収106万円)
④学生等でないこと
⑤従業員数が501人以上の企業
従業員が500人までの企業についての適用は3年以内に検討を加え、その結果に
基づき必要な措置を講ずるとなっています。
この改正も消費税収の財源絡みではありません。
7.産休期間中の保険料免除
産前6週間、産後8週間の休業期問中について厚生年金保険料、健康保険料が免除
になります。対象者は年間20万人程度と見込まれています。
附則として、国民年金の第1号被保険者に対しても産前・産後の期間、国民年金の
保険料免除について検討する旨の規定が設けられています。施行は、法律公布の日か
ら2年を超えない範囲とされています。
(社会保険労務士・後藤田慶子)
