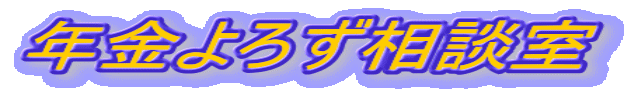A.退職後の年金・医療保険制度
会社では、厚生年金と健康保険はセットで加入していましたが、退職後は年金と医療保
険制度の手続が必要となります。
退職後の医療保険は・・・・
①国民健康保険
②任意継続
③家族の被扶養者に加入する
以上3つの方法があります。
①国民健康保険に入る
国民健康保険の経営者は市役所です。退職日から14日以内に手続が必要となります。
保険料は、前年の収入等によって決定されます。国民健康保険課で確認して下さい。
退職理由によっては減免されるしくみもあります。治療を受けた場合の3割負担は退職
前の健康保険と同様です。夫婦とも、国民年金の第1号被保険者の手続が必要となります
(60歳まで)
②任意継続になる
退職時に2力月以上の被保険者期間が必要です。
加入していた健保組合または協会けんぼに資格喪失日から20日以内に手続が必要とな
ります。最大限2年間加入することが出来ます。
保険料は、協会けんぽ大阪支部の場合は退職時に控除されていた保険料の額の倍か33
,000円のどちらか低い方です。保険料は当月10日までに納付しなければ資格喪失と
なります。納付書での納付、口座振替もでき、前納制度として6力月、12力月もありま
す。健保組合の場合は、それぞれの組合で確認してください。
注意点としては、任意継続被保険者の妻が被扶養者になっていても国民年金の第3号被
保険者にはなれません。夫婦とも第1号被保険者の手続が必要になります(60歳まで)
第3号被保険者とは
厚生年金又は共済年金の加入者の被扶養配偶者で
年収130万円未満の20歳から60歳までの人
です。
|
③家族の被扶養者になる
被扶養者になる為には、60歳未満なら年収130万円未満、60歳以上は180万円
未満などの要件が必要です。その他に同居・別居、被保険者の年収等について厳しい条件
もありますので確認して下さい。60歳未満の場合国民年金第1号被保険者の手続が必要
です。
【介護保険について】
介護保険の経営者は、市役所です。
65歳以上の人は、第1号被保険者になります。保険料は1力月5,000円程度で年
金から控除されています。前年の所得によって0.5から2倍の開きがあります。65歳
から一人一人が終身支払うことになります。
40歳から64歳までの人で医療保険の被保険者は、第2号被保険者です。保険料は加
入してしいる健康保険料に介護保険料率が加算されて納付しています。
(社会保険労務士・後藤田慶子)