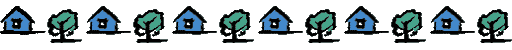
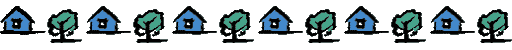
第4話 ベトナム中部フエへの旅
四日目の朝を迎えた。朝食にパンとオムレツ、それにココナッツジュースを食べ、部屋で荷物をまとめていると、約束の9時半を少し回ったところでチー君がロビーから電話をかけてよこした。
とりあえず、ホーチミンはここで終わりだ。二日後の夜にもう一度じホテルに帰る予定だが、その翌朝早くカンボジアに向かうから、事実上これでホーチミンとはお別れということになる。
今朝の送迎の車はカムリではなくワゴン、運転手も昨日までの見慣れた顔とは違う。空港に向かう車中でチー君から聞かされて驚いたのだが、きのうクチの帰りに昼食を摂るため立ち寄った「お好み焼屋」で、テーブルの上の食べ放題の青菜野菜を運転手だけが食べていた。ところが、そのあと、しばらくしてから運転手がひどい下痢の症状を起こしたのだという。私をホテルに送ってくれた頃には、もうおなかをこわしていたのだ。ということで、今日は急遽代わりの運転手が来たというわけだ。
あの青菜野菜、確かにみずみずしく、とてもおいしそうにテーブルで客を誘惑していた。だけど、(これを食べたら絶対腹をこわす)と、なぜかそう思っていた。ガイドのチー君も「やめておいた方がいいです」と親切に忠告してくれ、自分でも手を伸ばさなかったシロモノ。やっぱり、という思いと同時に、現地のベトナム人でも腹をこわす生野菜を、もし私が調子づいて口にしていたらどうなっていたことだろうと思うとぞっとした。
チー君は空港までの約30分間、あいも変らず自分の自慢話と売り込みに熱心だった。彼の人柄というものがだんだん分かってきて、別に悪意があって言っているのではないことが見えてきたので、別に不快に思うこともなく聞いてあげる余裕ができていた。
ホーチミンの空港は本当に小さい。チエックインカウンターも数基しかない。そのカウンターに近づく前に、一度荷物検査がある。大人に混じって中高生ふうの子供たちもいる。どうして彼らがモニターの回りに集っているのか不思議でならないのだが、X線から透けてみえる荷物の中身の映像をTVでも見るように顔を寄せ合い、食い入るように見つめている。検査というよりは、好奇心の方がまさっているようで、何度も不必要にボックスの中に荷物を戻しては透かしてチェックしている。
チェックインを終え搭乗券を受け取ったあとは、十数歩歩いた向かいのコーナーで国内便用に20,000ドンの空港利用税を払い白い横長の領収証をもらう。税額はベトナム人も外国人も変わらない。海外便だと空港利用税はひとり10USドルになる。
出発ゲートに入る前にもう一度手荷物検査とセンサーによるボディチェックがある。このゲートをくぐる前に、パスポートと一緒に空港利用税の領収書を提示し、半券を受け取る。このとき、旅行者ならぜひ確認しよう。パスポートと入国の際にもらった出入国カードの黄色い控えと税関申告書の淡いブルーの控えがちゃんとあるかどうか注意しなければならない。これがないと、ベトナムから出国できなくなる。
ゲートのそばまでようやくたどり着いたと思ったら、チー君ががっかりした顔をして「ディレイです。12時出発になりました」と私に告げた。私たちが乗るホーチミン発フエ行きのベトナム航空VN254便は11時20分発の予定だった。それからしばらく、搭乗ゲートの前のロビーで足どめを食うことになった。開けた窓ガラスごしに飛行場を見渡すと、駐機している飛行機もまばらで、日本のどこか地方の飛行場のような雰囲気だった。12時、やっとリムジンバスが迎えに来て飛行機に乗ることができた。しかし、出発の時刻になってシートベルトを締めてもまだ丸窓の外を見るとガソリンを給油している。なんてのん気なんだろう。
いらいらする私を、機内でなぐさめてくれたのは、アオザイを着た美しいスチュワーデスだった。白のすらりとしたパンタロンに、体にはりつくような大胆なショッキングピンクの上モノを身につけている。どちらも薄手の生地なので、透けてみえる。この国の女性たちは、案外大胆な下着を着けていることが、アオザイからわかる。透けて見えることを女性たちも知っているはずだが、だからといって恥ずかしがる気配はない。ピンクのアオザイ姿のスチュワーデスが、ほんとうに美しく感じるのは彼女たちの容貌に気品が漂っているからだ。この人々は、良い家柄の子女だと聞いた。
飛行機はエアバスA320。左右それぞれ3席ずつが並び、真ん中に通路がある。はじめガイドのチー君が気を利かせたのだろう、座席番号では窓際だったが、乗ってみるとすでにそこにはお婆さんが座っていた。何度も確認したが、私の席に間違いがない。そこで、搭乗券を示して(そこは私の席だと思いますが、間違っていませんか)と意思表示をした。お婆さんは、形ばかり自分の搭乗券を見て確認するふりをして、それから(いいから、いいから、お座んなさい)と言いたげにとぼけた顔をした。(ああなんだ、最初から窓際に座りたかったんだな)と分かって、私はそのまま本来はお婆さんの席のはずの通路側に座った。チー君は真ん中の席に座った。この国はお年寄りを敬う習慣があると聞いている。あまり不必要な文句を言っても仕方がない、と引きさがることにした。それに、ひょっとしたら、連なる三席に関しては「早い者勝ち」がこの国の暗黙のルールなのかもしれないとあきらめ、明らかに相手が間違っていることが分かっていたのに、クレームをつけることを憚った。いずれにしても、結果的にいえば、私が好きな「通路側」の席に座ることができた。
飛行機はやっと1時間遅れで、12時20分に離陸した。小型ジェット機だから、軽快に雲を突き進んでぐんぐん上昇するのだが、それだけ振動がジャンボ機よりは激しい。しかし、水平飛行に入ると機体は安定した。
ガイドのチー君は、飛行機が遅れたことで、これからのスケジュールを心配していた。フエ到着後は車が迎えに来ているはずだが、ホテルにチェックインしてから夕方までに回れる観光スポットが限られてくることに気を揉んでいたのだ。この機内で初めて知ったのだが、フエで彼が泊るホテルは私のホテルとは違うという。旅行会社「APEX」が手配した無料宿泊所がホテルの近くにあるのだそうだ。
機内で簡単な食事が出された。食事が終ってふと外を見ると、丸い窓ガラスの外を雨が激しくたたきつけている。日本を発つ直前に、インターネットの週間天気予報を調べたら、今日あたりこのエリアが雨と予想していた。残念だが、ピッタリ当たったわけだ。(まあ、こういうことも得難い経験だ)と大らかに構えることにした。フエの周辺は昨年暮れ、大規模な洪水の被害に遭い、美しい古都の景観の大部分が泥水で汚れてしまったと聞いた。ベトナム中部地方は年間を通して最も雨が多い地域で、日本の最多降雨地の屋久島よりも多い。それに、雨の日のフエは、気温が低く底冷えがする。日本を離れるときには厚手のものを羽織ってくるから、それがホーチミンでは始末に困るわけだが、フエでは逆にありがたいどころかそれがないと風邪でもひきそうなくらい寒さが身にしみる。「細長い国」の気候の多様性には驚かされる。
飛行機が着陸態勢に入った。雨で見通しが悪く操縦の手元が狂ったのか、機体は異常な速さで滑走路に突っ込み、激しい振動が体を揺さぶった。その乱暴な着陸に、機内からはどよめきに近い声が湧き起こった。誰しもが{あわや」と思ったに違いないが、無事着陸できたときには安堵のため息が漏れた。日本でも10年ほど前まで飛行機の着陸時にしばしばそんな光景を目にしたものだが、誰からともなく拍手が鳴り響き数名がそれに同調した。
飛行機は、離着陸の便数も少ない飛行場のせいか、一本の主滑走路のど真ん中に停まっている。それに群がるように整備の車やタラップ車などが集まってくる。ほんの短い距離だが、田舎の乗合バスのようなリムジンで到着ロビーに向かう。フエの空港のロビーといっても、中に入るとすぐ10歩も歩かぬうちに外に出てしまう。旅行会社の迎えの車が待っていて、すぐにフエのホテルに向かった。
空港からフエの市内までは国道一号線をハノイ方面に北上する。車でけっこう時間はかかる。道いく人々やバラックのような家並みをみると、このあたりが貧しい地域であることがわかる。薄汚れた黄色の建物が目立つ。この国の人々は高貴な色とされる黄色を好むそうだ。そういえば、マレーシアでも黄色は王族の色である。
今夜泊るホテルは「HUONG GIANG HOTEL」日本の読み方では「フォン・ザン・ホテル」と呼ぶらしい。国立のかなり大きなホテルである。昨夜までのホーチミンのミニホテルとはエライ違いだ。そうそう、この国でミニ・ホテルというとどうも、手軽なホテルという意味と、もうひとつ日本流でいえば「ラブ・ホテル」の意味も兼ね備えているようだ。公安の目が厳しいベトナムでは、従業員以外の現地人が一流のホテルに出入りすることを厳しく監視しているので、外国人向けの売春などをするときには「ミニ・ホテル」を利用するとのことだ。しかし、それとても公安が賄賂目当てに見て見ぬふりをしているだけらしく、いざとなれば踏み込まれ罰せられることがあるらしい。その話を聞いて、そうかこの国は社会主義なんだなと改めて感じた次第。
「フォン・ザン・ホテル」は、香りの川を意味する「フォン川」のほとりに立つ美しいベトナム式ホテルだ。レセプションだけでなく、いたるところで従業員がきちんと接客の訓練をほどこされていて、英語も通じる。
結局予定よりだいぶ遅れて2時半ごろチェックインした。部屋は奇麗なツインルーム。完璧だと思ったら、なんとお湯が出ないことがあとからわかった。部屋に荷物を置いてすぐに、まず車に乗って近くのレストランで昼食をとった。
いにしえの首都フエの町は古さと新しさが混在していて面白く、とても落ち着いたたたずまいだ。間口も奥行きも小さな店が、肩を寄せ合うように軒を連ねている。外見から見れば薄汚れて見えるが、中には外国人旅行者が必ずいる。外国人、特に旧宗主国民のフランス人がフエをたいそう好むという。だからか、通りにはインターネットのメールサービスの店もある。試しに、自分のホームページにアクセスしてみようとやってみたが、文字は化けるし画像のダウンロードが遅く、諦めた。1分約1円、文字も画像もうまく取り込めなかったので、お店の人は恐縮してお金は要らないといった。インターネットサービスの店は、観光案内所を兼ねていることが多く、近郊のオプショナルツアーなどをアレンジしてくれる。
私とチー君は、中心街の「マンダリン・カフェ」という店で遅い昼食を摂った。肉料理を2品。豚肉ライス1品。チャーハン1品。野菜スープ1品。飲み物2品。これでふたり分450円だった。フエは、ベトナムでも最も物価が安い地域だという。
昼食のあと、雨の中を車に乗りながら観光した。フォン川に架かる橋を渡り王宮の方に向かった。途中に国旗掲揚台がある。それらをひととおり見ながら、すぐにフエの「ドン・バー市場」に向かった。この市場は、ホーチミンの雑然とした市場とはまるで違い、フエの「文化的感性の豊かさ」を見せてくれる。とにかく、どの店もまるで「生活美術館の展示風景」とでもいえるように、売るものと売る人の姿が一体となって溶け込み「絵になる」のだ。陳列には視覚的なインパクトを計算しているようだし、売り子もそれなりに品良くおしゃれをしているのだ。ぜひ一度訪れてみることをおすすめしたい。とにかく、フエの市場は美術館の中に紛れ込んだような気がする。声をかけあう人々の人情も厚く見え、日本人が安心して回れるところがいい。
ホテルに帰る前に、疲れたので腕のいいベトナム式マッサージはないかとチー君に聞いたら、一軒知っているというのでそこに行ってみた。「SAIGON MORIN HOTEL」内の中庭に面した場所にある「サウナ&マッサージ」である。入場料8ドル。これは、外国人料金である。
簡単に仕切られた半個室で衣服を脱ぎ、そこにすえつけてあるタオルを体に巻きマッサージの前にサウナに入って体を温める。サウナ室はやや小さく、焼けた石状のものに自分でお湯をかける方式。マッサージは20代とおぼしき女性。顔は特に美人というわけでもない。マサージの技術は、まあまあの腕だったと言っておこう。ただし、45分が終ると、店の外まで送ってくれる。なんだか退院する患者が看護婦に見送られるシーンにちょっと似ている。白衣もナースキャップもないけれど。多分、マッサージする側も順番なのだろう。空いているからすぐ次にできるというわけでもなさそうだ。だから、一度来たお客さんには、できればまた明日も来て欲しいと思うのだろう。言葉は分からないが、自分は「9番」だということをしきりに伝えようとしていることだけはわかった。それから、雨の中を入り口でずっと立って見送ってくれるのは、馴れていないだけに妙な気持だった。
ホテルにいったん帰って休憩し、チー君と運転手は旅行会社が用意した別のホテルに向かい、そこでチェックイン済ませて日が沈んでからまた迎えに来ることになった。私はホテルで少し休息を取り、両替などをした。
ホテルでお酒を飲むのもつまらないので、どこか街中の安全なバーで軽く飲もうということになった。チー君も今日は歌を歌いたいといったので、彼の興味にまかせることにした。彼が以前言ったことがあるカラオケとディスコの店に向かった。ところがまだ7時を少し回った頃で、ちょっと早すぎたようだった。ドアは閉まっている。道を隔てた向かい側に庶民的なレストランがあった。まださほどお腹が空いていたわけでもなかったが、時間かせぎのためにふたりで軽い夕食をとることにした。外は小雨が降っていた。通りに面したふきっさらしの店には、われわれ以外に客はおらずガランとしている。余計に寒さがこたえた。
注文をとりに来たのが、まだあどけない少女だった。背も顔も小柄だった。私は「いくつかな」とチー君に聞いた。彼はすかさずベトナム語で彼女に聞いた。「16歳です」チー君が彼女の返事を受けて言った。私はえっと驚いた。この子が高校生なのかい?どう見たって小学生にしか見えなかった。そういえば、チー君はフエに着いてから、途中の車の中で面白いことを言っていた。「この周辺の人は背がとっても小さいので注意して見ていてください」と。確かに道ゆく人々の顔立ちが妙に子供っぽい。大人なのか子供なのか、よく見ても判断がつかない。全体として若く、いや幼なすぎるように見える。おそらくこの地方の遺伝的形質が、そのような顔立ちと体形を生んだのだろう。
チー君の発案で、今夜は寒いのでベトナムの鍋料理を注文しようということになった。あとは、大皿に盛った白いご飯だけ。小さな茶碗にご飯をとってそれに鍋のスープをかけ、好みで魚醤(ニョクマム)をかけて食べる。見た目は、ご飯に味噌汁をかけただけの「猫まんま」に見えるが、味はぜいたくだ。鍋には鳥のレバー、青野菜(火を通すから大丈夫)、トマト、パイナップル、タマリンドなど、日本の鍋料理とはいっぷう変わった具材がたくさん入っている。これが、独特の香りと味わいを醸し出している。酸っぱさはタマリンドのせいだが、パイナップルもトマトも甘酸っぱさを絡めてきて、タマリンドのきつい酸っぱさを和らげている。とにかく、スープだけでもおいしい。
外は雨。薄暗いレストランの電灯の下で、客は私たちのテーブルだけだった。気がつくと、さっきの女の子の家族五人が少し離れた隣りのテーブルで夕食を食べている。さっきの女の子に妹がいることがわかった。顔がよく似ている。おじいさんもわかった。しかし、彼女のとなりにいるのがお兄さんなのかお父さんなんか判別できない。顔が若すぎるのだ。年齢は19歳か20歳くらいに見える。もうひとりは背中を向けているので判別できない。女性だということはわかるが、お母さんかもしれない、いやお姉さんかもしれない。
ベトナムの田舎町の、みんなで力をあわせてレストランを切り盛りしているつましい家族の夕食の光景を、私もチー君も鍋を突っつきながらじっと見ていた。そばにテレビがあり、それを見ながらの団欒はどこにでもある光景。ただし、少女たちの表情が、健康的で晴れやかだった。ときどきテレビの場面が、品のいい彼女たちの笑顔を誘う。そのたびに姉妹や親たちと目を見合わせる。その表情が、透明に輝いている。(いいなあ、こういうのって)。家族の食卓風景も、家族が同じテレビをみて笑い合うことも、今の日本には少なくなった。あの少女は16歳だといった。日本なら、高校1年生の年頃だ。何だか、薄暗い電灯の下のその家族のやり取りが、私の目にはあまりにも眩しく見えた。
「いい家族だよね」と私がいうと、チー君も同じことを考えていたようだった。「そうですよね」と言葉を返した。
それから私たちは、筋向かいのカラオケ・クラブに行った。場末の感じで、客は少なかったが、ステージや踊る場所は広々としていた。こういう商売だから、電力の無駄遣いが許されないせいなのか、場内はやけに暗い。人の顔が見えないくらいだ。テーブルには「ろうそく」が点灯している。カラオケも、ベトナム語でさっぱりわからなかった。日本のカラオケ産業に比べれば真似事のようなシステムで、歌集も写真週刊誌ほどの薄さである。歌った人の歌唱力がスコアでスクリーンに出る仕掛けのものだったが、誰が歌っても一律75点だった。途中で、何度も店の人が「女性を指名して席に呼んでいただけますか」と言いにきたが、チー君は「まだ顔を見ていないのであとにします」と、生真面目に答えている。ところが、いつになっても「顔=好み」を確認できる明るさにはならない。いよいよディスコタイム。ディスコだから、生演奏だし明るくなるはず、というので期待していたが、ステージも天井の豆電球が数個点灯したくらいだ。演奏者の顔もステージ歌手の顔もまったく見えない。演奏する曲も、60年代や70年代にどこかで流行ったようなスタンダードばかりで、編曲もロシア民謡から借用している感じで奇妙だ。格好だけはロックンローラーのようだが、中身はまるで変(といってはいけないのだろう)。どこからか、司会者の玉置宏(みんな知らないかも)でも登場しそうな気配だった。あとでチー君に聞いたら、ベトナムではロックのようなうるさい音楽を国民は嫌うのだそうだ。柔らかいメロディアスなものを好むので、特に公安などがロックのような過激な音楽を禁止しているというわけではないとのこと。
11時頃その店を退散しホテルに帰った。なんだか不思議な経験だった。料金は、ふたりの入場料が60,000ドン(600円弱)。2名の女性を席に呼んだ(実は押し付けられた)格好になったのでそれぞれに50,000ドン(500円弱)、つまり指名料が100,000ドン(1000円弱)。あとは、テーブルチャージと飲み物代だが、入場料以外には230,000ドン(2,300円弱)だった。日本では、こんな劇安料金のナイトクラブはどこにもない。
トップに戻る
最新情報
プロフィール
遊佐へのメール
©Copyrights Yuza Taira,1999,2000,All rights reserved.
