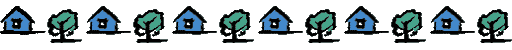
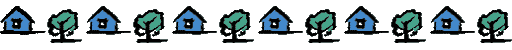
第7話 カンボジアのプノンペンを歩く
朝6時頃目覚めた。ホテルの部屋は乾燥しているせいか、どうしても眠りが浅くなる。それから、溜まっている画像処理や原稿書きを4時間くらい夢中で続けた。早く済ませないと、次の目的地のインパクトが強烈すぎて、前日の感動の熱が翌日の出来事のエネルギーに薄められてしまう。時間がたつと、それらを思い出そうとしても、適当な表現の言葉が浮かばない。描写も具体性に欠け、抽象的になりやすい。だから、毎晩自分を追い込む気もちで、ひたすら原稿を書き続けていた。
いつの旅行でもそうだが、町を観察するときや場所から場所へ移動するときに、片時もメモ用紙を離さないようにしている。これまで、いろんな国のさまざまな都市を訪れる機会があった。その際には、その土地らしい文房具、特に装丁に凝った小型のノートを記念に買うようにしてきた。そのノート類が、東京の自宅の部屋にずいぶん溜まってきていた。今度の旅のために、その中から、栗色の皮表紙の茶色いノートを下ろして使った。1986年エストニアのタリンという町で買い求めたものだった。
ゴルバチョフ政権が全盛の頃、いまはもうこの世に存在しない国家「ソ連」の対外貿易省の招きで、モスクワ、レニングラード(今のペテルスブルグ)、エストニアのタリンへと足を伸ばしたとき、タリンの文房具屋で見つけた思い出深いノートだった。そのノートは、現地では工芸作品として扱われていた。ていねいにも裏表紙に奥付けのようなものが貼ってある。安っぽい紙のラベルに、ロシア語で「1985年10月17日タリンにて制作」というような意味のことが書かれている。15年ぶりに、ベトナムとカンボジアでそれは息を吹き返した。チー君がホテルまで迎えにきて、空港まで送ってくれた。ホーチミンの空港は飛行場部分は同一だが、国内線と国際線ではターミナルが別になっている。どちらも「タンソニャット空港」だから、間違いのないように。国際線ターミナルでは、ガイドといえども空港内には入れない。ここでチー君ともお別れだ。プノンペン行きカンボジア航空VJ126便。ボーイング737−200QCの小型ジェット機で、私はプノンペンへと向かった。初めてのベトナムの旅は、たくさんの収穫を私にもたらしてくれた。
機内では、水平飛行に移るとすぐカンボジアの出入国カード、税関申告カード、それと事前にカンボジアのビザを持たない人のためにビザ申請用紙の3点フォームが配られる。ホーチミンとカンボジアのプノンペンの間の飛行時間はわずか40分だから、離陸と着陸の際のシートベルト着用時間を除けば、目の前のテーブルを倒してフォームに記入できる時間は、正味30分くらいしかない。スチュワーデスが運んでくる飲み物をゆっくり飲んでいる暇もないくらいだ。
夢中で記入しているうちに、外の景色も見る間もなくあっという間にプノンペンの「ポ・チェントン空港」に着いてしまう。カンボジアの空港は、一国の首都の空港としてはほんとうに小さく貧弱に見える。タラップを降りると、そのまま歩いて入国審査の建物に向かう。この間5分くらいである。入るとすぐに、ビザ申請カウンターに並ぶ。ここで、まず機内で記入済みのビザ申請用紙とパスポート、さらに予め用意しているタテ6センチ、ヨコ4センチの身分証明書用写真を一枚、合計3点をカウンターの係員に提出する。カウンター越しに目の前でビザの制作工程を観察できるのも面白い。自分のものが出来上がったら、レジ係に呼ばれるので(といっても無言でこれ誰のもの?とビザがプリントしてあるパスポートをかざす)、自分のものだったら近づいていき20USドルを支払ってビザ付きパスポートを受け取る。実に簡単なものである。この間15分から20分。そうしてようやく入国審査のパスポートチェック、税関審査を経て外に出れる。
ベトナムから急に思い立ってカンボジアに行く場合のビザ取得は、このように旅慣れていない人でも写真一枚用意してあれば、プノンペンの空港で到着後簡単にできてしまうので心配ない。分からなければ前の人(旅なれている風の欧米人の後などがいい)の後ろに着いていけば何となくわかる。入国審査のカウンターの方に行かずに、真っ先にビザの手続きをするのがポイント。(注意:このビザは延長ができないと聞いた、延長予定のある方は確認してください)
外に出ると、ガイドが迎えに来ていた。コン・サンロート(KHUN SAMLOTH)君。年齢は23歳で独身。まだ若いが、真面目そうな青年だ。とにかく謙虚で礼儀正しい。まず、チェックインする前に、予定されている昼食をセントラルマーケットのすぐ近くのレストランで摂った。食欲はあまりなかったが、仕方がないので出されたものに箸をつけた。ビールを頼むと、「ビンですかカンですか」と聞いてくる。ビンと言ったらあとで3ドル取られた。カンは2ドルと安いのだそうだ。ビンビールは大ビン。だからまあ3ドルは妥当なところか、と言い聞かせた。
ところでこのときガイドからカンボジアの予定を聞いて、ふに落ちないことがあったので、確認した。今日からの行動は、明日プノンペン→シエムリアップ、あさっての最終日が強行軍でシエムリアップ→プノンペン→ホーチミン(トランジット)→関西空港の予定になっている。ホーチミンから関空に向かうヴェトナム航空の帰国便は23時25分で深夜だ。ところが、旅行会社(APEX)が手配したプノンペン発ホーチミン行きのカンボジア航空の「最終便」は、なんと午前11時05分発(最終便がである!)。ホーチミンには午前11時45分に着いてしまう。ところで、どこが問題なのかお分かりだろうか。この旅行会社の手配でいけば、私は昼の11時45分から深夜の23時25分まで、ホーチミンのタンソニャット空港に缶詰にされる訳である。忙しいスケジュールをやりくりして駆け回っている身からすれば、こんな無駄な手配はないと怒るのは当然だろう。
旅行会社は、カンボジア国内をすべてVJすなわちカンボジア航空便にして費用を浮かせようとした。だから、ホーチミンに向う最終便(といっても朝便)に無理やり私を乗せようとしたわけだ。もしプノンペンとホーチミン間をベトナム航空便を利用すば、ごく常識的に夜の便でプノンペンを発ち、どのみちホーチミンの空港で何時間かは待たされるにしても、関空行き最終便に余裕をもって到着できる程度の時間調整ですむはずだ。
カンボジアに着いたばかりだというのに、私はこの手配の変更にずいぶん時間を取られてしまった。「手配のすべてはホーチミンのAPEXという旅行会社がやったのだから、プノンペンのAPEXでは変更できない」というのが、現地の回答だった。運が悪いことに、政府の指導で週休二日制が始まったばかりのベトナムサイドは、この時刻(土曜日の午後)オフィスがもう閉まっている。水掛け論が延々と続き、いらいらが募るばかりだった。私が前払いの形で支払えば、なんとかプノンペンサイドで、ホーチミン行きのベトナム航空便を一席押さえるという解決策で、すべては月曜日に対処することとなった。取れるかどうかは月曜日になってみないとわからないというので、不安が残るが仕方がない。ガイドのコン君も、被害者といえば被害者だろう。彼に責任はないものの、とんでもないことに巻き込まれたという顔をしている。
(注意:プノンペンとホーチミン間の飛行機の乗り継ぎ便には注意してください。特にトランジットで空港外に出ない場合には、便数が少ないせいもあり空港内で相当な時間のロスが予想されます。この点、タイのバンコク経由のほうが便利かもしれません。また、夜のタンソニャット空港にトランジットで滞在する際の別な問題もあります<「最終話」の文末をごらんください>)とにかく、日が沈むまでにひととおり観光はしようということになった。まず訪れたのがセントラルマーケット。黄色の立派な建築がとりわけ目立つ。黄色は、高貴の色だ。堂々とした建物だが、中は天井が高いだけで空洞の平屋になっている。中心を占めるのが貴金属や宝石の売り場。市場なのに、デパートの貴金属売り場にいる感覚だ。この「市場の中心をなす貴金属売り場」は、それからもカンボジアのさまざまな市場で目にした。ショーケースのなかには金のネックレスやブレスレットの類いがびっしりと並んでいる。通貨「リエル」の信用がまるでないため、人々は現金を金に変えて持っておきたがるという。こちらでは10Kが人気だとか。欧米の高級ブランドの時計などもおかれているが、すべて偽物だという。だから値段も極端に安い。この貴金属売り場を中心に東西南北に衣類や肉類の売り場の列が並ぶ。建物の外にも間口の狭いテント張りの店がびっしり集っている。人気なのが「中古製品」を売る店。新品よりモノがしっかり作られているので、靴などは中古のほうがよく売れるという。衣類なども、香港やタイなどから生地のしっかりした中古品が輸入されてくる。
市場の入り口の路傍で、ミルク色の小さなジャスミント(茉莉)の花弁を糸に通し輪にしたブレスレットを売っているお婆さんに出会った。これを腕につけておくと、顔に近づけなくても馥郁とした香りがただよう。カンボジアでは、この花はマリスと呼ばれている。日本でも「ジャスミン茶」とか「モーリー茶」とかいうときのあの香りのいい花だ。日本に持ち帰りたいほど華やかな香りだが、おそらく植物検疫は通らないだろう。
13世紀アンコール朝の記録(『真臘風土記』周達観)にも、この香りの花のことが書かれている。アンコール期の人々は男女をとわず上半身は裸だった。頭には髷(まげ)を結っていたのだが、その渦巻状にした「さいずち髷」の根元の周りを囲むようにジャスミントの輪を飾った。手や腕には金の指輪、腕輪をしており、その上に猫目石を埋め込んでいた。アンコール・ワットの回廊の壁には、そうした服飾をした人々(王室に仕える人々だろうが)のレリーフが描かれている。市場の回りに限らず、人が集る場所には必ずといっていいほど、戦争や地雷の事故で体の一部を損失した人々が物乞いをしている。日本でも昭和30年代の始め頃まで、「傷痍軍人」といわれる人々が、松葉杖で身体を支えながら盛り場の隅に立っている姿を見かけた。カンボジアでは、軍人というより、傷ついた一般の市民が目立つ。ベトナムにもそういう惨めな人々はいたが、カンボジアの首都プノンペンには無数にいる感じだ。女性や子供の乞食、物乞いの姿が特に目につく。人に危害を加える風はないが、子供の物乞いなどはかなりしつこくて追い払うのに困る。長い内戦による国中のひずみが、首都プノンペンに寄り集まり、洪水のように一気に吹き出しているかにみえる。
観光客は安全に注意するに越したことはない。しかし、ここ二年ほど、フン・セン首相になってから治安はずいぶん改善されたという。ベトナムでもさんざん聞かされたが、「カンボジアはベトナムよりものんびりした国だから心配はない」とのことだった。歩いてみて確かにそんな気がする。誰の親切心からだろうか、日本人は必要以上に警戒感を煽られているのではないかと思う。よく聞く夜間の拳銃の発砲事件など、いまだ皆無ではないらしいが、頻発しているわけでもないという。取り締まる警官も夜は信用できないと聞くが、実際は夜間に警官の服装をした詐欺泥棒が多数出没するのだそうだ。警官に偽装して袖の下を徴収するのが目的だという。こうなると、観光客ばかりが狙われるのではなく、ターゲットは無差別で地元民も被害にあっているというから防ぎようがない。
次に訪れたのが国立博物館。写真撮影は禁止なので(プノンペンは禁止場所が結構多い)、カメラは入り口で預ける。ガイドのコン君が数々の彫像を見ながらカンボジアの歴史を簡単に振り返ってくれる。12〜13世紀、今のベトナム中部にあったチャンパ王国と戦って勝利したジャヤバルマン7世(アンコール・トムの建設者)の頃、カンボジアは民族の統一が実現し版図も最大だった。インドシナに燦然と輝く帝国が誕生したのだ。しかし、彼の時代を頂点にカンボジアは凋落の一途をたどり、それは今も続いている。
ジャヤバルマン7世の治世の前後、仏教とヒンズー教の影響を交互に受けていく当時の時代を、コン君はさまざまな展示物を見ながら大づかみに説明してくれる。それにしても、ヒンズー教の美術品はくねくねと身体をひねりまわしていて動きに愛嬌がある。じっと見つめていると、なんだか、ハラハラ、どきどき、むずむずしてくる。仏教芸術の静謐な世界とは対照的だ。この博物館、東南アジアの歴史に興味を持つ人には応えられない面白さだろう。事前に勉強してここ訪れたら、きっと一日中飽きないはずだ。
博物館の天井裏にはコウモリが巣を作っているらしく、糞の臭いが気になるかもしれないとコン君は申しわけなさそうに言った。実際には、あまり気にならなかった。
博物館を出ると正面に大きな空き地があり、こどもたちが裸足のままサッカーにうち興じていた。カンボジアのサッカー熱は高い。アジア大会では最下位に終ったが、政治も安定し、経済の力もいま以上に増せば、これから力をつけていくに違いない。空き地を過ぎると、メコン(Mekong)川とトンレサップ(Tonle Sap)川、バーサック(Basac)川が一箇所で合流する場所がある。ここに、チャンチャヤ(Chan Chaya)殿と呼ばれる王殿がある。11月の水祭りのときなどシアヌーク国王がここに座り、派手に飾りつけをした船のレースを眺めたりする。
チャンチャヤのすぐ脇に南北にひとつずつ小さな祠(ほこら)がある。北側の祠をタードンボーンデック(Ta Dombang Dek)、南側の祠をプレアンドンカー(Prah Ang Dong Kar)という。人々に人気なのがプレアンドンカーの方で、何か願い事やお祝い事があるとここにきてお祈りする。私が書いた『スーはきっと踊り続ける』(1998年工作舎)にも、主人公が子供のころ目の病気を患ったとき母親が心配してこの祠に連れてきたという話が出てくる。プレアンドンカーの回りには、年老いた乞食がたくさんいる。よく見ると老婆だ。ガイドがいたせいもあるだろうが、物乞いといっても危害を加える感じはない。ベトナムのホーチミンの川沿いにへたり込んでいる麻薬中毒患者や売人たちには近づきにくいが、ここは観光客も比較的安全に見える。
祠は、畳わずか2畳ほどのスペースで、ここに上がり込むときには靴を脱ぐ。汚いスニーカーを私は履いていたのだが、盗まれないようにとコン君が気遣って見張ってくれている。祠の中には仏象を祭った祭壇があり、その回りにも乞食なのか物乞いなのか物売りなのか判断がつかない人たちがいる。誰かがこちらに線香を差し出した。どうやら買ってくれという意味らしい。それを無視して仏像の前で手を合わせ、5000ドン(50円弱)の紙幣を賽銭箱の口に差し込んできた。祠を出ると、体長5センチほどの一見「すずめ」のような形をした小鳥を篭に入れて売っている人がいる。一羽買ってその場で空に放してあげると、善行をしたことになるのだという。差し詰め「平和の鳩」ならぬ「平和のすずめ」を売る商売ということか。
川沿いには王立芸術劇場がある。最も権威のある宮廷舞踊、民族舞踊を一週間に何度か実演しているという。ここで踊りや芝居を演ずる人々は王立芸術大学の生徒や先生である。大学といっても日本でいえば小学生のような子供が入る。幼いときから、まず体形を厳しく審査され、将来成長したときの容姿がチェックされる。王様の前で踊るにふさわしい、選び抜かれたエリートたちでなのである。
それから、私たちはサムダッチ・ソーテールー(Somdech Sotearos)小学校、スバイポペ寺院(Wat Sway Popear)などを足早に回った。ふだん、観光客が訪れる場所ではないが、すべて先述の『スーはきっと踊りつづける』というノンフィクション作品の舞台になった場所である。
あのときは、聞き取りで想像しながら書いた。いま目の前にある場面を見て、当時とは異なったものであるに違いはないが、そこにその場所があったことだけは確かなはずだ。私は、懐かしいものに出会ったように、ひとりで静かに感慨にふけっていた。
ちょうど生徒の下校時に巡り合わせた。校門のフェンス越しに、生徒が校庭に集ってお別れの集会をしている様子が見える。校門の外には、子供を迎えに来ている家族でごった返している。やがてガードマンの手で校門のゲートが開かれ、彼らに先導された小学生たちが並んで出てくる。どこの国の小学校でも目にする下校風景だ。やがて、上級生だろうか、手をつないで二列になり道を塞いで横断歩道をつくり出した。交通を一切遮断して、生徒の下校を促している。バイクやクルマのドライバーも特に文句を言う気配もない。これは日本にない面白い光景だった。
しかし、ショッキングなこともあった。いまやソテールー通りは、「売春街」の別名のようになっていたのだ。これは思いもよらなかった。通りの小学校と反対側の土地はもともと政府のものだったが、スクワッター(不法占拠者)が占拠しスラムと化している。そして、今にも朽ち果てそうなバラックの小屋が軒を連ねている。小さな雑貨屋を除けば、そのほとんどが売春の部屋だ。粗末な板戸を堅く閉ざしているところもあれば、厚く化粧をした女が戸口のプラスチックの椅子に腰掛け昼間から客を引いている。これには胸がつぶれる思いだった。
売春窟の真向かいには、「サムダッチ・ソテールー小学校」がある。過去50に近い国々を転々としたが、教会の回りに売春窟があるという例は知っている。たとえば、ミラノやアムステルダムがそうだ。しかし、小学校の校門の外に軒を連ねた売春宿があるという例を他に知らない。
「しかたないです。彼らが後からやってきたのですから。初めからここが売春の街だったわけではないのです」
コン君は残念そうにそう言った。
じつは、プノンペンにはもうひとつ有名な売春通りがある。トゥオールコック通りと聞けば、誰もが知っている。この道の片側にはベトナム人、反対側にはカンボジア人が住んでいて、どちらも売春を生業にして生活している巨大なスラム街だ。この通りのはずれに、権威ある国の文化芸術のシンボル「王立芸術大学」がある。日常生活のすぐ隣に、おびただしい数の乞食や浮浪者がいて、誰はばかることもなく売春窟がある。首都プノンペンは、「カオス(混沌)」の町に見えた。市民生活のいたる場面で、長い戦争と内戦、そして政変の傷痕が残っている。戦乱が生んだ貧困と荒廃は、社会システムや経済システムだけでなく、人々の心のありかたにまで及んでいるように見えた。
生き延びるためのギリギリの挌闘が、町のあちらこちらで目につく。生存競争に敗れれば、人々は、物乞いや売春婦に転落していく。それを救う社会の仕組みはいまのところ皆無だ。どの国際都市でも、そうした後ろめたい部分は「隔離」された地域に閉じ込められるものだが、プノンペンではその「間仕切り」というものがない。行政の力が及ばないこともあるだろうが、生存のためのなりふりかまわぬエネルギーのほうが圧倒しているのだろう。「恥ずかしい」という思いは相対的なものだが、人の意識をかまう心がなくなってしまっているようにも思える。カンボジアの現実の中で生きていくのは、それほど過酷なのだろう。
小学校の校門の前で、家族が協力しあって生業として売春を支えている。それをレンズの向こうに捉えながら、この国の「病い」の根深さを痛感した。私は、脳みそが麻痺する思いで夢中でカメラのシャッターを切った。後日日本に帰って、現像した写真を見たとき、私は再び激しいショックに襲われる。「じつは、私が母のお腹の中にいるとき、父はポルポトの兵士に殺されました。だから、父のことはまるで知りません」
ガイドのコン君が、休憩のとき淡々とそう語った。23歳のコン君は1976年生まれだから、ちょうどポルポトが政権を握っていた1975年から1979年の間に誕生している。父親の悲劇が起った時期がぴたりと符合する。いま、生存のために格闘しているカンボジア国民の中に、コン君のように理由も分からずに家族を殺された人々が無数にいるはずだ。そのことが、カンボジアの特殊な社会事情を生んでいる。高校を卒業してすぐコン君は政府の給付留学生として日本に来た。電子工学を勉強し、コンピュータの専門家としての訓練を受けている。しかし、彼は何を思ったか、三年であえてふたたびカンボジアに戻っていく。日本に留まろうとする留学生が多い中で、彼はきわめて珍しい道を選択したのだ。それには、深いわけがあった。
在日カンボジア人の間でも、世代の意識のずれが顕在化するようになった。先輩が後輩の面倒をみる意識は年々薄らいできている。ある日彼は、奇妙な経験をする。カンボジアから日本に来た新たな留学生を、在日カンボジア大使館で歓迎するレセプションでのことだった。新人を前にして、先輩たちはなぜか決してカンボジア語を使おうとしない。カンボジア人しかいない場面なのにである。新人がカンボジア語でいろいろ質問しても、信じがたいことに、空々しく日本語で返答するのだそうだ。先輩カンボジア人どおしも、奇妙なことに日本語で話をしている。まるで新人をいじめているとしかみえなかったという。新人たちは、自分たちが歓迎されているのではないことを初めて知った。同朋と思い込んでいたカンボジア人の中で、彼らは話す相手もなく孤立感と疎外感を味わっていたという。
私はカンボジア人ではないので、どんな理由からそのようなことが起るのかわからない。しかし、私の知っているある在日カンボジア人も、本国に誇りを持つような発言はあまりしない。母国のことを見下すような発言も時々飛び出す。家族のことを語るときも「金のむしんをするばかりの人々」と、奇妙な表現をしていた記憶がある。在日カンボジア人と現地にいる肉親どおしの信頼感も薄れてきているのだろうか。
それから私たちは、今夜泊まるモニボン通り沿いの「プリンセス・ホテル(Princess Hotel)」(302 Street 228, Monivong,Khan Daun Penh,Phonm Penh,Cambpdia)に行きチェックインした。夕食は、コン君の勧めで同じモニボン通りにある有名なタイ料理のレストランでバイキングを食べた。食欲があまりなかったので、現地でなければ味わえないさまざまなフルーツをお腹一杯食べて済ませた。それでも、ずいぶん贅沢な気分を味わうことができた。
トップに戻る
最新情報
プロフィール
遊佐へのメール
©Copyrights Yuza Taira,1999,2000,All rights reserved.
