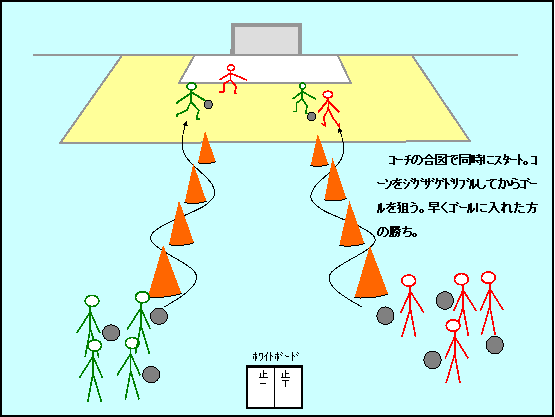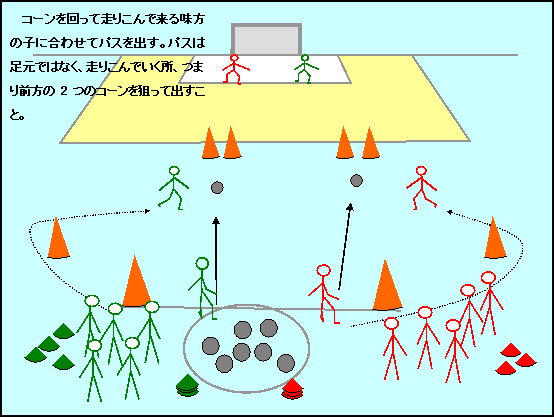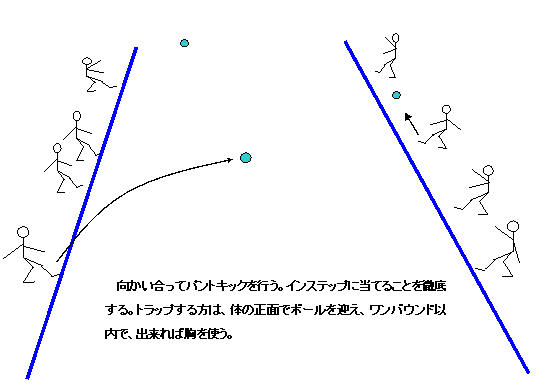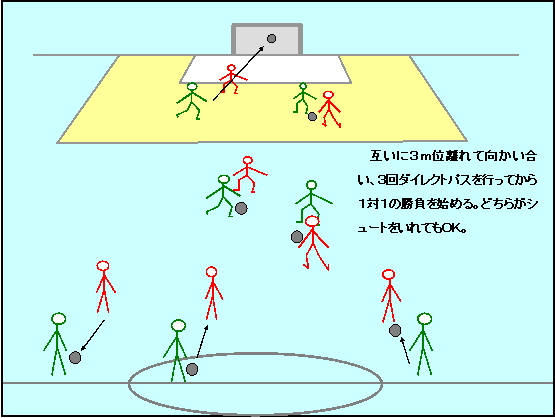|
�Q�N���̗��K���e�@ �Q�O�O�Q�N�U�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����F�����P�S�N�V���U���@ |
|
�ځ@�@�@�� |
|
���h���u������V���[�g�̋��� �W�O�U�O�h���u���̗��K�������葁����낤�Ǝv������A�R�[�����S�[���O�܂łQ�`�R���Ԋu�ŏc�ɕ��ׂĂ�点�邱�Ƃ������B�������A��点�Ă݂�ƃ{�[���ɔ����~�܂��Ă��܂������Ȉʂ������Ƃ������q�ł��q�����l������B�h���u���ő�������킷���ɂ́A�X�s�[�h���Ȃ��Ă͓G�����Ƃ͂ł��Ȃ����ȒP�Ɏ���Ă��܂��ł��낤�B����ȕ��ɂ̂�т�Ƃ���Ă���q�́A��������K���Ă�����ł͖��ɗ����Ȃ��B�����ő����h���u������Ƃ����ӎ����������邽�߂ɁA�Q�l�ŋ����`���ɂ��Ă݂��B �@ ���� �S�[���Ɍ������ăR�[�����S���c��2��u���B�S�������ɕ����ăR�[���̑O�ɏc�ɕ�����B�e�`�[�����ɑO����ԍ������킹�ď��Ԃ����߂�B���̏��ԂɃh���u���������s���A�L�[�p�[�����̏��ԂŌ�ւ���悤�Ɏw������B�܂��A���_�L�^�p�̃z���C�g�{�[�h����������B ���[������ �u������R�[�����W�O�U�O�h���u�����Ă���V���[�g�����܂��B�R�[�`���獇�}����������e�`�[���P�l���������ɃX�^�[�g���Ă��������B��ɃS�[���ɓ��ꂽ���������ł��B�������q�́A�z���C�g�{�[�h�ɐ�����{���������Ă��������B�������́g�������h�Ƃ������ɂȂ�悤�ɏ��ɐ���t�������Ă��������B�ǂ��炩�̃`�[����20�_�ɂȂ�����I���ł��B�L�[�p�[�͈ꏄ�������ւ��܂��B�v �@�u�h���u���̓R�[�`���猾���������ŕK������Ă��������B���[���ɏ]��Ȃ��q�͂��Ȃ����������܂��B�ŏ��́A�����̃C���T�C�h�Ō��݂Ƀ^�b�`�ł��B����ł͏����ł������ȁH���[�C�A�h���v ���������A�h���u���̂��������Ɏ��������Ԃŕς��Ă����B �@�E�Б������ōs���i�C���T�C�h�@���@�A�E�g�T�C�h�@�����݂ɍs���j �@�E���̗��Ń{�[�����^�� �@�E���R�ȃh���u�� ���� �@������������V���[�g�����悤�Ǝv���āA���ӎ��ɑ����h���u��������悤�ɂȂ�B �A�h���u�����K�����ł͂ӂ������肵�Ă��܂��q���A�����ɂ͕��������Ȃ��̂ňꐶ�������B �B���[���ᔽ���������蒼�����������ď����ɕ����Ă��܂��̂ŁA���낢��ȃh���u�����j���[����点�Ă��f���ɏ]���B �\�����Ȃ����Ƃւ̑Ή��� ���炭����Ă�����y�i���e�B�G���A�����O�ɏo�đ҂��\����L�[�p�[���o�Ă����B����ł͗��K�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA���̂悤�Ƀ��[����lj������B�u�L�[�p�[�́A�V���[�g����q���Ō�̃R�[�����Ă���܂ł̓S�[���G���A�̒��ɓ����Ă��邱�ƁB�R�[�����o�Ă�����O�ɏo�Ă��n�j�ł��B�v
|
|
�����肱���փp�X���o���Ă�����ăV���[�g���鋣�� ����͂T�����ŏЉ���u���肱���փp�X�v�̉��ǔłŁA���肱���֖�������p�X��������ăV���[�g���銴�o��{���͓̂��������A���X�s�[�f�B�ɂ�点�悤�Ƃ�����̂��B ���� ���}�Ɏ������悤�ɑ傫�ȃR�[�������E�Ώ̂ɂQ���u���B��O�̃R�[���̓X�^�[�g�n�_�B�ߑO�̃R�[���̓{�[�������炤���ɂ��̊O������点�邽�߂��B�{�[����u���G���A�����A�S���Ɏ�Ń{�[������ꂳ����B���_�p�̏����ȃR�[�����{�[���̒u���Ă�����Ɋe�`�[�����P�O���u���B ���[������ �u�܂��A�e�`�[�����Ƃɕ���ŏ��Ԃ����߂Ă��������B���̏��ԂŃL�[�p�[����ւ��܂��B����ł͍����烋�[����������܂��B�V���[�g����q�͍ŏ��Ɏ��̏��Ԃ̎q�ɒZ���p�X���o���Ɠ����ɂ��̎q�̔w�����܂���ĎߑO�̃R�[���̊O�������܂��B�p�X���o���q�͑��肱��ōs�����ɍ��킹�ăC���T�C�h�őO����2�̃R�[���Ɍ������ďR���Ă��������B���̃p�X�����������O���̃R�[�������킵�A���̂܂܃h���u���Ŏ�������ŃV���[�g�����܂��B�R�[�`�̍��}�łQ�`�[�������ɃX�^�[�g���A��ɃS�[���ɓ��ꂽ���̏����ł��B�������q�͏����ȃR�[�������w�֎����Ă����Ă��������B�v�ƌ����Ă���n�߂�B �@�@ �˂炢�ƌ��� �@5�����ł�������K�ɋ���������t���������̂ŁA���L�r�L�r�Ƃ��悤�ɂ͂Ȃ����B�����A�ǂ����Ă��ӂ����Ă��܂��q���o�Ă���̂ł܂��܂����ǂ��K�v�Ȃ悤���B
|
|
��w�N�ł́A �@�����オ�����{�[���̏�������� �A���ł�����ł��ܐ�i�g�[�j�ŃL�b�N�����Ă��܂� �Ƃ����q���قƂ�ǂł���B �@���ɂ��ẮA����ł����{�[���̖ڑ������A�ڂ̑O�Ńo�E���h�����{�[���������z���Ă��܂��B �A���ɂ��ẮA�v���Ƃ���ɂ͔�Ȃ��A�����R��Ȃ��A�������肷��Ƃܐ��ɂ߂Ă��܂��A�Ƃ��܂肢�����Ƃ͂Ȃ��B�Ƃ����̎��Ȃ�Ƃ������A1�N���̑�����������w�������Ă����q�ł����ӂ��Ȃ��ƂقƂ�ǂ��ܐ悾�����g���Ă��܂��B ����͂��̂Q�̉ۑ���Q�l��g�̃p���g�L�b�N�̗��K�ŋ��������悤�Ƃ������݂��B �����Ɛ��� �܂�2�l��g�ɂȂ��Ă��炤�B���Ƀ^�b�`���C�����𗘗p���Č݂��Ɉ��̋����i�Q�O���O��j�������ꂳ���Ă��玟�̂悤�Ɍ����B �u������Q�l�Ō��݂Ƀp���g�L�b�N���Ă��������B�p���g�L�b�N�����鎞�͕K�����̍b�i�C���X�e�b�v�j�ɓ��ĂĂ��������B�ܐ�ł̓{�[���͉����ɔ�т܂���B�{�[������q�͕K�������o�E���h�ȓ��ŁA����g�킸�Ƀg���b�v���邱�ƁB�{�[���͑̂̐��ʂŌ}���A�ł�����ɓ��ĂĂ��������B�g���b�v�͂P���ȓ��ōs�����ƁB�v ���܂������Ȃ��q�ւ̎w�� �p���g�L�b�N���n�߂�ƁA�ܐ�̕��ɓ��ĂĂ��܂��Ďv���悤�ɔ���Ȃ��q���\�z�ʂ艽�l������B���������q�͌��ł����猾���Ă�����Ȃ��B���ɍs���A�n�ʂ���R0�����ʂ̏��ŁA��Ń{�[��������������ԂŃp���g�L�b�N����点�Ă݂�B���̍b�̌ł������w�ʼn����A�u�����ɓ��ĂĂ����v�ƌ����ĉ��R�点��B�������R��Ă��邩�͎�ɓ`���Ռ��ł���������B���܂��R��ďՌ�������������ꂽ��A�u�����B���̏R����ō��i�B�v�ƌ����Ă��B�������ĉ��l���̎q�̎w�������X�Ƃ���Ă����B���̂����ɂ���܂łT��������Ȃ������q���˔@�Ƃ��Ĕ����L�т鎞������B�����Ȃ�Ɩʔ����Ȃ��čŏ������ꐶ�������悤�ɂȂ�B
|
|
��1�P�Œ����������h���u���˔j���V���[�g������K �@�ŋ߂̗��K���������ċC���t�������Ƃ����A���i����h���u�������ӂł͂Ȃ��q�͒c�q��Ԃ̒��ɕ��ꍞ��Ŗڂ̑O�ɗ����{�[����O�֏R�邱�Ƃ�������Ă��Ȃ��B�R���Ă����ǂ�������Ȃ�Ƃ������A�����R���Ă��̏�ɗ����~�܂��ă{�[���̍s�������Ă��邾�����B���܂ł���Ă������K�͉��������낤�ƍl����������B�A���I�ȃv���[�͏��Ȏq�����͂���Ă��܂��̂ł����͒P���̃v���[�ŏ\���������̂�������Ȃ��B�����������Ȃ���A��������͒��������̃h���u���˔j���K��S���ɂ�点�邱�Ƃɂ���B�h���u���Ŕ������M���������A�c�q�T�b�J�[����̒E��������悤�Ǝv���B�P�N�ʂ��̗��K�𑱂��Ă����A�����_�ŒP��v���[��������Ă��Ȃ��q�ł��A�������玩�M�����Ď����ł��낢��l�����v���[������悤�ɂȂ邱�Ƃ����҂��āE�E�E�B �����Ɛ��� �ŋ߂͐l���������Ă����̂Ő����͊ȒP�ɂ����Ȃ��Ȃ����B���r���[�Ɍ��������Ő������ς܂���ƁA����ʕ����ɑ����Ă��܂��Ă������ďC������ςɂȂ�B�܂��S�����Z���^�[�T�[�N���t�߂ɏW�߂č��点�A�Â܂�̂�҂��Ă���������n�߂�B �u�܂��A2�l�ŃW�����P�������čŏ��̍U���Ǝ�������߂܂��B�U���̎q�̓n�[�t�E�F�[���C���܂ʼn������Ă��������B�Q�l�͂R���ʗ���Č����������܂��B�U�����̎q����C���T�C�h�Ń{�[�����p�X���A������̎q�͗����{�[�����C���T�C�h�ŕԂ��܂��B������R��J��Ԃ�����1�P�̎n�܂�ł��B�ǂ��炪�V���[�g�����Ă����܂��܂���B�S�[���ɓ��邩�S�[�����C������o���珟���͏I���ŁA�U�炪��ւ��܂��B������܂������H����ł͍D���Ȏq�Ƒg��ň�ĂɎn�߂ĉ������B�v �@ �˂炢�ƌ��� ����܂ł́A���낢��Ȍ`��1�P������Ă����B����͂قƂ�ǂ��ǒn��̗��K�������B�������A�͂邩�����ɂ���S�[���Ɍ������ăh���u���œG���Ă����U���̊��o�ƁA�S�[����w�ɂ��Ȃ������Ă����Ƃ�������̊��o�͗{���Ȃ������B���̗��K�͂��̗��������˂Ă���B�������A�S�[���܂ł̋����������̂ŁA����������܂��ǂ�����čŌ�܂ŏ����͕�����Ȃ��B�P���ȗ��K�����A�T�b�J�[�̖ʔ����v�f���܂�ł��Ďq���B�͒N�����ڂ�Ȃ��B�S�����x�ނ��ƂȂ������悭�ł���Ƃ�����悢�B
|