|
日本初の「総天然色映画」作り
日本初の長編総天然色映画「カルメン故郷に帰る」が、東京劇場で封切られたのは1951年(昭和26年)3月21日だった。この後、4月1日に東映創立、7月12日には松竹太秦撮影所がオープンして、その後の邦画界の隆盛を予感させる。さらに9月10日、黒澤明監督の大映京都作品「羅生門」がベネチア映画祭銀獅子賞を獲得、翌年アメリカのアカデミー賞最優秀外国映画賞も受賞して、日本映画界の底力と黒澤の名を世界に知らしめている。
前年から日本映画監督協会でカラー作品の企画が持ち上がり、冨士フイルムからも松竹に働き掛けがあって実現したもので、当時37歳の木下恵介監督が監督協会の推薦を受けてメガホンを執った。木下監督がカラー企画用に書いた脚本は「アルプスの死闘」だったが、ロケ地の関係で断念せざるをえず、新たに書いたのが「カルメン故郷に帰る」だった。ちなみに「アルプスの死闘」は63年、「死闘の伝説」(出演・岩下志麻。太平洋戦争末期の北海道を舞台に物語は展開する)と改題し、パートカラーで映画化されている。
「カルメン…」の脚本と監督・木下にまつわる話が、岩波書店刊「講座・日本映画 6」の高峰と映画評論家・佐藤忠男の対談「子役スターから女優へ」に載っている。「…読んでみたら、バカのストリッパーじゃないの(笑)、ああ、木下さんはやっぱりわたしのことバカのストリッパーが一番いいと思って書いたんだなと思って笑っちゃったけど」。よけいなお世話かも知れぬが、実にいい話が書いてあるので、ぜひ一読をお勧めしたい。
カラーとモノクロの2本同時撮影(詳細は「諸々のこと3」を参照)のため、撮影日数は平常の2倍の71日間を要し、制作費は3900万円だったが、日本初の総天然色映画ということもあって、総配給収入は6800万円を記録している。当時、東京の封切り館入場料は80円、現在1500円として約20倍で計算すると、制作費7億8千万円、総配給収入13億6千万円ということになる。大作である。 |
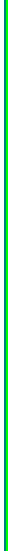 |
総指揮の高村潔は松竹の常務で、この一作に賭ける決意と情熱は並大抵ではなかったという。企画した日本映画監督協会も、若手の売れっ子・木下を監督に、小林、川頭、松山ら6人の助監督を配す熱の入れ方だった。
字幕意匠担当に漫画家・清水崑を起用して面白い。背景の漫画は映画のストーリーを追うように描かれていて、字幕だけで内容を知ることができる。ただし、初見の人には該当のシーンを思い出しようがないゆえ無理である。
冨士のフィルムはASA10と感度が低く、白黒撮影の3倍の明るさを必要としたため、夏場にロケが行われ、1畳ほどもある発光用のレフ(反射板)に囲まれた出演者は暑さと眩しさに閉口したという。また、セットの時はレフに加えて強烈なライトの熱で、出演者のまつげが焦げ、ポマードを塗った頭から煙が出たという話も残っている。とにかく、きれいな肌色を出すために、涙ぐましい努力が続いた。
「私たち俳優は、富士フイルムの技師やキャメラマンがパレットの上で調合し、こねまわしたドーランを塗ってはセッセとステージに走った。
ステージの中にはキャメラが待機していて、真夏の太陽を幾つも集めたようなライトの光芒が被写体、つまり俳優に向かって集中される。…ただでも蒸し風呂のようなステージの中はライトの熱が加わって四十度を越える暑さである。照明を変え、光量を変え、レンズの絞りを変え、幾通りかのテストフィルムを撮ると、俳優たちはまたセットを走り出て、またもや違うドーランを塗るために、再び化粧室へ舞い戻るのだった。…出来上がったラッシュの私の顔の色は、あるカットは猩紅熱にかかった金太郎の如く、あるカットは二日酔の白熊の如くで目も当てられない。試写室につめかけたスタッフは、カットが代わるたびに一喜一憂、全身がひとつの眼玉になったように画面を見つめて身じろぎもしない。思えば、なんともウブウブしく新鮮なカラー映画の夜明けであったろう、と懐かしい。
…どういうわけか一番ヘンテコな顔色に発色するのは校長先生に扮した笠智衆で、白く塗ればオハギにキナコをまぶしたようにまだらに写り、茶色く塗ればまるで安物の文鎮のような鉛色になる。笠智衆のテストフィルムが映るたびに、スタッフ一同は呆然として首をひねった」と、主役・高峰は撮影の模様を自著「わたしの渡世日記」に記している。 |
|