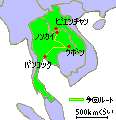| ���N�V�[�̃^�C��������@�ҏW�L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���N�V�[�E���[���h�@�ҏW��L�ł́A�֘A�T�C�g���Љ��ꍇ������܂����A������Q�l�ł��B�@�����ł͂���܂���B�@�i���j�@���ڃ����N�͂��Ă��܂���̂ŁAURL���h���b�O�E�R�s�[���Ďg���Ă��������B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06�N1��30���@�ߕ� �@�V�˃o�J�{���ɏo�Ă���x���͉��������e���˂��āu�ߕ߂���[���v�Ȃ�Ă���Ă܂��������B�@�t�@�C�u�E�h�A�̖x�G���ߕ߂͐����̗͂���������������܂����B�@�u�؋���͂߁I�v�̎w�߂�����c����������ɉ������B�@���̋c���͘V�l�В����ԂƐ[���Ȃ��肪�������B�@���̋c���͌������B�@�u�Ȃ�قǁA�Z���n�i�R�C�Y�~�j���@������Ă��B�@���̃n�i�V���܂��傤�B�@�C�`�S���A�I�k�V������̂��B�@���q�q�q�b�v�ȁ`��Đԍ�ӂ�Ŗ��k�B�@�}�ɐ��������Ђ��V���@�����A�����̂��߂ɋ]���ɂ��Ă��邱�Ƃ�����B�@��_���I�悷��B�@�t�@�C�u�E�h�A������܂ŃV���ŗ���ꂽ�̂��s�v�c���������B �@����ɂ��Ă����_�Ƃ������̂͐ߑ����Ȃ��ł��Ȃ��B�@�x�G�����A�����������グ�Ƃ��āA�߂܂����r�[�ɒ@���B�@�������ᑸ�h���Ă܂����B�@NEET�ɖ���^���Ă����̂ɁB�i��1�j�@������2���^���A�ނ̍u�����\�肵�Ă����̂ɒ��~�ɂȂ�c�O�ł��B �@�S������łĂ��ĕʂ̊p�x����荞�݁A�e���͂�����Ǝv���܂��B ��؋������c�����Ɩ[�̎����u�n�R����������A���̂Ƃ��ɔ�ׂ��}�V�v�ƌ����Ă܂������ǁA�O�ɏo���Ȃ����A�����Ȃ��ł�����B�@�}�V�Ƃ͌�����ł���B�@�����Ȃ�A�q�}�Ńq�}�ŋC�������ł���Ȃ��B�@�V�����炢�ǂ܂��Ă�����ł����˂��B�@�v���o���܂������ǁA20�N���炢�O�A�������Ƃ������S������o�Ă����l���{�����Ĕ���܂����ˁB�@30�N�ʑO�ɂ���������܂�@�ᔽ�ő�R�|�\�l���߂܂�܂������ǁA�ނ�͏n�N�|�\�l�Ƃ��č������Ă܂��B �����߉���� ��1�j�@NEET�y�т��̐���͍ݗ��^�̓��{��ƃV�X�e���������ł��B 06�N1��26���@�O�t���̔]�Ől�Ԃ��� �@���{�̌i�C���悭�Ȃ��Ă�������ł͎��X�ɑ傫�ȉ�ЂɊO�����{������A���{�̉�ЂłȂ��Ȃ��Ă䂭�B�@�����������̏����o�����͉̂~���Łi�ƌl�I�Ɍ��߂���j�A���{��ׂ����Ƃ����S�{���Ă̈Ӑ}����������Ƃ�����B�@�G�h�K�[�E�P�C�V�[�i��1�j�̗\���ɂ���A�u���{�̏d�v�ȕ����͊C�ɒ��܂˂Ȃ�Ȃ��B�v���I������̂����m��Ȃ����B �@�ŋߎ�荹������Ă��郉�C�u�h�A�͌o�c�̈ꕔ���j���[�X�ɂ��Ă��ꂽ�B�@���A�Ŋ��Ɣ����ɂ��Ĉꐡ�����̔F�������܂����B�@�����̉�Ђ̓j���[�X�ɂȂ炸�Ɏ��{���h���h������ւ���ĊO���̎��{���h���h�������Ă��Ă���B�@���{�̊����s��̊O���l�����Ƃ̊��荇����3-4���肾�Ǝv�������A���{��Ƃ͂��ꂾ�������̉\��������B�i��2�j�@���{�̊�Ƃ͑n�Ǝ҂��В��������肻�̖��Ⴊ�В���������ƁA�v������̐[���o�c�������ƕ����B�@����ȉ�Ђ��A�������č��̃n�Q�^�J����i��3�j�ɓn��A��̂���Ă��܂��B �@�����������̒l�i���Ĉ�̉��ȂB�@��ԉ���₷���l���āA����1�ł�����������痘�v�ƃ��X�N�������̃��m�ɂł���ƍl����B�@���Ƃ��Ă������悤�Ɋ����邵�A���v�����E�ł���قnjo�c�������铊���͈�ʓI�ɂ͍l���ɂ����B�@�X�Ɍ��Z����v������ł�����A�����Ȃ��Ă��^�c�ł�����A��ʉƒ�ɒu��������ƕs�v�c�Ȃ��Ƃ��肾�B�@��v������Ղ��l����A�����̍��v���茳�ɂ��邩�ǂ������B�@��������̏�ł��邩�瑀��ł��Ă��܂��B�@���Ɏ��ʃ^�k�L�̔�Z�p���B�@�������̎��ۂ͎�`�Ƃ��̎��ԍ��𗘗p���Ďd����Ă��邵�A������܂���`�������Ă����̉�����L�т�B�@�C�O�֘A��ЂƂ̑���܂łł��Ă��܂��B�@��ԉ���Ȃ��̂����Y�̕]�����B�@�Œ莑�Y�ł��]����͎c���Ă��邪�A���̉��l���Ȃ��B�@�s���Y�Ɏ����Ă͉�����ɉ��i�����߂Ă���̂��S���s�����B �@�����������v���A����̕ω��ɑΉ��͂��Ă�����̂́A�O�X���I���炢�ɍl����ꂽ���̂悤�ȃV�X�e���Ȃ̂�����o�����X�����Ȃ��ē�����O��������Ȃ��B�@�����Ȃ�A�l�Ԃ̂��炾���O�t���i��4�j�̔]�œ������悤�Ȃ��̂��B �����߉���� ��1�j�@�G�h�K�[�E�P�C�V�[�F�@�č��̗a���ҁA�G�h�K�[�E�P�[�V�[�Ə�����邩������Ȃ��B�@��̎d���ŁA�u���{�̑啔���͊C�ɒ��ނɈႢ�Ȃ��v�Ƃ�������Ă���B�@������č��ꂽ�u���{���v�v�Ƃ����f�悪����B�@���͕����I�ƌ��������A�o�ϓI�ɒ��ސ����ł���B ��2�j�@�֑������A�O���l�����Ƃ̑S�Ă��o�c�ɎQ�悷��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B ��3�j�@�n�Q�^�J��ЁF�@���Y���l�A�������l�̂����Ƃ�������A��Ђ�蔄�肵�ė��v�Ďc�[�͌v��|�Y��������A�����������肷��B ��4�j�@�O�t���F�@�Ñ�̐����B�@���݂ɃE�`�ɂ͗���̎O�t���̉�������B�@�~�n����o�y�E�E�Ȃǂ��Ă��Ȃ��B 06�N1��24���@�}�O���̎h�g��H�c���� �@�X����Ԓ��̃}�O���߂�̔ԑg���܂����B�@�ȑO�ɂ������̂ł�����ǁA����̓\�i�[��D�ɐς�ŋ��@�͋Z�p�v�V���Ă��܂����B�@�}�O���Ƃ����Ή���Ƃ���v���Ă����̂�1�{�ނ�A��������ނ��Ă��l��3�N��1�����ނ�Ȃ��A���Ă̂ɖ����r�C�ɏo�Ă䂭�B�@�C�̒j���[��������̂ɏ\���ȏ����ł��B�@�Ƃ��Ƃ�3�N�Ԃ��1�����ނ�A�V���ꂪ�����Ċ�ԁB�@������f������������܂����B�@���̔ԑg����ƃ}�O���̎h�g�͎c���܂���Ȃ��B�i��1�j�@���܂�Ă��̕��A�����c�������ƂȂ����ǁB �@�n���C�ɂ������}�O�������邻���ł��B�@�X�y�C���ł̓}�O�����̓`���I���@������ƌ����܂�����A�̂���߂��Ă��ł��傤�B�@�Ⓚ�D�̑D���������f���������ɂ͒n���C�ł͑傫�ȃ}�O���j���̂��D���猩���邻���ł����A���{�D�̓}�O���̕ߊl���o���Ȃ������ł��B �}�O���̉���T�C�g http://www.uomaru.co.jp/contents/zushiki.html �����߉���� ��1�j�@�c�̂̉���̗����A�����R�c���Ă܂��B�@�u�H�ו���e���ɂ��Ă͂����Ȃ��v�A�Ɖƒ�Ɗw�Z�ŋ���������Ă��܂�������A�w���I�Ɋ����܂��B�@�H���͎c���ƕ��Ɏ����܂�������B 06�N1��22���@�O�����ԑg�͈�Õ��S�����点�邩 �@�A�����������A�R�����������ƃO�����ԑg��TV�ŕ������Ă�B�@����Ȕԑg���Ă���ƐH�~�������B�@�����Ď����҂̐H���ɋN�����閝���a�i���A�a�E�ʕ��Ȃǁj�𑣐i����B�@�X�Ɍ��N�H�i�ԑg���C�P�i�C�B�@�H�ׂ�Ƒ̂ɗǂ��A���Ă̂���ŁA�H�ׂ�Ɩ����a�ɂȂ�Ղ����Ă̂�����Ȃ��B�@�R���͈����A�A���͕a�C�ɂȂ�A���Č��������ƍ����͌��N�ɂȂ�Ǝv�����ǂˁB�@�Ⴆ�A���R�[���A�������b�A�v�����𑽂̂��܂ސH�i�B �@23�̂Ƃ����R�o�������u�f�H���H���N�@�v�Ƃ���1���̖{�������̐H������ς����B�@���̂Ƃ�����Y�b�g���H�ɋC��z��̏d�͓�������1-2kg�����������N�̍����A�ϐ��̂Ƃꂽ�̌^���ێ����Ă���B�@���̖{�ɏo����Ă��Ȃ���A�H������V�̎����͋��炭���ƈႤ�̌^�ŁA��������̐��l�a������Ă����Ǝv���B�@�������N�ی����ƈ�Õ��S�z���グ�Ȃ��ׂɂ͂����ƐH�������炷�ԑg�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B 06�N1��21���@���Ă� ��_���̊_���̋Ȃ���p�`�@�E�E�E���Ă����ĂĂ������y�����i��1�j �@���w�̖���@�u�����сv�i��2�j�̉̎��ł���B�i���Ȃ��H�j�@�u���Ă����Ĉ�̉������H�v���Ďq�ǂ��B���畷�����Ă������ł���B�@�ŋߑ��Ă����̃A�J�M���i��3�j���̂ƕ��������Ƃ��Ȃ��B�@�i�Ɋ��n�͂ǂ����m��܂��j�@�̂͂ǂ�����~�̕������ŏ��w�Z��1�g�̒��ɂ�1-2�l�͂Ђǂ��q�������B�@�g�[�ݔ��͉Δ��A�ǂ��ĒY���x���i�����j�i��4�j�����Ȃ���ɁA�Ƃ͌��ԕ����������B�@���ݕz�c�i��5�j�Ɋۂ܂��ĐQ����Ă̂���ʓI�ƒ�ł�����B�@�h�{�͍��t������ŁA�`������1�{�̋����\�[�Z�[�W�����6�l��3��ɕ����ĐH�ׂ�B�@���ꂩ��l����ƁA���͖��̂悤�ȕ�炵�ł����˂��B �����߉���� ��1)�@���Ă������߂���y���Ȃ�̂ł���B�@�ł܂��Ă������������o�����炾�ƁA�o�T�}�͌����Ă��B ��2�j�@��\���\�~�@�\���\�~�@�h���~�b�~���`��@���܂��Ɋo���Ƃ�܂��Ȃ��A�S���K���Ō����܂����B ��3�j�@���Ă����A�J�M�����葫�ɂł��₷���B�@���Ă��͍ŏ���ꂽ�l�ɂȂ�A�Ђǂ��Ɣ^�悤�ɂɂȂ�B�@�A�J�M���͔畆�ɏ����ȋT��R�ł���B�@�{���ɐh�������̂͐��d�����Ȃ���Ⴂ���Ȃ��l�B�������ł���˂��B�@�Ⴆ�Ύ�w�B�@��ː��g���Ă鍠�͂悩�����B�@�n�����ł����������B�@���Ă���A�J�M���ŗ₽�����������^���C�ɋ���Ő����������B�@�����Ȃ���������������Ȃ��B�@���̎�w�͂����ƑS�����ŁE�E����������Ɗ����@�܂ł��ă��N���N�B�@���̂悤�Ȏ���ł����ˁB ��4�j�@�Y�̌@���x���ɓ����ėV��ł͂����Ȃ��B�@��_���Y�f���łŎ��ʂ���B ��5�j�@���ݕz�c�F�@���ł͎��ꂩ�H�@�z�c�𔖂��čd�����݂ɗႦ����g�\���B�@�Ȃ����������A�������N�g���Ȃ����܂��čd���Ȃ�A�ۉ��͂̌��Ђ��Ȃ��B�@���Ȃ͎g���قǖȂ����܂��Ă䂭�̂ŁA�ł������Ƃ����āA�Ȃ��t���t���ɂ���Đ��@���{�����B 06�N01��20�� �~�ѓ��̂���݂�܂т��A���������B�@������2290�~ �@http://www.rakuten.co.jp/nagano-tokyu/378207/423825/447731/ ���R���������^�C�̃J���I�P�T�C�g �@http://www2.neweb.ne.jp/wc/kyanara/thaikara.html THAILANDmap �@http://www.athailand.com/mf/_Fr/PlaceListPNZ.htm 06�N01�N19�� �@���I�� ���X�̓��V�A�𐪔�����Ƃ����Ӗ����������Ƃ͂ˁB http://www.tokakyo.or.jp/dentoyaku/seirogan/ ���I�ۂ̎听���̖�����N���I�\�[�g�����A�S���̖��̖h���܂̓R�[���^�[��������N���I�\�[�g�̂悤���B�@�ŁA�������͊����ǂ��Ƃ��B http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/t11304.htm 06�N1��15���@���I��ƃ��I�X�� �������ł͋�ʂׂ̈Ƀ^�C���k���C�T���n���Řb����錾�t�����I��A���I�X�Řb����錾�t�����I�X��ƒ�`���遄 �@���I��́A�Ⴆ�A�m���J�C�A�E�{���A�i�R�����`���V�}�i���X���̖��O�j�ȂǁA�n��ő����̈Ⴂ������B�@�u���I��ƃ��I�X��͊�{�I�ɂ͓��������A�n��Ɨ��j�̈Ⴂ�Ń��I��ƕ����I�ɈقȂ�v�@�ƁA����̃r�G���`�����K��Ŋm�M�����B�i��1�j�@�^�C�̋��ʌ�͂������^�C��ł��邪�A���I��̓C�T���n���̋��ʌ�ł���B�i��2�j�@���[�����ƌ����邱�̒n��̓`���I���x�̉̂̓��I��ʼn̂��CD�AVCD�ő����o����Ă���B�@�C�T���n���̓��{�l���݈��̒��ɂ̓��I��̓y���y���ł��^�C��͑S���m��Ȃ��l����������B�@�o���R�b�N�ł����I���b���l�͑�R����B�@�����̌o����ł̓^�N�V�[�^�]���8�����炢�̓C�T���n���o�g�Ń��I���b���B�@�^�C��ƃ��I��͌Z�팾��Ń��I��ɕ����͂Ȃ����A���I�X��̕����̓^�C�����Ǝ��Ă���B�i��3�j�@2�̌���̔����͏�p��̒��ł͑S���قȂ���̂��������邪�A����̌��t�͖w�ǃ^�C��̗}�g���C�T���d�l�ɕς��Ă����B�@�O����̉e���Ɋւ��ẮA���I�X�̏ꍇ�̓t�����X�A���n�x�z���Ă���̂ŁA�t�����X��̉e�����Ă����i��4�j�A�^�C��̏ꍇ�͉p��̉e���������Ă���ƌ����Ă���B�@ �@
�����߉���� ��1�j�@����P00��Ƃ����܂�����Ȃ��B�@1����x����E�E ��2�j�@���{�̈ߗ��Ƀv�����g����镶����99���p�ꂾ���A���{�̈ߗ������Ă���Ƃ�����t�@�V�����Ƃ͌����A�u����قǎ����̌����a�鍑�����n�Y�J�V�C�v�Ǝv����B�@�ߗ��ƊE���悭�l���Ăق����ł���B ��3�j�@���T�C�g�A�u�^�C���̗��j�v�@�Q�Ƃ��ꂽ���B�@�g�b�v �� �k����L�[�{�[ ��4�j�@�m�l�̃^�C�l�Ń��I�X�Ƀt�����X����w�тɍs�����҂ƃt�����X�������w�тɍs�����l������B ���Q�l�T�C�g�� ���I�X�� http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AA%E8%AA%9E �C�T����i���I��j http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%B3%E8%AA%9E
�@�R�����悭�ʍs���鎩����20�N�O����A�����ʏ�����_�ɂ����Ă�ƕ֗����Ǝv���Ă����B�@�^�]���Ȃ��l�͉���Ȃ������m��Ȃ����A�M���@�ɂ��킹�Ē�~�Ɣ��M�̂������ł���B�@���̎c���ԕ\�����������u�ԁA�u�������{�Ȃ�M���O�����v���i��1�j�p���ȁB�v�Ǝv�����B�@���߂Č����B�@���{�ɂ�����̂�������Ȃ��B�@�Ƃ����̂��������݂̖^���ɐq�˂�ƁA�u�ǂ̂��炢�ɂȂ邩�Ȃ��B�@�O���炠���B�v�ƕԂ��ꂽ�B �����߉���� ��1�j�@�M���O�����v���F�@�����Ԃ�o�C�N�ŐM�����X�^�[�g���}�Ɍ����ă_�b�V���͂��������V�сB�@�G���W���̐���������Z�p���ׂ�ڈ��ɂ͂Ȃ�B�@�����ԃ��[�X���ł��X�^�[�g�̍��}�͐M���@�ɂȂ��Ă���B�@ 06�N1��9���@�c�ɂ͊�Ȃ� �@�^�C�l�̃C�^�`���[�ɂ��A�^�C�̓c�ɂ̓o���R�b�N���y���Ɋ댯�x�������B�@���R�͌x�@�������Ȃ�����B�@�^�C�̑啔���̌x�@���̓^�C�̍��v�ɒ��ڌ��т��O���l������Ă����B�@�Ƃ��낪�c�ɂł͌x�@�����ɒ[�ɏ��Ȃ��B�@�c�ɂň�l�Ń^�N�V�[�ɏ���ĉ����֍s�����Ƃ͔��������������B �u�t�@�����i�^�C��ʼn��Đl�j�Ȃ����ɂł���l�ł��邺�B�v�ƌ����ƁA�C�^�`���[�͐�Ԃ��B�u�����̂����ɉf���Ă݂��B�v�@�Ԃ����t���Ȃ������B �@�^�C�ł́A�t�@�����i�����Đl�A���l�j�͍ȗk�}��{�ł������Đ키�Ƃ����Ă���B�@���ɓ��{�l�́A�^�C��Ń^�[�E�J�E�i�������ځj�ƌ����A���a�҂̎����w���B�@�S�����Ȃ��i��������ςȂ��j�����̃C���[�W���������B�@�C�O�ő_���Ղ����R��������Ȃ��B�@�@�푈���Ȃ��ƌ��@�ɏ�����Ă��邪�A�댯�ɎN���������R��`�E�E����Ȃ��Ƃł����̂����{�l�I
�@�O���Ȃ̈��S���ł́A���I�X�̏P���������������Ă���ꕔ�̒n��́A�u�n�q�̐�����������Ă��������v�A��s�r�G���`�����́u�\�����ӂ��Ă��������v�ƂȂ��Ă���B�@��ʋ@�ւ�_�������������E�P���������������Ă���B�@���O�ł͉����ł����Ă��u���S�ł��v�Ƃ͌����Ȃ��B�@�i�\���s�\�ȎE�l�̋N������{�����l�����B�j �@���I�X�ɂ�4��s�����Ƃ����݃^�C���̗F�l�ɂ��A���I�X�̓c�ɂł͎����E���̂���R����A�^�C�l���������̓��I�X�̓c�ɂɍs���Ƃ��̓{�f�B�E�K�[�h�Ƃ��ă��I�X�̌x�@�����ق��Ƃ̂��ƁB �����߉���� ��1�j�@���I�X�̓��I(LAO)�ɏ��L�i���邢�͕�����S���������B��Ɛ�������B�@���I�X�ƋL�q���悤�Ƃ���ƃ��[�}��-�J�i�ϊ��Łu�������v�Ɖ��x���Ȃ��Ă��܂����ɕs�����B�@�ǂ�����L���������ɓ��Ă�B�@�N���l�����B ���Q�l�T�C�g�� �O���ȊC�O���S���@�^�C http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=007#header �O���ȊC�O���S���@���I�X http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=020#header 05�N12��20���@�G�W�\���L�O�� �@�G�W�\���Ƃ������ł͕ی����̕������Ɏc���Ă��邪�A�����̃G�W�\���̂��Ƃł���B�@���̋L�O�肪���{�ɂ���E�E�����łȂ��A���̏��Ȃ͓d���̃t�B�������g�Ɏg�����|�̋������ł��铖�n�ɂ���Ƃ͂���܂��������B http://www.gijyutu.com/ooki/tanken/tanken2003/edison/edison.htm 05�N12��17���@�~�� "���N�̓~�͊����B�@���w�Z����̂悤���B�i��1�j�@��10���A�Ԃ̊O�C���v��������X�_��1���B�@�͂�2-3Km��������Ă��Ȃ���n�̏�ɂ���R���r�j�G���X�E�X�g�A�ł�3�x�B�@����4������������B�@���x�v���^���A�Ăьv��ɑ���B�@�덷�͂��邪�X���͓����B�@�ǂ����ăE�`�̎��肾�������H�@���ӂ͒g�������Ȃ̂ɁB�i��2�j�@ �@����Ȃ��ƂɊW�Ȃ��A���T�͉~������C�ɐi�B�@12��5���A121.12�~�i��3�j�̈��l��������A��1�T�Ԃ̗x�����o��16����115.73�~�ƁA���T1�T�Ԃň�C�ɖ�5�~�����Ȃ�I�����}�����B�@�܂�105�~���炢�܂Ői�ނł���Ȃ��B�@�߉ނ̏��̏�̑����ł��B�i��4�j�@�ł��ނ�̒��ł͂�����́A���ꂽ�́A�A�C�c����ߏo�����̂��낢�날���ł��傤�B <���߉��> ��1�j�@�̂͊��������B�@�n�����g���Ƃ������t�͂��̌�10�N�ȏサ�Ă��炩�������悤�ɂȂ����B�@�C����10�N�P�ʂő傫���ω�����A�ƌ����Ă��邪�A�����10�N�̎n�܂肪���N��������Ȃ����B�@���̍��͎R�e�̐��c�ɒ������X�̏��n�邱�Ƃ��ł������A�ŋ߂ł͕X���������Ȃ��N�������B�E�E���Č����O�ɐ��c�������Ȃ����B�@�����X�̒��鐅�c�͍��͍r�n�ɂȂ��Ă���B�@���c����Ă����g�b�c�A���͂̓W�T�}�ɂȂ���т���̖����ŗD��ɂ��B����炵�Ă���B�@���q�̕��̓T���[���[�}���ɂȂ�G�����Ȃ����B�@ ��2�j�@���͉��߂ɂ�����߂ɂ����A�Ƃ͏��w�Z�̂Ƃ����Ȃ̐搶���������B�@���̗����ł͉䂪�Ƃɂ͓~���x�����ďt���x�����锤�����B ��3�j�@�^��s�O�������i���l ��4�j�@����Ȃ̗͂��֎����悤�ƁA����Ƃ�_�ɂ̂��āA�����֔�т܂��邪�A�ǂ���ɔ��ł����Ă��߉ނ̎�̂Ђ�Ƀu�`������B�@�S�Ă͎߉ނ̏��̏�ł������A�Ƃ����n�i�V�B 05�N12��11���@��֎���� �@�V�т̋A�蓹�ŁA�č���֎ԃ��[�J�[H-D���i��1�j�̓W���������鎖���v���o���ĕ�ԍۂ̉��Ɋ�����B�@�D��100�����W���Ԃ�����ł����B�@�v�����Ŋ�������玎�摕�����Ȃ��B�@�r���[�G���i��3�j�ɂ�����ƌׂ��Ă݂��B�@�a�V�ȃf�U�C���͎��J�u�g���V�̃C���[�W���B�@�O�ς��X�e�A�����O���y�����^�[�h�i��4�j�̂悤�Ȋ��������������B�@2�C���̔r�C�ǂ������B�@�G���W���̌ۓ��������Ă���悤���B�@�ܘ_�~�����ł��B �@H-D�Ђ͍ŋ߁A��|��Ȏ�������{�e�n�ōÂ��A���{�s��ɔ��荞�݂������Ă���B�@�̔��䐔�̊g��X�����猾���ƁA���̂܂܂ł͓��{���̑�^��ւ͏����h�ɂȂ肻���Ȑ����ł���B�@H-D�Ԃ̐l�C�̓G���W�����������邱�ƂȂ���A�p�[�c�̃A�t�^�[�E�}�[�P�b�g�̑傫���ɂ���B�i�Ǝ����͓ǂ�ł���j�@�p���[�A�b�v�d�l�̌������i�͌����A�`���b�p�[�d�l�i��5�j�̕��i�A�N���[�W���O�d�l�i��6�j�̕��i���X�A�N�ヂ�m����ŐV���f���Ɏ���܂ŕ��i�_���͖����ɂ���A���\�N���O�̋��Ԃ��A�t�^�[�E�}�[�P�b�g�̐V�i���i�őg�ݗ��Ă��Ă��܂����ł���B�@���̓_�͓��{�̃��[�J�[���ǂ�ȂɊ撣���Ă��ǂ����Ȃ��AH-D�Ђ̖��`�̎��Y�ł���B �@�A�����J���E�E�@���̌��t�͓��{�ɂ͎����������Ȃ����A�č��̖@�萧�����x�͓��{�̖@�萧�����x�ɋ߂��Ƃ����͌�����B�@�������x�̂Ȃ��A�E�g�o�[���i��2�j�𑖂鎖��O��ɐv���ꂽ���������A�����������ăK�j�҂ɂȂ�̂��s�v�c�ȕĕ��i�A�����J���j�̕�����ʒʍs�҂ɗD�����E�E�����͕ʂɂ��āB�@����]�^��200����/���ł�300����/���ł��o����{�̑�^�Ԃ̃X�y�b�N��ׂ����̐��\�Ƀ��[�U�[�͖O���O�����Ă���̂��������B
�@5��1���̓��[�f�[�Ɠ��{��ł͏����B�@1886�N�̕č��̃f���Ɉ���ł���Ə�����Ă��邪�A����A�č��f��̋~���v���̃��C�f�C�iMayday�j���Ă͈̂�̉��ȂH�@�@�ꌹ�̓t�����X��� maider�@�ŁA�p���help me�ɑ�������悤���B 05�N12��9���@�S�ƐS�� �����a�̎��Âɍ����ڐA�Ƃ�����i������炵���B�@���̃h�i�[�𗊂܂ꂽ�F�l�A�����̍��۔���O�ɁA�S���̖��Ńh�i�[�ɂȂ�Ȃ��ƌ���ꂽ�B�@�S�d�}���ߋ��ɐS�؍[�ǂ����������������Ă���Ƃ������A�{�l�͑S���S�؍[�ǂ̋L�����Ȃ��B�@�Ƃ������Ƃ́A�S�؍[�ǂ͓���I�ɋN���Ă��邪�m��Ȃ��l����R������Ă��ƂȂ̂��H �@ �@���{��ł͐S���ƐS�͊����͓��������A�S���C���[�W�̈Ⴄ���m���w���B�@�p��ł̓n�[�g�͐S���ƐS�̗������Ӗ�����B�@�X�y�C����ł̓R���\���A����������B�i��2�j�@�^�C��ł��z���`���C�ƌ����A�����̈Ӗ�������B�@�E�E�Ȃǂƍl���Ă���ƁA�S���Ƃ������t�͒�������̗A���ꂾ�����B�@�S����������a���t�̓L�����B �@�L���͊����ŏ����Ɗ̑��̊̂��B�@�u�̂̓��{�͉�U�w�����B���Ă��Ȃ��A���w�ʼn�U���w�ԁi��3�j�܂ł́A�����̓������������{��́h�L���ƃ��^�i�̂ƒ��j�h���炢�����Ȃ������B�v�A�ƒ��w�Z�̎Љ�Ȃ̐搶���b�����B�@�u�̂������Ă���v�u�̂��ʂ��傫���v�u�̂ɖ����āv�A�ȂNĴ͖��炩�ɐS��������a���t�ł���B�@�u���ꂪ�ǂ������H�v�Ƃ�������ɂ́A�u�ǂ������˂���B�v�Ɠ����Ă����܂��傤�B �@�S���S���Ȃ�A�S���ɂ͍l������v�����肷��@�\������̂��H�@�Ɣ��_�������Ȃ�B�@�т����肷��ƐS���Ɉ��͂��|���邱�Ƃ����F�ł��邵�A�l�O�ł��܂���낤�Ƃ��鎞�͐S����������łB�@�����I�Ȃ��肪����ɂ���A�u�l����E�v���v�Ƃ����@�\�͂Ȃ��Ǝv����B �@�������A�S�͒P���Ɂu�l����E�v���v�������ƍ��x�ȕ�����i���Ă���A�ƍl�����Ă���B�@�Ⴆ�A�Ñ�C���h���K�ł͐S���̕����Ƀ`���N���i�_�ʗ͂��N�������j���݂��A�_���̈ꕔ�ł͐S���̕����Ɍ��i�݂��܁j������Ƃ��Ă���B�@�ǂ�����ڂɂ͌����Ȃ��B�i��4�j�@�����̎v�z�ł͐S���͕��̂Ɣ̂̓�d�\���ɂȂ��Ă���B
05�N12��8���@�e���b�N�X�@telex�i��TEX�j �@�́A�e���b�N�X�i��1�j�Ƃ������̂��������B�@���͂�d�b�̐����g���đ���ɓ`����ݔ��ł���B�@�e�`�w�̕��y�Ő�Ŋ뜜���i��2�j�Ɏw�肳��A�d�q���[���̕��y�Ő�ł����B�@�d�b����ŕ����M���𑗂�A�����̒[���@�ŐM�����f�B�R�[�h�����ɑł��o���B�@�[���̓^�C�v���C�^�[�Ɏ��e�[�v���r�E���ǎ�@�����Ă�����́B�@�d�q���[���̑O�g�ƌ��������A���[���X�M���i��3�j�̖|��@�Ƃ�������悤�Ȃ��̂��B�@�^�C�v���C�^�[�����̂悤�ȃC���N�W�F�b�g�ł��Ȃ���h�b�g�ł��Ȃ��B�@�����ق⍜���i���Ō���A�ʂ�`���ĕ��ׂ�ꂽ�A�[���Ɋ���������Ă���^�C�v���C�^�[�B�i��4�j�@�ǂ��Č���^�d���^�C�v���C�^�[�ŁA�������~����ɕ��ׂ��Ă���A�ǂ����ɂ��Ă����ł͌����Ȃ����̂��肾�B �@��25�N�O�ɕ������e���b�N�X�̏��b���Љ�悤�B
����Ɠ��� <���葤> �@���͂��e���b�N�X�[���@�ŃG���R�|�h�����e�[�v���r�E����B �A�d�b�����̒[���@�ɂȂ��e�[�v��ǂ܂���B �B�[���@���e�[�v�̌�����ǂ��A�M�������đ���̒[���@�ɑ���B �@ �@�v���^�C�s�X�g�̂悤�ɐ��m�ő����łĂ�A�d�b������q���ł����Ă��當�͂��^�C�v���Ă��ǂ��B �������^�C�v�̕s���ӂȓ��{�l�A�������̂̓o�J�������ۓd�b�Ȃ̂ŁA��\��ŏC�����J��Ԃ������e�[�v��ǂ܂�������R�X�g��}���邱�Ƃ��ł����B�@�^�C�v�͉��ĕW���̃A���t�@�x�b�g�Ƒ����̋L�������������̂ŁA���{�l���m�ł̓��[�}���\�L�Ȃǂ��g���Ă����B <��> �@�d�b������瑗���Ă���M�����e���b�N�X�[���@�Ń^�C�v����B ���邢�͎��e�[�v���r�E����B �A�r�E���ꂽ���e�[�v�͒[���@�Ńf�B�R�[�h���ČJ��Ԃ��ł���B �e���b�N�X�p��Q�l�T�C�g http://www.millionmiler.com/philippines/etc/Celphone_Abbreviation.html 05�N12��7���@���Ȃ����̃I���WTV�o�� �@�m�l�̂��Ȃ����̃I���W��TV�ɏo�������B�@�Ƃ����Ă��O�����ԑg�����B�@�|�\�l���H�ׂ�ׂŁA�u�J�j�k��v�̂悤�ɍ����ė����̐��������Ă����B�@���̏�ʂ��ƒ�p�r�f�I�̂悤�Ɏʂ��Ă����̂���ۂɎc�����B �@�Ƃ���ŁA�l���Έ�тł��Ȃ��ƌ����A���݂���i�����j���B�@�������̂��ȏd�͔����i���܁j���B�@�V�����͗����̃v���Z�X�ƍޗ����猾���Ɗ��������A�V�~�Y���̃E�i�M�͑S�R�����Ǝv��Ȃ��B�i�Ƃ͖J�߂��������j�@�������[���������閡�i�V�܂��Ă��ƂŎ���Ă����悤�Ȏ��������j���ȁB�@�������Ȃő҂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�i��1�j �����߉���� ��1�j�@�c�ɂŐȑ҂��Ă�X���Ă͖̂ő��ɂȂ��B�@�c�ɂ̈��H�X�͓X�ɑ��]�ƈ������Ȃ��̂ŐȂ�҂̂łȂ��A�Ȃɂ��ė�����҂̂ł���B�@�������A���݂���͏����ɐȑ҂��Ȃ̂ł���B�@�@�����҂��Ɛȑ҂��ł͑傫�ȈႢ�Ȃ̂ł���B 05�N12��6���@PDF���� �@�W�F�g���i��1�j�ɂ��A�^�C��2006�N1��1������@��Œ����(���ʂňقȂ�)�����g����B�@�ڂ������e�͗L���z�M�Ȃ̂ō��͏����Ȃ����L�эs�����͑A�܂������̂��B�@���{���J���҂̒��������N�オ��悤�łȂ��ƌo�ς͐L�тȂ��B �@ �@����Ȃ��Ƃɂ͊W�Ȃ��A�ŋߗ��s��PDF�`���̃T�C�g�B�@���@�[�W������1.0�オ��x�ɋ����ɏd���Ȃ�APDF�̃��[�_�[�����[�h�����܂ŁA�W�b�Ɖ�ʂ��ɂ݂��Ă���B�@�@���܂��ɃR�s�[�͂ł��Ȃ����A�o�[�W�������オ��ƁA�Â��o�[�W�����ł͓ǂ߂Ȃ��Ȃ�B�@�S������l���E�E�܂�ڋq�����x���E�E�x�O�������\�t�g�Ȃ̂ł���B�@����Ȃ킯�ŁAPDF�ō��ꂽ�T�C�g�̓p�X���Ă��邪�A�����G���W���ɂ͏�������Ă���Ƃ��������ƁA�������{�b�g�ł�HTML���l�Ɉ����Ă����ł��傤�Ȃ��B�@������Ƃ��날��B�@�������t�H���g�͊g�債�Ă��M�U�M�U�ɂȂ�Ȃ��Ƃ���ł���B �����߉���� ��1)�@�Ɨ��s���@�l���{�f�ՐU���@�\�@JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION(JETRO) 56�J���Ɏ������@ �E�������O��1,660���@ http://www.jetro.go.jp/jetro/ 05�N12��1���@�����S �u�˂��A��������A�h��������������h���Ăǂ������Ӗ��H�v�@�ۈ牀���̖Â��V�����玩���̓ǂ߂銿���������ĕ��i�܂莩���̌Z��j�ɖ₤�B�@�ޏ���genuine(�{����)�V�ˎ��ł���B�@�������ǂ߂邱�Ƃ��V�˂ł͂Ȃ��B�@�����Ȃ��Ă������Ńh���h���m���𑝂₵�čs���Ƃ��낪�A�V�˂́h�V�h�̕������B�@�m���s���ĂȂ������҂��̗��e�ł���B�@�ۈ牀���ɂ��ď��w1�N���̊����͖w�Ǔǂ߂����łȂ��A����ȏ�̊������m���Ă���B�@�u����́h������������h���ēǂނ�B�@��������������Ă��ƁB�v�@�ޏ��̕����������B �@�p�ݐ푈�̎��p�g���I�b�g�Ƃ����~�T�C�����悭����Ă����B�@�p�g���I�b�g�͓��{��ň����҂Ɩ��B�@�푈�ɂȂ�Ɓu�����v�Ƃ悭�����邪�A�����͒����Ԉ����Ƃ͍��������邱�ƂŁA�Ƃ������Ƃ������邱�Ƃ��Ɗ��Ⴂ���Ă����B�@���ł͈����S�Ƃ͎����̉Ƒ��A�g�����O���̐N����U��������B�@�X�P�[���_�E�����āA���v���l����E�E���Ƃ��Ɨ������Ă���B�@���̗����Ō����Ύ����͈����҂ł���B 05�N11��30���@ �@�č��ł̓T���N�X�E�M�r���O�i���ӍՁj���I���ƃN���X�}�X��F�ɂȂ�Ƃ������̋G�߁A��ʏ���A�č��ł͔��K���i�i�p�\�R���Ƃ��ߋ�j�̔N�Ԕ���̂V�O�������̋G�߂ɏW������Ƃ����B�@���T����{�i�I�ȃZ�[�����n�܂����ƕ��ꂽ�B�@���{�̃��W�I�����̖w�ǂ̔ԑg�ŃN���X�}�X���b��ɏ��̂ŁA�_���̃i�}�N���M�҂̎����́A��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ȋC�����ɂȂ�B�@���f����̓��{�l�̐S�i��1�j�͖����Ȃ����B �@���w�Z2�N�܂ŃT���^�N���[�X��M���Ă����̂ŁA�C�u�ɂ͌C�����Ԃ牺���ĐQ���B�@�K�b�R�ŁA�u����T���^�N���[�X�ɖ�����B�v�ƌ�������A�u�o�J���Ȃ��A�T���^�N���[�X�Ȃ�Ă��Ȃ����B�@����͐e���E�E�v�ƚ}���ꂽ�B�@�����ɋA���ĕ�Ɍ������B�@�u�ǂ����ċ����Ă���Ȃ��I�K�b�R�Œp�������B�v�@ �N�Ƌ��ɃN���X�}�X�̓L���X�g���̍s���Ƃ����T�O�������̒��ł͑傫���Ȃ�A�u�_���K���o���I�@�O���̏@���ɂ��ǂ킩�����ȁB�@�t�����V�X�R�E�U�r�G���������I�v�ƐS�̒��ŋ��Ԃ̂ł���B �@����Ȏ����l���Ă�����ɁA�O���l�̗F�l�B����N���X�}�X�J�[�h���͂��A�u���f����̏@���A�_���͂ǂ����₩���������A�r�W���A���ŏ��ĂȂ��Ȃ��B�v�Ǝv���̂ł���B �@�N���X�}�X�E�J�[�h�Ə��������A���̎����̓N���X�}�X�̌�ɐ���������̂ŁA�����[�E�N���X�}�X���n�b�s�[�E�j���[�C���[�������B�@�����Ē��ؐ���������̂ŔN��A�������̓��{�ł͐����C���������܂����Ă���͂��ꍇ������B�i��2�j�@���V�A�������N���X�}�X��1��7���ɁA���_�����ɂ��n�k�J�i��3�j�Ƃ����s��������B�@���_����25���B�i�˂��������������H�j�@���{�����͓V�c�a������12��23���Ȃ̂ł���B �����߉���� ��1�j�@���f����͍]�ˎ���̉��v����łȂ��A�ߑ�ɂȂ��Ă������Ă������Ƃ͑c��Ɠ��������o���̂��鎩���ɂ͗ǂ�����B�@�o�T�}�̐���ł́A�܂�̂̓��{�l�̓n�f�ɂЂ��炩�������T���߂ɁA���䂩�������邱�Ƃ������Ƃ���Ă����B�@�]���A���i�̐����͂����������Ă��n���Ȃ̂����{�l�Ȃ̂ł���B�@�������n���ȕ��͓����ɉꂽ���Ƃ����{��L����������������Ȃ��B ��2�j�@����̐����͂����Ă��̏ꍇ�A���z��1�����{����2����{�ɂȂ�B ��3�j�@�n�k�J�F�@�a.�b.�P�U�V�@�}�J�x�A�푈�Ń��_���l���������L�O�̍Ղ�B�@ �@�n�k�J�̍Ղ�Q�l�T�C�g�@http://www.zion-jpn.or.jp/p0406.htm 05�N11��28���@���イ���R �@�����̃j���[�X�Ń��t�[�̃T�C�g���x��j�Z�E�T�C�g�ŁA�u���イ��������ɍU�ߍ��v�Ƃ����T�C�g�����J�����j���ߕ߂��ꂽ�ƕ��������A�����11/25�͂��イ���̓ˑR�̌R�����K�A��������p�̌������̕����ȕt�߂ƌ����A�͖�-��t���C�g���啝�ɒx�ꂽ�B�@���イ���̌R�����K�͒ʏ펖�O�ɒm�炳��Ȃ��A���̗��R�́A�u�X�N�����u���ꏊ�̋@���v���������B 05�N11��27�� �@�g�t�^������B�@���������R�͌͂�͕�����B�@�u�����[�Q���̊G���v���o���B�i��1�j�@�R�ԕ��͕��i�����ɔN��10�炢�͍s���B�@�ߍ��̎�v�R���͉��P�����i��2�j�A�R���ɂ����Ȃ�s���₷���Ȃ��Ă����B�@���̂��߂��A�R���ɂ͎s��+�y�Y���̂悤�ȓX�������A��X�ɂ͒������R�̍K�����邱�Ƃ��ł���B�@�s���~�܂�̉��R���i�����j�̂���ȓX�ŁA�����ʋl�▢���H�̓����t���p���Ă����B �i��3�j�@ �����߉���� ��1�j�@�u�����[�Q���̊G�@�u�ᒆ�̎�l�v�@http://www.ne.jp/asahi/ynym/kim/u07.htm ��2�j�@���Ă̓J�[�u�E�~���[�ƃJ�[�u�̏o���̗��������Ȃ��瑖���Ă��������R���A���邢���@�����⋴���ɂ���Ē���������A�����g����2�ΐ��ɂȂ��Ă���Ƃ���͐�����Ȃ��B�@���ƎR�������ԓ��̉��P���x�ꂽ���Ƃ͐l���s�s���W���̌����̈�Ő���̎��s���낤�B ��3�j�@�p�͎Ԃ�w�����b�g�ɂ���Ƃ�����������Ȃ��B�@�����g�����������Ȃ������������A���̕��͔����Ă݂��B 05�N11��23���@�@�B���l�𐧂���� �������s�̎����Ԃ̃��R�[���Ńf�B���[�ɍs�����B�@�n�i�V�͔���邪�A�V�Ԃ��ƁA�X�����ڋq�ԓx������Ă����͎̂Ԃ��Ă���6�������ŁA�ȍ~�A���̂��q�͎ז����m�����ɂȂ�A�Ǝԉ��𗝉����Ă���B�i��1�j�@�V�Ԃ̔̔����v�͒Z�������ł���B�@���R�[���Ƃ��Ȃ�ƁA���ė~�����Ȃ��q�����@�I�ی���Ă���̂ŃC���C���Ή������i�悤�ɂ݂������{�l�̐S�͓ǂ߂Ȃ��j�B�@ �@�ȑO����Ă��ԂȂǁA�Â����i��2�j�Ԍ�����������ƁA�X�̗��ɒu����Ă����B�@������2-3�N�͓X���ɒu����Ă��������B�@����ȃf�B�[���[�ɂ͂����b�ɂȂ�Ȃ��悤�ɏ���҂ŏ����o���������B�@�Â��Ԃ��f�B�[���[�Ɏ������܂ꂽ��A�f�B�[���[�͖����Ń����e�E�C�����邭�炢�̃n���������Ă������B�@���̂Ȃ�A�@�Ԃ̑ϋv���̏��i��3�j�ł���A�A��������Ԃƃf�B�[���[�̐M�]�̏Ȃ̂�����B�@���A���Ԃ͂����������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�߂����B �@���āA����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悭�A�{��ɂ͂��낤�B�@����������͎̂ԍڃG�A�R���̓���܂ŃR���s���[�^�[�ɋL�^����Ă��邱�Ƃ��B�@�܂荱�ׂȎԂ̓���̗������c���Ă���B�@���̗����ɂ��čŏ��ɋ������̂�ABS�i��4�j�̓���L�^�������B�i��5�j�@�����͐��퓮�삩�A�ُ퓮�삩�L�^����Ă���B�@�Ƃ������Ƃ́A���̂��N�����Ƃ��A�u���[�L��/���܂Ȃ��Ń�������A�����w����͍쓮���ۂ��A�S�Ă��ԗl�������m�A�Ƃ������ƂɂȂ�B�i�g�ѓd�b�����Ă��邪�j�@�^�]�҂̈ꋓ�ꓮ���ԂɋL�^����Ă���B�@�₪�ċL�^�͕⏕�E�����ɁA�X�ɂ͊Ď��Ƃ������ƂɂȂ�B�@�^�[�~�l�[�^�[�i��6�j�A�Â��̓L���V���[���i��7�j�̕���w�i�ɋ߂Â��Ă����B ���������߁� ��1�j�@�ڋq�ԓx�̖��m�ȈႢ��ڂ̓�����ɂ���ƁA�u�s���R�v�Ƃ����v����B�@�u�����͖@�̉��ɕ����v�Ə��w�Z�̎Љ�̎��ԂɊw�сA�u�@�̉��v���u���z�̉��v�Ɗ��Ⴂ���������́A������������������Ƒ�ϕs���Ɏv���B�@���a�ȁu���z�̉��v�ł͐ŋ����R�[�߂�҂��������A�������g���Ă����l���G�����悤�����A�v�����^���A�[�g�Ƃ��ẮA�ǂ��������M�������Ȃ��B ��2�j�@������{�ł͎Ԃ͋C�ɓ��邩�璷�����̂ł���B�@���������Ԃ�v�`�̔����邱�Ƃ����[�J�[��̔��X�̌ւ�̃n�Y�Ȃ��ǁE�E���w�����̐��E���B�@ ��3�j�@���{�Ԃ̑ϋv���͏\���A�ȂǂƎv���Ă��͂����Ȃ��B�@��������Ă���ƁA���[�J�[�̍����o�Ă���B�@�����̋��x�␠�����i�͎g�p���Ŏ��n�ω��̕��i�e�X�g���ł��Ȃ��̂ŁA�����̑ϋv�͎��тƗ\�z�ł����Ȃ��B�@����������������ԍ����o��B ��4�j�@ABS�F�@Anti Lock Brake System�@�u���[�L���쓮�������Ƃ��A�����Ȃ�ւ̉�]���~������ƃ^�C��������A���������������Ȃ�B�@�^�C�������钼�O�܂ŗւ̉�]��}���R���g���[�����鑕�u�B�@�����H�A�G�ꂽ�H�ʂł͓��ɗL���B ��5�j�@�w����1-2�T�Ԃ߂̍��������B�@�䕗�ŗ�������ʂ̏��t�ɗւ�����A�O���ԂɏՓː��O�A�����炭���Z���`�Ƃ����M���M���̂Ƃ���Œ�~�����B�@�u���[�L�E�y�_���͐̂悤�ɍd�����ݍ��߂Ȃ��Ȃ����i�`�a�r�쓮�̏j�A�@�`�a�r���o�������͏��킩�炸�AABS�̌듮����^���������B�@ABS��4�֒��P�֊����Ă��S��ABS���쓮���A�����͊������ւ̐�����4�֓�������̎ԔC���ɂȂ�B�@����3�ւ������͂��ł����Ƃ��Ă��A��Ԋ����Ă���ւ̐����͂ɍ��킹����̂ŁA���������͑���������������Ȃ��Ă��܂��̂ł���B�i�����܂ł��ȑO�̘b�ŁA���͓Ɨ�����ABS��������������Ȃ��j�@ABS�͐�ɊW�Ȃ���X�̒n���ł͖{���ɕs�ւ��ƐS����v���Ă���B�@�}���z�[���W�̏�͓��풃�ю���ABS�������Ă��邪�A����͈�u�ŏI���̂ŋC�t���Ȃ���������Ȃ��B�@�@�G���W�����[��������ƁA�`�a�r�킪�ȒP�Ɍ�����B�@���[�^�[�쓮�̃u���b�N�{�b�N�X�ɁA4�ւ���L�т��u���[�L�E�I�C���̊ǂ��W�����Ă���B ��6)�@�^�[�~�l�[�^�[�F80�N��č��f��@�@�B�Ɛl�ނ̐킢�ɖ������Ă��関�����猻��Ƀ��{�b�g�����荞�܂��B�@�l�ނ̎w���҂̐�c���Ȋw�������B�̌���ō���₵�ɂ���ړI�ł���B�@���荞�܂ꂽ���{�b�g��|���ړI�ŁA�����ォ���m�����荞�܂�Ă���B�@�@�s�u�ʼn��x�����f���ꂽ�B�@�V�������c�F�l�b�K�[���b�a900�e���A�N�Z���^�[��������V�[�����v���o�[���B�@���B���s�\���Ȏ���̃��m�ł���B ��7�j�@�L���V���[���F(�L���C�[���ł͂Ȃ��E�E�O�̂���)�@70�N��̂s�u�A�j���B�@���{�b�g���x�z����n����l�ނ̑��S���|���Đ키�T�C�{�[�O��m�A�L���V���[���̎������E�E����Ȃ��A�퓬�̓��X�̕���B�@�I�m�Ɍ����Ȃ����A�G���ǂ������B 05�N11��18���@�J�b�g�\�[ �@�J�b�g�\�[���Ĉ�̂Ȃ��H�H�H�@cut saw�@�̂��Ƃ��Ǝv���ăV�Q�V�Q�ƒ��߂郌�V�[�g�B�@�X�̖����炵�ē���ł͂Ȃ��悤���B�@�J�b�g�\�[���l�b�g�Œ��ׂ�B�@ cut and sewn�@���t���̂͐��ĖD�������Ă��炢�̈Ӗ����H�@�j�b�g���i�炵�����������B�@�������₱�̂Ƃ���j�b�g�̃V���c����ʂɔ����Ă�ȁB �J�b�g�\�[�̐���������Ă�T�C�g http://www.ipphonecallcenter.com/bkd/cutandsawn/ 05�N11��16���@���[�C�J�g�[���@(P/C��OS��ݒ�ɂ���ă^�C�ꂪ�\������Ȃ���������܂��B) �@�����̓��C�J�g�[���Bลอยกระทง�@11���̖����̖�A��ɘX�C�����o�i�i�̗t�i�܂��̓��V�j�ō�������D���ׂ�B�@���i�I�ɂ͓��{�̓��U�����Ɏ��Ă��邪�A����ΐ��_�l�̍Ղ�Ȃ̂ł���B�@��̏��_�l���Ղ�V�����A�]���ē��U�Ɋ肢�����߂ė����̂������I�����ƂȂ��Ă���B�@�X�ɁA���̊肢�Ƃ͑��j���W�̕��ƂȂ��Ă���B�@�]���A��ɂ͑����̃J�b�v��������Ă���B�@��̋߂��Ŕ����Ă��铕�U���āA�肢�����߂Ő�ɕ����ׂ�B �@�^�C�ꃍ�[�C�͕����A�J�g�[���̓o�i�i�̗t���ςō������̂��ƁB�@�J�g�[���̓o�i�i�̗t�͒|�̎q�ō�����R�܂��͎��ō�������A�ŋ߂ł͘J�͂̐ߖ�ׂ̈Ƀz�b�`�L�X�i��1�j���g���Ă���B �@�č����Ă���^�C�l�̃I�o�T���ɂ̃n�i�V�B�i����G�a���Ɍ����E�E�����~�߂͋�����ۂ�^����j�@���[�C�E�J�g�[���ɂ�2��s�����B�@�ŏ��͑O�̒���ƁB�@��x�ڂ͍��̒���ƁB�@�ŏ��̒���̂Ƃ��͌��Ă��邤���ɓ��U���Ђ�����Ԃ����B�@��x�ڂ̒���̂Ƃ��͏�肭����Ă������̂��������B 05�N11��15�� �f�X���h���~�b�N�� �@�K�\�����̃��V�v���E�G���W���̃o���u���J���@�\���o�l�łȂ��A���b�J�[�A�[���ŋ����I�ŊJ�����J��2�̃��b�J�[�A�[���ōs���@�\�B�@�h�D�J�b�e�C���̗p���Ă���B �f�X���h���~�b�N�J���j http://www005.upp.so-net.ne.jp/takuro/article/motor/desmo.html 05�N11��13���@�u�����R�E�r���[ �@�u�����R�E�r���[�ƌ����A�č��̃E�F�X�^���E�V���[�̈����w�i�ɂ����N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�剉�̉f��A�����čŋ߂̃A�j���[�V�����f��g�C�Y�ł̓u�����R�E�r���[�̐l�`���e���ɂȂ��Ă����B�@�u�����R�͉p��Ŗ쐶�n�A�r���[�͐l���B�i��1�j �@����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悭�A����X�e�[�L���̃`�F�[���X���s���ɉ���������B(��2)�@�����́u�X�e�[�L�d�v���D���������̂ɁA���̑O�s������50���ԑ҂����i��3�j�A�Ă������̓��B�@�ǂ��������|���邩�̂悤�ɓ��̗ʂ͈ȑO��1/2���炢�ɂȂ��Ă����B�@�ɂ߂����A�l�i��1.5�{���炢�ɂȂ��Ă����ň��I�������B�i�ȑO�̓����`���i�������̂�������Ȃ��j�@�������̓X�͍s���܂��E�E�ȂǂƎv���O�ɁA���̃X�e�[�L�d�̓A���o�C�g�̃R�b�N�̍��܂������������̂��ǂ������m���߂ɍs������ł���B �@�f��u�����R�E�r���[�͎��̃T�C�g���Q�l�ɂ��Ă��������B�@���Ȃ��݃\���h���E���b�N�����@1980�N�č� http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=20783 �����߉���� ��1)�@�r���[�Ƃ����G�f�B�E�}�[�t�B�[�剉�́u�r�o���[�q���Y�E�R�b�v�v�ɓo�ꂷ��V�Čx���̃r���[��A�r���[�E�U�E�L�b�h�i��4�j���v���o������B ��2�j�@�����܂ł��@�h����X�e�[�L���h���s����ł��B�@�O�߂̘b�͖Y��Ă��������B ��3)�@�c�ɂł�����50���҂Ă�]�T������B�@�X�ɂ��q�ɂ��B�@�T���_�E�o�[�Ȃ�H�ו���̌������Ă����̂�30�����炢�܂ł͕��C�������B�@���̃V�X�e���͋q���q���~�߂Ă�����肢��i�������Ƃ͏��߂ċC�t�����B �u�H�ׂ������������ďo�悤���H�v�@�`���C�E���[���i��5�j�ɂȂ��Ă����B�@�Ƃ��낪�A���A��l�́A�u�������v�@�Ȃǂƌ����̂ŁA�{���̃��N�V�[�́h�{��̃J�E���^�[�h���o���Ȃ������̂��c�O���B �@�C�i�J�̓X�Ƃ����͓̂��X�Ґ��̌��ɂ߂�����B�@�c�ɂł͒��E���E�ӂ̐H�����Ԃ��w�NJF�ꏏ�Ȃ̂ŁA�X���Z�����̂͂�������1���Ԓ��x�ł�����z���Ƃ���ɂȂ�̂����ʂł���B�@�n��������������ɒ��ԏ�ƍL���X�������B�@����ɂ��킹�ď]�ƈ����m�ۂ���ƁA�q�����Ȃ����Ԃ���̖��ߍ��킹���ł��Ȃ��̂ŁA���̃C�i�J�̃��X�g�����͓y���̗[�H���͏]�ƈ��s���Ȃ̂ł���B ��4�j�@�r���[�E�U�E�L�b�h�@�č��J��̃K���}���B�@���ݐl���B�@���{��ł����Ȃ�u�q���̃r���[�v�B�@�u12�ōŏ��̎E�l�v�ȂǂƂ͉����̉̎��ɂ������B�@�|��������̐��������e�̏e�g�ɍ��݂����A21��21�̍��݂��������B �r���[�E�U�E�L�b�h�ɂ��Ă悭�킩��T�C�g http://www.kaho.biz/bk.html ��5�j�@�`���C�E���[���F�@�^�C��ʼn��l�q��A�{�鎖���w���B�@����ƃ`���C���S�A���[�����M���A�܂�M���S�Ȃ̂ł���B 05�N11��11���@��͐l�ׂ̈Ȃ炸 �@�u��͐l�ׂ̈Ȃ炸�v���Ă������������ƊԈႦ�ĉ��߂��Ă����B�@���̈Ӗ��͐[���ł��Ȃ��B ����܂ł̎v�����݁F�@��������Ă�����ƁA���̐l���Â��Ă��܂��A���ʂƂ��Ă��̐l�ׂ̈ɂȂ�Ȃ��B ���������߁F�@�{���͑S���t�ŁA�l�ɏ�������Ă����ƁA���菄���Ă₪�Ă͎������M�����Ⴆ��B�@�܂�A���̋������ƁA�u��͐l�ׂ̈Ȃ炸�A�Ȃׂ̈Ȃ�v���炢���H�@�������g�N���遨����Ӗ��~�[�ł��B 05�N11��9�� ginkgo biloba �@�C�`���E ginkgo�́u��ǁv��ǂ݊Ԉ�������������̂܂܉p��ɂ��ꂽ�B�@biloba�͓�t���́B�@�]�̌��s���悭������ʂ����邱�ƂŁA�s���̉��P�Ȃǂ̌���������Ă����i�Ə����Ă���j���A�э��ǑS�̂Ɍ��ʂ����邱�Ƃ���A�n�Q�̖�Ƃ��Ă����p����Ă���B�i�悤���j �ȉ��͔]�ւ̌��ʂ�������Ă���B�i���f��F���i�Ɠ��T�C�g�͖��W�ł��j http://www.mit-japan.com/ndl/ndl/Ityou.htm http://ityo.seo6.net/ �@�Ȃ��A���̃T�C�g�����N�H�i�A�T�v�������g���ۂ��Ȃ��Ă����Ⴂ�܂����B�i���N�g�Łj�@�u��ŕ����c���v�A�ƃo�T�}���悭�����Ă܂��������B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 �g�b�v�y�[�W |
�ҏW��L�o�b�N�i���o10 |
�ҏW��L�t�H�A�i���o12 |