(5) 地方自治と住民運動
<地方自治の本旨(=本来の目的・主旨)>=日本国憲法の表現
1 民主政治と地方自治
(1)自治制度
●住民自治
一定地域の政治は、その住民の意思に基づき、自らの手によって行われること。
●団体自治
地方公共団体(地方自治体)が、国からできるだけ独立して、政治を行うこと。
(2)地方自治は民主主義の源泉であるばかりでなく学校である
(地方自治は民主主義の学校である) ブライス『近代民主政治』
2 現憲法下では
第8章(92~95条)や地方自治法(1947(昭和22)年制定)がある。
3 明治憲法下では
中央集権的な自治(官治的自治)。府県知事は内務大臣が実質的に任命(官選知事)、市町村長の指揮・監督など強い権限をもつ。1871年廃藩置県、1888年市制・町村制、1890年府県制・郡制
<地方公共団体(地方自治体)の機能と権限>
1 地方議会
●議員
被選挙権は25歳以上、地方議会の選挙権を有する者(3ヶ月以上在住)。任期4年(議会は解散がある)
●地方議会の権限
条例の制定・改廃、予算の議決・決算の承認、首長の不信任決議
※条例
地方公共団体によって、法律の範囲内で制定され、その自治体の中だけで適用される。2年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すことができる。
※不信任決議 4 地方議会と首長の関係 参照
2 首長
行政の責任者。知事(都道府県単位)と長(郡や市町村単位)があり、補助機関として、知事は副知事と出納長、市長は助役と収入役がいる。被選挙権は、知事は30歳以上、長は25歳以上、首長の選挙権のない者も可。任期は4年。
首長の権限としては、固有事務や国の委任事務の執行権。議会招集・解散権。
【発展】固有事務と国の委任事務
1 固有事務 地方公共団体本来の目的を達成するための事務。
教育・地方公共団体自身の選挙などの公共事務と、治安や都市計画などの行政事務。
2 国の委任事務 国や他の地方公共団体から委任される事務。
(1)団体委任事務
保健所の設置や生活保護など、経費は国家が負担(国庫支出金)
地方自治法第2条
(2)機関委任事務
戸籍・住民法・国会議員の選挙など、国や地方公共団体からその地方公共団体の長に委任される事務。主務大臣の指揮・監督を受け、団体自治上問題となっている。
地方自治法第148条
3 行政委員会
国の場合と同じく、独立した行政機関として教育委員会や地方労働委員会などがある。
4 地方議会と首長の関係
(3)専決処分
議会解散中は、緊急のことについては首長の判断で処分できる。ただし、議会招集後に議会の承認を得る必要があることなどから、参議院の緊急集会に似ている。
<住民の権利>
イニシアチブ
条例の制定・改廃の要求 |
1/50 |
首長 |
首長が議会にかけ、その結果を報告する。 |
監査の要求
|
1/50
|
監査委員
|
監査の結果を議会・首長などに報告し、かつ、報告する。 |
解散の要求
|
1/3
|
選挙管理委員会
|
住民の投票に付し、過半数の同意があれば、解散する。 |
(議員・首長の)
リコール |
1/3
|
選挙管理委員会
|
住民の投票に付し、過半数の同意があれば、職を失う。 |
(副知事や助役などの)
リコール
|
1/3
|
首長
|
議会にかけ、3分の2以上の出席、その4分の3以上の同意があれば、職を失う。 |
※地方自治特別法の住民投票(95 レファレンダム)
<住民運動>
1960年代の高度経済成長期に四大公害病が起こり、公害反対運動がさかんになった。
<地方自治の問題点:三割自治>
(1)地方財政 自主財源の不足、高い国庫依存度。
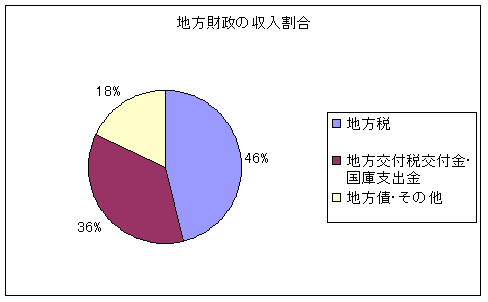 ・地方税=地域住民に課される税金
・地方税=地域住民に課される税金地方交付税交付金=地方税収入の格差是正のために国から出される補助金
・国庫支出金=国の仕事を肩代わりする代わりに、用途を指定された補助金
・地方債=経費調達のために出される債券(=借金)
(2)行政事務 固有事務は3~4割、委任事務が6~7割を占めている。
★三割自治
①国庫に依存しており、地方公共団体本来の財源である地方税が、収入の3~4割であること(ただし、最近は変化しつつある)、②委任事務が多く、地方公共団体本来の目的を達するための固有事務が3~4割であること、から言われる地方自治の状況のこと。国の委任事務と補助金・交付金で、地方自治は国にかなり干渉されていると言える。



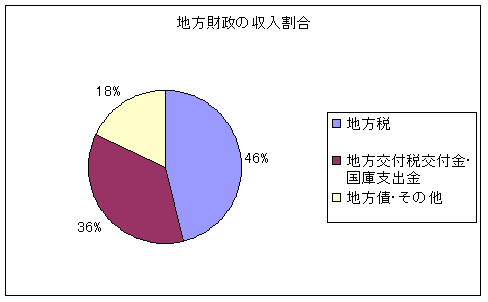 ・地方税=地域住民に課される税金
・地方税=地域住民に課される税金