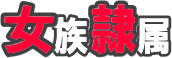
5−1 謎美女謎
「なんか、やっと帰ってきたって感じがするや」正樹は目の前にそびえたつ高級マンションを見上げながら、ボソリと呟いていた。
実際、これまでの田舎での単調だが落ちついた生活とことなり、この街にきてから驚きの全開だった。
たった二日で、いままでの正樹の人生の百倍ぐらいショッキングでそれでいて信じられないぐらい幸せな時間がめぐってきたように思えた。
田舎の親戚のおばさんと、近所の人たち以外女の人なんて見たこともなかったのが、突然目がくらむほどの美貌の冴子叔母さんと二人暮しがはじまったと思えば、なんとその冴子さん相手に初めてを行えたばかりか、電車の中では身震いするほどの金髪美女達あいてに逆痴漢され、さらには学校では学園中のあこがれの美人先生トリオを好き放題、そして部活さきのお茶の先生までも自分の物にしてしまうなんて…
「あうぅ」
思い出しただけで正樹はまた股間がズキンズキンと大きくなりおもわず前かがみになってしまう。
お母さんはこのことを知っていたのかな?
昔からの癖で正樹は腕につけた皮の腕輪をなでさする。
止め具が壊れ、クラスメイトにもらった輪ゴムで仮止めされたそれはいかにも頼りない。
だが、これが今のところ唯一正樹の不可思議な力を抑えてくれる重要な安全弁だった。
はずした途端、自分より年上の女性を魅了してしまう不思議な力。
正樹がまだ小さいときに死んでしまった母親はこのことを予見していたのか今の正樹にはまったくわからない。
それどころか、この力今後大きくなるのか?それともあっという間に消えてしまうのかさえ神ならぬ正樹には知りようが無かった。
「まぁ詳しいことは麻耶さんが調べてくれてるし、僕はこれ以上力が広がらないように気をつけないと」
正樹は自分に言い聞かせるようにぐっと皮の腕輪を上から押さえつける。
実際はずしただけで女の人を好きにできる力なんて夢のようなことだけど、それ以上に正樹は時々箍がはずれたようになる自分の精力に恐れを抱きだしていた。
ついさっきだって自分の欲望にまけて静江さんを相手にとんでもないことをしてしまったのだ。
まるで、自分の中から溢れ出した欲求にまかせるように。
頭の中に隷属の誓いを涙ながらに訴える静江さんの喘ぎ声がうかんでくる。
「本当にとんでもないことしちゃったよ、人の奥さんなのに」
正樹はぶるっと身を震わせると、深く深呼吸をする。
取り合えず静江さんは気にしなくてもいいっていってはくれたが、あの時の媚びた様な流し目は確実に自分の術中におちていることは間違いなかった。
自重した正樹は帰りの電車の中ではずーーと下をむき、女の人を見ないようにしながら、腕輪をぐっと掴んで帰ってきたのだ。
もしまた、とんでもない美人にあってしまったら腕輪を外してしまう誘惑に勝てるとはおもえなかったから……
もっとも正樹は知らないが、正樹が虜にしたような美女達がそうめったにいるはずがなく
そんな抜群の美女達ばかりを相手にして目の肥えた正樹が電車の中で目を開いても、心を疼かせるようなことはそうそうなく問題がなかったのだ。
「はぁ、本当にたいへんだった」
「あら、何かあったの?」
その時、正樹の背後から落ちついたしっとりとする声がかけられる。
「え?」
慌てて振り返るとそこには、和服をきた女性が優美に微笑んでいた。
「あ!新浜さん」
それは今朝エレベーターの中で知り合いになったこのマンションのオーナーでもある不思議な魅力をはなつ美女、新浜由乃だった。
今朝会った時とはことなる落ち着いた雰囲気の和服姿が、まるで一輪の華のように正樹の目に飛び込んでくる。
目の肥えた正樹を疼かせる美女が最後にまっていたのだ。
「どうなさったの?正樹さん」
「いっいえ、なんでもないんです……あっエレベーターきたから」
目蓋の裏に残像を残すほど優美な姿に正樹はドキマギしながら、ちょうど都合よくきたエレベーターに乗り込む。
すると、由乃もそっと和服の前を気にしながら同じエレベーターに乗り込んできていた。
「私もちょうど自分の部屋に戻ろうとしていたのよ」
にっこりと笑うその穏やかな笑顔とともに、ふんわりと心地よさげな香のかおりが漂ってくる。
「あっ、はい、じゃ屋上でいいですか?」
「ええ、お願いするわ」
正樹は緊張で震える指先でタッチパネルを触ると、自分の降りる階と屋上を選択する。
ポーーン
軽快な音を立て、エレベーターの扉が閉まると、そこはもう密室になっていた。
普通のつくりとは異なる、億ションらしい豪華なエレベーターはゆったりしたスペースに、豪華だが派手ではない品のいい内装がほどこされている。
たった二人の乗客には十分な広さと余裕があるはずなのだが。
「学校の初日はどうでして?」
そういいながら、にこやかに微笑む和服美人のマンションオーナーは正樹のすぐ側、体が密着しそうな程の位置にたっていた。
「え?がっ学校ですか?とっても大きくて驚きました、僕の田舎とは全然違うから」
「あら、そうなの?」
そっと口に手の甲をあてて笑う由乃の吐息が正樹の首筋に吹きかかる。
うっやばい。
正樹はわからないようにそっと制服の上着の裾をひっぱりおろし膨らんだ股間を隠そうと必死だった。
ううぅこんな美人のお姉さんと二人っきりだなんて、あぁまた大きくなってきちゃうよ。
「はっはい、僕の田舎の中学は人がすくなくて廃校になっちゃたんです、だから」
「まぁ大変だったのね」
「でっでも、こっちに来れてよかったって思います」
「まぁなんで?」
落ちついた大人の女性の声が先程よりさらに正樹の耳に接近してきこえてくる。
正樹はエレベーターのタッチパネルの方をにらみつけるような姿勢で硬直していた。
おそらく今、横をむけば目と鼻の先まで接近してくれた由乃さんの整った美貌をみられるだろう。
でも、そうしたら……
正樹には欲望に負けて腕輪を外す自分が簡単に想像できた。
「えと、学校の設備もすごくいいですし、とってもいい先生や友達もできたし、それに、そのいろいろです」
正樹は混乱した頭で真っ赤になりながらなんとか口を開く。
「ふふふ、いろいろね……その「いろいろ」の中には私に会えたことも含まれてると嬉しいわね」
「もっ勿論です!」
思わず力んで振り返った正樹の目の前には、まるで百合の花のように淑やかな美女の顔があった。
「あ……」
その涼やかな顔立ちに魅入ってしまい、正樹は声を失う。
そんな少年をそっと見つめる和服の美女は、ほんのり紅をさした唇を微笑の形にかえ見つめ返す。
正樹はぼんやりとその吸い込まれるような、しっとりと濡れた瞳をみつめていた。
「にっ新浜さん」
今まで制服の裾を掴んでいた自分の腕が無意識のうちに片手につけた腕輪の方に伸び、ゴムの仮止めに指先を這わせていた。
「ふふふ、嬉しいわ、お世辞でも」
その甘美な沈黙を取り払うように由乃さんが鈴の転がるような声をだす。
その声で正樹ははっとなると、目をしばたかせる。
あうぅ、まただ。
どうしても綺麗な人をみてしまうと、ついつい腕輪に手がのびちゃう。
僕って最悪だ。
正樹は自己嫌悪に陥りながら、ぎゅっと自分の手をにぎりしめ目の前の極上のご馳走を自分のものにしたい欲求にたえる。
「あら、どうしたの?顔色が悪いわよ」
「え、大丈夫です」
「そうかしら?汗もでてるわよ」
そう言いながら、由乃さんは着物の袖からそっと白いハンカチをとりだすと正樹の額に浮かんだ汗を拭い取る。
その動作にはなんのためらいもなかった。
「あっ」
「ほら、じっとしてて」
由乃さんが動くたびに甘い柑橘系の香りが正樹の鼻腔をくすぐり、着物の襟元から覗く白い肌がすぐ側でチラリと目に飛び込んでくる。
「そうだわ、気分が悪いなら私の部屋でやすんでおいきなさい」
とどめとばかり耳元にかかるその声に正樹のいつもながら細い理性がかるく切れる。
「ぼっ僕!」
「なに?正樹君」
にっこりとまるで菩薩のように微笑みかける妙齢の美女。
もうこんな美人なお姉さんとなら、どうなってもいいや!
皮の腕輪に正樹の指がかかった。
その瞬間
ポーーン
軽快な音をたててエレベーターの扉が開く。
正樹の部屋の階に着いたのだ。
その音がどこか遠くに飛び立っていた少年の理性をなんとか引き戻す。
「あ!つっ着いたみたいですから、あの、それじゃ僕これで」
あわあわと慌てながら正樹はカバンを持ち上げると、ペコリと一礼してエレベーターから転がり出る。
「本当に大丈夫?」
「あっはい、大丈夫です」
「そう、残念だわ」
由乃さんはそっと袖で口元を覆いながらクスリと意味ありげに笑いかける。
「え?」
おどろく正樹の目の前で
ポーーーン
と、また軽い音をたててエレベーターの扉が閉まりだす。
「それじゃあね」
「あ、はっはい…」
呆然とする正樹の顔がエレベーターのドアで隠れていく。
やがて最上階にむけて動き出したエレベーター個室の中で、和服の美女は一人クスクスと楽しげに笑いながら、少年の汗のついた白いハンカチをそっと胸元にしまいこんでいた。
「ふふふ、また明日ね、坊や」
誤字脱字指摘
1/14 ミラクル様 2/1 TKX様 5/4 あき様
ありがとうございました。
1/14 ミラクル様 2/1 TKX様 5/4 あき様
ありがとうございました。