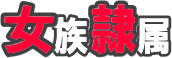
5−6 終日楽園
「ふぅう〜」正樹はボスッと寝巻き姿で、大きなベッドに倒れ込む。
冴子さんに用意してもらった自分の部屋だ。
田舎にいた頃は畳に蒲団をひいて寝ていたのでなんだか落ち着かない気分だった。
パリッとベッドメイクされたベッドは正樹が横に寝転んでも十分に余裕があり、ゴロゴロ転がりたくなる適度な柔らかさを背中に伝えてくる。
少年はしばらくそのベッドの広さを堪能すると、ぼふっと枕に顔をうずめ、お風呂あがりのほこほこと温かい身体を冷やすようにバタバタと脚を動かしていた。
本当に今日一日いろいろあったもんなぁ
正確には昨日の夜からだけど……
今まで一番幸せで謎めいた日だった。
美貌の叔母さん相手の脱童貞に、その後の夢のような一晩。
さらには電車の中での目も眩むほどの外人女性からの逆痴漢。
そして学校では、巨大な規模のその設備に驚かされ、そこの美人3女教師全員との腰のぬけるような交尾の連続。
最後には茶道同好会の講師の人妻を場所もかまわず犯してしまった。
とても、昨日まで女の人を知らなかった自分とは思えなかった。
そしてなにより、その原動力となった自分の知られざる能力。
母の形見の「腕輪」のお守りをはずすとどんどん年上の美女を魅了してしまうこの力。
そして今では、自分の性欲と体力が女性と交われば交わるほどにお互いどんどん強くなっていくのをはっきり感じていた。
一番自分と抱き合っている冴子さんとの時なんて、もう凄すぎたもんなぁ……
正樹は「はうっ」と満ち足りたため息をつきながら、冴子さんのことを思い出す。
冴子さん、自分の叔母さんであり、この新しい生活の保護者。
恐ろしいほど綺麗なプロポーションと知的な美貌。
スーツ姿がとっても似合うバリバリのキャリアウーマン。
そしてもう、正樹にとってなくてはならない大事な人の一人。
結局あのあとリビングで、大好きな美人の叔母さんに「もういいの?」などと言われれば、正樹はおとなしくテレビを見ているわけがなく……
また挑みかかるようにその甘い肉体に飛び掛り、床に四つん這いにさせるとその熟れたお尻を何度も何度も貫き体中に精液を塗りつけていたのだ。
その後、お互いの汗と体液でドロドロになるまで交わった二人はお風呂に直行したが、結局そこでも冴子さんの魅惑的なプロポーションに理性をうしない襲い掛かってしまった。
大きなバスタブに両手をつかせて何度も腰を使い、お互いボディソープでぬるぬるになった身体を抱き締めあい舌をからませあった。
ことが済んだ後も、ジャグジーバスの中で冴子さんを後ろから抱き締め、ち○ぽを気持ちのいい蜜壺に入れたまま、大きな胸をもんだり口づけをしたりと後戯にふけりながらいろいろとお話していちゃいちゃしているうちに正樹は湯あたりを起こしていたのだ。
顔を真赤にしてのぼせる正樹に冷水を口移しで与え、裸のままタオルであおいでくれる冴子さんの媚態にさらに正樹がクラクラしたのは言うまでもない。
どうも正樹の無限に近い精力をあたえる効果も湯あたりには効かないようだった。
「ふぃぃ〜〜」
ゴロンッとベッドの上で転がると天井をみつめる。
のぼせて熱くなった頬を自分の手でパタパタと仰ぐ。
その時、ふと今日一日を振り返っている正樹の頭の隅に閃くものがあった。
「あっそうだ!そういえば」
正樹はベッドの上をころがり、ハンガーの側にいくと制服のポケットから名刺をとりだした。
そこには正樹にはよく意味のわからない役職らしい物が複数の言語で印刷されており、そしてその裏面には正樹にわかるようにだろう、走り書きだが丁寧な書体でカタカナの名前と携帯の番号がかいてあった。
「マイカさんとレンさんか…また会えるのかな?」
正樹より頭一つ背が高い外国のグラビア雑誌の表紙から抜け出てきたようなスーツ姿の白人美女二人のグラマラスすぎる肢体と正樹を見つめていた熱い視線が思い出される。
電話をかければきっと喜んででてくれると思うけど……
正樹は冴子さんに渡された携帯電話からかけるのもなんだか気が引けていた。
冴子さんならきっと電話しなさいって言うだろうけど…そうだ、あした学校の公衆電話からかけてみよう。
お気楽にそう思い、正樹は秘密の電話番号のかかれた名刺を丁寧に制服の内ポケットに戻していた。
そして、その頃、その電話番号の繋がる先の携帯の前で…
二人のトップモデルも顔負けの美女がまんじりともせず電話をまっていた。
「こないわね、電話」
もう数時間になるだろうか、少年からの電話を待つのは。
豪奢な金髪の白人女性が大きな背もたれのチェアーをぎしりといわせる。
赤を基調としたオーダーメイドのスーツのスカートから光沢のあるストッキングに包まれた驚くほどの美脚がすっと組替えられる。
彼女の1分は百万ドルにも値すると言われるこの豪奢な美女を数時間も待ちぼうけをくらわせているものがいると知れば、驚愕と羨望で涎を垂れ流すことはまちがいないだろう。
そして今、世の男性とビジネスマンの憧れと嫉妬をうけるのは、デスクの上の鳴らない電話だった。
この電話に彼女達の大事な少年以外から電話がかかることはない。
今朝一番で、この電話番号を愛しい少年直通のものに変えたのだ。
彼のもっている携帯も、マンションの電話番号もすでに調べがついている。
「…調査部の調べでは、すでに帰宅して4時間13分が経過しています」
広くシンプルなつくりのデスクの側に控える真紅の髪の美女がすっと腕につけた時計をみつめ事務的に報告する。
その口調の裏には、彼女の上司にしかわからない落胆が交じっていた。
「そうね」
その上司、美しき金髪の支配者と呼ばれるマイカ・ルーベルトは形のいい眉を少しよせると、そのしなやかな指先で部下の提出した書類を摘み上げる。
それはすでに何十回と読み返したものだった。
最高ランクの重要度をしめす刻印の押された紙面に貼り付けられた一枚の写真。
そこにはちょうどクラスメイトだろう少年達と話しながら廊下をあるく高梨正樹の姿が写された。
「……正樹」
一瞬だけ、おもわず寂しげな心の声がもれてしまう。
そこには、情け容赦ないビジネス界の薔薇、稀代の女王、誇り高きマイカ・ルーベルトではなく一人の恋する女性の姿があった。
「…ボス」
彼女に長い間仕えてきたレンもこれほどの落胆ぶりをかいまみたことはない…
だが、どんな逆境でものりこえてきた彼女の気高き上司がこれほど落胆するのも無理がないと思えた…
彼女にも痛いほどその思いがわかるのだ。
同じ少年に身も心も隷属しているのだから…
せめて一声、一声、声を聞かせてくれたなら安心できるのに…
レンは心の奥で悲嘆しながら、今でも目蓋の裏にのこるプラットフォームではにかみながらこちらを見つめてくれた大事な大事なご主人様の最後の笑顔を思い出す。
それだけで、彼女の胸の奥はぎゅっと握り締められるようにせつなくなっていく。
…あぁ…正樹様……
「ところでレン、頼んでいた物は?」
珍しく物思いにふける赤毛の秘書にマイカが声をかける。
その顔はいつもの自信と気品にあふれた女王然としたものに表面上は戻っていた。
「…イエス、ボス…すでに川奈冴子、沢木薫子、春風弥生、鈴掛麻耶、一条静江の裏は取れています、こちらの資料を」
そう言って先ほどより分厚い書類の束を数冊マイカのデスクに滑らす。
白い指先がぺらぺらとそれらをめくり、青くするどい瞳が吟味していく。
「5人とも正樹様に接触をもったのは今日がはじめてだと思われます、まずは正樹様の叔母にあたる川奈冴子ですが……」
レンは彼女の上司が資料をめくるのに合わせて暗記していた内容を的確に述べていく。
それは、正樹が今日関係をもった女性達すべての公式からプライベートなことまで全ての詳細な記録だった。
マイカは書類を手早く捲りながら、レンの要求に的確に答える小気味いい説明に耳を傾ける。
「…以上のことから、彼女達に正樹様を害する怖れはないと思われます」
「そう、ごくろうさまレン」
マイカは軽くソバージュのかかった豪奢な金髪を後ろになびかせると、もう一度深々と椅子に背中をあずける。
「引き続き彼女達の監視と…あと自然にアプローチを取れる準備をしておきなさい」
「……すでに」
レンの返事にマイカは軽く微笑み返す。
マイカは彼女の息のかかった調査部からの報告を読み事態を把握すると、すぐに彼女なりの正樹へのスタンスを確立しだしていた。
マイカにしかできないこと、それは正樹の社会的、経済的な保護だと彼女は考えていた。
正樹が自分達の他に女性と親しくなっているのはあまり好きではない、いやマイカの本心を言えばこれ以上増えてはほしくない……が、それは正樹個人が決めること。
それに体のつながりがあるとはいえ、たった数十分の電車の中で、しかも自分達から無理矢理関係を強制したのだ。
もしかしたら正樹に嫌われているのかも……
いや、正樹があたしを嫌うわけがない!あたしの正樹が…
しかし、彼女の人生で初めてでおそらく最後の、男性への熱愛と奉仕の心はそう思おうとしても、雨雲のように湧きあがってくる不安に晒されてしまう。
兎にも角にも、マイカは少しでも正樹の役に立ちたかった。
幸いなことに自分に普通の人では得られない莫大な権力と資金、そしてそれを効果的に運用する知識と優秀な部下がいる。
決心したマイカの行動は恐ろしいほど素早かった。
正樹の通う「学園」、使うだろう交通手段、それに住まい、周りの生活環境、交友関係、そしてなにより少年の魅力に落ちた女性達の身の回り、その全てにマイカの息のかかった資金と人材をわずか半日で送り込み情報を集め出す。
そう、マイカとレンが正樹の能力を知りそれに対する対処法として選んだのが、正樹が気がつかず邪魔にならない程度で彼を守るという方法だった。
それは何より、大事な正樹を守るだけでなく、彼との蜜月を期待する二人にとっても重要なことだった。
「ねぇレン、ところで明日の朝の準備は」
「問題ありません、ボス」
赤毛の部下はいつもより多少興奮した声でそう答えると、そっと列車のダイヤ表を提示する。
「正樹様の乗られる列車へ間に合うようすべての手はずは整えてあります……あとご要望のありました例の車両も」
白い頬が明日の朝のことを考えるとほんのり紅色に染まっていく。
「ふふふ、そう、楽しみね明日が」
「……はい」
まってなさいよ正樹!このあたしに電話をかけてこなかったこと後悔するぐらいう〜〜んと可愛がってあげるんだから。
鳴らない電話をぐっと握り締めると、マイカ・ルーベルトはまるで獲物を狙う雌豹のようにその青い瞳を細めていた。
「うひゃ」
正樹は名刺を制服にしまった瞬間、突然、悪寒のようなゾクッとした感触に襲われすっとんきょうな声をだす。
のぼせたからといってゴロゴロしていたから、今度は湯冷めしたのだろうか…
「そろそろ寝た方がいいかも」
正樹はそう一人で呟きながら明日の用意をしようと、机の上に広げられた生物の宿題をしまいクラスメイトの寺田にアドバイスをもらった時間割をみつめる。
ちなみに山さんに借りたジャージはすでに全自動の洗濯機の中だ。
「明日は地理と、英語、それに基礎数学か楽しみだな、あっ体育もある」
今日の授業はほとんど聞けなかったし……
「きっと明日も先生たち離してくれないんだろうなぁ」
思わずベッドの上で裸の身体を寄せ合い誘うように手を差し伸べる三人の女教師の姿がもわもわと浮かんでくる。
「正樹様ぁぁん、くう〜ん」「きな正樹、させてやるよ」「少年、好きにしていいぞ」
はうっと幸せいっぱいのため息をつきながら、正樹は前かがみで時間割を机の上にもどすのだった。
そしてその頃!
正樹の心の中に描かれた3人の美貌の女教師達は、一軒の店でアルコールを楽しんでいた。
少し暗めの店内に薄暗い照明、天然木の木目と素材をいかした丸いテーブルに、わざと荒いつくりの椅子。
ウインナーやサラミ、チーズの盛り合わせの皿が乗ったテーブルの中央では丸いキャンドルがゆらゆら揺れている。
その光にてらされてほんのり頬を染めているのは正樹の担任教師、沢木薫子だった。
「えへへへ、今日はお酒がとってもおいしいわぁ」
店長の今日のお勧め赤ワインをグラスでゆらして香りを楽しむと、くいっと傾ける。
学園でも一、二を争う美貌がアルコールで染まり色っぽい。
ライトグレーのブラウスに黒の少し短めのスリットの入ったスカート姿だった。
しかも火照った体が熱いのだろう白いブラウスの上のボタンを開けてしまっているので、滑やかな首筋と驚くほどの爆乳の谷間が剥き出しになっている。
その大きすぎるバストがライトグレーのブラウスを押し出し、もたれかかったテーブルの角でむにゅっと柔らかいお餅のように形を変えていた。
「先輩飲み過ぎですよ〜、あっお兄さん!ビールおかわり」
そういって通り過ぎた店員に声をかけるは体育教師の春風弥生だった。
ベリーショートの茶色髪に、引き締った凛々しいワイルドな美人。
その格好はいつものジャージ姿ではなくVカットのニットにチェーンベルトのついた白のコットンパンツ姿だった。
ニットシャツの胸元は、鍛えられた胸筋に支えられ思わず掴みたくなるほどつんっと形よく突き出し、無駄な肉のないビルドアップされた腰と太腿にスラリとモデルのようなラインをつくっている。
そしてその整った顔も、首筋も、すでに程よく色づいていた。
良く見れば彼女の前にはすでに空になった特大ジョッキが5つ並んでいた。
「なによ、弥生あんただって飲みすぎよ〜、人のこと言えないんだから〜カンパーイ」
「ビールは水なんですよ先輩、カンパーイ」
酔っ払い同士の良くわからない会話のあと二人ともゴクゴクとグラスの残りを飲み干していく。
「ぷはぁ〜おいしいぃ」
「ぁあ、もうなくなっちゃいましたね、薫子先輩次何飲みます?強い奴いきますか?」
「よし!なんでもこ〜い」
店の雰囲気に合わないほどはしゃぎまわる二人。
その対面に座った最後の人物がはぁっと大きくため息をはく。
「おまえ達、いいかげんにしないと明日がつらいぞ」
ハスキーな声がそう呟くと、コクンと透明な液体の入った小さなグラスを艶やかな唇に運ぶ。
グラディエーションのついた黒髪、神秘的な深い翡翠色の瞳とそれを覆う縁無しの眼鏡、すらりと伸びた鼻筋、そして抜けるように白い肌の落ち着いた感じの美女、「第5保健室の魔女」鈴掛麻耶だった。
その美貌は蝋燭の光をうけて陰影をつくりよりいっそうミステリアスな雰囲気を引き立てている。
オーソドックスな襟が大き目の白シャツに足元にスリットの入ったパンツスーツ姿で、肩肘をテーブルにつくとパラパラと手元においた文庫本らしき物を眺め、時々紫煙を燻らせている。
薄暗い照明と蝋燭だけの店内とはいえ、これだけのレベルの美女が男を同席させる様子も無く、三人だけで飲んでいるのだ
周りの男達はちらちらと様子をうかがい、隙あらば声をかけようとねらっていた。
事実この店にくる途中から今までで、すでに両手で数え切れないぐらいの男達が声をかけていたが勿論全て玉砕していた。
彼女達にとって今もそしてこれからも、男性と呼べる相手は一人だけになっているのだから。
そんな熱い視線なんてまったく興味のない薫子が、麻耶にちょっかいをかけだす。
「なによぉ、麻耶ぁ付き合い悪いわよぉ」
どんっとテーブルを乗り越えそうな勢いでその顔を寄せてくる。
それにあわせて巨乳がぶるっんと震え、紡錘形に垂れた胸先がいまにも料理の皿につきそうなほどだった。
「ん?飲み過ぎは身体に悪いといってるんだ…まぁその気持ちわからんでもないがな」
弥生はともかくお酒に弱い薫子がこれほど飲むことはそうそうなかった。
そして今日はその理由がわかっているだけに止められそうにない。
少年に…彼女達のご主人様に出会った記念すべき日なのだから…
「ところで先輩、その本なんですか?」
こちらも普段の酒量を遥かに越えるハイペースでビールをゴクゴク飲む春風が、麻耶が片手間にぺらぺら捲る本を指差す。
「あぁこれか……少年…高梨に関したちょっとした調べものでな」
なんでもないと言った感じで「三奉金丹節要」古い書体で書かれた本をパタンと閉じる。
だが、いまのアルコールの回りすぎた目の前の二人の美女に「高梨」の言葉は火に油を注ぐような物だった。
「あぁぁ…正樹ぃさまぁ……薫子は、薫子はぁ、く〜〜ん」
くねっと薫子は何かを思い出したのだろう頬をピンク色にそめ、身悶える。
長い黒髪がさらっとゆれ、瞳がうるうると潤み出している。
「正樹ィ、あぁ明日の授業が楽しみだな、へへへへ」
春風が唇のはしを吊り上げるような卑猥な笑い方で淫らな妄想をはじめる。
「むむっ!ちょっと弥生、ずっこいわよ、体育の時間まるまるなんて」
「せっ先輩だってHR全部正樹と使う気じゃないですか、私はちゃんと自分の授業を削ってます」
「ふふん、いいもんねぇ明日は地理があるんだからぁ、ふふふふ、正樹様ぁ、朝のHRから2時間連続で…」
「あぁぁ先輩こそずるい!」
中学生の男の子の取り合いを美女二人がはじめる横で、麻耶は小さくクスリと笑いながらまた小さなグラスの中の透明な液体をコクリと嚥下する。
「くくく、少年明日が大変そうだぞ」
勿論昼休みの時間を自分と少年が甘く過ごすことは決まっている。
これだけは例え誰だろうと譲れない。
自分の初めてを奪った愛しい少年のことを思うと、下半身が熱くなり…
麻耶はそっと首筋につけられたキスマークを隠すように服の襟を立てると、カウンターの奥にいる店の主人に声をかける。
「おいマスター、テキーラストレートでおかわりだ」
麻耶の目の前にはすでに空になったショットグラスが無数に転がっていた。
「明日の準備はこれでよしと」
正樹は参考書に片付けた宿題、それに筆記用具をカバンに詰め込むとパタンと蓋をする。
それにしても、なんだかさっきまた寒気がしたような気がする。
しかも3回連続で…
これはちゃんと寝ないと風邪を引いちゃうかも
正樹はまったく疲れていなかったが無理矢理寝た方がいいかもと思い、もう一度ベッドに向かう。
明日は朝の一時間目から必修科目の地理があるから遅刻しないようにしないといけない。
それに放課後「茶道同好会」がある日のはずだ。
犬神さんが週に3、4回といっていたような気がする。
「そうすると、やっぱり明日の放課後は…」
狭い茶室で着物を身に着け落ち着いた雰囲気で正樹に深々と三つ指をついてお辞儀をする人妻の姿が脳裏に浮かんできていた。
またまたその頃!
正樹の想像した人物は自宅の檜造りの和風な風呂場で湯船につかっていた。
流れるような黒髪を頭の上で束ね白いうなじを晒し、その丸く女性らしい撫で肩にお湯をぴちゃっとかけ手ぬぐいでぬぐう。
開いた小窓から入る月明かりに照らされたその横顔は引き込まれるほど色っぽい大人の色香をはなっていた。
ぴちゃん ぴちゃん
「はぅ」
湯船から立ち昇る湯気の中、淑やかな吐息をはくその人は、茶道同好会の講師、一条静江師範だった。
清涼な檜の香りが漂う湯殿の中、艶やかで張りのある人妻の肌がぼんやりと湯煙の中に浮び上がる。
そのゆらゆらと揺れる浴槽の湯面には、豊満な二つの大きな膨らみ、すっと形のいいお臍、そして白磁の陶器の首のようにくびれた腰に、むっちりと肉付きのいいお尻へと大人の女らしい絶妙のメリハリをもって続いている体が浮かび上がっている。
だが浴槽の水面は周期的に波紋をたてて乱れると、一条師範の熟れた肢体を隠してしまう。
ぴちゃん ぴちゃん
「はん」
その長く肉付きいい優美な脚の根本、濃い茂みが覆う秘所に……人妻の指がそっと添えられていた。
そして肉厚の妖艶な唇のあいだからもれる桃色の湯気のような声。
「はんんっ…あぁ…」
彼女の声にあわせて、湯船のお湯が揺れ波紋を引き起こしていた。
「んんっ」
豊満な乳房がふるんっと動き、それが水面に小さな波をおこしているのだ。
近所でも貞淑で淑やかな良妻で通っている静江は、一人湯船の中でその身を慰めていたのだ。
「…あぁ…んっ」
なるべく声を殺そうとするが殺しきれない色っぽい声が木作りの浴室に木霊する。
やめなければ、と思えば思うほどその指ははげしく割れ目をなぞり、お湯の中にぬめった愛液を広げてしまう。
「はぅ…ぁぁ…うぅうち……あぁ、うち…」
んんっとその墨で引かれたような形のいい眉をよせて、下半身からじんわりと広がる温かさに身をゆだねていく。
その切れ長の瞳はまるで何かを思い出すかのように閉じられていた。
「はん…んっ」
ぴちゃ ぴちゃん
目をとじ指先だけを微かに動かし熟れたその身を恥らいながら慰め続ける。
その一条師範の目蓋裏に浮かぶのは、八年間つれそった彼女の夫ではなく……
「まっ正樹様ぁ……あぁうちの旦那様ぁ」
今日はじめてあったばかりの中学生。
高梨正樹だった。
あの茶室の中で彼に抱きつかれ犯してもらったこの体が疼くのだ。
『静江、もっともっと犯してあげるからね』
そういって飽きることなく自分に伸し掛かってきた彼の吐息とその温もり。
いまでも鮮明に思い出す。
舌を絡ませるあの動き、貪るように乳房に顔をうずめ、そして最後には何度も、何度も、静江を後ろから抱き締め、突き上げてくれたのだ。
「はうぅ」
ぴくんと動いた指先が陰部の上で息づく肉のお豆に触れる。
『たっぷり出すよ…静江の中に』
そして子宮の中に直接注ぎ込まれたあの熱く大量の精液。
『妾の静江に大事な精液をくださいませ』
拒まなければいけないはずの人妻は、そういって彼の全てを受け入れ、肉の妾に落ちたのだ。
そうあの時、狭い茶室の中でこの32才の熟れた女の肉体とそして心まで、全てまだ年端もいかない中学生のものになったのだ。
彼の…旦那様のあのお力で堕としていただいたのだ。
「あぁ…うち…うち…ほんまに幸せですぅ…あぁ」
明日になればきっとこの身体を求めてまた少年が貪るように犯してくれる。
明日になれば……またあの茶室で…
そう思うと、少年に貪られキスマークがたくさんついた豊満な胸をたぷんとゆすると美人人妻は軽いエクスタシーの中に落ちていっていた。
ちゃぷん
「なんだろ、なんだか寝付けないや」
部屋を暗くして正樹はベッドの中に潜り込んだ姿勢のまま目をらんらんと見開いていた。
興奮して眠れないと言うのもあるが、それ以上に普通に眠くないのだ。
まるでぐっすり睡眠を取った後のように睡魔がぜんぜんやってこない。
ときどき妙に背中というか股間がゾクゾクすることはあるんだけど……
どうしたんだろ?やっぱり力のせいなのかな?
よく考えれば昨日だって3,4時間しか寝てないことになる。
いままでの田舎ならもう今ごろの時間にはぐっすり睡眠をとり、朝日と共に元気に目を覚ますのが日課だったのに…
少し不安になり正樹は無意識のうちに自分の腕に手をやって「腕輪」をさわり安心しようとする。
その時、
「あれ?」
手触りが何かおかしい!
すべすべとしていた皮の腕輪の一部が妙にざらついているのだ。
あわてて、枕元のナイトスタンドのスイッチをいれると腕輪を外して照明に晒す。
「なっなんだこれ?」
そこには、腕輪の一部がまるでライターの炎で焦がしたように、真っ黒に煤け皮がけばだっていた。
腕輪を火に近づけた覚えなんてまるでない。
しかもこげた部分は絵文字のような部分が1文字分だけ綺麗になくなっているのだ。
偶然ではなく何か意図的に焦がされたような感じだった。
どうゆうことだろ?
しばらく考えてみたがさっぱりわからない。
指先でその焦げたような後をこすってみるが、表面でなく中から変色しているようだった。
「まいったなぁ」
まさか腕輪の効果がなくなっちゃうんじゃ
そう思うと正樹は先ほど以上の不安に襲われる。
人の人生を左右してしまうなんて気の弱い正樹にはぞっとする行為だった。
今まで力が発動したのは冴子さんや先生達といった恵まれたとても素敵な人たちが正樹の側にいたときだったが、それ以外だって十分考えられるのだ。
「とりあえず明日、麻耶さんに相談しないと…」
正樹がそう結論づけたその時、
がちゃり
「ちょっといいかしら?」
ドアが開いて、冴子さんが入ってくる。
「あっいいですよ、いま寝るとこ……さっさっ冴子さん!」
ナイトスタンドの小さな明かりで照らされたそこには、確かに冴子さんが立っていた。
そこには魅惑的な黒のランジェリーをまとった夜の女神がたっていた。
白い艶やかな肌に栄える黒いレースのついたきわどいブラがその突き出した形のいい胸を形ばかりに覆い、足先から太腿までのすらりと長いラインを細かい網目のタイツがガードしている。
そして太腿のタイツを吊り下げる凝った衣裳のガーターベルトがほそく引き締った腰に回されていた。
「ふふふ、どう?似合ってる?」
さっそうとモデルのように脚を交互につきだして歩きながら冴子さんはベッドのそばで、背筋をそらしその美体を余すことなく見せつける。
それは白磁のようなしっとりと甘い冴子さんの大人の肌にみごとに調和した黒の総レースのランジェリー姿だった。
正樹はただ股間を抑えながらコクコクと頷く。
きっ綺麗過ぎるよ冴子さん。
まるでファッションモデル雑誌の表紙から抜け出てきたような抜群のスタイル。
そんな美貌のお姉さんが正樹のベッドの横でスケスケの黒い下着を身に付けて誇らしげに腰に手をやってたっている。
その魅惑的な姿にいたいけな少年は腕輪のことも忘れてしまう。
「っす…すごい…きっ綺麗です」
ゴクリと生唾を飲み込んで正樹はそのプロポーションと美貌を見つめていた。
その時、正樹は形のいいお臍の下に違和感を覚える。
「あっ…」
そうだ!大事なところを包むショーツがないのだ。
下半身を覆うのは、すらりと伸びた脚を覆うタイツにその上を走るガータベルトの紐だけ。
魅惑的な臀部は筆の穂先のような柔らかな茂みが微かに覆っているだけだったのだ。
「ふふふふ、気がついた?」
冴子さんは正樹の目線の先が一箇所でとまったことに満足げに微笑む。
腰に手をやったままの姿勢で
「あっあの…その……」
「だってしかたないでしょ、ご主人様が約束させたのよ♪家の中ではショーツを履いちゃだめって」
そっそんな約束したのだろうか?……なんだか僕が覚えてないのをいいことに冴子さんがどんどん淫らな規則を作っているような気がしないでもない…
「それから、もう一つ」
腰に手をやったまま、冴子さんは前かがみになってベッドの上に座り込む正樹に顔を寄せる。
黒いレースに縁取られたブラに包まれた大きなバストがゆさっと揺れ、紡錘形になった乳房の谷間が目に飛び込んでくる。
そして顔を傾け正樹にキスをするランジェリー姿の年上のお姉さん。
ちゅっ
そっと重なり合う唇の間から慣れ親しんだ、しかしいつも少年を惑わす真赤な舌が侵入すると歯の間をノックしこじ開け潜り込んでくる。
「しゃしゃえこさん、んんん」
「はんっんっ…んっんっ、んんんっ……ちゅ、ちゅく、ちゅちゅ」
くちゅくちゅ ちゅるるる
ナイトライトに照らされた薄暗い部屋の中、美女は丁寧に丁寧に小さなご主人様の口の中を舐めまわし、舌をからませ唾液をすくい取るとコクリと飲み干す。
「んっんんっんくっ…んちゅ、んはぁあ……はん、ふふふふ、正樹くん、もう一つはね…」
冴子さんは口を与えるため前かがみになっていた姿勢をすっと戻す。
とろっと唾液の筋を真赤な唇から伝わせ黒い下着姿で腰に手をやり颯爽と立つその姿は絵画の中からでてきたように美しく、淫らでセクシーだった。
「冴子さん」
正樹は思わずその豊満につきだしたバストに手をのばそうとする。
「あら、だめよ、夜はそっちじゃないでしょご主人様」
その手をやんわり断った美女は、くすりと笑いながら正樹にくるりと背を向けると肩幅に脚を開き立つ。
「え?」
なんのことだかわからない正樹の目には、高級ランジェリーにつつまれた冴子さんの白くしなやかな背中と、細くくびれた腰、そしてショーツに包まれていないきゅっと盛り上がったヒップに黒いタイツに包まれた驚くほど長く伸びやかな美脚が飛び込んでくる。
冴子さんは首をひねって正樹を振り返る。
セミロングの髪がさらっとひるがえり、その美貌の半分を覆っていた。
「もう一つの約束はね」
そう言いながら髪の毛の間から正樹を見つめる切れ長の瞳。
その上半身を屈伸するようにゆっくりと倒し床に両手をついて、正樹にその白くすべすべとしたお尻をつんと突き出す。
そして両手を後ろにまわすと、自分でその白い肉のお饅頭のような尻タブをむにゅっと押し広げる。
「あぁう」
正樹は目の前に広がる美女の肉の秘密から目が離せなかった。
そして誘うように響く冴子さんの甘い声。
「夜は、お尻の調教でしょ?ご主人様」
正樹君の夜はまだまだ終りそうにないのだった。
『夜は、お尻の調教でしょご主人様』小さなモニターの中で、抜群のスタイルの美女がベッドに座る少年にお尻を捧げている。
やがて少年はベッドから飛び降り、目の前の美女の白いお尻にむしゃぶりついていく様子が映されていた。
「あら、ほんとうに元気な坊やなんだから、ふふふふ」
そういって笑う美女は薄いナイトガウンを羽織り紫色の個性的な下着で籐の背の高い椅子に腰掛け幾つか並んだモニターを見つめる。
そこには正樹が先ほどまで座っていたソファーやバスタブ、そしてキッチンが映し出されていた。
「こんなに可愛いくてとても元気だなんて、まだまだ力は未熟だけど、ふふふ、あの御方にとっても、そして私にも嬉しい誤算ね」
そう言いいながらそっとナイトガウンの中にその細い指先を滑らしていく。
「でもなんだか………あっあの坊やを見てたらなんだか私までへんな気分に…あっ……んっ…あっん」
ナイトガウンが乱れ椅子から伸びた脚がすっとのびる、ハラリとめくれたガウンから覗くその白い太腿には数字のような記号が刻印されている。
「あっ…あぁぁ…私も……いつかあの坊やに…あっあっあぁぁあああ」
正樹達の睦み会うマンションの屋上につくられた豪華なペントハウスの一室で妙齢の美女が謎をはらんだままその火照った身体をもてあますように指で慰め続けていた。
誤字脱字指摘
3/16 義29様 3/17 mutsuk0i様 北綾瀬様 4/6 あき様
ありがとうございました。
3/16 義29様 3/17 mutsuk0i様 北綾瀬様 4/6 あき様
ありがとうございました。