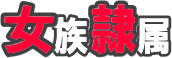
1日目(日曜日) 午前2 喫茶美猫
真紅のコルベットが、淀みない走りで駐車場にすべり込むと、そのスポーティな車体につりあった軽やかなスーツ姿の美女が運転席から降りてくる。黒のカットソーにスリットの深く入ったクールなタイトスカート、片手にはイタリア製の小さなポーチをもった彼女は急ぎ足で助手席のほうに回りこむ。
「はい、ついたわよ、正樹君」
そう言って助手席のドアを開けると、そこに座る彼女の甥にして最愛の主人をエスコートする。
「いっいいですよ、ドアぐらい自分で開けますって」
恐縮しながら小柄な少年が車から降りてくる。
「いいの、今日は私が正樹君を連れまわすんだから……そうね、じゃあ今度の休みは正樹君がホストになって何処かに連れてってくれる?」
そっと少年の腕を取りながら、冴子さんは可愛らしくウインクする。
「えっ僕が……う〜ん、僕まだここらのこと詳しくしらないし…」
「あら、そんなこと気にしなくていいのよ……なんだったら一日中ホテルの中でも私はOKよ、ご主人様」
くすっと笑いながら、最後のほうは正樹だけに聞こえるようにこっそり囁く。
「えっ……そっそれは」
思わずぼっと真っ赤になる正樹を見て、冴子さんは楽しそうに目を細めると、さらっと黒髪をなびかせて車にロックをかける。
「またそれは今度のお楽しみね」
今度のお休みに…冗談じゃなくて本当にしちゃおうかしら……
などとまた保護者らしからぬことを思い浮かべながら、冴子さんは正樹の腕をひっぱり駐車場から歩きだす。
「まずはご飯を食べてからね、ほらすぐそこよ」
そう言う彼女の目線の先は、すぐ通りの向こうマンションだろうビルの一階にある小さな喫茶店を指していた。
冴子さんと正樹が淫らな休憩を何度も繰り返すお買い物をしていたのは、彼女と正樹がはじめて出会ってから数日たったある日曜日のことだった。
実際、正樹が田舎から引っ越してきてから、この休日までに体験したことは驚きと、そして興奮の連続だった。
なにせ数日前にはじめて会ったばかりの美貌の年若い叔母さん相手に、童貞を捨てたことだけでも驚きなのだが、あまつさえご主人様と呼ばれてベタ惚れされているのは、この少年の驚くべき秘密の力に由来していた。
秘密の力、それは正樹にもいまだに詳細が分からない理由で、彼より年上の女性を魅了してしまうとんでもない物。
小さい頃、よく近所のお姉さんやおばさんにイジメられていたと本人は思っていたのだが、それさえも今となっては力の片鱗が引き付けていたのかもしれなかった。
兎に角、今正樹に分かっていることは、死別した正樹の母親が作ってくれた腕輪を嵌めていないと周りにいる年上の女性を自分の意志とは無関係にどんどんと魅了し隷属させてしまうということだった。
現に正樹は居候させてもらっている叔母の川奈冴子を皮切りに、電車の中で偶然出会った名うての企業家の外人美女二人組、学校の担任教師に体育教師、そして保健の先生と次々と篭絡し最後には人妻のお茶の師範にまで手をつけてしまったのだ。
しかも交われば交わるほどお互いに体力も精力も増していくおまけつきで、たった二日の間にこれだけのことをしてしまったのだ。
勿論、翌日から、正樹のことを「ご主人様」と慕う美女達に愛されまくったのはいうまでもない。
朝から美貌の叔母さんのフェラチオで目を覚まし、通学しようと駅に行けば外人美女二人がその有り余る財力にものを言わせ正樹のために特別列車と淫らな抱擁でお出迎えしてくれる始末。
学校でも先生達の熱烈な歓迎を受け、担任の美人爆乳教師とは寂れた準備室で、体育会系の女教師とはランニングコースの脇の茂みで、そしてお昼休みには魅惑的な保険医と肉欲の限りを尽くしていたのだ。
あげくに篭絡した人妻とも楽しみまくったりしてしまう毎日。
そんなこんなで正樹の転校してきてからの新生活は、素晴らしすぎる美女達に囲まれた夢のような日々になっていた。
「どうしたの正樹君」
「え?あっはい、何でもないです」
ここ数日の自分の恵まれすぎた環境を思い出し、ぼうっとしてしまった正樹は、冴子さんの怪訝な声と自分の肘にあたる柔らかい膨らみの感触に現実に連れ戻される。
「そう……あっここが私の行き付きのお店、クリソベリルよ」
「へぇ、いい感じの店ですね」
「OPEN」と書かれた木札の下げられたドアは、色ガラスのはめ込まれた繊細な作りになっている。
その横の手入れの行き届いたプランターの前には小さな黒板が置かれ今日のお勧めメニューがかかれ、彩りのいい花々やタイルで飾られていた。
そしてドアの上のひさしには、結構年代ものだろう真鍮製の猫を模った小さな看板があり、流れるような書体で店名が彫りこまれていた。
「喫茶クリソベリル」と。
「そうでしょ、このお店はね、私の大学の時のルームメイトが経営してるのよ……こんにちは」
冴子さんはそう言うと、正樹の腕を引いて店の中に入っていく。
チリンッ チリンチリン
ドアの上につけられたガラス製のベルが軽やかな音をたてて二人を迎え入れる。
店中はたいして大きくなく、テーブル席が4つ程、そして10人も座れば一杯になるカウンターだけの小さな個人経営の小奇麗な店だった。
店の主人の趣味だろうか、少しばかりかすれたレコード音源のBGMが静かに緩やかなテンポで流れており、そこかしこにレトロな小物がそれとなく配置されている。
そして、数人のお客さんがコーヒーを飲んでいるカウンターの向こうから女性の声が二人にかけられる。
「いらっしゃい……あら、冴子」
「久しぶりね、泪」
冴子さんがにこやかに返事をした相手は、匂い立つような大人の女性だった。
ゆるく波打った長い黒髪と、濡れたような瞳、濃厚な女を漂わせる肉厚の唇と、その左下のホクロが特徴的な男好きのしそうな女の人。
お店のロゴだろう子猫の柄のかわいらしいエプロンをつけているが、その下のニットと細身のロングスカートに包まれた肢体は、肉感的でグラマラスな曲線を浮かび上がらせ、子猫というよりむしろ発情期の雌猫のように濃厚な大人の女のフェロモンを常にあたりに振りまいている。
「あら、そちらの坊やは?」
泪と呼ばれたその美女は手にもっていたコーヒーカップ(これも子猫の柄)をカウンターに置くと面白そうにまじまじと正樹の方を見つめる。
「ふふふっ、私の恋人よ」
冴子さんはそんな泪に見せつけるように、正樹の腕をぎゅっと抱き締めると少し身をかがめて頬を寄せる。
本気ともとれる冗談すれすれの危ないラインのセリフ。
「へ〜え、冴子はいつから少年趣味になったのかしら」
しかし動じるかと思った喫茶店の女店主は、冗談と受け取ったのだろう軽く流すと、正樹のほうにちらりとその色っぽい眼差しを向ける。
「それで、坊やお名前は?」
ハスキーな声にのって溢れ出る大人の女性のフェロモン攻撃に正樹はクラクラとなるが、何とか声をだす。
「あっ!高梨、高梨正樹です」
「ほら、私の甥っ子よ、前に話したじゃない」
冴子さんは正樹の手を引いて、カウンターの中ほどに並んで腰掛ける。
ちょうど泪の正面にあたる位置だ。
「あぁあの、そう、君は今冴子の所で暮している子ね……私は桐生 泪、小さいながらもこのお店の店長よ、
まぁ店員は私の他に妹だけだけどね」
そう言いながら、泪は二人の目の前に手早く水とお絞りを差し出す。
「あっありがとうございます」
「いえ、どういたしまして、はいこれメニューよ、お昼のランチはもうすぐ終わりだからお早めにね」
微笑むその姿も妖艶なほどの魅力を放っており、すっと伸ばされた白い指先の端までピンク色のねっとりとしたオーラが滲み出しているようだった。
おそらく意識してのことではないのだろう、先天的にもって生まれた性的魅力というものだろうか……
なんにしろやりたい盛りで、しかも精力を持て余し気味の正樹にはある意味つらい昼食になりそうだった。
「ねぇ泪、妹さん達は?」
「今日も学校よ、なんでも試合があるとかでね…ところで冴子、だいぶ仲がいいようね、その坊やと」
友人のからかい気味のその口調に、冴子さんは余裕の笑みをもって答える。
「まぁね、深〜い仲ですから」
「あら、冴子は男の人に興味がなかったんじゃないの?仕事一辺倒で……あぁなるほどね、男の人じゃなくて男の子がよかったわけ?」
本気にはしていないのだろう、クスクス笑いながら、話をまぜっかえす。
「ふ〜ん、そう言う自分はどうなわけ、こんな所に収まっちゃって」
「いいでしょ別に、だいたい冴子は昔から……」
「はぁまた泪のお小言がはじまった、だいたい泪は……」
クールでやり手のキャリアウーマンの冴子と、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせる泪。
この組み合わせは、もう大学で知り合ってからの十年来続いており、軽口をたたき合いながらもお互いの本質を認め合う間柄だった。
そんな二人がなにやら楽しげで正樹には分からない女同士のテンポで楽しみ出している間、当の話の肴の正樹はと言うと、ちらちらと店内に視線を走らせていた。
本当なら美女二人の様子を見ていたかったのだが、どうしても泪のその色っぽい口元や、エプロンを押し出す円やかな膨らみに視線がいってしまい、股間が大きくなるのをとめることができそうになかったからだった。
勿論、横を向いて冴子さんを見ても同じことが起きてしまうため、少年は必死に意識を散らそうと視線を泳がしていた。
店内は半分以上の席が埋まっており、そのどれもが男性客だった。
泪の男を誘うフェロモンを溢れ出すあの肢体と物腰、そして自分では気が付いてないだろう無防備なほどの魅惑的な美貌を考えれば当然の結果だろう。
正樹が知らないことだが、このお店のコーヒーはその味と香りから噂がたつ程有名であり、その琥珀色の液体を味わうために訪れる紳士もいるにはいるのだが、それでもどの客も二度目からはコーヒー以上に魅力的な女店主に一目会いに来るといった具合だったのだ。
そんな店内は、いま静かだが男性にしか分からないグツグツと煮えたぎる程の興奮の坩堝と化していた。
いつもと違わぬ魅惑的すぎる魅力をその熟れた肢体から漂わせる美貌の女店主。
そして、その美貌に負けず劣らずの容姿で、カウンターに腰掛け扇情的なタイトスカートから白い美脚を晒すクールな面持ちの女性客。
これほど美味しい……いや、美しいツーショットなど人生でそうそう見られるものだろうか、いやない!
そんな訳で店内の男達はピリピリと殺気立つほどに緊張し興奮していたのだ。
奥のテーブルで新聞を読む老紳士は先ほどから同じ文面を何度も読み、向かいの青年の週刊誌は上下逆さま、そして正樹の後ろの中年男性はぼ〜と見とれた姿勢のまま、コーヒーに角砂糖を入れ続けている。
「でね、この新しい豆を仕入れてきたわけ」
「ふ〜ん、これね……んっいい匂いっ、悪くないかも」
「でしょ、でもね……」
そんな店の状態にまったく気が付いていない女店主は話に夢中でカウンターから大きな胸元が襟ぐりから覗きそうなほど身を乗り出し、受け答える冴子さんも足を組替えるたびに、チラリとなめかしい白い太腿を露出させていた。
ゴクリ
その度に、店中の男達の喉が生唾を飲み込み、椅子に座る青年が徐々に斜めに傾いたり、老紳士の新聞に小さな覗き穴が空いたり、中年男性が奥のトイレに駆け込んだりしている。
……なっなんだか、怖いや
正樹はその一種独特の場が形成されてしまった喫茶店で冷汗を流して引きつっていた。
もっとも、彼がまだ見た目子供だから冷汗ですんでいるのであり、もし成年男性だったら今ごろ男達の嫉妬の炎で焼け焦げていたことは間違いないだろう。
そんな悲喜交々の店内で、正樹はふとカウンターの奥に場違いなほど古びた椅子が置いてあることに気が付いた。
丸いクッションに1本足のデザイン。
他は新品に近いのに、その一脚だけはまるでごみ捨て場から拾ってきたように時代遅れで、店の雰囲気から浮いている。
……何の席だろあそこ
興味が沸いた少年は注意深く観察するが、その隅の席は椅子が違うだけで、他にはたいした違いはない。
まぁここは桐生さんに聞いたほうがはやいかな?
そう思って振り返ると、正樹が気にしていることに気がついたのだろう、冴子さんの視線もその椅子を追っていた。
「……まだ、あのままなんだ」
そして、まるで独り言のように呟く。
「えぇ、どうしてもね……私、駄目ね」
そう答える泪の瞳は光の加減だろうか、まるで泣いているように潤んで見えていた。
そんな二人の、何か通じ合った様子に正樹はそれ以上何も言うことができず、ただ黙って目線をそらすと手書きのメニュー表に視線を落とす。
目を潤ませた女店主がまるで誘うように色っぽかったこともあるのだが……
「あら、そんなに気にしないでいいわよ……さっ注文決めちゃって」
辺りの雰囲気を打ち消すように泪は努めて明るい声をだすと、親友の甥っ子に笑いかけてやる。
「えっ……はい、じゃこのお勧めサンドイッチセット…飲み物はミルクティでお願いします」
正樹はその親しみのもてる笑顔に救われたように、メニュー表の一番上の当店のお勧めをリクエストする。
「冴子は?」
「そうねぇ、私はいつもの…ん!ちょっとごめんなさい」
そう言うと冴子さんは小さなポーチから細かくバイブレーションする携帯電話を取り出す。
モニターで相手を確認すると、少しその整った眉をよせしぶしぶといった感じで電話にでる。
「もしもし、私よ、今日はオフだっていって……」
その途端、正樹の耳にも届くほどの大音量な女性の声が携帯からもれ聞こえる。
おそらく泣いているのだろうか、詳しい内容はわからないが「どうにもならないんです」とか「ごめんなさい」とか「川奈さんがいないとぉ……」とか、そんな感じだ。
どうやら、電話の相手は相当混乱しているようだった。
「落ち着きなさい……まず状況を……うん、それで……そう…わかったわ」
冴子さんは電話をしながらチラリと正樹の顔を見る。
その切れ長の瞳は、名残惜しげな何ともいえない寂しげな光をたたえていた。
急な仕事の電話というのはいかに中学生でも横で聞いていればわかるだろう。
本音を言えば、できれば少年に「今日は僕と一緒にいるんでしょ」と言って無理やりでも電話を切ってもらいたい……
しかし、正樹がそんなことをする子ではないことは、この数日一番肌を多く重ねた自分がよく知っている。
そこが彼のいいところなのだ。
「はぁ」
すっかり少年に隷属してしまっているキャリアウーマンは深々とため息をつくと
「………わかったわ、すぐ行く」
と、一言漏らし、嬌声を上げる携帯をオフにする。
「どうしたんですか?」
なんとなく分かっていたが正樹は少しの期待を抱いて聞いてみる。
「ごめんね、正樹君、急な仕事が入っちゃったの、部下の子がドジったみたいで、本当にごめんっ」
「そうですか……いいですよ、このお店、通学路の駅から近いみたいですし電車で帰れますから、僕なら大丈夫です」
正樹にできるのはこれぐらいだ。
ただでさえ居候させてもらっているのだ、冴子さんのお仕事の邪魔にならないでおこうと前々から自分に言い聞かせてある。
そんな聞き分けのよすぎる正樹……いや、小さなご主人様の態度が、さらに冴子さんの保護欲と愛情に火をつけていた。
もう離れたくない……できるなら今すぐ、正樹様を抱き締めてキスしてあげたい。
「あ〜〜ん、それなのに、もう、あのバカ娘、せっかくの私のご主人様とのデートだったのにぃ」
彼女にしては非常にめずらしく、その場の状況を忘れて思わず声に出して悔しがる。
この後の正樹との楽しい予定も全てご破算だ。
もう少し街をぶらついてから、最近はまっている会員制のスポーツジムにいって汗を流して、その後二人っきりでホテルで食事して、あぁぁそれから、それから……
朝までコースだったのにぃ。
「冴子?冴子?行かなくていいの、可愛い後輩があなたが来るの待ってるわよ」
泪の声ではっと気が付く冴子さん。
「わっわかってるわよ……泪、正樹さ…君をお願いできる?」
本当なら私が最後までご奉仕したいのに……
「いいわよ、ちゃんと面倒みたげるわ」
「……頼んだわよ、大事な人なんだからね」
少し恨めしそうな視線。
泪はやすやすとそれを受け流すと「はいはい」と答えてひらひらと手を振る。
そして冴子さんは、くるっと振り返るやいなや、少年の頭をひしっと自分の胸に抱き締める。
「うぐっ……さっ冴子さん」
ぷりんっとしたバストの柔らかさが布地越しに正樹を包み込み、嗅ぎなれた、しかし、飽きさせることのな
い冴子さんの美肉の甘い匂いが漂いだす。
デートを途中で放棄しなくてはならくなった悲劇の美女は、その耳元に精一杯の愛情と湧き上がる気持ちをこめて囁いてやる。
「正樹君、ごめんね本当に、許して……くれる?」
「うっうん」
柔らかく気持ちのいい肉の壁に抱き締められたまま正樹はなんとか返事をかえす。
「ありがと!……そうだ、この埋め合わせは今夜……たっぷりしてあげるわね♪」
「うっうん」
周りの客の視線が恐ろしい。
だが年上の美女は可愛い少年をなかなか手放すことができそうにもない。
「ふふっ、凄いご奉仕してあげるからね、お口がいい?それともお胸?それとも……」
そう言いながら、胸の中の正樹の口元にチロチロとピンク色の蠢かす冴子さんの口が迫る。
今夜どころか、今ここ、衆人観衆の目の前でその凄いご奉仕を始めそうな勢いだ。
「ゴホン」
その時、ちゃちゃを入れるような咳払いが喫茶店の中を響き渡っていた。
そこには「んっんっ」と口元に手をあてて抱き合う二人を見るのも恥ずかしいのか、目線をそらし咳払いを繰り返す泪の姿。
「!!!………なっなによ泪……こっこれはその……それよ……それ、そう!家族の親愛の情を示す…その一つのコミュニケーションなのよ!ごっ誤解しないでよね!私が甥っ子を誘惑してるとかそんなじゃないのよ……本当よ!……そっそれじゃご主人様また今夜ね」
冴子さんには羞恥で頬を染めながら逆ギレっぽくそう早口でまくし立てると、ダンとカウンターにお札をおいて店から駆け出していく。
チリンッ チリンチリン
店内に虚しく響くガラス細工のベルの音が呆然とする一同の上を通り過ぎていく。
……さっ冴子さん墓穴堀まくりだよ……しかも、最後は素でご主人様っていっちゃってるし……
とほほほっと涙をながす正樹の後ろから興味津々の艶っぽいに声が聞こえてくる。
「ふふふふっ、洗いざらい教えてもらおうかしら、坊や……あっご主人様…だったからしら♪」
そこには好奇心で満ち溢れた瞳を潤ます美貌の女主人が迫ってきていた。
「はははっ、何ででしょね」
今まで以上に冷汗を流し、口元をひくつかせる正樹だった。
「ふ〜む、坊やもなかなか強情ね」
「……しゃ、しゃべりませんからね、僕」
すでに時計の針は正午過ぎ、太陽もだんだん傾きだしている。
最寄駅から徒歩5分の場所にある雑居ビルの一階に小さな喫茶店「クリソベリル」。
駅裏にある小さいオフィス街と駅前デパートから流れてくる客層をターゲットにしているその店は、このビルのオーナーでもある先代の代から、美味しいと評判の自家焙煎のコーヒーを出す店として通の間では人気だった。
そして現在は先代の長女が店を引き継いでからは、美味しいコーヒーを美貌の女店主がだしてくれる店として、さらに人気を博していた。
そんな喫茶「クリソベリル」のカウンターで件の美人店主にまるで言い寄られるようにして、詰問されている少年。
彼、高梨正樹はほとほと困っていた。
冴子さんがとんでもないボロをだして、そのままアメ車をかっ飛ばして去ってからすでに1時間が経過している。
お昼の時間を過ぎてしまったからだろうか、もう店内には正樹の他に客はまったくおらず、レコード音源の聴いたこともない澄んだ音楽が流れ、色ガラスのはめ込まれた窓から優しい太陽の光が差し込んでいた。
それだけなら、別に何の問題もない、休日の素敵な午後の風景だっただろう。
しかし、正樹のすぐ隣、カウンターにもたれ掛かるようにこちらをじっと見つめる人物にたぶんに問題があった。
その人物はこの喫茶店のオーナー、桐生 泪。
その美しさと服の上からでもわかる秀逸な肢体、立ち振る舞いに話す声色、何もかも全てが色気のありすぎる魅惑的な美女。
軽く波打った黒髪はその端正な顔の輪郭をまるでフォーカスをかけたように彩り、つねに潤んだような瞳は見た者全てをベッドに誘っているのかと誤解してしまうほど濡れている。
そして、ぽっちゃりと肉厚な赤い唇と、その左下のホクロが、彼女を淫蕩に見せていた。
だれもが街で彼女に会えばまず間違いなく自分を誘っていると思うほど、男を引き付けるフェロモンを発しているかのように……
もちろん、正樹だってこんな美女と二人っきりでいるのは吝かではない。
しかし、問題はこの美貌のオーナーが正樹に迫ってくる理由だった。
「ほら、言っちゃいなさい、冴子と何があったのよ、ね」
にっこり笑いながら、その色っぽい美貌をそっと正樹のそばに寄せてくる。
そう、冴子さんの古くからの友人でもある彼女は、親友の失言、正樹をご主人様と呼んだり、公衆の面前で中学生の甥とはいえ他人に抱きついたりした行動に興味以上のものを抱きそれを追求しようとしていたのだ。
すでに様々な手管が使われたのか、正樹の目の前には、泪自慢の自家製アップルパイやシュークリーム、などなど様々な品が並べられている。
どうやら美味しいデザートで正樹の口を割らそうとしたらしい。
だが、正樹はガンとして真実に答えず、「冴子さんが言い間違えた」や「僕の方から抱きついた」と必死に弁明を繰り返すだけだった。
そんなこんなで、すでに二人っきりになって1時間が経過しようとしていたのだ。
「ねぇ、お姉さんがこんなに頼んでもダメ?」
「……だっダメです」
同じような問答の繰り返しで会話はまったく進展のない平衡状態だったが、しかし、二人の距離は意識してか無意識かこの一時間でだいぶ狭まっていた。
泪はどうやら、食事で釣るのは諦めたらしく、今度は会話の流れで少年がボロを出すのを引き出そうとするのか、エプロンをはずし、襟ぐりの広い黒のニットと、こげ茶色のロングスカート姿になるとカウンターから出てきて、正樹のすぐ側に立っていた。
「冴子さんはただの叔母さんなんでしょ?それなのになんであんなことしたのかなぁ?」
どうして坊や?
というように、泪は小首を傾げ、前かがみになると正樹の顔の側に「んっ」と近づける。
エプロンをはずしたその格好は罪作りなほどに扇情的で、正樹は思わず無礼を承知でまじまじと、ニットを押し出す胸の曲線とその襟ぐりから覗く白い肌と深い谷間を凝視してしまっていた。
「そっそれ……それは、カゾクのコミニュケーコンです」
意味もわからず冴子さんの受け売りをしてみる。
「……正しくはコミュニケーションね」
「……すいません」
正樹は自分が情けなくて涙がでてくる。
本当にこんな尋問めいた事が嫌なら、とっとお金を払ってこの場を立ち去ればいいのだ。
オーナーの泪も別に無理強いしたり、何が何でも聞き出そうとしたりしている感じではない。
どちらかというと、泪もまだ見た目も仕草も子供の正樹をかまうスパイスとして、この会話をふってきている感じだった。
なぜ、正樹が逃げないかと言えば、一重にもうちょっと泪さんとお話していたいなっと言う下心のなせるわざだったのだ。
しかし、そろそろ核心から離れるための、会話のネタが尽きつつあった。
冴子さんとの生活や、最近の学校の事など(勿論、女教師達の事は秘密だ)でお茶を濁してきたのだが……
「え〜と、そうだ、この前、学校のマラソンで……」
「お友達がみ〜んな倒れるぐらいハードだったのよね、それはもう聞いたわよ、正樹ちゃん」
いつのまにか、坊やの他に正樹ちゃんと言う呼び方が加わっている。
泪の姿勢はそのことを示すように、もう正樹の手が少し動けば腰に触れるほど近くにもたれ掛かり、両腕を前で組むとまるで流し目を送るように見下ろしていた。
その長い睫も、光を浴びて輝く肉厚の唇も、組まれた腕の上でむにゅっと盛り上がるバストも全てが魅力的で少年を誘うような雰囲気を漂わせている。
特に、カウンターにもたれ掛かったきゅっとしまった腰から、まろやかな重量感のあるヒップへのラインは思わず手を伸ばして撫でまわしたくなるほど、淫らな曲線を描いていた。
……ここは何とか話をそらさないと。
泪の店から出ることは考えないのは、正樹らしいと言えば正樹らしい選択だった。
その時、ふとカウンターの片隅、あの古ぼけた一本足の丸い椅子が思い出される。
そうだ!
質問には質問で返すのが、はぐらかしのテクニックだって本で読んだことがある!
正樹は、多少誤った知識を幸か不幸か思い出す。
「じゃぁね正樹ちゃん、冴子は正樹ちゃんのことお家ではなんて呼んでるの?」
まるでキスをするように唇をすぼめて質問をする美女に、少年は後先考えず先ほどの戦略を実践にうつしていた。
「そうですねぇ……ぼっ僕も泪さんに聞きたいんですけど、あそこに、隅にある古い椅子はなんなんですか?」
「え!」
泪は突然のその質問に本当にびっくりしたように、潤んだ瞳を一瞬大きく見開いて、まじまじと正樹の顔を見つめる。
……あれ…なんだろうこの感じ…
正樹は泪の瞳の奥に、どこかで見たことのある瞳を思い出していた。
「う〜ん、どうしよっかなぁ」
泪は悩んだような素振りで、すっと伸ばした人差し指を自分の唇にあてる。
そして、少年の視線が自分の口元に集中してりるのを見ると、カウンターにもたれ掛かっていたまろやかなお尻を少年に感づかれないように、少しずつにじり寄せていた。
「どうしても……知りたい?」
正樹の頬がぴとっと泪の人差し指で突付かれる.
「いっいえ、その…」
泪の甘ったるいローズ系の香りのする指先は、まるでその残り香を正樹の頬に塗りこめるようにピトピトと撫で回しだす。
……なっなんだか……様子がおかしくない……かな?
ようやく正樹もすぐ側に立つ魅惑的な女店主の様子が少しおかしいのではないかと疑いだしていた。
「正樹ちゃんはあたしのことが知りたくないのかな?」
つつっと頬を撫でた指先が正樹の唇に迫ってくる。
「そっそんな……泪さんが話したくないなら……」
正樹はドキドキと胸を高鳴らせて、その白い指先の軌跡に翻弄される。
……そうだ!この展開は!
正樹の疑問は確信に変わりつつあった。
頬を染めアルコールに酔ったようなトロンとしたセクシーな瞳。
「うふふふ、あのね……知って欲しいの…正樹ちゃんには……あたしの、秘密」
まるでにじり寄るように美女の腰がカウンターに乗り上げる。
ぎゅっと指を押し当てれば、むにゅっと淫靡な汁を溢れ出しそうな重量感のある大きな丸いお尻がまるで見せつけるように、カウンターの上に乗り上げる。
「知りたいんでしょ………」
細身のロングスカートに皺が寄り、まるで白磁のように艶やかで、濡れ光るような色気を染みださせる魅惑的すぎる美脚が露になる。
その足首に嵌められた十字架をかたどったシルバーチェーンのアンクレットがちゃりっと澄んだ金属音を響かせる。
「あっ…ああぁ……るっ泪さん」
目を皿のように広げた正樹の顔を這う回るルージュに濡れた白い指先。
正樹はその指一つで色気の金縛りあったかのように椅子からピクリとも動くことができなかった。
「ふふふふ、正樹ちゃんは…………」
濃密な霧のような誘惑のフェロモンを漂わせる美貌が妖艶な笑みを浮かべて迫ってくる。
間違いない、この潤んだような、そして濡れた目の輝き。
あの夜浴室で、電車の中で、校舎裏で、グラウンドの隅で、保健室で、そして茶室で!
正樹の腕輪が外れた瞬間に美女達が見せた瞳の色にそっくりなのだ。
そんなぁ……
あわてて自分の手首をチラリと目線を落とす。
だがそこには保健医によって留め金を直された例の皮の腕輪がしっかり嵌っていた。
じゃぁ、なんで??
まさかあの黒い焦げ跡のせい?
『私にもどうなるか正直わからんな』
そう言った保健医の困った表情が浮かんでくる。
どうしよう?どうしたら?
などと、いつも通りに混乱しながらも、目の前にせまる甘露のような美貌へフラフラと引き寄せられる正樹。
と、その時、
ピンッ
「いたっ」
突き出した正樹の鼻先が白い指先に弾かれる。
「ふふふ、何考えてたの、ス・ケ・ベ」
そこには、いたずらっ子をしかるように指先をくるくるっと回す、泪のちゃめっ気たっぷりの笑みがあった。
「え?ええ?」
「うふふふ、びっくりした?」
大人の女の余裕の光を宿す瞳には、先ほど正樹が感じたと思った虜になった兆しはまったくなかった。
……きっ気のせいだったの…かな
「だめよ、坊やにはまだまだはやいんだから」
スカートの乱した姿でカウンターに乗りかかり、少年の目と鼻の位置で指を左右にふる美女。
それは年上のお姉さんが中学生をからかって遊んでいるといった感じだ。
……でも、その仕草は色っぽ過ぎます。
正樹が少し赤くなった鼻先に負けないほど耳まで赤くしていると、そんなことを知ってか知らずか。大人の色気のつまったお尻ときゅっとしまった魅惑的な腰をカウンターの上にのせた美女はにっこり笑って、さらに身を乗り出してくる。
「ふふふふ、まぁお店にくる人ならたいがい知ってるんだけどね、あの椅子…私の婚約者の指定席だったの」
扇情的な女オーナーは椅子の由来をさらりと話し出していた。
その瞳は、まるでどこか遠くを見るような視線で古びた椅子を眺める。
もしかしたら、その視線は椅子ではなく、その恋人を追いかけているのかもしれない。
「……婚約者ですか」
…そうなんだ……残念
本音がちらりの正樹少年。
こんな妖艶な美女に男性がいないほうがおかしいだろう。
でも、なぜかがっかりしてしまうのは男の性だ。
「もう7年も帰って来ていないんだけどね」
「え?……単身赴任?」
なぜか正樹の頭に真っ先に思い浮かんだのはその単語だった。
「いいえ、彼は刑事でね、その捜査中に…ね」
泪は少し目を伏せ何かをまた思い出すように少し小首をふる。
そのことは帰って来ていない、ではなく、もう帰って来られないのだと言うことが正樹にも容易にわかった。
「まぁもう、昔の話ね」
努めて明るく言いなれた言い訳を口にしている、そんな感じだった。
まだ中学生で男女の機微には疎いほうの正樹でさえ、泪がいまだにその亡くなった婚約者を心から思っていることはすぐにわかった。
正樹はそうとうがっくり来たのだろう、少しばかり肩が落ちてしまっている。
そんな正直な正樹の様子に、いまだにカウンターの上に扇情的な格好で乗り上げている美貌のオーナーは面白そうに笑う。
「うふふふ、聞きたいから聞いたんじゃないの?どう他にも何かお姉さんに質問はあるかしら?」
なんだか質問されたほうが積極的だった。
こんな展開は予想していない。
黙り込んでしまう正樹に泪は、話を続ける。
「それにね、もう、昔の話よ、本当に、何となく捨てられなくて置いてるのよ……その……良かったら、あそこに正樹ちゃんの専用の椅子でも置いてみる?」
「え?」
「いっいいえ、なんでもないの……じょ冗談よ、冗談」
そう冗談にしながら、泪自身が一番驚いていた。
だが、ポロリと本当に素直に口をでた言葉はもう止まらない。
最初は本当にからかい半分だった。
少年と話すきっかけとして尋問のようなお遊びをはじめていたつもりだった。
もちろん冴子のあの劇的な変化の理由も知りたくないことはない、といえば嘘になる。
なにせ、あの川奈冴子が人前で男性に抱きついたのだ!
昔から独立性に富み、人一倍自分に厳しく、その分誰にも依存しなかった彼女、冷徹な瞳で物事を見極め、常に今自分がやるべき事を客観的に判断する力をもった才女。
それが川奈冴子、泪の無二の親友にして、そう……もっとも対極に位置する生き方を選んだ尊敬すべき相手だったはずだ。
その彼女をして、冗談でもあんな行動と言動をとらせることのできた少年のことが知りたかったのだ。
そして、話をしているうちに、可愛らしい親友の同居人がドキマギする様が、母性本能をくすぐるようでどんどん楽しくなっていた。
そんな正樹にこの店自慢のアップルパイやシュークリームを味わってもらいたくて、おやつで釣ると言う名目で色々食事をだし、話も弾んできた時だった。
……桐生 泪はようやく自分の異変に気がつきだしていた。
…なにかしら、この感じ。
何故かこの目の前の少年と話していると心が満たされるのだ。
しかもまるであの頃のように燃えるような気分がよみがえってくる。
気が付いた時には、正樹と二人きりになるために他の客を追い出し、店の看板もこっそり「CLOSE」に変えていた。
そして、自分でもわからない何かを期待して少年の側にそっともたれ掛かる。
自分はどうかしている。
こんな少年相手に……
相手は、親友の甥っ子なのだ。
それに、自分は操をたてた相手がいるではないか。
もう会える事はないけれど……
7年間そうしてきたし、それに苦痛は感じはしなかった。
そのはずなのに、こんな子供に……なんで……体が熱くなるの………
泪はこの1時間、自分の女の部分が潤んでくるのを感じながら、必死で平静を装い話し掛けていたのだ。
「あの……すいません、こんなこと聞いちゃって」
正樹の声にはっと意識を取り戻す。
おそらく自分が気にしていると思ったのだろう。
そう、そうなのよ、冗談なんだから!私はまだあの人のことを……あの人が…好きなはず…多分……好き…正樹……好き……好き…・・
「好き…」
最後の最後で、混乱する思考が呟きとなってこぼれだす。
「え?」
「あなたが好……いいえっ!なんでもないわ、忘れて……」
泪は思わずまたこぼれそうになった素直な言葉を飲み込む。
なっ!私、何を言おうとしたの?
このままでは、本当にダメになってしまう。
「…今日はもうこれくらいに……しておいてあげるわ」
ぼ〜っとまるでのぼせたようにふらつく体を無理やり動かすと、そっと正樹の側から離れようとする。
……これ以上、この子の側にいちゃ本当におかしくなりそう。
正樹のことを意識すればするほどまるでお酒に酔うにように、泪の頬は赤く染まり、胸の鼓動がはやくなっていく。
まるで目の前の少年から彼女を酔わす特別な何かが漂いだしてるかのように…
何…何なの……私……
ぐっと腕に力を込め、意を決して離れようとしたその時、
「泪さん?」
様子のおかしい彼女に声をかけていた正樹と目があってしまう。
心配げにこちらを見つめるまだ幼い少年の瞳。
……あぁぁ
ドクン
「あんっ」
「あっ」
ふらっとバランスを失った泪はカウンターに乗り上げた時にまくれたスカートのせいで、カウンターから滑り落ちていた。
魅惑的な肢体が捻られ、その反動でぱさっと泪の長い後ろ髪が跳ね上がる。
ふわっと広がる黒く波打った髪はまるで夜色のカーテンのように広がり、妖艶な雰囲気を放つ美女を際立たせる。
「きゃっ」
一瞬視界を遮られた泪は思わず手をつくタイミングを失い、そのまま正面にいた椅子に座る正樹の腕の中に倒れこんでしまっていた。
「だっ大丈夫ですか?」
まるでお姫様だっこをするように自分の膝の上で抱き締めた柔らかい感触にドキマギしながら声をだす正樹。
しかし、腕の中の泪からは返事はなく、乱れた黒髪に隠されてその表情が見えない。
「泪さん、泪さん」
「……このまま、このままでいて…お願い」
ほんのりと立ち上る魅惑的な甘い大人の香り。
乱れたスカートから覗く白い脚、腕に押し付けられるニット越しの柔らかい胸、すっぽりと腕に納まるむしゃぶりつきたくなる腰、そして掌に感じる埋もれるほど柔らかく淫靡なお尻。
広い襟ぐりから浮かび上がる細い鎖骨はまるで口付けてくれと言わんばかりに男を誘っている。
正樹にしてみればこの誘惑にたえるのは一種の拷問だった。
「……うん」
それでも素直に返事をかえす
「……ありがと」
無言のままのその時間は数分、いや数十分続いただろうか……
正樹は何がおきているか皆目見当もつかず、ただ言われたままに年上の美女を抱きつづける。
お昼過ぎの柔らかな光が差し込む喫茶店。
針の落ちたレコード盤を回し続けるプレーヤーの微かなモーター音。
やがて……
「ひどい子ね、坊やは」
胸をくすぐるような掠れたハスキーボイスが微かに響く。
ばさっとひるがえるウェーブの掛かった黒い髪。
そしてぬぅっと伸びた白い腕。
まるで闇夜の中から伸びる幻影のような白く蕩けるその甘い楔は、少年の頭の後ろでがっちりと逃がさないように交差する。
「るっ……泪さん」
椅子に座る少年の腕の中には魅力的な夜色の髪を広げる淫らな女神がいた。
「ねぇ、なにをしたの?」
波打つ黒髪はまるで絡みつく蜘蛛の糸ように少年にまとわりつき、その間から真っ赤なルージュの唇がまるでピンク色の吐息を吐くように突き出される。
「なっ…なにって」
正樹はその濃い霧のような色気に包まれぼんやりと答えるのが精一杯だった。
泪のまるで真珠のように濡れ光る唇が、そっとまるで撫でるように正樹の頬をかすめる。
その瞳は……正樹の見知ったそれと良く似た輝きを放っていた。
なっ…なんで…そんな…
…腕輪してるのに……
「ねぇ私にどんなことをしたの?」
「そっそれは……」
そのままゆっくりと赤い唇が、少年のそれに重なると、まるでその柔らかい感触を教えるためかのように擦りまわる。
正樹の胸にあたる魅惑的なバストの感触。
柔らかなニット地を突き上げるそれは、まさに男の手で揉まれるために存在するように淫らで、そして蕩けるようなバストの形を浮き立たせていた。
そして円を描くように動くその美体にあわせて、服越しでも固くなっていることがわかるその乳首が正樹に擦りつけられる。
「さあ全部言いなさい、正直に言えば怒らないわ」
正樹と泪の美貌は1ミリたりと離れていなかった。
女オーナーの犯罪的に甘い香りのする美貌は、正樹の顔に優しく重ねられ、その蜂蜜に漬けられたような、とろっとした唇が顔中を撫でるように這い回る。
その唇の感触は、まるで触れた肌を溶かすように熱く、そしてぬめった愛液のようにフェロモンを放っていた。
「おっお守りです……僕の力で……」
泪の性的魅力の放つ気持ちの良すぎる拷問に耐えられず正樹は力の秘密を話してしまう。
「それで…僕にもわからない力で…腕輪がはずれると・・…女の人が」
途切れ途切れになる声の途中では泪が促すように、唇を擦りつけ甘い吐息を餌に引き出していく。
「……今は…よくわからないけど…・腕輪の焦げ跡のせいじゃないかって…」
正樹ははぁはぁと荒い息をつきながらなんとか話し終える。
「なるほどね、坊やはこうやって目をつけた女の人を食べちゃってるわけね」
美女の魅力にクラクラしている正樹の話は要領をえなかったが、それでも一番大事なところは伝わったらしかった。
「そっそれは…そんな」
「冴子ともしちゃったの?」
上目つかいで、面白そうに少年を見上げる魅惑的な美猫。
つつっと顎をなでるピンク色のツメ。
「……うっうん、でも…あれは腕輪が」
「言い訳しないの、やったんでしょ?坊や」
ぐりっと泪の腰が動き、わざとボリュームあるヒップを正樹の手に押しつけ、その重みと溢れ出る卑猥なフェロモンを擦りつける。
「うっ…はい、冴子さんとしました」
「ふううん、それでご主人様って呼ばせてスケベな調教しちゃってるんだ、自分の叔母さんを犯すなんて……いけない子ね、坊やは」
真っ赤になって下を向く正樹。
だが、その耳に予想もしないセリフが飛び込んできた。
「ふふふふ、坊やの考えてることなんてお見通しよ」
「え…?」
にんまりとまるで猫のように笑う泪はまるで正樹の心を見透かすように話し出す。
「私も奴隷にしたいんでしょ?冴子のように毎日毎日犯したいんでしょ?だからこんな風にしたんでしょ?そうよね、坊や」
まるで正樹に「そうです」と言わせんばかりの詰問口調を並べながら、その指先で少年の胸元のボタンを弾き飛ばす。
「……あの、それは…その…泪さんのこと素敵だなって思いましたけど…でも、婚約者も…その」
正樹がちらりと古びた椅子のほうに目線を向けようとすると、
ぐいっ
むりやり美女の手がその顎先を掴んで視線を戻す。
「私は関係ないのよ、坊や……あなたの言葉一つよ、さあ、そのお口で言いなさい、坊やは私が、欲しいの?欲しくないの?」
まるで気まぐれな猫のように瞳を細めると、口付けるようにその唇を窄めて人差し指でなぞっている。
その肉厚の唇の下のホクロがさらに淫蕩で妖艶な雰囲気をかもし出していた。
「欲しくないの?ぼ・う・や」
ふうっと吐かれる大人の女の吐息は正樹の固まった判断力を蕩かすのに十分だった。
「ほっ欲しいです、欲しいに決まってます…でも」
しかし、そこは優柔不断の高梨正樹。
もぞもぞもと体を動かして言葉を続ける。
「やっぱり……こういうのは」
だが、そんな少年の迷いなど当の本人はまったく聞いてはいなかった。
「ふふふ、私が欲しいのね……ふふふ、スケベな坊やなんだから、しかたないわね……そうと決まれば、邪魔なのは…う〜んと、あぁ」
「??」
泪はまるで悪戯を思いついた子猫のように正樹の膝の上で小首をかしげると、やがて目的のモノを見つけ出す。
「これね」
「えっ!」
ピンッ
「あっ」
そこには、唖然とする正樹と、得意げに指先をくるくるっと回す泪の大人の笑顔があった。
そして正樹の腕から弾き飛ばされて床に転がる皮の腕輪。
「これで私は完璧に坊やの虜ってわけね……あぁ、ひどい坊やね、こんな得体の知れない力で年上のお姉さんを本気にさせちゃうなんて、ふふふ」
呆然とする正樹の唇に泪の柔らかく蕩けるような唇が重なり、しっとりとした温かさが伝わってくる。
「もう放さないわよ、いい?」
「うぅ、うん」
正樹にできることは、まるで猫に追い込まれた鼠のようにただカクカクと首を動かすことだけだった。
もっともその猫は、この世でただ一匹の鼠だけを獲物にする淫蕩で魅惑的な最高の美猫なのだ。
「ふふふっ、いいわ、これで私はあなたのモノよ、冴子のように」
まるで妖花のように艶やかにそして淫らな笑みを浮かべたその唇の間から、とろりとまるで花の蕾のように尖らせた舌が迫り出してくる。
「泪さん……」
美女のその白い肌から、湯気の出るように匂い立つ淫蕩さに絡め取られ、瞳の奥に揺らめく幻惑的な光に誘いこまれるようだった。
「ふふふふ、もう我慢しなくていいのよ、正樹ちゃんの口の中に私の唾液たっぷり流し込んであげるわね・・・・・・んんっっ」
泪の舌が正樹の唇にむしゃぶりついていた。
まるで獲物を捕らえた肉食獣のようにしっかりと少年の首にその腕をまわし固定している。
ちゅく ちゅるる じゅるるるる
交じり合った唾液がお互いの口の中を行き来し、粘着質な音が響き合う。
「あっ、んっ、おいしいっ、正樹ちゃんの唾液いいわよ、んっんんっちゅる、とってもおいしいの、んっんっ」
泪は丹念にだが、貪るように秀麗な顔を傾け、少年の口の中を舐めあげ唾液を啜り、かわりに自分の甘い淫液を注ぎ込んでいく。
「泪さん…んんっ…ううぅ」
美女の猫のようにざらついた舌の感触が心地よい。
トロっと交じり合った舌がまるで水を啜るように入念に唾液を啜りあげ、美女の喉の奥へと消えていく。
ちゅく ちゅるるる
「んっんっ、泪さんっ、あぁぁ」
「はぁ、いいでしょ坊や?んっ・・・・・・お姉さんのキスは最高かしら?……んんっ」
美女の猫舌は少年のそれに絡みつくと、まるでしっとりと吸い付くように蕩けあいトクントクンと唾液を交換し続ける。
「はいっ・・・・んっんっ、いいです…さいこ……んぐんぐ」
徐々に正樹もこの深く飢えたキスになれてきたのだろう、年上の女店主の口の中に自分の唾液を余すところなく注ぎ込み、その柔らかい唇や躍動する舌を味わいだす。
「あふぅ、んんっ、んぐんぐんぐ、いいわ、、好きよ、大好き、んんっ」
泪はすでに口付けを受けているだけで何度も軽い絶頂に達していた。
もう不思議な力だろうが、なんだろうが関係ない、この少年が自分を満たしてくれるのだ……一生ここに縛られていただろう自分を連れ出し、また、愛することを許してくれる人なのだ。
そう……この子に、この子なら、私の全てあげられる。
少年が送り込んでくれる甘露のような唾液を嚥下しながら、泪はピクピクと震え乱れたロングスカートの中の下着をぐっしょりと濡らしていく。
その色欲にくるった思考は、徐々に正樹中心に組み立てられ、自分でもその甘美な考え方に身も心も染まっていく。
そう今ならはっきりとわかる。
あの冴子がなぜこの少年を「ご主人様」と呼んだのか……
そして、いずれ自分もそう呼ぶことになるだろう。
あの時、少年の手首の腕輪を自分からはずしたあの瞬間から…・
発情期の猫のように扇情的で色気を放つ美貌の喫茶店店主、桐生 泪は、その淫らな肢体も、そして婚約者を待ちつづけた気丈な精神さえも目の前の出会ったばかりの少年、高梨 正樹に隷属させていた。
自ら進んで……
傾きだした太陽の光が差し込む喫茶「クリソベリル」
いつもなら「OPEN」しているはずのその小奇麗な喫茶店は今日はなぜか固くその門を閉じていた。
そして二人しかいない喫茶店の中、一人の少年が自分を見つめる美貌のオーナーの色気に圧倒されていた。
さらっとその美貌にかかる艶やかな黒髪。
ほんのり上気した白い頬。
ルージュの引かれた瑞々しい唇。
そしてその上をまるで飢えたように這いまわりチロチロと動く淫らな舌使い。
つい先ほどまで、自分をお子様としてまったく相手にしてくれなかったオトナのフェロモンを漂わす美女が、今は自ら望んでその体を差し出しているのだ。
ううぅ、泪さん、色っぽすぎるよぉ。
ぎゅっと膝の上に横座りになる女店主を抱き締めていた少年は、その濃厚で淫らすぎる形のよいバストを揉み続けながら、まるで誘われるままにまた顔を寄せていく。
薄く開けられた唇の奥では、真っ赤な舌が扇情的に、にちゃっとねとつく動きを見せ大好物のエサが与えられる瞬間を待ちわびている。
「ふふ、私にまたキスしたいのね坊や、いいわ好きなだけさせたげる、うふふふ、あたしの舌でたっぷり可愛がってあげるわよ」
「うっうん」
トロンと欲情におぼれた瞳の泪は、胸を少年に与えながら、首をひねってその真っ赤な唇を開いていく。
ねっとりと桃色の息をはく口腔内では軟体動物のような舌が蠢き、少年のそれを誘い込むスケベな罠のように待ち構えていた。
くちゅっ
水に飢えたドーブツがむしゃぶりつくように、正樹の舌が泪に絡みつくと、そのまま艶やかな唇に覆い被さり、むしゃぶりついていく。
「んんっ、んぐっ、んんっ」
「あぁっ、ちゅくぅ、んっ、上手いわよ、ほんとスケベな坊やね、んっ、んんんっ、ほら唾液もね、んんっ」
ちゅぱっ じゅるる ちゅくちゅくちゅく
泪はそのしなやかな肢体をぐいっとひねった格好で抱きつくと正樹の唇を貪欲に貪りつづける。
砂糖菓子のように蕩けるゼリー状の唾液をドロッと飲ませ、蠢く肉塊のように舌を絡まらせ思う様に少年を翻弄していく。
まるで溜まりにたまった妖艶なる欲望が具現化したかのような接吻だった
ちゅく ちゅちゅる んんんっ
「はぁ、ううぅ、泪さん……んんんっ・・・・・んっ」
「いいわよ、坊や、ほらお姉さんの舌をあげるわよ…んっんちゅ…んぐんぐ」
それはまさにキスというより少年の口の中を蹂躙する肉の食事といった具合だった。
妖艶な女店主は口唇をねじるように何度も何度も少年の口を舐めしゃぶり甘く噛むと、その歯の間から差し込んだ淫らな舌で丹念に丹念に口腔内を舐め清め全てを啜りとっていく。
「んっうぅ、んんっ…ぷはぁぁ……泪さんっ激しすぎっ…うぷぅ」
「だめよ、正樹ちゃ…ん……っと、味わせてもらうんだから、ふふふ、こんなにしたのはあなたなのよ」
泪の白い腕が正樹の頭を固定すると唾液の糸をひく唇をまた奪おうとする。
「私をこんな気持ちにさせるなんて…ふふふ、冴子もこんなふうにしちゃったんだ、本当に悪い子ね、今度二人でたっ〜ぷり可愛がってあげるわ……さあ、お口を開けなさい坊や……そうよ、いい子ね、お姉さんのトロトロの唾液、たっぷり飲ませてあげるわ」
異性を蕩けさす鼻の奥から抜けるような淫らな声を上げ、美貌で性的魅力を放つ女神は自分を堕落させてくれた大好きな少年の口の中に舌先にのせた唾液をとろっと流し込む。
「んふぅ、ほら、美味しいわよ」
「……うんっ、んっ」
くちゅ ちゅくちゅく
勿論、泪の蠢くヒルのようなピンクの舌が唾液を運ぶだけで終わるがはずがない。
そのまま少年の舌上をつつくように這い回ると、攪拌されて混ざり合った唾液をすくい上げ自分の濡れ光る唇の中に運んでいく。
んぐっ ごく ごく
じっと猫のような瞳が上目つかいに正樹を見つめたまま、まるで見せつけるように白い喉が上下に動くと二人の混合液を嚥下していく。
「うふふふふ、美味しかったわ、坊やのよ・だ・れ、とってもドロドロなんだもん、あらもっと飲んで欲しいの?……うふふふ、それともこっちが坊やは飲みたいのかしら?」
正樹の膝の上に横座りになった女店主は、からかうような口調でそう言いながら、正樹の腕に回した腕でぐいっと上半身を密着させ、ニットの上着を押し出す豊かな膨らみを強調する。
「るっ……泪さん」
先ほど溶けるようなキスをしたのにすぐにカラカラになっていく正樹の喉。
「うふふふ、本当に可愛いんだから、いいわよ、ご褒美あげる、お姉さんのおっぱい特別にもみもみさせてあげるわ、好きでしょ?坊や」
ニットの上着から両手でも掴みきれないほどの形のいい美乳を見せつけ、しっとりと包み込むような色気をはなつ美貌のお姉さんに、瞳を潤ませながらこんな許しをいただいて「いりません」というバカはいないだろう。
そして正樹も、美女のお願いに真っ赤になりながらも恥ずかしそうに頷く。
「泪さん」
「んっ…いいわよ、そう、ゆっくり手を差し込んで……あっ…今ブラを…いいっ上手いわよ、坊や……あっ、ああぁ、そんな…んんっ!」
椅子に深く腰掛けた正樹の膝の上で、ニットの裾を引き上げられ、こぼれ出た白い半球体が仄かに浮かび上がり、妖しくそして淫らに蠢く。
ブラのホックは泪の協力のもと早々にはずされ、その片手では隠し切れないバストの下に引き下げられ、ぷるんっと震えるピンク色の頂を露出している。
そして、その見る者を魅了してやまない柔らかな肉球に、少年が顔をうずめ貪り食うように舐め、吸い付き、やりたい放題に陵辱していた。
「あぁ、あぁぁ、そこは、あぁそんなところ舐めちゃ、あぅ、いいぃ、いい」
まるで肌に絡みつく蜘蛛の糸ような甘く響く声。
くちゅくちゅと交じり合うドロリとした粘着質な液体の音。
「あっあぁぁ、気持ちいいぃ、あぁぁ、はぁん、んんっ」
桃色の霧が噴出すかのように、荒くそして色欲に狂った女性の声が響きつづける。
「あぁぁぁ、いいわ、坊やにお胸吸われてる、いいぃ、あぁ」
美声にあわせ白い美脚がロングスカートを蹴り上げ、まるで白磁のように薄闇に浮かび上がると、その汗の浮かんだ太股がピクピクと震える。
「だっだめ、あぁあぁん、そんなに噛んじゃ、乳首っ、いいぃ、あぁ、あぁぁあああ」
赤いルージュの引かれた形のいい唇がまるで何をか誘うように、とろっと唾液の糸を引いて開かれる。
そのままがくんと体がゆれ、漆黒の黒い髪が宙を舞い、その汗にまみれた頬に張り付く。
泪は正樹に胸をいじられただけで軽くいってしまったようだった。
「はぁはぁはぁ…すっすごいんだから……冴子にたっぷりに仕込まれたのかしら?ふふふ」
「そっそんなことは…・…うひゃ」
ベロンっとざらついた舌が正樹の頬を舐め上げると、うれしそうに目を細める。
「でも、今日からは私も先生よ、坊やにたっ〜ぷりスケベなことを教えてあげるわ、体でね」
「よっよろしくです」
体に擦りつけられる、美女の柔らかな肢体に頬を緩めながら正樹はお気楽に返事する。
やわやわとニットの上着を捲り上げた美女のバストをもみつづける正樹は、実はもうすでにあるのかどうかさえ怪しい理性をとうに放棄していた。
ぷるっと目の前で薄い紫のブラがはずれ落ち、まるで雪のような白く柔らかいおっぱいが二つ目の前にこぼれ出た瞬間に、もうただひたすら魅力的な泪の虜となってその巨乳をしゃぶり倒していたのだ。
「ふふふっ、それじゃぁさっそく私の全てを教えてあげるわ」
にまりと猫のように微笑む女店主。
「この姿勢じゃ少し大変ね、んしょっと、失礼するわよ」
「んぐ・・…えっ?」
泪の胸の谷間に顔を埋めていた正樹が顔をあげると、美女はすっと正樹の膝の上に向かい合うように座ってくる。
「あっあの」
ニット上着を捲りあげ引っ掛けるように突き出したお餅のような雪肌のバスト、正樹の膝の上でゆれる驚くほど細い腰、そしてきゅっとくびれたロングスカートに隠された大きなヒップが正樹の太腿のうえに乗りかかってくる。
「ふふふふ、正樹ちゃんお待ちかねの、お姉さんの秘密の場所……食べさせてあげる、ここに」
ジーーー
「あっ泪さん」
正樹の股間のジッパーが下げられ、それだけで元気のよすぎるペニスが踊り出る。
「あんっ、うふふふふ、お尻にあたってるわよ、坊やの固いの」
にんまりと笑いながら淫らな女オーナーは、少年の耳元に囁きつづける。
「入れたいでしょ、私の中で突き入れて、吐き出したいでしょ、坊やのことだもん、もうドロドロに濃いのがいっぱい溜まってるのよね」
想像しただけで濡れてきたのか、自分から進んで淫乱な言葉をしゃべりながら、泪はロングスカートを広げて正樹の下半身をすっぽり覆ってしまう。
そのスカートで隠れて見えないが、すでに勃起しているぬるぬるの正樹のペニスの先に、少し腰を浮かした美女の柔らかな陰毛や、すべすべしたお尻の感触が伝わってきている。
「うふふふ、いまからお姉さんのトロトロのいやらしい所で、坊やのを溶かしてあげるわ、うれしいでしょ?」
「はっはい」
「あんっ……んっ、さぁ中に入れたげるわよ、坊や」
ずぶっうぅう
「あふぅうぅ」
「ううっ」
下着をずらした白いお尻の魅惑的なスリットが落ちる先は、正樹のいきりたったペニスの上だった。
ずぶっうう ずちゅ ずるるる
「くふぅ…あふぅ…とっても固くて…・あぁ」
「るっ泪さん」
気持ちよすぎる。
まるで何十枚もの肉の輪っかがまるでそれぞれ独自に収縮を繰り返し、正樹のものを舐めしゃぶっているようだった。
もっともっと味わいたい。
正樹はその欲求が導くままに動き出す。
ずちゅずちゅずちゅ ずずずずっ
「あんっ、きゃぁ、あぁぁん、そっそんな、激しっ、すぎ」
「るっ泪さん、泪さん、あぁっ、あっあっ」
正樹は我慢できず、椅子をガタガタならしながらまるで跳ね上がるように、その魅惑的な肉壷を亀頭の先でつきあげ、肉棒を回すようにえぐりまわす。
「すごいです、泪さん、中がぁ、あぁぁ」
「わっ私、いいわ、坊やのが、ぐいぐいって入ってきて、あぁお腹の奥を擦ってる」
うめき声を上げる正樹の膝上に、脚を開いて座る魅惑的な美女。
その細身のロングスカートのスリットからこぼれた真っ白な太股は、少年の腰を左右にわかれ挟み込み、二人の腰がぴったりと重なっていることを示していた。
「いいっ、いっ……あっあっあっ、溶けちゃいそう」
形の良い眉をハの字にした美女の腰がまるでうねるようにクイクイと動くと、それにあわせて卑猥な音が響きだす。
「あっううぅ、ぬるぬるして…あぁ」
ペニスにまるで搾り取るように絡みつく肉ヒダは微細な皺を蠢かし、その色気の詰まった美体に勝る名器となって少年を淫らに責めだしていた。
「泪さんっ」
正樹はその包み込む暖かな肉の感触と、喘ぐ美女の濃密なフェロモンにまるで麻薬のように脳髄を溶かされると、ぐいっと腕を抱き合う美女のお尻に回す。
「あひぃ」
びくっとびくつく泪を無視して、正樹の手は荒々しくスカートに包まれた美女のヒップに掴みかかると、まるでその熟れた肉をもぎ取るように掴みかかる。
むにむにとむっちりとした魅惑的なお尻をもみこむ少年の小さな手。
「あんっ、お尻いじめちゃ…だっだめよ…あっああぁん」
このお尻の向こうに自分のペニスが埋まっているのかと、正樹は背筋がぞくぞくとするような気分に襲われていた。
もっと、もっと、この柔らかくてしなやかな肉を貫きたい、うねるような肉ヒダを削り上げ、お尻の肉に手形が残るほど揉みまくりたい、と言う欲求に駆られていく。
「泪さん、動くよ」
正樹はすぐ自分の目の前で、トロンと目を蕩けさせ、誘うようにぽっちゃりとした唇を半開きにする女店主に声を掛ける。
「ええ、坊やの好きなようにむちゃくちゃにしていいわ…あぁぁぁん」
ずぐちゅ ずっぶううぅ ずっん ずっん
泪の言葉を最後までまたず、椅子の上に腰掛けた正樹の腰がねじ込まれ、自分の上にむっちりと圧し掛かる極上の肉餅の中を動き回る。
「あひぃ、あぁ、はっ…激し…あっあっあっ」
その若く荒々しい動きは一人身を守り通してきた喫茶店の女店主の身に余るほどの快楽を一気に与えてるものだった。
ずちゅ ずぶっ ずちゅ ずちゅ ずぅちゅっ
「あっあっあっ…あぁぁ、こっ壊れちゃ…うぅ」
「ぼっ僕も、気持ちよくてっっ、止まらないっ」
あまりに気持ちよく甘い香りで包み込む肉ヒダの感触に正樹は腰を止めることができず、さらに激しく短いストロークで太股の上の美女を突き上げてしまう。
「あひぃ、あぁぁ、こっこんなに、あぁっ、すっすご…んんっあっあっあっ」
何度も何度も軽い絶頂に駆け上がる泪は、先程までのお姉さんぶった態度とは正反対にむせび泣きながら、少年の肩に両手をおいてガクガクと揺れるにまかせズンズンと子宮口まで征服されていく。
ずぶっ ずっちゅ ずっ ずっ
「ううっ」
少年もぐっと歯を食いしばるように快楽に耐えながら、トロトロと絡みつき絞り上げるような肉ヒダとまるで吸引するようにコリコリと動く膣肉を小刻みに激しく突きまくる。
欲望にくるった少年と美女の振動が、カウンターに伝わると、カタカタとデザートの置かれた皿が動きまわる。
「あっあっ、ねっ、泪さん、いいでしょ?ねぇ」
ガクガク小さく揺れながら正樹は、んんっと快楽に溺れる美女に問い掛ける。
「えっ…ええっ、いっいいわ、あぁ、いいです…いいぃ」
せっぱつまった声をだす泪。
その体が揺れるたびに広がった黒髪と、少年の太股の上にのったボリュームたっぷりのお尻が卑猥な音とともに揺れ動く。
喘ぐように肉厚の唇を開き、とろっと涎をたらして揺れるそんな美女を見上げながら、正樹はさらに質問を続ける。
「何がいいの?ねぇ泪さん、言ってよ、ねぇねぇ」
勿論、そう言いながら、椅子の上で小刻みに腰を動かし、ロングスカートの奥で美女の膣肉を突きまくるのは忘れていない。
「はひぃ、あぁぁぁ…そっそんなこと…いっ言えないわ」
中学生の少年に子宮口を連突きされ、いいように弄ばれる女店主はその熟れた体を震わせながら必死に最後の矜持を守ろうとする。
こっ…こんなはすじゃなかったのに……
もっと自分が主導権をにぎって少年をリードして喜ばせてあげる。
そう思っていたのに、いざ正樹のそれを受け入れた途端、まるで強烈な媚薬にやられたように体が火照りだし、力が抜けるともう何もできなかったのだ。
ただ、少年の肉欲のされるがままになってしまっていた。
まるで自分が少年の性欲を解消するためだけに存在する従順な肉奴隷になってしまったかのように……
「うっうっ、言ってよ、何がいいの?」
「坊やのが…坊やのがいいのぉ」
飢えた大地が雨水を吸い込むように、魅惑的な大人の美女は少年の欲望の色に染まっていく。
ひくひくと引くつく白い太股が、電気を流されたように痙攣を繰り返し、ロングスカートで隠れた結合部の激しい交じり合いを伝えていた。
それでも少年は追及の手を緩めない、腰をふり美女のお腹の中の肉を貪りながら、その心まで犯していく。
「僕のナニがいいの?」
正樹は自分の手で艶やかな花を開いていく大人の美女の匂いを堪能するように、その顎先にペロペロと舌を這わせ、椅子の上で捻りこむように腰をガクガクと揺らす。
「そっそれは…あっあっ……それは…」
あぁっとまるでピンク色の塊のような息を吐きながら、泪は自分を犯す少年を見つめる。
快楽のために流れる涙で潤んだ瞳の先には、こちらを見つめる少年のまだあどけない顔があった。
線の細い体つきのほんとうにまだ子供……その子供に犯されているのだ。
子供の舌が、自分の顎先から唇の下のホクロをまるで唾液で浸すかのようにベロベロと嘗め上げてくる。
そして、その小さな手は後ろに回され肉付きのいいお尻を掴んで、まるで玩具を扱うかのように左右に引っ張り捻り上げ揉みまわしている。
そしてなにより、自分の膣内をかき回す元気すぎる少年自身。
ぐいぐいっと分け入り、小刻みに動き回りながら、彼女の中心を何度も突き上げるやらしく淫らな……そして何よりも気持ちのいいモノ。
そうとってもとっても気持ちがいい…
それを与えてくれる大切な坊や…
坊やの…
「坊やの……坊やのおち○ちんがいいのぉ」
頬を染め、うねるような栗色の髪に目元を隠した美女はおそらく自分の生涯で口から発したこと無い卑猥で幼稚な言葉を羞恥に震えながら叫ぶ。
「泪さんのスケベ」
そう言うやいなや、正樹はぐいっと泪のお尻を掴みあげた手を激しく上下に振り出す。
「そっそんなぁ、坊やが言わせたんじゃないっ…のぉ…あぁあひぃいい、ひどい…あぁ、気持ちいいぃ、おち○ちんいいのぉ」
一度吹っ切れてしまった美女は、頬を染めて震えながら、それでも自分の大事な坊やが言わせたがっていた言葉を好んで口にする。
まるで、跳ね回るボールを無理やり叩き付けバウンドさせるような粗野で荒々しい手の動きが、ボリュームのあるむっちりしたお尻を上下にふらせ、その奥で膣内に突きいる肉棒を擦あげさせる。
「いいでしょ?ほら?泪さん?」
「はいぃ、いいっ、いいのぉ、おち○ちん、おち○ちん、いいのぉ、おち○ちんがいいですぅう」
そして狂ったように卑猥な言葉を少年に強要される大人の美女。
その体が羞恥にふるえ、自分の声を聞くたびに恥ずかしさのあまり頬を染め、いやいやと顔を左右にふる。
ぐちゅ ぐちゅ ぐちゅ
「泪さん、泪さん、いいっいいよ、あぁ、ねぇもっと腰をふって……あぁぁ」
「ええっ、あっ…わっわかったわ、、坊やが望むなら、あっあっ、何だってしてあげるっ、あぁぁ」
とろんっと堕ちた瞳で快楽に浸る女主人は、少年の肩にのせた手に力を込めると自分から激しく腰をうごかしだしていた。
「あっあっあっいいよ、泪さん」
喘ぐ正樹の顔を見て嬉しそうにする泪さんは、さらに妖艶に肢体をくねらせながら、自ら卑猥な言葉を少年の耳元へ囁きだす。
「んっ…わたしもとってもいいわ…坊やの…おっ、おち○ちん、私の中に全部はいちゃってるのよね、あっあっ、すっすごいっ、坊やのおち○ちんっ」
頬を淫らな色に染めながら泪は、先程のお返しとばかりに正樹の耳元をベロンと嘗めまわし、さらに、んんっと快楽に耐えながら言葉を紡ぎ続ける。
「ほら、私、ぐちゃぐちゃにかき回されてるぅ、んっ、坊やのおち○ちん、ぐちゅぐちゅ動いてるぅ、あぁぁ、お腹の中でバターができちゃう」
そう言いながら、まるでダンスを踊るように捻られるたっぷりとした美女のお尻。
その中で魅惑的すぎる膣肉で溶かされるように嬲られる少年のペニス。
「あぁぁ、もうもう私は坊やのモノよ、だっだからぁ、たっぷりおち○ちんでかきまわしてね、ねっ坊やぁ」
泪は自分でも驚くほど、甘えた声を少年の耳元でだしていた。
さらにニットの上着をたくし上げられた剥き出しの大きなバストを、ふにゅっと形が変わるほど押し付け、ぐいぐいと腰を少年の太股にこすりつけながら肉棒を締めあげてやる。
「ねぇ、坊やいいでしょ?…んふふふ…た〜ぷり可愛いがってくれるわよね…ねぇ」
こんな色気たっぷりの美女にここまでご奉仕されて断れるはずがない。
そして、理性をうしなっている正樹は勿論一も二もなく喜んで答えていた。
「うん、いっぱいいっぱいしてあげるよ」
「ふふふ、嬉しい……あんっ」
そう言いながら泪は少年の耳元から頬へとざらざらした猫舌を丁寧に這わせながら。うっとり目を細め自分を貫くペニスの律動に身を任せる。
喫茶「クリソベリル」の美貌の女主人にして魅惑的な色気をもつ美猫、桐生泪が正樹のモノに堕ちた瞬間だった。
「それじゃそっそく…あっあっう」
もう十分に濡れている泪の体は力が入らないほど上下に激しく揺すられる。
「はひぃ、いいぃ、お腹の中、あぅ、つっ突いてるぅ、坊やがぁ」
羞恥と快楽に頬を染めて嬌声をあげる度に肉欲がさらに速度を加速させる。
正樹はその淫らで美しすぎる美女の媚態に欲望を高めると、ぐいっとそのみごとな曲線を描く腰に手を回し今まで以上に腰を叩き付け出していた。
ずつずっずぅ ぅちゅずちゅぅずゅう
「あぁぁあぁ、泪さん、ほら、もっともっと、あっあっ、気持ちいい、いいよ、いいよ、ほら、ほら、ほら」
「あっあっあっあっ、いいわ、いいのぉ、いい、いい、あっあっあっ」
ずん ずん ずちゅぅ ずん ずんっ ずちゅ
正樹はまるで一気に駆け上がろうとするように腰を掴むと、しゃにむに突きまくる。
その度に正樹の座る椅子がガタガタと激しくゆれ、まるでポルスターガイストの映画のようにその振動で動いていくほどだった。
「あひぃ、ひぃ、ひぃ、いいいぃ…また…そんな激しすぎっ、だめ、お腹の中がぁ、あぁっ」
泪の波打った栗色の髪は艶やかに広がり、まるで脈打つように上下に揺れる。
半開きの口からはピンク色の舌が飛び出し、とろっと快楽の唾液をたらし、むきだしのスケベな形のおっぱいが跳ねまわる。
「あひぃ、ひぃ、坊やのおち○ちん、あぁぁ、あっ奥で奥でぇ」
目の焦点はすでに合わず悦楽に汚染された美女の耳には、ワンテンポおくれて飛び跳ねるボリュームのあるバストと肉同士がぶつかる卑猥な音が響き渡る。
「きっ気持ちいいっ、泪さん」
「すっ……素敵よ、あぁぁ…・んっ」
正樹は腰から手を離すと目の前で暴れ馬のように上下にゆれ汗を飛ばす豊満な果実を両手で揉みしだく。
「あんっ……お胸っ、あぅう、ジンジンするぅ、あぁぁ、おかしくなるわ、坊や、すごいの、すごいぃい」
もう泪に大人の女性の余裕などまったくない。
むしろ経験の少なすぎる彼女は正樹のいいように翻弄され肉を貪られ、性の家畜となりさがっていた。
「うっうっうっ」
正樹のペニスがただ肉欲を満たすだけのために、美女の膣壁をえぐり先走りで染めあげる。
ずゅちゅずちゅずちゅずちゅ
やがて、泪が三度目の軽いエクスタシーに達していたその時、ついに正樹も限界を迎えていた。
「泪さん、僕、もう、出るよおぉお」
「えっ…そっそんな…あぁあぁ……だっだめ、だされちゃったら…でっ…できちゃうぅ」
激しすぎる正樹の腰使いに、フラフラになっている泪は、滑らかな髪をかきあげて必死に意識を集中させる。
すこしでも気を抜けばすぐにでも正樹の愛撫とペニスの抜き差しで意識が飛んでしまいそうだった。
「出したいんだっ、気持ちいい穴にださせて、泪さん」
「あんっ、こっこら、だめよ坊や、中はだっだめ」
小刻みにゆれる美しく秀麗な牝猫の熟れた体。
それに貪りつく中学生の少年。
その股間は根元まで美女の肉穴にはめこまれ、睾丸がぐっともちあがると、いますぐにでも子種を、汗を振り撒き肌をそめる大人の女の成熟された子宮に注ぎ込まんばかりの勢いだった。
だが、年上の美女は残りわずかの理性でそれを押しとどめる。
「そんなぁ、僕、僕、もう我慢できないよぉ」
「ダメなの、あっあぁっ、いいぃ、もっと、突いて、あぁそこ、あぁ」
だが、その理性も肉壁をぐりぐりとこねくり回し、乳首を捻り上げるやらしい攻撃によって急激に失われていく。
ずちゅずちゅ ずずずずぅ
二人の汗がたらたらと混じり合い、泪が激しく下から突かれる度に結合部から愛液がまるで潮を吹いたかのように垂れ落ちる。
「泪さん、泪さん、あぁいつもみたいに出させてぇ…ねぇ」
正樹はもう尿道の先までこみあげてきた射精感に我慢できず必死に腰の上の美女に膣内射精を要求する。
その言葉に泪はびくんっと胸を震わしていた。
「いっ…いつもみたいって…あぁぁ…坊や…まさか、さっ冴子にもいつも中に…あっうぅ」
「うん、毎日たくさん冴子さんのお腹に射精しちゃってるんだっ」
冴子ったらなんてうらやましい…いえ、なんてイケナイことを!
本当に坊やを甘やかせるんだから。
もう、しかたないわね。
冴子が甘やかしちゃってるんだもん。
もう女の人の膣内にザーメンを出すのに病みつきになっちゃてるのね。
「あぁっ泪さん、だからいいでしょ」
「あうぅ…ううぅ、本当に駄々っ子さんなんだから…中に出したいだなんて」
坊やにはかなわないもの…それにいつもやってることを我慢するのは体にも悪いし…
そうよ、坊やのためなんだから。
淫らな言い訳で自分を騙した泪は、正樹の腰の動きにあわせて腰を素早く動かしち○ぽを搾り出す。
「しっ、しかたないわね、今日だけ特別よっっ、坊やのザーメンお姉さんのお腹の中にださせてあげるわ」
そういって泪がそのしなやかな腰をぐいっとひねった瞬間。
「あぁぁぁ、泪さんんんっ」
ビュック ブビュッ ビュック
「あぁぁん、ぼっ…坊やのミルクでてる、あっあっあっ、凄い、あっ熱いわ、ふぁぁぁん」
少年の精液をその子宮で直にうける背筋を反り返らせビクビクと震える淫らな牝猫。
「ううぅ、うっ、うっ、ううぅ、出してるっ、僕、僕、泪さんのお腹の中にだしてるんだぁぁ」
征服欲を刺激された正樹は、しっかりと目の前の熟れた美女にしがみつき、腰を振るわせ膣内射精をし続ける。
「ええ、あぁぁっ、でっ出てる、出てるわよ、あぁっ、お腹の中にあたし、中学生の坊やのザーメン生でだされてるぅうう」
座位で腰をふる美女の胎内にまるで吹き上がるようにドプドプとこってりとした少年のザーメンが注入されていく。
相当じらされたその量は半端ではなく、泪は口をひらき涎の糸を引きながら、何度も何度も精子を受けながら絶頂に駆け上がっていた。
「あっあぁっ……あぁあああぁぁ」
ドクン ドクン ドクッン
やがて、正樹が満足げに腰を引くつかせると、荒い息をつく美女をその腕にしっかり抱き締め、つながった腰のまま嬉しげに囁きかける。
「泪さん、泪さん、泪さんは僕のモノなんだからね」
「あひっ、あっん…当たり前よ、こんなにたっぷり中で出ししちゃって……ほんとにもう、これで私はあなたのモノよ、よろしくね」
ほつれ毛を頬に張りつけた魅惑的な美女は、そのザラッとした舌で少年の頬をぺろっとなめて流れ落ちる汗を拭ってやる。
そんな後戯にふける二人は、仲の良すぎる姉弟のようにぴったり抱き合っていた。
「ごめんなさい、気持ちよすぎて腰が止まんなくて」
「ふぅ、だからって坊や…これは出しすぎよ。これじゃ確実に…」
そう言って視線を下に向けると、泪の長い脚から伝わり落ちた愛液と精液がミックスされた卑猥な汁が足首につけられたロザリオまでべっとりと包み込むように滴っている。
「ごめんなさい」
殊勝に謝って見せるが、いまだに女店主の良く締まる肉壷に根元まで挿入されたペニスはビクビクと脈動し、時折まるで間欠泉が噴出すように尿道にたまっていたゼリーのような濃い精液を美女の胎内に注ぎこんでいる。
「んふぅ……ああん、もう言ってるそばからまたお姉さんのお腹の中に出てるわよ……坊やのザーメン」
「あうぅ、ごめんなさい」
恥ずかしそうに下を向く少年。
泪はそんな様子に猫のように悪戯気に笑うと、愛しい御主人様の鼻先に、ちゅっと甘いキスを一つ上げる。
勿論、その間にも無節操にビクビクとひくつく中学生の肉棒は、熟れた美女の膣内で脈動し残液を噴き上げ続けている。
「あんっ…はぁ…しかたない子ね、じゃあぁお詫びに…そうねぇ」
びゅくびゅくとザーメンまみれにされ種付けされている下半身をぐいっと動かすと、泪は片目をつぶり正樹にしなだれかかるようにして、甘い吐息と共に囁いてやる。
「ふふふふ、これから一生濃〜いミルクを私のお腹の中に注ぎこむこと、いいわね坊や、もちろん出来たての新鮮なミルクよ」
泪はそう言うと、猫のような瞳に濃厚な色気を漂わせるてにこっと笑いけると、肉感的でグラマラスな肢体で呆然としているし少年に抱きつき、そのままカウンターにもつれこむように倒れていく。
「はっ・・・はい勿論…じゃあ早速!」
「あんっあんっあんっ…あぁぁまた出てるうぅ」
喫茶「クリソベリル」の臨時休業はまだまだ長くかかりそうだった。
誤字脱字指摘
9/20 三択様 11/16 あき様 9/20 H2様
ありがとうございました。
9/20 三択様 11/16 あき様 9/20 H2様
ありがとうございました。