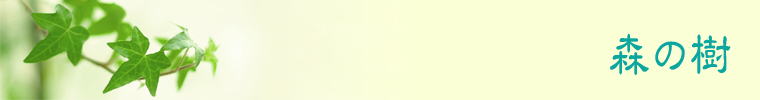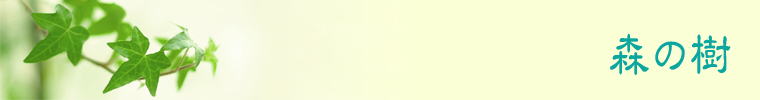|
【空気望遠鏡の歴史】
1608年に眼鏡職人のハンス・リッペルスハイが地上を見る望遠鏡を作った。
1609年にガリレオが凸レンズと凹レンズを組み合わせた望遠鏡(ガリレオ式と呼ばれる)で初めて月や木星などを観察した。その後天体望遠鏡を使った研究が盛んになり、ケプラー式と呼ばれる凸レンズを2枚組み合わせた優れた天体望遠鏡が登場して本格的な観測がはじまった。
1枚のレンズで対物レンズをつくっていたため、色収差が強くあらわれて像が見にくかった。高い倍率ではっきりと観察するには、対物レンズの焦点距離を長くすることが必要だった。本格的な反射望遠鏡が登場するまでの、1600年中ほどから1700年はじめに空気望遠鏡が活躍しました。
版画絵はヘベリウスが使った全長47.5mの歴史上最大の空気望遠鏡。このように巨大化した空気望遠鏡は風の影響などを受けかなり扱いにくかったようです。しかし、宇宙への限りないあこがれと夢がつくり上げた知恵と技術の粋を集めたものでした。
|