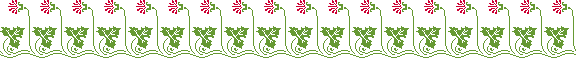
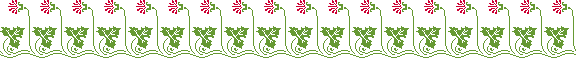
真夏のミラノ。インタビュアーのシニガーリャは、スカラ座のフォアイエから桟敷席への階段を、軽い足取りで上っていくフランコ・コレッリの後姿を見て、ほんとうに80歳!?と感嘆した。コレッリは桟敷席のビロードで覆われた手摺を撫でながら、静かに回想する。
そう、ここから私のアーティストとしての人生が決定的に方向付けられたんだ。スカラ座との愛の物語が始まったんだ。1954年のことだよ。私と同じアンコーナ出身のスポンティーニの『ヴェスタの巫女』が演目で、シーズンのオープニングだった。
私は恐れおののいていた。マリア・カラスが主演で、指揮はアントニオ・ヴォットー、演出はルキノ・ヴィスコンティ。ヴィスコンティが私をリチーニオ役に望んだんだ。その何ヶ月か前にローマの『ノルマ』で私を聴いたのだそうだ。聴覚的より視覚的な面、声より私の容姿が印象的だったらしい。彼は威風堂々としたローマの将軍、グラディエーターを求めていて、そこに私がタイミングよく現れたというわけだ。
幸いにも、私の声も、指揮者のヴォットーのお気に召したんだ。
直ちに彼の好意と指導を、私は享受できるようになった。とても歌手を助けてくれる方だった。私は、彼に特別の感謝を捧げているんだ。
ヴォットーは情熱と寛大さを兼ね備えた音楽家だった。彼のもとで歌うことは、とても気持ちよく素晴らしいことだった。
歌唱に問題があっても、必ず解決してくれた。微笑みながら、潤んだような優しい目で私をじっと見て、指揮台から救いの手を差し伸べてくれた。そして言うんだ。「さあ、コレッリ。気を楽にして」それから音楽再開だ。それは、まるでライオンが突進するような激しさだった。
ヴィスコンティは、ほんとうの意味の「達人」で、とても親切にしてくれた。これ以上望めないほどに。歩き、動き、跪き、身体を使って説明してくれるんだ。ものをつかんで、投げたり。
「ヴェスタの巫女」のリハーサルでの、カラスとの二重唱での演出ぶりのすごかったこと!何度も何度もだめをおされたよ。
私の指先にいたるまで見逃さないんだ。「しっかりと彼女を抱くんだ。」と声を張り上げる。「マリアに触れるんだ、遠慮しないで。彼女の衣裳の襞に指を差し入れて。」それからカラスに向って「いいかい、マリア。今、コレッリと向かい合っているが、君は彼の方に向き、聴衆に背中を見せる。彼が歌っている間は、そうしていなさい。」
そして衣裳のマントといったら!私はシーンに合わせて、5回も着替えたんだ。一番重いのは、やっとのことで肩で支えていた。それでも、さらに苦労しても、さらに学ぶことを誰だって望むだろう。ヴィスコンテイのもとで、どんなにか成長できたことか!後になればなるほど。
その『ヴェスタの巫女』のリハーサルの間に、あなたはアルトゥーロ・トスカニーニと出合ったのですね?
いや、リハーサルの最中ではなかった。終わってからだった。私は歌い終わってから、誰にも会いたくなくて、ひとつの通路に引っ込んだんだ。そうしたら、まさしくそこにトスカニーニがいてね。彼はリハーサルのアシストをしていたのだが、彼も人を避けて、ずっとそこにいたんだ。そこで我々は、はちあわせしたわけだ。
「君はこのオペラのテノールだな。」と、トスカニーニは私を指差して言った。「君の発声法は立派なものだ。それに声のヴォリュームもある。何も変えなくていい。だが、もう少し明暗をつけるようにしなさい。そうして、続けていくのだよ、お若いの。」
悪くないだろう?あの、ちょっと気難しい方に頂いた言葉にしては。とにかく永遠に忘れらない出来事がいくつもあった。
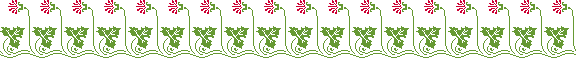
インタビュアーは、コレッリがオペラ界に入る前の、故郷アンコーナでの青春時代に話を向ける。
そう、私の生家は、海から30メートルしか離れてなかった。私の父は、造船所に勤めていたんだ。子どもの頃から、私は船舶関係の技師になることしか考えていなかったよ。
ボートや水泳のチームにも入っていた。測量技師と船舶の機械技師の資格を取って、敗戦後は、アンコーナの市役所の都市復興の部署に勤めていた。しばらくは、海のことも忘れていたくらいだった。
私の家は、空襲で破壊されていた。私は、もっと大きくてもっときれいな家を建て直すんだと、誓ったんだ。歌で稼いで、1958年12月には、その願いをかなえたよ。
私は1946年まで歌を歌ったこともなかった。よく覚えているよ。ある夜、午前1時か2時頃に、何人かの仲間と一緒に街の大通りを大声を歌いながら練り歩いて、通りに面した家の人々を起こしてしまったんだ。まだ、アンコーナが古きよき時代の頃さ。
ある晩、私はピアノの教師のもとを訪ねた。オペラが好きだったからね。そうしてオペラの一節を歌うことを始めたんだ。何人かの友人が「挑戦してみろよ」と言ってくれたが、私は疑心暗鬼だった。私は歌手というものは、生まれながらのものなのだと思っていた。研鑚を積むことによって、声が形成され美が生まれ、鍛えることで、強弱もつけられるようになるなんて、信じられなかったんだ。
とにかく私は、やる気になった。個人的な楽しみのために、週に3回ペーザロの音楽学校に通うようになったんだ。
 アンコーナ港 (2000年6月撮影)
アンコーナ港 (2000年6月撮影)
1950年にフィレンツェ五月音楽祭のコンクールの公示を知って参加することを決めたのも、コレッリにとっては遊びと楽しみだったのですか?
そうだね。友人と無料で旅行する機会があったんだ。偶然と幸運のおかげさ。ある女の子のせいで、私はオーディションにぎりぎりに間に合うはめになったんだ。息を切らせて、気もそぞろで、ヴォーカル・スコアさえ持ってなかった。
「何を歌えるのかね?」 「清きアイーダ!」
皮肉っぽい視線の中で、私はそのまま続けた。お遊びで、失うものは何もなかった。ひどい歌だったよ。私は鼻にもひっかけられないだろうと思っていた。ところが、審査委員たちは、私の歌に好感を抱いてくれた。審査委員長のイルデブラント・ピッツェッティにより、ただちに私に奨学金が授与された。さらば、大学よ!私はテノールになれるし、ならなければいけないと悟ったのさ。
しかしあなたは、『カルメン』の「花の歌」でスポレート音楽院の入学試験に最初失敗しましたね。その1年後、39度の高熱の中参加したオーディションに受かった後に、『アイーダ』を歌ってコンクールで優勝しましたが。
事態はもっと悪くなっても仕方なかった。フィレンツェでの一連のオーディションで、が、「いつか来る自由の日」の代わりにピッツェッティは私に『炎』を歌わせたがっていた。彼が望んだとおりにしたけれど、"Giunto
sul passo estremo"を歌うには、私の声には余裕がなかったんだ。
またもやフィレンツェでの別のオーディションのときだが、私が"Dal mio
cervel…"と歌い始めたら、「"Dal mio cervel" だって?」とシチリアーニが口をはさんだ。「ロマンツァは"Questa
e' Mimi"で始まる。7節前だ!」
「はい、マエストロ。でも、私はそれを知らないんです。」
「よしよし、わかった。それならこうして差し向かいでやっていこう。」
トゥリオ・セラフィンが向こうで微笑んでいた。フランチェスコ・シチリアーニはとても素晴らしい人格者で、驚くべき目利きだった。若者に寛大で、私を助けてくださったんだ。
それから少したって、スポンティーニの『ホーエンシュタウフェンのアニェーゼ』のテノール役があいていると私にもちかけてきてくれた。私はそれを受け、勉強して1週間で準備した。私は偉大な音楽家ではなかったが、なんとかものにしたんだ。いくらかの耳の力で十分だった。あとはすべて幸運の女神の微笑みにまかせたんだ。
幸運の女神、それに反感も厳しい批評も隠さなかった中傷者にも、キャリアの最初からことかきませんでしたね。
ああ、最初のうちからなんと多くの否定的な人物に、私は出会ったことか!
「だめだね。ひどい声だ。」 「この男は、音楽教育を受けたことがないじゃないか。」 「粗野なやつだ。」
うまくいったときには、こんなことを言うオーケストラの指揮者に会うだろう。
「そう、横隔膜のスピントはいい。うん、いい声だ。でも、私はこういった声のヴォリュームに興味はない。君はメッツァ・ヴォーチェができなくてはね。」 「聴いてください、マエストロ。メッツァ・ヴォーチェをお聴かせできます。」 「しかし、デミュニエンドもやってくれなくては。」 「はい、マエストロ。デミュニエンドも出来ます。」
こんな風に生意気に反発して、終わったものさ。でも、私は自分に素質があることに気づいていた。とにかく学ぶことが必須だった。一生懸命だった。根気と謙虚さをもって。
家で私は自分自身にメモを書いて、壁に貼ったものだ。 「フランコ、ばかなことをするな。ハイC、C、C、またCと何時間も繰り返して喉をだめにしたりするな。君を愛する友」
それらは役に立った。一日中、それを繰り返し読んで勉強していた。ああ、私は熱中するあまり、声を酷使する危険を冒していたものだ。それから、当然のことだが、神を信じなければいけない。
偶然、幸運、勉強、信仰ですか・・・。
私は神を信じているし、キリストが私を助けて下さったのだと信じている。私が歌を始める数ヶ月前に亡くなった母とともに・・・。
ローマでリハーサルをしていたときだが、『カルメン』の"liberte'"でハイCを出そうとしたら、声が落ちてしまった。医者に行ったら、「コレッリさん、あなたは1か月声を出してはいけません。しゃべらないで、この薬を飲みなさい。歌うのは、なおいけません。」と言われたんだ。私はそれから最後の日まで静かにしていた。指揮者のオッタヴィオ・ズィーノとローマ歌劇場の監督のカルロ・ラティーニが何を言おうと、まったく口も開かなかった。
いざ歌を再開してみたら、故障の前にそうだったような、新鮮な鍛え上げた声が出たよ。これこそ神の恩寵だと思わないかい?それは忘れられない思い出だ。