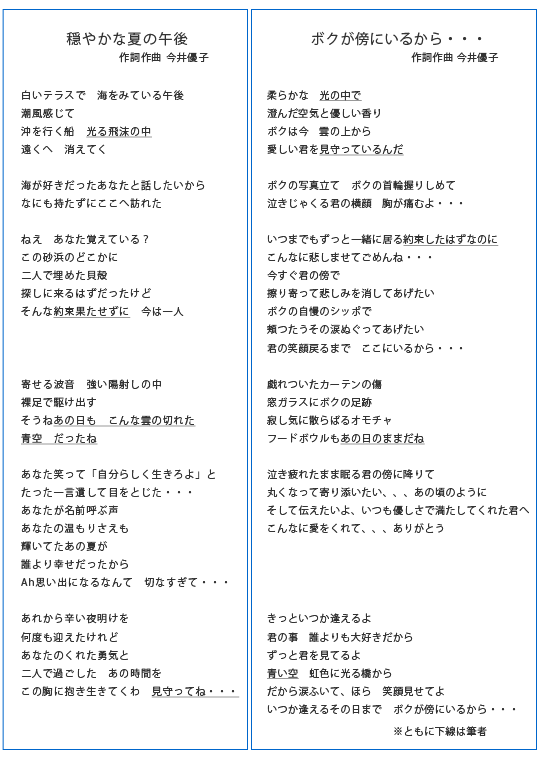�@�܂��A������q������������ʼn�����ɂ����A����䩑R�Ɠ��X���߂�����Ă��邩������܂���B���邢�́A��Ȏq��S�����Đ��J�����o���Ă��邯��ǂ��A�������̎��������ꂸ�ɂЂƂ�ꂵ��ł����邩������܂���B �@�܂��A�y�b�g�͂܂��Ⴍ�Č��C������ǂ��A�O�����ăy�b�g���X�ɂ��Ă̒m���������͎����Ă������ƍl�����ċ��鋰�邱�̃z�[���y�[�W�������ɂȂ��Ă��邩������܂���B �@�����Ȃ����ǂ̂悤�ȏɂ����肾�Ƃ��Ă��A�y�b�g���X�ɂ��Ă̂��S�������A����ɃA�N�Z�X���Ă������������Ƃɂ܂��͊��ӂ������܂��B �@�ȉ��̃G�b�Z�[�́A����������l�����芴���Ă��邱�Ƃ��Â������̂ł��B���N�l���Ă������Ƃ�����A�ŋߋC�Â������Ƃ�����܂��B������ƃy�b�g�̊W���l�����ł��Q�l�ɂȂ�����A������q��r�i�����ȁj�������߂��݂������ꏕ�ƂȂ��Ă���������Α�ς��ꂵ���v���܂��B |
���{�y�b�g���X����@�� �g�c��j |
| �z�[���y�[�W�̃g�b�v�� |
All rights reserved. |
�� �C�U�i�~�A����̎�_�ƂȂ� �@�����ōl���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�C�U�i�~������ɐ�l�̐l�X�����ߎE���Ƃ����قǂ̋����E�ӂ��Ȃ��������̂��ł���B�C�U�i�L�͓�����ɍۂ��āA����̌ˌ��ɂ����郈���c�q���T�J�ɑ傫�ȗ}���ƂȂ������u���ē����ӂ����B���̂��߃C�U�i�L�ƃC�U�i�~�̌𗬂͓r�₦�邱�ƂɂȂ�A������̗��������邱�ƂɂȂ�B �@�C�U�i�~�̓C�U�i�L�̎d�ł��Ɂu���Ȃ�������Ȃ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�A���͂��Ȃ��̍��̐l�X������ɐ�l���ߎE���܂��傤�v�Ƃ����Ė�烂̖����̎E�C��錾����B�ӂ���̕s�a�̂Ƃ�������Đl�Ԃ̓C�U�i�~�ɎE����˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�������ăC�U�i�~�̓{��̋]���ƂȂ��Đl�Ԃ͎��ʂ��ƂɂȂ������A���̃C�U�i�~�̂����͂܂�ō����A�H��Ō����m�炸�̐l�����ɒN�ނƂȂ��E������{��ɖ������ƍߎ҂̂悤�ł���B �@�����ŃC�U�i�~���A
�@��������C�U�i�L�Ɖ������C�U�i�~���≏����Ƃ́A���̐��Ƃ��̐����u�₷�鐢�E�ƂȂ������Ƃ����킵�Ă���B����̓C�U�i�L������̌ˌ���傫�Ȑłӂ����Ō�ʂ��Ւf�������Ƃɂ�邪�A���ꂩ��Ȍ�̓C�U�i�L���A�����Đl�Ԃ����R�ɉ���ɂ͂����Ȃ��Ȃ�̂ł���B �@�_�b�́A���҂Ǝ��҂̂������̈ӎv�̑a�ʂ��f����Č݂��̎��R�Ȍ𗬂��ł��Ȃ��Ȃ����̂́A�l�����҂ƂȂ�������ł͂Ȃ��A�C�U�i�L�ƃC�U�i�~�̗��_�̒��������������ł���ƌ��B�����āA���̒��������̐^�̌����͐��҂̃C�U�i�L�����҂̃C�U�i�~��|��ĐڐG�����ۂ������Ƃɂ��B �@���̂��Ƃ́A���҂Ɛ��O�̂悤�ɉ�b�����Č𗬂������̂ł���A���҂�|��Ȃ����Ƃ��ƌ���Ă���悤�ł���B������������ł́A���҂Ɛ[������肷����Ύ��̐��E�ɑ��ݓ���Ď�荞�܂ꂽ�܂܂��̐��ɖ߂��Ă���Ȃ��Ȃ�댯������Əq�ׂĂ���悤�ɂ��v����B�₳�ꂽ�҂��A���҂ƐS�̋������ǂ��Ƃ��Ă����悢����₤�Ă���悤���B �� �C�U�i�~�����{����킯 �@���ɁA�ł͂Ȃ��C�U�i�~�͓{�����̂��A�C�U�i�~���������{�闝�R�ɂ��Č����Ă݂����B�܂����͐�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���Ă͂����Ȃ��ƔO���������ɂ�������炸�C�U�i�L�͂����j�������Ƃ�����B�Ȃ̃C�U�i�~�́A���̕s�����ȕv�ɕs�M����������ɂ������Ȃ��B�����Ă���ȕv���������Ǝv���Ă��炾�������A���������ɂ��������ɑ��Ă����炾�����o���A�����ɂ��{�����͂��ł���B������{��͂��������Ɍ������Ă������̂����A���ꂪ�ӂ����є��]���ĊO�Ɍ������Ƃ��A�l�����Ȃ��قǂ̑傫�Ȗ\�͓I�ȗ͂�ŎЉ�̔j��҂ɂȂ�̂ł���B �@���́A�C�U�i�L�̎��Ȃ�ʐN���ɂ���Č����ɖ߂邽�߂ɍs���Ă�������̐_�Ƃ̌������f���ꂽ���Ƃ�����B�^���ɏ�ʂ̐_�ɂ��肢���Ă���Ƃ��ɃC�U�i�L�͏���ɕ����ɓ����Ă��Ďז����Ă������̂ł���B�C�U�i�L�̂��̍s�ׂɂ���ďd�v�Ȍ��͂Ԃ���n��̍��ɋA��b�͂��a�Z�ɂȂ��Ă��܂��B���̕s���͑傫���B �@��O�́A���������Ȃ����̂������đ傢�ɒp���������ꂽ���Ƃ�����B�p��������������ɂ́A�����p�����Ԃ��Ɍ������Ă�肽�����̂ł���B�����l�����̂ł���A����̓C�U�i�~�̃C�U�i�L�ւ̕��Q���ƂȂ�B�l�ɒp����������A����͓{��݁A���ɍ��݂ƂȂ�A�Ō�ɂ�
�@���̎��̐_�ƂȂ����C�U�i�~�������������l���ߎE���A�C�U�i�L�͈����ܕS�l��a��������Ƃ����G�s�\�[�h�͐��Ǝ��̋N����������_�b�Ƃ����B����������͉��O���c�������҂����҂����̐��E�Ɉ������荞�����Ƃ���b�ł���A�����ɖ߂�Ȃ��Ȃ������҂�����ƂȂ��Đ��҂ɜ߂�����`�[�t�̌��`�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B �@�����}���ɗ��Ȃ������Ɉ���I�ɗ�����˂������v�A�����ɖ߂鋖���o���Ă���Ȃ���������̏�ʂ̐_�A����ɂ͂����̐��`�K�C�V�m��_�ȂǂƂ����傻�ꂽ�_�ɂȂ��ĕv�Ƃ̒�������ƂȂǂ��d�Ȃ������߁A���ɃC�U�i�~���M��_�ƂȂ��Đl�Ԃ̐�����D���悤�ɂȂ����̂ł���B �@���e�̃C�U�i�L�́A�q�ǂ��̃J�O�c�`�����Ő�E���A��e�̃C�U�i�~����͂�q�ǂ��ł���͂��̖������ȒP�ɑ������悤�ɂ̂nj����������Ă��ߎE���̂ł���B�����ɂ͕����ƂƂ��ɕꌠ��D�ʂƂ���l�������Ď�邱�Ƃ��ł���B�v�w�Ԃ̃g���u���̂�����̋]���҂͏�Ɏq�ǂ��ł���B�l�����Ȃ˂Ȃ�Ȃ����R���Ñ�l�͂��̂悤�ɐl�m�����v�w�̐_�X���N����
�@��l�́A�C�U�i�~���ǂ���������C�U�i�L�����������Ƃ�����B�C�U�i�L�̓C�U�i�~�����₷��B�C�U�i�L�́A���������r�̂ƂȂ������������C�U�i�~�����������|�낵�������ɂ������Ȃ��B������v�ɓ�����ꂽ�Ȃ͑r����������A���̂Ă�ꂽ�Ɗ��������낤�B�������j�Ɏ̂Ă�ꂽ���͕s���ƂȂ�A���݂������{��ɓ]����̂ł���B�C�U�i�~�̓{��̒�ɂ͐[���߂��݂�����B�C�U�i�~�̓{��́A�S�̉��ɔߒQ���h�������тł͂Ȃ��������Ǝv���B�{��҂͏�ɐS�ɔ߈�������Ă���Ƃ݂�ׂ����B�C�U�i�~�͔߂��݂��܂s�����X�g���[�g�ɓ{��ɓ]�ł��Ă���B �@�C�U�i�~�͎v���B�C�U�i�L��A���Ȃ��Əo����Ă܂��������A�Ƃ��ɍ����Y�݁A���܂��܂Ȑ_�X���������A�Ō�ɐl�ނɂƂ��Č����ׂ��炴����Y�ݗ��Ƃ������A�u�Ȃ��Ŏ��͉���ɗ��������B�������Ɍ͂ꂽ���̂��炾������킵���s�Ƃ����Ă��Ȃ��͊������A�|�낵���Ƃ����ċ��₷��B���Ȃ��͎��̏X�����������B���Ȃ��͎��̎�����m�������A����ł��������������Ƃ����̂Ȃ�A���̋����ʂĂ��g�̂����ۂ��Ȃ��łق����B �� �l�����鑼�̃X�g�[���[ �@�ł͂��̕���̏��߂ɋA���ăC�U�i�L������̍���K�ꂽ�Ƃ��A����ꂽ�ʂ�C�U�i�~����a����߂�܂ł��ƂȂ����O�ł����Ƒ҂��Ă�����A�����͂Ȃ�Ȃ��������낤���B�����ōl�����鑼�̃X�g�[���[�W�J�������Ă݂悤�B �@�l�������1�̓W�J�@�C�U�i�L�͒����Ԃɂ킽���ĉ���̌�a�̊O�ő҂����ꂽ���A�ގ����䖝����B���̌�A�C�U�i�~�͖߂��Ă��āA����̐_�Ƃ̌������܂������A�����ɋA���Ă��悢��������������Ƃ��C�U�i�L�ɍ�����B��l�͊�шӋC�������Ēn��ɋA���Ă����A���c������Ƃ�����������B�����Ȃ�Αz������ɁA���̐��͍��Ƃ͑����ς�������̂ƂȂ��Ă���A�����ƏZ�݂₷���Љ�ɂȂ��Ă���B �@�l�������Q�̓W�J�@�C�U�i�L�͊O�Œ����ԑ҂����ꂽ���A��͂�ގ����䖝����B���̌�A�C�U�i�~�͖߂��Ă��邪�A����̐_�Ƃ̌��͐������Ȃ������Ƙb���B�C�U�i�~�͎d���Ȃ�����̍��Ɏc��A�C�U�i�L�͂ЂƂ�₵�������ɋA��B�����ł̂��c������Ƃ̓C�U�i�L�P�Ƃōs���B�C�U�i�L�ƃC�U�i�~�̒��͈����Ȃ��̂ŗ������邱�Ƃ��Ȃ�����̍��̌ˌ���傫�Ȑłӂ������Ƃ����Ȃ��������߁A�l�Ԃ����̐��Ƃ��̐������ł����R�ɍs�������邱�Ƃ��ł���B�j�_�͂��̌���A�Ƃ��ɖ��Ȃ��Ƃ��ǂ��A��������A������肵�Ă���B �@�l�������R�̓W�J�@�C�U�i�L�͂�͂蒷���ԑ҂����ꂽ���A�C�U�i�~�͖߂��Ă��ĉ���̐_�͋A�鋖������Ȃ��������Ƃ�������B�C�U�i�~�͉���̍��Ɏc�邪�A�C�U�i�L�ɂ����ɗ��܂�悤���肷��B�������ꂽ�C�U�i�L�͂��ꂩ�物��̐H�������A����̍��̏Z�l�ƂȂ��ăC�U�i�~�Ɠ�l���ǂ����_�ƂȂ��čK���ɕ�炷�B �@�C�U�i�L�͌����ɖ߂�Ȃ��������߂ɁA���̐��ł̂��c������Ƃ͂��̂܂܂ɂȂ�B����āA���̌�A�����ɖ߂��ă~�\�M�����ăA�}�e���X����������邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�A�}�e���X�̑��̃j�j�M�m����ɂ��V���~�Ղ͂Ȃ��A�I�I�N�j�k�V�獑�_�̎x�z������{���������Â��Ă���B���̂��߁A���E�͑����قȂ������̂ɂȂ�B �@�l�������S�̓W�J�@�����ԑ҂����ꂽ�C�U�i�L�́A�䖝�����ꂸ�a���ɓ����Ă����B�����Ō����C�U�i�~�̕ς��ʂĂ��p�ɋ������A�����������Ȃɂ͂������Ȃ��Ǝv���Ȃ����A���{�̂��߂�����̂ŕ��̂���ɂȂ��ĉ���̍��ɂƂǂ܂�B���̂��ߒn��̍��́A���̂܂ܕ�������Ă��܂��B �@�l�������T�̓W�J�@�C�U�i�~�͂��܂ł����Ă�����̌�a����߂��Ă��Ȃ��̂ŁA�d���Ȃ��C�U�i�L�́A�ЂƂ苕���������ɋA��B�����ł̓�l�̂��c������Ƃ͂��̂܂܂ɂȂ�B���̂�������P���~�\�M�͍s������������Ȃ����A����ȃV���b�N�͎Ȃ������Ǝv����̂ŁA����قǔM�S�ɍs�Ȃ����Ƃ͎v���Ȃ��B����ăA�}�e���X�E�c�N���~�E�X�T�m���̎O�M�q���ǂ����͋^�킵���B����Ƃ̒ʘH��łӂ����ł͂��Ȃ��̂ŁA�s�����Ǝv���s���邪�A���̌�C�U�i�L�̓C�U�i�~�Ƃӂ����щ���Ƃ����������ǂ����͂킩��Ȃ��B �@�����������낤�B���낢��l���Ă݂Ă��d���̂Ȃ����Ƃ��B�Î��L�͍�����X�g�[���[�����c���Ȃ������̂�����B���̉\��������Ƃ��Ă��A����͂��傤�ǃp���������[���h�i���s���E�j�̂悤�ɂǂ����ɕʂ̐��E�������āA���̐��E�Ɠ����ɐi�s���Ă���A�����ɂ͂����ЂƂ�̎���������Ƃ��Ă����݂ɍs�������ł��Ȃ�������A�݂��ɔF�����������Ƃ��Ȃ��̂ł���A����͂Ȃ��ɓ������̂ł���B �� �C�U�i�L�݂̂���E�̃��B�W���� �@���āA���܂ŏq�ׂ��C�U�i�~���k�R�ɖ������Ă����ɃC�U�i�L�ɋN���������ƁA���Ȃ킿�C�U�i�~��ǂ��ĉ���̐��E�֍s���ӂ����ђn��̐��E�ɖ߂�܂ł̂��Ƃ̓C�U�i�L�̌������e�ł��蔒�����̌��Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B�ߒQ�҂͂Ƃ��Ƃ��ĕϐ��ӎ����������A���܂��܂Ȍ��o�▲���l�̌�oneiroide Erlebnisse�ɏP������̂ł���B �@�C�U�i�L�̓C�U�i�~�ւ̒Ǖ�̔O��}�����ꂸ�ɂ��̐��֒T���ɂ����B���҂��ǂ����ɂ���̂ł͂Ȃ����ƒT��������A�ʉe�����߂Ă����炱�����T����邱�Ƃ͓T�^�I�ȔߒQ�s���Ƃ��Ă悭���邱�Ƃł���B�C�U�i�L�̓C�U�i�~�ɉ���ĉ�b�����킵�A�A��߂����Ƃ���B����������Ɏ��s���A�|�낵���ڂɂ����Ƃ����ς�ƒf�O���͂����ĕʂ�������Ă������痧�������Ă������Ƃ���B����͐S���Ŏ��҂Ƃ��킵���Θb�ł���A�ߒQ�҃C�U�i�L�̐S�̕ω��̉ߒ��ł���A�ϖサ�Ȃ��炽�ǂ����r�̋O�ՂƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B �@�C�U�i�~�̎Y��̔엧���������}���������Ƃ̓C�U�i�L�ɂƂ��ė\�z�O�̏o�����������B���̂��߁A�ˑR�̕ʂ�ɂ͖��ĂȎ������Ȃ������B���������e�∫���ɂ����Ȃ܂�Ȃ�����������������c�q���T�J�ʼn��߂ăC�U�i�~�ɗ����̐錾������i�K�ɂȂ��ĐS�̒�����r��������邱�Ƃ��ł����B�͂�����Ɨ��ʂ�`���邱�Ƃɂ���ăC�U�i�~�ւ̒f�O����ӎu�͂����܂����Ƃ�����B �@���̃G�s�\�[�h��\�����Ȃ������ˑR�̎��ʂƂ����O�I�ȑΏۑr������ɋN����A���̌�ɒx��Ă���Ă������I�ȑΏۑr���ɂ���Ď�����e����Ă������v���Z�X�̕\���Ƃ݂�A�C�U�i�L���C�U�i�~�̖������ς܂�����A�C�U�i�~�ɉ���߂ɗ�E�܂ł����Ă킴�킴�����ɂ�錈�ʂ������n���Ƃ����s���ȃX�g�[���[�W�J�����������̐����͂��B�}���̏ꍇ�A���̎������������悤�ɂȂ�܂ň��̎����K�v���B�������������ɂ������Ă����Ƃ��Ă��A�r�҂̓��I���E�ł��̎��o�����܂�Ȃ���Εʂꂪ�K�ꂽ�Ƃ͂����Ȃ��̂��B �@�_�b�̐_�͎������̑c��_�ł���c��ł���B���̑c��̐_�X�͎������q���Ɍ�肩����B���̃C�U�i�L�̉���̍��T�K�̕���́A�l�Ԃ��͂��߂Ƃ��鐶���ɂ͎�������A�ʂꂪ����Ƌ�����B�����Ď��҂Ƃ͉��߂Đ��_�I���ʂ����Č�����}��˂Ȃ�Ȃ��ƌ��B �@�C�U�i�L���C�U�i�~�ɂ����ė�����˂��t�����̂́A���҂Ƃ͈ȑO�Ɠ�����Ԃɂ��ǂ��ĂƂ��ɕ�点�Ȃ����Ƃ�m��������ł���B�C�U�i�L�͎��҂������ɘA��߂����Ƃ͂��͂�ł��Ȃ����Ƃ�������̂ł���B�����ł͎������Ɏ��҂������ɘA��߂����Ƃ͐_�ł��ł��Ȃ����Ƃ�������B�����鐶�����̂́A�ЂƂ��ю��炱�̐��ɖ߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�ǂ�ȂɈ�����Ώۂ����Ă��A���̕�炵���ǂ�ȂɊy�������X�ł������Ƃ��Ă��A�I���̓������邱�Ƃ�c��͎������ɋ�����B�_�b�͂Â��B �� �g�ɂ����������𓊂��̂Ă�C�U�i�L �@�i������j���̂悤�Ȃ��Ƃ��������̂ŁA�C�U�i�L�m��_�́A�u���͂Ȃ�Ƃ悲�ꂽ����킵�����ւ����Ă��܂����̂��낤�B���̂��߂ɐg�𐴂߂�
�@�����炪��n��̍��ɖ߂����C�U�i�L�́A�ւƂւƂɔ��Ă����B�����ō��܂ł̂��Ƃ𐴎Z���悤�Ǝv�������A
�@�������ăC�U�i�L�������鎩�Ȃ̏��L�������Ȃ���̂Ă�Ƃ������炳�܂��܂Ȑ_�����܂��B�~�\�M�̂��߂ɁA�g�ɒ����Ă�������̎��������P���̂Ă�Ƃ�������l�X����삷��\��̐_�X�����܂��̂ł���B����͉�������Ă���̂��낤�B�������͎��������Ȃ��Ǝv���Ă�����̂�A�����݂��Ă�����̂��痣��Đg�y�ɂȂ����Ƃ��A�B��Ă����d�v�Ȑ^���������Ă���Ƃ������ƂȂ̂��낤���B �@�����ɐ��肢�ł��_�X�́A����C�̈ړ��ɂ������_�������B�l���𗤘H��C�H���䂭���Ƃ݂āA���̈��S���C�U�i�L�_�͂����ǂ�̂ł���B�l�͐g�̓I�ɂ����_�I�ɂ������Ă������Ƃ��ł���Η��������Đ����Ă�����B���ɂȂ����C�U�i�L�́A�C�ɓ����Đg��������B �� ���[�j���O�E���[�N�Ƃ��Ẵ~�\�M �i������j�����ɃC�U�i�L�m���͐��ɂ�����ɂȂ�A�u���̏㗬�̐���
�@�C�U�i�L�͒��̗���̂��傤�Ǘǂ����̐��ɂ������đ̂�������B����́A������C�{�͌��������Ă������Ȃ����A�シ���Ă������Ȃ����Ƃ������̂ł���A���ׂ��炭���f�ł����̂��ǂ����Ƃ��q�ׂĂ���B����Ɖ���̍��̂�����≘�ꂩ��Ȃ郄�\�}�K�c�q�m�J�~�ƃI�I�}�K�c�q�m�J�~���n�߂ɐ��܂��B�����͂�������킴�킢�ƂȂ�
�@�_�b�ł̃~�\�M�́A���������ɊC���𗁂тĐg�̂̉����
�@����͕��r�̉ߒ��ɂ����ē����͉���݂�߈�����{���s����|��Ȃǂ̔ے�I�Ȋ���Ǝv�l���N�����łĂ����ɂƂ���邱�Ƃ������Ă���B�l�͂炭�ꂵ���̌�������ƁA����̓l�K�e�B�u�Ȉӎ��Ɏx�z�������̂ł���B����͂܂�������U��Ԃ낤�Ǝ��ȕ��͂��͂��߂�ƁA�����̌��_���_��B��Ă����R���v���b�N�X�Ȃnj������Ȃ����̂��肪�͂��߂Ɉӎ�����邱�ƂɑΉ����Ă���B �@����߂̎��o���Ȃ���A�P��ǐS�̉萶�����Ȃ��B�~�\�M�Ƃ͎��ȏȎ@�Ȃ̂��B�ߋ����ڂ݂Đ��Z���悤�Ƃ���Ƃ��A�g�ɂ��܂����ڂ������Ȃ�悤�Ȃ܂��܂������X���Ǝv������̂��܂����߂ɏo������̂ł���B �@�l�͂킴�킢���~�肩���邱�Ƃɂ���āA�͂��߂Ď��Ȃ��������A����ʓ_���C�����Č��サ�悤�Ƃ����ӗ~���o����̂ł���B���ꂪ�i�I�r�m�J�~�����̏o�����B�l�K�e�B�u�ŕs���a�Ȋ����v�l�ɕ���ꂽ��A������ꖇ�߂�����̉��ɂ������C�����悤�Ƃ��錚�ݓI�Ŕ��W�I�Ȋ����v�l�������B���̓�i�\���̈�A�̐S���I�Ȍo�߂́A�ߒQ�̉ߒ��ŏ�ɂ����邱�Ƃł���B �@���̌�A�C�U�i�L�͂���Ɏ�X�̃~�\�M�����邱�Ƃɂ���āA�_�X���������A�Ō�ɍł��d�v�Ȑ_�ł���A�}�e���X�����O�M�q�ށB�������ăC�U�i�L�̃��[�j���O�͍Ō�ɂ����Ƃ��n���������ĉ��Ă����̂ł���B���̃C�U�i�L�̈�A�̃~�\�M�̃G�s�\�[�h�́A�炭�ꂵ�����ʂ��痧�������čĐ����Ă����K���I�ȐS�̉ߒ����g�I�ɏq�ׂ�����Ƃ��ė������ׂ��Ȃ̂��B�����̐_�͓��Ȃ�_�Ƃ��Ă��ׂĎ������̂Ȃ��ɏh���Ă���B�_�b�͐S���w�ł���A�Î��L�͍ŌÂ̐S���w���ł���Ƃ����Ă悢�B �����̃P�K���Ƃ́A���̃I�\�� �@�����ŃC�U�i�L�̌�`�ɂ��ĐG��Ă������B�C�U�͗U���̈ӂł���A�i�L��
�@�C�̖��A���Ȃ킿���{�l�ɂƂ��Ĕg���̗����Ȃ����₩�ȊC�͐��Ƃƈړ��̖ʂ��玀���I�ɏd�v�ł���B�W�H���Ȃǂ�
�@�C�U�i�L�͉���ɐ悾�����C�U�i�~�ɁA���Ƃ��Ȃ��ō�����n��̍��͂��܂����I���Ă��Ȃ��̂ŁA�߂��Ă��Ăق����Ɨ����A�C�U�i�~�͂������傭�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B������ʂ藝������Ȃ�A��_�̍��삾�������̐��͂��̎��_�Ŗ������̂܂ܓ����o���ꂽ���ƂɂȂ�B�������A�C�U�i�~�Ƃ̗�����A�C�U�i�L�͒P�g�̓Ƃ�_�ƂȂ�A�ЂƂ�~�\�M�����ăA�}�e���X��O�M�q���͂��߂Ƃ��鑽���̐_�X����������B�A�}�e���X��͕����琶�܂ꂽ�q�ƂȂ�B �@���̂��Ƃ̓C�U�i�L�_���A�j�_�ł���Ȃ���~�\�M�ɂ���Ďq���Y�ޕꐫ���l�������̂ł���A����͗�����L�����������_�ƂȂ������Ƃ��Ӗ����Ă���B�������ăC�U�i�L�͂ЂƂ�ŕs������₢���������������E�����������Đl�ނ̑����ł��葾��ƂȂ��Ă����B���̃~�\�M�ɂ́A���̂�������͂炤�Ƃ����I�Ȃ͂��炫�����ł͂Ȃ��A�V���Ȑ����ݏo���n���I�ȗ͂����邱�Ƃ������Ă���B�@ �@�킪���ł̓~�\�M�̓C�U�i�L������̍��Őg�ɂ���
�@�C�U�i�L������قǘT�����Ĉ�ڎU�Œn��ɓ����A�����̂́A�E�Q�����Ǝv�����قǂ̊�@�������������炾�낤�B����قlj����|�������̂ł���B�܂�A����̍��Őg�ɂ������̃P�K���Ƃ������̖̂{���́A���̃I�\���ł͂Ȃ����i���j�B �i���j�y�b�g�̎����|�낵���̂́A�y�b�g���ꂵ��Ŏ���ł������Ƃɋ��|���������ł͂Ȃ��A�����厩�g���������̎q�Ɠ����悤�ɋꂵ��Ŏ���ł����̂ł͂Ȃ����Ƃ������|���萶���Ă��邩�炾�B�y�b�g���X�̃I�\���̒��ɂ́A�����Ɠ����悤�Ɏ����ɂ��������邱�Ƃւ̃I�\���ƕs�����܂܂�Ă���B �@����|��Ċ������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ�����i�^�i�g�X�j�ւ̗U�f��r�����悤�Ƃ���ӎu�������Ƃ������Ƃł���B����͐��i�G���[�X�j�ւ̗~�������i�^�i�g�X�j�ւ̗~���ɂ͂邩�ɑł������Ă��邩�炾�Ƃ�����B�l�Ԃ́A�C�U�i�L�̌������悤�Ƃ���ӎu�ł���A�G���[�X�̗~�������ׂ��炭���^����Ă���B �@���̂��Ƃ���҂́A����|��Ȃ��B���̊�]�������҂́A�C�U�i�~�_�̐M�k�ł��邪�A�l�Ԃ͂܂����̃C�U�i�~�̎��ɂ����Ȃ��~���^����Ă���̂ł��낤�B�l�̐����́A���Ȃ�C�U�i�L�S�Ɠ��Ȃ�C�U�i�~�S�̗��҂̗͓��̑��ǂɂ���Č��肳��Ă����̂��낤�B �@�~�\�M�ɂ͎��ɂ܂��|���s������菜�����ƂƁA������҂�S�������Ռ���炳�\��������̃I�\�����炭��\���y������Ƃ����傫�Ȃ͂��炫�����邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��Ƃ���ł���B�������A�~�\�M�͎�����������ɋ��ۂ��邱�Ƃł͂Ȃ��A��������A���ɗ����������Ă����p�ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B���̂��Ƃ̓~�\�M�̈�A�̍s�ׂ͎��̋��|���������A���ʂ̔߂��݂����z���ĐV���ɂ�݂������Ă������߂̕��r�ɂ�����Đ��Ɍ����Ẵ��[�j���O�E���[�N�i�߈��̍�Ɓj�ł��邱�Ƃ������Ă���B
|
||||||
�� �w鰎u�`�l�`�x�ɂ݂���{�l��
�@���܂��܂ȍГ�̂Ȃ��ł����ʂ͂����Ƃ��傫�ȋ��ЂƂȂ�B�O���I���ɏ����ꂽ�����̐��j�w�O���u�E鰎u�`�l�`�x�ɂ́A�`�l�i���{�l�j�͋ߐe�҂��S���Ȃ�ƁA�r��͑傢�ɋ����������A��̂�y�������̂��Ƃ��イ�̎҂�����ɂ����Đ������~�\�M�̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă���Ə�����Ă���B �@
�@���̋L�q�ɂ���ĎO���I����̌Ñ���{�l���ߐe�҂�
�@���̂悤��
�� �w�Î��L�x�̂Ȃ��̃��[�j���O �@�킪���ɂ�����~�\�M�Ɋւ��錻������ŌÂ̕��ނɑ�����L�ڂ͌Î��L�Ɍ��o����B�����ł��~�\�M�͋ߐe�҂̎��ʂ̌�ɂ����Ȃ��Ă���B�_�b�̒��̃~�\�M�́A��ȑΏۂƂ̕ʂ�̔߈�����̉Ɛ[�����т��Č����B����āA���̌o�߂��ڂ������Ă������Ƃɂ��悤�B �@�j�_�C�U�i�L�m���Ə��_�C�U�i�~�m���͕v�w�ƂȂ��č��݁A���̌㑽���̐_�X�B�������A�C�U�i�~�m���͉̐_�E�J�O�c�`�������A���Ă��A���ꂪ���ƂŎ���ł��܂��B�C�U�i�~�͎q�ǂ��ł���̐_���Ƃƈ��������Ɏ��ʂ̂ł���B����͂����ւ�ے��I�ȏo�����ł���B �@�͂�������̂��Ă��s�����A�����������D���B����C�U�i�~���Ō�ɉ̐_�݁A���̉ɂ���ď�������Ă����Ƃ����G�s�\�[�h�́A�q�݂����o�Y�\�͂��R���s�������Ƃ�\���Ă���B���Ȃ킿�A�����鐶���݂����L�`�̏��_�Ƃ��Ă̖������I�������Ƃ������Ă���A���̌�C�U�i�~�͐��Y�����Ȃ�_���物��̍��������ǂ鎀�̐_�ɕϗe���Ă����B�Ȃ̃C�U�i�~��r�����C�U�i�L�͂ЂƂ�₳��A�[���߂��݂ɏP����B
�@�_�b�ł́A�Ȃ̃C�U�i�~�͕v�̃C�U�i�L����Ɏ���ł��܂��B���̃��`�[�t�͏����͏o�Y�ɔ������S���邱�Ƃ��������������f�����Ă���̂ł��낤�B�����͎q����ŖL�`�������炷���A���ɂ͏�Ɏ��̃��X�N���B�����͒j���������̉e��w�������댯�ȑ��݂Ȃ̂��B�C�U�i�~���̐_���͂�݁A�Y�ݗ��Ƃ����̂��Ɏ��S����Ƃ����G�s�\�[�h�́A�C�U�i�~�����̐_�ƂȂ�v�f���܂�ł���B�C�U�i�~�_���n���������炷��_�ł���ƂƂ��ɉ���̎��_�Ƃ��Ȃ�䂦��ł���B �� �C�U�i�L�̗܂��珗�_�����܂�� �@�C�U�i�L�͔߂��݂̂��܂�C�U�i�~�̈�̖̂��ӂ⑫���Ƃŕ����ɂȂ��ċ��������B���̗܂���ЂƂ�̏��_�����܂��B�i�L�T�����m�_�Ƃ����A�����ɋ������܂̏��_�Ƃ����Ӗ��ł���B�߂������������b�ł���B������r�����C�U�i�L�̗����߂��݂̗܂͐_�X�������A�_�݂̂Ȃ炸������Ώۂ�S�������l�Ԃ��߂���ŗ����܂��������̂ł���B �@���̃i�L�T�����m�_�́A�����ޗnj�
�i���P�j���t�W�� (202)�Ɂu
�@�߂��݂ɂ��ꂽ�C�U�i�L�́A�C�U�i�~�̖S���[���o�_�̍���
�� ���ʂ͓{������� �@���āA�ň��̍Ȃ��q�ǂ��ɎE���ꂽ�Ɗ������C�U�i�L�͎q�ǂ����a��E���Ă��܂��B�J�O�c�`�͕��e�ɂ���ĉ���ɑ�����̂ł���B���̃J�O�c�`�͕�e������ɑ����Ă���B�Î��L�ɂ͎E���̘b�������B���̃C�U�i�L�̎q�E���͍����݂̂Ƃ��A���̗����Ȃ��s���
�@���̃G�s�\�[�h�͎��ʂ��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���A�������{��ނ��Ƃ���Ă���B���̎����͌Î��L�̂Ȃ��Ő_���{����݂����ŏ��̏o�����ł���B�����������ɂ͓{���Ďq�ǂ����E�߂��Ƃ����悤�Ȋ���I�Ȍ��t�͂Ȃ��A�C�U�i�L�͍��̒������āA�J�O�c�`�m�_��
�@���{���I�ł��A���̃V�[���͉��̊���\�����Ȃ��A�C�U�i�L�͒������Ŏq�̃J�O�c�`���a���ĎO�i�i�ꏑ�ɂ͌ܒi�j�ɂ��܂����A�ƂȂ��Ă���B�悯���ɕ|���\���ł���B���{�l�͔ߒQ����������ňÂ�����ȓ{������ƁA�t�Ɋ����}������ʼn��������Ȃ��Ȃ��ĒW�X�Ǝc�s�Ȏd�ł��ɏo�邱�Ƃ�����悤���B �@���̃J�O�c�`�͉̏ے��ł���ƂƂ��ɂ�������̂��Ă��Ėł��s�������̏ے��ł�����B�C�U�i�L�͑n���̐_�ł��萶�̐_�Ƃ��Ė������Ă��s�����ĉ���̐��E�ɗU���̐_���a��E�����Ƃɂ���Ď��i�^�i�g�X�j�ɑ��鐶�i�G���[�X�j�̗D�ʂ悤�Ƃ���B����Ɏq�ǂ����E�߂邱�Ƃɂ���ċ����I�ȕ��e���ƒj�����������̂ł���B�����ɂ͌Ñ�l�̎q�ǂ��ɑ��镃�e��D�ʂƂ��镃���Љ���݂ĂƂ邱�Ƃ��ł���B �� �C�U�i�L�̉���̍��T�K �@���̌�A�C�U�i�L�͐旧���ꂽ�C�U�i�~�ւ̎v��̏��f���������A���ǂ��ĉ���̍��ւ䂭�B�C�U�i�~�����߂����߂ł���B �����ɂ���
�@�C�U�i�L�_�̓C�U�i�~�_�Ɂu
�@�����A�����������̃X�g�[���[�W�J�͂����ɂ���ł���B�C�U�i�L�̓C�U�i�~�̎��ɂЂǂ����h�������ɂȂ��ċ��������B���̌�A��̂��k�R�ɖ������A���̎����Ƃ݂Ȃ����q�ǂ��̃J�O�c�`���Â��������{��ɔC���Ďa��E���B�������A�C�U�i�~�ɉ�����Ɨ~����≩��ɂ����C�U�i�~�Ɖ���Ăӂ���ʂ�̉�b�����킵�ċA���ė��Ăق����ƍÑ�����B�C�U�i�~�̕�������̍��Ŏ��҂Ƃ��Đ����Ă��萶�O�Ɠ��l�̎v�l�Ɗ�{���y�̊���������Â��Ă���̂ł���B���̕s�v�c�Ȍo�܂ɂ��˘f�����̂́A������_�X�̐��E�̂��ƂȂ̂ŁA���������������������肩�Ɣ[�����悤�Ƃ���B �� �C�U�i�~�������ɖ߂�Ȃ����R �@�C�U�i�L�E�C�U�i�~��_�ɂ�鍑���肪���f���ꂽ�����������̓C�U�i�~�̎��ɋ��߂����ł���B���̎��ɂ���ĕ�������~���������ɏI������ƍl����B�������A�_�b�͂����ł͂Ȃ����ɂ����Ƒ傫�ȗ��R������ƌ��B����̓C�U�i�~�ƃC�U�i�L�̗��҂���������Ă���B�C�U�i�~�̌����������B �@�C�U�i�~�́u���Ȃ����������Ȃ����Ƃ��������v�Ƃ����B�v�C�U�i�L����������̍��ɂ��Ď������~�o���Ă���Ȃ��������猻���ɖ߂�Ȃ��Ȃ����A���ꂪ����܂��Ƃ����̂��B����̍��̎ϐ��������H����H�ׂȂ������ɘA��߂��Ă����A�ꂽ�̂ɁA�ƃC�U�i�~�͂Ԃ₭�B �@�C�U�i�L������̍��֍s���x�ꂽ�̂́A�C�U�i�~�̖����̂��ߔ�k�R�܂ŏo��������A�J�O�c�`�����Ŏa��E���Ȃǂ��Ď����₵�����߂������B�C�U�i�~�͌����ɖ߂�Ȃ��ӔC������ȃC�U�i�L�ɕ��킹��̂ł���B����͕v�w�̊ԂŖ�肪�N�������Ƃ��A�u���Ȃ��������̂�I�v�Ƃ����Ă��ׂĂ̐ӔC��v�ɓ]�ł��悤�Ƃ���Ȃ̎p�Ɠ����ł���B�H�~�ɕ����������̐�����E�ϗ͂̂Ȃ����v�̂����Ȃ̂��B�����ł͌����ɖ߂�Ȃ��̂́A���ׂ��炭�v�C�U�i�L�������}���ɗ��Ȃ����߂��Ƃ���Ă���B �@�ł��x�ꂽ�Ƃ͂����A���Ƃ����v���}���ɗ��Ă����������̂́A���ꑽ�����ƂȂ̂ŋA�낤�Ǝv���ƁA���ɃC�U�i�~�̓R�����ƑO�����Ђ�����Ԃ��ċA��ӎu��\������B�킴�킴����܂Œǂ������Ă��邭�炢���̎����v���Ă���Ă���̂��ƍl�������Ė߂낤�Ƃ���̂ł���B�����ɂ͎����ѐ����Ȃ����ω����邽�тɔ��f��ς���C���̕ϒ����₷���g�̂��鏗���C�U
�@����̓C�U�i�~�_�Ƃ����ǂ������ɖ߂�ɂ͉���̐_�̍ى����邱�Ƃ������Ă���B����̍��ɂ͐V���̃C�U�i�~������ʂɂ����ĉ��������_������̂��B���ꂪ�Ȃ�Ƃ����_�Ȃ̂��Î��L�͌��Ȃ����A�C�U�i�L�ɂ��̐_�Ƃ̌���ʂ����Ă͂����Ȃ��Ƃ������������������ŃC�U�i�~�͎����ɂ��ǂ��Ă����i���Q�j�B �@�i���Q�j���҂̍����x�z�����ʂ̐_�ɂ��Ă̓C�U�i�~���A�����ČÎ��L�Ҏ[�҂��ڂ������Ȃ��B�����ł��܂�G�ꂽ���Ȃ��̂́A�B���Ă����������Ƃ����邩��Ȃ̂��낤���B���̐_�͓V�����̓V�_��ɍ����������Ƃ���邪�A���������͒D�����ꂽ�����ɏo�_�ɗ�����Ă��łɑ���ꂽ�y�����ō��_�̃I�I�N�j�k�V�ł͂Ȃ��������B�������A�I�I�N�j�k�V�̌Î��L�_�b�ւ̓o��́A�܂���̂��Ƃł���A�����ŏo�Ă��Ă��܂�����X�g�[���[�ɖ������������Ă��܂��B���̌�A�C�U�i�~�̓����c��_�ƂȂ薻�E�̎�_�ƂȂ��Ă����B�Î��L�_�b�ł́A���̐��̑匠���V�_�ꑰ�̃C�U�i�~�_�������Ă����̂ł���B �� ����Ȃ̔����J����C�U�i�L �@�Ȃ��Ȃ���a����߂�Ȃ��C�U�i�~�ɂ��т��炵���C�U�i�L�́A�҂����ꂸ�Ɍ����̒��ɓ����Ă��܂��B����ɃC�U�i�~������I�Ɍ���ȂƂ����������ŁA���̂��Ƃ��m���킯�ł͂Ȃ������B����Ȃƌ�����ƁA�������Ȃ���̂ł���B������A
�@�����A�T������n��g�e���r��l�b�g�ʐM�Ȃǂ́A���̂قƂ�ǂ��l�Ԃ̐ގ���]�������߂ɑ��݂��Ă���Ƃ����Ă悢���炢�ł���B�l�͐ގ��̂��߂Ȃ�Α���Ȏ��ԂƘJ�͂Ɣ�p��ɂ��܂Ȃ��B���̌����͉͂����낤���B����͍D��S�ł��낤�B�݂���E���킴��E��������̎O���A����͐l�̍s�ׂ��O�C�̃T���ɂȂ��炦���l�Ԃ̋[�������ł��邪�A�����ł͂Ȃ��A�����̗~����̂́A�݂����E���������E�������������������߂�~�]�[���I�Ȑ������ł���B�C�U�i�L�̓����������͈Â������B �@�i������j����ŃC�U�i�L�́A����
�@�C�U�i�L�̐ގ����㒅���������B�����ł̂��������C�U�i�~�̐g�̂ɂ̓E�W�����𗧂ĂĂ͂����A�̂̊e������͎�X�̃J�~�i�����苿���Ă����B�J�~�i���͉���_�ƌ𗬂���p�ł���A���ꂪ�C�U�i�~�̐^�̗e�Ԃ������B �@�Ñ�l�ɂƂ��Ď��Ƃ͏��X�ɑ̂������ʂĂĂ����ߒ��ł���A����͂����܂���������ł������B���͔��������̂��ƒN���������̂��B�r�͕̂����Ă����A���s���ĈُL������E�W���̉a�ƂȂ��Ă����B�C�U�i�~�͐}�炸�����̎������������̂ł���B���̂̎��͈�u�ԂɖK�����̂ł͂Ȃ��A���Ԃ������Ď���ł䂭���Ƃ́A����l�������������ł���B���͓_�ł͂Ȃ��o�߂ł��菙�X�ɐi�s���Ă����v���Z�X�Ȃ̂��B �@�C�U�i�~�̑̒����甭�����闋���͐_�̈ӎu���̂��̂������B�����́u�_�v�́A�u
�@�l�͗��Q�̂���ޏd�v�Ȍ����ɂ́A����̂܂܂̖{�����o����̂ł���B����ȏ�ʂ͐l�Ɍ���ꂽ���Ȃ����낤�B���Ă͂Ȃ�Ȃ����̂����Ă��܂����C�U�i�L�́A���̎p�ɕ|�ꂨ�̂̂��Ă��̏ꂩ�瓦�������Ă��܂��B �@����|��A���̖ڌ��҂ƂȂ邱�Ƃ�������悤�Ƃ���s���́A�قƂ�ǖ{�\�I�Ƃ����Ă悢���낤�B���ւ̕|���V���b�N�̊���͑��҂̎��̖ڌ��ɂ���ċN������̂ł���B���҂̎��ɗ�������Ƃ��玀�̊ϔO�͐��܂��B���l�̊�͐��C�������A�������͉�����炸�A�g�͉̂���������܂ܔ������ɂ��Ȃ��B���̕ώ������̂́A���O�Ƃ͂����炩�ɈႤ���̂ƂȂ�B���̃C���[�W�͑��҂̎r�̂ɂ���Ă����炳���B���͑��҂̎����琶�܂��̂��B����䂦�Ɏ��̖ڌ��́A��ɏq�ׂ��悤�ɋ����n���C�̑Ώۂɂ��Ȃ�̂ł���i�u �y�b�g���P�i�͂炢�j�v�Q�Ɓj�B �� �p���������ꂽ�Ƃ��ċt�シ��C�U�i�~ �@�_�b��������̂́A�܂�����Ȃ��l�Ԃł���B���̐_�b�̐��E�ł͐_�X�͎���������Â��A��{���y��D���̔O�������Đ��҂ɂ��܂��܂ȉe�����y�ڂ��B�_���l�ԂƈقȂ�_��������Ƃ���A�_�͎���ɂ����Ă��S�����R�ɐ��҂ɃA�v���[�`���邱�Ƃ��B�܂������Ă䂭���Ȃ̓��̂��ÂɌ��߂邱�Ƃ��ł���_�ł���B����̈ٗl�Ȏp�������邱�Ƃ�p�Ƃ���̂́A����̎����̗e�p�ɂ������̊���������炾�B �@�_���������̑����́A�l�ԂɂƂ��ėe�ՂɎ�ɓ���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����z�I�ȕ�������ł���B�_�b�̒��̐_�X�̒��l�I�s���́A�������肽���Ɨ~����l�Ԃ̉i���̊�]�����e����Ă���B �@���������Ȃ��������̂�����ꂽ�C�U�i�~�́A�Ђǂ��p���������ꂽ�Ɗ����ăC�U�i�L�ւ̌������{��ށB�u���Ȃ��łˁv�Ƃ��肢�����̂ɁA���̊肢���͂��Ȃ������C�U�i�L�ɃC�U�i�~�͋����G�ӂƕs�M��������A����̏X�������킹�ē�������ǂ�����������B�������A���̋��|�ɂ���ꂽ�C�U�i�L�́A���͂�C�U�i�~���瑫���ɉ������낤�Ƃ���B�������₵�������悤�Ƃ���C�U�i�L�̈ӎu�́A�C�U�i�~�̎��̐��E�ւ̗U�f�ɏ����Ă����B�C�U�i�L�ɂ͒n��̐��E�ɂ��c������ȍ�Ƃ��܂�����̂��B �i������j�����ň�S�ɓ�����C�U�i�L�́A���ɒ����Ă�������
�@���āA�����Ɍ��ꂽ�C�U�i�L�����X�ɒǂ�������
�@�C�U�i�L�͏X���ɎR�u�h�E��^�P�m�R��^���ē������鎞�Ԃ��������B����͂��傤�ǎ��_�ɐH�����������Ď����������ł������L�����Ɖ������͂����Ă���悤�ł���B�܂��A���͂ȉ��R�̕��������ɂ͌��ŐU�蕥���Ď���ϋɓI�ɔr�����悤�Ƃ���B�����͂����Ȃ鎀���������l�Ԃ̎p���̂��̂ł���B�������ɂł��鎀�ւ̑R��͍������_�ɂ��������H�ו�������Ă��@�����Ƃ��Ď������������A����Ď���U�蕥���Ă��������Ȃ��悤���B �i������j�Ō�ɂ́A�Ȃ̃C�U�i�~���g�����ǂ������Ĕ����Ă����B����ŃC�U�i�L�́A��l�œ����قǂ̑傫�Ȋ�������ς��Ă���
�� �C�U�i�~�͂ǂ������������̂� �@�C�U�i�~�́A����̍��̎��삽�������킹�ăC�U�i�L��ǂ������������A���ꂪ�s���ɏI���ƍŌ�Ɏ��炪�C�U�i�L�̌��ǂ������Ă����B��ɃC�U�i�L�́A�C�U�i�~��A��߂����ƌ�ǂ������ĉ���̍��ɓ����Ă��������A���x�͗��҂̗��ꂪ�t�ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B�����ł͐��҂Ǝ��҂��݂��̌�ǂ������Ď����̐��E�ɑ������荞�����Ƃ���B��ǂ��́A�������čs���đ���̎x�z��������ލs�ׂ̂悤���B �@�C�U�i�~�̓C�U�i�L��ǂ������Ăǂ����悤�Ƃ����̂��낤���B���炪�s��Ȏ���ƂȂ����p������ꂽ����ɂ̓^�_�ł͂����Ȃ��Ƃ��ĘA��A����肾�����̂��B�������ăC�U�i�L�������Ɠ��������̒p���ׂ��X���Ȏ��̐��E�Ɉ����������Ƃ����̂��낤���B �@����Ƃ��C�U�i�~�͎��̐��E�ł̐e���������ꂪ�ق��������̂��낤���B�����ɖ߂낤�Ƃ����C�U�i�L�̗U������x�͎悤�Ƃ����C�U�i�~���������A�{���͌����̎��̂悤�Ɏ���̐��E�ł��C�U�i�L�ƂƂ��ɕ�炵�����̂�������Ȃ��B�C�U�i�~�͂����l���Ă���̂ł͂Ȃ����ƃC�U�i�L�͓����Ȃ���ӂƎv���B �@������ƒǂ������Ă���B���肪������ƒǂ����������Ȃ�̂͐_�ɂ��l�ɂ������ɂ����ʂ��铝��I�ȏK���̂悤���B���āA�_�b�ł͂��̐��́A���̒j�����_�̋����ɂ���Ċ���������\�肾�������A���̌�̂���������A�C�U�i�~�̓C�U�i�L�̒n�㐢�E�ɖ߂낤�Ƃ����U��������邱�ƂȂ��A���ǂӂ���͍ŏI�I�ɒ����������ĕʂ�Ă��܂��B���̎��_�œ����̃C�U�i�L�_�̌v��͋����Ă��܂����B �@�C�U�i�L�ƃC�U�i�~�͂��̖��̎����ʂ�݂��ɂ����Ȃ����������B�����Ȃ��Ƃ́A�U���̉��I�ȕ\���ł���B�j���͑��݂̗U�������ɂ���ė������[�܂�A�����܂�Ă����B��_�͂������ď��������W�ɂ��������A�n��E�Ɛ_�X�̑n�������������킯�ł͂Ȃ������B �@�������A��i���������_�ŗ��҂̓R���r���������Ă��ꂼ�ꂪ�Ɛg�̓Ƃ�_�ƂȂ��ĕʁX�̓������ł䂭�B�U���U���邱�Ƃ��Ȃ��ȃ��A�݂�������ɓ����Ȃ��Ȃ����Ƃ����ʂ�Ȃ̂��B���̃G�s�\�[�h�́A��������l�ƕʂꂽ�l�̂��̌�̐��������l���邤���ň�̎�����^����B �@�l�͎��Ȃ̊�����ڂ����Đ����Ă���B���܂ꂩ��莀�ɂ���肵�ē]�����J��Ԃ��Ȃ���o����ς�Ő��E��m���Ă����B�o���͎��Ȃ̊����̕�ƂȂ�B���Ȃ̊����́A�m�b�̊����Ƃ����Ă������̂��낤�B���̊�����������ړI�Ȃ̂��낤�B�����A��ɂ��c�����o����̂ł���B���̂��c���́A�Ƒ���e�����҂ƕʂꂽ���Ƃ͂ЂƂ�ł���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���傹��͎n�߂���ЂƂ�Ȃ̂�����B�@�i�Â��j
|
||||||
�� �l�ԂƓ����̋C���͂炷�P�K�� �@�y�b�g��S�������ߒQ�҂̓��ʂ��玩�R�ɂ킫�N���邠�̎q�̎��ɑ���߂̈ӎ�������B�y�b�g���X�ɂ���Đ�����߂̈ӎ��Ƃ����Ă����̌����͂��܂��܂���B���b�����イ�Ԃ�ɂ��Ȃ��������ƁA���̎q�������ЂƂ�ɂ����ĂȂ�������ɂ������ƁA�a�C�̔������x�ꂽ���ƁA�ǂ���Â������Ȃ��������ƁA���ɗ�����Ȃ��������ƁA�T��������ł��łĂ���B �@������Ƃ��Ă̐ӔC�����イ�Ԃ�ɉʂ������Ƀy�b�g�ɋ�ɂ𖡂�킹�Ď��Ȃ����Ƃ����v��������A�l�̓y�b�g�ɑ��Ĉ������Ƃ������Ƃ����v���ƂƂ��ɐ\���킯�Ȃ��C�����ɏP���Ă����B�\���킯�Ȃ��́A���̔Ƃ����s�ׂɂȂ��ى�����]�n�͂Ȃ��A�����ɗ����x������ӔC�͎��ɂ���ƔF�߂邱�Ƃ��琶�܂��B �@�܂��A��������O�G����Ȃ��y�b�g���}�����A���������̌������s�m���ȂƂ��l�͕|�ꂨ�̂̂�����ƂȂ�A�v�l�͂قƂ�ǒ�~���Ă��܂��B��O�Ƃ��Ă͂��炭���ƂƂ����A���̌����͂��ׂĎ����ɂ���̂ł͂Ǝv���邱�Ƃł���B������y�b�g���s���Ȏ����}�����Ƃ��A�����Ƃ��T��ɂ���҂͂��̂悤�ȋ^�O�������̂��B����������߂̈ӎ��͐��܂��B����ɁA�N�Ⴂ���̎q�͐�Ɏ��ɁA���������������c���Ă��邱�Ƃɂ��߈����͐��܂��B �@���̂悤�Ƀy�b�g�ɂ��킢�����Ȃ��Ƃ����Ă��܂��\���J�����ł����ɗ�������ł���Ƃ����̂��A�y�b�g���X�ߒQ�҂̍߈ӎ��̓���̂悤�Ɏv����B�y�b�g�̎��ɂ���Đ��܂�鎔����̍߈������ǂ̂悤�Ȑ����̂��̂���m�邱�Ƃ́A�y�b�g�Ƃ̕ʂ�ɂ��O���[�t(�ߒQ)�𗝉����邤���ŏd�v�ł���B�����ō߈ӎ��̖����l����ɂ�����A�����������j�I�ɂǂ̂悤�ɍ߂𑨂��Ă������A����ɂ͂��̍߂��ǂ�����č������悤�Ƃ��Ă����̂���T���Ă������Ǝv���B �@���{�ɂ�����`���I�ȍ߂̊ϔO�ɂ��A�q�i������j��Ёi�킴�킢�j�������炷���͍̂߂Ƃ��ꂽ�B����͐l�Ԃ���肾�����Ƃ�����A�a�C�⎀�A����錌���悤�ȃP�K�i�P�K�́A�����ꂪ�ꌹ���Ƃ�����������j�Ƃ������������畗���Q�Ȃǂ̎��R�ЊQ�̂悤�ɐl�Ԃ̐����Ɣɉh��A�ƒ{���܂ޓ����̐���ƔɐB�ɏd��ȋ��Ђ��y�ڂ����̂܂ł���A�������Ж�������炷�Ƃ��č߂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B �@�l�Ԃ������̂Ƃ��ẮA������Љ�K�͂ɂ���Ĕ|���Ă����|�i�����āj�Ƃ���錈�܂莖��j��s�ׂ͍߂Ƃ��ꂽ�B�Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��|(���K�@)��Ƃ����Ƃ��A���l�͋����Ȃ킿�^�u�[�ɐG���|�j��������Ƃ��Ď��͂̐l�X����n���C(�n���G�Ƃ�����)�̎Љ�I���ق����B �@����ɂ͋����̂���̒Ǖ��⑺�����i�ڐG��f�u����l�O���N�g�i�����j���邱�Ɓj���������B�����͂�������ł͍��ʂɂ����邪�A�����E���w�Z�Ȃǂł̃O���[�v����̒Ǖ��△���Ȃǂ̃n���C�͂���B�܂��A�ܕ��i�������́j(�����Ȃ��Ƃ��Ă����o�����i)�Ƃ��č��Y�̖v����̔��Ȃǂ��������B�Ñ㍑�Ɛ������̗��߂ɂ����闥�i�Y�����K��B�Y�@�ɂ�����j�́A���O�̂������ōs���Ă��������̍߂����Ȃ킹�锱���̉e���������Ă���B �@������̌�́A�C�͂�i�C����j���炫�Ă���Ƃ����B�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���A�l�Ԃ⓮���̋C���͂炷���̂�������ł���A�߂Ȃ̂ł���B�C�͂���N���������́A���q�ׂ��悤�ɐl�Ԃɂ����̂�����Ύ��R���ۂ̂��Ƃ�����B�����A��Q����l�Ԃ⓮���́A���ꂪ�ǂ�Ȍ����ł���g�ƐS�͏��Ղ��A���̗��ʂɂ킽���Ĉ��e������̂ł���B �@���̂킴�킢�ƂȂ�߂������r������`���I�Ȏ�Z���P�S�i�n���C�~�\�M�j�ł���A������s�����Ƃɂ��l�Ԃ͐������������������S�Ƃ����{���̐��_�̋P���������ǂ����Ƃ��ł���Ƃ����B���̈Ӗ�����n���C�~�\�M�́A�����I�ȏC�{�@�Ƃ��������łȂ��߂����ꂩ��g����邽�߂̗\�h��ł�������A��Q�����ꍇ�ɂ͏C�����Ă��Ƃ̐���ȏ�Ԃɂ��ǂ����߂̉Z�p�ł��������B �� �n���C�~�\�M�ɐ�������{�l �@���{�_�����P�S�i�ӂ������j�̏@���Ƃ�����B����͐_���̖{�����n���C�ƃ~�\�M�ɂ��邱�Ƃ������̂����A����͓����ɓ��{�l���n���C�ƃ~�\�M�̉e���𑽑�Ɏ������ł��邱�Ƃ������Ă���B���{�l�̂��̂̍l�����⊴�����A����ɂ͓����ς�Љ�ʔO�Ƃ��������̂�����̉������@�Ɏ���܂ŁA�������͒m�炸�m�炸�̂����Ƀn���C�~�\�M�̊ϔO�ɂ��������čs�����Ă���̂ł���B �@��Ɂu�y�b�g�͎�����̕s���⊋����H�ׂĂ����v�i�u�y�b�g�Ɠ����I�ލs�i�O�ҁj�v�Q�Ɓj�Əq�ׂ��B���̂��Ƃ�`���I�Ȑ_���I�����ɂ����Č��A�u�y�b�g�͎�����̍߂�������i�₭�j�������P�i�͂�j������Ă����v�Ƃ����������ɂȂ邾�낤�B���̂悤�ɌÂ�����g���Ă�������\���ɂ��������Ɠ��{�l�̖��ӎ����ǂ��ɂ���̂��Ƃ������ƂƁA�������������Ƃǂ��������Ă������Ƃ��������Ƃ��悭�����Ă���B �@�����ł́u�s���⊋���v���u�߂�������i�₭�j�v�ɑΉ�����B�������͕s�����������炷�s���⊋�����S�����ۂł���A���_�Ǐ�ł��邱�Ƃ͗������Ă���B�������m���Ă��邪�A���̌����͎��Ȃ̊O���ɂ����Đl�Ɉ˂���Ă���߂�����̂悤�Ȃ��̂ł���A�킴�킢�ł���ƌ��Ȃ��Ă����B �@����͎��Ȃ̓����Ő�����X�g���X�́A�O������h���Ƃ��Ă���Ă����X�̗L�Q�ȃX�g���b�T�[�������Ƃ��Ă���Ƃ�������X�g���X���_��n�ōs���悤�Ȕ��z�ł���B�������͐S�g�̕��S�ɂȂ�X�g���b�T�[���ȗ��ɂЂƂ�����ɂ��āu�߂�����v�Ƒ��̂��Ă���B �@�܂��A�u�H�ׂĂ����v���u�P������Ă����v�ɂ����邪�A�s���⊋���Ȃǂ̃l�K�e�B�u�Ȋ�����y�b�g��������̑���ɂȂ��Ď�苎���Ă����Ƃ������̂ł���B�������Đl�̓y�b�g�𗘗p���Ă���̂����A�����Łu����Ɂv�����ƂȂ��Ă���B�y�b�g���l�Ԃ̐g����ɂȂ邱�ƁA���Ȃ킿�y�b�g�̎��㗝���ɂ��Ă͈ȑO�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���i�u�`��̔L�v�Q�Ɓj�B �@�����n���C�Ƃ����A�_�Ђł̐_��i����ʂ��j����ɂ�邨�P����A�z����l�������̂ł͂Ȃ����낤���B����͐_�ɋF�肵�Ė�i�₭��j����������A�C���P���̂��Ă��炢�g�𐴂߂�_���Ƃ��ė�������Ă���B�܂��A����Ə̂��Đ��������ɂ͎��������H�ׂČ��N��������肷��B�������A���Ƃ��Ɛl�X�̊Ԃł̓n���C�E�n���G�͍����Ƃ͂��قȂ�g���������Ă����悤���B���̂��Ƃ����Ă݂悤�B �@��O�\�Z��V�c�E�F����́A�剻�̉��V�̏فi�݂��Ƃ̂�j�\�V�c�������ɏq�ׂ����߂̌��t�B�u�䌾��v�̈Ӂ\�����Q������A���킽�������Ɉȉ��̊�ȏق��Ă���B �@�i������j�v��S�������������A�\�N����\�N���čč�������A�����̏����ł��ł��Ƃ��ɁA���̕v�w�̂��Ƃ��i�N�����j
�@����͍F���V�c�������̖��O�̏�Q���Ė��Ԃł̃n���G���ւ����قł���B�V�c���g�������������v��Ύ��̒ʂ�ł���B
�@�����ł����P���i�͂炦�j�Ƃ́A�������������낤���B�����Ă��̍s�ׂ��֎~�����Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��낤�B�P��ڂ́A�č��E�����Ɍ��炸�j������������ɂ������āA�����m�����҂����i�S����n���G��v�����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������̂ł���B �@����Ȃǂ͂��̒j���ƈȑO������[���W�ɂ������Ƃ��Ă��i�i�˂��j�ݐS���N�����ĕv�w�ƂȂ����҂ւ��₪�点�̂悤�Ƀn���G�����߂Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��낤�B�Ă��������Ă��ĕ������Ƀn���G�𐿋����Ă͂Ȃ�ʂƂ������Ƃ̂悤���B �@���̏ꍇ�A���������l�Ƃ͉����䂩����Ȃ������m�炸�̑��l�ł���A���i�S�͕��ʂ�����Ȃ����낤�B�������A���Đ[�����ł�������A���Q�W������̂ł���A���Âł͂����Ȃ���������Ȃ��B�����ł͎��i�ɔR�����l�Ԃ����Ă̂��Ƃւ̏��i���ȁj���Ƃ��đΉ������߂Ă���悤�Ɏv����B�l�̍K�������i�i�˂��j�ݎ��i���ˁj�ސS���́A�Ñ�l������l�����܂�ς��Ȃ��悤���B �@�Ƃ���ŁA�Î��L�E���{���I�i�ȉ��A�L�I�Ɨ����j�ł́u���i�v�̕������u���͂Ȃ�˂��݁v�Ɠǂ܂��Ă���B�u���͂Ȃ�v�Ƃ́A��Ȃ̂��ƂŁA�{�Ȃ��v�̌�Ȃ⏨�∤�l�Ȃǂ̏����ɑ��Ă˂��ނ��Ƃ��Ӗ����Ă����B�L�I�ɂ͐��Ȃ���Ȃ�ł����߂�b���悭�łĂ���B���i�̐S�́A�j���̏���߂��鏗�̏Ă����������̎n�܂�ł��邱�Ƃ��q�ׂĂ��ċ����[���B�����ł͍F���V�c�́u���͂Ȃ�˂��݁v�Ƃ͏q�ׂĂ��Ȃ��̂ŁA���̂˂��݂͎�ɒj�̂˂��݂ł͂Ȃ����B�@ �@�Q��ڂƂR��ڂ́A�͂��炸�����m��ʎ��l��ڌ����ĂЂǂ��V���b�N���ĐS�����i�����j���ꂽ�Ƃ��āA���҂̋߂����҂Ƀn���G��v������Ƃ������Ƃł��낤�B���⎀�҂͕s��Ȃ̂��B����������I�ȕ\���Ō����A���������Ȃ����̂��������Đ��_�I��ɂ������̂ňԎӗ����x�����Ƃ������Ƃ̂悤�Ɏv����B �@�܂��A�S��ڂƂT��ڂ́A������������ɂ܂��b�ł���B�Ñ�l�ɂƂ��Ă͉�p�����ϐ����Ȃǂ̐H�ɂ������s�ׂ͍����ȏ�Ƀi�C�[�u�Ȏ����������̂��낤���B�S��ڂ͌��m��ʎ҂��Ƃ̑O�ŏ���ɔт𐆂��̂͂�������Ƃ��ƈ��������ė��Ƃ��O������ƌ�������̘b�ł���A�T��ڂɎ����Ă݂͑����H���e���Ɉ������Ƃ��āA��������������Č��Ԃ�����т�悤�Șb�ł���B �@�ȏ�̓V���b�N������A�S����������悤�ȕs���ȑ̌��ɑ���������ꂽ�̂ŁA���ٍ̕ς�����Ƃ����v���ł���悤�Ɏv����B���̗v���҂����́A�u����͕s�g���A�킴�킢���B�������Ŏ��͉��i�����j���ꂽ��Q�҂��B�������܁i�����ȁj���A���i���ȁj���A���f�����͂炦�A����ɉ����悱��!�v�Ƃ��˂Ă���̂ł���B�����A�l�X�̊Ԃł̃n���G�Ƃ͂��̂悤�Ȃ��̂ł������B �@���̂悤�ɐS�������ꂽ�Ƃ����悤�Ȏ��Q�̖R�����Ǝv���鐸�_�I���ۂɑ��Ă����Ȃ������߂邱�Ƃ��J�i���܂��j�ʼn��s���Ă������߁A��͂��̂悤�Ȗ��Ԃł̃n���G���֎~�����ƍl������B�����A�n���C�E�n���G���l�X�̊Ԃł���Ȏg���������Ă�����������́A�n���C�̖{�����������Č����Ă���Ƃ������̂ł���B �� ���b�ɂ݂�n���C �@�u�P���v�̌�́u����v�Ɠ����Ƃ����B�܂��A�������x�����́u�����v�Ƃ��܂��ꌹ�������Ă���Ƃ����i�����a�F���A�Ɠ��{�l�A�p��\�t�B�A���ɁA����26�N�j�B�l�Ԃ⓮���̋C���͂�Ȃ��悤�ɑΏ�����s�����n���C�ł���A�߂��������菜�����Ƃɂ���Ă͂炤�����͂���鑤���㕅��Ȃ��C�𐰂炻���Ƃ����̂��낤�B���̂��Ƃ���n���C�E�n���G�́A�߂�Ƃ����҂֔������Ȃ��邱�Ƃ��Ӗ�������A��X�̌Y���킹��Ӗ������悤�ɂ��Ȃ����B �@���Ƃ��A�����������ɐ��������u���̕���W�v�ɂ���u��˂̍��̉��_�A���сi�����ɂ��j���~�߂����i���Ɓj�v�i����\�Z�A�攪�j�Ƃ������b�ɂ́A���Ԃōs���Ă����n���G�������[������Ă���B����͔�ˁi���݂̊��k���j�̉B�ꗢ�Ŏ����_�Ə̂��Đ_�Ђɑ��H���Đ��т̐l�Ԃ�H�ׂĂ����Ƃ����l�C�̎��ȉ������m���̒j�����s�����Ƃ��A���̉������Ɏ��̂悤�Ȍ����������������Ă���B �@�u���E�E�E��
�@�����łS�C�̉������́A��C�ɂ���i���j��20��قǑł��̂߂��ꂽ��A�R�ɒǕ������B�����ł͑̔��ɂ��n���G�A�����ꂽ�Ёi�₵��j�����ďĂ������n���G�A�R���֒Ǖ�����n���G�̎O�̃n���G�������Ȃ����Ƃɂ���ĎЉ�������Ă���B�܂�A���͕��a�ȓ���������ǂ��Ă���̂ł���B �@���̈������͂��炭���ւ̍ق��́A�W���I�O���ɂł������E�{�V���߂̌Y���Œ�߂�ꂽ��Y�i���傤�����j�Ɨ��Y�ɂ�����B��Y�Ƃ́A�ߐl����i���j���\���Ȃǂ�ł̔��ł���A���Y�i�g�̌Y�j�ł���B �@���߂ł͔Ƃ����߂̏d���ɂ���ď�Z�\��A�\��ȂǂƑł��K�肳��Ă����B�܂��A��Y���y�����̂�⚌Y�i�������j������A����͏���ׂ�⚁i�ނ��j�őłY�������B⚌Y�̓��`�ł��̌Y�Ƃ��Č��݂ł��C�X�����Љ�ł͌Y���Ƃ��čs���Ă���B �@���Y�͔ƍߎ҂��������ꂽ�s�ւȂƂ���֒ǂ����Y���ŁA�ւ�҂ȓy�n�◣���ɗ��l�Ƃ��đ����Ă����B���Y�͓k�Y�i�����̂��Ɓj���d���A���Y���y�������B���{���߂ł́A⚌Y→��Y→�k�Y→���Y→���Y�̂T�i�K������A���̏��ԂŌY���d���Ȃ��Ă����i���� ���{�v�z�̌n�R�A��g���X�A1976�N�A�⒍�i�ؘa�v�j�j�B �@���̉������ɂ͑�Q�i�K�̏�Y�Ƒ�S�i�K�̗��Y�����Y�i�@���ɂ��ƂÂ����Ɏ��I�ɖ\�͓I�Ȑ��ق������邱�ƁB�����`�j�ōs���Ă���A�������x�������Ƃ������玟�͋|��ł��E�����Y�ɂ���Ƌ�����Ă���B�����̌Y�͑��̉������A���Ȃ킿�l�X�ւ̌������߂Ƃ��Ȃ��Ă���B���̂悤�Ȏ��Y���@���̂Ȃ��Љ��@���̋y�Ȃ��Љ�ł���A�Љ�̈ێ��̂��߂ɗL���Ȏ�i�������B �@���̂悤�Ƀn���G�͂��Ƃ��Ɛl�X�̊ԂŎ��������ҊԂ̎��k�ɂ�菞�i���ȁj���ċ��i���x�������Ƃ�������A�����Ƃ��Ď��I�Ȑ��ق������邱�Ƃ��Ӗ����Ă����B�������A���̌セ�����������K���ւ��āA���Ƃ��ꌳ�I�ɔƍ߂��Ǘ����Y��������s�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă������B���ꂪ���ߐ��x�ł���B �@�܂��A���ߍ��Ƃ��x���邽�߂̃C�f�I���M�[���@���s�ׂɏ��i�E���W�����Ă��������̂��_���i���b�_���j�ɂ������P���V��̐_���ƍl������B�킪���̏ꍇ�A�Ñ㍑�Ƃ̐����ɂ�����@�ߏW�ł��闥�߂ƁA�_���V��͕s���s���ł���A�݂��ɕ⊮�������W�ɂ������Ƃ�����B �@�����ɓ��{�l�̐��_�I�x���Ƃ��Ă̎��R�M�ł������_�����V�c���Վ�Ƃ��鍑�Ɛ_���ƂȂ�Ñ㍑�Ƃƌ��т��K�R�����������B���̌��т��́A��������ɋߑ㍑�Ƃ��`�����邳���ɍĂт�݂�����A���̋��łȊW�͑哌���푈�̏I���܂łÂ����ƂɂȂ�B �� �X�T�m���̃~�\�M �@���{���̑̌n�I�@�����ł����߂̐��肩��x��邱�Ə\��N�A�a���l�N�i712�j�ɐ_�w���ɂ��ė��j���̌Î��L���Ҏ[�����B�����ɂ͒�̃X�T�m�����o�̃A�}�e���X�ɐ��X�̈��s���͂��炢���Ƃ���B�_���ł͂��̍߂�V�Í߁i�A�}�c�c�~�j�Ƃ����i��̓I�ȍ߂̏ڍׂ͌�q����j�B�����Ő_�X�͋��c���A�܍߂Ƃ��Ĉȉ��̃n���G���X�T�m���ɂ����Ȃ����Ə�����Ă���B �@�����ɔ��S�݂��b����
�@�����ł̓X�T�m���́A�����̍������܁i�����ȁj�����Ƃ��đ������o�������A�q�Q��点����Ɏ葫�̃c������������Y�����̂��A�V�E���牺�E�̏o�_�̍��֒Ǖ������Ƃ������߂̃n���C����B�������͂��炢�ēV�_�ɂ��ނ��č߂�Ƃ����҂ɂ́A�V���Ƃ��Đ_�X�͂��܂��܂ȌY����^����̂ł���B���̃G�s�\�[�h������A�n���C�E�n���G�͈��s��߂�����ɑ����܁i�����ȁj���Ƃ��ĕ��킳��錵���������ƌ��Ă悢�ł��낤�B �@�����[�����ƂɌÎ��L�w�҂̑q�쌛�i�ɂ��A�_�X���X�T�m���ɍs�킹������q�Q��点����A�����̃c������点��̌Y�͒P�ɒ����̂��߂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�X�T�m�������g�̐S�g�̐�������邽�߂Ɏ{�������̂ł���Ƃ����B�����ɑ̔����s���{���̖ړI��������Ă���B ���E�E�E��颂������A�葫�̒܂������肵���̂́A��������I�]�ڂł����āA�g�ɕ����Ă�����q���g�̂̈ꕔ�ł���颂�܂Ɏ��I�ɓ]�ڂ����߂āA���g�̐�������悤�Ƃ������̂ł���B �@���̓I���_�I��ɂ����̍s�ׂ́A�������͂��炭�߂₯������q�Q�\���{���L�ł͔��ɂȂ��Ă���\�Ɍ��W�����Ď��炪��������A�c���ɏW�߂Ĕ�����点�邱�Ƃɂ���Ď��g�̖{���̐���������Ԃɂ��ǂ����߂̏��u�ł��������Ƃ����B�@���{���I�E�_���E�掵�i�E�ꏑ���ł́A�_�X�͂���ɃX�T�m���̑��i�j�⟵�i�悾��j�ɑ��Ă��P�킹�Ă���B�܂�A���̐_���I�v�l�ł͐g�̓I�ȌY���ɕ�����Ƃ͐g�̂ɜ߂�����߂�����Ƃ����ŋC�����邽�߂̈��̎{�p�̂悤�ȍs�ׂƉ�����Ă����B �@�����őq��̂����u���I�]�ځv�Ƃ́A�g�ɐ��܂������q�i�����j���q�Q��c�����`��Ƃ��Ă��̕��ʂɂ��������邱�Ƃ������B�������ăq�Q��c���ɂ��߂�����������؏�����Ƃ����O�Ȏ�p�̂悤�ȍs�ׂ������B����͂����ꂽ�Ёi�킴�킢�j��g�̂̈ꕔ���Ɉړ������āA���̕a����E�o����Ƃ�����p�I�Ȏ��ÓI�s�ׂƂ����悤�B���Ȃ킿�A�q�Q��c���ɍ߂������w���킹��̂ł���A�����̂̓q�Q��c���ł����āA�������P���Ƃ�Ƃ����l���̓q�Q��c���Ɋ���]�ڂ������z�Ƃ�����B �@�����̃c������鎩�s�I�ȍs�ׂ��X�T�m��������ϋɓI�ɖ]�Ƃ͍l���ɂ������A�X�T�m���̐S��ɑ����čl����A�{�l�ɂ͍߂�Ƃ������Ƃւ̎��o������A�o�̃A�}�e���X�ɑ���Ӎ߂̈ӂ��������̂ŁA���̔��Ȃ̏�ɂ����ĉЁi�킴�킢�j���P�����Ǝ���̐g�������s�ׁA���Ȃ킿�~�\�M���Ď����I�ɐ��炵�߂悤�Ƃ����ƍl������B�~�\�M�́u�g����i���j���v���ꌹ���Ƃ����������邪�A����ɏ]���ΐg�ɂ����߂₯��������Ȏ��ÓI�Ɏ��炻�������ĐS���I�Ȑ���̏�Ԃ����肾���Ă����i�J�^���V�X�j�s�ׂƂ�����B �@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�n���C�͎��̂X��ނɊT�O��敪���邱�Ƃ��ł���B�����́A��̃n���C�̍s�ׂ̂Ȃ��ŏd�����邱�Ƃ�����B
�� �l�ԁE�����W�ɂ�����n���C �@���āA�_�b�����Ñ�Љ�ł̃n���C�����������ɏo���Ă��ꂱ�����Ă������A���̗��R�͌���l�̐l�ԊW�݂̂Ȃ炸�l�ԁE�����W�̂Ȃ��ɂ����炩�ɂ����ƋN���������A���ʂ���������o������ł���B�n���C�Ɠ��{�l�͐[���W�ɂ��邪�A����䂦�Ƀn���C�Ɠ��{�l�y�b�g���D�Ƃ��[���W�ɂ���ƌ�����̂ł���B������E�y�b�g�W�Ɋւ��Č����A����͈ȉ��̎��_�ł�������Ă���B �@���́A�y�b�g�̐��O�̂��ƂƂ��Đ�ɏq�ׂ��悤�ɁA�y�b�g��������̕s���⊋������苎���Ă����n���C�ł���B����͐l���y�b�g�ƕ�炷���R�Ɛ[����������Ă���B�y�b�g�Ƃ���Ɗy�����A�������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ�S�z���������Ă��y�b�g�͂������͂炢�̂ĂĂ����Ƃ������Ƃł���B �@�y�b�g��������𖾂邢�C���ɕς��Č��C�������炵�Ă����ƂȂ�A�킴�킢����菜�����������S�������ǂ��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�A����͂܂��Ƀy�b�g�Ƀ~�\�M�n���C�����Ă�����Ă���Ƃ����b�ɂȂ�B����̓y�b�g�̃}�X�R�b�g���̖��ł�����B�}�X�R�b�g�Ƃ́A������ɍK�^�������炵����A��������Ă����ƐM�����Ă��邽�߂ɁA��ɕێ������肩�킢�������肷��l�`�⓮���������B �@�}�X�R�b�g�̓t�H�[�`�����O�b�Y�i�K������т��ނ��́j�ł���A�댯����g������Ă����아�i�����j�Ȃ̂��B�����E���L�ȂǂƏ̂���y�b�g�͐������}�X�R�b�g�ł���B���̃y�b�g���Ȃ����Ƃ݂Ȃ����Ƃ́A�y�b�g���t�F�e�B�V���ɂ��邱�Ƃł�����i�y�b�g�ƃt�F�e�B�V�Y���i�������q�j�̊W�ɂ��ẮA������߂Ę_����j�B �@���́A�y�b�g�̒��i�Ƃނ�j���ɂ�����n���C�ł���B�y�b�g�����S����ƁA������͖����~���Ȃ��������Ƃ�A���b�����イ�Ԃ�ł��Ȃ��������Ƃɓ��R�̂悤�ɐ\����Ȃ��������A��������߈���������B����琔�X�̕����ڂ������������́A����䂦�܍߈ӎ�����y�b�g�d�ɉΑ����A�⍜�͎���Ɏ����A���čՒd������Ă˂�Ɉ��u����B �@����Ƀy�b�g�̍D���ȐH�ו������������A���܂��܂ȃ������[�O�b�Y���w������B�������Ă����ɂȂ����q�ƂƂ��ɂӂ����ѕ邷�̂ł��邪�A���ɂ͉��N�����\�N���������茳�ɒu���Ă���l������B���̌エ��ɖ������邪�A�����̓y�b�g�ƂƂ��ɓ�����n�������肷��B�܂��A����ɕ~�n������A�����ɑ���B��������āA�܂��߂��ɒu���ĂƂ��ɕ�炷�B �@�����{�͕����ڂ��͂����܂ŁA���Ȃ킿�C������
�@��ʂɑ��V�������莩��ň�e�Ɏ�����킹��Ȃǂ̒����́A���҂̈ԗ�ƒ����̂��߂ɂ����Ȃ���B�r�����q�̗���Ȃ����߁A���̍�����߂邱�Ƃ��ړI�ł���B�������A�����ɂ͂����̍s�ׂ́A�ߒQ�҂��������Ӎ߂�\�������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������B �@�y�b�g�̎��ʎ҂ŁA���̃y�b�g�������Ă��邠�����A���{���ÊŌ�Ȃǂłł������̂��Ƃ͂����Ɗ����Ă��鎔����Ȃ�A�[���߂��݂̒��ɂ����Ă�����݂̊����s���͏��Ȃ��ł��낤�B���̎q�ɂ͂��낢��Ƃ���Ă������̂�����A���̎q�������Ƌ����Ă����ɂ������Ȃ��Ǝv���B�����v����̂ł���A�ߒQ�҂͂���قNj�����������A�[���������Ƃ��Ȃ����������Ă������Ƃ��ł���B �@�������A���O�̉����Â��s�\���������Ɗ����Ă��鎔����ł���A�s���̕����������ƂȂ��Ďc��B���̕s�����͎���̂Ƃނ炢�⋟�{�Ɏ����z����Ē��J�ɂ����Ȃ��Ă����B����̋��{�ւ̌X���́A�����傪���O�ł��Ȃ��������{�̒u������displacement�Ƃ��ĂȂ���A������s���Ȃǂ̏�I��ɂ�⏞����s�ׂƂȂ�B�������Ƃނ炢�́A���҂ւ̒����ƈԗ�̂��߂ɂȂ����ȏ�ɏd�v�Ȍ��p�������炵�Ă���B����͈⑰�̃��[�j���O���[�N�i�r�̍�Ɓj�ɂ͂��炫�A�ߒQ����̗�������ɑ傫����^���Ă���Ƃ����_�ł���B �@��O��������S���Ƃ��Ă͂��炭�n���C�ł���B�y�b�g���X�̌��҂̂Ȃ��ɂ́A�����̓s���Ńy�b�g�������A�����̓s���Ńy�b�g�����Ȃ����Ǝv���l������B�����玩���̂����Ńy�b�g�͎��̂��Ǝv���B���̐l�����́A�y�b�g�̎��ɍۂ��Ď�����������Ď������̎q�����̂Ă��Ƃ��A���������̂悤�ɂ͂炢�̂Ă��Ƃ����v���ɂƂ���Ă��邱�Ƃ������B���͈̏玙���������ė������ޕ�e�̊��o�ɋ߂��Ƃ����邾�낤�B �@���̈���ŁA�₳���l�Ԃ́A������y�b�g�ɐ�Ɏ��Ȃ�邱�Ƃɂ���ĂЂƂ�u���Ă�����Ď������͂炢�̂Ă�ꂽ�悤�ȋC���ɏP������̂ł���B����͈��S��Ȃ����߂�^���Ă��ꂽ��e�Ɍ��̂Ă�ꂽ�q�ǂ��̐S���Ƃ��悭���Ă���B�l�Ԃ͔���哮����O�ɂ���Ƃ��̕�e�ɂ��q�ǂ��ɂ��Ȃ�̂ł���B����䂦���ʂ���ƌ��̂Ă���A���̂Ă�ꂽ���o�Ɋׂ�̂��B����͎�����ɂƂ��ăy�b�g�E����哮���͈����������̎q�ǂ��ł���A�����Ă�����e�̂悤�ł�����Ƃ������`�I�Ȑ���������l���I���݂ƂȂ��Ă��邩��ł���B �@���̂悤�ɔߒQ�҂ɂ́A�y�b�g���͂炢�̂Ă����ƂƁA�y�b�g�ɂ͂炢�̂Ă�ꂽ�Ƃ������҂̂͂炢�̊�����݂����P���i����j�s���Ƃ�����s����Ԃ�����A���ꂪ�y�b�g�r�����̕����s���̈ꕔ���\�����Ă��邱�Ƃ�����B �� �y�b�g�̍��Ղ��������Ƃ��鎔���� �@��l�́A�y�b�g��r��������A�y�b�g�̍��Ղ����ׂď������Ƃ��鎔���傪������ł���B�ߒQ�҂̂Ȃ��ɂ́A�y�b�g�ƕ�炵���̌��𑁂��Y��悤�ƃy�b�g�̐����p���ʐ^�Ȃǂ̎v���o�̕i�����ׂđ��}�ɂ͂炢�̂Ăď�������l������B����͖S�������q�̈�i������ƂЂǂ��߂����炭�Ȃ邩��ł��낤�B�����āA���̎q�ɂ��Ẳ�b����^�u�[�ƂȂ�A�������Ȃ��������̂悤�ɓ���𑗂�̂ł���B �@�������A�������邱�Ƃ͑r�����y�b�g�̑��݂��Ȃ��������Ƃɂ��悤�Ƃ���s�ׂł���B����͂��̎q�����߂��炢�Ȃ��������Ƃɂ��悤�Ƃ��邱�Ƃł�����B���Ƃ��Ƃ��Ȃ������̂�����A���̎q�̐����Ȃ������Ȃ��̂ŁA�߂������Ȃ��͂��Ȃ̂��B����͌������Ȃ��f���̃t�B�������I�ɐ����āA���̑O����Ȃ����킹�čς܂���悤�Ȃ��̂ł���A���������`�Ŏ���۔F���Ă���̂ł���B �@���̎q�������ɐ����Ă����ɂ����������������邱�Ƃ͏��F�ł��Ȃ����Ƃł���B���̌����s�\�Ȏ��g�݂����܂��������Ƃ͂Ȃ��A������͑��Ӄy�b�g�̎��Ƃ����������������������Ă����B�������Ēʏ�͎��Ԍo�߂ƂƂ��ɂ�ނȂ���������e���Ă����̂����A�y�b�g���X���痧�����ꂸ�ɂ���l�Ƃ́A���̌�����F�߂悤�Ƃ����A�r�����q�̑��݂�۔F���Â���̂ł���B �@�܂��A�y�b�g�̑��݂������ɂ͊O�I�Ȍ`�Ղ��Ȃ����ق��ɁA���I�Ȍ`�Ղł��鎔����̋L���̒��ɂ��邠�̎q�₠�̎q�Ƃ̓��X�̕�炵���͂炢�̂Ăď����Ă��܂����Ƃł���B����͎�����̋L���̂Ȃ����炠�̎q����ߏo�����Ƃł���B �@�y�b�g���X�ߒQ�҂��A�Ƃ��Ƃ��Č��u���̎q�Ƃǂ��������Ă��������o���Ă��Ȃ���ł��v�Ƃ��u�y�b�g�̍Ŋ��̗l�q�⎀�S�����Ƃ��̏�Ԃ��ǂ����Ă��v���o���Ȃ��̂ł��v�Ƃ����L���̌����́A���̎��ʂ̏Ռ��������ɑ傫�����������������̂ł���A���̃X�g���X�̋��Ђɑς����Ȃ��Ǝ��画�f�������߂̎�����̈ꎞ�I�ȐS���I�h�q�[�u�ł���B �@�������A���̎q�������ɂ�������炸�A���Ȃ��������Ƃɂ��邱�Ƃ́A�Ђǂ��s���R�ł���A���̂悤�ȐS����Ԃ��ێ����邱�Ƃ́A�������傫�Ȋ����������ď�ɋْ����������Đ����Ă������ƂɂȂ�B���̎q�Ƃ̌o�����������Ƃ��邱�Ƃ́A�����̌o���̈ꕔ���������Ƃ��邱�Ƃł��莩�Ȃ̔ے�ɂ��Ȃ���B���̃A���o�����X�Ȑ��_��Ԃ͂��܂ł��Â����Ƃ͂Ȃ��A�ʏ킱�̋L���̉B���͂��炭�̂̂��A���Ȃ킿�����������S�̏������ł���ɂ�ĂƂ�Ă���B �@�y�b�g���������A�����Ď��Ƃ����Ղ��������Ƃ���S���́A���ʒ���̎����傪���������ꂽ���Ȃ��Ƃ���S�I�h�q�@���ɍ������Ă��邪�A���̌�����̏�Ԃ���������邱�ƂȂ������ɌŒ����Â���Ȃ�A���[�j���O�E�v���Z�X�̐i�s���~�����邱�ƂɂȂ肢���ꂩ�̕a�I�ߒQ��U������v���ƂȂ�B���̎q�̌`�ՂE���������́A���̎q��������������A���������������������Ƃ��邱�Ƃł����āA���̌����ُ̈킳����ߒQ�G�ɂ����蒷���������肵�₷���i���P�j�B �@�i���P�j�y�b�g���X�̉��x���l�̂Ȃ��ɂ́A���́u�����̂ɁA���Ȃ��������Ƃɂ���v�۔F�Ƃ͔��ɁA�u���Ȃ��̂ɁA���邱�Ƃɂ���v�Ƃ��������۔F�ɌŎ����鎀�ʎ҂�����B���̎q�͍��������Ă���A�ǂ����ɂ���ɈႢ�Ȃ��Ƃ������z�������Â��Ă���l�ł���B����͗ՏI�ɗ�����Ȃ�������A��̂�������G�ꂽ�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������l��A�Α������ɎQ�����Ȃ������l�ȂǂɂƂ��ɂ݂���B �@���̂��Ƃ���A��i�����̂܂܂ɂ��Ă����ƖS�������y�b�g�ɂ��܂ł��������Ă��܂��̂ŁA�Ȃ�ׂ��������ׂĂ����������ق���������������Ƃ����̂͗Տ��I���Â��̂Ȃ�����������ł���B���ʒ���A�Փ��I�Ƀy�b�g�̐������v���o�̕i�X�����ׂĂ͂炢�̂ĂĂ��܂��A��X�������l������B���̐l�͕s�K�Ȃ��Ƃɂ���Ȃ�����w�����Ă��܂��̂ł���B��i�̐����́A�r�҂̔ߒQ��Ƃ̐i�s�ɂ��������Ĕ߈��������y�[�X�ɂ��킹�Ė{�l���[�����Ȃ���������i�߂Ă������Ƃ��D�܂����B �� �ߒQ�҂��P�S�i�ӂ������j�}�]�q�Y�� �@��܂́A�y�b�g��r�������ƁA���ȏ����Ƃ��Ă��܂��܂ȃn���C������ɕ��킹����ł���B����͔M�S�ȃy�b�g���D�Ƃ̒��ɂƂ��Ɍ����铹���I�}�]�q�Y���̐S���ƊW���Ă���B������q��S������������̒��ɂ́A���������S�ɂ����Ȃ܂�č߈����������A����Ȏ������������Ƃ��ł����ɂ��邱�Ƃ�����B �@���̂��ߎ��s�I�Ɏ�����Ђǂ��ӂ߂��ĂĎ��Ȕ����J��Ԃ�����A�w�͂��Ă���Ă������������玸�s������Ȃǂ��Ď����ɋ�ɂ�^���Ĕ����悤�Ƃ���̂����A���̍s�ׂɂ����̉����������o���Ă���悤�ȏꍇ�ł���B���̐l�����͔����߂ƍ߈��������ɂ��Ă����Ɩ��ӎ����Ɏv���Ă���A�N������^���Ă���Ȃ����߂Ɏ�����Ă����̂ł���B �@���̎������ߏ�ƂȂ�a���������Ăΐg�̂������鎩���s�ׂƂȂ�B���̂悤�Ɏ�����ߐl�Ƃ��Ĕ����邽�߂Ɏ���ɉߍ��ȘJ������������A���s�ɓ�������A�P�K���������肵�Đg�������ł����̂ł���B����͑O�ɏq�ׂ��X�T�m���������̃q�Q�┯��c��������Ď����ɂ݂��č߂��܁i�����ȁj�������{�I�ȃ}�]�q�Y���s�ׂɌ����Ă���ƍl������B �@���̐g�������s�ׂ��ɒ[�ɍs�����������������̂��A�ӔC������ĕ��l���l�ߕ�����Ď�������̐��ɂ͂炤�n���L���E�ؕ��ł��낤�B�����͎��P�Ȃ̂��B���̂悤�ȃn���C�~�\�M�̊ϔO����Ƃ����P�S�i�ӂ������j�}�]�q�Y���́A�X�T�m���E�R���v���b�N�X�Ƃ�ׂ���{�l�̐[�w�S���ɂ�����ϔO�����̎�̂��Ȃ��ƍl�����A�y�b�g���X�ߒQ�҂݂̂Ȃ炸�A���̂��܂��܂ȔߒQ�̌��҂̂Ȃ��ɂ��F�߂���B �@���ɁA�y�b�g���X�̌�Ɉ����z��������l�̂��Ƃł���B����͋C����ς��ĐS�@��]��蒼�������Ƃ�����������O�����Ȏp���̂悤�ɂ݂���B�܂��A�����̂����炱����ɂ��̎q�̎v���o���c���Ă��邱�Ƃɑς����Ȃ��Ȃ��Ă̓��S���̂悤�ɂ��݂���B�Ȃ��ɂ́A���̎q�̂��Ȃ�����ɖ߂邱�Ƃ����|�ƂȂ��Ă��܂������z��������l������B �@�ǂ̂悤�ȗ��R�ł���A�����͑����Y��悤�Ƃ��ĂƂ����s���ł���B����͂��傤�ǂ��̎q�ƔߒQ����Ƃ������ɒu���ĉƂ��o�Ă����悤�Ȃ��̂ł���B����A�S�������q�ɉƂ𖾂��n���ĉƏo������悤�Ȃ����������B
�@����͂��̏Z�܂��ɔߒQ��u���Ă������Ƃł���A�����ɂ��ׂĂ悤�Ƃ�����̂ł���B����͎�������������̈ӎ����ɓh��ł߂�悤�ɗ}�����邱�Ƃł�����B�����͎�������̓����ł������āA���ƌ����������Ƃ�����Ă����Ԃł���A�����ɂ͌������Ă��Ȃ��B �@����ɁA�ߒQ�҂�����e���Z�܂���X��ǂ���悤�ɏo�Ă����l�q����́A���͂₱���ɏZ��ł͂����Ȃ��Ƃ����֎~������ɉۂ��Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v���邱�Ƃ�����B����͂��傤�ǒ����Ƃ��Ď����ɗ��Y�̍߂��͂炢���킹�Ă���悤�ł�����B����Ɠ������R�ŁA���ʌ�̓��Ă̂Ȃ��������s������l�������ւ̗��߂��ۂ��Ă���悤�Ɏv����̂ł���B����āA���ʂ̔߂��݂̂��Ȃ��A�����z�������悤�Ƃ���l�ɑ��ẮA�炢���Ƃ��������ɓ��݂Ƃǂ܂��ĔߒQ�Ɍ��������悤�������邱�Ƃ��K�v�ł���B �@�܂�����A�����������ăy�b�g���C�t���y����ł͂����Ȃ��Ƃ����茾���߂�����ɕ��킷�����I�ȃn���C������B���̏�Ԃ���������邱�ƂȂ��Â��A���̐l�͓�x�ƃy�b�g�ƕ�炷���Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�B����ɂ́A�y�b�g�ƂƂ��ɐ����������Ƃւ̔����y�b�g���X�̋ꂵ�݂��ƂƂ炦��l�ł���A�Ȍ�̓y�b�g���������Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B �@���̂悤�Ȑl�������ߎ��A����������Ă��邪�A�����͂��������ɂ͎��̌o�߂Ƃ͊W�Ȃ����N�����\�N�ɂ��킽���ăy�b�g���X�̔ߒQ���獡����������Ă��Ȃ��l�����ł���B�킪���ɂ����Ă������N�ɂ킽�薈�N���̎��瓪�����������Ă���̂́A���̐l�����������Ă��邽�߂ƍl������(���Q�j�B �@�i���Q�j���{�y�b�g�t�[�h����E�S�����L������Ԓ����ɂ��A2019�N10�����݁A�S���̌��̎��瓪���͖�879��7000���i���v�l�j�ł���A�O�N�i2018�N�j�ɔ�ז�10��6000���̌����ƂȂ��Ă���B�܂��A�����������Ă��Ȃ�954�l�ɁA��������Ȃ����R���������i���̎���j�Q�v���j�ł́A17���ڂ̂����A�u�ʂꂪ�炢����v����Ȃ��Ɠ������l��2�ʁA�u���ʂƂ��킢����������v��5�ʁA�u�ȑO�����Ă����y�b�g��S�������V���b�N���܂��A�����Ă��Ȃ�����v��9�ʂƁA��������y�b�g���X�ɂ�����闝�R���������l�����ɑ����Ƃ������ʂɂȂ��Ă���B�ƒ댢�̎��瓪���́A2011�N��1193��6000�������ɖ��N����Â��Ă���A����8�N�Ԃ�313��9000�����܂茸�����Ă���B����͕��ς���Έ�N�ɖ�39�������������Ă���v�Z�ɂȂ�B���̖��N�̌��̌������A�����ł��Ď~�܂�̂��M�҂͒������Ă��邪�A���N�������͎~�܂�Ȃ������B �� �P���i����j�����ɋꂵ�ޔߒQ�� �@��Z�́A��͂�y�b�g�̎���̂��ƂƂ��āA�ߒQ�҂����͂̐l�X�ƗV�����邱�Ƃɂ���ČǗ����a�O�������Ȃǂ��ďW�c��Љ��s�i�������j�����Ēǂ����Ă���悤�ɂ͂������ł���B����ɂ̓y�b�g�Ƃ̕ʂ���_�@�Ƀy�b�g���ԂƂ̂��������Ȃ��Ȃ�����A�O�o������ƂȂ��Ĉ����������Ă����Ȃǂ��ĎЉ�Ƃ̐ړ_�������Ă䂭���ƂƊW���Ă���B���̃y�b�g���ʌ�̎Љ�I�Ђ����������̌Y���̘_�����猩�ĉƂł��ƂȂ����������Ă���悤����ɓk�Y�i�����j�̔���^���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B �@���̂��ƂɊ֘A���Ă����Ƃ��C�����˂Ȃ�Ȃ��̂́A�ߒQ�҂��y�b�g�̎��ɂ���Ă��̐��Ɏ�����Ȃ��~�߂Ă������̂��Ȃ��Ȃ����Ɗ����Đ������]���������Ƃł���B�����āA���̐����炠�̐��ɒǂ������Ă����悤�Ɍ�ǂ���������ł���B���̂��Ƃ͂Ƃ��Ƀy�b�g�Ɛ[�����т��Ă��邪�A���Ƃ̊W���ƂȂ��Ă���y�b�g���D�Ƃɂ����邱�Ƃł���B�����͎����s�v�Ȃ��������ɂ��邱�Ƃł��邪�A���̐S���͂�͂�߈ӎ����玩����ߐl�Ƃ��Ď��Y�ɏ����Ă���Ǝv����̂ł���B �@���̎q�̑��݂��L������������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ킩�����Ƃ��A�L����ێ����鎩�Ȃ̑��݂�S���҂ɂ��悤�Ƃ���̂��B���̎q�̑��݂����������Ƃ�����]�́A���̌㎩���ɕԂ��Ă��Ď����̑��݂�����������]�ɕς���Ă����B�y�b�g�Ƌ������ꉻ���Ă��鎔����ł���A�y�b�g�̑��݂�������ɂƂ��Ȃ��Ă����������Ȃ̑��݂��������Ƃ���̂ł���B �@�����͂��̐��ɂ����鎩�Ȃ̑��݂E�������Ƃ�����]�ł���A���Ȃ̊l���������ׂĂ̋L�����������Ƃ�����]�ł�����B���̂悤�ȋ�����]�Ɏ������̂́A���ɂ����Ȃ�قǔ�剻�����߈����̂䂦���B�����͎�������̐��֔ƍߎ҂Ƃ��ė����ő�̃n���C�Ƃ����Ă悢�B �@�����đ掵�́A���̔ߒQ�҂̍߈����╪���s�������}������������ɐ����ɐU��͂���ĉ������Ă������̃n���C�ł���B����ȑr�ł���A���Ԍo�߂ƂƂ��ɔ߂��݂�߈��������݂̔O���������Ƃ����������Ă����B����͔ߒQ�����������P���̂Ă��Ă�����ԂƂ�����B �@�������ߒQ�҂́A���̔߂����ꂵ����Ԃ���ꍏ�������̂��ꂽ���Ǝv�����ʁA�S�������y�b�g�̂��Ƃ������ĖY��Ă͂����Ȃ��Ƃ����v�����͂��炭�B�����ɂ͂��̎q�̂��Ƃ��ߋ��̂��ƂƂ��Ă������Ƃւ̒�R��������A�Y��Ă������Ƃւ̕s���i�Y�p�s���j������B���̎q�̂��Ƃ��߂��������o�����Ƃ��Ď̂ċ����Đ�ɐi�ނ��Ƃւ̕s���ł���B������͂��̂炢�̌���Y��Ă��܂������Ƃ����v���ƁA���̎q�̂��Ƃ����܂ł��v���Â��Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����̈قȂ�S��ɂ����Ȃ܂��̂ł���B �@�܂��A�ߒQ�҂͑�����������E���Ċy�ɂȂ肽���Ǝv������A�����ɔ���^���悤�Ƃ���_���炻���ȒP�ɗ��������Ċy�ɂȂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����S�����͂��炭�B�r�҂͂����݂̌��ɑ������銴��̔��݂ƂȂ��ċꂵ�ނ��Ƃ�����B �@���̗����l����������A���r�o�����g�ȏ�Ԃ͏�Ɋ����ނ��A���̂悤�Ȕ߈��̉ߒ��ɂ����Ă炭�s���Ȋ�����͂炢�̂ĂĂ������Ƃɔ����P���i����j�����ƌĂׂ镪�������i�ʂ�ɔ��������j������A�y�b�g���X�ߒQ�҂̗�������ɏ��Ȃ��炸�e����^���Ă���B �@�y�b�g���X�̃O���[�t�P�A�̖ړI�́A�����̕ʂ�ɔ����Đ����邠����l�K�e�B�u�ŃA���r�o�����g�i�����I�j�Ȏv�l�Ɗ����������A�y�b�g�ƂƂ��ɕ�炵�����Ƃ���тƊ��ӂ̔O�ɂ܂ꂽ�|�W�e�B�u�Ȏv�l�Ɗ���ɂȂ��悤�x�����邱�Ƃł���B�ߒQ�̌����o�邱�Ƃɂ���Đl�͑��҂̒ɂ݂�m�莩�ȗ�����[�߂Ă������Ƃ��ł���B���̂��߂ɂ́A���̃n���C�̐S���𗝉����邱�Ƃ����߂��Ă���B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�y�b�g���������Ƃ�������̂Ȃ��ɂ́A�����̎q�͎���Ƒ��̕a�C��Ёi�킴�킢�j�����Ɏ����Ă����Ă��ꂽ�ƍl����l������B�y�b�g��������₻�̉Ƒ��̕s�K�������肵�Ă��ꂽ�̂��Ƃ����B �@�܂��A�Ƒ�����͂̐l���y�b�g���a���⎖�̎�����������ɁA�u���̎q�͂��Ȃ��̈����Ƃ���������đS�������Ă����Ă��ꂽ�̂�v�Ƃ����ĂȂ����߂̌��t�Ƃ��邱�Ƃ�����B������͂���������ƁA������y�b�g�͎��̐g����ƂȂ��Ė{���Ɏ���ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�����̑���ɂ��̎q�����ʁB���̂Ȃ��̈������̂����炢�Ă��̎q�͎��ʁB�{���ł���A����Ƒ����a�C�⎖�̂Ŏ��ʂƂ�������̎q�͎���Ƒ��ɂȂ�����Ď��̂��ƁE�E�B���̂悤�Șb�͕M�҂��Ƃ����莨�ɂ���B �@�������A����ɂ��Ă��s���Ȃ̂́A�y�b�g��l�̐g����ɗ��ĂĎ��Ȃ���Ƃ����q��Ƃ͂������������z���ǂ����ăy�b�g�̎��ʎ҂₻�̎��ӂɐ��܂��̂��Ƃ����_�ł���B�y�b�g���X�ߒQ�҂Ƃ��̎��͂̐l���A���̂悤�ȍl��������悤�ɂȂ����������ǂ��Ă䂭�ƁA���{�_���́u�`��i��������j�v�̎v�z�ɂ��ǂ蒅���Ǝv����B �@�`��́A�l�`�i�ЂƂ����j�A�����i�Ȃł��́j�Ƃ����������̈�Ƃ����B�_���̋V���▯�ԐM�ł́A�߂₯�������菜���Ƃ��A�l�̑���ƂȂ�l�`��ߗނȂǂɍ߂�������z�������Ă������Ƃɂ���Ă킴�킢���P�i�͂�j���̂Ă邱�Ƃ��ł���ƐM�����Ă���A���̐g����ɂȂ���̂��`��Ƃ����i���P�j �@�i���P�j���̌`��̌��^������ɋ��߂�Ƃ���A����͓ꕶ����̓y��Ɏ���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�y��͉��̂��߂ɍ��ꂽ�̂��B�y��ɂ̓N�}��C�m�V�V��C�k�Ȃǂ̓��������Ȃ胊�A���ɑ��`�������̂����邪�A���̑����͂��̐��Ɏ��݂���Ƃ͎v���Ȃ��ٗl�Ȏp�Ƀf�t�H�������ꂽ���������ł���B�����ɂ͓��[�Ə����킪�����\�����傫���A���̐��ʂ̒����ɂ͏c�ɔD�P�����v�킹�鐳�������`����Ă���B����ŏ����Ƃ킩�邪�A���̒����̐��͎��S�����D�w����َ������o�����߂ɐ����Ղ��Ƃ�����������B����珗���y��͊��S�Ȍ`�ŏo�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A�K�����炾�̂ǂ�������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���y��͌̈ӂɔj��đ���ꂽ�ƍl�����Ă���B���̓D�l�`��g����̏��_�Ƃ�����A���_�Ƃ��Ĉ��Y��a�C������L�����F�O���Ă����ƍl������B �@�����w�̐܌��M�v�́A�`��i�����j���u�l�Ԃ��q�i�����j���w�����ĉ�(��)���Ă������́v�ƒ[�I�ɒ�`���Ă���(�ЂȍՂ�̘b�A�܌��M�v�S�W3���A�������_�ЁA���a41�N�A51��.)�B�����ł����u�����v�ɂ́A������ƂƂ��ɂ��̐��Ɏ����Ă����Ă������́A�Ƃ����Ӗ�����܂�ł���ƍl���č����x���Ȃ��낤�B �@�Â��͉A�z�t�����Ől�̂̌`��͂����q�g�K�^�����A�����g�̂̊����Ȃǂɕ��i�ȁj�łā\����ŁA�i�f���m�Ƃ����\�����������q�g�K�^�Ɉڍs�������̂��͐�ɗ�������Ă����肵�Ă�������P�����B����͎����̐g����ƂȂ镪�g�����A���̑�֕��ɐG��邱�Ƃɂ���č߂������������ɓ]�ʂ����Ď���̖�i�₭�j�𗎂��Ƃ����s�ׂł���B �@����͋�����p�Ƃ�������p�Ƃ����i�t���[�U�[���A���c����Y���A�}�����}�сA�������ЁA1994.�j�A�O�������ė��Đl�ԂɂƂ�����������킴�킢���`��ɂȂ�����Ĉړ������邱�Ƃɂ���Ď�菜���Ƃ������ÓI��������܂Ŏp����Ă���߂�����̃J�^���V�X�i�@�j�ł���i���Q�j�B�@ �@�i��2�j�J�^���V�Xcatharsis�́A�M���V����̏A�r�����Ӗ�����Ñ�M���V���̏@���I��w�I�T�O�ł���B�v���g���́w�p�C�h���x�̒��Łu�i�J�^���V�X�j�Ƃ́A���E�E�E�������ł��邾�����̂��炫�藣���A�����āA�������̂̂����镔�����玩�����g�ւƏW�����A���W���āA����Γ��̂̔��i���܂��j�߂���������A���݂��A�������A�ł��邾�������Ɏ��������ɂȂ��Đ�����悤�ɍ����K���Â��邱�Ƃ��Ӗ�����̂ł͂Ȃ������E�E�E���܂荰�̓��̂���̉���Ɨ��E���A���ƌĂ����̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂĂ��� (�p�C�h���\���ɂ��āA�v���g���T���E�̖����U�A�������_�ЁA���a41�N�A507��.)�B�v���g���ɂƂ��ẴJ�^���V�X�Ƃ́A�������̂̑������犮�S�ɉ������邱�Ƃł���A����͓��̂̎��ɂ���ē�������̂������悤�ł���B �@�`��ƂȂ���̂́A�l��l�̎�������͂������̂���łȂ��A���E�n�E���E���Ȃǂ�����z�Ŗ͂������̂��g��ꂽ�B����ɂ͓�����͂������肩�A���������ɐ������������`��Ɏg���邱�Ƃ��������i���R�j�B �@�i��3�j�Î��L�ɂ̓��}�^�m�I���`�ɖ��N�����̖������������b��A�r�ꂽ�C����߂邽�߂ɊC�ɔ�э���ł���Ԃ�_�ɐg������ă��}�g�^�P�����������I�g�^�`�o�i�q���Ȃǂ̋]���̘b������B�����͐_�̓{�����߂邽�߂ɎႢ������q�ǂ���_�ɕ�����l�g���V�̕��K�����Ă��������Ƃ������Ă���B���̂悤�Ȕ��ȍs�ׂ���߂Đl�Ԃ̑���ɐl�̌`��͂����l�`�⓮����p����悤�ɂȂ����ƍl������B�_�ւ̕������̂Ƃ��Đl�g�䋟�̑���ɓ�����p���锭�z�͓����̋[�l���ɑ��Ȃ�Ȃ��B�̂����������͐l�̐g����ł���B �@�����������ɍ߂킹��Ƃ����A�����͂܂��A�Ñテ�_���̃X�P�[�v�S�[�g�i�܍߂̃��M�j�̘b�����v�������ׂ�B����͐̃��_���ł́A�܍ߓ��Ȃ���̂�����A���̓��ɂȂ�Ɛl�X�͔Ƃ����߂�̃��M�ɕ��킹�������r��ɕ��Ƃ����@���V�����s�����B �@�l�Ԃ̍߂���g�ɔw�������]���b�̃��M�͂��̌�A�r��Ŗ삽�ꎀ�ɂ��邩�A�ߐH�����ɐH��ꂽ�ł��낤�B�������ĕ����̐l�X������������̍߂́A���M�̂����ɒu���������邱�ƂŐl�X�̍߂͏��ł���̂ł���B�������g�������l�̖ōߖ@�͐��E�e�n�ɂ��邪�A���̂悤�ȕ��@�ŔƂ����߂�������ƍl�����l�ԂƂ́A�ǂ��܂ōߐ[���������Ȃ̂��낤���Ǝv���B �� �K���]�ڂƌ`��]�� �@���č����A������y�b�g�̎�����̓y�b�g�Ǝ��ȓ��ꉻ���Ă��邽�߂ɁA�y�b�g��������̈ꕔ���ɂ��Ȃ��Ă���B������̈ꕔ�Ƀy�b�g���Ȃ�Ƃ́A�قȂ�A���ł����Ă��ڂ�������Γ�̎�͂���������̂ƂȂ��Đ����Ă����悤�ɁA������̐g�̂ƃy�b�g�̐g�̂��ڍ����ăy�b�g��������̂��炾�̈ꕔ�ɂȂ��Ă���悤�Ȋ��o�ł���B����͗��҂͈����Ƃ������͂Ȑڒ��܂ɂ���Č݂��ɐ[�����т��Ă��邱�Ƃ��V���{���b�N�ɏq�ׂ����̂ł���B �@���̂悤�ȐS����Ԃɂ��鎔���傾����y�b�g�̐H�~��������A�S�z���玩��̐H�~�������A�������a�C�ɂȂ�A�y�b�g�̕��������a�C�ɂ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����s��������B����͈�ʐl���猩��Δ��I�ōr�����m�ȕs�������A������ɂƂ��Ă͈Ӗ��̂���d��ȕs���ƂȂ�B �@����͗Ⴆ�Ă݂�A������̐g�̂ɂł����K���זE���y�b�g�̐g�̂ɑ��₩�ɓ]�ڂ��ĐI�i�ނ��j��ł����C���[�W�ł���B������̈������̂���S���̂ɂ���y�b�g�͂��ׂĂ��炢��̂��B �@���������Ɏ�����̃K�����A�y�b�g�ɐ����I�ɓ]�ڂ���ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��A�l�b���ʂ̊����ǂɂł�������Ȃ�����a�C�����邱�Ƃ��Ȃ����A�y�b�g�Ɠ��ꉻ����������S���ɂ����ẮA�����ɋN���������Ƃ̓y�b�g�Ɉڍs����̂ł���A�y�b�g�ɋN���邱�Ƃ́A���ׂĂ킪���ƂȂ̂��B �@���̂悤�Ȏv�l�͎�����̕\�ۏ�̑z���I�Y���ł����āA������̕s�����]���y�b�g�ɓ��e�i���ˁj���������ʂł���A���ꂪ�y�b�g�ɂ������Ă��邩�̂悤�ɂ���ւ�����]�ڊ���Ɋ�Â��Ă���B�����ł����]�ڂ́A�������S���w�I�ȓ]�ځA���Ȃ킿�u�Ώۂ�ϔO���قȂ�Ώۂ�قȂ�ϔO�ɂ����v�Ƃ����Ӗ������ł���B �@�K���Ȃǂ̕a�C���l���瓮���ɓ]�ڂ����Ǝv���̂́A�ЂƂ�̐l�̂̒��̐����I�]�ڂ��щz���đ��̑ΏۂƂ��Ẵy�b�g�ɂ������Ƃ݂銴��]�ڂ������ł���B���̂Ƃ������傪�A���܂��ɃK���������Ă������A��X�K���������Ă����ł��낤���Ȃ̃C���[�W���y�b�g�ɓ��������Ă����S���I�K���]�ڂ��N�����Ă���B������̓K���a�҂̎��ȃC���[�W�ꉻ���Ă���y�b�g�ɓ]�ڂ����Ă���ƍl������B�ʏ�K���͑��l�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ����A�S�I�]�ڂ͗e�Ղɂ����肤��B �@����͎����傪��e�̃C���[�W�����̑㗝�҂ƂȂ�y�b�g�Ɉڍs����i�����j�y�b�g�ւ̕�e�]�ڂ�����������A�y�b�g���X�ߒQ�҂��y�b�g�̃C���[�W�����Î҂ɂ����y�b�g�]�ڂ�������S�I���J�j�Y���Ɠ����ł���i���S�j�B �@�i��4�j������E�y�b�g�Ԃɂ����銴��̓]�ڂƋt�]�ڂ̖��͂���ɕ��G�ł���B�c��ȃy�b�g�\�����ł͐���܂��Ȃ��q�����l���Ă݂悤�\��l����Ă��ꍇ�A�y�b�g�͂����Ɏ�������e�Ƃ��ĔF������悤�ɂȂ�B�����傪�������ɂ��ĉ��x�Ǘ������A�~���N��^���r���̎�`��������Ȃǂ��Ĉ����������A�q���͂��̐l�Ԃɑ��ċL���ɂ���ꌢ�ւ̃C���[�W���d�˂Ă����B�q���͎�����ɕ�e�i�ꌢ�j�]�ڂ��������Ă���̂ł���A����䂦�Ƀy�b�g�ɂƂ��Ď�����͂����Ƃ���Ȉ����ΏۂɂȂ��Ă����B�����ł����t�]�ڂ͎�������e�Ƃ��Ė������ɕ炤�y�b�g�̎p�ɉe�����������傪�A���܂��܂Ȋ�����y�b�g�ɓ����Ԃ��Ă������ۂ������B���̏ꍇ�A�����傪�q���ɓ��������銴��́A��e�����c���ɑ��ĕ����{��I����Ƃ��قǕς��Ȃ��B�������ė��҂͊���̌������������Ȃ���݂��̊W���[�܂��Ă����B�y�b�g����Ƃ́A�y�b�g�ɕ�e�]�ڂ����������Ĉ�����������Ɍ��������A���̈���������������傪�A�܂��y�b�g�Ɉ�����Ԃ��Ă����Ƃ������݂̈����ɂ��z���I���Â��Ă����W�Ƃ�����B �@�y�b�g��������Ɠ�����Ԃɂ���ƌ��邱�Ƃ́A�y�b�g�����Ȃ̏��L���Ƃ��������ł̋[�l���ł���B�y�b�g�͎�����̕��g�ł���㗝�҂ɂ��Ȃ�B�y�b�g�͎��̐g����ɂȂ�₷���A�y�b�g�̐��O���玔����̌`��ƂȂ�\�����߂Ă���B���Ƃ����l�ԂɂȂ����ɂ́A���̒��̈������������Ƃ��Ă��炤�K�v������B �@�܂��A�y�b�g���q�ǂ��ɂ�����A�Ƒ��̈���Ƃ݂Ȃ��[���Ƒ����A�y�b�g���Ƒ��̐����̒N���̑����S�킹��s�ׂł���A�����͂��łɐl�̐g����ł���`��̖�����w���킹�Ă���i���T�j�B �@�i��5�j�v�w�Ǝq�ǂ��̂���Ƒ��̂Ȃ��ŁA�����Ă����y�b�g�����S�����ꍇ�A������v�w�͂��̃y�b�g���킪�q���~�����߂̐g����ƂȂ��Ď��̂��ƂƂ炦�A�q�ǂ��ɂ�������邱�Ƃ�����B���̂悤�ȗ����́A�Ƒ��̂Ȃ��Ŏq�ǂ��̈�l�����S�����Ƃ��A�e�͎��q���c�����q�̐g����ƂȂ����ƍl���A�c�����q�ǂ��ɂ����҂͂��Ȃ��̈������̂�w�����Đg����ɂȂ��Ď��̂�����A���̕��������萶����悤�ɂȂǂƋ���I�Ӗ������߂ċ����@���悤�Ɏ��̗��R����邱�Ƃƒʒꂵ�Ă���B �@������̓y�b�g��r���Ă��炻�̂��ƂɎv�����邱�Ƃ��������A�y�b�g�����C�Ȃ������炻��Ȃ��Ƃɍl��������Ԑl���ǂꂾ�����邾�낤���B�����A�y�b�g���`��Ƃ��Ď��̌�����������Ď��Ȃ����ƂȂ�A������S������݂āA���̐ӔC�͑S��������{�l�ɂӂ肩�����Ă���B �@�`��̔��z���y�b�g��S������������̔]���ɕ����Ԃ̂́A�Ȃ����̎q�͂��������`�Ŏ��ȂȂ���Ȃ�Ȃ������̂��̖₢�ɁA�`���I�ȃX�s���`���A���ȗ��ꂩ�炢�������̐��������Ă����Ƃ���ɂ��邩�炾�Ǝv����B �@�b��t��Ō�m�́A�S�������q�̎��ɂ��Ă̈�w�I�Ȑ����͂��Ă����B�������A���������m�肽���̂́A�a�C�⎀���̕a���I�Ȑ����ł͂Ȃ��A�ǂ����Ă��̎q�͂��̂悤�Ȗڂɂ����Ď���ł����Ȃ�������Ȃ������̂��ł���A�ǂ����Ď��͂��̂悤�ȂЂǂ��ڂɉ��Ȃ�������Ȃ��̂��̓����ł���B�����āA���̂��Ƃ͒N�������Ă���Ȃ��B �@���̎q�̎��̗��R���݂���Ȃ��Ƃ��A�y�b�g���L�҂͎�����ӔC�������Ă���_����A���̎����͎����ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���̐g����ƂȂ��Ď��̂��Ƃ����z���ɂƂ����͕̂s�m���Ȃ�������Ƃ��[���ł��鍇���I�ȓ����Ɏv����̂ł���B �� �`��h�q�̌��� �@�`��̑��݂͍����A�l�`���{��ЂȍՂ�Ȃǂ̏@���V���N���s���̒��Ɍ��o�����Ƃ��ł��A�L�����{�l�̂Ȃ��ɐZ�����Ă���B�܂��A���ׂ͐l�ɂ����Ǝ���Ɛl�X�̊ԂɐM�����Ă���W���N�X�Ȃǂ��A�`��̃Z�I���[�ɂ���Ă���Ǝv����B�a�C������Ƃ����\���͍����A�a���ۂɊ��������Ӗ��ŗp���邪�A�����͉u�a�_����肤���Ă������Ƃ̕\���ł��낤�B �@���{�l�͓`���I�ɍЖ�ƂȂ邯����∫����Ȃǂ͑��҂ɂȂ�����Ă����Ă��܂��A�킪�g�͂��Ƃ̍߂�����̂Ȃ�����ȏ�Ԃɂ��ǂ��đ|�����߂���Ƌ����قǖ��C�ɁA�����Đ^���ɂƂ炦�Ă���Ƃ��낪����B �@���̂悤�Ȍ`��ɂ��Ă̍l������{�l�����悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A���R�̎����͐_�삪�~�Ղ����ł���Ƃ���ˑ�i��肵��j�̎v�z�ɂ���Ă���ƍl������i���䓿���Y���A���ԐM�A�����[�A���a55�N.�j�B�_���͐A���⓮����z���ɂ����Ă��̐_�Ђ����R�̈З͂Ƃ��Ĕ������邪�A����͐l�ԂɂƂ��ĕ��������炷���̂�����ΉЁi�킴�킢�j�ƂȂ���̂�����B �@���̎��R�Ɛ_��ꎋ���鎩�R�M�ɂ����ẮA�P�_�����_���߂�����������R���ɂ����悤�ɐl�Ԃɂ������ċg����^����B�����͕ʂ̈ˑ�����߂đ��̑Ώۂɏ��ւ��Ă������Ƃ��ł��A������ǂ��������Ǝv���Βǂ��������Ƃ̂ł���t�����̂悤�Ȑ��������ƍl�����Ă���B�߂������������Y�����V���̂悤�ɐl�ɜ߂�����A�܂����̑Ώۂɂ��������邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă���̂ł���B �@���̌`��̓]�ڂɂ��ẮA�S�̂�����ƂȂ�߂₯����̊ϔO�╉�̊���𑼂ɓ]�ł����Ď���ɍ~�肩����킴�킢��h�����Ƃ��鍇�������ꂽ�u��������㗝�`���𒆐S�Ƃ��閳�ӎ��I�ȐS���I�h�q�@���ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��B������������́A���̌`��h�q�Ƃ������ׂ��h�q�H��ɐ��������Ƃ��Ă��A�g����ɗp�����Ώۂ������Ώۂ̃y�b�g�ł���_���ő�̖��ƂȂ�B �@�y�b�g���X�ߒQ�҂́A���炪�������Đ����c�������Ƃ���Ԃ����y�b�g���сi�����ɂ��j�̂悤�Ɏg���Ė�i�₭�j���P���A�`��̋]���b�ƂȂ��Ď���ł�����������y�b�g�ɍ߂̈ӎ��Ɗ���������ɂ̊����������̂ł���B �@���̃y�b�g���X�ߒQ�҂��P���߈����Ɖ�����܂����悤�̂Ȃ�����͌`��s���Ƃ�ׂ���̂ł���A���{�l������̃y�b�g�̑r���s���̗L�͂Ȉꕔ���߂邱�Ƃ�����B���̂悤�ȔߒQ�҂́A�u�������̎q�����Ȃ����v�ƒQ�����A���̓����ɂ́u�������̎q�����̐g����ɂ����Ď��Ȃ����v�Ƃ̎v�����B��Ă���B �� �l�l�R�V���ɂ��� �@���̂悤�ȏ̒��ŁA�ߒQ�҂͂ǂ�����ΐS���y�����邱�Ƃ��ł���̂��낤���B����͌���������A�ǂ����i���ȁj�����̎q�͋����Ă����̂��Ƃ��������傩��̋ꂵ���₢�����ł�����悤�Ɏv����B���̈Ղ����͂Ȃ����̉����Ɍ����Ďv�������炷���Ƃ��A�y�b�g���ʎ҂ɗ^����ꂽ�r���̉ۑ�ƂȂ�i���U�j�B �@�i��6�j�`��̔��z���y�b�g���X�̔ߒQ����̗�������ɗL���ɂ͂��炢�Ă���ƍl������P�[�X������B�ߒQ�҂̓y�b�g���������I�n����Ă��ꂽ���������̂Ȃ����݂Ƃ��Ă�舤��������Đ[�����ӂ��Ă�����A����ɂ͂��ꂩ�������ł����쓮���ƂȂ��Č�����Ăق����ƋF�O���ĐS���y�����Ă���悤�ȏꍇ�ł���B�܂��A������q�͒P�Ȃ�g����ł͂Ȃ��A������̂��Ƃ��Ō�܂Ŏv���Ă���Ă������݂Ƃ��ĂƂ炦�Ă���悤�ȏꍇ�ł���B�`��̎v�z�����ׂĂ̈⑰�ɐ��_�I��ɂ�^����g���E�}�̌��ƂȂ�����A�����߈ӎ��⎩�ӂ̔O�Ȃǂ̃l�K�e�B�u�Ȋ�����肪�c��s���N�Ȃ��̂ł���Ȃ�A���̂悤�Ȕ��z��l�͂��Ȃ��ł��낤�Ǝv���̂ł���B�`��̑z�肪�A�y�b�g���X�̔ߒQ�������ꏕ�ƂȂ邱�ƁA���Ȃ킿�`��h�q�ɐ������鎖��̑������Ƃ��t�L���Ă��������B �@���̉ۑ�̉����Ɏ��s����A������͔ߒQ�������錋�ʁA���̃y�b�g�������Ȃ��Ȃ��Ă������A�����Ȃ���ΔߒQ��������悤�Ɍ����Ă��y�b�g���������������A�y�b�g�����ɂȂ��Ă������ƂȂ�B�s�K�Ȃ��ƂɁA�����͂������������ɂƂ��ăy�b�g�ւ̏��i���ȁj���̍s�ׂƂȂ��Ă���̂ł���B �@��Ɍ`��͕����i�Ȃł��́j�Ƃ������Əq�ׂ��B�]�ˎ���̎��T�u�a�P�x�i�킭����j�v�ɂ́A�����͌`��̑��ɁA����͔L�̂��Ƃł���ƂłĂ���B�����Őg����̌`��ƁA���ł邱�ƂƁA�L���Ȃ����Ă���B�������́A�y�b�g�����킢���Ƃ����ĕ��ł�B�p��ł���petting�ł���B���̃y�e�B���O���y�b�g���炫�Ă���B �@������̓y�b�g�ւ̈���\���Ƃ��ĕ��łĂ���̂ł���A�y�b�g�͕��ł��Ċ��ł���Ǝv���Ă��邵�A������̕����A���̊��G�ɐS�n�悳�������Ă���B�������u�a�P�x�v�́A���̈���œ��{�l�́A�L��L��i�˂�����j�Ƃ��Đl�Ԃ̍߂�������Ȃ�������P���̓���ɗp���Ă�����������Ă���B �@���̂��Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��ߐ����{�l�͔L�ł邱�ƂŁA���܂��܂ȃX�g���X��L�ɂ����Ď�菜�����Ƃ��ł���ƍl���Ă������Ƃ������Ă���B�����l����ƁA�L�͐l�̍Ж���Ƃ�`�㓮���ł����P���i����j�����ł���Ƃ�����Ǝv���B �@�����A�l�Ԃ��炯�����Ёi�킴�킢�j����菜���̂́A�Z�I���c�q����n���T�X���q���Ȃǂ��P���̐_�X�₨�s������i�g����s�����L���ł���A����̓z�g�P�j�����邱�Ƃł���B�`��𗧂ĂĂ���ɂ������̍߂�����∫�����w���킹���P���ƂȂ�A����͌`��ɐ_�ɐ���������P���������Ă��邱�ƂɂȂ�B �@�������Ă݂�ƁA�`��ƂȂ���̂͐_�̐g����ł���Ƃ�����B�_�ɂȂ�������P��������̂�����A���̌`��͐_�̑㗝�҂ƂȂ�B�y�b�g���`��Ɏg�����ƂȂ�A�y�b�g��l�݂̂Ȃ炸�_�̑�p�Ƃ��Ďg�������ƂɂȂ�B �@�l�̓y�b�g���������܂l�Ԃ̐g����ɂ��邾���ł͂Ȃ��[�_�������Đ_�̐g����ɂ�����̂ł���B���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA����̃y�b�g�����͐��������ł���A�G���W�F���̂悤�Ȑ_�̑㗝�l�̖�����w���킳��Ă���Ƃ����Ă��悢���Ǝv���B�������̓y�b�g�̂Ȃ��ɂ��܂��܂Ȃ��̂�����B��ɂ͖����̐_���A���̈�ɂ��P���̐_�����悤�Ƃ��Ă���B
|
||||||
�@�����E�ł͂Ƃ��Ƃ��āA����Ƃ͕ʎ�̓�����ƌ�F���Đe���ȊW�ɂȂ邱�Ƃ�����B���Ƃ��A�k�Ăɐ�������쒹�̃V���E�W���E�R�E�J���`���E���l�Ƃ̑��ӂɒu���ꂽ�������̒��̋����ɒ��Ȃǂ̉a�����킦�Ă��Ă͐��T�Ԃ��̂������^���Â����Ƃ����b������B �@���҂͂ǂ����Ă��̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����̂��낤���B�g���ƃT�J�i�ł͎p���������قȂ邵�Z�ސ��E���Ⴄ�B�����A���������ʂɊ���o���Č���傫���������s���ɐG�����ꂽ�g���́A�����I�ɉa���^�ԗ{��s�����Ƃ��Ă��܂����̂ł���B�����̕����A�����p�N�p�N�����铮�������ΐH�ו������炦�邱�Ƃ��w�K�����̂��B �@����̓g���������̍s�������܂��ܖڌ����������A�c���������J���ĉa���Ñ�����p�Ɠ������悭���Ă������߂ɁA���̂��Ƃ��e���Ƃ��Ă̖{�\�I�s���������N�������i�����[�T�[�j�ƂȂ����Ďq��Ă��n�߂��ƍl�����Ă���B �@����Șb���ƁA�g�����Ĕn������ˁA�����������̎q�ǂ��Ɗ��Ⴂ���Ă������Ɖa���^��ł������A�Ɛl�͂�������������Ȃ��B�������A���͎��������قƂ�ǂ���Ɠ������Ƃ������Ƃ��Ă���Ă���̂ł���B��������ԂƂ����������đ�X�I�ɂł���B�y�b�g�E����哮�����������Ƃ��A�܂���������ł���B �@���L�Ȃǂ̚M��������Ԃ�V�̎������Ă�A���������͗{��҂ł��鎔��������̕�e�Ǝv������ň����ƈˑ��������Ă����B�c�ᓮ������̃y�b�g����Ƃ́A���̕�e����q�ǂ��𑁊��Ɏ��グ��(�f�v�E�U���Ƃ����Ă��悢)�A�킴�킴�l�Ԃ����e�ł���{��ƂȂ��ĕ�e�̖��������ɂɂȂ��s�ׂɑ��Ȃ�Ȃ��B �@�Ȃ�����Ȃ��Ƃ�����̂��Ƃ����A�Ԃ�V�̓����Ɏ���������ꂾ�Ǝv�����܂��ĕ�e������肽������ł���B�y�b�g����͎�����̎q��Ċ�]�i�{���]�j�ƁA���̓��������i�Ƃ��Ē���y�b�g�Ǝ҂̑o���̗��v����v���邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă���B �@���āA�q�ǂ��������ЂƂ��邱�Ƃ�������߂āA���̂Ԃ������܂����ƌ���������̕��������B���̎����傳��ɂƂ��āA�y�b�g�͂����ЂƂ�ق��������q�ǂ��̐g����i�㗝�j�ł���A���̂��߂킪�q�Ƃ��đ�ɐڂ��Ă����B�e�q�̂悤�Ȉ������`������̂ɂ��݂��̊O�`���̈Ⴂ�͂��܂�W���Ȃ��B �@�y�b�g���킪�q�Ƃ݂Ȃ��Ƃ��A������͎��̎O�̔F�m�I�ȑ�����s���Ă���B �@��P�̑���́A������y�b�g�͐l�Ԃł͂Ȃ����A�l�ԂƓ����悤�Ɉ������Ƃł���B����̓y�b�g�ł���َ�̓�����������ł���l�ԂƓ���ł��邩�̂悤�Ɍ��Ȃ��Đڂ��邱�Ƃł���A�[�l��`�ł���B �@��Q�̑���́A������̓y�b�g�Ƃ͌��̂Ȃ���͂Ȃ����A�e���Ƃ�킯�Ƒ��̈���Ƃ݂Ȃ����Ƃł���B�l�ԂɂƂ��ăy�b�g�͂��������҂ł��邪�A�����Đg���̈�l�Ƃ��Ĉ������Ƃ���B�Ƒ��̐����̂����z��҂͈�ʓI�ɂ͌��̂Ȃ���͂Ȃ��B���̓_�A�y�b�g�̈ʒu�͎�����̐��_�I�Ȕ����ɋ߂��Ƃ����邩������Ȃ����A�y�b�g�Ƃ͖@�I�ɂ��v�w�ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��_����݂ē����̍Ȃ�v�̂悤�ȑ��݂Ƃ����邩������Ȃ��B �@��R�̑���́A�y�b�g�͂킪�q�ł͂Ȃ����A���q�Ɠ����Ɉ����Ƃ������Ƃł���B�����������ł͂Ȃ����A�����������������̕�e�ł��邩�̂悤�ɐڂ��Ă������Ƃ���B����́A�܂ܕ�Ƃ܂q�̂Ȃ��ʒ��̊ԕ��ł͂��邪�A�{���̐e�q�̂悤�ɂȂ邱�Ƃł���B���̎O�̑���́A��P�����R�ɏ���ǂ��ĂȂ���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�O���قړ����ɔF�m����Ă����B �@���̂悤�ɂ��̐e�q�ł͂Ȃ����A���̐e�q�Ɠ����悤�ȊW���`�����邱�Ƃ͋[���Ƃ�����B�@���ł͋[���́A�{���͈قȂ���̂ł��邪����Ƃ݂Ȃ��Ƃ����l�����ł���A���̂��Ƃɂ���Ė@���I���ʂ��^������Ƃ��Ă���B�����Ƃ��l�ԂƓ����̊Ԃł͖@�I�ɐe�q�ɂȂ�{�q���g�͔F�߂��Ă��Ȃ��B�[���Ɋւ��Ė@���Œ�߂�Ƃ���͂����܂Ől�ԂƐl�Ԃ̊Ԃ����ł���B �@�܂��A�Љ�w�ł͗{�q���x���[���ɉ����Ȃ��Ƃ��錩��������B�������S���w�I�ɂ͗{�e�Ɨ{�q�E�{���̊Ԃɂ͌��̂Ȃ��肪�����Ă��Ȃ��Ă����҂ɂ͂�����₤�ɑ���[����Ɛ��_�I���т��������A�^�̐e�q�ƕς��Ȃ�������ȏ�̉Ƒ��ɋ[�����邱�Ƃ�����B �@����Ă��̂��Ƃ������ė{�q���g���x���L���[���Ƒ����āA�����ł͍l���������߂�B�����āA���ꂩ����Ƃ����������̐l�Ԃƃy�b�g�����̂�����ɂ����Ă��[���W�Ƃ��đ����Ă����B �@��P�̑��삩���R�̑���͂�������[�l���ɂ��ƂÂ��[���ł���A�����ɂ݂��鋤�ʓ_��������A�{���͈قȂ���̂ł��邪�A������̊�]�ɂ���ē������̂Ƃ݂Ȃ��Ƃ������z�ł���B���̎O�́A����������l�Ԃ̑�����o�Ă���Ȃ��]�ł����āA�������y�b�g�ɓ��e�����邱�Ƃɂ���ċ[���̐S���͐��܂��B �@�l�ԁE�y�b�g�Ԃɂ�����[���W�́A�����傪�y�b�g�𓊉e���ꉻ����S���@���A���Ȃ킿�����厩��̖��ӎ��I��]��~�����y�b�g�ɓ��������Ă�����y�b�g�̐����Ƃ��邱�Ƃɂ���Ď�����Ɠ���Ƃ݂郁�J�j�Y���ɂ���Đ��藧���Ă���B �@�����傪�y�b�g�Ɛl�Ԃ͓����ł���Ƃ݂Ȃ��A������̎�ϓI���E�ł͂���͂����Ȃ�̂ł���A���l�̍l�����������傽�������͂ɂ�����������A�Ԏ�ϐ��ɂ����Ă����̎v���͂��m���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�܂��A�y�b�g�Ǝ�����ł��鎄�ɂ͉���ς�邱�Ƃ̂Ȃ�������������Ă���Ƃ݂Ȃ��A�y�b�g�͎��̌����Ƒ��ƂȂ�B �@����ɂ́A�y�b�g�����̎q�ǂ��Ɠ��ꉻ�i���ꎋ�j����A�y�b�g�͎��̎q�ǂ��Ƃ��Ȃ�B���̎O�̑���������傪�s�����Ƃɂ���ăy�b�g�͂킪�q�ƂȂ�A�����ɋ[���e�q���a������B �� �`���l��Ō��т����{�̎�����ƃy�b�g �@�ł́A�l�͂ǂ����ăy�b�g�Ɖ��̐e�q�̊W�����ڂ��Ƃ���̂��낤���B�����傽�����y�b�g�������悤�ɐl�ԉ����A�Ƒ������A�q�ǂ������ẮA���̂��Ƃ��Љ�I�ɂ��e�F���Ă��炨���Ƃ���ɂ́A������ׂ����R���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����傪�y�b�g���킪�q�ɂ�������A�l�ԂƓ����Ɉ������Ƃ��錴���͂Ȃ낤�B �@���̋����[���₢���l����ɂ�����A���̂悤�Ȃ��Ƃ��y�b�g���D�Ƃ����́A�����̌����╟���𐺍��ɋ��Ԋ����Ƃ̂悤�ɓ���̎v�z�M������I�C�f�I���M�[�̂��ƂɏW�c��g��ňӐ}�I�ɍs���Ă���Ƃ́A�Ƃ��Ă��v���Ȃ��B�X�̎����傽�������i�ӂ����ӎ����邱�Ƃ��Ȃ��e���̎������ɂ����Ď��R�ɂӂ�܂��Ă���ɉ߂��Ȃ��B �@���̕ϑ��I�Ȑl�ԂƓ����ɂ��t�B�N�e�B�u�ȊW��ǍD�ɂÂ��Ă����ɂ́A�{���̐e�q�Ɉ��������Ȃ������́A���邢�͂���ȏ�̏�I�Ȍ����͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���҂͂Ȃ�猌���̂Ȃ��َ�ǂ����ɂ�������炸�㗝�e�E�㗝�q�Ƃ��ċ������S�͂�ۂ��Â���ɂ́A���҂͂Ƃ��ɂ��ꑊ���̓w�͂�v���邾�낤�B�����Ȃ��A���̊W�͂����ǂ���ɉ�̂��Ă��܂��͂��ł���B �@���āA�y�b�g�E����哮����r�����l�́A���X�������邤���ł����Ƃ���ς������Ƃ����̎q���T�ɂ��Ė����Ă��ꂽ�A������炩�����Ƃ����̎q���x���ɂȂ��Ă��ꂽ�ƌ�邱�Ƃ������B�܂��A���̋C�����������Ƃ��悭�킩���Ă���Ă����̂����̎q�������Ƃ������Ƃ��Ђ�ς�ɕ��������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��q�ł���B �@��������ł��Ă��Ƒ��̒N���������ƋC�Â����ɂ���Ƃ��A���������ށE�ޏ���͎�����̂����ƈႤ�����ȐS�̕ω��ɕq���ɋC�Â��ĐS�z�����Ȋ�����Ȃ���T��Ɋ��Y���Ă����B�������������Ƃ����яd�Ȃ�A�y�b�g�͒N�������̂��Ƃ��悭�킩���Ă���鑶�݂ƂȂ�B����͕v��Ȃ����A�q�ǂ������A�e�����A�F�l�����A�N�����ł���B �@�y�b�g��������l�����́A�l���̋��ɂ������Ƃ��A�����Ƃ�����ɂȂ����̂����̎q�������Ƃ����B�����铮���͎��͂̐l�Ԃɂ������ċ`���Ɛl��ɓĂ��Ǝ�����͎v���Ă���̂ł���B�l���������Ƃ��Ɏx���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐l�̂͂������A�y�b�g�����̕����l�Ԃ����`���������l��䂽�����Ɗ����Ă���̂��B �@����͂��Ɋ�Ȃ��ƂƂ���˂Ȃ�Ȃ��B�`���Ɛl��́A�{���͐l�Ԃ��������ׂ������̂͂������A���̐l�Ԃɂ͕s�����Ă��藊��ɂȂ�Ȃ��Ǝ�����͌����Ă���̂ł���B���{�l�ɂƂ��ďd�v�ȓ��ڂƂ����`���l���l�ɋ��߂��Ȃ��ƂȂ�A���ɋ��߂邵���Ȃ��B�l�ԈȊO�̑��݂ɐl�ԓI���������߂Ă��������Ȃ��Ȃ�B�y�b�g���[�l�����ċ[���W����闝�R�̈�������ɂ���ƍl������B����ɂ͐l�Ԃ��y�b�g������K�v�Ƃ��闝�R�������������Ƃ���ɂ���Ǝv����B �@���̂�������|���Ƃ������鎔����̓����ς́A���������͓��ɓˏo���ĕ����v�l�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����ł͂��ꂪ�����̃y�b�g���D�Ƃ����ɂƂ��Ă̋��ʔF���Ƃ��Ȃ��Ă���B���̂悤�ȏ�I�Ɍ��т����[���̉Ƒ��ӎ���e�q�ӎ��̓y�b�g�ƂƂ��ɕ�炷�l�����ɂƂ��ẮA�����ē��ʂȂ��ƂƂ͂������y�b�g���Ԃ̊Ԃł͂������ʂ̏������o�̂悤�ł�������B �@����䂦�A�y�b�g���`�����������Ƃ́A�������ɂƂ��ăy�b�g���y�b�g�ł��邽�߂̏d�v�Ȏ����ƂȂ��Ă���B���{�l�̓y�b�g�����ɑ��Ă��ǂ����ŏ�I�ȋK�͂����߂Ă���B����͔ނ��l�i�����Đl�ԂƓ����悤�Ɍ��Ă������Ƃ���̂�����A���̗v���͂���퓖�R�̂��ƂƂ����邾�낤�B �@����A�[���W�ł́A�����呤�ɂ��y�b�g�ɑ���`�������߂��Ă���B�`���Ƃ́A����Ƃ������Ă��������ŁA����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���Ȃ킿��I�ȓ����I�K�͂ł���A���ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��`�����Ƃ��Ȃ����ł�����B���������������ăy�b�g�����{�Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B����䂦�ɁA�y�b�g��S��������̗������݂̒��ɂ́A�y�b�g�ւ̋`�������イ�Ԃ�ɉʂ����Ȃ��������Ƃւ̐\����Ȃ������݂����Ȃ��炸�܂܂�Ă���B �@�`���̐e��`���̌Z�Ȃǂƌ����Ƃ��́A��ʂɂ͔z��҂̐e��Z�̂��Ƃ��������A����͂��̐l�����Ƃ͌����͂Ȃ��������҂Ɠ���Ƃ݂Ȃ��Ǝ�茈�߂邱�Ƃ������Ă���B�`���́A�����̖��i���̏ꍇ�͒j�����ł߂̔t�����킵�������j�ɂ��������āA�݂��ɑ���������҂ɉ������邱�ƂŎЉ�I���J�i�����ȁj�A���Ȃ킿�R�сi���イ�����j�̌`���ɂ͂��炭�B �@���ꂪ�y�b�g�Ƃ̏ꍇ�ł���A�o��̓���y�b�g�̒a�����ȂǓ��ʂȓ����ȋL�O�����j�����Ƃ��J���m�F������[�ߍ������肵�Ă���̂ł���B���̈Ӗ�����A������ɂƂ��ăy�b�g�͖̏�ɐ��藧���q�ł���_�ɂ����ċ`�q�i�`���̎q�j�ł���A�����厩��͋`�e (�`���̐e)�ɂȂ�Ƃ�����B �� �y�b�g�Ƃ̕�炵���ɔY�ތ���̎����� �@�����̌�����{�̎����傪�l�Ԃƃy�b�g�̊W�����̂悤�ɑ�����悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A���҂̂���ׂ��p�����イ�Ԃ�Ɍڂ݂�Ԃ��Ȃ��A�����\�N�\�ܔN�̊Ԃɋ}���Ƀy�b�g�̎�������ɓ˂��i��ł��������ߋ}���ɗ��҂̋������k�߂Ă�������肪����B �@���L�Ȃǂ̓������������炷��Ƃ������m�ȏK���̂Ȃ��������{�l�́A���ė��̃y�b�g�̎���@���悵�Ƃ��āA�����ŋ߂ɂȂ��ċ}���Ȑ����ʼnƂ̒��ɏ�������Ă������B�����A���������̓y�b�g�����Ɩ��ɐڂ���o������j�I�Ɏ����Ȃ��������߂Ɏ�����Ƃ��Ĕނ�ɂǂ̂悤�ɐڂ��Ă����悢�̂��̒m�����Ȃ������B �@���̂��ߓ`���I�œ���݂̂����q����I�Ɍ��т��Ƒ��Ԃ̏����b�ɂ����[���̌����W��������E�y�b�g�W�̒��ɂ������������Ă������B���̌Â�����̐����������f����͂Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ����R�Ŕ[�܂�ǂ��v��ꂽ���A����͓��{�̎����傽���ɂ����閳���o�I�Ȏ����v�l�������B���̑Ή��͈������Ƃł͂Ȃ����A�ߏ�ƂȂ�Ε��Q��������B �@���Ăł͈�ʂ̎s���w���y�b�g���������炵�e���ɕ�炷���j�����Ȃ��Ƃ���S�N�͂���B����ɂ����6�`7����͗D�Ɍo�Ă���B����ɁA�ꕔ�̕x�T�w�ł͌ܕS�N�ȏ�̃y�b�g�̎�������̗��j������B�Ƃ��낪�ނ�̓L���X�g���k�ɂ��Ē{�Y���̏K���Ƃ��āA�l�ԂƓ������Ɉ����悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B�l�ƃy�b�g���ڐ��Ō��Ȃ��Ƃ����M���̓y�b�g�������Ɉ�������ē������͂��߂Ă��ς�邱�Ƃ͂Ȃ������B �@�������A�������͒N�����ЂƂ��ш���ł��Ƃ̒��Ɉ�������ĂƂ��ɕ�炵�n�߂�ƁA���肪�ǂ�ȗe�p�ł����Ă���a���Ȃ��Ƒ��Ƃ݂Ȃ��Ă��܂��̂��B����͓��{�̘̐b�ɂłĂ���ߏ��[�̂悤�ɁA����̑f�����悭�킩��Ȃ��Ă������Ă���Ύ����ɏ�������ĕی삵�A���̂����C�S������ď���N���Εv�w�ƂȂ��ĂƂ��ɐ������n�߂�B���̑���̎��̂��l�ԂłȂ��߂ł������Ƃ��Ă��ł���B �@���Đl�̊���ė��L���X�g���̃o�C�u���ɂ́A�ƒ{�͐_���l�Ԃ̂��߂ɑn�����ė^�����ƋK�肳��Ă���B���̂��ߎ��瓮�����E�Q���ĐH�ׂ��背�U�[���i�ɂ��邱�Ƃ�A�J���Ɏ����邱�Ƃ͐_�ӂɂ��Ȃ��Ă���Ƃ��āA���̂��Ƃ�[���ɔY�ނ��Ƃ͂Ȃ������B���̂悤�ȉƒ{�ς̉�������ɂ���y�b�g�����ɑ��Ă��A�ނ�͎��������l�Ԃ̂��߂ɑ��݂���ƍl���Ă���߂����Đl�����ɂ͂���B �@�������̈���ŁA���瓮�������̎��{�Ǘ��₵���͂�������s���Ĕނ�����S�ɃR���g���[�����ɒu���Ďx�z����`�����Ă���ƍl���邱�Ƃ��Y��Ȃ������B���ꂪ�܂��_�̈ӎv�ł�����ƍl�����̂ł���B�������A���{�l�ɂ͂����������ƒ{�̗��j�͂Ȃ��A���������Ă��̂悤�ȓ����ς������Ȃ������B���̂��߂ɁA�y�b�g�Ƃ̕�炵���[�܂�ɂ�Ĕނ�Ƃ̂��������������Ă��܂��܂ɔY�ݎn�߂�̂ł���B �@���������Ƒ��͐l�ԂłȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ́A����̓��{�l�y�b�g���D�Ƃ͍l���Ă͂��Ȃ��B���������̉��Ō��������ĂƂ��ɕ�点�y�b�g�͉Ƃ̎q�ł���A�����̎q�ƂȂ�B���ꂪ�Ƒ��ł���g���Ȃ̂��B�y�b�g�����Ɛ[����������������́A���������̐e�������Z���[���W�����܂��ꍇ�����邱�Ƃ͒m���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B �@�y�b�g���D�Ƃ����̐e�Z���q�ǂ��Ƃ͑a���ɂȂ��Ă�����A�v����������A���邢�͊W���������Ă���悤�ȏɂ���A����͂܂��܂����蓾�邱�Ƃł���B���ɐe���Ƀy�b�g�ƌ��т��Ă���M�҂̃N���C�G���g����̒��ɂ��A�ߐe�҂Ƃ̊W���₦�����Ĉ��̋�����u���Ă���l���Ƃ����茩����B �@���̂悤�Ȑl�ɂƂ��ẮA�����Ƃ��g�߂ɂ���y�b�g�̕����͂邩�ɕK�v����M�����̓_�ŏd�v�Ȓn�ʂ��߂Ă���A���̌����Ƒ������y�b�g�ƂƂ��ɍ��[���Ƒ��i�㗝�Ƒ��j�̕������������̂Ȃ����݂ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ�����B�����̒��x�́A�����I�Ȍ𗬂̐[����ڐG�̐S�n�悳contact comfort�̖��x�ɂ����ėʂ�����̂ł����āA���̑Ώۂ��ߐe�҂ł��邩�Ȃ����A�l�Ԃ��l�ԂłȂ����͂���������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �@�����I�ɂ͋߂����A�S���I�ɂ͉����Ƒ���e���̊W������A�����I�ɂ͉������A�S���I�ɂ͋߂��y�b�g�Ƃ̊W������Ƃ������Ƃł���B�܂��A�����������܂����B��`�I�ɂ͋߂����A��I�ɂ͉����Ƒ���e���̊W������A��`�I�ɂ͉������A��I�ɂ͋߂��y�b�g�Ƃ̊W������ƁB �@�y�b�g�̎����e�̎������炢�Ƒi����l�������Ƃ��������́A�����Ӗ����Ă���̂��B���̂��Ƃ��ǂ����������A�����I�����I���̐���͕ʂɂ��āA�����y�b�g���X�̌��҂̑r�������ǂ̂悤�ȏɒu����Ă��邩���悭���������Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B �� �[���̐e�q�ӎ��Ɩ���ς͐[�����т��Ă��� �@�y�b�g���X�͐S�̂��ǂ���������̌��ł���A����ɂ��Ă������_�I�Ȏx������Ȃ������Ƃł�����B������͈�����q�Ƃ̕ʂ�ɂ���Đl���̋��𖡂킢�A�S�������q�̖��̂͂��Ȃ��ɑł��Ђ������B���̐��͂��肻�߂ł���A����ł���Ƌ����v���B �@���̎q�ɂ߂����������̂̎��̎茳�ɂق�̂������܂����̂��A�����ɑ��苎���Đ����Ă��܂��B�܂��܂����Ă����Ǝv���Ă������̎q�́A���������̂悤�ɏ����Ă��Ȃ��Ȃ�A��Ɏc�����̂͐S�ɋ��傫�Ȍ��ƌ�������B���̐��͂炢���Ƃ̑����J�����i�������j���Ɖ��߂Ď�������B��̌��ʂ��Ȃ��낤���s�m���ȗJ�������߂����Ă䂭���߂ɂ��̎q�͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���Ȕ���傾�����̂ɁE�E�B �@���̗��݂Ƃ��Ă����y�b�g�͂��͂₢�Ȃ��B���̐��ɂ͉��ЂƂ������̂͂Ȃ��A�ς��ʊm���Ȃ��̂ƂĂȂ��B���̐��͉��ł���A���̎q�̎p�����A���Ƃ��̎q�̊Ԃɂ��������Ƃ����ł���A�e�q���Ǝv���Ă����J�����A���ׂĂ͂����Ƃ��̎蕨���Ǝv���B �@������́A�����̎q�͓V�g�̂悤�Ȏq���Ƃ����B�������A�G���W�F���Ƃ͂��������V�̌�g���ł����āA�����͂��̐��ɂ���B�ނ�́A������Ȃ��Ƃ�`���ɂ����Ƃ����̐��ɂ���Ă��邾���ŁA�K�v�ȗp�����ς߂����ɂ��̐��ɋA���Ă��܂��̂ł���B�V�g�́A���̐��̎҂ł͂Ȃ��̂ŁA�ق�̂킸���������Ă���Ȃ��̂��B �@�M�҂̌���Ƃ���A������ƃy�b�g�����̐e�q�ɂȂ邱�ƂƁA���̐������̐��Ǝv������ςƂ͕��������������т��Ă���B���̗J�����Ől�Ɠ����͉��̐e�q�ƂȂ��ĂƂ��ɕ�炷�̂ł���B�Z���Ȏq��r�����߈��̂Ȃ��Ō������Ǖ炷�鎔���������ɂ��Ă����v���B �@������͑����̂킪�q���v���A�����i������j�̂͂��Ȃ������������B�����A���̂̂���������������Ώۂ��y�b�g�����Ȃ̂��B���ꂾ���ɁA�߂��݂̑������̐��Ƃ͕ʂɂ�����̐��E������A�����̓y�b�g���l���ꂵ�݂�Y�݂̂Ȃ��v���̐��E�ł���A����Ȑ��E����X�҂��Ă���ƍl����B�H���i�������j�ł���A�w���̋��x�͂��̂ЂƂł���B�[���̈ӎ��̓X�s���`���A���ȊϔO�Ƃ����ڂɂ�������Ă���A���̗����Ȃ����ē��{�l�̃y�b�g���X�Ǝ�����E�y�b�g�W�𑨂��邱�Ƃ͕s�\�Ǝv����B �� ���������[���̌������d��������{�Љ� �@���{�̎Љ�͋[���̌����Љ�Ƃ�����B���̃A�W�A�����ɂ�����Љ��C�X�����Љ�ȂǂƂ��قȂ�킪���͏��R���錌���Љ�ł͂Ȃ��A������͂����Љ�Ƃ�����B�{�q�E�{���▹�{�q���}���ĉ��̐e�q�ƂȂ��ĉƂ��p�����Ƃ����قLj�a���Ȃ��s���Ă������A�e���ɂȂ�����y���Z�M���A��y��핪�ƌZ��ɉ������ĕ\�����邱�Ƃɂ���Đe�������m�F�������Ă����B �@�E�l�̓k�퐧�x�ɂ�����e���E�q�������l�ł���B��q����i��q�ɂȂ�Ƃ����̂����q�ɂ��Ă��炤���Ɓj�����Ⴂ�E�l�ɂƂ��Đe���͂��̕��e�ł͂Ȃ����A���e�̂悤�ɐڂ��Ă������Ƃ����҂���邵�A�e�����Ⴂ�E�l�����̎q�ǂ��̂悤�Ɏv���Ĉ�ĂĂ����B�e�g�i����݁j�ɂȂ�Ƃ͂����������Ƃł���B �@�����̏��Ɣz���̓y���̊W���������e�E���q�������҂͌����W�c�ł͂Ȃ����A���ɂ͒����������A�L���̂����͊��e�̎P���ɓ����Đ퓬�ɉ�������B�C�����E�̐e���E�q����`�Z��̊W�������ł���B �@�܂���Бg�D�ł����e��ЁE�q��Ђ������i�e�E�c���Ȃǁj�Ɣڑ��i�q�E���Ȃǁj���o�c���Ă��铯����Ёi�t�@�~���[��Ɓj��联���Ђ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B����������ł���e�q�̊W�ɉ�Ђ��[���Đ[���o�c�W�ɂ��邱�Ƃ���O�ɃA�s�[�����Ă���ɂ����Ȃ��B �@�����������{�l�̐����Ɋւ��Ă������ł���B�Î��L�ł̓A�}�e���X�ƃX�T�m�I�̓C�U�i�M�̃~�\�M�ɂ���Đ��܂ꂽ�o�ƒ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�A�}�e���X�E�j�j�M�̎q���ł���퐶�n�̐l�����ƁA�X�T�m�I�E�I�I�N�j�k�V�̎q���ł���ꕶ�n�̐l�����́A�ߐe�҂ł���Ƃ������Ƃɂ��āA�Η��R��������Ă������B�x�z�ƕ��]�̊W�������Ƒ��̗͓��W�ɒu�������čI�݂ɗZ�������Ă����B�����͂��̗��n���̐l�Ԃ̍�����ł���B �@����ɓV�c�Ɛb���i���{�����j�̊W�����e�Ǝ��q�E�Ԏq(������)�Ƃ��Đe�q�̊W�ɂȂ��炦�Ĉʒu�Â����Ă���B�V�c�͉ƕ����Ƃ��Ďq�ǂ��ł��鍑�����Ɏv�����A�˂ɍ����ƂƂ��ɕ��ޑ��S(�����݂�����)�����Ƃ����(���{�Ō������d������B��̗�O���A�V�c�Ƃł���)�B���̂悤�ɐe�q�E�Z��E���Ƒc����Ȃǂ̌����҂ɋ[���ē�ҊW��W�c�g�D�̊W���K�肵�đ����邱�Ƃ��[���̌����ӎ��ł���A�����ł͋ߐe�Ƒ��̊W��͂Ƃ��čč\�������Ă���B �@�������A�����͂����Ă������A���{�̎Љ�ł͕p�ɂɗ{�q���g������s�Ȃ��K�v���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�Ƃ��p���Վ�肪���Ȃ��Ă��\��Ȃ��Ȃ�������ł���B�v�w�̘V�㐶���͗{�q�E�{�������Ȃ��Ƃ��V�l�z�[��������A���������̓������Ǘ�����g�������Ȃ��Ă��쉀���i�㋟�{���Ă����B �@�����A�����ł������Ƃ��Ă��N���ƂȂ����Ă������Ƃ����~���͎c��B�Љ�x���ǂ�Ȃɐ����Ă��Ō�܂ŋ��߂���̂�����B���ꂪ��I�ȂȂ�������߂�l�Ԃ̈����~���ł���B�������ɂ͂������Ȃ�Ƃ��ł��A��������Ώۂƈ������Ă����Ώۂ��K�v�Ȃ̂��B�l�Ԃǂ����̗{�q���g���������ɂ�āA���̊Ԍ���D���悤�Ƀy�b�g�Ɛl�Ԃ����q�E���e�ƂȂ��ĂȂ���[���e�q�������Ă���B �@�����̓_����݂āA�킪���ł͌������������ɋU�����������ł���A���������ɂ͌��̂Ȃ��肪�Ȃ��Ƃ��A�����������邩�̂悤�ɐU�镑�����Ƃɏd����u���Љ�Ƃ�����B����͂������邱�Ƃ����܂��܂Ȗʂ��獇���I�ŗL�����Ƒ����Ă��邱�Ƃ������Ă���B���{�l�̗쐫�Ƃ��������̂����̂悤�ȃv���O�}�e�B�b�N�Ȋ�������b�ɂ��Đ��藧���Ă���A�y�b�g�̎���������̎����I�ȍ�����`�ɏK���Đl�ƃy�b�g�Ƃ̊W���K�肵�Ă���B �@���̉��z�̊W�́A���������̂ɂ���J�̋����⋁�S�͂���{�Ƃ��đ��d�͂��邪�A����ɂƂ��ꂸ�Ɏ��R�ɍ��ς��邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă���B���̍L���肪�l�Ɛl�݂̂Ȃ炸�A�l�Ɠ����̊W�̗̈�ɂ܂ŋy��ł���킯�����A���̂悤�Ȏu���͓����݂̂��d�����錌�����S��`��r���A���������̂̎��r���I�ȕ�����E�炵���W�̍L��������Ƃ����_�Œ��ڂ��ׂ��ł���B �@���̋[���̍s�������́A�l�ł������ł��e�����Ȃ�A�����҂ɑ���悤�ɐe�����ڂ��Ă����Ƃ������e���������Ă���B���̂悤�ȋ[�����ӎ��������Ƃ̎Љ�S���I���p�͖��p�ȑΗ��E�ْ���h���A�����Ƃ��Ă̒��Ԉӎ���W�c�ӎ�����������Ă������Ƃɂ���Ƃ����邾�낤�B �@�[���̊ԕ��́A���������ɂ͌����͂Ȃ��킯������A����͋��\�ł���t�@���^�W�[�Ȃ̂����A�ނ��낻��䂦�Ɏ�����͎��R�ȕ����n�삵�Ċy���ނ悤�ɖL���őn���I�ȊW�ɔ��W�����Ă������Ƃ��ł���B���̈Ӗ�����A�y�b�g��l�i�����ĉ����̐e�q�Ƃ݂Ȃ�������S������T�ɗ���������Ƃ͂����Ȃ��B �� �[���e�q�̊�b�ɂ��鎔����̃A�j�~�Y�� �@�����傪�y�b�g���[�l���i�l�ԉ��j����S���̊�b�ɂ́A�]��������{�l����Ɏ����Â��Ă���A�j�~�Y���̊ϔO���͂��炢�Ă���B�A�j�~�Y���Ƃ́A�����E�A���݂̂Ȃ炸���Ȃǂ̍z����C��R�Ȃǂ̎��R���܂ޖ����ɂ͗썰���h���Ă���A�l�ԂƓ����悤�Ȋ����v�l��L���Ă��邽�߂ɐl�Ԃ͂����Ɛl�i�I�Ȍ𗬂��ł���Ƃ����l���ł���B �@���������āA�A�j�~�Y���̐��E�ςł̓y�b�g����O�ɂ��ꂸ�A�ނ���l�ԓI�Ȋ���������v�l���Ă��邽�߂ɐl�ƃy�b�g�݂͌��Ɉӎv�̑a�ʂ��ł���ƍl���Ă���B���̃y�b�g�����̕��Ɍ���Ȃ������悹�Ĉ�̊��悤�Ƃ��邱�Ƃ��[�l���ł���[���Ƃ�����B�y�b�g���q�ǂ��̂悤�Ɏv�����Ƃ́A������̎��R�ȐS�݂̍���̖��ł���A�l�Ԃƃy�b�g�����݂�������ǂ̂悤�ȑ��݂ƌ��邩�Ƃ��������ҊԂ̐S�̖��ƂȂ�B �@���������̓y�b�g���l�Ԃł͂Ȃ����Ƃ͂悭�킩���Ă���B�ɂ�������炸�A�킪�q�̂悤�Ɏv���͔̂ނ��l�ԕ��݂Ɉ����đ�ɂ��Ă����������A����̐l����ɂ��Ă����Ăق����Ƃ���������̈����ł��肢�ł���Ǝv���B���̐S���\���ے��I�ȕW�ꂪ�u�킪�q�v�Ȃ̂ł���B �@��ɏq�ׂ��悤�ɁA���L�Ȃǂ̗c��ȚM��������l�Ԃ���Ă�A�ނ�͎���������ꂾ�ƍ��o���ďI�����̂悤�ɐڂ��Ă����B���̎p�͎��R�E�ɂ͂Ȃ��l�H�I�ȕ�q�W�|�l�̎�ɂ��l�H�ۈ�Ƃ����\�������̂��Ƃ������Ƃ��悭�\���Ă���|�ł͂��邪�A�y�b�g�̕��͎���̏����ŖӖړI�Ȉ����{�\�ɂ��������čs�����Ă��邾���ł���A�l�Ԃ��e���ƐM�����܂���Ă���̂ł����āA�ނ�̂ӂ�܂����̂ɂ͗ǂ����������Ȃ��B �@�������A�������l�Ԃ��e���Ǝv���Ĉ����s���������A�����������ȏ㎔����͂���ɓ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̈�͏I�����{�Ƃ������Ƃ��낤���A���̂悤�Ȑl�דI�ɍ��ꂽ�t�B�N�e�B�u�Ȑe�q���J�i�����ȁj��ۂ��Â��Ă������߂ɂ́A�l�Ԃ̑��ɂ͗��҂̌��т��ɉ^���I�ȕK�R��������������悤�ȓ��ʂȕ��ꂪ�K�v�ƂȂ�B �@����͂��Ƃ��A�O���ł͖{���̐e�q�������Ƃ��A�O���ł͎�����ƃy�b�g�̗��ꂪ���������A���̎q�͐_�l�����킵�Ă��ꂽ�V�g���Ƃ����悤�Ȃ���������͂Ȃ��Ȃ�������A����킨�Ƃ��b�̂悤�Ɍ����X�s���`���A���ȃX�g�[���[�ł���B���܂ŏq�ׂĂ����[���W���A���̕���̈ꕔ�����\�����Ă���B �@���̂悤�ɑ����̎�����̓y�b�g�̐��O����y�b�g�Ƃ̊Ԃʼn��������̃t�@���^�W�b�N�Ōl�I�ȕ���������Ă���A������ɕێ����Ă���B���̑z���̓y�b�g�Ƃ̕ʂꂪ�N�������Ƃ��A�������痧�������Ă������߂ɂ��d�v�ȃG�s�\�[�h�ƂȂ��Ă���B �@�y�b�g�̎���A�y�b�g�����̐��։����čK���ɕ�炵�Ă���邱�Ƃ�A�ӂ����уy�b�g�����܂�ς���Ď��̂��Ƃɗ��Ă���邱�Ƃ��������A�����̎��゠�̐��ł܂���Ɉ�����y�b�g�ɉ�邱�Ƃ�M����Ƃ������悤�ɕ��������ɔ��W�����ĈӖ��Â����Ĉꉞ�̊����ɓ������Ƃ��ł���A������͗��������Ă������Ƃ��ł���B �@�������A�y�b�g�̐��O��������Ă����X�g�[���[�ɂ��܂��Ȃ���ꂸ�i���e�B�u���i���ꉻ�j�ł����ɂ���ꍇ�A������͉��邱�ƂȂ������ɗ��܂����܂܂ł��邩�A���邢�͖��{�ɓ����č������Â��Ă��邩�ƂȂ�B �@���̕���́A������̃t�@���^�W�[�ɉ߂��Ȃ��̂�������Ȃ����A����Ƃ͂��������t�@���^�W�b�N�Ȃ��̂ł���B�y�b�g�̐��O�A���̎q�͎��̎q�ǂ����Ɗ����������A���ꉻ�̑����̎n�܂�ł���A�y�b�g�Ƃ̊ԂɌl�_�b�I�ȕ�������L���邱�Ƃɂ���ăy�b�g�̓y�b�g�ɂȂ�̂��Ǝv���B �@�����Ȃ����Ƃ��A�y�b�g�͂����̓����ł͂Ȃ��A�[���Ȃ�������������ʂȑ��݂ƂȂ��Ă����B�y�b�g�̎���A�y�b�g�̂����̑O�Ńy�b�g�ɖ��S�ɕ���邱�Ƃ��A�F�肾�Ǝ��͎v���B����ς���̂̂����ɔ��ӎ��������Ƃ��Ă������{�l�ɂƂ��āA�y�b�g�����̂͂��Ȃ��̒��ɂ܂������̔����������o�����Ƃ�����A���̂悤�Ȕ��I�����@�i���I�Ȓ��a�ɂ�鎡���j�ɂ���ĕʗ�����̉��Ȃ���Ă����ƍl������B �@���������āA�J�E���Z���[�⎡�Î҂��A�y�b�g���X�ߒQ�҂ɉ������ړI�̂ЂƂ́A���̖������ƂȂ��Ă���l�I�ȑz���̕��ꂪ���N�I�Ŏ����I�Ȋ����ɓ�����悤�x���邱�ƂƂ����Ă��悢���Ǝv���B �@�y�b�g���X���́A�����̗썰�ς�y�b�g�����̎���̍s��̖���ʂ��Č�����{�l�̂��̐��ς⎀���ς��𖾂��邽�߂̗L�͂ȑf�ނƂ��Ȃ�B�܂��l�ԁE�y�b�g�W�̒T���́A���{�l�̐S���\����Љ�\���̉𖾂ɂ��Ȃ���B �@�y�b�g�����Ƃ����t�B���^�[��ʂ��Ă̂������Ƃɂ���āA�l�ԐS���Ɛl�ԎЉ�̉B���ꂽ�������_�Ԍ����Ă���B���l�ɏ��O���ɂ�����e�����̐l�ԁE�y�b�g�W��y�b�g���X����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ́A�e�����̐S����Љ���𖾂���L�͂Ȏ�@�Ƃ��Ȃ邾�낤�B �@����ɂ����A������̓y�b�g���X�̌���ʂ��Ď���̎����ς�l���ς����ł������Ƃ��ł���Ǝv���B�����āA���̖��̒T���́A����l�̍s���Â܂��ŊJ���A�V���Ȑ��E�ς�l�Ԋς��č\�z���Ă������߂̎����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͖����ɍl���Ă���B
|
||||||
�@�y�b�gpet�Ƃ������t�́A16���I�ɉp���k���̃X�R�b�g�����h�n���Ő��܂ꂽ�B�����́A�q�r�ɑ��Ă������ł������A���̌ꌹ�͕s�ڂł���B�Ȃ��y�b�g���y�b�g�Ƃ����悤�ɂȂ����̂��͂悭�킩���Ă��Ȃ��i�ȏ�́AThe concise oxford dictionary,1990. �ɂ��j�B �@�����y�b�g�Ƃ����ƁA���̑�\�I�ȓ����Ƃ��Č���L��e�⏬���Ȃǂ��������邪�A���̌��t�����ꂽ�Ƃ��͉ƒ{�̎q�r�i�����j���w���Ă����B���̗R���͂����ł���B �@�p���ł�15���I�㔼����17���I�ɂ����ĕ����̎�ɂ��_�z��������A�e�n�ɏ��̎�ł���W�F���g���Bgentry�i���J�j�⎩�c�_��yeoman�����܂�Ă������B�ނ�͂���܂œ���̏��L�҂̂��Ȃ������k��n�������J���k�n�Ɏ��R�ɓ��荞��Ŋ_�╻��݂��Ď��͂�ł͎��L�����͂���l�̖q�r�n�┨��n�ɂ��Ă������B����Ȑl�X�̒��ɂ́A���̔_��������ǂ��o���Ă܂œy�n���킪���̂ɂ���҂������Ƃ����B �@���̂����́A�����̃C���e���w�ɂ́A�Ђǂ������őe��ɉf��A�Ђキ���Ă����悤���B���Ƃ��A�g�}�X�E���A�͂��̒����w���[�g�s�A�x�i1516�N���j�̂Ȃ��ŁA�y�n�̈͂����݁i�G���N���|�W���A�j���s���r�����̘A��������\�s�ȗr�ɂ��Ƃ��āA���̂悤�ɔ�������Ղ�Ɍ���Ă���B
�@�r�͖ѐD���ɂȂ邵���ɂ��Ȃ�B�q�r�ɂ���Đ����̊�{�ƂȂ�߂ƐH�����������̂ł���B����ɉݕ����x�̕��y�ɔ����ނ�͂���邱�Ƃɂ���āA���������肳���Ă������B �@�W�F���g���B�����|���̐l�тƂ��W�F���g���}���i�a�m�E���M���j�̌��t�̗R���ƂȂ����|��A�Ɨ����c�_�������ɂƂ��ėr�͉�������ȉƂ̍��Y�ł���B�����傽���͕�e�̗r�����S���Ďc���ꂽ�q�r��A�{���������ꂽ�q�r������ƁA�����Ɉ�������ĕ�e����ɂȂ��Ĉ�Ă��B���̎q�r���y�b�g�Ƃ�B���ꂪ�y�b�g�̎n�܂�Ƃ����i�ڍׂ͌�q����j�B �@���āA��̃W�F���g���B��ɒǂ����Ă��čs������������_���Ƒ������́A���ꂩ�� �ǂ��Ȃ����̂��낤���B�ށE�ޏ���́A��ނȂ��s�s�ɗ������Ă����ɏZ�݂��Ă��������A���̒��ɂ͍s���|��ɂȂ�҂╂�Q�҂ɂȂ�҂������B���̕n�����~�ς��邽�߂̊������p���ɂ����镟������̎n�܂�ƂȂ����B �@���̌�A1�W���I�㔼�ɂȂ��ēs�s���́A���Ď���������ǂ��o�����n���̖q����̎q������Ă��r�̖т�a�����߂̌����I�Ȏ����a�D�@�B�����A���̐E�H�ƂȂ��ĎY�Ɗv�����N�����Ă����B �@�p�����͂ӂ����їr�ɂ���Đ����Ă������Ƃ��ł����̂ł���B�������Ĕނ�s�s�J�� �҂����͗r�т���n�߂ɖȂƍ��킹�Ĉߕ��ƂȂ�@�ێY�Ƃ̍H�Ɖ����͂���A�ߑ�s���Љ�A����ɂ͋ߑ㍑�ƌ`���̒S����ƂȂ��Ă����B �@���̋ߑ�s�s���Ɍo�ϓI�]�T�����܂��ɂ�āA�ށE�ޏ���͉���M����W�F���g�� �B�K���ȂLjꕔ�̎x�z�w��x�T�w���s���Ă������܂��܂ȓ����������K���������������s���悤�ɂȂ��Ă������B���̓����͎q�r�ł͂Ȃ��A����L�⏬���ȂǍ����y�b�g�̎嗬���Ȃ�������ʂ��Ăł������B�������ăy�b�g�������Ċy���ލs�ׂ��㗬�K�����牺�̈�ʎs���w�Ɍ������čL�����Ă������B �@�p���̃y�b�g�̎��瓪���́A�Y�Ɗv�����o���ߑ�s�s�����������Ƃɂ���Ă��̐��������Ă������B���̗���͒x��Ă킪���ł��N�����Ă���B���{�ł͋Z�p�v�V���O���ɏ��͂��߂����a30�N��̍��x�o�ϐ������ɂȂ��Ĉ�ʉƒ�ɂ����Đ������y�b�g��������悤�ɂȂ����i��1�j�B �@�y�b�g�͍H�Ɖ��Љ�ɔ����J���̂��߂ɉƂ𗯎炪���ƂȂ����v�╃�e�̂��Ȃ��j�Ƒ��������ƒ�ɓ�����悤�ɓ��荞��ł��̐��𑝂₵�Ă������B���Ƒ��i�q�ǂ��̂��Ȃ��v�w�݂̂̉ƒ��q�ǂ��̏��Ȃ��ƒ�j�̐�����P�g�҂ɂƂ��ăy�b�g�́A��������Ƒ��̐�����₤�㗝�Ƒ��i�[���Ƒ��j�Ƃ��Ă̖�����S���Ă���B �@�y�b�g�����͎q�ǂ��̑���ɂȂ邾���ł͂Ȃ��A�S���I�[������������_�ɂ����ĕs�݂̕v�╃�e�̑���ɂ��Ȃ�B���Ƒ����̍s�����́A������q�ǂ����������ĉƂ��o�Ă������Ƃɂ���ĕv�w�݂̂̉ƒ�ƂȂ�A���̌㔺���ɐ旧�����Έ₳���҂̓V���O���ƂȂ�B���Ƒ���P�g�҂̑����ƁA�y�b�g�̑����Ƃ̊Ԃɂ͐[�����ւ�����ƍl������B �� �y�b�g�́A���Ɖƒ{�ł��� �@�����A�p���pet����{��ɒ����Έ��ߓ����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�܂��Apet�͌`�e���ł�����A���߂���Ƃ��A���C�ɓ���̂ȂǂƖ��B�����{���Ƀy�b�g�����ߓ����Ȃ̂��낤���B�y�b�g�Ƃ������t������������̃X�R�b�g�����h�l���A�y�b�g���ǂ̂悤�Ɍ��Ă�������m�邱�Ƃ́A�y�b�g�Ƃ͉����𗝉����邤���ő����̎�����������Ǝv����B����āA��������l���������߂Ă݂����B �@�r���ƒ{�����ꂽ�̂́A������1���Q��N�قǑO�̐��A�W�A�ł������Ƃ����B����̓A�W�A���t�����Ƃ����쐶��Ƃ����B�r�̉ƒ{���͓⋍��n�����Â��A���������Ă����Ƃ������ɐl�ނ�������炵�Ă���B �@���^�̑��H�b�ł��������߂ɗr�͎�Ȃ����₷�������̂��낤�B����ɐ�Ƀg�}�X�E���A�������悤�ɗr�͏��H�ł���Ƃ������Ƃ������₷���v���ł������Ǝv����B���̗r���p���ł�16���I���납�瑝���Ă������B �@�ƒ{�Ƃ��Ă̑��̏����́A���ƂȂ����l��ꂵ�Ă��邱�Ƃł���B�l���������U�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ���{�ł���A�r�͑����̓����̒��ł����Ƃ����̓K�������������Ǝv����B���̓_�ł̓y�b�g�Ƃ��Ă̏����Ƃ������ł���A���łɓ鉻�������ƒ{�̒�����y�b�g���I�ʂ���Ă��������Ƃ͗��ɂ��Ȃ��Ă���B �@�ł́A�y�b�g�Ɩ������ꂽ�������A�������猢��L�ł��悩�����Ǝv����̂����A�ǂ����Ĕނ�ł͂Ȃ������̂��낤�B�ނ���l�ԂɎ���ꂽ�Ƃ����_�ʼnƒ{�ł��邱�Ƃɂ͂����Ȃ����A16���I�̃X�R�b�g�����h�ɂ��������L�͂����B �@�y�b�g�Ƃ������t�����܂��O���炷�łɌ����������炷��K�����p���̈ꕔ�̕x�T�w�ɂ͂������B����͈��ߗp�Ƃ��Ď����X�p�j�G�����Ȃǂł��������A�����̌��Ƃ����A�唼�͔Ԍ���q�r������Ȃǂ̍�ƌ��ł���g���������B �@�܂��L���M���ȂǂɎ���ꂽ�ꕔ�̈��ߗp�������ẮA�l�Y�~��߂铹��Ƃ��Ă̑��݂ł����Ȃ������B������ނ�̑����͊O��������{�ł���A���������[���╨�u���J�̂�����Ȃ��������Z���������B �@�����A�ƒ{�Ƃ����ƁA�H�ׂ邽�߂��є���Ƃ邽�߂̎Y�Ɠ������A���܂��܂ȘJ���ɗp����g�����w���Ă���B�������L�`�ɂ́A�y�b�g���l��������炵�������Ƃ����_����ƒ{�ɑ����Ă���B �@���̃y�b�g���l�Ԃ����킢�����Ĉ����ΏۂƂ��ėp����_�Ŏg���̈��ł���A����̓Z���s�[�h�b�O���l�Ԃ̖����̂��߂Ɏg����ƌ��ł���Ƃ����_�œ������g���ł���B �@�������y�b�g��������l����́A�����̎q�͉ƒ{�ł��g���ł�����܂���A���̎q�͎��̉Ƒ��ł��A�Ƃ����������Ԃ��Ă��邾�낤�B����ɁA�����̎q�̓y�b�g�ł͂���܂���A���̎q�ǂ��ł��Ƃ�������ɂ������Ȃ��B �@�����[�����ƂɁA�y�b�g�������D���Ȑl�̒��ɂ́A�y�b�g�Ƃ������t���D���ł͂Ȃ��l�������B����̓y�b�g�Ƃ������t�ɂ́A�������̂ł���ɂ�������炸�����y��������y�Ȉ��ߕ��Ƃ����悤�Ȉ�ۂ����邩��ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�܂��A�y�b�g���D�ƂƂ����\�������l�ɍD�܂�Ă��Ȃ��B�y�b�g���D�Ƃ͉p��ɂ���ƃy�b�g���o�[�Y�ɂȂ�B�y�b�g���D�ƂƂ���̂͌������A�y�b�g���o�[�Y�Ȃ�ǂ��ƌ������l�������B�p��Ȃ�ǂ����A���{��͍D�܂����Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤���B�܂��ƂɌ��t�͓���B �@���ߓ����Ƃ����p����A�l���Ă݂�Ί�Ȍ��t�ł���B���߂́A�����߁i���Ă����j�ԂƏ����B�����邱�ƂƁA�ߋ�̂悤�ɂ��Ă����Ԃ��ƂƂ����݂��ɑ�������悤�ȍs�ׂ����L����Ă���B �@����͈����Ȃ������ł̓I���`���̂悤�ɂ��Ă�����ł��悢�Ƃ������ƂȂ̂��낤���B����Ƃ������Ă��悢���A���Ă�����ł��ǂ���ł��悢�Ƃ������ƂȂ̂��낤���B���̂悭�킩��Ȃ��������Ă����ԑΏۂɂ���鐶�����̂����ߓ����Ƃ������ƂɂȂ�B �� �y�b�g�ƈ��ߓ����͈قȂ� �@�������A�y�b�g�Ƃ������݂́A���̌��t�����C���[�W���܂߂āA����قnjy�����̂Ȃ̂��낤���B�p��̃y�b�g�ɂ͈��ߓ����̈Ӗ������͂��Ƃ��ƖR�����B���̌��t���g���n�߂��X�R�b�g�����h�̐l�тƂ͓�������u���߂��铮���v�Ƃ��u���ߑΏۂɗp���铮���v�ȂǂƋK�肵�ėp���Ă͂��Ȃ������B���̂��Ƃ��ڂ������Ă������B �@�����_���n�E�X�p�a���T,1980.�ɂ��A�y�b�g�̌ꌹ�͐��m�ɂ͂킩��Ȃ����A�����炭�Ƃ��āA���̓�̐��������Ă���B���́Acade lamb�i�e���痣���Ď���ꂽ�q�r�A���邢�͐l�Ԃɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�q�r�j�Ɠ����Ӗ��Ƃ���pet lamb�@���g��ꂽ���A���̋t����i����Ȃǂ��؏��E�ό`������j��pet�ł���Ƃ����B �@���Ȃ킿pet�́A���Ƃ��Ƃ́u�ƒ{�̎q���l�Ԃɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�v�Ƃ����Ӗ��̌`�e�����������Alamb������������pet�������`�Ƃ��Ă��c�������̂ł���Ƃ��������ł���B�����ŋ����[���̂́A�p��ɂ́Apet�ɐ旧����cade�Ƃ����u�����̎q���e���痣��Đl�ԂɈ�Ă�ꂽ�v�����ŕ\�킷�`�e��������Ƃ������Ƃł���B �@cade�́A�����_���n�E�X�p�a���T�ɂ��A����E���p��Ƃ���14~15���I����ɐ��܂ꂽ�Ƃ����B���̂��Ƃ́A16���I�Ƀy�b�g�Ƃ������t�����܂��O�ɉ��炩�̎���ɂ���Đe�̗r����q�ǂ������������āA�l�Ԃ���Ă�s�ׂ����łɍs���Ă������Ƃ������Ă���B �@�����Ќ���p�a���T,1976.�ɂ��Acade�͂���Ɍ��肳�ꂽ�Ӗ��������A����́u�i�ƒ{�̎q���j��e�Ɏ̂Ă��莔���ɂ��ꂽ�v�Ƃ����`�e���ł���Ƃ����B��������́A�l���q�ǂ��̓��������ߗp�Ɏ莔�������Ƃ������A��e�Ɉ玙�������ꂽ�ƒ{�̎q��{�傪����Ɉ�Ă��Ƃ����j���A���X�����������Ȃ��B �@�܂�pet��cade�͓��ӌ�ł��낤�Ƃ����̂��A�����_���n�E�X�p�a���T�̐���ł���B����ɏ]���A���Ƃ��ƃy�b�g�ɂ͈��ߓ����̈Ӗ��͂Ȃ��A�u�l�Ԃ���Ă铮���v���Ȃ킿�u�莔�������v�ł���u���瓮���v�Ƃ����̂����m�ȂƂ���ł����i��2�j�B���Ȃ킿pet�́A����cade�Ɠ����悤�ȈӖ������Ŏg��ꂽ���A���̌ォ�킢���鈤�ߑΏۂƂ��Ă̓����ɉp�ꎩ�̂��Ӗ����e���ϑJ���Ă������ƍl������B �@�����_���n�E�X�̑��̐���́Apetty lamb�i�����ȃ����j���Z�k����pet�ɂȂ����Ƃ������̂ł���B���̐����q�r�i�����j����݂ł��邱�Ƃ́A���ڂ��Ă����������A������͏������ilittle, small�j���Ӗ�����petty��R���Ƃ��Ă���B����petty�́A���p��i11~15���I����g�p���ꂽ�p��j��pety (small, minor�̈�)�R�������Apety�͒��t�����X���petit�i���{�ł̓v�`�Ƃ����Ă���j���炫�Ă���B �@���̂��߁Apetty�̌ꌹ���t�����X���petit�ł��邱�Ƃ���Apet�̌ꌹ���t�����X���petit�ł���Ƃ��錩��������B���������̂��Ƃ�������petit ��pet�̌ꌹ�ł���ƌ��߂�̂͑��}�ɉ߂���Ƃ������̂ł���B�����_���n�E�X���q�ׂ�悤�ɁApetty lamb�i�����ȃ����j�����[�c�ł͂Ȃ����Ƃ����ɗ��߂Ă��������ǐS�I�Ƃ������̂��낤�B�����Ă��̓�ڂ̌������A�y�b�g�����ߓ����ł͂Ȃ��B �@���̓�̐�����������Ó��Ȃ��̂Ƃ��ē����̊܈ӂ���y�b�g���`���Ȃ����A�u�e���痣��āA�l�Ԃɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�q�r�Ȃǂ̗c��ȓ����v�Ƃ������ƂɂȂ�B���ꂪ�p���l�̌����y�b�g�ł��������A�����̓��{�l�̃y�b�g�ςƑ傫���������Ă���ƌ��킴��Ȃ��B�p�ꌗ�ł́A���݂ł��y�b�g��l����Ă鎔�瓮���̈Ӗ��������c���Ă��̌��t���p�����Ă��邪�A�킪���ł͂��̂悤�ȈӖ����܂�Ŏg���Ă͂��Ȃ��B �@�y�b�g�̔��˒n�ł���p���̎����m�炸�ɁA�y�b�g�Ɉ��ߓ����̈Ӗ�������ϋɓI�Ɏ������ă}�C�i�X�C���[�W�����グ�邱�Ƃɂ���Ă��̒n�ʂ��߂Ă������̂́A���ł��Ȃ������̎��������g�ł͂Ȃ��������낤���B �� �p���l�̍l����y�b�g�̂R�v�� �@���j�Ƃ̃L�[�X�E�g�}�X�́A�p���l�̃y�b�g�̗��j�ׂ����ʁA�y�b�g�̂R�v���i�y�b�g�𑼂̓����Ƌ�ʂ���O�̓����j�������Ă���B �@����́A(1)�y�b�g�͉Ƃ̒��ɓ��邱�Ƃ��ł����B(2)�X�ɖ��O���t�����Ă����B(3)�����Đl�Ԃ̐H���ɂȂ�Ȃ������A�ł���Ƃ����i�L�[�X�E�g�}�X���A�R����Ė�A�l�ԂƎ��R�E�`�ߑ�C�M���X�ɂ����鎩�R�ς̕ϑJ�A�@����w�o�ŁA1989�N(����1983�N)�A162-171�Łj�B���Ȃ킿�A�y�b�g�͎������炵�A���O�����A�H�ׂȂ��Ƃ������̂ł���A����3�_��������Ă��Ȃ���Ήp���l�̓y�b�g�Ƃ͍l���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �@�����u���ߑΏۂɂ��铮���v�Ƃ����킩��ɂ������ۓI�ȊT�O�����ł̓y�b�g�ł���Ƃ͔F�߂Ȃ��̂ł���B���̓_�A���{�ł̏]���̌��̎������́A���O�����邱�ƂƐH�ׂȂ��͂悢�Ƃ��Ă��A���{༁i����j�ȂLjꕔ�̏��^���ߌ��������đ����͊O�����������B �@���{�l�̌��̎������Ƃ����A�]�����Ƃ̊O�Ɍ�����������Ď������A����Ƃ̎��͂ɕ��������ɂ��Ă���Ƃ����̂���ʓI�������B���̂悤�Ȍ��̊O�����̏K�����ꕶ����̓ꕶ��������ŋ߂Ɏ���܂ŕς�邱�ƂȂ��Â��Ă����B �@���݁A���{�Ŏ����Ă���8���̌��L�͎�������Ɉڍs���Ă��邪�A�c���2���͍��ł��O�����������E���O���X�Ŏ����Ă���i2015�N�A�y�b�g�t�[�h����ׁj�B�p���l�̊��o���炢���ĊO�����̌��̓y�b�g�����ł͂Ȃ��A�ނ�����āA�����Č��݂��������Ă���悤�ɔԌ���q�r���Ȃǂ̎g���ł���B �@��������16���I�����̉p���̌��͊O�����̂��ߓD���炯�ŕs���������B���̂��ߎ����ɓ�������Ԃł͂Ȃ������B���̓_�A���܂ꂽ�Ă̎q�r�͏��X���������ŁA�����ɘA�ꍞ��Ńy�b�g�Ƃ��Ă��킢����ɂ��\�����Ȃ������B �@�q�r�Ɍ��炸�M���ނ̐Ԃ�V�������ň�Ă�A�y�b�g�͂����Ɏ�����Ɉ����s���������Ă���B���̎q���O�̌Q��ɋA�����Ƃ͔E�тȂ��v��ꂽ�����낤���A�܂��ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��������낤�B �@�����A�q�r�̗{�炪�ł��Ȃ��Ȃ�����r�̑���Ɏ����傪��Ă��̂��y�b�g�̎n�܂肾�������A�����n�߂Ă��邤���ɂ��킢�炵���Ȃ��Ĉ����������悤�ɂȂ��Ă������Ƃ����̂����������̏��ł͂Ȃ����낤���B �@�Ȃ��`���Ɏ������I�b�N�X�t�H�[�h�p�ꎫ�T�ɂ��A�y�b�g�ɂ͂�����̉B�ꂽ�Ӗ�������Ƃ����B����͔N���̂��킢���j�̎q�̈��l�Ƃ������̂ł���B���̏ꍇ�̃y�b�g�͓����ł͂Ȃ��l�Ԃł���A�N�Ⴂ�j�̈��l��\���Ă���B����͈��ߓ����ł͂Ȃ����ߐl�Ԃł���B�l�Ԃ��y�b�g�ɂ��邱�Ƃ́A�l�Ԃ̋[�y�b�g���ł���A�[�������ł���B���̈Ӗ��ł̗p�����́A�̂��̂��B��̂悤�Ɏg���Ă������Ǝv����B �@�ȏ�܂��������ŁA�I���ɕM�҂̍l���鍡���ɂ�����y�b�g�̐V�R�v���i�y�b�g�Ǝ�����̊W��\���O�̓����j�����������Ǝv���B����͈ȉ��ł���B
�@��̃L�[�X�E�g�}�X�̂����y�b�g�̂R�v���́A�y�b�g������O�ʓI�Ȏ����ł������̂ɑ��A�M�҂̓y�b�g�Ǝ������������ʂ̊W�ɖڂ����������Ǝv���B�Ƃ����̂́A����܂��܂��l�X�̃y�b�g�Ƃ̂����������ς���Ă����Ǝv���邪�A����͂ЂƂ��ɗ��҂̐S�̋���������ɋ߂Â��Ă����ƍl�����邩��ł���B �@�y�b�g�����́A�����ɂƂ��Ĉ�i�Əd�v�ȑ��݂ɂȂ��Ă������Ƃ��\�z�����B���̗���͂��͂�~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��߂肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤�B���������鍪���̂ЂƂɌ������芪���s����Ȏ���w�i������B�����ł�������w�i�Ƃ́A�C��ϓ��ɂ�鎩�R���N�������܂��܂ȍЊQ�̖҈Ђ������Ă��邱�ƂƁA�l�Ԃ��N���������ɂ��R���I���Ђ������Ă��邱�Ƃ̗��ʂ�����B �@����ɂ́A�V�ЂƐl�Ђ̋�ʂ����Ȃ��悤�ȕ��G�ȏ�����B���Ƃ��A������ꌴ���̕��˔\�������݂Ă��A�����͒n�k�ƒÔg�ɂ�鎩�R�ЊQ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�������s���̎��ԂɂȂ�瓝��ł��Ȃ����炢�ɋ��剻���������q�͔��d���������ʁA���o�����ʂ̕��ː������̎n���ɍ��㉽�\�N�������Ȃ܂�Ă����˂Ȃ�Ȃ�����Ȃǂ́A�����͈��S�ŃN���[���ň������ƌJ��Ԃ������Ă����������i�҂̌���M��������ɋN�������s�K�ŋ����Ȑl�ЂƂ��������悤���Ȃ��B �@���̂悤�ɉ��ɂ��т��Ă���̂����悭�킩��Ȃ���̌����Ȃ��s���Ȏ���ɂ����āA������_�I�Ɏx���A�S�Ɉ��炬��^����y�b�g�͑z���ȏ�ɏd�v�Ȗ�����S���Ă���B����䂦�y�b�g�������A�܂��܂���Ȑl���̃p�[�g�i�[�ƂȂ��Ă������Ƃ͋^���悤�̂Ȃ������ƂȂ��Ă���B �@�i���P�j���{�Ɖp�����r�����Ƃ��A�����̑����ɋC�Â��B�܂����҂͒n���I�ɑ嗤����͊C���u�Ă����قǑ傫���Ȃ������ł���C�m���Ƃł���i���y�ʐς͓��{�̕����p������1,5�{�قǑ傫���B���Ȃ݂ɓ��{�́A�嗤���ƃh�C�c�┼�����ƃC�^���A�����L���B����ē��{�͏����ȓ����Ƃ͂����Ȃ��j�B�Ƃ��ɍc���i�����j���������N�卑�ł��邪�A�c������`���Ƃł���B���{�l�ƃC�M���X�l�́A���Ǘ��������y�̒��ŁA�K�v�Ȃ��͎̂��������ōl�����������ō��グ��Ƃ����Ɨ������̈ӎ��������_�ł����Ă���B �@�p���͗r�������ĖѐD���Y�ƂW�����čH�Ɖ����͂��������Ƃɑ��A�킪���͗{�\�i�J�C�R���� �{�ł��B���Ă͓��{�̑�\�I�ƒ{�Ƃ�������̂��A�J�C�R�邾�����j�ɂ���Č��D���Y���A�a�ы@���J������Ȃǂ��čH�Ɨ����̓�����ݎn�߂��B�g���^�����Ԃ����̎����D�@���Ђ���n�܂����̂́A���̗ǂ���ł���B �@�킪���͍]�ˎ��ォ��哌���푈�܂ł̏��a�̊ԁA�C�O�ɗA�o���ĊO�݂��҂�����̂Ƃ������̌��D�����炢�����Ȃ��n�������������B���̊ԁA�J�C�R�͓��{�l�ƍ��Ƃ��x���Ă��ꂽ�B���̂��Ƃ͋L������Ă����Ă悢�B �@�i���Q�j�b��t�@�ł́A���瓮���́u�l�����炷�铮���v�i��P���̂Q�j�ƒ�`����A�u�b��t�́A���瓮���Ɋւ���f�Ëy�ѕی��q���̎w�����̑��̏b�㎖�������ǂ邱�Ƃɂ���āA�����Ɋւ���ی��q���̌���y�ђ{�Y�Ƃ̔��B��}��A���킹�Č��O�q���̌���Ɋ�^������́v�i��P���j�Ƃ��Ă���B�@�@�@�@�܂����瓮���́u���A�n�A�߂�r�A�R�r�A�A���A�L�A�{�A�����炻�̑��b��t���f�Â��s���K�v��������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂Ɍ���B�v�i��P�V���j�Ƃ���Ă���B �@���瓮���̔��ӌ�ɓ�����̂́A�쐶�����ł��낤�B�쐶�����͎��瓮���ł͂Ȃ��B�b��t�@�ł͖쐶�����͐f�Â��s���b�㎖�̑Ώۓ����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�������A�b��t�̒��ɂ͏�������a�C�������쐶�����̎��ÂɐϋɓI�ɂ������l������B���̖����N���A���邱�ƂɊւ��āA�ȉ��̉��߂��l������B��́A�쐶�������b��t��A��Ă����l���ی삵�����_�ŁA���瓮���Ƃ݂Ȃ����ƂŎ��Â��\�ɂȂ�Ƃ������̂ł���A���̈�͖쐶���������Â��邱�Ƃ́A�l��ƒ{�ւ̊����Ǔ��̕a�C��\�h���A�g���j�~����Ȃnj��O�q���ɂ�����邽�߂ɍs����Ƃ������̂ł���B
|
||||||||
�@�y�b�g�����ߑΏۂƂ��ď�����Ȃ����Ǝv�����Ƃ��琶���鎔����̍߈����Ɖ����̔O��a�炰�邱�Ƃ��A�y�b�g���X�E�P�A�ɂ�����d�v�ȉۑ�̈�ɂȂ��Ă���B�����傪���������ڂƂȂ邱�̐S�ɂ��������Ȃ���A�l�͍��゠�炽�ɓ��������ƗǍD�ȊW��ۂ��Ȃ����炵�Ă������Ƃ͍���ɂȂ��Ă����Ǝv���B �@�l�Ԃɂ̓y�b�g��r���Ă��ӂ����єށE�ޏ�����������Ƃ�e�F���A�����[�������邾���̂�����ׂ������ȗ��R������̂��B���͉��ė��̃y�b�g�Ƃ̕�炵���������ɐi��ł��邩��A���{�̃y�b�g���������������x��Ă��邱�Ƃ����������̂ł͂Ȃ��B�y�b�g���X�̃T�|�[�g�Ɋւ��Ă��A���{���ǂ�قnj�i���Ȃ̂�����ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��B �@�y�b�g���X�̃O���|�t�P�A�Ƃ��Ă̎��g�݂͉��Ăɔ�ׂĊm���Ɏ�x��͂����B������������Ƃ����ē��{�l���y�b�g���X�ɖ��S�������킯�ł͂Ȃ����A���{�Ƀy�b�g�̎��ʑ̌��҂����������x���X�L�����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B����A�ނ���`���I�Ȃ��̂���ŋ߂̂��܂��܂ȃy�b�g���X�E�O�b�Y�̓o��Ɏ���܂őr�i���j�����z���邽�߂̓w�͂�����A���܂��܂ȑΏ����@�����݂��Ă���B �@���āA�����{�l�ł���ꕶ�l�̐������������Ƃ��悭�c���Ă���̂��A�C�k�̐l�тƂ��Ƃ�����B���̐l�тƂ͎�̏W�����������ߖ쐶�̎l���b�⋛��߂��ĕ�炵�Ă����B�Ȃ��ł���^�b�̃N�}�͍ő�̂��������������B�ނ�̓N�}���E�Q���ĐH���Ă����B �@���̃A�C�k�ɂƂ��Ă����Ƃ���ȍՂ肪�C�I�}���e�Ƃ���N�}����̋V���ł���B�C�I�}���e�Ƃ̓A�C�k��Łw����𑗂�x�Ƃ����ӂł���A�ԗ�̋C���������߂ăN�}�̍����ɂ��̐��ɑ���o�����߂ɍs��ꂽ�Ƃ����B �@����ɂ͗t�Ƃ��ĎR�ɕ��������ăN�}���ˎ~�߂��̂��ɍs���V���ƁA�q�O�}��ߊl�����ꍇ�A�A��A���đ傫����Ă����ƎE�Q���čs���V�������邪�A��҂̕�������ɍs�Ȃ�ꂽ�Ƃ����i�����v�a���A�A�C�k�E�_�X�Ɛ�����l�X�A���w�فA1995.�Q�Ɓj�B �@����͖쎔���̖쐶��ł͂Ȃ��A���ƒ{�������莔�����������߂Ɉ������N�������낤���A���̌�E���ĐH�ׂ��̂�����{���ł�������߈�������߂����ɂ��P��ꂽ�ł��낤�B �@�������ނ�́A���̕����ڂƂȂ镡�G���܍ߊ����������ɍςނ悤�ȃN�}�̎����ς⑼�E�ς���肠���Ă����B�A�C�k�ɂ��A�N�}�̓J���C(�_)�ł���A�}���v�g�i�܂�тƁA�q�j�ł����āA���̐��ł͐l�ԂƓ����p�����ĕ�炵�Ă��邪�A���̐��ɍ~��Ă���Ƃ��̓N�}�̈߂�g�ɂ܂Ƃ��������Ă���Ă���Ƃ����B �@�Ȃ��n��ɂ���Ă���̂��Ƃ����A����͐l�ԂɎ����̑̂��~�A���Q�Ƃ��ė^���邽�߂��Ƃ����B�~�A���Q�Ƃ́A�����ǂ���g�������邱�Ƃł���A���̓��{��ɂ����錾�t���y�Y�i�~���Q�j�ł���B�A�C�k�w�҂Ŏ�����A�C�k�̒m���^�u�ۂ́A�����q�ׂĂ���B
�@���̈���ŁA�A�C�k�̓N�}���`���}���e�v�i���炪���Ƃ���́j�Ƃ��̂��Ă���B�A�C�k�̐l�X�ɂƂ��ăN�}�͐l�Ԃɕ߂����邽�߂ɂ���̂ł��邪�A����ɂ͐₦�邱�ƂȂ���ɃN�}���R�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂǂ��������Ƃ����A�N�}���d���߂��̂��A�ނ�̍D�ސH�ו��₨����������������Ċ��ӂ̋C������\���A���̐��ɂ��ǂ�Ƃ��ɂ�������Ɏ����čs���Ă��炤�B �@��������̃~���Q����������N�}�͂��̐��ɋA���Ă����A���Ԃ��ĂъĐ���ȉ�����J���Ă��ĂȂ�������B�����Ŏ����͂ǂ������̒N�Ɏˎ~�߂�ꂽ���A�����ւd�ɍՂ��đ���o���Ă��ꂽ�ƌ��B �@����������̎҂������A�����������ƂȂ�Ύ������ǂ������̒N�̂Ƃ���ɍ~��Ă����Ďˎ~�߂��悤�ƌ��߂�B�{�l���܂������s�����Ǝv���B�������ăA�C�k�͖��N�N�}����ɓ���A�L�Ɍb�܂��B �@���̂悤�Ȃ��̐��Ƃ��̐����s��������N�}�̎��ƕ����Đ��̕���������Ƃɂ���ăN�}���ˎ~�߂ĐH�ׂ���є�ɂ��Ă������߈����⏞�i���ȁj���̔O�ɉՁi�����ȁj�܂�邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă������Ǝv����B �@�N�}����̋��V���Ȃ��s�����Ƃɂ���āA�N�}�̍��͖������ƂȂ����̐��ɋA���Ă������Ƃ��ł���킯������A�c�����N�}�̖є�����A�̂�荏��ŐH�ׂĂ��Ƃ��ɍ߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��l�����ɂ������Ȃ��B �@�A�C�k�̐l�тƂɂ��A�N�}�͂��̐��ɗ���ړI��m���Ă��邵�A�N�Ɏˎ~�߂��邩���m���Ă���B����ɂ́A���̐��Ƃ��̐����ړ����Đ����邱�Ƃ��m���Ă���B�܂�A�N�}�͏��߂��玩��̉^�������ׂĒm���Ă���̂ł���B�����ł���A���͂�N�}�͂����̂����̂ł͂Ȃ��_�ق�тт����b�ƂȂ�B���̔������Ԃ�̂������Ƃ��������ȃA�C�k�̃N�}�������ǂ��l������悢�̂��낤�B �@������������N�}���E���Đ����Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ������l�X�����������̍s���𐳓������A������S�����Ă����ɂ́A�N�}�������̓]�����J��Ԃ��ē��̂Ɩє��l�Ԃɒ��Â��鑶�݂ł���Ƃ��铮���ς��K���������Ƃ�����B �@�N�}��_�ɂ܂肠���đ�Ɉ����ė��z������p�́A�N�}�̎E�Q�ɂ���Đ��܂��߂̈ӎ���\����Ȃ��@���邽�߂̍����������v�z�Ƃ�����(���̂��ƂɊւ��ẮA�~���҂̕����̒��삩�玦������)�B���̂Ƃ��A�����Ƃ��ĕ�������N�}����ԂƂ������H����x��̐��X�́A�l�ԎЉ�Ŋ�����̂��Ƃɂ���č\������Ă���B �@���̂悤�ɑ����̋V����݂Ă��A�N�}�͐l�ԂƂ��ă~���[�V�X�i�͕�j����Ă��邪�A���̃N�}�̐l�i���̓A�C�k�ɂƂ��āA�����Ă����炭�����{�l�ɂƂ��Ă��N�}�������ɑ�ȑ��݂ł�����������Ă���B���̂悤�ȓ����ւ̎v�l�́A����ɂ܂Ŏp����ăy�b�g���X�̌��҂̐S���Ɍ��o�������Ƃ��ł���B �@�y�b�g�̎���A������͂��̃y�b�g�������ɗǂ��q�ł���f���炵���q�ł����������v���A�l�ɂ��������B�������̂悤�Ȏq�͓�x�Ƃ��Ȃ��ƐS����v���B�����̎q�ǂ��̌��i���Ƃ킴�j�ɂ���u���ʂ�q�͌��ڂ悵�v�A���Ȃ킿�������ʎq�́A��ʂ��ǂ����̂ł���A�Ƃ����S���̓y�b�g���X�ߒQ�҂��܂����������ł���B �@�܂��A������͐_���ɂʂ������悤�Ƀy�b�g�̂����ɐ[�X�Ɠ��������č������A�Ԃ�������č�����B���̂悤�Ȍ����̓y�b�g��������l�X�ɂƂ��Ă͓��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ���������Ȃ����A���̂悤�ȕ��r�ɂ�������V���������s�ׂ̒��ɂ́A�����̗��z���⍇�������܂܂�Ă���B �@�Ȃ�����قǂɑr�����q���ق߂�����A������킹�Đ����̋F��������̂��B����͖��߂悤�̂Ȃ������ڂ����܂�Ă��邩��ł��낤�B�B���悤���Ȃ��قǑ傫���c��オ���������ڂߍ��킹����̂������̎]���̌��t�ł�����X�̗�q�Ȃ̂ł��낤�B �@���������邾�����������A�ق߂邾���ق߂����邱�Ƃɂ���ĕ����ڂƂȂ��Ă���߂̈ӎ��͕�ݍ��܂��悤�ɉB����Ă����B�����A�c�~�̌ꌴ�̓c�c���ł���A�c�c�~�B�����̂Ȃ̂��B�߂͔�ߎ��̂悤�ɉB���˂Ȃ�Ȃ��B�l�ɂ����Ԃɂ��A�����Ď���ɂ������ӎ�����邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B�������Ď�����̎���͂��낤���Ď���邱�Ƃɂ���āA�ꂵ���r������Ă������Ƃ��ł���B���̐S���@�������z���ł��荇�����ł���B �@�������́A�߂��݂�߈����⎩�ӂ̔O�Ȃǂ̕s�����ȑ̌��������B�܂��A�s����|���������Ƃ��D�܂Ȃ����A���M��r����������ɂ����Ȃ܂�邱�Ƃ��h�����Ƃ���B�������ɂ́A���܂��܂ȋ�ɂ��������A�炢�̌��͑����Y���ȂǕs���ȕ�����L������g����邽�߂̐S�̂͂��炫��������Ă���B �@���̂͂��炫��S�I�h�q�@��(�P�ɖh�q�@��)�Ƃ����A�������邱�ƂŐS�͈��̈��肵����Ԃ��ێ����A�l�i�̓������i�S����ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂������Ă����ԁj��ۂ��Ă���B �@�y�b�g�ɋꂵ�݂�^���Ď��S�������Ɗ����Ă���悤�ȏꍇ�A������͓��R�̂悤�ɐӔC�̏d����Ɋ�����B���̗�ɂ��ꂸ�A�y�b�g�̎������z�Ƃ��鎀�ɕ�����قlj������̂ł������Ƃ��A������͔ۉ��Ȃ��ɍߐӊ���\���킯�Ȃ����������Ď��M�������Ă͗�������ł������̂ł���B �@�����̗}�������H���~�߂�ɂ́A���z�̘g�g�݂�ς��Ă��̎q�̎��͗��z�̎��ł͂Ȃ��������A���̎q�͗��z�I���݂ł������Ɨ��z�̒u�����������邱�Ƃɂ���Ď�����̕����ڂ͑��E����Ă����̂ł���B�����v�����Ƃɂ���Ď�����x����S���I�̐����h�q�@���ł���B �@����͊�����R�[�g���͂���A������V���c�P���ʼn߂������ƂƂ��قǕς��Ȃ����낤�B�������͂ǂ̂悤�ȉ^���ɖ|�M����Ă��A�Ō�܂ł������莩�Ȗh�q�͂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B �� �����̌�ǂ�������l�� �@�A�C�k�̃N�}�ςɘb��߂����B�ł́A�A�C�k�̐l�тƂ́A��̂悤�ȗ�I�X�g�[���[��^���b�Ƃ��Ė{�S����M���Ă����̂��낤���B����Ƃ��A���������̂���Ȃ�̂̂���c�������s���悭����Ă��ꂽ�@���I���b�Ƃ��ĐM����ӂ�����Ă��������������̂��낤���B���̐l�тƂ́A�����̃X�g�[���[���^�����ƂȂ��M������ł����Ǝ��͎v���B �@���ɃA�C�k�̐l�X���N�}���E�߂ĐH�ׂ邱�Ƃɉ�����܍߈ӎ��������Ȃ������Ȃ�A���̂悤�ɃN�}���[�l�����A�_�i��������̂��������邱�Ƃ��Ȃ��������낤�B����ɂ́A�E���ꂽ�N�}�̗삪���݂�{��̊��������Đl�Ԃɜ߂���ĕ��Q���邱�Ƃւ̂����ꂪ�Ȃ�������A��͂肱�̂悤�ȗ�I����Ɏd���ďグ��K�v���Ȃ������ɂ������Ȃ��B �@�l�Ԃ��N�}���d���߂�Ƃ��A�ނ�̏Z�ސ[�R�ɓ����đ��Ղ╳�Ȃǂ̍��Ղ�T���B�N�}�̂킸���ȍ��Ղ�����ƁA���̌�𒍈Ӑ[���ǂ��Ă����B�N�}����ɓ����ɂ̓X�g�[�J�[�ƂȂ��ĔM�S�Ɍ�����K�v������A�Ō�܂ł��������ǂ����Ďˎ~�߂��҂��r�̂悢�t�ƂȂ��i��1�j�B �@���̃N�}�̓A�C�k�ɂ��A���̐��Ƃ��̐��̊Ԃ��������藈���肵�Ă���ƍl���Ă���B�A�C�k���g�����l�ɁA���̐��Ƃ��̐��̊Ԃ܂�ς�莀�ɕς�肵�Ȃ��牝�҂��鑶�݂ƍl���Ă����i��2�j�B���̂��Ƃ́A�A�C�k�̓N�}��ǂ����߂Ă��̐��Ƃ��̐��̊Ԃ��s�������Ă���̂ł���A�����i������j�ƗH���i�������j���҂ɂ����ăN�}�̌�ǂ������Ĉړ����Ă���ƌ��邱�Ƃ��ł���B �@�A�C�k�ƃN�}�Ƃ̊W�ɂ��Ď������܂����Ă��ꂱ��q�ׂ����A���n�̓��{�l������ɂ�����ʐl�ԁE�����ς�����Ă����ƍl������B����͍����̎������̓����ɑ��鑨�����̂Ȃ��ɂ��ꕶ�l����₦�邱�ƂȂ�����邠�鋤�ʂ̐S��ƍs���Ƃ��ēǂݎ�邱�Ƃ��ł���Ǝv���B����͐l�Ԃ͂˂ɓ����̌�ǂ������Đ�����Ƃ������Ƃł���B �@��ǂ��́A�ǂ��Ă����������肪�l�ł��ꓮ���ł���d�v�ȉ��l������A���̑Ώۂւ̋�����S���������Ƃ������Ă���B�܂��A�ڋߗ~���������A�Ώۂ̂��Ɋ�肽���Ƃ��A�������Ă������Ă������Ȃǂ̂悤�Ɉ����t������S�����ۂł�����B �@�{�E���r�B�̈������_�ɂ��A��ǂ��͓��c������e�Ƃ̏�I�J�����߂Ď����T�^�I�Ȉ����s���̈�ł���A����͎q�ǂ����ړ��ł���悤�ɂȂ鐶��X��������̂͂��̎������猻��n�߂�Ƃ����B
�@�l�Ԃ̔��B�ߒ��ɂ������ǂ��́A���c�����l���b�̂悤�Ɏl����ɂȂ��ē�����i�K�ɂȂ�ƕ�e��T�����߂�s���Ƃ��Č����B�l�����s���\�ƂȂ�A�͂��͂������n�߂铮���I�i�K�Ɏ��������c���ɂƂ��ẮA�����Ƃ��S�̂���Ώۂł����e�ɂ˂ɐڋ߂��悤�ƌ��ǂ��Ă͂���邱�Ƃ͋ɂ߂Ď��R�Ȗ{�\�s���Ƃ�����B�l�ԂɂƂ��ď��߂ẴX�g�[�L���O����͕�e�ł���B �@����A�y�b�g��������l�́A�y�b�g�̂��ɂ˂ɂ������Ɗ肤�B�܂��A�y�b�g�����ǂ��ɂ��邩�������c�����Ă��������Ƃ��肤�B���Ȃ킿������́A�y�b�g�Ɨ��ꂽ���Ȃ����߂ɁA�y�b�g���ǂ��ɂ��邩���˂Ɋm�F���悤�Ɩڐ��ł��s���ł��T�����߂Ă���̂ł���A�ǂ����߂Ă���B���ꂱ�����y�b�g�̌�ǂ������Ă���p�Ƃ�����B �@��ǂ��s���́A�ǂ��҂̒ǂ���҂ւ̈����̕\��ł���ƂƂ��ɁA�ˑ����������̂ł�����B������ǂ��́A�����ˑ��S�̕\��ł�����B�y�b�g����́A�����傪���Ȃ��炸�y�b�g�ˑ����N�������Ƃ�O��Ƃ��Ă���B����͌��N�I�ōD�܂����K���I�Ȉˑ�����A�s���N�ŕa���I�ȕs�K���I�ˑ��܂ł��܂��܂ȃG�s�\�[�h���F�߂���B �@������̃y�b�g�ւ̈����ƈˑ��̓y�b�g�������Ă���ԂƂ͌���Ȃ��B�y�b�g�̎��セ��炪��苭�܂邱�Ƃ����邪�A����͌������v��̔O�Ƃ��Č����B����ȔߒQ�҂̒��ɂ́A�߂��݂Ƌꂵ�݂̂��܂�A���̎q�̂Ƃ���ɍs���Ă��܂������ƍl����l������B���̒Ǖ�̑z���������ő�̌�ǂ��S���Ƃ����邾�낤�B�������A���������s���Ɉڂ��l�́A�ɂ߂Ă܂�ł��邪�E�E�B �@�����̓��{�l�ɂƂ��Č�ǂ��Ƃ����A��ǂ��S�����ǂ����E��A�z����̂ł͂Ȃ����낤���B��ǂ��S���Ƃ́A�S���������l�┺���ȂLj�����l�̌��ǂ��Ă����ɂÂ��Ď��ʂ��Ƃ������B�S���Ƃ͖{���A�����̒j�������]�݂��Ȃ������Ƒ��Ȃǂ��A�ꂻ���Ă�������Ɏ��ʂ��ƂȂ̂ŁA�����^�C�����O�������ǂ��Ƃ͂��قȂ�Ǝv���̂����A�����͂��܂茵���ɍl���Ȃ��Ă��悢�悤���B �@�܂����{�l�́A��i���Ɓj������̈Ӗ��Ƃ��ėp���邱�Ƃ�����B���ɂ䂭�l�������̎���̂��Ƃ��₳���l�ɑ����Ƃ��u���Ƃ��X�������̂ށv�Ȃǂƌ������肷��̂����ꂾ�B���̗p�@�ł����ƁA��ǂ��͎���̐l��ǂ������Ă����Ƃ������߂ɂȂ�B �@������ɂ����ǂ��S���́A�旧�l�Ɨ��ꂪ�������߂ɒǂ������Ă������Ƃł���A���̂��߂Ɏ���̈ӎv�Ŏ��疽�����Ƃ������B����āA���₢�⎀�ʂ킯�ł͂Ȃ��̂Ō�����l�����Â�ɂ���Ď��ʖ����S���Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��Ȃ��B �� �c���ꂽ�҂͎��҂̐Ղ�Ő����� �@��Ȑl���������Čォ����Ă������Ƃ���ǂ��ł��邪�A�\�L�Ƃ��ĐՒǂ��Ƃ��������Ƃ�����B���̐Ղ�ǂ��Ƃ����\���ɂ͊�d�ɂ��d�v�Ȏ������܂܂�Ă���B�Ղ�ǂ��Ƃ́A�Ղނ��Ƃł�����B����͎��҂�ǂ��Ď��ʂ��Ƃ���ł͂Ȃ��A���̐��ɂ����Ď��҂̑��Ձi���������j�����ǂ邱�Ƃł�����B �@���̂��Ƃ��e�[�}�ɂ����a�̂�����B����͊������i�����������犙�q�����̉̐l�A���y�ƁA���ҁj��18���눤���镃�e��r�����Ƃ��ɂ�̂̂����ł���i�ȉ��́w�������W�x����j �Z�݂�тʂ������͉z���o�̎R���Ă��ɐe�̐Ղނׂ� �@�Ղ�ǂ��Ď��ɂ����Ƃ��������ɑ�������́A�S���Ȃ����l�̐��U���ӂ�Ԃ�A���̐l���ǂ̂悤�Ȑl���𑗂����̂����ڂ݂邱�Ƃ�A���҂Ǝ����Ƃ̊Ԃɂ��������Ƃ����߂Đ[���l���Ă������Ƃ���ł���A�������Ă��̐��ɂ����Ď��҂̑z�����p���ł������Ƃ��c���ꂽ�҂̂Ȃ��ׂ����Ƃł͂Ȃ����Ƃ����B �@���Ȃ݂ɁA�����̕��e�͐_��i����ʂ��j�ł���A���Ƃ͐_���̉ƌn�������̂ŁA�����̏���݂Ă���͐_�E���ɂ߂Ă������Ƃ��Ɗ�����͂��Ƃ����Ǝv����B����̏����������Ă��A�����͌�ǂ����v���Ƃǂ߂āA���̌�������Ă������B �@������50�̂Ƃ��o�Ƃ��A����8�N��A���Ď��炪����������A�ނ����A�J�s�A�Q�[�A��n�k�̍ЊQ���߂��ڂŌ��߂A����𗬂��悤�Ȕ����łÂ����s�v�c�Ȑ��M�������B���ꂪ�u�䂭�͂̂Ȃ���͐₦�����āA�������A���Ƃ̐��ɂ��炸�v�Ŏn�܂�w����L�x�ł���B�������́A�w����L�x��������4�N���62�ő��E����B������800�N�O�̐l�ł���B �@���̓y�b�g���X�ɂ����Ă�������́A���l�Ƀy�b�g�̐Ղ�ǂ����Ƃ��ۂ����Ă���Ǝv���B���̎q�ɂЂƂ߉�����A���̎q�����܈�x�������������A���̎q�̂���Ƃ���֍s�������Ƃ��������v��̏�ɂ�����̂��y�b�g�E����哮���Ƃ̕ʂꂾ�B �@�����A������ݍ���ŖS���Ȃ������̎q�̈ꐶ���ӂ�Ԃ�A���̎q�̌��������������Ƃ͂Ȃ����̂��B���̎q�͉��̂��߂Ɏ��̂Ƃ���֗��Ă��ꂽ�̂����ڂ݂�B���̎q���c���Ă������܂�������Ă��Ȃ���������̂��݂₰�|����͈ꐶ���̂��݂₰��������Ȃ��\������A������ɂ͖��J���̂��݂₰���Ђ��Ƃ���Ƃ��c���Ă���B���ꂪ�r���ɂ����Ĉ₳���ߒQ�҂��Ȃ��ׂ��d�����Ǝv���B �@���̎q�͂�����������Ă��ꂽ���ƁB�����ŐS�̐������Ȏq���������ƁB�Ō�܂Ő����悤�Ƃ�������q���������ƁB�ǂ���Ƃ��Ă����K�����Ƃ������B������A���̎q�̐��_�����ݎ���Ďp���ł������Ǝv���B���̎q���狳�������������̂��Ƃ����Ɏ��߂āA���ꂩ��������Ă����B �@���ꂪ�A���̎q��^�ɐ��������Ƃł���A���̎q�ւ̂�����̉��Ԃ��ł͂Ȃ��낤���B�������邱�Ƃ��A�ő�̂����{�ł���A���̎q�̐������������̒��ɍ��ނ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B �@���̈Ӗ��ŁA���̎q��ǂ��������Ƃ͂��ꂩ��������ƂÂ��B����͔ߒQ���痧�������Ă��Â���������Ȃ����A�ꐶ�����邩������Ȃ��B����A�ꐶ�������Ă��S���͂Ƃ��Ȃ���������Ȃ��B�����ƂȂ��Ďc�镔���́A�����Ɏ����z���āA����ɂÂ��Ă����̂�������Ȃ��B �@�i���P�j�X�g�[�J�[�͉p��̃X�g�[�Nstalk�ɗR�����A���Ƃ��Ɗl���̓����ɔE�ъ�邱�Ƃ�A�����ƒǐՂ���Ȃǂ̈Ӗ�������Bstalker�́A��������l�̂��Ƃł���B���������āA�����X�g�[�J�[�������N�����l�Ԃ́A�l���ɂ��܂Ƃ��đ_����ҁ|�@��Ƃ��̂Ŗ��҂Ƃ��������������|�̂悤�ȃX��������x���𖡂���Ă���Ǝv����B�X�g�[�J�[�ɂƂ��ċC�Â���Ȃ��悤�Â��ɒǂ�����͎��̓����̂悤�ɉf���Ă���̂��낤�B �@�i���Q�j���{�l�ɕ����̏�y�v�z���L�������ꂽ�̂́A�������l�Ԃ����̐��Ƃ��̐����s�������鑶�݂ƍl����M���ꕶ����̑��Â�����Ƃ��Ƃ���������ł���Ƃ����w�E�́A���łɔ~���҂ɂ���ĂȂ���Ă���B�~���Ғ��A���{�l�́u���̐��v�ρA�������ɁA1993�N.���Q�Ƃ̂��ƁB �@�e�a�̏�y���w�ł��������̎v�z�ɂ��A�l�͎���Ɋy��y�։������A�����ɂ��܂ł��s�����ςȂ��ł���̂ł͂Ȃ��A���܂��܂Ȗ�������邱�̐��ł���O�k�i����j���E�ɂӂ����і߂��Ă��āA���̐��E�̔��W�̂��߂ɂ͂��炭�B �@������Ƃ́A���゠�̐��։�����������i���������������j�ƁA�ӂ����т��̐��Ɋ҂��Ă���ґ�����i�����������j�̓�������A�l�����̉��҂��J��Ԃ����Ƃ͐��E�̐v�҂ł��鈢��ɔ@���̈ӎu�ɂ���ĉ^���Â����Ă���A���̂悤�ɐ����邱�Ƃ���F�s�ɑ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����B���̂悤�Ȏv�z���A�l�Ԃ̐��܂�ς���O��ɂ��Ȃ���ΐ��藧���Ȃ��B
|
|||||||||
�@�l�Ԃ̎�肤��s�ׂ̒��ŁA�����Ƃ��������ƂƂ͂Ȃ낤���B����͐l�ԂɂƂ��Ă����Ƃ��d���߂Ƃ͉����ƌ��������Ă��悢���Ǝv���B����ɂ͑����̐l���l�E�����Ɠ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�ł͐l�Ԃ��������E�����Ƃ́A�ǂ��Ȃ̂��낤�B �@�A�W�A�̕������ł͓`���I�ɐ������̂��E�i����j�߂邱�Ƃ��ւ��Ă����B�����k�Ƃ��Ď��˂Ȃ�Ȃ��|�i�����āj�Ƃ����܉��ɂ́A�s�E�����i�������̂��E���Ȃ����Ɓj���܂����ɂ����Ă���B���̌�ɂ́A�s�������i���݂����Ȃ����Ɓj�A�s�����i���Ɋւ��ė���Ȃ����Ɓj�A�s�ό���i���������Ȃ����Ɓj�A�s�������i�������܂Ȃ����Ɓj���Â��B �@�����͌Ñ�C���h�̕����҂ɂ���Ē�߂�ꂽ���A�l�Ԃ̂����Ȃ��̒��ōł��鈫���ƍl������̂��܂����ďd�����Ɏ������̂ł��낤���B�����ł���Ƃ���Ε����k�́A�E���֒f�����Ȃ����Ƃ������čő�̏d�߂��ƌ��Ȃ������ƂɂȂ�B �@�E���֒f�Ƃ́A�E�����ւ���Ƃ����ӂ����A����ɂ͎E�l�݂̂Ȃ炸���b�⋛���E�Q���邱�Ƃ�A��������E�ߊl���邱�Ƃ̋֎~���܂܂�Ă���B�܂�E�l�Ɠ��l�ɓ������E���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���i���j�B �@�y�b�g���X�̌��҂̒��ɂ́A������Ƃ��Ă̐ӔC���d�������āA�����̂����ł��̎q�����Ȃ����ƍl����l�����Ȃ��Ȃ��B���ꂪ�ߒQ�҂��߂̈ӎ������}������Ɉ������ޗL�͂Ȍ����Ƃ��Ȃ��Ă���B �@���̎v���͎��Ƃ��āA����Ȃ���������Ď��������̎q���E�i����j�߂��Ƃ����v�l�Ɋg�傳��Ă������Ƃ�����B�y�b�g���X�̗Տ��ł́A�u�������̎q���E������ł��v�Ǝv���߂Č��N���C�G���g����͒��������Ƃł͂Ȃ��B �@���̂悤�ȂƂ��A�ߒQ�҂̓y�b�g���D�Ƃ����������Ƃ��̎�����s�v�ɂȂ����y�b�g���{�݂ɑ��荞��ŎE��������g����Ȏ�����Ɏ�����Ȃ����悤�ȋC���ɏP����̂ł���B �@�y�b�g�������鎔����ɂƂ��ăy�b�g�����̎E�Q�Ɏ�������߂邱�Ƃ́A�����Ƃ��s���Ă͂Ȃ�Ȃ��p���ׂ��s�ׂł���A�����ɒl����̂��B���̎q�����E���ɂ����Ƃ����v���ɂƂ���ꂽ������́A���̂��߂Ɏ���������̏d�������˂Ȃ�Ȃ��ƍl���₷���B �@������S�����猩�ăy�b�g�͑�Ȏq�ǂ��ł���A���S�Ɩ�����^���Ă������S��n�ƂȂ��e�̂悤�ȑ��݂ł�����B���̂悤�ȓ_����A�y�b�g������̎�ɂ���Ď��Ȃ��邱�Ƃ͎q�ǂ����E�߂��悤�ȁA�e���E�߂��悤�ȁA���邢�͂��̗��҂��ɎE�߂Ă��܂����悤�Ȑ�]�I�ȋC���Ɋׂ��Ă����̂ł���B �@�q�E���ɂ��e�E���ɂ��C�G����E�Q�҈ӎ���������ߒQ�҂́A�o���̌����Ȃ��d�ꂵ���߈����������Ƃɉ����A���̂悤�Ȑӂߋ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���炪�ߋ��Ɏ��Ԃ��̂��Ȃ��悤�ȉ����������Ƃ���������ł͂Ȃ����Ƃ������ʉ���I�ȍߋƊ������Ƃ������B �@�ߋƁi���������j�Ƃ́A�����̒��j���Ȃ��v�z�ł���B����͂��鎖�����N�������Ƃ��A�����Ȃ�ɂ͈ȑO�ɉ����̌����ƂȂ邨���Ȃ��ɉ����āA�U���i��������Ƃ�j�ƂȂ邨���Ȃ�������������ł���A�����̂����Ȃ������킹�ċƁi�J���}�j�Ə̂����B�����āA�����̒��̍Ђ��ƂȂ錋�ʂލs�ׂ��ߋƂɂȂ�ƍl�����B �@����͍����̐l���̂����Ȃ�����łȂ��A�ߋ����ł���O����O�O����O�O�O���E�E�E�ɂ킽���Ĉ��������Ȃ��ƂȂ鈫�Ƃ��Ȃ��A�������̌��ʂƂ��ėǂ��Ȃ�����Ƃ������̂ł���B �@���͍̕���̐l���̂������Ɏ邩�A����ɂ��̐��ɍs���Ď��ɐ��܂�ς��܂ł̂������̑؍݊��ԁi���̎��Ԃ𒆗L�i���イ���j�܂��͒��A�i���イ����j�Ƃ����A�l�\����ԂƂ����B���ꂪ�����A�⑰�̑r���̊��Ԃɂ�����j�Ɏ邩�A�����Ȃ��Ύ��ɐ��܂�ς���������������������������E�E�E�̂ǂ����ŕK����Ƃ����⍓�ł����������Ȃ̂ł���B �@�܂�A�ЂƂ��єƂ��������s�ׂ͌����ă`�����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A������ĂЂƂ��ѕ����ꂽ�u�[�������̂悤�ɂ����K�������ɋA���Ă���Ƃ����e�͂̂Ȃ������낵���N���ł���B�������A����ɂ͋~��������A�ߏ�ƂȂ鈫�s�ł͂Ȃ��P�s��ς߂Δ��ɉʕ�Ƃ��Đ�X�悢���ʂ�������Ƃ��Ă���B �@���̍ߋƊ��ɂ����������̌��p��F�߂�Ƃ���A����͎���̂����Ȃ��̂ǂ������������̂����킩��Ȃ��Ƃ͂����A���̍ߋƂ�����邱�Ƃɂ���č~�肩�������Г�͎����ɐӔC������Ƃ��Ď�����Ԃ߁A����ɂ͂�����߂֓������@�ɂȂ�Ƃ��������₩�ȗ����ł��낤���B �@�Ƃ�������������̓y�b�g�Ƃ̎��ʂɂ���āA��������ȑ��݂�L���Ȃ����グ��ꂽ�Ɗ����ĕs�K�̂ǂ��ɓ˂����Ƃ����B���̂������炪�y�b�g�ɑ��čs�������Ƃɏd��ȗ����x���������Ǝv���Ƃ���A�y�b�g�����S���������ȗ��R��������Ȃ�������A���̗��s�s���ɔ[���ł��Ȃ��ł���Ƃ��A������͎����̏���ȓs���ł��̎q���E���Ă��܂����Ƃ����v���Ɏ�����Ă����̂ł���B �@�����āA�����Ȃ鎩���͂���ۂljߋ��ɉ����̈������͂��炢���ɈႢ�Ȃ��Ǝv������ł䂭�B�y�b�g���X�̌��҂������̂悤�ȓ��قȎE�����R���v���b�N�X�́A�y�b�g�ƕ邵�����Ƃ̂Ȃ��҂ɂƂ��ẮA�܂������Ƃ����Ă����قǗ����ł��Ȃ����낤�B �@������������y�b�g��S�������r�҂ł���A���ꂪ�ʏ�̔ߒQ�ł���A�s�K�ɂ��ĕa�I�ȃG�s�\�[�h�����������̂ł���A���̎���ʂɂȂɂԂ̑��Ⴊ�������Ƃ��Ă������ȂׂĂ��̃R���v���b�N�X�i�S�I�����j�͔F�߂���B �� �ߋƊ��ƎE�����R���v���b�N�X�ގO�̗��R �@�ł́A�ǂ����Č���̃y�b�g���D�Ƃ̑������A�y�b�g�����̎��ɍۂ��Ă��̂悤�ȍߋƈӎ���[�߂�E�����R���v���b�N�X��w�����悤�ɂȂ��Ă��܂����̂��낤���B����ɂ͎��̂R�̗��R������Ǝv����B
�@�P�́A�y�b�g�̎��ʑ̌���������ɔ���鎀���������悤�Ƃ���h�q�{�\���A�ɗz�Ɋ����������邱�Ƃ���������B������ɂƂ��Ĉ�����y�b�g�Ɏ��Ȃ�邱�Ƃ́A�����Ƃ��|�낵�����Ƃł���B �@���̂��߃y�b�g�������Ă���Ƃ�����A���̎q�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͓w�߂čl���Ȃ��悤�ɂ��Ă������A�y�b�g�̎���A�z�����邠���鎖�������N�ł��Ȃ����ƂƂ��ĉ������Ă����B �@�c�O�Ȃ��ƂɁA���̒��ɂ̓y�b�g���X�̒m���������Ƃ��܂܂�Ă���Ǝv���B���̂��Ƃ͋t���Ƃ��āA������ɂ͖{�\�I�|��⋑�⊴�ɍR���ăy�b�g�̐��O����̃y�b�g���X���炪�K�v�ł��邱�Ƃ��������Ă���B �@�������Ď������͎���}���̑ΏۂƂ��Ă������A���ꂾ���Ɍ����Ƀy�b�g�̎��ɒ��ʂ����Ƃ��A������͂Ђǂ�����ĂĂ��܂��p�j�b�N���N�����Ă��܂��̂ł���B�g�߂ȑ�ȑ��݂̎��́A��Ɏ�������Ȃ�����ɏ������悤�Ƃӂ�܂��l�Ԃ̖{�\���u�����i���т�j�����A�ꎞ�I�ɐl�i�̓����������킹��B �@�y�b�g�������Ƃ���܂ʓw�͂����Ă������X�̍s�����������k�J�ɏI������Ƃ��A������͎��ɍR�i���炪�j�����Ƃ̂ł��Ȃ������s�k���ƍ��܊��ƂƂƂ��ɁA������ӔC�̏d���ɉՁi�����ȁj�܂�Ă����B���̏d�����́A�y�b�g�̎���������������ɂƂ��ẮA�قƂ�ǕK�R�̂��Ƃł���B �@�����������߂����҂̎�������悤�Ƃ���l�Ԃ̖{�\�I�~���́A������͈ӎ�����邱�ƂȂ��S���[���ɑ�����Ă���B����������y�b�g�̎����z�������Ă��Ȃ������`�œˑR����������A���̖S���Ȃ�������c�Ȃ��̂ł������Ƃ��Ȃǎ��̏Ռ��������������A���ւ̕|��Ƃ��ċ������o����Ă����B �@�y�b�g�̎����^���鋺�Ђ́A������̐Â��ɖ��鎀�̉��{�\��ڊo�߂����ĐS���I�ȍP�퐫�����������B���̌��ʂƂ��āA�{�l�����ĕs�E���̝|�i�����āj�̔j���҂ł���֊��̏d�߂�Ƃ��҂Ƃ��Ă̈ӎ���h��N�����̂ł���B �@�Q�́A������ɐ�����y�b�g�ւ��܍߈ӎ��ł���B�܍߂Ƃ́A�Ƃ����߂₠��܂��ɑ��č������̑������������܁i�����ȁj�����Ƃ������B������͔ߒQ�̂��Ȃ��A���炪�����ɐg����Ȏ�����ł����������v���߈����Ɛ\����Ȃ��ɏP���Ă����B �@�y�b�g�������Ă��邠�����A�ށE�ޏ�����Ɉ������ƂȂ��A������̈���I�ȓs���ňԂݎ҂̂悤�ɏ�����G�S�C�X�e�B�b�N�ȋɈ��l�̂悤�Ɏv���Ă��Ď���ꂵ�ݎn�߂�̂ł���B �@����̓y�b�g�������������̂̑傫���ɑ��āA���̂��Ԃ��Ƃ��Ă����炪�^�������̂����܂�ɏ��Ȃ��Ɗ����邱�Ƃɂ���Ă���B�܂�y�b�g�Ǝ�����̂������łȂ���鋋�t�Ɣ����t�̃v���X�E�}�C�i�X�̒��K������Ȃ��܂ܐ�Ƀy�b�g�Ɏ��Ȃꂽ���߂ɁA���c���ꂽ������͕s���S�R�Ă��N�����Ă��܂��̂��B �@�y�b�g���X�ɂ���Đ��܂�����ɂ́A�ށE�ޏ���ւ̕ԗ炪�\���ɉʂ�����Ȃ������ɐ旧����Ă��܂������Ƃւ̌��߂����Ǝ��ӂ̔O������Ǝv���B�����ƃy�b�g�Ƃ̊W�͑Γ��ł������Ƃ͂������A�����ȎЉ�I�������������Ă��Ȃ��Ƃ����s�ύt�Ȏv���́A���ʌ�̎�����̃X�g���X����苭�߂Ă������낤�B �@���̂悤�ȓ��������ʕs�S������������ɂƂ��č߂̈ӎ�����߁A�Ƃ��߂��܂ʂ����s�ׂ��c����Ă���Ƃ���A����͒ǑP���{���s�����Ƃł���B�ǑP���{�Ƃ́A���҂̗�ɐH�ו��Ȃǂ̕��i�����������Ċ��ӂ̔O��\���A���҂̖����i���̐��ł̍K���j���F��s�ׂ������B �@�y�b�g�̐��O�A�����b����Ȃǂ̎��{�Ǘ����\���ɉʂ����Ȃ������Ƃ����v���������c���Ă��鎔����ł���A����̃y�b�g�̗썰�ɂ������鋟�����͗B��ł���ԗ�Ƃ��ďd�v�ȈӖ��������Ă���B �@�y�b�g�̎������Ɏ�����̂Ȃ��ׂ���Ƃ́A���{���狟�{�ɕω����Ă����̂ł��邪�A���{��M�S�ɍs�Ȃ����Ƃɂ���ď��S���鎔������܍ߐS���͏��X�ɔ���Ă����B���������̕s�����������܂ł��Â��悤�ł���A�ߋƈӎ���������E�����R���v���b�N�X�͂��̌�����炮���ƂȂ������Â���ƍl������B �@�R�́A�y�b�g�̎��ʑ̌��҂��x����l�X�̒��ŁA�`���I�ɂ�������Ă����@���ƁA�肢�t�A��}�t�E�ގҁi�V���[�}���j�Ȃǂ̎�p�E�@���I�E�\�҂�V���Տ]���҂�̑Ή��̖��ł���B �@���̐l�X�͎���̓����ւ̒����E�ԗ�ƈ�̂̏������@�������Ă��ꂼ�ꂪ�M�����@�ɂ��������Ď���s�����Ƃ����߂�B���̂��������̍s�ׂ�ӂ邱�Ƃɂ���Đ������i����j����M�i�����j��Ƃ�������I�ȍЂ����֑�Ɍ�邱�Ƃɂ���āA�]����肢������ɑr�҂̕s�������Ă����悤�Ɏv����B �@���̌��ʁA�r�҂̔]���ɂ̓y�b�g�̗�ւ̕|��ƂƂ��ɍߏኴ��ߋƊ������荞�܂�Ă����B���̂悤�Ȃ��Ƃ��ݑ�ɂ킽���ČJ��Ԃ����A����͂����l�X�ւ̒����ɂ킽�闧�h�Ȑ��]�ł���@���I�A��I�x�z�ƂȂ�B �@���̖��́A�S���Ȃ��������ɍ��܂�Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜������|���������{�l�̓�����ɑ���߈˕����≅��j�ςƂ��[���֘A���Ă���B���{�̐��_�����́A�_���ƕ������������Ăł������̂ł���A�����̎����������̉e����Ƃ�Ȃ��B �@�y�b�g��r�����l�����ɔ߂��݁A���ɗJ���Ă��邩�Ƃ��������Ƃ��A�{�l�̂�������m��ʂƂ���ł����̉e�����Ă���B����ăy�b�g���X�̌��҂��Ԃ��Ɍ��Ă������Ƃɂ��A���{�l�̎����ς⓮���ς̖{�������������m�邱�Ƃ��ł���B �@�ȏ�A�ߋƊ��ƎE�����R���v���b�N�X�̐��܂��w�i�����Ă������A���̂��ƂƂȂ�E�Q�҈ӎ��������Ƃ����Ăɕ\���̂��A�y�b�g�����y�������Ƃ��ł���B������̓y�b�g�̒���������Ă����ɂ�������炸�A�����͂��̐^�t�Ƀy�b�g�̖��������ŏk�߂˂Ȃ�Ȃ��B �@������͂��̔ϖシ�銋����U����āA�܂��킸���Ɏc���Ă��鈤����q�̖�����ɂ���苎�邱�Ƃƈ��������ɏI�点��B����́A���������͓����ւ̈�s�ׂƂ��ďb��t�ɏ��u���Ă��炤�̂����A��������߂�͎̂�����ł���B���̋�a�̌��f��������ɐ[���_���[�W��^���Ȃ��킯���Ȃ��B �@���̂Ƃ��b��t���͂��ߊŌ�m�⓮���a�@�J�E���Z���[��̖����͑傫���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�����a�@�X�^�b�t�͎�����Ɉ��y�����s�����Ƃ̈Ӌ`�i�y�b�g�̈��y���́A�ނ��ɓ������E�����Ƃł͂Ȃ��A��ɂ���菜�����߂̎�����̎��ߐS����ł��Ō�ɍs�����Âł���Ƃ������Ɓj�����炩���ߏ\���Ɏ��Ԃ������Đ������A�[�����Ă��炤���Ƃ��ɂ߂đ�ȍ�ƂƂȂ�B �@���̍s�ׂ��s���S�Ȓ��ň��y���ɓ��ݐ�A������͏d��ȐS���I��Q���N�����\��������B�����̂��Ƃ��悭�悭�������������Ńy�b�g�E����哮���̈��y���͂Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@������̎E�����R���v���b�N�X�����I���Z���I�Ɍ���������ɍs���������ꍇ�A�����Ƃ����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͎̂����̗U�f�ł��낤�B���E�́A�����Ƃ�����ލs�ׂł���A���ȏ����~���̍ł�����̂ł���B�y�b�g�̎��̂̂������厩��̎��i�^�i�g�X�j�̗~�������݉�����̂́A�y�b�g���E�߂��Ǝv�����Ƃւ̒����ӎ��̍��܂�ɂ��B �@�܂��A���̂悤�Ȉӎ������܂�w�i�ɂ́A�y�b�g�������Ă���Ԃ̓y�b�g�̐��̕����Ɠ��ꉻ���Ă��������傪�A�y�b�g���S���Ȃ邱�Ƃɂ���ăy�b�g�̎��̕����Ɠ��ꉻ���Ă������Ƃ��玀�ւ̊�]�����܂邱�Ƃ�����Ƃ��Ă�������B �@����ɂ͎��E�҂̎���ł��l�т��܂��Ƃ����\�����܍ߊ��ɋN��������̂ł���A����̓y�b�g�̖��ƈ��������Ɏ����̖��������o���ď��i���ȁj�����Ƃ���s�ׂƂ�����B���̎q�����Ȃ��Ȃ�A���̐��Ɏ�����Ƃǂߒu���p���Ȃ��Ȃ����Ǝv��������́A���͂₱�̐��ɂ͕s�v�ȑ��݂��ƍl���A������E�����̑Ώۂɂ��Ă��܂��̂��B �@����͕s�v�ɂȂ����y�b�g���l�m�ꂸ�E��������Đ��̒���������Ă������ƂƏd�Ȃ�B���̈Ӗ�����A�����͎Љ��̖��E�ł���A���̐����炨�������ƂȂ��Ēǂ������āA���̐��ɕ�������邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B���̐��ɒǕ����ꂽ������̍��́A���̎q��T�����߂ĈيE�����܂悤���ƂɂȂ낤�B �� ���{�̃y�b�g���X�͓���ȕ����ɂ�����ł��� �@�y�b�g�Ƃ̊W�́A�y�b�g�̎��ƂƂ��ɏI���킯�ł͂Ȃ��B������̓y�b�g��r������A�����r�i���j�̊��Ԃ������Ƒς��E��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�ߒQ�҂͂��̊Ԃ��r�����q��S�̒��ł͐������Â��Ă���A���O�Ƃ͈قȂ�`������肩�������A�Ƃ��ɕ�炵�Ă���̂ł���B �@����ł킩���Ă������������낤���B�y�b�g���X���痧������Ă��Ȃ��l�́A�O�̎q���S�̒��ɋ�������Ă��邽�߂Ɏ��̎q�����܂ł��V���ɏ�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���̂��B �@�y�b�g�Ǝ҂��y�b�g�Ƃ���Ɗy�����ł���A���₳��܂���Ƃ����Đl�Ƀy�b�g���������Ƃ����߂�̂͗ǂ��A�����a�@���y�b�g�Ǝ�����̂��߂ɁA�����ꓪ�y�b�g���������Ƃ����߂�̂��ǂ��A�y�b�g�V���b�v������Ȃ��킢���ߕ���֗��ȃO�b�Y������܂���Ǝ�����Ɋ��߂�̂��\��Ȃ��B �@�������A�ЂƂ��т��̃y�b�g������ł��܂��ƁA���܂ł�������Ă����l�тƂ́A�g�������悤�ɁA���������Ɏ����傩������Ă����̂ł���B�����Ď�����͂ЂƂ���c�����̂ł���B����͎��������Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��A�y�b�g��S�����������̔ߒQ�҂�����Ă��邱�Ƃł���B �@�����Ď��ɔߒQ�҂͘m�i���j�������ނ悤�Ɏx�������߂���Ŕ��������Ȃ�ʍߋƊ���ߏኴ������Â�����B���̂����A�S���Ȃ����q�͂��Ȃ��̔߂��ގp��]��ł͂��Ȃ��Ƃ��A�����Ƃ��̎q�͐����ł��Ȃ��Ȃ�ȂǂƂ����Ĕ߂��ނ��Ƃ��ւ����邽�߂ɁA�܂��܂��ߒQ�����ɂ������Ă�����Ă����B �@���̓��{�I�w�i�����������̘A���̌��ʁA�V���ȃy�b�g���������Ƀy�b�g������N��������A�y�b�g�����ɂȂ�l�тƂ𑝂₷�Ƃ������ǂ�ł���̂ł���B �@���̂悤�Ȉ��z���ډ��̂킪���Ŋm���ɐi�s���Ă��邪�A���̌��ۂ͐��E�I�Ɍ��Ă������قȃy�b�g���X�̌��̕��ނɑ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�ʂ����Ă��̂܂܂ŗǂ��̂��낤���B �@�u�y�b�g���X�͐���ł��B�y�b�g���X�̔߂��݂������Ƃ͂ł��܂���v�Ƃ��������ĉ������Ȃ��̂ł���A����̓T�|�[�g�ł��P�A�ł��Ȃ��A����͕��u���l�O���N�g�i�����j�ɓ������B���̂悤�ȕs�𗝂ȋ������ȁi���Ƃ��j�߂��Ă��鎔���傪�A���̎q���ӂ����ь}�������ƐS��v�����낤���B �@������̐��_�ی����猩�Ă��A���͂₱��ȏ�A�ߋƊ����E�����R���v���b�N�X����������y�b�g���D�Ƃ𑝂₵�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�ł͂��̂��߂ɂ͂ǂ�����悢�̂��B����͏�X�\���グ�Ă���ʂ�A�y�b�g���X�̃T�|�[�g�̐���S���I�ɐ������邱�Ƃɐs���邪�A���̑O�ɂ܂��́A��������P�A�̂ł���y�b�g���X�E�J�E���Z���[����邱�Ƃ��挈�Ƃ�����B �i���j�����̂��ƂƂ��āA���������͓����E�������I�ɍs�Ȃ��Ă���B�����̐H�K���Ƃ��ē����̓��◑��H�ׂĂ��邩�炾�B�Ƃ�킯���{�l�́A���j�I�ɂ��q�{���ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A�H���͂��߂Ƃ���S�ʂ̐����X�^�C���͖q�{���̂���ł���B �@���̓p���Ƀo�^�[���ʂ�A�n���◑��H�ׁA�R�[�q�[��g���ɂ͋��������Ĉ��ށB���͓����̍��łƂ����_�V�̂������X�[�v�̖˂�H�ׂ�B�O���ɂ͓����b�łł����N���[����������X�C�[�c�𖡂키�B��͂����������������ق���B�����͖��炩�ɒ{�Y���̐H���`�Ԃ��B �@�܂�������돊�����邨�C�ɓ���̃o�b�N��T�C�t��x���g��C�͓����̂��炾�̕\�ʂ��Ȃ߂����琻�i�ł���B���̂悤�Ɏ������̃��C�t�X�^�C���ƕ����͓����̓j�E�i�Ƃ��j�̏�ɐ��藧���Ă���B �@�����������̐l�X�͓����̉�̌���ɒ��ڗ�����@��͂Ȃ��A�����i����v���i���p�[�c�ɕ�����Ă��ꂢ�ɉ��H����Ē���邽�߂ɁA�ƒ{�̎E�Q�ɉ��S���Ă���Ƃ��������͖R�����B�����̎E���͎���Ƃ͖����̂ǂ��������o�����̂悤�Ɏv���Ă���̂�����ł���B�����A�����E�Q���������������Ċ��������ƂȂ��Ă���̂��y�b�g���X�̌��ł���B
|
||||||||
�@�����ł̉ƒ댢�̎��瓪���͂������N���肶��ƌ���Â��Ă���B�y�b�g�t�[�h����̒����ɂ��ƁA��N(2015�N)�́A�Ƃ��Ƃ�991��7000���i���v�l�A�ȉ����j�܂Ō�ނ��Ă��܂����B2011�N��1193��6000������2015�N�܂ł�4�N�Ԃς���Ɩ��N��50�����̊����Ō����Ă���B �@���̎��瓪�����������͂��߂����R���A�y�b�g�W�҂͂��܂��܂ɘ_���Ă���B���钘���ȃh�b�O�g���[�i�[�́A����͌��̎��������т����炾�ƎG���ɏ����Ă����B����������Ȃ͂��͂Ȃ��낤�Ǝv���B�m���Ɍ��̎����͉��тĂ��Ă͂���B���������̉��т͂������N�ɂ͂��܂������Ƃł͂Ȃ��B �@����30�N�����̕��ώ����́A�قږ��N�킸�������L�тÂ��Ă���A����Ɍĉ����邩�̂悤�Ɏ��瓪���������Ă������B�������̒������������Ȃ�A����30�N�Ԃ̂ǂ����ł��̂悤�Ȓ���x���x�͂����Ă��悳�����Ȃ��̂����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B �@�܂����錤���҂́A�����ꂪ�i�s���Ă���͔̂L�̕����D�܂�邩��ł���A���̗��R�͔L�͂�����U���Ȃǂ̎��{�Ǘ��Ɏ�Ԃ������炸�A�ꏊ������ȂɂƂ�Ȃ����炾�Ƃ����B �@�m���ɁA��������Ȃ����R�Ƃ��āA�w�\���ɐ��b���ł��Ȃ�����x�Ƃ����l�����ɑ������Ƃ́A�y�b�g�t�[�h����̃f�[�^�ɂ��\��Ă���B���������̂��Ƃ��������肾�����������N�ɂȂ��Č����n�߂����Ƃł͂Ȃ��A���̑O���猾���Ă������Ƃł���B �@�܂��L�̕����D�܂��Ȃ�A���̂Ԃ�L�̓����������͑����Ă��悳�����Ȃ��̂����A���������͔L�̎��瓪���͂���10�N�ȏ�ɂ킽���ĉ����̏�Ԃ��Â��Ă���B�����傪���h����L�h�ɏ�芷�����̂Ȃ�A�L�������Ƒ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂������A�L�̐��͓��ł��̏�Ԃł��������ɑ����Ă��Ȃ��B �@�܂�����ł́A�y�b�g�s�̏Z���̂��߂ɑ����Ȃ��̂��Ƃ�������������B������y�b�g������Ȃ����R�Ƃ��ď]�������Ɍ����Ă������Ƃł���A���̂��Ƃ͂�͂�f�[�^�ɂ��\��Ă���B �@������������������肾�������ɂȂ��Č����n�߂����Ƃł͂Ȃ��B���������̓y�b�g�̏Z���}���V�����͖��N�����Ă���̂ł���B�܂�A�y�b�g�s�̏Z��͑S���I�ɂނ��댸���Ă��Ă���͂��Ȃ̂��B�Ȃ̂Ƀy�b�g�������Ȃ��A����͂ǂ����ĂȂ̂��H �@�܂�������������̂Ŏ��������Ă������Ȃ��l�������Ă��邩�炾�Ƃ����ӌ����悭�����B�m���ɂ��������l���������邾�낤�B�����������Ȃ�A���{�̌l���Z���Y1700���~�̂���������70�Έȏオ�ۗL���Ă���Ƃ������Ƃ����A���̐���̐l�����̌����ꂪ�Ȃ��N�����Ă���̂��B���Ȃ��Ƃ�70�Α�̐l�тƂɂ��ẮA�������p�̖�肾���ł͂Ȃ����Ƃ͊m�����B �@�ƒ댢�������Ă������R���A���̒������ł����b�Ŏ�ԂЂ܂�������ł��Ȃ��A�L���D�܂�邩��Ƃ��Z����o�ϓI���R�ł��Ȃ��Ƃ���Ή����낤���B�����ň�l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���{�̐l�����̌����ł���B �@2015�N�ɍs��ꂽ���������ɂ��ƁA���{�̑��l����1��2709��4745�l�ł���Ƃ����i2016�N10��26���A�����Ȕ��\�j�B����͑O������2010�N�ɔ�ׂ�96��3��l�̌����ł���A1920�i�吳9�j�N�̒����J�n�ȗ��A���̐l�����ł���Ƃ����B �@����A�������̌��̓������݂�ƁA2010�N��1186��1000������`���Ɏ�����2015�N��991��7000���ƁA���̊Ԃ�194��4000���������Ă���B����5�N�ԂŐl�Ԃ�96���l����A����194���������Ă���B���v��̂��ƂƂ��āA�킪���ł͐l����l���Ȃ��Ȃ�ƁA����2�����Ȃ��Ȃ�̂ł���B �@�l�Ԃ̌����ƌ��̌����Ƃ̊Ԃɂǂ�قǂ̑���������̂��A�M�҂ɂ͕s���ł���B���Ɍ��̌����ɐl���������e����^���Ă���Ƃ����ꍇ�A�L�̐��͌����Ă��Ȃ��̂�����L�͐l�����̉e�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�A�Ȃɂ��Ȃ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă���B �@���͌��̌����Ɋւ��āA��ɂ��������܂��܂ȗ��R��������ɏd�v�ȗv��������ƍl���Ă���B����̓y�b�g���X�ɂ��������ł���B���̂��Ƃ̓y�b�g�t�[�h����̒������ʂ�����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B �@����͌�������Ȃ����R�i������̑j�Q�v���j���������f�[�^�ł���B����ɂ��A�w�ʂꂪ�炢����x��������Ȃ��Ƃ����l��2013�N�͎���Ȃ����R��4�ʂł������̂��A2014�N��3�ʂƂȂ�A2015�N��2�ʂɏオ���Ă���̂ł���B �@�����Ƃ̎��ʂ̂炳����V���Ɍ�������Ȃ��Ȃ�l���N�X�����Ă���̂��B������̃y�b�g����Ƃ����`���Ƃ��ăy�b�g���X�̖�肪�\�ʉ����Ă���̂ł���B �@���������Ă����Ƃ������Ƃ́A�O�̌����S���Ȃ��Ă����̌�������Ȃ��l���������Ƃ������Ƃ��A���߂Č��������l�����������̂����ꂩ�ł��낤�i���̗��������肤��j�B���̒��ŕʂꂪ�炢���玔��Ȃ��Ƃ����̂́A�����܂ł��Ȃ��唼�͑O�҂̐l�����ł���B �@���̎咣�́A�����Ƃ͌���r���Ă����܂łȂ���炭���Ď��̌����������ɂȂ��Ă����̂��A�������N���̎q��V���Ɏ���Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���A���������l�������ډ��̓��{�ɂ͑����Ă���Ƃ������Ƃł���B �@���Ȃ݂ɁA�y�b�g�t�[�h�����2015�N�̌�������Ȃ����R�̂P�ʂ́w�\���ɐ��b���ł��Ȃ��x�A�R�ʂ́w�����������邩��x�A�S�ʂ́w���ʂƂ��킢����������x�i���@������y�b�g���X�̖��ł��I�j�A�T�ʁw�W���Z��ɏZ��ł��āA�֎~����Ă��邩��x�A�U�ʁw�Ō�܂Ő��b�����鎩�M���Ȃ�����x�A�V�ʁw�ȑO�̃y�b�g��S�������V���b�N�������Ă��Ȃ�����x�i���@����͊��S�Ƀy�b�g���X�̖��I�j�ł���B �@�����Ƃ̏���J�i�����ȁj���ɂ���l�X��������ɂ�āA���̑r���ɂ��Ռ��ƃ_���[�W���傫���Ȃ肷���Ă��܂��A�\���ȉ��݂Ȃ��܂܌�������N�����Ă���Ƃ����̂��A�ߔN�̂킪���ɂ�����y�b�g���X�̈�̓����I�ȃG�s�\�[�h�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@���̏ꍇ�A������ɂ͎��������Ă����̎q�������Ȃ��Ȃ��Ă����l�ƁA���͂������育�肾�ƂȂ茢�����ɂȂ��Ă����Ƃ�����ʂ�̃^�C�v������B���̗��҂͂���������ʂ̔ߒQ�����̌�������ƈ��������Ă���l�����ł��邱�Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA���{�l�̃y�b�g���X�̌��͏��O���Ɣ�ׂāA�����قȕ����Ɍ������Đi��ł���Ƃ����������B �@����͓��{�l�̃����^���e�B�ɐ[�����������l�ԂƓ����̊W�̖��ł���A���̂悤�Ȍ��ʂ������炷�y�b�g���X�̌����킪���ɐZ��������Ƃ���A�C�O�̃y�b�g�����y�b�g���X�̃f�[�^�͂��قǎQ�l�ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �@�����W�҂ł���A�y�b�g�̎�����y�b�g������Ȃ��Ȃ�l�̘b����x���x�͕��������Ƃ�����͂������A�W�҂�͂��̂��Ƃ����܂�[���Ȗ��Ƃ��đ����Ă��Ȃ������t��������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@���������A���̌��ۂ��S���I�Ɋg����n�߂Ă���̂ł���B���������Ă������ƂƁA�L�������Ȃ��Ƃ�����̌����Ƀy�b�g���X���[����������Ă���Ƃ������ƂɃy�b�g�ƊE�͂܂����M���^�̂悤���B �@�y�b�g�Ƃ̕ʂ�ɂ��ߒQ�̂����ꂪ�A������̃y�b�g��������������A���̎���Ґ������������Ă��邱�Ƃɓ����W�҂͂܂��C�Â��Ă��Ȃ��B�y�b�g���X�̏d�ĉ��́A�������Ɛi�s���Ă������߂Ɍ�������₷�������ɁA�������҂��y�b�g���D�Ƃ��y�b�g���X����G�ꂸ�ɔ����Ă����Ƃ����\���I�ȑ��ʂ������ۂȂ����ɁA�C�Â��ɂ����ӓ_�ƂȂ��Ă���B �@������̌����ꂪ������ł���Ƃ������Ƃ́A���ƕ�炷���Ƃ𑍍��I�ɔ��f���ė��v�����s���v�̕��������ƍl����l������������ł͂Ȃ����낤���B�����������Ƃ���т�b��ƂȂ炸�A�t�ɂ��܂��܂ȃX�g���X��X�N���y�ڂ��Ǝv���悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�l�ƌ����邷���Ƃ́A���҂��Ƃ��ɗ��v������ł��鑊�������I�ȊW�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ�����I�Ɉ����e������ЊQ��p�̂���W���Ƒ�����l�ɂƂ��ẮA�����������Ƃ����S�ƂȂ����ƂȂ�ɂ������Ȃ��B �@�y�b�g�t�[�h����̃A���P�[�g�ł́A�w�ǂ̂悤�ȃT�[�r�X�������Ă����݃y�b�g�̎���͂ł��Ȃ��Ƃ������R�x�ɂ��Ă������Ă��邪�A���̂P�ʂ͏Z���Ńy�b�g�֎~�����A�Q�ʂ́w���Ƃ��ɔ߂����E�ʂꂪ�炢�x�Ƃ����A��͂�y�b�g���X�̖��ł������B �@�������A�����傽�������ǂ̂悤�ȃy�b�g�̃T�[�r�X�����߂Ă��邩�i�w�������炢���Ǝv������T�[�r�X�x�j�Ƃ����ʂ̒����ł́A�y�b�g�̐��b�₵���̑�s��A�ی��Ɋւ���T�[�r�X�Ȃǂ̎��v�������A�y�b�g�̃^�[�~�i����X�Ɋւ��鎔����P�A�̗v�]�͏��17���ڂ̒��ɂ������Ă��Ȃ������B �@���̂��Ƃ͎�����T�C�h�ł́A�y�b�g�Ƃ̎��ʂ̔ߒQ�ɋꂵ�݂Ȃ���������y�b�g���X�E�P�A�̏d�v�����悭�F�����Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���B�����厩�炪��������_���\���Ɏ��o���Ă��Ȃ��̂ł���B����ɂ͋������ׂ��y�b�g���҂̑��ɂ�������T�|�[�g�ɂ��ė����̖R�������Ƃ����̈���ɂ���Ǝv����B �@����A�����ɂ��������҂́A�y�b�g���X�̌��҂ւ̃T�|�[�g�Ǝ�����ւ̎��O�̃y�b�g���X����ɑ����̓w�͂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�C�Â������ɂ͎�x��ƂȂ�Ȃ����߂ɂ��A������y�b�g�E����哮����S�������l�X��A���ꂩ��S�����Ă����l�X�ւ̎����I�Ȏx���Ɏ��g��ł������Ƃ��}���Ƃ�����B
|
||||||||
�� �ߒQ�ƃy�b�g���X�ލs �@���Ď��ɁA������ɋN����ލs�̂Q�Ԗڂɂ������y�b�g�Ƃ̕ʂ�ɔ����ލs�ɂ��Ęb�������߂悤�B����͍��܂ŏq�ׂĂ����悤�ȃy�b�g�Ɛڂ��邱�Ƃɂ���ċN����ލs�Ƃ͔��ɁA�y�b�g�Ƃ̐ڐG�E�𗬂��D��ꂽ���߂ɋN����ލs�ł���B���Ȃ킿�A�y�b�g���X�������Ƃ��鎩��G�l���M�[�̓P��withdrawal�̖��ł���B �@��Ɏ�����Ɛ��O�̃y�b�g���ڂ��邱�Ƃ���N����ލs��l�ԁE�y�b�g�W�ɂ�����P���I�ލs�ƌĂ̂ɑ��A���̃y�b�g���X�ލs�́A���̌�ɗ���ލs�Ƃ����_����l�ԁE�y�b�g�W�ɂ�����Q���I�ލs�Ƃ�����B�܂���͂��ɁA�y�b�g�̐��O�ɂ�����u����ȕa�C�v�ւ̑ލs�ɂ��Ă��G�ꂽ���A����͐V���Ȑ����ď���͂����ނƂ��ɐ�������قȐS�����ۂ������B �@�������ʂ�ɂ���Ĉ�����Ώۂ��������Ƃ��ɂ���͂�E�B�j�R�b�g�̂����u����ȕa�C�v�Ƃ��������悤�̂Ȃ����܂��܂ȑލs�I�ω���������B�l���ɂ������琁i���������j�Ɨ��ʂƂ������̎n�܂�ƏI���ɗ�����Ƃ��A�l�͏�O���킵�₷���悤���B �@�����납��y�b�g�Ǝ��Ȉ��I�ȓ��ꉻ�������ʂ����Ă���������ł���A�y�b�g�������邱�Ƃ�ʂ��Ă��������������F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邩������Ȃ��B���̂悤�Ȑl���y�b�g��r���Ύ���̑��݂���������鎩�ȑr���̊�@�Ɋׂ�\������ƂȂ�B �@���ȑr���Ƃ͎��Ȃ��������̌��ł���A���ꂩ��ǂ�����Ηǂ��̂����킩�炸�r���ɕ�ꂽ��A�l���ɐ�����Ӌ`�����o���Ȃ��Ȃ��ĂЂǂ��������ނ悤�ȏ�Ԃ������B������y�b�g�̏I���ɂ���Ď�����͎���̖����I�����}�����悤�Ȑ��������r��������Ԃɒu�����B����͈ꎞ�I�ɐ����͂��͊������A����Δ��������̂悤�ȗe�̂ł���A�S���I�ȉ�����ԂɊׂ��Ă���Ƃ�����B �@�y�b�g���X�̌����l�ɂ���Ă͑z���ȏ�̏Ռ��ƂȂ�̂́A�����Ƃ���Ȏ��Ȃ����������N���ꋺ�Ђɂ��炳��邩��ł�����B���̂��߁A���̂悤�ȏ�Ԃ��}����炳��S�ʓI�ɉ�����邽�߂Ƀy�b�g�������Ƃ��������ȂɔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��l������B���̎q������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ύ������ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂����F�ڂ킩��Ȃ��Ȃ鋰�|���瓦��悤�Ƃ���̂ł���B���ꂪ���Ȉ��̋}���ȐN�P��Q����g����邽�߂Ƀy�b�g�̎��̔۔F���N����w�i�ƍl������B �� ���Ԃ�r������y�b�g�̎� �@������y�b�g�̑r���ɂ��A�l�͂����Ύ��Ԋ��o�������B���̑r���ł���B���Ԃ��~�܂��Ă��܂����悤�Ɋ����邩�Ǝv���ƁA�P���A�P�T�ԁA�P�������Z����������A�t�ɒ���������ꂽ�肷��B�܂��A�P����P�T�Ԃ��Z�����������Ƃ������Ƃ����킩��Ȃ��Ȃ�l������B����͌����̂��ƂȂǁA�ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă��܂�����ł���B���Ԃ̊ϔO�ɂ����S���Ȃ����Ă��܂��̂��B�y�b�g���S���Ȃ������̓����玞�Ԃ��Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�̂ł���B�y�b�g���X�̏Ռ����A�������ވӎ������킹��̂��B �@�ł́A�ߒQ�҂̐S���I���Ԃ͏P�������܂܉��������Ă��Ȃ��̂��낤���B���̗��ꂪ���܂܁A�ق�Ƃ��ɉ��������������~�܂��Ă��܂��Ă���̂��낤���B���̂Ƃ��A������̎��v�̐j�͐�ɐi�ނ��ƂȂ��Î~���Ă���悤�Ɍ�����B�������A���������͎��Ԃ̐j�͊������ǂ����悤�ɐ���ɉߋ��Ɍ������ē����Ă���̂ł���B���̎��ʌ�ɋN����S���I�P�ނ́A�ߋ��ɂ��ǂ��Ă�����x��蒼�������Ƃ�����]�ɂ��ƂÂ��Ă���B �@���ʂɂ���Ĉӎ��͉ߋ��ɑނ��Ă����B�Ƃ��Ƀy�b�g���S���Ȃ�Ƃ��ɂ��ǂ��Ă����B�ӎ��͎����ɏW�����A�Ȃ����̎q�͎��̂��A���̎q�̎��ɕ��͂���ł悩�����̂��낤���Ƃ����_�ɒ��ӂ͏W��A���̂��ƂɌŎ����Ă����B�y�b�g�����Ɏ���܂ł̏�i�����肠��ƌJ��Ԃ��v���N������A������͂��̂��ƂɂƂ���Ă����B�����Ȃ�̂́A�����ɂ������Ă�����x��蒼�����̎q�̖��͎��Ԃ����͂��ł���A�����ł�����̎q�͍��������Ă���͂����Ƃ������łȑz���������邩��ł���B �@�܂��A�����ɂ˂Ɉӎ������ǂ�̂́A���̂��Ƃɂ����Ƃ������S���I�V���b�N���Ă��邩��ł���A���̂��߂ɑ傫�Ȋ������Ă�����A�Ƃ��Ƃ��ċ��|�̌��ɂ����Ȃ��Ă��邩�炾�B������ɂ͖S�������y�b�g�̊��p�����n���̂悤�ɐQ�Ă��o�߂Ă��z�N�����B�y�b�g�̎���A������͐��O�Ƃ͐������قȂ�V���Ȗv���Ɏx�z����đލs���Ă����̂ł���B �@���̔��������z�N�́A���ʂ̋��Ђ��Ȃ��߂���A��������S�����čĂї��������Ă������߂ɕK�v�Ȏ��Ȏ����̂��߂̎��ԂƂȂ邾�낤�B���������āA���̂悤�ȌJ��Ԃ����z�N�͋�ɂł͂��邪�A�}����ׂ��ł͂Ȃ��A�����͌͊�����܂ŁA���Ȃ킿�o�s�����܂Ŏ��R�ɕ��o�����Ă������Ƃ��L���ȑΏ��@�ƂȂ�B �@�y�b�g���X�́A�������̎q�ɉ�Ȃ��Ƃ��������ȗ��_�ɉ����A���͂�q�ǂ��ɂ���e�ɂ������������đލs����x�y�𖡂킦�Ȃ����ł��ɂ��Ă���B���̑ލs�r���i�ލs�����Ă��炦�Ȃ����Ƃւ̑r�����j�Ƃ��ĂԂׂ����ۂ́A�y�b�g���X�̗}���Ǐ�ݏo��������Ȃ��Ă���ƍl������B �@�܂��A��ɐ��O�ɂ�����y�b�g�͎�����̐��ݓI�s���⊋�����y�����Ă����|���q�ׂ��B���̃y�b�g�������Ă��Ȃ��Ȃ������A���̗}���̊W���Ƃ�邱�Ƃɂ���āA���Ƃ��ƕ����Ă����s���⊋��������A����炪�y�b�g���X�ߒQ�̒��ɓ��肱��ł��[���ȕs���⊋���̏Ǐ���`������ꍇ������A���̂��Ƃ��y�b�g���X�̏d�lj��̈���ɂ���ƍl������B �� �y�b�g�Ƃ̕ʂ�ƐH�~ �@�y�b�g���������Ƃ��A�l�͐[���߂��݂̒��Ŗ��͊��ɂƂ���ĐH�ו����A�i�̂ǁj��ʂ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��悭�N����B���̐H�~�ቺ�́A�����̏o���������ꂽ���Ȃ��Ƃ����S�����炭��g�̂ւ̓]���Ǐ�Ƃ��Ă̕������傫���B���̂Ƃ��A�H�ו��̓y�b�g���X�̌����ے����Ă���A�����H�ׂ����Ȃ��Ƃ́A�i�����Ⴍ�j���Ĉ��ݍ��݂����Ȃ��A�����z�����������Ȃ��Ƃ����z�����\���Ă���B����͈�����y�b�g�̎�����e�������Ȃ��Ƃ���������̈ӎv��[�I�ɕ\���Ă���B �@�܂��A�y�b�g�̎��ɑ��鎩�ӊ��������玩�ȏ����������܂�A���̎q�͐H�ׂ��Ȃ������̂�����A������̂��̂��ƐH�ׂĂ͂����Ȃ��Ǝv���₷���B����Ɏ����傪�H�s�U�������炷������̌����Ƃ��Ă�������̂��A�y�b�g�������Ă����ߋ��ɂ��ǂ肽���Ƃ������̑ލs�~���ɊW����Ǝv����ꍇ�ł���B �@�������͐H�ׂȂ���ΐS�g�͐��サ�A�G�l���M�[�͓P�ނ�]�V�Ȃ������B���̌��ʁA�����Ɣ��B�͎~�܂邪�A�����Ȃ�ΈȑO�̏�Ԃɂ������Ǝv���̂ł���B�y�b�g����������ɂ��ǂ肽���Ɗ肦�ΐH�ׂȂ���悢�Ǝv���Ă��܂��̂��B���������āA�y�b�g���X�̔ߒQ�҂̐H�v�s�U�ɂ͐S���I�ȋ��H�X���\�H�ׂĂ͂����Ȃ��Ǝ����ɋ֎~���͂��炫�����镔���\���ǂ̂��炢���荞��ł��邩�����ƂȂ�B �@���̂Ƃ��A�Ƃ��ɑr���̏����ł���A������̓y�b�g�̎���۔F���ĕ\�ہi�C���[�W�j�̒��ł������i���u���Ăł��y�b�g�����Â��悤�Ƃ���B���̂Ƃ��y�b�g�����l�ɉߋ��ɘA����ǂ���ΐ����Ԃ�Ƃ����t�@���^�W�b�N�Ȏv�l�Ɏ�����₷���Ȃ�B�i���̃y�b�g��]�ގ�����̊肢���ލs�S���ނ̂ł���B �@��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�y�b�g�̐��O������̓y�b�g�Ɠ��ꉻ���Ă��邪�A���̐S���@���͒ʏ�y�b�g�����S���Ă����炭�͉������ꂸ�Ɏ��̔۔F�ƂƂ��ɁA�Ƃ��ɂ͂�苭���ێ������B���̂悤�ȏꍇ�A���炪�ލs�I�ȍs�����Ƃ邱�Ƃ͓����Ƀy�b�g���ߋ��ɑދ������邱�Ƃł�����B���Ȃ킿�����傪�H�ׂ��ɂ��邱�Ƃ́A�������\�ۂ̒��̃y�b�g�ɂ��H�ׂ������ɂ��邱�Ƃł����āA�������邱�ƂŃy�b�g�����l�Ɍ��C�ȍ��ɗ������ǂ点�����Ƃ������ӎ��I�Ȏv�l���͂��炢�Ă���ƍl������B �@���̂Ƃ��A������̑ލs���q�Ƃ��Ď�����̐S���I�Œ��_�i�������̕����ł���A����������������Ă���_�j�ƂȂ��Ă��钼�ڂ̎������N����O�̎��_�ɗ��������낤�Ƃ���͓����͂��炭�B���̌��ۂ͌����ɂ���ẮA�y�b�g�̐��O�ɂ̓y�b�g�̗͂���Đ̂ɂ�����ލs���ʂ����Ă��������傪�A�y�b�g�̎���͂��ꂪ����Ȃ��Ȃ������߂ɁA�y�b�g�̗͂Ȃ��ɓƗ͂őލs���Ă���p�Ƃ�������B �@�������y�b�g�̎��̔۔F�����Â���r�҂ł����Ă��^���鋺�Ђ⊋���̑傫�����炻���ւ̉�A���N����ƍl������B���̏ꍇ�A�S���ł͈�����y�b�g���t�@���^�W�b�N�ɍ��o���Đ������Â��邱�Ƃɂ���āA���̑z����̃y�b�g�Ɖˋ�̐S���I�����W������łƂ��ɑލs�����݂Ă���p�ƍl������i��z��̃y�b�g�Ƃ̋U�����I�ލs�j�B �@�Ƃ���ŁA�y�b�g���X�ߒQ�҂ɋN����ېH��Q�̒��ɂ͔��ɉߐH�ɑ���l������B���̏ꍇ�̐S���@���́A�܂����܂܂łƂ͈قȂ�A�ʂ̂������̌���������Ǝv����B��́A���q�ׂ��悤�ȐH�~�s�U�ɂ��ߋ��ɑލs���Ă��ǂ낤�Ƃ��邱�ƂƂ͋t�ɁA��ʂɐH�ׂđ��������E���B���Ƃ��Đ�ɐi�݂����A�ꍏ��������������E�������Ƃ����~���ɂ��ƂÂ��Ă���B����͑ލs�ł͂Ȃ����v�̐j�𑁋}�ɐi�s�����đ����������o���Ė����̎��ɍs�������Ƃ����肢�̕\��ƍl������B �@����ɂ��܈�́A�y�b�g�ƐH�������l�Ƃ݂Ȃ���Ă���悤�ȏꍇ�ł���A���̎�����̐H���i�݉ߏ�Ɏ�荞�ޏ́A�y�b�g����ɓ��ꂽ���Ƃ��A�y�b�g���킪���̂Ƃ��Ď���������Ȃ��A����ɂ̓y�b�g��H�ׂđ̓��Ɏ�荞��ň�̉����͂��肽���Ȃǂ�������y�b�g�����Â����]�̌��ʂƂ��ĐH�~�i�����Ă����Ԃ��l������B �@���̏ꍇ�A�y�b�g�͏d�v�Ȉ�����ΏۂƂȂ��Ă���_����A�y�b�g������ł���A�y�b�g���H���ł��邩��A�y�b�g������H���̊W�����藧�B���Ȃ킿�A���̉ߐH�͈����㏞�ł���H���ɓ]�ł���������introjection�ł���A���̍s���͈�����f���ꂽ�Q�슴�ƕ����s���ɂ��ƂÂ��Ă���ƍl������B �@����Ɏ�����́A������q�����Ɏ�������O��������Â��ăy�b�g�Ɠ��ꉻ(���ꎋ)���Ă���_���猩�āA�H�ו����ʂɐۂ邱�Ƃ́A������\�ۂ̒��ɍ��������Â���y�b�g�����ł����Ȃ����߂ɐH�a�E���т�^���Ă���p�ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����傪�ӂ���H�ׂĂ���ȏ�ɐH����ێ悵�Ă���Ƃ���A���̑������H�a�ʕ��̓y�b�g�̂��̂ł���A����̓y�b�g�ɗ^���Ă���̂ł���A�y�b�g�ƂƂ��ɐH�ׂĂ���Ƃ�����B �@����͐��_�I�ȈӖ��ł̎��҂Ƃ̋��H��A�z������B���������ҋ��{�Ƃ��ĂȂ���鋤�H�͖S���Ȃ����҂̗썰�ƂƂ��Ɉ₳���҂��H�a���Ƃ�̂ł����āA����͑��肪���S���č����I���݂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B���������̏ꍇ�́A���̔۔F���邢�͎��̊u��isolation�i���̎q�Ǝ��͖��W���Ƃ��ė��҂�ʂ̂��̂Ƃ��Ĉ��������h�q�@���̈�j�Ƃ��Ďg���Ă���A���̍s�ׂ͂����������̎q������ł͂��Ȃ����Ƃ�����(����)�ɔ[�������邽�߂ɍs����U���I�ȃA���o�C�H��̂悤�ł���B �@�Ȃ��l�͔ߒQ���ɂ��̂悤�ȉ�肭�ǂ����Ȃ��Ƃ�����̂��낤���B ����̓y�b�g�̎���ɂ����Ă����̖��ĂȎ��o���Ȃ��ȏ�y�b�g�͂܂������Ă���̂ł���A���������ăy�b�g����������̍Ж�����Ă����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�����Â�������ɉۂ���ꂽ�����Ƃ���Ȏd���ƂȂ��Ă��邩��ł���B �@������ɂƂ��āA�y�b�g�̖��������ł��i�炦�����悤�Ƃ���w�͂́A�y�b�g�������Ă���Ԃ����̂��Ƃł͂Ȃ��A���Ƃ��y�b�g�����S���Ă��܂����Ƃ��Ă��A���̎������Ȃ��Ԃ́A���܂܂Œʂ�y�b�g�����{������������̍�Ƃ͂��̂܂܌p������Ă���B������͎��ʌ�����炭�̓t�[�h�Ɛ��������������O�Ɠ�������̈ʒu�ɒu������A���牘��Ă��Ȃ��̂Ƀy�b�g�V�[�c����X��芷����Ȃǂ��Ă��������y�b�g�����������Ă���悤�ɍ�Ƃ��Â���B �@���N�ɂ킽���Ċ���e����ł������̏K���́A��������o���オ�������X�̌X�������Ƃ��Ă����ɂ͉��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̋������ߋ��������������ލs�I�ȍs���́A�����傪���f����r�ɓK�����Ă������߂̕K�v�Ȃ�ނ�������V���ł���A�ʏ�͖{�l�̔[�����䂭�܂ŁA���Ȃ킿���ʂ�F�߂���悤�ɂȂ�A���̒��i������j�߂����܂łÂ����邱�Ƃ������B �� ������̜߈˂ƃt�@�N�V�~���a �@���Ă����Ńy�b�g�̎��ʂɍۂ��āA�Ƃ��Ƃ��Ď�����ɋN���鋻���[���ލs���ۂ̂ЂƂɂ��Ă��̊T�����ȒP�ɏЉ�Ă������B����͓����I�ލs�Ƃ����ɂӂ��킵���s���ł���A�y�b�g���X�̔ߒQ�S���̐�������ʂł悭�\���Ă���B �@���̌��ۂ͑r�҂Ɍ�����s���Ƃ��Ă��łɃ`�Y�b�N��(1977)�ɂ���Đl�Ԃ̎��ʂŕ���Ă���u�t�@�N�V�~���a(��������ȕa�C) facsimile illnesses�v�Ƃ�����S�g��(�g�̕\������Q)�ł���B����͈⑰�����҂̖S���Ȃ�Ŋ��̏Ǐ�Ƃ�������ȐS�g�Ǐ���������̂ŁA���̏Ǐ�ɋ���̈Ⴂ�͂��邪�A���ʌ�▽���O�ォ��o�����邱�Ƃ�����B����͉��ʔߒQ�����Ƃ���������̂ł���A�}�����ꂽ�ߒQ�̈��Ƃ����B �@����30��̓Ɛg�j���́A������a�C�ŖS���������A���̌��͎��̂܂���ɋ�ɂ̕\��������Ȃ���ꂵ�����ɃM�����Ƃ悭������ł����Ƃ����B�ނ͈�����y�b�g�̎���A�[���߂��݂ɏP��ꂽ���A��ɂɑς��������Ȃ�Ƃ��̌����Ŋ��Ɏ������M�����Ƃ����炢�����l�̕\��ƂƂ��ɕ����̒��łЂƂ苩�Ԃ悤�ɂȂ����B�ނ͂���Ȏ����������������v�������A�ꂵ�݂����݂����邽�тɂ������Ă����B �@�܂����钆�N�����́A�t���t���ƕ����Ă͉��x���|���_�o�Ǐ�������Ȃ��玀�S�������L���Ŏ�������A�r�����݂̂Ȃ炸�P�N��̖����ɂ����̈��L�̎����̍s���Ƃ悭�����悤�Ȃ߂܂��Ƃӂ�����N�����A�������Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��Ȃ�Q����ł����B�܂�����20��̏����N���C�G���g�̓y�b�g�̎���A���O�y�b�g�������Ă炻���ɂ��Ă����̂Ɠ������ʂɋC���I�ُ킪�Ȃ��ɂ�������炸�ɂ݂��N�����A��ɂȂ�Ǝ��S�����y�b�g��������������Ă����Q���ɂ����ē����悤�Ȏp�����ĐQ�Ă����B �@�����͂ق�̓�O��ɉ߂��Ȃ����A�����̎�����ɋ��ʂ���_�́A���ɂ䂭�y�b�g�̍Ō�̗e�̂ɋ����Ռ����Ă���A���̋L�����N���ɏĂ����ď��Ȃ��炸�S�I�O�����N�����Ă��邱�Ƃł������B���Ȃ킿�A���̍Ŋ��̕ʂ�̎p�͑z�����Ă������̂Ƃ͂Ђǂ��������ꂽ���̂ł���A�s�{�ӂȂ��킢�����Ȏ��Ȃ����������Ƃ����ӎ��������A��l�ɂ��̎��������ł����B �@���̂悤�Ɏ����傪�y�b�g�̕\���d�����[�ԉ�����ɂ͎���ƁA���҂Ɍ����ĉ��炩�̗�����������Ă���ƍl���˂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ��Ƃ������̋[�������E�[�y�b�g�����ꂽ������̍s�����������ɂ���Ƒ�������Ύ��S���������̗삪���ڂ��Ĝ߁i�Ɓj������Ǝv���Ă��܂����낤�B���̂悤�ɍl�����Ƒ��͔ߒQ�҂̂��Ƃ����ꂱ��S�z���͂��ߔz���������邾�낤���A����͎�����ɂƂ��Ď���ɊS���Ă��炦�邱�Ƃł��蓯���邱�Ƃł�����B �@���̊�Ɍ����錻�ۂ͓����삪�߈˂����̂ł͂Ȃ��A������̃y�b�g�ւ̂���Ȃ��̉������߂铯�ꉻ��]�ɂ��ƂÂ��Ă���B���̂悤�Ȃ��Ƃ��N���錴���Ƃ��Ă܂��l������̂́A���̔۔F�ƖS�������y�b�g�ւ̍ĉ�̖]�݂ł���B������͋L���ɂ���y�b�g�̍s�������Ȃ̐g�̂�p���Ė͕킷�邱�Ƃɂ���čČ������Ă���B�������Ď�����́A�ЂƂ����������ĖS�������q���Đ������Ă݂��邪�A���Ȃ��Ƃ����̊Ԃ̓y�b�g�͐����Ă���̂ł���A������q�������߂��ɂ����Ă���������Ă���B �@�ȏ�A�y�b�g�̐��O���玀��Ɏ��鎔����̑ލs���ۂ����܂��܂Ɍ��Ă������A�����̑����͌��N�I�Ŏ����I�A�n���I�Ȗʂ������Ă���B�������ꕔ�ɂ����Ă͕s���N�ŕa�I�A��n���I�ȑލs������Ƃ�����B�y�b�g�̐��O�̂��ƂƂ��āA�����ƕ�炷���Ƃɂ�莔���傪�Љ������������ē������ɂȂ�A���ɊS���Ȃ����l�K�e�B�u�ȑލs�I�s�����N����댯���ɂ��Ă͒��ӂ����N���Ă��������Ǝv���B������Y��铦���s���Ƃ��ăy�b�g�͍ŗǂ̑���ƂȂ�B�������́A�������悤�Ǝv���y�b�g�ƕt���������Ƃɂ���ĎЉ��ڂ����ނ��A�l�Ƃ̐ڐG��f���Ă������Ƃ��ł���̂��B �@�܂��A���̂悤�Ȑl���y�b�g��S�������Ƃ��A����Ɉ����������ăl�K�e�B�u�ȑލs�I�����s���ɂƂ���Ă����Ă��܂����X�N�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�ǂ̂悤�ȑލs���N����ɂ���A�������̐g�ƐS�͂��������̂Ƃ���͂ЂƂ��щ߂��������̂ɂ͂��͂�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ߋ��ɗ��̂������ɂ������Ă�����x��蒼�����Ƃ͊���Ȃ��̂��B���̂��Ƃ͈�����q��r�����Ƃ��A������͋��낵�������Ƃ��Č������˂�������̂ł���B�����A�������̂ɂ͎����K��邱�Ƃ�A���Ԃ͂��Ƃɂ��ǂ��Ȃ��Ƃ����⍓�Ȍ�����������̂��A��͂�ނ�Ȃ̂��B �@���������Ɛڂ��邱�Ƃɂ���Ĕނ�́A�������l�Ԃ�����ꂽ���Ԃ̒��ɐ����铮���ł��邱�Ƃ��C�Â�����B�ނ�́A����̐������ɂ̂��ׂĂ𑫑��Ɍ����邱�Ƃɂ���āA�������ɂ������悤�ɐ������ɂ̂��邱�Ƃ�������B������͓��������ʂ��Ƃɂ���Ď���������̂悤�Ɏ��ʂ��Ƃ�m��B���̂����œ��������́A�������̐S�̒��ɐ�����䂽���ȓ��������悭���Ȃ����ƌ����Ă���B�������ɖڂ��悭���J���Ď���̑������������茩��Ɩَ����Ă���悤�Ɏv���B
|
|||||||
�� �y�b�g�ɂ���Č����I�v�����N���������� �@���ɁA�y�b�g�̐��O�ɂ������߂̑ލs�A���Ȃ킿�����傪�y�b�g�̕�e�I�����S�����Ƃɂ���ċN����ލs�ɂ��čl���Ă݂����B�����̎�����̓y�b�g���q�ǂ��̂悤�ɔF�����邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ����A���̂��Ƃ͈���Ŏ����傪������y�b�g�̕�e�̂悤�ɑ����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B������̎��ȕ\�ۂƂ��Ă̎�����\�ۂ���e�\�ۂɋ߂��[���͂��̎q�̃}�}��Ǝ����傳��͎�����v���Ă���Ƃ������Ƃł��[�Ƃ������Ƃ́A�l�ԁE�y�b�g�W�ɂ��܂��܂ȉe�����y�ڂ��Ă���B �@���Ƃ��A�q����q�L�⏬���������n�߂�ƁA�l�̓y�b�g�̕�e�\����ł͂Ȃ���Ă̕�e�i�{��j�ł���A�㗝��Ȃ����͌p��i�܂܂͂́j�\�Ƃ��ď�ɒ��ӂ��悤�ɂȂ莔�{�Ǘ���y�b�g�̌��N�Ɉӎ����W�����Ă����B���̐S���͕a�C��P�K���N�����₷�������Ȏq�ǂ�������������e�Ƃ��قǕς��Ȃ��B����䂦������͓����̗{��ɐ[���̂߂荞��ł������̂��Ƃ���ւ̊S�����炢�ł����i������A�y�b�g�Ƃ���ƌ��Ȃ��Ƃ͖Y���Ƃ��������b�g���������琶�܂��j�B �@�������ăy�b�g�̖�������Ă邱�ƂɔM�����Ă������A���̉ߒ��Ńy�b�g�̂킸���ȍs���̕ω��┽���ɂ��q���ɂȂ�A��ʂŃi�C�[�u�Ȑ��_��Ԃɂ�����Ă����B����̓y�b�g�������ɂ���Ƃ������ł͂Ȃ��A�a�C�⍂��Ő��b���삪�K�v�ɂȂ����Ƃ��ł������ł���i������A������͏I�n�A�_�o���ɂȂ邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����邽�߂ɐS�g�����Ղ��₷���A���̂��߂Ƀm�C���[�[�₤��ԂɂȂ�₷���Ƃ����f�����b�g���������琶�܂��j�B �@�܂��A�y�b�g���Ⴂ�����牽���̏�Q�⎾�a�������Ă���A������͉ߕq�ŕs����Ȑ��_��Ԃ���Ɏ����Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������Ȃ��B���̂悤�Ȏ�����̐S���́A�C�M���X�̐��_���͉ƃE�B�j�R�b�g���l�Ԃ̕�e���Ԃ�V�݈�Ă�Ƃ��̐��_��Ԃ��̂��āu��e�̌����I�v���vPrimary maternal preoccupation�Əq�ׂ����ƂƂ悭���Ă���A���̃Z�I���[�łقڐ����ł���B �@�E�B�j�R�b�g�͕�e�ƂȂ��������̗Տ��I�ώ@����A�u����Ă���������ꂼ��قȂ��Ă��Ă��Ԃ�V���o�Y����ƁA�ǂ̕�e���݂Ȉ�l�ɐԂ�V�̕��ɋ����S�ƒ��ӂ��������q��Ăɖv�����Ă����Əq�ׂĂ���B���̂�����e�̊��͔��ɋ����Ȃ�@�ׂŏ����₷�����Ȃ�Ƃ����i������A�y�b�g����삷��Ƃ��ł����͎҂�y�b�g�V�b�^�[�Ȃǂ��K�v�ł���A����łЂƂ�Ńy�b�g�̍Ŋ����Ŏ�����ꍇ�Ȃǃg���E�}�̌��ɂȂ�₷���A���������ăy�b�g���X�̃��X�N�������Ȃ�₷���j�B �@���̂悤�ɁA���̂��Ƃ��l�����Ȃ��Ȃ�q��Ăɖ����ɂȂ��ĂƂ���Ă����ω��͐Ԃ�V�̐��b�����Ă��������ł̕K�v�ȑލs�ł���A�E�B�j�R�b�g�͂��̏�Ԃ��̂��āu����ȕa�C�v�Ƃ������锽�����Əq�ׂĂ���B �@�܂�A��e�͐V�������������������Ƃ��A���̖�������ĂĂ������߂Ɏ���̐S�g��a�I�Ƃ�������ލs��Ԃɗ��Ƃ�����邱�Ƃɂ���ĐԂ�V�̗{��ɓK�����悤�Ƃ���B���̐S�������I�ω��́A���̖ړI��B�����邽�߂ɂ͗��ɂ��Ȃ��Ă���A����͕a�I�Ƃ�����e�Ԃ������̂悤�ȓ��قȊ����ł́A���̂悤�Ȉُ퐫���ނ��됳��(�ʏ�)�Ƃ����锽�����Ƒ������Ă���B �@������̓y�b�g�������Ɓu�͂܂�v�Ƃ悭�����B�y�b�g�ƕ�炵�n�߂�ƁA�y�b�g�̂����炵����]�����ɂ������荛�ꂱ��ł��܂��A�[������𒍂����ނ悤�ɂȂ�B�y�b�g�̕����A������Ɉ����������悤�ɂȂ�ˑ����Ă����悤�ɂ��Ȃ�B�������ȑΏۂ�����A���̑�����������D���ĕK�v�Ƃ��Ă����B���̑��v�����̂悤�ȏ[�����͑��ɏ�����̂͂Ȃ��A���̈�����Ƀy�b�g�͂҂�������荞�ނ̂ł���B �@����͎�����̗{���]����������ĕ�e�Ƃ��Ă̊�т������邱�ƂƐ[����������Ă���B�y�b�g�͎��������q�ǂ��ɂ��ǂ��Ă���邾���łȂ��A��e�ɂ������Ă����̂ł���B���̕ꐫ�Ɨ{��ɂ������{�\�s���̖����͉����ɂ��ウ���������낤�B�y�b�g�����Ƃ��J�i�����ȁj�Ƃ́A������ƃy�b�g�݂̌��̖{�\�Փ��ɂ���Ă�������ƌ`�����ꂽ��I�Ȍ���(�{���h)�Ȃ̂��B �@���҂̌��т����{�\�A���Ȃ킿�����I�ȓ����ɂ���ċK�肳��Ă���Ƃ������Ƃ́A������ɂƂ��Ă��̃y�b�g�Ƃ̏o��͂ǂ����^���I�ł���K�R�I�Ȃ��̂Ɋ������Ă������낤�B�{�\�s���ł���A����͖ӖړI�őI���̗]�n���Ȃ��قnj���I�ł���A�������m�����͂��炩���ɔ@���Ƃ����������̂��B����āA���̊W������̂ɋA����r���̌��͉^���ɂ���Č���Â����Ă������т����j�ӂ���Ă������Ƃɑ��Ȃ炸�A������͕��X�Ȃ�ʏՌ��ƃX�g���X����ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�ꐫ��{��{�\�Ƃ����ƁA�����̓����̂悤�Ɏv��ꂪ�������A�����͂����Ƃ������Ȃ��B���Ƃ��A���{�l�̐��i�����Ȃǂł��A���l�j���̂Ȃ��ɂ͕��������ꐫ�̕��������l���������Ƃ������Ă����B����͓��{�l�j���͕����ʂ��R�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ꐫ�̕���������苭���l�������Ƃ������Ƃł���B�Ȃ��ɂ͐l�Ԃ̎q��Ă���������D�����Ƃ����j�������邵�A�������␅���ق̗D�G�Ȏ�����̂Ȃ��ɂ��j�����吨����B���̃N���C�G���g����̂Ȃ��ɂ��A�y�b�g�̐��b�����M�S�ɍs�Ȃ��A���̂��Ƃɑ傫�Ȋ�тƐ��������������Ă���j�������ł͂߂��炵���Ȃ��Ȃ����B �@���͒j���E�������킸�����̎�����́A�������邱�ƂŐ��Ԃ̔ς킵�����炵���������Ă���̂ł���B�S��D����悤�ɉ��Y��ăy�b�g�̗{��ɐ[�����荞��Ŗv�����Ȃ���ލs�ł���K�����Ă���̂��B�����l����ƁA�Ȃ������̌���l���y�b�g�y�b�g�Ƃ����ĔށE�ޏ�����������ɒu���n�߂��̂��̓�̂ЂƂ�������悤�Ɏv���B �@���̃y�b�g����Ė{�\�I�[���Ď����̎���^�����Ă����l���A�y�b�g��ˑR���グ���Ă��܂���@�A���ꂪ�y�b�g���X�̌��ƂȂ�B���̐l�ɂƂ��Ă͍K���̌���ł����e�ƂȂ邱�Ƃ����グ���邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B��e�̖�����D��ꂽ������́A��ł��邱�Ƃ�ے肳�ꂽ�ɓ������r�����ɏP���邱�ƂɂȂ�B �@���͎q�ǂ��ɂ����邱�Ƃ������đލs�Ƃ����Ɛ�قǂ���q�ׂĂ������A��L�̓_��������킩��ɂȂ�ʂ�A�\�ۂƂ��Ă̕�e�ɂ����邱�Ƃ������đލs�ƍl���邱�Ƃ��ł���Ǝv���B����͎q�ǂ������肪�i��őލs������Ήd���ƂȂ邪�A�����Ȃ�Ύq�ǂ����������Ă����ɂ͕K�R�I�ɕ�e�̉e���Z���Ȃ��Ă����B���̐������ɂ��ǂ�A��e�̑̓��ɓ����đَ��Ƃ��ĕ�e�̈ꕔ���Ȃ��Ă����B �@���̂悤�ɔ����̓������������̂ڂ�Η��҂͌���Ȃ��ڋ߂���̉����Ă����B��e������Ǝq�ǂ�������͈ꌩ�َ��̂悤�Ɏv���邪�A���Ƃ��ƕ�q�͖������ō��ꉻ���ꂽ�t�@���^�W�[�̐��E�ɂ��������Ƃ��l����A���҂͐S���w�I�ɂ͂ނ���ڋ߂������݂Ƃ�����B �� �����_�Ƒ���M�� �@�Ƃ���ŁA���̎�����ƃy�b�g������ɐe�����𑝂��A���҂̊W����������Ɛ[�܂�ɂ�āA������̐S�̒��ł��̓����������Ă���傫�ȕω������܂�Ă���B����͎����傩�猩�Ă��̓������q�ǂ��̈ʒu�����e�I�Ȉʒu�ɕϗe���Ă������Ƃł���B �@�y�b�g�Ƃ̐[�������́A���҂̕�q�̊W���������t�]�����Ď����傪�q�ǂ��ƂȂ�A�y�b�g���e�I�ȑ��݂Ƃ��Ċ����n�߂�B�������傫�ȕꐫ�I�ȑ��݂Ɋ������Ă����̂ł���B���Ȃ킿������ɂ͓����͕�ł���Ƃ������Â���l�Ԃ������Â��Ă������[�������\�ۂ��\��Ă���B �@��������ł���Ƃ����M�O�́A�_�ϔO�̒a���Ɠ������炢�Â��B����͓����͐_�ł���Ƃ����M�Ƃ˂Ɉ�̂ł���A���̂��Ƃ͏@���̋N���Ƃ����ڂɂ�������Ă���B���n�̐l�тƂ́A�����ɐ_�������o���ƂƂ��ɂ����ɖ����݈�Ă�ꐫ�����o���Ă����B�n��_�M�Ɍ�����悤�ɑ�n�ƕ�Ɠ����̎O�҂͈�ł���A���ꂪ�_���ƐM�����̂ł���B �@�����Ƃɂ��Ă������n�l�����ɂƂ��āA�ő�̊S�͓����ł��肻�̖L�ł������͂����B���������̐��E�^�D�͓��������������Ă���A�ނ���d���߂��邩�ǂ����Ɉꑰ�̑��S���������Ă����B���������̉^���͂��̎n�܂肩��ޓ��Ɉς˂��Ă����̂ł���B �@�l�Ԃ̒a���ɓ���������������Ƃ����_�b�͑����B����������i�����ځj�ł���l�Ԃ͂��̕�Ȃ铮���ɂ���đ���ꂽ�Ƃ����n���_�b�́A���E�̊e�n�ɑ��݂��Ă���B�Ñ�G�W�v�g�ł���ΎR�r���A�k����C���h�ł͖ċ����A�k�A�����J�ł̓R���[�e���A�M���V���ł͖Ď����A�Ñネ�[�}�ł͘T(���{��̃I�I�J�~����_���炫�Ă���)���A�l�Ԃ݈�Ă��Ƃ����_�b�������Ă���B�����͉����Ӗ�����̂��낤���B �@���n�l��Ñ�l�̓����ɑ���ӎ��͌���l�ɔ�ׂĂ͂邩�Ɍ��l�ł���A�ɂ߂Đ؎��ł������ƍl���˂Ȃ�Ȃ��B�ނ�ɂƂ��āA���������͖L�`�������炷�ؕ|�Ɛ��q�̑Ώۂł���A���������Ĕނ�̒��ɖ����ݏo���_�X�⑾��E�O���[�g�}�U�[�������Ƃ��Ă�����s�v�c�ł͂Ȃ��B �@�l�ނ̐[�w�S���ɕ��ՓI�ɔF�߂��邱�̓����ς́A�����Ɏ����Ă�����l�̖��ӎ��̌Ñw�Ɏp����Ă���B���̖��͎O�߂̑ލs���q�ł��铮�����ꐫ�I�\�ۂ�S�����Ƃɂ���Ď����傪�q�ǂ��̗���ɂȂ��Ă������ƂƊ֘A���Ă���B �@������̓y�b�g�����ɖ��₳��Ԃ߂���Ƃ����B������ނ炪���������Ƃ����B�����A�����Ƃ��Ԃ߂�Ƃ����s�ׂ́A��q�̊W���炢���A�{����e���q�ǂ��ɂ��邱�Ƃł����āA�c�q�i�����Ȃ��j����e�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ��B�����炭�����́A���n�̎��ォ��ꐫ�Ɠ������͋ɂ߂Đڋ߂��������ł��邱�Ƃ���������Ă����̂��낤�B �@�����A������͖{���̂Ƃ���y�b�g�ɉ������߂Ă���̂��낤���B���͑����̎�����͐S�̉��[���Ƃ���Ńy�b�g�ɕꐫ�I������߂Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����̒��ɕ�����Ă���̂ł���B������͓����̒��̕�Ȃ���̂ɕ�܂�Ĉ��S���Ă����Ƃ��q�ǂ��ɂ��ǂ��Ă���̂��B �@�����̐l�X���y�b�g��g�߂ɒu���悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A���ꂾ�����̎Љ��ꐫ�����@���n�߂Ă��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B����Љ�ɕn����ƍ߂�e����푈���g�U���錴���������ɂ���̂ł͂Ȃ����B�ꐫ�I���r�������Љ�́A�����̌`�ŕ���Ă��������Ȃ��B������������i�����ӂ��j����肾�ĂƂ��Đl�X�����߂��Ώۂ��������ł���y�b�g���̐��E�ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���B �� �������ɕ�ۂ����l�Ԑ� �@�ł́A�l�͓����Ɛڂ���ƁA�ǂ����đލs���Ă��܂��̂��낤���B���̕s���ȑ傫�ȓ�������ɂ������āA�܂��n�߂ɍl���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�l�Ԃ̋N���ɂ�����邱�ƂƂ��āA�����͂��ē����ł������Ƃ�����肪����B �@�S���I�ލs�͌��݂���ߋ��ɉ�A���悤�Ƃ��Ă͂��炭���ӎ��I�ȗ͓������A����͌l�j�ɂ����Ă͐�����̑k�y�ł���A���̃x�N�g��������ɂ��ǂ�A�l���ĉƑ��╔���▯���̉ߋ��ɂ����̂ڂ��Ă����B���̐������ɉ����Ă䂯�Ύ푰�Ƃ��Ă̐l�ނ̌n���������t�i���āA�s������͎����Ɠ����̒i�K�ɂȂ��Ă����B �@�܂�A�ލs�̋ɒv�͂�������̖ڂ̑O�ɂ��邻�̓����̂悤�ɂȂ邱�Ƃł���B������������A����A���Ȃ킿�l�Ԃ������I�i�K�ɋA��Ƃ́A���������ǂ��������ƂȂ̂��낤�B����͉������Ƃ��N����ƈӎ�����Ɍ��̏�Ԃɂ��ǂ��ĕ��������������Ƃ���l�Ԃ̎w����~���ƊW���Ă���̂�������Ȃ��B�������̐S�̉��ɂ́A��@���������Ƃ��ȂnjÑ��ɋA�낤�Ƃ���A���{�\������悤�ɓ����I�Ȃ��̂Ɍ��n��A���悤�Ƃ��鐫�����������킹�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@����Ȃ��Ƃ��N����ƁA�������͍��܂ł̕��݂�����ŗǂ������̂��ǂ�����U��Ԃ�B���Ȃ���ȂƂ͂����������Ƃ��낤�B�ߋ��ɂ��ǂ��āA�������������x�l���������Ƃ���B���_�ɗ����Ԃ��ĕ������l����B���̌��_�Ƃ͉ߋ��̎����ł���A�����������Ƃ��Ďn�܂�Ƃ��ł��낤�B�ލs����Ƃ́A����ƈꑰ�̂��ǂ��Ă����n���������̂ڂ��Đ��������Ɏ��낤�Ɛ�c�Ԃ肷��s�ׂł���A�����_�b�I�ɏq�ׂ�A�n�c�ƂȂ�c��_��{�i�����j�����݂ƂȂ�B �@����͌���������u�����Ƃ��Ă̐l�ԁv�Ƃ������_�ɗ��������邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B�������͏��Ղ��邾���̋@�B�ł��Ȃ���A�����������邾���̃R���s���[�^�[�ł��Ȃ��B�������͌��ɐ����鐶�g�̏����₷�������Ɩ{�\���u��t�^���ꂽ���_�����̂Ƃ��Ă̓����ł���B�l�Ԑ��̒��ɑ��Â��������ɖڂ��������ɐl�Ԃ𗝉����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���͐l�Ԑ��Ƃ͂ނ���L���������̒��ɕ�ۂ���鑮�����ƍl���Ă���B �@�l�Ԃ𗝉�����ɂ�����A�l�Ԃ�����藣���̂ł͂Ȃ��A�������̒��ɐl�Ԑ��������ۂ�g�ݍ��܂�Ă���ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B���̂��Ƃ͐l�Ԃ�������̈�ނł���Ƃ��������w��̎�����������m�Ɍ����邱�Ƃł���B�������͚M���������Ƃ�����B�M����the mammals�Ƃ������̂́A18���I�̕��ފw�҃����l�̑��ꂾ���A����͓����̒��ł����ɕ�e������A��e�̂��炾�̂ǂ����ɂ͓��[mamma�����Ă��āA���܂ꗎ�����q�͊F��l�ɁA���O��p���Ă��̓��[�ɋz�����Ă������藎������`��������Đ������тĂ����ꑰ�A�Ƃ���������������Ă���B �@�M�����铮���Ƃ����_�ł́A�l�Ԃ����̚M���ނƉ���ς��Ƃ���͂Ȃ��B���̓_�ł͌����L���e���n���X�^�[���t�F���b�g���l�Ƃ������鍷�ق͂Ȃ����ނł���B���̂��߂ɂ���ꂩ�猩�āA�ނ�̍s���͗������₷�����������₷���B�y�b�g�����ƂȂ鑽���̓������M���ނł���Ƃ������R�����Ȃ�����B �@�l�ԁE�y�b�g�W�̍��q�ƂȂ�e�[�}�́A������ƃy�b�g�����Ԃɂ����鈤��attachment�Ƃ��̑r��loss�ł���B�����̓y�b�g�̐��Ɋ֘A���A�r���͎��Ɋ֘A����B�����Ƒr���̖��͂Ƃ��ɁA�����E�ɂ����鐶���Ǝ��ł̌��ۂ̒����猩�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������_���\�z�������_�Ȉ�̃{�E���r�B���A�Ȃ�������܂œ����̍s���ƐS���ɂ���������̂��Ƃ����A����͐l�ԗ����ɂ͍L���M�����铮���Ƃ��Ă̐l�Ԃ�m�邱�Ƃ��d�v���ƍl���Ă�������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�@�i�����j
|
|||||||
�� ������̕s���⊋����H�ׂĂ����y�b�g �@���݂̔��B�i�K����ȑO�̒i�K�Ɍ���ǂ肷�邱�Ƃ�S���w�ł͑ލsregression�Ƃ����Ă���B��ʓI�ɂ́u�q�ǂ�������v�Ƃ����Ă�����̂ł���A����͉����������Ƃ��č��̏�Ԃ���ߋ��̂�薢���B�ȏ�Ԃɂ��ǂ��Ă��܂����Ƃ������B �@������̓y�b�g�ƐڐG����ƌ��Ȃ��Ƃ�Y���Ƃ����B�܂��A�S�����炢�Ō��C�ɂȂ�Ƃ��A�����ȋC�����ɂȂ�Ƃ������B���̂悤�ȐS���ɂ͓��S�ɋA���Ă��������̂Ȃ����R�ȉ�����ɐZ���Ƃ�������������悤�Ɏv���B�y�b�g�����͎��������q�ǂ��̎���ɂ������Ă����̂ł���B�����ł���Ώ����ɁA�j���ł���Ώ��N�ɂł���B �@�܂�����ɂ́A�����ł���ΐS�̉��ɗ}������œ��̖ڂ����邱�Ƃ̂Ȃ��������N�̐S���y�b�g�Ƃ̌𗬂ɂ���ČĂт��܂���邩������Ȃ����A�j���ł����͂�}������ʼne�̂悤�ɐ����Ă��������̐S���ĂыN������邩������Ȃ��B�y�b�g�Ɗy�����V��ł��邤���Ɏ�����̕\�ۂ͂��܂��܂Ȏh�����ăt�@���^�W�[�̂Ȃ��ŁA�i���̏�����i���̏��N�ɂ����Ă����̂ł���B �@�����Ƃ��ł��q�ǂ�����ɋA���Ƃ����̂́A�傫�Ȋ�т��B�q�ǂ��ɂȂ��Ă��܂��A��l�Ƃ��Ă̏d���ӔC���ʂ����Ȃ��čςނ��A�Љ�l�Ƃ��Ă̂��܂��܂Ȑ�����������B���������Ƃ⌙�Ȃ��Ƃ������Ă��������ׂΎ��肪���Ƃ����Ă���邵�A��������Ă����B���Ɏ����ɔ������Ƃ��Ă�����ȏ�Ƃ��߂��邱�Ƃ��Ȃ��A���ꂪ�q�ǂ����B �@���������A���炭�O�ɋL�҉�̐ȂŐ���������̕s����Njy����āA�l�ڂ��͂��炸�ɂЂǂ�����������c���������B����͑������Z������Ǝv�����A�����Ռ��Ƌْ���������ꂽ���߂ɔނ͎q�ǂ��ɂ��ǂ��Ă��܂��A���������s�����Ƃ����̂��Ǝv���B�q�ǂ��̂Ƃ��勃�����đʑʂ����˂����ȏ�͐ӂ߂��邱�Ƃ��Ȃ����܂��}������̂������Ƃ��A�ނ͑�l�ɂȂ��Ă�����Ă���̂ł���B������ލs���ۂ̈ꎖ�Ⴞ���A�������A����͂قƂ�ǎ��s�������B �@�y�b�g�Ƃ̐ڐG�E�𗬂Ɋւ��Ă����A������͈ꎞ�I�����I�ȑލs���ʂ������Ƃɂ���Č����̂��܂��܂ȕs�����瓦��邱�Ƃ��ł���B�y�b�g�������ΏۂƂ��邱�Ƃɂ�莔����͉��̐S�z���Ȃ��̂т̂т������R�Ȏq�ǂ��̂悤�ȐS���ɂȂ��Ĉ��S�ƈ��S�Ă���B�ލs�͎�����̎���̖h�q�Ƃ��čL���g���Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A������̓y�b�g����X�̕s���⊋���ɑ���h�q�ɖ𗧂ĂĂ���̂��B �@�����A�y�b�g�����͎�����̐S���I�T�|�[�g����S���Ă���A���_����s���V���Ȏg���Ƃ��Ă̖������ۂ����Ă���B�����̌���l���y�b�g���������悤�ɂȂ����傫�ȗ��R�̈�ɂ��̂��Ƃ�����Ǝ��͍l���Ă���B�y�b�g�͎�����̕s���⋰���H�ׂĂ����̂ł���B���ꂪ�y�b�g�����ɂ��������ʂ̖{���ł���A���̋@���͐S���I�ȑލs�ɂ��ƂÂ��Ă���B �@�܂��A�������̓y�b�g���a�����A�������ʂ�̌��C�Ȏp�ɂ��ǂ��Ăق����Ɗ肤�B���̂Ƃ�������̓y�b�g�����N�������ȑO�̏�Ԃ������ǂ����Ƃ���B�������ɂƂ��ăy�b�g�����N������Ƃ́A�y�b�g���ȑO�̎��Ԃɂ��ǂ邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B�v����ɁA�y�b�g�����C�������ǂ����ƂƂ́A�ߋ��ɂ��ǂ邱�Ƃł���A������̓^�C���X���b�v����悤�ɉߋ��ɋA�邱�Ƃ�]��ł���̂ł���B���̂悤�Ȋ�]���ލs�S���ݏo���������i�g���K�[�j�ƂȂ�B�M�҂͈ȏ�̂悤�Ƀy�b�g�����Ƃ̂������̒��Ŏ����傪�N�����l�X�ȑލs���ۂ̂��ē����I�ލs�ƌĂ�ł���B �� �Ώۈ��Ǝ��Ȉ����܂ރy�b�g���̓��ꐫ �@�l�ԁE�y�b�g�W�̂Ȃ��Ŏ�����ɋN����ލs���ۂ́A��ʂ��Ď��̂R�����݂���B��P�́A���q�ׂ��悤�ȃy�b�g�������Ă���ԂɎ����傪�N�����ލs�ł���B��Q�̓y�b�g�Ƃ̕ʂ�ɂ������Ď�����̔߈��ߒ��ŋN����ލs�B����͎��ʌ�A�S�������y�b�g�ɉ�����Ȃ��āA���̎q�������Ă����ȑO�̏�Ԃɂ��ǂ肽���Ƃ����z�������܂����Ƃ��ȂǂɋN����S���ł���B�����v��̔O�ɂ���ꂽ��A�����������o����Ƃ��l�̈ӎ��́A�y�b�g�ƂƂ��ɕ���ł����ߋ��̎��Ԃɏ��Ȃ��炸�A���Ă�����̂ł���B �@���̎��Ԃ̋t�s�͂���ɐi��Ő�̑ʁX���q�̂悤�ɂ�肢�������̂Ɏq�ǂ������肷�����ǂ���܂�ł���B�y�b�g��r����������̒��ɂ́A�߂��݂̂��܂�]���܂���đ勃��������A�{��ɂ܂����Ă�߂��U�炷�ȂǗ~���s���̑ϐ����ɒ[�ɒቺ���Ă��܂��l������B���̂悤�Ɋ�����܂��ė}���̌����Ȃ��c���I�ȍs����������悤�ȏꍇ�ł���B �@��R�́A���̃y�b�g���X�̔ߒQ�҂����I�O���[�t�P�A���Ă��邠�����ɋN�������ÓI�ȑލs�ł���B����͖ʐڎ��ɂ�����N���C�G���g�̃J�E���Z���[�i���Îҁj�ւ̈ˑ����̖��ƊW���Ă���B�N���C�G���g�̓y�b�g�̎��セ�̈ˑ��Ώۂ��y�b�g����J�E���Z���[�i���Îҁj�ɕς��ē]�ڊ�����������Ƃ����邪�A����͐��O���̃y�b�g�ɂǂ̒��x�ˑ����Ă������ɂ����i���̑�R�̉���͊�������j�B�ȉ��A��P�E��Q�̑ލs�S���ɂ��ď���ǂ��čl���Ă݂悤�B �@��P�́A�l�Ԃ������ƐڐG�E�𗬂��͂��邱�Ƃɂ���ċN����h�q�I�ȑލs�ł���A�����l�ԁE�y�b�g�W�ɂ����鎔����̈ꎟ�I�ލs�Ə̂��邱�Ƃ��ł���B����͎�����ƃy�b�g�����̐S���I���ݍ�p�i�l�ԂƓ������݂��ɐS��ʂ킹�ăR�~����P�[�V�������͂���j�̌��ʂ�����ލs�ł���B����͒ʏ�A�����̎����傪�o�����Ă���Ƃ���ł���A�T���Č��N�I�ʼnt�I�ȑލs�ł���(���P)�B �@���̐S���@���ɂ͈ȉ��̎O�̌������l������B��߂̓y�b�g�Ƃ̎��Ȉ��I�ȓ��ꉻ�ɂ��ƂÂ�����ލs�ł���A��߂͎����傪�y�b�g�̕�e�I�����S�����Ƃ��炭��ލs�B�O�߂͓�߂̕�q�̖����W���t�]���ăy�b�g����e�I�����������Ƃɂ���Ď����傪�q�ǂ��̗���ɒu����邱�Ƃ��琶����ލs�ł���B�����O�̔w�i���݂͌��Ɋ֘A�������Ă��邪�A������ɂ���Ă��̋���̒��x�͈قȂ��Ă���B�ł́A��߂��猩�Ă������B �@������S�����猩�āA�y�b�g�͎��̂��̂ł���A���I�ȏ��L�ɂȂ���̂ł���B�y�b�g�����͊O�I�ΏۂƂ��ĊO�ς͌Ƃ��Ă̓Ɨ���ۂ��Ă��邪�A������ɂƂ��Ă͎��Ȃɑ�������́A���Ȃ킿�y�b�g�͎�����̃}�C���i���̂��́j���Ƃ�����\���������āA�y�b�g���X�Ƃ̓}�C���̑r���Ƃ�����\�B�y�b�g�͑��̒N�̂��̂ł��Ȃ��A���̎q�͂���Ԏ��̂��̂ł���A�������̎q�Ȃ̂��B���̎��ȏ��L�ɂ�鎄�I���o�����܂�A�y�b�g�͎��̉������ƂȂ�A���̈ꕔ�ɂȂ��Ă����B �@���I���L�̑Ώۂ͎��ȂɋA�����A���Ȃ��̂��̂ɂ��Ȃ�₷���B���Ȃ킿�A�y�b�g�͎��Ɏ�荞�܂�Ă������Ƃɂ�莄���g���\������ꕔ���ƂȂ��Ă����B���̋@���̓y�b�g�ɂ�鎔����̎���⋭�ƂȂ邾�낤�B�y�b�g�Ƃ́A������ɐS���I�ɐێ�i������j����A���̐S���ɓ��荞��ňꕔ�����߂邱�Ƃɂ���Đ����c���Ă������݂Ȃ̂ł��낤�B �@���������y�b�g���Ə̂��Ă�����̂̒��ɂ́A�Ώۈ��Ƃ��Ẵy�b�g�����ł͂Ȃ����Ȃւ̈����B��Ă���B�����傪�\������u���ƃy�b�g�͂�������v�ł���A�u���Ƃ��̎q�͈�S���́v�Ƃ������E�̓y�b�g�Ƃ̓��ꉻ���������̂ł��邪�A�������ăy�b�g��������Ƃ́A�Ƃ���Ȃ��������g��[�������Ă������Ƃł�����B������̓y�b�g�ɑ��Ď��Ȉ��I�ȓ��ꉻ���N�����Ă���Ƃ����_����y�b�g�͎��������鎄�̈ꕔ�����Ȃ��Ă���i���Q�j�B �@�l�Ԃƃy�b�g�����̋��E���s�N���ƂȂ�A�����܂��ɂȂ��ĂЂƂɗn���������o�́A�[����I�����Ȃނ��낤�B������ɂƂ��Ă��݂��ɕ����荇���Ă���Ƃ����v���͋�����̊��⋤�L�����͂����ށB���̑̌��͓��c���ƕ�e�̊Ԃɐ������̊����������I�Ȉ��̌`�Ԃɗގ����Ă���B��q�̏�́A���ׂĂ̈��̋N���ł��茴�^�Ƃ����邪�A������E�y�b�g�Ԃɂ������́A���̕�q�W��͌^�Ƃ��Ă��܂��܂Ɍ`��ς��Ĉَ�ԂŃt�@���^�W�b�N�ɍČ�����Ă���B �@�Ԃ�V��c���q�ǂ��́A��e�Ǝ��ȂƂ̋�ʂ̂��Ȃ����E�̕s���Ăȃt�@���^�W�[�̐��E�ɐ����Ă���B�ނ�͎��Ȃ���̂Ƃ����������Ȉ�l�̂̐��E�ɂ���č\������Ă���A��e�͎��Ȃ̈ꕔ�ƂȂ��Ă���B�����ł͓��e���ꉻ����̂Ƃ������Ȉ������S�ƂȂ�B�y�b�g�Ƃ̐ڐG�E�𗬂͂��̌����I�ȕ�q��̊��̋L����z�N�����A����ɂ���Ď�����̎���͑ލs���Ă����ƍl������B�����傪�y�b�g�ɑ��Ď��Ȉ��I���ꉻ����Ƃ͂����������Ƃł���B �@�ǂ����ăy�b�g��������܂łɂ��Ƃ��������킢�炵���̂��A�܂��ǂ����ăy�b�g�̊�т��킪���Ƃ̂悤�Ȋ�тɊ�������̂��B�܂��A�y�b�g���ق߂���ƁA�ǂ����Ď����ق߂��Ă���悤�ȍ��o�ɂ�������̂��B����ɂ̓y�b�g�̋�ɂ��ǂ����Ď��̋�ɂɒu��������Ă炭�Ȃ��Ă����̂��B����͂����ɂ���y�b�g�͎��ł���A�y�b�g�͎��̋����ł��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B �@���̂悤�ɍl����ƁA�y�b�g�Ƃ͏��L�҂ł��鎔����ƈ�̉����͂��邽�߂ɑ��݂��铮���A���Ȃ킿���ꉻ�����ł���Ƃ�����悤�Ɏv���B�ލs�I�ȓ��ꉻ���ł���Ƃ������x�̑Ώۂ����߂Đl��������l�H�I�ȓ����A���ꂪ���������Ƃ��Ẵy�b�g�ł���Ƃ�����Ǝv���B�������́A���̂悤�ȃy�b�g���̎�����ȍ\���ɂ��Ă悭���Ă����K�v�����邾�낤�B �� �l�Ԃ̖��ӎ���������������y�b�g �@�܂��A�����傪�y�b�g���[�l�����邱�ƂƑލs�S���̊W�ɂ��Ă��l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������̓y�b�g��l�Ԃ̂悤�Ɉ����B�Ȃ��ł��l�Ԃ̎q�ǂ��̂悤�Ɍ����ĂĂ��邱�Ƃ������B������S���Ƃ��āA�y�b�g�͎q�ǂ��Ƃ��ĔF������Ă���B����͌������ƌ��킸�A�L��L�ƌ��킸�Ɂu�j�̎q�v��u���̎q�v�Ƃ�������A�u�����̎q�v�Ƃ����\�����D��ŗp���邱�Ƃ�������������B�ȑO�̃G�b�Z�[�w�Y�ꂦ�ʌ��t�x�̒��ŏЉ��������S���������w�l���u���̎q�͌��ł͂Ȃ���ł��B���̖��Ȃ�ł��v�Ƃ����Ă����悤�ɂ킪�q�ł���A�킪���Ƃ��Č��Ă����B �@���̂悤�ɑ����̎�����͒ʏ�A�ӎ��̕\�w���x���ł̓y�b�g�����̏��L�ɂȂ鎄�̎q�ƍl���Ă���B�������A�y�b�g�̒��ɐl�Ԃ̎q�ǂ������Ă���Ƃ́A�ʂ����Ă��ꂾ�����낤���B�l�Ԃ̎q�ǂ��Ƃ����Ă�����͒N�����Ă���̂��낤�B������S������ǂ݉����A�����Ō��Ă���q�ǂ��Ƃ͂��Ă̎����ł���A����ɂ͎��̐S�̉��ɍ������ɐ���ł���q�ǂ��̐S�̕����ł͂Ȃ��낤���B�܂�y�b�g��ʂ��āA������͎��̒��̎��̎q�����Ă���̂��B �@������̓y�b�g�̓��������Ɣ`�i�̂��j�����ށB�����Ɏʂ鏬���Ȑl�e�͗c������̎����B���̎q�ǂ��͉ߋ��̎����ł���A����Ɏ��̒��ɍ����m���ɐ����Â��Ă��鏭�N�⏭���ł���B�y�b�g�ƐڐG���邱�Ƃɂ���Đl�͎���̒��ɐ���ł��银�S�����������Ɗ������͂��߂�B�y�b�g�Ƃ̏o��Ƃ́A������̒��̖Y�ꂩ���������Ŗ��C�Ȏ����Əo��̌��ł�����Ǝv���B �@���Ȉ��Ƃ́A���̎����������邱�Ƃł���B������������Ƃ́A���݂̎��������ł͂Ȃ��A���݂Ɏ���܂ł̎��������܂߂Ĉ����邱�Ƃł�����B���͎q�ǂ�����������̂��Ă̎����������A�Ȃ����������̒��ɏh���Ă���q�ǂ��̐S����������B���̂��ǂ��Ȃ��q�ǂ��ɂ����Ƃ��߂����݂��y�b�g�ł���B�������̉������_�̋L�����v���N����������́A���ꂪ�����ł���B �@�y�b�g�����͐l�Ԃ̖��ӎ����h�����Ċ�����������B���̂悤�Ȑ��_�̕ϗe���N��������y�b�g�����ƐS��ʂ킹�邤���ɁA�������ނ�Ƃ̗Z�������̊��������͂��߂�B�y�b�g�������邱�Ƃ́A���������邱�Ƃł�����B�y�b�g�������邱�ƂŗD�������e�I�ȋC���ɂȂ��đ��҂Ɋ��e�ɂȂ�����A���Ȃɑ��Ă��m��I�Ŏ�e�I�ɂȂ��Ă����w�i�ɂ́A�y�b�g���̂��̂ւ̈�����n�܂莩�Ȉ����͂����܂�A����ɑ��̑Ώۂ֏���g�傳��Ă����y�b�g���̎����قȐ������[����������Ă���B�����l���Ȃ���A�y�b�g���������킢���邱�Ƃɂ���Ď����ւ̍m�芴�������A�D�܂����Љ��������ɏ�������Ă������R�̐��������Ȃ��B���̌��ۂ̓A�j�}���Z���s�[�̎��Ì����ɂ��[����������Ă��鎖���ł���B�@�i�����j (���P)�@�ލs���ۂ́A�y�b�g�����ɂ��N����B����L��������ƋY��Ă���Ƃ��ȂǁA���L���c���I�s���������Ă��邱�Ƃ�����B���̍s���̑����́A��������e�ƌ����Ă���q�W�̍Č��ł���B���L�ȂǚM���ނ̃y�b�g�����́A�����Ȑ����Ƃ��킢�炵�����d�v�ȗv�f�Ƃ��Ă���B���̃y�b�g�Ƃ��Ă̗v���������i��Ƃ���ɂ͗c�`���n(�c�ᐫ���c�����܂ܑ�l�ɂȂ��`��B���тƂȂǂ����̗�)�̌̂��Z���N�g���Ĉ�`�I�ɌŒ艻���邱�Ƃł���B�������邱�Ƃɂ���ĂR�`�S�g���قǂ̗c�q�̂����炵�������܂ł��ێ����邱�Ƃ��ł���B �@�܂��A�ʏ�y�b�g�ƂȂ铮���͑�l�ɂȂ�O�ɋ����E��D�����Đ����n��}���邱�Ƃɂ���Ĕ���ƔD�P�o�Y�A����ɂ͎q��Ă��ł��Ȃ��悤�ɃR���g���[������B���Ȃ킿�A�������̓y�b�g�����𖢐��n�Ȕ��B�̏����i�K�ɗ��ߒu���đލs�������܂܈ێ��Ǘ�����w�͂����Ă���B���̂��Ƃ͑����̎����傪�y�b�g�ɑ��Ĉ��ߐ���e�a���݂̂����߂ĔށE�ޏ���̎�ɌŗL�Ȑ��Ɛ��B��ɐB�ɂ�����鐶���S�������{��̔ς킵���Ƃ��ċ��߂Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���B �@�����������E��D����s�ׂ͌����A�{�Y������J���̎�����炵�E�鉻�̂��߂ɍs���Ă�����Z�ł����āA��������̂܂܃y�b�g�����ɂ����p���Ă���B���̓_�ł́A�y�b�g�E����哮���͑��̉ƒ{�Ǝ��{�Ǘ��̔��z����@�͓����ł���B���̓������������ĘJ���ɂ�����s�ׂ́A�����Ȃǂ̋��嗤�ɂ�����{��̛�����q�ǂ��̔�����ۂ��߂ɋ�������C�^���A�̃J�X�g���[�h�Ȃǂ̂悤�Ɋό��I���u���{���ē��قȖɂ��Ƃ����_�ŋ��ʐ�������B �l�̋����͈���ŁA�험�i�ł���z��ɂ����Ȃ�����A�ƍߎ҂ւ̌Y���Ƃ��ĂȂ��ꂽ���j���L�����O���ɂ���B�l�Ԃ̒f��Ɠ����̒f��ł͗��j�I�ɂ͂��āA�ǂ��炪��s�����̂��B�ϔO�I�ɂ́A�����ɑ�������悾�悤�Ɏv���邪�A�{���͂ǂ��Ȃ̂��낤�B�t���C�g�͐l�Ԃ̂�����s���̍����ɂ͋����s���Ƌ����R���v���b�N�X�̖�肪����Əq�ׂĂ��邪�A�����ł���Ƃ���A�����̐��E�ł͐l���l�Ɏ{�������s�����Ă����ƍl���Ă����������Ȃ��B �i���Q�j�@�������̓y�b�g��������Ƃ������A�����̎����傪���̃y�b�g�����ɂ����鈤��̒��ɂ̓y�b�g�ւ̑Ώۈ��ɉ����Ď����傪����ɂ��������A���Ȃ킿���Ȉ��������Ɋ܂܂�Ă���B���Ȃ킿�A�y�b�g�����{���邱�Ƃɂ���Ă͂����܂��y�b�g���Ƃ́A�y�b�g�Ɍ������Ē�����鈤�݂̂Ȃ炸�A�����厩�g�Ɍ��������傳���Ă�������������ƍl������B �@���̈Ӗ�����A�y�b�g���Ƃ͑Ώۈ��Ǝ��Ȉ��̗����������킹�����Ԉ��Ƃ����Ă悢��������Ȃ��B�Ώۂւ̈��Ǝ��Ȃւ̈��̗��҂̌��������Ƃ���ɐ��܂�����ȏ�A���ꂪ�y�b�g���ɑ��Ȃ�Ȃ��B�܂��A�y�b�g�����Ȉ��I���ꉻ�̑ΏۂƂ���Ƃ����Ă��A�y�b�g���̂��̂ւ̏����ȑΏۈ����܂�����������͂����Ȃ��A�y�b�g�ւ̑Ώۈ��Ǝ��Ȉ��Ɍ�������S�I�G�l���M�[�̔z���́A�l�ɂ���Ă��قȂ�ƍl������B
|
|||||||
�����тȓ��{�̃y�b�g�Y�� �@�ŋ߂͎��Ԃ�����Ȃ����߂ɁA������Ђ��߂��������邪�A�]�����猢�L�̎��瓪���͂܂��܂�������Ƃ����y�Ϙ_������B���̂悤�ɂ����l�����̍����̂قƂ�ǂ̓A�����J�̃y�b�g����Ǝv����B�A�����J�ł́A���͖�5000�����A�L��5000�����ȏ�i���m�ɂ͂킩��Ȃ�������葽���Ƃ����Ă���j�������Ă���B�A�����J�̐l���͂R���l�Ȃ̂ŁA3�l��1�l�ȏオ�����L�������Ă��邱�ƂɂȂ�B�A�����J�͕����ʂ萢�E�ő�̃y�b�g�卑���B �@����ɑ��A�킪���ł͐l���P��2000���l�ɑ��A�ډ��̂Ƃ��댢�L�����킹�Ă���2000�����ł���A��ɏq�ׂ��悤��6�l��1�l�����L�������Ă�����߂��Ȃ��B���{����X�A�����J���݂̃y�b�g��������܂�3�l��1�l�����L�������悤�ɂȂ�Ǝv����̂ŁA�����Ȃ���̔{�̃y�b�g���ƂȂ�A�y�b�g�Y�Ƃ�����1�����牭�~�̎s�ꂩ��{�ɐ�������Ƃ����b�ł���B�������A���̋��C�̗\���͍���G�ƂȂ�A�y�b�g�ƊE�͏����L�]�ł���A�܂��܂��L�т�Ɛ������Ă����l�����́A��ڂ琁���ɂȂ����B �@���̓y�b�g�����ނ�݂ɑ�����悢�Ƃ͎v��Ȃ��B�܂��A�y�b�g�Y�Ƃ�������������ȃ}�[�P�b�g�ɐ�������悢�Ƃ�����Ă��Ȃ��B�������������Ƃ��������Ƒ�Ȃ��Ƃ́A�^�ɂ䂽���ȃy�b�g��������邱�Ƃł���A������ƃy�b�g����(����哮��)���K�����傳���Ȃ���A�Ƃ��ɂ䂽���ɐ����Ă�����Љ�̎d�g�݂�����Ă������Ƃ��Ǝv���Ă���B���ꂪ���ɂƂ��ă|�X�g���_�j�Y�����l���邤���ł̎w�W�̈�ɂȂ��Ă���B���̌��ʂƂ��Ẵy�b�g���̑����ł���A�y�b�g�Y�Ƃ̐����Ȃ�A��������͌���Ȃ��B �@�������A����̓y�b�g���s��o�ς̓���Ƃ��Ă��܂�ɗ��\�Ɏg��ꂷ���Ă���B�y�b�g���������Y���痬�ʁA�̔��Ɏ���܂ň�ʂ̏���ނƉ���ς�邱�ƂȂ����Ƃ��ď�ɐ��Y���ƃR�X�g���l���Ȃ������Ă͔����Ă���B�y�b�g�ƊE�͂䂪�`�Ŕ�剻�����̂ł���B �@�Ⴆ�A�H�c�s�ł͍��ł��w�O�Ƀy�b�g�̈ړ��̔��Ԃ�����Ă��Đ������������Ă���Ƃ����B����Ȃǂ͐̓��̃y�b�g�̉��䔄��Ɖ���ς�炸�A�����ł͓����@�ɐG���s�ׂł���B�H�c�x�@�͑����A�����܂�ׂ��ł���B�܂��A���炭�O�ɂ͍ĂсA�Ȋ��Ō��L��ɐB���Ă��������ȃu���[�_�[���}�X�R�~�ł��b��ƂȂ����B���x�ƂȂ��J��Ԃ����S���ł���B �@���{�̃y�b�g�Y�Ƃɂ́A����̂��тȎs�ꌴ�����Ïk����Ă���B���̓y�b�g�������s��o�ς̗����Nj��̑Ώۂɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�Ȃ��Ȃ�Γ����̖��Ɠ����̈�`�q�́A�ނ炪�����i���̉ߒ����o�Ċl�����Ă������̂ł���A����͐l�Ԃ̂��̂ł͂Ȃ��ނ�̂��̂ł���A�l�Ԃ͂��̈ꕔ��ނ炩�炨�����������Ă��炢�A�����l�ނ̋��ʂ̎����ł���A��Ȍ������\�F��O���̂��Ƃ����u�Љ�I���ʎ��{�v�\�Ƃ��Ďg�킹�Ă��炤�ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv������ł���B �@�ډ��̓��{�̃y�b�g�ƊE�ɂ�����ő�̖��́A�u���[�f�B���O���痬�ʁA�̔��Ɏ��邻�ꂼ��̕���Ńy�b�g���҂̉��ʂ����Ԃ����l�Ԃ͑吨���邪�A�ق�Ƃ��̃y�b�g���҂����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B���₵�����y�b�g���҂Ȃ�A���G�Ȍ�z���J��Ԃ��ĕ�q�Ƃ��Ɍ��N���Q����܂Ŕ敾�����A���̌��ʂƂ��Đ�V����Q���`�𐔑������o���A���̎q�B�����ɕ�e�����������(�ꐫ���D)�A�����̃V���b�v�Ő��̔̔�����Ƃ������d�ɂ��킽��ߌ��Ƃ����ƂȂǂƂĂ��p���������Ăł��Ȃ��͂����B �@�������������Ƃ����ʂ��Ȃ����Â��ĉ��߂悤�Ƃ��Ȃ��y�b�g�Ǝ҂́A�o�c�҂��炻���ł͂��炭�]�ƈ��܂Ńy�b�g�̐��҂ł����҂ł��Ȃ��ƒf���ł���B�p�����������Ȃ��A����Ȃ��Ƃ����Â��邱�Ƃ��y�b�g���ƂłȂ����Ƃ��ؖ����Ă���B��ʐl��y�b�g���D�Ƃ�������̔�l�������w�E����Ă����߂Ȃ��y�b�g�Y�Ƃ̏]���҂Ƃ́A�����������҂Ȃ̂��낤�Ǝv���B �@�y�b�g�Ǝ҂͋Ǝ҂ŁA�������̓y�b�g�̐��Ƃ���Ȃ��ƚ��i�����ԁj����������Ȃ��B�܂����Ɓi�Ȃ�킢�j�Ƃ��ĉƑ���]�ƈ��̐�������邽�߂ɂ���Ă���ƁA�J�����邩������Ȃ��B�������A�O��������Ђキ���A���w��������Ă���e�G�ȃu���[�f�B���O�┽����I�ȃy�b�g�V���b�v�̐��̔��������ȏ�Â��邱�Ƃ́A����ƋƊE�̒v�����ɂȂ�݂̂Ȃ炸�A�Ђ��Ă͊C�O�ɂ�������{�̒n�ʂƐM�p�𗎂Ƃ����Ƃɂ��Ȃ�B �@�킪���̃y�b�g����̌�i���ɐS�ɂ߂Ă���l�͑��O�����B�O���l������{�̃y�b�g�V���b�v�̌�����w�E����Ēp���������o���������l���������낤�B����������̓y�b�g���������ɂ����������߂���B��������A�y�b�g�V���b�v�Ő������q�����Ղɔ������߂�K���́A������߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Đl�Ȃǂ͓��{�̒x�ꂽ�y�b�g����ɂ��ĉ����m��Ȃ��Ǝv���Ă������ԈႢ�Ȃ̂��B�ނ�͑S���m���Ă���̂ł���B �@����͂���ӓ�������̕����畷�������Ƃ����A�ȑO�A���Ă̂��鍑�̖ӓ����c�̂ɖӓ����Ƃ��ėp���錢���A�����č����̎{�݂Ő��I�Ɉ��ɐB�������Ɛ\���o���Ƃ���A���{�ɒ���Ƃ��̌���̈�`�I�`�����ʖڂɂ���Ă��܂��Ƃ������R�Œf��ꂽ�Ƃ����B��������ł͏b��t���厔��҂̊Ǘ����Ńu���[�f�B���O���s���\�肾�������A���{�̃y�b�g�E�u���[�_�[��y�b�g�s���ɑ���s�M�����狑�ۂ��ꂽ�̂������B �@����قǔ߂����p���������b������܂��B���{�̃y�b�g�Ǝ҂́A�����̖��_��ւ���ȁi���Ƃ��j�߂Ă�����肩�A�⏕�����[�U�[�ɂ��s���v��^���Ă���̂��B�킪���͓����̂��ƂɂȂ�ƁA�ˑR�Ƃ��ăA�W�A�̎O�����ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���B ���A�W�A�I��i���̒��ɂ�����{�̃y�b�g �@�ȑO���钘���ȏo�ŎЂ���A��������A����R�~�b�N�̊ďC�����Ăق����Ɨ��܂ꂽ���Ƃ�����B�b���ƁA���̃R�~�b�N�͂����̏o�ŎЂ����s����T�����N�}���K�G���ɖ��T�A�ڂ��Ă���A�l�C���Ă���Ƃ����B����𒀎��P�s�{�ɂ��Ă���Ƃ������Ƃ��������A���������S���𑗂��Ă����̂Ō��Ă݂�ƁA�c�ɂ���s��ɏo�Ă����V�R�{�P�̂悤�Ȏ�l���̏��̎q�i�G�����킢���A�j���ǎҌ����ɃT�[�r�X���_�����ȃL�����N�^�[�Ɍ������j���A�y�b�g�V���b�v�ɋ߂�悤�ɂȂ�A�����ł��낢��Ȏ������N����Ƃ����X�g�[���[�������B �@���D���̎�l�����A�y�b�g�V���b�v�Ō����ɂ͂��炭�p�ɂ͍D�������Ă��B���̓X���̂��Z����i����܂��J�b�R�����j�������⎔����̂��Ƃ��悭�l���Ă���l�������B�o�ꂷ�铮���������\��L���ɕ`���Ă��āA���̃R�~�b�N�����ď����̓y�b�g�̎d���ɏA�������Ǝv���e�B�[������������ɂ������Ȃ��Ǝv�����B �@�Ȃ������Ăꂽ�̂��Ƃ����A�X�g�[���[�̍���̓W�J�Ƃ��āA���炭�y�b�g���X���e�[�}�ɂ������ƍ�҂ƕҏW�҂͍l���Ă���A���̃A�h�o�C�X���ق����Ƃ������Ƃ������B���Ƃ��A�f�闝�R���Ȃ������̂Ŏ��͏������A���ꂩ�玑�������������Đ��������葐�e�������Ă�����Ă͎��������Ȃǂ��ċ��͂����B�قǂȂ��y�b�g�Ƃ̎��ʂ��e�[�}�Ƃ��邻�̑@�ׂȏ͔͂��\����A���̖����͂���͂���ŏI������B �@�������A���̃R�~�b�N�ɂ́A���Ƃ��ƂЂƂ傫�Ȗ�肪�������B����̓V���b�v�̒��Ő������q�����P�[�W�ɓ���āA����������O�ɔ����Ă��邱�Ƃł������B�����A���͑����Ă����R�~�b�N�{������Ȃ�A���̂��Ƃ��C������ɂȂ����̂ō�҂ƕҏW�S���҂Ɏw�E���āA��������߂�悤�������B���������߂�Ƃ����Ă��A���łɂ��̃V�[���͉������{�ɂȂ��ďo�Ă��܂��Ă���B �@�ҏW�҂ɂ��A���̃R�~�b�N�͊C�O�ł����łɏo�ł���Ă���Ƃ������Ƃ������B���͉��Ăł��̃R�~�b�N���o���琶�����y�b�g���X�Ŕ����Ă���l�q���������Ă̓ǎ҂���͓��R�A�����s�҂��Ƌ����R�c���邾�낤�Ǝv���A���̂��Ƃ�ҏW�҂ɖ₢�������B����Ɣނ�����̂��Ƃ͂��łɂ킩���Ă���A���̂��ߊC�O�ł͉��Ăł͏o�ł����ɃA�W�A�n��݂̂ŏo�ł��Ă���Ƃ������Ƃ������B �@�o�ŎБ��́A���̃R�~�b�N�����[���b�p��k�Ăŏo���Ζ��ɂȂ邱�Ƃ��Ƃ��ɒm���Ă����̂������B��҂��ҏW�҂��y�b�g�V���b�v�̐��̔̔��ɖ�肪���邱�Ƃ�m��Ȃ��獑����A�W�A�����ɂ��̃V�[����`���Â��Ă���̂������B �@���͍�҂ƕҏW�҂ɁA����Ȃ���ꂩ��X�g�[���[�̒��Ŏ�l����X������܂߂Ęb�����������ʁA������~�߂Ă��������ɘb�������Ă����悤�ɂ���悢�ƒ�Ă����B����������̃R�~�b�N�͗ǂ��]�����A�y�b�g���̂Ƃ��ď����c���Ă������낤�Ƃ����������B�������A�ށE�ޏ���́A���̈ӌ��ɂ��������X���邱�Ƃ͂Ȃ��A���̂悤�ȃX�g�[���[�W�J�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B �@���͂��̃}���K�Ƃ��o�ŎЂ��A���̔̔����~�߂Ȃ��y�b�g�V���b�v�Ƃ��܂�ς��Ȃ��l�������Ǝv���B���������ɂȂ邱�Ƃ�m��B����邩�甄��A�����ɂȂ邩��Â���B����邩�珑���B�����ɂȂ邩��Â���B���̋N����Ƃ��납��́A�����Ǝ�������B�킩��Ȃ���Â���B�����ɂ̓����������������̔��z���Ȃ��A���ꂪ�����ɔ��B��Q�∤����Q�������炵�A�Ђ��Ă͎�����ֈ��e����^���Ă������Ƃ��l���悤�Ƃ����Ȃ��B���ꂪ�y�b�g�Ɋւ���A�W�A�I��i���̌���ł���B �@�킪���́A����T�[�r�X������Ĕ���Y�Ƃɂ��Ă��A�Ȋw�Z�p��|�p�����ɂ��Ă��A���E�̃g�b�v���x���𑖂��Ă��镪�삪���Ȃ��Ȃ��B�������A���ƃy�b�g�Y�Ƃƃy�b�g�����ƂȂ�ƁA���ɗ����x��Ă���̂�����ł���B���̗��R������A���܂��܂ȓ�����p�ӂ��邱�Ƃ͂ł���B�������A�����痝�R�������ĉ��P���ׂ��_���w�E���Ă��A������҂����\�������s�����ǎ҂��܂ށ\�����߂悤�Ƃ��Ȃ���A���̑O�i���Ȃ��B �@�킪���̃y�b�g�Y�Ƃ̍ő�̉ۑ�Ƃ����A�����Ɍg���l�����ɕς�낤�Ƃ���ӎu���R�������Ƃ��B���ɂ͐�������Ȃ��A���̔̔����Â���y�b�g�V���b�v�̈�p�łʂ��ʂ��Ɠ����a�@���o�c���鐸�_���ǂ����Ă������ł��Ȃ��B�܂��A���̕a�@�Ńy�b�g�̌��N�̂��߂Ə̂��Ă͂��炭�b��t��Ō�m�̐S��������ɗ����ł��Ȃ��B �@���ɂ͔ނ�͓����������f���Ȃ���A�������瓾����o�ϓI���v��Nj����邱�ƂƁA���̊������v����邱�Ƃɂ������l�������Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����̂ł���B���̍߂͏������Ȃ��B�ނ�͂���̓r�W�l�X���ƌ�����������Ȃ��B�������A�Ȃ̌Ќ������̂��s�ׂƂ��Ă͂��̑㏞�����܂�ɑ傫������B���̂܂܂ł͓������l���s�K�ɂȂ����ł���B �@���̂悤�ȓ_���猩��A���t�J�f�B�I�E�n�[������������������ƁA�������܂�ς���Ă��Ȃ���������Ȃ��B�n�[������炵������̓��{�́A�Љ�S�̂��n�����A����Ȓ��ŃA�W�A�̎O������E���Ĉꓙ���ɂȂ낤�ƊF�������������ł���B���������͖�nj��E��ǔL�ǂ���̘b�ł͂Ȃ�������������Ȃ��B�y�b�g�����V���⊦��̉���Ŕ����Ă������낤�B�����A���͂���Ȏ���Ƃ������B �@�������A���Ƃɂ�����獡�͐̂ƕς��Ȃ��ǂ��납�A�����ƌ�ނ��Ă���̂�������Ȃ��B�Ƃ����̂́A�y�b�g�̐��Y�┄���v�悩����}�ɏ��i�o�ς̒��ɑg�ݍ��݁A�]�肪�o����s�v�ɂȂ�s��������������ĎE�Q����Ƃ��������܂����s�ׂɂ����͎����߂Ă��邩��ł���B�����������������Ȃ��Ηe�F���Ă��������̕����A�y�b�g�����ɑ��Ă͂邩�ɖ����߂ň��t�ɂȂ��Ă���Ƃ����邩������Ȃ��̂��B ��2020�N�܂ł̉ۑ� �@���Ă̂悤�ɔL��|������ނ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�������l�A�Ƃ�킯����̓����������́A�L�⌢���o�ϗ����̑ΏۂƂ������Ȃ��Ȃ����B���̔ނ�ɗǐS��M�����҂��ăy�b�g�V���b�v�̐��̔̔�������I�Ɏ~�߂Ă��炤���Ƃ́A���͂�s�\�ɋ߂��B��������I�ɐi�߂Ă���̂Ȃ�Ƃ��Ɏ~�߂Ă���͂����B�Ȃ��s�\�Ȃ̂��Ƃ����A�ނ�͎��������̍s���Ă��邱�ƂɈ��̎��o�������Ȃ����炾�B���ӂ��Ȃ��̂ł���B���s�����Ă���Ƃ�������������A�ǐS�����������Ȃ����邾�낤�B �@�������ނ�ɂ͒��N�̏��K�����ɂ��A�߈�������ӂ̔O���Ȃ���Ό��߂������Ȃ����߂ɗǐS�ɒp���邱�Ƃ��Ȃ��B������A���o�̖�Ⴢ����ނ�ɗǐS��i�ʂƂ������ʂ���̐E�ƓI�K�������҂��邱�ƂȂǂ��肦�Ȃ��̂��B�����Ȃ���Ƃ́A�����͂ɂ���čs�������������肪�Ȃ��̂ł���B �@�����A���̊̐S�̍s���������x��Ă���B�킪���̃y�b�g�Y�Ƃ̌�i���́A�y�b�g�����ɂ������s���@�ւ̌�i���ł�����B���Ȃ̓����@�̐��������ߒ������Ă��A�y�b�g�Ǝ҂ɂ��f���𗧂ĂĊ�F�����Ȃ���s���Ă���B���̂����́A�܂�œD�_�������܂��ɓD�_�����҂��Ęb���悤�Ȃ��̂ł���B �@��̓����@�����ŁA���12���ȍ~�̓y�b�g�V���b�v�Ńy�b�g���Ă͂����Ȃ��ȂǂƂ����@���́A12���܂łȂ�y�b�g�����R�ɔ����Ă��悢�Ƃ������Ƃ������F�߂����ƂɂȂ�B�܂��Ƃɋ����Ȏ�茈�߂ł���A���@�ł���B�y�b�g�V���b�v�Ȃǂ͂���Ő��̔̔��̂��n�t���𐳎��ɂ��炦���Ƃ��Ă݂Ȋ��ł����Ƃ����B �@���Ȃ͌��ʂƂ��ăy�b�g�����̒�Ɏ��݂��Ă���A�y�b�g�ƊE�̑O�ߑ㉻���Œ艻�����Ă���̂ł���B���Ȃ��o�Y�Ȃ̂悤�ɂȂ��āA�ƊE�̗��v�E�s���v��u�x�i�����j����悤�ɂȂ��Ă͕S�N�����Ă����̖��͉������Ȃ����낤�B���Ȃ͂�����y�b�g�̋ƊE�c�̗̂��v��i�삷�銯���ɂȂ����̂��낤���B �@����A�y�b�g�Y�Ƃɂ������҂��E�ƓI�ւ�Ǝg�����������A���h�����ƊE�l��ڎw�������̂Ȃ�A�O���l�݂̂Ȃ炸��ʂ̐l�тƂ�y�b�g���D�Ƃ�������̔�l�������w�E����A���������悤�Ȑ������͉��߂Ȃ���Ȃ�܂��B�y�b�g�Y�Ƃ��ˋƂł͂Ȃ��͂����B �@�y�b�g�ɂ������E�Ƃ́A�y�b�g�̐�����a����l�Ԃ̕��������ɂ͂��炫�A���̍��̃y�b�g��������ĂĂ����������ɂȂ��������d���d���̂͂��ł���B�悢�y�b�g�������Y�݈�Ď�����ɒ����莔�������w�����邱�Ƃɂ���āA�y�b�g�����Ɛl�Ԃ̋������͂��藼�҂̕����ƍK���̎����Ɋ�^����B���̂������ăV���v���Ȗ���̎��s�҂������ɂ������E�Ɛl�ł��낤�B �@�������A���̎��H�͂��������ɂ͂���߂č��x�Ȑ�含�ƌo����L����҂ɂ����ł��Ȃ��s�ׂł���B�����A���ꂪ���ケ�̕���̐E�Ɛl�Ƃ��Đ����c���Ă������߂̗B��̓��ł���A���ݗ��R�ł��낤�B����Ȏu�i�����내���j���Ȃ���Η��O���Ȃ��A����������H�����ɂ��ė��v���グ�邱�Ƃ����ᒆ�ɂȂ������l���W�܂��āA�����������̍��̃y�b�g�������ǂ��Ɏ����Ă������Ƃ����̂��낤�B���̂悤�Ȏ҂��y�b�g���Ƃ̊�����ăy�b�g�����̖��������ȂǁA����قNJ��m�ŃO���e�X�N�Ȃ��Ƃ��Ȃ��B���ꂪ����Љ�̕a���łȂ����ĉ��ł��낤�B �@2020�N�ɂ́A�����I�����s�b�N���J�Â����B���̍ہA�吨�̊O���l���������ē��{�ɂ���Ă���B���̐܁A���̃y�b�g�V���b�v�ɂ��������B�����ŔށE�ޏ���́A���n�Ȃ����ɔ��B�̈����₹�ׂ����q����q�L�������܂Ԃ����P�[�W�ɓ�����ĉ�����q�f�����Ȃ�����Ă������Ȏp������B���̂܂Ȃ����́A������͌��̕Ђ��݂ŕm���̎q����q�L�������Ƃ��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ����낤�B �@�����āA�ށE�ޏ���͋����̔ߖ�������B���{�l�͂Ȃ�Ǝc���Ȗ�ؐl�Ȃ̂��ƁB���{�l�͐e�ŁA�����ĂȂ����ɂ���ƕ��������A���������ɑ��Ă���ȂЂǂ����Ƃ�����Ă���̂��B����œ��{�̓z�X�s�^���e�B�̂��镶�����ƂƂ�����̂��ƁB �@���Ă��ׂ̊؍��́A�I�����s�b�N���J�Â����Ƃ��A�\�E���̕\�ʂ�ɗ������ԋ��(���̓�)��H�ׂ�X��������āA�\���猩���Ȃ����ʂ�ɗ����ނ������Ƃ����B����͂��̏ꂵ�̂��̎{��̂悤�ł����������A������������ē��ǂ͋Ȃ���Ȃ�ɂ��A���̑O�ߑ�I�Ȗ��ɉ�����������B�������͔ނ�̍s�ׂ�o�i���j���邾�낤���B����H�ׂ邱�ƂƁA�������q���B�����ɕ�e������������Đ��̔̔�����s�ҍs�ׂƂ͈قȂ邪�A�����ɑ���A�W�A�I��i���������_�ł͓����ł���B �@�ł́A���Ȃł����J�Ȃł��_���Ȃł������{�ł�����Ғ��ł��������ł��ǂ��ł��悢�A�ʂ����Ă킪���̖�l�ɂ́A�������I�Ȑ��̔̔�����߂Ȃ��y�b�g�V���b�v�ɑ��Ċ؍��Ɠ������Ƃ�f�s����C�T�����邾�낤���B �@���������̊����Ƃ���́A��͂�2020�N�܂łɌ��L�̎E���������[���ɂ���Ƃ������������B��^���ł���B�����A���̔���̂��Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�܂��B����͎q���E�q�L�ւ̐��U�ɂ킽�鈤����Q�╪����Q�������炷���炩�ȋs�ҍs�ׂł���B������ɂ���A�����I�����s�b�N�܂ł���5�N�����Ȃ��B�������������A�y�b�g�O�����͂�߂ɂ��悤�B�����āA���{���y�b�g�Ɋւ���@�������E�ł����Ƃ��������Ƃ����鍑�ɂ��Ă������B
|
|||||||
�����t�J�f�B�I�E�n�[���Ɩ�ǔL �@�������ɓ��{�ŕ�炵�����t�J�f�B�I�E�n�[���i���_�j�́A���̐��M�w���{�̖ʉe�x�̒��ŁA�L�Ɠ��{�l�ɂ��ċ����[�����Ƃ�����Ă���B����ɂ��A�����ɏZ��ł��邱��A���~�̒�ɖ�ǔL���悭����Ă����Ƃ����B�n�[���́A���̔L����Ȃ����悤�Ƃ������A�ǂ������܂������Ȃ������悤���B���̂����肪�ʔ����̂ŁA���p���Ă݂悤�B
�@���̉��~�ɖ��f�ŐN�����Ă���L������B���̂₹�ׂ�����ǔL�͂Ȃ��Ȃ��̑�D�_�ŁA�������x�ƂȂ��X�������悤�Ǝ��݂����A���ǂ͑ʖڂł������B���i�����j��������ɁA���܂��ܐK���i�����ہj�������̂ŁA�L���i�˂��܂��j�Ƃ��������L�ł͂Ȃ����Ƃ����悩��ʉ\�i���킳�j�������Ă����B �@���͖���24�N�A����1891�N�̂��ƁA�ꏊ�͏o�_�̍��̏��]�B��������ǔL�������̂ł���B���������̖�ǔL�́A�₹�ׂ�A���i�����j�������A�V�b�|�����������Ƃ����B�V�b�|����������ȂƎv�����A���ꂪ�傫�Ȗ�肾�����B�����̓V�b�|�̒����L�́A�������������L�̔L���ɂȂ�ƐM�����Ă����̂ł���B �@�L���̘b�́A���̌h�����銙�q����̃G�b�Z�C�X�g�E���D�@�t�́w�k�R���i��Âꂮ���j�x�ɂ��o�Ă���i�֑��Ȃ���A�ق��{�G�b�Z�[�́w��Â�y�b�g�̑��x�Ƃ����^�C�g���́A�����܂��������̕s���̖���ɂ��₩���Ă���j�B����͂����A�d�����I���ċA��r���̒j���A�s�ӂɔL���ɏP���ċC�����]����b�ł���B����������͔L���ł͂Ȃ��A�A���Ă�������l�������ĈÈł̒������т��Ă����������������Ƃ����I�`�ɂȂ��Ă���B �@���̂���L�͔N�o��Ɖ����L�ɂȂ��Đl�ɐH�炢���ĎE���Ƃ����ĕ|����Ă����̂ł���B�Ƃ����������L�E�L���̘b�͌Â�����L�܂��Ă���A�����ɂȂ��Ă�������̖��M�͏o�_�n���ɂ��������c���Ă����悤���B�n�[���̘b���Â��悤�B
�@�o�_�ɂ��A���܂�������K���̔L�����邱�Ƃ͂���B�������A�K���������܂܈�Ă��邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B�����L�ɂȂ�̂́A�L�̐����̏K���ł���ƌ����Ă��邩��A�����}����ɂ́A�e�L�̂����ɐK����邵���Ȃ��Ƃ���Ă���B�������A�K���̗L�閳���ɂ�����炸�A�L�ɂ͖���������A���̂�x�点��͂�����̂��B����ɔL�قǂ̉��m�炸�����Ȃ��B �@�ƁA���Ȃ�茵�����B�����ŋ����������̂́A�o�_�ł͒����V�b�|�̔L�͊�������A�قƂ�ǂ��q�L�̂����ɐ藎�Ƃ����Ƃ����_�ł���B�m���ɃV�b�|�ɂ́A�Ȃɂ��l�q�����p���[�����肻�����B���������l�ɂ͂Ȃ����̂Ȃ̂ŁA�V�b�|�͂��łɐl�q���Ă���̂�������Ȃ��B���̂��߃V�b�|�͈ؕ|������A�̎������ꂽ�B�u�V�b�|�����ށv�Ƃ����A���܂�������A�B���������Ă����؋������Ӗ����������A�u�V�b�|�������v�Ƃ����\�����A�l�����܂�����A�B���������Ă������Ƃ���āA�����̔炪�͂����Ӗ��Ŏg�����肷��B �@�܂�A�V�b�|�͐l�Ԃ�����������A���܂����肷�鈫���z�������Ă�����̂Ȃ̂��B����ȕ��C�Ől�����������̂��A�������ł���A���������ĔL�͉������Ȃ̂��A�Ǝ��ł͂Ȃ��A�����̏o�_�l�����͍l�����̂ł���B���̂��߂ɁA���̃p���[���h���Ă���|���V�b�|�͑��������ɐ����Ă��܂�˂Ȃ�Ȃ��̂��B �@�������A�V�b�|������͔̂L�����ł͂Ȃ��B���ɂ����Ă���B���̌��̃V�b�|�͈������͂��炩�Ȃ��̂��B�����������ɂȂ�Ƃ����b�͕����Ȃ����A�������ɂȂ�Ȃ����߂ɂ��̃V�b�|���Ƃ����b�͂���ɕ��������Ƃ��Ȃ��B���̃V�b�|�͗ǂ����A�L�̃V�b�|�͑ʖڂ��Ƃ���A����͂Ȃ��Ȃ̂��B���̓��{�l�̎v�l�͋����[�����A�V�b�|���A�L�̐����̐������ς���āA�����L�ɂȂ�Ȃ��Ƃ������z���܂��悭�킩��Ȃ��B �@�����L�̐�����ς������Ƃ����̂ł���A�V�b�|���̂łȂ��A���̂����ɂ���^�}�^�}���������������肭��B�����E�J�X�g���[�V�����ł���B����������ɁA�ǂ����ăV�b�|�ɂȂ�̂��B�����̋��������������Ȃ��������̍��ł́A�����̑�p�Ƃ��ăV�b�|������̂��Ȃǂƍl���Ă݂��������B �@����ɓ��{�ɂ̓V�b�|�̒Z���a�L�������̂��A��̗��R����A���ꂪ�D�܂ꂽ�̂ő������̂��Ǝv���B�Ȃ��A�Z���̓��{�L�͓��{�l�����N�ɂ킽���ĔL�̃V�b�|���Â�������A���̊Ԃɂ��Z���Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�ˑR�ψق��Œ艻�����̂ł��낤�B�L�͖{���A�V�b�|���������̂ł���B �@�f���͒ʏ�A�V�b�|�����s���N��������A�����Ȃǂ̂��߂�ނȂ��؏�����ق��A���̏ꍇ�ł���A�J�����Q�ƂȂ�V�b�|�̓����Ȃǂ�h�����ߎ��O�ɐ�������A�w���̋ؗ͂����邽�߂������肵���B�܂��A���̏K�������̌���̗e�p�Ƃ��Ē蒅�������߂Ƀt�@�b�V��������e�ړI�Œf�����ꂽ�肵���B�������A�����L�\�h�̂��߂ɔL��f������Ƃ����b�́A����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ������B�����L����j�~����Ƃ������R�ŔL�̒f��������K�������O���ɂ���̂��A�Ǖ��ɂ��Ď��͒m��Ȃ��B �@�����������������L�Ƃ����̂��A�ǂ�ȔL�Ȃ̂����R�Ƃ��Ȃ��B�����̓��{�l�����Ă��������͔L���������킯�ł͂Ȃ����낤����ڂ��������ł���l�����Ȃ����낤�B�N���������Ƃ��Ȃ������ɁA�悯���ɑz���͖c��݁A���|�S����������ɑ������Ă��܂��̂ł���B �@�悭�����L�Ƃ����ƁA��Ȗ�ȍs���i����ǂ�j�̖����Ȃ߂ɗ���ȂǂƂ����B�͍̂s���̖��ɂ́A�~����i�^�l����p�����̂ł��낤���B���̒m�����A�L�̒��ɂ͖����D���Ȏq������B�ȑO�����Ă�����C�̔L���I���[�u�I�C�����D���ŁA�������̃r���������Ă���ƁA���Ɋ���Ă��Ă͒��g���ق��������B����������ƁA�y���y���Ƃ��܂����ɂȂ߂Ă����B �@���̔L�́A�s�[�i�c�I�C�����D���������B���̎q�͗m�L�̃`���`���y���V���̒j�̎q�ŁA���Â��ȕi�̂���q�������B16�܂Ő��������A���̊ԂƂ��ɕς�������Ƃ��Ȃ��A��������L�ɂ��Ȃ�Ȃ������B���̔L���A�킪���{���̒����ɐ����Ă�����A�s���̖�����D���ɂȂ��Ă������낤�B�����Ȃ�A�L���ƌĂ�Ă�����������Ȃ��B �@���͑z������̂����A�ނ�����C�̑傫�Ȗ�ǔL���Ŗ�̒����ǂ����̉��~�ɔE�т���ōs���̖����h�{�⋋�̂��߂Ƀy�`���y�`���ƂȂ߂Ă���Ƃ�����Ɛl�Ɍ������Ă��܂��B�C�Â��ꂽ�L�́u�݁@���@�ȁ`�v�Ƃ���������Ĕ�����̒��ŗ�̈��S�̂悤�Ȃ��߂������������Ƃ�����A�Ɛl�͍����������ɘT�����āu�����L���[�A�L�����[�A�����ā[!!�v�Ƒ呛�����邾�낤�B���̐��ł��A�˂ɕ|��͕|�ꂩ�琶�܂����̂ł���B ��������Ă����ƔL �@�L���s�g�ȓ����Ƃ��Č���ꂽ�b�́A�ȑO���炢�낢��ƕ����Ă���B���m�ł��ƔL�͓r������C�x���A�����ɓ����Ă����������A�����̎��̂悤�Ɏv��ꂽ�����������Ƃ����B�܂�����ȑ̌��������B���ăC���h�ɍs�����Ƃ��A�j���[�f���[�ő�w�̐搶�ƃ^�N�V�[�ɏ�����B���炭����������A�ˑR�^�N�V�[�̉^�]�肪�����Ȃ�ʌ`�������ĎԂ��~�߂��̂ŁA�������Ǝv���ėׂɂ������̐搶������ƁA�ނ��s���ȕ|��ɂ������悤�Ȋ�����Ă���B�����ƁA�^�N�V�[�̑O�����܍��L�����������̂��Ƃ����B �@���ꂩ��^�]��Ƃ��̐搶�́A�Ȃɂ��b���n�߂����ƁA�^�]��͊O�ɍ~��Ă����āA���̂킫�ɗ��q���Y�[���̐_���̏��܂ōs����ʈ��S�̋F������������̂������B������̐搶���������邱�Ƃ�]��ł̂��Ƃł���B���L���ڂ̑O���悬��ƍЂ����N����Ƃ������M�́A���{����łȂ��C���h�ɂ�����̂��B �@����Șb���ƁA���L�������Ă���l�͂ǂ��Ȃ�̂��A�����ڂ̑O���������Ă���Ǝv���̂����A���̐l�����͖����s�K�Ɍ������Ă���̂��Ƃ��������Ȃ��Ă���B���Ȃ݂ɁA���̃C���h�l�̐搶�́A������Ƃ����n���̑�w�̏y�����Ƃ����C���e���ŁA���������͓����w�������B���̐搶����w�ł́A���L��������ƍЂ��������炷���璍�ӂ��悤�ȂǂƂ܂������Ă������Ă��Ȃ����Ƃ�M�������B���āA�n�[���́A��ɂÂ��Ă���Ȃ��Ƃ������B
�@���{�̌��i���Ƃ킴�j�ł́A�����`�����Ă���B�u���͎O�������A���̉����O�N�͖Y��Ȃ��B�������A�L�͎O���ł��̉���Y���v�B����ɁA�L�͂�������D���ł���B���A��q�Ɍ��������A�����Œ܁i�߁j�������B�������A�L�͎�i�̂�j��ꂽ�����Ȃ̂��B���Ɂi�Ԃ��j������i�ɂイ���Ⴍ�j�̍ۂɁA�L�ƓŎւ������܂𗬂��Ȃ��������Ƃ���A���̓�C�̓��������͋Ɋy��y�ɍs���Ȃ��ƌ����B�����Ɍ��炸�A�܂��ق��ɂ����ꂱ�ꗝ�R�������āA�o�_�ł͔L�͂���Ȃɉ��i���킢�j�����Ă��Ȃ��B�����Ă��͖�O�ɒǂ�����A���̂܂ܖ�ǔL�Ƃ��Ĉꐶ�𑗂炴��Ȃ��B�B �@����͂܂������s���Șb���Ǝv���B���͂����ǂ�ŁA���{�ł͂Ȃ���ǔL�����������Ɍ���Ȃ����̗��R���قڂ킩�����C�������B���{�l�̔L�ɑ���|��ɂ������l�K�e�B�u�ȃ����^���e�B����ǔL�����o�������ɂȂ��Ă����̂ł���B���̔L�𔖋C�������������Ƃ��Ėь������镗�y�͂ǂ����ō����Â��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�܂��A�n�[���������悤�ɁA�L�͉��m�炸���Ƃ��悭������B�������A���͍ŋ߁A�l�b�g��YouTube�ŁA�����ւ��l�v���̔L�����邱�Ƃ�m�����B����̓A�����J���낤���A��O�Ō��ɏP���Ă��鎔����̎q�ǂ��������悤�Ƒ����Ă������ɑ̓����肵����A�����錢�̌��ǂ������Ēǂ��������E���ȔL����̉f���������B���͂������������Ă��܂��A���̌㉽�x�����̉f���������B����ł��L�͉��m�炸�Ƃ����邾�낤���B �@�܂��n�[���́A�L�͂��߉ނ��S���Ȃ�Ƃ��A�܂𗬂��Ȃ������̂ŋɊy�ɂ͍s���Ȃ��ƌ����Ă���Əq�ׂĂ��邪�A����ɂ��ƁA���{�̔L�͕����o�T���l�Y�~�̊Q�����邽�߂ɕ��m���嗤����A��Ă����Ƃ������Ă���B���������Ȃ�A���������N�����̕S�ς��琳���ɓ����Ă����鉻3�N(538)�A����ɋԖ�13�N(552)�ȍ~�̂ǂ����̎��_�ŁA���{�ɘA��Ă����ċA���������ƂɂȂ�B�L���l�Y�~�̊Q���畧�T������Ă����Ƃ���A����Ȃ�ɔނ�͂��߉ނ���╧���ɍv�����Ă����̂ł���B �@�n�[���́A�L�̌��_�����낢��Ƃ�������Ă��邪�A�l�I�ɂ͔L�������������킯�ł͂Ȃ��悤���B���̏؋��́A���̉��~�Ɉ����z���Ă��鎞�A�u�ȃZ�c�A�����A�q�L�ƂƂ��ɂ킸���ȉƋ�����������āv�]�������ƃn�[���̌����҂ŁA�{���̖�҂̒r�c��V�������Ƃ����ŏq�ׂĂ���̂ł���B �@�n�[���́A�ʂ̔L�������Ǝ����Ă����̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A�n�[���������ŏq�ׂĂ���L�ɑ���Ђǂ����������́A�����̐l�тƂ̔L�ςł����Ĕގ��g�̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B�����L�̏K�����������ƐM���Ă�����A�ƂĂ��|�낵���Ď��������̂ł͂Ȃ������͂����B �@�������A�n�[���͉��~�̒�ɗ����ǔL�ɑ��ẮA���i�����j�̈�����D�_���Ɨe�͂��Ȃ��B�����Ƃ��̔L�͉������Ȃ��A�n�[��������ƈЊd������A���̂���邾������Ă͂����ɓ������邩���Ă����̂��낤�B�����炭���̔L�͒N�ɑ��Ă������ł������ɂ������Ȃ��B���͂�A�l�ɐS���J�����Ƃ͂Ȃ��A�l�Ԃ�������M�p�ł��Ȃ��Ȃ��Ă����̂��Ǝv���B �@�����A�l�Ԃ��ǂ��v�����ƁA���̖�ǔL�ɂ��Ă݂�ΓD�_�ҋƂ����Ă���Ƃ����ӎ��͂܂������Ȃ��������낤�B�v�z�Ƃ̃f���_�́A�L�͎��炪���ł���Ƃ����ӎ��⊴��������Ȃ����䂦�ɁA�ނ�͗��Ő������Ă���킯�ł͂Ȃ��Əq�ׂĂ��邪�A����Ɠ��l�ɔނ�ɂ͓��݂����Ă���Ƃ����ӎ����Ȃ��ȏ�A����͓��݂ł͂Ȃ��B�ނ͓w�͂��Ċm�ۂ����Ȃ��ɂ���l����ނ̏K���ɂ��������ĕߊl���Ă��邾���ŁA�l�Ԃ̂��̂������߂Ă��������Ȃ��A�l�Ԃ͂ނ��낻�̎ז����Ă�����x�����ׂ����҂��炢�Ɏv���Ă������낤�B �@�쐶�����ł���A���R�Ɏ�������쐶�̓��A����߂��ĐH�ׂ�悢���A�ނ�͖쐶�������������Đl�ԎЉ�ɘA��Ă���ꂽ�������ɂ͎��R�̐H�ו��͂Ƃ��ɂȂ��B��ǔL�͓���A�W�A�̎��@�ɂ���悤�Ȓn��L�A�R�~���j�e�B�E�L���b�g�ȂǂƂ͈قȂ�A�ߗZ�����������炵�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŊF����ϋɓI�ɐH�ו���^�����邱�Ƃ��Ȃ��B �@�n�[������ǔL(��L)�Ɋւ��ẮA�����̓��{�l�Ɠ����悤�ɔF���s���������Ǝv���B�ނ͖�ǔL�������ȑO���炻���ɐ��݂��Ă͓��݂��͂��炭���f�Ȗ쐶�����̂悤�Ɍ��Ă��邪�A���̌����͌���Ă���B�܂���ǔL�����́A�쐶��ł͂Ȃ��B�ނ�́A���Ė쐶�����������R�L��l�Ԃ��쐶������������Đl�דI�Ɏ�����炵�č��グ���Љ�I�ȉƒ{�ł���B�ƒ{�Ƃ����̂́A�l���˂ɉ�����Ĉێ��E�Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł���B �@�������č��ꂽ�Ȃ��ΐl�H�I�Ȑ������Ȃ̂ŁA�I���l�Ԃ��ʓ|�����ė{�炵�Ă����K�v������B�ނ�́A���͂�l�ԂȂ��Ɉ�l�ł͐����Ă䂯�Ȃ��g�Ȃ̂��B����ɂ������R�ɂ����ǂ�Ȃ��B���܂���R�L�ɂ��ǂ��āA�R���Ŏ���������ĕ�点�ƌ����Ă��A����͂ł��Ȃ��̂��B���̂��ߐl�ԂɎ̂Ă�ꂽ�ނ�́A�l�Ƃ̎��͂����Ƃ��Ďd���Ȃ��������Ă��������Ȃ��B����āA�ނ�ɂƂ��Ă̎�Ƃ����A�l�Ԃ̏��L���������ߎ���Ă��������藧�Ă��Ȃ��̂��B �@����͓����Ƃ��Ă͖{���̎p�Ƃ͎��Ă������ʕs���R����܂�Ȃ������ł����āA����͖쐶�����ł��Ȃ��A���ߓ���(�y�b�g)�ł��Ȃ��Ƃ����ǂ��������̊�ȑ��݂Ȃ̂��B���̓����A�N�������{��ӂ������ߔނ�͎d���Ȃ��ɖ�ǂɏo�Ď������ɐB������������A��ނȂ��l�̂��̂��Ƃ�悤�ɂȂ����̂ł���B �@�₹�ׂ�����D�_�̖�ǔL�ɂ����̂́A���������N���B�낭�ȐH�ו����^����ꂸ�A�Q�����Ȃ����ŁA�G������l�Ԃɂ��P���邩�킩��Ȃ��M���M���ْ̋��̒��Ő����Ă���A�₹�����̂��������炻���ȑ��e�ɂ��ς�邾�낤�B�l�̑��������₦����������l���ŁA�l�����ۂ��Ȃ��琶���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ނ�̐S���͂䂪�܂���Ȃ��B �@���������A�l�Ƃ͖����Ɏ��R�̒��Ő����Ă����쐶�L���ƒ{�����Đl��ꂳ�����̂͒N���B�l�Y�~��߂点��g���Ƃ��āA���邢�͎₵����킷���ߓ����Ƃ��Ĕނ��g�߂ɒu�����̂͒N���B���̎����r���ŕ������Č��̂Ă��̂͂��������N���B����͂����l�Ԃł���B�f���Ĕނ�͍D���D��Ńm���Љ�̃A�E�g���[�Ƃ��ēD�_�̓��ɓ������̂ł͂Ȃ��B���̌�����������̂́A���ׂĐl�ł���B �@���̔L�������������Ƃ����Ĉ���Ō���������Ď����̂���ʏ�������B����ȓx��������̒��ɓ��{�̖�ǔL�����͒u����Ă����B���́A�y�b�g�̎E�����ɍs�����o���������Ȃ�A�����ƐV���Ȏ�����T���Ɍ����������ׂ����Ǝv���B���ꂪ�g����ŋ��~�Ȑl�Ԃɂł���A���߂Ă��̏����ł͂Ȃ����B �@����ɁA�s���s���ƂȂ����y�b�g�̑{���i����͐����ʂ�̃y�b�g���X�̖��j��y�b�g�̎��ʃP�A�ɍs����������Č��������������������Ƃ��s���Ăق����Ǝv���B�����̊����ɂ͌���������邾���̉��l������B����ɂ����́A�y�b�g�ƕ�炷�l�Ԃɂ��������ł�����B �@�y�b�g���X�̃T�|�[�g�́A������Ƃ����l�Ԃւ̎x����ړI�Ƃ��Ă���B���L����14�Έȉ��̎q�ǂ��̐���葝���A���v���6�l��1�l�����L�ƕ�炷����ɂȂ������A�s���������̖��Ɏ��g�ނ��Ƃ́A�����̐l�тƂւ̃T�[�r�X�ɂȂ�B�y�b�g�̂��ƂƂ����Ă��A�������ɂ��Ă���̂̓y�b�g�Ɋ֘A�����l�Ԃ̐��_�ی���̃e�[�}���q�ׂĂ���̂ł���B �@�����������b������ƈȑO����A�y�b�g��y�b�g�������Ă���ꕔ�̐l�X�̂��߂����Ɍ�����g�����Ƃ́A�����������ƂƂ���ŋ��̎g�����Ƃ��ĕs�������Ƃ����c�_�����邪�A����͂������Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�A�ǂ̕���ł������𓊓����Ă����ꂪ�S�Ă̐l�����b�������ނ�Ƃ����̈�͏��߂��瑶�݂��Ȃ�����ł���B����͎q��āA����A������ÁA�����{�݂̌��ݓ��X�ł������ł���B���ꂼ��ɂ������̂���l�X���������v�ΏۂƂȂ�B �@��N���s���Ă�����ԎR���Ό�̋~����s���҂̑{�����A��Ў҂�⑰�Ƃ����ꕔ�̐l�X�̂��߂ɁA�����̌�����g���Ă���B�q��Ďx���Ȃǂ��A�q�ǂ��̂���v�w�ɂƂ��Ă͉��b�ɂȂ邪�A�q�ǂ��̂��Ȃ��v�w�ɂƂ��ẮA���b�ɂ͂Ȃ炸�t�ɕ��S�ƂȂ�B�悻�̎q�̉ƒ�̂��߂ɁA�ǂ����Ď��������܂Őŋ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ƕs���Ɏv���l�����邩������Ȃ��B����ɂ��ꗝ����B�������f�肵�Ă������A���͂����Ɍ���𓊂��Ȃ��Ă悢�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ͕t�L���Ă��������B�@�i�����j
|
|||||||
�@
�@����4�ʁE5�ʁE6�ʂ����킹��ƕ�����(�D���Ȃ������R��������)�ł́A����55.8���ɂȂ�B����͌��ƔL���Ē��ׂ����ʂł��卷�͂Ȃ��Ƃ����i����57.9���A�L��54.2���j�B���Ȃ킿�A���̒����ł͓�l�Ɉ�l���̐l���y�b�g�Ƃ̎��ʂɗ���ŁA���̃y�b�g���������ɂ��邱�ƂɂȂ�B�܂��A�P���i��������R��������j�̏ꍇ�ł́A���̎O�����킹���20.8���ƂȂ�A��5�l��1�l�Ƃ����v�Z�ɂȂ�B���Ȃ݂ɁA�P���ł́u�ʂꂪ�炢����v�́A�u�����������邩��v���ĂR�ʂɕ��サ�Ă���B���̂��Ƃ́A�y�b�g������Ȃ����R���A�������p�̖������y�b�g���X�ɂ��ʂ�̂炳����ɂ���l�̕����������Ƃ������Ă���B �@��L��4�ʁE5�ʁE6�ʂ̎O�̑i���́A�ʏ�̃y�b�g���X�̔߈��v���Z�X�ł́A��������}�����Ǐ�A���Ȃ킿�y�b�g��S�����Ă�����������܂肽���Ă��Ȃ����Ԃɑ����G�s�\�[�h�ł���B�Ƃ���6�ʂ̃y�b�g��S�������V���b�N�������Ă��Ȃ��Ƃ����\���͈�ʓI�ɂ́A���ʒ���ɑ����G�s�\�[�h�ł���B���̒����ɂ́A�����Ώێ҂��O�̃y�b�g���ʂ���ǂ̂��炢�����������Ă��邩�̕\�L���Ȃ����߂ɁA���m�ɂ͌����Ȃ����A���y�b�g�������Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��A���̐l�����̂��ׂĂ��ŋ߃y�b�g��S�������l����ł͂Ȃ��͂��ł���B���̉������l�����̒��ɂ͎��ʂ��牽�J�������N�������Ă���l������ɂ������Ȃ��B �@���Ƃ���A���̐l�����̒��ɂ́A�ʏ�̌o�߂����ǂ��ė��������Ă����y�b�g���X�̌��҂ł͂Ȃ��l������\��������B�ʏ�̃y�b�g���X�̎��ʔ����ł���A���q�ׂ��悤��4�ʁE5�ʁE6�ʂ̑i���́A�}�����̃G�s�\�[�h�Ǐ�Ƃ��ĕ\��邪�A���Ԍo�߂ƂƂ��ɂ����̕\���͏��X�Ɍ����Ă����A�Ɍ������Ă����B�����āA���炭���ė��������čĂю��̎q��������悤�ɂȂ�B�������A�����̏Ǐ��܂炸�ɂ��܂ł������Â���̂ł���A����͐���i�ʏ�j�Ƃ͂����Ȃ��y�b�g���X�Ƃ������ƂɂȂ�B���̐���Ƃ͂����Ȃ��y�b�g���X���A�y�b�g�͍D�������V���Ƀy�b�g���}���邱�Ƃ��ł����Ƀy�b�g������N�����l��A�y�b�g�����ɂȂ��Ă����l�ݏo�������ɂȂ��Ă���̂ł���B �@�܂��A���̎O�̃y�b�g���X�ɂ������v����������̐���ʂŒ��ׂ��f�[�^������ƁA��������N������Ȃ��Ă����قǂ��̊����������Ȃ�X�����F�߂���B����ɁA70��̐l�тƂ�����Ώۂɂ��Ē��ׂ����ʂł́A���̎�����́u�ʂꂪ�炢����v���A�u�Ō�܂Ő��b�����鎩�M���Ȃ�����v�ƂƂ���1�ʂ������A�u���ʂƂ��킢����������v��2�ʁA�u�ȑO�̃y�b�g��S�������V���b�N�������Ă��Ȃ�����v��5�ʂł���B70��̔L�̎�����̌��ʂł��A�u���ʂƂ��킢����������v����͂�2�ʂƂȂ�ȂǁA��������y�b�g���X�ɊW�����肪�V���Ƀy�b�g������Ȃ��傫�Ȕ}��v���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���Ă����B����͎����傪����ɂȂ�Ȃ�قǃy�b�g���X�̏Ռ��ƃ_���[�W���傫���Ȃ��Ă���ƍl�����邱�ƂƁA���̌��ʃy�b�g������N�����Ă����l�������Ă��邱�Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ́A����҂̃y�b�g����ƃy�b�g���X���ɂ́A�Ƃ��ɒ��ӂ��K�v�����邱�Ƃ��������Ă���B����҂̌ǓƂ�a�O���̌y���Ƀy�b�g�͔��ɗL�����ƍl�����邪�A�y�b�g�̎��{�Ǘ���I�������̎菕���A����ɂ͎��ʌ�̎x���̐��܂ł�z�����������ł��N���Ƀy�b�g�������߂�ׂ��ł���B �@�܂��A�`���̑j�Q�v��7�ʂ́u�Ō�܂Ő��b�����鎩�M���Ȃ�����v�y�b�g������Ȃ��Ƃ������R���A���̐l�����̂Ȃ��ɂ́A�V��y�b�g�̉���I�����P�A���s���Ă������Ƃ�A�y�b�g�̍Ŋ��̊Ŏ��ւ̕s���⋰�ꂪ����ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�y�b�g���X�͈�ʓI�ɂ́A�y�b�g�����S���Ă���N����Ǝv���Ă��邪�A���������̓y�b�g���S���Ȃ�O���炷�łɎn�܂��Ă���B�����I�ȔߒQ�ł���B���̍Ō�܂Ő��b�����鎩�M���Ȃ��Ƃ́A�Ŋ��̐��b��Ŏ������鎩�M���Ȃ��A�y�b�g�̎��͂炢�����Ƃ����ނ肽���A�Ƃ����Ă���悤�Ɏ��ɂ͕�������̂ł���B �@����ɍ���̒����ł́A���L�𑽓��������Ă���l�ɂ��̗��R���Ă���i�u����������̗��R�i�����j�v�A�����Ώێ�322�l�j�B����ɂ��A�u�P�����ƃy�b�g���₵����Ǝv��������v�i42.9���j�A�u�y�b�g���m�ŗV�Ԃ̂ŁA�^���s���������ł��邩��v�i35.4���j�A�u1���̎������y�b�g�ɖ�����邩��v�i17.7���j�Ȃǂɍ������āA�u�S���Ȃ����Ƃ��ł��A���̃y�b�g�ɈԂ߂��邩��v�Ɖ����l��9���A�u�y�b�g���X��h�����߁v�Ɩ��m�ɓ������l��7.8������Ƃ����B�O�҂͌�҂ƂقƂ�Ǔ����܈ӂƌ��Ă悢�Ǝv���̂ŁA���҂����Z�����16.8���ɂȂ�B �@����16.8���̎����傳���́A���łɃy�b�g���X�ւ̗\�h�����ĕʂ̎q�������Ă���̂ł���B����̓y�b�g���X�����邩�瑁����������ꓪ�����Ă������Ƃ��鎔����̖h�q�I�ȍs���ł���B�����[�����Ƃɂ��̐l�X�ɂ́A���܂ŏq�ׂ��悤�ȃy�b�g���X���y�b�g������Ȃ��j�Q�v���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A���ɐV���Ȏq���}���鑣�i�v���ɂȂ��Ă���̂ł���(�y�b�g�Ƃ̎��ʒ���ɗ҂�����炳�ɑς����˂āA�V���Ȏq���Փ���������l�̏ꍇ�ł����A�y�b�g���X�����̎q���}���鑣�i�v�����Ƃ�����)�B���Ɏ����傽�����y�b�g���X��Ƃ������@�ŊF�����������s�����Ƃ�Ƃ���A��������҂�����ɑ����邱�ƂőS�̂̃y�b�g���͌��炸�ɂ��ނ��A�ނ��둝���Ă������ƂɂȂ邩������Ȃ��B �@�����A���ʂɔ����Ă����ꓪ�����Ă������Ƃ��ߒQ�̉ɂ悢�ƁA�����P���ɂ͂����Ȃ��B�ꓪ�̎q���S���Ȃ��Ă��A�����ꓪ���邩��ʂ�͂炭�Ȃ����Ƃ����ƁA����Ȃ��Ƃ͂Ȃ�����ł���B�V���Ƀy�b�g�������n�߂��Ƃ��Ă��A�O���炢��q�ւ̈���Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ����낤�B�y�b�g���X�̔ߒQ�̒��x�́A���̃y�b�g�ɂ����Ă�������̒��x�ɑ傢�ɍ��E�����̂ŁA������������u����Ńy�b�g���X�͉����I�v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂��B����͐e�ɂƂ��āA���j��r���Ă��A���j�����邩�璷�j�̎��ʂ͔߂����Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ��Ȃ��̂Ɠ����ł���B �@�������A�ꓪ�����̃y�b�g��S�����������傳��̒��ɂ́A�l���̂��ׂĂ��������悤�ȋ������Ƌ�����]���ɏP����l�����邱�Ƃ������ł���B���̂悤�Ȑl�����Ă��āA���Ƃ����ꓪ����Δ߂��ݕ��͂�����������������������Ȃ��ƍl���Ă��܂����Ƃ�����B�����A�������������Ă���N���C�G���g����̒��ɂ��A�S�������q�����ʂȑ��݂ł���A�r�����Ƃ��̔߂��݂Ɨ��_�͔��ɑ傫�Ȃ��̂ɂȂ�l������B����āA�����ꓪ�y�b�g������A���̃y�b�g�ɈԂ߂��āA�y�b�g���X��h����ƒf�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �� �@�y�b�g�ƊE�͂��܂܂ŁA�y�b�g���ɂ��鎔����̏��A�����̖������Ƃ����ސl�X�̎��ߐS�Ɏx�����Ă����܂Ő������Ă����B�����ċߔN�́A�y�b�g����͐S�g�̌��N�ɗǂ��Z���s���e�B�b�N�Ȍ��ʂ�����Ƃ��A�q�ǂ��̗È�ɂ��悢�Ƃ���AAT(�����x���Ö@)��AAA�i�����x�������j�Ɋւ���Ȋw�I�f�[�^��������ɂ�āA�����W�҂͂�����傫�ȃZ�[���X�|�C���g�ɂ���悤�ɂȂ����B�y�b�g�Y�Ƃ�b��ÊW�҂��͂��ߓ����ɂ������l�X�ɂƂ��āA�����ɂ͖������ʂ�����Ƃ������ƂقǍD�s���Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂ł���B���̌��t�قǃy�b�g����𐄏����邤���Ō���I�ƂȂ�S���������͂Ȃ������B���̂��ߓ����W�҂́A�������Ĕ�т����̂ł���B���̌��t���т̌���Ƃ��邱�Ƃɂ���ē������҂͂��̕���ł͂��炭�ւ�����Ă�悤�ɂȂ������A���������̑��ݗ��R���������ꂽ�B�܂��A�ƊE�̃C���[�W���ȑO�ɔ�ׂĂ����Ԃ�ǂ��Ȃ��Ă������B �@����ɑ��A�y�b�g���X�̖��́A�y�b�g�W�҂ɂƂ��ď]�����炠�܂�\�����ɂ������Ȃ��e�[�}�������B�y�b�g�����ʂ炳�𐢊Ԃ̐l�X���m��A�y�b�g������Ȃ��Ȃ�Ƃ�����@�ӎ�������������ł���B�y�b�g�̎��̖��́A�Ȃ�ׂ����ɂ��܂��ĐG��Ăق����Ȃ������������B�������A�y�b�g�W�҂��������������ł݂��Ƃ���ŁA������̃y�b�g���X�̔߂��݂��Y��������킯�ł͂Ȃ����A���̂炳���J���A�E�g���邱�Ƃ���߂����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�y�b�g���X�̌��҂̌��Ɍˌ��𗧂Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B �@�ŋ߂́A�Ђ�ς�Ƀy�b�g���X�֘A�̏��Ђ��o�ł����悤�ɂȂ����B���̂Ȃ��ɂ́A�y�b�g���X�̃T�|�[�g���s���Ă���@���Ƃ⓮���W�҂�J�E���Z���[�Ȃǂ����������̂����邪�A�y�b�g��������l������̃y�b�g���X�̌����ڍׂɂÂ������̂������Ă����B�ǂ̂悤�Ȑl�����M����ɂ���A�����������{�����������ɏo�Ă��邱�Ƃ́A���ꂾ���y�b�g���X���s�����Ă������ʂ��Ɖ��߂������B�y�b�g���X�̂��Ƃ͓����W�҂��S�z����܂ł��Ȃ��A�����傽������ԐS�z���Ă��邱�Ƃł���B�y�b�g�Y�Ƃ̏]���҂��A�y�b�g��������l�X�̂��Ƃ��v���̂Ȃ�A�y�b�g�r���ɂ���Ċ�]���Ȃ����Ĉ����������Ă����l�ɉ��炩�̎���������������ƍl����͂����B �@�y�b�g�̎��ʖ����I�[�v���ɂ��Ď��g�ނ��Ƃ́A�y�b�g�Y�Ƃ̐����ɐ����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̗��R�́A�y�b�g���X�̃P�A�����Ďx����ƂȂ邱�Ƃɂ���Ď�����̃y�b�g�����h�����Ƃ��ł��邩��ł���A���̂��߂܂��V���Ȏq���}������悤�ɂȂ邩��ł���B�����Ȃ邱�Ƃ��A�y�b�g���X�E�T�|�[�g�̖ڕW�̈�ł�����B�����傪���������Ď��̃y�b�g�������Ăуy�b�g���C�t���y���߂�悤�ɂȂ�B���̏z��f����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ́A�y�b�g�Y�ƑS�̂Ƃ��Ă��傫�ȃ����b�g�ɂȂ�B�y�b�g���X�E�P�A�͎�����l�̂��߂����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�Ђ��Ă̓y�b�g�Y�Ƃ̂䂽���Ȕ��W�ɂȂ��邱�Ƃ�F�����Ăق����Ǝv���B���{���͂Ƃ��Ă����A�����J�̃y�b�g�Y�ƊE�́A�y�b�g���X�Ɋւ��Ă��łɂ��̔F���������Ă���B �@����ɂ��Ă��A���N�̃y�b�g�t�[�h����̃f�[�^���Ԃ��Ɍ���ƁA�y�b�g���X�Ɋ֘A���ăy�b�g������Ȃ��Ȃ�l�������ɑ������ɋ��������B���4�ʁE5�ʁE6�ʂ��u�y�b�g�̎���ʂꂪ���邩��v�Ȃǂƈ�ɂ܂Ƃ߂ďW�v����A����j�Q�v���̒f�g�c�̂P�ʂɖ��o��B�P���̕��ł��A�O���܂Ƃ߂�Q�ʂɂȂ�B�����̌��ʂ́A�����뜜���Ă������Ƃ������ƂȂ��Ă������Ƃ���Ă���B���̈Ӗ�����A���̃f�[�^�͕M�҂��ȑO����咣���Ă������Ƃ��I�ɗ����Ă���Ă���i���G�b�Z�[�w������x�Ɠ����͎���Ȃ��x���Q�Ƃ��������j�B �@�y�b�g���X��肪�y�b�g�Y�Ƃƃy�b�g�������W�̋t���ɂȂ邩�A����Ƃ��ǂ����ɂȂ邩�́A���ꂩ�玔����⓮�����҂ւ̐������y�b�g���X��������邱�ƂƁA�������肵���T�|�[�g�̐����\�z���邱�Ƃɂ������Ă���B����ɂ̓y�b�g�̎��ʃP�A����������ł���y�b�g���X�E�J�E���Z���[���K�{�ƂȂ��Ă���B���̃J�E���Z���[�͍���Ă����Ȃ�����̍��ɂ͐��܂�Ȃ��B���̐l�����́A���R�ɓV����~���Ă��邱�Ƃ��Ȃ���A�n����N���Ă��邱�Ƃ��Ȃ��̂ł���B���Ԃ������ĂЂƂ�ЂƂ�琬���Ă��������Ȃ��B���̖��́A�����ڐV�����y�b�g���X�E�O�b�Y������čL�߂���A��������������ɍs���Ή����ł���Ƃ������x���̘b���ł͂Ȃ��̂��B �@�y�b�g�t�[�h����A���̂悤�Ȓ�������N����n�߂��̂��A�����ł̌��L�̎��瓪���⎔�琢�ѐ����������͂��߂����炾�낤�B���L�ȊO�̃y�b�g������͂��߂Ă���B�y�b�g�����S�̂Ƃ��Č����Ă����Ƃ������Ƃ́A�`���Ŏ������P�ʂ���P�P�ʂ܂ł̂��܂��܂ȗ��R�Ŏ����Ȃ��l�����������Ă��邱�Ƃ�\���Ă���B����Ȍ���̒��ŁA���̌�����H���~�߂�ɂ́A�y�b�g���X���͂��ߑ��̎���j�Q�v�����W�҂��y�b�g���D�Ƃ��F�Œm�b���o�������Ȃ��狦�͂��Ĉ��������Ă��������Ȃ��B���̓w�͂�ɂ��߂A�܂��܂�������̃y�b�g���ꂪ�i�ނ��낤�B �@���͒P���Ƀy�b�g����������Ηǂ��Ƃ͎v���Ă��Ȃ����A�y�b�g�Y�Ƃ���������ɂȂ�Ηǂ��Ƃ��l���Ă��Ȃ��B�����]��ł���̂́A�䂽���Ȑl�Ԃƃy�b�g�̕��������̎Љ�����Ƃł���B�y�b�g���X����y�b�g�������Ȃ��Ȃ�l��A�y�b�g�����ɂȂ�l������̂͂ƂĂ��c�O�Ȃ��Ƃ��Ǝv���̂ŁA���������l�͂Ȃ��������Ɩ]��ł���B�y�b�g�Ƃ̕ʂ�ɂ������āA���4�ʁE5�ʁE�U�ʂ̖�肪�A�䂽���ȃy�b�g���C�t��j�Q���Ă����匴�����Ƃ���A�y�b�g���X�̃O���[�t�P�A�������Ɉ�i�Əœ_�����킹�Ă����K�v������B�����ɔ����߈����i�\����Ȃ��j�����⎀�ʂ̃V���b�N�̌y���m�ȉ����ڕW�ɂ��邱�Ƃ��A���ǂ��ɂȂ���͂��ł���B���N�ȍ~�A���̃y�b�g�t�[�h����̒������ʂ��ǂ��Ȃ�̂��A�ڂ������Ȃ��B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�i�P�j �@�M�҂͂��炭�O�A�y�b�g���X�̔ߒQ�P�A����݂āA��������̌��ʂ����҂ł��A�������D�ꂽ�R����������y�b�g���X�̋Ȃɏo������B����̓V���K�[�\���O���C�^�[�̍���D�q����̉̂��w�{�N���T�ɂ��邩��E�E�E�x�Ƃ�����i�ł���B���̊y�Ȃ����A�y�b�g���������l�X�̊ԂŁA�Â��ɍL�������B �@���̂b�c�́A�x���E�b�h�E���R�[�h�i�L���O���R�[�h�n��j����2012�N7���Ƀ����[�X����Ă���B���̋Ȃ͂��łɃC���^�[�l�b�g��YouTube��2008�N����A�C���X�g���[�^�[�̂l�`�q�t����̊G�{����Ƃ̍���̂c�u�c�Ƃ��Ĕ��\����Ă���A����͂���ł����R�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���̃C���X�g���܂��W�[���Ƃ���f���炵����i�ŁA���҂̃R���{���ƂĂ��悢�̂����c�O�Ȃ��炱�̂c�u�c�͂܂���������Ă��Ȃ��B �@���̍�i�́A�߈���Ƃ̑��i�ɂ͂��炭�Ǝv����B���Ȃ킿�A�y�b�g���X�̌��҂͐S����\���ɔ߂��܂��Ă��炦��̂��B�������A���̋Ȃ̂悢�Ƃ���́A�����ɂ��܂ł��Ƃǂߒu����邱�ƂȂ��A��������E���グ���Ă��ʂ���m��I�ɐU��Ԃ邱�Ƃ��ł���悤�Ȕz�����Ȃ���Ă���B����͋~���ł���B���̂悤�ȓ_���炱�̍�i�́A����哮����r�����l���Ԃ߂��Ė����Ɋ�]������������q�[�����O�E�A�[�g�Ƃ�����Ǝv���B �@���d�ɂ��A�M�҂͂��̊y�Ȃɂ��āA���������_�]���Ă݂����Ǝv�����B�����A���ɂ͉��y�Ɋւ���f�{���Ȃ��B�ߓ��A���䂳��A���̋Ȃ�16�r�[�g�łł��Ă���A���������Ȃ�8�r�[�g���16�r�[�g�������Ƃ������������Ƃ�����B�������A���ꂪ�ǂ������Ӗ��Ȃ̂��悭�킩��Ȃ��B���������r�[�g�����ł��邩���킩��Ȃ��B�����Ńr�[�g����g�̍��ꎫ�T�Œ��ׂĂ݂����A�w���Ƃ���������x�Ƃ����o�Ă��Ȃ������B�w���Ƃ���������x�̂��Ƃł͂Ȃ��͂������A����ȏ�̂��Ƃ͂킩��Ȃ��B����āA���̍�i�̐����̂��Ƃ͂ЂƂ܂����ɒu���āA�܂��͂��̎����̂ق����猩�čs�����Ƃɂ��悤�Ǝv���B�`���͎��̂S�傩��n�܂�B �@�_�炩�ȁ@���̒��� �@�����ł́A���łɂ��̐��ɗ���������C�̔L�̃{�N����l���ł���B�{�N�͍�҂̍���D�q�������Ă������L�ł���A�V����S������B����̓{�N�����V���ĉ_�̏�ɏ���Ă���Ƃ��납��n�܂�B�����͏_�炩�Ȍ��ɕ�܂�ċ�C�͐��݁A�D����������Y���ق̂ڂ̂Ƃ����ƂĂ����S�n�̗ǂ������ȂƂ��낾�B�����ɏ������{�N�́A�������爤����������̎p��������Ă���B �@���̂S�s���������ł���A����ɂ���ĕ���̏ݒ肪�Ȃ����B���������̏��i�͏�i�`�ʂ����o�I���o�I�ɂȂ���Ă��邽�߂ɁA�����҂͊��o���Ƃ��Ȃ����f��������悤�ɂ��̓V���̃C���[�W���E�ɂ���Ȃ���荞��ł����̂ł���B���̎��͎�l�������S�����Ƃ��납��n�܂�Ƃ����ꌩ��ȏo�����Ȃ̂����A���̂��Ƃ����قLj�a���Ȃ��������̂́A�����V�����u�_�炩�Ȍ��v�Ɓu����C�v�Ɓu�D��������v�Ƃ����S�n�悢�A���j�e�B��ԂƂ��ĕ\������Ă��邩��ł���B���̂��߂ɒ�����͖������悤�ɂ������胊���b�N�X���Ă��܂��̂��B����������͂��������C�ɗ�������悤�Ɍ����̐��E�Ɉ������ǂ����B �@�{�N�̎ʐ^���ā@�{�N�̎�ֈ��肵�߂� �@���Ɏ�l���͂������王���𗎂Ƃ��Ēn��߂�B����ƃ{�N�̎ʂ��Ă���ʐ^���Ă₢���g���Ă�����ւ����肵�߂ċ����Ă���N��������B���̎����̐��ڂ͂��̐����炱�̐��ւ̎��_�̈ړ������A���䂳��̎��͂����ł��J�������p�������Đl����ǂ��悤�ɉf���I���B���͂Â��B �@���܂ł������ƈꏏ�ɋ�������͂��Ȃ̂� �@���̒i�ł͎�l���̃{�N�̓��ʂ��J�������B�N�̔߂��ގp�������{�N�͋���ɂ߂�B����͂��܂ł��Ƃ��ɕ�炷�����Ă����̂ɁA���ꂪ�ʂ����Ȃ���������ł�����B������҂Ƃ̊Ԃɂ͖���Ɍ��킳���B����͉i���̈��̖��B���������̌_��͉ʂ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�i���ɂÂ������Ȃǂ͂��̐��ɂ͉������݂��Ȃ����炾�B �@�Ƃ�킯�����Ƃ̊W���������B�Ƃ��ɂ��邱�Ƃ�~���Ă����������̎����͋ɒ[�ɒZ���B���L�ł������ď\���N�̖����B������ނ�Ƃ̊Ԃł��낢��Ȗ����킵���Ƃ��Ă��[�Ƃ����Ă��A����͎����傪����I�Ɏ�茈�߂���̂����[����͂����������̂ɂ����^���ɂ���B���Ȃ킿�����Ƃ̖Ƃ́A������̊�]�̕\���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̍�i�͂��̈Ӗ�����A�y�b�g�E����哮����������������̉i���̊肢���̂������̂ł���Ƃ�����B �@���̎��͂��łɖS���Ȃ��ė�I���݂ƂȂ����L�̖ڂ�ʂ��Č���邪�A���̓_����݂āA���̍�i�͓�̕��G�ȍ\���v�f���������Ă���B��́A���̐��Ƃ��̐����������鐢�E��ݒ肵�A���̐��̐l�ԂɖS��ƂȂ����L���z����`����Ƃ����_�ł���A���̈�͂��̌���{����邱�Ƃ̂Ȃ��������[�l�����Đl�Ԃ̌��t����点��_�ł���B �@�����ł����l�Ԃ̌��t�Ƃ́A��҂̌��t�ł���B�{�N�͍�҂ł��鍡�䂳��̌��t�����L�ł���A���������Ă��̔L�͍��䂳��̕��g�ł���A�����ł�����B���䂳��̌��t������ׂ�L�́A���䂳��Ɠ����悤�Ȏv�l�����A�����悤�Ȋ����������A�����悤�Ȑ��E�����L���Ă���B����ĕʂ�ɍۂ��Ă��A�����悤�ɔ߂��ށB �@�����ł͎����傪�y�b�g������l�ԉ����邱�ƂƁA�A�[�`�X�g�̌|�p�I�n���Ƃ��ē�����l�ԉ����邱�Ƃ̓�d�̋[�l���̎x�z���Ă���B����āA���̍�i�͓��R�̂��ƂƂ��č�Ƃ̓����̎����ς�썰�ς�����邪�A���䂳��͓����ɂ���������ނ���l�Ɠ����悤�Ɏ��ʂƓV���ɉ����ƍl���Ă���B�����͉_�̏�̐���̓��F�Ɍ��鋴�����������Ƃ��낾�B �@���̍�i�͈��́i�G���W�[�j�Ƃ��قȂ邵�A�����́i���N�C�G���j�Ƃ��قȂ��Ă���B�܂��y�b�g�Ƃ̎��ʑ̌��������Ă���ɂ�������炸�A����I�ɔ߂��݂�U�������̉A�����������Ɋ��������Ȃ��B���̗��R�̈�ɂ́A�V���̖��邢��i�`�ʂ�����Ǝv����B�����ł͓V�E�͐��݂�������Ɏ��F�̓��������₭���ł₩�Ȍ��ʂ̐��E�Ƃ��ĕ`����Ă���B����y�b�g�����̉����ފ݂̐��E�͋ꂵ�݂̂Ȃ����a�Ȍ��̊y���Ȃ̂��B���̓������̂悤�ȋ��D���������V���̃C���[�W�͍��䂳����F�߂�ʂ�A��ҕs�ڂ̎��w���̋��E���C���{�[�u���b�W�x�ɂ��̈ꕔ���Ă���B �@�܂����̃��`�[�t�́A�N���X�`�����̕�e�̉e��������Ɩ{�l�͌����B�m���ɂ������������Ƃ����邩������Ȃ��B���������̍�i�̑S�̂�ʂ��Ă݂���ۂ́A�ނ���`���I�ȗ����ς�썰�ς̉e���������p������i�ł���A�l�X�̐S�̓����ɂ���Ƃ�����̗��z���E�ɂ��Ẳ����L�����ĂыN�����悤�ȉ��y�Ɏv����̂ł���B�A�[�`�X�g�Ƃ́A���̊�т�搂�������ƂƂ��ɁA�l�Ԃ̖��ӎ��̒�ɗ���鎀�̌����i���l�������̂ł��낤���B �i2�j �@�M�҂͂��̂c�u�c��i���������āA����͌���̔\���Ǝv�����B�\�y�͐�����ɂ���đ听���ꂽ���A���̌`�����畡�������\�Ƃ�����B�����Ƃ����̂́A�X�g�[���[���O���ƌ㔼�̓��\���ɂȂ��Ă��邩��ł���A�����\�Ƃ�����̂́A����̓W�J���쒆�l���̂܂ǂ�ޖ��⌶�̂Ȃ��Ői�s���邩��ł���B �@����𐢈���̔\�̒�^�Ⴉ���������Ύ��̂悤�ł���B���������闷�̑m�����閼�����Ղ�K�˂�B����Ƃ����ɂЂƂ�̌��m��ʐl�����ߊ���Ă��āA�����ňȑO�N���������j�I�ȏo���������n�߂�B�����Ď����͂��̓����҂ł����l���ł���Ƒm�ɍ����ď����Ă䂭�B �@���̖�A�m�����Ƃ��Ƃ��Ă���Ɩ��ɒ��ԏo������l�����A���x�͐��O�̗e�p��g�ɂ܂Ƃ��čĂь���A���̐��ɂ������Ƃ��̂��Ƃ�����ɏڂ����b���n�߂�B�m�͖����̒��ł��̈ꕔ�n�I���Ă������A���̐l���͌��I����ƂЂƂ��������A���{��������̂��A�يE�ɋA���Ă䂭�B���̐l���́A���̒n�ɉ��̐[���H��ł���A����̑z����`���ɂ���ė����̂������B�ЂƂ�c���ꂽ�m�́A�ӂƉ�ɕԂ肱�̑̌���[���l�������˂�B�����Ƃ���ȓ��e�����A������͂��̂悤�ȕ�����Ԓ������̎��R�`�ʂ�D�荬�����H���̔��������ĕ\������̂ł���B �@���̏ꍇ�A�����ꌩ�̗��̑m�̓��L�i������j�ł���A�V�e(��l��)�͎��҂ł���B�\�͗�I���݂����̐��������Ă��āA���̐��̒N���ɑz����`���悤�Ɩ�킸���Ɍ�肩���镨�ꂪ�����B�����ŋ����[���̂́A��l���̖S��͈�x�A�����ɑm�̂��Ƃ�K��邪�A���̖�A�Ăєނ̂��Ƃ�K���B���������x�͑m�̕\�ۂł��閲�̒��Ɍ����̂ł���B �@�H�삪���ԁA��ʐl�Ɠ����悤�ɖ������Ղ������邱�Ƃ�����̂��ǂ����͂悭�킩��Ȃ����A�����S���w�I�ɉ��߂���A����͑m�������������ƍl������B�������Ƃ͊o�����Ĉӎ��̂���Ƃ��Ɍ��閲�������A���o�Ƃ����B���̑m�͒��ԁA���o�����A���̖�A���ł��̂Â�������̂ł���B���Ȃ킿�����\�́A���L�̐l�Ԃ̌����⌶���ȂǕϐ��ӎ��̎Y���ł���A�V�e(��l��)�Ƃ����Ă��A����̓��L�̐l���̌��閲�̒��ɐ����鑶�݂ł���A�\���҂̓��L�̕\�ې��E�̃G�s�\�[�h�������Ă���̂ł���B �@�������A�Ƃ�킯�m�̒��Ԃ̑̌������o�ł���A���̑̌��͑m�̐��_�����o������ϓI���ۂȂ����͕a�����ۂƂ������ƂɂȂ�A�q�̂Ƃ��Ă̗H��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B���������̐l�Ԃ́A�������������ۂ��I�̌��Ƃ��Đ[���M���Ă����߂�����B�ł͌���l�ɂ������������Ƃ��N�������Ƃ����Ȃ�ΐl�͂ǂ������邾�낤���B���_���猾���A�����̌���l�͂����������b���ɂ͂��łɉ��^�I�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�������̏ꍇ�A������y�b�g��S�������ߒQ�҂ŁA�������ĉ�̖]�݂��̂Ă��ꂸ�ɋ����v�炷�鎔����̑O�ɂ��̂悤�Ƀy�b�g������ĉ��������n�߂��Ƃ�����ǂ��ł��낤�B������͂��̑̌���P�Ȃ錶�o�⍪���̂Ȃ����߂̖��Ƃ��ĊȒP�ɐ�̂Ă邾�낤���B����Ȃ��Ƃ��l�����Ȃ���A�w�{�N���T�ɂ��邩��E�E�E�x�����߂Ă݂�ƁA���̃��`�[�t�͂ނ�������ɂƂ��ČÂ��ĐV�������ƂɋC�Â������̂ł���B �@�Y������J�[�e���̏� �@���ʂ͎����~�߂�B������q�̎��ƂƂ��ɁA�����銈���͒�~���A���ׂĂ��u���̓��v�̂܂܂ɂȂ�B�r�����炵�炭�̊ԁA�y�b�g�̃O�b�Y��P�[�W�Ȃǂ��G����Ȃ��Ȃ�l������B�����͕Еt�����邱�ƂȂ����̂܂ܕ��u�����B�����Еt���Ă��܂��A���̎q�����Ȃ��Ȃ������Ƃ�������������Ă��܂����A����͎��̌�����F�߂邱�ƂɂȂ�B���̎q�̂��Ȃ���炵�ɑς����Ȃ��Ǝv���A�l�͂��̏�Ԃ��Â��悤�Ƃ���B���̎��Ȃ͍��䂳��̎��̌����琶�܂ꂽ���A�炢�ʂ��̌������l�łȂ���Ί����Ȃ����Ƃ��A����̂܂܂Ɍ���Ă��邱�Ƃ�������̂��Ƃ��@���邱�Ƃ��ł���B �@������ꂽ�܂ܖ���N�̖T�ɍ~��� �@�{��i�͎����ƌ��z��D������Ȃ���A���̐��Ƃ��̐��̗��E���s�������鑶�݂Ƃ̌𗬂�`���Ă���_���猩�Ĕ\�Ƌ��ʂ̃e�[�}���Ă���B�܂��̎����\������Ȃ�A�������Ė����Ă��郏�L�̏����̖T�i������j��ɗ삪�~��Ă��đz����`����Ƃ���㔼�̏�ʍ\���Ȃǂ������\�I�ł���B�܂�DVD����ł͍Ō�ɃV�e�̔L�͏����̎��͂̋��ЂƂ����������Č����Ă���̂ł���B �@�����Ƃ���������� �@���̊y�Ȃ̓y�b�g���X�Ƃ����y�b�g�������錻��l�Ɍ����������I�ȃe�[�}�̂悤�Ɍ����邪�A���������͎��ʂ���������ΏۂƔފ݁i�Ђ���j���Ȃ킿�A���̐��ōĂщ��ƐM���鑾�Â���l�X�������Â��Ă������ՓI�e�[�}�������Ă���B�����Ă��̍�i�́A�l�⓮���͎���ǂ��։����A���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��Ƃ����l�ނ��������m�ȉĂ��Ȃ��e�[�}���܂�ł���̂ł���B�y�b�g���X�̌��҂́A�ߒQ���ɂ����̗�I�Ȗ��ɓ˂������邱�Ƃ������B�����āA���̂悤�ȗ�I�ۑ������ɖ₢�����邱�Ƃ́A�ߒQ�҂��y�b�g���X������邤���ł̏d�v�ȑr�̍�ƂƂȂ�B �@�y�b�g���D�Ƃ̒��ɂ́A����哮���ƂƂ��Ɋy������炷���Ƃɍł��傫�ȉ��l��u���Ă��邽�߂ɁA�y�b�g�Ƃ��邱�ƂƐl����藣���čl���邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�������B���̂悤�Ȑl���y�b�g���X��̌�����ƁA���̐悠�̎q�Ȃ��łǂ�����Đ����Ă䂯�悢�̂����킩��Ȃ���]�I�ȋC���ƕs�����ɏP���邱�Ƃ�����B����͂��傤�ǁA�Ȃ��Ƃ߂Ă���������ĂȂ�̖ړI���Ȃ���Y�����̂悤�ɁA�l���̐i�ނׂ��������������������o�Ƃ����Ă悢��������Ȃ��B���̂悤�Ȑl�ɂƂ��ẮA����哮���Ɛ[�����ÂȂłȂ���Ƃ́A���炪���̐��Ɛ[���Ȃ��邱�Ƃɓ������̂ł���B �@�ł́A�͂����Ă��̂悤�ɂȂ����ߒQ�҂͂��̊y�Ȃɂ���ė��������Ă������Ƃ��ł���̂��낤���B����������A���̉̋Ȃɂ̓y�b�g���X�̔ߒQ�҂��ɓ������͂�����̂��낤���Ƃ������Ƃł���B���������̖₢���A��〈���������ł��邱�Ƃ͕M�҂����m���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���̎��͔̂ߒQ�Ö@��ړI�Ƃ��č��ꂽ�킯�ł͂Ȃ�����ł���B���̍�i�͓Ɨ�������̏����|�p�ł����ĐS�����Â≹�y�Ö@�̎��ÍނƂ��ĊJ�����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B �@�����A�����ł���ɂ�������炸���͖`���ŁA���̍�i�͗�������̌��ʂ����҂ł���Əq�ׁA�߈���Ƃ̑��i�ɂ͂��炭�Ǝv����Ə������B���̕M�҂̈Ӑ}�͖����ł���B���͂��̋Ȃɑr�̍�Ƃ�i�߂��ŁA���̌��ʂ�����ƍl���Ă��邩��ł���B�r�̍�Ƃ��i�ނƂ́A���̋Ȃ��Ă����Ɋ��ׂȂ��߂��݂����������Ƃ��A�������Ƃ�ċC�������₩�ɂȂ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�炢���Ƃ����A��������A������҂̂��Ȃ��Ȃ������ɋꂵ�݂Ȃ����������K�������Ă��̐����Ɋ��炵�Ă����ߒ����r�̍�Ƃł��낤�B���������āA���̓��̂肪�y�����͂��͂Ȃ��B �@�ډ��A���̋Ȃ͕���̃z�[���y�[�W�ɂ��f�ڂ���Ă��邪�A�y�b�g�Ǝ��ʂ��������҂̒��ɂ͒����Ƃ������Ĕ߂��݂ɏP����̂ł炢�Ƒi����l������B�����A����̓y�b�g���X����ڂ����炷���ƂȂ��߂��݂Ɍ��������Ă���p�ł����āA���̍s�ׂ͔ߒQ�̑��i�ɂ͂��炢�Ă���Ƃ�����̂ł���B�O���[�t(�ߒQ)�P�A�̓_�����Ȃ��Ƃ́A���ʎ҂͎v�����苃���ď\���ɔ߂��݂�������鎞�Ԃ������Ƃ����A�������邱�Ƃ͂��łɔߒQ�ɗ����������Ď��g��ł��邱�Ƃ������Ă���A���̊y�Ȃ͂��̋M�d�ȏ����Ă���Ƃ�����B �@����������̂́A���͍̉̂�҂��ʂ�̔߂��݂���ڂ����ނ����Ɍ��߂����ʁA��̗�I���������o�����Ƃɂ���đr�������z���Ă�������i������ł���A���̐����ߒ������̍�Ƃ̑r�̍�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ�����ł���B���̋Ȃ͖S���y�b�g�����ɑ����Ĕނ�̈ӎv�������傽���ɓ`���钇����������̂ł���A��̈ˑ�i��肵��j�i�_�삪���̐��������Ă��āA�ꎞ�I�ɏh��ꏊ����́j�ƂȂ�悤�ȍ�i�ł���B���̓_���猩�āA���̊y�Ȃ͖S���q���Ái���́j�ѓ����̗���Ƃނ炤���߂Ƀy�b�g���X�̔ߒQ�҂��K��錻��̂��Ёi�₵��j�Ƃ�����Ǝv���B �i�R�j �@���āA���䂳��́w�{�N���T�ɂ��邩��E�E�E�x���쎌��Ȃ���ɐ悾���āA���łɕʂ���e�[�}�ɂ����d�v�ȍ�i�\���Ă���B���ꂪ25�̂Ƃ��쎌��Ȃ����w���₩�ȉĂ̌ߌ�x�Ƃ����y�Ȃł���B���݁A���̍�i�͖{�l�ɂ���āw�S�����l��z���́x�Ƃ������肪�����Ă���B����͈�����l�Ƃ̎��ʂ����������䂳�g�̑̌��ɂ��ƂÂ��y�Ȃł���A�w�{�N���T�ɂ��邩��E�E�E�x�̐�s��i�ƌĂׂ���̂ł���B �@���҂͓����Ɛl�̑r���̌��̈Ⴂ�����鑼�Ɉ���͋�A��������͊C���e�[�}�ɂ���Ȃǎ��̓��e�₻�̓W�J���قȂ�ɂ�������炸�A���̓�̍�i�ɂ͐[���֘A�������藼�҂ɂ͋��ʓ_���������F�߂���B���̂��Ƃ͓�̎�������ׂĂ݂邱�Ƃɂ���Ă�肢���������������(�����̕\�Q��)�B���҂̎��ɋ��ʂ��郂�`�[�t�A����́u���̒��v�u�v�u���̓��v�u����v�����āu�����v�ł���B�����ɂ��ĕ��͂��邱�Ƃ́A��҂̔ߒQ�ɑ��錩������g�ݕ����_�Ԍ��邾���łȂ��A�L���r�҈�ʂ̐S���𗝉�����_������Q�l�ɂȂ�Ǝv����B����āA���ɂ��̎��ɂ��Č��Ă������Ƃɂ��悤�B�w���₩�ȉĂ̌ߌ�x�́A���̂悤�Ɏn�܂�B �@�����e���X�Ł@�C���݂Ă���ߌ� �@�w���₩�ȉĂ̌ߌ�x���w�{�N���T�ɂ��邩��E�E�E�x�Ɠ��l�ɖ`���̂S�s����Ȃ铱�����ɂ���ď�ʏ�������Ă���A��͂莋�o�I�C���[�W�̗N����i���ݒ肳��Ă���B���������̍�i�ł́A�C�l���牓������Č���ƂȂ��Ă䂭���z�̑D���������銴�����Ȃ����\��ɒǂ��B����͂�������������l��S���������Ƃɂ���ď��r�����Ă��܂������̂悤�ł���A���̕`�ʂ���͈�����l�����ɕ�܂�ĉ������E�ɏ����Ă��������Ƃ��Î�����Ă���B�l�����������҂̂����ނ����E�͂˂Ɍ��̒����B���̖`���̗}���̌���������̂Ȃ���i�`�ʂɂ���č�҂̐S�̏��̐[�����Ƃ��Â��ɕ\������Ă���B �@�C���D�����������Ȃ��Ƙb���������� �@���ɁA�Ȃ��C�ɂЂƂ藈�����������B�ߒQ�҂ɂƂ��ĂƂ�킯��Ȃ��Ƃ́A�S���Ȃ����l�Ƃ̑Θb�ł���B���ꂪ�ł���ꏊ�͔ނ̍D���������C���B�����č��l�ɗ������Ƃ��A���̋L������݂�����B����͗��l�Ƃ̊ԂŌ��킵�����B �@�˂��@���Ȃ��o���Ă���H �@�ނƂ̖Ƃ́A���l�ɓ�l�Ŗ��߂��L�k��T���ɗ��邱�Ƃ��������A�������������Ȃ��Ȃ����B�����č��ƂȂ��Ă͍L�����l�̂ǂ��ɖ��߂��̂������킩��Ȃ��B���ꂩ��́A�S�̒��ɔ�߂Ă����u���̓��v�̑z�������ӂ�o���B �@��g���@�����z�˂��̒� �@���Ȃ����āu�����炵���������v�� �@��Ƃ͏��S������邽�߂ɍ�i������B���̍�i�͎��ʂ̔߂��݂��痧���������ߒ��ŏ����ꂽ���Ƃ��킩�邪�A�܂��\���ɉɎ����Ă���Ƃ͂����������悤�Ɏv����B���̎��Ȃ͍��䂳���l��S�����Ă���R�N��ɍ���Ă���B�R�N���o�����̎��_�ł��u���̓��v�̂��Ƃ��Ȃ����ޗ]�T�͂Ȃ��A�߂����v���o�Ƃ��ĐS�̉��ɂ��܂����ނ��Ƃ͂ł����ɂ���B �@���ꂩ��h���閾���� �@�������A���͂��܂ł������ɗ����~�܂��Ă��Ă���Ȃ��B�ނ̂��߂ɂ��߂��݂����z���đO�ɐi�܂˂Ȃ�Ȃ��B���������ĕ���ł������Ƃ��A������E�C�������Ă��ꂽ�ނւ̍ő�̂��Ԃ��Ƃ��Ȃ�B�����ĉ������Ƃ��ɉ߂�������l�����̎v���o�͂��ꂩ��������邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�������͎��҂ɑ��Ă����O�Ɉ��������ĂȂ�������߂�B�₳���҂ɂ́A�̐l�Ƃ̊Ԃɉi�����邫�ÂȂ��K�v�ł���A���̈�̕\��́A���������܂ł�������Ă��Ăق����Ǝ��҂Ɋ肤�z���ł���B�悾�l�Ɍ����l�E���҂ɂȂ��Ăق����Ƃ����z���́A�⑰�̂����Ƃ��؎��Ȋ肢��������Ȃ��B����͈������Ȑl�ɋ���ꂽ����A�����Â����̐l�_�I�ȋ���ǂ���Ƃ��Ă�������ł���B���O�A�x���Ă��Ă��ꂽ�悤�ɁA������ς�炸�x����ł��Ă���邱�Ƃ�]�ށB�������͎��҂̏�������Ȃ���A���҂̂��Ȃ��V���Ȑl�����č\�����Đ�J���Ă����̂��B �@����A��������ƂȂ�̂͐l����ł͂Ȃ��B���������l�ł���B��쓮���A���b�A�X�s���`���A���A�j�}���ƌĂ����̂��A����ł���B�w�{�N���T�ɂ��邩��E�E�E�x�̔L���܂��ɂ��ꂾ�B��쓮���ƂȂ邱�Ƃɂ���āA����������̐����猩���A�܂��K�v������ΖT�܂ł����ď�����B�������āA���̔L�͐�����ꏊ�Ɨ�i��^�����Ď��_��_��̎g���ƂȂ��āA���ꂩ���������̕\�ې��E�̒���������ƂƂ��ɐ����Â���B �@�����Ȃ邱�Ƃ�������̂́A���ł��Ȃ��₳��鑤�̐l�Ԃł���B�l�͎��҂������Ȃ��Ă���邱�Ƃ�]�݁A���̓��������Ȃ����ƐM����B�r�҂͎��҂����҂ɂȂ������Ƃ��m�M���邱�ƂŐ[�����J��B�����M���邱�Ƃɂ���Đl�͂͂��߂ă^�C�g���ɂ��鉸�₩�ȐS���ɂȂ��B���V�����y�b�g���S���₩�ɂȂ��Ă���邱�ƂŁA������̐S�̏������₳��ĉ��₩�ɂȂ��̂��B�����āA���ɂ��̂悤�ɂȂ����Ƃ��A�₳�ꂽ�l�̔߈��͏I���̂��낤�B
|
||||||
�@ �@���ʂ���5�����قnjo�����낲�A�������������A���d�b�ł̑��k�Ɩʒk���s�����B����͓d�b�ł̑��k���������A���̂Ƃ����̕��̌�������Ƃ��ƂĂ���ې[���������̒�Ɏc���Ă���B�����̂��Z�E�Ɏ��������Ƃ��A����Ɍ��̂�������������ɓ���Ăق����Ɨ���A�l�Ɠ����͈Ⴄ�������������Ȃ���ƌ���ꂽ�Ƃ����B �@���̂��w�l���d�b�̌������ł������ƐÂ��Ɍ����e�́A�ЂƂЂƂ��M�҂̋��ɐ��ݓ�����̂ł���A�y�b�g���X�Ƃ͎��ɂ����������̂��Ƌ�������B����āA�����ɍČ����悤�Ǝv���B �@�g�������悹��悤�ɁA�����������߂��݂����܂����B �@�����Ă���̏��߂�3�����͂ǂ�����ĕ�炵�Ă������A �@�����[�����邾���ŁA����ȂɉƂ̒������邭�A �@�����̖���S�������悤�Ȋ��������܂��B
�@��������A���̔����͊C�ł���ł���������̂ĂāA �@�����[������̂Ŏ��͕|������܂���B
�@��������A���������Ă����ł��傤���A
|
|||||
�@ �@��̕��Ő������́A���̒��ł��|�W�e�B�u�ŐϋɓI�ȕ��ł���B���̊y�Ȃ��痧�����邫���������������Ƃ�����A�V���ɐ������]�����o�����Ƃ���y�b�g���X�̌��҂��吨���邱�Ƃ��낤�B���������̎��̓O���[�t�i�ߒQ�j�E�P�A�̊ϓ_���炢���āA�ЂƂ̑傫�Ȗ����������Ă���B����͖`������n�܂�u���̂���̑O�ŋ����Ȃ��ł��������v�ƌ����Ă���_�ł���B �@���̓��{�ꎌ�i�V�䖞����j�̑�ӂ́A���̂悤�ł���B����̑O�ŋ����Ȃ��ł��������B���͎���łȂ��������Ă����Ȃ��B�����炨��̒��ɂ͂��Ȃ��B���͕��ɂȂ��āA���𐁂��킽���Ă���B�܂��A�����ɂȂ��č~�肻��������A����ɂȂ��āA���Ȃ���������Ă���B�����狃���Ĕ߂��܂Ȃ��łق����A�Ƃ������̂ł���B �@���̓y�b�g���X�̂����k�ɂ݂���N���C�G���g����Ƃ��̎��������Ă��b�����邱�Ƃ�����B�����A����̑O�ł����Ă��A�ǂ��ł����Ă��߂���������䖝���Ȃ��ŋ����Ă�����ł���A�ƕK���������Ƃɂ��Ă���B��������Ȃ���A�߂��݂��������炦�Ă��܂��댯�������邩�炾�B�߂��݂̊����}�����邱�Ƃ��A���ʂ���̏����ȉɂ����ɂ悭�Ȃ����͍��܂ŏq�ׂĂ����ʂ�ł���B �@���������̉̎��́A���ʎ҂ɋ����Ȃ��łق����ƌ����Ă���̂ł���B������Ώۂɐ旧���ꂽ�l�̋U�炴��S��Ƃ��Ă͔߂����Ďd�����Ȃ��ɂ�������炸�ł���B�ł���A�r�҂͎��R�ȏ�ɋt����Ė{�S�������E������Ȃ��Ȃ�B���̌��ʂ́A���������������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���o�����X�Ȋ����ނ��ƂɂȂ�B���ꂪ�S�g�̗ǍD�ȏ�ԁi�E�G���r�[�C���O�j��ۂ̂ɗǂ��킯�͂Ȃ��B �@���̉̎���^�ɎĔ߂��݂������}�����A�����s�ׂ����S�ɕ������ꍇ�A�r�҂͂����y�ȋC���ɂȂ邩������Ȃ����A�ߒQ������߂����Ƃɂ���Ă������Č�X�A�ߒQ���������舫�������邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����ƌ��O�����B �@���̎��͎��������Ȃ��Ȃ��Ă��₳���l�X�͔߂��܂Ȃ��łق����Ɗ肤���ɂ䂭�҂̋C������u�x�i�����j���Ă���A������Ώۂ�r�i�����ȁj���ė�������ł���l�̔߂��݂�a�炰�Ă��������Ɗ肤�P�ӂ��琶�܂ꂽ�ł��낤���Ƃ͑z�������B����������҂��҂́A������҂�S�������Ƃ��ɐl�͂Ȃ��܂𗬂��Đ[���߂��ނ̂��Ƃ������Ƃ�A�r�҂ւ̂ӂ��킵���ڂ����ɂ��Ă̗����ɑa���悤�Ɏv����B �@�r�҂͂��̗Y�ӂȊy�Ȃɂ���Ă����Ƃ����������������g��������������āA�����ߒQ���������ꂽ�悤�ȋC���𖡂키��������Ȃ��B�������A���̎��͑r�ɔ������҂ɑ��邳�܂��܂ȂƂ������������v���ɂ͉��瓚���Ă��Ȃ����߂ɁA���炭�̌�A�r�҂͂ӂ����ї�������ł䂭�̂ł���B �@���̎��͕��r���ɂ���l�̂���ׂ���{�I�ԓx��F�߂Ȃ���i�ł���A�r�҂ɑ��Ă炢�ߒQ�ɂ͌�������Ȃ��Ă悢�Ƃ�����������b�Z�[�W�𑗂��Ă���̂ł���B�r�҂�߂��܂��Ȃ��Ƃ����z���͎��͂܂������Ă���B������Ώۂ�S�������l�ւ̎��͂̑Ή��Ƃ��ẮA�S�䂭�܂ŏ\���ɔ߂��܂��Ă����邱�Ƃ��A�����Ƃ���Ȕz���Ȃ̂��B �@���̎��́A���҂͈⑰�̗܂����邱�Ƃ�]��ł͂��Ȃ��̂�����A�����Ȃ�����������Ƃ����Ă���̂Ɠ����ł���A����䂦�Ɉ⑰�ɔߒQ�Ɍ����������Ƃ��������ɂ͂��炩���ĉ�������Ă��܂��\���������Ă���B���̓_���炢���āA���̋Ȃ̓O���[�t�E�P�A�̖ʂ���́A�g�����ɂȂ�Ȃ��ǂ��납�A�t���ʂ������炵�ď����ȉ�j�݂��˂Ȃ��̂ł���B �@�ł́A�����ł���ɂ�������炸�A���̉̂͂Ȃ��y�b�g���X�̌��҂Ɏ�����Ă������̂��낤���B����͂��̂悤�Ȃ���ł����Ă��A���̎��͗썰�̑���������A�����Ɏ�������Ă�肢������������{�l�ɂ��������悤�`���I�ȉԒ��������̎��R�ς��U��߂ď�I�ɍ\������Ă��邩��ł���B�܂��̂���̏H�R��j���̑�z�����̏��͂ƃp�t�H�[�}���X�Ɏx�����Ă���_���傫���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B���̏؋��ɁA��Ȏ҂̐V�䖞�����{�l���̂��u��̕��ɂȂ��āv�����ăl�b�g��Œ��������Ƃ����邪�A����Ȃ���A���Ȋ������炵�čēx���������Ƃ͎v��Ȃ������B �@�ߒQ�҂͔ߒQ���͋��������̂��B���ꂪ������q��S������������Ƃ��Ă̎��R�Ŗ{���̎p�ł���A�߂��������狃���č\��Ȃ��̂��B�܂������Ȃƌ�����A�]�v�ɋ��������Ȃ�̂��l��ł�����B��������ۂɂ́A�ߒQ�҂͂��̋Ȃ��Ă�������Ƃł͂��邪�A���߂��߂Ƌ�����̂ł���B�l�͋U�炴�鐳���ȐS���ɋt�炤���ƂȂǂł��Ȃ��B�r�҂͎��ʂ̔߂��݂��B���K�v�Ȃǂ��Ƃ��ƂȂ��̂��B �@���̎��̂ɂЂƂ~��������Ƃ���A����͕ʂ�̔߂��݂�U����Đ�ɐi��łق����Ɗ肤�悾�҂̈ӎv������őr�҂�O�����Ɉ�������グ�悤�Ƃ���_�ł���B�����������Ȃ�O�ɐl�́A�v���苃���ĔߒQ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������ʉ߂��Ȃ���Η�������͂Ȃ��̂��B �� �@���������̎��̒��Ő����Ă��镗�́A�]�����{�l�̐S�ɐ������镗�Ƃ͖��炩�ɈقȂ��Ă���悤�Ɏv����B����҂��s���Ƃ͂������Đl�i�H�j�̍삾���炾�낤���B�����A���{�l�ɐ������͕����I���ς�Y�킹�����̂������B����͖���̕��ł���B���Ƃ��A���q����̑m�E���@�̎莆�����Ă݂悤�B���q��S��������e�ɓ��@�͂���ȐS�̂��������ꕶ�𑗂��Ă���i�����j�B �@�~�肵����܂��~�ɂȂ�~��A�U�肵�Ԃ��t�̖K��ƂƂ��ɍ炭�B�ǂ���������̕��ɏ������l����́A�Ăт��̐��ɋA���Ă��Ȃ��̂��낤�B��������߂������Ƃł���B����߂������Ƃł���B���l�ł������A �@���̎莆�͓��@���S���Ȃ�\�����O�ɏ�����Ă���B���g���������߂����Ƃ��@�m���Ă���A���̐��ő��q����ɉ�����Ȃ�A���Ȃ��̒Q����`���悤�Ƃ����Ă���B���̎莆�ł́A���q����̎���̕��ɏ������l�ƌ`�e����ق��ɁA�����ɉ_�������肻�̌����R�ɉB��Ă��܂������Ƃ�A���܂�ɍ炭�Ԃ����ɐ�����Ă͂��Ȃ��U���Ă��܂������Ƃ�栂��Ă���B�u��̕��v�̎��Ƃ͎����ƃg�[�����قȂ邪�A���R�`�ʂ𑽗p�����\����i�Ƃ����_�ł͂��݂��ʂ������Ƃ��낪����悤�Ɏv���B �@�܂��A��������̑m�E�@�@���Ƒ���S�������l�ֈ��Ă��莆�͎��̂悤���B �@�l�̐��̒�߂Ȃ����肳�܂��悭�l���Ă݂�A�ق�Ƃ��ɂ͂��Ȃ����̂́A���܂�A�炿�A����ł䂭���̂悤�Ȑ��U�ł���B�܂��l���ꖜ�N�̎��������Ƃ������Ƃ��Ȃ��B�ꐶ�͂����ɉ߂��Ă��܂��B �@���̎莆�́u�����̏́v�Ƃ��u�����̌䕶�i���ӂ݁j�v�Ƃ���ꓖ���A�����̐l�X�ɏ��ʂ���ēǂ܂ꂽ��A�߂����ĉ̂�ꂽ�Ƃ����B����A�����Ő�̕��Ƃ���������̂ł���B�@�@�͐l�Ԃ̎������\�Z�Ƃ���ꂽ����ɁA���\�܍Ƃ���������S�����������U�Ɏl�x�A������S�����Ă���B���̎莆�́A�ߐe�҂�r�i�����ȁj�����M�҂���Ɉ��Ăď����ꂽ�Ƃ����Ă��邪�A���̐S���͎���̎��ʑ̌��ɂ��ƂÂ������̂悤�ɂ��v����B �@�܂��A������������O�@��t�E��C����\�N�A��Y��������q�ʼn����q�̒q��i������j��S�������Ƃ��̒Q���Ɏ����Ă͂������B �@���i�����j�Ȃ�Ɓi���ȁj�A���i�����j�Ȃ�Ɓi���ȁj�A�܂����i�����j�Ȃ�Ɓi���ȁj�B
�@���̂悤�ɍO�@��t�Ƃ����ǂ�������Ώۂ�S�����Δ߂����Ă��傤���Ȃ��̂��B����ɍO�@��t�ɂ��Ă��A��̓��@��@�@�ɂ��Ă��A��Ȑl��r���ė������ސl�X�ɋ����Ǝ��҂������ł��Ȃ��Ȃ邩�爣���ނȂƂ͌����Č����Ă��Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ�����A���̏@���I�V�˂�͕����҂ł���O�ɗD�ꂽ�T�C�R���W�X�g�ł���A��}�Ȑl�Ԋώ@�҂��������Ƃ��킩��B �@����t�������@�����@�@����𐁂����������́A�炭��������w�̔ߕ����B��̕��Ƃ́A��������̕����Ӗ����Ă���Ƃ���A�S�n�悢������ł͂Ȃ��A�Ȃ��ɂ͐Ȃ������邹�Ȃ��������邾�낤�B�������ǂ����ŕ��������Ă���B����������r�����l�ɂ�������������B���̐l�͂��܁A�ǂ�ȕ��ɐ�����Ă���̂��낤�B
|
|||||
�@ �@���ʂƂ����Ă����̎���ɂȂ�ƒ��삪�����Ɏ�����̂ł͂Ȃ��A�喼���b���̎҂Ɏ�̖�(�����̂������҂ɗ^���������Ȋ���)�Ƃ��ďo���Ă����̂ł���������p�����̂��낤�B���ɐ����̊��ʂ����Ƃ����Ȃ�ΈȑO�A���ɂ̂ڂ��ėL�͂Ȍ��Ƃ̂��ƂȂǂɐg���Ă͓s�̌x��Ȃǂɓ������o�������������Ǝv����B�`���I�ɕ��l�͂������������Ƃ����Ċ��ʂĂ����̂ł���B �@�叟�i�������j�͂܂��Ⴉ�����B��\�������炩�߂������炢�ł͂Ȃ��������Ǝv����B���炭�O�ɍȂ��߂Ƃ��Ă������q�ǂ��͂܂����Ȃ������B���̔ނ�����Ƃ��̖������藧�Ă�N�v�Ɏ�S���������B���̔N�͕s��̂��߂ɂ����̂悤�ɍ앨������Ȃ������̂��낤�B����������˂����̒j�͔_�������߂˂Ȃ�Ȃ��N�v�ĂɎ�����������Ă�����̂ł���B �@���̍s�ׂ́A���̉ƘV��d�b�����ɒ叟��ǂ����Ƃ��i�D�̍ޗ���^�����B�������G��槌��i����j�˕Ԃ������̐����͂��l�������̒j�ɂ͂Ȃ������B�����𐰂炻���ƕK���ɍR�ق����������ʂ������B����ǂ��납�ނ̐g����Ԃ܂��ɒǂ����܂�Ă��������߁A��ނȂ��Ȃ��Ē��d�����B���̂Ƃ��Ȃ͐g�������Ă����Ƃ����B �@���Z�̍�(���̊�)�܂œ������ӂ���́A�Ґ�(��������)�̋߂��̏������K�i�ق���j�̈���ɓ��������A�����ɉ��Q�̂����������ł����������邱�Ƃɂ����B���������܂ł�����ȂƂ���ɗ��܂��Ă���킯�ɂ������Ȃ������B���Z�ɓ���Ă����̂����ɓ��Ă������Ă̂��Ƃł͂Ȃ������B�����̂��Ƃ肠�����Ȃ̎�������ē��������邾���Ő������ς��������̂ł���B�����A���͂⎘�ɂ͖߂�Ȃ��B����ɐg�d�̍Ȃ�����B �@�叟�͍l�����������ɍs�����Ƃ����߂��B���ɍs���Ȃ�Ƃ��Ȃ邩������Ȃ��A�����l�����ނ́A�Ȃ��c���ĒP�g���Ɍ��������B���Z�̒n��T�����セ���ɍȂ��}�����͂��������B�����s�j�̊ւ�����܂ŗ����Ƃ��A�ނ͒ǎ�ɕߔ�����Ă��܂����B�叟�����̌�ǂ��Ȃ������͋L�^�Ɏc���Ă��Ȃ��B�����������̕��m�̏K���ɂ��������đ��n�˂ɑ���ꂽ�̂��ؕ���\���t����ꂽ�ƕ����͓`���Ă���B �@�ł͂��̌�A�Ȃ͂ǂ��Ȃ������B�Ȃ͐������т邱�Ƃ��ł����B���̏����������������̂́A�叟���ޏ��̂��Ƃ͍Ŋ��܂Ō�������Ȃ���������ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă���B�Ȃ͂��̌������ɓ��ɗ��܂�A�قǂȂ����Ēj�����Y�ݗ��Ƃ����B�ޏ��͕v�̋A���҂���т����A�v�͂��ɋA���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ������B���炭�̌�A���̕ւ�ɕv���߂܂��Đؕ��������Ƃ�m�炳���ƁA�������낵�v�̕����Ƃނ炢���̈���ɓ��̓���ƂȂ����B�����H���T��Ƃ����A�l�X����̑��������Ƃ����B �@���̏����́A�����̍����̌`�Ԃ��炢���ĕ��Ƃ̖��������Ǝv����B������r�����Ƃ��ޏ��͂܂���\�ΑO��ł�������������Ȃ��B��ƂȂ�ً��̒n�Őe�ނ≏�҂̂��Ȃ����łǂ̂悤�ɂ��Đ������A�q�ǂ�����ĂĂ������̂��낤�B�ߍ݂̐l�тƂ���̕z�{�݂̂𗊂�Ƃ��Đ����Ă����̂��낤���B�������������Ƃ͍��ƂȂ��Ă͒m��R���Ȃ����A���̐l�͐M���قƂ�ǗB��̎x���Ƃ��ċC��ɐ����悤�Ƃ��Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł���B�H���̑T��Ƃ������́A�N���t�����̂��낤�B�H�̌��͐���Ŕ������B�����A�ǂ����҂����ł���B �@���̌�A��q�͒�����ɋy��œV��@�̑m�ƂȂ����B�����̋��łȃq�G�����L�[���x�̂Ȃ��ɂ����Ă��͂�ǂ��ɂ������Ȃ���E�҂������铹�͏o�Ƃ����Ȃ������Ǝv����B�ނ͂��̌�A�_���Ꝅ���哱����y�^�@�E�����̑c�ƂȂ�{�莛�@�@�Əo��A���̒�q�̖��ȂɘA�Ȃ�A���𗹔O�i���R�j�Ə̂����B��y�^�@�ɉ��@�������O�́A�������N(1460�N)�A���̊��{���s�ɐ��Ǝ��Ƃ����ꎛ��a���肻���ɏZ��ŊJ��i�����ŏ��ɊJ�����m���j�ƂȂ����B�ȏ�̂��Ƃ́A���Ǝ����N�Ƃ��Č��`�����Ă��邪�A���l�̂��Ƃ͊��j�i�ʎj�Ғ����Z��ܕŁj�ɂ������Ă���B �@��y�^�@�́A�@�c�E�e�a���ȑтɓ��ݐ��Ă��炻�̖@�����p���҂͌������q�ǂ���݂��Ȃ���M�����𑱂���悤�ɂȂ�A��������`�Ƃ���悤�ɂȂ����B���O������ɂ��ꂸ�ȑт��q��݂����B�����Ȃ����ŁA�ĂĂȂ��q�Ƃ��Ĉ�����A�E�g���[�̗��O���A�Z�މƂ������Ƒ������悤�ɂȂ����̂ł���B���̎q�ǂ��͎����p����͂茋�����Ďq���Ȃ����B��������Ă��̉ƌn�͑�X������ۂ��č����Ɏ����Ă���B���͂��̎q���ł���B �@���̂��Ƃ��������Č�邱�Ƃ͎��ɂ͑����̂��߂炢������B���͎��̐�c�ł��鑊�n�叟�Ƃ����߉^�Ȓj�Ƃ��̍Ȏq������łȂ�Ȃ��̂ł���B���������叟���ǂ�Ȉ������͂��炢���Ƃ����̂��B�N�v������Ɍy�������̂͌���������y���ȍs���ł�������������Ȃ����A�̖��������ݕ��S���y�����邱�Ƃ��ؕ��ɒl����قǂ̔؍s�Ȃ̂��낤���B����Ƃ��d�b��ɂ͒叟�̌��������������ʂȗ��R�ł��������̂��낤���B槌�����C�b��C�b�ƌ��������Ƃ��ł��Ȃ��Ë��ȓa�l���a�l�ł���B�����������Ƃ����ނׂ��͂��̕������C�b�����ł��낤�B���̐�c�͌v���ɛƂ߂��ċl�ߕ���炳�ꂽ�B���̛C�b�����́A���̌���˂��������Ă͐l����搉̂��Ă������ɈႢ�Ȃ��B���n�˂Ƃ͎��ɕ��肫�����˂ł���B �@���͎v���̂ł���B���n�叟�Ƃ����N�͐��Ԓm�炸�̂��V����܂������ɑ���Ȃ��A���قNj�J���邱�ƂȂ��������Ƃ̉ƘV�E�������p�����̂ł��낤�B�������g�D�̒��ł��܂�������邱�Ƃ��͂Ȃ͂��s����ȗv�̗̂ǂ��Ƃ͌����Ȃ���҂������Ǝv���B�����ď�ɂ��낭���Ȑ��`�����玝�����킹�Ă����B�V�Ԃȏd�b�������猩��ΐK����U���Ă�����ƌ���낤�Ƃ��Ȃ�����ȕs�H�ȐN�̎p�́A���������̓��������������˂Ȃ����������݂ɉf���Ă��������낤�B���łɂ��̒���͒叟�̌�������͊���o�Ă������Ǝv����B �@���͎Ⴍ���ĉƘV�ɎQ�����Ă����叟���d�b�����̉����d��Ȕ閧��m�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����łȂ���Αg�D����݂Œ叟����艟�����Ă����ɐؕ������Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���̂ł���B���͔N�v�̉��̂����Ă����̂͑��Ȃ�ʂ��̉ƘV�����ł���A���̔��o������ĔG�ꂬ�ʂ�叟�ɕ��킹���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���j�ɂ��u�i���n�叟�́j�̎�ɂ����˂�ƘV��d�b�ɂ��槑i�v�Ə�����Ă���ł͂Ȃ����B �@槑i�i���j�Ƃ́A���l�����Ƃ�����邽�߂ɖڏ�̐l�ɁA��������Ȃ����Ƃ����������邱�Ƃ������B�d�b��͒叟�ɍ߂����Ԃ��ĔƐl�Ɏd���Ă��j�Z�b���ł����グ�������œa�l�ɕ���B�Ɛb�ɂƂ��ēa�l���}�f�ł������قǁA�����납�玝���グ�Ă����˂��Ă�������Ύ��������ɓs���̂悢�˖����o�����邱�ƂȂǂ��₷�����Ƃ������낤�B �@�叟�͎��ʂƂ������v�������낤�B���K�̓�����܂���ȂƂ܂����ʎq���v�������낤���B����̂��Ƃ��v�������낤���B����Ƃ������ׂ����n�̗̖������̂��Ƃ��v�������낤���B���������Ƃ����ꂽ�y�i�₩��j�ւ̍��݂�������ł��낤���B�Ƃ��������A�叟�̐l���͖{���ł�����ꂩ��I�I�����n�܂�͂����������A�����Ŗ����̂܂I��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B���̖��O���͑z������ɗ]�肠��B �@������]�V�Ȃ�����Ă͂��Ȃ��U�������n�叟���Ⴍ���ĉǕw�ƂȂ��Ĉً��ňꐶ���I�����H���T����A�]���U�ł͂Ȃ������B�ӂ���͂��̐��ł̉h�B�Ǝ��K�ɂ͂��Ƃ��������A������߂�ꂽ�h���Ƃ��Đ������Ǝv���B���̂��߂��낤���A����m��ʔO���m�̗��O�₻�̎q���͂ǂ����ɉ}���ς�����s�𗝂Ȃ��̐��ɂł͂Ȃ���y�ɂȂ����߂Ɗ�]�����o�����Ƃ��Ă����悤�ł���B�����ۂ��b�����A���ꂪ���̃��[�c�ł���A���̐l���������̑����Ƒ���ł���B�ȏ�̂��Ƃ͎��������A���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă��邱�ƂƉ������ɂ����ĉ��قǂ��W���Ă���̂�������Ȃ��Ǝv�����̂ŁA�������邷���Ƃɂ����B
|
|||||
�@ �@����A����n���̃y�b�g�쉀�̕����炲�A��������A���̂Ƃ���Ŋw��Ńy�b�g���X�P�A���s���Ă���l�Ɖ�����Ƃ������̐l�̂��Ƃ���ꂽ���A���ɂ͂��̖��O�ɕ����o�����Ȃ������B�����A���̐l�͎��̂Ƃ���Ńy�b�g���X���w�Ƃ����Ă���Ƃ������Ƃ������B���̐l�ɂƂ��Ă͎��̍u���Ȃǂ���x�ł������������ł����������ƂɂȂ��Ă���̂�������Ȃ������B�����A�l�ԁE�y�b�g�W��y�b�g�̎��ʂɂ��Ă̒m�����s�\����������A�y�b�g���X�̎���������Ď����Ȃ������ɗՏ��������n�߂�l���łĂ���悤�ł���B �@��������̓y�b�g���X�E�J�E���Z���[���̂��Ă���l�����ł͂Ȃ��A��Ï]���҂̂Ȃ��ł������悤�Ȃ��Ƃ��N�����Ă���B�ŋ߂͂�⌸���Ă������A�ȑO�́u�y�b�g�������炢�łǂ����Ă���Ȃɗ������ނ̂ł����H�v�Ƃ��u�������̎q��������������Ȃ��ł����v�Ȃǂƃy�b�g���X�̔ߒQ�҂ɕ��C�Ō�����t��J�E���Z���[�����₽�Ȃ������B�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�Ə̂���l�̒��ɂ́A�������ɂ���Ȃ��Ƃ������l�͂��Ȃ��Ǝv�����A����ɕC�G����悤�Ȍ�T��Ƃ��Ă���l������B �@�������������Ƃ́A�ЂƂ��Ƀy�b�g���X�̒m�����L�܂��Ă��Ȃ����Ƃ���N����Ƃ����邾�낤�B����̓y�b�g���X���炪�s���Ȃ邪�䂦�̖��Ƃ����邪�A���̈�ɂ́A�y�b�g���X�������鑤�̃��x���̖�肪����B�ŋ߂́A�y�b�g���X�u�����e�n�ő����Ă����B���̂��Ƃ͂����ւ��������Ƃł���B���������ɂ͔h��Ȑ�`���肪�ڗ����āA���̓��e�ƂȂ�Ƌȃy�b�g���X�u��������悤���B�����m��Ȃ��l�́A�ڂ���܂��֑̌�L���ɂ܂�܂Ƃ͂܂�킯�ł���B �@�܂��A�M�����������Ƃ����y�b�g���X�ɂ��Ă̍u�`���قƂ�ǂȂ��Ƃ����ʗd�ȃy�b�g���X�E�J�E���Z���[�̗{���u��������Ƃ����B����́A���̍u�������l���畷�������ƂȂ̂ŁA���Ԃ�{���Ȃ̂��낤�B�����ł̓J�E���Z�����O��e��S���Ö@�̘b����Ŋ̐S�̃y�b�g���X�ߒQ�̃P�A��HAR(�q���[�}���E�A�j�}�������[�V����)�̉���͂������x�������Ƃ����B����Ŏ�u�҂͐�X�ǂ�����ăy�b�g���X�̃P�A�ɂ�����̂��낤���A�C������ł���B �@���R�̂��ƂȂ��炱�̋���Ɍg���҂́A�y�b�g���X�̐��҂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̕���̋��t�ł���ΐ[���y�b�g���X�̒m���Ə\���ȗՏ���(���̈�̗Տ����ł��Ȃ��A�y�b�g�̗Տ�����g���[�j���O���ł�����܂���)�������������ł��̒m���ƌo����蔄�肷����̂��Ǝv���̂����A���炭���̐l�����͂��̈�����������������Ă���̂��낤�B�����������͂���炪�Ȃ��Ă��A���Ƃ̊�����Ăʂ��ʂ��Ƌ��d�ɗ��ĂA���̒m���������Ȃ��f�l��w���̓y�b�g�� �X�E�J�E���Z���[�u���Ƃ͂����������̂��Ǝv���Ă��܂����낤�B��u�����������Ȃ����Ƃ�ʂ��ӓ|�̒�̐��Ƃ����������ꂽ�Ƃ��Ă����̂��Ƃɂ����C�Â����C�����Ă����̂ł͂Ȃ����B �@�������������Ƃ͊w�ԑ��ɂ��ꔼ�̐ӔC������Ǝv���B���k�̐^���Ȗ₢�����ɂ���ċ��t�͒b�����Ă����̂ł���A���ꂪ�Ȃ���Η��҂̔��W���Ȃ��̂ł���B����Ɋw�K�������Ɩ₢�����Ă���l�̂Ȃ��ɂ́A���̎��i������ďA�E���͂���̂��Ƃ������ƂƁA�����炩����̂��������Ă���l������B�ǂ�Ȃ��Ƃ��w�K����̂���A ���̓��e�ɂ��āA�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�͂ǂ�ȎЉ�I������Ӌ`������̂��Ƃ������Ƃ͂ǂ����ɂ����Ă��܂��āA�d���ɂȂ邩�Ƃ������ƂƁA�������p�ɂ����S���W�����Ă���B����炪�d�v�Ȃ��Ƃ��悭�킩�邪�A���̕��Ƃ���A���̂悤�Ȑl�ɂȂ��y�b�g���X�̃J�E���Z���[��p���J�E���Z���[�ɂȂ肽���̂����Ă݂����Ȃ�B �@�ȑO�A�⍇���̓d�b�����Ă����l�ɁA�y�b�g���X�͎����傳��Ƃ����l�Ԃ̖��ɂ�����邱�Ƃ�����̂Ŋw�K�͑�ςł���A��������|�[�g�̒�o����������܂���Ɛ�������ƁA�u���ꂶ�Ⴀ�A�����ł��v�Ƃ����ēd�b���ꂽ���Ƃ�����B���̐l�̓y�b�g���X�P�A���������������Ǝv���Ă���̂��낤���Ǝv���A��������������B���������l�́A���̂悤�Ȃ��Ƃɂ͂��Ƃ��ƕs�����ł���{�����e�B�A�Ƃ����ǂ��s���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�����鑤�ɂ��������鑤�ɂ��A�����ăT�|�[�g���鑤�ɂ����߂���y�b�g���X���r�߂Ă������Ă���҂�����̂��B���̂悤�Ȑl�̓y�b�g���X�̖{���𗝉����Ȃ��|�����̒m�炸�ł���A���̂Ƃ��낱��قǃy�b�g���X�̌��҂�n���ɂ����҂����Ȃ����낤�B �y�b�g���ʂ��l�ԁE�����W�w���Â�����ꂽ���̂ł���B �@�ł́A�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�̓K���Ƃ��ẮA�����ǂ��Ƃ����w���̃G���[�g�ł�������̂��Ƃ����ƁA������Ⴄ�Ǝ��͍l���Ă���B�m���ɁA���̗̈�̒m����l�������}�X�^�[���A�������Ă����ɂ͒m�͂◝��͂��K�v�ł���A���̊w�K�ɑς����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�Ƃ��čł���Ȃ��Ƃ͉����Ɩ����A����͂������������Ƃ����������ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���B�m����v�l�͂́A���Ԃ�������Όォ��ł����Ƃ��Ȃ�B�������l�Ԃ̐������ƂȂ�ƁA���Ԃ������Ē�������������Ƃ����ē�������̂ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B����͓V���̕������傫���悤�Ɏv���̂ł���B���Ȃ킿�A���̐l�ɐ��܂��������������ł���B �@�㐹�q�|�N���e�X�́A��t�̓K���Ƃ��Ă܂����ɕK�v�Ȃ��̂͂��̓V�����Ƃ����Ă���B�V���̑f�����Ȃ�����ׂĂ͂ނ��ɂȂ�Ƃ��q�ׂĂ���B���̐��܂���̑f���̔�������҂��A�悢���̂��ƂŒ����ɂ킽�鋳����ď��߂Ă��̂ɂȂ�Ƃ����B���̎�������̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂������Ă���̂��͂悭�킩��Ȃ����A�q�|�N���e�X�͐����҂��Ȃ킿��������Ƃ�����Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ă���B���̂��Ƃ͈�ÂɌg���҂Ɍ������o��𔗂��Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���܈�t�ɂȂ�l�͍��Z���̎��̕��l���ٗl�ɍ������A�e����t���Ƃ��T�����ȂǂŌ��߂��Ă���B�����͂�������{�l�ɂ悢��҂ƂȂ�f�������邩�ǂ����Ƃ͂��܂�W���Ȃ����Ƃł���B�������������Ƃ́A �y�b�g���X�̃P�A���X�g�ɂ��������Ƃ�������悤�Ɏv���B �@���́A���̐�V�̋C���͂��̐l�̐�c��e����p������`�I�Ȍ`���ƁA���܂�ς��ɂ���Ė{�l������܂ŌJ��Ԃ��Ă����ߋ���(�O��)�ɂ�����̌��̑o���̏W�ςɂ���č����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���������Ȃ�ƁA�����i����̐l���j�̖{�l�̂�������m��ʖ��ӎ����ł��ꂪ���߂��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�A�{�l�̓w�͂������ċy�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ȗ����܂ނ��ƂɂȂ�B��₱�����Ȃ�̂ł���ȏ�̐[����͔����邪�A�Ƃ����������́A �������������Ƃ����Ă����ɂӂ��킵���f���̂���l�Ԃ�S������W�߂āA�悢�y�b�g���X�E�p���J�E���Z���[��y�b�g���X�E�J�E���Z���[���������̒��ɔy�o�������̂ł���B�����āA�킪���𐢊E�Ɋ�����y�b�g���X�P�A�卑�ɂ̂��グ�����̂��B���ꂪ���ł���B �@��u���ɑ����p�Ό��ʂ͂Ɩ����ƁA�����ɋ����Ă��܂����A�����̂��߂ɋ��炪���Ȃ��͔��������ƍl���Ă���B���̂��Ƃ́A���Ď�����J������ꂽ���ƂȂ̂ŁA�������Ă������ł���B�w�K�������Ƃ��������M�ӂ�����̂Ȃ�A���������Ă��������Ǝv���̂ŁA�o�ϓI�Ɍ������ꍇ�́A�\�Ȍ���̕��[�����Ƃ��Ă���B�܂�����́A�n���_�Y�����i�̕��[��A������ƂȂǂɂ��J���[���l���Ă���B�N��A�L�����A�A�w���͂��قǏd�v�ł͂Ȃ��B�v�́A�����Ȏu�i�����내���j�����邩�ǂ����ł���B���n��ɒ������������Ȑl�Ԃ͌����Ȃ��B���́A���̕�����`���l�́A���������l�Ԃł����Ăق����Ȃ��Ɗ���Ă���B �@���āA�^�C�g���ɂ��Ȃ��Ă���y�b�g���X�E�J�E���Z���[�͐��̒��ɕK�v���ǂ����ɂ��ē����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̉Ƃ��čs���s���ɂȂ����y�b�g��{�����郌�X�L���[�̑��l�҂ł���1984�N�ȗ��J�Ƃ���Ă��邱�̕���ł͐��E�I�Ȑ��҂̂ЂƂ�ł�����A�C�y�b�g�T��ǂ̔��V���搶�̌��t�����p�������Ǝv���B �@���V�搶�͂��̒����̂Ȃ��ŁA�u���B�͗��v��ɂ͂قlj������A�s���@�ւœ������Ƃ��s���ĖႦ��܂ł͑����čs�������ƍl���Ă���B�����悻�Љ�ɕK�v�Ȃ��͎̂��R�ɐ����c��A�s�K�v�Ȃ��͓̂�������Ă����ƐM���Ă���B�v (�u���̔L�@�N�̔L�H�v�ߑ㕶�|�ЁA1995.)�Əq�ׂĂ���B����͂���܂ŒN�����g�܂Ȃ��������Ƃ��Ȋw�I�m���Ɋ�Â��Ĉꂩ��n�߂�ꂽ���V�搶�̎��̌�����o�����t���Ǝv���B�����ʂ�̃y�b�g���X�̖��͎�����ɂƂ��Ă��y�b�g�ɂƂ��Ă����ɐ[���ł���A�܂��Ƃɓ����Ȃ̂ŁA���̌��t�������ē����� �ウ�����Ă������������Ǝv���B
|
|||||
�@ �@�����ňȑO�s�������Ƃ̂���ߏ��̃y�b�g�V���b�v�֍s���A�I�[�i�[�̂������ɁA�u���̕ӂň�Ԙr�̗ǂ��b�コ��͂ǂȂ��ł����H�v�ƕ����ƁA����͂j�搶���Ƃ����B����Ō��܂肾�����B�����A������̐搶�Ƃ͖ʎ��͂Ȃ��B�����ł��̐搶�̓����a�@�̓d�b�ԍ��ׂĂ��d�b���������B�j�搶�ƂȂ������̂Ŏ����b���ƁA���R������w�̐�y�ł��邱�Ƃ��킩��A���̂��Ƃ������Ă��A����Ȃ莄������Ă����������B���ꂩ����Ȃ��A���͎��K���Ƃ��Ăj�����a�@�ɂ��f�����邱�ƂɂȂ����B �@���K�����̒��A�a�@�֗E��ōs���Ɛ搶�͂����������������ɁA���ꂩ�炠�鎔���傳��̉Ƃւ�����͂��ɍs���̂ŁA���ė���悤�ɂƂ������B�搶���^�]����Âт��o���̌y�����Ԃ̏���Ȃɓ��悳���Ă��炢�������炨�b���f���ƁA���̂����͌��ŁA���@���Âɐ�S���Ă�������̌��Ȃ����S�����̂Ńy�b�g�쉀�ʼnΑ����Ă��炢�A�����玩��ɓ͂��ɍs���̂��Ƃ����B�����傳��́A�������S���Ȃ����ƍ�����ꂽ�Ɠ����ɁA�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Α���搶�Ɉ�C�����悤�������B �@�����傳��̎���ɒ����ƉJ�˂͕܂����܂܂ɂȂ��Ă����B���ւɓ���Ɖ����狃���͂炵�����ߊ炪�N�V���N�V���ɂȂ����n�N�̂��w�l���L����Ǔ`���ɂ���낵�Ȃ��猻�ꂽ�B���̗l�q����́A�������Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��قǜܜ��������Ă��邱�Ƃ����Ď�ꂽ�B����l�����ɂ���̂����A������Ђ��O�����x��ł���Ƃ����B���̂���l�͏I�n�A��������邱�Ƃ͂Ȃ������B �@�搶�́A���w�l�ɔ����܂ɕ�܂ꂽ�����n���A�S���Ȃ�o�߂�a��ɂ��Ď�Z�ɐ����������A�ޏ��͂��ނ����܂܂炭�߂������ɕ����Ă��邾���������B���͂������R�Ƃ��Ă������ނ݂̂������B�����Đ搶�ƂƂ��ɐ[�X�Ɠ��������Ă����Ƃ܂����B �@���̓y�b�g�������Ă����܂ŗ�������ł���l�������̂͐��܂�ď��߂Ă������B���������̕��������ȊO�ł͏��߂Ẵy�b�g���X�̌��҂������B�A��ہA�u�g�c�N�A�܂�ɂ��������l�������ł���B�ł��A�������܂łȂ��Ă��܂��ƂȂ��v�ƁA�Տ��ƂƂ��Ē����ɐM����z���Ă����������̐搶�Ƃ��Ă��A�����Ȃ�Ƃǂ����Ă悢���킩�炸���f���Ă���l�q�������B �@���ꂪ���̓����a�@���K�̑�P���̃N���C�G���g����ł���B�����1973�N�̂��Ƃł���A���̎��A�����J�ł��܂��y�b�g���X�Ƃ������t�͐��܂�Ă��Ȃ������B���ꂪ���̓�\�̉Ă̑̌��ł���B���̏Ռ��I�ȑ̌��͂��̌�A�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��Y��邱�Ƃ͂Ȃ��A�ق̉��ɐ[�����܂ꂽ�܂܁A���Ƃ��邲�ƂɎv�������ꂽ�B���̑̌����Ȃ�������A���͂��̌�y�b�g���X�P�A�̓��ɐi�ނ��Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��Ǝv���B���������_����A���̂��w�l�ƌ́E�j�搶�ɂ́A���ӂ��Ă����ӂ������Ȃ��v��������B �� �@���ꂩ��7�N���1980�N�A���͐S���w���U�����w�@�������Ă����B27�ɂȂ��Ă������A�܂��w�������Ă����B���̉āA�����Ɛ��ɂ��铮���쉀�ɑ��������ʂ��ẮA���Q��ɗ���l�X�ɃC���^�r���[�����ĉ���Ă����B���~�̂��낾�����̂ő����̐l�X���A�S�������y�b�g�̂����[�����ɗ��Ă͎�����킹�Ă����B����l�ɂƂ��ăy�b�g�����͂ǂ̂悤�ȑ��݂Ȃ̂��A���{�l�͓�������ǂ��݂Ă���̂����y�b�g�쉀�ɗ���l��Ώۂɒ������Ă����̂��B �@���ׂĂ��������ɁA�Q�q�ɗ��Ă���l�̒��ɂ́A�y�b�g���X���痧�����ꂸ�ɂ���l�����邱�Ƃ��킩���Ă����B���钆�N�̂��w�l�́A�������R�N�O�ɖS�����Ė����������A���ꂩ��Ƃ������̖����̂悤�ɂ��̏����Ȃ���ɂ��Q��ɗ��Ă͉Ԃ�H�ו������������A�|�������Ă����B���ꂪ���̂��w�l�̓��ۂł���A������ړI�̂悤�ł��������B���{�l�Ƃ��b�������Ƃ��A�u����̐l���猩��A���̂��Ă��邱�Ƃ̓L�̎������ł��傤�ˁv�Ƃ����Ă����B���̐l�Ƃ́A���̗쉀�ɒʂ��Ă���ԁA���x���o����Ă����B �@�܂��A���鍂��̒j���́A�s���R�ȑ�����������Ȃ���Q�q�ɗ��Ă����B���L�����N���O�ɖS�����Ă������A�Ƃ����藈��Ƃ����B���̐l�͐́A�]�����̂̂��ߏႪ���҂ƂȂ������ߕ������Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ������B�u���͐V�������܂��������Ƃ�����܂���B�ǂ������܂ōs���A��������͎��ۂɑ����Ă���p�������邻���ł��v�Ƃ����Ă������A�����܂ŏo���������Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B���̐l�͊O�o���邱�Ƃ���V�Ȃ̂����A�y�b�g�̂��Q��ɂ͏o�����Ă����̂������B�Ⴊ���̂�����́A�s���͈͂�����������A�y�b�g�Ǝ����ɂ��邱�Ƃ��������߃y�b�g�ւ̈����͂��̂��Ɛ[���Ȃ�B���̌��ʁA�y�b�g���X���d���Ȃ�₷���Ƃ������Ƃ��A���̂��뗝���������Ƃ������B �@���́A�����������l�����̕�����蒲�������Ă������ŁA�y�b�g�̎��ʑ̌����z���ł��Ȃ��قǏd���Ȃ�l�����邱�Ƃ�m�����B�܂��A�y�b�g���X�ɂ���Č�ǂ����E�������l������Ƃ������킳�b���A���̍����������l�������畷�����悤�Ɏv���B�����Ă���͂��蓾�邱�Ƃ��Ǝv���悤�ɂȂ����B���̂��Ƃ͌�N�A���̗Տ��o���ƐM���ł���b��t�Ƃ̌l�I�ڐG�Ȃǂ���y�b�g���X������Ƃ��鎩�E�̃P�[�X�����邱�Ƃ��킩���Ă����B �@���̍��̎��́A�S���w�𐳎��Ɋw�юn�߂ĂQ�N�ʂ����o���Ă��Ȃ������B�����ăy�b�g���X�ɂ��Ă̒m��������I�ɕs�����Ă����B���̂��߁A�y�b�g��S�������l�̃O���[�t�E�J�E���Z�����O��P�A�����܂��ȂǂƂ������Ƃ́A�����Ă������Ȃ������B�����������̏ꍇ�A��w�ł��y�b�g���X�ɂ��ċ����Ă����搶�����Ȃ������B�w�����Ă����t�����Ȃ������̂ł���B �@������w���w�@�ł����b�ɂȂ����搶���́A���ꂼ��̕���ł͈�ƌ������搶�������������A���ƃy�b�g���X��g�`�a(�q���[�}���E�A�j�}���{���h)�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�f�l�Ƃ��܂�ς��Ȃ������B��傪�Ⴄ�̂ł����āA����͋��߂�ׂ����Ȃ����Ƃ������B����āA���Ƃ͎����Œ�������Ȃ�Տ�����ς�Œm���𑝂₷���A�O��������ǂ�Ō������邵���Ȃ������̂ł���B �@�����������̎��́A�J�E���Z�����O��S���Ö@�ɂ��Ă��w�Ɠr���ł���A��������ʂ�̓}�X�^�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��g�������B���́A��w���O�̍u�`��Z�~�i�[�ȂǂɎQ�����Ȃ���A�w�����k���ŃP�[�X�������Ă͐S���Տ��ɐe����ł������B���̂���́A�T���ґz�̐S�����͂��߁A�N���ȍ~�̊w�Z�E�E��s�K���A�K���S���w�A�_�o�ǂȂǂɊS�������Ă����B �@��w�@�̌㔼�ɂ͌������q�ǂ����ЂƂ萶�܂ꂽ�̂ŁA�ƒ닳�t�Əm�̍u�t�����Đ��v�𗧂ĂĂ����B�ꎞ���A��̂j�搶�̂Ƃ���ŏ�������Ă������Ƃ����������A����͌��C�̂��߂ł����Ď����ɂ͂Ȃ�Ȃ������B����ɂ��̂Ƃ��ɂ́A�y�b�g�̗Տ��ł͂Ȃ��l�Ԃ̗Տ��ɐi�ޓ���I��ł����̂ŁA�����a�@�̗Տ��b��t�ɂȂ邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ������B����Ȋ��̒��ŁA�y�b�g���X��A�j�}���Z���s�[�Ɏ��g�ނƂ������Ƃ͎��������Ō��������Ȃ��A����͂܂��܂���̘b�Ɋ�����ꂽ�B �@��w�@���C���������́A���ł�30�ɂȂ��Ă����B�Ƃ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�m�l�̋��͂ēs���ɃJ�E���Z�����O���[���i���́u�}�C���h���T�[�`�Z���^�[�v�A���N�u�}�C���h�Z���s�|�Z���^�[�v�ɉ��́j�����S�����k��K�����k���s���Ȃ���w����N���[�g�ЂƊW���ċ��玏��A�E��ɐ��i�e�X�g��K���e�X�g���쐬���Ă������B�܂��A����Ȃ��Ƃ����Ȃ�����w�Z���w�ŐS���w�̔��u�t�̐E�Đ������Ă����B �@���ƂȂ��Ă͎������ĐE�ƓK�����������쐬���Ă������Ƃ�m��l�����Ȃ��Ǝv�����A���̃G�r�f���X�̈�[�������Ƃ���A����(2013�N)�ł��ғ����Ă�����̂����������B����́A����Y�Ƃ̒����o�ŎЂ����Z�������ɍs���Ă���E�ƓK������������ŁA�����ł����Z���̐i�H�w���̎Q�l�Ɏg���Ă���B �@�S���J�E���Z�����O�Ɋւ��ẮA�w����Љ�l��ΏۂɊw�Z�E�E��̐l�ԊW��̖���A�E�E�]�E�w���Ȃǂ̑��k�����Ă����B��������ėՏ����������Ă��邤���ɁA�܂�Ƀy�b�g���X�����ރP�[�X���o�Ă���悤�ɂȂ����B����͎�i�͕ʂɂ���A���̂��߂ɑ��k�ɗ����̂����A�b�����Ă��邤���Ɂu���́A�ŋ߃y�b�g�����ɂ܂��āA���̂��ߗ]�v�ɗ�������ł��܂��v�Ƃ������e�̂��̂������B�����悤�ȃp�^�[���͂��̌�A�����������B�������A�y�b�g���X����i�Ƃ��đ��k����]����l�̓y�b�g���X�P�P�O�Ԃ��n�߂�܂ŁA�ЂƂ�����Ȃ������B�y�b�g�������������J�E���Z���[�̑����A�y�b�g���X���P�A�̑ΏۂɂȂ�Ƃ͍l���Ă��Ȃ������̂ł���B �� �@���̍��ɂ́A�y�b�g���X�̌��҂����ݓI�ɂ͂������邱�Ƃ�A���̒��ɂ͏d���Ȃ�l�����邱�Ƃ��킩���Ă����B���������ς�炸�S�̑����ǂ��Ȃ��Ă���̂����悭�킩��Ȃ��B�����������n�߂Ȃ���A���̐�킩��Ȃ���Ԃ����܂ł��Â��B�������Ȃ���Ƃ����z�������≟�����悤�ɁA�u�R���p�j�I���E�A�j�}�����X�E�T�|�[�g�E�z�b�g���C���E�y�b�g���X�P�P�O�ԁv�Ƃ������O�����Ė����d�b���k���J�n�����̂��A1996�N11��24���B�N��́A40���Ƃ��ɉ߂��Ă����B �@�Ȃ����̓��Ȃ̂��Ƃ����A���̂��뉽���̗p���Ŏ�ނ����ǔ��V���̂l�L�҂ɁA�������������Ƃ��n�߂悤�Ǝv���Ă���ƌv���b�����Ƃ���A�قǂȂ��L���Ƃ��ĐV���Ɍf�ڂ��Ă��ꂽ�̂��A���̓��Ȃ̂ł���B���ʂ́A���Ă悱���Z���`�̏����Ȉ������������A�u�y�b�g���X�P�P�O�ԁ@���̋g�c����A�����ŏ��̊J�݁v�Ƃ��ĎЉ�ʂɏЉ�ꂽ�B �@����͓��j���̒������������A���̓�����d�b���������Ă����B��t�͖��T���j���Ɛ��j���̌ߌ�T������V���܂łƂ����̂����A������������͎���Ȃ������B�����̌��j���ɂȂ�ƁA�T���O����d�b����͂��߁A��b�킪�u���Ȃ���ԂƂȂ����B�d�����Ȃ��̂łW���ɓd�b���Ă��������Ƃ��A�X���ɂ����Ă��������ƌ�ɂ��Ă��炢�A��x���ɂ���ƏI������B���̌�A���E���j�͓����悤�ȏ�ԂƂȂ�A�I���̂��P�Q�����߂��邱�Ƃ��������B���̊ԁA���͕K���ɂȂ��Ęb���A�킩��Ȃ����Ƃ̓N���C�G���g����ɐq�ˁA���̎��_�Ő������ƐM����P�A���s���A�L�^�ɏ������߂��B �@���̂����d�b�ԍ��݂̂��Ƃ�����������A�j���Ǝ��ԂɊW�Ȃ��l�Z�����������Ă���悤�ɂȂ����B�^�钆�⒩���ɂ������Ă��邱�Ƃ��������B�y�b�g���X�P�P�O�ԂƂ����̂�����A�������Ă��悢�Ǝv���Ă��܂����悤�������B�����̂��̈��ُ�Ȍ����́A���������ɂ̓y�b�g���X�̑��k�������ɂ͂Ȃ��A��͂Ȃ��玄���ЂƂ�ʼn����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ�������������B�܂��������������Ƃ��A�d�b�����鑤�ɂ͋C�y�����������Ǝv��(���݂́A���x�����\�͂̂Ȃ����͕ʂƂ��Č����L���ł�)�B �@����ȏȂ̂ŁA�d�b���������Ă��Ă������ɏo���Ȃ����Ƃ������������߁A���k�҂̒��ɂ́u�������Ă��b��������Ȃ����A��̂ǂ��Ȃ��Ă���I�v�ȂǂƓd�b�̌������œ{�肾���l���o�Ă���n���������B����ɂ��Ă݂�A������͏���Ȏ����̂���@�l�c�̂��������ł�����Ă���A�d�b�������炷���ɏo�Ă���̂����R���Ƃł��v�����̂��낤�B�����Ƃ玞�Ԃ������Ă̓{�����e�B�A�ň�l�ł���Ă���̂ɁA�Ȃ�œ{���˂����Ȃ��̂��Ƃ��v�������A���ꂾ��������K���Ȃ̂ł������B �@����Ƀy�b�g���X�ł͓{���G�ӂ������Ȃ�A���ꂩ���X�P�[�v�S�[�g�Ɏd���ĂĔ��ė~���s���𐰂炻���Ƃ��邱�Ƃ�����A���̈��S�ȑΏۂɃJ�E���Z���[�≇���҂��Ȃ�₷���Ƃ������Ƃ�����킩���Ă����B����͓d�b���k�̂Ƃ��A�N���邱�Ƃ��������B�x�������߂Ă��ĉ��Ƃ����Ăق����Ƃ����Ă����Ȃ���A�������G�������舫�Ҏ����邱�Ƃɂ���ē{��𐰂炻���Ƃ��閵���ɋC�Â��Ȃ����炢�������Ă���l������̂��B �@�܂����̌�A�ʐڂɂ�鎖��������邱�Ƃɂ���āA�J�E���Z���[�͎���ꂽ�y�b�g�̐g����ɂȂ邱�Ƃ��킩���Ă������Ƃł���B����̓y�b�g���X�E�J�E���Z�����O�̋Z�@�⎡�Í\���ɂ�����鎖���ł���B�y�b�g�������Ă���Ƃ������傳��̓y�b�g�ɖ�����A�y�b�g�Ɏx�����Ă������A���ʂ̃J�E���Z�����O��ʂł̓J�E���Z���[�͎�����̎x����(�C�l�u���[)�ł��������ƂȂ��ăy�b�g�̉ʂ����Ă��������Ɠ��l�̗�����Ƃ邱�ƂɂȂ�B���̗��҂̖����̗ގ����́A������y�b�g��S�����ď��S���Ă��鎔����ɂƂ��ăJ�E���Z���[���y�b�g�̑㗝�҂ƂȂ�f�n���\���ɔ�߂Ă���B �@����n�N�����̃N���C�G���g����́A���Ƃ̖ʒk���Ɏ��̔w��ɖS�������y�b�g���I�n����悤�Ɋ�����Əq�ׂ��B���������̎�����͑r�����y�b�g�ɑ��A���킢�炵�������������݂Ƃ������m��I�ȗz�����������Ă���A���̈�����d�v�ȑ��҂Ƃ��Ẵy�b�g�Ɏ����ʂȊ�����J�E���Z���[�ɓ��e������B���̖ʐڏ�ʂŔߒQ����N���C�G���g���J�E���Z���[(���Î�)���U�y�b�g���E�U����������S���́A�]�ڌ��ۂ̈��ł���A�y�b�g�]�ڂƌĂт���B �@��̓{���������������݂āA�{���I�ɂ͎�����u������ɂ��Ă��Ȃ��Ȃ����y�b�g�Ɍ������銴���}�����đ��҂ɓ]�ł��Č����Ă����_���炢���Ĉꎞ�I�ɋN����y�b�g�]�ڂƍl������B�y�b�g�̎��ʑ��k�ł͓d�b���k���܂߂āA���̓]�ڊ���ƁA���̉e������J�E���Z���[�̊���(�R�]��)���ǂ̂悤�Ɉ������ɂ���ăP�A�̐��ۂ����E�����B �@�y�b�g���X�Տ��̋Z�@�⎡�×��_�ɂ��Ă͍e�����߂邪�A�ʐڎ����ɑ����g��邱�Ƃɂ���āA���{�l�̃y�b�g���X�̎����Ƃ��̐l�����ւ̃P�A�̎��ۓI�Ō��ʓI�Ȑi�ߕ��Ɋւ��đ����̂��Ƃ��𖾂���Ă����B�܂��A���Ă̕��������Ă��Ă������Ă������Ƃ��������A���̌�O���̌����҂�Տ��Ƃ�ƌ𗬂��͂��߂����Ƃɂ���ĉ��Đl�Ɠ��{�l�̃y�b�g���X�̌��ł͂��܂��܂ȓ_�ňقȂ邱�Ƃ��킩���Ă����B �@���������āA�ʐڎ��Â̐i�ߕ������̂��Ƃ�O���ɂ��Đi�߂Ȃ���A���܂������Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B���Ẵy�b�g���X�P�A�̍l�������Z��M�Ă��̂܂ܖ͕킷�邱�Ƃ͊댯�Ȃ��Ƃł������B�����������_������{�l�Ⓦ�m�l�̃y�b�g���X���������邱�Ƃ́A�\���Ӌ`�̂��邱�Ƃł���B �� �@�����̂��Ƃ��ꉞ��������Ă������߁A2000�N��10���A���͎҂āA���{�y�b�g���X����𗧂��グ�A�p���J�E���Z���[�̗{�����n�߂��B���̉������������̎傽��ړI�́A�y�b�g���X�̃P�A���X�g���琬���邱�Ƃɂ������B�p��(��)�J�E���Z���[����n�߂��̂́A���̕����C���y����������ł���B�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�����ƂȂ�ƁA����͑厖�ł���ӔC���d��������ꂽ�B �@�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�ɂȂ邱�Ƃ��y�ł͂Ȃ����Ƃ́A������Ԃ悭�m���Ă�����肾�B���͊w���Ƃ��ďb��w���S�N��(���̂���͂S�N��������)�w�сA�����Ə@���w���R�N�Ԋw�сA�S���w���T�N�Ԋw�B�����Ԃ��蓹�������悤�ł����邪�A�������邱�Ƃɂ���ĂȂ�Ƃ��y�b�g���X�E�J�E���Z���[�ƂȂ鉺�n����邱�Ƃ��ł����B�������㑱�̐l�ɂ́A���Ɠ���������܂������Ƃ͎v��Ȃ��B���������Ȃ�ƁA�y�b�g���X�E�J�E���Z���[�ƂȂ�l�ɂ́A�����̒��̕K�v�Ȓm�����R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂ċ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͑�ςȎ����Ǝv�����̂ł���B �@�J���L�������Ɋւ��ăy�b�g���X����̃X�^���_�[�h�����Ăɂ����m�ɂ���킯�ł͂Ȃ������̂ŁA�Œ�ł����ꂾ���͒m���Ă����Ăق����Ǝv�����̂�ԗ������B������e�ɂ��Ă͏�������������Ă����Ǝv�����A�����s���ȓ_�����邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�����A�����ł������Ƃ��Ă��A�y�b�g���X�̃T�|�[�g���ł���l������Ă������Ƃ��K�v�������̂ł���B �@���͑����̃y�b�g���X�̌��҂����Ȃ��Ƃ�������āA�����܂ł���Ă��邱�Ƃ��ł����B�y�b�g���X���ǂ��������̂��́A�y�b�g���������N���C�G���g������������Ȃ���^���̌��t�Ō���Ă����B���̐��ɋ��S�R���Ɏ����X���˂Ȃ�Ȃ����A���̎����傳���͑�Ȃ��Ƃ��܂��A�����������狳����Ă���B���̐l�ԂƓ����̊Ԃ��s����������̂̒��Ƀy�b�g���X�̗����Ƃ��̉����@���B����Ă���C������B �@�y�b�g���X�P�A�͎�����Ƃ����l�Ԃ�Ώۂɂ���̂ŁA�l�̐S����Љ�ɂ��Ă悭�m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��{�͂��̓��������݂��邱�Ƃ���n�܂��Ă���B����ăy�b�g�����̐��V�a���ɂ��Ă͂悭�l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B������̈ꐶ�����E���A����҂�����B���܂��́A�����������҂Ȃ̂��H
|
|||||
�@ �@������ߐ��́A������l�̎葫�̑���Ƃ��Č�ʂ�_��Ƃ̘J���ɗp���邱�ƂŏW����͂����Đ��Y�������߂Ă����B�ߑ�ɓ��蓮���́A�����ΏۂƂ��Đl�X�̐����̒��ɐ[���Z�����Ă������B���e��v���J���͂Ƃ��ĐE���H��ɏo�čs�������߂ɕs�݂ƂȂ����ƒ�ɔނ�͓�����悤�ɓ����Ă��āA���̂����Ԃ߂Ă��ꂽ�B�܂��A�V���O���̐l�X�₨�N���̐��_�I�v���ɓ����邽�߂ɁA�����̓y�b�g(���ߓ���)�A���Ȃ킿���������Ƃ��ďd�v�Ȗ�����S���Ă������ƂƂȂ����B �@�ނ�͂ǂ̎���ɂ����Ă���ɉ��̉��Ŏ��������x���Â��Ă����B�����A�����͈ˑR�Ƃ��ē������d�v�ȐH�������Ƃ��Ă��邵�A���̂��炾�̓o�b�O��C����z�Ȃǂ̔�v���i�Ƃ��Ă��p���Ă���B���̐����X�^�C���͂����ɂ͕ς���ꂻ�����Ȃ��B �@�����č����A�y�b�g���R���p�j�I���E�A�j�}��(��������)�ƌ�����悤�ɂȂ��Ă������Ƃ�����킩��悤�ɁA�����Ɛl�Ԃ͐S���Љ�I�ȋ������k�߂Ȃ����i�Ɛe�����𑝂��Ă���B�܂��A�ӓ��������Ȃǂ̃T�[�r�X�E�h�b�O�A����ɂ̓Z���s�[�A�j�}���Ƃ��ĐS�g�̎��Â�È�ɗ��p����Ă��錻�������ƁA�����̉ʂ�������������ɂ���ĕϑJ�𐋂��Ȃ���l�ԂƓ�������苭����I�����Ȃ��`�������邱�Ƃ͋^���]�n�̂Ȃ��Ƃ���ł���B �@��@�ɑ�������Ɛl�Ԃ͓����ɏ��͂����߂�B����͏����Ȏq�����s�������������A��e�ɏ��������߂Ă����p�ɂǂ������Ă���B�q�ǂ��͈��S����S����(���т�)�����ꂽ�Ƃ��A���̋^�����������ɕ�e�ɂ����݂��Ă����B�q�ǂ��ɂ���ΐg�̊댯�����������A��e�ɋ~�������߂邱�Ƃ͂���������O�ł���A���̂��Ƃ����߂čl���邱�Ƃ��Ȃ��قǂɎ������A���ӎ������Ă���B �@����Ɠ������Ƃ��ǂ̎���ł������͓����ɑ��Ă���Ă����B�����Ĕނ�͂���ɂ��ȋC�ɂ������Ă���Ă���B���݁A�����̐l�X�����̍���Ȏ�������z���悤�Ƃ��ē����̗͂ɗ����Ă���B�����������_����݂āA��������l�������邳�܂��܂Ȋ�@�̉����Ɍ����ăy�b�g�����A�R���p�j�I���E�A�j�}�������́A�������̐��_�������A�ʼn��x������Ō�̍ԂƂ�����̂ł͂Ȃ����B
|
|||||
�@ �@���̂悤�ȏ�Ԃ͂�������y�b�g���X�̌����疢���ɗ��������Ă��Ȃ����Ƃ��������̂ł���B���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɂ������߂��݂��������i�ǂ���̐����ɖ߂����Ƃ��Ă��A�����������悤�ɂȂ�����A���܂ł��y�b�g�ɐG����Ȃ��̂ł���A���̐l�͗�������̃v���Z�X�̂ǂ����ō����܂������܂ܕ����I�ɗ��܂��Ă���ƍl������B���ʂ̔ߒQ����̉ɒ�܂��������͑��݂��Ȃ��B���������Ă����Ƃ������A���Ԗ��܂������Ȃ��l������̂��B �@���̏ꍇ�A���̐l�����̑r���̌��̂Ȃ��ɗ��������W���Ă��鉽���ے�I�v��������ł���A��������ɂ߂Ď�菜���Ă����Ȃ�����A���̐l�����͂��܂ł������ƕ�点���ɉ߂������ƂɂȂ�B �@���́A���̂悤�Ȑl�X���������ƕ�点�Ȃ��ł��錴����T��A�����������ĐV���ȃy�b�g���C�t���y���߂�悤�ɂȂ��Ă������������Ɗ���Ă���B���̗��R�͎��ʂɂ��߂��݂�ߐӊ��������ɑ傫���ɂ���A�����ƂƂ��ɐ������т≶�b�̂ق����͂邩�ɑ傫������ł���B �@�y�b�g�u�[���ƌ����ċv�����B���a30�N��̍��x�������Ɏn�܂邱�̗���͂��ł�2�E3����ڂɓ���B���̊ԁA�y�b�g��������l�������������܂ꂽ�B���������̈���Ńy�b�g�Ƃ̕ʂ�ɂ����܊���㖡�̈�������y�b�g�����ɂȂ�l������Ă����B�y�b�g���X���N���u���Ă������Ƃɂ���Ă��̃u�[���̉A�Ńy�b�g������N�����l�𑽐�����ł����̂ł���B �@�����ɁA���Ē����V�����s���������[������������(2004�N9��25������)�B����͖���ׂɑI��2833�l�ɃA���P�[�g���������̂ŁA����ɂ��u�y�b�g���D���ł����H�v�Ƃ����₢�ɑ���68���i1927�l�j���u�͂��v�A32���i906�l�j���u�������v�Ɠ����Ă���i����́A2010�N�̓��t�{���_�����ŁA�y�b�g���炪�D�����Ɠ�����20�Έȏ�̐l�i�y�b�g���D���j����72���A���������ăy�b�g�͌������Ƃ���20�Έȏオ��28������Ƃ����f�[�^�Ƌߎ����Ă���̂ŁA�܂��M�����Ă��悢���낤�j�B �@�����āA�u�������v�Ɠ������l�ɂ��̗��R���ƁA1�ʂ��u���b���ʓ|�v(535�l)�A2�ʂ��u�Ƃɉ����A�ɂ��������v(499�l)�A3�ʂ��u�m�~��_�j�Ȃǂ��S�z�v�i444�l�j�ł���A4�ʂ��u���ɕʂꂪ��Ɂv(415�l)�Ƃ������̂ł������B�Ȃ��A5�ʂ́u���������������v�i251�l�j�A6�ʂ́u�Ƒ������������v(97�l)�A���̑�(102�l)�ƂȂ��Ă���i������������j�B �@�����ŁA���ڂ��Ăق����̂��A����4�ʂ́u���ɕʂꂪ��Ɂv���Ȃ킿�A�y�b�g�͎��ʂ��猙�����Ƃ����l�ł���A�����Ƃ͂������������̐l�̎���46�����߂Ă���Ƃ����_�ł���B�����V���Ɠ��t�{�̒����𑍍�����A���{�l�̐��l�̖�3�����y�b�g�����ł���A�����Ȃ����l��4�����Ƀy�b�g���X�̌�������ł���Ƃ������ƂɂȂ�B �@���̃f�[�^��M����ɑ���Ƃ���[���̊W�R���͍����Ǝ��͓���ł���̂����[�������{�l���l�̎����ɒ����A���̐��͔��[�Ȑ��ł͂Ȃ��Ȃ�B�ǂ̂��炢�̐l���ɂȂ�̂��Ƃ����A����O�S���l�ł���B���̐l�����́A�����y�b�g���X�̔ߒQ����������邱�ƂȂ����ɔ�߂��܂܁A�y�b�g������N�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B �@���̐l�����́A�܂�����Ȃ����Ă̓y�b�g�ƕ�炵�����Ƃ�����l�����ł���B�����1�ʂ���3�ʂ̐l�����ɂ����̉\���͂��邪�A��������1�ʂ���3�ʂƁA�S�ʂ́u���ɕʂꂪ��Ɂv�ł́A�y�b�g�����ɂȂ錴�����{���I�ɈقȂ��Ă���B�P�ʂ͎��{�Ǘ�����ςŎ�ɕ����Ȃ��Ƃ��ʓ|�������Ƃ������̂ł���A�Q�ʁE�R�ʂ͉q���ʂ̖��ł�������y�b�g�̕a�C���l�ɂ���S�z�ł������肷��B�������u���ɕʂꂪ��Ɂv�Ƃ����̂́A�����Ƃ͖��炩�Ɉَ��ł���A����̓y�b�g��S����������̐��_�I�ꂵ�݂̖��ł����āA����I�X�g���X���e�[�}�ł���B �@���O�S���l�Ƃ������́A�ډ��̌��ƔL�̎���������킹�������ł������l�S���l(��)�ɓ�������l���ł���B���̂��Ƃ͓��{�ł́A���L���D���łƂ��ɕ�炵�Ă��鎔���吔�ɔ��鐨���Ńy�b�g���X�������Ƃ��ăy�b�g�����ɂȂ�l���������Ă��邱�Ƃ������Ă���B �@�܂��A�����V���̒����ł́A�y�b�g���D�����Ɠ������l��59���̓y�b�g�������Ă��Ȃ��Ƃ����B���̗��R�́A�u�}���V�������y�b�g�֎~�v(���A38�Ώ���)�ȂǏZ���̐���ł�������A�u��l��炵�ŋA����x���v(�ޗǁA46�Ώ���)�A�u����̂��߁A�y�b�g����ɖ{�l�����̐��s���̐S�z�v�i�����A70�Βj���j�Ȃǐ��b���������Ă��ł��Ȃ��������ق��ɁA�u�Ƒ����l�ɕ�炵�������̎��ɑς����Ȃ��v(�_�ސ�A34�Ώ���)�Ǝ��ɕʂ�̂炳���������ӌ���������ꂽ�Ƃ����B �@���̃y�b�g�̎��ɕʂ�ɑς����Ȃ��Ɠ������l�����������Ƃ����f�[�^�ɂ́A����������Ă��Ȃ����߂ɏڍׂ͕s�������A�y�b�g���D���ł������Ȃ��l�X�̂Ȃ��ɂ����Ȃ��炸�y�b�g���X���[���e�𗎂Ƃ��Ă���l���������邱�Ƃ������Ă���B �@���̂��Ƃ���A�y�b�g���X���@�Ƀy�b�g������Ȃ��Ȃ�l�͐�̃f�[�^�������ۂ͂���ɑ����ƍl������B�����A���̎��Ԃ͒������ꂽ���Ƃ��Ȃ����߂Ɏ����܂߂Ă��̂��Ƃɐ��m�ɓ�������҂͒N�����Ȃ��B�������y�b�g���X�̌��ǂ��A�y�b�g���D���Ȑl�ɂ������Ȑl�ɂ����܂��܂Ȃ������ʼne�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ́A���̗Տ��o������m���ɂ�����B �@����A���̐l�����𑝂₷�����炷���́A�y�b�g���҂�_�ی��]���҂݂̂Ȃ炸�A�y�b�g�������鎔���傳�����܂߂��l�X���A�y�b�g���X��ɊS�������A�ǂꂾ���͂𒍂��ł������ɂ������Ă���B�y�b�g������N�����l�X�������Â��ĊF���u�y�b�g�͎��ʂ��玔���͎̂~�߂悤�v�Ƃ�����������A�y�b�g�Y�ƂɂƂ��Ă��y�b�g�ɂƂ��Ă����邢�����͂Ȃ��̂��B�����āA���̃c�P�͂܂��y�b�g�̎����傪�������Ƃɂ��Ȃ�B�y�b�g�����������Ƃ��̗���A�O������A�y�b�g���̂��̂��n�߃y�b�g�t�[�h���Ô�̒P���͍����Ȃ邾�낤���A���̕i��̌��L���ق����Ƃ����Ă��A���̎��ɂ͂��������ɂ͗ǂ��u���[�_�[�����Ȃ���������Ȃ��B �@�č��ł�1980�N��̏��߂Ƀy�b�g���X��̏d�v���ɂ��������C�Â��A���g�݂��n�߂��B�킪���Ƃ��Ă��y�b�g���X���ɂ��܂ł��t�^�����Ă����̂ł͂Ȃ��A�^���Ɍ����������������Ƃ�����B�y�b�g���X�̃T�|�[�g�́A�܂��̓y�b�g�ɂ������d�������Ă���l���������悵�ē�����ׂ������A���̂��ƂɃy�b�g�W�҂͂����ƕq���łȂ�������Ȃ��Ǝv���B�u�y�b�g���X�Ȃ�ĉ������ɂ͊W�Ȃ��v�u�킽���̓y�b�g���X�ɊS���Ȃ��v�ȂǂƓ����W�҂������Ă���悤�ł͂܂��_�����B �@�܂��A�u�y�b�g���X�A�y�b�g���X�Ƃ��܂葛���ȁB�l���y�b�g������Ȃ��Ȃ邶��Ȃ����v�ƐS�z����y�b�g�Y�Ƃ̐l������B���̐l�����́A�y�b�g���X������������킩���Ă���A���ꂪ�m��邱�Ƃ�����Ă���̂��B�y�b�g���҂Ȃ�A���̖�������Ēʂ낤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A������Ƀy�b�g���X�ɂ��Ă̐������m���������A����ȏ㈫�����Ȃ��悤�Ɍ����Ӗ�������̂ł͂Ȃ����B���̖��ւ̎��g�݂́A�Â��ɖ���q���N�����Ă���̂ł͂Ȃ��A����悭�Ȃ��Ƃ����ċN���������l���x������s�ׂȂ̂��B
|
|||||
�@ �@����炪��i���������ƁA�r�f�I��Ђ̐l�����Ƃ͕ʂ�Ď��͂ЂƂ�j���[���[�N�Ɏc�肠��l���̉Ƒ���T�����Ƃ��Ă����B���̂���l���Ƃ́A�y�b�g���𐢊E�ŏ��߂Đl�Ԃ̐S�����Âɓ������ăA�j�}���Z���s�[�ƃq���[�}���E�A�j�}�� �����[�V�����i�l�ԁE�����W�w�j�̐��҂ƂȂ����{���X�E���r���\���ł���B �@���r���\���́A1984�N�ɂ��łɖS���Ȃ��Ă���B���́A���r���\�����m�Ƃ͐��ɂ܂݂��邱�Ƃ͂Ȃ������B���̉����͂��ꂩ��������Â��邾�낤�B�����A���͂�r���\���ɉ�Ȃ��̂Ȃ�A���߂Ă��Ƒ��������������Ǝv���Ă����B �@�������A���̂Ƃ����r���\���̋ߐe�҂ɂ��Ă̏��͂قƂ�ǎ������킹�Ă��Ȃ������B�B��킩���Ă���̂́A�R�����r�A��w�̃}���[�������r���\���̕]�`���������ꕶ�iMallon,G.P. 1994. A generous spirit: The work and life of BORIS LEVINSON. Anthrozoös, volume�Z, number 4, pp.224-231.�@����͂��̌�A���r���\���̋L�O���ׂ�����ڂ̒����u�y�b�g�E�I���G���e�b�h�E�`���C���h�E�T�C�R�Z���s�[�i�y�b�g�w�������S���Ö@�j�v�̉�����Q�ŁA�M��u�q�ǂ��̂��߂̃A�j�}���Z���s�[�v�Ɏ��^���ꂽ�j����A������̓��[�X�E�o�[�R�E�B�b�c�Ƃ������ł���A��l�̑��q������Ƃ��������炢�������B �@�����A���ꂾ���ł͂ǂ����悤���Ȃ��B�������͓����Ȃ����Ǝv���āA�ʎ��͂Ȃ�������Dr.�}���[���̌������Ƀz�e������d�b�����Ă݂����A�����ɂ��s�݂ŗ���d�ɂȂ��Ă����B����͌�ł킩�������Ƃ����A�}���[���̓��r���\���̂��q���Ƃ͐ڐG�������Ƃ��Ȃ��������Ƃ���A�}���[���ɕ����Ă����r���\���̉Ƒ��̏����ɂ��Ă͂킩��Ȃ�������������Ȃ��B �@���r���\���͐��O�A����̈ꎺ��ʐڎ��ɂ��ĐS���Ö@���s���Ȃ���A�j���[���[�N�̃C�G�V�o��w�ŋ��ׂ���Ƃ��Ă����B������j���[���[�N�̂ǂ����ɏZ��ł����͂����B�����Ȃ�Ζ��S�l�i�Ƃ����Ă͂����Ȃ��������B���́u�v��S�������ȁv�ƌ���Ȃ�������Ȃ����ƂɂȂ��Ă���j���A���q���������j���[���[�N�ɂ��邩������Ȃ��B����ȒW�����������Ȃ���A���̂Ƃ����ɂł��邱�ƂƂ����A�z�e���̈ꎺ����d�b�������Ȃ��烌�r���\���Ɩ��̂��l�Ɉ�l�ЂƂ�d�b�������Ė₢���킹�Ă݂邱�Ƃ������B �@���͂����������s�Ɉڂ����B�u�n���[�A���̓{���X�E���r���\�����m�Ƃ����S���w�҂̂��Ƒ���T���Ă��܂��B���Ȃ��́A���r���\�����m�̋ߐe�҂ł͂���܂��H�v�u�������A�Ⴂ�܂��v�u�ǂ������炵�܂����v�B���̃��r���\���ɂ����Ă݂�B�u�n���[�A���̓{���X�E���r���\�����m�Ƃ����S���w�҂́E�E�E�E�v�u�m��܂���I�v�B�܂����̃��r���\���ɂ�����B�u�W����܂���I�v �@��������āA���l���̌��m��ʃ��r���\���ɂ��������ƁA�ЂƂ�̒j�����d�b���ɂłĂ����B���͓����₢����ƁA�d�b�̌������ł��̒j���͂������Ƃ����������������Łu����́A���̕��ł��v�Ƃ������B���ꂪ�A���r���\���̒��j�}�[�e�B���E���r���\������Ƃ̂͂��߂Ă̐ڐG�������B �@���͂��ǂ��ǂ����p��Ŏ����������A���Ђ���������|��`�����B����Ɣނ͖����A���傤�Ǖꂪ�����̉Ƃɂ���̂ŋX����������A�ǂ��������ł��������Ƃ����Ă��ꂽ�B�����A���͋�����ꂽ�Ƃ���j���[���[�N�E�N�C�[���Y�n��ɂ���}�[�e�B������̂�����։��������Ă������ƂɂȂ����B �@�Ƃɂ��ƁA�����ɂ͒��N�̂��v�w�ƃL�����Ƃ��������ȘV�w�l�ƈꓪ�̃~�b�N�X�Ǝv�����^�����o�}���Ă��ꂽ�B�}�[�e�B������Ƃ��̉�����A�����ăA�C�[�_�E�y�i�����_�E���r���\���v�l�ƃ}�[�e�B������̈����ł������B������́A���ϓI�A�����J�l�̏Z�ލL���ŁA�傫�����Ȃ����������Ȃ��A��������r�I�ȑf�ȍ�肾�����B�����̂ނ����ɂ͔L�������B���e����̂������A��͂蓮���D���̂悤�������B���v�w�ɂ͓��m�������炵���ǂɂ͍ז��Ȑ��n�悪�����Ă������B �@�}�[�e�B������́A���Z�̗��j�̐搶�����Ă���A���͒�N�̂��ߔ��Ŋw�Z�ɂ����Ă���Ƃ����B���v�w�ɂ́A��w�Ŗ@�����w�Ƃ������q���ЂƂ肢�邪�A���łɓƗ����ăr�W�l�X�}�������Ă���Ƃ������Ƃ������B �@���r���\���̓A�j�}���Z���s�[�̃t���C�g�Ƃ�������B���̔ނ��A�Ȃ��A�j�}���Z���s�[���͂��߂��̂��A���͂����m�肽���Ǝv�����B���Ƒ���K�₵���ő�̗��R�������ɂ������B���H���͂���Ń}�[�e�B������ƃ��r���\���v�l����͍݂肵���̃��r���\�����m�ɂ��Ă��܂��܂ȋM�d�Ȃ��b�����������邱�Ƃ��ł����B�܂��A���̎���ɑ��Ă����ӂ���́A���ꂼ��̗��ꂩ�璚�J�ɓ����Ă����������B�ȉ��A�o���Ă��邱�Ƃ������Ƃ߂Ă݂邪�A�܂��̓A�C�[�_�E���r���\���v�l�̂��Ƃ���͂��߂悤�B �@�A�C�[�_����́A��ȂŃ��r���\�����S���Ȃ�܂ł̔ӔN�̏\�N�Ԃ��Ƃ��ɉ߂������B�ޏ��́A�{���r�A�o�g�̌��O�����ł���A���{�ɂ����C�������Ƃ�����Ƃ�����ςȃC���e���̕��������B�������A�Ȃ�ƕ��e���{���r�A�̑哝�̂������Ƃ����B��b�̂��Ȃ��ޏ����A"My father was a President of Bolivia."�Ƃ������Ƃ��ɂ́A��u�����^�����B���߂�"President of Bolivia?!"�ƕ����Ԃ��ƁA�ޏ��͂͂�����Ƃ���������"Oh,yes yes! "�ƔO���������B �@�ޏ��ɂ��A�j���[���[�N�̓����}���V�����œ����ЂƂ��炵�����Ă������r���\���ƒn���ɂ��郉���h���[���ł͂��߂ďo������Ƃ����B���@��t�@�蕷���킯�ɂ������Ȃ������̂ŏڂ����͂킩��Ȃ����A�ޏ������r���\���Ɠ������č��ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�A�C�[�_�́A���r���\���͂ƂĂ��n���T���ŗD�����l�������Ƃ����B�����������ɂ��悭���Ăċ���i�ނ͔M�S�ȃ��_�����k�������j�ɍs���ƁA���Ă��鏗����������́u�搶�A�L�X���āI�v�u���ɂ��L�X���āI�v�ƃL�X�������܂�邱�Ƃ��������Ƃ����B �@�܂��A���r���\���͌����ʂɊւ��ĐV�������z����Ɉ��o�Ă���^�C�v�������炵���A����Ƃ��A�C�[�_�Ɂu�����ɃA�C�f�A���o�Ă���v�ƘR�炵���Ƃ����B���̂��߁A�x�b�h�̘e�ɂ͋L�^���ƃy������ɂ����Ă���A�����l���������ԂƖ钆�ł��N���ď�������ł����Ƃ����B�܂��ɁA�Ђ�߂��̐l�������B���r���\���̓��_���l���L�̖����ȓ��]�̎����傾�����悤���B �@���������̃��r���\���ɂ͈�̎�_���������B����͌��N�Ɋւ��邱�ƂŁA�ނ͓�a�Ƃ���郊���[�}�`�i�����A�P���a�Ƃ��̂����j���Ⴂ�����犳���Ă���A�Ƃ�������@�����Ă����Ƃ����B�A�C�[�_�����Q���Ă��Ă��ꂽ�A���r���\���̎ʂ��Ă���A���o���������Ă������������A���̂Ȃ��ɂ͓��@���ɎB��ꂽ�x�b�h�ɍ��|���Ă��郌�r���\���̑s�N�̂���̎ʐ^���������B �@�ނ͌����Č��N�Ȑl�ł͂Ȃ������̂��B���̂��߁A�Ⴂ����͕������Ə��ɂȂ������A���U�����Ԃ̉^�]�����Ȃ������Ƃ����B���̃A�����J�Љ���ԂȂ��Ő������邱�Ƃ́A�����Ƒ�ς������Ǝv���B �@���͂���܂ŁA���r���\�����A�j�}���Z���s�[�i�ނ́A�͂��߃y�b�g�Z���s�[�ƌĂсA���̌�q���[�}���E�R���p�j�I���A�j�}�� �Z���s�[�Ƃ������Ă����j��y�b�g���X�������͂ɐ����i�߂��o�C�^���e�B�[���ӂꂽ�p�C�I�j�A���Ǝv���Ă����B����͈�ʂł͐������������A�ނ����a�̂��߂ɓ��މ@���J��Ԃ��Ă����l�������Ƃ������Ƃ͑z�����Ă��Ȃ������B �@���������̌�A���r���\�����a��ł������Ƃ������Ƃ��A�ނ𗝉����邤���ŏd�v�Ȍ��T�O���Ǝ��͍l����悤�ɂȂ����B���r���\���̌����������ǂ�Ƃ��A�ނ̂܂Ȃ�������ɎЉ�̎�҂Ɍ������Ă������Ƃ��킩��B��w�𑲋Ƃ��A�j���[���[�N�̍s���}���ł��镟���������Ƃ��ē����n�߂�ƁA�ނ̎����͎Љ�̍ʼn��w�ł������z�[�����X�̐l�X�Ɍ������Ă������B�ނ͂��̌�A����̃z�[�����X���Ɋւ���_���������Ă���B �@�܂��A��w�@���łėՏ��S���m�Ƃ��Ċ�������悤�ɂȂ��Ă�����A���ǂ��͂��߂Ƃ����Q�����q�ǂ������̐S���Ö@�ɂ������Ă���B�ނ̉s�q�Ȋ����́A��Ɏ�҂�������҂Ɍ������Ă������A����͎���̕a�C�̌��ɐ[���������Ă���Ǝv����̂ł���B�ꂵ�ގ҂̖{���̋C�����́A���炪�ꂵ�݂𖡂�����҂ɂ����킩��Ȃ����̂��B �@����ɁA���r���\�����l����ɂ������āA�����ЂƂd�v�Ȃ��Ƃ�����B����̓��V�A�v���̂�������Ă̂��Ƃ��낤�A1923�N�A�ނ�16�̂���ږ��̎q�Ƃ��ē������g�A�j�A���a���̃|�[�����h�����ɋ߂��J���o���A�iKalvarija�j�Ƃ����Гc�ɂ��痼�e�ƃT�C�����ƃ\�������̌Z��ƂƂ��ɐV�V�n�A�����J�ɓn���Ă����Ƃ����_�ł���B��p�ꌗ�̐l�Ԃ��e�B�[���ɂȂ��Ă���n�Ă����̂�����p��̏K���ɂ���J�������낤�B�ނɂ͏I���A�p��ɂ�⋭���Ȃ܂肪�������B �@�܂��A���r���\���̕��e�͈ߕ����������l�ł������Ƃ������A�o�ϓI�ɂ͌b�܂ꂽ�ƒ�ł͂Ȃ������悤���B�}�[�e�B������ɂ��A���̂��ߕ��e�͌C���Ċw����҂��ł����Ƃ����B�C���œ����Ă����̂ł͂Ȃ��A�C�̍s�������Ă����̂��B�ނ͓����Ȃ���w�Ԑ��^�̋�w���������B �@���r���\���́A�j���[���[�N�s����w�ł̓T�C�G���X�S�ʂ��w�B�A�C�[�_�ɂ��A���r���\���͍L�����R�Ȋw�ɋ����������A�V���w�ɂ��S���������Ƃ����B��w�@�C�m�ے��ł͋���w���A���m�ے��ł͗Տ��S���w���U�����B �@���́A�ӂ���Ƀ��r���\�����m�͂ǂ����Ĉ�w���֍s���Ĉ�t�ɂȂ�Ȃ������̂��Ǝ��₵�Ă݂��B����ƃA�C�[�_�́A��l�͂��炾����v�ł͂Ȃ��������炾�Ƃ����A���q����͕��͂������Ȃ��������炾�Ƃ������B���b���f���Ď��ɂ́A���̗��������Ă͂܂�悤�Ɏv�����B �@���r���\���ɂ́A�ނ̐��_�̎u�����炢���Ĉ�t�ƂȂ��Čb�܂�Ȃ��l�X�̖��ɗ��������Ƃ����������ꂪ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B��������t�ƂȂ邱�Ƃ́A�܂�����������߂Ă����Ǝv���B�����A���r���\������t�ɂȂ�Ȃ��������Ƃ��A�ގ��g�̂��߂����ł͂Ȃ��㐢�̐l�X�ɂƂ��Ăނ���傫���K�������Ǝ��͍l���Ă���B�ނ����_�Ȉ�⏬���Ȉ�ɂȂ��Ă����Ȃ�A1950�`60�N��̂���������݂āA�������y�b�g������l�̎��Âɗp���钅�z�Ď��s�Ɉڂ��ȂǂƂ����O�㖢���̎��g�݂��ł���͂����Ȃ������Ǝv������ł���B �@���̂��Ƃ́A���r���\�����y�b�g�Z���s�[��Տ����p���L�������m�F�������Ƃ��w��\�����Ƃ�����ނ��S���Ȃ钼�O�܂Ŏ��X�ɂÂ������_�Ȉ�ɂ��ᔻ���݂Ă����炩�ł���B���r���\���̍s�������@�i���r���\���@Dr. Levinson's method�Ƃ�����j ���ᔻ�ɂ��炳�ꂽ�̂́A�ނ̎��×��_�Ƃ��̋Z�@�������Ƃ��Ă͎a�V���������߂ł����������A�����ЂƂ͔ނ���t�ł͂Ȃ��������Ƃ��������邾�낤�B �@���r���\���́A�����A�����J�Ŗu�����������N���j�J���E�T�C�R���W�X�g�i�Տ��S���m�j�ł������B���r���\�����A�u���R�̔����v�ƌĂԎ��ǎ��W���j�[�ƃ��r���\���̈����W���O���Y�i���̐��E��L���ȃZ���s�[�h�b�O�̓V�F���^�[���������Ă����~�b�N�X���������j������̖ʐڎ��ł��܂��ܐڐG�������Ƃ���A�j�}���Z���s�[�̒��z���̂�1953�N�B���̖����A�����J�S���w��ɍŏ��ɔ��\�����̂�1961�N�A�����60�N��ɓ����Ă����B �@���̎���A�A�����J�̓P�l�f�B�̈ÎE�ɂ͂��܂�x�g�i���푈��h���b�O�A�l�퍷�ʁA�������^���i��Âɂ�����C���t�H�[���h�E�R���Z���g�ւ̊S����������n�܂�j�̍��܂�ȂǑ����̖��ɒ��ʂ����B�����āA���̐S���ʂł̑Ή���Ƃ��Ă��܂��܂ȐS���Ö@���҂ݏo���ꂽ�B�ނ̊v�V�I�Ȏ��݂��\�ɂ����̂́A60�N��̔�r�I���R�ȕ��͋C�̂Ȃ��ŁA�S���Տ��ɗL���Ȃ��̂�����Ή��ł�������Ă������Ƃ���C����������Տ��S���w�̗���ƌĉ����Ă���B �@���݂ł́A���_�Ȉ���͂��߂Ƃ����t��̃A�j�}���Z���s�[�ɑ��錩�������X�ɗl�ς�肵�Ă��邪�A���r���\������ڂ���������ނ͐��_�Ȉォ��͂����ԂȎv����������ꂽ�炵���B����̓y�b�g�����Âɗp�����Ƃ������Ƃɍ��킹�āA�ނ��Տ��S���m�������Ƃ����_�����邾�낤�B���_�Ȉ�ł��Ȃ��҂���t�܂����̂��Ƃ����Ď��������̗̈��N���n�߂�����łȂ��A���̂�������k�Ȃ炢���m�炸�펯�͂���̎�@�����n�߂����Ƃɂ���B�A�C�[�_�́A�u��l�́A���_�Ȉ�������Ă��܂����iMy husband hates psychiatrist.�j�v�Ƃ����Ă����B���ꂪ�A�����Ӗ�����̂��E�E�E�B �@�ǂ̗̈�ł���o�҂́A�I�͂���̔�]�₠�����������̂炵���B���ꂪ�t�@�[�X�g�����i�[�̏h���Ȃ̂��낤�B�������A���ꂪ���Ƃ��ǂ�Ȃɔn�������ᔻ�ł������Ƃ��Ă��A�_������ǂ܂��Ύ����̐�������F�߂����邽�߂Ɏė����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A�w�҂Ƃ������̂��B���r���\���̌㔼���́A�����̎��Ԃ��_���ɔ�₳�ꂽ�B�����A����Ș_�������X�J��Ԃ��ꂽ�Ƃ�����A���r���\���ɂ�����X�g���X�͐r��Ȃ��̂ƂȂ������낤�B�ނ̌��N�́A�ނɑ���]���̍��܂�Ƃ͗����ɏ��X�ɐ��ނ��Ă������B �@��b�̒��ŃA�C�[�_�́A���r���\������ϗD�����A���炵���l���������Ƃ����x�ƂȂ�������B���������́A�{���̃��r���\���̎p��m�肽���Ǝv���Ă����̂ŁuDr.���r���\���́A����Ȃɂ��������D�����i�W�F���g���ȁj�l�������̂ł����A���l�̂悤�ɁH�@���ɂ͂����͎v���Ȃ��̂ł����E�E�v�ƁA�����ɕ����Ă݂��B����ƁA���̈Ӑ}��ǂ̂��}�[�e�B������́A���̒j�Ȃ班���͕��̂��Ƃ�b���Ă��悢���Ǝv�����̂��A����ȃG�s�\�[�h���I���Ă��ꂽ�B �@����́A�}�[�e�B�����܂��q�ǂ��̂���A���邱�Ƃŕ��e��{�点�Ă��܂������Ƃ��������Ƃ����B���̂Ƃ��A���r���\���͍��̃x���g������ă��`�̂悤�ɐU��u����͉��p�S���w�i�A�v���C�h�E�T�C�R���W�[�j��!!�v�Ƃ����ē{���I��ɂ����Ƃ����B���́A���̃W�F���g���}���炵����ʃ��r���\���̘b���āA�܂��܂����r���\�����D���ɂȂ����B�ނ��l�Ԃ炵������̒ʂ����l�ł���A�[���q�ǂ����v���ЂƂ�̕��e���������Ƃ𗝉������̂ł���B �@�܂��A���r���\���ɂ͓��{�l�̒m�荇�����N�����邩�ƕ����Ă݂����A���ӂ���Ƃ����r���\���ɂ́A���{�l�Ƃ̐ڐG�͂Ȃ������Ƃ������Ƃ������B�}�[�e�B���v�ȂɂƂ��Ă��A�l�C�e�B�u�̓��{�l�Ɖ�̂͂��ꂪ���߂Ă��Ƃ����B���v�w�́A�f��u�V�����@�E�B�@�_���X�v�i�������I���W�i���Łj��ʔ��������Ƃ����Ă����B���̂��v�w�����{�f������Ă������Ƃ́A�������������B���̉f��̌�A���h�ēƎ剉�̑������コ��͌��������Ɠ`����ƁA���v�w�́A�Ӂ[��Ƃ���������Ă����B������́A���{�����ɂ��S������炵���A"seppuku"�Ƃ������t���m���Ă����B �@�}�[�e�B������́A���������Ε��e�����O�A�����������L�^������Ƃ����ăJ�Z�b�g�e�[�v���K���玝���Ă��ĕ������Ă��ꂽ�B�����ɂ́A���r���\���̓����Ő��������⍡�܂ł̂��Ƃ�����Ă����B�Ȃ܂�̋����p��̂��ߕ������ɂ����������A�������肵����⑁���̘b�����������B���̉�]�������̂��낤�B���͎����Ă����J�Z�b�g���R�[�_�[�Ƀe�[�v�̋�������^�������Ă����������i���̖����\���������r���\���̓����͂��̌�A���x���������u����Ŕ��\�����j�B �@���̓��r���\���̒a�����ɂ��Ă����₵���B�}���[���̕]�`�ɂ́A�ނ�1907�N�V���V�����܂�ƂȂ��Ă���B�V���O�������߂ł������Ȃ̂ŁA����͖{�����ǂ����^��������Ă����̂��B����ɑ��A�}�[�e�B������́A���̒a�����̓��_�����ŕ\����Ă���̂ŁA����ɒ����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B���q������L���X�g���ł͂��ɂȂ�̂��A�悭�m��Ȃ��悤�������B1907�N�̐��܂�́A�ԈႢ�Ȃ��悤�����A�V���V���Ƃ����̂́A���r���\���ꗬ�̃W���[�N��������Ȃ��B �@�}�[�e�B�����e�ɂ��A���������₪����܂����ƕ������Ƃ��A���͎v�킸�u���N�͂������ł����H�v�ƕ����Ă��܂����B�ނ́A��ł����ċ�������A���̓��r���\�������̂Ƃ��q�ǂ����������̂��́A�}���[���̃��r���\���̕]�`�ɂ�������Ă��Ȃ������̂Œm���Ă������������̂��B���ȓ��m�l���ˑR����Ă��āA�Ȃ�ł��悢���畃�e�̂��Ƃ�b���A���Ȃ��͍������Ȃ̂��ƕs�^�ɕ����ꂽ�̂�����A�Ȃ�Ƃ���V�m�炸�ȓz���Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B���v���o���Ă��Ԗʂ��Ă��܂��B �@�܂��A�}�[�e�B������́A���e���A�j�}���Z���s�[���ŏ��Ɏn�߂���������������Ƃ����̂ŁA���Ќ������Ƃ����ƁA�����܂ł킴�킴�ԂŎ���A��Ă��Ă��ꂽ�B�r���A�s���}���ق̉���ʂ����Ƃ��A���͂Ђ�ς�ɂ����ɒʂ��Ă͎d�������Ă����Ƌ����Ă��ꂽ�B �@���r���\�����Z��ł����Ƃ����Ƃ́A��͂�N�C�[���Y�ɂ���Â��ȏZ��X�T�j�[�T�C�h�ɂ����K���Ă̓����̍������������B�C�M���X�ɂ悭����ꌬ�̉Ƃ��Ɏd�����X�^�C���ŁA�����čL���Ȃ��B�����ɍŏ��̉����[�X�ƃ}�[�e�B������A�����Ď��j�̃f�C�r�b�g����i���݁A�f���w�̑�w�����B���̌�A�ނ��B�e�������r���\���̐��O�̎ʐ^�𐔖������Ă����������B���̂Ȃ��ɂ́A���r���\�������ۂɃZ���s�[����p���Ďq�ǂ��̎��Ò��̋M�d�Ȃ��̂��������j�ƈ����W���O���Y�������B �@�}�[�e�B�����Ƃ̃x���������ƂȂ����璆�N�̏������o�Ă����B�ӂ���͉�b���͂��߂����A���Ζʂ̂悤�������B�ǂ����A���݂̏Z�l�͂����������r���\���̎���ŁA���̉Ƃ��A�j�}���Z���s�[���˂̒n���Ƃ������Ƃ͒m��Ȃ��悤�������B�}�[�e�B������͂��̏��L�҂̋��āA���𗠒�ɘA��čs���Ă��ꂽ�B��������͂P�K�̔������ǂ�ꂽ���̂��镔�����������B�ނ́A���̕��������r���\���̐S�Î��������Ƌ����Ă��ꂽ�B�����ȕ������B�����ׂ͗��L�b�`�����Ƃ����B�̋Ƃ��͂��߂́A�킸���ȋ�Ԃ���l�m�ꂸ�N������̂̂悤���B���̎����ɂ͓���Ȃ������̂ŁA�Ƃ̊O���牽�����ʐ^�Ɏ��߂��B �@���r���\���̂��Ƃ��l����Ƃ��A�ނ͊w���E��n�ʂ邽�߂Ɏg��Ȃ��������A�Ȋw�i�����j�\�w�̂��邱�Ƃ��ւ�����A�w�҂Ԃ��Č����т炩�����Ɓ[�Ƃ����Ȃ������B�������������������Ȃ�A���̂悤�ȓ����Ƃ��Ă͏����ǂ��Ȃ�Ƃ��킩��Ȃ����X�N�̑����̈�ɓ��ݍ��ނ��ƂȂ��A�����ƌ������������������낤�Ǝv���B���̕���̔��W�́A���̐��҂���̚}�₳�����ޔᔻ�ɋ����邱�ƂȂ������Ǝ��H���Â������r���\���̗E�C�ƐM�O�ɕ����Ƃ��낪�傫���B �@�A�C�[�_�́A���r���\�����S���Ȃ���̂��Ƃ��b���Ă��ꂽ�B���̓��́A�C�G�V�o��w���N�ސE�������ƕ�E���Ă����u���[�x���[�������ÃZ���^�[�ŁA�ӂ���̐��_�Ȉ�ƂЂƂ�̐S���w�҂Ɖ�����Ƃ����B���̌�A�S������ɂ���ĐE�����ɖS���Ȃ����Ƃ������Ƃ������B�ޏ��́A������v�̖���D�������������_�Ȉ�ƐS���w�҂Ƃ̋c�_�ɂ��S�J������Ǝv���Ă���悤�������B���r���\���͖S���Ȃ钼�O�ɔޏ��ɓd�b�������Ă��āu�A�C�[�_�A���͂������߂��A�A�C���u���[�v�ƌ����c���A����30�����1984�N4��2���A�ߑO11���ɑ�������������Ƃ����B76�������B �@�u��l�������Ă�����A���Ȃ��ƂȂ���ł��낢��Ȃ��Ƃ��������b���������Ƃł��傤�ɁA���ꂪ�ł��Ȃ����Ƃ��������c�O�ł��v�ƁA�A�C�[�_�͂����Ă��ꂽ�B���ʂ�̎��A�ޏ��Ƃ͍��E�̖j�Ɩj���y�����ăL�X�����B���̎��A�A�C�[�_�͏����Łu�A�C���u���[�v�Ǝ��ɂ����₢���B�Ƃ����̂��Ƃ������̂ŁA���͉��Ƃ����悢���킩�炸�u�~�[�A�c�[�v�Ƃ��������Ȃ������B �@�A�C�[�_����́A���̌�A���ƂȂ��Ă͎�ɓ���Ȃ����r���\���Ɋւ��鎑�����܂ޑ����̕����𑗂��Ă����������B���̂Ȃ��ɂ́A���r���\�����g�ɂ���č��ꂽ�����ژ^�����������A�R���ڂɂ��čŌ�̒����uAUTISM�i���ǁj�v���܂܂�Ă����B���̂������������āA���r���\���̎�v�Ȓ���͂����������낦�邱�Ƃ��ł����B �@�����A�C�[�_�ɂ��ڂɂ��������Ƃ��́A�v���r���\����S������14�N�ڂɂ�����B�ޏ������r���\���ƕ�炵�����Ԃ����łɒ����Ă����B�A�C�[�_�͂�����ꍑ�̃{���r�A�ɋA��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă����B�A�����Ƃ���A�Ƃ��ɋA�������낤�B���̂Ƃ��A���ɂ������Ă��ꂽ�v���o�̂܂������̃��r���\���̃A���o���ƁA�ނ̒���ƂƂ��ɓ�Ăɗ��������̂��낤�B�ޏ��̎v���o�̒��ɐ����郌�r���\���́A�������D�������݂��₳�Ȃ��W�F���g���}���̂͂����B�A�C�[�_�ɂ�����Ă��獡�N�ł��ł�15�N���o���A���̌�͂�����Ă��Ȃ��B���͂�A���̐��ɂ͂����Ȃ���������Ȃ��B
|
|||||
�@ �@�����ł����K���I�����Ƃ����̂́A�y�b�g��S�������l�ɕ\���邳�܂��܂ȕω��̑����͑r���̏Ռ��ɑ���S�I�h�q�@��(�V���b�N�⓮�h���玩�����낤�Ƃ���S�̂͂��炫)�ł�������A�S�̍P��I�ȋύt�i�������ɂȂ�悤�o�����X����낤�Ƃ���S�̍�p�j��ۂ��߂ɁA�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ω��Ƃ����Ӗ��ł���B�܂�A�y�b�g���X���̐S����s���́A�ň��̎҂Ƃ̕ʂ�Ƃ������قȑ̌����炢���Ă��̂悤�Ȕ����������N�������Ƃ��ނ��뗝�ɂ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B �@����āA�y�b�g��S�������Ƃ��̑唼�̃G�s�\�[�h�i�ł����Ɓj�́A���̖ړI�ɂ����ĕK�v�������ĕ\���Ă��邱�ƂȂ̂ŁA�ނ�݂ɗ}������������肷�邱�Ƃ́A�߈�������ɐ��ڂ��Ă����v���Z�X��W���邱�ƂɂȂ邽�߂ɁA���ʂƂ��ĉ�x�点���藧������Ȃ��Ȃ����肵�₷���B�������A���̖��ĂȎ��������܂Ō��߂����ꂽ���������Ȃǂ��Đ����ɗ�������Ă��Ȃ������B����ɂ͂������̗��R������悤�Ɏv����B �@���̑��́A�������̎Љ�A�Ƃ�킯�ߑ�Љ�ɂ������Ĕ߂��ނ��Ƃ��Öٗ��ɔF�߂Ȃ��Љ����肠���Ă������Ƃ����邾�낤�B�߂��ނ��Ƃ́A���Ȑl�Ԃ̂��邱�Ƃł���A�������Ƃ͒p�ł���A���̂悤�Ȋ����\������҂͕s�K���҂Ƃ��ĎЉ�͔ߒQ�҂�r�����悤�Ƃ��Ă����B�ߑ�l�͔߂��ނƂ����A���܂₩�ő�ȏ�����������Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ����̂ł���B �@���̗��R�́A�߂��ނ��Ƃ��ߑ���x����x�z�����ł���W�c��`�Ƌ��������̂�����ɂƂ��Ă����Q�ނ��̂ł���������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�H���E��œ����ɋ�����Ƃ��c�ނƂ��A�ЂƂ肾���W�c����O��Ă��܂ł��߂��܂�Ă͑S�̂̐��Y����������������ቺ���Ă��܂��̂ł���B �@�܂��A�悫�����ł���Y�Ɛl���琬���邽�߂̊w�Z������A�W�c��Ώۂɂ��Ĉ��̒m����Z�\��Z���Ԃɐg�ɂ������Đ��ɑ���o�����߂ɂ́A���k�ɂ������߂��܂��Ƃ���������Ȋ����������邱�Ƃ͕s�s���Ȃ��Ƃł������B �@�܂��A���������̓����́A���̐��_�ɂ���ɔ��Ԃ��������B�Y�ƊE������E�����̂��Ƃ�ٔF����ǂ��납�A�㉟�������Ă����Ǝv���B����ɁA���j�I�ɋߑ㍑�Ƃ��A�Ŏx����R����`�v�z�A���Ȃ킿�����R���Ɨǂ��R�l����邽�߂ɂ́A�G�ƂȂ鑼�҂̔߂��݂�m��l�ԂȂǂ͎��ɕs�v�ȑ��݂������B�x��������ڂ����ߑ㍑�ƂɂƂ��āA�߈��̊���͂��̖ڕW��j�Q���u�C�̒ቺ�������ő�̓G�ł��������B �@���ɁA�������͎��ƌ�������Ȃ��Ȃ������Ƃ���������B����Љ�́A����r�������Љ�ł�����B�������ɂƂ��Ď��͂˂ɕs���Ȍ��ۂł���A���m�̂��̂��Ƃł���B�ߑ�l�̍�����`���炢���Ă����͉��������̋y�Ȃ����̐��̂ł����Ƃ��B �@����䂦�Ɏ������́A���̖����S�̒��S����͂����A�ӎ��̂��Ȃ��ɒǂ�����Ă��܂����B����̐��E��썰�̖��ȂǂƂ������s���̎��ۂ́A�������Â��ɂ��ė}���̑ΏۂƂ��Ă����B�����āA����ɑ�����̂Ƃ��āA���̐��̕����I�ɉh��o�ϓI�����ɍő�̊S���Ă����B �@���̓_�A�ߑ�l�͍��܂ł̂ǂ̎���l���������������A�}���Ă����l�������Ƃ����邾�낤�B�������́A���ɂ��ĐG��邱�Ƃ��^�u�[�����A���ƌ����������Ƃ�����Ă����B���̎��������Ƃ�����Ă���̂��A�����ߑ�l�ł���B�����āA�������͎����y�����邱�Ƃɂ���Ď��̖���\�ʓI�ɂ͍����������̂悤�ɐU�镑���Ȃ���A���S�͎�����ɋ���Ă���Ƃ����s�ύt�ȏ�Ԃ��Â��Ă���悤�Ɏv���B �@�l���܂��Ƃ������قǁA�ǂ������Ă���B�����Ε����قǁA�߂Â��Ă���̂��A���̖�肾�B�����̎����a�i���Ɓj����̂́A����ʂ��Љ��a���Ă��邩��ł�����B �@��O�ɂ�������̂��A�l�Ԓ��S��`�̍l���ł���B�����̎�����������Ɍy������X���́A�����⎩�R�Ƃ̐ڐG���a���ɂȂ�ɂ��������ċN�����Ă���B������Ȃǖ쐶�����ɐ����������ˑ�����l�X�́A�����邽�߂ɓ������E�Q���邪�A�ނ�݂ɎE�����Ƃ͂Ȃ����A���̎����y�邱�Ƃ��Ȃ��B�ˎ~�߂������͒��d�ɏ�������A���̗�͎�������i�Ƃނ�j����B �@�������A�������͓����⎩�R�������ɒǂ�����Ď���̗D�ʂ悤�Ƃ����B�ߑ�l�̎��s�́A���̕�Ȃ��n�͎��������l�Ԃ̂��߂ɑ��݂���̂��ƍ��o�����Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����B�����ł͓����̒n�ʂ͑��ΓI�ɒቺ���A�����Ƃ͗�������́A�����Ȃ����́A���l�̒Ⴂ���̂ƂȂ�B�܂��A�����͐l�Ԃɕ�d(�T�[�r�X)���ׂ����̂ł���A�{�\�Փ��̂܂܂ɐ���������ȑ��݂ȂǂƘc�Ȃ������߂�l�͔ނ�ɗ^���Ă����B�������͂����������l�Ԓ��S�̎�ϓI���E���瓮���𑨂��Ă����B �@���̈���ŁA�����̒n�ʂ��߂悤�Ƃ��������̗��R�́A��ł��铮���������Ƃ��Ē��N�ɂ킽���ĎE���ĐH���Ă������Ƃւ̍߈����ƃR���v���b�N�X�������̐[�w�S���ɂ���Ǝ��݂͂Ă���B�܂��A�������E���Ȃ��܂ł��A�l�Ԃ͓����̐�����S�������Ċ�`���Œ艻���邱�Ƃ܂ł��Ď��R�E�ɂ͂Ȃ��`�̂����o���Ďg���∤�ߓ����Ƃ��Ă����B �@�܂��A�|�������Č������ɂ�����A�Ϗܗp�ɋ�����Ȃǂ��Đl�ԑ��̈���I�ȓs����~���Ŕނ������Ă����B�������������Ƃւ̌��߂��������邾�낤�B�����������������B���ɂ́A�����͐l�Ԃ���������������������ł���A�m�����Ӕ\�͂��R�����ዉ�ȑ��݂��Ƃ݂�����͂邩�Ɋy�ł������Ƃ�����B �@�A�j�}���Z���s�[�̐�o�҂ł���Տ��S���w�҂̌̃{���X�E���r���\���́A���āu�y�b�g�ɂ���Đl�Ԃ̎Љ�́A�l�Ԃ炵�������邱�Ƃ��ł���v�Əq�ׁA�y�b�g��S�����Âɗp���铹���J�����B���̈ꌩ��Ƃ��v���邪�Ӗڂ��ׂ������Ƀ��r���\���̎v�z�̊j�S�����߂��Ă���B �@�܂��A����N���C�G���g����͎��Ɂu�����͕��ʂ̊���̂���l�ԂɎ������Ă����v�Əq�ׂ��B���Ȃ݂ɁA���̕��͂Â��āu���e��������炾�ƕ��ʂ̊���̂���l�Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������B���̐l�́A���������납�獂���I�Ƃ�������p�ˋ���e��������ʁA�s����Q�����������̂������B �@���r���\���₱�̃N���C�G���g����̂悤�ȓ����Ɛl�Ԃ̊W�ɂ��Ă̂����ꂽ���@�́A�]���̋ߑ�l�̔��z��l�Ԏ����`�̍l������͓����o����邱�Ƃ͂Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�ΐl�Ԃ��l�Ԃ炵���Ȃ�̂́A�����܂Ől�Ԃ̗͂⏊��ɂ��̂ł����āA������y�b�g�����i���������j���l�Ԃɐl�Ԑ���^����ȂǂƂ������z�́A�l�Ԃ̗�����含�ɍő�̉��l��u���l�Ԓ��S��`����͐��܂��͂����Ȃ�����ł���B �@�������A���ܑ����̃y�b�g��������l�X�́A�������傫�Ȑ��_�I�x���ɂȂ邱�Ƃ�A�ނ炪�����Ă���邱�Ƃ̂����ɑ傫������̌�����m��悤�ɂȂ��Ă���B�����āA���̓��������Ƃ̕ʂ�́A�������ɖ��̑�������Ӗ��ɂ��Ă��g�������ċ����Ă���邱�ƂɋC�Â��͂��߂Ă���B�������҂₱�̕���̌����҂�́A���̂悤�Ȏ����傳���̎p����납��ǂ������Ă���Ƃ��낪����B �@���̍��ׂƂ�������ɂ����āA�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�l�ԂƓ����Ƃ̐V���ȊW�𑨂������Ȃ���A���������g�₱�̎Љ�V�X�e���̘g�g�݂��č\�z���Ă������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B���̂悤�Ȑ܁A�������͉���M���A���𗊂�Ƃ��Đ�����悢���̎w�j�������͎������ɖق��Ď����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
|
||||||
�@ �@�y�b�g������������̔ߒQ�҂̂Ȃ��ɂ́A���ꂩ�牽������悢�̂����킩��Ȃ��Ȃ�قǜܜ����A�����Ă���l������B���̎�݂ɂ�����A���܂��܂Ȉ��s���\�ƂȂ邾�낤�B�ł́A���̂悤�ȗU�f��p���A�y�b�g���V�҂Ƃ��č����E�Ɨϗ���ۂ������邽�߂ɂ́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��K�v�Ȃ̂��낤���B �@���������������ՋƂ́A�u���₵�v�Ɓu���߁v��������ƍs���A�N���[���ȗ����̌n��ݒ肷�����ōςނ��ƂȂ̂��낤���B����A���ꂾ���ł͂���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�Α��Ƃ͈�̂������R�₷�����̍�Ƃł͂Ȃ����A�����Ƃ͍����̂�y�ɖ��߂邾���̍s�ׂł͂Ȃ����炾�B���Ɉ�̂��Ă��˂��Ɉ������Ƃ��Ă��A�u���₵�v�u���߁v���s���āA��p�����邾���Ȃ�A�s�̐��|�ǂ�y�؍�ƈ��̎d���Ƃ��قǕς��Ȃ��B �@�y�b�g���V�ҁA���Ȃ킿�������Ճf�B���N�^�[�̖{���̎d���Ƃ́A�����̍���V�ɂ��Ԃ����邱�ƁA���Ȃ킿�����ł����Ƃ���̈��y��y�ւ̗������������邱�ƂƁA�⑰�ƂȂ鎔����̗�������Ɍ����Ă̔ߒQ�P�A���s�����Ƃł���B����͉Α��E�����⋟�{�ՂȂǂ̑����ʂ��ē����̒����ԗ�i����E���ꂢ�j�i�����̗썰�������߁A�Ȃ����߂邱�Ɓj���i��҂ł���A�����̍������̐��ɑ���Ƃǂ��钢���̐��҂ł�����B����������������́A���V�����_�傳��Ȃǂ̏@���ƂłȂ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��͂��ł���B �@�܂��A�����[�����̎��l�ł���Ԑl�ł���������Ȃ���₳��鎔����̐��_�I�x���҂Ƃ��Ă͂��炭�҂ł�����B�܂�A���̋Ɩ��Ɍg���҂Ƃ́A���ƍĐ����J��Ԃ����̐��Ƃ��̐��̏z�̂Ȃ��ŁA�����Ɛl�Ԃ̕R�сi���イ�����j���Ȃ킿�A�f�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ���Ȍ��т���[�������Ȃ̌`���Ɗm�F����`�����_�I�A��I�擱�҂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����������F���Ǝ��o�Ȃ����ăy�b�g���ՋƎ҂⓮�����Ճf�B���N�^�[�Ƃ��Ă͂��炭�ւ��A�E�ƓI�g�������炽�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �@�y�b�g��S�����������傪���̏��S���痧�������Ă����ɂ́A�y�b�g���V�҂̗͂��s�����B����A�����̑��ՋƂ́A�d�v�ȎЉ���̈�Ƃ��āA����ɕK�v���𑝂��Ǝv����B���������āA���̎d���Ɍg��錻�C�҂�V���ɂ��̗̈���u���l�X���A���̏d���M���~�b�V�����𐬂������邽�߂ɂ́A��荂�x�Ȑ��Z�\�̏C���ƂƂ��Ƀy�b�g���X�̃O���[�t�i�ߒQ�j�P�A�̒m�����s���ł���B
|
|||||
�@ 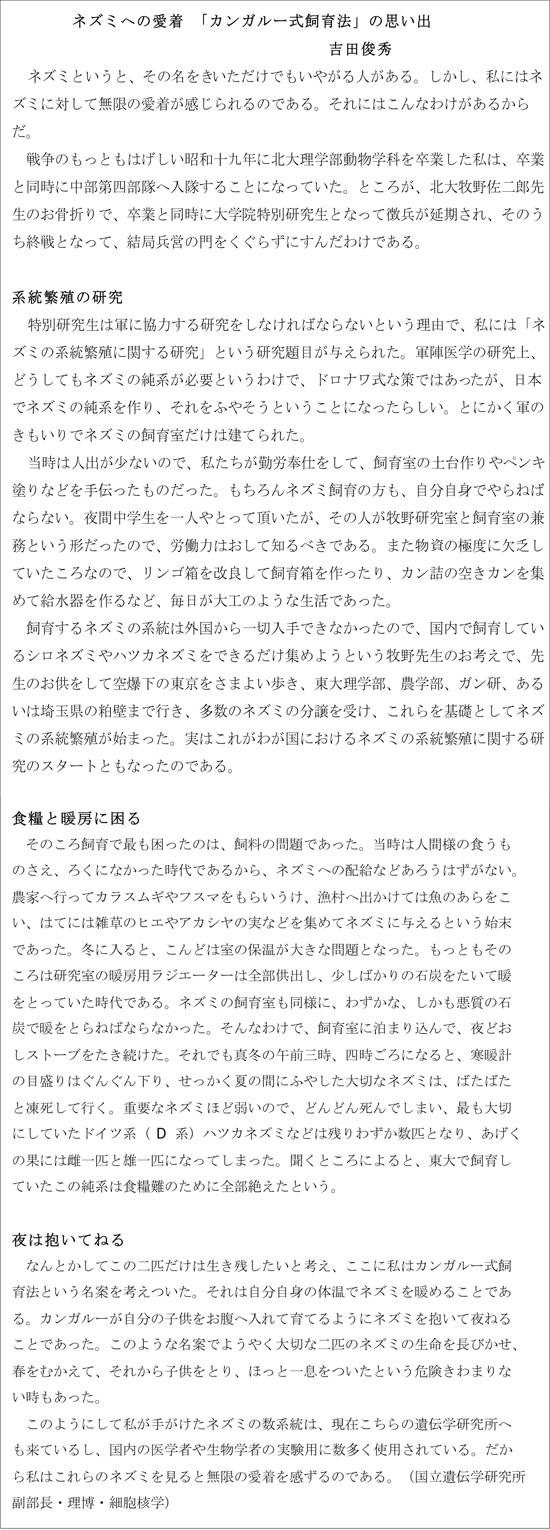
�@���̃G�b�Z�[�́A���̕���36�̂Ƃ����������̂ł���B���͂��̌���w�������𑗂�A�E����N�ސE���Ă�����O���̎���̃K���[�W�����ǂ��ăl�Y�~�������Ă͔ɐB������A�쐶�l�Y�~�̈�`�i���̌������Â��Ă����B�G�T���͕����`���Ă����B���̍�Ƃ́A����66�ŖS���Ȃ�܂łÂ���ꂽ�B���̈ꕶ�������ꂽ�Ƃ��A����3 ���������ƂɂȂ�B �@�������E���Ă��獡�N�ł��ł�27�N�����B����S�N�O�ɖS���Ȃ����B���̃G�b�Z�[ �͎��Ƃ̕�̈�i�����Ă���Ƃ��A���R�������B��͂��̋L���̐蔲�����ɂƂ��Ă����B�~�̎D�y�Ńl�Y�~������Ēg�߂��Ƃ����b�͕����瓖���͐H�ׂ���̂��Ȃ��ĉh�{�����������Ƃ������ƂƂ��킹�ĕ��������Ƃ��������B�������A�ڂ������Ƃ͂��̃G�b�Z�[��ǂނ܂ł悭�m��Ȃ������B �@�����AD�n�}�E�X�́A���������Ƃ��Ĉ�w��b��w�̌�����V��̊J���ɐ���ɗp�����Ă���B�l�Ԃ�y�b�g�̕a�C���Q�̍����Ɍ����đ����̃l�Y�~�����������]���ɂȂ��Ă���Ă���B���͎��炪�J���K���[�̕�e�̂悤�ɂȂ��ĂӂƂ���ň�Ă��l�Y�~�̎q���������Ȋw�̔��W�Ɋ�^���Ă��邱�Ƃ��A�܂����Ă����B �@���̃G�b�Z�[�ł́A�͂��߂Ƀl�Y�~�ɖ����̈�����������Əq�ׁA�Ō�ɍĂѓ������t���J��Ԃ��ďI����Ă���B���ɂƂ��ăl�Y�~�̓A���t�@�ɂ��ăI���K�ł���A�G���h���X�̈����Ώۂ̂悤�������B���������̓y�b�g�ł͂Ȃ����A���̂悤�Ȍ`�ł̓����������邩�Ǝv���B �@���͐��U�l�Y�~�������ƂɎ��S�������A���ۂ̓l�Y�~�ɂ���Đ�������Ă����悤�Ɏv���B�G�b�Z�[�ɂ͑�w�̑��ƂƓ����ɒ�����l�����ɓ������邱�ƂɂȂ��Ă����Ƃ��邪�A�I��܂łɂ܂���N�܃J������B���̕��������̌�A�k���������̂�����������̂��A���ꂩ��̂��Ƃ͂킩��Ȃ��B �@�l�Y�~�̂��Ƃ��Ȃ���A���͐푈�ɋ�肾����Ď���ł�����������Ȃ��B���̐���̒j�����́A���̋����Ȑ푈�̂��߂ɂ����Ƃ��������𗎂Ƃ��Ă���B�������Ȃ���A��Əo����Ƃ��Ȃ������̂�����A�������Ȃ��������ƂɂȂ�B �@���O�A���͎����̉���������Ă����B�u�����@��J��z���i�`���E�`���E�C�� �N�����\�[���j�v�Ƃ����B�N�����\�[���Ƃ́A�u���F�́v�̂��Ƃł���A��J�������z���Ƃ������Ƃ炵�������B���̐��܂ꂾ�������ɂ́A����ȗV�ѐS���������B �@�������A���̉����́A���ۂɎg���邱�Ƃ͂Ȃ������B���l�̎����p�������̌Z���{���̗��h�ȉ������������Ă��ꂽ�B�����A����̉����̕������ɂ͂ӂ��킵���C������B���ɂ���ɂ�������x������Ƒz���B������Ƒz�����A����͂��̐��ɉ����܂Łu�҂āA���������v�Ǝ����Ɍ����������Ă���B ���āA����Ȑl�Ԃ������Ƃ������Ƃ�m���Ă���������K���ł��B (�t�L)
|
|||||
�@ �@���̂Ȃ���͂Ȃ����A�e�q�̊ԕ��ɂȂ낤�Ƃ���s�ׂ́A�[�����x�Ƃ����A�̂���L�����݂��Ă���B�{����Ɨ{�q�A�E�l�̓k�퐧�x�ɂ�����e���Ǝq���A�C�����E�̐e���Ǝq���̊W�Ȃǂ�����ł���B �@�̂Č��E�̂ĔL�̕ی슈���ł��A�V���Ɏ�����������邱�Ƃ��y�b�g�̗��e�T���Ƃ����Ă��邪�A����͖��炩�ɗ{�q��{���̉��g���x�ɂȂ���Ă���B������ƂȂ�l�𗢐e�ƌĂ�ł���̂�����A������Ă����y�b�g�͗��q�ł���B �@�y�b�g����������������A�g���[�j���O��O��I�ɂ����Ȃ��ď]���ȃy�b�g�Ɏd���Ă����邱�ƂɔM�S�Ȏ�����ł���A�����I�Őe���C���̋����l�Ƃ����邩������Ȃ��B�܂��A�������������Ă��鎔����ł���A��������̎q�������Ɉ͂܂ꂽ�e���Ƃ��ĕ�炷���Ƃ�]��ł���̂�������Ȃ��B �@�������A�������Ȃ��َ�Ԃ��Ƃ����̂ɁA�������Đe�q�̂悤�ɐ[�����т����Ƃ���l�ԂƓ������ǂ��l����悢�̂��낤�B���҂ɂ͂��������ǂ�ȉ��A���Ȃ킿�W��������Ƃ����̂��B �@�����ĉ�������ƌ����A�����ŏo������Ƃ����n���͂��肻�����B�u���[�_�[�����s�ɂ����̂Ō��ɍs���Ă��̎q�Ə��������Ƃ��A�q�L�����܂��ܖ�������ł����̂Ŏ����n�߂��ȂǁA�o��������n��ŋN�������Ƃ������ł���B���������A�ŋ߂͖�ǔL��n��L�Ƃ����Ă���A�R�j���j�e�B�E�L���b�g�̂��Ƃ��i��������Ȃ�n���L�ƌĂт����j�B �@�������A�����̎����傳��́A�y�b�g�Ƃ̏o��������Ɛ[���^���I�Ȃ��̂Ƒ����Ă���B�^���I�ȏo��E�E�E�^���I�ȏo��E�E�E�ł͉^���I�ȏo��Ƃ͉����B�����������A�킽�������͂܂������ɑO������̉��A�h�����v���B���̎q�Ƃ͑O���̂ǂ����łƂ��ɕ�炵���̂�����A�����ł��o����ĕ�炷�̂��ƍl����B�[���h���ɂ���Č��ꂽ���Ȃ̂�����A���܉�ׂ����ĉ�����̂��Ǝv���B �@���ꂾ�����낤���B����A�����ЂƂ�ȑz��������B����͂��̎q�́A�_�l�����̂��߂ɂ������Ă��ꂽ��ȑ��蕨�Ȃ̂��Ƃ����z���ł���B�ނ�́A�V�̔z���ɂ���Ď��̂Ƃ���ɗ��Ă��ꂽ�V�g�̂悤�ȁA��F�̂悤�ȑ��݂��ƐM���Ă��邱�Ƃł���B �@�����ł́A�y�b�g�̓y�b�g�łȂ��Ȃ�A�_���������т����Ȃ铮���A���Ȃ킿���b�ł���A�X�s���`���A���E�A�j�}���ɂȂ��Ă����B�����Ȃ�Η��҂̊W�́A���l�����荞�߂Ȃ��قǏ��x�̍������ƍ��̌��т��ƂȂ낤�B����͏����ł���B�����Ȃ����Ƃ��A�l�ԂƓ����̎p�̈Ⴂ�⌌���̗L���ȂǂƂ��������Ƃ́A���͂�ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă������낤�B
|
|||||
�@ �@�[�l���́A�Ώۂ�O�E�𑨂��邽�߂̔F�����@�̂ЂƂł����āA�悭�킩��Ȃ�����������Ǝ������݂Ƃ��ė������邱�Ƃɂ��A�s���������Ώۂ𗹉��\�ȑ��݂ɂ���̂������Ă���B������ƃy�b�g�̊W�ł����A�y�b�g�ɐl�ԓI�ȑ�����^���Ĕނ�̍s�������߂��邱�Ƃɂ���đ��肪�킩�����悤�ȋC�ɂȂ�̂ł���B����͎����傩��݂�Η��҂̋������O���Ək�܂��ăy�b�g�����g�߂ȑ��݂Ɋ������邵�A�e���݂����N���Ă���̂��B �@���̊�b�ɂ́A����ړ�sympathy�̃��J�j�Y�����͂��炢�Ă���ƍl�����Ă���B���Ȃ킿�A�y�b�g��O�ɂ��Ď�����͂��܂��܂Ȋ���������A�������y�b�g�Ɍ������ē���������i���e�j���Ƃɂ���āA������ł͂Ȃ��y�b�g����������Ƃ��ĔF�m����̂ł���B �@�Ⴆ�A�u�y�b�g�����˂Ă���v�Ƃ��u�����̎q�͊Â���V�̎q�v�Ǝ�����͂������A�u���˂�v�Ƃ́A�u�S���˂����ĉ�ӂ�B�s���ŏ]��Ȃ��v�i�O�ȓ��V�����сj���Ƃł���A�u���Ȃ��ɏ]��Ȃ��ŕs���炵���ԓx������B�ӂ����v�i�p�썑�ꎫ�T�j���Ƃł���B �@�������A����L�͖ʔ����Ȃ�����Ƃ����ĐS���˂����ĉ�ӂ�����A�s����s���̂��߂ɂ��Ȃ�����Y��Ăӂ���邱�Ƃ����邾�낤���B���̂悤�ȕ\��������Ƃ��ɂ͂��łɎ�����̊���ړ��ɂ���ăy�b�g�͐l�ԓI�ɏC������Ă���̂ł���B �@�܂��A�u�Â��v�͓y�����Y�ɂ��A�l�Ԃ̕�q�W�ɂ�����ˑ��Ǝ������߂����Ĕ����������̂ŁA�l�ԑ��݂ɖ{�������̂́u�����̎�����ے肵�A�����̎������~�g�i���悤�j���邱�Ɓv�ƒ�`���A�l�Ԃ̖{���I�ȐS���ł���ƍl���Ă���B �@����ɁA�y���ɂ��ΊÂ��͕��ՓI�Ȑl�ԐS���Ƃ��������{�l�̐S���ɍ����������قȐS���ł���Ƃ����B�y�b�g���Â₩���A�y�b�g���Ê��݂���Ƃ������y�b�g���[�l�������\���̑��ɁA�y�b�g�ɊÂ���Ƃ���������̕\���͓��{�l���L�ł���A�����ɂ͂킪���ŗL�̎�����E�y�b�g�W���W�J���Ă���Ƃ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����̏K����s�����w���Ƃ̂���l�Ȃ�A���t���瓮���̍s�����[�l�����ĉ������Ă͂����Ȃ��ƌ���������ꂽ���Ƃ����邾�낤�B�����̐S����s�����������S�ɉ��߂�����A�l�Ԃ̃��x���܂ň����グ�ė������邱�Ƃ͋q�ϐ������߂���ώ@�҂Ƃ��Ă����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯���B �@���̗�Ƃ��ėL���Ȃ̂��A���߂ĉF�����s�����ċA���Ă����`���p���W�[�̘b���B�ނ͉F�����疳�����҂����Ƃ������ނ��o�����\������Ă������߁A�l��́A���̃`���p���N�͉F�����s�i���Ċy����ł����Ɛ��������B�������A�`���p���W�[�ɂƂ��āA�j�b�Ə��Ă���悤�Ɍ����邱�̕\��i�������ʁj�͎��́A���|�̕\���ł������B�[�l���������߂������Ƃ͐^�t��������ł���B �@�������Ɋւ��Ă���Ȃ��Ƃ�����B������������̋��̂�����̃|�V�F�b�g�ɓ���Ď����������Ƃ����s���Ă��邪�A�������̓u���u�������s����Ȋ��⍂���͖{���I�ɍD�܂Ȃ��B���͐l�Ԃ�L�Ȃǂ̂悤�ɐi���̉ߒ��Ŏ��㐶����̌����Ă��Ȃ��������ߒn�ɑ������Ȃ��ꏊ�⍂���Ƃ���͕s���肾�B������q���̂��납�炵�Â��Ă���A�X�g���X�ɂ���ď�s����Ȑ��i���ł��������Ă��܂����낤�B �@�l�Ԃ̕�e���Ԃ�V�𗼘r�ŕ��������Ă��₵����A�������Ђ��ŋ��ɌŒ肵�Ĉړ�����͎̂��R�Ȏp�ł����āA����͐l�Ԃ̗{��s���i�����͒ʏ킱�̎p���ōs����j�∤��̕\���ł�����B�������A���͎����̎q�ǂ��ɂ��̂悤�ȗ{��s���͎��Ȃ��B �@�����́A�m�炸�m�炸�ɐl�Ԃ�쒷�ނƂ��Ă̗{��s���∤��\�����Ƃ��Ă���A������y�b�g�����ɂ��邱�Ƃɉ��̋^���������Ȃ��Ȃ��Ă��邵�A�������邱�Ƃ��ނ�̍K�����ƐM���Ă���B �@������A�y�b�g��������l�ɂƂ��ẮA�y�b�g�Ɠ����ƂɏZ�݁A�������𒅂āA�������̂�H�ׁA�l�ԂƓ������Â��{���A���ɂ͓�������ɓ��肽 ���Ɩ]�ނ��Ƃɉ��̈�a�����Ȃ��̂��B�E�C�Y�@�y�b�g�ƁA�y�b�g��l�ԕ��݂Ɉ������Ƃ́A�y�b�g���D�ƂɂƂ��Ă������ʂ̂��Ƃł���B �@�����l����ƁA�y�b�g�ƕ�炷��тƂ́A�y�b�g���[�l�����Ċy���ނ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���̏؋��ɁA�y�b�g�V���b�v�ɍs���y�b�g��l�ԉ�����O�b�Y���Ƃ��닷���ƂȂ��ł���ł͂Ȃ��ł����B����Ȃ��Ƃ���A�y�b�g�Y�ƂƂ̓y�b�g�̋[�l���Y�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����肷��B�y�b�g�̈�Â��l�ԕ��݂�ڂ����č��x�����i��ł���_���炢���ċ[�l���Y�Ƃ̈��Ƃ��v����̂��B�����A�y�b�g�̋[�l���̂��������A�y�b�g���X���d���������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�t�L���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
|
|||||
�@ �@���̂悤�ɂЂƂ��炵�̐l���ꓪ�̌��Ȃǂ̃y�b�g�ƂƂ��ɉ߂����Ƒ��`�Ԃ����́A�u�ЂƂ�v���X�����Ƒ��v�ƌĂ�ł���(�����Ƃ����Ƃ���ɒ��ӂ��Ăق����I)�B����A��l�Z�܂��Ɍ��ꓪ�܂��́A�L�ꓪ�Ƃ����悤�ȉƑ��������Ă����̂��낤�B �@���āA�u���̉Ƃ́A�ꌢ�i�ڂ���j�ƒ�ł��v�Ƃ������N���C�G���g�������B���b���ڂ������������ƁA���̕��ɂ͂���l������̂����P�g���C�ʼn����ɂ���A���܂ɂ����A��Ȃ��Ƃ����B�q�ǂ��͂ӂ���̍��ӂō��Ȃ������B�����ꓪ�����Ă���A���̎q�Ƃӂ��肾���ł�����炵�Ă����Ƃ����B������A�ꌢ�i�ڂ���j�ƒ�Ȃ�ł��ƁB �@���̕��́A��������q�ƒ�����f�B�t�@�C���Ă����q�ׂ��̂����A�q�ǂ��̏��Ɍ������Ă���̂��A�������Ă���Ǝv�����B���̐l�ɂƂ��ẮA��͂茢�͂킪�q�Ȃ̂��B�����āA���������������ӂ���͌��������悤�ɂ��Đ��i���j��ł����B �@���̐l���A�킪�q�ł��鈤����S�������B�����ӂ��肾���Őe���Ȏ����߂����Ă����������A����������ɕ�e�̖ڂ̑O����p�������Ă��܂����B���̂��߁A���ꂩ��ǂ�����ĕ�炵�Ă䂯�悢�̂��A�����킩��Ȃ��Ȃ����E�E�E�B��ЂƂ�q�ЂƂ�̉ƒ�̎q�ǂ����e������Ɏ���ł��܂��B�ЂƂ��i�̂��j������e�̒Q���ƈ����݂��A���̐l�̃y�b�g���X�̌����B �@�ЂƂ�v���X�����Ƒ����ꌢ�ƒ���A���Ԃ͓����悤�Ȃ��́B�����āA���҂͂Ƃ��Ƀy�b�g���X���d������v��������͂��ł���B
|
|||||
�@�����A�킪���͏��Ƒ�����V���O�����̖����������Ȃ��疢�\�L�̒�����Љ�i�s���Ă���B����ȂȂ��ŁA�y�b�g�ƕ�炷���Ƃɂ���ăy�b�g����ȉƑ��ƂȂ�A�S�̋��菊�ƂȂ�ɂ�ăy�b�g�̎�������A�������悤�Ƃ���X�����܂��܂����܂��Ă���悤�Ɏv���B���̂��Ƃ́A���E�̂Ȃ��œ��{�l�̃y�b�g���X�������Ƃ���Ȃ��ƌ��������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B �@�y�b�g���X�ւ̑Ή���Ƃ��ĉ��Ăł́A������x���������Ȃ������a�@�J�E���Z���[�iVC�j��A�����a�@�\�[�V�������[�J�[�iVSW�j��A�y�b�g���X�J�E���Z���[�����X�ɑ����Ă��Ă���B �@�������A�킪���ɂ�����y�b�g���X�E�P�A�𒆐S�Ƃ���������ւ̎x���̐��́A�����W�ҁA���_�ی����ҁA�{�����e�B�A�����ƂƂ��ɖ����s�\���ƌ��킴��Ȃ��B���̂��Ƃ��A���{�l�̃y�b�g���X�������Ƃ���Ȃ��Ɗ뜜�� ����̗��R���B����̎�����]�܂��B
|
|||||
�@�����ł́A�y�b�g�ˑ��ɂ��čl���Ă݂����̂����A���̑O�ɂ��������ˑ��Ƃ͉����ɂ��ĐG��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�A�����J���_���͊w��ł́A�ˑ����u�[����K����ړI�Ƃ��đ��҂ɗ��낤�Ƃ���X���̂��Ɓv�i�A�����J���_���͊w�� ���_���͎��T�A�V�j�ЁA1995.�j�ƒ�`���Ă���B �@�������͏�ɂ��܂��܂ȗ~���������Đ����Ă���A�����������Ƃɂ���Ď�������܂����ɍ��킹�Ă������Ƃ��Ă���B���̗͂ɂȂ��Ă��ꂻ���Ȑl�������蕨������A����ɗ����Ă������Ƃ��ˑ��ł���Ƃ����B �@���̒�`�́u���ҁv�̂Ƃ�����u�y�b�g�v�ɒu��������A�y�b�g�ˑ��̒�`�Ƃ��Ēʗp���邾�낤�B���Ȃ킿�A�u�[����K����ړI�Ƃ��ăy�b�g�ɗ��낤�Ƃ���X���v�ł���B�������A�[����K����ړI�Ƀy�b�g�ɗ���Ƃ́A���������ǂ��������ƂȂ̂��낤�B �@��ʓI�ɂ̓y�b�g�Ɉˑ����Ă���l�Ƃ����A�u���͂��̎q�����Ȃ��ƃ_���v�Ƃ��u�y�b�g�����Ȃ��Ɩ���������Ȃ��v�Ȃǂƌ����������A�z���邾�낤�B�܂��A���̎q��������Α��ɂ͉�������Ȃ��ƐS�̒ꂩ��v���ăy�b�g�ƕ�炷���Ƃɍő�̉��l�����������A���̂��ƂɊS�������Ȃ��Ȃ��Ă���悤�Ȑl���C���[�W���邩������Ȃ��B���̂悤�Ȗʂ������ł���A�y�b�g�Ɉˑ����Ă���Ƃ݂Ă悢���낤�B �@�����A���E�ی��@�ցiWHO�j�͈ˑ��ǁi�ˑ��nj�Q�j���u���镨�����邢�͂����̕����g�p���A���̐l�ɂƂ��ĈȑO�ɂ͂��傫�ȉ��l�������Ă������̍s�����A�͂邩�ɗD�悷��悤�ɂȂ��Q�̐����I�A�s���I�A�F�m�I���ہv�iICD-10�j�Ɛ������Ă���B �@���̏ꍇ�A�u���镨�����邢�͂����̕����g�p�v�̕������A�u�y�b�g�i�Ƃ��邱�Ɓj�v�ɒ����āu�y�b�g�i�Ƃ��邱�Ɓj���A���̐l�ɂƂ��ĈȑO�ɂ͂��傫�ȉ��l�������Ă������̍s�����A�͂邩�ɗD�悷��悤�ɂȂ��Q�̐����I�A�s���I�A�F�m�I���ہv�Ƃ���A�y�b�g�ˑ��ǁi�y�b�g�ˑ��nj�Q���邢�́A�y�b�g�n�ȁi���ւ��j�j�̒�`�ɂ��Ȃ邾�낤�B �܂�A����܂Ŋy�����Ƃ��A����Ɗ����Ă������̂��Ƃ����A�y�b�g�̕����i�i�ɗD�悳���悤�ɂȂ����ꍇ�Ƃ������Ƃł���B �@�܂��A���̂Ƃ��ˑ��ǂ��Ƃ�����ɂ́A�����̍s������ɋ����I�ɂȂ���Ă���ꍇ�������B�����ł��������Ƃ́A�y�b�g�ˑ��ǂɊւ��Č����A�y�b�g����邳�܂��܂Ȑ��_���ʂ����Ƃ����~�������ɋ����A������~�߂悤�ɂ��~�߂��Ȃ��Ȃ��Ă�����A�y�b�g���������ɂ��Ȃ����Ƃɂ���Đ�����s�������a��������邽�߂Ƀy�b�g����ɋ߂��ɒu�����Ƃ���ؔ������v�l��s���������B �@���̂悤�ȋ����I�y�b�g����Ɋׂ��Ă��鎔����̑唼�́A�y�b�g�ƕ�炷���Ƃɖ���̊�тƖ��������������Ă��邪�A���̈���Ńy�b�g���V���邱�Ƃ�a�ނ��ƁA�����Đ��ɂ͎���ł��܂����Ƃւ̋������⊴�Ƌ��������Â��Ă���B�y�b�g�𗊂݂Ƃ��鎔����̐S����j�i�͂j�݁A�Ђ��Ă͏[����K���ւ̎��݂�W����ő�̌����́A�y�b�g�̘V�a�����B������A�y�b�g�̕ی���Â�t�[�h���͂��߂Ƃ���y�b�g�Y�Ƃ̑����́A�l����s�����ăy�b�g�̓V���ɍR�i���炪�j���Y�Ƃ��Ƃ����Ă��悢��������Ȃ��B
|
|||||
�@�ށE�ޏ���͎��Ă�͂�U�肵�ڂ��Ă�������Ǝv���̂����A�݂Ȉ�l�ɖڂɗ܂��ɂ��܂��Ȃ�����i����j�����ƁA�\���킯�Ȃ���\�����Ă����B �������v�����悤�ɉ^�����C�o���ɕ����������Ă��܂����̂́A�������O�ł��낤�B�܂��A���_����M���Ē��N�������Ă��ꂽ�Ƒ�����͂̐l�X�̊��҂ɓ������Ȃ��������Ƃ��v���Ζ{���ɂ��܂Ȃ��Ƃ����C�����������N���邾�낤�B �@�Ђǂ���������͕̂����������̐��i�̎�����Ƃ�����B�����Ƃ��A�I�����s�b�N�Ƃ������E�ő�̃X�|�[�c�̍ՓT�ɁA�����ł̂���ȋ��������������ďo�Ă��邮�炢�����畉���������������̂��̂ɈႢ�Ȃ��B �������������Ƃ������Ƃ́A�܂����i���j��ދC�����������Ƃ������Ƃ��B ���̉����������܂ł��c�����Ƃ����Ȃ�A����̔O���ЂƂ������낤�B �@�y�b�g��r�i�����ȁj�����قƂ�ǂ̐l�����x�̈Ⴂ�͂���A���������������ɂ���B�����܂́A������q��S�������߂��݂����ł͂Ȃ��A�����ɉ����܂��܂܂�Ă���B �@�y�b�g���X�Ƃ́A������Ƃ��Ă��̎q�̖����������Ȃ������Ƃ��������i��������j�̔O�ƁA�\���킯�Ȃ��i�߈����j���v�����薡��킳���̌��Ƃ����Ă����B���̉���݂́A���̎q������ł��܂������������ǂ͎����ɂ���ƍl���Ď�����ӂ߂�S���ł���A�����Ȃ���������p�ł�����B���̎q�͎��̂����ŋꂵ��Ŏ���ł��܂����̂�����A���̐ӂ߂R�̂��ƂƂ��ĕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B �@�܂��A�����₷�₷�Ɨ��������Č��C�ɂȂǂȂ��Ă͂����Ȃ��B���܂��͈ꐶ�ꂵ�܂Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����Ƃ�����B�����������ɗ^���钦���i���傤�j�|���炵�ߔ����邱�Ɓ|�ł���B�܂��A���̎��悭�N����̂��A���H��w�i�Ƃ����H�~�s�U���B���̎q�͋ꂵ��ʼn����H�ׂ��Ȃ������̂����炨�܂����H�ׂĂ͂����Ȃ��A���̎q�̂炳���������������ƍl���ĐH�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B �@�܂��A�����ӎ����ɒ[�ɂȂ莩�s�I�ɂȂ�l������B���̗�Ƃ��ĈȑO�A�J�E���Z�����O���������邲�w�l�̃P�[�X�������悤�B�ޏ��͈�����S���������A�y�b�g�̖����������������a�@�̏��u�ɔ��ɕ��S���Ă���A���̕a�@�Ƃ��̏b��t��I�������Ђǂ��ӂ߂Ă����B����Ȏ������ǂ����Ă��������Ƃ��ł����A�䏊�ɗ����ĕ����ɂ���������A����̎w�̈�{��藎�Ƃ��Ă��܂����B���̌�A�藎�Ƃ����w������������킹�ĕa�@�֍s���ڍ����Ă�������Ƃ����B �@�����܂ł̎����s�ׂ͋ɂ߂Ă܂ꂾ���A����͓{���G�ӂ�����������Ď���������ʂƂ����悤�B���̕��́A������I�X�g���X���Y�ɑς����Ȃ����߂ɋɒ[�Ƃ�������s�����Ƃ��Ă��܂����B �@�����������s��������܊��𖡂�����Ƃ��̊������┽���́A�Ώۂ��قȂ��Ă��Ă��ǂ������ʂ��镔��������悤���B�y�b�g���X���y�b�g��������l�����̓���ŕ������ȃG�s�\�[�h�Ƃ݂邱�Ƃ͊ȒP���B�����A�l���ɂ�����r���̌�����ܑ̌��̂ЂƂƂ��đ������������A�����ɂ͕��ՓI�ȍL����������Ď������ɖ₢�����Ă���d�v�ȃe�[�}������悤�Ɏv���B �@�I�����s�b�N�ɑ����ăp�������s�b�N���n�܂�B�Q���I��̒��ɂ́A���ďႪ���������ނ������A�傫�ȑr�������]���𖡂�����l������ɈႢ�Ȃ��B�������������Ƃ����z���ăA�X���[�g�Ƃ���簐i���Ă��邱�Ƃ��v���ƁA���̑I�肽���̎p�ɂǂ����_�X������������͎̂��������낤���B
|
|||||