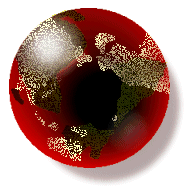 |
世界の終る夢 |
| ある日突然終る世界 辿り付く、還り付く場所。 何処に向かうかも、判らないけれど、 回帰する居場所程度なら、知っているから。 腕の1本、足の1本千切れても、 最期には必ず辿り付くから。 |
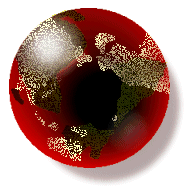 |
世界の終る夢 |
『もし明日、世界が終わるとしたら、貴方ならどうする?』 「って、何の事だにゃ?」 レギュラーだけが居残りで練習をしていた後。軽口を叩きながら部室に入った英二が、部室の机の上。ページが開かれたまま無造作に放り出されている雑誌を見咎め、不思議そうに首を傾げ、独語する。 部活に来た時には忙しくて、誰もが机の上に放置されている物になど気付きはしないから、それが一体いつから置かれていたのか、英二の記憶にはなかった。 開いたページで指で挟み、ヒックリ返して表紙を眺めれば、ソレは女性雑誌というより、若干若い、低年齢の女の子が読むに相応しい表紙をしていた。 |
| 「桃、お前の?」 いかにも、多感な時期の女子が好みそうな雑誌に、感銘を受ける筈もなく、英二は指で挟んだページを無造作に開くと、グルリと周囲を見渡し、奥で着替えよとしている桃城に逡巡なく、幾許の哄笑を滲ませ、問い掛けた。 「何でソレが俺のだと思うんです〜〜英二先輩」 躊躇いなく訊いて来ると言う事は、英二には自分はそういう風に見えているのかと、桃城はガクリと肩を落とした。 英二の科白に、隣に佇む頭一つは低い小柄な持ち主を窺えば、その視線を感じたのか、リョーマはチラリと桃城を見上げ、意味深に笑い、口を開いた。そのタチの悪い笑みに、桃城は大仰に溜め息を吐き出している。 「そりゃ桃先輩が、見掛けに反して手が早いタラシだから」 「そりゃ桃だから」 「越前、そのファンタ返せ」 予想どおりの小生意気なリョーマの科白に、半ば自棄で、呟くと、 「せこい男は、嫌われますよ、桃先輩」 嘘は言っていないと、リョーマはシレッと言い除ける。 その横で『どーせ俺は手ぇ早ぇよ』と、リョーマに抱け聞こえる小声で桃城は嘯いていた。 実際、その自覚は多大に有る桃城だったから、強い反駁など、できよう筈もない。 「俺が此処で返したら、慌てるくせに」 自分に甘い桃城の事をリョーマは良く判っている。返せと言われて本気で突き付ければ、動揺する事など手に取るように判る。いっそ突き付けてみようかと、悪戯心が湧く程だ。 近頃では『取りあえず付き合っている』と言う言葉の効力など、ゼロに等しい。下心なく大切甘やかされている心地好さを覚えてしまった今。そんな言葉は自分への言い訳にもならない。 「お前なぁ〜〜」 「ハイハイ、先輩です」 脱力する桃城の横で、リョーマは顔色を買えず、ファンタを飲んでいる。 「桃、憐れ……」 二人の見慣れてしまった日常光景に、英二はクツクツ笑って桃城を眺めた。 昨年は入学したてで自分に良く懐いていた後輩は、いつの間にか大切な人間を見付け、成長している。 気安い笑顔と開放的な雰囲気で、誰とも馴染むのが早い桃城は、けれど他人との境界線を明確に引くラインと言うものの在処をとても大切に心得ている人間だから、実際その本質的な部分に招き入れる人物の少なさも、英二は良く心得ていた。その桃城が、とても慎重にリョーマとの距離を図って、大切にしている事が可笑しかったと同時に、リョーマが入学するまでは、部内では自分が一番桃城と近しい距離に接していたから、英二は幾許の淋しさも覚えていた。 「英二先輩〜〜」 「ソレね、僕のだよ」 楽しんでる所悪いけどと、英二の背後で声を掛けたのは不二だった。 「不二〜〜〜?」 不二に女性雑誌。その取り合わせに、英二は眼を円くする。不二には歳の離れた美人の姉が在るが、姉の雑誌を不二が校内に持ち込むとは、到底思えなかった。まして、開いているページがページだ。到底不二の興味を引くとは思えない。 「アレ?英二知らなかった?教室で女子が何か面白がってたの」 集中する視線に、不二が莞爾と笑って口を開いた。 昼休み。噂好きな女子が数人集まり、雑誌を片手にキャアキャア騒いでいた所、女子から突然質問された不二は、そのまま女子から雑誌を貰ってきたらしい。 「っんで、それがどうしたんです?不二先輩」 手早く制服に着替えながら、シャツのボタンを嵌めつつ机に近寄り、桃城が英二の手元の雑誌に視線を落とし、 「なんか、いかにもって記事」 女子が読むものらしいと、苦笑する。 「世界の終わりに何をしてるか?」 喉が乾いていたのか、些か過剰な糖分摂取をした後、やはり手早く着替えたリョーマが、桃城の横で英二の手元の雑誌を覗き込んだ。 記事内容を声に出した半瞬後、その内容に、リョーマは呆れた表情を刻み付けた。 女性雑誌のアンケート欄の記事らしいそれは、恐怖の大王の降臨もなく、無事新世紀を迎えた現在では、多少遅すぎた質問内容にも思えたが、けれど多分女子に、そういうものは無関係なのだろう。女子はそういう内容が大好きだし、だから女性雑誌のアンケートから、この類いのものは消えないのかもしれない。けれど判る事と理解は程遠い。リョーマには、何故そんなアンケートがアンケートとして成り立っているのか、不思議でならなかった。 当然だろう。自分の足で歩く事を知っているリョーマにしてみれば、そんな内容は無駄に等しい事柄だったからだ。 「心理テスト、みたいなもの、だけれどね」 「んで不二は、女子に質問された訳だ」 訳知り顔で英二がウンウンと一人頷いている。 同級である不二と英二は、昼休みを一緒に過ごしている事が多かった。けれど今日に限って、英二は昼食後大石と会っていたから、不二は教室で一人読書に勤しんでいた。その時女子から声を掛けられたのだ。 テニス部員、或いはクラスでも余程近しい距離に居る者でない限り、不二の本質を知る物は少ない。だから試合最中、本気でその実力を発揮している不二ではない限り、教室では物腰柔らかい笑みを絶やさない彼は、周囲には恐れなど感じさせず、女子にとっては軽口に乗ってくれ、尚且つターゲットになりやすいNo1だった。 中等部新聞部のリサーチで、『彼氏にしたい人間』の五本の指に入っている常連者だ。 彼の本質を知るテニス部の面々曰く『知らないってのは、平和だ』と言う意見が一致している。 本気の不二は、誰より辛辣で容赦などない。瀟洒で鋭利な切っ先さながら、人を斬るタイプだ。彼が笑っているからと言って、決して内心笑っているのかは、計り知れない。けれどそんな不二の本質を知るのは、テニス部でも、極近しい人間だけに限られている。いるから、女子は臆面なく、質問できるのだ。 不二にしてみれば、別段普段なら興味を引くものではなかった筈が、不意にらしくない感傷さで、脳裏に手塚の事が過ぎったから、女子から口八丁で、雑誌を譲り受けてきたと言う顛末が付く。 それは手塚の留学話しが持ち上がっている事も、少なからずの影響はしているのかもしれない。 追い続け、共に歩く事はもう難しい事を、不二は正確に理解している。 「それで、不二は何て答えたんだ?」 突然、気配なく現れたのは乾だった。 話題に集中していたとはいえ、聡い面々に気配一つ感じさせず背後に近寄り、メガネ越しで笑みを漏らしている。 「乾……お前相変わらず、神出鬼没だにゃ……」 部室の扉をたった今開いて入って来た乾が、どうして自分達の会話を理解しているのか、考えればそれは乾だからの一言で集約されてしまうだろう科白に、英二は脱力していた。 科学と物理に精通しているとしか思えない、人間PC宛らのデータ収集、分析能力を誇っている乾の事だ。部室に盗聴器の一つや二つ、設置する事は簡単な事だろう。だろうと、ついつい誰もがそんな考えを脳裏に巡らせてしまう。 「ん〜〜僕としては、皆の答えが聴きたいけどね」 いつの間にか机の周囲に群がり、雑誌を眺めている面々を眺め、不二の視線がリョーマに向けられる。その視線を感じ、リョーマが半瞬嫌そうな表情を浮かべた。 何の事はない。不二は最初から、その目的で、口八丁で、女子から雑誌を貰ってきたと言う事だ。 「特に越前君」 「……何で俺なんスか?」 不二の指名に、リョーマは桃城の横で、途端憮然とした顔をする。 こういう時の不二のタチの悪さを、リョーマは嫌と言う程心得ている。此処で応える言葉一つ間違えれば、後々遊ばれてしまう事もよく理解していた。 「聴きたいから」 憮然とするリョーマに、けれど不二は莞爾と笑うだけだった。その様は、流石女子に彼氏にしたいと言わせしめる程度の物腰の柔らかさが備わってはいたが、それが外見上のものだと言う事も、リョーマはよくよく心得ていた。 一癖も二癖も有る個性の強いテニス部で、レギュラーを維持している面々の事だ。 外見と内面の違いなど当然の事だろう。まして不二はレギュラー選出以来、校内ランキング戦を勝ち続け、その位置を維持しているのだ。並の才能と努力と情熱ではない筈だ。 「俺もオチビの答え、聴きたいにゃ」 「だから、何で俺なんスか?」 憮然としたまま不二を見れば、やはり莞爾と笑っているだけに、タチが悪い。物腰の柔らかさがイコールで、性格が良いとは限らないのだ。 桃城との関係を、隠す術もなく簡単に見透かされている事を知らないリョーマではないから、タチの悪い先輩達が、どんな答えを要求しているのかも、判らない筈はない。けれど此処で遊ばれてしまう程、リョーマの性格もおとなしくはなかったから、隣でポリポリと蟀谷を掻き、他人事のような顔をしている。 蟀谷を掻いての他人顔など、不二の意図は桃城にも明確に判ってると言う事だから、リョーマに遠慮など微塵もなかった。 リョーマは酷薄な口唇に意味深な笑みを滲ませると、 「桃先輩は?」 尋ねた。 「ハッ?」 突然振られたリョーマの科白に、桃城は頭一つは低い位置に佇むリョーマに視線を向ければ、リョーマは意味深に笑っている。その笑みに、桃城は内心深々溜め息を吐き、ガクリと肩を落とした。 「そうだ、桃は?桃」 「ア〜〜俺は」 言い澱む。吐き出す言葉に逡巡を覗かせ、けれど視線は相変わらずリョーマに注がれたままだった。それが何より雄弁な答えだと、知らないのは多分当人だけだろう。 「桃はさ、明日世界が終わるとしたら、どうする?」 リョーマと良く似たタチの悪い笑みを浮かべている不二の質問に、桃城は大仰な溜め息を吐き出すと、 「俺は、多分何も変らないと思いますけど」 サラリと、笑った。 「何だそりゃ?」 「ん〜〜桃らしいって言えば、桃らしいね。青学一の、曲者」 不服そうな英二の声と、冷静に笑った不二の声が、同時に上がる。そして改めて視線がリョーマに注がれた。その視線を受け、やはりリョーマは小生意気に笑っている。 「俺も変らないスね。明日どうにかなるって言われても、どうにもならないし。個人で出来る事なら最善尽くすって手も有るけど、国家規模や世界規模じゃ、個人規模の最後の享楽愉しむ程度しか、出来る事なんて、ないっスね」 「オチビ〜〜冷静すぎるってのも考えもんだよ。普通さ、好きな人と一緒に居たいとか、せめてどうにもならないなら、一緒に最後とか、言うもんじゃん」 冷静すぎるリョーマの受け流しに、英二は複雑な顔をする。 小生意気すぎる後輩は、見ていて痛々しい程端然としている。その高潔さに、時折憐れが湧く程だ。そのくせに、失えない存在の在処など知っているのだろうと思えば、桃城も随分厄介な相手に惚れたものだと、思わずにはいられなかった。けれどリョーマはそんな英二の内心など素知らぬ顔で、笑った。 「って、菊丸先輩は思ったんですね」 ラヴラヴと、抑揚を欠いた一本調子の声で笑われ、英二は理不尽に憮然となる。リョーマの横で、オイオイと窘めているのは桃城だったが、当然、リョーマに効力などある筈もない。ないから、半瞬だけ意味深に笑った後、 「サイテーで人でなしの悪党だけど、俺が居ないと冷静じゃなくなるバカが居るから、最後の最後には、辿り付いて上げようかなって事くらいは、思ってますよ」 やはりシレッと言いのけた。 そんなリョーマの姿に、菊丸の負けだなと、クツクツ笑ったのは乾で、桃城は少しだけ複雑そうな表情をして、綺麗な横顔を眺めていた。そして被害を被るまいと、最後まで会話に加わらなかったのは海堂だったから、賢い選択肢と言えるのかもしれない。 「んで、お前、実際の所は、どうなんだよ」 「って何が?」 空色の双瞳が、キョトンと桃城を見上げた。その無防備さに、これは本当に質問の意味を理解していないと、桃城は苦笑する。 帰宅途中。リョーマの父親に夕食に突き合わされ、結局済し崩しに外泊になってしまった桃城は、夕食後リョーマの部屋で寛いでいる。 飄々とした掴み所のない南次郎は、冷静な洞察力で、リョーマと桃城の関係を早い時期から見透かしていた。それでも反対しないのだから、桃城にとっては益々掴み所などない性格で、仮にも恋人と呼ばれる後輩の父親だ。内心穏やかである筈もなかったが、それもいつか慣れてしまったから、人間は慣れの動物だと、一種冷静に考える余裕も近頃では有った。 『人間、開き直りが肝心だ』 桃城が身に刻んだ教訓の一つだ。 そして南次郎は、南次郎で、桃城を気に入っていた。 未だ現役で青学テニス部の顧問をしている竜崎スミレから、曲者と呼ばれていた南次郎だ。手塚から曲者と呼ばれてしまっている桃城の本質など、早期に見透かしていたのだろう。 でなければ、リョーマに近付けはしなかっただろうし、そういう関係だと判った時点で、切り離し計画をしてのけただろう。 「不二先輩の質問」 「アア」 質問の意図が判ったのか、リョーマはフローリングの床に座り込み、愛猫と戯れている桃城に、ベッドの上から横着に視線を投げた。 ベッドの端に背を持たれている桃城は、リョーマからは背中しか見えない。けれど愛猫の甘えた鳴き声と、時折見え隠れするご機嫌状態に揺れる尻尾を見れば、カルピンが桃城にひどく懐き甘えている事は容易に知れた。 愛猫は、桃城にだけは懐いている。家族以外の手には懐かない部分のあったカルピンが、桃城の手に抱かれて帰宅した時は、心底驚いた程だ。そんな愛猫の姿に、南次郎には『ペットは買い主に似るって言うが、本当、お前とそっくりだな』と笑われる始末だ。 後を追ってきたのだろう愛猫を、校内で見掛けた時は言葉を失った。授業中で教室を飛び出す事もできず、それでも愛猫を見間違える筈もなく、部活を放り出し一時帰宅をしてみれば、案の定の行方不明で、アノ時どれ程捜したか判りはしない。 だからその愛猫が、桃城の腕に抱かれて帰宅した時は、本当に驚いたのだ。 以来、カルピンは桃城にだけは懐いて抱かれているし、彼が遊びにくれば、膝の上は指定席だと思っているのか、即座に纏い付く始末だ。それが少々面白くはないが、ネコに嫉妬する程リョーマはバカではなかったし、矮小でも狭量でもなかったから、ベッドの上に寝転がり、雑誌を読んでいる。 「桃先輩は?」 「お前と同じだろ。世界の終りなんて個人規模でどうこうなんてねぇだろ。だったら個人の享楽、未練ねぇように、し尽くすな」 「それで、わざわざ何で訊くの?」 ベッドに寄り掛かる姿勢で背を向けている桃城の首に、背後から長く細い腕を伸ばすと、リョーマはクスリと笑った。 「お前のその、享楽、楽しむって所」 回ってきた腕を引き寄せると、力一つ入っていない腕が絡んでくる。背後で、意味深な笑みが漏れ聞こえてくるのに、桃城も穏やかな笑みを見せている。そんな二人に、何か察する部分もあるのだろうカルピンは、桃城の膝の上で尻尾をユラユラ揺らし、リョーマと良く似た蒼色の瞳で、二人を見上げている。 「テニス」 「言うと思ったぜ」 端然と即答するリョーマに、桃城は溜め息を吐いた。 「大丈夫」 大仰な溜め息を吐く桃城に、リョーマは身を擦り寄せるように近付くと、コトンと小作りな頭を、幅広い肩口に埋め、やはり笑っている。 「大丈夫だよ」 吐息で囁く程に潜められた声は、桃城に情事の最中のリョーマを思い出させた。 「何だよ?」 肩にコトンと擬音を付け埋められた小作りな頭を、ポンっと撫でてやる。 「最後には、ちゃんと辿り着くから」 「越前?」 情事の最中を連想させる吐息で囁く声は、けれど瞬時にそれは色を変え、何処か切なげなものが見え隠れする。 「俺言ったじゃん。『サイテーで人でなしの悪党だけど、俺が居ないと冷静じゃなくなるバカが居るから、最後の最後には、辿り付いて上げようかなって事くらいは、思う』って」 「サイテーで悪党で人でなしかよ」 リョーマの科白に、けれど桃城は何処か倖せそうにクツクツと笑っているだけだった。 リョーマのその悪態めいた科白も、もう聞き慣れた言葉しかないから、今更だ。英二には『憐れ』と言われてしまう関係も、そんな小生意気な態度と軽口は、リョーマは桃城にしか叩かない。それは精神的距離の近さを綺麗に顕しているカタチだから、誰かにその立場を譲つもりはなかった。自分がリョーマを傷つけてしまう存在ではない限り。 「あんた、俺に関しては、滅茶冷静になりすぎる程になって、感情失くしちゃうか、俺の事探し回るか、どっちかでしょ?」 それでも、きっと、そういう自覚はないのかもしれない。 呆れる程大切にされ、甘やかされている自覚はリョーマにも有る。 英二が『憐れ』と親しみやすい哄笑さで笑った科白も、それはそのまま、桃城の図る距離を現している。明確に引かれていた筈のラインは、此処最近不明瞭になる一方な気がしてならない。それでも、だからこそ、桃城は意識して明確にラインを引こうと慎重になっているのが、リョーマにも判っていた。 互いの内界に存在する境界線を弁えている桃城の慎重さ。 土足で踏み込んで来ないソレは呆れる程で、時には苛立ちの対象にさえなっている事を、桃城は知らないのだろう。 亜久津に疵を負わされた時の事を考えれば、自分に何かあった場合。冷静すぎる冷静さで、桃城は相手を許さないだろう。現実、そう言われたのだから。 冷静すぎる冷静さで、告げられた言葉があった。それでも、腹の奥底に鋭利な切っ先を潜ませていた事を、リョーマは容易に感じ取った。アノ時、理解していたのかもしれない。 大切と言う言葉が生温い程、大切にされている。そのくせに、決して最後の最後には甘えさせはくれない男だ。 だから最後にはちゃんと辿り着かなくてはならないと、痛烈にそう思う。 最後の最期には辿り着いて…。 「そんなバカ遺いて、たとえ世界が終わっちゃっても、勝手に死んでらんないし」 ちゃんと辿り着いて…。 「バーカ、お前はおとなしく待ってろ」 リョーマらしい小生意気な科白。けれどその奥底に、不思議と本音が垣間見える気がして、桃城は深い微苦笑を滲ませる。 「お前に何かあったら、捜し回るのが俺だってんなら、お前はおとなしく待ってろ。じゃなかったら、すれ違っちまうだろ」 「ヤダ」 「お前なぁ〜〜」 「あんたこそ待ってればいいの。ちゃんと辿り着いてあげるから」 「ダメダメ。そんな時はせめて俺に華を持たせて、『待ってるから迎えに来て』くらい言え」 軽口を叩くと、ゴメンなと、膝の上に在るリョーマと何処に似た印象を受けるネコを脇に置き、桃城は態勢を入れ替えた。 フローリングの床の上に跪く格好で、桃城は上半身だけリョーマの上に覆い被さっている。 吐息が触れ合う程間近に有る造作に、桃城は改めてその造作が繊細に縁取られている事を思い知る。 リョーマのルーツを正確に辿る蒼の瞳。日常では小生意気な科白に、冷ややかな熱を灯す切っ先さながらのその双眸の所為で、彼の華奢な姿態が脆弱に映る事はないが、組み敷く都度、その細さを実感する。 綺麗で繊細な造作。細い首筋。薄い肩。美少年と言うより、未成熟で発達途上の躯は、ボーイッシュな女の子にさえ見える。けれどそれらが決して脆弱に映らない、意思の強い冷ややかな双眸だ。それがとても好きだと、思い知る。だから最後が来るのなら、最後までその視線を閉ざさず、見ていたいと願う。 綺麗なフォームで繰り出される、鋭利な白い軌道の行方。 リョーマを一番綺麗に見せるのは、疑いようもなくテニスをしている時だから、最後が訪れるのなら、テニスをしているリョーマを見ていたいと思う。 「お前さ、俺に会って、テニスするのか?」 「テニスは、一人じゃできないよ」 吐息で囁き笑うかのような声。 リョーマは真上から覗き込まれる造作に細い腕を伸ばすと、桃城の精悍な造作を包み込んだ。 「回避出来ない状況で追及する享楽がテニスってのは、お前らしいな」 どれ程の情熱と努力が、リョーマをソコに立たせているのだろうか?組み敷くこの細身の躯の何処に、どれ程の情熱が隠されているのだろう? 鮮やかなステップと、鋭利なスマッシュ。熱を灯しながら、冴える月のように、冷ややかな凛然さを刻み付けて行く双眸の強さ。どれ程の強さがあれば、躊躇なく佇む事ができるだろう?考えても、決して推し量れる筈はない。父親の名に押し潰されないその強さは、どれ程のものを傾ければ、得る事ができたのだろうか? 生まれ乍らの資質や才能すら、当人の努力なくしては原石で終わる。だったなら、リョーマはどれ程の情熱を掲げて来ただろうか?無責任な称賛や羨望に曝されて尚。崩れない強さは、一体どれ程のものを、この小さい身の裡に孕んでいるのだろうか?考えてみた所で、判り得る筈もない。 察する理解が答えではないと知る桃城は、だから隣に立つ事はなく、半歩下がって、リョーマの佇む視界の先が見たいと願った。それは決して感傷ではなく、これから先もリョーマと在る為に、自らの為に選んだ事だ。 所詮ヒトは自分の為にしか生きられないと、知っている。 だからこそ、下らない綺麗事を言うつもりはなかった。 「死ぬ気で限界までテニスして、最後の最期には、姦り殺されても構わないって思うんだけどね」 最後の最後には、ちゃんと辿りついて。 そんな夢のような事が適うなら、それはそれで、とても倖せな事に思える。 死ぬ最期の一瞬までテニスをして、享楽を追及できる状況は、そう多い機会ではないだろう。そう思うのだから、自分は父親や桃城も責められない、テニス莫迦なのだろう。 「姦り殺されても、ね」 「俺達が、今知る必要のない言葉は『限界』でしょ?」 以前桃城に言われた科白で、南次郎に言わせれば、大概桃城に甘やかされている。そういう事になるらしい。その南次郎の言葉の意味は、けれどリョーマには判らない部分が殆どだった。 甘やかされている事は判っていても、その科白から南次郎が何を感じたのかまで、リョーマには判らない。それでも、二人の爛れた関係を知って尚。止めない南次郎の事だから、何か思う部分も有るのだろう。 「お前、著しく、意味が違うぞ」 クツクツ苦笑する。 「でもまぁ、それもいいかもな」 結局、自分達が考えていた事など、可笑しい程何一つ違わないのだから、桃城としては苦笑するしかなかった。所詮テニス莫迦、そういう事だろう。 大切にしてもしたりない存在は、裏を返せば、失いたくない存在を、いつか失う可能性の在処にも気付いてしまう事と同義語だったから、終わる世界なら、遺こされてしまう事もないだろう。 会話をするようにテニスをして、互いの鼓動を何より近くに感じて。万が一にも世界の終わりが訪れても、そんなラストなら、悪くない人生だったと笑えるだろう。 「でもそうしたら、俺本気でするから、テニスで死ぬかもね、桃先輩」 「まったく生意気だな」 「だって桃先輩は、そー言う俺が、好きでしょ?」 大切にされ甘やかされ溺れきって、その心地好さに自我まで手放してしまう自分など、リョーマには到底想像できる筈もなかった。 望むのは、対等な位置。年齢や何かを差し引いて、守られるだけでも、甘やかされているだけでもなく、望む物はそういうもので、多分そういう眼には見えないカタチなのだ。 けれど、その一方で、決して追いつけない1歳の差と言うものも、自覚している。 「もし、万が一にも終わる世界なんて来たら、限界までテニスして、限界まで桃先輩と居てあげる」 桃城の精悍な面差しを包む細い指先が首筋に回る。ソレはゆっくり色香が灯るように、緩やかな動きを辿っている。 「だったら、やっぱお前は、此処でおとなしく待ってるんだな。此処じゃなきゃ、コートなんてねぇんだから」 背筋に回った指先に灯った気配に、桃城は苦笑を刻み付ける。脆弱に映る事がないだけで、細い姿態なのには間違えがないリョーマは、けれどその内側に雄を受け入れ、のたうつ快楽の淵というものを知っている。 幼いと言える肉体を、慣らしたのが自分だと思えば、一瞬の罪悪と後ろめたさを拭いきれない。けれど手放す気も、失う気もないのだから、そんな感情すら傲慢なものだと桃城は自覚している。 第一、そんな感情のままリョーマに触れても、彼は桃城の機微には敏感だから、すぐに気付かれ、足蹴にされてしまう事は間違いがないだろう。 「イヤだ」 「お前、何で拘るよ」 「桃先輩こそ」 「年上の恋人としては、そりゃ当然の権利だろ」 「何ソレ」 何が権利で、年上と言う言葉が意味を成すのか、甚だリョーマには判らなかった。 「一つしか違わないくせに」 永遠に追いつけない1歳の差。それに時折無性に苛立ちを覚えさせられはするけれど。 「それでも、立派に年上だ」 「俺がね、迎えに行きたいって、それだけ」 迎えに行きたいと言う言葉にも、多分語弊が有るのだろう。可笑しい程、テニスに回帰されるというのに、最後の最後。辿り着きたい場所は桃城なのだから、始末に悪い。 呈示されている居場所なのだと、こんな些細な、有る筈もない夢物語りで、気付かされて行く。 誰かに感情を預けてしまうなど、恋愛は何処か殺人行為に似ていると思ってきた。それなのに、包まれる安堵と言うものを知ってしまった今。それを手放せない自分が在るのだから、これは成長と言うものなのか?リョーマには判らなかった。 「あんた本当に、莫迦だから」 気付かないだろう、桃城は。辿り着きたいと願う場所が在るのなら、待っている事などできない願いの在処と言うものを。 桃城の吐息を首筋に感じ、気付かなくともいいと、リョーマは思う。 世界の終わる夢、それは夢物語だ。 万が一にもそんな刻が訪れたら、 「ちゃんと、辿り着くから」 最後の最後くらいは、ちゃんと辿り着くから。 「お前、今夜はえらく感傷的だな」 フト不安になる。リョーマが感傷的になる事など、滅多にある事ではなかったからだ。 埋めた場所から顔をあげると、桃城は息を飲んだ。 桃城の眼前で、リョーマは柔らかいばかりの笑みを滲ませている。その笑みの意味など、当然桃城に判る筈もなかった。 「別に」 「そうか?」 多分リョーマ自身にも、言語に置き換えて理解する程、明確なものは判らないだろう。 「あんま煩いと、迎えに行かないスよ」 「だから俺が来るから、お前は待ってろって行ってるだろ?」 堂々巡りの会話。それさえ倖せなのだから、大概終わっていると、思わずにはいられない桃城だった。 「でも、世界が終わるなんて、夢物語だから。この際、目先の享楽追及しないと、損っスよ、桃先輩」 「お前な…」 大仰に溜め息を吐くと、桃城は、それもそうかと、本格的にリョーマを貪るべく、姿態をあわせていった。 ちゃんと、必ず、辿り着くから。 最後の最後には、ちゃんと辿り着くから。 待っていて。 |
| オマケ其の1 |
| オマケ其の2 |
| back |