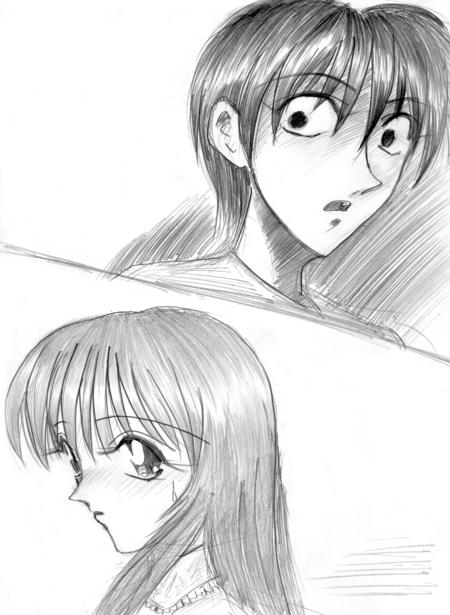
午後の恋人たち
Ⅳ 木曜日はドレスアップで
深澄音玲奈の通っている学校は非常に長い歴史を有している、いわゆる名門である。バブル期に調子に乗って校舎を移転したりなどと愚かしい真似もせず、学費も私立校としては比較的安く押さえられている。従って、校舎は非常に古臭い物だった。柱も壁も非常に頑健で、誉めようとすれば重厚だが要は陰鬱で威圧的な印象を与える。更についこのほど一般教室に冷房が導入されて、卒業生がうらやましがっている、そんな学校だ。
図書館もその例に漏れない。と言うより、この学校で最も暗い印象を与えるのがそこなのだ。何しろ直射日光は書物の大敵、元々窓が小さく作られている。机が置かれている区画には十分な照明があるものの、書架の方は何か妖怪でも出そうだとまことしやかにささやかれている程だ。しかし、玲奈はこの空間が好きだった。元々本は好きだし、このような所に住み付く妖怪ならいっそ会ってみたい。多分本好きの、内気な妖怪だろうと思うのだ。
ただしかし今日の彼女は意中の本を見つけるでもなく、なんとなく面白そうな物を探すでもなく少々狭い棚の間を歩いていた。本来かなり広いスペースを有する建物なのだが、それを上回って蔵書が多い。彼女はその背表紙にも目をくれようとしない。
「どうしようかな…」
そんな事をつぶやいてゆっくりと進んで行く。この場合、彼女にとっては人のいないところで歩く所に意味があったのだ。人がいるとうるさくて自分の考えに集中できないし、かといって座るなどして止まって考えていても今のところ良い思案が浮かばなかった。
「深澄音先輩…?」
いくらなんでも怪しい彼女の挙動に、一人の生徒が目を止めた。しかし玲奈は考えに没入してしまっているので全くこれに気がつかない。見咎めた生徒は少し声を大きくしようとしたが、ここが図書館であることを考えてそれは止めにした。代わりに近づいて行って声をかける。相手の歩みはごく遅いからすぐに追いついた。
「先輩」
やはり無反応だ。仕方なく、彼は彼女の細い肩を叩いた。
「先輩、どうしましたか?」
「あっ…」
小さくであったが、彼女は確かに飛びあがった。そして慌てて振り向く。
「り…涼馬さんでしたか。びっくりしました」
白い手が胸のあたりに置かれている。涼馬と呼ばれた少年は頭を下げた。そうしても視点がまだ玲奈より高い。
「済みません。そんなつもりは無かったのですが、二回呼んでも気がつかないものですから…」
「あ、そうでしたか。気がつかなかった私が悪いんです。気にしないで下さい」
玲奈も頭を下げ、それから見上げる形となった。背の高い少年だ。
澤守涼馬。玲奈より一級下の二年生で、現在は生徒会長を務めている。そこまでならこの学校の人間であれば誰でも知っている、学校一の有名人である。ここの校風はリベラルで、生徒会の影響力が大きいためでもあるが、特に涼馬個人に関しても色々と風評があるのだ。成績は学年トップ、スポーツも万能で生徒会活動に従事していてなお様々な部から声がかかるほど。家庭環境は両親ともに大学教授をしていて兄は世界的に有名なバイオリニストだと言う。ここ二十年で最も会長にふさわしい逸材とされていた。もっとも、この少年が有名な最大の理由は下手な美少年タレントでは比較にならないほどの美貌で、全学年の女子から圧倒的な支持を集めている。
ただ、玲奈の場合去年は二年生代表として生徒会の副会長を務めており、涼馬は一年生代表の副会長であったため他の生徒よりは深い面識があるのだ。
「ええ。しかし何か心配事ですか」
涼馬はそれこそ心配そうに聞いてきた。自分の成績や能力を鼻にかけたりしない、誰にでも優しい少年だ。
「え…そんなふうに見えましたか」
「ええまあ。普通の様子には見えませんよ」
「そうですね…」
指摘されてみれば確かに妙だ。昭博のことばかり考えている時には気付きもしなかったが。涼馬は微笑んで言った。
「差し出がましいかもしれませんが、僕でよろしければ相談に乗りますよ。深澄音先輩にはずいぶんとお世話になりましたし」
「お世話と言うほどのことはしていませんが…そうですね。お言葉に甘えましょうか。丁度同い年ですし」
「は?」
「あ、済みません。今お話しますね」
玲奈は事の顛末や、医師から聞いたことをかいつまんで話した。こういうところの要領は決して悪くない。話を聞いた涼馬は、考えをまとめるのにそう長い時間をかけなかった。
「そうですね、それなら音楽がいいと思います。リラクゼーションの効果があるそうですから。明日穏やかな曲調のCDを何か選んで持ってきましょう」
「できれば今日が良いのですけれど…」
「それでは…そうだ。この図書館でもCDの貸し出しをしていますから、探してみましょう」
自分のことのように張りきって涼馬はCDのコーナーへと歩いて行く。
「すみません、わざわざ」
「いえ、いいんですよ。僕はまだ受験生ではありませんし、今日はただ面白い本でもないかと思って来ただけですから」
そう言って笑ってから、涼馬は早速CDの物色を始めた。手にとっては元に戻す、を繰り返している。心当たりが多すぎて却って困るらしい。真剣に悩んでいた。
玲奈はその横顔を見ながらふと考えに入った。あまり誰と誰がくっついただとか、あるいはあのクラスのあの人が恰好いいだなどの話題にはあまり興味のない彼女であったが、しかし知り合いということもあってこの少年がこの学内で最も女子からの人気を集めていることくらいは知っている。
確かに成績は文句のつけようがないほど良い。運動もできる。顔立ちも綺麗だし、背が高くて足も長い。何より真面目で優しい。玲奈もそれは分かる。誰からも好かれる人間だ。ただしかし、女の子達が彼の姿を見かけるたびにきゃあきゃあと騒いだり、話したことも無いのにラブレターが届くように手配するのはなにか違うと思うのだ。人を好きになるとはそんな事なのだろうか…。
「先輩、深澄音先輩」
また肩を叩かれて、玲奈は我に返った。涼馬が苦笑する。
「またなにか考え事ですか。先輩は考えに入ると周りが見えなくなるから」
「済みません…」
「それが先輩の持ち味ですから。それで、CDですけれどこれはどうでしょう。作曲家も演奏家もあまり有名ではないのですが、その相性が良いらしいですね」
涼馬が取り出したCDは、多少クラシックを聞く玲奈にもなじみの無いヴァイオリンソロだった。
「そうですね。涼馬さんがそう言うのなら、これにしてみることにします」
「いや…これは兄がここに寄贈した物です。正直な所僕は聞いたことがありません。兄がこれは心が安らぐと言っているのを覚えていただけです。しかし音楽に関しては兄の方が信頼できるでしょうから。音楽に限らず芸術は人間の主観による部分が大きいから、人に薦める時には余程注意するか適当にしてしまえ、というのがそれこそ兄の受け売りなのですが」
苦笑しながらの説明だった。
「なるほど…。じゃあ、私も何か好きな物を探して持って行くことにしますね」
「ええ、それが良いでしょう」
結局玲奈は自分の趣味でもう一枚を選んで、貸し出し手続きを済ませた。その頃にはもう昼休みが終わりかけている。それですぐに二人とも図書館を出た。
「今日はわざわざ有難うございました」
「いえ、どう致しまして。それでは僕はこれで」
さわやかに笑って、涼馬は二年生の教室の有る方向へ歩いていった。その背中を見ながら、玲奈はもう一度どうして彼に恋心を抱く女子生徒が多いのかを考えた。それから逆に、何故自分が彼を好きにならないのかについても考えてみた。しかし結局、回答らしいものが見当たらぬまま彼女も自分の教室に戻った。
四度目ともなると昭博の家も見慣れた気がする。玲奈は右手が鞄でふさがっているので左手でインターホンを押した。
「今出る」
すぐさま昭博の不機嫌そうな声がした。もっともこの少年の場合普段からそう聞こえるだけで、実際に不機嫌ならもっととげとげしくなる。だから安心して、玲奈は待っていた。
「こんにちは、昭博さん」
扉が開く前から玲奈は自然と笑顔になっていた。そのまま昼の挨拶をする。そうしていつもの昭博の顔を見て、玲奈は学校で考え続けていたことの答えを見つけたような気がした。
「…………」
浸っている玲奈を前に、昭博はそう長いことではなくとも確かに無言だった。まじまじと彼女を見つめている。これでは玲奈で無くとも不安になるところだ。
「あ、あのう…どうしましたか」
「え? ああ、いや、何でもない。上がりなよ」
ふいっと顔を背けて、昭博は中に入っていった。不審さを抱えたまま、玲奈がそれに続いて行くことになる。
「あのさ…」
「はい」
「君、普段はそう言う格好なんだ」
昭博は何故か振り向かずに聞いた。玲奈は少し身を固くして答える。
「ええ、そうですよ」
「ふうん…」
妙な応対のまま、二人はいつもの居間に入った。そしてソファーにつく。そうすると嫌でも昭博の目に玲奈の姿が飛び込んでくるのだった。
「…うん、今日のほうが似合うよ」
玄関から居間までためらっていたのであろうが、昭博はようやくそう言った。
ピンクを基調として襟や袖口などに白を配し、さりげなくリボンとレースを飾ったワンピース。スカート部は少し長めで、フレアになっている。足元はワンピースのアクセントに合わせた白い短いソックスで、上がるまでは明るい茶の革靴でまとめていた。それが今日の玲奈の服装だった。ヘアスタイルは美しく長い髪の魅力を生かしてそのまま流している。それから、白い肩掛けの鞄を手に下げていた。
十八歳という彼女の年齢を考えれば少々可愛らし過ぎるかもしれない。しかし彼女の雰囲気と合っているのか、この格好は現実離れしているほど似合っていて、綺麗だった。口の達者でかつ極めて悪い昭博がまずその姿を見て黙り込み、そして今も賞賛しかできない。
「あ…ありがとうございます」
貴重な賛辞を受けて、玲奈は顔を輝かせた。それでまた昭博がどきりとしてしまう。ほとんど必殺技である。
実はこの時、玲奈は安堵してもいた。罪の無いものではあるが、先程嘘をついたのである。普段着、とは言い切れない。確かに彼女はこの種のワンピースなど可愛らしい類の服を好むが、これは一番のお気に入り、つまりとっておきだ。普段から着る物ではないのである。これを見て昭博がどう反応するか、玲奈としてはかなり気がかりだったのだが、結果は大成功と言って良いだろう。その意味での安堵もあった。
そして…二人とも黙ってしまった。玲奈は誉められた台詞の反芻を頭の中で始めてしまっているのだから仕方がない。そして昭博は人を誉めることがあまりない困った人間なので、慣れない事をして後が続かなかった。何を言おうかとかなり真剣に悩んでしまう。
ようやく事態が進展したのは、玲奈が現実世界に戻って来た後である。
「それで昭博さん、今日はCDを持ってきたんですよ」
「ん、CD?」
「はい、怪我の療養には音楽がいいかと思って」
そう言いながら玲奈は鞄からCDケースを三つ取り出した。一つは澤守に薦められた物、もう一つはそこで玲奈が借り出した物、それから自宅から持ってきた一番気に入っている一枚である。ヴァイオリンソロ、オーケストラ、そしてソプラノ歌手の曲集の取り合わせであったが、少なくとも全てクラシックである。
「ほお…高尚だね」
とりあえずクラシックは聞かない昭博はジャケットを見てまずそう言った。それからソファーの背もたれに体重を預ける。
「しかし別にそんな物持ってこなくても、順調に治ってきているぞ。そんなにやわじゃないんだから」
「いえ、昭博さんには早く良くなってもらわないと」
「まあそうか。あんまり俺にかかずらわっている訳にも行かないもんな」
別に何を意図してもいない台詞であったが、玲奈はほとんど泣きそうになった。確かに、否定的な見方をすれば早く縁を切りたいがための行動と取れないこともない。
「そんな、私は…」
悪意を持って放った台詞ならこれでも動じなかったであろうが、そのような意図が無かっただけに昭博も少々慌てた。
「あー、悪かった。それじゃあ早速聞くとしようぜ。とりあえず飲み物でも用意するから」
逃げるように立ちあがる。それで玲奈も機嫌を直した。
「はい、それでプレーヤーはどこですか」
きょろきょろと居間を見渡してみる。しかし機械物はテレビとその下にビデオデッキ、そして強いて言うなら電話があるくらいで、スピーカーも何も見当たらない。これでこの家にプレーヤーがないととでもなったら大笑いである。
「普通居間にプレーヤーは無いと思う」
台所で苦笑しながら、昭博はこう言った。
「そうでしょうか」
玲奈が真っ向から反論する。
「だって居間で音楽なんて聞くものじゃないだろう。うるさがられるだけだ」
「うるさがられるって、それは音楽ですから音は出ますよ」
「……」
「……」
二人とも妙な認識のずれに首を傾げた。やがて昭博がぽんと手を叩く。
「もしかしてさ、君が言っているプレーヤーって、こういうでかい奴?」
昭博はかなり大袈裟に手を回した。しかし玲奈はそのままうなずく。
「そうですよ。プレーヤーって、そう言う物でしょう。ポータブルの物でなければ」
玲奈が考えているのが本格的なコンポであることを昭博は了解した。彼が今までイメージしていたのは、彼の部屋に有るミニコンポである。
「金持ちだな…」
かなり偏見に満ちた感想が口をついて出た。実際全く無関係とは言いがたいが、居間にコンポがあるかどうかは基本的に家族全体として音楽を聴く趣味があるかどうかの問題である。玲奈の家は両親とも音楽をたしなむが昭博の家でCDを買う、借りるなどしてまで音楽を聴くのは昭博だけ、その違いだった。
「そうでしょうか」
「うちの親はCDなんて聞かないもの。だから俺の部屋にミニコンポがあるだけだよ、この家は」
「なるほど、そうですか。それでは昭博さんのお部屋に行きましょうね」
「ああ」
午前中に近所のスーパーで買ってきたオレンジジュースをコップに注ぎながら、昭博は何気なく答えた。コップがそれ意外に形容しようの無い、オレンジ色で満たされて行く…。
「…あ?」
不意にその手が固まった。
「昭博さん、コップ、コップ!」
こぼれそうなジュースを見て玲奈が慌てる。昭博もすぐに我に帰って瓶を縦にした。
「とっとっと」
気がつくともう、表面張力の見本のような状態になっている。少しでも遅ければこぼれていた所だ。今日はせっかくちょっと気合を入れて100パーセントの物を買ってきたのだから、かなりもったいない。
「昭博さん、私がやりましょうか」
「いいって、いいってば!」
腰を浮かしかける玲奈を、昭博が慌てて制した。行儀悪く置いたままのコップに口をつけて量を減らしてから、もう一つのコップにジュースを注いで行く。しかしそうしながらも、彼の頭の中は危険な発想で一杯になっていた。さっきのコップの比ではない。
昭博の部屋とは言うまでもなく彼の勉強部屋兼寝室である。そこに行くのだ。玲奈と二人で。しかもこの家には今日他の誰かが来る当ては全くない。しつこくなるが敢えて要約すると、寝室で邪魔者も無く二人きりになる。それを自ら進んで言うなど、もしかしたら…。
「昭博さん…入ってませんよ」
「あ…?」
気がつくとさっきと全く同じ角度で瓶を傾けている。量が減っているのだから、もっと傾けないと中身がコップに注がれないに決まっているではないか。
「あ。あははははは。あはははははは…」
一種異様な笑いを見せながら、昭博は何事もなかったようにジュースを注ぎ終えた。
「何か心配事ですか」
「いや、なんでもないよ、うん」
現実主義者を自認する昭博は自分の妄想をさっさと打ち消した。玲奈がそのような深読みを要する思考の持ち主なら、そもそもこの出会いがなかっただろう。彼女はただ、本当に何の気なしに自分が持ってきたCDを昭博に聞かせるために、プレーヤーがある部屋に行こうとしているだけなのだ。余計な考えをするだけばかげている。
「そうでもないようですし、お盆は私が持ちますね。こぼしたらいけないですから。済みませんがCDの方はお願いします」
あまり素早くはない、しかしその分優雅な動作で立ち上がった玲奈はコップが二つ乗った盆を手に取ると慎重に二階へと歩いて行った。何となくペースを乱してしまった昭博がCDを持ってそれに大人しく続いて行く。
階段を上がる途中で、昭博は玲奈のお尻が目の前にあることに気がついた。広がった形のスカートだから形としては上の方の丸みが分かるだけだが、階段を上るにつれて左右に振れている様子は良く分かる。何気ない動作だが、今の昭博にはどうにも悩ましかった。それに今ふっとかがめば、そのスカートの中が間違いなく見える。人目があるわけではないから玲奈にさえ気がつかれなければ誰にも分からない…。などと考えているうちに階段が終わってしまった。また馬鹿らしい事を考えていると、昭博は自嘲するはめになった。
しかし現実問題だけを考えても、この家には今昭博と玲奈しかいないのである。昭博を止める人間は誰もいない。いくら傷が癒えていないとはいえ、腕力がまるで違うのだから、もしどれほど玲奈が嫌がったとしても、昭博には自分の思う通りにする力がある。都合良く布団も敷いてある事だし、ちょっと肩に手をかけて力をこめて、後は服をはいでしまえば…。
昭博はそこまで考えてぞっとした。元々自分のことを優しい人間であるとは思っていない。玲奈のと初めて会ったときの喧嘩で見せたように、情容赦のない部分があることを自覚している。ただそれはあくまで彼自身にとっては正当防衛、やましい訳ではないのだ。しかし今は違う。どろどろとした物が自分の中にあることを改めて思い知らされて、昭博はそれを吐き出すかのように荒く息を吐いた。
後ろで何を考えているのかに全く気付かず、玲奈は昭博の部屋の扉を開けた。
「あー…お布団片付けていないんですね。もう…」
とりあえず盆を勉強机の上に置くと、玲奈はさっさと布団を片付け始めた。それこそ妙な意識は全くないらしい。それで昭博も気分を変えて、一緒になって布団を片付けた。それから二人分の座布団と小さ目の机を持ってくる。普段昭博は勉強机に付属した椅子に座るか畳にじかに座るか、あるいは布団の上で寝るかしかしないので、人がもう一人いるとなると別の用意が必要になるのだ。
「さて、それでは…聞くとしましょうか。まずはやっぱりこれですね」
ミニコンポの前で、玲奈が持ってきたCDの中から一枚を選び出す。昭博がそれを後ろから覗き込んだ。
「それが一番のお勧めって訳か」
「私も聴いたことはないのですが…」
「何だそりゃ」
「澤守…ええと、澤守静馬という方をご存知ですか」
確か生徒会長の澤守の兄の名前はそう言ったはずだ。
「聞いたことはあるな。なんだか思い出せないが。その人の曲…って訳じゃないな。これは外人だ」
「世界的に有名なヴァイオリニストなのですが、その方の推薦なんです」
「ほお…そう言えばそんなんだったっけ」
何度かテレビで見たことがある。天才的な演奏家というだけでなく、長身で細面のいい男なので本来クラシックに興味のない女性ファンも多いらしい。案外ミーハーな所もあるのだな、と昭博はそんな受け取り方をした。
多少の誤解を生じながら、玲奈がCDをかけた。それぞれ用意された座布団に座りながら、音楽が始まるのを待つ。
やがて流れ出た旋律が緩やかに柔らかに部屋を満たして行く。曲調は素朴で優しげで、愛の歌であるように思えた。身近な人に改まらずに語りかけるような、そんな曲だ。玲奈は目を閉じる。
何をするでもなく座っている二人。部屋は少し寒いが、暖房などはつけずに肩を寄せ合ってただ互いのぬくもりを分け合う。ふと一人がもう一人にもの問いたげな視線を向ける。問われた方は迷わず答えを選び出し、そしてささやく…。それが玲奈のイメージだった。
やがて次の曲に入る。素朴さと優しさに変わりはない。しかし今度は、どこか物悲しかった。高音中心のメロディーが切々と訴えている。想いの届かぬ人なのか、それとも伝えるべき人は既に失われているのか…
一度何かに没入してしまうと中々戻ってこない、玲奈はそういう人間である。運動神経に恵まれていないことともあいまって、鈍そうに見られることも珍しくない。決して知的に劣っているのではないのだが。それはさておき、彼女は既にここが昭博の部屋であり、また彼がそばにいることも忘れて曲に聞き入っていた。
そしてとうとう、CDアルバムが一枚終わってしまった。名残を惜しみながら、玲奈はゆっくりと目を開ける。するとそこは彼女が二度目に入った昭博の部屋で、彼は目を閉じてうつむいていた。
「昭博さん…」
わけもなく呼びかけてみる。彼はこくり、とうなずいた。
「あの…」
どこか優しい気持ちで、話しかける。彼はもう一度こくり、とうなずいた。それからもう一度こくり…と。
「…………」
寝ていた。それもかなり熟睡している。いびきこそかいていないが、呼びかけても反応していないところを見るとそう言って良いだろう。そのくせバランス感覚が良いせいか、あぐらをかいて座っている体勢を崩していない。
玲奈はくすりと笑って、次のCDをかけた。寝ているという事はリラックスした結果であろう。それならば悪いことではない。むしろ起こす方が良くないから、玲奈は勝手に音楽を聴くことにしたのであった。どうせ激しい類の音楽は持ってきていないから、そう簡単に目を覚ましはしないだろう。
昭博はふと目を覚ましていた。自分は音楽を聴いていたはずなのに、沈黙が耳を支配している。その不審から、彼は目を開けた。すると視界一杯に玲奈の顔が広がっていた。
「……!」
とっさに声も出せずにのけぞる。なまじ綺麗なだけに、視界を占領されると現実離れして恐い物があった。常識的な間合いが出来た所で、玲奈がくすくすと笑い出す。そうして見るとやはり驚いたのが申し訳なくなるほど可愛かった。
「終わりましたよ、CD」
そう言われて、昭博は適当に返答するしかなかった。
「ああ、じゃあ次の奴を…」
「いえ、そうじゃなくて、持ってきた物は全部掛け終わってしまったのですが。もう一度掛けましょうか」
「あ、えっと…」
寝起きなのでうまい返答が出来ない。玲奈は笑い続けていた。
「どうでしたか、感想は」
「あ、ええと…良かったよ、うん」
「最後のCDの二曲目が、私の一番好きな曲なんです」
「ふうん…」
聴いていない。全く。記憶もない。冷や汗が出た。
「これは私のですから、よろしければお貸ししますよ」
「そうだな…」
「本当にいい曲ですから、寝るのはもったいないですよ」
「…………」
昭博はようやくばれていることを思い知らされた。今回は玲奈の一本勝ちである。彼女はちょっと吹き出してから、話題を変えた。
「もしよろしければ、ここにある物も聞いてみたいのですけれど」
「あ、ん…俺の奴?」
「はい」
「君が聞いて面白いとも思えないけどな…ま、別に構わないよ」
「ありがとうございます」
今度は花がほころぶように笑ってから、彼女はミニコンポの脇に有る棚の前に座りこんだ。昭博がCDその他を雑然と置いてある場所だ。人並みに音楽は聴くが特に何にはまっているとか、あるジャンルのマニアだとか、そういったことのない昭博としてはごく普通の物を置いているつもりでいる。しかし玲奈は実に興味深そうにCDを取り出してジャケットを眺めるなどしていた。
「それではこれを…」
結局彼女が取り出したのは、去年一番売れた、男性五人組バンドのアルバムだった。アップテンポからバラードまで、幅広くこなすバンドである。元々昭博はハードロックなどは好きではないし、どちらかと言えば男性ボーカルの方を良く聴くのでこう言う曲調が多くなる。
「ああ、そうだな。これは結構いい感じだから…」
と、階下で電話が鳴った。昭博は不快感を隠そうともしない。
「誰だ、ったく…ちょっと出てくるから、適当に聴いてていいよ」
「はい」
昭博はどかすかと階段を降りて、居間の電話の受話器を取った。どうせ電話勧誘だろうから、まともなことを言ってやらない。
「はい、関東地獄組東京第二支部」
こんな応対をするくらいなら居留守を使うとか取ったその瞬間に受話器を置いてしまうとか、そうすれば良いような物だが昭博は思わずやってしまうのだった。意地が悪い、と言えばそれまでである。
いくら何でもこのような台詞を聞かされた側は絶句した。しないほうがおかしい。それにもしそのまま何事もなかった様に要件が始まったら、却って恐いものがある。しかし、ようやく発せられた電話の向こうの声によって、今度は昭博が絶句することになった。
「…手塚君か? 虎田だが…」
低い、しっかりした中年の男の声であった。
「あ…虎田先生」
先ほどの比ではない冷や汗が出た。そして弁解をする。
「済みません、最近勧誘が多くて…」
「別に構わんよ。職業柄その筋の人間の相手をすることも少なくないのだし」
「へえ…そうなんですか。もっと高尚な世界かと思ってましたけど」
「そんな事はない。現実として法廷は紛争解決の場であり、そして連中は紛争を食い物にする。もっとも彼等が表立って法廷に出てくることはまずないが」
「結局どろどろした世界ってわけですか」
「そうではないと言いたい所ではあるが…」
「ま、言われてみればそうですね。俺の一件だってそうなんですし」
「ん…」
「所で、お忙しい中こんな所に電話とは、まだなにかありましたか」
「まあそうだな。さっき君の学校の先生から連絡があったよ。最近出席はしていないそうだね」
特にとがめるような調子はない。ただ伝えられた通りのことを更に話している、そんな調子だ。それゆえ昭博も悪びれはしなかった。
「ええまあ。行っても何も面白いことはありませんから。あっちの人は停学処分だとか自主退学だとか、ヒステリックに喚き立ててませんでしたか」
「いや、別に。用件は出席をしていないから私のほうから注意をしてほしいとの事だけだったよ」
「ほう…。さすがに教師だけあって小知恵が回りますね。普通の生徒が休みがちになったらすぐに自主退学をしろとか言い出すくせに、相手が人権派弁護士、虎田富士夫先生となると急に大人しくなる。まったく、人生の見本としてはまことにふさわしい人達ですよ。学力の方が今一つでも見逃してやれますね」
情容赦なく、彼は切り捨てた。電話の向こうの弁護士は少し黙ってから話の方向を少し変えた。
「それから、これに関しては遠回しにだが、君が同じ学校の生徒に怪我をさせたようなことを言っていた」
「仲原以下四人ですか。あれは正当防衛ですよ」
「解釈問題ではあるが、日本の刑法では重傷者が出た時点で正当とは言わんよ。少なくともいわゆる喧嘩の場合は。過剰防衛だ。しかも四人全員が凶器を首から上に受けている。下手をしたら殺していたぞ」
「なに言ってるんですか。こっちは一人、向こうは四人ですよ。そうでもしなきゃ俺が重傷を追わされてましたよ。それが分からない先生でもないでしょう。ナイフを持ってた人間もいたんですし、実際俺もちょっと腕をやられましたからね」
「君が怪我をしたとは初耳だ。大丈夫なのか」
「かすり傷です。医者の見立てでは全治一週間、あれから三日も立ってますから、もう直りかけですよ」
「ならいいが…。裁判で重んじられるのは社会常識よりまず判例だ。君の言う通りではあるが、法廷に出たとして君の主張が認められる目は少ないぞ」
「分かってます。でも大丈夫ですよ。この一件を持ち出して得をする奴なんて誰もいませんから。俺は面倒ですし、連中にしてみればたった一人に無様にやられたことをおおっぴらにしたくはないですよ。学校も警察沙汰なんて避けようとしますから必死になって隠してくれますって」
「確かにな…しかし自重することだ。世の中は君のように理屈の分かる人間ばかりではない」
「それは知ってますよ。この前先生にお願いした件で思い知らされましたから。しかしまあ、別に少年院くらい入ってもいいんですけど。どうせ俺には壊れる将来なんて有りませんから」
「そうか…」
感情を隠すように平板な声で、弁護士は答えた。昭博が苦笑する。
「そんな事を言うな、とかやはり学校に行ったほうがいい、とかそういうふうには言わないんですね」
「私は弁護士だよ。言葉の力を知っている。その無力さもね。君にそう言って何になる。君は頭のいい人間だ。先の見通しをつけて、その上で行動しているのだろう。高校などもう大学に行くための資格でしかないし、やりたい学問がなければ大学も行く意味がない。少なくとも君にとってはな。それならば、私が言う事は何もないよ。ご両親の名を持ち出すような怪しげな真似もしたくはないしな」
「そうですね」
今度は昭博が平板に言った。
昭博が電話に出ている頃、玲奈は何となく彼の部屋を見回していた。主が席を外したりすると、客が誰でもすることではある。CDはかかっているのだがあまり聴いてはいない。興味の対象がまず部屋の様子の方に移っているのだった。
とりあえず目が行くのは本棚である。その人の本棚を見れば人柄が分かると言われている。そこまで行かなくとも、趣味、好みを読み取れることは確かだ。とりあえず少年誌系の漫画が多いが、多少文庫本なども置かれている。平均よりは良く本を読む方かもしれない。下のほうの雑誌棚はやはり漫画雑誌が中心になっている。多少なりとも興味があるのか、ファッションを中心とした男子高校生向けの雑誌も時々買っているらしかった。ただどこの雑誌を買うと決めてはいないらしい。数種類のものが、号数もばらばらに適当に並んでいる。
「…最近は買っていないのかな」
秋物の特集をした物がない。今は丁度季節の変わり目だから特集記事などは花盛りのはずだ。少なくとも玲奈が買っている女の子向け雑誌ではそうだった。むしろ今するのは遅いくらいで、夏の盛りに秋物の特集をしても一向におかしくはない。何月号か確認してみても、やはり今月、あるいは先月の物はなかった。
たまたま興味がなかっただけかもしれないのだが、玲奈は何処か違和感を覚えた。元々この家、そしてこの部屋には何かおかしいものを感じていたこともある。いくら両親が旅行中とはいえ、昭博が厳然として住んでいるのにもかかわらず廃墟のような印象を受けることがあるのだ。
そして改めて漫画雑誌の方に目をやってみる。かなり適当に並んでいるが、それでも良く見れば毎号買っていると分かった。確かにこの種の物は気が向いた時に買うだけではあまり意味がない。しかし…新しい物がなかった。どれも古びている。特にこの種の雑誌は耐久力のある紙を使っていないから、注意してみればすぐに分かる。昭博には少し悪いと思いながら玲奈は一冊取り出してみた。ここにある中で、号数的には一番新しい。普段少年誌には興味がないので玲奈は表紙を見てもとっさには分からなかったが、しかし最後部の発行日を確かめてやはり古い物であると確かめた。それが一箇月前になっているのである。通常雑誌の類は慣習として名目上の発行日より前に発売する物だから、実際にこの雑誌が店頭に並んだのは一箇月より更に前だ。
それにさっき見たCDも、新譜はなかった気がする。音楽は頻繁に聞くからそれは分かる。
この部屋は死んでいるのだ。何十日も前から。
悪寒が背筋をしつこく繰り返し上下したあげく全身に広がった。昭博はそんな部屋で寝起きしているのだ、この何十日間も。一体何を考えてか。いや、違う。恐らくは何も考えずにただそうしているのだろう。まるで自身が、死んでいるかのように。
玲奈は自分の考えを否定する材料をまず自分の中から見つけようとした。新しい雑誌の類は別の場所、例えば居間などに置かれているかもしれない。…それはない。この前この家の掃除をしたのは、他ならぬ彼女なのである。新しい雑誌が数冊固まっている事はなかった。それでは単に今まで読んだものに飽きてしまっただけでは…。しかしそれまで継続的に読んでいた物を代替物もなしに一斉に止めるなど、余程のことだ。人間の神経として正常であると言いがたい。
それから素早く、彼女は部屋中を見渡した。勉強机は…これは元々死にやすい、物置と化しがちな代物ではあるが、しかもそれが勉強など止めてしまっている昭博の物である以上絶望的だ。実際ここ最近何かの作業をした形跡はない。そして広くもない部屋である。棚と机、それから布団を敷くスペースでほとんど終わってしまっている。後には何もない…。
玲奈はもう一度、本棚を見やってみた。そうすれば、単なる勘違いと分かるかもしれない。しかし得られた結論に変わりはなかった。
「どうして…」
言いようのない不安にさいなまれながら、玲奈は視線を落とした。と、雑誌の棚の中に一冊、他の物と少々色合いが違うような物が、奥のほうに押し込んであるのに気がついた。
「…これは?」
そろそろ勝手に部屋を漁っては悪い、という感覚を鈍らせながら、玲奈はその一冊だけ浮いているならぬ沈み込んでいる本を引っ張り出した。それなりに美人の、髪の長い若い女性が表紙の雑誌だ。
ちょっと見て、玲奈はその雑誌がどのような種類の物か良く分からなかった。いわゆる週刊誌にしては型が大きいように思える。写真週刊誌…かも知れないが「ピュア・ビューティー」の雑誌名に覚えはなかった。最近流行りの地方情報誌、だったら少なくともここでは「東京」とタイトルに入るはずだ。
表紙とその誌名だけ見て首をかしげていても仕方がない。玲奈はページをめくった。
…肌色だった。
それがまず玲奈の感じたことだった。何が肌色なのかと言うと、ばかばかしくなる。肌が写っているのだから、肌色なのだ。
玲奈はページをめくった。
…肌色だった。
肌の色である。それがページの大部分を占めている。正確に言えば、肌色の肌を有している動物は人間しかいない。また、更に厳密に言えば、日本人の言うこの「肌色」の肌を有しているのは北方に住むアジア人のみ、日本人自身でも例えば「小麦色」のように「肌色」ではない肌を有している者は少なくない。英語圏であれば、この色をペイル・オレンジ(薄い橙色)などと形容する。現に絵の具などで「肌色」を作る場合には白に橙を形成する赤と黄を混ぜるものだ。
要はエロ本だ。女性の肌を最大限、あるいは男性の情欲を効果的に刺激する範囲で露出させる、定義するならばそういう本だ。つまり女を裸にして写真に取り、それを雑誌にして売っている。
とりあえずこの雑誌の編集方針等を理解して、玲奈は固まった。不潔、嫌らしい、汚らわしい! …とは、彼女は思わなかった。そう感じたのならまずそんな物を持ったまま突っ立っていたりはしない。彼女の目はしげしげとその写真を見ていたのだった。
元々そうそう過激な本ではない。あたりのコンビニエンスストアに売っているような、ただ女の裸が写っている程度の本である。それもそこまで過激なポーズなどは取っていない。それで本来の持ち主としてはつまらなくてそのあたりに放置し、そして玲奈が掃除をする段になって慌てて本棚に紛れ込まされ、そしてまたそのままになって結局今彼女に発見された代物であった。いきさつはさておき、普通に同じ女性の裸体が写されているのだから、玲奈としてはそこまで驚く理由がないのだ。
ただしかし、驚愕はなくとも興味は十分にある。もちろん男が持つような好色な興味ではなく、女性としての興味だ。バストだとかヒップだとか、他の女性が自分とどう異なっているのか、それは気にかかるところである。体育の際の着替えなどで目にすることもないではないが、まさかその時にしげしげと、心行くまで観察するわけにも行かない。
しかし今回、相手はどれほど、穴が開くまでやらない限りいくら見たところで微笑みを返してくるだけだし、ご丁寧にスリーサイズも脇の方に書いてある。まさかこの種の本を買ったことがあるでもないし、わざわざ見せてくれるような悪友を持たない玲奈としては、思春期以来の疑問の答えを一度に示してくれる物だった。これを見逃さない手はない。
まず注意が行ったのは、やはり胸だった。顔を除けば、通常女性として最も気になる体の部位であろう。この写真のモデルは相当に豊満なバストをしていた。しかもそれを強調するようなポーズを取っている。「たわわな」という形容がまことにふさわしかった。大きさとしてはさすがに西瓜とは行かないまでも片側だけでメロンくらいはありそうな気がする。形も丸っこく、ぱんぱんに膨らんでいるように見えた。
いくらなんでもこれには勝てない…と玲奈はまずそう考えた。付記されたサイズを見ると何と102。メートルを超えている。身長も書かれていて、それは165であったから相当な物だ。太っているとも言いがたい。世の中にはこのような人間もいるものだ、という程度に思うしかない。
しかし、よくよく見るとこれはどうかな、と思う所がいくつかあった。それはあまり競争心豊かとは言えない彼女にも確かに存在する「女の意地」が見つけさせたのかもしれない。
まず少し、形が良くない気がする。実るほど、頭をたれる…ではないが、大きく膨らんでいるだけあって、さすがに重力に抵抗し切れなくなっているようだ。理想よりは全体的に少し下に過ぎているように、少なくとも玲奈には思える。それに先端もちょっと下を向いてしまっている。そもそも人体のバランスとして、これでは大き過ぎるのではないか、とそんな事も考えた。
それに先端部のあたりがよろしくない。色が白いせいか黒ずんではいないのだが、乳輪が本体の膨張によって引き伸ばされたか、と思えるほど大きいのだ。ある種微笑ましい、そしてある種険悪な見方をすればパンダの目のようにも見えてくる。
これはどうだろうか…と玲奈は自分自身の乳房の記憶と写真とを見比べながら思案に入った。形状としては、彼女自身の美的センスが明らかに自分の勝利と判定している。しかしながら美の感覚は人それぞれだと承知してもいるし、男性は大きい方が好みだとは良く耳にする所である。大きさであれば絶対に勝てない。もしどうにかして彼女がこの大きさを手に入れようとすれば、かなり恐いことをしなければならないだろう。
しばらく悩んだ末、とりあえず彼女は結論を棚上げにした。そう簡単に答えの出る問題ではないだろうし、それに少なくともまだ一つ、検証すべき大きな問題が残っている。玲奈の視線は白い肌をなぞってへそを通り過ぎ、下へと降りていった。
ヘアヌードとやらが解禁されてそろそろ数年になる。しかしそれが厳密にいつなのか、誰も知らない。刑法が改正されたのは平成七年五月のことであるが、しかしこの改正の主眼は漢文書き下し調の全面的な現代語化、および二十年以上前、昭和四十八年四月四日に最高裁判所大法廷(慣行上当該事件、法令において憲法違反か否かを判断する必要がある時または判例を変更する時に開かれ、最高裁に所属する十五人の判事全てが出席する。憲法判断が行われない、または判例に変更のない場合、裁判は五人の判事からなる小法廷において行われる)が下した刑法200条、尊属殺人の違憲判決にもとづき、ようやくその条文が削除されたことである。
現代語化に関しては極力旧規定の表す意味の変更を避け、現代語への直訳が図られている。学会において問題があるとされていた条文もそのままただ現代語にされたのみというケースも少なくない。また全面改正である以上、敗戦後の憲法改正によって削除された第七三から七六条(皇室に対する罪に関する規定)、および第八九条(戦時同盟国に対する行為)など「削除」としていわゆるナンバリングを残すのみの欠番とされた条文などを、条文番号ごと抹消して番号の振り分けをやり直しても良さそうなものだが、それらの条文番号と「削除」の二文字が空しく残されるなどしている。
これはつまり、その当時刑法に関わっていた人間が大幅な改正は迷惑と考えていたためである。
第七三条から七六条は全264条の刑法の中でも比較的前、第二編罪第一章と第二編の先頭を飾っている。第二編は別名各則とも呼ばれ放火、殺人、窃盗などいわゆる犯罪を具体的に処罰する規定が並んでいるのだが、何故先頭に「皇室に対する罪」が来るかというと、これはこの刑法が原則として重要性の高い順に組織的に配列されており、そして本来明治憲法下で制定されたためである。つまりその時代では疑いようもなく天皇および皇族が最も重んじられるべきであったのだ。この後遺症として現代語化に当たってナンバリングを詰めようとすると各則に置かれている全ての条文の番号が変わってしまう。放火も殺人も窃盗も、全て一から番号を覚えなおさなければならなくなるのだ。刑法の教授が大教室で自分の知識をひけらかすべく資料を見ずに「刑法一九九条、殺人は…」と開口一番言ったところで新しい六法を手にした学生が「違うよ、それ」と嘲笑混じりにささやき合うなどならまだ可愛らしい事態である。もっともそれが最大の理由かもしれないが、さておきこれが法廷で検事や弁護士、あるいは裁判官が条文を間違えると洒落では済まされない。
それに改正によって文章がそれまでとは別の意味に取れるようになると、その問題点について綿密に議論をしなければならない。それはそれで非効率であることはなはだしい。
大体そのような訳で、刑法第175条(猥褻文書頒布等)の「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若シクハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金若シクハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」という現代では最早日本語とも思えない文章は、同じく175条(わいせつ物頒布等)、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする」となった。かろうじて読めるようにはなったが、しかし直訳にこだわったがための苦労がにじみ出る文章になってしまっている。
まず、せっかく現代語訳を試みたにもかかわらず、「頒布」「陳列」となどの古い熟語は残っている。この二つは最早、この条文がらみでしか使われないものである。多少名が知られていてワープロで変換してもきちんと出てくるのはこの条文が有名であるためだ。それぞれ「配布」「展示」とでもしていればじきに消える語彙である。また、せっかく「猥褻」をひらがなにしたのに「若しくは」と言う表現が残ってしまっている。「もしくは」で良いはずだ。ちなみに、このような場合広辞苑を引こうなどと思ってはいけない。却って混乱するのが落ちである。上記の「陳列」もこれをもとに「展示」とし、また「頒布」に関しては「くばりわけること」とあったため単純に漢字を充てて「配布」とした。
また、それを抜きにしても漢文書き下し調の要素をなるべく残そうとしたせいか、表現に現代語としての難が残ってしまっている。「…頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は…」ちょっと読み辛い。二字熟語がサ変動詞によって動詞化されたものが並列されているのだからそれはまとめた方が自然である。つまり「…頒布、販売、または公然と陳列したものは…」となる。この方が読みやすいし意味も取りやすい。
このように涙ぐましい努力を払っていると認められる以上、刑法175条の意味は改正以前と以後で全く変更されていないと解釈するのが正しい。つまり表現がいかに変わろうとも、少なくともこの件に関して法律はまるで変わっていないと言って良いのだ。
しかしながら、気がついてみれば以前は下の毛が写っていればとりあえず発禁、普通に売るためには修正を入れなければならなかったのが、今や毛ぐらい平然と、本来エロ雑誌ではない週刊誌にさえ写されている。法律の運用とはある種そのようにいい加減な所があるのだ。この場合「わいせつ」というあいまいな言葉をどう解釈するかによって合法か否かがきっぱりと分かれてしまう。この事例では、どうやらいつの間にか「毛が写っていればわいせつ」であったものが「性器が丸写しになっていなければわいせつではない」と解釈が変わったらしい。
具体的に誰の解釈が変わったのかというと、これは取り締まり機関である警視庁および全国の道府県警察である。警察が「わいせつ」と判断しないから取り締まられないのだ。逆に言えば警察が「わいせつ」と判断できる物を発見した場合これは取り締まらなければ職務怠慢、立派な犯罪になる。しかし警視庁、道府県警察本部の上部機関である警察庁が「毛が写っていてもわいせつではない」との通達を全国の警察に出したこともないし見解を示したこともない。それで「ヘアヌード解禁」であるから警察というものも微妙な所がある。逆に「裸であれば全てわいせつ」と解釈して全てのエロ本を取り締まることも理論上は可能であるから、もしそうなれば中々に恐いことではあるのだ。
もっとも、日本に裁判所というものがある意義の一つは万が一警察がそのような暴走を始めた場合にそれを制止することであるし、そもそも警察を構成する個々の警察官も日本という社会の中で暮らす一人の人間であるから、組織全体として常識を極端に外れるということにはなりにくい。
さて、そのようないきさつを踏まえて、玲奈は合法的に他人のその部分をじっくりと観察することができた。玲奈は今十七歳、この種の本はいわゆる十八禁で各都道府県条例によって十八歳未満の人間への販売および提供が禁止されているが、少なくとも未成年が見ることを禁止する条例ではない。またこれの所有者である昭博も未成年で、この条例が処罰しているのは成年の未成年に対する行為であるから彼にも責任はない。
これだけ胸が張っているのだから下のほうもさぞかし…と思いきやそんな事はなかった。面積もそれほどではなく、何より量が少ないように見える。地肌の色がわかるほどの薄さで、そのまま下の写っていない部分へと消えていた。
胸であれば同級生などの物を多少は見たことがあるものの、その部分となるとこれはもうほとんど初めてに近い。銭湯には行ったことがないし、二年次の修学旅行の時はホテルの都合で風呂でも水着着用が原則になってしまっていた。そうすると比較対象は自分しかなくなるのだが…。これを考えようとして、玲奈は途方にくれてしまった。果たしてどのようなものが「良い」あるいは「好まれる」のだろうか。胸であれば漠然と大きい方が良いようなことが言われているが、しかしこれに関して何が良いのか、少なくとも玲奈は知らなかった。大概の人間がそうであろう。一部にはそんな物ない方が良いとし、そのイデオロギーを実行に移してしまう人もいるようだが、ヘアヌードがもてはやされることを考えればそれは多数派ではないと推測するのが自然だろう。だから良くない、とそういう問題ではないが。
はっとして、玲奈は数ページめくってみた。するとモデルが変わっている。数人の女性が脱いでいるのだと、彼女はこの種の雑誌のシステムを理解した。一人の女性のみが写されているのなら、それは通常写真集と呼ばれる物である。雑誌であれば複数の女性を登場させるのが普通だ。
今度は顔も胸も見ずに、彼女の視線はそのまま下へに向かった。下品…との批判は酷であろう。その際の彼女の感想を一言で表せば、「すごい」であった。
まず何がすごいかというと、履いている下着がすごい。とりあえず今度のモデルはそれを履いてはいるのだが、しかしその下がほぼまるきり透けて見えた。ある種のストッキングのような生地で出来ているらしい。世の中にはこんな物があるのかと、感心してしまう。もっともこんな物は普通それこそこの種の雑誌かあるいはエログッズの専門店でしか見られない。それが家にあるとしたら…それは普通ではないと考えるべきだろう。
そしてそこから透けて見える物がまたすごかった。今回は濃い。わさわさと、しかも広範囲にわたっている。ある種海藻のようだ。それで改めて、胸の方に目をやってみるとこちらはそう極端な巨乳ではなかった。形は違うが大きさとしては自分とほぼ同じであると玲奈は判断した。どうやら胸の大きさとそれの量に相関関係はないらしい…。
「あー…ったく、忙しいくせに話し出すと長いんだよな、あの人は」
昭博が部屋に入ってきた。自分の部屋であるから特にノックもしない。いきなり扉を空けて後ろ手に閉め、そのまま自分の座布団に座りこんだ。そしてかかっている音楽に耳を傾ける。
「いい曲だろ、これ。丁度いいタイミングで帰って来れたな」
しかし玲奈の反応はなかった。聞き入っているのかと思ったが、どうもそうではないらしい。ぽかん…と口を半開きにして彼の顔を見ている。それでも美人なあたりはさすがと言うほかないが、しかし心配になる。
「おい…?」
昭博の視線は彼女の顔からゆっくりと下へと降りていった。白く細い首があって、鎖骨が少し見えているのがなまめかしくて、それはさておきひたすら可愛らしいワンピースがあって…そしてエロ本があった。
「…………!」
これには昭博の目がこれ以上ないほど見開かれた。いくらなんでもあんまりだ。何よりもまず彼の頭をよぎったのはそんな事である。美少女がエロ本など読んではいけない…。そんな意味もない考えがしばらく頭の中を四列横隊で行進してから、彼はようやく彼女の手にしている本が自分のものであることに気がついた。いくらなんでもあんまりだ…。
昭博が目を見開くに連れて、玲奈は自分のやっていることに気がついた。それまでは事態の急転に思考回路がダウンしていたのであるが、気がついてみれば彼女は人の部屋に上がりこんでその本棚を勝手にあさり、挙句彼女の主観で言う所の「エッチな本」を読みふけっていたのである。いくら何でもあんまりだ…。
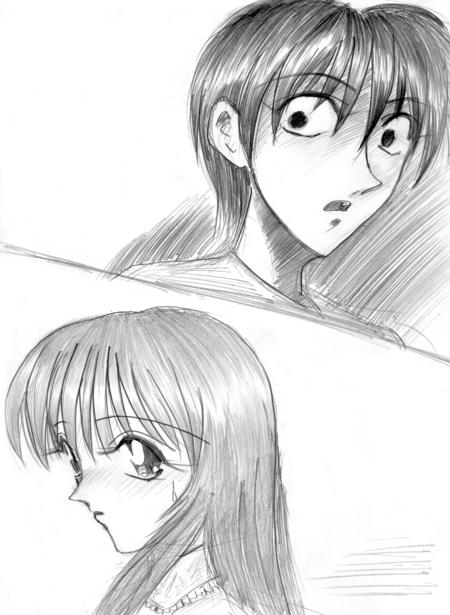
やおら、昭博の手が動いて玲奈の手から雑誌をひったくった。そしてその手を後ろに回す。それがきっかけで、ようやく二人とも口が動かせるようになった。
「こ、これはだな!」
「あ、あの、これはですね!」
全く同時に、二人とも意味のないことを口走る。しかし何か考えている訳ではないので、お互いに相手がなにか言ってくれることを期待してまた黙ってしまった。相手からどんな罵声を浴びせられるにせよ、沈黙をもって報われるよりはまだましだ。結果、最悪の沈黙が訪れる。二人とも、相手の顔が見る見る真っ赤になりそして自分の顔も火照っているとわかっていた。
「だから…」
「ですから…」
そしてまた同時。よって結果も同様である。みたび、沈黙。もう収拾がつかない。
「それは友達にもらった奴で俺は別にいつも見ているとかそう言うことはなくてだな、たまたま本棚に放りこんでそのままにしていただけなんだ。そもそもそんなに面白い訳じゃないし、って、あ、そりゃまあ一回は見たんだけどさ、でも、でもなあ、本当にそれっきりにして、そのまま忘れていたんだ。だから俺はそんな…」
「あ、あの、ごめんなさい、私そんなつもりはなくてちょっと開いてみただけで、変な興味があったとか、そう言う訳ではなくてそれは確かにちょっと見てみたいなあ何て気はありましたけど、で、でも、いつもそんな事考えてる訳じゃないんです…ほんとです…」
ここまで言った所で、昭博がその不毛さに気がついた。お互い、まずい事をやっていたのだ。言い訳をしようとするだけ自分も相手も追い詰める。なお、彼の方が言っている量が多いのは純粋に早口なためである。左手は背中に回したまま、彼は右手で玲奈の肩を叩いた。彼女は身をすくめるが、彼はその目をじっと見据える。
「…………」
「…………」
すさまじい緊迫感が部屋を埋め尽くす。そして、一言。
「…なかったことにしないか?」
玲奈は五回ほど長い睫毛をしばたかせて、それからうなずいて了解の意思を示した。
昭博はまずなかった事になった物を持ったまま立ち上がって、部屋の外に消えた。そして問題の物は、彼が帰ってきたときにはきれいになくなっていた。どこかに捨てて来ただとか、また別の場所に隠しただとか、そのように考えてはいけない。そんな物、元からなかったのだ。それが大人の、政治的な解決である。
「さて、別のCDでも掛けようか。俺としてはこっちの方がお勧めなんだ」
「あ、そうですね。是非聞きたいです」
玲奈も子供ではなかった。そして軽快な曲が流れ出す。
しかし…政治的妥協とはえてしてその双方に不満を残すものだ。人間の多くが自分の利益よりも損失を大きく見積もり、そして自分の利益より他人の利益を大きく見積もる、そういう感覚を有している。それを承知で妥協を為し、先へ進んで行くのが成熟した態度なのであろう。それができないのなら相争い、結果双方に多大な損害を出すしかない。人間は耐えて行かなければならないのだ。例えばそう、気まずさなどに。
これほど気まずい状況が、果たしてあり得るだろうか。それをとっさに思いつける人間が居るとしたらそれは余程の想像力の持ち主である。そして少なくとも、昭博も玲奈もそこまで想像力豊かではなかった。昭博は部屋の入り口付近の天井の隅、玲奈はそれと全く反対方向、床の隅の方を眺めやっている。別に音楽を聴いている訳でもない。やがてCDアルバムが終わってしまい、昭博は機械的にまた別のアルバムを掛けた。そしてまた同じ事の繰り返し。リピートをかけた方がまだましだったかもしれない。もうこうなってしまってはどうしようもない。やがて昭博は、手段はどうあれ状況を打開することを決断した。
そのアルバムが終わってから。
「さて…何かもう暗くなってきたし、そろそろ帰った方がいいんじゃないのか」
「そ…そうですね。それでは私はこれで…」
「ああ」
可愛らしいワンピースを翻して、玲奈は部屋を出た。昭博は見送るそぶりも見せなかった。
二時間後、昭博は居間のソファーに沈み込んでいた。…と言うよりむしろ、半ば屍体のように転がっていた。寝るのなら自分の部屋に行けば良いようなものだが、しかし向こうには居たくなかった。あの空気が、まだ澱んでいるような気がしてならない。
「…嫌われただろうな…」
常識で考えれば、そうなる。しかし止せばいいのに彼は、ここでも一人で澱んだ空気を生産していた。じきに自分の家の中に居場所がなくなるに違いない。
「ふ…ははははははは…いいじゃないか、どうせ。元々この前知り合ったような人間なんだから、嫌われたって、元に戻るだけだ。それに俺は、一人で生きていけるんだから…」
力なく笑って、彼はのろのろと立ちあがった。そして自分の部屋へと戻って行く。その後彼は、一枚のメモを手にして電話の前に立つこととなった。彼の筆跡ではない字で、八桁の数字が記されている。机の上に放り出してあった、玲奈が自分の電話番号を記したメモ、それが目にとまったのだった。
「やっぱりこれは何とかしておかないとな…」
そうつぶやいて、受話器に手が伸びる。そして彼はふと、何故そうしなければならないのかと疑問に思った。それは…。
「えい、んな事はどうでもいい。後で考える」
はき捨てるように言ってから、彼はやや荒っぽく受話器を手に取った。何かその際に音がしたようだが、気にしない。そしてメモに視線を走らせる。
「…と、5始まりか。やっぱり新しいんだな…」
東京二十三区の市外局番は利用者の増加に伴う回線不足を解消する為に数年前に四桁化されたが、その際に以前からあった回線の市外局番には先頭に3がつけられ、新しい物には5が先頭につけられた。そのため二十三区内なら、その回線が以前から使われていた物か新しい物かが大体分かるのである。もっとも近年の携帯電話、PHSの普及に加えて空前の大不況により通常回線の加入者は頭打ちとなり、むしろ移動体通信の方に番号改正が必要と言う皮肉な事態となっている。二十三区の番号改正が行われたのが丁度バブルの絶頂期であるから、現状として市外局番は三桁で足りているのかもしれない。昭博の家族は昔からここに住んでいるから、市外局番は当然3で始まっている。
「あ…あれ? ええと…昭博さんですか?」
と、受話器から回線がつながっていることを示す「プー」と言う一様な電子音ではなく、少々戸惑った、しかし涼やかな響きの良い声が聞こえてきた。聞き間違えようがない。玲奈だ。
「あ、え? ん、ああ…」
最近の電話は思っただけでつながるようになっているのか、それとも望んだような幻聴が聞こえるほど危険な状態に入ってしまっているのか、昭博は内心かなり動揺した。
が、真相はそうではなかった。玲奈の声が弾むのが分かる。
「珍しいこともあるものですね。かけた瞬間に受話器が取られるなんて。まるで待ち構えていたみたいです」
「あー…あ、なんだ、そういうことか。俺はちょっと驚いたよ。そっちにかけようとしたら、君の声が聞こえてくるんだから」
受話器を持ち上げる前の音は、コールの始めの部分だったのだ。普段であるとそれは一回鳴るごとのものが記憶されるから、部分的に聞くとかなり分からない。
「…じゃあ、昭博さんも私の所にかけようとしていたんですか」
「ああ、まあな」
「それはますます珍しいですね。ほとんど同じ時間に、同じことを考えていただなんて」
「うん…しかし全く同時にかけようとしていたなら、お互いに話中になっちまってた訳だ。確かに面白い…」
二人して笑いあってから、昭博ははっとなった。今電話をしようとしたのは、言いにくい件を言おうとしたからだ。しかしこうして声を聞いてしまうと、何と言っていいかも分からなくなる。だから昭博は、まず相手の用件を聞いてみることにした。
「それで、わざわざ電話だなんてどうしたんだ」
何気なく切り出したつもりだったが、玲奈は息を呑んでしまった。
「え、ええと…それはその…」
それからしどろもどろな声が出る。昭博は何となく言いたいことが分かったので、内心の動揺を抑えて聞いてみた。
「遠慮することなんてないぞ。俺はそんな物受け止める神経なんて持ち合わせてないんだから。なんでも言ってくれよ」
「あ、あの、あ…そうです、昭博さんの方の用件をお先にどうぞ。昭博さんも丁度私の所にかけようとしていたのでしょう。私は後で構いませんから」
これが一番効く。今度は昭博がしどろもどろになる番だった。
「あー…いや、別に大した用じゃないしさ、あれなんだけど。だからそう…君が先でいいって」
「あ、いえいえとんでもない。昭博さんから…」
「いや、だからいいってばさ。君から…」
「いえ、私の方は本当に、つまらない用事ですから…」
「つまんなくてもまず聞くよ。何だい?」
そしてとうとう、二人とも押し黙ってしまった。やがてこうなる。
「じゃあ、俺から…」
「それでは、私から…」
今回も発声のタイミングが完璧に一致していた。きりがない。ここは昭博が踏みこむことにした。やや語気を強める。
「いや、もう、こうなったら俺が先に言わせてもらう。いいか?」
「あ…はい、どうぞ」
どうやら彼女は受話器の向こうで居住まいを正したらしかった。そうされるとますます言いにくいが、これはもう仕方が無い。昭博も背筋を伸ばした。
「あのさ…ええと…あれだ。何て言うか、見えるような所に変な物置いておいて悪かったな。女の子が来るんだから、片付けて当然だったのに…」
これで彼女が自分を見直してくれるとも思っていない。ただ、昭博は謝っておきたかったのだ。すると、ちょっと控えめに驚いた声が返ってくる。
「え…あの…昭博さん、怒っていませんか。勝手に本を読んだりして…」
「あ? いや、別に。だってあれは本棚の良く見れば分かる所に押し込んであったんだし、見るなって言う方が筋違いだよ」
「そうですか…私はてっきり、昭博さんが怒っているものとばかり思って…安心しました」
安堵の溜息が、受話器にかかったようだ。それが届いているはずもないのに、昭博はくすぐったいような気分を覚えた。
「何だ、そんな事を気にしてたのか。部屋に入ったんだから、本棚くらい見て当然だよ。構わないって。ま…できれば見て欲しくなかった物だけど、俺の落ち度だからな…」
「やっぱり…済みませんでした」
「いいっていいって」
「今度からはあんなこと、しないようにしますから…」
「いや…もう君が来る時にあんな物は部屋に置いておかないよ。そこまで間の抜けた人間じゃない」
玲奈が泣きそうな声を出すものだから、昭博は合っているのかいないのか良く分からない返答をした。
「では…またうかがっても構いませんか」
気がつくとそう言う話の流れになっている。これはもう、イエスというしかない。
「ああ、別にいいけどさ」
「はい、ありがとうございます。それではまた、明日」
「うん、じゃあ、明日な」
そして電話が切れた。耳障りな音がしない所からして、まず回線を切ってから受話器を置いているらしい。感心なことだ。昭博はそのまま受話器を置いた。
「さて…メシにでもするかな」
空腹ではあるが今から何か材料を買ってそれから料理をするなどと言う気力は既に残っていないので、彼はコンビニ弁当でも買ってくることにした。買いに行く途中の夜風が、今日の彼には妙に心地よかった。