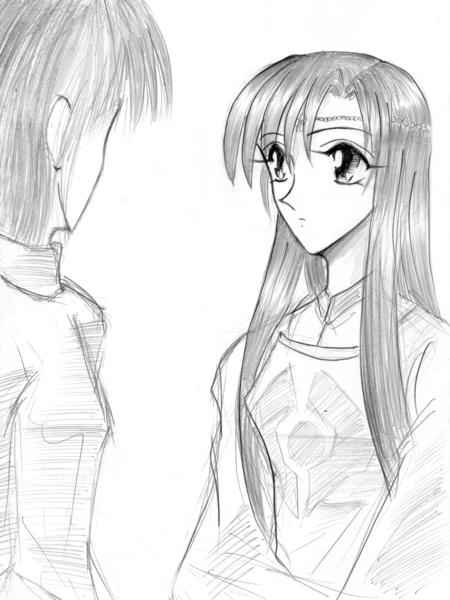
王都シリーズⅢ
王都家出人調書
エピローグ 神官
翌日、ストリアスが起床した時、外は暗かった。一瞬、速く起きすぎたかと思ったのだが、それにしてはどうも何かがおかしいと感じ、とりあえず店の方の様子をうかがってみた。そこではファルラスとエレーナが、店じまいの支度をしているところだった。
とっさの混乱が収まってから、ストリアスは平謝りに謝った。要するに、昼間中寝ていたのである。前日の疲労が、そうさせたらしい。ただ、元来温和なファルラスはもちろん、エレーナも特に責めることもなく、その日はそれで終わってしまった。夜も、とくに寝つけないということはなかった。
通常の生活に戻ったのは、さらにその翌日からである。この日エレーナは所用とかで朝から外出していたため、店主ファルラスとともに仕事をすることとなった。こまごまとした事務作業その他雑用を、一つ一つ潰してゆく。少なくとも足を使った人探しよりは、こちらの方が性に合っていると確認することができた。
そして夕刻、ファルラスは客と商談を進めている。聞き耳を立てる趣味もないので、ストリアスはお茶でも淹れることにした。
こう見えて実は、お茶を淹れるのにはちょっとした自信がある。別に料理その他が得意ということではない。できるのはお茶だけだ。
色や香りから茶葉の状態を判断し、それに最適な湯の温度と泳がせる時間、そして容器の温度を見極める。それらを手際良く操って、お茶という作品ができあがる。その過程が専門の魔術で扱う、鉱物の精錬過程に似ている。と、ストリアスは思っている。少なくともそれが単なる彼の思い込みだけではないことはことは確かで、彼の淹れるお茶は魔術研鑽所でも好評だった。ここしばらく、そのことも忘れていた。
間を置いた割には、この時のできも中々のものだった。軽いひと作業を終えて、満足の行く香りが立ち上る。少しだけ機嫌よく、作品を盆に載せて店先に出た。
「あれ? 若旦那、今のお客様は?」
ただ、そのとき既に客の姿はなく、店主は後片付けをしているようだった。
「もうお帰りになりましたよ。詳細はこちらから先方にお伺いしてお話しすることにしましたから」
「ああ、そうですか。すみません、やることが遅くて」
何も考えずに茶葉と沸いた湯を容器に放り込んでしまった方が、できあがりは早いに決まっている。そうしなければ、急ぎの客には間に合わない。ただ、ファルラスとしてはむしろ、せっかちな客の方が悪いとでも言いたげな顔だった。
「謝ることではありませんよ。それより、折角いい香りがしているのを冷ましてしまってはもったいないですよ。いただきましょうか」
「はい、どうぞ」
という訳で、男二人でのんびりお茶。などという何となく不健康な気がする状態を防いだのは、また新たな来客だった。
「ああ、これはティア様、いらっしゃいませ」
「いらっしゃいませ」
立ち上がって会釈をする二人に対し、ティアもぺこりと頭を下げる。そして、一通の手紙を差し出した。例によってというべきか、包みにはファルラスの名前だけが簡単に記されている。
彼がそれを読む間、ストリアスはティアのためにもう一杯お茶を入れていた。さらにその時、また別の人物が入ってくる。
「遅くなりまして、申し訳ございません」
「いえ、こんな時間までご苦労様でした」
「お帰りなさい、エレーナさん。今お茶を淹れますね」
ティアはまた無言で頭を下げた。彼女に挨拶をしてから、エレーナはストリアスに向き直る。
「お茶でしたらわたくしが」
「たまには人の淹れたお茶を飲むのも面白いですよ、エレーナさん」
味をみたファルラスがそう言って彼女を座らせる。そして手紙をしまいながら、全員を見渡した。
「ちょうど良い機会ですから、まずはエレーナさんに報告をお願いしましょうか」
「はい」
そして彼女が語りだしたのは、先々日士官学校の演習庭で捕縛された人間についての、その後の捜査の状況だった。
あの夜最後にレンを人質に現れた中年の男、あれがグレスなのだという。不法侵入の他、殺人、誘拐の未遂等々の容疑で取調べを受けているが、本人はいざこざを起こした手下たちを止め、事態を平和的に収拾するためにやってきたのだと主張している。彼以下の証言も同様に罪を逃れようとするものだったが、それぞれが自分の身を優先しているから相互に矛盾することも多い。多少時間はかかるものの、特に主だった者達が処罰を免れるのは極めて難しいとのことだった。
なお、グレスが実質的な経営者となっていた店は、証拠隠滅のほか不正蓄財の疑いがあるなどとして閉じられている。そのまま潰れる可能性が高いという。
「働いていた女性たちはどうなります?」
他に行き場もないことが多いそうだ。そのことが少し、気になった。ティアもうなずいている。
「どうしてもその稼業が良いとおっしゃる方は仕方がないとして、それ以外の方の身の振り方は考えなければなりませんね。院長にも助力をいただくことにして、私も動いてみることにしましょう」
ティアが深々と、頭を下げた。ファルラスは笑顔を返す。
「まあ、こういう問題は急くと仕損じますからね。明日から腰をすえてあたるとしますよ。それでレンさんなんですが、無事お子様の所に戻られたそうです。これからがまた大変ですが、まずは温かく見守るとしましょう。ええと、ストリアスさん以下、この件に関して尽力をいただいた皆様には心からお礼を申し上げます、との院長の仰せです」
そして手紙を見ながら告げる。エレーナも、ストリアスを見やっていた。彼女も関わった一人だが、筆頭にストリアスの名がある以上彼が何か言うべき、とでも思っているのだろう。
「あ、いえ。僕なんかはお役に立てませんで」
こういう場面が苦手なのは良くないとは思うのだが、治す方法が思いつかないのだった。ティアは首を振ってから、笑ってくれる。それで余計に、気はずかしくなってしまう。
「えっと。あ、ええと、あの時、変な所を触ってしまって、申し訳ありませんでした」
そしてつい、よせばいいことを口走ってしまった。ティアは一瞬不思議そうな顔をしたが、やがて見る間に赤くなる。緊急のこととはいえ、彼女を塀の上に押し上げるためにストリアスがお尻を触ったのを思い出したのだ。そんな顔をされると、ストリアスとしても恥じ入るばかりで何も言えなくなる。
無理もないことだが、エレーナがほとんど睨むような視線を送ってくる。事情を知らずに今の言葉だけを聞けば、女性としては不快感を誘われるのも仕方のない所だ。
同じく事情は知らないはずだが、助け舟を出したのはファルラスである。
「まあまあ。ティア様も怒っていらっしゃらないところを拝見すると、ストリアスさんにも悪気はなかったのでしょう?」
「は、はい。それはもちろん」
このとき、ストリアスよりもティアの方が力一杯うなずいていた。確かに、不埒な行動に対して神の正義を実践すべき神官が抗議しないとすれば、それは不名誉なことだ。エレーナはまだ何か不審そうな顔をしているが、とりあえずもう追及はしないことにしたらしい。
「マーシェさんや、タンジェスさんほか士官学校の皆様には、追々こちらからお礼を申し上げておきますね。そろそろマーシェさんも、また学業の方に専念しなければならないというお話でしたから」
ファルラスが話の流れを修正して、ティアはもう一度頭を下げた。言われてみれば確かに、マーシェの姿が見えない。まあ、事件が解決したのだから当然と言えば当然である。頃合を見て自分から彼女をたずねてみようかと、ストリアスは思った。それにタンジェスにも、もう一度会っておいたほうが良いように思える。
そして頭を上げたティアは、ファルラスを正面から見据えた。
「お願いが、あります」
「修行のために、機会を見てわたくしどもの仕事を手伝いたいというお話でしょうか」
まだ全く内容に触れていないのにいきなり言い当てられて、ティアは目を丸くした。ただ、すぐに得心が行く。事後報告を兼ねた礼状だ、と彼女が院長から渡された手紙には、その旨よろしく頼むとのことが書き添えられていたのだろう。
ファルラスにしてみれば、一々口数の少ない彼女から聞き出すよりは、自分から言ってしまった方が早いという所らしい。
「お世話になった上、さらにあつかましいお願いであるとは承知しておりますが」
彼女にしては、珍しく言葉が多い。それだけ真剣なのだろう。ファルラスはうなずいた。
「なに、報酬はいらないとのお申し出を断る理由なんて、わたくしどもにはありませんよ。ねえ、エレーナさん」
「はい」
短い返答には、ここの経営状態に関する彼女の意見が凝縮されているように感じられた。
「というわけです。そう申し訳なさそうになさらないで下さい。必ずその機会があるとは申し上げられませんが、あなたにふさわしい件があれば、最優先でお願いすることはお約束いたします」
「ありがとうございます」
また頭を下げるその顔には、満足そうな様子と同時に決意も感じ取れた。そして不意に、ファルラスが手を叩く。
「ああ、そうそう。それで、ストリアスさん」
「何でしょう」
ここで自分に話が振られるとは思っていなかったので、ストリアスは少し驚いた。それに構わず、話が進められる。
「体の方はもう大丈夫なようですし、魔力も戻ったとうかがいました。今回悪質な犯行を防いだことですし、研鑽所へ帰参のお願いをしてみましょうか。この際院長の口ぞえもいただけると思いますが」
功績をもって罪を赦す、武官では良く行われることである。魔術師の場合前例がないので不確かだが、優秀な魔術師は優秀な武官と同様かそれ以上に貴重だ。
「ああ、ええと、僕は…」
言われるまで気がつかなかった。ただ、それで特に考えが変わってはいない。自分なりの結論は出しているつもりだ。しかしそれが受け入れられるかどうか分からなくて、少し口ごもってしまった。
「もうしばらく、こちらにいらっしゃるべきだと思います」
と、いきなりそんな声がする。とっさに誰がそういったかさえわからず、ストリアスはきょろきょろとしてしまった。女性の声だったのでやがてエレーナに視線が向くが、彼女も不思議そうな顔で首を振っている。
ようやく気がついてティアを見やる。彼女はじっと、彼を見ていた。
視線を交錯させたまま、沈黙が流れた。
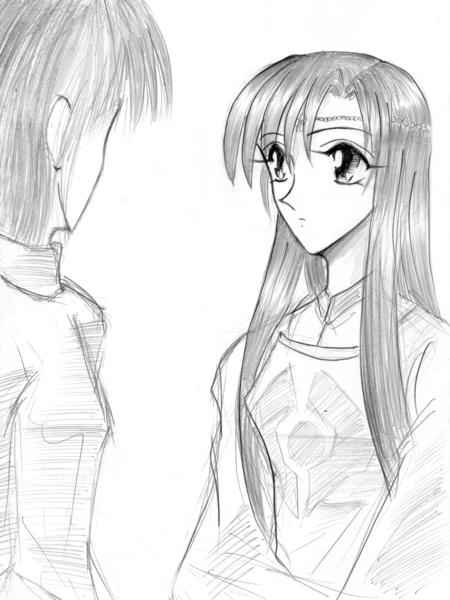
「ええと。ストリアスさんに異存がないなら、それも良いかと思いますが」
やがて声をかけたのは、ファルラスである。ちょっと苦笑しながら二人を交互に見ている。ストリアスは慌ててうなずいた。
「ああ、はい。よろしくお願いいたします」
自分ももっと、研究以外で色々と経験をつみ、また広い知識を蓄えた方が良いように思う。そのためには引き続きここで働くのがとりあえずは最良だと考えたのだが、自分のように研究以外に能のない人間をこれからも置いてくれるかどうか不安だったのだ。
ファルラスの言いようは渡りに船である。この際余計なことは言わずに乗せてもらうことにした。何やら自分の意志があまり重視されていないような気もするが、そういうことは気にしないのがストリアス=ハーミスの良さでもあるのだと思っておく。
ティアは大きくうなずいていた。どうして彼女が、らしくもなく急に口を挟んだのかストリアス自身にも良く分からない。とりあえず自分の内心を察してくれたのかなと、彼は考えていた。
ともかく、これでストリアスもティアも、引き続きこの茜商会に関わってゆくことになりそうだった。
一方、その頃。士官学校の学生用談話室では、マーシェが懸命に以前の授業内容を整理して書き記していた。見易さを損なわない範囲で流麗な、ある種お手本のような字だ。その向かいの席で、タンジェスは黙々と教科書を読んでいる。
談話室で黙って勉強、というのも別に珍しい光景ではない。元々ここは単に茶飲み話をするための部屋なのではなく、学業に関する話し合いのためのものなのだ。共同学習についての打ち合わせや、戦術、戦略論等に関する議論をしたりする。図書室の続き部屋になっており、資料を借り出すのにも便利である。
マーシェは正面のタンジェスを盗み見て、そして彼に聞こえないような極小のため息を漏らしてから作業に戻った。
それ以前に色々あったことは確かだが、一昨日タンジェスの機嫌が極めて悪かった直接の原因を作ったのは、彼女だった。間違いなく。
グレスらに人的数量の面で対抗すべく、あの日マーシェは学友たちに対し、自分と一緒に行動してくれる有志を募っていた。それに対して真っ先に応じたのは、他ならぬタンジェスである。元々彼女をファルラスに紹介したのは彼であるので、それなりの責任を感じたのだろう。
しかしマーシェは、その申し出を断った。他の学生はともかく、彼だけはまずい。
別に信頼していないわけではない。むしろ逆だ。元々の技量は確かで、それを鼻にかけない人柄の良さもある。それに停学している間に実戦を経験したらしく、それが以後普段の生活には落ち着きを、そして訓練時には他の学生にない気迫を与えているように見えた。ファルラスを紹介されて依頼を二つ返事かつ無償で引き受けたのも、明らかにはされないその変化の原因を、詳しく知る機会があるかもしれないと思ったからだ。
ただ、マーシェ以外の学生たちは深夜、閉門後に抜け出して合流する予定だったので、もし見つかれば何らかの処分を受けてしまう。基本的には反省文や訓練の過重などで済む微罪ではあるのだが、しかし停学が解かれたばかりの人間では話が違う。退学になるかもしれない。信頼する学友を失う危険は極力避けたかった。
タンジェスはその場では、むしろあっけないほど簡単に引き下がった。ただ、それをマーシェと、参加を承諾してくれた他の学生たち全員が不審に思った。おとなしくしているふりをして黙ってついてくる気ではないのか、そう考えたのだ。何しろ彼ら自身が教官の目を盗んで大挙外出する予定だという後ろ暗い部分があったので、やや他人が信じられなくなっていたのかもしれない。
その時タンジェスが実際にどうするつもりだったかは、本人にしか分からない。確かなのは、程なく先手を打ったマーシェらによって彼が拘束されてしまったという事実だった。この前習ったばかりの捕虜拘束法に従って縛り上げ、猿轡もかませ、例の城跡兼倉庫に放り込んだ。寒くなるといけないので、ついでに毛布巻きにしてやった。この作業に時間をとられたため、その日マーシェは自分が思っていたより遅い時間に茜商会に到着することとなったのである。
そしてこの方法も今の所謎なのだが、彼はその後拘束状態を脱出したらしく、普段学生たちが抜け出しとその帰りに使っている城跡脇の塀につながる道で、待ち伏せていたのだった。あの時マーシェがのこのこと現れていたら、また別の大騒ぎになっていたことだろう。
後で説得すればタンジェスなら分かってくれる、とマーシェは思っていたのだが、縛り上げられて長時間放置された人間には、別の見解があるようだ。翌日放課後、「話を聞こうか」の一言とともに彼女の前に立った彼は、正直な話恐かった。剣技ではむしろ彼女の方が強いのだが、それとは別の力関係の強弱があるとこのとき思い知った。その話し合いの結果が、今のこの状況なのだった。
談話室には今、二人きりだ。普通男女でそうしていると、学内での男女交際を禁じる旨の校則を踏まえたうえで、冗談になる範囲でからかうものが出る。しかし今日ばかりは、それが一切ない。
学友たちはマーシェの頼みに応じて校則違反の夜間外出をやってのける程度には友誼に厚かったが、今の彼女を見捨てるくらいには薄情だった。下手に割って入ろうものなら、今度はその人物がタンジェスの怒りを買うことになる。犠牲者は彼女一人で十分である。そもそもこの談話室にここまで空席が目立つなど、マーシェは初めて見る。全員、逃げたに違いない。
「な、なあ、やっぱりこういうことは…」
ふと、マーシェがつぶやくように言って手を止めた。彼女が整理しているのは、タンジェスのためのものである。彼が停学していた間の遅れを取り戻すための、手伝いだった。元々彼女自身についてはきちんと授業を聞いて理解して、その上で必要と思われる点については記録を残しているので、談話室に来てまで作業をする必要はほとんどない。
「ふうん」
タンジェスはそれだけ言って、完璧に表情を消した視線を向けた。そして、それを足元に落とす。
「やっぱり、こっちの方がいいかな」
マーシェはすぐさま、力一杯、首を横に振った。それだけは、やはり勘弁してもらいたい。タンジェスはまた教科書に視線を落として、まるで他人事のように熱のない口調で言う。
「じゃあ、それを続けた方がいいと思うけれどね」
渋々、マーシェは作業を続けた。タンジェスの足元の鞄には、勉強道具一式のほかに、荒縄と猿轡が入っている。「俺と同じ目にあうのと勉強を手伝うの、どっちがいい?」というのが、彼の主張だった。マーシェは瞬間的に、思わず後者を選んでいた。後悔しないではないが、しかし前者ではもっと後悔したような気もする。
お嫁にいけなくなってしまう。
そんな恥辱を受けたとあってはこの先騎士として、軍人として生きていけない。などというより、まず思いついたのはそんなことだった。事実はともかく、変な噂が立ってしまってはまだ見ぬお婿さんに嫌われてしまうかもしれない。そう心底心配している。
この国でも他国でも女性の武官はごくごく少数である。士官学校に行くと言い出したときには「嫁の貰い手がなくなるぞ」などと言って思いとどまらせようとした知人も少なくない。それを覚悟で受験して、しかも難関と呼ばれる試験を楽々突破した彼女であったが、今は希望を捨て去ってはいなかった。
男女交際は学内で禁じられているだけなので、故郷に恋人や許婚を残している、あるいはこの王都に来てから恋人を作った、などという男子学生は結構いる。この前発覚したことだが、同じ学年で既に妻子もちの奴がいた。男どもがそれなりに「人並の幸せ」というものを掴んでいるのに、女だからというそれだけの理由でそれができないのは不公平だ、と思う。それもこんな美人が、などと結構本気で考えている。
絶対幸せになってやる! という決意とともに、結局資料の整理を続けるマーシェだった。
そんな彼女の内心に現在そもそも興味がないタンジェスは、ただじっと教科書を読んでいた。士官学校には留年などという生ぬるい措置がなく、不適格者とみなされれば退学になりかねない。そのため彼の興味は今、もっぱら次の試験を無事乗り切れるかどうかに注がれているのだ。
ちなみに彼の見解によれば、特にマーシェのように体力も気力も十分にある「活きの良い」人間を本気で拘束するなら、縄より鎖の方が良い。
ともかくも、とりあえず表面上、士官学校を含めてこの日の王都の夜は平和裏にふけて行った。
王都家出人調書 了
↑
この作品を登録していただいている小説検索サイト、
「NovelSearch」のランキングへの投票ボタンとなっています。
もしこの作品を気に入っていただけたのなら、一票を
投じていただきたいと存じます。
なお、連続投票や30日以内の同一作品への再投票は
禁止だそうですので、投票なさる場合はその点に
おきをつけ下さい。