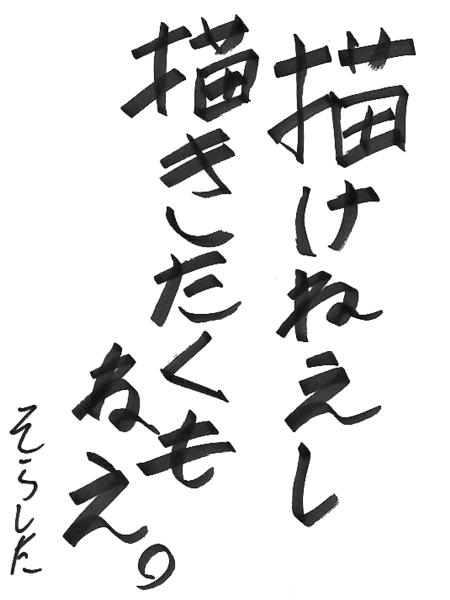
正しい同人誌即売会の過ごし方(?)
17 分かりやすい待ち合わせ時刻を指定しておきましょう
先行き不安ですっかり鬱になってしまった裕也を、まあ何しろ彼であるので光樹はフォローしようともしなかった。さらにそれをしてくれる可能性のあった美月に話しかけて、救われる道を完全に閉ざしてしまっている。
「所でこれは、どこへ向かっているんだ」
「あ…」
美月のあいた口が、塞がらない。おしゃべり好きで、また熱中すると他の事が見えなくなる。その性格が見事に悪い結果を招いてしまったようだ。普段だったら裕也が気をつけてやったりもするのだが、このばではそもそもどこに何があるのかを把握していなかったので、それも不可能だった。
「本当にもう、こいつは」
「ごめんごめん。それじゃあ、ええと…」
美月がカタログを取り出す。しかし結局行き先を指示したのは、光樹だった。彼の方がやはり、地図を読む能力に優れているのだ。
「印のつけてあるところへ行けばいいのだろう。ここから最も近いのはこの印になるが」
「うん、そうだけど、売り切れる可能性のある壁サークルから回らないと」
「ならあの先だ」
本当に早い。造りの同じホールが並んでいる上、人通りが多く見通しが利かないのだが、迷うそぶりすらない。カーナビばりの能力を通り越して、軍用の高性能火器管制コンピュータのようだ。どうも複数の目標を同時に捕捉できるらしい。現にミサイルを積んだりできれば恐るべき存在になるが、そうでないのが世のため人のためかもしれない。
「あの先って…うーわー、マジかよ」
しかし一瞬で、ミサイル搭載型の方が良かったのではないかと思えてくる。近寄ることさえ恐ろしい障害物が、そこには立ちはだかっていた。できればなるべく遠くから、排除したい所だ。
それは人の壁だ。凄まじいまでの人数が密集して、進路を塞いでいる。いや、良く見れば微妙にうごめいているのが分かった。何か巨大な生物の内臓、とでも形容したほうが適切かもしれない。
しかも、である。それを構成している人間のほぼ全てが、男なのだ。少なくとも裕也が見渡した限りにおいて、女性らしき人影は見当たらない。あるいは背の低い人が群れの中に隠れているのかもしれないが、しかし目を凝らして探すことはためらわれた。むしろできれば、目をそらしたい。
何しろぱっと見ただけで、彼らのシャツが汗でべっとりとぬれていることが否応なしに分かってしまうのだ。この暑いのに密集しているのだから、当然といえば当然である。むさくるしいことこの上ない。それにこれは偏見かもしれないのだが、普通に町で見かける同年代の男性と比較して、平均体重が重いように見えた。あるいは逆に極度にやせた人間もいるが、そんな男に限って手入れが行き届いているようには見えない長髪を、無造作に束ねていたりする。
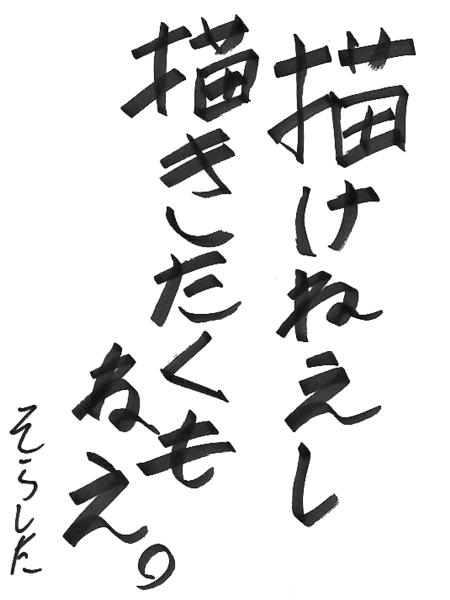
「うひゃあ、ダンマクだあ」
美月が肩をすくめる。裕也は思わず聞き返した。
「弾幕?」
それはそれこそ光樹の…もとい、現代戦では高性能なレーダー、コンピューターシステムのバックアップのもと、味方を守るために展開される火力の壁のことである。時代をもっと遡ると、とにかく撃ちまくって敵を寄せ付けない、という作業になる。
裕也は光樹ほど軍事には明るくないのだが、流行りの漫画がその種のシステムを搭載した艦船が中心になるストーリーだったため、覚えていた。また、確か昔見たアニメの登場人物の中にも、それが薄いのどうの言っていた人がいたように思う。
「んー、裕也が言ってるのは弾丸の幕のことでしょ。『弾幕薄いぞっ! なにやってんの!』って奴」
「それそれ」
確か件の漫画は美月も読んでいたはずだ。裕也は友人から単行本を借りて読んだのだが、彼女が興味を示したので、所有者の許可を取って転貸した覚えがある。しかし彼女はアニメの方をより強く覚えているようだ。
「ここでダンマクっていったらそりゃあ、男の膜のことよ。あ、マクは布じゃなくて、生物の内臓の、にくづきで書く方ね」
「うげえ」
何か考える前に、思わずそんな声をあげてしまう。内臓のような印象を持った人間は、どうやら裕也の他にもいたようだ。
「まあ、当然ながらローカル言語だから、表記が決まってるわけじゃないんだけどね。男は一緒でも、布の方の幕で書く人もいるし」
「気休めにならねーよ。これから焼肉や焼き鳥やモツ煮込みを食いづらくなることには変わらないだろうがっ!」
裕也には基本的に、嫌いなものがない。焼肉ならカルビからぎあらまで、何でも食べる。特にビールを飲みながらの場合、普通の肉の合間にモツをたべると実に旨いのだ。焼き鳥も、始のうちはネギ間や手羽先など普通のものを頼むのだが、酒が回ってくると次第にレバーやらミノやらが欲しくなってくる。そして居酒屋のモツ煮込みも、これがまた中々のものである。
どれも別に大した素材や、味付けではない。少なくとも自分たちがいつも行くような安い店でのそれに、始めから期待もしていない。それは頭では百も承知だ。しかしあの雰囲気で、そして酩酊感の中で食べるあれが、旨いのだ。
その楽しみを、全く奪われそうな勢いだ。
「そんなこと言ってもさあ。例えば牛タンって、良く考えたら死んだ牛とこれでもかとディープキスを…」
美月がむくれて反論する。それにしてもゼミの親睦会として彼女と一緒に焼肉に行ったこともあるのだが、彼女は何よりネギタン塩がお気に入りだったはずだ。
「止めんかっ!」
とりあえず、軽くではあるが小突いて黙らせる。これ以上気持ち悪くさせられたら、冗談抜きで吐きそうだ。
「論点がずれている。行くか戻るか、どうする? 少なくともここで立ち話をするのは得策ではないな。あの光景を見続けるし、通行の邪魔にもなる」
そしてここは、光樹が正論を吐いた。表情こそ変わっていないが、発言内容から判断して彼としても長居はしたくないらしい。
美月がこくこくとうなずいてから、答える。
「あたしは行くよ。どうせ会場内での移動にはあれがつきものだって、始めから覚悟してるわけだし。ただ、裕也と光樹くんについて来いって無理強いはしないけど」
「私も行く。さっさと済ませてしまおう」
言い捨てて、まず光樹が歩き出す。美月は少し慌ててその後を追った。
「あーもう、しょうがないなあ」
ため息をついてから、裕也は長い足を生かして追いつく。そしてむしろ、二人の先頭に立った。
「はい、ちょっとごめんなさいよ!」
危険にならない程度の強引さで、人波を突破してゆく。時折明らかにべっとりとしている人肌に触れることもあったが、一々気にして立ち止まっては、接触時間を増やすだけだ。気合で切り抜けるしかない。
そしてその後にできた狭い通路を、美月がするすると抜けてゆく。光樹は最後尾で、再び狭まろうとする人の壁が美月にぶつかるのを防ぐ役割を果たしていた。
「さーん、きゅうっ!」
最早裕也の中では悪名高きものとなった「男膜」を抜けるなり、ぽん、と美月が裕也に対してハイタッチをする。もっとも「ハイ」と言っても身長差がかなりあるので、裕也としては軽く上げた手に、彼女の手が触れた程度である。
あれほどその辺の連中には肌と肌で触れ合いたくないと思っていたものが、少なくとも美月に対しては特になんとも感じないのが、少なくとも理屈の上では不思議だった。感覚としては、当然ながらその通り、である。
そして美月は、光樹に対しても手を上げる。彼はぎこちないしぐさで、それに応じていた。
「いやあ、裕也ったら凄いね、実は。どうしてあんな大群衆を、簡単にかき分けられるの?」
「別に簡単でも何でもないぞ。俺だけじゃなく本人もあの混乱状態じゃあ気づいてないだろうが、実は肘やら何やらが当たって後で青あざができたりして」
「そ、それはどうよ」
さすがの美月がひるむ。そこで裕也は、笑ってごまかした。
「ははは。実際多分、大したことにはなってないよ。臨時バイトでコンサートの整理スタッフとかやったことがあるから、分かるんだ」
それはまあ、確かに。大したことではない。裕也はそう、経験から学んでいた。
何しろ、お互い様なのだ。極度の混乱状況では自分が相手を負傷させたとしても、逆に自分が負傷していたとしても、かなりの重傷でない限り気がつかないものである。
そこそこ高い日当をもらって帰宅した後で、自分の体にできたあざを見て愕然としたことがある。その後で果たして割に合ったのだろうかと、考えてしまう自分が少し情けなかった。さらに、金銭的な事情からやむを得ず結局もう何回か同じ仕事を引き受けてしまっては、くりかえし同じ感想を抱くはめになった自分という存在はもっと情けなかったのだが。
「止まってる、あるいは動いているにしてもゆっくりの人間の集団は、実はそんなに怖くないんだ。何しろ大人数だから目の前にすると正直びびるけど、でもそれを悟られないようにちょっと強めに当たれば、大概向こうが引いてくれる。なんだかんだ言って、相手は押しに弱い日本人だからね」
「じゃあ、速く動いてる人間の集団は? それこそさっきの開幕ダッシュ、みたいな」
「俺だったら抵抗せずに逃げるねえ。怒鳴りつけてたスタッフの人は、正直勇敢だと思うよ。押しに弱いっちゃあ押しに弱い日本人だけど、それはお互い同士に押されている、要するに一丸になって行動しているときは、洒落にならないから」
それこそ、先程美月と光樹の二人が話していたように、本気で止めるのならば銃火器を使うしかない。例えば機動隊でさえ、暴徒が突進してきたら正面からは相手にしないのだ。うまく誘い込んで、特に先頭を切って突っ込んでくるような悪質な人間だけを確保する。そんな光景を、いつか何かの大規模なお祭りに関するニュース映像で見た覚えがあった。
裕也がアルバイトをしたのは男性アイドルグループのコンサート、つまり客のほとんどが女性であったのだが、それでも初回でなめてかかっていたら青あざだらけという目にあっている。一対一なら相手は女性なのだからという配慮ができるのだが、それが突進してくる群集となるともう、考えるだけ損である。事態を決するのは、純粋に物量だ。性別は大した要素ではない。
「なるほどねえ」
一通り感心してから、美月は視線をやや遠くにやった。
「やだ。あっちはあっちでけっこう並んでるなあ」
「それでもさすがに、客層が何となく『大人しい』けどな」
別に、他の所の客層が乱暴などと言っているつもりはない。「男膜」を構成している人々も、それはそれで大人しく列を成している。逆にある程度そうでなければ、それは言わば「濁流」になってしまって、「膜」にはならない。
しかしともかく、美月が見ているところの列は、どこか雰囲気が比較的ではあるが穏やかなように思えた。光樹が珍しく、特に論評を付け加えるでもなく、ただ単純に賛同してうなずいている。
「まあね。さすがに、エロじゃないし」
ひらひらと手を振ってから、美月は少し考えた。
「んー、でも、どうしよう。予想外だなあ。勢いで連れて来ちゃったけど、並ぶのにはつきあってもらっても、意味がないのよね。無関係の人がいると列整理の邪魔にもなっちゃうし」
「なら私は、少しそのあたりを見て回ってくる。合流は先程の君のスペースでいいな」
美月が考える時間をとる前に、光樹が即答した。当然ながら、彼女の反応は少し遅れることになる。
「ん。それもいいけど、できるなら正午にまたここで。三人で一緒に行きたい場所が、他にもあるのよね。合流に失敗したら、スペースに戻るってことで」
「分かった」
「あ、そうだ。それなら今のうちに、あれを渡しておくね」
美月が鞄の中から、カタログを取り出す。そしてそこに挟んであった一枚の紙を、光樹に手渡した。
彼は軽くそれに目を通してから、すぐにうなずく。どうやら、あるいはさすがは、と言うべきか、ごく短い間に情報を正確に処理する能力があるらしい。
「じゃあ、俺は、どうしようかな」
光樹が予想外に手早く行き場所を決めてしまったので、裕也としては行き場を失ってしまった。それを見た美月が、すぐに指示を出す。
「あー、えっとね。迷うようなら裕也、できれば光樹くんと一緒にいて欲しいんだけど。ばらけたらそれだけ集まりにくくなるし、裕也は携帯持ってるじゃない。正午ごろなら少しは、混線も解消すると思うの」
「しょうがない。じゃあそうしよう」
別に光樹についていくのが目的なのではない。それを確認したうえで、裕也はうなずいた。あるいは美月ならば光樹の携帯電話の番号を知っているかもしれないと思っていたのだが、彼女の口ぶりを信用する限り、光樹はそもそも携帯電話など持っていない、今時にしては珍しい学生だと考えたほうが良さそうだ。
「悪いな」
「別に、お前に謝ってもらわなきゃならないことでもない。美月に頼まれたから、やっているだけだ」
彼の口からそんな台詞を聞くことができるとなどかけらも思っていなかったので、逆にそっけなく、裕也は答えてしまう。それに対して反論するでもなく、光樹はうなずいた。
「そうか。なら遠慮はしない。行くぞ」
「おうよ」
すたすたと歩き出す光樹の後ろへ、裕也は美月に対して軽く手を上げてからついてゆく。美月は同様に軽く返してから、すぐに目当ての行列の後ろへと並んだ。
続く