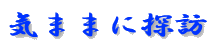 「蔵の町並み 須坂」 (2)
「蔵の町並み 須坂」 (2)<<<Back Next>>>
 ■「蔵の町並み」
■「蔵の町並み」 江戸時代は、須坂藩主堀氏の館町(陣屋町)として、また大笹街道の追分の地として、数々の商取引が行われました。
その後、明治から昭和初期にかけて近代製糸業によって繁栄し、今も豪壮な土蔵造りの旧製糸家建物や繁盛した大壁造りの商屋などの町並みが残されており、蔵を生かした商店、博物館、美術館など当時を偲ぶことができます。








 ★蔵と倉が混在の蔵の街
★蔵と倉が混在の蔵の街製糸工場では原料となる繭を農家と契約してはきたてた繭を土蔵に保管していました土蔵は乾燥し温度も安定し繭が成虫になるのを遅らせるため適しており、この様な3階建ての蔵が街のあちらこちらにありました。
製糸工場からバトンタッチした電子部品工場も精密部品の保管に適していることで現在でも使っている所もあります
須坂には武家屋敷や商店の土蔵のような年代の古い蔵と大正昭和の初期の製糸工場の繭倉が混在して蔵の街を形成しています。
 ★豪商の館 田中本家 (国の登録有形文化財指定)
★豪商の館 田中本家 (国の登録有形文化財指定)江戸中期・享保18年(1733)初代新八は、現在の須坂市で穀物、菜種油、煙草、綿、酒造業などの商売を始めました。 代々須坂藩の御用達を勤めるとともに、名字帯刀を許される大地主へと成長、3代と5代は幕末には士分として藩の財政に関わる重責も果たし、その財力は須坂藩をも上回る北信濃屈指の豪商となりました。今は博物館として一般公開をしています。



 ★ ふれあい館まゆぐら (国の登録有形文化財指定)
★ ふれあい館まゆぐら (国の登録有形文化財指定)ふれあい館まゆぐらは、現在地から南東に約180メートル離れた立町に、明治期に建てられた三階建ての繭蔵を移転・改修したものです。 都市計画道路の整備により解体を迫られたこの建物を、製糸業で栄えた須坂の歴史を後世に伝える歴史的に貴重な建築物として曳き家移転を行い、保存再生しました。
 ★ふれあい館くらふじ (国の登録有形文化財指定)
★ふれあい館くらふじ (国の登録有形文化財指定)もとは旧須坂藩の奉行だった浦野氏が建てた住宅で、そこを買い取り、病院を開業しました。主屋は明治初めの建築で、武家住宅の伝統的様式がみられます。診療室のあった洋館は土蔵造りですがデザインは洋風のモダンな建物です。庭は公開していますが建物の中は一般には非公開、会議などに利用可能です。