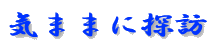 [千曲市博物館めぐり] 蔵し館 (1)
[千曲市博物館めぐり] 蔵し館 (1)<<< Top Next>>>
 ■蔵し館
■蔵し館 長野県千曲市稲荷山
蔵し館は明治期に生糸輸出で栄えた「カネヤマ松源製糸」の松林源之助・松林源九郎が築いた「松林邸」を修復・再生した建物です。
稲荷山は当時、北国西街道稲荷山宿と最大の宿場町であり荷物の集積場として古くから発展した街です。
明治になり繭・生糸の集散場として発展し、県内有数の商都として栄えましたが、その当時の生活や稲荷山の歴史を展示した資料館です
■蔵の街 稲荷山
711年(和銅4年)更級の里に養蚕を伝えた京都山城の泰氏にならい稲荷を祀り(治田神社)それが町の語源。
1582年(天昇10年)上杉景勝稲荷山城を築き人々を住まわせ町が形成される
1804年(文化1年)養蚕が盛んとなる。
1847年(弘化4年)の善光寺地震では、長野だけではなく稲荷山宿でも大火となり木造家屋が殆んど焼失。
1880年(明治13年)生糸の輸出高が群馬を抜いて全国1位となり経済の中心地となり現在の八十二銀行の前身六十三銀行の本店が開設され稲荷山町が商業の全盛期を迎えた。
1888年(明治21年)信越線屋代駅、明治23年篠ノ井線稲荷山駅の開業でメリヤス産業が盛んとなが大正12年の関東大震災、昭和初期の生糸の価格が暴落により衰退となる。
善光寺地震稲荷山大火で殆んどを焼失し耐火造の土蔵に建て替え現在も町のあちこちに、繁栄をきわめた頃の土蔵造の町屋や、生活用水として町中に縦横に巡らせた水路・水濠の跡をみることができます。
展示パネル及びパンフレット参照







◆案内図
長野道 更埴ICから車で10分
電車 しなの鉄道屋代駅からタクシー10分
バス 更埴地域循環バス 姨捨線・太田原線
バス停「本八日(もとようか)」下車 徒歩5分