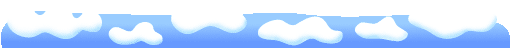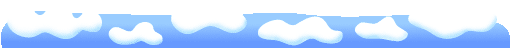音楽評論あるいはエッセー
ぼくの好きな作曲家
ぼくは、「作曲家の中ではだれが好きですか?」と聞かれると、「好きな作曲家はたくさんいますが、一人挙げるとしたらモーツァルト、三人挙げるとしたらバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンです。」と答えることにしている。たいへん平凡な答えだが、多くの人はこれでぼくのことを普通の趣味だと思うようで、満足してくれる(もしブルックナーだと答えるとクラシックのマニアだと思われてしまう。実際マニアなのでそのように思われても構わないのだが、上記の三人の名前を挙げる方が無難だということだ)。
しかし、ぼくの本音を言うと、好きな作曲家は九人である。それは上記の三人に加えて、ハイドン、シューベルト、ショパン、ブルックナー、ブラームス、ドビュッシーである。九人だと区切りが悪いので、もう一人これら九人に匹敵するくらい好きな作曲家ができて10人になるとちょうど良いのだが、今のところヘンデル、マーラー、ラヴェルが横一線に好きだが上の九人ほど好きではない。従って好きな作曲家をちょうど10人にするのはちょっと困難だ。
一般にはチャイコフスキーが好きという人が多いようだ。ただぼくはチャイコフスキーやドヴォルザークなどいわゆる民族楽派の作曲家は、なぜか野暮ったいような気がしてあまり好きになれない(ただしシベリウスだけは例外的に好きだ。シベリウスはブルックナーを尊敬していたそうだが、確かに彼の交響曲を聴くとブルックナーに通じるものが感じられる)。もっともこれは現時点での話であって、ぼくも10台の頃はご多分に漏れずチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番に大感動したし、ドヴォルザークのチェロ協奏曲が好きだった頃もある。
ぼくの好きな演奏家
これは難しい質問だが、答え甲斐のある質問だと思う。好きな演奏家は曲によって違うし、また年齢を経るに連れて変わってきてしまう。
しかし一般論として、ぼくの好きな演奏家は、指揮者では年齢順に、ワルター、バーンスタイン、ジュリーニ、アーノンクール、ピアニストではバックハウス、ルービンシュタイン、アラウ、リヒテル、ブレンデル、アルゲリッチ、ピリスと多く、ヴァイオリニストではミルシテイン、フランチェスカティ、クレーメル、チェリストではカザルス、フルニエ、マイスキー当たりになると思う。何か支離滅裂のようだが(例えば、ワルターとアーノンクールは正反対のスタイルの演奏をする)、音楽を含む色々な分野でまるで個性の異なるものが好きになることは、別に珍しいことではないと思う。
自分の例で挙げると、絵画では、セザンヌの「サン・ヴィクトワール山」とカンディンスキーの抽象画は油彩画であるということ以外に共通点はないといってもよいくらい違うが、ぼくは同じ位大好きだ。、そしてそのことを不思議がる人には今まで出会ったことはない。
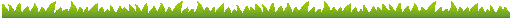
朝比奈隆、93歳のブルックナー
2001年7月25日、東京・サントリーホールで、朝比奈隆指揮大阪フィルの東京公演を聴いた。曲はブルックナーの第八交響曲である。朝比奈は今年で93歳。半世紀以上にわたり大阪フィルの音楽監督を務めている。朝比奈を生で聴くのは今日が最後になるかもしれない、そう思いながらサントリーホールに足を運んだ。
当然の事ながら、会場は満席だった。客層を見ると、男性が女性よりも多いが、男性ばかりというほどでもなく、また若い人が少ないという
こともない。意外にバランスが取れている、と思った。というのは、いわゆる朝比奈ファンというのは、中高年の男性が大半というイメージを何となく持っていたからだ。
さて大阪フィルの団員が入場した後、朝比奈が舞台に登場したが、非常に元気そうに見えた。昨年来日した88歳のギュンター・ヴァントは、指揮台に向かって歩いて行く際に介添えの人
がついていたが、朝比奈には、介添えの人はおらず、しかも背筋をピンと伸ばして普通人と同じ位の歩調で指揮台に向かって堂々と歩いていく。本当に93歳なのだろうか?少なくとも10歳若く見えた。指揮台でも座ったりせず、普通の指揮者と同様立ったままである。
演奏の方だが、テンポが意外に早かった。朝比奈の場合、老人特有のユックリズムはないようだ。そしてここまで読まれた読者ならもうお察しになると思うが、演奏そのものは良くなかった。まず大阪フィルの音が美しくない。弦楽器もそうだが、特に木管・金管の管楽器の音が悪い。
演奏そのものも、音が全体的に大きすぎ(最初から最後までフォルテ、フォルテッシモだらけだった)、テンポに緩急をつけなさすぎ、クレッシェンド等も非常にワンパターンだった。要するに典型的なダメ・ブルックナーなのである。ぼくの隣席の男性(40代くらいのもサラリーマン風の方だった)はそのように感じたのか、演奏が終わった後も拍手をしなかった。