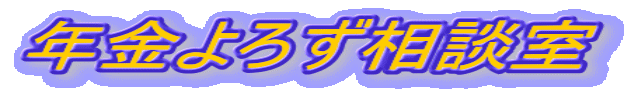A.平成26年度における年金制度の詳細
①特例水準から本来水準の年金額へ
特例水準で2.5%高く支給されていた年金を解消するため、平成25年10月分か
ら1%減となりました。平成25年12月15日の振込から減額となっています。さら
に平成26年4月分から1%減となります。
重ねて平成27年4月分から0.5%減となり、平成27年4月分からは、本来水準
の年金が支給されることになります。なお、平成25年1月~12月の対前年物価変動
率によっては、26年4月から物価スライドによる改定もあるかも知れません。年金を
受けている方にとっては、「年金が減っていく・・・」が実感ですね。
②国民年金の保険料
26年4月から ・・・ 15,250円
(16,100円×0.947)
25年4月から26年3月まで ・・・ 15,040円
(15,820円×0.951)
③消費税8%引き上げに連動して施行
◎繰り下げ支給の取り扱いの見直し(平成26年8月までに)
70歳の数ヵ月後に繰り下げ支給の申し出を行った場合、今までは5年の時効により
申し出のあった翌月以降の年金額が、支払われていたのを70歳に遡って申し出があっ
たとみなして支払うことになりました。
◎未支給年金の請求範囲の拡大(平成26年8月までに)
今までの請求範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でしたが、施行後は
生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配信者等に拡大されます)
◎遺族基礎年金の父子家庭への支給拡大(平成26年4月)
今まで遺族基礎年金を受けられるのは、その人によって生計維持されていた子(18
歳未満)と子のある妻でした。国民年金の第1号被保険者である自営業家庭の場合、妻
が亡くなっても夫には遺族基礎年金は支給されなかったのです。「妻」の文言を「配偶
者」に改めることになり、子のある夫に遺族基礎年金が支給されるようになります。
支給要件の男女差解消の一つと言えるでしょう。
ただし、国民年金の第2号被保険者の、被扶養配偶者である第3号被保険者が亡くな
った場合については、今後の政令等で対応される予定です。
(社会保険労務士・後藤田慶子)