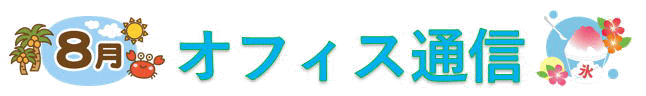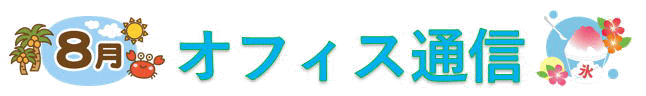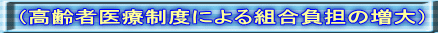
大企業等の健保組合は、保険料率の設定、法律よりも上乗せの給付、疾病予防のための保
険事業等、独自の取り組みが可能であるため、組織の中の経営努力がそのまま反映しやすい
ことが最大の利点とされてきました。
これにより健康度が増し、医療費下がり、組合の負担が減り、結果保険料率を低く設定で
きる優良な保険集団として機能してきました。
しかし、現在健保組合の経営は悪化しています。
平成29年度は1,400組合のうち4割以上が、支出が収入を上回る赤字状態となりま
した。
高齢者向け医療費の増加を、現役世代が加入する被用者保険からの拠出金で賄われること
になったからです。
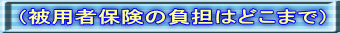
健保組合全体の19年度の平均保険料率は9.218%ですが、中小企業が加入する協会
けんぽの平均の保険料率である10%を上回る健保組合は302組です。
10%の維持は協会けんぽの大目標ですが、維持が困難になるかもしれません。
医療費の伸びを年間1.8%とすると、協会けんぽの保険料率は22年度で10.3%、
25年度で10.9%となり、これを上回る健保組合は解散の可能性が高くなります。
ただし、昨年解散した健保組合の平均保険料率は協会を少し上回る10.26%でした。
健保組合には独自の付加給付なども考えられるため、協会の保険料を超えたから即解散とい
う訳ではありませんが…。
仮に、すべての健保組合が解散となり、加入者が協会けんぽに移行した場合、協会には給
付費の16.4%の国庫負担があるため、国庫負担は6,300億円ほど増加することにな
ります。
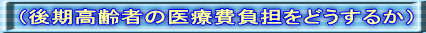
健保連は団塊の世代が後期高齢者となり、拠出金負担が急増する「2022年危機」向け
高齢者医療費の負担構造改革に取り組み、現役世代の負担軽減に併せ、医療費の適正化や保
険給付範囲の見直しなどの施策が不可欠としています。
介護納付金の増加の問題もあります。納付金が被保険者1人当たりの人数から収入に応じ
た負担制度となり、19年度では初めて10万円を超え、22年度には13万4,823円
にまで達しました。
医療や介護に要する負担増は、実質的には「隠れ増税」でもあり、このままの状態が続け
ば健保組合はいっそう厳しい状況に追い込まれるでしょう。
これからの日本、後期高齢人口が急増する一方で、現役世代の減少する社会となるのは明
らかです。
16年度における後期高齢者の医療費はそれ以外の若者の4.3倍であり、75歳以降で
は生涯医療費2,700万円のうち40%の1,063万円を消費することになります。
そのためには医療費の適正化や健康づくりなどの施策も大切ですが、安定財源の確保が最
も大事です。
増加する高齢者の医療費を誰がどのような形で負担するのか、国民全体が医療保険全体の
給付と負担について考える必要があります。
(2019年6月18日労働法令通信より)

(社会保険労務士・後藤田慶子)
|