04�N1��3���@���Y�H�|�i2�j�̋L���X�V
�@�X�p���u���̑��ɂ��āA�^�C������������炢�܂����̂ŋL�����X�V���܂����B�@�@�ւ̑��̂Ƃ���ł��B�@�@�ւƂ͕����̒��ŁA����|���P�i�����j�̏ے��̗ցi�z�C�[���j�ł��B�@�^�C�ł͉~�Ռ^�̂��̂����������܂��B�@�i���N�V�[�E���[���h
���^�C�̂������`�F���}�C�Q�Ɓj�@�o���R�b�N�̃i�V���i���E�~���[�W�A���̓�K�ɂ���������܂����B�@�����̉~�Ղ͖͗l���֑ɗ��̂悤�ł��B�@�֑ɗ��Ƃ͕��̐��E���G�ɂ������̂Łi�ڍׂ͎��T�ȂǂŒ��ׂĂ��������j����ύׂ��ȊG�ɂȂ��Ă��܂��B
04�N1��1���@04�N����낵��
�@2004�N�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�@���N����낵�����肢���܂��B
03�N12��19���@�J���[�s�u�\������
�@�����V��������������B�@�킴�킴�V�������̂�T���ɍs���Ȃ��Ă��A�V�������Ɓi����̗���j�͌������������Ă���B�@�^�C�̃q�b�g�f��u�X�b�E�o���K�`�����v�i��1�j��VC�c2���g�݁AVCD�Ȃ���{�ł�������A�Ƌ��N�^�C�Ŕ������B�@�ȑO�A���{�̃v���[���[�ɃZ�b�g����ƁA�h�����ɂȂ�܂���h�i��2�j�ƕ\�����ꂽ�B�@���ۂɌ���Ȃ��Ɖ������B�@���������~�߂ƍl���Ă���PC�ł����S�Ɍ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B�i���̗��R�͕s���j�@���S�o�[�c���̂Ă��Ǝv���Ă����Ƃ���A���R�������č���͂����ɂȂ��悤�ɂȂ��Ă���B
��1�j�@�X�b�͐킢�B�@�o���K�`�����͒n���B�@�q�����J�^�J�i�\�L�ł́A�X�b�g�E�o���O���`�����Ƃ��������������邩���m��Ȃ��B
��2�j�@���E�ɃJ���[�s�u�̕\�������͂R�A���{��NTSC�A�^�C�͂o�`�k�iPhase
Alternation Line�j�����B�@����SECAM������B�@���{�Ɠ��{�͌݊����������B�@�̂̃^�C�ݏZ���{�l�͓��{�̃r�f�I�����邽�߂ɁA���{�̃r�f�I�E�f�b�L��TV���^�C�Ɏ�������Ŏg���Ă����B�@�d����220V����100V�ւ̕ϊ��@�Ă��B�@�i���͂ǂ����m��Ȃ��B�j�@���{���瑗���Ă���r�f�I���B��̓��{��ԑg�ł������B
�@�ʔ̓d�C���A�G���L�e���i�����j�ŕ������Ƃ���ADVD�̏ꍇ�̓J���[���������łȂ��A���[�W�����i�n��j������A���{�̏ꍇ�͑S�ĂQ�A���[�W�������Ⴄ�ƌ���Ȃ��炵���B�@�������A���̃e�̕��͓��i����+�@��ʋ@�\�ɂ���āA���삳���Ă݂Ȃ��Ɖ���Ȃ��B�@�r�f�I�E�f�b�L�����ẮA�u���j�o�[�T���^�C�v���A�ǂ̕����ŋL�^���Ă����Ă����{��TV�Ō�����v�A�ƕ����A�₪�ẮA�u���̃r�f�I�f�b�L�͑S�����j�o�[�T������Ȃ��́v�A�Ƃ������B�@���ێЉ�i��ł����A�ϊ��@�\�̑I�����炢�ł���d�g�݂ɂ��Ă��炢�����ł���ˁB�@������1�Ő��E���������L�^�}�̂̓J�Z�b�g�E�e�v���R�[�_�[���炢�ł��˂��B�@����̂ɂ����i�������I���Ă��Ȃ��B�@�t�B���v�X�͓���������炸���E���ʉ����v�����B�@�̂��B�@
���Q�lWEB�T�C�g��
�@���E�̃J���[�����@�E�E�@���ʕ����ꗗ
http://www.interq.or.jp/blue/rhf333/TV-FORM.HTM
�@DVD���[�W����
http://www.fantasium.com/code.asp
���E�̓d������@�E�E�@���ʓd���̃v���O�`�E���g���E�d���@
http://homepage1.nifty.com/spur2000/doc/trip/power.htm
�@�ǂ����ē��{��2�̎��g�������邩�ɂ��āA���w�Z�̂Ƃ��搶���b�����B�@��������ɓ��{�œ����������d�@�̐��Y�����֓��E���ň�����炵���B�i���̃Z���Z�A�]�k���D���ł����Ȃ��B�@�������D���ł����B�j�@�@�����ׂ�WEB��������B�@�h�C�c�A�č������̂Q�J���B�@
�@���g���̈Ⴂ�ɂ��ď����Ă���
http://www.remus.dti.ne.jp/~rmina/faq/frq_v.html
�����ɏo�Ă���A�č�GM���h�C�c�@�V�[�����X�����������ЁA�Ƃ����Ƃ���͂������ł��˂��B
03�N12��15���@���p
�@�č��f��u�z�b�g�E���b�N�v�@���o�[�g�E���b�h�t�H�[�h�剉�B�@��s�̋��ɌW�ɍÖ��p�������A�������J�������Ă��܂��B�@���ɌW�ɂ͗\�߁A�Ö��p�������Ă����A�L�[���[�h�������ƁA�w�������s�����J�n����B�@���b�h�t�H�[�h�̓G���x�[�^�[�̒��ŁA���ɉ�W��ɃL�[���[�h�u�A�t�K�j�X�^���E�o�i�i�X�^���v�Ƃ����B�@���TV�ł���Ă����Ö��p�̔ԑg�͂��̉f��������������悤�Ȃ��̂������B�@���ꂪ���p�����Ɛ������ƂɂȂ�B�@�������邩���m��Ȃ��B�@�b�h�`���j�f�a�����������炵���B
�@
�@�ȉ��̓C�^�`���[���畷�����b�ł���B
�@�Ö��p���g�����������Q�O�N�قǑO�Ƀo���R�b�N�ŗ��s�����B�@�Ɛl�͋��i�������Ă������Ȑl�ɋ߂Â��A���ʂɐ���������B�@�ʂɌ��t�I�݂ł͂Ȃ��B�@����q�˂�Ƃ��A�o�X�H�����Ƃ��́A���肫����̉�b�ł���B�@��Q�҂͂��̂Ƃ�����Ö��ɂ�����A���i�̑S�Ă������o���Ă��܂��B�@�����ĉ����������������̂悤�Ɏ���ɋA��A���z�������i�i��1�j�Ȃǂ��������ƂɋC�Â��B�@���i�������Ă��܂������Ƃ͋L���ɂ��邪�A���̂Ƃ������l���č����o�����̂�����Ȃ��B�@����Ȕ�Q�����l���o�āA�o���R�b�N�̉\�ɂȂ����B
�@�C�^�`���[�̗F�l�̓����V�b�g�i��`���班���A���^�������Ɍ��������ߍx�̒��j�Ńo�X�H����q�˂���Q�ɂ������B�i��600�o�[�c�Ƌ����i�F������600�o�[�c�͍���艿�l�������j�@����ɒ����Ċo�����A��Q��m��B�@�������ĉ������Ė���Ȃ��B�@�A�H��S���o���Ă��Ȃ��������B�@�f��́A�낤�����������B�@�ʂ�ł��̎����ɑ����A���i�������o���Ă���r���A�ʍs�l���A�h�\�̎����h�ƋC�Â��A�u������Ă�I�v�Ƌ��ׂɍÖ��p���͓��S�A�m�l�̔�Q�҂͍Ö������߂��ɋA��A���낵���Ȃ����Ƃ������A�ȋ^�S�Ȃ����ꂪ���R�̐U�������̂悤�ɋ��i�������o�����Ƃ������Ƃ͊o���Ă���炵���B�@���̍Ö��͕K������ɂ��Ă���C�Â��B�@�K���A��̌�ʔ�͎����Ă���̂ŁA��Q�҂̋A�r�Ńg���u�������o���鎖�͖��������B
��1�j�̂̃^�C�l�͋����i�A�l�b�N���X�A�u���X���b�g�A�w�ւȂǂ���������g�ɂ��Ă����B�@���������ȂǁA�ؗ̓g���[�j���O�p�̃E�G�C�g�Ǝv���邭�炢�g�ɂ���B�@���͏����i24K�j�Œʉ݂̎��ɗ��ʂ��ǂ��A�L���̏ꍇ�͒ʉ݂����M����������B�@
03�N12��14���@�u�^�C��������lj��v
�@���N�V�[�E���[���h�E�t�@���̊F�l�A����ɂ��́B�@�C�܂���ȍX�V�ɂ��ւ�炸�x�X�K�₵�Ē������肪�Ƃ��������܂��B�@���̃T�C�g�̖ړI�͓����A�����X�҂�ΏۂɃ^�C�����̉���ƁA��`�L���̖ړI�ŊJ�ݒv���܂����B�@�ŋ߂͗����ȊO�̎ʐ^�Ŋg�����Ă��܂������A�^�C�����Ɋւ���s���A�ȖK��҂������A�{�������̒��x�̓��e�ł͂��e���ƍl���A���O���C���A�^�C�����������ƍL���[�������Ă��������Ǝv���܂��B�@�]���܂��āA�u�����̂��́v�͑��B���b���������܂��B�@�i���e�p�ʐ^�͑��B�𑱂��A�������ɏo����������ڔ������ł����B�j�@�@�搔�����̓^�C��������A�u���̂���v�̑����A���j���[�E�y�[�W�̎ʐ^�������i��1�j�Ȃǂɓw�߂܂��āA�����K�����҂����Ă���܂��B
��1)�@HP�J�ݓ����́u�z�[���y�[�W������ቤ�v�i�����j�Ƃ����\�t�g�ŁAHP�̎d�g�݂Ȃǖ���킩�炸���鋰�����Ă����̂ł����A���A�������Ă݂�ƁA��ϏX���ʐ^�ƌ��ɂ����\���ɂȂ��Ă��܂��B�@�\�t�g�̏����l�͉摜��e���L�^�i��3�j���邱�ƂɂȂ��Ă�����ł��˂��B�@��������jpeg������Ȃ�������ł������Ȃ��ł��˂��B�@HTML�Ȃ�Ă����ƒm��Ȃ�������ł��B�i��2�j�@���e�̊g����D�悷��ƁA�ǎ��ʐ^�ɍ�蒼���Ă������܂��˂��B�@�@�f�U�C���̃Z���X���Ȃ��̂ŁA�Z���I�\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͎����ł��������Ă��܂��A�l�}�l�������Ȑ��i�ł�����A�Z���X�̗ǂ���ʂ��}�l�č��ȂǂƂ������Ƃ͏o���܂���B�@
��2)�@HTML�Ƃ́A�z�[���y�[�W�����R���s���[�^�[�p�̖��ߏ��i�܂��͂��̋K���j���w���܂��B�@�������������̓R���s���[�^�[�ɋ������Ȃ������B�@�����܂ō�ꂽ�̂́A�H��D������������B�@���w�Z�̐}�H�͓��ӂ������B�@���ӂ̈Ӗ�����Ƃ���́A�H�삷��Ɖ��ł��N���X�ŏ��3�Ԉȓ��ɍ��I���B�@�����B�@�o���h���͕ʂɂ��āE�E�B�@�@���ꂪ��HP�ɏo�Ă���B�@���ꂪ�s���ӂŁA�u�Q�Q�����̍�҂̍l�����q�ׂ�v�@�I�Ȏ���́A���\����ƕK���}���́B�@���͂Ȃ�ĕs���ӂɌ��܂��Ă�B�@������ʐ^�ŃS�}�����Ă����B
��3�j�f�t�H���g��jpeg��e���L�^����@�\�ɂȂ��Ă��ł��˂��B�@�傫�Ȏʐ^�Ȃ炢����ł����A���N�V�[�̂悤�ȍׂ��ȉ摜�ł͔@���ɕn�コ������Ă��܂��B�@����gif�͒�i��32KB�̑傫���ɂȂ��Ă�����ŁA�d���y�[�W�Ȃ̂ɉ摜���e����������ł��B�@�Ƃ��������A�����ɂ��̂܂܂̃y�[�W������B
�@03�N12��8���@��l�̃G���^�e�C�����g�@�i�m�y�lj��j
�@NHK����ԑg�ŗ[������Ă�u�n�b�`�|�b�`�E�X�e�[�V�����v�B�@�O�b�`�i�����|���͂���Ȃ��j���O���l�̎�i����p��ŃA�[�e�B�X�g�j�̃p���f�B������B�@�c���E���������ԑg�̊Ԃɋ��܂��Ă��邪�A��l�̃G���^�e�C�����g�B�@�����̐e�̐��オ�����ґΏۂł���˂��B�@�p���f�B�Ώۂ̊O���l�A�[�e�B�X�g���S�������̒m���Ă���N����̂���B�i����p��ŃJ�u��j�@1960�N��`1980�N��@�A�Â��̓r�[�g���Y�A�����L�[�Y����A�[�X�E�B���h���t�@�C���[�A�}�C�P���W���N�\�����炢�܂ŁB�@�J�c��+�ߑ��ŕϑ��A�̂��̂��B�@�@�K�����w�Ɗ|�����킹�āA�P�ȂƂ��Đ��藧�悤�ҋȁA�ւ��̂ɂ���Ă���B�@���s�[�g��������{��̎��������ɒu��������Ƃ��A���w����X�C�b�`����Ƃ��B�@���̂܂˂ƁA�ւ��́A�ҋȂ���ϖʔ����B�@���ꂪ��l�̌|����Ȃ��A�Ƃ��Â��v���̂ł���B�@�i�̌^���w�ǂ̊O���l�A�[�e�C�X�g�ƍ����Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B�j
�����L�[�Y�̃T�C�g�@�ithe monkees�j
http://www.100megspop2.com/monk/eng/80sen.htm
03�N12��4���@�u�}�l�[�̓Ёv
�@���ƉƒB���A�C�f�B�A�ɑ��X�|���T�[�ɂȂ�ԑg�B�@�^�C�g���̃I���W�i���A�u�}���[�̌ՁA�n���}�I�v�Ɣԑg�̓��e���A�����̒��ł͑傫����������B�@���X����E�E�Ƃ�������������A�E�E�Ƃ������Ă��܂��B�@�N�Ď҂������K���ɐ����������ŁA�X�|���T�[���͎��X�В��炵������ԂȃZ���t��������l������B�@��ȃA�C�f�B�A���Q�l�ɂȂ邪�A�X�|���T�[�̔�����\������̂ɒ��͂���B�@�ނ�e�l�̐��i�E�w�i��c�����Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��A�w�ǃn�Y���B�@���ꂪ������悤�ɂȂ�A�h���ƉƂɂȂ��v�f����Ȃ��h�@�Ƒ����~���邪�A���ꂾ���O���ƋN�ƉƂɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ���������B�@����Ȃ��ƂƂ͊W�Ȃ��A���̔ԑg�̃E���͂ǂ��Ȃ��Ă�̂��A��ϋ������킭�B
03�N12��3���@�u�~�X�^�[�E�{�E�W�����O���Y�v
�@1972�N�A���y�Ɋo�������B�@�j�b�e�B�E�O���b�e�B�E�_�[�g�E�o���h�i��2�j�̃~�X�^�[�E�{�E�W�����O���Y�i��3�j�ɏՌ������B�@�č��̃J���g���[���u���[�O���X�i��4�j�Ƃ����A���{�ł͊���ȃW�������̃o���h�������Ƃ��m�炸�ɁB�@���N�̎����ɂƂ��ĉ����A�����f�B�A����A�ǂ�����V�N�������B�@�m�y�ɋ����X�|���A���ꂪ����Ԃ��i��1�j�ւ̓�����ɂ��Ȃ����B�@
�@�ŋ߁A�����ԉ�Ђ�TV�L���Ŕނ�̉��t�ɂ��A�~�X�^�[�E�{�E�W�����O���Y���g���Ă����B�@�u���̋ȍD���Ȑl���Ă���ς肢��B�v�@�Ƃ��݂��ݎv���̂ł������B�@����A�ӂƎv����Google�i��5�j�ł��̃o���h�̖��O�����Ă݂�ƁA�o���I�@30�N���o�������Ɋ������Ă���B�@�����o�[�������ԓ���ւ���Ă�悤���B�@��������Ă�A���o���̒��ɁA�̂̋Ȃ̃^�C�g�����������o�����Ƃ��ł���B�@�@
�@��1000�~�̏��������烌�R�[�h�Ȃǂ͔������Ƃ��ł��Ȃ��������i�����̃��R�[�h��2800�~�ψ�j�A�\�t�g�ɂ������g����قǁA�S�͖L���łȂ������B�@���R�[�h���悤�ɂȂ����͎̂Љ�l�ɂȂ��Ă��炾�B�@����܂łɔ������Ƃ��ł��Ȃ��������R�[�h����LP��90���ȏ�ɂȂ����B�@�����̈���͕������������B�@�k�o�͂₪�Ăb�c�ɕς�邱�Ƃ͂��������A���̍��������Ȃɂ͍����O���Ă��Ȃ��B�@�~�X�^�[�{�E�W�����O���Y�Ȃlj̎��͖Y��Ă��A�y�킲�Ƃ̉��������ɑh��B
���������߁�
��1)�@���=���m�B�@���Ԃ�=���������B�@���m�ɋ����⓲��������Ƃ�̎��I�ɕ\������B
�@���̌��t�̎���w�i���炷��Γ�Ƃ́A�C�X�p�j�A�i�X�y�C���j�A�|���g�K���ɑ������邾�낤���A�����͍����ʼn��B�l�͔ނ炵�����Ȃ������̂�����A���B���w���Ă������̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ����C�����Ŏg���Ă���B
��2)�@The Nitty Gritty Dirt Band
�����T�C�g�@http://www.nittygritty.com/
�j�b�e�B�E�O���b�e�B�������Œ��ׂĂ��ڂ��Ă��鎫���͏��Ȃ��B�@���������̐S�ȂƂ��A�����̂Ƃ�����������ł���B�@�č��l�ɕ������Ƃ���ł̓C���t�H�[�}���i�����́A�ς́j�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂��������B�@�m���Ƀo���h�̃����o�[�͎n�I�ς���Ă����B
��3)�@�~�X�^�[�E�{�E�W�����O���Y�@�yMr.
Bojangles�z
�V�����_���T�[��`�����������I�̎������D��U���B�@��ɁA���̋Ȃ́A�T�~�[�E�f�C�r�X�E�W���j�A�Ƃ��W�����E�f���o�[�ɂ��̂�ꂽ�B
�@�̎��͈ȉ��̃T�C�g�Q�Ƃ�������
http://www.mudcat.org/@displaysong.cfm?SongID=4061
�@����A���̃T�C�g���Ăь����Ƃ���A�`���b�g�ɐF�X�o�Ă����B�@�{�E�W�����O���Y�̐��̂ɂ��ĂƂ��M�^�[�R�[�h�A�t�҂ɂ��Ă��B
��4)�@�y�u���[�O���X�z�@�p����
�A�����J�̓`���I���y�̈�ŁA�q���r���[�i�����艹�y�j���甭�W�����Ƃ�����������B
�@�f��u�^�C�^�j�b�N�v�̖`���V�[���ŏ�q�̓A�C�������h�̈ږ��ł��邱�Ƃ������A�C�������h���y�̉��t�Ɨx�肪�o�ꂷ�邪�A�u���[�O���X�ɋ߂��B�@�u���[�O���X�̓A�p���`�A�R���𒆐S�Ƃ���A�C�������h�n�̈ږ��ɂ���ē`�����Ă���B�@��\�I�Ȃɂ̓t�H�M�[�E�}�E���e���E�u���C�N�E�_�E���A�f��u�������ɖ����͂Ȃ��v�Ŏg���Ă����B�@�u�r���������[�ƃu���[�O���X�E�{�[�C�Y�v�����j�I�L���o���h�ł���B�@�y��̓t�B�h���i�o�C�I�����j�A�o���W���[�A�t���b�g�}���h�������S�ɁA�M�^�[�A�h�u���A���b�V���^�u�o�X�A�_���V�}�[�A�I�[�g�n�[�v
�ȂǁB�@�ifiddle, banjo, flat mandolin, dobro, washtub
bass, dulcimer, auto harp�j
�ȉ��̃T�C�g�ʼn��킩�̊y������邱�Ƃ��ł���B
http://www.bluegrassworld.com/instruments/�@���̑��̊y������ׂ�Ɩʔ��������m��Ȃ��B
��5)�@Google�̓A���t�@�x�b�g������ƁA���{�̃T�C�g�����łȂ��A���̂܂܃��[���h���C�h�̌������ł���̂œs���������B�@�����Ќ���Ή��A�^�C�ꌟ�����ł���B�@
���[���h���C�h��Google�i�A���t�@�x�b�g�Łj�ł�"�^�C����"�Ɠ��{��Ō������Ă��A�u�^�C�������N�V�[�v�@�ȂǂƓ��{��ŏo�Ă���B�@�p�P���Ԃ�Ⴂ�œ����ƁA�C�����Č������Ă����B�@���́A�u�^�C�����@���N�V�[�v�̃T�C�g�ɂ�Google����̃W�����v����ԑ����B
�@http://www.google.com/intl/ja/�@�i���{��j�@�@http://www.google.com/�@�i�A���t�@�x�b�g�j
���j�@�֘A�T�C�g���Q�l�Љ�
�@�֘A�T�C�g�̌f�ڂ́A�����܂ł��Q�l�Љ�ł��B�@�����߂Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�@�u���E�U�̋@�\�Ȃǂɂ��\���ȉ{�����o���Ȃ���������܂���B�@��`�L���̂���܂���������̂�����܂��B�@�ŋ߁A�����T�C�gGoogle����c�[���o�[���_�E�����[�h�����Ƃ���A�̂ŁA�u�z�b�v�A�b�v�E�u���b�N�v�@�\�����Ă��܂����B�@�]�v�Ȑ�`�L���T�C�g���J���Ȃ��̂ʼn��K�ł��B
03�N12��3���@�u�V���b�L���O�E�u���[�v
�@1970�N�̑O���Ǝv���B�@�r�[�i�X�Ƃ����ȂŃq�b�g�����A�V���b�L���O�E�u���[�Ƃ����o���h���������B�@�p�ꌗ�ȊO�̍��̃o���h���Ǝv�����B�@�ǂ����Ă����u�T�C�P�f���R�ƃV���b�L���O�E�u���[���d�Ȃ�B�@�V���b�L���O�E�u���[��LP�͂P�������Ă���B�@Google�Ō��������Ƃ���A��̂킩��Ȃ������A�L���������H�݂����̂��o�Ă��ăT�b�p������Ȃ��B�@URL�̂��K���h�����h���Ăǂ������H
�@�ȉ��̃T�C�g�̓r�[�i�X�̃W���P�b�g�̂悤��
http://www.geocities.com/gbrecordsuk/shockingblue.gif
�@���̎�����āA�T�C�P�f���b�N�A�ipsychedelic�@���́A���_�́A�S���̂Ƃ������Ӗ������ǁA�����Ɛi�߂�ƌ��o�Ƃ��S��Ƃ��j�Ƃ��������t�����s������Ȃ��B�@���������ΑO�ɁA�p�t�B�[���̂��Ă��A��ߍ����`�����B�́`��A�Ƃ����Ȃ̓r�[�g���Y�̏����̍��̃x�[�X�ɂ������肾�����Ȃ��B�@�i�Ȗ��͎v���o���Ȃ��j�@���̂������������͂����X�L�ɂȂ��Ă��܂��B�@���y�̍D�݂͎v�t���ɂ�����̂��B
03�N11��24���@�u�k�����&�L�[�V�v�Ɓu���傤�����N���v�̂����t�@�C����uni-code�ɏC��
�@�}�j�A�b�N�����m��܂��A����s�ǖh�~�̂��ߗ��_�ʂ�ɂ��܂����B�i���j�@���܂łƌ����ڂ��g��������ς��Ȃ��ł��傤�B
�@����A�C�^�`���[�Ɂu�v�[�p�b�E�y�b�v�������Ă�������B�@�v�[�p�b�E�|���J���[�ɓ��h�q�����ꂽ���̂������ĂԁB�@����͐��������āA�v�[�p�b�E�|���J���[�����������������B�@�A���A���߂ă^�C������H�ׂ�l�͂����炭�h���ă����B�@�H�ׂĂ݂����l�́A�v�[�p�b�E�y�b�g�𒍕����Ă��������B�@���j���[�ɂȂ��Ă����^�C�����͂ł��܂��B�i����f�ނ̏ꍇ�͎��O�ɒ������K�v�ł��j
<���߉��>
���j�������ォ��K�v���͗������������e�̕s�ւ��̗��R�ŕ��u�B�@5.5�ł����̕�������������Ƃ���邪�A2���A�����œ��{��͕s�g�p�A���̂܂܂ł��g����Ɣ��f�B�@�J�������A�����Ƃ�5.5�z���ʼnғ�����������m�F�ς݂����A�����ɂ�����Ȃ��Ɖ����N���邩����Ȃ��B�@
03�N11��22���@�^�C�̓����ʐ^�lj�
�@�^�C������{�ɂ���ƁA���{�l�ł������b�����v�����Ƃ����낢�날��B�@��`����o��ƁA�悸�͐F�̐��E���W�~�B�@�����A�^�C�̋��̎ʐ^2�_��lj������B�@�����̋��͓��{�ł͔M�ы��ƌĂ�邩������Ȃ��B�@�^�C�l�̃C�^�`���[�Ɛ������i��1�j�ɍs���ƁA�u���̋����������v�Ƃ��A�u���̒n���łƂ��v�Ƃ�������b�ɂȂ�B�@�^�C�ł��Ϗܗp�̋��͔����Ă��邪�A�����炭�^�C�����̋��ɈႢ�Ȃ��B�@���{�Ō����Ȃ�A�n�[��t�i�������Ă���̂Ɠ����ł���B�@�@�Ƃ��낪�A���{�Ńt�i�Ƃ����_�J�Ƃ��������Ă��ӏ܂Ƃ��Ă͖ʔ����Ȃ��B�@�����W�~�߂���B�@�n�[���E�i�M�Ɏ����Ă͓��������Ȃ��B�@�i�n�[�͎��������Ƃ����邪�A�G�T����������B�@�������̂����H�ׂȂ��j�@
�@�����u�^�C�̓����v�T�C�g�ɂ́A�ؐ����Ƌ��Ԃ̑g�ݍ��킹�̎ʐ^�����邪�A�{���̋��̈����ʐ^���������̂ŁA�����̂���l�͎��̃T�C�g���Q�Ƃ��ꂽ���B�@http://www.pbase.com/image/18257597
�@�^�C�Ő��̋����������Ԃ̃V�[�����B�肽���������A���̂悤�Ȍ��i�ɏo����Ƃ��Ȃ������B�@
�@�����Ƃ͌����A�w�ljƒ{�ɂȂ��Ă��܂��A���R���������҂��Ă������X�ɂ͊��҂͂���Ő\���킯�Ȃ��B�@�쐶��������ނɍs����HP�ɍڂ������C�����̓��}���}�ł����E�E�B�@���ԂƃJ�������K�v�ł��Ȃ��B�@���̉ƒ�p�J�����ł́A�Ռ��I�Ȏʐ^�̓����B�@�蓮�œ_�A���邳�A�ڎʁA�]���Ȃǂ̋@�\���K�v�B�@�쐶���������ɂ́A�ɓo��Ƃ��A�c���ł��@���ĉ����Ԃ��B��đ҂B�@�쐶�̃g���Ƃ��ۂ̐��ԂȂǎB���Ă݂����˂��B�@�쐶�����Ƃ����A���������w���̍�����TV�ԑg�A�u�쐶�̉����v�i��3�j�@�u�A�t���J��q��v(��3)�A�����ă^�C�؍ݒ��ɂ݂��u�i�V���i���E�W�I�O���t�B�v(��3)�ȂǁA�����S�Ɏc���Ă���B
�����ߐ�����
��1�j�^�C��Ő����ق̂��Ƃ��@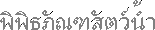 �@�s�s�^�p���E�T�b�g�E�i�[���i����F���������̔����فj�Ƃ����̂ł����A���̃s�s�^�p���̔������^�C�l����s�j�^�p���Ƃ͂����蕷���Ă��������́A���̐l�Ɖ�b���A�͋����s�j�^�p���ƌ����Ă��܂��A�u�Ȃɂ���H�A�s�s�^�p������Ȃ��́H�v�Ǝw�E���Ă��܂��A���̒P��������Ă��ꂽ�l�ɋ����������v���o������܂��B�@�����A���̒P��A�s�s�^�p�����܂��܂��Ǝ����Œ��ׂ��Ƃ���A�s�s�̈Ӗ�����Ƃ���́u���낢��v�A�p���̈Ӗ�����Ƃ���͊��ł����B�i��4�j�@�ق��ɐ����ق��p-�^�C���T�Œ��ׂ�Ɓ@ �@�s�s�^�p���E�T�b�g�E�i�[���i����F���������̔����فj�Ƃ����̂ł����A���̃s�s�^�p���̔������^�C�l����s�j�^�p���Ƃ͂����蕷���Ă��������́A���̐l�Ɖ�b���A�͋����s�j�^�p���ƌ����Ă��܂��A�u�Ȃɂ���H�A�s�s�^�p������Ȃ��́H�v�Ǝw�E���Ă��܂��A���̒P��������Ă��ꂽ�l�ɋ����������v���o������܂��B�@�����A���̒P��A�s�s�^�p�����܂��܂��Ǝ����Œ��ׂ��Ƃ���A�s�s�̈Ӗ�����Ƃ���́u���낢��v�A�p���̈Ӗ�����Ƃ���͊��ł����B�i��4�j�@�ق��ɐ����ق��p-�^�C���T�Œ��ׂ�Ɓ@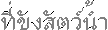 �@�Əo��������̓^�C-�����T�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B �@�Əo��������̓^�C-�����T�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B
�����Ƃ������Ȃ��ƂɁA����^�C��̋����{�ł́@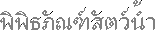 �@�ƕ\������Ă����i��2�j���A����̓~�X�ł��낤���A����Ƃ��̂̕\�L���i���a44�N���s�ł͂��肦��j���m��Ȃ��B �@�ƕ\������Ă����i��2�j���A����̓~�X�ł��낤���A����Ƃ��̂̕\�L���i���a44�N���s�ł͂��肦��j���m��Ȃ��B
��2)�@�g�[�E�i�[�������g�[�ɃJ�[���������Ă�B�@�������炷��Ƃ����炪��������ł���˂��B
�����̃y�[�W�̃^�C��\�L�́A�^�C�������N�V�[�́u�k�`�������L�[�V�v �@�ō쐬����A�摜��荞�݂���Ă��܂��B�@�@���ꂩ�玩���̃^�C��̕��̂��߂Ƀ^�C����ڂ��Ă��������Ǝv���܂��B �@�ō쐬����A�摜��荞�݂���Ă��܂��B�@�@���ꂩ�玩���̃^�C��̕��̂��߂Ƀ^�C����ڂ��Ă��������Ǝv���܂��B
��3�j�@�ԑg���
�@�u�쐶�̉����v�@���Ă̔ԑg�B�@���E���́A��Ƃ��ăA�t���J�̎��R�����̃t�B�����������ĉ������B�@�ԑg�̎n�߂ƏI���ɁA���m�l�̔��m���o�Ă��ĉp��ʼn�������B�@�ԑg�̏I���ɁA���̔��m���u���C���h�E�L���h���v�Ƃ����Ɖ�ʂ��Z���t�F�C�h�E�A�E�g����B�@���̃V�[�������I�ł��B�@�t�B�����S�̂����F�������Ă����Ǝv���܂��B�@�]�k�ł����A�̂̃A�����J�̉f��͐�������̂����������B�@�d�C���ʼn��ŁH���ĕ�������A�R�_�b�N�̃t�B�����͐݊|�����Ďʂ�A�Ƌ����Ă��炢�܂����B�@���̓d�C�L�`�̃W�b�����͂����S���Ȃ�܂����B
�A�u�A�t���J��q��v�@�`���N�E�R�i�[�Y�剉��TV�f��B�@�A�t���J�̎��R�����ی��ړI�Ƃ��ē����q���B�@�n�ɏ���ăG�����h�Ȃǂ̑�^�A���e���[�v�ނ𓊂���łƂ炦��V�[�������܂�Ȃ��ǂ������B
�B�u�i�V���i���E�W�I�O���t�B�v�@���E���̎��R�����B�f�I�ɂƂ炦���|�p���̍����ԑg�B�@����͂ǂ��̕����ǂ��L���ɂȂ��ł����A�p��̔ԑg�ł����˂��B�@�����^�C�g���̎G�������E���Ŕ��s����Ă���B�@������܂��A�ʐ^�|�p���������B�@���{��ł�����B�@���z�[���y�[�W�̃^�C�g���A�u�^�C�E�W�I�O���t�B�v�̃q���g�ɂȂ��Ă���B
��4�j�@�s�ƃp�̊Ԃ̃^�����̔������邩�������܂��B�@�@�A���t�@�x�b�g�ŏ�����
phiphit + phan = phiphithapahan �@�@�ꖖ�̕������q���̏ꍇ�́A�P����q�����Ƃ��ꉹ���܂ޔ����ɂȂ�ꍇ�����邩��ł��B�@���̒P��ƊW����܂��A���G�]��������܂��B�@
03�N11��21���@���V�s�̔Y��(���V�s�������l���Y�ނƂ����Ӗ��j
�@�C�Ɋ|�����Ă邱�Ƃ��^�C�����̃��V�s�ł��B�@�^�C�����̃��V�s�������T�C�g�͑�R���邵�A�{�����đ�R�o�ł���Ă��܂��B�@�ǂ�ȃ��V�s�ɂ���^�C�����͍ޗ��W�߂��^�C�w���ł��B�@����̓����������n�[�u����ł��B
�@�Ⴆ�`���[�L���ɂȂ����g�������N���B�@���h�q��R�R�i�b�c�~���N���x�̓w�b�`�����Ƃ��Ă��A�n�[�u�ނ͂ǂ����܂����H�@�������O���X���^�C���I�A�R�u�~�J���̃n�b�p�A�p�N�`�[�̓^�C�H�ސ��X�łȂ��Ƒ���Ȃ��B�@���ɑ������Ƃ��Ă����X�ŐH�ׂ鉽�{���̒l�i�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�i�e�Ȃ��X�Ȃ�o���R�b�N�̂悤��2-3�l���̐H�ރL�b�g�����邩������Ȃ��j�@���V�s������ƍޗ�����̓���ɓ�̑���ł��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���{�̖^�H�i���[�J�[�̃g�������N���̑f�����ł������Ă��邩�ǂ����킩��܂��A����͈�̉���������ł��傤���B�@�^�C�����̃g�������N���ƑS���Ⴂ�܂��B�@�C�^�`���[�i���j���m��Ȃ����łł��B
�����߉����
���j�@�W�b�g�E�v���b�`���i�ŃR�b�N�����Ă鎞��ɁA�u�b�T���J���ɕ��ɂ����܂����B�@�u�b�T���J�����W�b�g�v���b�`���i���o���R�b�N�̘V�܁E�L���X�ł��B�@�^�C�����@���N�V�[�̓W�b�g�E�v���b�`���i�̖����x�[�X�ɂ��Ă��܂��B�@�C�^�`���[���W�b�g�E�v���b�`���i����̎ʐ^�����X�Ɍf�����Ă���܂��B�@
03�N11��20���@����ꂽ�t�B����
�@����̗��������ŁA�ߍ��T�C�g�̗e�ʂ����b�`�ł��B�@���ׁ̈A�ǂ����Ă��傫���ʐ^������X���ɂ���A�{���Ɏ��Ԃ������邩���m��܂���B�@���N�V�[��HP�|���V�[�́u�ʐ^�����A�������Ȃ��A�Ōy�����āA���e�Z���v�i��1�j�ł��B
�@�ŋ߂���ƃ}�p�[���i�V�[�E�}���S�[�j�̎ʐ^��������A�f�ڂł������ł��B�@�t�B����(��2)���J�����ɓ������܂�2-3�N���̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����B�@�^�C�ɏZ��ł�ΊȒP�Ɏ�ނł����ł����ˁB�@�ʐ^�t�B���������̂܂ܕ��u���Ă����Ƃǂ��Ȃ邩�E�E�E�@�Ԃ̒��ɒ����ԕ����Ă�����(��4)���Ƃ������āA���������������A�S�ăs���N�F�������Ă��܂����B
�@�t�B�����Ƃ����A�c�O�Ȃ̂�93�N�A���R����ŎB�����t�B�������Ȃ����Ă��܂��܂����B�@�����ʐ^��������ʼn���܂�܂��B�@��͐�̂������̋u�B�@��������̓��I�X�������܂��B�@��͐�ǂ̉��ł��B�@�����A���I�X�����i��3�j�ɂ�50�������Ɍx����������ƕ����܂������^�U�s���ł��B�@���̋u�͔����₪���w�ɂȂ��Ă���B�@�~�j�`���A�ł����A���E�{�����ɂ���܂����B�@�B��Ƃ����낱�����菤�l�������O�̃t�B�����Ɏc���Ă܂����B
�@����1�ӏ��͑�ł����A�ꂪ�����ΊD��ƌ������Ղɂ́A�召�͂���܂������l�������ʂ̒��a�Ő[����50-60�������炢�̐^��ۂ������������Ă��܂����B�@��������R�Ȋw�̎Q�l�ɂȂ���̂ł��B�@���������u���N�V�[���[���h
�� �^�C�E�W�I�O���t�B�v�ɍڂ��Ă�����ł����B
���߉��
��1�j�@�������ɂ��Ă݂܂����B
��2)�@�s�v�c�Ȃ��ƂɃt�B�����Ə����Ă���̂ɕ��ʂ̐l�̓t�C�����Ɣ������܂��B
��3�j�@70�N��Ɂu�p�e�g���I�v���j���[�X�ɂ悭�o�Ă��܂����B�@���I�X�l���������A�Ɩ�Ă��܂������A�^�C��̃v���e�[�g�E���I�̂��ƂȂ̂��Ȃ��A�Ǝv���܂����E�E�ǂ��ł���H�@���I�X�ɏڂ����������āB
�@�@�@�@�p�e�g���I�̊֘A�y�[�W�@http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Report/pdf/2001_03_06_12033.pdf
��4�j�@���������̏������H�ƊE�p���ʼn������������ȒP�ɍ��܂�
�@���N�V�[��HP�̓j�b�`�i���ԁj�ł��B�@�����̃T�C�g�ɍڂ��Ă鎖�͂Ȃ�ׂ�������č���Ă��܂��B
03�N11��18���@�@���Ђ��i���j
�@�ߓ����J�́u���̂���v�̒lj��y�[�W�̐H�i�A�i�X�Z�����E�ɂȂ��Ă��܂����B�@�^�C�������N�V�[�̃R���Z�v�g�̏�A�Z�����̂����J�ł��Ȃ����̂������Ďc�O�ł��B�@���̃y�[�W�͋���ɉ��h�����������Ȃ��Ă��܂��܂����B�@���̉��Ђ��A���̉��Ђ��A�����̉��Ђ��B�@���Ђ��͐H�i�ۑ��̓`���I��@�ł��B�@���̓`���I�H�i�ۑ��̕��@�͊����A���y�A�����A�����Ђ��Ȃǂ�����܂��B�@�^�C�ł͍����Ђ��┭�y�������ł��ˁB
�@���͐l�̂Ɍ������Ȃ��~�l�����ł����A��肷����Ɨǂ��Ȃ��ƕ����Ă��܂��B�@����҂ɕ������Ƃ���ł́A�i�g���E���͑̂ɐ�����ۑ����Ă��������������i��2�j�A�̓��̐����ʂ������ƌ����������Ȃ�B�@���{�l��Na�i�i�g���E���j��̂ɕۑ�����̎��Ȃ̂ŁA�������ɂȂ�₷�������ł��B�@���ɂ����{�l�͐F�X�Ƒ̓��ɕۑ����₷���̎��炵���A����TV�ԑg�ł́A�i���̉ߒ��ŁA�Q��ɑς�����̎����`�������A�Ɖ�����Ă��܂����B
�@���{�ł͍ŋ߂܂��i���j�I�Ɍ����ŋ�=20-30�N���ĂƂ���ł��傤���j�A�Е��ł������ł���R�̉����g���Ă��܂����B�@�ȑO�͒Е������h���������A�V�����Ȃǂ͕��ɉ�������܂�����Ă����̂ł��B�@�Ƃ��낪�ŋ߂̌��N�u�[���i��3�j�ŁA���������s�������܂����B�@��Â̐i�������m��܂��A���̐ێ�ʂ������ƌ������R�Ō��N���Q����l�̐��͂����ԏ��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������܂����B
�@�T�C�g��̐H�i�͂ǂ�������ŁA���������̂ł�����Ɣ��ł����x�ł��B�@���{���ɍ����܂��˂��B�@���N�V�[�̍D���ł��B�@�@�^�C�������̂��͉̂��h����ł͂���܂���B�@�t�@�~���[���X�g�����i����p��Ńt�@�~���X�j�̗�����艖�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�@
���
��1�j���������\���ɍ����A�����E�����ł��Ȃ��ĉ����A�l�オ���҂A�������\�������瑊�����Ԃ�������B�@��������Ђ��ƌ����B�@�o�u������ɁA�܂���o���ς�3��8��~���炢�Ŕ������l����R���āA�o�u������セ�̐l�B�����̗p���A�����Ă����B�@
��2�j���w�Z6�N���̎��搶���畷�����B�@�h���S���ł́A�����Ċ����ł�Ɖ����s�������ŁA�H��̒��ɉ����u���Ă���B������r�߂Ȃ��瓭���B�h�@�{���̂Ƃ���͂킩��Ȃ����A�̘̂b�����m��Ȃ��B�@������~���铭��������Ƃ���A��ʂ̊��ŒE����h���ƌ������R�Ȃ̂����m��Ȃ��B�@�m���Ă�l�����ĂˁB
��3�jTV�̌��N�ԑg�A�����ł��ˁB�@���̍������N�ی���Љ�ی��̐��x���猾���A���̂��炢�`������ł���Ă����Ɨǂ��Ǝv���̂ł����B�@���N�ԑg�ŋC�ɂ�����̂������͑̂ɗǂ��A�Ƃ����������R�����߂��āA�ǂ��Ƃ�������̂���H�ׂĂ��瑾���Ă��܂����A�Ƃ����肦�܂��Ȃ��B�@�����҂͂悭�l���܂��傤�B�@�ǂ��ƌ���ꂽ�u�Ԃ��������̂łȂ��A�p�����Ȃ��ƌ��ʂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ�悸���ɓ���܂��B�@�p���ł��Ȃ������̏u�Ԃ����ێ悵�Ă��Ӗ����Ȃ������_�g�����Ȃ��A�ƂȂ�A�������^�����������������A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B
�@�h�{�w�͖����������������ł�����ς�镔�������������m��܂���B�@�����A�v���o���̂������B�@�����̓J�����[������=�̂ɂ����A�Ɛ͍̂l�����Ă����悤�ł��B�@���ł�������Ηǂ��ƌ����P���Ȕ��z�ł��傤���B�@�Ƃ��낪�̂Ɉ����A�Ƃ����o�����B�@�l���Ö����͓����ǂ��Ȃ�ƌ���ꂽ�炵���B�@�Ƃ��낪���\�N���O�ɐl���Ö����u�`�N���v�����̒��𑛂������B�@���̘b�肪�Y�����Ɛ����������̂ɗǂ��Ȃ��Ƃ����Ă邱�Ƃ�A�_�C�G�b�g�u�[���̉e���ŁA��J�����[�̐l���Ö������g���Č��݂Ɏ����Ă���B
�@�`���R���[�g�A�͍̂��������B�@�����ǂ��Ȃ�Ƃ����Ă����B�@�Ƃ��낪�A�c���ɗ^�������Ē������������B�@���x�͊Â�����^���Ȃ����ꂳ�������B�@�����Ă�����ƑO�ɂ̓R�R�A�i�`���R���[�g���R�R�A�������J�J�I������ł���j�����ɗǂ��ƕ���A�S���̏����X����o���z�[�e���̃R�R�A������ꂽ�B�@�����A�ȑO�����������Əd�Ȃ�܂����A��䍂��Ă���������Ȃ��ł����B�@
03�N11��17�� �����̖�����蕨
�@�����̍D���ȏ�蕨�͉����̖�����蕨�ł���B�@�ԂŌ����I�[�v���^�C�v�A���ł�HD�i�w�r�[�f�B���[�e�B�j�ȃW�[�v�i��1�j�@���]�ԁA�I�[�g�o�C�A���^�{�[�g�A�n�Ȃǂ����̔��e���B�@����ǂ��������傫�炢�ŁA�����̂Ȃ���蕨�͓��{�ł͔��N�������Ȃ��A���������L���邱�Ƃ͔����y�ɂȂ��Ă��܂��B�@�i�n�Ɏ����Ă͎���ϑ����ʼnƒ��P�����j�@�^�C�Ȃ牮���̖�����蕨�ł���N������̂ɂȂ��A�Ɖ������v���B�@�������Ԍ����Ȃ�����D���ȗl�ɏ�蕨������B�@�����͉������D���Ȃ̂ŁE�E�@�n�R�Ńp�[�c���������A�R���g���i��2�j�Ō����Ă��������ǂƂ��S�����������n�ڂ��āA�y�g���b�N��{���̃`���b�p�[�i��3�j�ɂȂ肻�����B
��1�j�@�O�HJ57�͗ǂ������̂ɁB�iHD�w���̐l�����Ȃ��Ȃ����H�j
�@�W�[�v�͏��i���ŁA�������N���C�X���[�̏��W�o�^�A���{�ł͎O�H�������g����A�Ɛ̓ǂ��Ƃ�����B�@�z���_�E�o���X���ǂ������B�@�o���X�͌y�g���b�N�̃I�[�v���^�C�v�A�\���^�C�����O�Ɠ��̊Ԃɂ��Ă����B�@�o���X�̖��O�̗R���͒m��Ȃ����A�X�y�C����ŁA�P�l�̕����́u�s���v�Ƃ����Ӗ��̒P��Avamos�@��������Ȃ��B
�@�O�HJ57���悭���肻���ȃT�C�g
http://www.wombat.zaq.ne.jp/pepe/jeep.htm
��2�j�@�R���g���E�E�i�R���J�Z���̒��Îs��B�@���Â̕��i���G�݂̘I�V�s��B�@1990�N��̎n�߂Ƀ^�C�ŕ��������b�F�@���n�̍H���80���~���炢����S���̋@�B�����܂ꂽ�B�@���݈����R���g���ł���������A�����߂��Ă����B
�@�Q�ƁF�@���N�V�[���[���h�@���@�����̂��́@���@�����@
��3�j�@�`���b�p�[�@�E�E�����Ō����`���b�p�[�Ƃ̓o�C�N�̃`���b�p�[�̂��ƂŁA�x�[�X�t�@�Ƃ��d�C��H�̂��Ƃł͂Ȃ��B�@�ܘ_�A�A�j���̐Ԃ��X�q�����Ԃ������ł��Ȃ��B�@�`���b�p�[���̂̈Ӗ��́u�e���荏�ށv�Ƃ����Ӗ��ŁA���{��Ō������獷���l�߁u�Ԃ�����v���炢�ɑ������邾�낤���A�o�C�N�E�̃`���b�p�[�̌ꌹ�͎��̂悤�Ȕw�i������炵���B�@1950�N��č��ŋA�ҕ��������������̂œ��i�o�C�N�ɏ���Ă����A���^�ŏ���Ă�Ɠ��i�Ƃ������Ƃ����̂ŁA���䂩���o�����āi�`���b�v���j���̕��i�Ƃ����፬���ɂ��čđg���Ă����B�@�����́i��4�j��
��4�j�@�`���b�p�[�͂₪�āA�����������������悤�ɂȂ�A�J�X�^���E�o�C�N��V���[�E�o�C�N�ւƔ��W�����B�@���Ă͓��{�ł͎Ԍ����������ꕔ�̖��@�ҁi��6�j�������̎�ނ̃o�C�N�ɂ͏��Ȃ��������A90�N��ɂȂ�ƋK���ɘa�ʼnJ���⡂̂悤�ɍL�������B�@�������A��^��ւ̉^�]�Ƌ��͎��₷���Ȃ����B�i��5�j�@�`���b�p�[�̖{�Ɩ{���͕č��A�n�[���[�E�_�r�b�g�\���iH-D�j�̃o�C�N���`���b�p�[��J�X�^���ɂ��Ă����z�����m�A�Ƃ����鏊�Ȃ��B�@�Ƃ��낪H-D�͑�^��ւ�������Ă��Ȃ��B�@�z�����m�̃`���b�p�[��J�X�^���E�o�C�N�ɏ��邱�Ƃ́A���[�U�[�̈ӗ~��~�����āA���{��H-D�s��͈�C�Ɋg��A�����Ƀ`���b�p�[�E�u�[���i�Ƃ��������ȍ~�͂��ꂪ���ʂɂȂ����j�ɂ����Ԃ��|�������̂ł���B�@
�@�~�b�L�[=���[�N�剉�̉f��A�u�n�[���[�E�_�r�b�g�\���ƃ}���{���E�}���v�A�n�[���[������Ă�̂�H-D�̃J�X�^���B�@H-D�̓~�b�L�[���g�̂��̂ƂȂ��Ă��B�@H-D�ȊO�ɂ������̓_�Ŕ��I���o�������ƃV���N���i�����j����f��ł���B�@�Ⴆ�n�[���[�̊ۊ���+�s�A�X�B�@�Ⴆ���[�T�[���X�[�c�B�@�Ō�̃V�[���ő��_�}���{���}���̓��f�I�ɏo��B�@�J�����̎��_�̓E�G�X�^���E�u�[�c�������Ɍ������B�@�J�E�{�[�C�n�b�g�͈ɒB�ł͂Ȃ������B�@�������n�D���Ƃ����_�ł������Ƀq�b�g�i����j����Ƃ��낾�B�@�}���{���}���F�o�l�b�T=L=�E�B���A���Y
�@�ȉ��̃T�C�g�Ƀ|�X�^�[�A�P�Ԃ̎d�l�Ɖ����ӏ��̈ꕔ���ڂ��Ă���B
http://www.geocities.com/MotorCity/5187/hdamm.html
�@�Â��Ƃ���ł́A�u�C�[�W�[���C�_�[�v�i��7�j�@�s�[�^�[=�t�H���_�剉�B�@�J�X�^���E�o�C�N�i�����͂܂��`���b�p�[�ƌĂ�Ă������H�j���S�̉f��Ƃ��Ă͗��j�I�ł��傤�B�@�L���v�e���E�A�����J�^��H-D�͍D���ɂȂ�܂���B�@�r���[�̏���Ă��������D���ł��B�@��Born
to be wi�`ld��@�̃T�r�̕����A���Ɏc��܂��Ȃ��B�@�X�e�b�y��=�E���t�́u���C���h�ōs�����v�B�@���̃T���O���X�͗��s��A����Ɏ����t���[���̊ዾ�����s�����B�@�i�h�C�c��̂悤�ȃu�����h���E�E�v���o���Ȃ��B�j�@���̉f���2�x���܂������A�݂͂ǂ��낪�����܂���ł����B�@�@�T�C�P�f���b�N�ȉf�����A���N�X������Ă�l�ɂ͗ǂ�������ł��傤���H�@�@�ē̓r���[�ɂȂ��Ă��f�j�X�E�z�b�p�[�B�@���łɑ��̃o�C�N�f��Љ�́i��8�j�Q��
�@�ȉ��̃T�C�g�ŃC�W�[���C�_�[�̎v���o�̎ʐ^�͂�������ꂻ���B
http://www.bikemenu.com/photoseasyrider.html
��5�j�@�č��n�[���[�E�_�r�b�g�\���Ђ͕č����{�����āA�u���{�ŃE�`�̃o�C�N������Ȃ����R�́A���{�̓�ւ̉^�]�Ƌ����x�ׂ̈ł����B�@�ق�܂͌̈ӂɑ�^��ւ����Ȃ��i����Ȃ��j���Ă�Ⴄ�����H�@����ԐړI�ȗA���K����ł��I�v�@
�Ɠ��{���{�ɔ��������߁A����܂ŏa���Ă�����^�Ƌ��i�r�C��400�����ȏ�j�����Ղ������̂ł������B�@�i��q�̂悤��H-D�͓��{�̉^�]�Ƌ��̊�Ō�����^��ւ������Y���Ă��Ȃ��B�j
�n�[���[�E�_�r�b�g�\���Ђ̃T�C�g�@
http://www.harley-davidson.com/selector.asp
��6�j�@1982�N�H�A�a�J�Ō��܂����B�@���h���ׂ��`���b�p�[�B
�u�Ԃ�����v�Ƃ����ꌹ�ɋ߂��{���B�@CB750K2��K3���炢�̃x�[�X�B�@�����O�E�t�H�[�N�@�t�H���[�h�R���g���[���[�A���W�b�g�Ƀ����V�[�g�͂Ȃ�ƍ��z�c�B�@�n���h���A�}�t���[�ڍׂ͖Y�ꂽ�B�@�������Č��Ă���ƃo�C�J�[�i���̎�̓�։^�]�҂����C�_�[�ƌĂȂ��j������Ă����B�@����܂��f���炵���I�@�h�C�c�R�w���ɔ�W�����A�����W�[�`�����ɂ͋������̃o�b�`�������ɂ��Ă���B�@���܂�̔������Ɏv�킸���������Ă��܂����̂ł����B�@���Ȃ瓖����O�����ǁA�����Ȃ�ύX���i�P�_�����ł������s�ǂŕK�����܂�肳��ə�߂��邩��ˁB
��7)�@�������O�̃o�C�J�[�W�c�A�������O�̎G��������܂��B�@�ǂ����H-D&�`���b�p�[�����ʌ�ł��B�@���̏W�c�̂����A�\�j�[�E�o�[�W���[�Ƃ������O���v���o���܂����B
��8)�@���Ƀo�C�N�̏o�Ă�����ۓI�f��́u�t���[�r�[�ƃr�[���v�g���C�A���Ԃŏa�̎Ԃ̏�𑖂�܂���B�@�u���z���R���s�������v�i�Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�T�u�^�C�g����?
�n�b�L���o���Ă��Ȃ��j���g�N���b�T�[�ő���܂���B�@�u�}�b�h�E�}�b�N�X�v�I�[�X�g�����A�̖\�����f��B�@�J���T�LZ1�ƃ}�b�N�X�^�[����̃E�B���[���f���炵����i�B�@�F�l�̈�l�͂��̉f������Ċ����A�R���ڂɃo�C�N�����B
03�N11��16���@Windows�@�A�b�v�f�[�g
�@���̃T�C�g��ǂ�őՂ��Ă��܂����X�͏��Ȃ��炸�p�\�R���Ɋւ��̂�����Ǝv���܂��B�@�����͂����ƃp�\�R���ɂ͋���������܂���ł����B�@2001�N�āA�f�W�J�����Ă��痸�ɂ����i����p��Ńn�}��j�Ă��܂��܂����B�@�g���Ă���ƁA�\���◝���Ȃǒm�肽�����Ȃ�Windows�Ƃ����\�t�g�Ɋւ���Ă�������܂���B�@
�@�v���o�C�_����̃T�[�r�X�Ŏ��XWindows�̃v���O�����ɏC�����������A�Ƃ̘A�����܂��B�@����܂ŋC�Â��Ȃ���������ǂ��A�C���ӏ��͕K���Z�L�����e�B�E�z�[���i���P�j��搂��Ă��܂��B�@�@���ۂ��o�O�̏C�����Ǝv����ł��B�@������A�Z�L�����e�B�ɖ�肪�����Ƃ��A�n�b�J�[�̃A�^�b�N���Ȃ��Ƃ��̔��f�ł��̂܂܂ɂ��Ă��������A�A�b�v�f�[�g�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv����ł��B�@���ێ����̎g���Ă�Me�̓}�C���\�t�g�E�u�����h���g���b�N�E�{�[���i��3�j���l�ꔪ�ꂵ�Ă��ڑ��ł��Ȃ������B�@�Ƃ��낪���C�u�E�A�b�v�f�[�g(��2)������A����Ȃ�ڑ����Ă��܂����B�@�}�C���\�t�g�Ђ��u�o�O�v�i��4�j�Ƃ������A�u�Z�L�����e�B�E�z�[���v�Ƃ������t���p���Ă��ł��傤�B
��1)�Z�L�����e�B�E�z�[��
�@�v���O������̊Ď�̌��B�@�R���s���[�^�Ɉ��Y���鈫���q����R���s���[�^�[�����ׂ̃v���O�����ɋĂ��錊�B�@�������爫���q�������Ă���B�@�����q�͂ǂ�ǂ�m�b�����A�̗͂𑝂��Ă���̂ŁA�Ď�����Ƌg�����K�v�ł��B�@
��2�j���C�u�E�A�b�v�f�[�g�@
�@�������̃\�t�g�X�V�Ƃł������܂��傤���A���ʂȂ�A�_�E�����[�h���v���O�����̎��s�A�����ƂŌJ��Ԃ��Ƃ���A�I�����C���Ń\�t�g�̍X�V���s�����ƁB�@�����͂��̑O�A�n�b�J�[�ɂ��ꂽ�̂ŁA�������s���܂��B�@�i��������Ă��Ȃ��B�j�@2001�N�H�̂��ƁA�w���́����ł̂��̂܂����������C���X�g�[���A���q�悭�g���Ă����B�@���C�u�E�A�b�v�f�[�g���Ƀn���O�E�A�b�v�����̂̓Z�L�����e�B�E�`�F�b�N���������������ׂ��ǂ����A�������ċ^��ł��B
��3�j�g���b�N�E�{�[��
�@�g���b�N�E�{�[���Ƃ͖��ߍ��^�}�^�}���w��ŃR���R�������ă|�C���^�i��ʂɏo����j�����A����}�E�X�̋����ɂȂ������c�ł��B�@�@�̂̓m�[�g�p�\�R���ɂ͑��ꂪ���Ă����悤�ȋC�����܂����A���ł͂���Ȑ��i�͔����ق��炢�ł������邱�Ƃ��ł��܂���B�@�킴�킴�����Ă܂ŕt���Ă���͎̂����̂悤�Ȋ���҂ł��B�@�g���b�N�E�{�[���ׂ͍��ȑ���ɂ͌����܂��A�|�C���^��U��Ƃ��ɑ�ϑ����������ł���̂ŁA��Ϗd�Ă��܂��B�@��瓮�������A�w�悾���łł���̂Ől�̍H�w�I�ɍ����I�ł��B
�@���łɁA�����̎g���Ă�g���b�N�{�[�����Љ�܂��傤�B�@�悸�A�ł����B�@�A�����J�l�����ł��傤�B�@�N���b�N�E�p�b�h���s�A�m�̌��Ղ̂悤��4�����Ă��܂����A�傫���ă{�[���ɐe�w���悹���4�̃p�b�h�܂ł͊��S�Ɏw���͂��Ȃ��B��p��2�������Ȃ��ł����B�@�A���w���ł��̂Ō듮�삪�Ȃ��A�{�[���͒��a��3�������炢����̂Ńm�[�g���ڕi��葀��͗ǍD�ł��B�@���ł̓}�E�X�͐ڑ��������Ă��܂���B
��4�j�o�O
�o�O�Ƃ����Ɖ�X�ɂ̓s���Ƃ��܂���B�@����̒��ƌ������t���Ȃ��݂�����܂���B�@�����H���Ďg���Ȃ��Ȃ�ƌ����Ӗ��̂��ƂƂ͎v���܂����A�l�����v���O�����ł�����A����ɖ������H���킯���Ȃ��A�����Ȃ�悤�ɐl��������̂ł�����A�����Șb���s�Ǖi�̍����ł��B�����S���ɕ����������S������ƁA����͑��̃����S�����点�Ă��܂��̂Ɠ����ł��B�@�����͂����茾���Ȃ��R���s���[�^�[�ƊE�̓o�O�A�Ƃ����}�C���h�Ȍ��t�ɒu�������Ă��܂��B�@�Ƃ͌����A���l�̎g���g�����S�Ď��O�Ɏ����i�f�o�O�j���ƂȂǕs�\�A�����ď����ڑ������ł��낤���Ӌ@�Ƃ̐ڑ��Ȃǂƍl����Ɗ��S�ȓ������邱�Ƃ͓�������m��܂���B
���������Ē��߂��蒷�������Ă���ƁA�̓ǂc�����́u�Ȃ�ƂȂ��N���X�^���v���v���o���܂��B�@�@�������͈Ⴂ�܂����A������͌ŗL��������p��̉�������������B�@�ނ�̒��߂͈ꎚ��哦�����ǂ݂܂����B�@���߂��ʓ|�Ȑl�͔����������}�j�A�ł������łȂ��l�ł��ǂ���ł��ǂ߂��ł���ˁB�@���������Ӗ��ł����N�V�[���[���h�̕��͑S�Ē����ƌ������ƂɂȂ�܂����ȁB�@
03�N11��15���@�^�o�R
�@�o���R�b�N�ł͍ŋ߁A�։��ꏊ�������Ă���̂Ƀ^�o�R���z���l�������Ȃ����悤�Ɋ����܂��B�@�C�^�`���[�̃I�g�b�c�@���͓c�ɕ�炵�ŁA���ł�90���Ă��܂����A�^�o�R���z���܂��B�@�����ł��B�@���݃^�o�R�������Ŏ��Ɋ����ċz����ł��B�@�����ɂ͕Е��̉��Ɋ����������Ђ����Ă��āA�����I���ɉ����Ȃ߂Đڒ����܂��B(��1)�@�������i��2�j�����݃^�o�R�������Ă��ł��˂��B
�@���������Ƃ́A�^�C�ł̓^�o�R��H�ׂ钎�����邱�Ƃł��B�@���{���玝���Ă������M�d�ȃ^�o�R�͗①�ɂȂǂɂ��܂��܂��傤�B�@�p�b�P�[�W�Ɍ��������ĐH���r�炵�܂��B�@�^�o�R���̂��̂͂���قǃq�h���H���r�炳���Ƃ�����ł͂���܂��A���ɒ��a1mm���̌����������A���������C���z���Ă��܂��̂ŁA�^�o�R�̉����z���܂���B
�@���{�l���C���[�W����^�o�R�̂��Ƃ��^�C��ŁA�u���[�A�Ƃ����܂����A�L�`�ł̃^�o�R�̓��[�E�X�b�v�i����F�z����j�Ƃ����܂��B�@�^�C�̖k�̕��ɍs���ƁA��ȃ^�o�R���Ă��܂��B�i�ŋ߂̓o���R�b�N�ł������Ă邩���m��܂���j�@���̂����ʐ^���ڂ��܂��傤�B�@���Ԃ�^�o�R�̗t���ςł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�t�͂܂��ΐF�ł��B�@���������t���̂悤�Ȋi�D�����Ă��܂��B�@���N�V�[�͗t�������X�z���܂��i��4�j�̂ŁA�t���̖������҂�����A�܂��͓��ʂȂ��̂��ƁA�z���Ă݂��Ƃ���A���̉��̖��������Ȃ��̂ł����B�i��3�j�@����͓`���I���[�E�X�b�v�Ƃ̂��Ƃł��B�@
��������
��1)�@�́A�A�j���Łu�r��̏��N�C�T���v�Ƃ������Ȃ����ؑ叫���n�ɏ�����悤�ȕč������J��̓��n���N����l���ɂ����ԑg������܂������A���̔ԑg�ŃE�C���Q�[�g��ƂƂ������̏W�c�̈�l���b�h���A���̊����̒[���r�߂ă^�o�R�������ċz���Ă����悤�Ɏv���܂��B�@
��2�j�@���{�̃^�o�R�̊����͒ʏ�ɐi�Ɏ_?�j�����Ă����āA�Εt�����悭���Ă��邻���ł��B�@�p�C�v�E�c�E�ɂ��A�����͂��̏ɐ̉����̂ɗǂ��Ȃ�=�p�C�v�̕����̂ɂ悢=�����ł��B
��3�j�@80�N��̏��ߍ��A�T�[�t�@�[�̊ԂŃC���h�l�V�A�Y�̃^�o�R�A�u�K�����v���������Ɏ��Ă���Ƃ��ŗ��s�������Ƃ�����܂��B�@�n�b�p�Ɏ��Ă���Ƃ��Řb��ɂȂ�����ł����A�S���̑��ł����B�@�^�o�R�Ɠ����i�X�Ȃ̐A���Ƃ͕����Ă��܂��B�@�@�z���߂��ɒ��ӂƂ�������Ă���̂ŁA�j�R�`�����܂�ł��邩���m��܂���B
��4)�@�������z���̂̓V�K�����ł��B�@�V�K�[���V�K���������{��ł͗t���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A�V�K�����͎����������炢�̑����ŁA�V�K�[�̏����p�Ƃ������܂����A���i��傫�������x�����ɂ����Ă���̂ł��B�@�t�����s������L���܂ł����āA�L���[�o�̉��Ƃ��A�Ƃ����t���́A�A���~�̊ʂ�1�{�������Ă܂��B�@�i�̂�1�{2���~�ƕ����Ă����j�@�ʐ^��f��ł����������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�L���O�R���O���z�����炢�ł����̂ł��B�@�@�t���̈��D�Ƃ͗t���J�b�^�[�������Ă��āA1�{�z���Ă��܂킸�A�r���ŃJ�b�g���Ē����ɂɂ��܂��Ă����܂��B
�@�@�����Ă����^�o�R�̃p�b�P�[�W���Љ�܂��傤�B�@
| ��i�̓p�C�v�p�ŁA�����X�E�F�[�f���̃{���N���E���[�t�R��A�E�����R�B |
|
 |
 |
���i�͑S�ăV�K�����B�@�����Ɖ���3�Ԗڂ��ƈ�A����4�Ԗڂ��p���A���̑��S�Ęa�����B�@ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
�@�@���E�̃V�K�����]���T�C�g
http://www.cigar-cult.at/englisch/stn302.htm
�@���R���ǂ����m��܂��A�����̔����V�K�����͖w�ǃI�����_���ł��B�@��`�̖ƐœX�ȂǂŔ�������A�^�C�ł̓X�N���r�b�g�ʂ�̖�ǂł悭���������̂ł��B�@�t���̈�Ԉ�ۓI�ȉf��̓N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�́u�r��̗p�S�_�v�i��5�j�ł��B�@�C�[�X�g�E�b�h�͉����ŗt�������ݒ��߂Ă��܂����B�@�G�W�v�g�̃N���I�p�g���Ƃ��������^�o�R�͂��Ȃ�t���ɋ߂����̂������܂����B�@���{�ł̓����o�[�W���b�N������Ȋ����������悤�ȋC�����܂��B
�@�p�C�v�E�^�o�R����R�z���܂����B�@�t�B���^�[�Ȃ�Ă���܂���A�x���ɂȂ��Ă�������������܂���B�@�p�C�v�̈�ʓI�Ȃ��̂̓s���p�I�Ƃ����̍�����������܂��B�@�@�ۂ����ōd���A���j���O�ɂłɂ����ގ��ł��B�@�|�p�C�̂��킦�Ă���̂͂��Ԃ�g�E�����R�V�̍ގ��ł��傤�B�@�p�C�v�^�o�R�͑��A�����F����t���Ă���܂��B�@���{�ł͓��R�E�E�v�����i�[�h�Ȃǂ���܂����B�@�O�����i�����낢�뎎���܂������A�ŏI�I�ɂ̓{���N�����[�t�ɂȂ�܂����B�@�D���������f�����p�C�v�D���ŁA�J�i�_�Y�̃L���v�e���E�N�b�N�i���������ȁj����������Ƃ���500�������肭�炢�̊W���J�b�v�ɓ����Ă��āA���̗ʂɃ^�}�Q�^���Ƃ�����܂��B�@�i���ʂ̗t����50������̑܂ɓ����Ă���j
�@�@�p�C�v�̃T�C�g�i�X�E�F�[�f����ƌ����S������Ȃ��j
http://www.cigarworld.de/shopdata/shop.php4?UserID=1073226709360&aktion=auswahl&wgr=Pfeifen
�@�t�����X���^�o�R�̎�����Ƃ����̂��́A���{�Ŕ����Ă��܂����B�@���������Ă��邩�ǂ����B�@�����Z�b�g���āA���ō��ꂽ�����̍a�ɍ��݃^�o�R������B�@�r�j�����̑т����邭��Ƃ��ꂢ�Ɏ��������ł���̂ł��B�@���̂������̃y�[�W�Ɏʐ^�ł��ڂ��܂��傤�B�@���{�ł������݃^�o�R�̓L�Z���p�Ɂu�j�[�v�Ƃ������i���Ŕ����Ă��܂��������A���邩�ǂ����H�@�L�Z���͂Q-�R���ŋz���I���A�^�o�R���l�ߒ����A�܂�������A�Ǝv���Ă����Ƃ���A���̓��̃c�E�ɂȂ�Ƌz���I�����Ύ���L�Z���̉ΎM����Ύ����̂Ђ�ɒ@�����Ƃ��A�D����������Ă܂��L�Z���ɖ߂��B�����Ď��̃^�o�R���l�߂邻���ł��B�@���̋Z�͌������Ƃ�����܂���B
��5�j �@�C�[�X�g�E�b�h���������l���̃K���}���A�_�u��������Ă��܂����������߂悤�Ƃ��邪�{�X�Ɍ�����A�e�����ĂȂ��悤�ɂƁA����N�V���N�V���ɔn�ɓ��܂��B�@�������ɏ�����ꌊ�q�ɂ�����A�S�ŊZ��������A����ڂ�e����ɓ����B�@�@�L�Y�̖������Ƃ��{�X�ƌ�������B�@���̓��A�|���`���̉��ɓS���Ԃ牺����B�@�{�X�͉��ׂ���C�[�X�g�E�b�h�����B�@�O�e�I�����A�s�x�|���̂ɋN���オ���Ă���B�@���x�����x���E�E�B�@�S�̊Z�ɓ������Ă��邩�炾�B�@�e�ۂ��s���A�C�[�X�g�E�b�h������ڂ�e�̈ꌂ�Ń{�X��|���B�@
�@�ǂ����Ă����܂ŏڂ������������B�@����̓N���T��+�O�D�́u�p�S�_�v�̃R�s�[������ł���B�@�O�D�����}���Ԃ𗠐�B�@���E���ɉ�������ɏ�������B�@�����ɘU��A���ӂ̓����Ȃ��̂ŁA��ő����|���ׂɕ������A���P�����A������������ȋZ�ɖ����グ��B�@�L�Y�̖�����������A�U���Ă����������o�āA���}�̃{�X�Ɍ����ށB�@�B�������Ă�����𓊂������|�����B�@�N���T��+�O�D�́u���l�̎��v�����쌠�N�Q�Ɂu�r��̎��l�v������B���̃X�g�[���[�������K���}���ɂȂ��������ł���B�@���̉f��͍��L���X�g�������B�@�W�F�[���X�E�R�o�[�����i�C�t�����̖���Ƃ��ēo�ꂵ�Ă����B
�����K���}���̗���Ŏv���o���̂��A�Ӗڂ̋��������A�����s�B�i���V���Y�剉�V���[�Y�f��j�@���̃}�J���j�E�E�G�X�^���i��1�j�ł��u�u���C���h�}���v�i1971�N�j�B�@�Ӗڂ̃K���}���ň����Ɛ키�B�@�剉�̖��͒m��Ȃ����A�r�[�g���Y�̃h���}�[�A�����S�E�X�^�[�i��2�j���e���o�����Ă����B�@�L�����f�B�[�Ƃ��������o���Ă���B�@TV�ł�2���B�@���߂Ɍ��������͂�1978�N�����B
��1�j�@�������s�����E�G�X�^���f��̃C�^���A���B�@�ꌹ�ɂ̓C�^���A�̃C���[�W�̃}�J���j���E�G�X�^���ɑ��������́A�ƕ����Ă���B�@�W�����E�E�G�C���ɑ�\����鐳���I�č��E�G�X�^�������l�ԏL���������o�Ă����C���[�W���B�@�Č�ł́u�X�p�Q�b�e�B�[�E�E�G�X�^���v�Ƃ����ƕč��l���畷���āA�}�J���j�E�E�G�X�^���͘a���p��Ǝv���Ă���B�@�m���ɁA���{�̉䂪�Ƃł̓X�p�Q�b�e�B�����}�J���j�̕����H��Ɍ��ꂽ�̂͐悾�����B�@�i��3�j�@
�@�u�r��̎��l�v�A�u�r��̗p�S�_�v�ƃt�����R�E�l���剉�u���r��̗p�S�_�v�A�W���A�[�m�E�W�F���}�剉�́u�r��̂P�h����݁v�A���[�E�o���E�N���[�t�剉�́u�h�N�E�z���f�C�v�A���w���̂Ƃ����Ă�������܂����Ȃ��A����ȃK���}�����B�@�i�X�g�[���[���P���ŃW�����E�F�C���͍D���ɂȂ�܂���ł����B�j
��2�j�@�{���@���`���[�h�E�X�^�[�L�[�i�Ƃ͂ǂ��ł��������j�B�@�h������@���ĉ̂��̂Ƃ����s�v�c�����������B�@�r�[�g���Y�̉f��B�e���ɉ��Z�͂��A���҂����邱�ƂɂȂ����B�@�r�[�g���Y�̉́A�u�A�N�g�E�i�`�������[�v�i���R�ɓ����j�Ȃǂł͉f��o���̂��Ƃ��S�ɂ��Ă���B�@�u���C���h�E�}���ł͈��}�̖����҂����荇���Ă����悤�Ɏv���B�@���̌�A�u�������Ȃ������ȐΊ�l�v�i����u�P�C�u�E�}���v�j�ł͎剉�B�@�g���_�Ƃ������O�B�@�u�g���_�A�T�N�T�N�A���i�v�i���n�l��Ńg���_�̓��i���D���j�Ƃ����Z���t���Y����Ȃ��B�@���̃T�N�T�N�Ƃ̓��C�N�E���u���w���Ɖ���ɂ������B�@����Ō����̂�1982�N���炢���������E�E
��3�j���łɎႢ����̕��ɓ��{�̐H�����̐��m���̐��������悤�B�@���m�̕������������͖̂����ېV�˗��Ǝv���Ă��邩������Ȃ����A����̓u���W�����̘b�ŁA��ʐl�͐�セ����A��㕜�������������Ă���ł���B�@���������āA���m�̐H�ו������菉�߂��̂����a30�N��i1950�N��̌㔼�j�Ƒz�������i���N�V�[�͏o���O�Ȃ̂ŕ������b�j�B�@�@���̕����̕s���ŁA�H���I���̗]�n���Ȃ������͂��B�@���a30�N��㔼�i1960�N��j�ɓ���ƍ��x�����ʼn҂������������܂��Ă����B�@�����͐��m���ɔ�т��Ă������B�@���m�̕��͗T���Ő������ꂽ����̃C���[�W�������B�i�ɈႢ�Ȃ��B�������b�j�@
�@�l�I�Ȍ����ł́A������20�N���O�ɂ́A���{�̐H�����͂��̂܂ܐ��m������čs���A�ĂȂǂ͕s�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������z�������B�@�Ƃ��낪�A�ǂ��������{��������������A�m�H���͏����y�[�X�_�E�������B�@�����͂��̗�����A�c��̐���̉ƒ뉻�ƕ��́i�ȁ`��Č����Ă݂����j���Ă���B�@�c��̐���i��4�j���Ɛg�̎��͊O�H�ŗm�H��H�ׂ���A�V������ɂ͉ƒ�ŗ����{�Ў�ɍ�������A�q�����o���A�ƒ�Ƀh�b�v���Z����ƁA��{�͕āA���X�`�ƒЕ��̐��E�������A�Ƃ�����ł���B�@
��4)�@�c��̐���͂�������̓��{�����ݏo�������A���H�W�̑傫�ȃ��[�u�����g�̈�ɂ͋i���X������B�@���̐��オ�t�̍��͔��Â������̋i���X�����������B�@�������Â��Ƃ���ɍs�������C���[�W���������̂��낤�B�@�w���^���A�s�b�s�[�E�X�^�C���A���R�����Ȃǂ͓��l�̐e�̐��ォ��͔ᔻ�𗁂т邱�Ƃ������������A���ɂ͋삯�����Ƃ������S�������������B�@���l����A�����I�ȓ��{�Љ��̒E�炾���������m��Ȃ��B
�@10�N�قǑO����A�}�ɋx���͎R��c�ɂɏo������l���������B�@�̂͌����ďa���Ȃ������A�����Ȃ��n�Y�̎R�ւ̊X���͖��T�x���ɂ͏a����B�@�����ăK�[�f�j���O�E�u�[����_�Ƒ̌��w�K�̏o���ȂǁA�Ȃ�ƂȂ��y�E���Ԃւ̊S�����������Ȃ�̂�50���炢�ł͂Ȃ����ƍl����ƁA������c��̐���̕����Ƃ��v����B�@�̗̂��s�茾�t�Łu���h�E��O�h�v�ƌ���ꂽ���A��O�Y�܂�ƁA��㐶�܂�ł͎u�����Ⴄ��������Ȃ��B�@
�@���̂悤�ɒc��̐���𒆐S�ɍl����ƁA�悪�Ȃ�ƂȂ������ԁB�@�c��̐���͐��̕����ł̃x�r�[�u�[���Ő��܂ꂽ���ゾ�B�@1945�N���I��Ƃ���ƁA�擪��2004�N�̍��A����N���61���B�@��N�ސE�������X������������B�@�i���@���A���X�g�����܂ށj�@�����ŁA���̗��s�����X�g���ɂȂ��Ă���B�@���X�g���u�[���͂��Ǝb�������B�@�܂��c���Ă���l����������B�@���̌ォ��{�i�IXX�u�[��������Ă���B�@XX�͐l��60�ɂȂ�Ƃ�肽�����Ƃł���B�@�����c�ɂɂP�ˌ��Ăɂ��āA�ƒ�؉��Ƃ������s��B�@��������ƁA�����ŏo������́A�]��̂Ŕ�����B�@�����č��ƈႤ�X�^�C���̎s��i�����j���o���������B�@�H�i�͍����Ă����S�⌒�N�x�̍������̂ɂ��V�t�g����B�@
�@����A�ސE���̎g�������Ȃ��T���ȕ��X�������B�@����ƁA�悸�͎茘���M���A�����Ċ��Ƃ��ɂȂ�B�@�悸�͔����킯������A�����ɂȂ�B�@���͏オ��B�@
|
