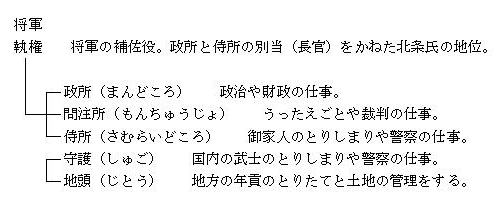1.鎌倉時代
1
壇ノ浦の戦いで平氏を破った源氏は、
1192年、
源頼朝が征夷大将軍となって鎌倉幕府を開いた。その後、
1333年、元弘の変で新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼすまでを鎌倉時代という。
2 鎌倉幕府のしくみ
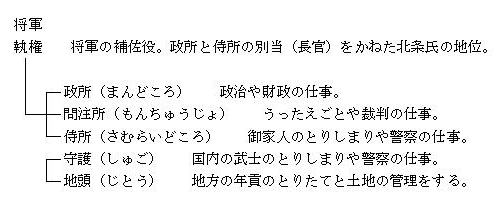
幕府と御家人は、
御恩と
奉公という双務的な主従関係で結ばれていた。
【考察】「双務的な」とはどんなことだろう。朱子学に基づく江戸時代の主従関係(封建制度 feudalism)とこの時代の主従関係はどこがちがうのだろう。
3 執権政治
すぐれた指導者であった頼朝のもとでは、将軍独裁の体制で政治が運営されていたが、彼の死後は、
北条氏が有力御家人の中から台頭してきた。北条氏は名ばかりの将軍をたて、自らは
執権となって政治の実権をにぎった。
※執権=政所と侍所の別当(長官)をかね、将軍の補佐役となった北条氏の地位をいう。
(1)承久の乱(1221)
後鳥羽上皇が討幕をくわだてて起こした反乱。幕府側が勝利。
(2)御成敗式目(貞永式目)(1232)
武士がつくったはじめての法律。
1232年、
北条泰時が頼朝以来の武士の慣習をまとめた。
cf.泰時消息文(泰時から重時へ)
4 元寇と幕府のおとろえ
元の国から日本も従うようにという国書が送られてきたが、当時の執権
北条時宗はこれをこばんで、九州の守りを固めた。
1274
文永の役
1281
弘安の役
2度にわたる元軍の襲来があった(元寇)。
【課題】元寇をきっかけに、幕府がおとろえていった様子をまとめてみよう。
5 鎌倉文化
【課題】鎌倉時代の仏教は、それまでの祈とうや学問中心のものから、内面的な深まりを加え、広く庶民にも広がりました。
法然、親鸞、一遍、日蓮、栄西、道元について調べてみよう。