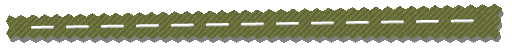
真空管オーディオのページ
 |
左の写真は、6L6GB全段差動プッシュプルのパワーアンプ。 初段;12AU7 ドライブ;6FQ7(6CG7) 終段;6L6GB(6L6GCがほしい) 出力は、最大10W程度かな? (回路構成) 下の写真は、シールドケースに入った12AU7単管のプリアンプ(トランス出力)。2本見えますが、1本は予備として実装しています。(回路構成) |
| 家主が、最近大好きだった無線機にさわらないと思っていたら今では時代遅れ?の真空管アンプをつくっていたんだね〜。 この浮気者。 でも、冬場は近くにいくと真空管があたたかくていいね〜。 |
 |
| 【家主から一言】 このパワーアンプは、木村 哲氏のホームページから影響を受けて改造した全段差動増幅のPPアンプです。もともとは、6L6GB PPの普通のアンプでした。 木村さんのホームページをみていて、最初は計測器でもないのに何で差動増幅なのかなという感じでした。それも、わざわざ真空管で差動増幅しかも最終段までと思っていました。でも、興味があったので確認しなければと思うようになり改造することにしました。 差動増幅の設計方法がわからなったときに、木村 哲氏の作品をみていましたが、なかなか設計方法をアップしてもらえなかったのでメールで設計方法を質問したところ丁寧に質問に答えていただきました。そして、すぐにホームページにもアップされました。ありがとうございました。 このアンプは、まだ改造の余地がたくさんあるのですが、あとの楽しみにとっています。でも一応、気に入っています。 プリアンプは、差動増幅ではないのですが、少し贅沢にタンゴのトランス出力としています。球は、やはり12AU7の一段ですからゲインはトータルでは、ほとんどありません。出力ケーブルを少しくらい長くしてもドライブできるかな。 このプリアンプは、入力のセレクターもありません。音量調整用VRのみです。セレクターは、外部にロータリーSWだけのものを作成してあります。プリアンプもパワーアンプとも共通しているのは、電源SWです。操作性の悪い背面か電源トランスの近くに配置しています。AC100V系を信号系の近くにもってきたくなかったからです。 どうせ私しかつかわないのでこれで良しとしています。 また、各アンプのヒーターは全て直流点火としてあります。 プリアンプは、シングル動作なので、B電源はトランジスタによるリップルフィルタをとうしています。出力インピーダンスは、150オームと600オームの2種類です。 (調整中の本機) できれば、このプリアンプも差動増幅に改造したいと考えています。球も6SN7あたりにかえてみたいなとも思っています。トランス出力なので、理論上は効果は期待できると思っています。 |
 |
パワーアンプのTopViewです。 シャーシが比較的小さいので部品配置には、苦労しました。普通のアルミシャーシなので薄く、小型のL型アングルでサイドと内部で機械的強度を保つため、補強してあります。もう少しシャーシ面積があると作成は容易だったと思います。内部の配線も結構大変でした。各段の定電流回路は改善が必要と考えています。負帰還は、6dB程度かけています。 (その他の写真集は、こちらです) |
| 右の写真のスピーカは、フォステクスの10センチフルレンジ FE-103を使用したダブルバスレフです。第一ダクトは、100Hz、第二ダクトは、50Hzで設計しました。 すべて自作です。でも、FE-103での駆動はちょっときついようです。16センチクラスのユニットに替えてみたいと思いますが残念ながらこの箱にはスペースがなくテストできません。もう少し大きめに作っておけばよかったと思うけど後の祭りです。 |
 |
 |
左の写真。 フォステクスFE-127 2本とテクニクスのツイータを使ったトールボーイ形スピーカです。こちらの箱を作るときも苦労しました。中域がイマイチかな。と思っています。クロスオーバ周波数が問題なのか?でもネットワークは簡単にはかえられないし困ったものだ。あとテクニクスの16センチのユニットを取り付けたバスレス式のスピーカもあります。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる