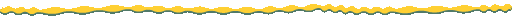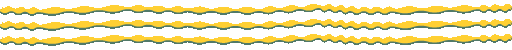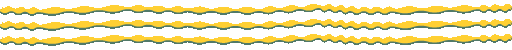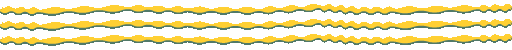
2001年3月
( この月の末尾へ )
3月1日(木)
今日は霧雨みたいな中途半端な雨が降っていた.年度末で道路工事も多かったので,
あちこち道路に土が出ていた.というわけで,そんな中を走ってくると,車がドロドロになってしまったのであった.
ざーっと大雨が降ってくれないかな.
大津インターを降りると,料金所に赤色灯をつけた紺色のR34スカイラインがいた.そのスカイラインは料金所を出ると,
Uターンしてまた高速道路に入っていった(このときは赤色灯はついていなかった).その後,国道1号線に出ると,
白のCREWが右折しようとしていたが,横を通りながら観察すると,リアトランクにあやしいアンテナ,ルームランプのあたりにあやしい箱,
フロントにはあやしいフォグランプがついていた.このフォグランプは黄色ではない可能性が高いかな.
今日もトヨタ部品共販に,この前,注文したブレーキラインのクリップと,ATのドレーンボルト,ガスケットを受け取りに行く.
しかし最近,どんなカー用品店よりも,部品共販の方に多く来ているような気がするのは気のせいか.
なお,純正のドレーンボルトには,ATFの種類を示す「D-II」という文字が刻まれていた.
3月2日(金)
今朝,寒いなと思っていると,山中越えは雪が降っており,路面も半分,凍結状態.
でも雪が降ったり凍ったりするのも,今年はもう最後じゃないしら.来週くらいにはスタッドレスからノーマルタイヤに替えよう.
朝,大学のパソコンのスイッチを入れると・・・げげっ,動かん.リセットしてもだめ.
「ピー」っというのがならないのであった.そういえば,昨日,フリーズしたことがあった.
CPUがKatmaiのときには24時間くらいつけっぱなしでもフリーズなんてしなかったことを考えると,
Coppermineに換えたことが関係している可能性がある.本体を開けてCMOSをクリアしてみる.
そうすると,ちゃんと起動してBIOSのセットアップ画面になった.しかしセットアップを終了してWindows2000を起動しようとすると・・・
あ,また死んじゃった.やっぱりP2B-Fだとだめなのかしら.マイクロコードのアップデートの関係なのかな.
しょうがないので,明日にでも日本橋に行ってCoppermine対応のマザーを買うことにする.
私の使っているSDRAMはすべてECCタイプなので,440BXのボード(できればCUBX-E)がいいのだが,なければまた考えよう.
注:DRAMのエラーレートについて
DRAMに限らずメモリ製品においては,自然界の放射線のため偶発的なデータエラーが生じることがある.
過去にはLSIのパッケージに含まれる微量の放射性物質から出るα線の影響が大きかったが,
パッケージに使われる材質の純度を高めることで現在ではほとんど問題にならくなったという.
もう一つの原因として,宇宙からの放射線によって生じる二次的な荷電粒子の影響があり,これは対策が難しい.
これらをトータルした場合のデータエラーが生じる確率は10年に一回程度であるという(高々度を航行する飛行機内では100倍以上,
エラーレートが上昇するらしい).
この程度であれば家庭用として使う分にはECCは必要なさそうなのであるが,気分的に大事なデータが失われたりするといやなので,
ずっとECC付きメモリを買い続けている.でも,最近の133MHzのマザーだと,SDRAMモデルはECCないのよね.
RAMBUSはECC付きなんだけど,高いからなぁ・・・.
参考文献:富士通研究所
『DRAMのスケーリング則に中性子ソフトエラー効果を追加』
3月3日(土)
予定通り,マザーボードを買うために日本橋に向かう.何軒か見て回ったが,440BXとしてはCUBX-Lしか見つからなかった.
CUBX-Eとの違いは,Ultra100ATAがついていないことと,USBの拡張コネクタがないことくらいであるが,大学ではUSBは使っていないし,
PromiseのUltra100ボードがもともと買ってあるので,今回はCUBX-Lで妥協する.値段は¥10800.大学に戻るとすぐに交換作業を開始.
Socket370はCPUの取り外し・取り付けが面倒くさい.それ以外は普通の作業である.コネクタ類をつけ直して,
いよいよ電源投入・・・・「ピッ」おおっ,動いた動いた.BIOSセットアップをすると,Hardware Monitorの項目で,
Power Fanの数値が赤色になっているのが気になるが,無視してSave & Restartすると,起動画面中で「Hardware Error」
が出て止まってしまった.どうもPower Fanの回転数が正常範囲以下のためらしい.しょうがないのでBIOSセットアップで「Ignore」
を選択すると,ちゃんと次に進んだ.
注:この電源ファンは,共立電子で¥500で買ったジャンク品の9cmファンで,
いちおう3pinタイプだったがコネクタが違っていたのを切断して,適合するコネクタにつけなおしたものである.
しかしP2B-Fでは回転数が表示されなかった.ジャンク品だししょうがないな,と思っていたのだが,
このCUBX-Lではちゃんと表示されるので,ファン自体は問題なかったらしい.ただ9cmなので8cmのファンよりは回転数が低いのは当然だろう
(だいたい1600rpmくらい).回っているのだから問題はないはずなので,警告する回転数を変更できるようになっていたらよかったのに.
ところが,今度はSCSIの初期化部分でタイムアウトが発生して止まってしまった.で,AHA-2940AUのBIOS設定メニューに入り,
SCSI Utilityを起動しようとするが,やはりタイムアウトしてしまう.外部機器F(外付けMO,HDD)のSCSI IDを変えてみてもだめ.
念のためケーブルをSCSI I/Fから抜いてみると,今度はOK.そこでケーブルを慎重に差し込んでみると,あらら,ちゃんと認識しました.
ケーブルの接続がまずかったということか.リセットすると,ちゃんとWindows2000が起動.よしよし.
さてちゃんと動いたことだし,メールの確認でもしようか・・・「ピピピッ」.あり?「サーバのアドレスを取得できません」
もしかしてDHCPサーバが死んでるのかな.見ると,たしかに死んでいる.再起動,再起動っと.
さて,起動したはずだぞ.どうだ.「サーバのアドレスを取得できません」なんでや〜.
しょうがないので,クライアントも再起動.今度こそ.「サーバのアドレスを取得できません」うが〜っ.
今日はあきらめて,明日,原因を調べよう.と思い,シャットダウンして帰り際,EthernetHUBを見ると,
ランプがいつもより少ないような気がする.もしや・・・と思い,マシンの裏を見ると,案の定,Ethernetケーブルが抜けたままだった.
なんともお間抜け.
3月4日(日)
今日は雨.山中越えには路面に大量の落ち葉が流れ出していた.秋,木から落ちた葉は地面を覆い,
生き物たちを冬の寒さから守っているのだろうか.そして春になると雪解けとともに落ち葉は流れ去り,
あとに新しい生命が芽吹いてくる.温度計は6℃という表示だった.山にも春が近づいてきていることを実感させられた.
↑上のような書き込みをしたら,ニュースでは今夜は大雪とのことで,鹿児島県でさえ雪が積もっている映像が流れていた.
まったく,人の思ったことを見事に裏切ってくれるものだ.でも,さすがにそろそろ今年の雪も終わりだろう.
3月5日(月)
この前のCoppermine850が動かなかったのはマザーボード(P2B-F)が古かったからだということがわかったのだが,
そういえば以前にもこのP2B-FでCoppermine600Eが動かなくなったことがあった.
このときも取り付けてから1週間くらいで動かなくなったのだが,もしかすると同じ原因かもしれない.
そこで押入に眠っていたCoppermine600Eを取り出してきて,これまでCu-Cerelon566が差さっていたマシン(マザーはP3B-F)に差してみた.
そうすると・・・やっぱし.ちゃんと動くじゃない.メモリはPC133なので600MHz(システムクロック100MHz)でも問題なく動いている.
なぁ〜んだ.でも壊れてなくてよかったよかった.そうすると,いまKatmai-500の差さっているP3B-FをP2B-Fに交換して,
捻出したP3B-Fを余っているCerelon566,128Mのメモリ,10GのHDDと組み合わせると,もう一台,パソコンができるなぁ.
今日は意外にもよく晴れていた.阪急電車に乗って桂川を渡っていると,北の方におわんをかぶせたような山が見え,
あ,あれは嵐山だ,という認識がわき,何だかうれしくなった.で,その東側を見ると,五山送り火の一つ,鳥居が見えた.
あら,こんなところにあったんだ.ここ数ヶ月ほど毎週ここを通っていたのに,初めて気付いた.
う〜ん,いつもよく見ているつもりで,実はあまりちゃんと見ていなかったがわかった.でも収穫,収穫.
3月7日(水)
きょうは洛西に行く日だが,名神に乗ろうとすると西行きは工事のため1車線に規制中.
まぁ,工事が必要なのはしかたないんだけど,もうちょっと影響の少ない時間にできないものかしらね.
でも,もともと大津から京都にかけてのあたりは道路自体が少なくて,ちょっとしたことで交通がマヒしてしまうという現状があるので,
こっちの方を早くなんとかしてほしいところ.第二名神が神戸北まで全通すればかなり改善されるだろうが,何十年後のことやら・・・.
いまは草津から亀山まで工事中で,草津JCT付近の工事を見ると2〜3年でできそうにも見えてしまうが,
先日,信楽付近を走ったときには,途中のトンネルなどは工事をしているが,地上区間の工事はまだほとんど手つかずのようだった.
これだと早くても7〜8年後くらいだろうか.う〜ん.
3月8日(木)
今日は研究の進行状況を発表する日.でも最近,バイトが忙しくてほとんど用意ができてない.
で,朝早く大学に行ってレジュメの作成.図と写真をいくつか貼り込んで字を書き足したら,まぁ,それらしいのができた.
では印刷開始〜・・・遅いぞ〜っ.カラー写真があるからなぁ.待つこと数分.ありゃ?字が化けてる.設定を変えて再出力.
う〜ん,やっぱり化ける.再起動しないといけないのだろうか?でもそんな時間ないしなぁ.しょうがない.これで10枚出力,と.
コートを着込んで出撃用意完了.さて,そろそろ全部,出力されたかなぁ・・・げげっ,何にも出てないし,データそのものが来てない!
ぎゃぁ,時間がない〜.再立ち上げして出力しなおし.遅いなぁ(スプールデータ67Mbytes.インターフェースは100BASE-TXなのだが,
速度は10BASE-T程度だなぁ・・・画面上での残りデータバイト数を見ていると約0.3Mbytes/sec).おっと,今度は字が化けてない.
やっぱり再起動したのがよかったのか.う〜ん,急がば回れを地でいってしまったな.結局,ちょっと遅れてしまったが,
なんとか発表自体は無事,終了.めでたし,めでたし.
というわけで精神的に少し楽になったので,久しぶりに大学生協へ本を買いに行く.2月は短いので,
あっというまに次の月の雑誌の発売日になってしまう.それはともかくとして,今日の収穫は『京都地図物語』.
タイトルだけ見ると京都の地理学上の歴史のようだが,実際の内容は現代地理が多い(もちろん歴史的記述も多いが).
京都を交通・経済・環境などを考える上でいろいろ興味深い本である.
夕方,外を見るとえらい雪が降っている.その後,外を歩くと大文字も雪をかぶっていた.でも平地にはまったく雪はない.
最近,毎回,雪が降るたびに「これで今年の雪も最後かなぁ」と言っているのだが,なかなかそうは問屋が卸さないらしい.
でも今週末はタイヤをスタッドレスからノーマルに戻すぞ〜.雪が降ったら?・・・そんなの知らん!
3月9日(金)
上のようなことを書いていると,日付が変わる頃に,どうもくしゃみが出るので何気なく外を見てみると,
あらら,真っ白け.ほんの3時間前に家に帰ってきたときは何ともなかったのに.翌朝,家の前は10cmほどの積雪で,
新雪を踏み分けて車までいき,車ももちろん雪だるま状態なので雪下ろしに励む.これから山中越えをしないといけないので,
できるだけ車を軽くしてやらないと登り坂でスタックしてしまう恐れがあるから,面倒でもしっかり雪を除去しておかないといけない.
朝のいい運動になってしまった.車のまわりにも雪がたくさんあるので,まず駐車場から出るときにこの雪で動けなくなる可能性があったが,
幸い,駐車場は道路に向かって下り坂になっているから,ここは無難にクリア.家の周囲の道路は融けかけたシャーベット状態で,
そんなに滑りやすいわけではない.しかし京阪電車をくぐって,西大津バイパスへ上がっていく坂道が次の難関.
以前,雪の降った日に途中の信号で停車したら再発進不能になったことがあったので,ここは前方の信号をよく見て,
信号で止まらなくてもいいようにタイミングをはかって通過した.ここの坂道は山中越えの最大斜度とほぼ同程度(10%)だから,
ここを登り切れれば山中越えも登り切れる可能性が高い(もちろん山中越えの方が標高が高いから,凍結はより強いだろうけど).
さて,西大津バイパスを越えて山中越えに入っていくが,ここでは轍がシャーベット,それ以外は積雪という状態.
とりあえず轍をはずれないように,また登り坂でラフなアクセル操作とならないように30km/hほどで走行.
峠の料金所を過ぎた下り斜面は,完全な圧雪路となっていたが,その向こうではシャーベット状.
他の車について20km/hほどでのろのろ走る.反対側の大津方面への登り坂では,途中で登れなくなったのか,
道の真ん中でチェーンを装着中の車が2台ほど,乗り捨てられた車を1台見かけた.
たしかに大津側に住んでいる人はスタッドレス等の備えをしているが,京都の人はそんなのしてないだろうからなぁ.
それでも北白川の温泉を過ぎると,車線内はほぼ雪は融けており,だいたい普通に走れるようになっていた.
というわけで,無事に京都に到着.しかしこういう条件下でもちゃんと越えてこれたということは,
山中越えに関しては冬でも走れないことはないということか.ただ濡れた路面が凍りついたブラックバーンなどの経験はないので,
もしそんなのができていたらやばいんだろうけど,幸い,このあたりの気候は,冷え込むときは底冷えが多いので,
本当に寒いときは雪が降らず,雪が降るときにはあまり寒くない,というありがたい性質をもっているので,
東北や北海道のような怖い目にはあわなくてすんでいるようだ.
昼,所用でいったん家に戻るが,そのときは山中越えも路面の雪はほぼ融けており,普通に走ることができた.
日射しが強くて,おかげで路面からはうっすらと水蒸気がたちのぼっていた.
さすがにこの雪では,山中越えを走る車はふだんよりもだいぶ少ない.
大津側の景色は,真っ青な琵琶湖と平地に積もった雪のコントラストがなんともいえず美しい.なんか得をした気分.
でも昼間も断続的に雪が降ってきて,天気予報だと明日からもまた寒くなりそうだとのこと.タイヤ交換はそのあとにしたほうがいいかな.
3月10日(土)
今日も少し雪がちらついてはいるが,積もるほどではなさそう.とりあえず,もう雪の中を遠出することもないので,
チェーンをトランクから降ろして夏用の蛇腹のボックスに積み替えた.これで家の中が少し整理できそうだ.
また大津のロードスターにプラグの新品サンプルを1本と,アーシング用のコルゲートチューブを買いに行く.
コルゲートチューブは銀色,赤,青の三色しかなかった.緑がほしかったのだが・・.また純正プラグであるが,
近江大橋のロードスターではDENSO PK20R11だったのに,こちらではNGK BKR6EP-11であった.外したプラグはBKR6EP-11だったので,
プラグの使用前後の比較という意味ではこちらのほうが確かに理想的ではある.値段はどっちも¥1500で同じであり,
TOYOTA GENUINE PARTSの箱に入っていた.またそれとは別に,以前にトヨタ部品共販で注文してあった,
プラグコードを支持するクランプを受け取りに行く.折ってしまったものは黒色だったが,届いた部品は白色だった.
材質も少し柔軟性があるような・・・対策品??まぁ,折れた部品は10年間,エンジンの熱と振動にさらされていたわけだから,
経年変化でもろくなってただけかもしれないけど.
(新聞より)
本日,保津川開きと琵琶湖開きが行われたとのこと.そういえばミシガンは2回乗ったけど,保津川下りはまだしたことないなぁ.
トロッコ列車で上がって,川を下ってくるのがいいのかな?また考えておこう.
3月11日(日)
昨日に続いてレンタルCD屋さんでシングルCDばかり12枚借りてくる(昨日は20枚借りた).
借りたCDはいったんHDDに落として,そのうちオムニバス形式に編集してCD-Rに焼くようにしている.
またタイトルをデータベースに入力し,歌詞はテキスト形式で入力.これまで借りたCDの枚数がついに700枚を突破してしまった.
歌詞をおさめたテキストファイルもすでに650kバイトほどになっている.しかしまぁ,われながらよくやったものだと思う.
そういえば今年はこの店から年賀状が来ていた.枚数だけなら,この店でいちばん多く借りているのかもしれない(シングルだけだけど.
ベストアルバムは原則的に自分で買う).
3月12日(月)
今日,大学の教務課の前に人がたくさん群がっていた.よく観察すると,彼らは教務課へ入る道の両側に2列に並んで,
その間を通る人を待っているように見受けられた.また昼間,バス停でバスを待っていると,
向こうから大きなうさぎのぬいぐるみが歩いてくる.このうさぎのぬいぐるみは,背中のところに「××ハウジング」
と書かれたジャケットを着ていた.今日は何の日だろう?ちなみに後期の入試は明日と明後日なので,これとは関係なさそうである.
3月13日(火)
今日から後期の入学試験だと,昨日に書いたのだが,はたして今朝,目が覚めるとあたりはうっすらと雪化粧.
やっぱり入試には雪がつきものだね.でもって高速道路を走ると,栗東インターを越えたくらいから雪が目立つようになり,
竜王インター付近では風で樹木に積もった雪が吹き飛ばされてダイヤモンドダストのようになっていた.
しかし気温が中途半端に高いため,道路はべちゃべちゃで車が泥だらけになってしまった.まったく・・・.
3月14日(水)
帰り道,蹴上の東山ドライブウェイの入り口にある温度計は8℃だったが,その上に表示される文字が,以前は「凍結注意」
だったのに今日は「カーブ注意」だった.温度によって表示する内容を変えるとは,なかなかやるな.
ちなみに西大津バイパスや山中越えの温度計は,温度表示だけで文字は表示されていなかった(このときの表示されていた温度は7℃).
3月15日(木)
昨日の温度計だが,西大津バイパスは2℃だったけど凍結注意表示はなかった.何℃以下になったらつくんだろう?
以前から自動車内で使用するLEDの電流制限方法について考えていたのだが,ふと可変シャントレギュレータ
(LM317L)
のアプリケーションノートを見てみると,定電流源として使用する方法が書いてあった.
これはLM317LのVOUT-ADJ端子間の電圧が1.25Vになるようにコントロールされることを利用して,
VOUTから62Ωの抵抗を介してVOUTおよび負荷に接続すると,
1.25V÷62Ω=20.1mAの定電流源として使用できるのである.たいていのLEDは順方向電流の定格が20mAであるからちょうどよい.
これによりバッテリー電圧が変動しても一定の電流(明るさ)をキープすることができるようになる.
部品は下の回路図のようにLM317Lと抵抗器1本ですむし,購入価格も¥100もしないだろう.
LM317Lは小信号用トランジスタと同じパッケージなので,サイズもコンパクトにできる.これはいいことを発見した.
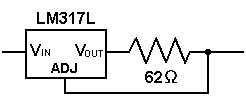
3月16日(金)
夜,東山ドライブウェイの横を通ると,「凍結注意 4℃」と表示されていた.昨日は5℃で「カーブ注意」だったので,
どうも4℃以下で「凍結注意」となるらしい.ただしこれは新型の数字がオレンジ色の表示器の場合で,
西大津バイパスなどにある旧型の数字が赤色のタイプの場合はまだ調査中である(でも,もう次の冬まで調査できないかも).
3月17日(土)
昼間,日野町に行ったついでに,グルメ情報誌に載っていた日野町のパン屋に寄ろうとしたのだが・・・ない.
地図に示されたあたりを見回しても,それらしい店は見当たらない.住所はどこかのマンションの1階のようだったが,
それらしいマンションすらない.どういうことだ?
3月18日(日)
今日は朝方,雨が降っていたが,昼からはよく晴れた.車の中は暑いくらい.昼間はずっとクーラーをかけていた.
本日の車内温度の最高は42.6℃を記録(直射日光の当たらない場所で).うがぁ.で,午後に山中越えを走っていると,
前を遅い車が走ってるなぁと思っていたら,琵琶湖霊園に入っていってしまった.そうか,もうお彼岸だったんだ.
今日はLM317を買いに日本橋まで行ったが,まず往き道,新御堂筋が異常な渋滞.千里から東三国までで1時間近くかかってしまう.
何だろうと思っていると,事故だった.東三国〜新大阪間で2カ所,同じような事故で車線が規制されていた.
その事故の手前で,ちょうど今しがた追突事故を起こしたらしい車が止まっていたが,それは渋滞の中だったので,
それ自体はあまり交通には影響していなかった.
実家から日本橋に向かったが,松屋町筋を下っていくと,右端の車線に大きなコンクリートミキサー車がいた.
それをよけて走っていくと,同じようなミキサー車が数台,連なっている.それも抜いていくと・・・
その前方にもさらにミキサー車ばかり10台くらい連なって走っている.これはどうもただごとではなさそうだ.
よくそのミキサー車を観察すると,側面に横断幕がかかっていた.どうもいわゆる示威行動(デモンストレーション)であったようだ.
右翼の街宣車のようにうるさくはないが,威圧感はこっちが勝っているかも.だって,ぶつかったら・・・
自動的にコンクリート詰めにされてしまう?!
でも,このミキサー車はミキサー部が回っていなかった.ちょっと安心(何を?).ミキサー車たちは千日前通りを西へ曲がっていったが,
その先にもミキサー車が延々と連なっていた.うぐぅ.
日本橋では,まずTWO-TOPに潜入.ジャンク品のマザーボード各種¥4800で売られていた.
P3V,P3Aに混じってP3B-FとCUBXがあった.家のCu-Cerelon用にCUBXを購入する.共立電子産業では,
LM317LZが¥100だった.62Ωの抵抗とあわせて1ダースほど買っておく.5000〜8000mCdの各色LEDを数個ずつ購入.
白の5000mCd(φ5)も,以前は¥600したけど,今は¥360だった.もうすぐφ10のタイプも販売されるとのこと.
ECUの電源強化用に,105℃グレードの電解コンデンサを探したのだが,16V470μFまでしか売っていなかった.
47000μFくらいがほしいのに・・・.85℃グレードでがまんするか.寿命は短くなるが,安いからまぁ,よしとしよう.
電解コンデンサの横に松下のゴールドキャパシタを発見.5.5V 0.47Fまであった.スーパーキャパシタはないのかな?
そういえばスーパーキャパシタは,昔,デジットで5.5V 1Fを買ったような記憶がある.自動車用だと3個直列にしないといけないので,
容量は1/3になってしまうから,それに見合った数を用意しないといけないだろう.
スーパーキャパシタにしてもゴールドキャパシタにしても,
いちおう宣伝文ではバッテリーバックアップのニッカドやリチウム電池の置き換えを主眼としていたような気がするので,
ECUまわりのような急速充放電に耐えられるのかどうか不安があったのだが,
本田技研の「インサイト」の試作車はスーパーキャパシタを使用していたので(市販車はニッケル水素電池),
問題ないような気がする.アーシングが終わったらバイパスコンデンサ強化に使ってみよう.
それと熱収縮チューブを探していたのだが,赤,黄,青,白,黒,透明はあるのだが,緑はない!うぐぐぐ.
仕方ないので透明を買ってしまったが,実際には黒を使うことになりそう.
3月19日(月)
阪急河原町駅に行くと,ホームにある列車の行き先案内板がLED式のものに変わっていた.
そういえば,2週間くらい前に桂駅の大阪方面ホームのものも同じものになっていた.
LED式の案内板は,JRでは以前から使用されていたが,これは赤・橙・緑しか出なかった.
阪急に採用されたものは青や白も表示できるタイプなので,ちょっと進化している.
『近江東海道』が読み終わってしまった.
次は『近江中山道』だ.
3月20日(火・祝)
ふと気象庁のページを見ていると,潮干狩りのしおり
が出ていた.しかし関東周辺しかないぞ.ダメやん.
滋賀県からだと,いちばん手頃なのは三重県かなぁ.直線距離は100kmもないんだけど,1号線で鈴鹿越えをするしか道がないので,
時間はかなりかかってしまう(3時間くらいか).でも第二名神ができたら1時間半くらいで行けそう.早くできてくれないかな.
暑さ寒さも・・・というが,さすがに彼岸の中日ともなると,昼間の気温は20℃近い.
もう雪が降ることはないだろう,ということで,スタッドレスタイヤからノーマルタイヤに戻すことにした.
昼間は両親が遊びにきていたので,夜になってからタイヤ交換をした.タイヤを1個ずつ風呂場で洗い,
3解から駐車場まで運んで,車を一輪ずつジャッキアップし,タイヤを交換.さて交換したのはよいが,
保管時には空気圧を半分くらいに下げているため,タイヤがどれもパンクしたみたいな状態になっている.
足踏み式ポンプは疲れるので,12Vのコンプレッサーで空気を入れたが,これが結構うるさいので,夜に使うのは気を遣う.
だいたい入ったな,と思ったところでやめて,空気圧を確認する.おっと,左前輪以外はどれもほぼ2.0気圧になっている.
左前輪だけ1.7気圧だった.すでに夜10時を回っているので,家の駐車場で空気を入れるのはやめて,
近くの琵琶湖ホテル跡地までゆっくりと走っていく.ここだと近くに民家はないので,コンプレッサーの騒音も気にならない.
ガガガガガガッ・・・・・ さて,測ってみると・・・2.0気圧.OK.ちなみに2.0気圧というのは車の指定空気圧だが,
ふだんは2.2気圧くらいにしてある.まぁ,とりあえず2.0気圧あれば問題なく走れるので,
そのうちガソリンスタンドに行ったときに2.2気圧まで上げることにしよう.というわけで,西大津バイパスへ試走に行く.
まず交差点を曲がるときに,スタッドレスタイヤであった腰砕け感がまったくなく,しっかり踏ん張っているのがわかる.
直線走行では乗り心地を確認したが,スタッドレスと比べて特に硬くなったという感じはしないので,よしとする.
このREGNO GR-5000もスリップサインが出かかっているので,近いうちにGR-7000に交換の予定である.
3月21日(水)
朝の新聞を見ていると,フィギュアスケート世界選手権
(TBSのサイト)の予選結果が出ていた.あ〜あ.関東では放送あるんだなぁ.
関西では女子シングルの決勝しかやらないんだろうなぁ.つまんない.
阪急桂駅で,例のLEDの表示板をじっと見ていたが,どうも白が表示されるのは列車種別の「普通 LOCAL」
の部分だけで,あとはオレンジ色しか表示されていないような気がする.これは手抜き(コストダウンともいう)だろうか?
3月22日(木)
今日はトヨタ部品共販でフューエルフィルターとパワステポンプのフローコントロールバルブを注文しておく.
フローコントロールバルブは,パワステポンプのハウジングによって数種類あるのを忘れていて,
途中で車に戻って確認しなおすという失態もあったが,なんとか注文を完了.
タイヤをノーマルに戻してから,初めての遠出.高速道路・一般道路とも走ってみたが,
スタッドレスの感覚に体が馴れてしまっているためか,どうも違和感がある.路面の凹凸のゴツゴツ感は,
やっぱりスタッドレスよりは強い.ハンドルが少し重く,また轍に流されやすいような感覚がある.
コーナーでの腰砕け感はないのだが,フロントの食いつきが今ひとつという印象を受ける..
で,帰りに草津のディオワールドでタイヤ交換をしてもらう.REGNO GR-7000 195/65R15で,一本あたり¥13000なり.
空気圧は2.2気圧を指定.ここでは窒素充填はやっていなかった.まぁ,それはそれとしてさっそく乗ってみると・・・・
こ,こ,これは,激やわらか.乗り心地からいうとスタッドレスタイヤ並みのやわらかさで,路面の凹凸はほとんど吸収してしまう.
かといってスタッドレスタイヤのような腰砕け感はなく,フロントの食いつきも悪くなさそうである.
まだ帰り道の15kmほどを走っただけで,高速や峠道を走ってはいないから,結論を出すほどではないが,第一印象としてはなかなか.
先代のGR-5000のときは,細かい凹凸の吸収についてはスタッドレスと比べると明らかに負けていたが,
今回のGR-7000だとほぼ互角という感じで,確実な進化を感じた.
実験が終わった後,渇いたのどに南アルプスの天然水のおいしいこと.っぱ〜っ.うめぇ.
3月23日(金)
LEDは電流を流せば流すほど効率がよくなるものだと思っていたが,最近の超高輝度LEDはそうではないらしい.
データシートのグラフを見てみると,電流と明るさが比例以上になっているのは20mAくらいまでで,それ以上は,
たとえば電流が2倍になっても明るさは1.6倍くらいにしかならない.その一方で端子電圧は上昇しているので,
消費電力は2.1倍くらいになるから,エネルギー効率でみると20%ほどダウンしてしまうのである.
結局,多くのLEDにおいて,順方向電流の絶対最大定格が50mAであるのに,推奨電流が20mAどまりなのかというと,
エネルギー効率が20mAくらいがいちばんいいから,ということのようである.具体的に言うと,
1個のLEDに40mA流すより,2個のLEDに20mAずつ流した方が合計として明るく,消費電力も少ないのである.
これでまたひとつ,謎が解けたような気がする.
昼前,ふと大学構内を見ると,掲示板の前に人だかりが.もしや合格発表というやつか.
そういえば秘書さんが,昨日の教授会で「合格者判定会議」があった,って言ってたなぁ.
いちおう,誰を合格させるか最終的な決定をするのがこの会議なのだが,まぁ実際のところは,
成績順に受験者の点数が並んだ表を回覧して,ここまで合格ということでいいですね,
というだけのもので,10分もかからず終わってしまうらしいんだけど.
夜,川端二条から京大まで久しぶりに歩いて戻った.大学生の頃は毎日,三条京阪から歩いて通ったんだけどなぁ.
最近は車に乗るようになって,歩くということがほとんどないような気がする.不健康だわ.
でも,毎日,鴨川の堤防を歩いてると,四季折々の風情を肌で感じることができたような気がする.
かといって,自動車通勤でも季節を感じないわけではない.たしかに都心に住んでコンクリートジャングルの中を年中,
通勤しているだけでは季節も感じようがないのかもしれないが,今のように毎日,比叡山を越えて通勤していると,
山の木々,空,琵琶湖の色などなど,それはそれで季節の移ろいを感じることができる.やっぱり住むなら少し田舎なくらいがいいよね.
3月24日(土)
今日はGR-7000で山中越えを走る.さすがにスタッドレスとはコーナーリング時の安定性が段違いだが,
段差の乗り越えもMZ-02よりやわらかいようだ.さすがにコーナーリング中にはTEMSがHARDになることもあって少し衝撃を感じるが,
直線路ではまさに滑るように走り,ロードノイズも一般道の速度では聞き取れないくらい.
あとは来週,高速道路を走った時にどうか,ということかな.
夕方,大学に来て某BBSを読んでいると,その少し前に激しい地震があったという書き込みがあった.
さっそく防災気象情報にアクセスしようと試みたが,,,重い〜っ.
きっとアクセスが殺到しているのか,なかなか表示が出ない.しょうがないので,BBSの返事を書いたりしていると,
やっと表示が出た.見ると,広島県付近の瀬戸内海が震源で,マグニチュードは6.4となかなか大きい.
広島付近では震度5強くらいまで出ているようだ.京都では「すごい揺れて怖かった」という人と「えっ,地震なんかあったの?」
という人がいた.ちなみに京都は震度2であった.私は車の中だったので,もちろん気付くはずもなかった.
3月25日(日)
夕方,鴨川沿いを走ると,道端のゆきやなぎが満開だった.そういえば来週はもう4月だから,
桜の開花宣言も出ちゃうだろうし,そろそろ桜も咲く準備をしといてくれないと困るしね.
3月26日(月)
朝,また大学の教務課付近に人だかりができていた.金曜日の合格発表で合格した人の手続きかなぁと思ったが,
医学部の後期なんて10人しか通らないのに,そんなに集まるほどのものなんだろうか,と思っていたら,
実は卒業式も同時に行われていたのであった.そりゃ,人も多いわな.
3月24日より阪急京都線のダイヤが変わり,桂駅に特急が停車するようになった.往きは急行だったが,
急行も高槻市までは各駅停車となっていた.帰りは特急が来たので,特急に乗って帰った.
そういえば阪急京都線の特急に乗るのは生まれて初めてだったかも.神戸線はよく乗ったんだけど,
実家から京都に行く時は京阪電車の方が圧倒的に便利だったからなぁ.
阪急の特急も,悪くはないんだけど,シートの座り心地に関しては,JR新快速と京阪・阪急の特急を比較すると,
京阪の特急がいちばん上のようだ(慣れの問題か?).
P.S.
昔,京阪神間では国鉄vs私鉄間の競争が激しかったことから,いたずらに到達時分だけを競うような時代もあった.
国鉄時代の新快速は,新大阪さえ通過(超特急でもすべて停車するのに)していたし,京阪や阪急も似たような状況だった.
しかし10年ほど前から新快速は新大阪と高槻に停車するようになり,京阪でも数年前から特急が中書島と丹波橋に停車している.
今回の阪急の停車駅変更も,この流れに沿ったものであろう.本来,鉄道会社にとっていちばんの上客は沿線住民であるわけだから,
たまにしか乗らないような大阪・京都間の直通客にアピールするよりも,
沿線住民の利用しやすいダイヤを組んで路線内での利用促進を図る方が,鉄道会社の収益につながる,という判断である.
おそらくこれは正しい考え方なのであろう.昔のように道路が悪く,航空機も発達していなかった時代には,
実用的な移動手段は鉄道しかなかったので,1時間に1本とかいうダイヤでも利用客があったのだが,
現代では長距離ならどこへでも飛行機で行けるし,自家用車も相当,普及している.
そういう状況で鉄道会社が生き残るためには,飛行機で行くほどではなく(数十km以内),
混雑した道路よりは速く快適に移動できる,ということを追求しなければならない.
専用軌道を走る鉄道は,通常,一般道路を走る自動車よりも速いが,列車待ちの時間が長くては結果的に遅くなってしまうこともある.
それを避けるためには列車をたくさん走らせ,運転間隔を短くする必要がある.ただ線路容量には限りがあるし,
列車本数を増やすとコストもかかるため,全体の本数を変えずに停車駅を増やすことで,結果的に待ち時間が短くなるようにしたわけである.
この場合,停車駅が増えることで長距離客にとってはかえって時間がかかるようになることもありうるが,
今日,桂駅で見た例では,河原町行きの普通電車が停車している横に河原町行き特急が入ってきた.
これは途中の駅において,今までだと単に通過待ちをしていたのを特急・急行と各駅停車が乗り継ぎできるようにして,
たとえば急行の停車駅が増えて遅くなるのならその代わりに特急が利用できる,という形で長距離客にも配慮した運行形態としているようだ.
阪急のLED式行き先表示器を,さらによく観察してみた.その結果,河原町駅と桂駅では,
表示器のレイアウトは同じなのだが,桂駅のものは列車種別のところだけがフルカラーで,あとは赤・緑しか出ない.
河原町駅のものは行き先と停車駅もフルカラーであった(3段目は赤・緑だけのようである).
駅のランクによって表示器もランク分けされているとは,うみゅみゅみゅ.
街中を歩いていると,ハクモクレンや早咲きの桜が咲いているのを見た.
大津市の皇子が丘でも早咲きの桜が満開だそうだ.う〜ん,春なんだなぁ.
3月27日(火)
タイヤを替えてから,初の高速道路.スピードを上げていくと・・・う〜ん,やっぱり,
ぬあわkm/hくらいになると振動が出てくる.それまでが静かすぎるので,ちょっと振動が激しく感じられる.
これまでタイヤを3種類,ホイールも変わったけれど,どれも同じ速度で振動が出てくる,ということは,
タイヤバランスじゃなくて,ベアリングやブレーキローターなど,別の原因かもしれない.やっぱり,ローター交換かな・・・.
近江大橋有料道路に入って信号で停車し,ふと後ろを見ると,あやしげな黒塗りセドリックがいた.
こちらはガソリンスタンドに入るために左車線を走っていると,右車線を前方へ走っていったのだが,
信号で並んだ時によく観察すると,バックミラーの左横にもう一つバックミラーがあり,
助手席側Aピラーの外側にサイドミラーが余分についていて,トランクにはアンテナ,天井のルームランプのあたりにも箱がついていた.
さっき前を70km/hくらいで走ってたのでちょっと心配だったのだが,助手席に乗っている黒い背広の兄ちゃんは,
なにやら書類を読んでいて,こちらのことなど気にかける様子はない.まぁ,いいか.
そのあとで入った,近江大橋沿いのよく行くガソリンスタンドでは,ハイオクがついに100円を切って99円/Lとなっていた.
レギュラーも89円/Lである.まぁ,安くなるのはいいことだ.
3月28日(水)
京都では,桜が咲き始めている.ということは,見頃は来週始めかな?で,滋賀県はそれより数日遅れかしら.
今朝の新聞では,海津大崎の桜祭りは4月7・8日(開花時期によっては14・15も)と出ていた.
早朝の誰もいない時間を見計らって行くのがいいかも(午後になると,大津方向の161号線がやたらと混む).
今日,このページのアクセスカウンタが「100」になった.100番をとったのは,うちの弟だったらしい.
そりゃ,たぶん一人で全アクセス数の半分くらいはとってるだろうから,100番だってとれるだろう,とか思ってしまった.
でもこれからアクセスが増えるかもしれないから,1000番ゲットは難しいんじゃないかな?
(え,アクセスカウンタいじれば簡単だって? それは反則だろう)
3月29日(木)
ベランダに植えたネギから,青々した葉っぱが伸びてきている.それはいいことなのだが,
植えた人によると,「これは白ネギだったはず・・・」らしい.伸びるとだんだん白くなるんだろうか?
夜,家に戻ってくると雨がぱらついてきた.しかし空を見上げると,雲はほとんどなく,星がとてもきれいに輝いている.
どこから降ってきた雨なんだ?しかも降り方が,雪に似ている.空気がとても冷たいので,
どうも上空では雪だったものが融けて雨として降ってきた,というように思える.
3月30日(金)
山中越えの料金所を少し京都側へ下ったところに,小さな梅林があるのだが,
そこの梅が咲き始めていた.しかし下界ではもう梅は終わって,桜が咲き始めているというのに.
山の上,それも谷間なので季節が遅いんでしょう.そういえば比叡山の桜祭りはいつも4月末のゴールデンウィーク中なのよね.
帰り道,蹴上のところの温度計が「2℃ 凍結注意」と出ていた.車の外はずっと雨が降っており,
「この気温だと北の方は雪かな」と思っていたら,西大津バイパスの藤尾奥町あたりから本当に雪が降ってきた.
ううぎゅ.
3月31日(土)
朝のニュースを見ると,あちこちで雪が降っているようだ.窓の外は,特に雪が積もっている気配はない.
というわけで普通に出かけようとすると,山がなんか白っぽい.山中越えを登っていくと,頂上付近は0℃で,
道端はうっすら雪化粧.路面には何も積もってないからいいんだけど,明日はもう4月なんだから,
ちゃんと暦相応の天気になってほしいものだ.
京都市西京区の国道9号線中山交差点の近くにある国道9号線の9kmポストの写真を撮った.
このポストは最新型で,四角柱の道路側に9号線9kmの表示が,歩道側には地域にちなんだ絵と,設置位置についての情報が書かれている.
そこには「烏丸五条から9km」と書かれていた.えっ,9号線は堀川五条からじゃないの?と思ったが,そこでハタと気付いた.
国道24号線や国道367号線は烏丸五条が起点である.実は9号線も烏丸五条が起点で,烏丸から堀川までの間は1号線と重複している,
ということではないのだろうか.あとで調べてみると,確かにそうであった.う〜ん,また一つ,賢くなってしまったなぁ.
久世橋から洛西ニュータウンに向かう府道201号中山稲荷線の物集女町内では4車線化工事をしているのだが,
3日前の水曜日に見たときは1軒だけまだ道路予定地内に建物が残っていた.ところが今日,そこを通ってみると,
はみ出ていた建物がなくなって更地になってしまっていた.まぁ,壊すのは丸一日あればできるだろうから,
そんなものなのかもしれないが,とにかくこれでこの付近も数ヶ月後には4車線になるようである.
ただ,阪急の踏切のところや,JRをくぐっている部分は2車線しかないが,ここはどうするんだろう?
( この月の初めへ )