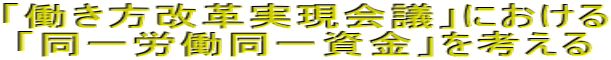
平成28年10月24日、政府は「第2回働き方改革実現会議」を開催した。
第1回では、「同一労働同一資金など非正規雇用の処遇改善」を1番目のテーマにあ
げ、第2回目では、在宅勤務などの柔軟な働き方の在り方、多様な採用機会などについ
て議論が行われた。
「働き方改革」は、安倍総理が打ち出した、ニッポン一億総活躍プランの最重要課題で
ある。
先日、この会議の構成員である、東京大学教授 水町勇一朗氏の講演に参加した。内
容はつぎのとおりである。
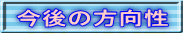
「同一労働同一資金」とは、職務の内容が同じであれば、同じ賃金を払うべきという
考え方である。
フランスやドイツなどのヨーロッパでは、「客観的な理由のない不利益扱い(待遇格
差)の禁止」という形で法律に規定されている。
日本では職務そのものではなく、職能給(職務とキャリア展開)で賃金を考えるため
「同一労働同一資金」を法律での導入するのは難しいという議論がある。
しかしヨーロッパでの実際の運用例などを参考にすれば、待遇格差の合理的な理由に
ついて、「ガイドライン(政府としての指針)」を示すことが有用と考えられ、内容の
検討がされている・・・とのこだ。
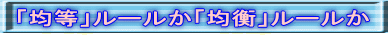
均等ルールは、例えば通勤手当や食堂利用など、職務の内容に関係のしない給付は、
正社員であってもパートタイムであっても同じ給付をすることが求められる。
均衡ルールは、基本給や職務手当、教育訓練等の職務内容に関連する給付は、異なる
ことが許容される。
待遇格差の「合理的理由」には、この2つのルールが含まれると考えられる。
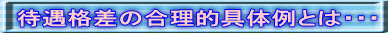
正規社員と非正規社員との間に、待遇格差があるとしても、その性質、目的に添って
次のように個別具体的に判断されることが考えられる。
①基本給…職務内容、労働の質、経験、資格、学歴、勤続年数、採用の緊急性などの
などの違い等
②退職金…勤続年数の違いのみ
③賞与 …一定期間の勤務や企業業績に応じて支給される性格があるならば、勤続期
間の違いのみ
参加者から質問が出た。
「退職金をパートタイムにも支払うということですね。いっそのこと、退職金をなく
してしまったら不利益変更になるでしょうか。」
不利益変更に違いないが、有期雇用無期転換ルールに照らしあわせ5年以上で全員に
支給といった制度変更など、今後は多様な対応が求められていくのだと実感した。
待遇格差合理的理由の「ガイドライン」は、12月策定を目指しているとのこと。法
改正は3年後の2019年を目指しているが、その後の運用による様々な事例のもと、
本格的な効果がでるのは10年後かもしれない。
  

10月1日より、従業員501人以上(※)の企業の社会保険加入条件が次のとおり
になりました。
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万以上)
③勤務期間1年以上
④学生は適応除外
※501人とは、10月1日前の適応対象者の数です。
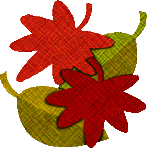
(社会保険労務士・後藤田慶子)
|