
育児・介護休業法と男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日から施行され
ます。
前回の改正は平成22年、中小企業は一部施行が猶予されたため、平成24年に育児・
介護休業規定を改定された会社も多いのではないでしょうか。
そのため「またか。」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法律が改正にな
ったため、会社は就業規則や育児・介護休業規定や社内書式の見直しを行う必要が出てき
ます。
育児・介護休業方のポイントは・・・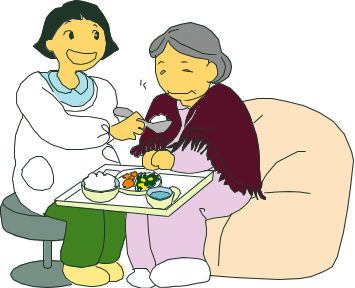
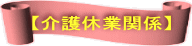
①休業の分割取得
要介護状態にある対象家族を介護するための介護休業について
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、分割し
て取得するこたが可能になります。
今までは、家族1人につき通算93日まで、原則1回に限り取得可能となっていました
②所定労働時間の短縮
介護休業とは別に、利用開始から3年の間であれば2回以上、所定労働時間の短縮制度
を利用できるようになります。
今までは、季語休業と通算して93日の範囲内でしか利用することはできませんでした
③残業の免除
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまでの期間について、残業の免除が受けら
れる制度が新設されます。
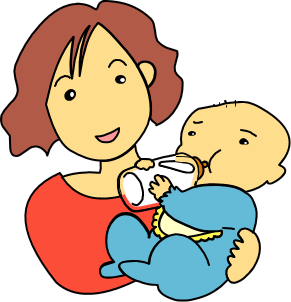
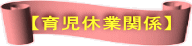
④対象となる子の範囲拡大
養子縁組里親に委託されてる子、特別養子縁組の監護期間中の子も新たに
追加されます。
⑤有期契約労働者の取得条件緩和
有期契約労働者で将来的に来よう契約があるかどうか分からない人でも取得可能となり
ます。
⑥マタハラ・パタハラなどの防止措置の設置
マタハラ(女性労働者に対する、妊娠・出産等を理由とした嫌がらせ)やパタハラ(男
性労働者に対する、育児休業の取得等を理由とした嫌がらせ)などを防止するために、企
業が措置を講じることが義務化されます。
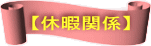
⑦子の看護休暇について
1日単位から半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得可能になります。
⑧介護休暇(※)について
1日単位から半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得可能になります。
(※)介護休暇とは、介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行
うための休暇をいいます。
改正法で、労働者にとって仕事と介護の両立をしやすくなる一方、企業は、労働時間短
縮など新たな対応、配慮など求められる点が多くなります。
例えば、介護休業の分割取得により、休業申請や残日数の管理をどうするのか等、現状
の就業規則では対応しきれない部分も出てきます。
対応として、育児・介護休業規定や労使協定の見直しが必要になることから、早めに整
備を進めておきたいものです。
 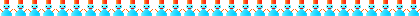 
(社会保険労務士・後藤田慶子)
|