
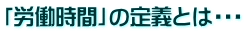
2月28日、「過重労働による健康障害の防止について」の研修を受けてきました。
講師は元労働基準監督官で社会保険労務士の角森洋子氏。
労働基準法で次のような定義があります。
・ 32条(労働時間)休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させ
てはならない。
・ 34条(休憩)労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には
1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
・ 35条(休日)毎週少なくとも1日の休日か、4週聞を通じて4日以上の休日を与えな
ければならない。
・・・・等
何時間までなら0K、何日なら0Kなど、基準がはっきりしていますね。
しかし、どのような時間が「労働時間」として扱われるのかの定めはありません。
行政解釈や指針、判列では示されていますが、実務的には、客観的に個別具体的に判断され
ます。
(行政解択・指針の例)
・ 研修時間 ・・ 出席しないと不利益がある、内容が業務との関連性が高い、受
けなければ業務に支障がでる等に当てはまれば労働時間。
・ 健康診断受診時間・・ 業務遂行と関連がないので労働時間ではない。特殊健康診断は
業務遂行にからむので労働時間。
・ 自己申告制残業 ・・ タイムカードと申告時間に著しい乖離が生じているときは実態
調査で補正をした時間が労働時間
就業規則で「研修は自由参加で労働時間でない」と定めていたとしても、実態で判断される
ということです。
角森氏の「同じ労働時間でも経営者側と労働者側では感じるストレスは違いますよね、経営
者だからムリができるんです」というお話しに納得!

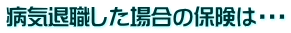
病気で治療に専念するため会社を退職すると、加入していた健康保険、厚生年金、雇用保険
の資格を喪失します。
退職後はどのような手続きを行い、どのような給付があるのでしょうか。
(年金)
国民年金第1号保険者となります。
保険料は1ヶ月16490円ですが、申請すれば失業による特例免除や前年所得による免除
があります。
(医療保険)
退職時の健康保険に継続して加入する「任意継続」、市区町村で手続きする「国民健康保険
」、家族が加入する健康保険の「被扶養者」 の3つの選択があります。
「任意継続」は会社が負担していた保険料も自身で払うことになりますので、現在の2倍と
なります。ただし、保険料には上限があります。「国民健康保険」は市区町村により過職によ
る減免があります。また「被扶養者」になる要件の収入には、傷病手当金や失業給付も含めま
す。
(健康保険傷病手当金)
1年以上被保険者であって、退職1時に傷病手当金を受けていれば、退職後も受けることが
できます。受給期間は、支給開始日から1年6ヶ月間です。
(雇用保険失業等給付)
失業給付は、一定の要件を満たして失業中に就職活動をしている人が対象ですので、病気で
働くことができなければ受けることはできません。通常、失業給付の受給期間は退職後1年間
ですので、それを過ぎると失業給付を受ける権利がなくなってしまいます。しかし、30日以
上病気で仕事ができない状況であれば、申請により最大4年に延長することができます。
延長には申請が必要ですが、平成29年4月の改正により、申請期日が延長後の受給期間最
終日までの間であれば可能となっています。

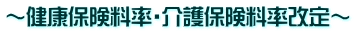
【健康保険料率】※平成30年3月分の保険料より
| 都道府県 |
現行 |
改訂後 |
| 京都府 |
9.99% |
10.02% |
| 大阪府 |
10.13% |
10.17% |
| 兵庫県 |
10.06% |
10.10% |
| 奈良県 |
10.00% |
10.03% |
【介護保険料率】 ※平成30年3月分の保険料より
(全国一律) 現行1.65% → 改定後1.57%
【労災保険料率】※平成30年4月1日より
全業種平均4.5/1,000(平均で0.2/1000引き下げ) となる予定です。
※雇用保険料率は平成29 年度料率据え置きの予定です
(社会保険労務士・後藤田慶子)
|