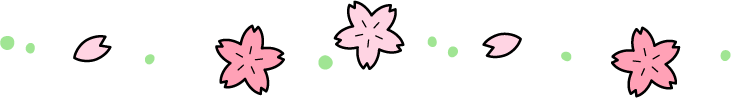 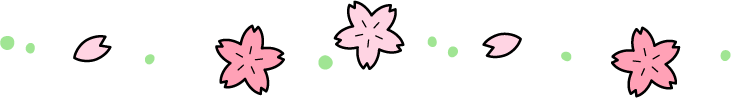
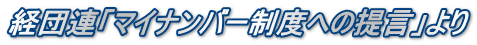
2016年1月にスタートしたマイナンバー制度。
行政手続きコストの削減と民間企業の高度化に通じた社会の効率化や、個人の世帯の実情に
応じた行政サービスを可能とするのが目的である。
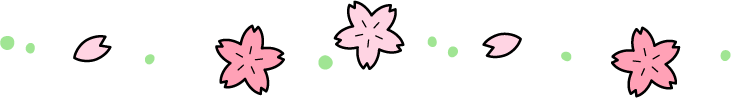 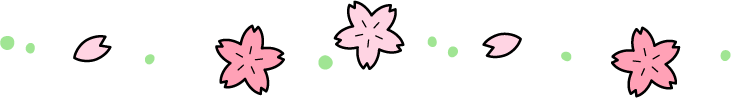
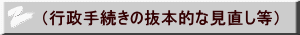
・ 現状では、株式会社の設立登記の申請に、本人確認の為、印鑑証明書や住民票の写し等
の提出が求められている。
・ 社会保険分野では氏名・住所変更に伴い、従業員や会社は日本年金機構、ハローワーク
健康保険の保険者に対して手続きを実施している。複数機関への重複した移動手続きは廃
止すべきである。
・ 年末調整時に従業員は、「給与所得者の扶養控除申告書等(異動)申告書」や「保険料
控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を会社に提出している。
年末調整を行った後に内容に誤りがある場合、税務署は、会社に源泉微収額の是正を求
めるが、納付すべき税額等の情報を併せて提示することは原則としてない。会社は税額算
出のための大きな負担が生じる。
個人の所得情報、個人番号等のデーター連携を進め、国税局における正確な把握を実現する
ことにより年末調整の内容に誤りがある場合には、納付すべき税額等の情報を会社に提示して
源泉微収の是正を求めることとすべきである。
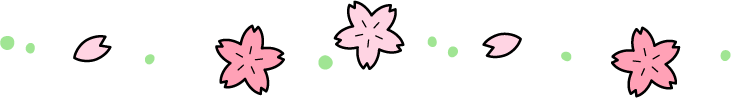 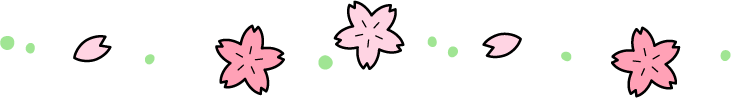
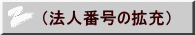
・ 税務署、監督署、ハローワークでの手続きは会社単位でなく、事業所単位で実施するも
のが多い。
事業所は法人番号の付番対象でないため、これまで同様名称や住所地から事業所を特定
する必要が生じている。
官民における事務の効率化を促すため、事業所単位で法人番号を付番すべきである。
・ 個人事業主は法人番号の付番対象ではないため、個人事業主が取引先の場合、会社は法
人番号を利用して管理することができない。
そこでプライバシー保護に充分な配慮を行ったうえで、個人事業主に対しても法人番号
と同様に、一般に公開される番号を付番することを検討すべきである。
官民における事務も効率化を促すため、事業所単位で法人番号を付番すべきである。
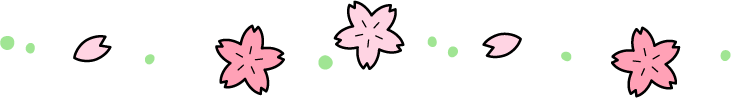 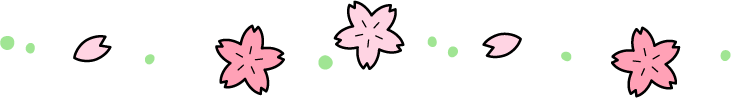
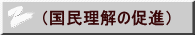
・ マイナンバー制度を新たな社会基盤とするためには、国民の幅広い理解が欠かせない。
これまでも官民を挙げて周知・広報活動続けてきたが、会社が顧客や従業員からの個人
番号の提出を拒絶される事案が発生するなど、さらなる理解の醸成が求められる状況であ
る。国民の理解を促進するため、税務調査等、制度の導入に伴い効率化が進んだ分野にお
ける効果を定量的に示すことが望ましい。
それに加え、行政の透明性向上のため、同一機関内部での特定個人情報の授受について
も閲覧できるようにすべきである。
(社会保険労務士・後藤田慶子)
|