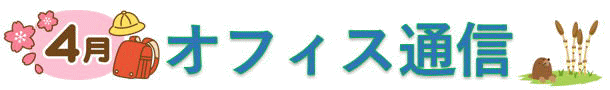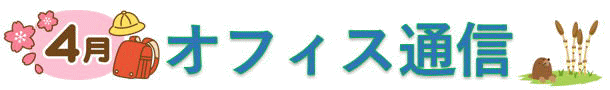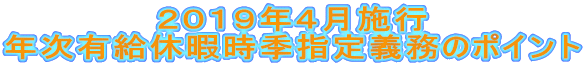
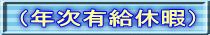
4月から働き方改革の一つである年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用
者の義務となりました。
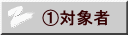
年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者です。管理監督者や有期雇用労働者も含
まれます。
自ら5日以上の年次有給休暇を取得する(した)人は対象になりません。
パートタイム労働者など、付与される日数が10日未満の人も対象とはなりません。
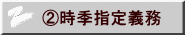
使用者は、労働者に年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に「時季を指定し
て」取得させることになります。
時季については、労働者から聴いた希望に沿うように努めることとされています。
4月1日以後に付与する日数から1年間に5日取得させる必要があります。5月が付与日
であれば5月から、9月であれば9月から1年間ということです。
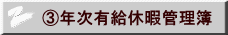
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません
必要な項目は、基準日(付与日)、時季(取得した月日)、日数です。期間の満了後、3
年間の保存義務があります。
この管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調整することもできます。
必要なときいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支え
ありません。
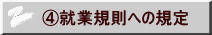
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項のため、年次有給休暇の時季指定を実
施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規
則に規定しなければなりません。年間5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、罰金
が科されることがありますので注意が必要です。
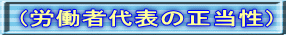
就業規則の作成・変更時には、労働者代表の意見が必要になります。また、36協定の締
結にあたっても、使用者には労働者の過半数を代表する者と協定を結ぶよう定められていま
す。
4月からこの労働者過半数代表者選出の要件に次の規則が追加されたことに注意です。
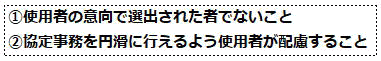
使用者が過半数代表者選びに介入することを阻止する狙いがあります。
過半数を代表する者は、労働者側で適正な方法で選出すべきであり、使用者の意向を反映
する方法は適法ではない、ということです。
最近の裁判では労働者の代表を選ぶ手法が不当だとして、協定が無効とする判断が相次い
でいます。
労使協定が否定されれば過去の残業代が発生する可能性もあります。代表者の選び方が潜
在的な経営リスクになりかねません。労働者の正当性をどう確保するかは、大きな経営課題
となります。
(社会保険労務士・後藤田慶子)
|