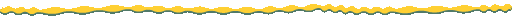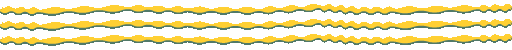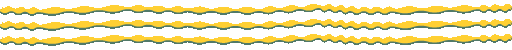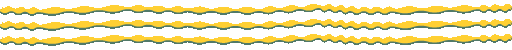
2002年1月
( この月の末尾へ )
1月1日(火・祝日)
朝,まず大学へ寄っていったのだが,いつものように山中越えを登っていくと,
比叡山ドライブウェイから下りてくる車が料金所のあたりで数珠繋ぎになっている.
いつもはこの時間はまだ営業開始前なので,上から車が下りてくるところなんて滅多に見ないのだが,
今日だけは特別だな.
そのあと,大阪の実家に行って,父方の親戚の家に挨拶回りをする.1月1日の朝は道路は空いていると思われたので,
久しぶりに大阪まで国道1号線で走っていくことにした.実際には東大阪の親戚のところに向かったので,
途中から国道170号線(大阪外環状線)だったが,どちらも思った通り流れはスムースで,予想より早く着くことができた.
で,調子に乗って帰りも国道1号線で帰ることにした.ただし,大日までは中央大通り→中央環状線を経由した.
中振あたりまでは,中央環状線から寝屋川バイパスに入るところが混んでいた程度で順調だったが,
枚方バイパスはかなり車が多い.反対車線を見ると,こちらは天の川先頭のいつもの渋滞のようだ.
京都府に入るとさらに混雑してきて,木津川のあたりから本格的な渋滞になってしまった.
カーナビのVICS表示を見ていると,渋滞の先頭は久御山森付近,京滋バイパスの手前・・・
ということは,休日恒例のジャスコシティ久御山が原因の渋滞ということか.そこで左に折れ,
久御山中央公園の横を通って久御山森交差点に出てみると,右折レーンから右側車線が渋滞しているだけで,
左側車線は普通に流れている.な〜んだ.
1月3日(木)
今日は大阪南港の母方の親戚の家に行く.ふだんは阪神高速で港大橋を越えるのだが,
今日は正月なので中央大通りをまっすぐ走っていくことにした.道はわりあい空いていて,40分ほどで到着.
帰りも咲州トンネルを通って中央大通り経由で帰ってきた.
夕方から,X80系のオーナーの方と会うことになった.その人は姫路なので,間をとって明石海峡大橋の下,
舞子タワーのあたりで待ち合わせという話になった.その前に,弟を新大阪駅まで送っていったのだが・・・.
新御堂筋は特に渋滞なく,新大阪駅に入る道を曲がっていくと,いきなり大渋滞.駅まであと300mくらいなのだが,
そこからがまったく進まない.たしかに今日が帰省からのUターンのピークなのだが,それでもこれまでとは・・・.
しかたなく流れに沿ってちょびちょびと進む.そうこうするうちに新大阪駅の前をなんとか抜け出して,
名神豊中インターを目指す.渋滞の可能性のない中国道→山陽道→西神自動車道経由にしようかとも思ったが,
今日は東行きは混んでいても西行きはそれほどでもないだろう,という読みで,名神→阪神高速神戸線→第二神明のコースを選んだ.
名神高速は問題なし.阪神高速も乗ってしばらくは大丈夫だったのだが,その先,摩耶付近と,第二神明道路から延々と渋滞の表示.
カーナビが一般道に降りるよう指示するので,真野で降りて2号線を走っていった.しばらくはあまり渋滞はなかった.
しかし浜手バイパスを降りるところから,かなりひどい渋滞.その先も少しは走るのだが,信号待ちばかりである.
そうしているうちに,たまたま左折専用レーンに入ってしまったのを機会に,海側の通りに回ってみた.
後で地図を見ると,これは和田岬を通ってくる道で,こちらの方はかなり空いていた.最初からこちらを通ればよかったかもしれない.
少し先でまた国道2号線に合流するが,そこから先はまずまず流れている.しかし,須磨の先で4車線から2車線に減るため,
そこからまた延々と渋滞している.カーナビのVICSの表示を見ていると,だいたい垂水の駅前から連なっているようになっていた.
そこで,少し手前の塩屋のあたりから山側を抜けて垂水駅付近に出てくることを考えた.
1月4日(金)
今日は,少し寒さがマシのようだ.家の近くの道路に,ところどころ白くなっているところがある.
別に凍るような温度じゃないので,どうも凍っていた時にまいた塩が固まっているだけのようだ.
真空計(Defi BOOST V.S.D.)であるが,ワーニングの機能があるので設定しているのだけど,
機能的には注意(黄LED点灯)と警告(赤LED点灯)の二段階に設定できるはずなのに,
実際には注意の段階で両方ともLEDが点灯してしまうようだった.具体的には注意が-100mmHg,
警告は-20mmHgに設定しているので,-100mmHgで黄LED点灯,-20mmHgで赤LEDも点灯となるはずなのに,
実際には-100mmHgで黄と赤の両方のLEDが点灯してしまう.そこで,両者の設定を逆に,
つまり注意を-20mmHg,警告を-100mmHgにしてみたところ,-100mmHgで赤LEDのみ点灯,
-20mmHgで黄と赤の両方が点灯という具合になった.これはこういうものなんだろうか.ううむ
よく考えると,要するに黄色と赤のLEDを入れ替えたら,ワーニング設定も含めて完全に整合がとれるのだ.
ワーニングのLEDがちょっと暗いということもあるので,明るいLEDに交換ついでに色を入れ替えてしまう手もあるな.
夜,家に帰ってきたとき,駐車場の前の壁に映る自分の車のヘッドライトの色が左右で違っているのに気づいた.
車を降りて観察すると,左側のライトが時々わずかに暗くなる.どこかの接触不良だろうか,
それとも CATZ ZETA のユニットの問題なのか.ヘッドランプ回りのグレードアップ(リレーユニット導入)を考えよう.
1月5日(土)
そろそろ雪が降るようになってきたのと,正月の旅行や実家への往復が一段落したことから,
スタッドレスタイヤに交換することにした.とりあえず作業は終わったが,空気圧ゲージが見当たらなかったため,
空気は適当にしか入れていないので,まだ空気圧はバラバラと思われる.調整した方がいいのだが,近々,
スタッドレスタイヤを買い替える予定なので,そのままでもいいかもしれない.
タイヤ交換後の走行では,やはり夏タイヤよりは少し柔らかい感じ.夏タイヤのREGNO GR-7000も,
交換直後にはスタッドレスとあまり差がないような感じだったのだが,約25,000kmほど走って5分山くらいになっているので,
最初に比べると少し硬くなっているのかもしれない.あと,とりあえずハンドルが軽い.まぁ,これはいつものことだが.
また空気圧をきちんとしていないのだが,とりあえずハンドルをとられるとか,そういう感じはない.
家の『南アルプスの天然水』がなくなっているので,京都市内で1ケース買ってきたが,
そのころ(午後5時過ぎくらい)から京都市内でも雪が降り出してきた.山中越え経由で大津に戻る時には,
山中町より上では路肩は真っ白で,一部,路面もシャーベットになりつつあった.真っ暗な空から降りしきる雪が,
街灯の光を反射し,真っ白になった景色となかなかマッチしてきれいである.2年ほど前に冬の飛騨高山に行った時も,
こんな感じだったなぁ(といっても,このときは路面温度-6℃で路面も完全に真っ白,初めての雪道で生きた心地がしなかったが).
まだ路面は凍ってないので安心して見られる.さて,家に帰って夕食を食べてから,午後7時頃に再び山中越えを京都方向に走っていくと,
このときには雪はやんでいたのだが,展望台より上では轍以外は少し雪が残っている状態.
さて最高点の比叡山ドライブウェイ入り口を過ぎると・・・いきなり路面が凍りついている.路面温度は-1℃の表示.
たしかに,このドライブウェイ入り口手前の京都側の斜面がいちばん凍りやすいんだよな.
で,なにやら対向車線で車が何台も止まっているのが見えた.前の車に続いてゆっくりと走っていくと,
どうやら凍結で坂を登れなくなった車が何台も立ち往生しているらしい.JAFの車も来ていたが,
とりあえずみんなで凍結防止剤をタイヤの周りにまいて対処しているようだった.この寒いのにご苦労なことです.
で,こちら車線も,カーブのところで外側の溝にランエボがはまっていた.四駆だから曲がれなかったのかな.
それにくらべると,この車は,いくら4年経ってプラットフォームが出かけとはいえ,腐ってもスタッドレス,
まったく安定して走れた.まぁ,4年経ったと言っても,使うのは毎年冬の3ヶ月だけで夏の間は押入の中に置いてあるため,
紫外線などで劣化することもなく,今でもトレッド面のゴムの状態は見た目,新品時とそんなに変わりないくらいだから.
久しぶりにスタッドレスタイヤのありがたさを実感させられた.
1月6日(日)
朝,起きると,家の周囲は雪が積もっている.ここだと道路には積もっていないようだ.
昨夜のこともあるので,今朝は山科経由で京都へ.さすがに日曜の朝だと,夜中と同じ程度にすいすい走れる.
京都市内は雪が積もっている感じはない.しかし北山くらいまでいくと道ばたに雪があり,
岩倉だと結構,多い.道路が凍っているのは大原より北の方のようだ.
夕方,山科のお好み焼き屋さんに食べに行ったが,まだ6時くらいだというのに家族連れですごい混雑.
30分以上待っただろうか.たしかに夜10時くらいに行ってもちょっとは待たないといけないくらいの店なので,
しょうがないのかな.
1月7日(月)
今日は少し寒さがマシのようで,夕方も降ってきたのは雨だった.明日はまた寒いらしい.
明日は火曜日なので信楽を通る予定なのだが,道路は大丈夫なのだろうか.
自分の車のデジタルメータについて,レオスタットでのテールキャンセル機能の実現方法を,
修理書と新型車解説書を見比べながら検討してみた.その結果,どうやらレオスタットの T 端子にテールランプがきていて,
それをレオスタット内部のスイッチを通して出力しているのが Tc 端子ということのようだ.
すなわち,テールランプ OFF → Tc 端子 OFF,テールランプ ON でレオスタットのテールキャンセル OFF → Tc 端子 ON,
テールランプ ON でレオスタットのテールキャンセル ON(右に回しきった状態)→ Tc 端子 OFF,
というわけで,現在,BOOST V.S.D.の減光信号としてテールランプの配線に接続しているのを,
レオスタットの Tc 端子の配線に変更するだけで,BOOST V.S.D.の減光をレオスタットのテールランプキャンセル連動にできるようだ.
これなら30分もかからないので,近いうちに試してみよう.
1月8日(火)
本日,このページも2000ヒットを達成.2000ヒット目は,
「あやしいひと協同組合」の ゆう さんだった.
それにしても,1000になったのが8月22日頃なので,最初の半年で500ちょっと,biglobeに移行して次の1ヶ月で500,
でそこから4ヶ月ほどで1000ということなのね.やっぱり8月のアクセス数が異常だ.
昼休み,ちょっと街中をはずれた国道沿いのパーキングエリアで,エンジンのインテークまわりのクリーニングをやってみた.
泡状のクリーニング剤をエンジンの吸気側から吹き込むのだが,異臭がするのと少しエンジンをふかさないといけないので,
あまり住宅密集地ではやってはいけない.滋賀県の場合,田舎なので車で5分も走ればそういう場所が見つかるのでありがたい.
で,作業であるが,スロットルバルブ手前のエアホースをはずし,そこからクリーニング剤を吹き込む.
このときエンジン回転が落ちることがあるので,手でスロットルバルブを少し開いてエンジン回転を高めに保つ.
でも寒いせいか,いまいち噴き出しが弱く,どうも効いてるのかどうかよくわからない.
そこで第二段階.エンジンを止め,サージタンクについているエアホースの一つをはずして,
そこからクリーニング剤をサージタンク内に多めに吹き込む.そしてヒューズボックスを開けてEFIのヒューズをはずす.
これでイグニッションキーを回してもエンジンはかからない.その状態で10秒間くらいクランキングし,
クリーニング剤を燃焼室内にまわして数分間,待つ.ただ待っているのもあれなので,その間,弁当を食べながら待っていた.
で,食べ終わったらEFIヒューズを戻し,エンジン始動.アクセルを少しあおってエンジン回転を高めにしておく.
これでマフラーから白煙が出なくなったら終了なのだが・・・・白煙自体があまりよくわからない.
作業終了後も,エンジンの回転具合はあまり変わらないようだ.もう少し暖かい時にやり直してみよう.
スタッドレスタイヤが,プラットフォームが出るまであと1mm弱くらいで,あまりシーズン終わりになると,
在庫がなくなる恐れがあったので,今日,タイヤ交換に行った.いちおう銘柄は,現在MZ02を使っているので,
後継のMZ03にすることを考えた.最初に行った草津のディオワールドでは,やはりこの前の雪でタイヤ交換を思い立った人が多かったのか,
待ち時間が90分以上となっており,さらに私の車のサイズがなかったため,ここはあきらめて,他の店を探すことにした.
次に近江大橋のロードスターに行ったところ,モノはありそうだったが,ここも少し混んでるようだったので,
膳所のタイヤ館に行ったら閉まっていた.しかたなく大津のロードスターに行くと,
ここには在庫があって値段も少し安かった(Bridgestone MZ03 195/65R15 で1本¥15200)ので,
ここでしてもらうことにした.ついでに窒素ガス充填もやってもらったのだが,
実際に作業が終わって走り出してみると,乗り心地については特に変わりないようだったが,
MZ02では顕著だったハンドルの軽さやコーナーリング時の腰砕け感がなくなっているように感じた.
まだちょっとしか走ってないし,肝心の凍結路の走行がまだなので,最終的な評価はできないけれど,
第一印象としては非常によいと思われた.
タイヤ探しのついでに,そろそろ Kei のオイル交換をしないといけなかったのを思い出し,
オイルやオイルフィルター等を買いそろえた.オイルはスズキ純正ECSTAR turbo 10W-30を使っている.
1月9日(水)
山中越えを走ってみたところ,今日はまだゆっくり目に走ったのだが,タイヤの接地感はよいようである.
MZ02に替えたときに感じた,走行時の「コォーーー」というパターンノイズ?が聞こえなくなったように思う.
というわけで,現時点での評価としては,MZ02にあった欠点がほぼ解消されているようで,
おそらく氷上性能も向上こそすれ落ちていることはないだろうから,まずまず合格といえるだろう.
今年の冬は金沢くらいまで行ってみるか.
1月12日(土)
今日は,今年初の八幡行き.やっぱり正月だったせいか,あまり入れ替わってはいないようだった.
というわけで,今日のところはあまり収穫なし.とある車の中に落ちていた社外品ハイマウントストップランプ(室内用)
をもらっておく.これをどうするかだが,LEDを最新の超高輝度タイプに交換して,純正ハイマウントと二段重ねにしようかとたくらんでいる.
ハイマウント,夜は結構まぶしいくらいなのだが,昼間は見えにくいように思うので,昼間だけ二段で点灯させるようにするわけである.
さて,どうなることやら.
駐車場のプランターに植えてあるタマネギが,プランターによってどうも育ちが違う.
カブトムシ?の幼虫が入っているプランターと,ミミズを入れたプランターは育ちがいいが,
何も入れてないところはどうもいまひとつ.この前,少し肥料を足したらちょっと育ってきたが,
それでもまだ違いがあるし.やっぱりカブトムシは偉大だ.
いつものように家の近くの道を走っていると,西大津バイパスへ登っていく道の途中に置いてある凍結防止剤が,
前の黄色い袋から青い袋に変わっていて,横に「赤穂ロード」と書いてあった.これは「赤穂の塩」という意味だろうか?
京都市内に入ると,百万遍の交差点などがたくさんの小旗で飾られていた.
よく見ると,県対抗女子駅伝が行われるらしい.そういう季節なんだ.
どうも,走っていてカーナビがよく道をはずれるようになったような気がしたので,
原因を考えてみたら,今週,タイヤを交換していたことを思い出した.カーナビの説明書に,
タイヤを交換したときはセンサーリセットして,新しいタイヤでセンサーの学習をやり直すように書いてあった記憶がある.
このカーナビは,冬季のみスタッドレスタイヤに交換するような使用法を考慮してか,
センサーの学習メモリーが2つ用意されていて切り替えて使用することができる.たとえば夏タイヤのときはメモリー1,
冬タイヤの時はメモリー2を使用するようにしておくと,春になって冬タイヤから夏タイヤに戻したときにも,
センサーをメモリー1に戻せば,直ちに以前使用していたときの学習状態を引き継いで使用できるわけだ.
試しにセンサー学習状況というのを見てみると,今は夏タイヤで学習した状況で冬タイヤを使用していたためか,
本日の学習状況は「もうすこしがんばりましょう」になってしまっていた.そこでメモリーを切り替えて,
改めてセンサーリセットを実行してみた.しばらく走ってから本日の学習状況を見てみると,
「たいへんよくできました」になっていた.ふむむむ
ブースト計についての質問を受けたので,それに対する回答を考えていたら,
ふと自分の車のアイドリング時のバキューム圧について,エアコンをつけたままだったのを思い出した.
そこでエアコンやカーナビ,ステレオなどの負荷を可能な限りOFFにしてアイドリング時のバキューム圧を見てみたら・・・
やっぱり-450mmHgくらいしかない.まぁ,1番のシリンダが死んでるみたいなので,これはしょうがないかな.
1月13日(日)
いわゆるヘッドランプ用のリレーハーネスというものを自作しようかと思い,いちおう回路図ができたので,
部品の買い出しに日本橋まで出かけた.最初にシリコンハウス共立に立ち寄る.
まずリレーであるが,小信号用(1A程度)では1回路と2回路のものがあったが,
見ると2回路のものはコイル電流が1回路にくらべて3倍くらい多い.部品数が増えても1回路のものを2個使った方が,
消費電流は少なくなるようだ.というわけで1回路のものを5個くらい買っておく.単価は¥220くらい.
次にパワーリレーであるが,小型のものは10Aくらいまでで,それ以上だとかなり大きくなってしまうし,値段も高い.
10Aだとコーナーリングランプ程度なら問題ないが,ヘッドランプに用いるには少し容量不足のような気がする.
カー用品店で自動車用として売られている20〜30Aのものの方が,サイズも小さいし値段も安いような感じである.
というわけで,今回はコーナーリングランプ用として予備も含めて3個ほど買っておいた.こちらの方も1回路と2回路があり,
内部の構成はほとんど同じで,おそらく消費電流も同じと思われたが,コーナーリングランプは左右別々の制御なので1回路でよい.
これは1個¥380だった.他に逆流防止用のダイオードが必要だが,これは制御用信号用なので1Aもあれば十分.
定格1Aの1N4001は10本¥90.あとスイッチが必要であるが,LED照明入りスイッチが6.3Vしかなかったので
(12V用は電球だった),ニノミヤ無線
のエレホビー店5階の電子部品コーナーに行って探してみたところ,12V用のLED照明入りプッシュスイッチがあった.
オルタネート/モーメンタリーの種別はもちろん,1回路と2回路のものもあった.サイズ的にも,
カー用品店で売っているスイッチ取り付けステーの穴(9mm径)にあうようだ(もっと大きいものや小さいものもある).
その中から今回はロックのかかるオルタネートタイプで1回路のものを,赤と緑で1個ずつ購入.1個¥530である.
だいたいこんなところ.残りのリレーは明日にでも近くのカー用品店で買うことにしよう.
帰りも名神高速で帰る.スタッドレスタイヤのときは時速90kmしか出さないようにしているので,
それで左端車線をのんびり走っていると,道がわりあい空いているため,前の車にはぜんぜん追いつかない.
というわけで久しぶりにオートドライブなど使ってみた.こういう時は速度を気にしなくていいので楽だなぁ.
上り線の天王山トンネルを抜けたところの合流を過ぎたあたりで,反対車線(大阪方面)に赤色回転灯をつけた車が数台,
止まっているのが見えた.横を通過する時に見ると,バスなど数台の車が止まっている(斜めに止まっているものもあった)
のも見えた.ただ,この区間は上り線側が少し高い位置を走っているため,防音壁に遮られて状況がつかめない.
路側ラジオを聞こうかと思ったが,ラジオは新幹線高架下あたりからしか入らないので,
ラジオにしたままで走行.やっと入ったと思ったら,「キーン」というすごい音がして,
ほとんど音が聞き取れない.この音だが,どうも車のエンジン回転に関係しているような周波数変動がある.
自分の車かと思ったが,今までこんな音が出たことはないし,雑音防止用コンデンサが壊れた可能性も考えた.
でも,どうも音の変動が自分の車の回転数とは違うようだし,しばらく走っていると,急にその音が小さくなった.
どうやら近くを走っている別の車の影響だったようなのだが,実際にはどうなのだろうか.
最近はアーシングが流行りだが,これも線の引き回し方によってはラジオに雑音が入るらしいので,
そういう車が走っていたのかもしれない.それはそうとして,上り線の山崎バス停の先に「速度自動取締路線」
の看板が新しくできていた.ただ反対車線の事故に気を取られていたので,具体的なオービスの設置状況はわからなかった.
下り線と同じ場所にできるのかな?
1月14日(月・祝日)
冬は毎朝,車に夜露や霜がおりるので,どうしても車が汚れてしまうのだが,
朝,ガソリンを入れに行ったときに天気がとてもよかったので,この機会に洗っておくことにした.
洗う前にTVとGPSのアンテナを外しておかないといけない.アンテナベースははがせないのでそのままだったが,
洗ってから観察してみると特に問題はなかった.
今日は Kei のオイル交換その他の作業を行った.まずはフロアジャッキを使って車をジャッキスタンドに載せる.
軽自動車って,軽いので上げるのが楽だぁ.持ち上げたら車の下に潜ってエンジンルーム下部の点検.
この車はエンジンアンダーカバーというものはないのだが,非舗装路は走っていないためか,
非常にきれいな状態.電動パワステのため,ステアリングギヤボックス周辺の構造が非常にすっきりしている
(パワステの機構部は室内側にある).しばし,車の下にもぐったまま,ぼぉ〜っとエンジン周囲に見入ってしまった.
あっと,オイルを交換するんだった.で,廃油受けを下においてドレーンボルトを緩めるわけだが,
そのままではレンチを入れる隙間がないから,ハンドルを切って隙間を作る.ジャッキアップしているのでハンドルは軽く回る.
17mmのロングメガネを使用したためドレーンボルトは簡単に緩んだ.あとはプラスチック手袋をしてボルトを手で緩め,
最後にエイヤッ,と引き抜くと,勢いよくオイルが出てくる.ずいぶん黒いな・・・でも,この黒さは,
なんかモリブデンの添加剤の色っぽい.オイル約3Lに1本入れたので,ちょっと濃すぎたかな?
次は半分くらいにしておこう.だいたい流れ出たら,次はオイルフィルターをはずす.
カップレンチを使って2回転ほど緩め,後は手で回していく.緩んでくると,接続面からオイルが漏れ出てくるが,
下向きのオイルフィルターのため,オイルフィルターがオイルまみれになって,ちょっとばっちい感じがする.
どうせ使用後は捨てるものなので気にする必要はないのかもしれないが,ちょっと,ちょっとだなぁ.整備性はとてもよいんだけど.
ともかくオイルフィルターを外して,しばらく待つ.だいたい滴が落ちてこなくなったら,取り付け部のオイルを拭いて,
新しいオイルフィルターを,Oリングにオイルを少し塗ってから取り付ける.オイルフィルターの指定通り,
手で当たるところまで回して,あとレンチで3/4回転締め込む.次にドレーンボルトを締めるわけだが,
ガスケットだけ新品にしてボルトは再使用する.締め付け後,周囲のオイルを拭き取って,
オイルが漏れてこないか確認.で,いよいよ上からオイルを入れる.たしか取扱説明書によると,
オイルフィルター交換時のオイル必要量が2.9Lだったような記憶があるが,ほぼオイル缶(3L)の全量近く入った.
またモリブデンの添加剤も,今回は容器の半量ほど入れておく.この時点でレベルゲージを見ると,ほぼFULLの位置.
エンジンを回してオイルを循環させ,1分ほどで止めてレベルゲージを確認すると,だいたい8割くらいの位置になっている.
ちょうどいいくらいだ.もう一回,下から観察して,オイル漏れのないことを確認したら,オイル交換作業は終了である.
さて,オイル交換は終わったのだが,せっかく車を持ち上げていることだし,
ここで他の作業もいっしょにしておきたい.具体的には,エンジンブロックへのアースの追加と,
フロントバンパーへのマーカーランプ取り付け作業である.まずアースであるが,
理想的にはオルタネータとスタータにつけるのがベストだと思うが,ちょっと適当なところが見あたらない.
力を受けている部分は,あまり下手にはずすと不具合が起こりそうだったので,できれば力のかからない部分がよい.
そういう観点で見てみると,ちょうどオルタネータとスタータの中間付近のエンジンブロックに,
おそらくECU関連と思われる純正アースポイントが見つかった.というわけで,バッテリーのマイナス端子から,
ここまで14sqの線を引っ張ってくる.この電線は耐熱性の非常に高いLKGB線なので,保護管は使用していない.
また電線は,極力,純正のワイヤハーネスに沿って敷設し,ワイヤハーネスに要所要所でくくりつけている.
こうすることでプラス側とマイナス側の電流が平行に流れるため誘導が減り,高周波インピーダンスを下げる意味もあるし,
メンテナンス性に影響を与えにくいということもある.
シガーライターソケットにささっている,方位磁石入りライトの,
本体とフレキシブルアームの接続部付近が割れていて,点灯しなくなっていたので,修理することにした.
以前にも同様の故障があって修理しているので,それと同じと思われた.本体のビスを外して開けてみると,
確かに前回,折れていて接着した,ビスをねじ込む支柱が同じように折れていた.ここは同じように接着剤を使ってくっつける.
また今回は,スイッチのリード線がハンダ付けされている部分が外れていたので,そこもハンダ付けしておいてやる.
これで修理完了.接着剤が固まるまで,24時間以上は車に乗せずに部屋の中に置いておくことにした.
1月15日(火)
今日は雨.でも路面は濡れてるのに,雨はほとんど降っていない.こういうのは最悪.
前車の跳ね上げる水しぶきで,車がどろどろ.せっかく昨日,洗ったとこなのに.
特に信楽に向かう道は,第二名神の工事のため路面の土が多いので,帰ってきて見たら,昨日の洗う前より汚くなってる.
うがぁ〜
今年になってから初めて部品共販に行ってみる.今回の目的は,インジェクター周辺の交換用部品の調達.
とりあえず不調が確実な1番シリンダは,インジェクターを交換してみようと思うので,その分の1本と,
他の5本も外して清掃・チェックはしておきたいので,再組み付け用のOリング類,
そしてフューエルデリバリーパイプとフューエルパイプ接続用のガスケット類も注文しておいた.
なんか,あと注文しないといけなかったものが・・・・思い出せない.
あとで考えると,パワステのエアコントロールバルブ用のホースを買うのを忘れていた.まぁ,急がないから来月にしよう.
1月16日(水)
今日も一日中,雨だったが,朝,山中越えを通っていくとき,峠付近でも気温が12℃あった.
明日からは寒くなるらしい.
夜9時過ぎに西大津バイパスを走っていると,前の方を散水車のような車が走っていった.
で,その後ろを走っていくと,その車は長等トンネルを出たところで非常駐車帯に停まってしまった.
その付近には,なにやら工事の車とおぼしき車が数台,停まっていた.なるほど,
10時になったら片側交互通行にして何か工事をするのね.
1月17日(木)
先日,注文したインジェクター,フューエルプレッシャーレギュレータ,パルセーションダンパーその他を受け取り,
ついでに前に忘れていたパワステ用のエアホースや,バキュームセンサー用のガスフィルター,各種ボルト類を注文した.
今月は,こんなものかな.
前を走っている車のマフラーから,水が,じゃばっ,じゃばっ,とこぼれている.
まるで水没した車のようにも見えるが,別に水没したわけでも雨水がたまったわけでもなく,
この寒い時期でマフラーが冷えたままなので,ガソリンの燃焼時に生じた水蒸気がマフラーで冷やされて凝結し,
マフラー内にたまっていただけなのだが.私のように3日に1回くらいは1時間以上,走行するような場合は,
マフラーが十分に加熱されるのでマフラー内の水分も飛んでしまうのだが,毎回15分程度しか走らない場合は,
マフラーが暖まらず,水が溜まったままになってしまうわけである.これはマフラーの錆による穴あきの元なので,
あまりよくないのであるが.
信楽から水口にかけての国道307号沿線でも,第二名神の工事が始まったようだ.
黄瀬付近のインターチェンジ?と取り付け道路の工事は前からやっているが,こちらもやっと本格的に開始のようだな.
でも,この付近,秋に走ると紅葉した沿道の木立がなかなか綺麗だったんだけど.
まぁ,便利さと引き換えということで,しょうがないのかな.
1月18日(金)
今朝は比叡山や京都北山は雪化粧.でも山中越えの温度計は2℃〜3℃で,あまりたいしたことない.
たしかに,これから寒くなってくるのかもしれない.ちなみに明後日は暦の上では「大雪」になっている.
大学の中を歩いていると,掲示板に,大学入試センター試験の試験会場案内が掲示してあった.
よく見ると,門のところにも大きな立て看板が出ている.どうも明日が試験ということのようだ.
1月19日(土)
今日も朝から八幡に行ってきたが,あまりおもしろいものはなかった.
たまたまフェンダーの外れている車があったので観察していると,ヘッドランプ周りのハーネスが気になり,
ハーネステープを切って「解剖」してみることにした.私はこれまで,ランプ類の配線は左フェンダーを通っているとばかり思っていたのだが,
実際にハーネスをばらして見ると,実際には右フェンダー内側を通って室内に入っていた.
そして右フェンダーエプロンのところにある12極くらいの大きめのコネクタが,ランプ類の中継コネクタになっていた.
これを使えば,純正ハーネスを切断することなく,ランプのリレーハーネスが組めそうである
(でも,切断しちゃった方が簡単に組めそうだし,配線も太くして最適化できるんだけど・・・).
帰りに部品共販に寄って,木曜日に注文したボルト類を受け取る.エアホースだけは約2週間後になるようだ.
今日は珍しい現象を見た.午後3時過ぎ,山中越えで京都に向かっている途中,前方に「虹」が見えた.
でも,ええっ.普通,虹というのは太陽と反対側に見えるものなのに,今のは西側(太陽と同じ向きで少し右側)に見えたぞ.
道の曲がり具合と山の稜線の関係で,しばらく進むと,今度は太陽の少し左側に虹のようなものが見えた.
これでだいたい,全体像がつかめた.要するに太陽が傘をかぶった状態なのだが,その雲が厚いせいか,
普通は白い輪にしか見えないものが虹のように色分かれしていたのだ.そういうこともあるんだ.
夜,弟の会社で不要になった無停電電源装置をもらいに,大阪まで行ってくる.
さすがに鉛蓄電池入りだけあって,すごい重さだ.ついでに日本橋に行って,スイッチを買ってくる.
前に緑と赤のスイッチを買ったのだが,青や白もないかな,と思って見たら,ちゃんと売っていた.
このLED照光式のプッシュスイッチだが,前に買ったのはミヤマ電器のものだったが,
レジの前のあたりに日本開閉器工業のものが売っていた.
両者を比べてみると,日開のはボタン部分がクリアで無色なのに対し,ミヤマのものは少しスモークで発光色と同色である.
軸の部分は日開は黒,ミヤマは青であり,ミヤマのものはLEDに抵抗が入っていて12V系に直接つなげられ,2回路入りもある.
全体の長さは日開の方が短い.また日開には標準サイズの12mm径以外に8mm径のものもあった.値段的には日開のほうがちょっと高い.
それぞれ一長一短があるが,単純に色の好みで,赤・緑・青に関してはミヤマのものを,白は日開のものを買うことにした.
白のものは,用途の関係で8mm径のモーメンタリー型を,他は12mm径のオルタネート型にしている.
1月20日(日)
今日は,いよいよエンジンのフューエルインジェクターの交換を行うことにした.
準備として,市販のインジェクタークリーナーを購入する.これは本来はガソリンに混ぜて使用するものだが,
今回はインジェクター単体を取り出すので,原液のまま内部に通して洗浄を行う予定である.
もちろん電流を流さないと液が通らないから,電源装置,スイッチなども用意した.
作業前に,新品のインジェクターを使って,インジェクターのテスト装置の予行演習をしておく.
医療用の注射器(使用済みのものを洗浄して使用)にインジェクタークリーナーを吸って,
インジェクターのお尻に差し込み,圧力をかけた状態でスイッチをONにすると,見事にインジェクターから液が噴射された.
スイッチをOFFにすると噴射は停止する.というわけで予行演習は終了.実車での作業にとりかかる.
なお,買ってきた部品のネジ径をチェックしてみると,パルセーションダンパー付け根の六角部が22mmのオープンエンドレンチ,
バキュームセンサーのガスフィルターは24mmのディープソケットが必要で,今日は作業できないことがわかった.
(実際の作業については,別ページで)
なお,インジェクターを取り付ける前に,サージタンクやインテークマニホールド内にエンジンコンディショナーを吹き込んでおいたので,
EFIヒューズを抜いてから10秒ほどクランキングして,片づけ作業中,そのまま放置しておいた.
片づけ終了後,いよいよちゃんとエンジンをかけてみる.キーを回してみると・・・なかなか回り出さない.
これはインジェクターを取り外したため,フューエルデリバリーパイプ内に燃料が入っていなかったからで,
数秒してインジェクターに燃料が回るとエンジンが回り出した.でも,ちょっと変・・?
どうも振動が大きいような気がする.とりあえず走ってみると,走るのは走るが,おかしな振動がある.
停車時,ギヤをニュートラルにすると,エンジンが脈動する.アイドリング時の負圧を見ると,-330mmHgほどしかない.
これは,どこかのバキュームホースの差し込み忘れで,エアを吸ってしまってるな,と思い,
エンジンルームを探ってみると,たしかにECUのバキュームセンサーのホースがはずれていた.
それを戻すとエンジン回転も落ち着いた.しかし,振動は前と変わらずだな・・・.
インジェクターのカプラーを抜いてみても,1番と4番は抜いても回転状態が変わらず,2番と6番だと著明な不調になる
(3番と5番は手が入りにくかったため試していない).1番と4番が具合悪い,ということは,
これはECUの同じ端子から出てくるはずなので,ECU側の問題なのだろうか.
一度,他の車から外してきたECUに交換してみる必要がありそうだ.
1月21日(月)
ECU交換の前に,ECUの中身を一度,チェックしてみることにした.ビスを外して中を開けてみると,
基盤は上下2枚が配線で蝶番のようにつながれており,コネクタのついている側がアナログ部,
上にかぶさっている側がデジタル部と思われた.使用されている集積回路は,まだこの時代だとほとんどがDIPのパッケージで,
基盤裏面にはチップコンデンサやトランジスタ,ダイオードなどが張りついていた.
電解コンデンサの寿命を考えて,電解コンデンサだけ新品に交換しようかとも思ったのだが,
電圧が63Vや35Vとちょっと特殊で,すぐに代替できないため,今回は見送った.明日,ECUを交換したら,
もともと車に付いていて外してきたのを,リフレッシュできるかどうか確かめてみようと思う.
1月22日(火)
今日はECUの交換を行ってみた.解体屋で買ってきたECUは2個あり,そのうちの1個('90年8月という少し古いもの)
は前に試してよくなかったので,もう一方('91年2月の検印がある.今の車についていたのは'90年10月のもの)
に交換してみることにした.ECUを交換するついでに,インジェクターの配線の状態を調べるため,
ECUのコネクタからインジェクターを含めた配線の抵抗を測定してみた.インジェクターは,プラス側がIGN2から,
マイナス側はECUのそれぞれのグループの制御端子につながっている.インジェクター単体の抵抗値が13.5Ω程度だったので,
2個並列で,配線抵抗を加えると,7〜7.5Ωくらいになるだろうか.実測してみると,3グループとも7.3〜7.4Ωであり,
配線の異常はなさそうだ.まぁ,たしかにインジェクターの作動音は,どのインジェクターも変わりなかったから,
電流値自体は問題ないはずなのだが.なお,コネクタの穴が小さいので,普通のテスタリードでは電極に届かず,
ICクリップを使用した特製のテスタリードを使用して測定した.
それから用意していたECUに交換して,ネジ止めする前にエンジンがかかるか点検.これはうまくかかった.
だが・・・エンジンの振動具合などは,交換前と変わりがないような気がする.交換したばかりの時は,
ECUがまだエンジンの状態を学習できていない(長い間,電源につないでいなかったので,学習した記憶が消えている)
と思われたので,とりあえずインパネを元に戻し,走ってみることにした.今日一日で約100kmほど走ったが,
残念ながらアイドリング時の振動は変化がない.インジェクターの1番と4番を抜いてもアイドリングに変化がないのも,同じである.
こうなると,やっぱり原因はエンジン内部ということになってしまうのかなぁ.今度はエンジンオーバーホールか・・・.
あと,修理書の配線図ではインジェクターのグループ分けが( 1-5, 3-6, 2-4 )になっていたが,
新型車解説書では( 4-1, 5-3, 6-2 )になっているので,どちらが正しいか,インジェクターのカプラーにきている線の色を見てみると,
( 4-1, 5-3, 6-2 )が正しいことがわかった.今回の問題の1番と4番が同じグループになっているところが,
ECUやインジェクターの異常を示唆していたのだが,残念ながらハズレだった.
1月23日(水)
エンジン不調の原因について,いつも出入りしている掲示板で尋ねてみたところ,
インテークマニホールドとシリンダーヘッドの間のガスケットの部分からエアを吸い込んでいると,
特定気筒のみアイドリング異常が生じる可能性がある,という返答をもらった.
たしかにこれだと,アイドリング等の負圧の大きい時は吸い込み量が増えるが,燃料の噴射量はサージタンクの圧力で決められるので,
相対的に燃料が薄すぎて燃焼しなくなる.で,アクセルを踏み込んでいくと,負圧が減るので吸い込み量も減り,
一方で燃料の噴射量は多くなるので,きちんと燃焼するようになる.こう考えると,
アイドリング時には失火して,加速時のパワーには変化がない,という状態が説明できることになる.
点検方法は,インテークマニホールドの接合部分にブレークリーンなどを吹き付けてみて,
液の様子を観察してみるとわかるのでは,とのことだったので,一度,確認してみよう.
さて,それでもし異常があったら,ガスケットの交換が必要になるわけだが,それにはサージタンクを降ろさないといけない.
でも,もうインジェクターを外したことがあるわけだから,サージタンクも少しがんばれば降ろせるなぁ.
サージタンクを降ろすと,ふだんは下からしか交換できないフューエルフィルターも上から交換できるようになって楽だし,
バッテリーのマイナス側からの配線がエンジン基部についてるところも一緒に交換できるだろう.
一日,朝から晩まで空いてる日を探してやってみようか.
夜,西大津バイパスを京都方向に走っていたら,前を走っているトラックの屋根上などから,
ときどき雪の塊が落ちてくる.まぁ,それくらいはいいのだが,最後の国道1号線に合流するところのカーブでは,
カーブの外側に,そういう雪の塊が吹きだまって凍りついていた.なんで雪降ってるわけでもないのに,
ここだけ凍ってるんだ? っていう感じだった.
1月24日(木)
今朝の山中越えは,料金所付近が -2℃,山中町入り口で -5℃,北白川の温泉前で -4℃と,
今年,見た中ではいちばん寒かった.天気が良かったので凍結はしていなかったようだ.
週末は少し天気が崩れそうだが,北陸でも雨の予報で,今日に比べるとそんなに寒くはならないようだ.
車のドアを開けた時に,ドアにランプがついていて点灯するようになっているが,
修理書などではこのランプは「ドアカーテシランプ」と書かれていて,ずっとどういう意味かわからなかったのだが,
今日,いろいろ辞書などで調べてみた結果,“courtesy light”で辞書に載っているのを見つけた.
“courtesy”自体は「礼儀上の,優遇」などの意味があるようだ.でも,いまひとつすっきりしないなぁ.
久しぶりに大学生協に行って,『理科年表 2002年版』を買った.机上版は¥2400,
文庫サイズは¥1200だったが,ここはやはり机上版を購入.隣に『理科年表 CD-ROM』もあったが,
¥26000もするので,あきらめた.これはちょっと,個人で買えるものじゃないなぁ.
で,2002年版になって内容をちらっと見てみたら,昨年版には載っていなかった鳥取県西部地震が書いてある.
その一方で,昨年,たしか金沢で最深積雪が記録されたはずなのに,このページの統計は2000年春までで更新されていない.
ダメじゃんか.
1月28日(月)
今日は,我が家に珍客が訪れた.
1月29日(火)
今日はブレークリーンを持ち出してきて,インテークマニホールドのところに吹きかけてみた.
でも・・・すぐ蒸発してしまって,よくわからない.そもそもシリンダーヘッドとの接合部のところは,
ラジエータホースなどが邪魔でよく見えない.結局,エア吸い込みについては判定不能だった.
しかたがないので,部品共販にインテークマニホールドのガスケットを買いに行く.
ガスケットは,シリンダーヘッド側とサージタンク側の両方にあるので,両方とも購入.
大きいわりには1枚500円程度と安い.あと,インジェクターのデリバリーパイプをはずさないといけないので,
フューエルパイプのガスケットも買っておく.これは1枚80円程度.ついでに,純正のバキュームホースも買っておく.
市販の色つきシリコンホースもあるのだが,どうも純正より硬くて,1年ほどすると褪色,硬化してきているようなので,
次に交換する時は純正に戻そうかと思って,買っておくことにした.
使用場所の長さに合わせて切ってあるものもあるが,割高なので,長いままのものを購入する.
これも30cmくらい単位で6種類くらいの長さがあったが,今回は1.3mのものを購入.これは1200円程度.
夜中,家に帰る途中,蹴上の少し上のあたりで,警察の車が何台か止まっていて交通規制をしている.
通り過ぎるときに横目で見てみると,パジェロとおぼしき車の運転席側ドアが激しく凹んでいる.
この信号のある交差点,山科側からくると,きついカーブの出口にあたるので,直前にならないと交差点の状況がわからないのよね.
いちおう予告信号はあるんだけど・・・.これも4車線化されたら,もうちょっと見やすくなるんだろうな.
1月31日(木)
今朝,家を出る時,大津では少し雪が舞っていて,車や道路脇などにうっすらと雪が積もっている状態.
さて,山中越えは大丈夫かなぁ・・・と思いながら走っていくと,少し登ったあたりから轍の部分以外は白く雪が積もっている.
今日はKeiの方に乗って出てきたので(給油とタイヤの空気圧調整のため),これは四駆とはいえ夏タイヤであり,
ちょっと怖いかなぁ,という感じになってきた.ただし大津側の登り斜面は,けっこう日が射すので雪が融けている部分も多かった.
で,問題の料金所を過ぎたところの下り斜面だが,ここは西向きで,かなり昼近くにならないと日が当たらないので,
交通量の少ない大津方向の車線は完全に真っ白になっている.路面温度計は -2℃の表示.
みんな時速10kmくらいで,そろそろと下っている.そこを無事にクリアすると,そこから先はさほどでもない.
北白川の温泉のあたりまでは少し雪があったが,そこから先は路面が濡れている程度で,ほぼ普通に走れた.
( この月の初めへ )