

| 明日のための提言 その1.2002.02.22 そんなに難しくない。難しくしているのは、すぐ忘れるからです。 記録用紙をパッと見た限り、バレーを知らない人には絶対に書けません。唯一公式に教わるのが、年度初めの審判講習会。1日がかりでの講習会ですが、大勢の受講者の中でたった数十分記録の実技をしても理解できるわけがない。私も初めは毛嫌いしていましたが、いまではドンドンこい!状態で全然OKです。書き方のシーケンスさえ判れば、たいしたことはありません。一番恐いのは、書き方を忘れることです。公式試合が数ケ月単位の為、記録用紙に触れる機会は当然その程度の間隔になってしまいます。なので、その間にだんだん書き方を忘れてしまうケースが多々あるみたいです。練習試合のときにでも、思い出したように書く習慣をつければ公式試合でも多少は余裕の記録ができることでしょう。 明日のための提言 その2.2002.02.22 記録員はだれでもいい。正確に書ける奴ならば。 群馬県内の小学生バレーの試合を見ていると、ほとんど選手が書いてますね。県大会の準決勝あたりなら、審判部が担当して記録をつけますがそれ以外は選手が書いています。でも、去年あたり埼玉の支部の大会を見に行ったら、ほぼ全チーム大人の人がつけてました。全国的には大人、選手の比率はわかりませんが、冷静にスピーディに正確に書ける人ならば子供だろーが、じーさんだろうが、変なおじさんだろーがだれでもOKです!ルールブックには、記録員の仕様はありません。私の意見としては、大人の人につけさせたいですね。イザというときに論理的判断が出来るから。ということで、ステージでお茶飲んでいる父兄の皆様。皆様が書いてくださっても全然OKなんです。 明日のための提言 その3.2002.02.23 記録は一人で書く。これが、原則。 県内の小学生バレー公式戦を見ていると、選手が2名で記録をカキカキしています。一名が左側のチーム、もう一名が右側のチームをそれぞれ担当して書いている模様です。しかし、記録は一人で記載するものです( 1名→記録用紙の記入を専門に担当。 残り1名→記録の補佐。補佐する項目は1.サーバーの確認(記録と実際のサーバーが合っているか確認)。違ってたら、大声で副審に「サーブ順が違う!」と知らせる) 2.得点版の確認(記録と得点版が違ってたとき、得点版を速攻で直しに行く) 明日のための提言 その4.2002.02.23 本来はボールペンで書くみたいです。 みなさん鉛筆でかいてますよね。記録。でも本当はボールペンで書くみたいです。改ざんできないようにするためでしょう。神奈川で行われた関東ブロックの審判講習会で私も始めて知りました。私は、堂々シャーペンで書いたら怒られました。( 明日のための提言 その5.2002.02.23 主審、副審の方も記録の仕方を知っておくべき! 帯同審判で主審、副審をされる方で、記録の付け方を知らない方おりますか?結構あぶない橋を渡っていると思います。タイムアウトの後、サーブがどっちからか記録用紙を見て判りますか?メンバーチェンジが正確に行われたか記録用紙をみて判りますか?今サーブ権は、どっちのチームの何番が持っているかわかりますか?サーブローテーションミスがあって得点を元に戻すとき、何点まで戻せばいいですか?全て記録用紙を見れば判ります。特に副審の方は、記録が正しく書かれているか?確認していないと、あとで手痛いしっぺ返しを食らうと思いますよ。保険に入る意味合いで主審、副審も記録をつけろとはいいませんが、何をどう記載しているのかくらいは知っておく必要があると思います。 と、まあいろいろウンチクたれましたが、そろそろ実践編と行きますか?Are You Ready? 実践編 ACT.1 記録用紙をゲットしよう!2002.02.26 ここでは例として、欧州組vs格闘連合というとても小学生とは思えない男子チームの県大会の試合を記録するという前提で話を進めて行きたいと思います。(←チーム名、いろいろ考えたんですよ。ディズニーモドキとか、ルーカスフィルムLoversとか...) 県大会の場合、たいがい準決勝以上の試合を除いて帯同審判で試合は進行していきます。なので、自分のチームがたった今試合を終わり、惜しくも相手チームに負けたとします。そうすると暗黙の了解で、次の試合の主審は勝った勝利チーム、負けた自分のチームは副審、記録、ラインジャッジ、得点表示すべてを担当することとなります。 さて、自分のチームが負けて悔しい思いをしている場合ではない。監督に怒られるのは後にして(メモ)、記録担当の人は大会本部行き「A-2(試合番号)の記録用紙をください!」といって記録用紙をもらおう。 用紙をもらったら記録席に座ろう。しかし、たいてい前の試合の記録の人がまだ長々と記入しているはず。記入が終わるのを待ちましょう(メモ)。 さて、もらっていた記録用紙を見てみよう。Fig.1のような感じになっていますぅ!ブルーの部分が大会本部で記載している箇所です。 Fig.1 大会本部からもらってきた記録用紙(例) ①大会名 ②試合番号 → コート名(A,B,C...)と試合順(1,2,3…)の組み合わせ。トーナメント表についている奴と合致してます。 ③試合設定時間 → この時間は、記録をしようとする試合のプロトコールをスタートさせる時間です。 ④チーム名 → 対戦するチーム名が記載されてます。 ⑤スターティングラインアップシート → 試合をするチームから提出されたラインアップシートが、貼り付けられている もらってきた記録用紙が自分がこれからつけるべき記録用紙であることを確認できたら、今時点で記入できる箇所を次に記入していきましょう。 ACT.2 プロトコールまでの前処理 2002.02.28 さあ、記録用紙をもらって記録席に座りました。記録員はここから既に試合開始です。 記録席に着席しました。プロトコール開始までまだ数分。次の試合をする欧州組と格闘連合が、コートの中に入って練習を開始しています。記録席の周囲には、主審と副審、またラインジャッジの4人がウロウロしています。さあ、この時点で記入できる項目はとっとと記入してしまいましょう。その記入できる項目とは以下の項目です(Fig.2 参照)。 Fig.2 プロトコール開始までに記載する項目 ①男子or女子のチェック欄 → 男子なら男子の四角にバッテン、女子なら女子の四角にバッテンをします。レ点は駄目ですよ! ②場所 → 市、郡、町、村単位の住所を記入します。番地はいらないです。(大会本部で記入しているケースもあります) ③体育館 → 試合会場の体育館名を記入します(大会本部で記入しているケースもあります)。 ④日付 → 試合日を記入します。バレーは国際スポーツなので、私は西暦で記入しています(大会本部で記入しているケースもあります)。 ⑤審判員氏名 → 主審、副審、記録員の名前をフルネームで記入します。本来ならば記録員が全部記入しますが、主審の方、副審の方に自分の名前を記入していただいても結構です。また都道府県の欄には群馬の「群」を記入します。私は秋田生まれなので「秋」って書きたいのですが、無難に「群」を書いています。自分の現住所なのか?審判登録している県を記入するのか?定かではありません。 ⑥ラインジャッジ氏名 → ラインジャッジ4名の名前をフルネームで記入します。本来ならば記録員が全部記入しますが、ラインジャッジ一人一人から順番に自分の名前を記入していただいても結構です。記入する順番は記録席から見て、左奥が1番、左前が2番、右前が3番、右奥が4番になります。間違えやすいので気をつけてください。 Fig.4 記録員の位置 以上でプロトコールまでの前処理は終了です。この時点で親切に既にサービスオーダーを記録席に提出するチームがありますが、正式にはプロトコール開始時に行われる、コイントスでサーブとコートが決まった後に提出されなければなりません。しかし、記載に誤りがなければ受理しておいてください。あくまでも受理して保管するだけです。 ACT.3 プロトコールスタート 2002.03.01 試合設定時間になりました。主審が両チームのキャプテンを呼んで、コイントス。プロトコールの開始です。 Fig.5 コイントス終了後記載項目 主審がコイントスを行いました。その結果、サーブを欧州組がとりました(必然的に格闘連合はレシーブとなります)。格闘連合はコートを記録席からみて左側を選択しました。それを受けて両チームから第一セットのサービスオーダーが記録席に提出されました。以上の前提条件で、記入を進めていきましょう!ここから真剣勝負です。間違いは絶対に許されません。なので記入したら再確認しましょう。 できるならば、主審、副審にも確認してもらいましょう。 ①A,Bチームの割り当て → 第一セット、記録席から見て左側のチーム(格闘連合)がAチームになります。反対に右側のチーム(欧州組)がBチームになります。対戦チームの○の中にA,Bを記入しましょう。 ②サーブ、レシーブの表示 → 第一セット、サーブを選択したBチーム(欧州組)のSの部分をバッテンします。また、レシーブ側のAチーム(格闘連合)のR部分をバッテンします。レ点は駄目ですよ。バッテンです。記録用紙は、各セット毎に記録席から見て左側のチームを記録用紙の左側に、右側のチームを記録用紙の右側に書くように対応しています(Fig.6参照)。記録用紙も第一セット、第二セットもコートチェンジに対応して、反転180度します。第二セット、Bチーム(欧州組)はレシーブ、Aチーム(格闘連合)はサーブと絶対なりますので、私はこの時点で第二セットのS、Rもバッテンつけます。 ③サービス順 → 提出されたサービスオーダーを転記します。ローマ数字で記載されたサーブ順の下に、対応する選手の背番号を転記しましょう。記入したら再確認してください。 Fig.6 コートと記録用紙の関係 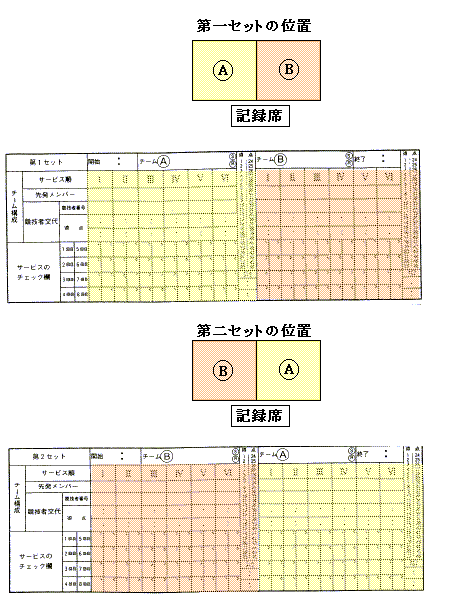 サービスを記入したら、サービスオーダー用紙は副審に渡してください。記録用紙にサーブ順を書いたらもう変更はできません。監督、コーチ、あるいはマネージャーが「ちょっと待って!間違ってた!」と言ってきても、駄目です。Too Late!です。支部の大会なら大目に見てもかまいませんが、県大会では記録用紙に転記した時点で変更は不可能です。変更するなら、試合が始まった時点で正規の選手交代をするしかありません。 ここまできたら、あとは試合開始の笛を待つのみ。しかし、それまでの間記録員はコート上の選手を良く確認しておいてください。スターティングラインアップシートに記載された選手のみがコートに入れます。それ以外の選手がいる場合は、主審、副審に報告し、コート上から退去させましょう(メモ)。 これからは、正確にスピーディに書くことが必要となってきます。準備はいいですかぁ? 嵐の第1セット 得点記載の基本シーケンスを覚えよう。 炎の第2セット ややこしい記載、タイムアウト、選手交代を制覇しよう。 暁の第3セット 最後の第三セット 不規則なコートチェンジの記載を覚えよう! もしも遅延行為があったなら 遅延行為があった場合の記載を覚えよう! もしも警告、退場、失格がでたら 覚えたくないが警告、失格、退場があった場合の記載を覚えよう! |
